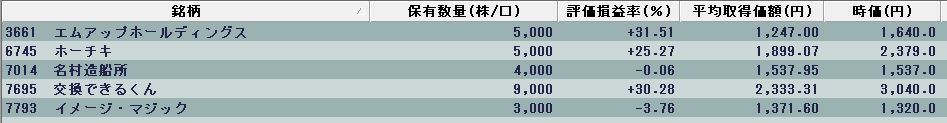プロローグ~
【プロローグ】
「ヒュー。ドドーン。バチバチバチ。
ヒュゥー、ヒュー、ドドーン、ドドーン。」
遠くから微かに聞こえる祭囃子。
夜空には打ち上げ花火が色とりどりの花を咲かせていた。
彼は、じっと夜空を見つめていた。
が、彼の目の焦点は夜空を彩るその美しい花火たちに合ってはいなかった。
…そして、花火の最後を飾る、とりわけ大きな大輪の花が空一杯に広がり、
残像が漆黒の闇に溶けるように消えていった。
しかし、彼はいつまでも、そこに坐って、何も無い夜空を見つめていた。
彼の眼には、涙こそ浮かんではいなかったけれど、
そこからは、彼が生まれて初めて感じる、どうしようもない空虚さが溢れていた。
そして…。
彼は、静かに立ち上がると、賑やかな祭囃子に背を向け、暗い路地へに向かってとぼとぼと歩き、その小さな背中は闇の中に消えていった。
2
時刻表、改札、自動発券機、ポスター…そこにあるものは見慣れたものばかりなのだけれど、初めて降り立つ駅というものは凄く新鮮なものに感じられる。
桜井鈴香は、そんな気分を楽しみながら、階段を一歩一歩確かめるように降りていた。
そんな鈴香の前を歩きながら、黒田遼介は時折彼女を気にするように振り返り振り返りしていた。ただ、それでも彼にとってはいつもの順路なのだろう、すいすいと淀みなく前を歩いて行く。
外に出ると、少しだけ涼しい風が吹いていた。
駅前の広場。ぽつぽつと人影が見える。鈴香が、噴水の横のデジタル時計に目をやると、ちょうど8時32分になったところだった。
客待ちをしているタクシーの運転手が、フロントグラス越しに視線を寄越すが、鈴香は「違います」というような目で答えながら、小走りに遼介に追いついた。
人気が少なくなったところで、やっと二人は街路樹の下を並んで歩き始めた。
「それにしても、さ…『夏休み後半ガンバロウコンパ』とか、ホントに凄いこじつけだよね。」
「先輩達…とにかく、飲めりゃいいって感じなんだよね。
でも、…オレも3回生ぐらいになったらあんな感じになっちゃうのかな。」
「えーっ。あんまり想像したくないなー。」
遼介はほろ酔いだった。そして鈴香は最初の一杯を三分の一ほど飲んだだけで、あとはジュースだったけれど、それでもまだ頬が少し紅潮していた。
鈴香は顔に当たる夜風を感じながら、見知らぬ街を眺めながら歩いていた。
8月も最後の週になっていた。
…が、大学生になって初めての夏休みは、それでもまだこれから先一ヶ月近くあるのだった。
9月になってもまだ、これからひと月も休みがある…という、掴み所のない自由というか、嬉しさというか…。
大学一年生の感じる独特の感覚を…それを滲ませながら、二人はゆっくりと足を踏み出していた。
「…何だか、悪いね。」
遼介は街灯の作り出す自分の影に目を落としながら言った。
「ううん。いいのよ、どうせ定期券だし…。それに、私の下宿はすぐ隣の駅だから、ちょっとぐらい遅くなっても大丈夫。」
「うん…でも、何だか…立場が逆かな?って」
「ふうん。遼介って案外古いんだ。」
鈴香はちょっと窺うように目線を遼介に向けた。
鈴香と遼介は身長差が20センチもあり、立って話す時はちょっと見上げるようになってしまう。
遼介は左を歩く鈴香の、自分を見上げるような視線からちょっと逃げるように車道へ顔を向け、
「…別にそんなことないけど。」
と呟くように言った。
そんな遼介に構わず、鈴香は続ける。
「だって。私…。遼介んちの博物館、見てみたいんだもん。」
「もう、こんな時間だから…開いてないよ。」
「分かってまーす。外観だけでも見て帰りたいの。
…折角『二次会、二次会』って、しつこい先輩達を折角振り切ったんだから…いいでしょ。」
「うん…。」
以前から、遼介の祖父が私立の博物館を持っているということを聞いていた鈴香は、一度見たいと言っていた。
それが、急遽今夜実現しようとしていたのだ。
一次会の終わった居酒屋の前でワイワイ騒いでいる先輩や同級生達を置いて、
「今日はちょっと用事があるんで」と、それぞれに抜け出した二人だった。
実は、宴会の最中に、遼介の携帯電話にメールがあったのだ。
「今日、一緒に帰らない? 博物館、見たいな。」
それは鈴香からのものだった。
同じサークルの鈴香を前から意識していた遼介にとって、それは彼女と二人きりになれる絶好のチャンスであり、願ってもないことではあった。
遼介は、「いいよ。じゃあ、一次会が終わったら、駅で。」とだけ返信し、あとは上手く抜け出して駅で落ち合ったのである。
「…ふうん。でも、ウチのって『博物館』ってほどのもんじゃないよ。何だか『変』だし。」
「いいのよ。そんなの気にしない。」
見上げる夜空には、まだ少し夕暮れの明るさが残っているような感じさえした。
近くのビルの屋上ではビヤガーデンをやっており、その光が空に乱反射して駅周辺の空は白っぽくなっているせいもある。
少し陽が落ちるのが早くなったような気がするけれど、まだまだ夏、であった。
夜風にあたりながら歩く二人の背後に、明るい駅前の光が少しずつ遠のいていた。
3
たわいもない話をしながら、二人は大きな通りを暫く歩いた。そして、綺麗に整備された水路脇の道へと入って、また少し歩いた。
そこで遼介は告げた。
「そこの角を曲がったところなんだけど。」
「わあ。ドキドキしちゃうわ。」
「そんな、ホントに大したもんじゃないからね。」
そう言いながらも、遼介は彼女の反応を楽しみにしていた。
「ここさァ、最近大きなマンションが建っちゃって、目印としてはいいんだけど、」
見通しが悪くなっちゃって。
結構…迷惑なんだよね。」
そんなことを言いながら、遼介は先に角を曲がった。
道路脇の水路には比較的沢山の水が流れていた。
その黒い水面に、街灯の光が映ってゆらゆらと揺れている。それがちょっと幻想的でいい感じだったので、鈴香は「もう少しここを歩いていたかったな…」と、ちょっぴり名残の視線を残しつつ、遼介に付いてもう一本細い道へと足を向けた。
そこは、両側が古い街並みのような…白壁の倉の間を歩いているような感じで、また独特の情緒がある道だった。
そこを暫く歩いて行くと、向こうの左手に少し広くなったテラスのようなものが見えてきた。ぼんやりと常夜灯の明かりも見えていた。
テラスが見渡せるところまでやって来ると、一気に視野が開けた感じになった。 その広場への入り口自体は少し狭い感じがしたが、そこから中は割と広い広場のような感じになっているのだった。
そして、その正面。…洋館というにはそれほど大きくはなく、民家というには洒落ている、こぢんまりとした建物…。
一見、公民館かなにかと思えるような建物がそこにひっそりと佇んでいた。
「まあ、素敵…。これが噂の博物館ね。」
「うん。まあ…チンケだけどね。」
「…そんなことないよ。凄く洒落てるじゃない。」
「そう? 本当に? それ、聞いたらお祖父ちゃんが喜ぶよ。」
多少古ぼけた感じはするものの、その古さがまた一種の味わいになっているような、そういう意味では均整のとれた建物だ…と素直に鈴香には思えた。
そして、その建物の脇には比較的新しい建物があった。
遼介は正面に向かって歩きながら、その新しい建物を示して、
「こっちはさ…、最近建てたんだ…。
これでも『別館』だって。笑っちゃうだろ。」
鈴香は立ち止まり、その『別館』の方を向いて暫く黙っていた。
その建物は、正面の建物よりはやや小さめで、少々モダンな感じだった。
背は高かったけれど、小さなアパートぐらいの規模のものだった。
「3年ぐらい前に建てたんだけど、最近こっちの方が最近ちょっと有名になってさ。」
その建物の前には「黒猫館」と彫りつけられた木の杭とベンチ、…そして子どもの背丈ぐらいなコンクリート製の台の上に、猫のブロンズ像が置かれている。
「…私、これ見たことある。」
突然鈴香が声を上げた。
「そうそう。これよ…。 私…、やっぱりそうだったのよ。」
薄暗闇ではあったが、鈴香の表情が輝くのが、遼介にも分かった。
「嬉しい…。…ちょっとうろ覚えだったんだけど、まさかここにあったなんて。 …感激だわ。」
聞けば、彼女は以前、雑誌か何かで紹介されている、この博物館を見たことがあったのだそうだった。高校時代のことらしいが、彼女はその当時から「猫」という題材に興味があったので、「猫」にまつわるものばかりが展示されている博物館のことが記憶にとどめられていたということであった。
が、高校生の身分ではすぐにそこを訪ねるわけにもいかず、結局受験勉強などに紛れて、すっかり存在を忘れていたのだそうであった。
彼女はいたく感動していた。
「忘れものをしていたこと、それ自体を忘れていて、…それをふいに思い出した時みたい」と、何だかワケの判らない説明を鈴香から受けて、遼介はちょっぴり苦笑いした。けれども、素直に喜ぶ彼女を見て、自分もちょっぴり心が高揚しているのを感じていた。
4
「私、『猫』をテーマに卒業論文が書きたいの。」
鈴香は遼介と同じ大学の文学部の1回生だった。
遼介も同じ1回生だったが、彼は法学部であり、二人は同じサークルで知り合ってそれほど間もない、所謂「友達以上恋人未満」の関係であった。
遼介は、鈴香は卒業論文を「猫」で一体どうまとめるのかな…などと、ちょっぴり疑問に思ったりもしたが、そこは自分とは畑違いのことでもあるし、何か祖父の趣味が彼女のためになるのならば、またそれも面白いと、さらりと思うのだった。
「昔、ウチは割と大きな農家だったらしくってさ…、蔵を倒す時、中に結構色々なものがあって…、中にはかなり珍しいモノもあったみたいでさ…どうせならそれを展示しようって、お祖父ちゃんのお祖父ちゃんだか誰だかが始めたんだって。
で、古民具とか、美術品とかそういうものを展示してたんだけど、お祖父ちゃんが妙に猫好きでさ、もともと猫が描かれた絵とか掛け軸もあったらしいんだけど、新たに随分蒐集したみたいでさ、結局それの展示スペースがなくなっちゃって、とうとう別館まで建てちゃって…。
で、今ではすっかりそっちの『猫博物館』の方がメインみたいになってきたってワケさ。」
遼介の説明を、鈴香は、本当に目を輝かせながら聞いていた。そして言った。
「今度…、ゼッタイ…ゆっくり見せてもらいに来るわね。」
遼介も、思いの外喜んでくれている鈴香の様子に、気をよくしていた。
「うん。いつでもいいよ。鈴香も猫が好きだって聞いたらお祖父ちゃんも喜ぶだろうし、入館料なんか要らないから。」
「そう…ありがとう。でも、タダってのは悪いわ。私もちゃんとバイトしてるんだから、入館料は払いますからね。」
そう言って微笑む鈴香だった。
そして彼女がふと目をやるった先、ちょうど新館の前辺りに植え込みがあり、その脇に感じの良いベンチと常夜灯があった。
何となく鈴香はそこへ歩いていって腰掛けた。
遼介もゆっくりと歩いてきた。
「ここのベンチ…、これって昔からあってさ、前はここから…あっちの方…は、とても見通しがよかったんだけど。」
そう言いながら鈴香の横に少し距離を置いて腰掛けた。
そして遼介が指さした方向には、先程のマンションがあった。その無機質な背の高い建物はちょうどそちらの方角を塞いだ恰好になっていた。
「満月の時にはさ、あの…向こうの山から月が昇ってくるんだけど…。
で、前は月の光が綺麗にこのテラスに差し込んでさ、凄くロマンチックだった んだ。
…だけど。 ほら、今はちょうどあの陰に隠れちゃうんだ。」
遼介の口調は本当に残念そうだった。
「…お祖父ちゃんは、よくここに座って月を眺めてたんだ。だけど。あのマンションのせいで台無しだってぼやいてるんだ。」
「へえ。それは残念ね。でも…ロマンチックなお祖父ちゃんね。」
「うん。でも、オレもよくお祖父ちゃんに付き合わされて、ここに坐って月見をしてたんだけどさ、本当に綺麗なんだ…、
青白い月光がさ、植え込みの樹の陰をテラスに映し出して…何だか凄く幻想的でさ。」
今夜はあいにく月も出ていなかったが、鈴香は空を見上げながら遼介の言葉に耳を傾けていた。
「…でさ、新館を建てる時に、あそこの常夜灯もつけかえたんだ。」
「?」
「何でも、満月の時の明るさで、そこの樹が影を落とすようにって、かなりこだわってさ。」
確かに、遼介に言われ、鈴香がテラスに目を落とすと、そこには綺麗な影が揺らめいていた。
「ほんとだ。…ステキね。…遼介のお祖父ちゃんってホント素敵な人…。
…是非会ってお話したいな。」
「ああ、いつでもどうぞ。きっと喜ぶよ。」
「うん。」
そう言いながら、遼介は立ち上がった。
5
遼介に続いて立ち上がった鈴香は、ベンチのすぐ脇に目をやって言った。
「このブロンズ像もステキね。」
そこには、コンクリート製の台があり、その上にはブロンズの猫がいて、静かに闇を見つめていた。
「ああ…これね。これもお祖父ちゃんの特注らしいんだけど…。
若い頃、知り合いの彫刻家に無理を言って造ってもらったらしいんだ。」
「ふうん。」
それは、よく猫が眠るときにそうするような…地面に臥せた恰好をしているが、少し首を擡げ、どこか遠くを見ている…そんな感じになっていた。
「あの猫ちゃん、何を見てるのかな。」
と鈴香。
「さァ…、よく分からないんだけど、何だかお祖父ちゃんはあれを置く位置とかにもかなりこだわっていたらしいんだ。」
「ふうん。じゃあ、それは新館が建つ前からってことね。」
「うん。そうみたいだよ。もう、随分昔のことみたい。実際、『黒猫館』もこの猫に合わせる感じで建てたみたいだし。」
確かに、新しく建てられた『黒猫館』とその猫の位置関係はばっちりであった。が、『黒猫館』が建つ前を想像すると、本館とこの像の位置関係はかなりアンバランス…と鈴香には思えた。
そして鈴香は、その視線のやりようを実に猫らしいものだと感心しながら、もう一度「お祖父ちゃんって本当にこだわり屋さんなんだね。」と笑った。
と同時に、
遼介は早くにお父さんを亡くしたらしいから、さぞかしお祖父ちゃん子だったんだろうな…
そんな感慨に耽りつつ、彼女はしみじみと彼の横顔を見つめていた。
それに気付いてかどうかは判らないけれど、遼介が不意に口を開いた。
「そろそろ帰らなきゃ、遅くなっちゃうよ。」
「そうね。」
時計を見ると、もう9時30分を回っていた。
「…じゃあ駅まで送るよ。」
遼介の言葉に、鈴香はちょっと申し訳なさそうに言った。
「…本当なら、『悪いから、いいわ。』って言いたいとこなんだけど…。
私、結構方向音痴なのよね。
…ちょっと一人だと駅まで真っ直ぐ帰る自信がないかも…。」
遼介は笑って、
「いいよ。きっとそう言うんじゃないかって思ってた。」
「まあ、やあね。」
「ごめんごめん、でもいいんだ…本来ならそうするべきだろうと思うし。」
「そう、ありがとう。…じゃ、お言葉に甘えて…。」
そして二人は、闇を見つめる黒猫と植え込みから聞こえてくる虫の声に送られ、広場をあとにした。
〈第1部終・続く〉
第2部
1
週末、遼介は再び駅前で鈴香を待っていた。
午後1時30分。約束通り鈴香が改札口から姿を現した。
ベージュのワンピースに日除けのカーディガン。真っ白な帽子が目に鮮やかだった。
鈴香のスカート姿をあまり見たことの無かった遼介は、何だか新鮮な彼女のいで立ちにちょっぴり胸がときめいていた。
「お待たせ。」
「うん。」
そう言いながら自分をじっと見つめる鈴香。
遼介はちょっと照れたような感じで視線を思わず泳がせてしまった。
鈴香はそんな遼介の様子を目ざとく察知して言った。
「あ、…『何だかいつもと違う』って思ったでしょ。」
「ああ…うん。」
それを受けて、鈴香は改めてちょっと照れたような感じで答えた。
「へへ。今日はちょっとお洒落してきちゃったの…。
遼介のお祖父ちゃんにお会いするの…初めてだし。やっぱり女の子らしい恰好の方がいいかなって思って。」
「うん、喜ぶと思う…よ。」
「あ~。何だか素っ気ない。ホントは遼介に見せるためだったのにナ。」
「何言ってんだよォ。…昨日も大学で会ったばかりだろ。」
「ふふ。」
キラキラと輝く光の中、笑いながら眩しそうに夏空を見上げる鈴香は、とても可愛かった。
そんな様子の彼女を見ながら、本当に遼介の胸はどきどきし始めていた。
「私、方向音痴だから、もう…すっかりわかんなくなっちゃった。」
先日、夜の訪問の際に見た景色ではあったが、やはりこうして昼間に見るとまた全く趣が違うものだ…と、実感しながら鈴香は告げた。
「…まあね。この辺り、まだ結構昔の街並みが残ってたりするんで、ただでさえ結構ややこしいんだ。
道路が真っ直ぐ通ってないしさ。しかも、この間は夜だったろ。」
「うん。でも、あの背の高いマンションは覚えてるわよ。」
「そうだね。」
駅舎の屋根ごし、遠目に大きな建物が見えている。
「…さあ、行こうか。」
「うん。」
と、歩き始めた二人であったが、鈴香は「この間と同じ道なんだろうけど、何だか随分違うな…」と、妙な感慨に耽っていた。
先日は夜だったので気付かなかったが、街路樹の緑がとても綺麗で、水路の水は思ったよりもずっと澄んでいた。
鈴香は、強い陽射しをいっぱいに受けて輝く水面を見ながら、何だかこれから凄く楽しいことが始まるような予兆を感じていた。
…それは、もちろん初めて見る「黒猫館」への期待でもあったが、それだけではなかった。
少し前を歩く遼介の背中…ちょっぴり頼もしく見える彼。
そんな遼介のことを想うと、胸の隅っこが甘く疼いた。
「どう? 昼間に見るこの街は?」
と、遼介の問いかけに、ぼんやりしていた鈴香はちょっと言い淀んでしまったが、
「綺麗な街ね。」
と、短いけれど心をこめて答えるのだった。
「ありがとう。…っていうか、少しでも印象を良くしようと思って、考えて綺麗な道を選んで歩いてるんだけど。
…近道もあるにはあるんだけど、ちょっとゴミゴミしてるから。」
鈴香はそれを聞きながら、遼介の少し前に出た。
「へえ…。でも、そういう所も案外情緒があっていいかも知れないよ。今度はそこを通ってね。」
と、こちらを振り向いて言った。
「…うん。」
やや素っ気ない返事であったが、それとは裏腹に遼介の内心は昂揚していた。
自分が生まれ育った街を、自分の好きな女の子が褒めてくれる。…それに、またきっと「今度」がある…。
彼の見上げた空は青く、どこまでも高かった。
2
10分ほど歩くと、この間のマンションがかなり近づいてきた。
前は夜だったからもう一つ良く分からなかったが、やはり明るい日中で見ると案外高い建物である。
ちょっと凝った外観が却って周囲から浮いて見える感じ…と、鈴香は思った。
見れば、4階あたりを、派手な服を着た若い女性が歩いているのが遠目でも分かる。彼女は、少し前を行く遼介に言った。
「近くで見ると随分高いわね。。」
彼は、少し鈴香の方を振り向きながら、
「ああ、別にあんなに高くする必要ないと思うんだけど…。
あ、…あと2、3分ってとこだから。」
と告げる。
8月も終わりではあるが、予報通り残暑が厳しいここ数日であった。
「良くない予報ってのはホントよく当たるよな…」と心の中で呟きながら、遼介は、鈴香が被っているつばの大きな帽子を羨ましげな思いで眺めていた。
と、道路脇の壁に、夏祭りの宣伝用ポスターが貼ってあるのを鈴香は目に留めた。
「ねえ、遼介…。『夏祭り』って書いてあるけど、この辺り、夏のお祭りってまだなの?」
「そうなんだ。…季節的にはお盆を過ぎてるし、暦の上でももう『秋』だろ、それなのに、なぜかこの辺りでは『夏祭り』って昔から呼んでるらしいんだ。何か謂われがあるらしいんだけど。」
と、遼介。
「9月13日、14日の二日間なの…。」
鈴香はポスターの下に記された期日を読みながら呟いた。
「そうなんだ、結構盛大にやるんだよ。『季節外れの大夏祭り』さ。」
「いいじゃない、富山の『風の盆』みたいで。」
「そうだね。…そう言えば、お祖父ちゃんも前そんなこと言ってた。」
「そう…やっぱり。私絶対遼介のお祖父ちゃんと話が合うわ。」
鈴香は本当に嬉しそうに言った。
そして、見覚えのある角が目に入ってきた。
遼介は後ろの鈴香を気遣いながらそこを曲がった。
彼について足をすすめながら、鈴香は何となく不思議な感覚にとらわれていた。
「既視感」というのか…それに似たような、何となく懐かしい感じだった。
それは景色というか、雰囲気というか、その辺り全体から感じられるものだった。
実は、鈴香はこの間の夜も同じような感じに襲われたのだが、同じ場所でのことだった。
言葉では巧く説明できないけれど、何か不思議なものを鈴香は肌で嗅ぎ取っていた。
しかし、鈴香がそんなことを感じているとはつゆ知らず、遼介は先を行きながら告げた。
「お祖父ちゃん…、今日はきっと本館の方にいると思うよ。」
昨日と同じ路地を抜けると、テラスが見えてきた。
色や模様はこの間見た時とは随分と感じが違っているけれど、少し緑のかかった煉瓦色のそれは鈴香のイメージ通りだった。
本館も「黒猫館」も、とても綺麗だった。
そして、これもこの間は気付かなかったけれど、本館と別館の間に大きな欅の樹があり、その木漏れ日がキラキラと輝いていた。
鈴香は思わず駆けだしていた。
3
遼介よりも先に本館の前に到着した鈴香。
後ろを振り返ってにっこり微笑んだ後、嬉しそうに建物の外観を眺めている。
今日は扉に、「開館」と彫りつけられた木製のプレートが掛けられていた。
鈴香にとっては、ちょっぴり緊張感もあったが、それよりも期待感の方がずっと強かった。
穏やかな表情の遼介がゆっくりと追いついて来ると、彼女は入り口へのステップの最後の2段を、タンタンと跳びはねるように駆け上がった。
遼介が入り口の扉をグイと押し先に進む。鈴香はそれに続いて中に入っていく。
古い本の匂い。そして防腐剤であろうか…薬品の匂い。
それらが混ざりあった、何となく懐かしい匂いが漂っている。
そこには小さなガラス窓があった。
「一応、ここが窓口なんだ。」
と、ちょっぴり恥ずかしそうな遼介。
見れば、「大人200円 小人100円」と、白ペンキか何かで書かれた石版が置いてあった。
「大学生は当然『大人』よね。」
そう言いながら鈴香がバッグから財布を出そうとしたところで、脇のドアが開いた。
「おお、遼介か。噂の彼女をエスコートしたのかな。」
鈴香が見ると、そこにはチェックのパンツに革のベストを羽織り、ベレー帽を被った老紳士が立っていた。
彼が、言うまでもなく遼介の祖父であることは明らかであった。
鈴香はちょっと背筋をピンと伸ばし、帽子を脱いでペコリとお辞儀をした。
「こんにちわ。…初めまして、桜井鈴香と言います。
…いつも遼介君にはお世話になっています。今日はお邪魔します。」
と、その紳士は満面の笑みを浮かべ、
「ほほ。これはこれは、ご丁寧なご挨拶どうも、どうも。
私、黒田平蔵と申します。こちらこそ、いつも遼介がお世…。」
その言葉途中、平蔵は一瞬言葉を失ったかのようにポーズしてしまった。そして、
「お世…いや、あ…、の…お世話になっとります。」
その後の慌てた様子は明らかにちょっと普通ではなかった。
鈴香は初対面であるし、「ちょっと、どうしたのかな…?」という感じで、ニコニコしていたが、遼介はそんな祖父の様子に気付いて、
「おじいちゃん。どうかした?」
と、声を掛けた。
が、祖父は、何食わぬ顔で言った。
「いやいや、お嬢さんがあまり美しいので、ちょっと驚いてしまっての。お前には勿体ないくらいじゃわ。ふァっはっは。」
遼介は、その笑い方がすっかりいつもの祖父の様子であることを確認し、ほっとしたが、それでもさっきのは何だったのだろうか…と疑問が残った。
しかし、それは敢えて口に出さなかった。そして、
「もう。お祖父ちゃんはすぐ余計なこと…。」
と、こぼしつつ、
「…お祖父ちゃん。桜井さんは、特に今日は『別館』が見たいんだって。
…彼女は文学部でさ、『猫』をテーマに色々と勉強したいんだ。」
平蔵はそれを聞いて目を細めた。
「そうですか。それは面白いですな。
…まあ、ここは寄せ集めじゃから、余り参考にならないかも知れないけど、ゆっくり見ていって下され。案内は、遼介がするじゃろうけど、分からないことがあれば、何でも聞いておくれ。ワシはここにおるでの。
あ、それから入館料はサービスするから、…の。」
そう行ってウインクをして微笑むのだった。
鈴香は、
「あ、でも。申し訳ないです、払いますよ、ちゃんと。」
「ええんじゃ、ええんじゃ。どうせ道楽でやっとるもんですしの。それに、あってないような入館料ですからな、ふァっはっは。」
「…え、本当にいいんですか。」
「ああ、いいですとも。まあ、そこの台帳に名前だけでも書いといてくれるとありがたいですな。」
「はい。もちろん書かせて頂きます。」
そこには、よくこういう施設にある、来訪者が名前を記帳する台帳があった。
早速鈴香は名前を書き始めた。
平蔵は鈴香のその仕草を嬉しそうに眺めていたが、
「じゃあ、ごゆっくりの。」と言うとまたそこの部屋へと入っていった。
4
平蔵が部屋へ入っていくのを見届けた後、鈴香は言った。
「優しそうなおじいちゃまね。それにお洒落。」
「まあね、でもいつも一言多いんだよね。」
「そんなのどうでもいいじゃない。とっても素敵よ。
私ファンになっちゃいそう。」
「何言ってんだよ。」
そこで遼介は言った。
「でもさ…、いつもの調子なら『ワシが案内しちゃる。』とか言って、しゃしゃり出てきて余計な説明までしくれそうなんだけど、今日は何か調べものでもあるのかな…。」
「あら、そうなんだ…。残念ね。」
その言葉を聞いて、
「あ、そう。オレじゃ不満?」
「いえ、そういうワケじゃないの。
…何だか、気を遣ってくれたのかしら…。」
遼介はちょっと憎まれ口を言ったものの、鈴香の言う「気を遣う」の意味に気づき、「ちょっと野暮だったかな」とちょっぴり反省しながら、
「しかし、普通ならそんなことはお構いなしなんだけどナ…。」
と、小さく呟いた。
鈴香はもう展示物の方へと歩き出していた。
「本館、別館とか偉そうにつけてるけど、実際は凄く狭いんだ。1時間もあれば充分回れちゃう…。」
そんなことを言いながら、それでもまずは本館から、見て回ることにした。
遼介は、鈴香と一緒に歩きながら、展示品に対して知っている限りの知識を披露した。
鈴香も瞳をキラキラと輝かせながら、一生懸命彼の言葉に聴き入って、頷いたり時折は質問したりするのだった。
本館は、以前の話の通り、古民具、昔の藩札や古銭、掛け軸などが一階にあり、二階には作者不明の洋画や工芸品、屏風などが所狭しと並べてあった。
「博物館っていうより『美術館』かな、とも思うんだけど、何だか節操がなくってさ、結局『博物館』なのかなって。」
その言葉に、鈴香は、
「ううん。そんなことない。別に有名とか無名とか、値段がどうだとか考えない方が、その物自体をしっかり見られるから、却っていいのよ。」
確かに、鈴香の言う通りだな、と思う遼介だった。
そして、言葉通り、彼女はそれら一つ一つの物にじっくりと見入っていた。
遼介は、どれだけゆっくり見ても両方で二時間はかからないだろうと踏んでいた。しかし、、実際にこうして説明をしながら回ってみると、本館を7割ほど見て回っただけで、もう一時間が来ようとしていることに、自分でも少々驚いていた。
そして約一時半ぐらいかけて本館の見学が終わった。
「じゃあ、今度は別館だね。」
と、移動を始めようとした時、出口のガラス窓が「ガラリ」と開いて、中から老眼鏡を掛けた平蔵の顔が覗いた。
「どうでしたか、お気に召しましたかな?
…これからいよいよ本番じゃね。」
鈴香は、
「はい。本館も面白かったです、とっても刺激的でした。
…次はいよいよ猫ちゃんたちに逢えるのでウキウキです。」
と愛想良く返す。
平蔵は窓越しにニッコリと笑って、
「遼よ、今日は、あっちは青木さんが来てくれてるから、よかったらお茶でも出して貰え。」
と、見送ってくれた。
テラスを歩きながら、遼介は言った。
「さっきの『青木さん』ってさ…学芸員なんだ。
一応さ、これでも中に何点か市が指定している文化財もあるんで、学芸員の人が事務職員も兼ねて週に二回来てくれるんだ。
…で、今日はその日なんだよ。」
鈴香は、
「ふうん。でも、…失礼だけど、思ってたよりずっと立派だわ。
これをお祖父ちゃん一人で…。『道楽』って言っても、これだけできれば凄いと思う。」
「確かに…ね。」
鈴香の言葉を受け、客観的に考えてみると、確かに祖父は凄いのかも知れない。と、そんな妙な感慨が遼介の心に湧き上がった。
そして、それは決して悪いものではなかった。
外に出ると幾分か陽射しが午後っぽくなっており、テラスの半分ほどはもう日陰になっていた。
南向きの本館の影がちょうど欅の木陰の上にかかり始めている。
鈴香はその影と日向の境目のテラスの上を、小さな子どもが綱渡りの真似をするように両手を横に伸ばしてちょっぴりおどけて歩いて見せるのだった。
そんな鈴香の様子を遼介は優しい目で見つめていた。
5
別館の前まで来ると、あのブロンズの猫が、この間と同じようにちょっと斜め上を見つめてうずくまっているのが目に留まる。
ちょうどそこは欅の木陰になって気持ちよさそうである。
鈴香は「猫ちゃん、こんにちわ」と、ちょっと芝居がかった声を掛けている。
「別館」は、流石に『黒猫館』と呼ばれるだけあって、本当に猫だらけだった。
まずは入ってすぐのフロア。そこには黒い招き猫がずらりと並んで入館者を迎えてくれる。これは圧巻だった。
よくもまあ、これだけ黒い招き猫ばかり集めた物だと思えるぐらい、入り口正面の棚が埋め尽くされている。
実は、鈴香はこれに見覚えがあった。
「あ、これこれ。これが雑誌に出てたのよね。」
とやや興奮気味である。
その様子を、入り口のフロアの端にあるデスクの向こうから、眼鏡の女性がちょっぴり怪訝そうな顔で見ていた。
遼介はそちらに向き直ると、
「あ、彼女…桜井さん。オレの友だちです。」
と告げた。鈴香もぺこりとお辞儀をする。
遼介の言葉が届くと、その女性…青木さんは表情を和らげ、
「ごゆっくり」と笑みを浮かべた。
新館の1階には、堅苦しい事務室や受付窓口のようなものはあえて設けてなかった。入ってすぐの広間には、受付がわりの小さなカウンタがあり、その隅にデスクが置かれているだけで、全体的にオープンフロアのような感じになっていた。
学芸員の青木さんはそこのデスクで細々とした雑務をこなしたり、窓辺に備え付けてある簡単な湯沸かしでお茶を淹れたりして過ごしている様子だった。
遼介によると、平蔵も、学芸員さんが来ない日は、黒猫館でゆっくりしていることも多いのだということだった。
新館は2階建てで、規模的にも余り大きくないのだが、さすがそれを目的として建てただけはある感じで、あちこちに猫の絵やらオブジェやら、また細々とした民芸品の類が巧く陳列されていた。
2階へと昇っていく階段も、途中から一階のフロアを見下ろせるような構造になっていた。
短いけれど、螺旋状になった階段も、幅を広くとってあり、途中にはあちこちに猫の像が置いてある。
「まあ、素敵。」
鈴香はその言葉を連発して、大はしゃぎであった。
が、階段を昇りきったところで、彼女は急に無言で立ち止まってしまった。
それは、すぐそこにある大きな油絵の前だった。
それは、立派な額に入れられた比較的大きなものであった。
ピカソの「青の時代」を思わせるような、全体に青みがかった色調で、そこには石段か何かの途中で坐っている黒猫が描かれていた。
鈴香はその前で暫く無言で立ち尽くしていた。
「その絵、なかなかいいだろ。」
遼介がそう声を掛けたが、鈴香は黙って頷きはするものの、視線は絵に注いだままで、取り憑かれたようにその絵に見入っていた。
そして呟いた。
「私、この絵、どこかで見たことがあるような気がする…。」
6
絵の前で立ち尽くしたまま動かない鈴香に、遼介はもう一度声を掛けた。
「この絵に、何かピンときた? …奇遇だね。
…実は、この絵がお祖父ちゃんの原点なんだ。」
そこで始めて鈴香は遼介の方へと向き直った。その目は真剣だった。
「…この絵って、昔からウチにあってさ。
本当は本館にあったんだ…。多分、地元出身の無名の画家の作品だろうなってお祖父ちゃんは言ってたんだけど、実際よく判らないんだ。
その右隅にサインが見えるだろ? AとTとOって微かに…分かるかな?
『阿藤』って読むのかな…。でも、そんな人はお祖父ちゃんも聞いたこと無いってさ。
ひょっとしたら「アット、オー」かも知れないな…なんてちょっと思ったりもしたんだけどね…。」
鈴香は黙って聞いていた。遼介は続けた。
「…でさ、この絵というか、ここに描いてある黒猫にお祖父ちゃんは取り憑かれちゃったんだって。つまり、何だか妙にこの黒猫ちゃんに魅せられてさ、
それで何時からか猫コレクションを始めたんだってさ。
…それが高じてここまで来たんだ。」
遼介はそこで、一息ついた。
鈴香はまだ黙って聞いていた。が、唇を少し口を尖らせ、何かを確認するかのように小さく頷いていた。その目は穏やかだった。
遼助はそんな鈴香に、
「…だから、この絵もちょくちょく色々な所で紹介されてて…だから、鈴香…それでも見たんじゃない?」
と、問いかけた。
鈴香は、ちょっと考えながら、
「そうかも知れないわね。でも…。」
「でも?」
「何だかちょっと違うような気がするのね。そういうのとは…。」
「そういうの…って?」
「うまく言えない…。」
鈴香はそう言うと、また暫く黙ってその絵を見つめていた。
結局、随分とそこで時間を潰してしまい、その後もゆっくりと館内を回ったので、そんなこんなでかなり時間が経ってしまっていた。
ふと見れば時計はもう4時30分を過ぎていた。
帰り際。
鈴香は、
「お祖父ちゃんにお礼を言って帰らなきゃ。」
そう言って、また本館へと向かおうとした。
と、後ろの方から声がした。
「どうでしたかな。お気に召したでしょうかな」
振り返ると、祖父がベンチに腰掛けてパイプを燻らせていた。脇ではあのブロンズの猫が空を見上げている。
鈴香は平蔵の方へ満面の笑みを浮かべて歩み寄り、
「はい。とってもよかったです。萩原朔太郎の『青猫』の初版本があったのには感動しました。あれ、手にとって見て良かったんですか?」
「ああ、いいですとも。あれも私の想い出の品でしてな…。
…で、研究の資料になりそうなものは見つかりましたかな?」
「はい。まだ自分の研究って、大して進んではいませんが、本当に、参考になりました。よければ、…またお邪魔してもいいかしら?」
「ほうほう。…そうですか、それは何より。お金なんかいいですから、たびたびいらっしゃい。」
鈴香の笑顔を見て、平蔵もご機嫌そうだった。
遼介は、
「彼女、今日はこれからバイトなんだ。だから、駅まで送ってくる。」
と、時計を見た。
すると、祖父はゆっくりと立ち上がり、口を開いた。
「桜井さんとおっしゃいましたな。」
「はい。」
「お嬢さん、…ところで、あなたは、お住まいはどこですかの。」
鈴香はいきなりの質問にちょっと驚いたような目をしていたが、すぐに笑顔になって答えた。
「はい。今はここから二駅向こうに下宿してるんですが…。実家は…。」
彼女は、遼介たちが済む県の隣の県の北部にある小さな町の出身だった。
鈴香の地元には文学部のある大学がなかったので、こちらの大学に進み、今は近くに下宿をしている…と平蔵に簡単な説明をした。
平蔵は、それを聞くと、
「そうですか。あそこは冬場は雪がたくさん降りますよね。」
「あ、ご存知ですか。近くにはスキー場もあるんですよ。」
「そうじゃった、そうじゃった。」
平蔵はにこにこと笑い、そして続けた。
「ところで。お嬢さん。よければ、今度…祭りの時にでもまたいらっしゃい。」
「あ、あのポスターの…」
鈴香は、平蔵の言う「祭」というのが、あのポスターに出ていた夏祭りのことだとすぐに判って答えた。
「そうそう、よろしければ、是非いらっしゃいな。
花火大会もあるしの。ちょうどここから花火もよく見えるんじゃよ…。」
「あ、そうなんですか。私、打ち上げ花火大好きなんです。嬉しいな。」
鈴香は、平蔵が向けた視線の先を見た。
そこは、ちょうど新しいマンションと本館の間で、そこからは遠くが見渡せた。
どうやらそのずっと先に広場か河原があるのだろう、そこだけは何も遮るものが無かった。
「花火の時はの…このベンチが特等席なんじゃよ。」
そう言って、お祖父ちゃんは右手でベンチの脇を撫でながら、また煙草を深く吸い込み、そして紫煙をゆっくりと空へ向けてふーっと吐き出した。
鈴香は、
「はい。じゃあ是非。」
とにこやかに答えた。
遼介は、自分が誘う前に祖父に先を越されてしまったことを、ちょっぴり悔しく感じもしたが、それはそれで、巧くことが運んだことを嬉しく思っていた。
実は、彼も鈴香をお祭りに誘おうと思っていたのだった。
けれど、それをいつ切り出そうかと悩んでいたのだ。その矢先の祖父のお誘いだったのである。
しかし、遼介は、祖父がなぜ急に出身地なんかを彼女に尋ねたのか、それについては分からずにいた。
まさか身上調査…? と、ちょっぴり妙な気もしたが、やはり初対面の時の祖父のあの様子とこれには何か関係があるに違いない…。
と、そう感じた。
しかし、それがどのようなものかということは、あれこれと勘ぐってみても、特に何も心当たりは浮かんでこなかった。
「じゃあ、ありがとうございました。失礼します」
そう鈴香は告げ、遼介と一緒に夕陽が差し始めているテラスを後にした。
第2部終
© Rakuten Group, Inc.