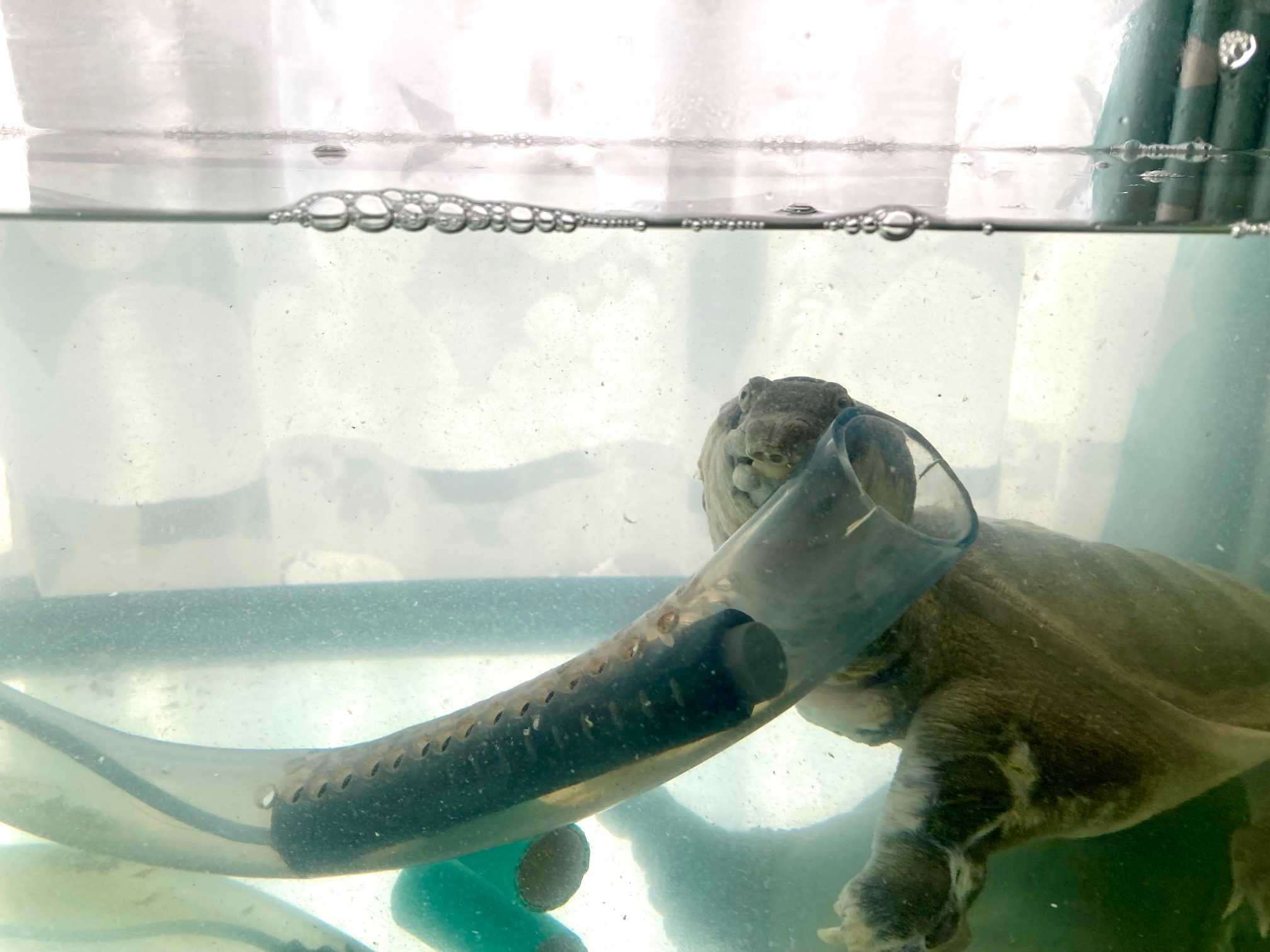2023年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

散歩にて
近所をプラプラ散歩…数日前から 杖なしで歩くようになっている。出会った花たちをパチリしました。アガパンサスユリ…日本と中国はユリの宝庫と言われている。日本のユリを 外国に紹介したのは 江戸末期に来たシーボルト。持ち帰ったユリの球根が、ロンドンでは高値で競売されたとか‥「こんにちわ~」と声をかけたが‥応答なし。二体とも 案山子さんでした。(*´ω`*)都忘れかな? この系統の花は種類が多いので見分けがつきにくいです。したがって名前が違ってたらゴメンナサイですキキョウ今日も いろんな花に出会いました。
2023.06.16
コメント(2)
-

検診の日とネジバナ。
月日の経つのは早いものだ‥大腸の手術をして退院し、ついこの間3月に三か月検診したばかり‥三か月検診の時は、内視鏡カメラで腸の中を検診しポリープを三個切除した。その後、今日まで何事もなく過ごしている。退院後、6か月目の今日の検査は、採血と肺のCT。肺は、三か月検診の時に、少し影がみえる?‥との事で今日、肺のCTとなったわけだが、結果、心配するようなことは無く、腫瘍マーカーの数値も、正常に戻り、良い結果となっていた。帰りにアピタに寄り買い物をする。買い物前に、毎年この時期に ネジバナが咲いている海辺の空地へ…ネジバナ… 別名、モジリバナラン科、ネジバナ属名前の通り小さな花が螺旋状についている。ねじれは左巻き、右巻きなどにこだわりはなく、大体Ⅰ対Ⅰの割合で混在している。ネジバナは 隣り合う花の向きを調整することでハナハチが 隣の花に移動する頻度を コントロールしているものかと考えられている。ハナハチが頻繁に訪れることで、種子生産の面から自己受粉をより防ぐことと考える。ネジバナ、雑草と馬鹿にすることなかれ…見ていると飽きなくて可愛い花です。(*´ω`*)
2023.06.15
コメント(2)
-

ヤマモモ、アメリカデイゴ。
梅雨の晴れ間…少し足を延ばして、いつもとは違った公園へ…芝生の上には…キノコ落ちている赤黒いのは、ヤマモモの実。ヤマモモの実は傷みやすい。ヤマモモは基本無農薬なので、虫がいることもあるので、食べる前にはⅠ時間くらい塩水に浸けて、虫を追い出してから、水でよくすすぎ、冷蔵庫で冷やすと美味しいんだとか‥因みに 私はヤマモモを食べたことがありません。( ;∀;)ヤマモモ…ヤマモモ科、ヤマモモ属の常禄樹中国大陸や日本を原産とする。アメリカディゴ…マメ科の落葉低木。南アメリカ(ブラジル及びアルゼンチン)を原産とする。日本に渡来したのは江戸時代末期。和名…カイコウズ寒さを嫌うため、日本で植栽されているのは、本州南部から沖縄にかけて。地面には、終わった花がら…。
2023.06.13
コメント(2)
-

引き出しの中から‥
あまり使用しない 引き出しの中を片付ける。ど~でもいいような物が、ごちゃごちゃと入っていた。壊れた電卓、今では使えないフロッピーやカセットテープ…そして‥懐かしい? アベノマスク…と自作のマスク…自作のマスクは、色が変わっていた。そうだよねェ…あの頃は、マスクが無くて…すっかり忘れていたよ‥で、全部、捨てた。見てみたい‥と急に興味が湧いた植物がある。で、豊橋動植物園にTELをして聞いてみたら、「今、植物担当の者が席を外していないので、分かりません」との事。結局、その植物があるのか、無いのか‥分からなかった。((+_+))芭蕉その植物は「芭蕉」という植物で、英名は「ジャパニーズバナナ」と言うが、中国が原産と言われている。実がなる事は余りないが、バナナ状となり一見食べられそうに見えるがタンニン分を多く含む種類もある為、」食用には不適らしい。芭蕉の花平安時代の文献上では、古今和歌集に登場していた‥とある。古から庭園や寺院を中心に植栽されていた植物のようで、葉の繊維を利用して「芭蕉布」を織り、衣類などに使用していた。江戸時代の松尾芭蕉は、深川の自宅の庭にあった「芭蕉」を見て自分の名を芭蕉とした…と伝えられている。湿地に咲くあの水芭蕉は、葉っぱが大きくなると芭蕉の葉に似る。そして湿地に咲くことから水芭蕉になった‥と。沖縄ではよく見かける植物のようですが‥
2023.06.07
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- NEXCO激怒発表に反響殺到 「二度と通…
- (2025-11-14 18:00:05)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンでパートナーと相談…
- (2025-11-13 20:30:13)
-