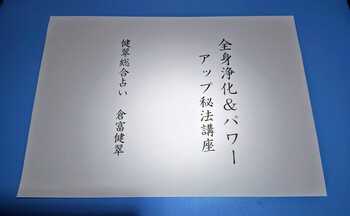おんな紋
おばあ様を思い出した時、その葬儀に一族の女性の着物姿
おんな紋に圧倒される思いがあった。
おんな紋
母から娘へ、女だけにつたえられる紋。
詳しいことは国立民族博物館のホームページ
http://www.minpaku.ac.jp/staff/kondo/wp09.html
玉岡かおるという作家は「をんな紋」という小説も書いている。
ちょっと宮尾登美子を意識した歴史大河ものを最近目指しているような。
彼女は、私と同じ播磨地方出身。書きたい気持ちに駆られたところが理解できる。
女は結婚すると親しんだ苗字を失う。
おばあ様の葬儀で並んでいた娘、孫娘はみな一人として同じ氏でない。
しかし、両胸と背中に同じ紋を持つ。
同じ、筋であると。
私の母は五女である。4人の伯母の子どもはみな男の子。
私の姉が初めての女の孫。祖母はことのほか喜んだという。
わたしには娘ふたり。
おんな紋を伝えていきたいが、時代が必要としないかもしれない。
最後に国立民族博物館のホームページ該当箇所一部を転載。
興味ある方はお読みください。ながいです。
もっと詳しくは上記のホームページへどうぞ。
モノがもつ魂
近藤 調べはじめてわかったことは、かみさんが生まれた姫路あたりでは、それがあたりまえで、結婚するときは「絶対に父親の紋ではいかない。母親の紋でいくという。受け入れる側も、それを当然として迎える。だから、冠婚葬祭の場で夫妻の着物の紋がそろわない。関東では、嫁ぎ先の家紋を問い合わせてから嫁入り道具を用意しますから、夫婦の紋がそろう。紋をそろえるのが、嫁ぎ先の人間になるという意思表示なんですよ。
─ ふん、ふん。
近藤 その後、成城大学の教授だった平山敏治郎さんの『民俗学の窓』(学生社 1981年)を読んで、上方の女性たちのあいだにも同じ習慣があることを知って、調査範囲をひろげました。すると、瀬戸内海周辺地域からも出てきました。いろんなバリエーションがあることもわかりました。
娘に伝えていく「おんな紋」の習慣がきわだっていたのは、 京阪地方と播磨地方、岡山県から広島県にかけて です。で、祖母が岡山県備前市の人だったというお嬢さんが「女三界に家なし、と言われるけれども、女の人の魂は、母方をじゅんぐりにたどっていって、母方の先祖のもとに帰っていく。そのためにおんな紋が必要なんだと聞いて育ちました」と教えてくれたときに「そうか! これなんだ」と思った。
─ でも、どこまでたどれるのか・・・。
近藤 よくわかっている人で五代前くらい。そのへんで止まるんですが、じつは、その止まったところが、たいてい、発生源だったんですよね。
─ 五代前といったら、江戸時代になりますね。
近藤 はい、かみさんの「おんな紋」も、追跡してみたら姫路藩の大庄屋だった某家にたどり着きました。江戸時代になって、武家から足を洗って帰農した有力者の一族が、その後は大庄屋みたいになって続いた。山中鹿之助が先祖だと言う鴻池氏のように、町民になった者もいますけどね。そうした人たちが、もとの家柄を誇るために紋章にこだわっていたんですよ。世が世なら大名のお姫様。そういう感覚なんですね。
そういう家だと、嫁入り支度は、当然、派手になりますよね。そして「おんな紋」をつけて持参した嫁入り道具は、嫁ぎ先の財産にはならないというのが、またふるっている。大坂の船場では、とくにこれがはっきりしていて、店がつぶれて家財道具を売り払っても、お嫁さんの嫁入り道具には、決して手をつけない。「そんなやつは男の風上におけない」っていう風潮があったそうです。それに、離縁されたら全部実家にもって帰る。
─ 「おんな紋」は、いってみれば、家の格をあらわすという感じだったわけですね。
近藤 そうですね。でも、じつは、着物などに「おんな紋」をつける習慣は、昭和20年代から急速にひろまるんです。「娘にはもたせてやった」という例がたくさんでてきたんですよね、アンケートをとってみると。だれもが、経済的に豊かになったからです。で、それまで自分の「おんな紋」をもっていなかった人たちは、たいてい「五三の桐」を着けるようになります。呉服屋さんにすすめられてそうするんです。近ごろは「おんな紋ゆうたら、五三の桐や」って答える人が多くなりました。本来はそうじゃなかったんですけどね。
もともと、女性の着物には、紋は着いていなかった。自分で糸を紡いで縫いあげる着物が女性の財産だとされていたころには、喪服など立派な晴れ着をつくることは、男が家を建てるのと同じくらい価値があった。そういう意味の財産だった着物は、文字通り人が着るものだし、つくった人のおもかげが残るので魂がこもっているように思えてくる。「形見分け」で、なくなった女性のもっていた一番上等の着物が、一番近い身内の女性に与えられるのは、そういう意味があるからですね。
─ モノには、魂だとか、象徴的なものがいっぱい入っているということの 好例ですね。とくに着る物は大事。
近藤 着物以外だと、鏡台です。鏡掛けにも紋を入れるんですね。「姿見」ですから、これも魂がこもっていると感じられる。ちなみに、一番先に嫁ぎ先に運び入れる嫁入り道具は鏡台だったんです。
・・・・・
お疲れ様でした。
© Rakuten Group, Inc.