2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年02月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
地域間格差は大きなチャンス
地域間格差といわれています、地域間格差が開いているためにどうにかしろという論点です、しかし地域間格差というのは逆に言えば大きなビジネスチャンスなのです、宮崎県の最低賃金は619円です、それに比べて東京の最低賃金は739円と120円高くなっています、宮崎の方が東京よりも16パーセントも低い賃金で雇うことが出来ることとなっていますよく言われていることがコールセンターです、コールセンターは東京の高い賃金よりも安い地方に立地をして人件費を浮かすという手段が用いられています、経理なども中国で事務作業をするということが言われています、中国の人件費が安いからです、人件費が安くとも中国でするのではという不安もあるでしょう、逆に日本で安くできるところでやりたいという需要があるのではないのでしょうか、中国では安いけど不安だということを地方は狙えるのではないでしょうか、東京でやるよりも何割か安くすることが出来る、また日本語であるために安心だという安心感を打ち出すことによっ手うまくいけば中国から仕事を奪い返すことができます、またいろいろな事務作業もわざわざ高い東京でやるのではなく地方でやるということも一つの手ではないでしょうかある会社がバイクのエンジンを沖縄で作っていました、沖縄で作ることによりエンジンにmadeinjapanという表示をつけることが出来ます、人件費も安くまた東南アジアから距離が安いために物流コストが低くなるという利点があるためでした東南アジアから物流費が安いということ、また人件費が安区物流費が安いという利点を生かして沖縄旅行でショッピングをして安く買うことが出来るということを生かしてみたらどうでしょうか、地域間格差といいます、逆に考えてみれば人件費が安い地域が出来ていてわざわざカイガイに行かなくともコストダウンをすることができるという利点もあるのです、安い人件費ということを生かせば大きなビジネスチャンスになるのではないでしょうか、地域間格差がhろがることは大きなビジネスチャンスでもあるのです、地域間格差を何とかしろということを国に訴えるのではなく逆に地域間格差を生かしたビジネスということを売り出してみたらどうでしょうか
2008.02.27
コメント(0)
-
道路特定財源と景気悪化
道路特定財源の廃止事態は日本経済自体の縮小再生産をもたらすものでしかありません、日本経済が更に落ち込み韓国にまで抜かれて先進国からの脱落という自体にもなりかねない恐ろしい政策です実際に道路特定財源の暫定部分を廃止するだけで2兆円以上ものgdpが失われてしまいます日本経済が90年代後半から経済成長が止まりました、この失われた10年といわれるものは"土建国家"からの脱却とその生みの苦しみでした、最盛期には建設業は700万人もの雇用がありまた好況事業は名目gdpの8,4パーセントをしめていました、建設業従事者も10パーセント以上も従事しました公共事業が最盛期だった95年には生活保護者が一番少なく生活の貧窮をする人が一番少なかった時代でした、その後政府は公共事業の削減と減税による経済の活性化ということを頻繁に行いました、好況事業のほうが減税よりもどんなに少なくミッ持っても数十パーセントも効果があります、効果がある好況事業を削り減税をしたことにより国の経済は疲弊をきたしてしまい、97年をピークにgdpが数十兆円も落ち込む事態となってしまいました、また公共事業は雇用を生み出し健康で文化的な最低限度の生活をもたらすものでした、しかしこの公共事業悪玉論によってその健康で文化的な最低限度の生活を営むための措置が壊されてしまいました、10パーセントあまりを占めている建設業従事者ですがホームレスの54パーセントもの人が建設作業員でした、公共事業は日本版セフティネットでした、このセフティネットを壊してしまって新たに何を作るのかということが問題となってきます無駄な公共事業といっても、その無駄な公共事業で食べている人がいるのです、公共事業がなくなったならばこれらの人のセフティネットをどうするのかという問題も含めて考えるべきです、その部分も含めて暫定事業の廃止を語るべきです
2008.02.27
コメント(0)
-
製造業は日本を救うことが出来るのか
製造業は日本を救うことが出来るのだろうか、製造業が強い日本やドイツは先進国の中でも低成長にあえいでいる、逆に製造業に見切りをつけたアメリカやイギリスなどでは高成長を続けている、製造業が強いといっても日本で製造業に従事している人は昨年12月現在でたったの1166万人全集業者数のたったの18,23パーセントとなっています、平成15年の12月と昨年の12月を比べると就業者数が6307万人から6396万人まで増えています、日本の景気が回復してきたのはものづくりが好調だからだそうです、しかしものづくりは雇用という面ではマイナスとなっています昨年の12月は1167万人だった製造業従事者数が今年の12月には1万人減少しています、逆に平成15年の12月に比べて4年間で16万人も減少しています逆に情報通信業は平成15年の12月から150万人が213万人へと63万人も増えています、医療、福祉は平成15年の12月が509万人、昨年の12月が587万人と78万人も増やしていますサービス業も851万人から935万人へと84万人の増加となっています、ぺティークラークの法則にあるように、経済が成熟化していくと第3次産業へとシフトしていくということなのです、優秀な企業経営者やマスコミなど庭セルと日本は優秀な”ものづくり国家"なのだそうです、しかしものづくりでは国民を食べされてはいけない、サービス産業などの第3次産業へシフトしてきているということが如実に現れてきています、道路の暫定議論などを見ていると日本はものづくり国家などと勘違いをしてしまいます、しかし今はテレホンオペレータや医療、福祉などの第3次産業の時代なのです、いつまでもものづくりということにこだわっているのでしょうか、
2008.02.27
コメント(0)
-
土建国家はいつ終わったのか
土建国家といわれて久しい、道路整備特別会計の暫定問題にかかわる集会などを見てみると未だに土建国家だとおもわれるかもしれないこれは土建国家の最後の残った本丸をどうするかということだけでありが土建国家としての日本の幕は閉じつつある土建国家日本、その公共事業が一番行われたいたときが79年だった、そのときのgdpに占める割合が9,8パーセントだった、その後建設業が冬の時代といわれて公共事業藻減り続けていた、しかしバブルの崩壊による公共事業により建設業の事大が終焉しかけてきたのが再び復活した一番建設業の従事者数が多かったのが97年8月、そのときの建設業従事者数はちょうど700万人だった、その月の就労者数が6590万人で全就労者数に占める割合が10,62パーセントだった、それが昨年の12月には建設業従事者数が537万人まで減ってしまった、又就労者数しめる建設業従事者数は8,39パーセントまで2,23パーセントも減っている、土建国家の終焉が日本にもたらした副作用が日本経済自体を苦しめている、各地域で公共事業を行い地域の均衡ある発展を合言葉にしていた、また公共事業をすることにより困っている人を救う日本独特のセフティネットが出来上がっていた、生活保護者数が最低になったのは95年、その年には公共事業が一番行われた歴史的な年だった、そのあと06年までの11年間で半分以上に減少ををしてしまったこの年を境に生活保護者数が増加をした、又90年代後半になると日本独特の公共事業の大幅な減少によりセフティネットの恩地を受けられない人が急増してきた、00年代後半になるとネット難民や日雇い派遣という公共事業というセフティネットを受けられない人が大幅に増えてきた、道路特別会計の暫定部分の撤廃は大幅な公共事業の減少、それとともに建設業従業者数の失業問題、又最後のセフティネットが崩れてしまうという危険性もはらんでいる、公共事業に変わる新たなるセフテイネット網の創設というものを行わなかった、又公共事業に変わる新たなるリーディング産業を創設できないことによる0日本経済は生みの苦しみを体験しているのだ
2008.02.27
コメント(0)
-
命のガソリンから命の道路へ
今回の問題は賃金5原則の中の一定払いの期日です、賃金は期日が特定されていて、期日が周期的に到来する、一定期日に支払う必要がありますそのために毎月最後の週の金曜日などというものは認められていません休業手当は賃金の一種と解されています、そのため賃金支払日に支払う必要があります命の道路などという言葉を良くききます、道路整備が他の地域に比べて遅れている為に使われている言葉です、道路整備のために使われている命の道路という言葉は安いガソリンや軽油などの価格だからこそ言えるのです、ガソリン格価格が高騰を続けていいます。今の150円台が160円台にさらに170円台にあがっていった場合には命の道路ということが本当に言えるのでしょうか、ガソリンが高くなり、車を使って買い物に行く頻度が少なくなり、又ガソリン代が高くなった為に他の消費を抑制して景気が悪くなる、その場合今のように安いガソリン価格を下げる為に石油にかかる税金を下げるべきだという声が高まってくるでしょう石油価格は需給の面で言えば今の半分ぐらいの価格だといわれています、しかし投機的な資金が流れ込んで高くなっているとも言われています、実際は投機的資金+将来を見込んだ先物買いというのも原因ではないかと思われます、というのも中東の油田が枯渇をし始めているのではないかということでした、サウジアラビアでも06年度の石油の産出量が減少したという情報もあります、又増産余力が高いといわれていたサウジアラビアでも石油の増産をすることができなくなった、巨大なカフジ油田でも自動的に石油が出てきたのが今では水を注入して巨末意的に原油を産出しているという状態です、北海油田は枯渇をし始めて99年以降石油の清算が原書しています、イギリスでは石油の輸出国から輸入国へと変わっていしまいました巨大油田の発見がなされていず、開発をしやすいところはあらかた開発をしてきてしまっています数年後には石油の清算がピークに達して、そのあと産出量が減少するという予測もありますガソリンが高くなっても命の道路として暫定価格を引き下げないで道路計画を進めないのでしょうか
2008.02.27
コメント(0)
-
グローバル化からローカル化へ
ついにニューヨークでも1バレルが終値で100ドル台となった、いったいいくらまで石油の値段が上がることのなるのだろうか、この石油の値段がどんどん上がるようになってくると世界規模で進んでいるグローバリゼション化が後退することになる今までは安いガソリン価格ということを前提として経済の仕組みが組み立てられていた、そのためにグローバル化が進んだ、しかし高い値段になるとグローバル化が進まなくなってくる海外へ物を運ぶこともできた、このまま石油の高騰が続くと物流費に跳ね上がってくる、今までは石油の値段が安い為に海外から物を運んできた方がこすとてきにゆうりになってきた、人件費などのコストが高くとも物流費の安い近くの工場の方が有利になるということが起こってくるのではないのか又海外に気軽に行っていたのが燃料費が高くなってしまったために気軽に海外へ行くことができない時代になってきている、人と物の流れが滞っていくことになる、昨年は石油の高騰のおかげで海外旅行に行く日本人の数が減少した、石油の高騰により航空料金が何万円も高くなり物流費も高くなる、今までの世界経済は石油などのエネルギーが安いという前提で成り立っていた、油田の枯渇の始まり、又新規油田の小型化、石油需要の伸びの増加などを加味すると石油の値段が大幅に下がることは難しい、石油の高騰はグローバル化の後退とローカル化が進む、その分貴店に今果たさされているのではないのか
2008.02.27
コメント(0)
-
ものの見方
いろいろなものの見方というものがあります、たてから見るのと横から見るのでは違って煮えてきます、今話題になっている道路の暫定問題も各方面から見ればどうなるのだろうかということを見て生きたいと思います建設業者から見れば道路特別会計で工事などを受注をしているのでやってほしい一方一般の庶民から見れば道路特別会計で高い車の維持費やガソリンを払っているのでやめてほしい、運送業者から見たら高い軽油代やトラックなどの維持費がかかる、それが負担になっているのでやめてほしい製造業などの会社の経営者からしてみると、車の維持費が税金で持っていかれる、また軽油代などが高いために物流コストとして跳ね上がってくる、それが国際競争力を弱めることになってくる社会保険労務士などの社会保険の専門家から見れば暫定税率があるために車を持つ人の税負担が高くなっている、そのことが従業員の給料にも跳ね返って国際競争力を弱めれている、更に暫定税率があるために高い給料を払わざる得ずそれが社会保険や労働保険などに跳ね返ってくる、もしそれがなくなれば社会保険料などが軽減されるという利点があります、
2008.02.27
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-
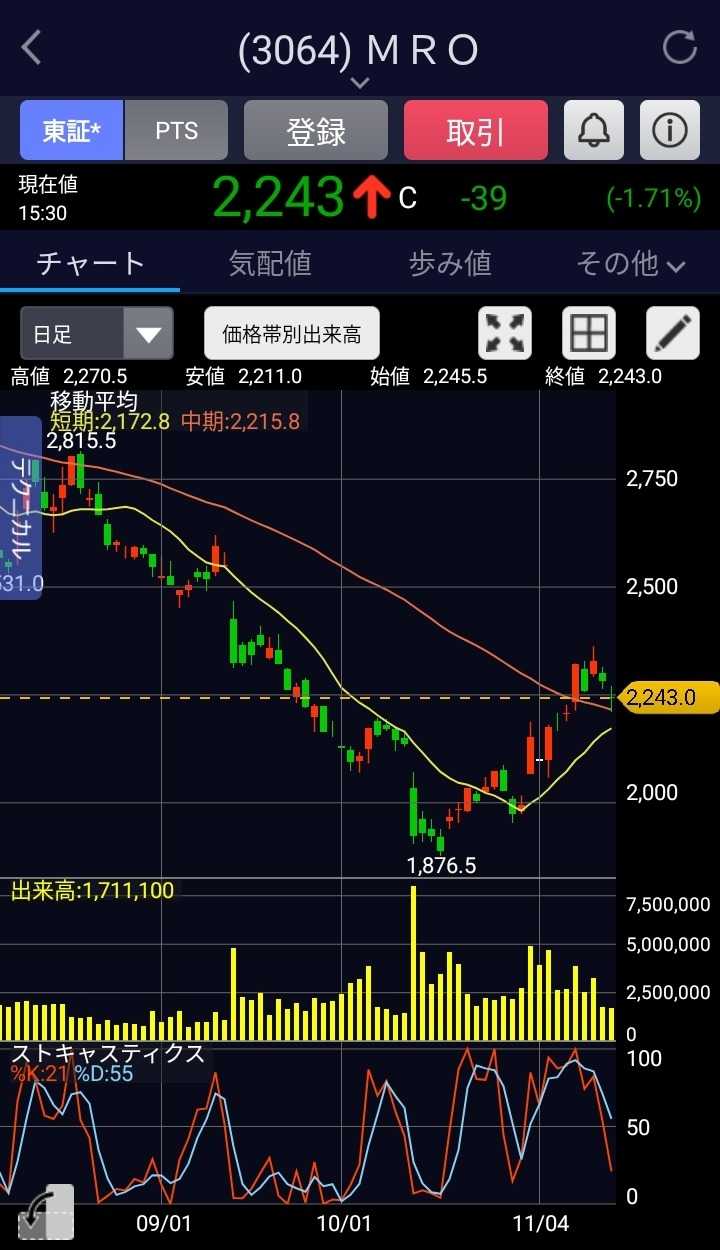
- 株式投資日記
- 株式資産は減少、精神的な不安定回復…
- (2025-11-14 17:07:04)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 情報漬けになるな!!
- (2025-11-14 08:02:13)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…
- (2025-11-14 19:41:15)
-


