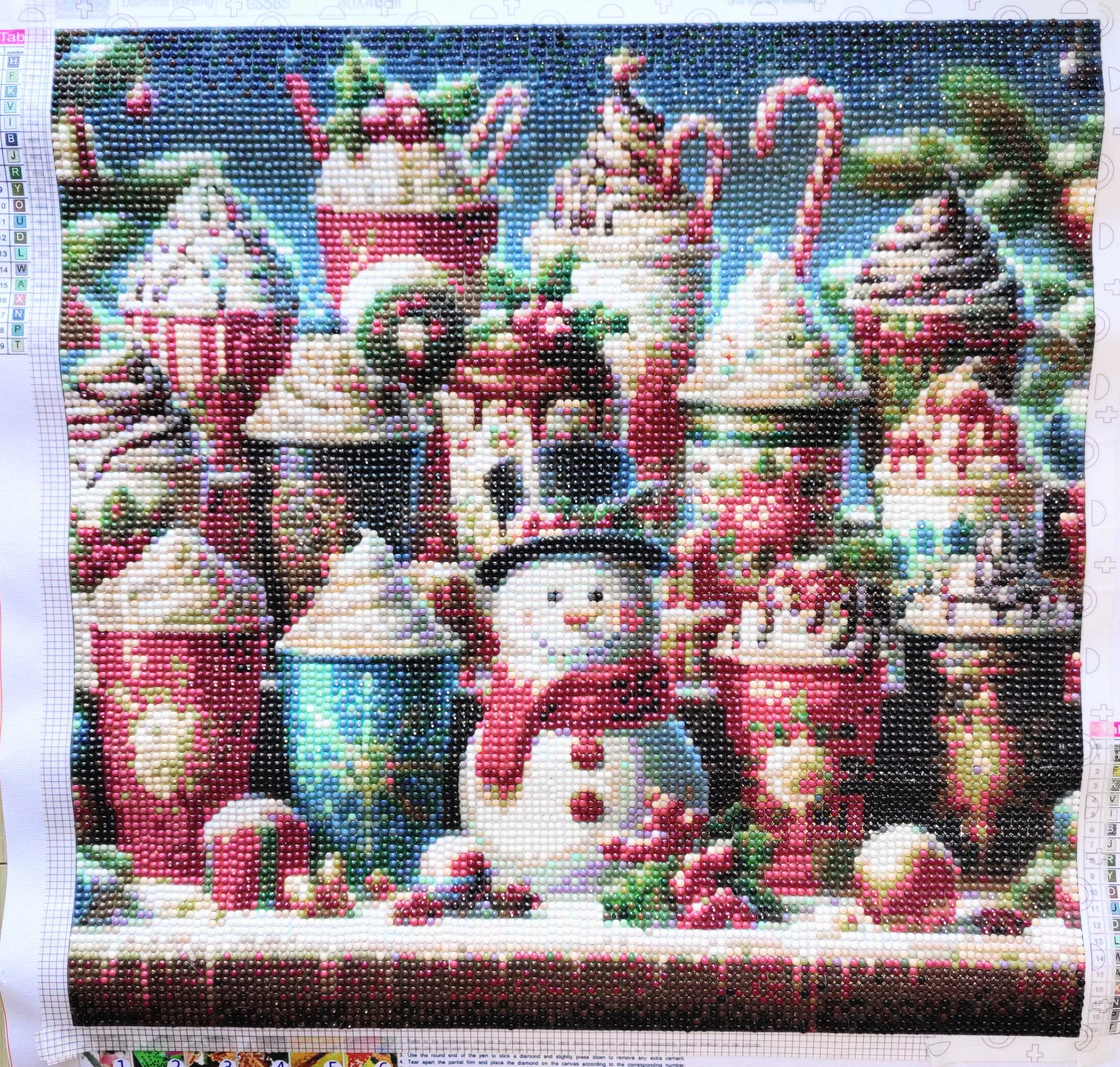ことわざ/状況別(ビジネス・訓話)
人気blogランキング
商い三年
(あきないさんねん)
└商売は始めてから三年くらいたたなければ、利益をあげ
るまでに至らない。三年は辛抱せよということ。
商いは牛の涎
(あきないはうしのよだれ)
└商売は、牛のよだれが細く長く切れ目なく流れ出るよう
に、こつこつと気長に辛抱せよ、利益を急ぐなという意。
浅い川も深く渡れ
(あさいかわもふかくわたれ)
└たとえ浅く見える川でも、どんな危険が潜んでいるかわ
からないもの。深い川を渡るように、用心が肝要である
ということ。油断を戒めることば。
生き馬の目を抜く
(いきうまのめをぬく)
└生きている馬の目を抜くほどすばしこいという意。ずる賢
く立ち回り、他人を出し抜いてすばやく利益を得ること。
油断もすきもないさまのたとえ。
一将功成りて万骨枯る
(いっしょうこうなりてばんこつかる)
└一人の将軍が挙げた立派な手柄の陰には、多くの兵卒の
痛ましい犠牲があるということ。縁の下の力持ちとして
陰になって働いた、多くの部下たちの苦労が顧みられず
に、指揮者・代表者にだけ華々しい功名が与えられるこ
とを嘆くときにいう。
一寸先は闇(の夜)
(いっすんさきはやみ(のよる))
└「一寸先」は、ほんの少し先の未来の意。未来は闇の中
にあるようなもので、ほんの少し先であっても何が起こ
るか前もって知ることはできないという意。未来のこと
は、まったく予測できないというたとえ。
一銭を笑う者は一銭に泣く
(いっせんをわらうものはいっせんになく)
└たった一銭、と笑う者は、その一銭がなくて困るはめに
陥るということ。たとえ非常にわずかな額でも、金銭は
大事にしなくてはならないという戒め。また、わずかな
額でも心がけて節約や貯蓄をするように勧めることば。
一擲乾坤を賭す
(いってきけんこんをとす)
└「擲」は投げる、「乾坤」は天地の意。天下を取るかす
べてを失うかの思い切った大勝負に出ること。
売り出し三年
(うりだしさんねん)
└商いは開業当初が経営も苦しく、辛抱が必要だが、三年
もすれば軌道に乗るものだという教え。
運根鈍
(うんこんどん)
└成功するためには、幸運に恵まれること、根気があるこ
と、鈍いと思われるくらい粘り強いこと、この三つが必
要だということ。「運鈍根」ともいう。
飼い犬に手を噛まれる
(かいいぬにてをかまれる)
└普段かわいがっている自分の犬に噛みつかれる。日ごろ
面倒をみたり、かわいがっていた人や部下から、思いが
けずに裏切られたり、損害を受けたりすることのたとえ。
隗より始めよ
(かいよりはじめよ)
└遠大な事業を起こすときでも、まず手近なことからやっ
てみるのがよいということ。また、何事も言い出した本
人から始めよ、の意にも用いること。
風が吹けば桶屋が儲かる
(かぜがふけばおけやがもうかる)
└一つの事件が予想もできないような結末を招くこと。見
込みのないことを当てにすること。
危急存亡の秋
(ききゅうそんぼうのとき)
└「秋」は大切な時期の意。危険がそこまで迫っていて、生
き残れるか否かの、瀬戸際の意。出典は「諸葛亮」。
鶏口となるも牛後となる勿れ
(けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ)
└大きな集団で人のあとにつくより、小さな集団でもその
長となれという意。独立心の貴重なことを説いたことば。
好機逸すべからず
(こうきいっすべからず)
└よい機会は逃してはならないということ。
狡兎死して走狗烹らる
(こうとししてそうくにらる)
└獲物の兎が狩り尽くされると、猟犬は煮て食われてしま
う。敵国が滅びると、戦功のあった忠臣も不要となって
殺されてしまうということ。役に立つ間は大切にされる
が、不要になると捨てられるたとえ。出典は「韓非子」。
先んずれば人を制す
(さきんずればひとをせいす)
└人より先に行えば、有利な立場に立てるということ。
小異を捨てて大同につく
(しょういをすててだいどうにつく)
└小さな意見の違いは問わずに、重要な点が一致する意見
にしたがうということ。
賞は厚くし罰は薄くすべし
(しょうはあつくしばつはうすくすべし)
└褒美は過分に与え、罰はできるだけ軽くするのがよいと
いう教え。
商売は草の種
(しょうばいはくさのたね)
└商売は草のようにたくさんの種類がある。商売の種は尽
きないということ。
末大なれば必ず折る
(すえだいなればかならずおる)
└枝や葉が茂って重なると、どんなに頑丈な幹も折れて
しまう。転じて、組織は下の者の勢力が強くなると、
上の者が統率できなくなるというたとえ。
前車の覆るは後車の戒め
(ぜんしゃのくつがえるはこうしゃのいましめ)
└前を行く車がひっくり返ったら、あとから来る車は注意
する。転じて、先人の失敗はあとに続く人の教訓、戒め
になるということ。
船頭多くして船山へ上る
(せんどうおおくしてふねやまへのぼる)
└指揮する人が多くてまとまりがつかず、物事がまったく
的はずれな方向に進んでしまうことのたとえ。
創業は易く守成は難し
(そうぎょうはやすくしゅせいはかたし)
└「創業」は、新しく事業を興すこと、また国の基礎を固
めること。「守成」は、できたものを堅実に守っていく
こと。事業を新しく興すのは容易だが、それを受け継ぎ、
衰退しないように維持していくことは難しいということ。
損して得取れ
(そんしてとくとれ)
└一時は損をしても、それが結局大きな利益に結びつくの
ならば、目先の小さな利益を捨てて、あとの大きな利益
を得るほうがよいということ。
治にいて乱を忘れず
(ちにいてらんをわすれず)
└泰平の世でも乱世を忘れない。いつでも万が一のときの
用心を怠らないこと。
朝令暮改
(ちょうれいぼかい)
└朝に出した命令を夕方に改めること。法律や命令が次々
に変わって定まらないこと。出典は「漢書」。
時は金なり
(ときはかねなり)
└刻々と過ぎ去る時間は、金銭と同じように貴重であると
いうこと。時間の貴さを教えることば。
泣いて馬謖を斬る
(ないてばしょくをきる)
└秩序・規律を保つために、愛する者でも私情をはさまない
で処罰せざるをえないことのたとえ。出典は「十八史略」。
為せば成る
(なせばなる)
└物事は、やる気になってやれば何でもできるということ。
名を棄てて実を取る
(なをすててじつをとる)
└名声や名誉を得るよりも実利を取るほうが賢明であると
いう意。
日計足らずして歳計余りあり
(にっけいたらずしてさいけいあまりあり)
└日々の計算では儲けがないようだが、一年を通しての計
算では利益が出る。目先の利はないが、長い目で見れば
利益が上がること。
猫の手も借りたい
(ねこのてもかりたい)
└猫の手さえ借りたいという意から、だれでもいいから手
伝ってくれる人が欲しいほど、忙しいことのたとえ。
敗軍の将は兵を語らず
(はいぐんのしょうはへいをかたらず)
└戦争に敗れた将軍は、軍事について発言する資格はない。
失敗した者は、そのことについて意見を述べる資格はな
いというたとえ。出典は「史記」。
裸一貫
(はだかいっかん)
└財産や元手など何もないこと。頼りになるものは自分の健
康な身体だけであるということ。男性に対してのことば。
万卒は得易く 一将は得難し
(ばんそつはえやすく いっしょうはえがたし)
└多くの兵卒を集めることは簡単だが、優れた大将は一人
といえどもなかなか得られない。指導力や統率力を持っ
た人物は少ないものであるということ。
一旗揚げる
(ひとはたあげる)
└新しい事業を起こす、また一仕事をして成功すること。
勇将の下に弱卒なし
(ゆうしょうのしたにじゃくそつなし)
└勇気ある強い大将の下には、弱い兵はいないという意。
指導者や上役が立派であれば、部下も感化されて優れた
働きをするということ。
寄らば大樹の陰
(よらばたいじゅのかげ)
└雨宿りなどで身を寄せるには大きな樹の下がよい。頼る
のであれば、力のある人や大きな組織のほうがよいとい
うたとえ。
© Rakuten Group, Inc.