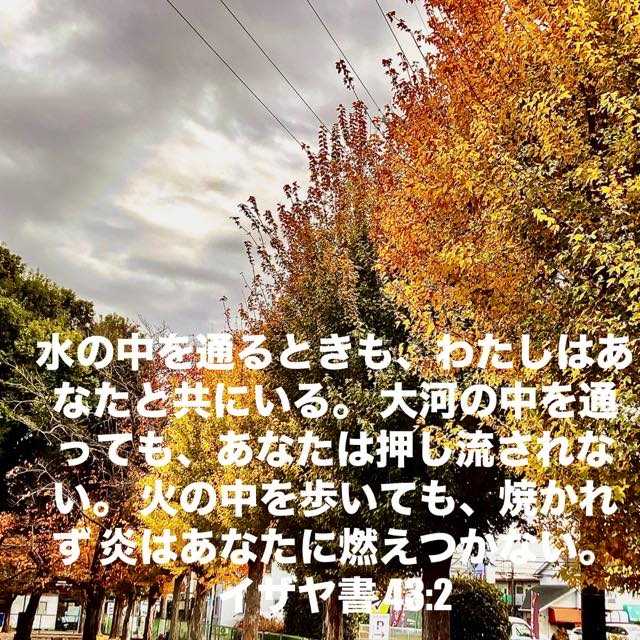楽園のサジタリウス3 七
「いててて……あー痛い。麻紀の奴いくらなんでもあそこまでやらんでも……いいよなきっと。まあチクられなかっただけよしとしなきゃ」
深夜。見張りを除くほとんどの隊員が寝静まった中、松明の灯りも少なくなった即席露天風呂に一機一人が浸かっていた。
結局麻紀は一機の悪行を誰にも言わなかった。いつの間にか縄がほどけてボコボコにされてたことについては完全黙秘を貫いたので誰にもバレていない。まあ戦闘準備中だったから端で死んでる男になんか構っていられなかったからというのが正直なところだが。
そんなこんなで、一機が目を覚ましたのはもう夜。仕方なくこんな夜更けに入らざるを得なくなった。せっかくあるのにそのまま寝るってのはもったいないし。
「しっかし、あーいい湯だ。疲れ全部溶けていってるみたい……ブクブクブクブク」
まあこの際満天の星空の下一人占め気分を楽しむことにした。巨大な赤い月が不気味といえば不気味だが、よく見ればなかなか風情があるように思える。思うことにした。思うことにしよう。
とりあえず温泉は文句なし。湯加減もちょうどいいし広さも抜群、首まで浸かってバシャバシャ叩いて楽しんだ。
「にしても……さっきのあれ、何にも出なかったよなあ。この峡谷入って敵の攻撃は落とし穴と岩落としのトラップかはてまた鳴子ぐらいしかないし、はっきり言って拍子抜けだな」
一機の言う「さっきのあれ」とは、無論入浴中に近くに敵がいるかもしれないといったことである。
あの後(一機が気絶している間)親衛隊隊員たちはすぐさま着替えて鎧を装着し、武器を手に取りMNに搭乗した。さっきまで入浴していたと思えないほど素早い動きだったらしい(麻紀談)。
が、そんな神速で戦闘配置についたにもかかわらず――何も、誰も来なかった。
崖の上に露天風呂を作るくらい、少なくとも石ケンがあるということは近くに誰かがいることは確実なはずが、誰も襲撃して来ず矢も剣も飛んでこなかった。ただ完全武装の親衛隊がその場で緊張しつつ待ちぼうけを喰らっただけの結果に。なんだか間抜けである。
「だけど、どうして何にも来ないんだか……夜襲に来る気配もないし。ここの墓守はどうした……いや、まさかな」
一機の脳裏にまたあの『疑念』が浮かんだ。それはほぼ確信となっていた。それが事実なら……嬉しいというか幸運というか。しかし確証がないので口にはとても出せなかった。多分、他の連中も気付いているが同様なのであろう。
だが、だとするとこの石ケンは……
「まあいいか。必要なことはあっちが考えるだろうし、俺の意見なんか聞いてくれるわきゃないしなあ」
「そう腐るな。最初から決めつけていては何も始まらんぞ」
「うっ、え!?」
一人言を返され、びっくりして振り返る。
果たしていたのはヘレナだった。しかもバスタオル一枚という刺激の強過ぎる姿で。いや、全裸見といてなんだけど。
「ちょっ、ヘレナさんなんで!? さっき入ってたのに!」
「ああ、どうも寝付けなくてな。嫌な汗をかいてしまったら入りなおそうと思ったんだ」
「なるほどね……って納得できるか! 俺が先入ってるんですけど!?」
一機は湯の中でオタオタしているのに、ヘレナはバスタオルなどで隠しきれないその豊満な身体をそのままに平然とした様子。なんだ、女という生き物は布切れ一枚で羞恥心が消えるのか。だとしたら顔を真っ赤にしているであろう自分が馬鹿みたいではないか。
「わ、わーったよ! 俺はすぐ出るから、後はごゆっくり!」
「待て、お前体ちゃんと洗ったのか?」
「え? ま、まだだけど……」
「風呂に入って身体も洗わん馬鹿がどこにいる。ほら、洗ってやるから出ろ」
「はい? ちょっ、なっ!?」
言葉の意味を理解できないまま強引に引きずり出される。あわててタオルで大事な部分を隠した。
「い、いえ結構です! ていうかこんなとこ隊員に見られたら今度こそ殺されるわ!」
「心配するな、もう夜中だぞ? それに、そんなことする奴はウチの隊にはいない」
何言ってんださんざん殺そうとしただろ! と言いたい一機だったが、それ以上告げなくなってしまう。まあ彼女たちが本気なら自分なんかとっくに殺されていたろう。そう思っているうちに木製のイスに座らされた。
「さあもうおとなしくしろ。ほら、髪洗ってやる」
「……お手柔らかに」
ここまできたら観念するしかない。タオルを腰に巻いて、決してヘレナの方を向かず目をギュッと閉じた。頭の中で雑念払おうと般若心境を唱えていたら、頭からバシャッとお湯をかけられる。
「あち、あちちっ!」
「こら、じっとせんか。頭洗ってやるから。石ケンは……ああ、これか」
さすがにシルヴィアにシャンプーなんて便利なものはない。ヘレナが石ケンを泡立てている音が一機の耳に伝わってくる。
「よし。それじゃ、頭動かすんじゃないぞ」
「あいよ……うおっ?」
むにっと、非常に柔らかく懐かしい感触のものが背中に押し付けられた。
何事か、と確認する前に脳髄に電気信号が走り一機の体を硬直させた。
「ふむ……一機、どうだ、かゆい所とかあるか?」
「ソウデスネ、ゼンシンカイテクレルトアリガタイノデス」
「はあ? お前どうして声上ずらせているんだ?」
ヘレナの声が近く聞こえる。本当に近く、息がかかるくらい。
そしてこの感触。数日前にも味わった。あの時は顔でだったが。
すなわち、この女は一機の背中に胸を押しつけている。
――って、何してんすかぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!
心の中で大絶叫する。肉体は硬直して動けないが、マインドにいる一機は悶絶打っていた。
そりゃ俺ちょっと前かがみになってるかもだけど、そこまでひっつかなくてもいいというか、わざとか、わざとなのかぁ!! ああ、柔らかい感触が、ああ、ああああああああぁ!! と脳が見たこともない斬新な激しい踊りを乱舞する。
「うん? お前もうちょっと頭を上げんか。これではやり辛くて仕方ない。ほら、もっと」
「いいえ、このままでお願いします」
理性はブレイクダンスを踊りながら崩壊寸前だというのに本能は煩悩フルスロットル。言った後で口勝手に動くなぁぁぁぁぁぁぁぁっ!! とわめいたところでどうしようもない。胸に加わり細くしなやかな指のなめらかさが頭蓋から伝わり頭と背骨が溶けそうになる。
「一機、さっきからどうしたんだ? 呼吸も荒いしどこか小刻みに震えている。顔を心なしか真っ赤に思えるし、のぼせでもしたか?」
「――なら、水を思いっきりかけてくれるとありがたいのですが」
「なんだ、元気ではないか。あいにくそんなものはない、湯で我慢しろ」
ちょうど洗い終わったのか、湯を桶でザバッとかけられた。うむ、少しは正気に戻れた。
「どうだ、さっぱりしたろう?」
「ありがとうございます。では、お返しに頭を洗って差し上げましょうか?」
「おお、そうしてくれると助か――いや、やはりいらん。一人でできる」
「かしこまりました」
丁寧に礼をしつつ、なんだか昂ってた興奮が一気に冷めていくのを一機は自覚していた。
間違いない。こいつ俺のこと男扱いしてねえ。
前回のは不意打ちだったし、それなりの恥じらいというものは当然持ち合わせているのだろうが、俺のことを男とはあまり感じてはいないらしい。バスタオル一枚という無防備過ぎる姿もその証だ。
――まあ、ヘレナは王女様だし、しかも騎士だからこんな枯れ木みたいな細くて頼りない男は相手にしないんだな。きっと体長二メートルくらいあってもっとムキムキしてヒゲとか胸毛とかモジャモジャしてて化け物ウサギとか生で骨ごとガブリとかできて……あれなんでだろう、無性に殺したくなってきた。
自分で作った男と仲良くなるヘレナ思い浮かべ殺したくなるというアホなことをしていると、ヘレナが心配した様子で声をかけてきた。
「一機、本当にお前おかしいぞ? 大丈夫なのか?」
「――問題ないです」
「そうか……? まあいい、今度は背中を洗ってやろう。ほら、そっち向け」
「――ありがとうございます」
もう血が上ることもない。身も心も完全に冷めきり背を向ける。
そりゃ、男として自分が頼りないのはわかる。運動なんか全然やらんし体力もない。腕力に至っては弓道やっている麻紀にも劣るだろう。こんなモヤシシルヴィアでは虫けら以下かもしれない。しかし、いくらなんでもこうあからさまだと……と地面にのの字を書きながらネガティブスパイラルに陥っていると、背中にピタとタオルを付けられゴシゴシこすられる。
「どうだ、強くないか?」
「あーちょうどいいです。て言うか慣れてますね。普通王女様だったらお付きの従者が体なんか洗ってくれると思いましたが」
「はは、お前の国ではどうだか知らんが、私は王女である前に騎士だぞ? 大抵のことは一人でできんでどうする。……まあ、皆と風呂に入ると私が洗うとうるさいんだがな」
なるほど、あの隊長様が好きで好きでしょうがない連中はその手で愛するお方の裸を間近でガン見したり肌の感触を味わったりしているのか……それ以前にこの人寝込みとか集団で襲われたりしないんだろうか? さすがにそこまでしないのがあるいは互いにけん制し合っているのか。恐らく後者だと一機は推測する。
「ほら、後ろ終わったからこっち向け」
「え!?」
「何を驚く。別にいつもの……いや、なんでもない」
またしまったという顔をされた。なんだか嫌気が刺した一機は言われるまま前を向こううとしたが引っぱたかれてしまった。ううん理不尽。
そんなわけで、タオルを借りて自分で体を洗っていると、ふと後ろにいるヘレナに話しかけた。
「そういえば……ヘレナって、妹いるんでしたよね。王女様の」
「うん? ああ、姉上がな。私と同い年だが」
「え、双子だったの?」
「そうだ。姉上は私と違って騎士にはならず、王女としての執務に尽くしている。とても聡明で次期女王としてはふさわしい方だ……まあ、少し気弱なところはあるがな」
気弱、と聞いて一機は気弱で聡明な文系ヘレナを想像しようとした……が無理だった。このヘレナの弱気というか女らしい顔なんかまったく思い浮かばない。……体の方は百パー女だが。
「……一機、お前何か失礼なこと考えてないか?」
「いえ、何も」
どうして俺のまわりの女はこう勘が鋭いんだろう、なんてことを考えていると湯をかけられた。
「ああ、ありがとうございました。じゃ、お礼に洗ってあげますね」
「うむ、頼むぞ」
「それでは前から洗いますのでタオルを取ってこちらへ向いてください。」
「わか……って何を言ってるんだお前は!」
「もうちょっと早く気付いてくれないかなぁ!」
その間二十秒。一機からすると「いっそこのままやっちまったほうがいいんじゃないか」と悩み苦しんだ二十秒であった。
「いい、一人でやるから、お前は湯に浸かっていろ」
「了解です」
泡を流した一機はそのまま湯船に戻る。風呂から出ればよかったのではないかと思ったが入った後ではもう遅い。ゴシゴシとヘレナが体を洗うのを聞いていると、湖で見た絶景(からだ)がオーバーラップして緊張のあまりカチコチになり出るに出られない。
「そ、そういや第一王女の双子の妹ってことは、王位継承権は第二位ってことだよな? それじゃ他に王位継承権持った人っているの?」
「うん? 正式に王位継承権を持っているのは姉上だけだ。私は騎士になったときに返上しているからな」
「え? 他に異母姉妹……あ、いや、女王制だから異父姉妹か。他に第三王女とかいないの?」
「おいおい、異父姉妹などいないぞ。仮に王位継承権を持った女王の直系が亡くなったら、緊急に王族から出すことになっている。まあ、シルヴィア五百年の歴史でそんなことは一度もなかったがな」
「ふうん、俺の世界の王なんか自分の親族残すために側室バンバン作ってたけどね」
「そんなハレンチな真似男系国家だからだろ? シルヴィアではあり得んよ」
「――てことは、ヘレナは妹とか弟とかいないんだ」
「ああ」
一機の脳裏には、あの時借りた鎧に書かれた名前が浮かんでいた。
「ハンス・ゴールド……ねえ」
「何か言ったか一機?」
「あ、いえなんでも……ってわぁ!」
いつの間にかヘレナはもう洗い終えており、湯船にちゃぷと入った。あわてて出ようとしたが自分のタオルがどこかへ行ってしまったため出られず、せめてもと少し離れ明後日の方を向く。
「そういえばさ、今どのくらいまで行ったのかなこの峡谷。あんまり遅いから進んでないとは思うけど」
「どれくらい? ……ああ。それが、よくわからないんだ」
「? わからない?」
「なにしろ、ここの詳細な地図などないのだからな」
そういえば、ここは四十五年前グリード皇国が籠城して以降一度も他者の侵入を許さなかった要塞だったか。なら地図などあるわけがない。今までのような調子で手さぐりしながら行くのかと思うと嫌な気分になる。
「とにかく今日は罠を破る道具とこの温泉を見つけてくれたことは例を言うぞ。正直私もあの大量の罠はうんざりしていたからな……この湯でずいぶん癒された」
「いや、あのモップもどきはともかく風呂は俺の功績ってわけじゃ……」
「あ、それとあの悪魔払いの術。あれはずいぶん助けられたしな。感謝してるぞ」
ぶふぉと吹き出しそうになりとっさに湯に頭をぶち込んだ。ヘレナがびっくりするのも構わず爆笑を泡へと変える。
「な、何してるんだお前?」
「ぶくぶくぶく……なんでもありません。お気になさらず」
気にするなというのが無理な奇行だったが、ヘレナも臆したのかそれ以上聞いてくることはなかった。
「礼なんか結構ですよ。あんなの大したことじゃないし俺の世界じゃ常識的ですから」
「いや、それでも我々の世界では画期的だからな。アマデミアンは時に我々よりはるかに優れた知識をもたらすという――五十年前反乱を起こした者も、アマデミアンだと聞いているしな」
「え? 皇帝グリードとかいう奴のこと? あいつもアマデミアンだったの?」
「さあ、それはわからん。ただ、あれだけのアマデミアンをまとめ上げたことといい、MNという元はあれど強力な兵器を作れたことといい、その可能性はかなり高いと母上は申していたな」
母上、というのはヘレナの母でつまり女王陛下のこと。これまで一機が教えられたメガラにおける歴史のことは全部その母上から聞いたことらしい。一国の女王なのにずいぶん詳しいねと言ったら、ため息の後に「母上は政(まつりごと)や武(いくさ)は疎いのだが、そういったことには関心が強いんだ」と気落ちした様子で語られた。
「とにかく、その男一人のせいでシルヴィアの歴史は大きく歪ませられたものだな……戦争末期には、グリード軍の城まで追いつめ火攻めまでしてそうだが」
「火攻め? だったら皇帝は死んだんじゃないの?」
「ところが逃げられたらしい。兵の話では皇帝本人も焼かれたのだが遺体は発見されなかった。それで今に至るというわけだ」
なるほど――と納得しそうになる一機だったが、ふと奇妙な引っかかりを感じた。火攻め、焼かれた? 何故だろう、最近どこかで似たようなフレーズを聞いたような。
「その時倒せなかったから、シルヴィアは五十年続く内乱と、これを契機に始まった各地の反乱の日々となったということだ。兵も不足している。お前も早く一人前になれるよう、明日から鍛え直さねばならんな」
「ぶくぶくぶくぶくぶく……」
また沈んだ。体も気持ちも。
そうだった。それを忘れていた。あの地獄の日々が再開されるのだ。考えるだけで憂鬱になる。
「ははは、一人前になったらあのMNにも乗せてくれるんですか?」
「馬鹿を言うな、MNは動かすだけでも相当の鍛錬が必要なのだ。お前みたいな新米は動かすこともできんぞ」
たしかにこの世界へ来た時乗ったMNを一機は指先一つすら動かせなかった。やはりそう簡単に動かせる代物ではないらしい。
「でも、麻紀は一発で動かせたけど。そりゃ気持ち悪くはなってたが」
「ああ、それは私も驚いた。素人があれだけ動かせるなんて信じられんよ」
「そういやあいつあれで弓道部だったっけ。精神統一くらいは慣れたものだったのかもしれないなあ」
高校の放課後、弓道場で麻紀が弓を射っているのを見かけたことがある。いつもの学生服とは違う弓道の白筒袖と紺の袴に包まれた麻紀が、凛とした表情で矢を放ち、的へ当てていく。にやにやと小馬鹿にしたような顔しか見てこなかった身としては引き込まれそうな魅力が――って何を考えてる俺はと頭を抱えた。
「弓道? なんだ、弓をやるのか?」
「ああ。ケガが治ったら見せてもらったら? って、親衛隊に入るんだから弓やらないわけないよな」
「いや、腕が治ってもあの目では……」
「目? 麻紀の目がどうしたの?」
「え? ――あっ!」
そこで「しまった」とばかりに口を塞いで視線をそらした。あまりにも怪しい様子に何か寒気を一機は感じた。
「……どういうこと? ケガは大したことないって、麻紀の奴言ってたぞ」
「そ、そうだ、大したことはない。あいつに問題なんかないから気にすることは……」
「そんなかえってそういうことにしたほうがいいのかななんて思うくらい明らかに目を泳がせといて、何もないわけないだろ」
ぐいと顔を詰めよる。さっきまでの動揺と興奮はどこかへ消え、別の理由で心臓の動悸は激しくなった。
最初は顔を背けていたヘレナも、真剣な一機を見て意を決したように口を開いた。
「……腕や、その他のケガは問題ない。ただ問題は、麻紀の右目なんだ」
右目と聞いて、一機の脳裏に包帯で包まれた麻紀の顔が浮かぶ。いつもの半眼で見下す瞳が四分の一になっていた。あの目が、まさか……
「看護兵が言うには、目が傷ついてしまったそうでな」
「まさか、眼球が使い物にならなくなったのか?」
「いいや、目の中心にある――なんだったかな、水晶体とやらを覆っている透明の膜のようなもの」
「角膜?」
「それだ。その角膜とやらが、傷ついているようで……」
「……は、はは、はははははっ!」
突然一機は哄笑し出した。肩の力が抜けおおいに脱力する。
「か、角膜? なんだ脅かしやがって。んなもん大したことないじゃん。角膜なんか移植しちゃえば……」
そこで哄笑をピタリと止める。同時に温泉が冷めたんじゃないかと思うくらい急激な寒気が一機を襲う。
「――看護兵が言うにはだな。その角膜とやらが傷ついてしまったから、もう薬でも手術でもどうにもならんそうだ。あいつの、麻紀の右目は……」
ヘレナは言葉を切り、青ざめた顔の一機に宣告する。
「二度と、光を取り戻さないそうだ」
その宣告を理解するのに、脳は少しの時間を必要とした。
否、認めるのを拒絶したのかもしれない。
真っ白になった頭で、絶望的な結論を導き出す。
――角膜治療くらい簡単? たしかにそうだ。
角膜移植なんてありふれたものだ。完全に事実だ。
でもそれって――どこの世界の話だ?
「なんで……だってあいつ、大したことないって、全然問題ないって……」
「麻紀が言ったんだ、黙っていてくれと」
呆然とする一機に告げる。ヘレナのその言葉は、しかし一機にはいわれるまでもないことだった。
「あいつが言ったのか? 心配掛けたくないとか」
「あ、それが……」
言いにくそうにしていたが、やがてぼそぼそと呟いた。
「「自分のせいだなんて変に落ち込まれたらうざったいですし、だいいち私らそんなかんけいじゃありませんしねぇ」――なんて言ってたぞ」
「へっ、やっぱそんなこと言ったか」
あまりにもあまりな台詞だと思っていたヘレナは失笑した一機に驚きは? と目を白黒させてしまう。
そんなヘレナを無視して天を仰ぐ。巨大な紅の月と輝く星の中、向日葵を揺らして嘲笑する女を幻視した。
「……あの馬鹿」
温泉から出ると、一機は替えの服を着て湯船に背を向けてしばらく黙って座りこんでいた。
やがてヘレナが湯から上がり、着替える音がすると、一機はゆっくりと声をかけた。
「……なあ、ヘレナ」
「な、なんだ一機」
「ここの……峡谷の地図ってさ、あるの?」
「ち、地図?」
うっかり約束を破り喋ってしまったことを悔やんでいたヘレナは、不意の質問の意味がわからず戸惑ってしまう。
「地図は――ない。この峡谷はグリード軍残党が制圧してから一度も攻略されていないのだ。峡谷の入り口は何か所もあるから、中心が抜けた大まかな地図しかないな」
「でも、だいたいどれくらいまで進んだとかはわかるだろ? 進軍スピードとかで。中心までもう間もなくなのか?」
「中心? まさか、今までの速度からすると――まだまだ最初のはずだぞ」
「ふうん……」
「――一機」
「ん、うえっ?」
そこでしばらく考え事をしていると、突然後ろから声をかけられた。着替え終えたヘレナだ。
「これ、お前にやろう」
「え? なにこれ、ネックレス?」
ヘレナが首にかけてくれたのは、鎖のネックレスだった。少々錆びているが銀製らしい。
しかし、中心に同じ銀製のアクセサリーが通されている。その形は、王冠に剣が刺さっていて――あれ、これはMNにも刻まれていたな。何かのエンブレムだろうか? 王冠の部分にはパチンコ玉程度の黄土色の石が埋め込まれていて……
「って、これ何さ」
「それはな、まあお守りのようなものだ。子供の頃、母上がくれた」
「は? 大事なものじゃん。もらう訳にゃいかないよ」
「いいんだ。お前はどこか危なっかしいからな。それにお守りというのは非力な人間こそ持つべきものだ」
「――なんか納得しそうな自分がいるのが嫌だ」
「ふふっ、とりあえず持っとけ。気休め程度だが、まあ損はないさ」
それだけ言うと、腰を上げて自分の寝床がある寝台車へ戻っていった。
「……気付かれたと思ったけど、大丈夫かな」
軽く一息つくと、一機も戻ることにした。
「――俺、ここで今日寝るんだけどなあ」
寝台車に戻ってみると、この三日間と同様麻紀がベッドで包帯と三角巾を巻いたまま眠っていた。窓から入る月明かりになんとまあ穏やかな寝顔が写っていた。
ケガも治り五体満足となった男が一緒に寝るというのに無防備過ぎるだろうこの女は。しかしそれは一機を信頼し(ナメ)ていることの証明であり、事実この男は二年近く寝食を共にして何もしてこなかった。
ただ単に、ゲームをして寝て飯を食べてゲームをして寝て飯を食べて……それのみだったのだ。
「何が週末の悪魔だ……アホらしいことこの上ない」
その『アホ』は麻紀なのか一機なのか、それも考えずぽつりと呟いた。
そもそも、ネットもさせてくれない厳しい親が週末だろうが外で寝泊まりなんて許すだろうか。おまけにネカフェで出会った後見せてもらったものはごくごくノーマルな……つまり何のカスタマイズもされてない標準の機体だった。
恐らく、あの時麻紀は鉄伝を買ったばかりの素人だったのだ。あのネカフェには鉄伝の解説書が多くある。それを読みながらプレイしようとしていたに違いない。そこでたまたま一機に会って――今に至ると。
どうしてわざわざ一機の家でプレイしようなんて言い出したのか、そもそもこいつは鉄伝に興味が本当にあったのか……それすらわからない。一機は麻紀のことをほとんど知らない。この二年近く、麻紀のことを何一つ知ろうともしなかった。
そんな女が、自分を救うため庇い、そして重傷を負った。
「…………」
ふと、胸元からまたアマダスを取り出した。
そしてもう一つ、記憶の中からみたび引き出す、進路希望調査票。
――『アマダス』は人の感情、主に強い思いに反応し力を生む。
「俺のせい、なのかねえ」
何も書かれてない紙。それは要するに進路、未来に何の展望を抱いてなかったからだ。
将来は保障されている。黙っていても、食うには困らないであろう未来が。
でもそんなのつまらない。何か新しいものが、新しい世界が欲しい。全く違う退屈の無い世界へ行けた少女のように、一機は楽園へ自分を導いてくれる兎が現れるのを待ち続けていたのだ。だからあんな怪しいメールにも返信した。
しかし、その自分の逃避に麻紀を道連れにしてしまった。
仮に自分の「この場所から逃げ出したい、もっと別の世界に行きたい」という願いが『アマダス』に反応したなら、麻紀は単なる巻き添えを食った不運な女。
もしあっちにいたままなら、角膜による失明なんてすぐ治せたろうし、そもそもケガなんてしなかったはずだ。こいつが勝手にやったこと、と言いきれるほど一機は図太くない。
「なにが捨てられるかも、だ。やばいのはお前の方じゃないかよ……」
一機は親衛隊だろうが一応男、親衛隊がダメなら正規の騎士団に飛ばせばいいし、兵士が向かないなら他の仕事をと手を打ってくれるはずだ。
だが、麻紀は女でしかも片目が見えない。弓のみならず兵士なら目がどれくらい大事か一機にもわかる。いくらヘレナが優しくてもモノになりそうにない人間を置いておくわけにはいかないし、一般兵にもなれまい。他の仕事とはいえ女手でアマデミアンなんて異邦人を受け入れてくれる所などどこにあるか。最悪――を想像して怖気が走った。
明日も知れぬ身は自分の方。にもかかわらずこの女は二年連れ添った相棒に心配されまいとした。一機に気負ってほしくないとか、責任を感じないようになんてお優しい理由ではあるまい。そんな女神(ビーナス)のように慈悲深い女ではない、こいつは悪魔なのだ。
「無茶しやがって……別に俺らそんな仲でもあるまいし」
恩や義理を感じる仲ではない。助ける理由も助けられる理由もない。
単に、何の意味もなく出会った二人が何の意味もなく同じところにいたというだけのこと。じゃあどういう仲と聞かれれば……答えようがない。一機自身よくわかっていないのだから。
そんな女が自分を助けてしまい、そしてそのせいである種危機に瀕している。なら、自分はどうすべきだろうか?
「んー…………」
天を仰いで目を閉じ、しばらく考える。
ヘレナに嘆願すれば温情はくれるだろうが、あちらも隊長という立場がある以上そんなわがままも言えない。こちらの事情に詳しくはないからこちらを追い出された後の麻紀がどうなるか保証できない。やはりこちらへ留めてもらうのがベストだが、理由もなしにそれは無理だろう。
「理由、ねえ……ん?」
ふと眼を開け、麻紀の方を見てみると、視界に向日葵が二つ入った。
トレードマークの三つ編みツインテールをほどいた麻紀は、寝るためにいつも付けているヘアゴムを外して枕元に置いていたのだ。すっかり色あせた、向日葵のアクセ付きの。
「こんなもんもいつまでつけてんだか……しかし、寝顔だけは可愛いもんだな」
いつもの人を馬鹿にした笑みと半眼がない麻紀の寝顔は、この歳の少女そのものの美しさがある。痛々しい包帯を除いてはだが。
「……うし、決めた」
また少し考え込んで、ゆっくりと腰を上げる。借りたシャツとズボンを脱ぎ出した。
「ええと、制服制服……あったあった」
部屋の隅に木箱と共に保管されていた一機の制服を取り出す。破片が刺さったところは一応洗濯されたようだが、赤黒い染みは残ったまま。死にかけたことを思い出しゾクリとしたものの、贅沢は言えないとそれを着こむ。
「あとは……と、これだ」
同じく置かれていた木箱から、あの日麻紀が買ってきたスナック菓子と清涼飲料水数本を取り出す。こちらへ飛ばされた時一緒についてきたものだが、保護された後どうしようか悩んでとりあえずそのままにされていた。
その二つを寝床に備え付けのリュックにぶち込む。
「他は……剣持ってても使えないし、持たない方がいいか。いやでもなんか必要かなあ……」
そして、親衛隊からもらった皮靴も脱ぎ、こちらへ来た際のシューズに履き替えると、数時間前にメモリを全消去された携帯を取り出す。
「もう四年くらいになるが……まあないよりマシか。電源は入ってるから問題ないと……お」
気付くと、木箱の底に麻紀の携帯が転がっていた。きっとこちらでは使いようもないけど投げるのもなんだと置いておいたのだろう。せっかくだと一機は借りておくことにした。
「光源は多い方がいいもんな、後で怒られるかもしれんが、まあいい。どうせそん時はいろんな人からボコられてるの確実だしな――と」
不意に、まだヘレナからもらったネックレスをかけたままなのを気付いた。外そうかとも思ったが、なんとなくやめておいた。
「とりあえず、必要なものはこれで十分かな。正直全然足りない気がするけど、贅沢言ってもしゃーないか」
リュックを背負い、身支度を整えるとドアに手をかけたところで止まった。少し逡巡すると、顔も向けず麻紀に話かける。眠っていることを承知で。
「麻紀――決めたよ」
無論返事はない。しかしそれでも続ける。
「『魔神』を手に入れる。それもこの手で。俺一人手で」
そう。それが一機が導きだした『方法』だった。
麻紀が確実に安全が保障されているのが親衛隊で、麻紀にそこに留まらせる力が無いとすれば、一機自身がそれを手にすればいい。それも強大で、他とは一線を画す絶大な力を。
だがそんなもの一朝一夕で手に入るものではない。訓練なんてしてもどうしようもないなら、そんな力を自分のものにすればいい。
伝説で語られるFMN、その力が真実なら、親衛隊にとって多大な戦力になるだろう。そうすれば自分の権威もグット上がる、かもしれない。その結果麻紀を留まらせるという融通を効かせることも可能だろう、多分。
ただし、それは一機一人の力で為し得なければならない。親衛隊の皆と一緒に行っては一機の力量を示したことにはならないし、『魔神』をこの手に収めることができないかもしれない。
だから、こうして夜中寝静まったところを狙い抜け出し、一人で『魔神』を奪い返す。そして『魔神』を我が物とすれば、ヘレナやグレタ、親衛隊の皆が一機を認めざるをえまい。
「――なんてなるわけないよな。仮に持ち帰ったところで褒められるどころか勝手な真似しやがってってボコボコにされるのがオチだ」
自嘲気味に笑う。一機だって完全な馬鹿じゃない。こんな計画が希望的観測に乗っ取りすぎたあまりにもいい加減で無茶な代物だということは理解していた。
だとしたら、どうしてこんな無謀なことをする気になったのか? 自分でもそれはわからない。ただ、やろうと思っただけである。
「んー……ま、パートナーはパートナーを助けあうってことか。そう思っておこう。って、鉄伝じゃお前がサポートするだけで俺はお前のこと助けたことなかったよな、ハハハ」
乾いた笑いにも返事はない。聞こえていたら麻紀はどう反応するだろう。推測するまでもないなと一機は口元をゆがめ、ドアを開ける。
「そんじゃ、行ってくるわ」
それだけ言ってドアを閉める時、「――ヘタレが無茶するとロクなことないですよ」なんて聞こえた気がしたが、自分がさっき考えた麻紀の返しと一致し過ぎていたため、自分の声か幻聴が判別できなかったためそのまま閉じた。
「さて……」
外へ出ると暗いのは相変わらずだが、月明かりとポツポツ灯る松明でそれほど視界は悪くない。周りの見張りは数も少なくどいつもこいつも眠そうでこちらを注視していない。いける、と判断しこそこそ進んでいく。
目指すは温泉、が出たあの崖。崩れた崖はちょっと斜めになっており、ロッククライミングの要領で登ることは不可能ではない。一機経験ゼロだけど。
単独でのFMN奪取。この無茶苦茶なことにしかし一機は考えなしで行動したわけではない。ある推測があったため、行う気になったのだ。その推測が正しければ、実現は難しくはない。可能性低いけど。
とにかく進む。何故か不明だが、いやに気分が高くなって駆け出しそうになるのを懸命にこらえひそりひそりと進んでいく。やがて見張りの影が消えると、本当に駆けて行ってしまった。
十年近く退屈に寝そべっていた身体は、兎を追うこともなく走り出していた。
© Rakuten Group, Inc.