後編
「いつまでも痛がってんじゃないわよ、ご飯がまずくなる」
「いやでも、カカト落とし額命中はきついぞ……?」
日が暮れ、夕食時。荷馬車の中でマリーと2人で食事を取っている。鎧を外し、額をさすりながら。
「だからその話はもう無し。謝ったんだし、いつまでもグチグチ言わないでよ」
「はいはい……」
もう面倒くさくなった。スープを口に運んで腹を膨らますことに専念するとしましょう。
ふと窓から空を見上げた。星々の瞬きはどちらの世界も同一らしい。天文学など受けてないから北極星の位置すらわからない俺に違いなど判別できないし。
「……ん?」
「どしたの?」
「いや、変な星があるなと……ほら、あの大きな2つの星」
一瞬月かと思ったが違う、なんか大きいし、第一2つ並んでいる。乱視ではなく、ちゃんと2つあるようだ。
「……変って、あれ双子星(ふたごぼし)じゃない。今まで気付かなかったの?」
「双子、星?」
双子星と言うと、2つの恒星が両者の重心の周りを軌道運動している天体のことか? にしちゃ大きさ同じだし、第一あんなでかい恒星2つもあったら今昼間だろ? じゃああれは恒星じゃないのか?
「昼も見える日あるわよ。たまに欠けてたりかたっぽ無かったり両方無かったりするけど」
「……それ、まんま月だな」
なんか呆れてしまった。やってることは月なのに増えている。似てるのか似てないのかはっきりしないな。
「あんたの世界にもあるの?」
「ああ。あっちは1つだけどな」
そう言うと、「……ふうん」とだけ言ってそのまま黙りこくってしまった。物思いにふけるその顔は、今まで見たことがなく、誰だかわからなくなってしまった。
「……マリー? どうかした……」
「……一人きりなんだ、そっちの子は。私みたいに」
「え?」
ふいに、なんの前触れも無く発された一言に言葉を失った。
「あの双子星ね、シルヴィア各地にいっぱい言い伝えがあるんだ。運命が選んだ魂の伴侶とか、離れ離れの2人もいつかはめぐり合い、寄り添う日が来るのを見守っているとか」
その言葉は、俺にかけられたものではなかった。自分自身に、自分に語りかけていた。寂しげに――悲しげに。
「……私にも、いるんだって、そういう人」
「……マリーにも?」
「うん。魂を2つに分けた伴侶。お母さんが言ってたんだ。あなたは1人じゃない、あなたと同じ魂を持つ人がいるって。魂が引き合って必ず会えるから、それまで希望を持って生きなさいって」
フッ、と笑って言葉を切った。腕を差し出してくる。
「――私の肌さ、みんなより色が濃いと思わない?」
「え? い、いやそんなことは……」
口では否定しながら、心の中では同意していた。
確かに濃い。というか黒い。あきらかに、というほどでもない為、日焼けかなと思っていたが、よくよく見ると違う。他の親衛隊員は白なのに、マリーだけ少し褐色が入っている。
心の中を読まれたのか、また薄く笑った。
「私のお母さんさ、カリータ人なんだよね」
「カリータ……?」
聞き覚えがある言葉だ。褐色黒目の人種で、シルヴィアに対してのテロ行為が1番活発な民だと聞いた。
「父さんはシルヴィアの人だったからまだ良かったけど、やっぱ風当たり強くてさ、村から仲間外れにされてたよ」
その辛辣な内容に愕然とした。あのあの明るい機械オタクの姿からは到底予想できなかった。自分の外面しか見ない目に失望しながら、続く言葉に耳を傾ける。
「村のみんなから嫌われて、阻害されて、それでも……母さん笑ってた。その言葉を言い続けた。いつか、あの双子星のように寄り添って生きられる日が来るからって。……結局、お母さんが逝っちゃってから何年も経った今も、会えてなんかいない」
あはは、と笑った。いや、笑ってなんかいない。通常の感情表現では表すことのできないなにか、それを表現する術を知らず、笑うことしか出来なくなっているだけだ。その笑顔に、薄ら寒い思いすら抱いた。
「そのあと、王都に出稼ぎに行ってた父さんが帰ってきて、王都に連れてってくれたんだ。そこで整備の技術を教えてもらって、隊長に拾われて……父さん、もっと早く連れてってくれればよかったのに」
残念ながら、最後の言葉の意味が理解できないほど馬鹿ではなかった。マリーの父は、村で妻子が酷い目にあっていると知っていながら放っておいたのだ。シルヴィア王都において、宿敵であるカリータ人の妻子がいるなどと知れれば自分も同じく迫害され、最悪職を失う。だから地方に置いておいた。そして、妻が死んだのを得たりとばかりにカリータ人とはわかり辛い娘を呼び寄せたのだ。
「隊長は良くしてくれるけどさ、はっきり言って親衛隊内でもあんまよく思われてないんだよね。みんななんとなくわかってるみたいでさ。ジェニスなんか生粋のシルヴィア貴族だから、余計だろうね」
そう言えば、マリーとジェニスは仲が良くなかった。性格的なものかと思っていたが、そんな事情があるだなんて。
「……ねぇ、一機」
「え……?」
声をかけられた。その声はとても儚く、風1つでも吹けば消え入りそうだった。
だがそれ以上に俺を震えさせたのは、マリーの瞳だった。何も見ていない。こちらに目を向けていながら、瞳の中には何一つ映っていない。無機質で、空虚――。
手がガクガク震えるのを止められない。寒気が全身を覆い、凍りつきそうだ。
「――魂の伴侶って、誰なんだろうね。どこに――いるんだろうね。なんで――会えないんだろうね。――お母さん、どうしてそんなこと言ったんだろうね――」
「…………」
何か言わなくては、と口を開こうとする。でも、無理だった。
凍り付いていたからじゃない。その資格が無かったからだ。
俺はずっと不幸だと思っていた。報われないと、満たされないと。
だが、この世界に来て知った。自分のどこが不幸なのだ?
嫌われもした。避けられもした。失いもした。だけど、それら全てを差し引いて余りあるほどのものを手に入れていた。手に入れることが出来た。積極的に行使しなかっただけ。要するに余裕だったのだ。
この世の地獄を味わった女に、天国の沼に足を突っ込んだ程度の男が語る舌などどこにある?
ただ俺は、その場に阿呆のように突っ立っているしか能が無かった。
――ちなみに、この同時期に、
荒れた大地にそびえ立つ山々の地下で喜々として機械の猛獣をいじくり回していた少女が山脈に響き渡るかと思うほど盛大なクシャミをしていたなど、この二人が知る由も無かった。
「……ん」
掛け布団の重みが感じられず、はっきりしない意識で右手を無造作に動かして辺りを探る。何かに手がぶつかった感触がして、それを引っ張ってみる。
「……あだだだっ!?」
なんかうめき声が聞こえた。空いた左手で眼鏡を探すが、それらしいものの感触は無い。
「ちょっと、なに人の髪引っ張ってんの!?」
「いでっ!?」
手を離され、はたかれる。それで意識がはっきりし、眼鏡がもうないこと、そして今掴んだのは掛け布団ではないのを悟った。
「いったあ……」
「痛いのはこっち! 寝ぼけてんじゃないわよ!」
「あいたた……ちょっと、電気つけてくんね? 掛け布団どっかいっちまって……」
「寝相悪いからでしょ。ったく、ちょっと待ってなさい」
パチリと電灯がつく。光が矢のように目を突き刺して痛い。ようやく慣れてくると、時計が深夜を指していることに気づく。
「あーあ、まだ夜中じゃない。こんな時間に髪引っ張られて起こされるなんて……」
「悪かったよ……ああ、あったあった。……ん?」
ふと妙なことに気付いた。なんかおかしい。
「……なあ、マリー」
「なによ」
「なんかさあ……傾いてない?」
「え?」
その言葉にキョロキョロ見回してみると、マリーも何かが変だと感じ取ったようだ。
調度品、荷物、窓から見える景色その他、妙にずれている気がする。なんか右肩が斜めに下がっているような感じもするし。
掛け布団が取れた理由も傾きで滑ったのだとすれば納得だが……何故にずれている?
まず落ち着いて昨日寝る前から思い出してみる。食事を取った後、ここらへんは魔獣が出没するから気をつけろとヘレナに注意され、注意しろってどうすりゃいいんだあのデカ物と思いながら崖っぷちにサジタリウスの移動車両と一緒に置かれた荷馬車に戻って……あ。
「……ま、まさか……」
機械のようにギギギギ……と振り返ると、マリーも同じ結論に達したらしく顔を真っ青にしていた。と、
ギギギギ、グァシャーン!!
「わあっ!」
「ええっ!?」
突然大地が割れたような振動と音が響いた。その轟音に思わず耳をふさぐ。
しばらくすると音も止み、静寂が包んだ。
「な、なんだったんだ今の……?」
「か、一機、あれ!」
俺より早く回復していたマリーが窓をさす。覗いてみて……絶句した。
「……な、なんだよこれは……」
これは、と言ったが別に何かあったわけではない。むしろ無かったのだ。サジタリウスを輸送していた輸送車両が。地面ごと。
明らかに崖崩れで車両が落っこちたのだ。
「あらら……大変だこれは。サジタリウス無事かな」
「多分大丈夫だと思うけど……でも輸送車はどうか……な……?」
ふらっ、と立ちくらみが来た。2人ともに。
違う、立ちくらみじゃない。なんか重力が斜め下から来ているような……って。
「あ……ひょっとして……」
マリーと顔を見合わせる。お互いの顔が自分自身の顔を映す鏡となっていた。やばい、と一言書かれた顔を。
ズッ、とまた傾いた。そろそろ立っているのが困難になってくる。
まずい、逃げろと体が警告しているのに動けない。マリーと一緒に「あ、あはは……」と乾いた笑い合戦しか出来ない。
ズズッ、と来た。ふわっと体が宙に浮いた。重力が無くなってしまったかのように。
しかし、それは幻想だった。
ガラガラガラァ!!
「「わあああああああああああああああああああああああーーーーーー!!!」」
落ちていった。荷馬車ごと。
目の前に泣き叫ぶマリーの顔があった。
「つ……いたたたた……」
腰や肩などに鈍い痛みを感じて覚醒した。目の前が真っ暗だ。体が重い。特に二の腕辺り……。
「…………」
状況の整理から行こう。確か荷馬車が落っこちて、叫び声を上げてたら崖にぶつかったのかガシャンガシャン揺れて、何か頭にぶつけたような……。うん。そうだ。それで気絶したんだきっと。そうに違いない。
それはいい。それは。だが……。
――なんでマリーが俺に覆いかぶさってんだよおおおおおおおおおおおおおおおおっ!?
いやいやいや、冷静に考えればわかることだ! マリーも気絶して、たまたま俺の上に落ちてきた、たたそれだけ! うん、そうだ! 決して夜這いとか逆レイプとかそんなものでは……!
「う、うん……」
変な声出すなあああああああああああああああああああ!! 艶かしい声出してんじゃねえええええええええええええええええええええ!!
ああああ、動くな動くな! な、なんか二の腕辺りに奇妙な感触が……二の腕にはマリーの……マリーの……!
「…………!」
ああああああああああああああああああああああああああああああっ!!
こ、これは『円柱』発言は訂正する必要が……馬鹿ぁ! 何考えてんだ俺は!?
ていうかイーネにあんだけやられといてまだこんなんかよ!? 落ち着け、落ち着け! ヘレナやイーネに比べりゃ無いも同然ではないかこんなの! レミィ……はいい勝負かな……じゃないだろ!
ああああ、どうして俺はこう免疫が無い!? あいつにも保健体育の授業でそれらの話になって動揺を悟られないように顔を覆ったら「かわいいですね、うぷぷ」なんて嗤われるし、チクショオオオオオオオオオオオオオッ! 何でこんな目にぃ!
「ん、あれ……」
「あ……」
脳内がパニックに陥っていたら、マリーが目覚めた。すっごい気まずい。
「なんで……あんた……」
「あ、いや違う、誤解だ! なにもしていない!」
憤怒で歪み始めた顔から殺られると判断した俺は必死で弁解を試みる。と、その時、
「ギシャアアアアアアアアアアアッ!!」
「「……!?」」
耳を劈く叫び声に俺たち2人ギョッとして横転した荷馬車の上を見上げる。
「な、なんだ、聞き覚えがあるような……」
「魔獣!?」
魔獣、の言葉を理解する余裕を与えずマリーは1人荷馬車の外へ。俺も何とか追いかける。そこにいたのは……
「……げっ!」
そこにいたのは、猿のようなゴリラのような二本足で歩くケダモノ。だが、俺が知る猿は犬歯が鋭く尖っていないし、体中からの角のような突起を生やしていないし、第一15mちかくも大きくない。
しかし、それら全てよりもはるかに異様なのはその2つの目だった。暗闇の、視力が強くない俺にも十分わかるほど、巨大で、かつ、血のように、紅い。
「……ヒッ」
その真紅の瞳に見入られ、体が硬直した。まさに蛇に睨まれた蛙の如きその姿は見ていれば滑稽だったかもしれない。
長く爪が伸びた巨大な手が振り下ろされるても、何もできなかった。逃げることも、断末魔の悲鳴すら上げられなかった。
「なにやってんのこの馬鹿!」
ぐん、と体を引っ張られた。そのすぐ後に、さっきまで俺がいた場所に魔獣の腕が叩きつけられた。一瞬でも遅れていたら、俺はペシャンコに潰されていただろう。
「ボケっとしてんじゃないの、死にたいの!?」
「え、あ……」
気が付くと、俺はマリーに引かれるまま走っていた。マリーの瞳には怯えや恐怖は感じられない。自分がものすごく矮小な存在だと宣告されているようだ。
「お、おい、どこ行く気だ!?」
「このまま魔獣に殺されるのを待ってる気!? 迎え撃つのよ、あんたが!」
まったく予測していなかった指名に愕然した。自分に何ができるというのか。指先1つ震えさせることもままならなかったのに。マリーのほうがよっぽど適任だ。
「馬鹿言うな、俺にどうしろって……」
「あった!」
足を止めた先にあったのは、グシャグシャに潰れ、バラバラに砕けた輸送車。そして……
「サジタリウス……そうか、これなら……!」
「早く乗って! 来る!」
魔獣の地鳴りにも似た足音がどんどん近付いてくる。揺れに足元を掬われながらも必死の思いで取り付いた。
「大丈夫なのか!? あんだけ高いとこから落ちて……!」
「……大丈夫、問題ない。早く!」
「お、おう!」
ちょっと見ただけで判断したマリーに不安を抱きながらも、言われるままサジタリウスに乗り込む。マリーも一緒に。外にいたら危険だから当然だが。
コクピットに座り、シートに備え付けのベルトを締めて精神を集中させる。
「転身、開始……!」
視界がぶれて、サジタリウスのコクピットから外の崖下へと景色が変化する。と、そこに魔獣が。
「う、うわっ!」
突然のことに対処できず、モロに体当たりを食らう。
「がっ……!」
腹に鈍い痛みが走った。サジタリウスの重量は生物の激突ぐらいではビクともせず、ひっくり返されることは無かったが、衝撃は十分すぎるほど来た。
「きゃあ!?」
耳元でマリーの悲鳴がした。転身中はコクピット内部の姿を見ることができない。
「耳元で騒ぐな! くっ、また!」
また魔獣が突っ込んできた。今度は受け止める。
「ぐううううう……」
力比べではやはり重量で勝るサジタリウスのほうが上だ。徐々に押していく。自分の力ではないとわかっていながらも、優越感が生まれていく。
「よし、このまま……ぐっ!?」
いきなり横っ面をぶん殴られたような衝撃が来た。魔獣の手はこっちが押さえている。殴れるはずが無い。
「馬鹿な……どうして……」
攻撃されたほうを振り返って、目を見開いた。
そこには、今押さえつけている化け物と同様の姿をした化け物が。
「仲間がいたのか……? ぐわぁ!!」
また衝撃。今度は後方から再びイレギュラーな攻撃だ。
「敵は何匹いるんだよ!」
首を振って周囲を見回す。1、2、3、4……5匹!?
「5対1かよ、冗談じゃ……だっ!」
気を取られている隙に体当たりが直撃した。しかも2匹。ダメージは一匹の時とは2倍以上で、一瞬呼吸が止まる。つい手を離してしまった。
「まずい……これじゃ46(フォーティシックス)が使えない……!」
46cm砲は長距離戦専用の武器。こんな近距離じゃ背中に背負ってて邪魔なだけだ。ましてサジタリウスは46cm砲が全てのMN。接近戦は最初から考慮されておらず、その重量と背中のバックパックで格闘はほぼ不可能だ。
「離れなくちゃ……どわっ!?」
ガシャア!!
背中に強い一撃を食らった。またしても体当たり、それも今度は魔獣一団となって突撃したらしい。前のめりに倒される。
「があ……!」
ドシン、と激しく打ち付ける。重量が今度は仇となり、全身に電気が通ったような鋭い痛みが走る。
「く、くそ……うお!?」
背中に激しい衝撃が走り、まだ痛みが続く身に更なる追い討ちをあげる。魔獣たちが伸し掛かって蹴りつけているらしい。
――伸し掛かって、蹴りつけられて……
ふと、デジャブを感じた。
心の奥底に厳重にしまっていたなにか、ドアの中に放り込んで鍵をかけ、鎖で巻いて二度と開けられないように閉じ込めていたなにか。
それが、そんな鍵など何の役にも立たないよ? と嘲笑うかのように簡単に開き、そして飛び出していく。
すぐに俺の全身にまとわりつき、覆い尽くしていく……。
『ははははは、あーはっはっはっはっは……』
『お前はこのクラスのクズだ! 死んじまえっ!』
『バーカ、はっはっはっはっは……』
「あ、あ……あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっっ!!!」
危険だと思った。倒されたサジタリウス操縦席の中で操縦席に縛られ宙吊りになった一機を仰ぎ見る形になりながら唇を噛んだ。
サジタリウスを修理してきた私にはわかる。サジタリウスは格闘には向いていない。というより格闘戦を考えずに作られた機体。あの巨大な大砲を運用するのみのMNで、それ以外ではほぼ無力なのだ。
そんなこと一機を乗せる前からわかりきっていたこと。それでも、あの時は他にどうしようもなかった。6連機関砲や中口径砲、小型連射銃も積んでいるのでなんとかなる、最悪倒せなくてもこの重装甲が破られることは無い。隊のみんなが来てくれるまで持ちこたえることができれば、と思っていた。
でもまさか、押し倒されるとは。こうなるとどうしようもない。サジタリウスの背中の武装収納庫はかなり重く、これを上にされたら自力で起き上がるのはかなり困難。一方的にやられるだけだ。
どうすんのよ、と聞こうとしたら……一機が絶叫した。
「ああああああああああああああああああああああああああああああああぁぁぁぁぁぁっ!!」
「な、なに!? どうしたの一機!?」
こちらの声などまるで耳に入っていない。ただただ常軌を逸した叫びを上げるのみ。魔獣のようでいて、魔獣よりはるかに狂気に満ちた咆哮を。
ふいに、ガクンと機体が揺れた。攻撃を受けたのかと思ったが違う。倒されたことで横になった操縦席が正常な位置に戻ろうとしている。それは、自分が座っている場所がずれて操縦席に寄って行くことにも繋がっていた。
――嘘、立ち上がっている!? どういうこと!? ……転身、開始!
MNの操縦席には窓などの直接周囲を見れるものは無い。操縦者はアマダスを介して転身し擬似的に視神経をMNに接続しMNの視点から周囲を見回すためである。そのため、同乗している人間には周囲を知る方法は無い。
だが、操縦者が転身している時なら、その視覚内容を同時に見ることができる『同時転身』が可能である。ただしこれは操縦者の見ているものを同時に見るだけで視覚の自由は利かず、また操縦も不可能である。まあ自分にはMNを操縦する力は無いが。
そして一機の、サジタリウスの視界を手に入れた私は状況の確認に勤めようとした。だけど、自分の目の前の出来事に呼吸が止まるかと思ってそれどころではなかった。
立ち上がろうとしている。ゆっくりと、確実に。自力で立ち上がれないはずのサジタリウスが、手を地面につけ、膝を曲げて、静かに、確かに……。
「どうして……」
さっきまで攻撃をしていた魔獣たちが後ろ足に引いていく。本能だけの化け物の瞳には、明らかに『恐怖』があった。
「ああああああああああああああああああぁぁぁぁっ!!」
思考はケダモノの咆哮によって中断させられた。完全に立ち上がったサジタリウスが、両腰の小型連射銃に手をかけた。
「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああっっ!!」
ババババババババババババババババババババッ!
2丁の小型連射銃の音色と薬莢が飛び散る様は、軽快でまるで大きな都市の祭のようでもあった。
だけど、祭では肉が引き裂かれ、血があたりを飛び交うことはあるまい。
数秒の間で大量の銃弾を浴びた魔獣は肉が千切れ飛び、血がとめどなく流れ、泣き叫ぶような悲鳴を上げた。
「右ガトリング砲、左15.5センチ砲旋回! 撃てぇ!!」
一機の意思に従い、サジタリウスの両肩の武装はお互い別の敵に照準を向け、同時に発射される。
ガガガガガガ、ガガガガガ!
ゴゥン、ゴゥン!!
片方は小さい穴を際限なく開け肉を2つに分け、もう片方は猛獣の肢体を簡単に貫き爆発させ宙に肉の雨を降らす。どちらもものの数発で動かなくなるが、それでもなお撃ち続ける。
目の前で繰り広げられる文字通りの血祭りを見ていられなくなり、転身を解除する。自分の肉体に意思が戻った。
「もうやめて一……機……」
言葉は続かなかった。一機の瞳に、戦うその姿に気圧されてしまった。
瞼は限界まで開ききり、瞳孔は血走っていた。犬歯をむき出しにして、額には筋が大量に立っている。
痛みに泣き叫ぶ魔獣とこの男、どちらがケダモノだろうか。
「一機、もう止めて、これ以上……」
「笑うな……」
「え?」
「笑うなああああああああああああぁぁぁっ!!」
何かが爆発したかのような音がしたかと思うと、ぐんと一気に後ろに引っ張られ、操縦席の壁に叩きつけられた。痛みに顔をしかめていると、また強い振動が操縦席内に走る。何かに激突したようだ。
「きゃあ!」
とても立っていられず、床に倒れる。頭がクラクラする。
「一機、落ち着いて、ちょっと待って……」
ガン、と鈍い音がした。また1回、1回と定期的、断続的に続く音と何かが潰れるような音が。おそらくサジタリウスが魔獣を殴りつけているのだろう。
「聞いてよ、一機、やりすぎだって……」
「誰が馬鹿だぁ!」
何の脈絡もなく突然出てきたその言葉に、一瞬あっけに取られる。
「誰がクズだぁ! どいつもこいつも俺を馬鹿にしやがって! ふざけてんじゃねぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!」
私はやっと悟った。一機は今私の声を聞いていない。いや、魔獣と戦ってすらいない。一機が戦っているのは、牙を振るっているのはもっと別のもの、心の中に潜む、もっと違うなにか。
「貴様らに! 馬鹿にされるいわれも、愚弄されるいわれもねぇんだよ! どいつもこいつも馬鹿共が! 貴様らのほうがよっぽどクズだろうがぁ!!」
怨嗟の言葉を吐きながら、殴り続ける。多分魔獣はもう絶命しているだろう。そんなこと関係ない。一機が殺したいのは魔獣なのではないのだから。
「笑うんじゃねぇ馬鹿にすんじゃねぇっざけてんじゃねぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!」
ギリリ、と肩の武装が旋回する音がした。それも2つ。
6連機関砲と中口径砲の照準が向けられたのだ。
バババババババババババババババババババババババッ!!
ガガガガガガガガガガ、ガガガガガガガガガガガガガ!!
ゴゥン、ゴゥンゴゥンゴゥンゴゥン!!
サジタリウスの白兵戦用火器全てがたった一匹にむけて火を噴いた。
操縦席の中では見えないが、魔獣の肉体は原形などまったく留めていないだろう。
「はあ、はあ、はあ、はあ……」
荒く息を吐きながら、脱力した一機は、そのまま眠るように気絶した。
「一機……」
操縦席の狭い密室で、壁に背中を預けて一機と寄り添うように横になっていた。疲れた一機は眠り続けている。寝顔は穏やかなもの。さっきまでと同一人物とはとても信じられない。
「……なんで、話したんだろう」
一機に自分の過去を話したのは、全然考えもせずとった行為だった。口からこぼれるように言葉が紡がれていき、話した後すぐ後悔した。
過去を話すのは好きじゃない。変に同情されてもやり辛いだけ出し、励ましや慰めの言葉を投げかけられても困るだけだ。ましてや、魂の伴侶の話なんて冗談じゃない。きっと会えるよなんて無責任な言葉は聞きたくなかった。
にもかかわらず、会ってそれほど経っていない一機に親衛隊の誰にも話したことのないことをあそこまでベラベラ喋るなんて、一時の気の迷い、なんらかの事故としか言いようがない。双子星の魔力がそうさせたのだろうか。
「――双子星の魔力、だって。馬鹿みたい……」
自分らしくない言葉に、思わず笑いがこぼれる。
シルヴィアのカルディナ神も、母が祈り続けていたアルガルフの神も信じてはいない。10何年も村で迫害され続けたのに、いくら祈っても何もしてくれなかった。死ぬまで祈り、願い続けた母なのに、命でダメなら何を捧げろというのだろうか? 神様は。
母が死んだあの日、母とは違う生き方をすると決意した。祈ったりなんかしない。願ったりなんかしない。全て自分で行う。自分の力で、手に入れる。それが、あの迫害され続けた日々で得た唯一のもの。
「……一機も、そうなのかな。ひょっとして……」
ひょっとしたら、一機に喋ってしまったのは、自分と似た何かを感じたからかもしれない。世の中から否定され、隔絶され、何も信じられなくなった――自分と、同じものを。
「――ねえ一機、あんたは――いったいなにを抱えてるの――?」
深いまどろみの中を漂い眠り続ける一機に問いかける。返事は無論返ってこない。
きっと、起きていても反応はこれっぽっちも変わらないだろう。断言できる。結局意地っ張りなのだ。この男は。
「……大丈夫かな。このままサジタリウスに乗せておいて」
とりあえず一機の心の闇は後にして、当面考えなくてはいけないのはそっちだろう。あのときの一機は正気じゃなかった。今回は味方が誰もいなかったからよかったもののもし密集戦などでまたあんなことになったら収拾が付かないのではないか。隊長に相談して降ろすべきではないだろうか。
「……まぁ、大丈夫よね。あの小心者の一機に、そんなことできるとは思えないし」
よっこらせと一機の隣に寝転がる。疲れた。眠い。
言わなくていいと思ったのは一機にできるわけがない、と思ったのも1つ。
だけどもう1つある。見てみたいと思ったのだ。手塩にかけて修復したサジタリウスが、一機によってどんな存在へと変貌していくのか……恐れと共に、好奇心がくすぐられているのを自覚していた。
――後に、マリー・エニスは、
このときの判断を死ぬほど後悔することになる――。
「う~む、今回はマリーが大変だったな。落ちるは魔獣に襲われるはとは……いや、それよりも男と始終一緒にいたということのほうが大変だったろうな。隊長も辛い命令をなさる。どうしてあんな奴と……あ、これは失礼。世はシルヴィア王国騎士団親衛隊隊員、ライラ・ミラルダと申す。次回は双子看護姉妹の1人、ナオ・ローラグレイが主役らしいな。一機に頼みごとをするそうだが、あのナオが頼みごと……大事件にならなければいいのだが。次回、サジタリウス~神の遊戯~ 第8話 『小悪魔賛歌』を頼み申す……ずいぶん抽象的な予告だな。何も決まっていないのが見え見えではないか」
to be continued……
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-
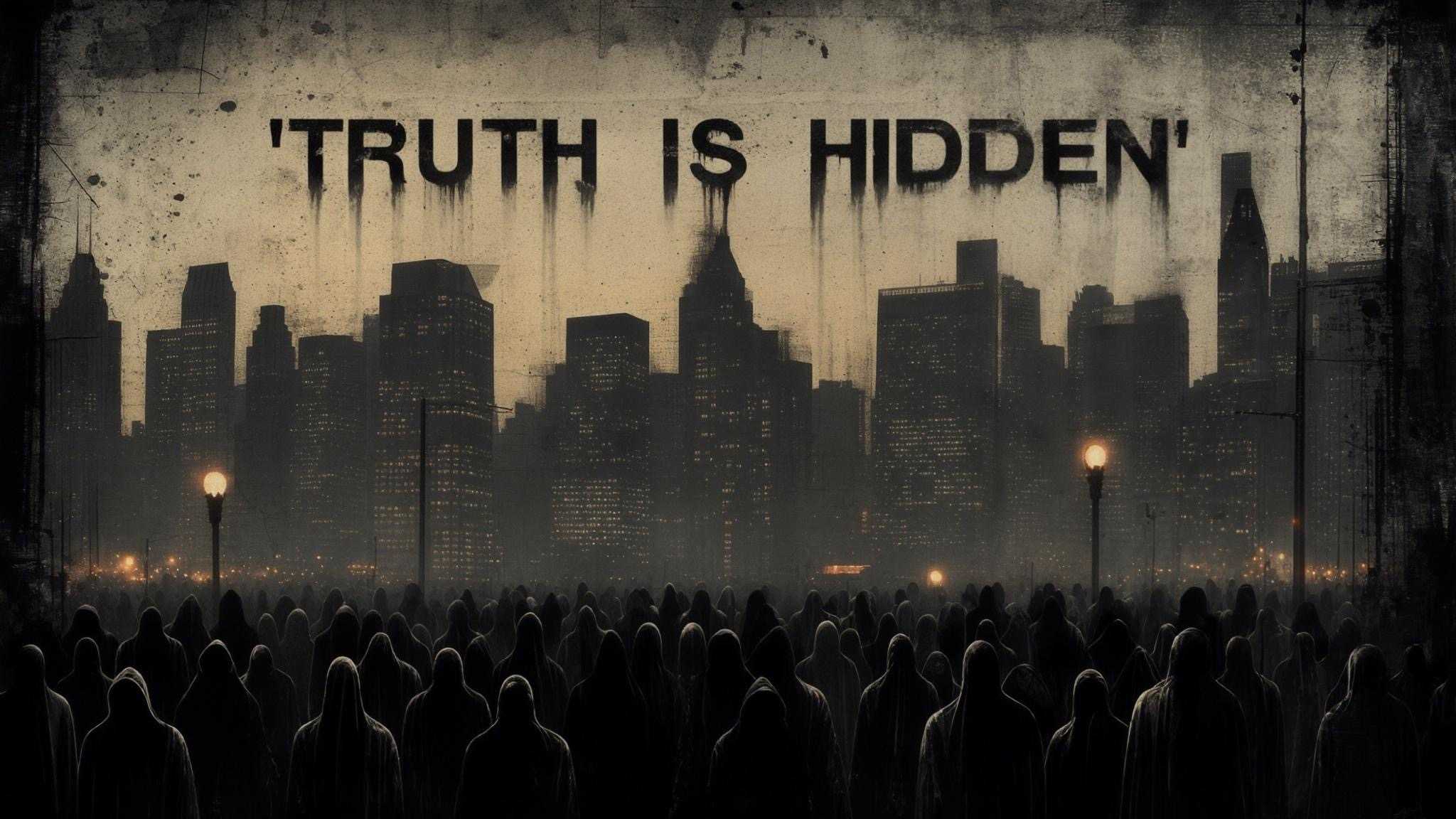
- 人生、生き方についてあれこれ
- 陰謀論はなぜ生まれるのか|権力の不…
- (2025-11-21 12:57:17)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY2
- (2025-11-21 09:24:57)
-
© Rakuten Group, Inc.



