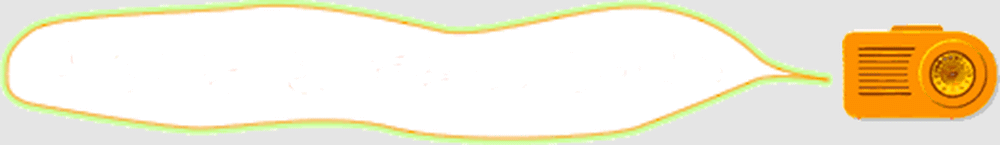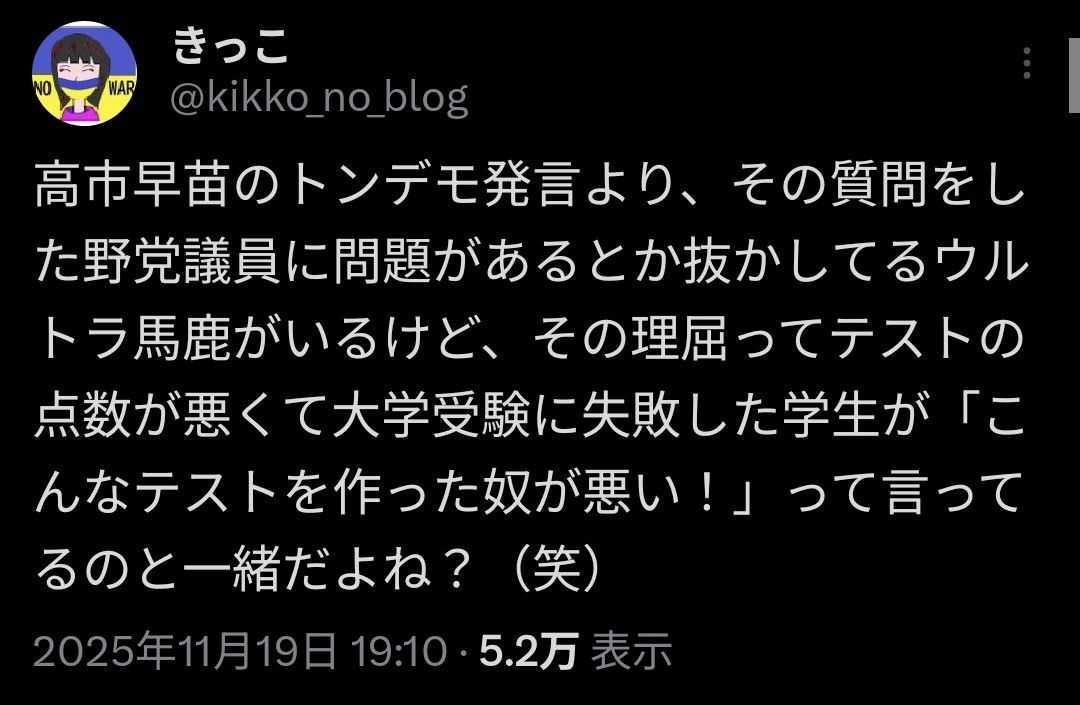父親たちの星条旗
やっと世間の評価が、実力に追いついてきたようで、ファンとしてはホッとしている。
なにより驚いたのはこの作品が大作であったことで、いかにスピルバーグ制作とはいえ、テレビ出身であるということだけで、あるいはイタリア製西部劇に出演したというだけで差別され続けたイーストウッドも、こういう大作を堂々と撮れるようになったんだなあと、感慨深かった。
映画はいつものイーストウッド映画と同じように、これ以上はないくらいオーソドックスで、回想シ-ンもどれがどれやらわからなくなるようなことはない。
構成は、スピルバーグ制作のためか、「マディソン郡の橋」に似ている(関係ないか)。
オーソドックスなのだが、前半、硫黄島上陸の戦闘シーンの凄さはちょっと例がない。戦争映画はかなり観ていると思うが、ここまですさまじい(というか、観ていて恐い)のは、「地獄の黙示録」のロバート・ディバル扮する大佐が、ヘリでベトコンの村を襲撃するシークエンスくらいしか思いうかばない。戦闘が始まる直前の不気味なサスペンスもさすが。
僕は戦後を描く後半が好きだ。
戦場における英雄とはなにか・・・というテーマが浮き上がってくるが、イーストウッドの人間を見つめる眼はやさしく、それぞれの立場が納得できるように描かれている。大人なのだ。
イーストウッドは、「ハートブレーク・リッジ」という、グレナダ侵攻を描いた監督・主演作(これもまた、頭の悪いヤツらに差別された)の時、映画の海兵隊が使用している装備が時代遅れだと、アメリカ軍の協力を拒否されたことがある。
その時イーストウッドはこう啖呵を切ったそうである。
「古い武器で殺されようが新しい武器で殺されようが、死んだ人間の価値に違いがあるか」
戦場で何があったのか、語らないまま死んでいこうとする父親が、死ぬ間際ひとつだけ戦場でのエピソードを口にする。そのエピソードが静かに流れるラストシーンは、美しい音楽(イーストウッド作曲!)と相まって、久しぶりに映画のラストシーンなんだ、本物の映画を観たんだと思わせてくれる。
「硫黄島からの手紙」も当然観なくてはなるまい。
戦争をお互いの立場から撮るという発想は新しいものではなく、今までにもあったが、それを別々の映画で撮る・・・というのは、初めての試みだろう。なんという自由で、かつ公平な心を持った人なんだろうか。日本人として嬉しく思うし、日本人を描いた戦争映画の最高傑作になっているだろうと確信する。
30年前からクリント・イーストウッドのファンであったことを、僕は誇りに思う。
© Rakuten Group, Inc.