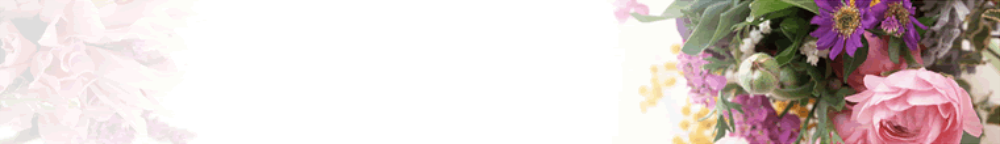短編小説「やさしい結末」前編
出掛けに雨が降ってきた。公園に行くのだと折角機嫌よく靴をはいた3歳の息子が駄々をこねる。泣きたいのはこっちなのに。それに洗濯物を取り込まないといけない。私は心の中で小さく舌打ちをした。泣いている息子を言葉であやしながら家事を片付け終えると、雨は一層激しくなっていった。夏の終わりを告げるかのように、激しい音をたててどの家にも惜しみなく降り注ぐ夕立を、幼子を寝かしつけながら私はぼんやりと眺めていた。すこしの恐怖と、あるやさしい回想の念をもって。そうして私は急速に二十歳の頃へと帰っていった。
もしも、もう一度同じ状況におかれたなら、やはり同じように恋におちたのであろう。薔薇の木に薔薇の花咲くようになんの不思議もないように私はその恋におちてしまった。仕掛けてきたのは、あるいはあの人の方ではなかったか。なぜ器用に格好よくこなせなかったのか。まさか。無様で不器用でない恋など一体誰がするというのだろう。
当時、入社して間もなかった私はいつもぽつんとお昼を食べていた。人に疲れ、慣れない仕事に疲れていたのである。
「もう、仕事慣れた?」
やさしい声ではあったが、私を驚かせるには充分であった。
「ああ、ごめんな。驚かせて。」
「はあ。」
彼のことは知っていた。二つ上の先輩で、目立つような顔立ちではないけれど、涼しげな目元には彼の意思の強さが表れていて、やさしさと清潔な感じが互いに漂う人であった。私は、なんか用かな、くらいにしか思えなくて、ぽかんとしていたのだろう。
「あっ。これ、ふたつも出てしまって。よかったら、あげる。」
言い返す間もなく、その人はそそくさと行ってしまった。私はぽつんと置かれたそれを見た。みかんの缶ジュ-スであった。こんな子供みたいなもの、飲むんだ。あわてて立ち去る後姿と、食堂のモノト-ンの光景の中でぽっかりと明るいオレンジ色のそれとを交互に見て、私はくすくすと笑った。それはまるで暖かい灯のように私の心を灯したのである。
その人の噂は知っていた。父親が病気で借金があり、裕福な婚約者の家で肩代わりしてくれているというものだった。
(後編へつづく)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…
- (2025-11-22 20:32:53)
-
-
-

- 鉄道
- 【2025/10/30】江ノ島電鉄線 22‐62…
- (2025-11-26 17:21:32)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- 三沢基地航空祭2025.09.21
- (2025-11-25 06:30:06)
-
© Rakuten Group, Inc.