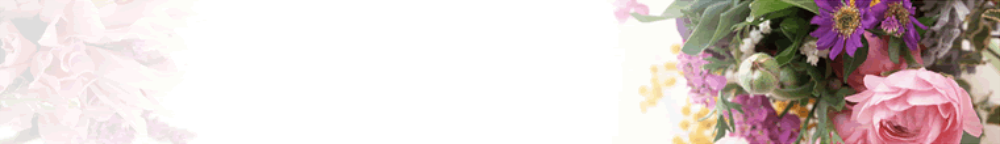短編小説「やさしい結末」後編
彼と再び言葉を交わしたのは、一月後であった。課の送別会が終わり、皆は三々五々、二次会にくり出そうとしていた。
「もう帰るのか?」
酔っているのか目の淵が少し赤い。でもちっとも嫌な感じはしない。一週間の仕事を終えたという開放感が私を少し大胆にしていたのかもしれない。
「一緒に帰りませんか?」
自分でも驚くような言葉がでた。Nも驚いた顔をしていたが、すぐに嬉しそうに笑い、
「いいよ。帰ろう。帰ろう。」と言った。
そうして私たちは、賑やかに騒いでいる集団から誰にも気づかれないようにそっと抜け出した。Nの方が慎重であった。私はふとNの噂を思い出した。
「こんなことしていいんですか。」
「まだなんにもしてないよ。」
怒ったようにそう言ってNは煙草を取り出し火をつけた。手馴れたそんな仕草に、私はどぎまぎしてしまい、顔が赤くなった。Nは、
「そんな可愛い顔するな。」と笑い、
私の頭をくしゃくしゃと撫でた。やさしい声だった。
しばらく、何を話すでもなく並んで歩いていた。そんな私たちをめがけてまるで何かの啓示を受けたかのように突然雨が降り落ちてきた。
「いそげ!」
Nが私の手をつかみ、私たちは手をつないで走った。雨宿りできそうなところはどこにもなく、仕方なく公園の藤棚で雨を逃れた。
ぬれねずみになった私は急に抱き寄せられた。
「ごめんな・・・。」
何をあやまるのか。どうかあやまらないでほしい。私は黙って、そして、いつまでも、このやさしい雨が降り続いてくれることを願った。
恋というものに理屈や原則など何もない。自分が恋した瞬間に相手もまた恋におちてしまうという不思議がこの世の中にはあるのだ。
婚約者のいるNとの恋愛は1年ほど続き、そして突然に結婚したNの一方的な別離で、その恋は終わったのである。何年かが過ぎ、Nが離婚したと風の噂できいた。私はある種の憐憫の念とほんのすこしの意地悪な気持ちが入り混じった感情で、その話を冷静にきいた。
恋愛が素晴らしいのは恋が始まったその瞬間ではないだろうか。
人は誰しもこれから始まるであろう未知の自分の運命に浮かれ喜ぶのだ。あの夏の夜の激しい雨の中、抱きしめられながら私は何を思ったか。
いつの間にか静かな寝息をたてているちいさな息子に、タオルをかけてやってから、私は立ち上がって窓の外を見た。雨は勢いを増し当分止みそうにもないだろう。容赦なく降り注ぐ薄暗い雨のむこうに、私はいつだったかのやさしい足音をきいた。Nとふたりで雨の中を走っている私がいる。ふたりはけっして手を離そうとはしない。私は窓辺に立ち尽くしいつまでもふたりをみつめていた。
(終)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…
- (2025-11-26 00:00:05)
-
-
-

- ゲーム日記
- 《モンスターハンターワイルズ》風鋏…
- (2025-11-26 20:00:09)
-
-
-

- 絵が好きな人!?
- ボタニカルアート教室に慣れてきまし…
- (2025-10-25 19:13:07)
-
© Rakuten Group, Inc.