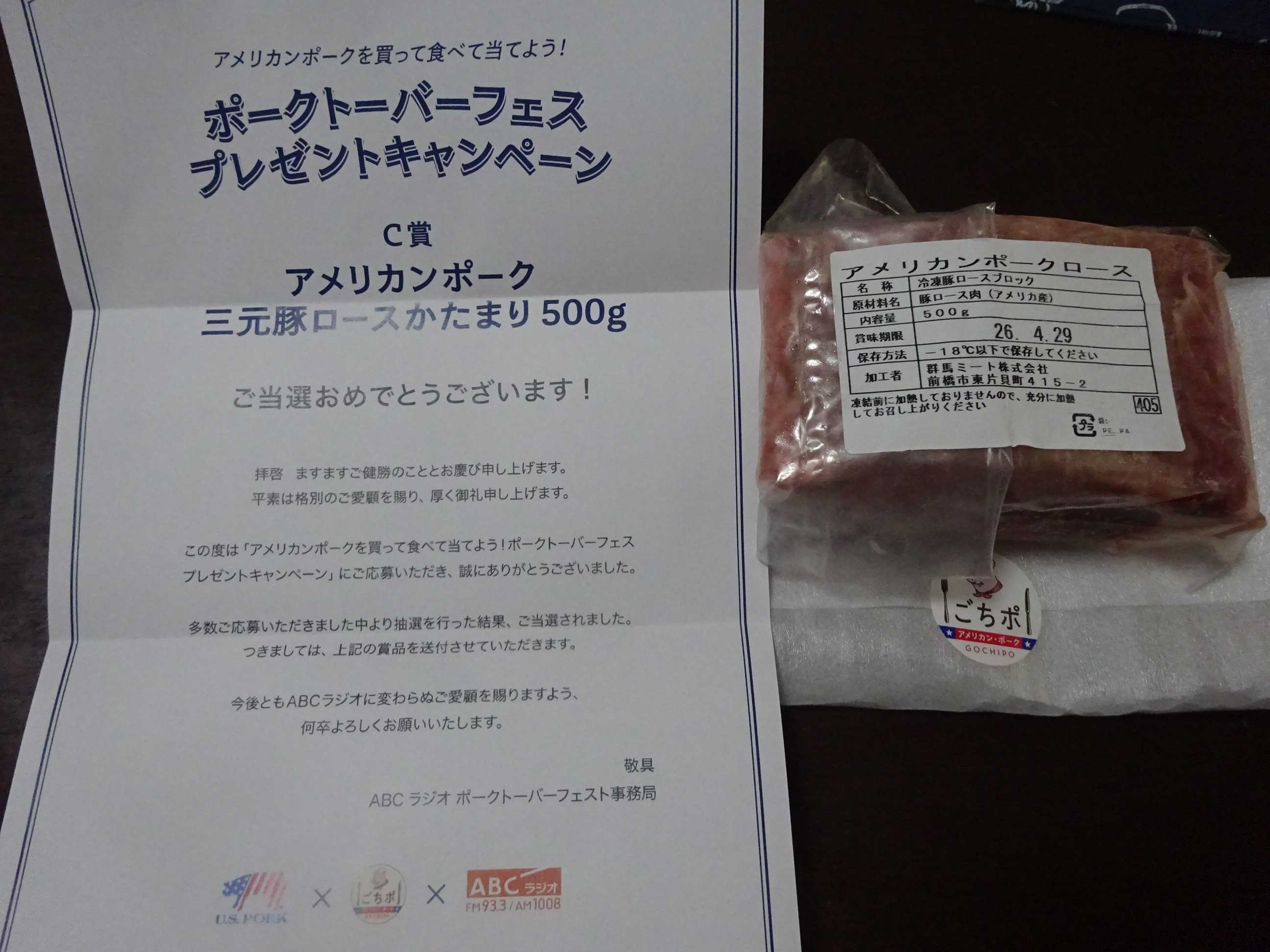大砲の時代(前編)
世界史コンテンツ(のようなもの)
~大砲の時代(前編)~

「ようやく始まったみたいだな。まったく…前回の更新から2ヶ月以上経過しているぞ」

「まあまあ、このまま適当にスルーされ続けるよりはよかったんじゃない?」

「それはそうだが…」

「それよりも、今回から新しい講師になるって話だったよね。誰が来るのかな」

「誰でもかまわんさ。早く始めて貰いたいものだ」
 「こんにちは~。この講師を務めさせて頂く琥珀と申します。よろしくお願いしますね~」
「こんにちは~。この講師を務めさせて頂く琥珀と申します。よろしくお願いしますね~」
「あ、琥珀が来た。あんたが講師?」

「なるほど。大砲は『火薬』を使うからな。それにちなんだ人選か。相変わらずASDICは芸がない」
 「適材適所ですよ、涼子さん。他に相応しそうな人ってのも、なかなか見あたりませんし。ここは一つ私が引き受けましょうと思ったわけです」
「適材適所ですよ、涼子さん。他に相応しそうな人ってのも、なかなか見あたりませんし。ここは一つ私が引き受けましょうと思ったわけです」
「確かに難しい人選だ。この際、贅沢は言うまい」

「それじゃ、さっそく始めちゃってよ」
 「はい。僭越ながらこの琥珀が講義を始めさせて頂きます」
「はい。僭越ながらこの琥珀が講義を始めさせて頂きます」
「ところで、どの年代の大砲について講義するつもりだ?」
 「やっぱり世界史コンテンツということなので、大砲の起源から時代を追って近世くらいまでを説明する形式がいいと思っていますけど、どうですか?」
「やっぱり世界史コンテンツということなので、大砲の起源から時代を追って近世くらいまでを説明する形式がいいと思っていますけど、どうですか?」
「それが無難だろう。現代の戦車砲や、りゅう弾砲ならば、わざわざこの講義でやる必要もない」
 「それでは、いきなりですが質問をしちゃいます。火薬が発明されたのはどこでしょう?」
「それでは、いきなりですが質問をしちゃいます。火薬が発明されたのはどこでしょう?」
「そのくらい知っているわ。中国でしょう?」
 「アルクさん正解アル。中国4000年の歴史が生み出した世界三大発明の1つアル」
「アルクさん正解アル。中国4000年の歴史が生み出した世界三大発明の1つアル」
「それがどうしたんだ?そんな中学生くらいで習うような…いや、最近はゆとり教育とやらで教えていないのかも知れないが」

「ゆとり教育は見直しされるみたいよ。しかし勝手なもんよね~管理教育が子供の個性を歪めるとか言って、ゆとり教育を導入したのに。そしたら学力が下がったとかで急に叩かれてるなんて莫迦みたい」
 「まぁ、ゆとり教育は置いておいて…。確かな資料が残っていないため、正確には分かりませんが、中国で生まれたのは火薬だけではなく 大砲も中国が起源
であり、13世紀頃、大砲等と共にシルクロードを介して伝わったのではないかと考えられているのですよ」
「まぁ、ゆとり教育は置いておいて…。確かな資料が残っていないため、正確には分かりませんが、中国で生まれたのは火薬だけではなく 大砲も中国が起源
であり、13世紀頃、大砲等と共にシルクロードを介して伝わったのではないかと考えられているのですよ」
「へぇ~大砲って中国が起源だったんだ。起源と言えば 某半島 を思い出すけど…アレは 『ロケットはウリナラ起源』 だったっけ。まぁ、今回はどうでもいいわね」
 「大砲と言っても、壺みたいな容器から鉄の矢を打ち出すという 実用性皆無のオモチャ
みたいなものなんですけどね」
「大砲と言っても、壺みたいな容器から鉄の矢を打ち出すという 実用性皆無のオモチャ
みたいなものなんですけどね」
「例え実用性皆無であっても、火薬を装薬として弾を筒から射出する兵器を考案した意義は大きいだろう。最初は何でもそんなものだろう。重要なのはいかに改良して実用化するかだ」
 「中国人は花火とか平和的な火薬の用途もいろいろと伝えたアルが、 欧州では専ら銃砲に関する部分を学んだ
みたいアル。欧州人は中国人と違って好戦的アルね」
「中国人は花火とか平和的な火薬の用途もいろいろと伝えたアルが、 欧州では専ら銃砲に関する部分を学んだ
みたいアル。欧州人は中国人と違って好戦的アルね」
「チベット…天安門…」
 「アルクェイドさん!そういう政治的発言はいけないと思います」
「アルクェイドさん!そういう政治的発言はいけないと思います」
「別に中国人がチベットで 民族浄化 を行おうが、失地農民を 武力弾圧 しようが、 美 し い 色 鮮 や か な 七 色 の 河 が流れているような土地で生活していようが知ったことではない。続けてくれ」
 「・・・で、では続けますね。火薬の知識を最初に明らかにした欧州人は 『ロジャー・ベーコン』
です。彼の『芸術と自然の知識の業についての手紙』には、 黒色火薬の処方
が記されていました」
「・・・で、では続けますね。火薬の知識を最初に明らかにした欧州人は 『ロジャー・ベーコン』
です。彼の『芸術と自然の知識の業についての手紙』には、 黒色火薬の処方
が記されていました」
「あれ?中国で発明された大砲はどうなったの?そっちが起源なんでしょ」
 「そうなんですけれど…結局、大砲が発展するのは欧州においてなので、中国に関する記述はやらないことにしました」
「そうなんですけれど…結局、大砲が発展するのは欧州においてなので、中国に関する記述はやらないことにしました」
「ふ~ん、別にいいけど。 『突火槍』 とか中国の火薬兵器は取り扱わないのね」

「大して実用性のない虚仮威し兵器などどうでもいいだろう。大事なのは大砲だよ、大砲」
 「皆さん、なかなかお詳しいじゃないですか。中国で発達した火薬兵器は、まったく実用性皆無というわけでもないのですが、後世に与えた影響では欧州の大砲に適わないと考えまして、今回は講義内容から除外したのですよ」
「皆さん、なかなかお詳しいじゃないですか。中国で発達した火薬兵器は、まったく実用性皆無というわけでもないのですが、後世に与えた影響では欧州の大砲に適わないと考えまして、今回は講義内容から除外したのですよ」
「それじゃ悪いけど1つだけ質問させて。何で中国にはロケット兵器みたいなものがたくさんあるのに欧州では、ほとんど見かけないわけ?」
 「私が思うに 火薬文化の違い
ではないでしょうか?先ほども言いましたけど、中国では戦争以外でもいろいろと火薬を利用していました。それには、硝酸含有率が高いものから低いものまで様々です」
「私が思うに 火薬文化の違い
ではないでしょうか?先ほども言いましたけど、中国では戦争以外でもいろいろと火薬を利用していました。それには、硝酸含有率が高いものから低いものまで様々です」
「ロケットの推進薬は比較的燃焼速度が遅い…すなわち硝酸含有率が低い火薬だ。欧州人が火薬を専ら銃砲用途に用いたのならば、なるべく硝酸含有率の高い火薬を求めるはず。そして、そのような火薬はロケット推進薬には適さない、ということだな」
 「ご明察。それに、当時のロケットなんてどこに飛んでいくか分からないような兵器で非効率的ですから。当初は高価だった火薬をそんな無駄なことに使おうと思うはずもなかったのではないですかね」
「ご明察。それに、当時のロケットなんてどこに飛んでいくか分からないような兵器で非効率的ですから。当初は高価だった火薬をそんな無駄なことに使おうと思うはずもなかったのではないですかね」
「・・・今回は講師が2人いるみたいね」
 「さて、話を戻しますよ。 『ロジャー・ベーコン』
は火薬を危険なものとして一般に知られないように、本に火薬のことを書くときに暗号使ったりして、欧州に火薬が広まらないようにしたそうですが、全く無駄でした。中国から様々なルートで入ってくるのだからどうしようもなかったでしょう。というかその火薬の製法の写本は 偽書
とも言われており、この説はちょっと怪しかったりもするんですけど」
「さて、話を戻しますよ。 『ロジャー・ベーコン』
は火薬を危険なものとして一般に知られないように、本に火薬のことを書くときに暗号使ったりして、欧州に火薬が広まらないようにしたそうですが、全く無駄でした。中国から様々なルートで入ってくるのだからどうしようもなかったでしょう。というかその火薬の製法の写本は 偽書
とも言われており、この説はちょっと怪しかったりもするんですけど」
「まぁ、昔のことだから仕方がない。それより具体的にはいつ頃、欧州に火器が登場したんだ?」
 「さすがに正確な年代までは不明ですが、少なくとも 1320年代には一般的な兵器になりつつあった
ようです。フィレンツェには『金属の大砲』の調達を命じる1326年2月11日付けの書類が残っているそうですよ」
「さすがに正確な年代までは不明ですが、少なくとも 1320年代には一般的な兵器になりつつあった
ようです。フィレンツェには『金属の大砲』の調達を命じる1326年2月11日付けの書類が残っているそうですよ」
「その時代の砲兵の編成・装備・軍事ドクトリンは?」
 「え~と…今回は具体的な運用についてはパスしちゃいます。とりあえず、当初は野戦ではあまり役に立たず、 専ら攻城戦で運用された
と憶えておいてくださいな」
「え~と…今回は具体的な運用についてはパスしちゃいます。とりあえず、当初は野戦ではあまり役に立たず、 専ら攻城戦で運用された
と憶えておいてくださいな」
「チッ…つまらん」

「それじゃ今回は大砲の何について教えてくれるわけ?」
 「いいですか。大砲そのものについての説明もしますが、大砲を語るにはまず火薬、そう 黒色火薬
について理解を深めておく必要があります。この黒色火薬が大砲という兵器を生んだのですから基本として押さえておくべきでしょう」
「いいですか。大砲そのものについての説明もしますが、大砲を語るにはまず火薬、そう 黒色火薬
について理解を深めておく必要があります。この黒色火薬が大砲という兵器を生んだのですから基本として押さえておくべきでしょう」
「う~ん…言わんとすることも分からなくはないけど…」
 「黒色火薬は、可燃物として木炭と硫黄、酸化剤として硝酸カリウムの三成分の混合物で色は黒く、吸湿性がある。発火温度は粉火薬で290℃、粒状薬で300℃で炎・摩擦・静電気・衝撃に対して敏感で発火しやすい。燃焼速度は数cm/s~400/sであり爆轟はしない。木炭は酸化して熱と炭酸ガスを発生し、衝撃感度を鈍化させる効果を有する。硫黄は着火温度を下げガス発生量を増し炎を大きくし衝撃感度を高めると共に爆発生成物中の一酸化炭素と青酸の発生を抑制する。爆発すると、固体物質が約55%、気体が約45%発生する。爆発熱は約700~750kcal/kgである。比較的安定で長年貯蔵してもほとんど変質せず直射日光にさらされてもほとんど変化しない…」
「黒色火薬は、可燃物として木炭と硫黄、酸化剤として硝酸カリウムの三成分の混合物で色は黒く、吸湿性がある。発火温度は粉火薬で290℃、粒状薬で300℃で炎・摩擦・静電気・衝撃に対して敏感で発火しやすい。燃焼速度は数cm/s~400/sであり爆轟はしない。木炭は酸化して熱と炭酸ガスを発生し、衝撃感度を鈍化させる効果を有する。硫黄は着火温度を下げガス発生量を増し炎を大きくし衝撃感度を高めると共に爆発生成物中の一酸化炭素と青酸の発生を抑制する。爆発すると、固体物質が約55%、気体が約45%発生する。爆発熱は約700~750kcal/kgである。比較的安定で長年貯蔵してもほとんど変質せず直射日光にさらされてもほとんど変化しない…」
「あ~分かった分かった。もういいから」

「話にならんな。米軍仕様の RDX (MIL-DTL-398D-Amendment 1,RDX,April 17,1999)の爆速は8950m/sだぞ」
 「現代の爆薬と黒色火薬を比べないでください!そんなこと言うなら octanitrocubane
の爆速は9898m/sですよ」
「現代の爆薬と黒色火薬を比べないでください!そんなこと言うなら octanitrocubane
の爆速は9898m/sですよ」
「・・・確かに比較は無意味だ。すまない」
 「はい。それでは続けますね。当初、 黒色火薬は欧州で非常に貴重品
でした。それは黒色火薬の原料となる硝石が欧州では産出されないため輸入に頼らざるを得なかったからです」
「はい。それでは続けますね。当初、 黒色火薬は欧州で非常に貴重品
でした。それは黒色火薬の原料となる硝石が欧州では産出されないため輸入に頼らざるを得なかったからです」
「中国から輸入していたの?」
 「中国南部と南アジア一帯、特にインドのガンジス川峡谷あたりで質の良い硝石が産出されました。それを輸入していたわけですね」
「中国南部と南アジア一帯、特にインドのガンジス川峡谷あたりで質の良い硝石が産出されました。それを輸入していたわけですね」
「火薬がなければ大砲などただの金属塊に過ぎない。その火薬の値段が高いということは、 運用側が思うように使用できないという意味 だ。火砲黎明期の大問題だな」
 「火薬の値段も問題でしたが、もう1つ大きな問題がありました。それは 大砲の強度の問題
です」
「火薬の値段も問題でしたが、もう1つ大きな問題がありました。それは 大砲の強度の問題
です」
「大砲が 暴発 しちゃうわけね」
 「はい。14世紀初め頃の大砲は 鍛鉄砲
、すなわち鍛冶屋さんが鉄の輪をいくつも並べて溶接して、最後にタガをはめて作る大砲が主流なんですが、この溶接が不完全で頻繁に暴発したのですよ」
「はい。14世紀初め頃の大砲は 鍛鉄砲
、すなわち鍛冶屋さんが鉄の輪をいくつも並べて溶接して、最後にタガをはめて作る大砲が主流なんですが、この溶接が不完全で頻繁に暴発したのですよ」
「そういえば 『barrel』には砲身と樽という意味があった が、この当時の鍛鉄砲を作っていた職人が樽職人だったからと聞いたことがある。素材は違うが基本的には樽と似たような作り方で大砲を作っていたようだな」

「そりゃ暴発もするわね」
 「ですから、 初期の大砲は比較的小型なものが多かった
ようです。しかし、やがてその状況に変化が訪れることになりました。なんだと思いますか?」
「ですから、 初期の大砲は比較的小型なものが多かった
ようです。しかし、やがてその状況に変化が訪れることになりました。なんだと思いますか?」
「頑丈な砲身を作れるようになったとか?」
 「それはもうちょっと後の話ですね~」
「それはもうちょっと後の話ですね~」
「そうなると答えは、もう1つの火薬の問題が解決した…ということになるな」
 「はい。欧州でも 醸成場で硝石を生産できるようになりました
。その為、値段がどんどん下がっていったのですよ」
「はい。欧州でも 醸成場で硝石を生産できるようになりました
。その為、値段がどんどん下がっていったのですよ」
「どのくらい安くなったの?」
 「そうですね。14世紀末から値段が下がり始めたのですけれども、値段の下落が終わる 15世紀末には1380年代の2割以下
になってました」
「そうですね。14世紀末から値段が下がり始めたのですけれども、値段の下落が終わる 15世紀末には1380年代の2割以下
になってました」
「へぇー~なかなかお手頃価格になったもんね」
 「 石造りの穴蔵と動物の糞尿さえあれば硝石を生産できる
のですから、典型的な農民の産業となって広く普及したわけです。輸入品に加えて豊富な欧州産硝石が出回った訳ですから、需要と供給の関係で、そりゃもうお安くなりますよ」
「 石造りの穴蔵と動物の糞尿さえあれば硝石を生産できる
のですから、典型的な農民の産業となって広く普及したわけです。輸入品に加えて豊富な欧州産硝石が出回った訳ですから、需要と供給の関係で、そりゃもうお安くなりますよ」
「火薬が安く容易に入手可能になるということは、 大砲を導入するインセンティブが大きく高まった ことになるな。大砲の普及が進めば大砲そのものも値段が下がるだろう。そして技術革新も進んだに違いない」
 「14世紀末から15世紀半ば頃までに 鍛鉄砲の値段も2/3
くらいになっていますね。技術的にも、より大きな砲が作れるようになっていったようです」
「14世紀末から15世紀半ば頃までに 鍛鉄砲の値段も2/3
くらいになっていますね。技術的にも、より大きな砲が作れるようになっていったようです」
「大きいって言ってもどれくらい大きいの?」
 「そうですね~有名どころではエディンバラ城にある 『モンス・メグ』
ですかね。ブルゴーニュのフィリップ善良公のためにフランドル地方で鋳造された大砲で、後にジェームズ2世に贈られたものですが、スペックは口径19.5インチで549ポンドの石弾を打ち出せたみたいですよ」
「そうですね~有名どころではエディンバラ城にある 『モンス・メグ』
ですかね。ブルゴーニュのフィリップ善良公のためにフランドル地方で鋳造された大砲で、後にジェームズ2世に贈られたものですが、スペックは口径19.5インチで549ポンドの石弾を打ち出せたみたいですよ」

「口径だけなら大和級戦艦以上か…。さすがに砲弾の重量では劣るようだが」
 「もっと大きいのもありますよ~。 『ドゥレ・グリート』
という鍛鉄砲は、口径25インチで750ポンドの石弾を打ち出す化け物です」
「もっと大きいのもありますよ~。 『ドゥレ・グリート』
という鍛鉄砲は、口径25インチで750ポンドの石弾を打ち出す化け物です」

「・・・莫迦でかい大砲ね。こんな大砲で攻撃されたら当時のお城なんてひとたまりもなかったんじゃないの?」
 「ところが、そういう訳でもないのです。これらの大きな大砲は強力ではありましたが、圧倒的な火力と言うほどの威力はありませんでした。なぜならば、脆弱な砲身を暴発の危険から守るために、装薬につかう火薬の量を制限していたからです。また砲身の内壁と石弾の隙間も意図的に大きくしてあったのですが、これも 弾道学的特性よりも安全性を重視した結果
でした」
「ところが、そういう訳でもないのです。これらの大きな大砲は強力ではありましたが、圧倒的な火力と言うほどの威力はありませんでした。なぜならば、脆弱な砲身を暴発の危険から守るために、装薬につかう火薬の量を制限していたからです。また砲身の内壁と石弾の隙間も意図的に大きくしてあったのですが、これも 弾道学的特性よりも安全性を重視した結果
でした」
「つまり、小さな初速でしか石弾を打ち出せないということか…。『運動エネルギー=速度の二乗×重さ÷2』だから初速が小さい分、威力も低いという訳だな」
 「逆に言うと、初速が低い石弾しか打ち出せないという技術的制約の範囲内で、石弾に十分な運動エネルギーを与える最良の方法が、 大砲の口径を大きくすること
だった、ということですね」
「逆に言うと、初速が低い石弾しか打ち出せないという技術的制約の範囲内で、石弾に十分な運動エネルギーを与える最良の方法が、 大砲の口径を大きくすること
だった、ということですね」
「でも大砲を大きくしたら使う火薬の量も増えるから、 暴発の危険が大きくなる んじゃないの?」
 「いえいえ、大砲が大きくなれば、その分砲身を肉厚にすることによって安全性を確保するわけですから、大きい大砲だから暴発しやすいというわけではありません。とは言っても暴発したら悲惨なことになってしまいますけど。『モンス・メグ』なんか攻城戦の指揮を執る ジェームズ2世を暴発事故でミンチ
にしちゃってます」
「いえいえ、大砲が大きくなれば、その分砲身を肉厚にすることによって安全性を確保するわけですから、大きい大砲だから暴発しやすいというわけではありません。とは言っても暴発したら悲惨なことになってしまいますけど。『モンス・メグ』なんか攻城戦の指揮を執る ジェームズ2世を暴発事故でミンチ
にしちゃってます」
「危なっかしいわね~」
 「他にもいろいろ問題があったんですよ~。それで、このような初期の巨砲はやがて廃れていくのです訳なんですけどね。『モンス・メグ』は総重量5トンにも達し、 水路を利用しない限り移動が極めて困難
で、実際に運用するのは大変だったようです」
「他にもいろいろ問題があったんですよ~。それで、このような初期の巨砲はやがて廃れていくのです訳なんですけどね。『モンス・メグ』は総重量5トンにも達し、 水路を利用しない限り移動が極めて困難
で、実際に運用するのは大変だったようです」
「 安全性と威力を確保しようとすると機動性が損なわれる 訳か。いくら強力でも必要な場所に移動させることが出来なくては意味がない」
 「そうですね~。『モンス・メグ』なんて出陣したときに エディンバラ城の外に出たとたんに砲架が壊れて出発が3日遅れた
とか、お莫迦なこともありましたし。古代ローマの時代と違って道もよく整備されていないから重量物を運搬するのはとても大変でした」
「そうですね~。『モンス・メグ』なんて出陣したときに エディンバラ城の外に出たとたんに砲架が壊れて出発が3日遅れた
とか、お莫迦なこともありましたし。古代ローマの時代と違って道もよく整備されていないから重量物を運搬するのはとても大変でした」
「間抜けね~。 大砲って実はあんまり役に立たなかったんじゃないの? 」
 「 そうですよ
。手間が掛かる割には役に立ちませんでした。少なくとも黎明期の大砲は」
「 そうですよ
。手間が掛かる割には役に立ちませんでした。少なくとも黎明期の大砲は」
「え?冗談のつもりだったんだけど…。役に立つから高価な大砲を頑張って揃えたんじゃなかったの?」
 「それがそうでもないんですよ~。初期の大砲は音と煙で威嚇効果は凄かったんですけどね。従来から使われていた 投石機の方がよほど役に立つ場合も多かった
ようです。木製で軽く、分解して運搬でき、現地で修理が可能。そして射程・命中率・投射質量どれをとっても当時の大砲と同等以上の性能でしたから」
「それがそうでもないんですよ~。初期の大砲は音と煙で威嚇効果は凄かったんですけどね。従来から使われていた 投石機の方がよほど役に立つ場合も多かった
ようです。木製で軽く、分解して運搬でき、現地で修理が可能。そして射程・命中率・投射質量どれをとっても当時の大砲と同等以上の性能でしたから」
「それに大砲は高価で重く、故障しても現地で修理は不可能。その上、暴発の危険まである。投石機と比べて優位点が多いとは言えないな」

「・・・何でそんな大砲なんかが普及したの?」
 「15世紀に入れば大砲もそれなりに使えるようになってくるのですけどね~。投石機という必要十分な能力を持った兵器があるにもかかわらず、14世紀の大砲黎明期に、なぜ少なくないリソースが大砲に投入されのかは難しい問題です」
「15世紀に入れば大砲もそれなりに使えるようになってくるのですけどね~。投石機という必要十分な能力を持った兵器があるにもかかわらず、14世紀の大砲黎明期に、なぜ少なくないリソースが大砲に投入されのかは難しい問題です」
「精神分析学的に言えば、大砲はある種の 性的象徴性 をもっている兵器であると言える。その心理的衝動によって不合理な大砲への投資を合理化することは出来ないだろうか?」

「 銃火器は男根を象徴 してるってやつ?そんな莫迦なことってあるのかしら」
 「正直分からない部分が多いですから。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。私は 木工ギルドに対する金属工ギルドの経済闘争
が影響しているという説を押しますけど」
「正直分からない部分が多いですから。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。私は 木工ギルドに対する金属工ギルドの経済闘争
が影響しているという説を押しますけど」
「なるほどね。 『攻城兵器市場』に新規参入したのが金属工ギルド だったということか。既存の投石機や攻城塔は確かに木製だ。木工ギルドに独占されていた市場に新製品で殴り込みをかけたわけだ。となると、当然ダンピングや政治工作でシェア拡大に突っ走り、初期の大砲がもつ技術的・経済的不利をカバーできたとも考えられる」
 「そうは言っても、確かに初期の大砲は手間が掛かる割には役に立たたないんですが、まったくの役立たずという訳でもないのです。大砲がやってきただけでびっくりして、城を明け渡したなんていう例もありますし、費用の掛かる攻城戦を短縮させることに貢献できる場合が多かったみたいですよ。主に 心理的因子
なんですけどね」
「そうは言っても、確かに初期の大砲は手間が掛かる割には役に立たたないんですが、まったくの役立たずという訳でもないのです。大砲がやってきただけでびっくりして、城を明け渡したなんていう例もありますし、費用の掛かる攻城戦を短縮させることに貢献できる場合が多かったみたいですよ。主に 心理的因子
なんですけどね」
「えぇ~大砲でびっくりさせることがそんなに重要だったの?」
 「 心理的因子
は意外に重要なんですよ!」
「 心理的因子
は意外に重要なんですよ!」
「戦争では 士気の喪失を誘う心理戦も重要 だ。防御側が進んで講和を行わせる気持ちにさせるためには虚仮威しも必要な場合がある。日本でも大阪冬の陣で淀君が家康側の大砲を恐れ講和を進めたという事例があっただろう」

「う~ん…大金かけて揃えて手間暇かけて得られる成果が心理的効果ってのも何だかね~」
 「別にそればかりではないんですけどね~。それに 攻城戦には大きな資金が必要
ですし、 野戦軍が長期間釘付け
になります。そのリスクを少しでも低減させる手管があるならば、何だってやろうと思いますよ」
「別にそればかりではないんですけどね~。それに 攻城戦には大きな資金が必要
ですし、 野戦軍が長期間釘付け
になります。そのリスクを少しでも低減させる手管があるならば、何だってやろうと思いますよ」
「結局のところ、 初期の巨砲は威力も大したことがない上に取り扱いが面倒なので廃れていった ってことでいいの?」
 「そうですね~。14世紀末から火薬は安くなっていったけど、装薬を増やすと暴発し易くなるし、仕方ないから口径を大きくすると重くなって動かすのが大変になってしまいます。ちなみに、この問題を改善するにはどうしたら良いと思いますか?」
「そうですね~。14世紀末から火薬は安くなっていったけど、装薬を増やすと暴発し易くなるし、仕方ないから口径を大きくすると重くなって動かすのが大変になってしまいます。ちなみに、この問題を改善するにはどうしたら良いと思いますか?」
「先ずは金属加工技術の発達を促し、軽くて丈夫な砲身を作ることだな。その上で火薬も燃焼速度の速い強力なものにする。あとは砲弾の改良くらいか」

「動かすのが面倒だったら 敵の城の前で大砲を作ってしまえばいい んじゃないの?そうすれば、どんなに大きな大砲でも問題ないんじゃないかな。ははは」

「ハァ?そんなこと誰がやるというのだ?敵の目の前で溶鉱炉でも作ろうというのか?。戦場でできるわけがない」
 「 マホメット2世
」
「 マホメット2世
」
「1453年にコンスタンチィノープルを陥落させたトルコのスルタンがどうかしたのか?」
 「貴方が聞いたのですよ。 『そんなこと誰がやるというのだ?』
って」
「貴方が聞いたのですよ。 『そんなこと誰がやるというのだ?』
って」
「 ・・・何の冗談だ? 」
 「いえ 事実
ですよ~。運搬が困難であるならば、現地で作ってしまえばよい…圧倒的な国力を持つ当時のオスマン・トルコだからこそ可能だった荒技ですけどね」
「いえ 事実
ですよ~。運搬が困難であるならば、現地で作ってしまえばよい…圧倒的な国力を持つ当時のオスマン・トルコだからこそ可能だった荒技ですけどね」
「あの三重防壁の目の前で、大砲を鋳造したというのか…。信じられん」
 「無茶ではありますが、不合理ではありません。そこまでしなければコンスタンチィノープルの三重防壁は破れなかったということでしょう。歴史に残る偉人はスケールが違いますね~」
「無茶ではありますが、不合理ではありません。そこまでしなければコンスタンチィノープルの三重防壁は破れなかったということでしょう。歴史に残る偉人はスケールが違いますね~」
「 全て私の読みどうりね! 」

「・・・ふん。 なんとかと天才は紙一重 と言うからな」

「私って天才~」

「.。oO(・・・莫迦は放っておこう)」
 「このエピソードは、実はトルコと欧州のその後の明暗を分ける重要な示唆を含んでいるんですけどね。 軍事技術の方向性というか考え方の違いが如実に表れちゃってます
」
「このエピソードは、実はトルコと欧州のその後の明暗を分ける重要な示唆を含んでいるんですけどね。 軍事技術の方向性というか考え方の違いが如実に表れちゃってます
」
「どういうことだ?」
 「トルコは 単純に大きな大砲
を作ることによって、威力を増大させ、大砲を攻城砲として進化させていきました。それに比べて欧州では逆になるべく小さくコンパクトにする替わりに初速の速い大砲を開発して、 野戦・攻城戦どちらにも対応できる柔軟性の高い大砲
に進化させていきました。これがやがて軍事力の差となって現れてくるのですが…そろそろ終わりの時間になってしまいました」
「トルコは 単純に大きな大砲
を作ることによって、威力を増大させ、大砲を攻城砲として進化させていきました。それに比べて欧州では逆になるべく小さくコンパクトにする替わりに初速の速い大砲を開発して、 野戦・攻城戦どちらにも対応できる柔軟性の高い大砲
に進化させていきました。これがやがて軍事力の差となって現れてくるのですが…そろそろ終わりの時間になってしまいました」
「時間切れか。残念だが仕方ない。ちゃんと次の講義でしっかり教えてくれ」
 「はい、承りました。次回は巨砲から機動力のある軽量化された大砲へと進化していく過程と野戦での運用についての講義とします。どうぞお楽しみに~」
「はい、承りました。次回は巨砲から機動力のある軽量化された大砲へと進化していく過程と野戦での運用についての講義とします。どうぞお楽しみに~」
「それじゃ、またね~」
次回へ続く(未完成)
※アイコンは 眠りの園 よりお借りしています。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 超多忙の目黒蓮、共演者も驚がく 浜…
- (2025-11-20 17:00:14)
-
© Rakuten Group, Inc.