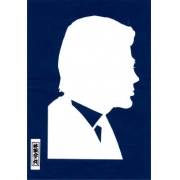テーマ: 落語について(2722)
カテゴリ: カテゴリ未分類
【粗筋】
「この行灯なら10両で買おう」
「え、そんなにするんですか」
「お前、どこで手に入れた」
「え、それは、そのー……」
「ここに、盗人の門(かど)閉(た)てて行く夜寒かな、という句が書いてある。これは能祇法師という、立派な先生の名前も入っている」
泥棒が驚いて能祇の家に行って謝ると、こんこんと意見をして、
「ところでお前に聞きたいことがあるが、最初に伊勢物語の本を持って逃げる時、どうして門を閉めて行ったのだ」
「へえ、開けっ放しでは物騒でございますから」
【成立】
【蘊蓄】
宗祇は飯尾宗祇(1421〜1502)。連歌師。
連歌は、上の句(五七五)と下の句(七七)を交互に作り、和歌として意味が通るようにするもの。普通百句一組(百韻)で、十セットを作る。第一は「発句(ほっく)」といって、その場への挨拶だから、その季節、集まった人々や自然、目の前の情景を描く。二句目は「脇」で、その雰囲気をつなぐ。第三からはどんどん世界が変わっていくようになる。四季が登場しなければならず、花と月は定位置がある。釈経(宗教)、恋なども出なければならない。
ここから俗な日常を読むようになったのが俳諧。ここでは和歌では詠まない病気、夫婦の営みなどまで登場する。本文の句は泥棒が出て来るのだから、連歌ではなくもう俳諧になっている。
発句だけがその場を詠むというので、松尾芭蕉は『奥の細道』で初めて、発句だけを記録することに挑戦した。最初の方では「表八句を庵の柱に懸け置く」として、連歌を詠んでいることを明らかにし、批判をかわしている。中に出て来る句(芭蕉のもののみ)がちょうど50句というのも、百韻の連歌を意識しているのである。これから発句だけを詠むことが始まる。
発句というのを「俳句」と呼ぶようにしたのは明治の正岡子規。彼は和歌も「短歌」と呼ぶようにした。

「この行灯なら10両で買おう」
「え、そんなにするんですか」
「お前、どこで手に入れた」
「え、それは、そのー……」
「ここに、盗人の門(かど)閉(た)てて行く夜寒かな、という句が書いてある。これは能祇法師という、立派な先生の名前も入っている」
泥棒が驚いて能祇の家に行って謝ると、こんこんと意見をして、
「ところでお前に聞きたいことがあるが、最初に伊勢物語の本を持って逃げる時、どうして門を閉めて行ったのだ」
「へえ、開けっ放しでは物騒でございますから」
【成立】
【蘊蓄】
宗祇は飯尾宗祇(1421〜1502)。連歌師。
連歌は、上の句(五七五)と下の句(七七)を交互に作り、和歌として意味が通るようにするもの。普通百句一組(百韻)で、十セットを作る。第一は「発句(ほっく)」といって、その場への挨拶だから、その季節、集まった人々や自然、目の前の情景を描く。二句目は「脇」で、その雰囲気をつなぐ。第三からはどんどん世界が変わっていくようになる。四季が登場しなければならず、花と月は定位置がある。釈経(宗教)、恋なども出なければならない。
ここから俗な日常を読むようになったのが俳諧。ここでは和歌では詠まない病気、夫婦の営みなどまで登場する。本文の句は泥棒が出て来るのだから、連歌ではなくもう俳諧になっている。
発句だけがその場を詠むというので、松尾芭蕉は『奥の細道』で初めて、発句だけを記録することに挑戦した。最初の方では「表八句を庵の柱に懸け置く」として、連歌を詠んでいることを明らかにし、批判をかわしている。中に出て来る句(芭蕉のもののみ)がちょうど50句というのも、百韻の連歌を意識しているのである。これから発句だけを詠むことが始まる。
発句というのを「俳句」と呼ぶようにしたのは明治の正岡子規。彼は和歌も「短歌」と呼ぶようにした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
Freepage List
© Rakuten Group, Inc.