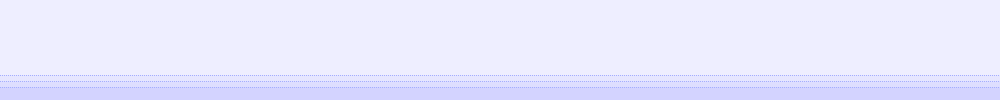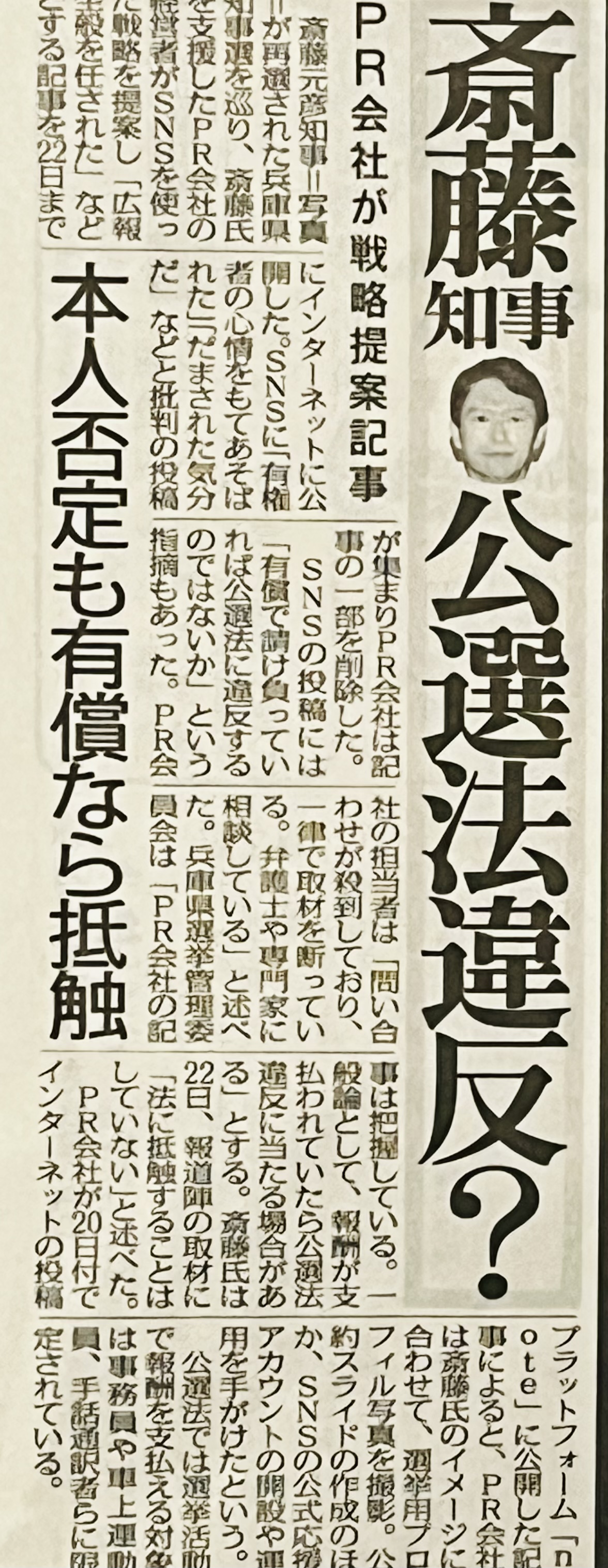[法律、制度] カテゴリの記事
全133件 (133件中 1-50件目)
-
夫の借金と妻の責任
うちの事務所でたまにある光景ですが、離婚がらみの相談ということで、夫である男性がこういった話を持ち出すことがあります。「私は借金をたくさん背負って、妻にも迷惑をかけたので、この際、妻と離婚したい。私には妻に与える財産はほとんどないので、私の持っている自宅の名義を妻のものにしたい」といった話です。弁護士ならこれを聞いて、誰だって「財産隠し」を疑うことでしょう。借金を背負った男性が、自分の資産を差し押さえられないように、離婚した妻への「財産分与」の名目で過大な資産を譲渡するわけです。こういった譲渡は、そもそも無効だし(民法94条、虚偽表示)、夫の名義に戻されて差し押さえされるし(民法424条、詐害行為取消権)、刑法上も犯罪になることがある(刑法96条の2、強制執行妨害罪)。ですからこういう相談については、上記のことを指摘しますし、「あなたがどうしてもやるというなら私は何も言わないが、私がその依頼を受けることはできません」ということにしています。そもそも、夫の借金はあくまで夫のものであって、妻に責任が及ぶわけではない。だから「夫の借金が妻に及ばないようにしたい」ということ自体が、法的に言えば誤りということになります。ただ「夫の借金は妻に及ばない」(妻の借金も夫に及ばない)という原則には、いくつかの例外があります。たとえば、妻が夫の保証人になった場合(それがイヤなら保証人のハンコをついてはいけない)、夫が死んで妻が相続した場合(借金が過大な場合は相続放棄すべきことになる)、日常の家事の範囲で夫が借金した場合(夫がツケで家庭用の食料や日用品を買ったなど)、がこれにあたります。それ以外に、夫の借金で妻に累が及ぶ場合として考えられるのは、債権者(貸主)がヤミ金融その他、違法な(またはスレスレの)取立てを行う類の人であり、妻に法的責任はないとわかっていながら嫌がらせ目的で取立てをする場合、が挙げられます。今回唐突に離婚と借金の話を書いたのは、小室哲哉が借金のあげくに5億円の詐欺事件で逮捕され、妻のKEIKOさんと離婚するとかいう話を報道で聞いたからです。これはあくまで一般論ですが、お金が集まるところには、あやしい人たちも集まってくるみたいなので、KEIKOさんにも違法な取立てが行っていたのかも知れません。「ダンナの借金は私にゃ関係ない」と開きなおればよいのですが、それでは済まないような背景もあったのかも知れないなと勝手に想像しています。
2008/11/05
-
「切腹しろ」との脅迫メールは何罪か
芸能ネタはあまり取り上げないようにしているのですが、春風亭小朝と泰葉の離婚後の騒動に関して法的に考察します。最近、ワイドショーで何度か取り上げられていまして、当人同士にしてみれば離婚についてはいろんな原因があるんだろうけど、他人から見ればまあ、取るに足りない話ではあります。離婚後、泰葉がブログで小朝のことを「金髪ブタ野郎」と書いて罵り、また何度も脅迫メールを送りつけていたと、泰葉がわざわざ自分で記者会見を開いて明らかにしていました。これらが名誉毀損や脅迫などの犯罪にならないのかについて、触れておきます。名誉毀損は、具体的な事実を指摘しつつ他人の名誉を毀損することを言います。刑法230条で3年以下の懲役。では「金髪ブタ野郎」はどうか。「金髪」は事実(髪を染めている)だけど、別に名誉を毀損するようなものでない。「ブタ」や「野郎」(男性に対する蔑称)、これはいまだ抽象的に留まるものです。このように具体的事実を伴わない場合は、侮辱罪という別の犯罪が成立します(刑法231条、30日以下の拘留または1万円以下の科料)。では、脅迫メールを送った点についてはどうか。脅迫は、人に対して害を加える旨を告知することを言います(刑法222条、2年以下の懲役)。「殺すぞ」「痛い目にあわすぞ」などと言うのが典型的です。泰葉がどんなメールを送ったかというと、記者会見のテレビなんかを見ていますと、「切腹しろ、私が介錯してやるから」といった内容だったとか(取るに足りないとか言いつつけっこう見ている)。「私がお前を殺す」と言えば脅迫ですが、「自分で切腹しろ」と言ってるわけですから、やや微妙です。もっとも、義務もないのに切腹を無理やりさせようとしたということで「強要罪」(刑法223条で3年以下の懲役)の未遂にあたる可能性や、自殺をそそのかしたということで自殺関与罪(刑法202条で7年以下の懲役)の未遂にあたる可能性が出てきます。実際には、小朝が警察に被害届を出すとは思われないし、警察もこんな話、立件しようとはしないでしょう。しかし、言葉も使い方次第では犯罪になるのであって、ブログやメールなど言葉を発信するのがいっそう簡単になった現代においては、よくよく考えてからしなければいけないのだと、改めて認識させられます。
2008/11/03
-
内容証明郵便を使うべき場合とは
前回の続き。費用が高くて手間もかかる「内容証明郵便」、これを利用すべきなのはどういう場合か。結論から言いますと、それは、「ある法律上の請求をするにあたって、それが認められるために必要な要件として、ある意思表示を一定の時期にしたことが要求されている場合」です。平たくいうと「ある意思表示をしたことについて、後から相手に『知らん』と言われると困る場合」です。具体的に示したほうが分かりやすいと思いますが、一番典型的なのは、「時効」を中断するときです。たとえば知人にお金を貸して、返済期日になっても返してもらえないままになっている。そのままだといずれ時効で権利が消滅してしまうので、時効期間(10年とか5年とか、権利の内容により異なる)が過ぎる前に「はよカネ返せ」と催告しておく必要がある。催告しておくとそこから6か月間は時効にならない(民法153条。ただきちんと時効を中断するためには訴訟を提起して訴状を相手に送る必要があります。同147条)。つまり、時効が来る前に催告したことを証拠に残しておかないと、あとから相手に「催告なんか受けていない」と言われると、時効が認められて借金を取り立てられなくなるわけです。だから、内容証明でもって、「カネ返せ」と言ったことを残す必要がある。この場合、配達証明や配達記録だけだと、「ある郵便物が届いた」ということしか証拠に残らないので、後で相手に「何か郵便が来たみたいだけど催告じゃありませんでした」とトボケられると困ることになるわけです。他に身近なものとしては、訪問販売で要らないものを買わされたので、特定商取引法に基づいてクーリング・オフで取り消したい、という場合があげられる。所定期間に取消の意思表示をする必要があるので、それをしたことを証拠に残す必要があります。(民法を勉強している方は、他に内容証明が必要なのはどういう場合か考えてみてください。ヒント、民法412条3項、467条2項、541条、591条など)このように、ある時期にある意思表示をしないと権利が消滅してしまうことというのは、かなり限定的であって、日常そうそうあるわけではない。ウチの事務所では、上記のように本当に必要なときにしか内容証明は使いません。相手にきちんと届いたかどうか不安だ、というだけなら、わざわざ内容証明ではなくて配達証明だけで充分なので、ウチではよくこちらを使います。何でもかんでも内容証明、というのは手間と費用の無駄です。配達記録という制度はなくなりますが、配達証明という方法がもっと利用されてもいいように思います。
2008/08/27
-
配達記録と内容証明
ネット上の記事で見たのですが、「配達記録郵便」が廃止されるらしい。配達記録郵便とは、郵便が届けられたときに受取人から受領印を取ることで、その郵便が届けられたという記録が郵便局に残るものです。郵便物を送ったことが後々の証拠として残る「ナントカ郵便」にはいろいろあって紛らわしいですが、それらを区別して適切な方法を選択すべきです。今回はそういう話。多くの方が聞いたことがあると思われる「内容証明郵便」とは、「こういう内容の手紙を送った」というのが証拠として郵便局に残るものです。だから郵便局でそれを出すときにはコピーを持参して保管してもらうことになる。1行何文字、1ページ何行までという字数制限があるなど、割と面倒です。料金は内容にもよりますが、だいたい1000円くらい。また、「配達証明郵便」というのもあって、これは郵便物が相手に配達されたことと、その日付が、郵便局からハガキで知らされる。ただ郵便物の「中身」(手紙に何を書いたか)まで証拠に残るわけではない。料金はだいたい800円くらい。この2つをミックスして、「内容証明」と「配達証明」の両方がついた郵便というのも可能で、そうすると、「こういう内容の手紙を何日に発送して」「それが何日に相手に届いた」ということが証拠に残る。料金は2つを足して2000円前後です。冒頭の「配達記録郵便」は、受取人から受領印を取るが、それが差出人に知らされるわけではない。ただ、あとあと何らかの問題が生じた際には、郵便局で調べればその郵便が付いていたかどうかがわかる。料金は安くて200円くらい。これが廃止されるらしいですが、うちではあまり使わないので、特に影響はありません。さて、「内容証明郵便」というのは、上記の通り所定の文字数や書式があり、手続きが面倒なだけあって、普通の手紙に比べると少し厳めしい感じがします。だから、例えば知人が借金を返さないなどといったトラブルの際に利用されることが多い。実際、内容証明を送りつけると、相手が驚いてお金を返してくれるようなこともある。しかし、内容証明郵便は法的に見れば単なる「手紙」です。郵便局がハンコを押してくれて、「こういう内容の手紙を送った」ということが証拠に残るだけであって、その内容が正しいと認められたわけではないし、その主張に法的な強制力が発生するわけでもない。何でもかんでも内容証明を送る、という人がいますが、実際には内容証明にする意味のない場合も多い。不必要なのに内容証明を出すと、手間と費用が無駄にかかるだけです。何より、相手を驚かせてやろうと思って内容証明を出したのに、わかる人が見れば逆に「こけおどしだ」と内心笑われることも予想される。では、郵便物を内容証明で出すべきなのはどういう場合か、これは次回に続きます。
2008/08/26
-
法曹人口問題6 改革と増員の行方
法曹人口問題について、あと少しだけ。我が大阪弁護士会では、上層部と若手で増員に対する提言の内容に温度差がありますが、重要なのは、増員しすぎは見直せ、という点では一致しているということです。「法曹」(裁判官、検察官、弁護士の三者をいう)を増やすと言いながら、裁判官・検察官はほとんど増員されない結果、「裁判の迅速化」という司法改革の最重要課題は進展がない一方、弁護士だけがハイスピードで増え、若手弁護士の就職難が顕在化しつつある。司法改革の一環として導入された「法テラス」(相談先がない人に弁護士等を紹介する)や「被疑者国選弁護」(刑事裁判が始まる前から国費で弁護士がつく)は、経済的弱者の保護という美名のもとに、実際には弁護士に安い対価で仕事を押し付ける結果となっている。かような現状を、若手弁護士は深刻な問題として受け止めている。もっとも、先日の大阪弁護士会の臨時集会では、若手側の「提言」は上層部の組織票に押しつぶされ、政治的配慮に満ちた玉虫色の上層部案が通ったようです。私もいちおう若手の世代に入ると思うのですが、この問題に対して私がどういう立場を取ったかと言いますと、「特に何もしなかった」というのが実際のところです。若手グループの多くの人を私は直接存じておりますが、いずれも私以上に弁護士として優秀な方ばかりであり、したがってこの人たちは自分が仕事にあぶれるという心配をしているのでなく、自分の次の世代のことを考えてやっているのに違いありません。ただ、私はずるい人間なので、私自身のことしか考えていないだけです。司法改革や法曹増員が今後どうなろうと、私自身は弁護士としてとりあえずやっていけると思っています。それ以上のことは考えていません。法曹増員という政府方針が正しいことなのかどうかは知りません。どちらかというと疑問を持っています。でも、やるならどうぞ、というスタンスです。改革だ、増員だ、競争せよ、というなら、私はそれでけっこうです。でも、競争するからには国選弁護のような制度に協力はしないことになると思いますし、弁護士費用を払えないような人には、「ウチじゃなくて『法テラス』に駆け込んでくれ」と言うことになると思います。そうしないと、正当な対価を支払ってくれるウチの依頼者のための仕事に集中できないからです。弁護士間の競争になれば、おそらく何割かの弁護士が同様のことをするでしょう。それによって、「依頼者への法的サービス」は充実することになり、その点では「司法改革」の目的は達成されるでしょう。経済的理由などで弁護士に依頼できない人は、「法テラス」のような「セーフティーネット」で救済されることになるのでしょう。私自身は、弁護士というのは行き過ぎた競争は必要ない代わりに、自発的に弱者のための公益的活動をする、というのが美しい姿である(そのためセーフティーネットが自動的に働く)と思っているのですが、司法改革と法曹人口増員によってそのような弁護士のあり方は今後少しずつ失われていくことになるでしょう。それが大多数の国民にとって望ましいことかどうかはわかりません。しかしこれが司法改革と法曹増員の近い将来の姿となると思われます。最後がまとまりのつかないままとなりましたが、ひとまずこの話題を終了します。
2008/08/12
-
法曹人口問題5 「3000人」への増員は見直すべきか
法曹人口問題について、あと2回ほど続く。法曹の質の確保のために適切な司法試験の合格人数は、私の個人的経験からして1500人程度だろうと書きました。司法改革についての政府方針は年間3000人をめどとしているが、それだと多すぎることになります。で、次の問題。ではこの3000人への増員は見直すべきなのか。ここでも書いたとおり、先日、日弁連会長が「見直し」を提言したところ、官房長官が「見識を疑う」と言った。日弁連会長が言ったのは「質の確保のための見直し」であって、人数を減らせと明言しているわけではないが、端から見れば「今になってどうして」という感じを受けるかも知れない。これはおそらく、今から10数年くらい前、現在では弁護士界の長老となっている人たちが、当時の財界や政府に丸め込まれたということでしょう。司法改革とか法曹人口増大とか、当時は多くの弁護士が「ジイサンらが調子のエエこと言うてよるなあ」くらいに聞き流していた。それが近年では、実際に司法試験合格者数が増加し、一部で弁護士の就職難が現実化した。今さら何をと言われても、ここでこの流れを止めないと、と思っている人も多い。そしてこの問題は、私が所属する大阪弁護士会でもホットな争点となっており、いくつかの新聞に報道されたのでご存じの方もおられると思います。大阪弁護士会の会長以下の上層部と、若手弁護士たちの間で意見が割れている。もっとも、上層部も若手も、増員問題に見直しをすべきであるという提案を採択してアピールしようという点に違いはない。ただ上層部は「適切な見直しをすべきだ」という玉虫色の表現を取るのに対し、若手は「直ちに1500人程度に減少すべきだ」という、言わば政府方針に明確に反対するアピールをしようとしている。詳しい話は省きますが、上層部には各方面に対する政治的配慮が働いていることが容易に想像されます。若手グループにはそういった配慮は必要ない。しかも自分たちのすぐ次の世代の弁護士や司法修習生が、満足に就職もできずにいる場面を直に見ているので、増員見直しは深刻な課題となる。この問題に対し、当の弁護士としてはどうアピールすべきか、私の考えは次回に続くということで、ひとまずお茶を濁しておきます。
2008/08/08
-
法曹人口問題4 弁護士間競争の弊害について
法曹人口問題について、続き。弁護士に資本主義の論理や競争原理を単純に導入するのは問題となる余地を含むと前回書きました。市民法律相談や当番弁護士などを例として挙げましたが、そういった制度的なこと以外でもっと重要なことがあります。弁護士としての日常業務の中で、「この人にはお金がないけど何とかしてあげたい」という人はたまにいる。私自身、そういうときに、着手金を分割払いにするとか、ほとんど「実費」だけで事件を処理することも、なくはない(普通はしていませんので、それを期待して当事務所に来ることはご遠慮ください)。私だけでなく、多くの弁護士が似たようなことをしていると思います。これはいつか改めて書きたいと思いますが、たとえば無実の罪を着せられて再審で無罪を獲得したとか、そういう重大事件でも、弁護士がほとんど対価を受けていないこともある。しかしこれなど「不採算事業」の最たるものでして、市民相談みたいに半日の拘束で済まずに、何年がかりになることもある。そんな事件でも受けるのは、弁護士の多くが「素朴な正義感」を持っているからですが、裁判官や検察官みたいに税金から給料をもらっていない立場でもそんなことができるのは、「弁護士の経済的基盤が安定しているから」です。つまり、弁護士の多くは、正義感だけでやっている不採算事業ばかりでなく、相応の経済的対価を見込める事件も抱えている。両方をこなしていれば、トータルとして法律事務所の経営は成り立っていくわけです。しかし今後、弁護士の数を増やして競争させるようにすれば、経済的にも心理的にも余裕のない弁護士が今よりは増えるでしょう。経済的に余裕があって初めての正義感です。妻子に満足に食わせずに儲からない事件ばかりやっているとすれば、弁護士としては立派でも、人間としては失格でしょう。今はまだ、自分や家族が食べていくことのできない弁護士はいないでしょうけど、増員が過ぎると、特にこれから弁護士になる若手においてそういうことになりかねない。かくて、弁護士に競争は、もう少しはあってもいいけど、行き過ぎると弊害が生じる。それが「弁護士の経済的窮迫」で済めば、個々の弁護士の自己責任だからまだ良いが、大げさに言うと「国民の間に正義が実現されなくなる」という大問題となる余地もあるのです。
2008/08/04
-
法曹人口問題3 弁護士に「競争」を行わせるべきか
法曹人口問題について。3回目。弁護士人口を拡大して弁護士に「競争」させることの是非について。法曹人口増加論者の主張の大きな根拠の一つとして、弁護士にも競争原理を導入すべきだという論理がある。競争が起こって市場原理が働けば、弁護士のサービスもよくなり、依頼するときのコストが下がるだろうということでしょう。「弁護士が増えすぎると食うにも困るようになる」などとして増加に反対する弁護士に対しては、業界のエゴだとか、自らの収益を改善せよとか言った批判が向けられることが多い。私自身としては、たしかに日本全体で見れば弁護士はまだ数が少ないと思うし、もう少し増やして競争させたほうがいいと思う。当ブログでも何度か似たような話をしましたが、私は弁護士とはサービス業だと思っています。その私から見て、人間的にちょっとおかしいのではないかと思えるような、到底サービス業に向かなさそうな弁護士は割合多い。何十年か前、もっともっと弁護士の数が少なかったころなら、「昔、司法試験に受かった」というだけで一生をエラそうに生きていくこともできたのかも知れませんが、私はそういう弁護士など仕事にあぶれてさっさと退場してくださればいいと思っています。そういう意味で、ある程度は競争があってもよいと考えるのですが、それを強調しすぎると、明らかにおかしなことになりそうに思っています。資本主義社会におけるような競争原理が働くことになると、弁護士は一般の私企業と同じ考えのもとで行動し、収益改善のためにコスト削減や不採算事業からの撤退といったことが行われるようになります。不採算事業として撤退が予想されるのはこういうものです。半日間ほど拘束される、市役所などでの「無料市民法律相談」。弁護士が受ける日当は1万円少々です(市からはもっと出ているけど弁護士会が「負担金」名目でピンハネしているらしい)。弁護士なら、その時間帯に自分の事務所で通常の相談業務をしていれば、2~3万円の収益になる。ならば市民相談なんてやめようということになる。こんな計算をするのは私自身イヤですけど、収益を改善するというのはこういうことでしょう。刑事事件の容疑で逮捕された直後に弁護士が出動する「当番弁護士制度」。これも同じように、拘束時間は長く、日当も1万円程度です。これもヤメるという弁護士が増えれば、たとえば痴漢冤罪で警察に連行されても面会に来てくれる弁護士がいなくなる。競争せよ、収益体質を改善せよ、と言われれば、現役の若手弁護士はいくらでもするでしょうけど、果たしてそれでよいかは疑問です。この問題については次回もう少し書きます。
2008/08/01
-
法曹人口問題2 質の確保のための合格人数は
法曹人口問題について。第2回。質の確保のために適切な合格人数はどれくらいかということについて。「3000人合格」見直し論者の多くの方は「1500くらい」という数字が適切としているようです。一方、法曹関係者以外の方からすれば、「司法試験なんてもともと難しい試験なんだから、何万人の受験者のうち上位3000人くらい合格させても優秀な人が取れるんではないか」と感じる方も多いかも知れません。私としては、結論的には法曹関係者の多くと同様、1500くらいが妥当と考えているのですが、以下、自分自身の狭い経験に基づいて私なりの根拠を述べます。私は平成9年、司法試験に落ちて、翌10年に二度目の受験で合格しました。過去には司法書士試験や社会保険労務士試験など、法律系の国家試験には難なく受かってきた(と自分では思っている)ので、司法試験も一発合格を目指したのですが、さすがに手ごわく、「合格発表を見にいったときに自分の受験番号がない」という経験を生まれて初めて味わいました。思い出話はともかく、私が落っこちた平成9年の司法試験では、マークシート試験には受かったものの、次の論文試験で落ちました。論文試験に落ちると、自分の成績はどれくらいであったのかということが、AからGの7段階にランク付けされて通知されます。要するに、あまりにランクが低い人はさっさとあきらめなさいということでしょう。私のランクは「C」ランクでした。これは「上位1501番~2000番」を意味します。こうして私はもう1年間、再起を期して勉強を再開しました。詳しくは書きませんが、その時期は「猛勉強」したと言い切らせていただきます。そして2年目に合格しました。その年(平成10年)の合格者はたしか812人でした。受かった後になって思えば、1年目の受験のときもかなり勉強はしたつもりですが、やはりまだ理解が浅かったし、論文試験のときに書いた答案もまだまだ甘い内容だったと思っています。私が「法律的なものの考え方」なるものを身につけて、現在何とか法律家の端くれとして弁護士業務をしていられるのも、受験2年目で身に付けたところによるものが多いと思っています。仮に私が1回目の受験で合格していたとしたら、不充分な実力のまま司法試験に一発合格したことで「やはり俺はエリートだ」と増長してしまい、弁護士としてまた人間として、どこかで道を誤っていたような気がしています。そして現在に戻って考えてみますと、現在の合格者数は約2000人です。繰り返しますが私が1回目に受験したときの成績順位は「1501番~2000番」ですから、現在なら、私は1年目の実力で合格していたことになります。近い将来、これが3000人になるとされているから、当時の私を下回る実力の方がさらに1000人も合格することになる。私自身の過去の反省も踏まえて考えてみて、私の受験1年目程度の実力の方を弁護士として世の中に出すのは、少し危なっかしいと思っています。だからそれを排除するということで、1500番までくらいが妥当なのではないか、というのが私の個人的経験からの実感です。
2008/07/30
-
法曹人口問題についての考察
最近の法曹人口問題の動きについて。私も弁護士の端くれとして、この話題には触れないと、と思っていましたので書きます。「司法改革」の一環として、司法試験の合格人数を年間3000人程度にするという政府の方針について、日弁連の宮崎会長が「法曹の質を確保するための見直しをすべきではないか」と言ったとか。それに対して、政府側の町村官房長官は、今さらそんなことを言い出すとは「見識を疑う」と言ったらしい。司法試験の制度改革についてはここでも何度か書いたと思いますが、少し前までは合格人数が毎年4~500人だったのが、私が合格した平成10年では800人、最近では2000人程度になっている。なぜ司法試験の合格人数を増やすかというと、裁判官の数を増やして裁判の迅速化を進めることや、弁護士の数を増やして競争させて依頼するときのコストをさげたいなどの、経済界の要望に基づくものであると(他にもいろんな要素はあるかも知れませんが)一般的に言われています。しかし、司法試験の合格人数を増やしてみたものの、裁判官や検察官はそれと比例して採用人数が増えているわけではなく、弁護士になる人だけが加速度的に増えている。それで、これから弁護士になろうという司法修習生には、都市部では採用してもらえる弁護士事務所がないという就職難の状況が増えているようだし、現在弁護士をやっている人でも、今後競争激化による収益の悪化を不安に感じている人もいると聞きます。さて、これらの現状を前提として、この問題について触れてみたいと思うのですが、論点としては、・法曹の質の確保のために適性な司法試験の合格人数はどれくらいなのか。・合格人数を増大させることによって弁護士に競争を行わせるのが果たしてよいのか。・日弁連会長が言ったように、合格人数増大という政府方針は見直すべきなのか。これらの点について、収拾がつくのかどうかわかりませんが、私の個人的な考えを次回以降に述べてみたいと思っています。(司法試験改革にからんで、法科大学院制度については過去の記事に何回かに分けて書きましたので、興味ある方は合わせてご参照ください。長いですけど)
2008/07/29
-
道交法改正と過失相殺
先週書いた、ブログ読者からのリクエスト編、続き。以前も書きましたが、ご希望のテーマがありましたらお寄せください。ただし私の得手・不得手により、内容には程度の差が生じる(不得手なテーマは浅い話しか書けない)のでご了承ください。道交法改正により自動車の後部座席にもシートベルト着用が義務づけられるようになったが、これはいかなる影響をもたらすか。特に弁護士としては、「過失相殺」(かしつそうさい)の判断に与える影響に興味があります。誰しも常識的にご存じかと思いますが、交通事故に遭った被害者は加害者に対し、治療費などの損害賠償を請求できる。しかし被害者自身にも何らかの落ち度があれば、双方の落ち度(過失)の割合に応じて、賠償金額が割引される。これを過失相殺といいます。運転席や助手席の人なら、シートベルトをしていなかったせいで衝突により大ケガをしても、請求できる賠償額は大幅に割り引かれるでしょう。後部座席であっても、シートベルトをしないためケガが拡大することがあるのは以前から知られていると思います。そして実際、ベルトなしでケガが拡大したと言える事故であれば、過失相殺が働くでしょう。そう言えるかどうかは、被害者のケガの内容によって判別するのでしょう。(たとえば体が前に飛び出して頭や胸をどこかにぶつけてケガしたのなら、ベルトによって防げたと思われ、ムチ打ち程度であればベルトの有無であまり違いはないかも知れない)結局、過失相殺が働くか否かは、被害者が被害防止のためにどれだけ注意を払っていたか、そして注意を払っていないことがどれだけ被害拡大につながったか、という観点から判断される。その点は、道交法が改正される前でも後でも変わるところはない。では、今般の道交法改正はどういう意味を持つか。違反者から点数を引く以外に意味はないのかというと、たぶんそれだけではない。この改正により、従来よりいっそう、後部座席にもシートベルトが必要という意識が広まるようになると思いますし、そういう意識の広まる中で、ベルトをしないことによってケガが拡大した場合、過失相殺の割合(賠償金額が割り引かれる割合)が増えていくという傾向が判例上も見られるようになると思います。私自身は車を運転しないので、最近の道交法改正とガソリンの値上げはあまり身近でない話として聞いておりまして、このような浅い話しか書けません。個人的には、大阪でタクシーに乗ったとき運転手さんが「ベルト締めてや」とあまり言わないのが不思議に思っており、タクシー会社は今般の改正をどう考えているか知りたいのですが、その辺は機会があれば調べてみます。
2008/07/08
-
民法772条とその裏の「声なき声」
民法772条のことについては、従来から何回も書いてきました。もっとも私自身、真に書きたかったのは、この条文そのものというよりは、「ある制度の改廃を論じるにあたっては、特定の事例だけを取り上げて短絡的に結論すべきでない」ということであって、それを民法772条を題材に書かせてもらったということです。この条文のせいで出生届を提出されず、戸籍がない子供がいる。母親がその子を抱いて、「この子にも戸籍を与えてください」などと涙ながらに訴えている場面を見せられると、「そうだ、かわいそうじゃないか、こんな悪法は廃止してしまえ」と感じる人は少なくないでしょう。しかし、その部分だけを取り上げてこの条文を廃止するとどうなるか。ある女性から生まれてくる子供が「本当に」前夫Aの子供であった場合、Aがその女性を「追い出し」的に離婚してしまったとしても、Aは子供の養育費を払わなくてよくなる。その子は「前夫Aの子」と扱われなくなるからです。女性がAと死別した場合は、Aの財産の相続権は子供でなくAの両親、つまりその女性からみて舅と姑に行く。舅と姑はきっと、ニンマリほくそ笑むことでしょう。民法772条は本来、生まれてくる子供を保護するための規定です。これを制定した当時(昭和20年代)は、夫Aと離婚または死別した後ほどなく生まれてくるのは通常そのAの子であると考えられ、その期間に別のBの子供が生まれるなどということは、あまり想定していなかったのでしょう。「時代に合わない」などと言ってこの条文を廃止すれば、通常想定されているケース(子が実際にAの子であるケース)の保護がなくなり、上記のようなことになる。そうなればその母親がその子を抱いて、「この子に養育費を」「父の子としての相続権を」と涙ながらに訴え出すでしょう。そしてその数は間違いなく、現在「この子に戸籍を」と言って泣いている女性の数の比ではないくらいに膨大でしょう。ある制度によって不利な扱いを受けている人がいて、その人が声をあげて、制度を改正(または廃止)すべきだというベクトルが働く。しかしその一方では、その制度のおかげで保護されてきた人々はたくさんいるはずで、改正すべきでない、現状を維持すべきだというベクトルも働いている。その現状維持のベクトルはたいていの場合、「声なき声」であって目立ちにくい。民法772条の問題に限らず、特定のケースや一部の「声」だけで制度を廃止・改正すると、もっと不都合なことが起こる。だから「声なき声」を慎重に聞かないといけない。とはいえ民法772条と戸籍の問題は、「一部の特殊なケースだ」「そんな時期に別の男性の子供を生んだ母親の自己責任だ」と言って済ませられないほどの状況になりつつあるのは事実です。そういう事実を前にして、民法772条を変えるか否かは、最終的には国会が決めることです。ひいては国会議員を選ぶ私たち国民が決めます(私自身は変える必要はないと思います)。今回、最高裁がやろうとしたのは、存在する法律を尊重しつつ、かつ一部で不合理なケースが生じているのを救済するために運用を改善するということであって、妥当な結論であると考えます。
2008/07/05
-
民法772条と認知調停
民法772条に関する最近の動き、続き。最高裁は、この条文のために実父Bではなく前夫Aの戸籍に入ってしまうのを回避する方法として、家庭裁判所での「認知調停」が使えるとの見解にたっているようです。認知というのはご存じのとおり、父親が生まれてきた子供を「自分の子だ」と認めることです。本来の単純な「認知」は、父親が役所に届出を出すだけでできる。もし父親が認知しない場合は、子供(実際は母が代理)が父親を訴えて、裁判によって認知の効力を認めてもらう「強制認知」という手続もある。「認知調停」というのは、子供(と母親)が父親を相手として「話し合い」の上で認知してもらおうという手続です。調停の相手方となるのはこの場合、上記の実父Bです。前夫Aとはケンカ別れしていて疎遠になっていても、Bはきっと母親に協力的だろうから、当然話し合いにのってくれて、認知するという調停が成立することが容易に予想できる。いわば「出来レース」なのですが、これをやることの意味は何かというと、家庭裁判所という公の場で、裁判官や家裁調査官も介入して、母親や実父Bから事情を聴くことによって、Bが父親であると認めてよいかを判断するというプロセスが入るということにあります。実父Bが役所に届け出るだけの単純な認知であれば、民法772条によって前夫Aが父と「推定」される効力が勝ってしまう。そのため、法律を執行する立場にある役所としては、Aと離婚前または離婚後300日以内に生まれた子供は前夫Aの子供と扱わざるをえない。最高裁は、その「推定」が破られるのはどういう場合であるかの指針を示したわけです。家裁が介入して一応の調査をした上で行う認知調停が成立したのであれば、役所としてはBの子と扱ってよい、ということです。それでもまだ「どうして実父の戸籍に入るためにわざわざ認知調停まで起こさないといけないのだ」と感じる向きもあると思いますが、お役所の判断ひとつで推定が破られる(Bの戸籍に入る)かまたは破られない(Aの戸籍に入る)かが決まるより、よほど明確でよいように思えます。
2008/07/03
-
民法772条問題 最高裁、遂に動く
当ブログが以前から取り上げております、民法772条の問題について、最近の動きを補足します。過去の経緯も含めて書いたら長くなったので、最新の動きのみサラッと読みたい方は、( )の中を飛ばして読んでください。民法772条とは、前夫Aとの離婚前、または離婚後300日以内に、別の男性Bとの間に子を生むと、真の父親である男性Bの戸籍でなく、前夫Aの戸籍に入ってしまうという規定です。それを避けたいがために母親が出生届を出さずに、住民票や戸籍がない子がいることが問題とされてきました。(この条文の趣旨と、これまでの問題については過去の記事にて整理しておりますので、ご参照ください。こちら )先月、報道されたところによると、総務省がこれらの子供を一定の条件のもとに住民票に記載する扱いを進めており、各役所に通達を出すらしい。(その要件というのは、1 子供が日本国籍を有するが、2 民法772条により前夫の子と扱われてしまうために、3 実父Bが認知するか、前夫Aとの調停(親子関係がないことを確認する)を進めている、といったものであるようです)ただこの通達というのは、「住民票」(住民基本台帳)に記載するための要件であって、これを満たしたところで実父の「戸籍」に入れてもらえるわけではないようです。住民票があれば確かに、実生活上の不都合はかなり解消されます。私も司法試験を受けるときに住民票を提出した記憶があるので、もし私に住民票がなければ弁護士になれていなかったわけです。それでも、根本的なところの戸籍の問題、誰かこの子の父親になるのかという問題は残る。住民票の問題は上記の要件でクリアされたとしても、民法772条が存在する以上、離婚後300日以内に生まれてきた子は前の夫の戸籍に入るのです。(それを救済するため、昨年5月に法務省が通達を出しました(詳細は上記記事)。ただこの通達で救済されるのは、前夫との「離婚成立後」に懐妊したことが証明できる場合に限られるため、離婚成立しないままに新しい子を身ごもった場合は救済されない問題は残っていました)そこで、新しく生まれた子供が前夫の子であるという推定を破り、民法772条の効果を排除する必要がある。(従来は、母親が子供を代理して、前の夫Aに対して「親子関係不存在」の確認を求める調停を家庭裁判所に起こし、そこで前夫に自分の子でないことを認めてもらうという方法がありましたが、それだと前夫の協力を得る必要があった。前夫がイヤで逃げてきたとか、前夫と音信不通とかいう人は利用できないわけです)この点に関しては遂に、最高裁が動き出したようです。最高裁が、各地の家庭裁判所に対し、「認知調停」の手続を活用できると通達する動きをとるらしい(本日の産経朝刊より)。と、書いているうちに長くなったので、これがどういう手続であるかは次回に続く。
2008/07/02
-
自動車運転致死傷罪と民事・刑事の責任
今日の話題は、「自称ブログ愛読者」の方からのリクエストにお答えします。自動車に関わる仕事をしている関係で、近年の刑法や道交法の改正、特に「自動車運転致死傷罪」や「後部座席のシートベルト着用の義務化」が、自動車運転者の民事責任・刑事責任にどう影響を与えるか知りたいと。30代男性の方からです。この方からはリクエストのメールをいただいてから長らく放置していましたが、読者の皆さまもリクエストがあれば寄せてください。女性からのリクエストであれば迅速にお答えするかも知れません。さて、自動車運転致死傷罪について。これは比較的最近、平成19年の刑法改正で定められたものです(刑法211条2項)。通常の業務上過失致死傷(同条1項)は上限が懲役5年ですが、自動車運転に関して不注意で人をひいてしまうと、上限は7年になる。自動車で人を死傷させた場合の罪が軽すぎるのは昨今言われていることです。すでに平成13年には「危険運転致死傷罪」が規定され(刑法208条の2)、酩酊などの危険な状態で車を運転して人をはねると、死亡させると懲役20年まで、ケガだけでも懲役15年までに科することができる。しかし、この罪の成立には、「当時酩酊状態であった」(かなりのアルコールを摂取している必要がある)、そして「それを認識していた」という比較的厳密な要件が要求され、福岡で公務員が車を追突させて3人の子供を死なせた事件ではこの厳罰が適用されなかったのはここでも書いたとおりです。 過去の記事1 過去の記事2業務上過失致死傷罪(5年)では軽すぎ、危険運転致死傷罪(20年)では重過ぎる、または立証するのが困難である、というときのスキマを埋めるのが、自動車運転致死傷罪であり、今後、車で人をひいた場合は、基本的にこちらが適用されることになるでしょう。この自動車運転致死傷罪を定める刑法211条2項には、一応の安全弁がついていて、傷害が軽いときは情状により刑を免除できるとある。軽いケガで済んだ場合は、犯罪は犯罪だけど、刑は科せられないということもある。その場合でも、民事上の責任は免れるわけではなく、ケガをさせた被害者からは損害賠償の請求がきます。実際の刑法の運用としては、刑を免除してよいかどうかの判断材料として、きちんと民事上の賠償が行えているか、示談が成立しているかという要素が考慮されることになるでしょう。さて、もう一つ書こうと思っていた、「後部座席のシートベルト着用の義務化」の問題については、また改めて、書くことにします。リクエストいただいた方にはすみません。
2008/06/30
-
「愛のムチ」条例は必要か 続き
教師による体罰の話、続き。学校教育法によると、学校の先生は、生徒に体罰を加えてはならないとある。では、体罰を加えた教師はどうなるかというと、学校教育法は体罰を加えた教師に対する処罰を定めていないので、刑法上の暴行罪・傷害罪を適用することになる。では、教師は体罰が禁止されている以上、刑法35条(法令または正当な業務による行為は罰しない)が適用されず、生徒に手を出したら必ず有罪になるのか、というと、そうはならないと思われます。判例にも実際に「正当な懲戒権の行使にあたる」として教師を無罪としたケースがあるようです。一方、体罰で生徒を死なせた事案では有罪とされたものもある。つまり、学校教育法が禁ずる「体罰」というのは、「度を越した体罰」を言うのであり、適切な体罰は「正当な懲戒」であると解釈されているようです。結局、親も教師も、適切な範囲であれば体罰は正当ということになる。じゃあ学校教育法11条の「(教師は)体罰を加えることはできない」というのは全く意味のない但し書きなのかというと、おそらくそうではない。「正当」と解釈される範囲が、親に比べて教師の場合はずいぶん狭くなることを意味すると思われます(親は多少行き過ぎても処罰されないが、教師はちょっと行き過ぎると処罰される可能性がある)。東国原知事がいう「愛のムチ条例」などはなくとも、適切な体罰は法的にも許容される。では、あえてこれを条例化する意味はあるかというと、教師にとって許される体罰の基準を決めるという意味はあると思われます。しかし、実際にそれを定めるのは極めて困難でしょう。「愛のムチ」と言っても、「愛」とはその人の主観的なものですから、どういう場合に「愛」があるといえるかを法で定めるのは現実的に不可能です。加えて、本来これは「生徒の肉体に苦痛を与える体罰はいかなる範囲で正当化されるか」という峻厳な問題であり、それを「愛のムチ」とか「げんこつ」という微笑ましい名称にしてしまうことで、問題の本質が見えにくくなってしまい、不要な体罰が横行しそうな気がします。ちょうど不良少年たちが、「集団による強盗傷害」という重大犯罪を「オヤジ狩り」というユーモラスな名称で呼び始めたために、やっていることの悪さが理解できなくなり、軽い意識で犯罪を繰り返すようになったのと似たようなことになる懸念を感じます。かくて、「愛のムチ」条例はなくても適切な体罰は許されるし、あえてそれを作るのは困難であり、むしろ体罰が横行する危険を含む、ということで、そんな条例は要らないと考えます。
2008/06/25
-
「愛のムチ」条例は必要か―体罰の法的根拠
宮崎県の東国原知事が、「愛のムチ条例」「げんこつ条例」を作ってはどうかと、どこまで本気かわかりませんが言ってました。曰く、昔は学校なんかでも悪いことをすると「げんこつ」で教えられたものだが、今はそれができなくなっているとのこと。「『愛のムチ』または『げんこつ』」と書くのが面倒なので、以下客観的に「体罰」と書きますが、同知事は、適切な範囲で体罰を復活させたいということでしょう。さて、この知事のいうように、昔は体罰が許されたのが今はできなくなったのか。その根拠はあるのか。そして、法律や条令で体罰ができると定める意味はあるのか。といったことについて、法的に検討したいと思います。戦前はどうだったかというと、きちんと調べていませんが、親や教師が子供に体罰を加えるのは法律以前の「当然」のことと考えられており、特に問題とされていなかった。戦後はどうか。親の場合は、戦後に改定された民法にいちおう規定がある。民法822条によると、親権者は必要な範囲で子を懲戒できる。明文に書かれていないけど、ここには体罰も含まれると解されます。親が子供に体罰を加えるのも、医師が患者の体をメスで切るのも、暴行や傷害にあたりうるけど、刑法35条は「法令または正当な業務による行為は罰しない」と定めているため、親や医師は処罰されない。もちろん、行き過ぎた体罰は単なる「虐待」であり、暴行罪・傷害罪で処罰されるし、親権が剥奪されることもある(民法833条、834条)。学校の先生はどうか。議論はあるところですが、憲法23条(学問の自由)や26条(教育を受ける権利)を根拠として、小中学校の教師には、生徒に対する「教育する権利」が認められるとされる。さらに直接的には、学校教育法11条に、「教育上必要があるときは懲戒を加えることができる」とありますが、この条文には親の場合と違って但し書きがあって、「ただし、体罰を加えることはできない」と明確に規定されている。ここからすれば、学校の教師は一切、生徒に体罰を与えることはできなくなりそうです。先生の体罰は一切禁止されるのか。だからこそ条例でそれを定める意味があるのか。長くなりましたのでその検討は次回に譲ります。
2008/06/24
-
強盗致傷と酌量減軽 3
続き。少し話は変わりますが、近年、犯罪の凶悪化と国民の処罰感情の高まりを受けてか、犯罪の法定刑は重くなりつつあります。例えば殺人罪は、少し前までは最低で懲役3年だったのが、法律が改正されて懲役5年になった。強かん罪は、最低懲役2年だったのが最低3年になった懲役刑の上限も、15年だったのが20年になった。ところが、こういった厳罰化傾向にあって、唯一、法定刑が軽くなった犯罪があります。それが強盗致傷です。少し前までは最低で懲役7年だったのが、6年に下げられた。なぜ強盗致傷に限って軽くなったかというと、それはこの犯罪がかなり容易に成立しがちだからです。ゴマキの弟もたぶん、最初から強盗致傷を働こうと思っていたのではない。こっそりと盗みをしようとしていたのであって、人を傷つけるつもりはなかった。それが警備員に見つかってしまい、頭に血がのぼって、逃げようとして手が出た。警備員のケガの程度は知りませんが、ちょっと血が出たとか、血がでなくてもアザになったとかすれば傷害にあたります。同じ強盗致傷でも、たとえば包丁片手に誰かの家に押し込んで、住人に切りつけて抵抗できなくした上でモノを取ったようなケースであれば、重く処罰されて当然といえる。強盗致傷罪の罪が重いのは、典型的にはこういう場合を想定しているからだと思われます。一方、ちょっとした出来心で万引きやコソ泥をしたら見つかったので手が出てしまって相手にケガをさせた、これも同じ強盗致傷です。もちろんこれも犯罪行為であって処罰されるべきは当然なのですが、上記のような押し入り強盗と全く同じに考えてよいかというと、ちょっとためらいが残る。そこで、法定刑の最低ラインを下げて、柔軟に刑罰を決められるようにした。7年が6年になっただけの違いですが、ここは極めて大きい意味を持ちます。前回書いた酌量減軽が適用されると、6年の半分の3年になる。懲役3年だと執行猶予をつけることができるのです。刑法上、3年を超えると執行猶予をつけることができない。これまでは酌量減軽を適用しても3年半となってしまい、犯人に同情の余地があっても3年半は刑務所に行かないといけなかった。(実際には、ちょっとしたケガであれば目をつむって、強盗致傷でなく単純な強盗として、それだと最低懲役5年、酌量減軽で半分の2年半にして執行猶予をつける、といった少しムリな処理をすることもあったようです)そういう次第で、強盗致傷でも情状によっては執行猶予をつけてもらえることになったのですが、ゴマキの弟は複数の犯罪を行っていたので実刑となった次第です。刑法を勉強した人であれば誰でも知っていることだと思いますが、ゴマキの弟の事件をきっかけに解説してみました。以上です。
2008/05/30
-
強盗致傷と酌量減軽 2
前回の続き。罪を犯しても、特に酌むべき事情があれば、「酌量減軽」で罪が軽くなると書きました。それでゴマキの弟は、強盗致傷で懲役6年以上になるはずなのに、5年半になった。今回はやや細かい話になりますが、単なる情状酌量と、「酌量減軽」は大きく異なるということについて書きます。世の中のたいていの犯罪には、酌むべき事情がある。「いや、新聞やテレビを見てると情状酌量の余地のないひどい犯罪ばかりじゃないか」、と思う方もいるでしょうけど、それはああいう事件がセンセーショナルに取り上げられるから印象が強く残るだけであって、犯罪の99%には何らかの酌むべき事情がある。そこで行われるのは単純な情状酌量です。強盗致傷を例にとると、最低で懲役6年、最高で無期懲役。この法定刑(法律で定められた刑罰)の範囲の中で、なるべく最低ラインに近いところをとってあげようということです。「酌量減軽」は違います。法定刑を破って、さらに軽い刑にすることができる。懲役6年より軽い罪を採用できるわけです。どれだけ軽くなるかというと、一気に半分になる(刑法71条、68条)。(なおゴマキの弟の場合、犯罪が一件だけなら懲役6年の半分で3年で済むこともありえたのですが、他に何件かの窃盗事件を犯しているため(併合罪、刑法45条)、罪が加算されて最終的に5年半になったと思われます)かように、酌量減軽というのは刑の重さが半分になるわけですから、単なる情状酌量とは異なる、特別に酌むべき事情であることを要します。有名な例としては、若い女性が長年に渡り父親から虐待(性的虐待を含む)を受け、思い余って殺した、といったケースがありますが、こういう余程の事情に限られます。ゴマキの弟の場合はどんな事情だったかというと、「まだ若く、身重の妻がいるから」といったことのようです。果たしてこれが酌量減軽に足る事情かというと、少し疑問な気もしますが、裁判官も強盗致傷という重罪を科するにあたって悩んだ末の選択であったものと思われます。たぶんこの話がもう少し続きますので、飽きてなければお付き合いください。
2008/05/29
-
考察 死刑と終身刑について 続き
前回の続き。「終身刑」導入に向けて、国会議員が動き出しているそうです。「量刑制度を考える超党派の会」というのがあるらしい。多くの方はご存じと思いますが、日本の刑法の「無期懲役」というのは、「いつ期限が終わるかが決められていない」というだけで、一生を刑務所で過ごすわけではない。ちなみに、有期懲役の上限は20年(刑法12条、少し前までは15年だった)。ただし、再犯や併合罪(複数の罪を犯した)などの事情があれば、特別に30年まで延ばすことができる(刑法14条。少し前までは20年)。無期懲役というのは、懲役の過程で更生が見られなければ30年を超えて懲役にすることもできるというだけで、いつかは出てくることが想定されている。最近の法改正で有期懲役の上限が長くなったとは言え、死刑と無期懲役の間には大きな差がある。そこで、社会復帰を前提とする無期懲役では軽いが、死刑とするにもためらいが残るという場合に、両者の間をとって、社会復帰のありえない「終身刑」を創設しようということです。その趣旨はわかりやすいですが、さて、どんなものでしょう。容易に想像できるのは、終身刑の囚人というのは、時代小説やB級の香港映画(「炎の大捜査線」とか)に出てくる「牢名主」になってしまわないかということです。牢獄のボスになって、囚人を支配し始めると、刑務官が刑務所秩序を保つのが困難になるかも知れない。この点、現在の法律(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律)によりますと、囚人は、性別や、死刑か懲役かに応じて分離して収容することになっている(4条)。だから終身刑が創設されることになれば、終身刑の囚人専門の施設が作られるのでしょう。そこには当然、国家予算の問題が出てきます。予算の問題をクリアして終身刑だけの施設ができたとして、そこの秩序を平穏に保つのは、これまた困難でしょう。なんせ、そこにいるのは、何があっても一生をそこで過ごすしかない人ばかりです。懲役刑の囚人は「いつか出られる」「問題を起こせば刑期が延びる」と思うからこそ、真面目に暮らしている。死刑囚の生活というのは今ひとつ分かりませんが、「問題を起こせば法務大臣が死刑執行のハンコを早く押す」と思っておとなしくしている部分もあると思う。しかし終身刑の人は、何をしようが、「一生そこにいる」というだけで、その状況が良くなったり悪くなったりすることはない。どうせそれならばと投げやりになって、刑務官に暴行を働くとか、施設を損壊するとか、脱走を図るといったことも起こりやすいでしょう。そんな問題を起こすヤツは、縛り付けるなり、ムチで百タタキにするなりすればいい、と考える人もいるでしょうけど、そのような「体刑」は現行の刑法では採用しておらず、それを行うには新たな法的根拠が必要になる。そして、囚人に百タタキなどという前時代的な罰を残している我が国は、果たして国際的にみて恥じない国家と言えるかどうか。終身刑を制度として採用している国がどの程度あるのか、そこでの囚人への処遇はどうなっているのか、調べたわけではありませんが、すぐに思いつくだけでも上記のような問題があり、これを本当に導入するのであれば、慎重を極めた論議をすべきでしょう。
2008/05/17
-
考察 死刑と終身刑について
まず雑談から書きます。かなり以前のことですが、ある刑事事件の関係で被告人に接見(面会)するため、タクシーで大阪拘置所(都島区)に向かっていました。拘置所というのは、裁判が終わるまでの間、被告人が身柄をそこに確保されている施設です。たとえばライブドアの堀江氏は、証券取引法違反の刑事裁判の途中に保釈が認められて、少しやせた顔になって東京拘置所から出てきました。さて拘置所に向かうタクシーの中で、運転手は、行き先からして私が弁護士とわかったのか、いろいろと刑事裁判に関する話題を振ってきました。ちょうど、誰かは忘れましたが大阪でとある死刑囚に対する死刑が執行された直後のことで、運転手は、「こないだも死刑が執行されましたねえ」と言ってきました。私は、「ええ、死刑が執行されたのも、あの拘置所なんですよ」と答えました。誰しもご存じだと思いますが、懲役刑の判決を受けた者は、「刑務所」という施設に送られる。しかし、死刑判決を受けた死刑囚は、刑務所でなく拘置所に送られます。いわゆる「死刑台」というのは、刑務所ではなく、全国何か所かの拘置所内に設置されている。タクシーの運転手は、後者のほうは知らなかったみたいで、「へえ、そうなんですか。どうして死刑囚だけは、刑務所じゃなく拘置所なんでしょうねえ」と言いました。実は私も、長らく疑問に思っていました。拘置所というのは裁判の判決が出るのを待っている人が入るところ、刑務所は裁判が終わって有罪判決を受けた人が入るところ、と大別すると、死刑囚が拘置所に入るというのには違和感を感じていたのです。答えられずにいると、その運転手は先ほどの発言に続けて、こう言いました。「やっぱり、死刑判決を受けた人なんていうのは、働いて更生させなくてもいい、ってことですかねえ」私は、なるほど、と思いました。刑務所は、懲役刑を受けた人が入る。刑務所内の作業場でいろんな仕事をさせられ、懲役が終わって社会復帰する際には手に職がついた状態になっていて、マジメに働いて生きる助けになる。一方、死刑囚は、社会復帰ということがない。死刑になるのを毎日「待っているだけ」の状態です。だから、刑務所に入れなくてよい。どちらかといえば、判決が出るのを「待っている」被告人が入る拘置所に入れておくのがよい。刑務所は更生するための施設、拘置所は何かを待つための施設、ということです。どうしてこの話を最近思い出したかというと、最近、「終身刑」の創設を目指す動きがあるという話をよく聞くからです。一生、外に出ることのない終身刑の囚人は、刑務所に入るのか拘置所に入るのか。そんなことを考えました。終身刑に関する問題については、引き続き次回に触れたいと思います。
2008/05/16
-
続編 裁判員に心のケア
裁判員制度について以前少し書いた、「心のケア」の問題ですが、少しずつ制度ができつつあるらしい。前の記事はこちら先日も書いたとおりですが、昨日の産経の記事によると、死体写真をみたり遺族の話を聞いたりすることによって、精神的ショックを受けてPTSDになる人が出る可能性が指摘されているとか。PTSD。心的外傷後ストレス障害。体を大ケガすると後遺症が残ることがあるように、心に強いショックを受けた人はずっとそのショックを抱え続けるということです。きちんと調べてませんが、たしかベトナム戦争に出ていたアメリカ兵が戦場の恐怖で廃人のようになってしまう(映画の「ディア・ハンター」がそういう話でしたか)、そういうケースが多数出て、そこから注目されるようになった病気だとか。それに対してどのようなケアが準備されているかというと、電話による24時間相談と、そして希望者には面談での相談・診療が予定されているとか。報道によると、オーストラリアやアメリカの一部の州には同様の制度があるらしいのですが、日本ではどうなるのか、詳細はまだ決まっていないようです。それにしても、電話での相談ひとつとっても、どの範囲の人が、どの範囲の相談をすることができるのか。実際に裁判員として事件に触れてショックを受けた、という人は相談の対象となる。では、事件と関係なく、法廷で隣に座っている裁判員のオジサンに交際を迫られた、といった女性裁判員の相談はどうか。さらに、裁判員に選任されていないけど、いつ裁判員に選ばれるかと思うと不安だ、という人は。広報用の上戸彩のポスターが欲しいという人(私)は。相談の範囲はよく分かりませんが、それにしても24時間電話を受け付けるなんて、国の制度としては警察と消防くらいしか思いつかないわけで、これはかなりの大ごとです。予算もそれだけかかるでしょう。それに話が戻って、PTSDにも程度は色々あるのでしょうけど、心に後遺症を残すなどというのは、これも相当に大ごとです。裁判所は、「裁判員制度にぜひ参加してくださいね」といかにも簡単そうに言いつつ、心の中では(PTSDになるかも知れないけどね)と言っているわけで、この一事をもってしても、やはり相当に大変なことになりそうだなあと思うのです。
2008/05/13
-
裁判員に「心のケア」だそうです
裁判員制度に関して今しばらく書きます。少し前の日経新聞で、「裁判員に心のケア」(13日朝刊)と。裁判員として刑事裁判に関った人たちが、事件に触れることでショックを受けて心身に変調をきたしたときに備えて、電話相談やカウンセラーを置いて手当てする仕組みを作ろうと、最高裁は考えているらしい。たしかに私も、ハードな刑事事件で弁護を担当すると、その法廷が終わるたびにグッタリします。おそらく、訴追する側の検察官も、壇上にいる裁判官も同じでしょう。重大犯罪に対して、有罪か無罪か、死刑にすべきか無期懲役にすべきか、プロの裁判官でもグッタリするであろう判断を、「素人」の裁判員がさせられるわけです。精神的負担は大きいでしょう。事件の内容に触れること自体も、一般の人にはツライことが多いと思う。殺人事件であれば、「証拠写真」として死体の写真なども見ることになるわけですから、相当の精神的ショックを受ける人もいるであろうことは容易に想像できる。ちなみに弁護士や検察官や裁判官は、司法修習のときに、死体解剖に立ち会ったりとか、刑事事件の記録を通じて一通りのジャンルの死体写真を見たりとかしていますので、その手のことには一応慣れています。(もちろん中には慣れない人もいて、そういう人は民事事件専門の弁護士の道を選ぶことになります)そのような刑事裁判の過程で、不幸にして心に傷を負った人をケアしようというわけですが…。たしかに国民に「義務」として刑事裁判への協力を求めるわけですから、ケアはしておくに越したことはないのかも知れません。しかしこのことが却って、一般国民に対して「やっぱり裁判員って大変なんだ」というイメージを与えてしまわないか。そうだとすると、最高裁がこれまで必死で「裁判員は大変じゃないですよ」と、イメージキャラクターに上戸彩まで借りだして(あのポスターは欲しいけど)アピールしてきたことからすれば逆効果じゃないかと。そしてもっと根本的なことを考えてみると、そこまでやるんなら、いっそ裁判員制度なんてやめたら?やっぱり人を裁くのはプロじゃないと無理では?というところに行き着いてしまうわけです。それでも裁判員制度施行の閣議決定が成立したみたいで、実施に向け準備は着々と進んでいるようです。
2008/04/16
-
裁判員制度と大政奉還
いつものことながら更新頻度にムラがあってすみません。裁判員制度について昨日に引き続き、底の浅い話を書きます。従来から私が思ってきて、そしておそらく、同じように感じた方もおられるのではないかと思っているのは、裁判員制度というのはつまるところ、「大政奉還」みたいなものではないかということです。鎌倉幕府以来、武家が日本の政治を行ってきたのを、徳川15代将軍・慶喜が朝廷に政権を返上した。幕末、徳川幕府が弱体化し、外国からは開国を迫られ、民衆の間では攘夷熱が盛んだった。西国の「雄藩」は幕府に逆らいだして、国内の政情も揺れはじめた。朝廷の公家は、幕府は何をしてるんだ、外人は追い払えず、国内をまとめることもできないのか、と散々責め立てたことでしょう。で、徳川慶喜は、「そんなに言うならアンタらが政治をやれ!」と言って、朝廷に政権を返上しまったわけです。で、裁判員制度の話。大昔、罪を犯した人を裁くのは民衆の仕事でした。例えば殺人を犯した人に対しては、遺族が復讐するか、村人の多数決や村の長老の裁きによって処置を決める。しかし、復讐なんて遺族にとっても大変だし、復讐はさらなる復讐を呼ぶことになる。また、人口が増えるに連れて、多数決も困難となり、長老でも治めきれなくなる。それで、近代国家ができていく過程で、罪を裁くのは国家に任せようということになった。それが近年では、裁判所という国家機関に対する風当たりが強くなった。人を殺しておいて無期懲役はなかろう、心神喪失で無罪なんておかしい、裁判官は常識を知らなさ過ぎると、そういう世論が強くなった。それで裁判官たちが、「そんなに言うならアンタらが裁判をやれ!」となって、人を裁く権利を国民に戻したというわけです。国民の良識を裁判に取り入れるというのが裁判員制度のタテマエで、そう表現すると聞こえは良いのですが、これは言い方を変えると、裁判官が常識を知らないというのであれば、アンタらが実際に事件に接して、アンタらの言う常識ってもので判断してみろ、ということでしょう。大政奉還のときは、幕府から「政権は預かっていたものだから返す」と言われると、朝廷はそれを断る理由を持たなかった。でもその後、新国家建設のためには物すごい苦難があったはずです。裁判員制度導入にあたっては、裁判に国民の良識を取り入れると言われると、それ自体は良さそうなことなので、国会は反対する理由もなかった。裁判員制度が根づくかどうかはわかりませんが、どちらにせよ、今後の苦難が予想されます。
2008/04/10
-
裁判員制度がいよいよ施行
裁判員制度が来年5月から始まると決まったらしい。裁判員法(正式名称は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)はもう成立していて、あと施行の問題でした。この裁判員法は平成16年5月28日に成立していて、いつから裁判員制度を始めるかについては、成立から5年までの範囲で「政令」で定める、と規定がある。「政令案」では、「平成21年5月21日から開始」、とされるようなので、まさに5年ギリギリまで引き伸ばしたような形です。「政令案」と書きましたが、政令は今朝の時点でまだ決まったわけではないみたいです。もっとも、政令というのは内閣が作る決まりですから、あとは福田総理以下、10数名の大臣が集まって閣議決定すればそれで決まる。ほぼ決定ということで、裁判員制度の導入を進めてきた裁判所の偉いさんはひとまずホッとしているでしょう。一方、裁判員に選ばれたら面倒でイヤだと思う方も多いでしょう。現場の裁判官や弁護士にも、制度に反対する意見があるみたいです。私自身は、当ブログでもやや懐疑的にこの制度に触れたことがありますとおり、積極的に賛成はしていません。それでも、法律自体は主権者たる国民の代表である国会で決まったことだし、やるんならどうぞ、といった気持ちです。弁護士は裁判員に選任されない(裁判員法15条1項6号)ので、他人事のように考えているところはあるかも知れません。私自身がこの制度に関わるとすれば、私が弁護する被告人の刑事事件に裁判員が参加するような場合です。各都道府県の弁護士会では、裁判員の参加する裁判に対応するために研修を強化すると言っているらしい。義務だから出ろ、と言われれば出ますが、あまり研修の必要を感じていません。私は手前味噌ながら、依頼者の前で法律の専門用語を使って話すようなことはしてこなかったつもりだし、法廷で問答する際にも、傍聴人が居るときならその人たちに「何が行われているかがわかる」ように話すことを心がけてきたつもりです。裁判員の方が参加するようになっても、同じ調子で弁護するだけです。それに、これまで刑事事件で対峙してきた多くの検事の顔を見ていると、私のほうが「善人」っぽく見えるので、裁判員に対するアピールという点では問題ないと思っています。今回は浅い内容ですみません。引き続き、裁判員制度についてもう少し書くつもりです。
2008/04/09
-
「予算と法律の不一致」 ガソリン減税へ
ガソリン減税の話です。「一生ペーパードライバー」を決め込んでいる私としては、ガソリンスタンドの値引きは縁のない話だと思っております。むしろ、減税による財政難で公共工事がストップしたりして、ウチの依頼者でとばっちりを食う方はいないかと心配しております。さて、なぜガソリンが安くなったかといえば、ご存じのとおり、ガソリンにかかる税率を暫定的に高める租税特別措置法が期限切れになり、その税率を継続するための法律案は、参議院で第一党としての勢力を誇る民主党の反対により成立しなかった。冒頭に書いたような身近なことばかりでなく、今後の混乱は容易に想像されます。本年度の予算はすでに成立しており、この国の運営にあたって何にどれだけお金を投じるかは決まっている。それなのに、そのための原資となるべき税収を得るための法律が存在しない。このように、予算と法律が食い違ってしまう場合を、「予算と法律の不一致」といいまして、憲法の教科書の「財政」の章のところに必ず出てきます。(「人権」とか「国会」の章よりは地味な話が多いので、たぶん学生や司法試験受験生には不人気な分野だと思います)議院内閣制をとり、国会での与党の多数派が内閣を構成する日本では、この不一致が生ずることは少ないです。憲法上、予算は、政府(内閣)が作って国会が承認する、法律は、国会が作る、というのが憲法のタテマエだけど大抵は役人(つまり政府)が原案を作っている、というように、予算も法律も国会と内閣の協同のもとに作成されるからです。憲法のことはともかく、今のこの国は、サラリーマンが4月からの月給を突然下げられた一家のような状態です。国を動かすためのお金がないのです。当面、ガソリンは安くなるかも知れませんが、その後の影響が心配です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・(この先は憲法の勉強をしている人向けです)教科書でよく出てくるのは、予算は成立したが、その支出を命ずる法律が成立しなかった(例、「ナントカ庁」を作るために予算を組んだが、その根拠となる「ナントカ庁法」は国会で成立しなかった)というものですが、今回のは、予算は成立したが、その収入の根拠となる法律が成立しなかった、という状態で、これは珍しいパターンかも知れません。もう一つ、教科書に出てくるのは、法律は制定されたが、予算が成立しなかった(例、「ナントカ庁法」はいったん成立したが、国会が「そんな省庁やっぱりムダだ」と言い出し、そこに予算を組むことを認めなかった)というケースで、おカネがないという点では今回はこちらに近い。この場合は財政法上の補正予算等で対応するとされていますが、今回もそういうことになるのでしょう。
2008/04/04
-
「俺は心神喪失だ」と言えば本当に無罪になるか?
前回の続き。(誰が言ったか)「セレブ妻」こと三橋歌織被告人に「心神喪失」の鑑定結果が出たことについて、報道を見る限り今のところそれほど反響はないようです。前回も少し触れましたが、この類の報道があるとよく聞くのは、「人殺しでも『心神喪失』だと言えば無罪になるのか」という言葉です。もちろん、きちんとした新聞等の報道においては、そんな感情的な論調は見られません。この手の話は、酒場や銭湯での与太話であったり、ネット上での発言においてよく聞かれます。ただどのような形であれ、そういった「世論」が一定程度存在するようなので、これについて触れておきます。人を殺しておいて、「俺は心神喪失だ」と言えば無罪になるのか、という問いですが、その答えは、「イエス」です。ただし、それには以下の条件がありますので、この後の話をよく読んでください。・まず、人を殺した際に、隠蔽工作をしようとすると、「犯行現場で合理的な行動ができているから心神喪失ではなかった」と判断されるおそれが高い。・犯行が発覚したら、逮捕されて留置場に入ります。そこで、警察官相手に「俺は心神喪失だ」と言い続けるのも極めて大変です。・刑事裁判で心神喪失を主張すれば、それを判断するために医師等の鑑定人が選ばれ、鑑定手続に入ります。長い裁判になります。その間、ずっと勾留されたままです。・鑑定では、医師から心神喪失の診断を得るのも大変だと思います。映画「刑法39条」も、心神喪失を装って人を殺した犯人が、最後に鑑定人によってウソを見抜かれてしまうという話でした。・心神喪失の鑑定結果が出ても、前回書いたとおり、裁判官は無罪判決を書くとは限らない。「俺は『心神喪失』だ」なんて、専門用語をきちんと知ってる被告人には責任能力がある、と裁判官なら言いそうな気がする。・心神喪失で無罪判決が出たとしても、放免されるのではなく、医療施設に強制的に収容されます。その先は、いつ出てくるのかはわかりません。・そこを出て家に帰っても、事件がもとで妻や子供には逃げられ、一家は離散しているかも知れない。以上の条件つきですが、人を殺して心神喪失と言えば無罪になります。以上のことを聞いて、「いいことを聞いた、よしやろう」と思った方はまずいないでしょう。心神喪失で無罪など、そうそう認められるものではない、それが認められるのは、私たち健常者からすれば極めて特異なケースに過ぎないのであって、「人殺しでも『心神喪失』と言えば無罪になるのか」などと、そう軽々に言うべきものではないと思います。刑法39条に関する話については、また折に触れ書くことがあるかと思いますが、これまで、精神医療に関わっているという方々から、当ブログに対し貴重なご指摘のメールをいくつかいただきました。機会がありましたらいつかご紹介したいと思いますが、ひとまずこの場を借りてお礼申し上げます。
2008/03/12
-
ロス疑惑と公訴時効の再考
「ロス疑惑」報道が連日行われています。法的観点からあれこれ書こうと思っているうちに、新聞やテレビで語り尽くされてしまった気がするので、あとは簡単に雑感を述べるに留めます。私が最も関心を持ったのは、前回にも書きましたが、アメリカでは州によって殺人罪の時効がないということです。新聞や週刊誌によると、時効がないため捜査官は古い事件に関わっていることができ、実際、昔の事件の解決に一定の成果を挙げているらしい。日本でも、これらの制度は多いに参考にすべきかと思います。ただアメリカでの実際には、古い事件が積もっていく一方で、新しい事件が発生するので、捜査官は常に古い事件に関わっていることができず、手持ちの事件の余裕ができたときにたまに扱う程度だということも新聞報道で知りました。(自分で調べずに報道の受け売りばかりで申し訳ないです)となると、古い事件は捜査官の気の向いたときに、気の向いた事件だけが扱われるということで、それが事件関係者にとってよいことなのかどうか(ある遺族は捜査を続けてもらえるが、別の遺族は無視されることになる)、私にはわかりません。アメリカには、昔の事件を専門に扱っているような部署もあるとか聞きました。日本にもそのような部署を作るかどうかは、予算と人員配分との兼ね合いです。そのような部署を作れば、優秀な警察官の何パーセントかがそちらに取られ、予算も相応に注ぎ込まれるでしょう。それでやっていることの多くは、何十年も前の、もう解明しようもなさそうな事件です。少し前にも書きましたが、そうなっては「仕方ないから捜査を継続しているフリをする」だけにならないか。もちろん、遺族は「それでも捜査を続けてほしい」と思うでしょう。あとはそれを主権者である国民全体が納得するか否かです。あと、今回の報道で聞くのが、「科学技術の発達によって、過去であれば犯罪の立証ができなかったものができるようになった」ということです。ロス疑惑の件でそのような証拠が出たかどうか、それはアメリカ当局も明らかにはしていません。しかし、これだって怖い話です。例えば「30年前の殺人事件の現場に付着したDNAとお前のDNAが一致した」などと言って突然逮捕されたらどうなるのか。30年前のアリバイなんて、出せと言われても難しい。そもそもDNA鑑定の正確性だってまだ未解明の部分があって100パーセント信頼できるわけではないらしい。刑事訴訟法で定める犯罪の公訴時効までの期間は、ようやく4年ほど前に少し「延長」されました。「廃止」すべきか否かは極めて慎重に考えるべきでしょうけど、仮にそうなるとしてもまだまだ先の話でしょう。
2008/02/29
-
ロス疑惑にみる日米の刑事訴訟法の違い
昨日書いた、「ロス疑惑」での三浦和義氏の逮捕、さすがアメリカと思わせる早い展開になっています。三浦氏の保釈を、アメリカ当局は許可しなかったと報道されています。三浦氏は依然逮捕されたままで、しばらく取調べを受けることになるのでしょう。この辺、きちんとアメリカの制度を確認していませんが、アメリカの映画でも、容疑者が逮捕されたらすぐ弁護士が駆けつけて、警察当局と交渉し、容疑者が釈放されるというシーンがあったりします。確かマット・デイモンの「レインメーカー」にもそんなシーンがあって、ある女性が逮捕されて警察署に面会に訪れたマット・デイモン扮する弁護士に対し、警官が「お前の腕がよければ釈放されるだろう」と言うシーンがあった気がします(うろ覚えで書いています)。日本でも同様だと考えている人もいるみたいで、逮捕されても、腕のいい弁護士(または警察・検察や政治家に顔のきく弁護士)に頼めばすぐ出してもらえる、と考えているような人が多いように見受けます。私自身は、腕がいいかどうかはともかく、少なくとも警察や政治家に顔はききませんので、実際のところはどうか知りません。しかし日本ではそのようなことはまずないです。容疑者を釈放するか否かは裁判官が慎重に検討することになっている。もっとも、残念ながら実際には、裁判官はあまり慎重になっておらずに、逮捕状や勾留状にすぐハンコを押すのが実情だと感じています。でもこの制度はアメリカよりはマシだと思っています。上記の「レインメーカー」での描写が事実かどうかは知りませんが、もし事実だとしたら、お金を持っていて腕のいい弁護士をやとえる容疑者は早く釈放され、お金のない容疑者(生活苦でやむなく罪を犯したような人は大半がそうでしょう)は釈放されないわけですから。加えて、重要な違いとして、日本の刑事訴訟法では「保釈」という制度はそもそも、捜査が終わって刑事裁判が起訴された後でないと認められない。逮捕の翌日に「保釈」手続きを取るなどということは、日本では考えられないのです。捜査のための勾留期間は10日または20日間で、その間は警察・検察側の持ち時間となる。勾留自体を中断するための手続きは制度上存在しますが、それが認められることは極めて例外的です。三浦氏を保釈するか否かの審判の様子が報道されていたことから、これは公開法廷で行われたのでしょうか。これまたアメリカ的です。日本では、勾留するとか保釈するとかの判断は密室で行われます。この点はアメリカ的になるのが望ましいかも知れません。もう少し続く。
2008/02/26
-
公務員制度改革で何が変わるのか
公務員「労働基本権」先送り。本日の日経朝刊の見出しです。政府が、検討中の「国家公務員制度改革基本法案」に、検討事項の一つであった国家公務員への労働基本権付与を盛り込むことを断念したと。労働基本権とは、社会科の時間にも出てくるのでご存じだと思いますが、要するに労働者の権利、特に勤務条件や職場環境の改善を求めて組合を作ったりストライキをやったりする権利のことです。国家公務員がストライキなんてやると国の行政事務が遅滞するということで、これらの権利は与えられていない。国家公務員がストライキをやると処罰されることもある。憲法の教科書を見ると、公務員も国民の一人であるのに、憲法に書いてある労働基本権が与えられないのはなぜかという議論が必ず書かれています。それをここで述べるのは控えますが、一般人としての感覚で言えば、民間に比べればはるかに身分が保障され、労働条件も恵まれている公務員が、ストライキとは何ごとだ、という印象をお持ちかも知れません。この件についての捉え方は人それぞれでしょう。実は私も、人権派弁護士(自称)でありますが、正直なところ公務員に労働基本権は要らないのでは? と思っているほうです。政府方針では5年後に再考するとのことです。もう一つ、国家公務員試験について、幹部(いわゆるキャリア)を採用する1種試験と、それ以外の職員を採用する2種・3種試験の種類分けを廃止すべきか否かの点について。どの試験を受けるかによって将来の出世の度合いが決まってしまうのはおかしい、入り口は一本化して、あとは本人の能力次第で出世できるようにすべきだ、とよく言われます。政府方針では、上記法案に「幹部候補の確保を想定して行う」と表現される範疇の試験が温存されるようで、どうも実質上は「キャリア制度」が残ることになりそうです。この点については別の機会に触れたいと思います。で、結局、公務員改革法案で何が改革されるの? というところですが、政治家との接触を規制するとか、どうもありきたりの、かつ実効性がよくわからないような部分が残されたみたいです。法律一つで公務員が変わるわけでもないでしょうから、改革法案に過度に期待すべきではないのでしょうけど、それにしても何が改革なのかよくわからない流れになりつつあります。
2008/02/18
-
民事の時効と刑事の時効 続き
先週書いた、時効制度についての続きです。前回は、殺人事件の加害者に対する損害賠償について、民事上の除斥期間の適用を認めなかった東京高裁の判決を紹介しました。 これに関して、刑事事件のほうの時効を書こうと思ったのです。前回も少し書いたように、刑事事件の時効のことを公訴時効といいます(刑事訴訟法250条)。これが成立すると、犯人だとわかっても起訴・処罰することができない。殺人事件でも15年間逃亡していれば時効になった(ただし国外逃亡の場合は時効にならない)。しかしこれも、近年になって25年に延びました。被害者保護の流れの一環でしょう。 先週、どこだったかの社説で、冒頭の事例に触れた上で、刑事事件においても恒久的に時効を適用しないことも検討してよいのではないか、といった論調の記事を見ました。 たしかに、社会の耳目を集めた殺人事件で時効が成立したというニュースを見ると、公訴時効とは何と不合理な制度だろうと思います。ただ、仮に公訴時効という制度がないとどうなるか。容易に想像できると思いますが、時効にかからない事件がいつまでも「積もっていく」ことになるでしょう。例えば、今の京都府警が坂本龍馬暗殺の下手人は誰かといったことを捜査しているようなことになる。もちろん、やれと言われれば警察も役人ですから「ハイ」と従うでしょう。その結果、警察には膨大な人員と予算が振り分けられることになる。でも実際は何十年も何百年も前の事件の証拠を探すのは不可能または極めて困難ですから、実態としては「捜査するフリをしてブラブラしていた」ということになると思います。そうならないためにも、どこかで過去の刑事事件は「線引き」してあきらめざるをえない。だから公訴時効という制度があるのだと思います。では、時効期間が過ぎた直後に犯人が捕まったとか自首したとか、そういうケースであっても処罰できないというのはどうか。さすがに不合理ではないか。この場合も、憲法上は「自白だけでは処罰できない」ことになっている。冒頭の事件は26年前の殺人でしたが、この人を処罰するには、26年前のこの人の殺害経緯について、本人の自白だけでなく裏づけとなる証拠を取る必要がある。それはやはり膨大な捜査コストを要することになると思います。かくいう次第で、公訴時効という制度はやむをえないものだと思います。その不合理さを取り除こうとしたのが、今回の、民事上の時効を否定して賠償請求を認めた東京高裁の判決であると理解できます。
2008/02/14
-
裁判所との意思疎通における不公平について
前回、福岡の事件に関して、裁判所と検察官の密接な意思疎通について触れました。そのことでもう少し書きます。私が司法修習生として大阪地裁の刑事部にいたときの話です。刑事部の裁判官室の一角に机を置かせてもらっていたのですが、いつも、その日の法廷が終わると、担当検事が部屋にやってきて、裁判官と話をしている。私が修習生として裁判官の部屋にいたころは、たいていパソコンでソリティアをやっていたので、何を話していたのか特に意識していなかったのですが、おそらく、当日扱った事件について、今後の問題点や審理方針などについて話し合っていたのでしょう。そんなものかな、という気持ちで横目で見ながら、ソリティアをしていました。しかし、ちょっと考えてみると、不思議な話ではあります。先ほどまで法廷では、検察官と弁護士が一つの刑事事件について争っていた。それを裁判官は、中立の立場で見ていた。その法廷が終わると、争っていた一方の側である検察官が、中立の審判たる裁判官のところへやってくる。弁護士はやってこない。私たち弁護士が、裁判所に対し意思疎通する際は、せいぜいファクスです。裁判官にじかに会うことはありません。それをしたいと思っても認められない。ただ一度、過去にある刑事事件(当時それなりに新聞報道された傷害事件)で、第2回法廷が開かれる日に、法廷に行く前に裁判官室に寄ってくれ、と書記官から連絡を受けたことがあります。珍しいこともあるものだなと思って裁判官室へ行くと、裁判官だけではなくてすでに検察官も来ている。裁判官の話の内容は要するに、被害者との示談をまとめるよう励んでくださいといったことでした(その事件はその時点で示談がまとまっておらず、結審ぎりぎりでまとまった)。このケースでもおそらく、裁判官と検察官は、じかに会った上で話しながら、示談の成否が今後の審理の焦点になってくるな、という意思疎通が充分にできて、その上で弁護士を呼んだ、というわけです。弁護士の私が呼ばれるときには充分、裁判官と検察官は息を通じ合っているのです。このケースは確かに、傷害の事実は争いなく、示談できるか否かだけの事件だったので問題は少ないのかも知れません。しかし、検察官と弁護士が有罪か無罪かで正面から争っているケースで、裁判官と検察官だけが法廷のあとに意向を通じ合っているのだとしたら、不公平であり問題であろう、と思ったのです。今もそのようなことが多く行われているのかどうか知りませんが、ふと思い出して書いてみた次第です。
2008/01/19
-
判決がすぐに出る--即決裁判手続
光GENJIの赤坂、でしたか、覚せい剤の所持だか使用で最近逮捕され、タレントという存在のはかなさに思いをいたしていたら、早速、執行猶予つきの有罪判決が出たと。えっ判決がそんなに早く出るの? と一瞬驚いてしまったのですが、法改正で新たに制度化された「即決裁判手続」が適用されたとのこと。いちおう、最近の刑事訴訟法の教科書にはそういうのが載ってるなあ、という程度には知ってはいたのですが、具体的にどういう制度で、いつから適用されるというのはチェックしていませんでした。最近の刑法や刑事訴訟法その他、刑事関連の法律の変化の早さは、弁護士でも驚くくらいのものがあります。それはともかく、即決裁判とは、一定程度以下の(詳細は省略)軽微な犯罪で、被告人自身も弁護人も特に争いのない案件であれば使うことができる、簡単・迅速に裁判を終わらせる制度です。簡単・迅速といえば、軽微な交通事故なんかでよく利用される「略式裁判」は従来から存在していました。これは、裁判所が書類だけ審査して、罰金刑を下す手続きです(罰金より重たい懲役刑や禁固刑は下せない)。新しくできた即決裁判は、これと違い、実際に法廷が開かれる。正式の裁判と異なるいちばん大きな特徴は、裁判を開いたその日に判決言渡しができるということです(正式裁判なら、審理は終了して判決は後日、ということになる)。懲役刑や禁固刑も言い渡すこともできますが、その場合は執行猶予をつけないといけないことになっています。軽微な事案で、やったことには争いがなく、情状酌量の上で執行猶予が予想されるようなケースは実際たくさんあります。そういうとき、(冒頭の赤坂は保釈されていたからいいけど、)保釈金がなくて拘置所にいる被告人であれば、さっさと判決を出してくれ、というでしょう。そういう場合に有用な制度ではあると思います。コトは犯罪ですから、あっさり手短に、というのを強調しすぎるのは不謹慎なのですが、時間と労力を節約できる事件は早く済ませて、本当にじっくり審理しないといけないような(たとえば冤罪かどうかが争われているような)重大事件に労力を注げるようになれば、刑事司法のあり方としても望ましいものと考えています。
2007/11/22
-
法律に「人の思い」を盛り込むべきか
前回、戸籍という行政上の制度に対し、人が「生きた証」を求めるのは筋違いだと書きました。このように、「気持ちはよくわかるけど、それを法制度に求めるのは違うのではないか」と感じることは多いです。ここで取り上げるケースにも、その表れと見ることのできるケースは多い。少し前に書いた、内縁の夫婦の間にできた子を「非嫡出子」として届けるのがイヤだからと出生届を出さないために住民票が発行されないことを違法だと争ったケースでは、東京高裁は違法ではないと判決したと紹介しました。このとき書いたように、出生届や住民基本台帳という制度は、親と子の関係を法律上の呼称に従って簡便に整理しておくための制度です。非嫡出子という存在に対する社会的差別や、呼び名そのものの妥当性については、それとは別途争っていくべきことであって、法律上は非嫡出子と呼ばれる子供が出生したら、それはそれとして届けないことには、住民基本台帳が混乱してしまう。その人の気持ちや考え方はともかく、とりあえず法律に定められたことは守ってもらわないと困る。もちろん、法律やそれに基づく制度というものが、素朴な感情や正義感と食い違うものであってはならないと思う。しかし、法律というのは、それら感情や正義感のうち最大公約数的なものを抽出して、とりあえずこの社会で生きていくためにはこれだけは守ろう、ということで成り立ったものです。現代は、個人の価値観や考え方が多様になりつつあり、かつそのそれぞれが尊重されなければならない。でも、だからこそ、その多様な価値観を尊重する前提として、最大公約数たる法律や、それに基づく手続きは守られるべきであるし、法律や行政上の制度に個人の考え方を盛り込むことを求めるのは間違っているように個人的には感じます。
2007/11/16
-
戸籍の記載とその人の存在意義
先日の新聞報道で見た記事から。いつどこの新聞で見たのか、うろ覚えなのですが、戸籍に関する問題です。現在、戸籍簿が従来の「紙」製による台帳方式から、コンピューター化されて電磁的記録での管理方式に移行しつつあります。台帳方式によるよりは収納スペースが省けて、また戸籍謄本を取る際にも、縦書き・手書きの見にくいものでなく、横書き・活字書体の見やすい書式に変わりつつある。ただ、戸籍がコンピューター化されるにあたって、すでに亡くなってしまった人は、コンピューターには記載されなくなる。これに反感を感じる方もいるらしい。たとえば、自分の子供が病気や事故で幼くして亡くなったとして、その後、その市役所の戸籍が台帳からコンピューター方式に移行することになった。となると、コンピューターに情報を移すにあたって、すでに亡くなっているその子供の名前は削除してしまい、新たな戸籍簿には載らなくなる。これがコンピューター化される前はどうだったかというと、死んだ人はその名前の記載の上に×印がされるだけで、名前の記載自体は残る。たとえば、私の出身地である大阪市東成区は、まだコンピューター化が遅れていて台帳方式です。このたび入籍するにあたって戸籍謄本を取り寄せてみたら、昨年亡くなった父親の名前の上に×印が書かれてあり、名前の記載自体は残っていました。しかし、コンピューター化後の戸籍謄本には、その名前自体が載らなくなるわけです。そのことを、「自分の子供が『生きた証』が否定されるに等しい」として、コンピューター移行後の戸籍にもその名前の記載を求める親もいるらしい。もっとも私は、亡くなった人の名前が抹消されるのは、やむをえないことだと思います。戸籍というのは、あくまで、現在生きている人の本籍や親族関係を明らかにするための制度であって、過去に生きていた人の「生きた証」を明らかにするためのものではない。亡くなった子供の「生きた証」をどこかに求める気持ちは分かりますが、それを戸籍制度に求めるのは筋違いだと思います。それに、亡くなった子供の名前が戸籍という行政上のつまらない文書から抹消されるだけで、その子の存在意義が消滅すると考えるのであれば、却ってその子の存在意義を軽んじることになるでしょう。戸籍からその子の名前が消滅しようが、その子が仏壇の前の遺影で微笑んでいて、その子の思い出がいつまでも心の中にある、それこそが「生きた証」ではないのかと。私の出身地である大阪市東成区も、そのうち戸籍がコンピューター化されるでしょう。その際、亡くなった父親の名前は削除されるでしょう。それでも、亡父は私の実家の仏壇の前の遺影で、微笑んではいないけど貧相な顔をさらしていて、そしてその戸籍から出てこのたび新たに入籍した私が、今こうして一家をなそうとしている、それだけで、ウチの父親の存在意義は充分に認められようと思うのです。そういう次第で、亡くなった人の名前は、もはや戸籍なんていうつまらない行政文書に記載される必要はない。戸籍から退場してもらっても、それでもその人の生きた証は消えないと思うのです。
2007/11/14
-
内縁問題について身近に考える
何度かネタにしましたとおり、現在私は内縁関係にあります。内縁というと何となく淫靡で後ろ暗い響きがありますが、もともと内縁の定義は、「社会的事実としては夫婦共同生活の実質を備えながら、婚姻の届け出を欠くために法律上の婚姻と認められない男女の関係」を言います。昔のドラマに出てきそうな、妻子持ちの男性と愛人女性の世を忍ぶような関係もそれだし、今の私のような、ひとまず新居への移転を先に済ませて婚姻届を出す日を待っている状態もそれです。何年間は一緒に住んでいないと内縁と認められない、と考える方もいますが、内縁の定義そのものに何年間という要件があるわけではありません。もっとも、ある女性が内縁の妻としての保護が与えられるか否かに関し、内縁関係の有無につき疑義が生じた際は、何年か住んでいることがその証拠となることはあるでしょう。では、ある男女が内縁関係と認められるとどうなるのか。民法をかじった方なら誰しも思い浮かぶことでしょうけど、「実質的には婚姻に近いので、婚姻関係に準ずる扱いがされる」「内縁の妻は可能な限り法律上の妻と同様の保護が与えられる」ということになります。たとえば、法律上婚姻している夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。私はだいたい守っています。家事は任せきりかも知れませんが。それから、貞操(ていそう)義務、つまり他の異性と浮気してはならないという義務も負いますが、これも今のところ守っています。浮気すると、内縁の妻であっても慰謝料請求権が発生します(だからというわけではありませんが)。今、突然私が死んだらどうなるか。内縁の場合、相続権はないので、私の財産は親に行くことになります。内縁関係はあくまで事実上のものでしかないという限界がここにあります。労災で死んだ場合の遺族年金には、たしか内縁の妻も遺族として含まれるはずですが、私は事業主なので労災保険に入っていません。だから当分死なないように気をつけます。また、法律上の夫婦であれば、その間にした契約はいつでも取り消すことができる(民法754条)。夫婦間では何でもナアナアで約束してしまいがちなので、法的拘束力を認めない趣旨です。この規定が内縁関係でも準用されるかといいますと、どうもそのようです(たとえば内田貴「民法4」補訂版p153)。というわけで、結婚指輪を明日の日曜に買いに行こうという約束を先ほどしてしまったのですが、これはどうも取消しが認められるみたいです。
2007/11/10
-
混合診療のあり方と健康保険法の解釈
昨日少し書いた、混合診療に健康保険の適用を認めない扱いを違法とした東京地裁の判決について触れます。混合診療とは、健康保険が適用されて治療費が安くなる(自己負担3割のみ)医療行為と、それ以外の医療行為(全額自己負担)を併用することを言い、いまだ政府に認可されていないような新しい医療技術を併用したい患者が利用することが考えられます。ところがそれをやると、なぜか、保険適用外の分だけでなく、もともと保険対象だった分までその適用を外されてしまい、すべての医療行為が全額自己負担分となるとされていました。東京地裁は、健康保険法にはそんなこと書いてない、保険の対象になるか否かはそれぞれの医療行為ごとに別個に判断されるのだ、と言った。法律家としては、妥当な判決であると思います。いつものクセで卑近な例で考えてみますが、例えば、デパートのバーゲンセールで、在庫品は20%OFFだが、新品のブランド物はセール対象外で値引きナシとされていたとする。そこで在庫品(割引あり)と新品(割引なし)の両方を買おうとしたら、店員が、「新品と一緒の場合は在庫品も割引なしになります」と言ったとしたら、誰だっておかしいと思うでしょう。他の例。刑事事件の被告人に国選弁護人がついたが、被告人としては弁護人はたくさんいるほうが心強いと思って、もう1人の弁護人を私選でつける。この場合、国選弁護人は解任されます。費用低廉な国選弁護人と、それなりの費用がかかる私選弁護人は併用できない。弁護人を2人つけたいのなら、「全額自分のお金でつけろ」ということになる。ただこれは法的根拠がある。国選弁護人は「貧困その他の理由で弁護人をつけられないとき」に選任されると刑事訴訟法に規定があります。翻って、混合診療。低廉な保険対象の医療と、全額負担の対象外の医療を併用しようとすると、保険対象のものまで保険が外されてしまう。こういうあり方の是非については、議論があるみたいです。未認可の医療行為が広く行われることになり危険だとか、お金持ちだけが医療行為を選択できることになり格差が生じるとか。しかしそれは、東京地裁も言ったように、健康保険法の解釈とは別次元の問題なのです。法解釈としては、本来保険が適用されるべき医療行為にそれがなされていない以上、違法と考えざるをえない。普通に考えれば誰しもおかしいと思える事柄について、法的根拠がなく、誰もが理解できる理由があるわけでもない。となれば、その事柄は「違法」と評価されざるをえないわけです。医療の現場というのはよく知りませんので、今の形の混合診療が果たしてよいものなのか否か、それについては深くは触れずにおきます。でも医師会や厚生労働省の官僚が、今の形を残すというのであれば、その制度の合理性を説くだけではなく、健康保険法にそのことが明記されるように働きかけていくべきでしょう。
2007/11/09
-
改めて国選弁護制度について考える 5
国選弁護制度について、まとまりのないまま書いてきました。弁護士の公益活動は儲けにつながるものではないけど、多くの弁護士はそれをやってきた。しかし、競争原理を強調しすぎると公益活動をする弁護士は減り、かといってそれを強制すればイヤイヤやる弁護士が増えてしまいはしないか、という危惧を感じます。以上、私が言いたかったことの要約です。だから以下は余談です。私自身は現在、「多忙」を理由に登録をはずしてもらっているので、国選弁護の仕事はまわってきません。もちろん、刑事弁護をやらなくなったわけではありません。私が4年間勤務した事務所のボス、つまり私の師匠にあたる上坂明弁護士は、「人権感覚を忘れないためにも刑事弁護に常に関わっておくべきだ」とおっしゃっていました。だから私選の刑事弁護の依頼がきたときは断ったことはありません。それから、「当番弁護士」にも登録していました。このブログで書いたことがありますが、逮捕直後の被疑者の要請に応じて面会に駆けつける制度です。登録しておくと、年に何回か日を指定され、その日は要請に応じて出動できるよう、事務所で待機しておくことになります。しかしこれも、昨年度までで登録を外しました。昨年度までは、土日の当番をしないことを条件に登録するなど、細かい注文ができたのですが、今年度からはなぜか「土日を外すのはダメ」ということになりました。私は、土曜日は司法試験予備校などで講義を持っていることもあって、土曜に当番を指定されると困るのです(代わりの人が見つかればいいけど、見つからなければどちらかをサボらないといけなくなる)。公益活動をせよといいつつ、ちょっとした事務処理上の便宜を図ることすらヤメてしまった弁護士会の方針には、ここでこっそり異を唱えておきます。とはいえ、刑事弁護制度は充実しつつあります。刑事訴訟法の改正で、起訴後の裁判段階だけでなく捜査段階でも国選弁護人がつくことになりました。刑事弁護に熱心に携わっている弁護士たちからは、大きな前進だとの声があがっています。弁護士にとっては儲からない仕事が増えるだけなのですが。富山の強姦冤罪事件でも、捜査段階で国選弁護人がついていれば、かなりの確率で冤罪になるのを防げたと思います。かくて、行き過ぎた競争原理は弁護制度(特に国選弁護をはじめとする刑事弁護制度)を揺るがしかねないものであるとはいえ、心ある弁護士はそんな状況でも制度の充実に尽力しています。私自身は国選も当番も現在やっておりませんが、自分なりに刑事弁護制度をいかに充実させていけるかを日々の業務の中で考えていきたいと思います。
2007/10/26
-
改めて国選弁護制度について考える 4
国選弁護制度について概要を書いてきました。弁護士の感覚として、国選弁護をやって儲かるのかといえば、率直に言ってそんなことはない。警察署や拘置所(被告人との面会)、検察庁(捜査記録の閲覧・コピー)、裁判所(公判)に度々出向いて、8万円程度が後払いされるだけなら、他の仕事をやったほうがマシです。でも刑事事件の被告人には弁護人をつけてもらう権利があると憲法にも書いてあるから、憲法上の、いわば公益上の要請として、協力しようという気持ちでやっている弁護士が多い(と思う)。もっとも私個人は、日々の業務で、どの事件でいくら収益があるといったことはいちいち考えていません。儲からない、ペイしないような仕事もあれば、正当な報酬の出る仕事もある。分け隔てなく仕事をこなしていけば、トータルとして法律事務所が成り立つだけの収益があがる。そういう感覚です。ところが最近、司法制度改革が云々されるようになった。「弁護士の人数は規制されすぎている、もっと数を増やして、弁護士にも競争原理を取り入れないといけない」と、主に経済界から言われるようになった。今後、弁護士人口は増えることが必至の状況です。たしかに、現時点では弁護士はまだ少ないと思うし、もう少し競争させてもいいように思う(法務大臣が「増やし過ぎ」と言ったらしいですが、その辺りの議論はまた改めて)。しかし、弁護士もサービス業とはいえ、普通の商売と全く同じに考えると、やはりおかしくなる部分はある。国選弁護など公益的な役割を果たさないといけない部分が多い職業だからです。弁護士ももっと競争せよ、と一部の経済人が言うなら、若手弁護士としては「そうおっしゃるなら競争しますで」と言うでしょう。すると、国選弁護などの、ペイしない仕事は誰もやらなくなります。そんな経済原理に反するような仕事をしていては競争に負けてしまうからです。その兆しはすでにあらわれていて、東京や大阪の弁護士会では、国選弁護などの公益活動を義務化し、一定量以上の公益活動をこなさない弁護士は名前を公表するとか、課徴金を取るという制裁を科することになった。従来は、儲かる仕事もそうでない仕事もこなすことで、バランスが取れていた。それが社会の要請として競争原理が強調されるようになれば、国選弁護などの公益的な仕事は誰もしようとしなくなる。その一方で弁護士会は制裁をもって公益的業務を強制する。すると後はどうなるか。「イヤイヤながら、やる」ということにならざるをえないでしょう。かくて片手間の国選弁護が増え、富山の冤罪事件のようなことがまた生じかねないのではないかと、それが不安です。あと少し続く。
2007/10/24
-
改めて国選弁護制度について考える 3
国選弁護についてのお話の続き。このシリーズ「2」で、大阪弁護士会における国選弁護人選任のシステムと、仕事の流れの概要をお話ししました。「1」では、国選弁護の報酬は(最も単純なケースで)8万円程度で、私選弁護の着手金である30万円程度(これも弁護内容によります)だとお話ししました。富山の強姦冤罪事件では、国選弁護人が初動のころの弁護を手抜きした可能性がある。さて、国選弁護人だと刑事弁護をしっかりやってくれないものなのか。もちろん、そんなことがあってはいけない。国選でも私選でも、受けた事件に手抜きしてはいけない。これはタテマエだけではなくて、少なくとも私個人はそう思っています。私自身の宣伝になってしまいますが、かつて国選弁護を受け持った被告人が執行猶予で出てきて、そのあと私の事務所にアイサツに来ました。そのとき彼はこう言って感謝してくれました。「国選でここまでやってくれる先生はおらんぞ、って、警察署で何回も言われてたんです」この件は起訴された後の「追起訴」(ついきそ=複数の事件が順次起訴されるため、そのぶん取調べに要する期間が長くなる)があったり、自分なりに事件内容に疑問点があったりして、それで何度も警察署に面会に行ったケースでした。普通に面会に行っていたつもりが、警察署の人も驚くくらいに頻繁の面会となっていたようです。ひるがえって考えると、これはつまり警察署の人間にも、「国選弁護人は手抜きして面会にもあまり来ないもの」という観念があるということかも知れません。警察官や、その他一般の人々に対し、そのような観念を形成してしまっているとしたら、弁護士全体が反省すべきでしょう。さて、かような国選弁護の実情、と言いますか私が浅い経験からちょっとだけ垣間見た事情を踏まえて、もう少し述べたいところもあるのですが、それは次回に。p.s.前回、亀田大毅選手のことをネタにした直後に、内藤選手の家へ謝罪に現れたようですね。アポなし突撃とは言え、いちおうの謝罪はした。そのあたりの論評については、今となっては「まあどっちだっていいや」と昭和のいるこいる風に述べておきます。
2007/10/22
-
改めて国選弁護制度について考える 2
国選弁護制度について。続き。国選弁護人は基本的に、起訴されて刑事裁判を受けることとなった被告人につきます。逮捕直後の段階(被疑者の段階)は基本的につきません。「基本的に」といったのは、最近の法改正で、一定の場合にはつけられることになったためです。後で述べます。従来型の、起訴後の国選弁護のイメージは以下のようなものです。なおこれは大阪地裁管内の扱いで、他の都道府県によって運用は微妙に違うかと思います。まず、弁護士は年に何日か、国選弁護を担当する日を割り振られる。この割振りは、各弁護士が「年に何回引き受けます」と大阪弁護士会に申請しておくことによって、毎年所定の時期に「この日でお願いします」という通知が来る(引き受けない、つまり国選はやらないという選択もある)。その担当の日の4週間前になると、弁護士会の窓口に、「あなた担当の日の裁判予定はこれです」というリストが開示されるので、自分が弁護を引き受けてもよいと思う被告人の名前のところに自分のハンコを押す(早い者勝ちです。たいてい、ラクそうな事件から埋まる)。国選弁護人を選任するのは国、具体的には裁判所ですが、その選任は、この弁護士会からあがってきたリストに基づいて行われます。それで、担当事件が決まると、裁判までの4週間の間、弁護活動を行うわけです。まず、裁判所で起訴状をもらう。で、警察署か拘置所か、その被告人が勾留されている所に接見(面会)に行って、挨拶かたがた、事実関係に間違いないか、弁解すべき点はあるかなどを聞く。裁判の2、3週間前になれば、検察側が事件の捜査記録を開示してくるので、それを見に行く。それに基づいて改めて被告人と詳細に打合せをして、裁判に臨む、そういうイメージです。裁判の審理は多くは1日で終了し、あとは判決を聞きに行くだけとなる。今書いたのは刑事裁判の中でも、最も簡単なケースです。事件が複雑だとか、件数が多いとか、その他打ち合わせが必要となるような事情があれば、もっと頻繁に接見に行くことになりますし、裁判自体も1日では終わらない。ちなみに、今回問題となっている富山の強姦冤罪事件では、報道によると国選弁護人は裁判まで2回しか接見に来なかったらしい。特に争いのない事件なら2回で済ますこともあるでしょうけど、「自分はやっていない」と否認している事件で2回というのは、たしかに少ないなという印象を受けます。続く。
2007/10/17
-
改めて国選弁護制度について考える 1
富山の痴漢冤罪事件について書いていますが、一部報道からも指摘がされていますとおり、弁護士としても反省すべきところがあるのかも知れません。あの事件の弁護士は、いったい何をしていたのだと。日弁連も、当時この事件を担当した国選弁護人からの事情聴取を行うらしい。当時、この元被告人は弁護士にどんな説明をし、それを受けて弁護士はどのような弁護活動をしたのか、たいへん興味あるところだし、弁護活動に問題があるとすれば公表して、弁護士に対する戒めとすべきでしょう。本当にやっていないと言っている被告人を前にして、その弁解を聞き届けなかったとすれば、弁護士として懲戒モノでしょう。山口県の母子殺害事件の弁護士よりもよほど問題です(山口の事件の弁護士は、やり方の当否について議論はあるだろうけど、弁護活動は行っている)。この点については、事実関係の調査がされるのを待つとして、国選弁護制度についてお話ししたいと思います。刑事事件の被告人として裁判を受けることになったけど、弁護士がいない場合に国がつけてくれるのが国選弁護人です。弁護士がいない事情はいろいろありましょうが、最大の理由は弁護士を雇う経済力がないことでしょう。刑事事件で弁護士に依頼すると、内容にもよるでしょうけどだいたい30万円程度の着手金がかかります。国選弁護人がついてくれると、そのお金が要らない。その場合、弁護士に対しては国が費用を払います。金額は、事案にもよりますが簡単なケースでは8万円程度です。この8万円は、裁判が終わったあと、国からその被告人に請求できる建前なのですが、実刑判決をくらってしまったとか、貧困とかを理由に免除されることも多い。弁護士からしてみると、同じ刑事事件でも、普通に依頼を受けて行う場合(国選との対比で私選弁護人という)は30万円を受領できるのに、国選なら8万円(しかも後払い)というわけです。それで、世間一般の考えでは、国選弁護人は私選弁護人に比べて、費用が安い分、きちんと力を入れてくれないと捉えられているようです。果たして国選弁護人は手抜きを行うものなのか。この機会に国選弁護制度について何度かに渡って書いてみたいと思います。
2007/10/15
-
裁判員制度と報道規制
毎日朝刊から。最高裁の参事官(エライ地位にある人)が某所で裁判員制度に関する講演を行い、制度導入後の報道のあり方について懸念を示したと。いわく、「容疑者が自白したとか、その弁解が合理的でないとか、識者のコメントとかを報道するのは、裁判員となるべき一般国民に対してその事件と容疑者に対する予断(偏見)を生むことになるのではないか」と言ったらしい。私自身は、当ブログでも折に触れ話してきましたように裁判員制度には疑念を感じているので、ほら、無理な制度を導入するから、何だかおかしなことになってきたじゃないか、という思いです。たしかに、証拠に基づいて明らかにされた事実と、新聞や週刊誌で報道された事実が異なることはザラにあると思う。報道された事実をうのみにして、刑事弁護を行う弁護士を批判するのも的外れです。しかしそれでも、報道機関が自身の取材に基づいてその思うところに沿って報道すること自体は、表現の自由(憲法第21条)を持ち出すまでもなく、決して妨げられてはならないし、そんなことが行われるともっとやっかいな世の中になるでしょう。最高裁のエライ人は、報道規制をせよと言っているのではなくて、あくまで「懸念を示した」だけではあります。裁判官は報道に左右されることなく、証拠に基づいた事実を認定できるよう訓練されているが、一般国民はそうではない。報道された事実が真実だと信じ込むおそれがある。だから、容疑者が容疑事実を認めているとか、その言ってる弁解が不合理だとかいう報道がされれば、それを読んだ裁判員は「コイツが犯人だ」と思い込んで裁判に臨むことになる、ということを懸念しているのです。何と言いますか、裁判員制度は、裁判というものに一般国民の常識や感覚を盛り込もうというタテマエで始められたはずです。しかしそれを受け入れる現場の裁判官としては、国民はバカだから報道に左右されやすい、国民と一緒に裁判をするのなら報道規制を行わないとダメだ、と肌で感じているのでしょう。裁判員制度が、「国民の良識を司法に取り入れる」という美名の下に何だかよく分からないまま導入されてしまったように、気をつけていないと、「国民の良識がタチの悪い報道でゆがめられてしまうのを防ぐ」という名目で報道規制がされてしまいかねないですよ。おそろしい話です。と懸念を示しておきます。
2007/09/28
-
ホワイトカラー・エグゼンプションの復活なるか
大阪の法律事務所で職員が殺害されたとか、ショッキングな事件もありましたが、これに対する論評は、もう少し事件の概要が明らかになってから書くことにしまして、今日の朝刊で興味を持った記事から。舛添要一厚労相が、「ホワイトカラーエグゼンプション」制度を日本に導入する法案がかつて野党やマスコミから「残業代ゼロ制度」と翻訳されて批判を浴びたことを受けて、今後は「家庭だんらん法案」と呼べと厚労省の事務方に指示したとか。ホワイトカラーエグゼンプション制度は、主に専門的職能を持つ従業員の給料を、時間ではなく職能に応じて評価する仕組みで、残業しても直ちに残業代につながるわけではない。私も法律事務所に勤務していたころは、給料は定額プラス歩合で、残業代はつかないけど、自分の手持ちの事件さえこなしていればあとは自分で時間を決めることができて、早く帰ろうがサボろうが文句は言われなかった。かように、特に専門職にとっては合理性のある制度だと思う。ところが、これが「残業代ゼロ制度」と訳されたことで世論そして野党の反発を受け、昨年の国会では廃案に至った。このあたりの話は過去の記事へ。そこで今回の言い換えですが、「家庭だんらん法案」。どんなものでしょう。何となく、「家庭にはだんらんがあって当然」と言わんばかりのネーミングで、何だか厚労省に家庭生活のあり方まで指示されているような気がする。だんらんのない家庭や、家庭を持っていない独り者には適用されないような印象を与える。他にも舛添氏が例として挙げたのは、「パパ早く帰ろう法案」。これも独り者に適用されない印象です。早く帰ろうとする独身の社員に、課長が「お前はパパじゃねえだろ」と言いそうな気がする。そこでさらに舛添氏が他の候補として挙げたのが「バカな課長の下で仕事するのはやめよう法案」。ここまで来るとさすがに本気では言ってないのでしょうけど、こんな名前の法案が国会を通過したらまさに痛快ではあります。早く帰ろうとする社員に、課長が「俺がバカってことかよ!」と怒ってそうな気がする。冒頭に書いたように、舛添大臣が厚労省の事務方(厚労省の官僚のことでしょう)に、然るべき呼び名で呼ぶように指示したということで、お役人がどんな呼び名を考えてくるかは楽しみです。
2007/09/12
-
「被害者に国費で弁護士」制度の是非
たしか昨日の日経だったかたと思いますが、刑事事件において、被害者にも国費で弁護士をつける制度が検討されているらしい。いい制度のように思えますが、全く手放しで喜んでいいものかどうか。被害者側の弁護士の役割は、おそらく、これから制度化されるであろう刑事弁護への被害者参加において、その指導をするとか、民事上の損害賠償請求の代理人に立つとか、社会的に注目される事件であればマスコミ対策をするとか、そういったことが考えられるでしょう。刑事事件において加害者である被告人には国選弁護人がつく、被害者にも国費の弁護士がついて当然だ、という均衡論は、たしかにわかりやすい。ただ、刑事事件においては、加害者を訴追する検察官が被害者の気持ちを代弁し、それを裁判官がくみ上げて判決を下すというのが、本来の刑事訴訟制度のあり方のはずです。被害者側に弁護士をつけるというのは、検察官が「私ら被害者の気持ちを代弁できてません」と言っているに等しいのではないか。また、「被害者の参加」を標榜する近年の刑事訴訟制度の改正が、実は被害者や一般国民にとって理解しがたい、場合によっては負担となりつつあることを、国が認めているに等しいのではないか。私を含めて、刑事事件をやっている弁護士はみな同じ考えだと思いますが、従来も、刑事事件の弁護人は、「加害者の弁護をするのか」と時になじられながら、実は被害者救済のために一番役割を果たしてきたという自負があります。そのあたりの話は過去の記事。今回、国費で被害者のために弁護士をつける制度が検討されているというのは、検察その他の国家機関は被害者保護を実際に果たしてこなかったこと、それを果たしていたのは弁護士であることを追認するものであって、かつ、「国の制度上、何か問題があったらそこは弁護士にやらせよう」という国の安易な思考の表れであるように思うのですが、これは一弁護士の思い込みに過ぎないでしょうか。まあ、国費で弁護士の仕事の領域を拡大してくれるというのですから、ありがたいことではあるのですが。
2007/08/25
-
司法試験はどこへ行く 完結編
司法試験制度改革について、私なりの浅い見解を述べてまいりましたが、これで最後にします。少し具体的な話なので、ここで書くことにためらいを感じなくもないですが、過去こういうことがありました。私はここ6年ほど、司法試験予備校や大学で講師をしていますが、ある年度の予備校のクラスで、講義に熱心に通ってくれる大学生がいました。彼を仮にA君としておきます。A君は講義後の質問などにも積極的に来る方だったのですが、その彼があるときを境に、ぱたりと講義に来なくなりました。何かあったのかなと思っていたら、後日、同じクラスの別の受講生から伝え聞いたのはこういうことでした。そのA君がとあるロースクールの入試面接を受け、面接官に「今どのようなことを勉強しているか」と問われた。A君は「大学での講義のほかに、司法試験の予備校に通って熱心に勉強している」といったことを答えた。すると面接官は、「うちのロースクールでは司法試験予備校に行っている人など要らない」といった趣旨のことを言ったらしい。A君はそれにショックを受けて、予備校に来れなくなったと。もしこれが事実だとしたら、私はこの面接官に憎しみを感じます。大学院側は、予備校などは受験のための小手先のテクニックを教えるためのところで、大学院がホンモノの法学を教えるところだという意識がある。でも私は、自分自身の受験生時代がそうであったように、今の受講生にも、小手先ではなく(小手先で受かるような試験ではない)真っ当な勉強をするように、受験テキストでなく学者が書いたきちんとした教科書(基本書)を読みこなせるように、意識して伝えて、かつそのような講義をしているつもりです。予備校に対する勝手な偏見で、若いA君の学ぶ気持ちを殺いでしまったその面接官には大きな反感を禁じえません。話かわって、最近、こういうこともありました。これも過去に私の講義を受けていた受講生の方の話です。B君としておきます。このB君が久しぶりにメールをくれて、質問したいことがあると。何かというと、大学の学部の講義で課題が出て、「内容証明郵便」を書かされることになった。その書き方が分からないから教えてほしい、とのことでした。質問にはお答えしましたが、私の考えでは内容証明郵便の書き方なんて、民法の基本がしっかりしていれば一瞬で理解できます。そんなことは小手先のさらに先のことであって、司法試験を終えてからでいい。最近の法学部や法科大学院は、法曹としての適性をじっくり養うために、実務的なことも学ばせるというのが一つの傾向らしいですが、そのやっていることが一片の内容証明郵便を書くことであるというなら、嗤うべき「実務教育」であると思います。少し前に書いた、ロースクール講義で司法試験の問題漏洩疑惑が生じたなど、制度はまだ混乱しているような印象があります。でも、こんな状況の中で司法試験に挑戦しようというこれからの受験生には、心から激励したいと思います。そして、時代や制度がどうあれ、真っ当な勉強をする人が最後に勝ち残るのだということを強調したいと思います。(何だか今回は、一般向けというより受験生向けの話になってしまいました)
2007/07/23
-
司法試験はどこへ行く 4
さて、ダラダラと書いてきました司法試験改革についてのお話ですが、先週末のうちに自分なりにまとめてしまうつもりが、いろいろ慌しくて更新できないままになりました。これまで書いてきたところからだいたいお分かりかと思いますが、私自身は今般の制度改革については懐疑的なスタンスでおります。苛烈な一発試験と、そのための極端に重い受験勉強の負担という弊害を取り除くことを目的としながら、結果的に司法試験が「受けにくい」ものになってしまったという点が問題だと思います。制度改革の建前はともかく、その本音の部分はこういうことでしょう。すなわち、受験生がみな大学ではなくて司法試験予備校に流れてしまう。本来なら、大学の学部教育を充実させることによって学生を大学に取り戻すべきなのだけど、そうはせずに、法科大学院という、国家お墨付きの機関を出ないと司法試験が受けられないようにする。教えることの「中身」ではなくて、「権威」によって学生を取り戻すということでしょう。とはいえ、批判ばかりではなくて、改革に見るべきところもあるということで、いちおうフォローしておきます。たとえば、すでに書きましたが、法科大学院を出た後の受験資格は、「卒業後5年以内、回数で3回以内」です。受験回数・年限に制約が設けられた。これまではどうだったかというと、このような制限は全くナシ。だから、中国の科挙みたいに、試験に受からないまま受験生歴20年や30年、というような人が実際にもいた。しかし、あくまで私の個人的な考えですが、5年も10年もやってダメな人は、20ないし30年やってもダメなように思います。そういう人は、どこかでやり方を間違っているので、それは年数をかけて解決できるものでもない。でも、いったん受験を始めてしまった人は、途中でやめると言い出せなくて、何年も受験を続けることになる。何年も努力してきたことを自分の意思であきらめるというのは、自分自身でも認めたくないだろうし、周囲に対しても恥ずかしい。それで仕方なく、あきらめる理由がなくて続けてしまう。3回以内、5年以内といった制限をつけてあげれば、受験する側もあきらめがつくのです。自分はホントならもっとがんばれたけど、制度上は仕方ないのだと。受験回数の制限にも賛否両論あると思いますが、私はこういう次第で、あきらめのつかない人に対して国家が強権的にあきらめがつくようにしてあげるという点で、意味のある改革ではあると思います。
2007/07/22
-
司法試験はどこへ行く 3
司法試験が一発試験でなくなったせいで、かつての私がそうであったように「一念発起型」の受験ができにくくなったことについて、もう少し書きます。この制度改革によって、例えば、経済的に裕福でない家庭の子供が働きながら夜学に通って苦学して司法試験に受かる、というようなパターン(NHKの「生活笑百科」の解説をしていた三瀬顕弁護士がたしかこれだった)もやりにくくなる。法科大学院に通うのにもまたお金がかかるわけですし。なぜこういう制度になったか。制度改革を中心になって推進した一人である、憲法学者の佐藤幸治教授などはこう言います。この人、司法試験受験生なら誰でも知っている教授です。一昔前の司法試験受験生は、ほぼ皆この人の書いた憲法の教科書を読んでいた。私も、600ページを越えるこの人の教科書を暗記するくらい(と言うと誇張ですけど)読み込みました。この佐藤教授は、私がかつて勤務弁護士として勤めていた事務所の所長(上坂明弁護士)と、とある審議会で席を並べていた時期があって面識があるらしく、そのため、この教授が著書を出すたびに、うちの所長あてに一筆箋つきでその本が送られてきていました。私は勤務弁護士時代、「へー、あの佐藤幸治が」と思いながら、所長室の本棚に並んだそれらの本を手にして読んだものです。と、私ごとに話がそれましたが、その佐藤教授がそれらの著書の中でこう言っていました。何の本かは忘れましたので記憶で書いているのですが(詰めが甘くてすみません)、「法科大学院制度に反対する人に対しては、人の人生に関わるような仕事をする法曹を採用する試験が『一発試験』でいいのですかと問いたい」と。医師国家試験などは、それを受けるまでに医学部で長年教育されることを引き合いに出して、充実した法曹教育の重要性を説いておられます。しかし…。一発試験はダメだから制度を変えるというのは、かなりの飛躍であるように思うのです。国家に関わる仕事をするキャリア官僚を採用する国家1種試験は一発試験なわけですから。それに、司法試験自体は一発試験でも、その後、司法研修所でそこそこしっかり勉強をやらされて、研修所を出るにも卒業試験があるので、法曹になるまでの過程は決して一発試験ではない。しかも、一発試験は望ましくないということを当然の前提のようにおっしゃるわけですが、一発試験だと優秀な法曹が育たないといった事実は実際に検証されたわけではない。普段は常々、人権を制約するような法律や制度に対しては、そのような制度が必要とされるような事実(「立法事実」のことです)があるかどうかを厳密に検証しないといけない、と言ってる憲法学者が、こと司法試験制度改革については、その検証を全く抜きにして制度を変えてしまった、それが私の印象です。たぶんもう少し続く。
2007/07/19
-
司法試験はどこへ行く 2
司法試験の制度改革について書こうとしています。前回書いたとおり、これまでの司法試験は、いわゆる「一発試験」でした。一発といっても、択一式(5月)、論文式(7月)、口述式(10月)というふうに行われるのですが、とにかくこのすべてに1回でパスすれば、司法修習生になって、法曹となる資格を得ることができます。今後は、法科大学院(アメリカのロースクールに倣ったもの)に2~3年通い、それを卒業してようやく司法試験の受験資格が得られます。これまでは、受けようと思えば基本的に誰でも受けられる試験だったのが、これからは、試験を受ける資格を得るために大学院に入らないといけない。その大学院にももちろん入試があります。大学院を出たあとの司法試験も、もちろん受かる保証はなくて、卒業後5年以内に3回に限り受験できる。それで受からなければ受験資格が失われる。制度改正当初は、大学院さえ出れば8割は受かるようにする、とか言われていました。大学院で時間をかけてじっくり教育を受けて、その代わりに試験自体は受かりやすいものにして、時に中国の「科挙」にもなぞらえられたほどの司法試験の苛烈さを和らげようというのが狙いでした。ところが実際は、ふたを開けてみると合格者は大学院出身者の4~5割程度にとどまっています。私自身は、前回も書いたように、大学卒業後、司法書士の資格を取って司法書士事務所に勤めていましたが、やっぱり弁護士になりたいと一念発起して司法試験の勉強を始めました。24歳のころのことです。でもこのとき、今の制度みたいに、司法試験を受けるにも大学院に2~3年行かないといけなかったとしたら、そういった方針転換をしたかは疑問です。私が司法試験予備校での講師の仕事を始めた平成14年のころは、受講生にも30歳前後の方や、またはそれ以上の年齢の人など、「一念発起型」と思われる人がチラホラとおられました。最近のクラスは若い方が多いです。もちろん、若い人が早い段階から進路を見定めて、司法試験を目指して勉強することはよいことです。でもその一方で、大学を出てある程度の経験をした人が、一念発起して法曹を目指すには、あまりにも面倒な制度になってしまったということです。制度が変わってしまったので、今さらこれを論じてもどうなるものでもないかも知れませんが、もう少しだけ続くと思います。この話。
2007/07/18
-
受験生たちの夏~司法試験はどこへ行く
連休いかがお過ごしでしたでしょうか。大阪では、えらく大きな台風が来る、と身構えていたら、あまり大したものがこなくて、安心して連休最後の昨日に遊びに出たら夕立で大雨が来てやられた、といった方も多かったのでは。とは言っても幸い、大阪では大きな被害はなかったようです。台風や地震で被害を受けた地方の方にはお見舞い申し上げます。さて、先週の土日といえば、司法試験の論文試験が行われた日でした。司法試験受験生の最も暑い日だったかと。試験制度が改革されて、今後はロースクール(法科大学院)を卒業して初めて司法試験が受けられるという制度になります。この土日に行われたのは旧制度の試験で、この制度ももうすぐなくなるので、まさに駆け込みできるかどうかの瀬戸際です。私自身ももちろん過去にこの試験を受験しています。司法書士事務所に勤務していましたが、一念発起して弁護士になろうと決意して、勉強を始めて、平成10年の試験に合格しました。その後、毎年この時期には、「今年も受験生は大変だなあ」と他人事のように思っていたのですが、今年は、私が講義をしている司法試験予備校から、論文試験に出題された問題の参考答案と解説を書いてくれ、と依頼がありました。私なんかでいいのかなと思いつつ、6教科のうち2教科を担当することになってしまい、そのためこの連休は、たまっている残務を片付けるのと、司法試験の参考答案を書くために費やす羽目になりました。そんな私ごとはともかく、試験制度改革によって、今後かつての私のように、一念発起して一発試験に受かれば人生が変わる、みたいな話はなくなっていくわけでしょう。さて、このような試験制度改革の良し悪しと、それが今後の司法制度にどう影響を与えていくのか、私なりの浅い経験に基づく見解について、次回にでも書いてみたいと思います。
2007/07/17
全133件 (133件中 1-50件目)