2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
Windows Vista及びInternet Explorer7の使用制限について
1.Windows Vista環境での国保中央会介護伝送ソフトの使用制限について 国保中央会介護伝送ソフトは、現時点で、マイクロソフト社OS Windows Vista環境での動作検証を完了しておりません。Windows Vista環境では本ソフトをご使用いただいた場合、パソコン本体及びソフトに異常が発生する可能性がございますので、Windows Vistaのインストールされているパソコンで本ソフトをご使用いただかないようお願いいたします。2.国保中央会介護伝送ソフトとInternet Explorer7を同一パソコンで使用することへの制限について 国保中央会介護伝送ソフトは、現時点で、マイクロソフト社Internet Explorer7を同じパソコンに導入(インストール)した場合の動作検証を完了しておりません。 国保中央会介護伝送ソフトとInternet Explorer7を同一パソコンでご使用いただいた場合、エラー等障害が発生する可能性がございますので、ご使用いただかないようお願いいたします。Windows Vista及びInternet Explorer7への対応については現在検討中です。 決まり次第本ホームページ等でお知らせいたします。07/01/30 国保中央会
2007.01.31
コメント(6)
-
【老後を考える】〈4〉NPOなど支援サービス
お買い物の荷物宅配【マンション快適ライフ】 エレベーターが設置されていない古いマンションでは、体力に不安を持つ高齢者の買い物などを支援するNPO法人が登場している。 また、高齢者向けに商品配達の料金を割り引く生協もある。マンションで独りで暮らす高齢者が目立つようになり、支援サービスが広がってきた。 千葉市美浜区の女性(84)は築30年以上の分譲マンションに会社員の息子と2人で住んでいる。部屋は5階にあるが、エレベーターがないため階段の上り下りに苦労している。そこで2005年10月から、NPO法人「ちば地域再生リサーチ」の買い物宅配サービスを利用している。料金は、買い物の量によらず1回50円だ。HPのつづき・・・2007年1月30日 読売新聞“NPO”と“NPO法人”の違いですが、“NPO”は「民間非営利団体」「非営利組織」などと訳されます。営利を目的とせず、社会貢献を目的として活動する民間の団体のことをいいます。広義のNPO、狭義のNPOなどその範囲によって含まれる団体が異なりますが、一般的には、NPO法人だけでなく、法人格の無い市民活動団体やボランティアグループなども含めてNPOと呼ばれています。 一方“法人”とは、法律の規定によって、成立する団体のことで、営利を目的とする株式会社や有限会社等および営利を目的としない財団法人や社団法人等があります。“NPO法人”は、特定非営利活動促進法(NPO法)の規定によって成立した団体のことをいい、正式には“特定非営利活動法人”といいます。法人格を持つNPO法人に対して、法人格を持たないNPOは任意団体という扱いになります。確かに、自分だけの力で暮らすには不便や不安を感じる高齢者は多いと思います。>「高齢者の生活を支援する地域サービスが、社会の仕組みの中でうまく機能するようになれば、高齢者個人や行政の負担も少なく、高齢者の生活の安心につなげることができるのでは」私も、そう思います!
2007.01.30
コメント(0)
-
どうにか、こうにか:父が認知症になった時/30 老親介護の男性に聞く/上
一つの症状の対応に慣れると次の症状が始まる--陽炎(かげろう)を追うような介護の日々。アルツハイマー病の父は昨年末に肺炎を原因とする急性呼吸不全で他界した。老親介護の経験者、そして、今まさに奮闘中の男性たちのメッセージを3回シリーズで届けます。◆異常行動も受け入れて--元日本テレビアナウンサー・小林完吾さん(74)◇「介護」ではなく「看病」 病気や老人症(認知症)を患った老親の世話をすることを「介護」と表現することが多いようですが、どうも違和感があります。79歳の時に脳梗塞(こうそく)で倒れ、寝たきりの身となった母は、しばらくしてからわが家で暮らすようになりました。その時、私たち家族は「介護」ではなく、「看病」をしたのです。「介護」という言葉は行政用語のような気がし、親子など家族の間で使うにはふさわしくない表現だと思っています。HPのつづき・・・07/01/27 毎日新聞 この記事を読んでいて、「介護」、「介助」について、用語そのものの意味を調べたくなりました。明治になり、近代医療の登場により、職業看護婦が出現し、「介助」という用語が、医師の補助行為、医師への介助として、「日常的で療養上の世話」とは別な捉え方をしていたようだ。当時の「介助」という用語は医師の補助行為活動として対利用者(患者)へのサービス行為の用語であったのだろう。 「介助」や、「世話」という用語に比べると「介護」という用語は、戦前使われたとする記述は見当たらない。戦後、社会福祉行政とりわけ、生活保護行政の加算用語として「介護」が使われたとする記述があり、また、1957年頃から始まった「家庭奉仕員」に世話活動。1963年にできた『老人福祉法』に常時の介護を要する者…という日常生活に支障をきたす部分に公的に保障するものとして「介護」という用語が行政用語として次第に一般化したのではないだろうか。60年代、70年代と親なきあとの介護、在宅介護や施設の介護労働の量と質、専門性、資格問題などが問われてきた。「介護は介助行為によって、対象者の日常生活を支え、本人の生活力を明日につなげる活動、援助でなければならない。介護とは、相手の人格や生活を分析し、その個人の社会的生活を保障し、自立にむけた援助行為(活動)であり、そのための食事、入浴、移動、就寝、排せつなどの介助を通して、社会的人間として活動する上で必要な部分を補完、代行することであろう。」(財)日本障害者リハビリテーション協会発行 (亀山幸吉 氏)>これから老親のお世話をされる方に言いたいのは、お年寄りや親が元気なうちに昔話をよく聞いておくということです。そうしておかなければ、世話をする段階で、お年寄りの「現実」に付き合うことができず、苦労します。
2007.01.28
コメント(2)
-
介護予防 ~基準の緩和を要望~
昨年四月の介護保険制度改正で始まった介護予防事業について、都は二十五日、基準が厳しいためにサービスを受けられる高齢者が少ないとして、基準の緩和など制度の見直しを厚生労働省に要望した。 現行制度では介護予防サービスの対象になるかどうかは、原則的に高齢者本人が運動機能や認知症などに関するチェックリストに記入し、該当する項目数などで判定される。 都によると、この基準が厳しく、都内ではサービス対象者が昨年十一月現在で高齢者人口の0・41%だけ。同省は5%(初年度は3%も可)を見込んでいた。 都はチェックリストの基準緩和に加え、介護予防サービスが必要と医師が判断すれば対象者と認めるなど、地域の実情に応じた運用を要望した。07/01/26 東京新聞>介護予防サービスが必要と医師が判断すれば対象者と認めるなど、確かに、行政(支援センター、高齢者・障害者福祉課)、地域の介護事業所・民生委員 等からの説得力の弱さの所よりも、納得が行く医師からの言葉の方が、より介護予防の理解度は高まると思いますね!>地域の実情に応じた運用を要望した。そうですね!地域だけとは限らず、対象者の実情は、最も大事な事だと思いますよ。
2007.01.26
コメント(2)
-

昨日は、デイで新年会!
昨日の小規模のデイでは、午後のレクの時間に“新年会”をしてくれました。スタッフそれぞれ出し物をしてくれて、私たちを楽しませて頂きました。もう、ここに通うのも4年目になりますが、初めての試みのようです。スタッフも変われば、行事も変わるという事でしょうか?長年 利用する者にとっては、飽きずに継続して利用出来る、良い試みではないでしょうか?★あ い さ つ★★漫 才★☆ケコちゃん トコちゃん ピンクシャドウズ☆★コ ン ト★☆ビッキー&スパイシー☆★二人羽織★☆杉本&大竹☆★合 奏★☆白ちゃん 大ちゃん とあいはなチンドン☆★手 品★☆ミスター大竹☆★マジック★☆トントン&リンリン マジックショー楽しませて頂きました。 有難うございました。次回は、どんな出し物をしてもらえるか、楽しみにしていますよ!
2007.01.24
コメント(3)
-
在宅介護:一人でがんばらないで 乗り切るコツは…サービス利用と愚痴言える友
在宅介護のコツは「がんばらないこと」--。 公的サービスを活用して介護者のストレスを減らし、介護の質も高めていこうという草の根の運動が広がっている。 02年に設立された民間団体「がんばらない介護生活を考える会」(委員代表・鎌田實諏訪中央病院名誉院長)は「手抜きでも介護放棄でもない。 一人で抱え込まないことは介護する人、される人双方にゆとりをもたらし、介護殺人や高齢者虐待、介護疲れによる自殺も減らせる」と指摘する。07/01/22 毎日新聞HPのつづき・・・自分の身内がいきなり倒れたとき、その家族の方々は、介護のことをまったく知らない、いわゆる“ズブの素人”であることがほとんどです。入浴の仕方、身体の拭き方、ひげのそり方、着替えのさせ方、薬飲ませ方、車椅子の使い方、ベッドへの移り方、などなど。何も知らない状態で、いきなり自宅へ帰ってきても、まず何から手をつけていいのか、わかりません。間違った方法で介護をすることで、介護を受ける本人・家族の負担は何倍にも増えて、共倒れになってしまう危険があります。何もわからないまま、在宅介護を始めなければならないという、危険な状況にならないようにするために、病院に入院しているうちにできるだけ情報収集することが大切です。病院の医師・看護師の方々に自宅で介護することを考えて、どうしたら本人が楽に着替えられるか、薬を飲むことができるのか、どんなときに病院に連絡した方がいいのか、など細かに聞いておきましょう。病院によってはメディカルソーシャルワーカーという、相談員を置いていることもありますので、ざっくばらんに自宅での介護について相談してみましょう。身内の方が倒れてしまうと、気持ちが揺らぎ、なかなか先のことを考えるのが難しい状態になってしまいますが、より苦しい状態になることを防ぐためにも、病院に対する情報収集をしていただきたいものです。 「介護」ガイド:川内 潤 氏より
2007.01.22
コメント(0)
-
特養に第三者評価
認可保育所も都、公表含め義務付け 社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームや認可保育所などに対し、東京都は新年度から、第三者機関によるサービス内容のチェックとその公表を実質的に義務づける。 公表などを都の補助金支給の条件とすることで、利用者がサービス内容を比べられるようにして、施設に質向上を促すのが狙いだ。 年間の事業費や補助金額などの「経営情報」についても、定期公表させる。都によると、第三者評価の義務化は全国初という。 都では、補助対象となっている約1350か所の施設すべてで2007~08年度に「利用者からの聞き取り」調査をまず義務化し、09年度末までに提供されている食事の質や職員のマナーなどについて第三者評価を受けさせる。 また、年間の総事業費や人件費、職員数のほか、都が独自財源を充てている補助金「サービス推進費」の内訳などについても、新年度から開示を求める方針だ。 都道府県などは福祉施設への立ち入り検査権限があり、通常は実地指導や監査で運営上の問題を見つけて改善を促している。これとは別に、都では03年度から、都の外郭団体である財団法人から認証を受けたNPO法人や企業が、訪問調査や利用者の聞き取りでサービスの内容を評価する「第三者評価制度」を本格導入している。 しかし、実際に第三者評価を受けるかどうかは施設を運営する事業者の判断に任されている。このため、05年度の実績では、特別養護老人ホームでは363施設中、チェックを受けたのはほぼ半数の186か所、認可保育所でも全体の6分の1強にとどまっていた。 都内では昨年8月、東大和市の特養ホームで、職員が認知症の女性に性的な暴言を吐いていたことが明らかになるなど、社会福祉法人の管理能力が改めて問われている。施設の情報開示を進め、運営側に改善を促すことにした。 第三者評価の結果は、都の財団が運営する都福祉サービス評価推進機構のホームページで公開される。2007年1月19日 読売新聞いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」 (2006・10・04の記事) を紹介します。「第三者評価って何だろう?」 【Q】「第三者評価」と「介護サービス情報の公表」とはどう違うのですか。また、「介護サービス情報の公表」を実施すれば第三者評価を受けたことになるのでしょうか。【A】 「福祉サービス第三者評価」の目的は、利用者のサービスの選択又は事業の透明性の確保のための情報提供と、事業者のサービスの質の向上に向けた取り組みの支援という2つからなっています。一方、平成18年度から新たに開始された「介護サービス情報の公表」は利用者のサ-ビスの選択に資する情報の提供が目的となっています。 また、「福祉サービス第三者評価」は利用者の意向を把握するための「利用者調査」と、経営層及び全職員の参加による自己評価を経て評価者が多面的な視点から評価を行う「事業評価」の2つの手法を用いて実施をします。そして、その結果を利用者に公表するとともに、事業者にフィードバックすることによりサービスの質の向上に向けた取り組みの支援を行うしくみとなっています。 「介護サービス情報の公表」では、事業者が提供するサ-ビスや経営状況に関する客観的な事実について、事業者の責任において公表するものであり、その項目は「基本情報項目」と「調査情報項目」から成り立っています。そのうち、調査情報項目において事業者が「ある」とした項目について調査は行われますが、調査員は当該事実の評価を行ってはいけないこととされています。また、利用者への調査を行うことはありません。 このように、両制度は目的において一部重なっている部分はあるものの、事実のみの公表とそのような事実を前提とした上での第三者による評価という異なった性質をもっており、「介護サービス情報の公表」は「第三者評価」のプラットフォーム的な位置づけといえます。そのため、「介護サービス情報の公表」における事実の公表を実施すれば「第三者評価」を受けたことにはなるというものではなく、利用者や職員も含めた事業所の現在の状況を適切に把握し、よりよい事業所としていくためには「介護サービス情報の公表」を前提とした上での「第三者評価」を実施していただくことが必要であると言うことができます。 (福ナビ より)
2007.01.21
コメント(4)
-

昨日のデイのランチはバイキング!
昨日は、特養併設のデイでしたので、ランチはバイキングに当たりました。ランチバイキングは、特養でのショートステイも含めると、2年半で7~8回ぐらいになりましか?初めの頃は、気にしないでよそっていましたが、最近は お腹が・・・☆ 最近は、お腹が出てきたので控えめにしました! ☆★ 特養の北川ちゃんです! ★ごちそうさまでした!
2007.01.19
コメント(8)
-
災害弱者リスト作成ようやく協議 京都市と消防局 阪神大震災12年
国が自治体に作るよう求めている災害時に自力避難が困難な高齢者や障害者ら要援護者のリストについて、京都市健康福祉部と消防局は、作成に向け、ようやく協議を始めた。 阪神大震災や台風23号などの教訓として災害弱者の支援策作りが急がれるが、市は「都市では人口も多く、個別に同意を求めたり希望者を募る方式は難しい」とし、道のりは険しそうだ。 国は2004年度末、各市町村に要援護者リスト作成と避難支援プランの策定を求めた。だが個人情報保護が壁となり、防災部局と福祉部局間や、地域の自主防災組織など外部との情報共有が難しく、作成は進んでいない。 05年度の消防庁の調査では、災害時要援護者の情報を防災部局が共有する自治体は全国で約2割にとどまる。1月17日10時7分配信 京都新聞HPのつづき・・・>「弱者の情報を民生委員が知っていても、自主防災会などとの共有には守秘義務の壁がある。行政が中心となった共有の仕組みづくりが必要」と話している。確かに、色々な問題はありますよね!ただ、せめて自分の実態だけは、ご近所に把握してもらっている事が重要ですよ!
2007.01.17
コメント(2)
-
介護事業者様向け『FC事業者連携サービス』を2月1日より開始
有限会社インターネット・テクノロジー(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:笠原 正博)は、居宅介護支援事業者と居宅サービス提供事業者間の情報を連携するシステム『First Care(以下 FC)事業者連携サービス』を2007年2月1日より開始いたします。また、提供開始に先立ち、居宅介護支援事業者エリアパートナーを本日1月15日より募集。更に無料モニターキャンペーンを2007年2月1日から1ヶ月間実施いたします。詳しくはホームページをご覧ください。■『FC事業者連携サービス』とは 居宅介護支援事業者・居宅サービス提供事業者間の「提供票/別表・実績報告(提供票)」の受け渡しを、専用ソフト『FC事業者連携版ソフト』が、専用のデータセンター『FC連携センター』を介して行うサービスです。 事業者様は、今まで通り現行のソフトをお使い頂き、各ソフト間で比較的操作に独自性の少ない利用票/別表の作成、実績管理を『FC事業者連携版』ソフトで行うことにより、事業者間の「提供票/別表、実績報告」の連携が図れる様になります。07/01/16 @Press HPのつづき・・・居宅介護支援事業者・居宅サービス提供事業者間の「提供票/別表・実績報告(提供票)」の受け渡しは、結構 コスト・労力がかかるみたいですね!詳しい事業所内の仕事については分かりませんが、職員さんが事務処理を簡潔に出来るシステムならば、良いかも知れませんね!
2007.01.16
コメント(2)
-
障害者サービス利用負担、高すぎる 法施行後に舞鶴市策定委が調査
京都府舞鶴市の市障害者計画策定委員会がこのほど、市内の障害者を対象に福祉施策の改善要望などを聞くアンケートを行い、結果をまとめた。障害者自立支援法施行後のサービス利用負担の収入に占める割合についての質問では、「収入の7-8割に相当」とした人が25%を超え、「ほぼ同じ」「超える」とした人も合わせて17%に上った。 同委員会は、市の来年度から10年間の「市障害者計画」と、同支援法に伴うサービスのあり方を決める「市障害者福祉計画」策定のために設置。昨年11月中旬から、アンケートを約1000人に協力を求めて実施し、415人が回答した。 同支援法施行後の利用者負担については4問あり、全回答者のうち約220人が回答。収入に占める割合では「1-3割」とした人が48・6%と最多、「7-8割」が25・9%、「収入を超える」が11・3%と続いた。負担感については「高過ぎる」が52・3%を占め、今後のサービス利用意向では「今の利用を継続したい」が72・1%と多く、「利用を止めたい」「減らしたい」は合わせて19・4%だった。 自由記入の欄には「1カ月の収入が2000円なのに負担額が2万円近い」「これからの福祉を考えると、不安で長生きしたくない」などと悲痛な声を書き込む人もいた。 同委員会はアンケート結果を踏まえ、本年度中に両計画案をまとめる。 同支援法は、通所施設や生活支援などの福祉サービス利用に対して、以前の所得に応じた応能負担から、応益負担に切り替えて利用料の原則1割負担を求め、全国の障害者から負担の重さを訴える声が上がっている。07/01/13 京都新聞これは、障害者でも完全に自立生活している人と、家族などからの支援を受けている人との違いかも知れませんが、このように、障害者でも色々な立場の方がおられます。それを、一まとめの施策で済ませようとする、国の考え方にも無理があると思いますね!介護保険においても、色々な年齢、立場、目的もある訳ですから、それに見合った介護保険というものが、今後は求められて来ると思いますよ!“障害者の負担上限引き下げ”の記事
2007.01.15
コメント(0)
-
山間の左京・久多「福祉受ける意識薄い」 佛大生、2週間泊まり調査
過疎、高齢化が進む京都市左京区北部の久多地区の福祉の現状を佛教大(北区)の学生らがまとめ、13日、現地で地元住民を対象に報告会を開く。 2週間にわたる実地研修をもとに、福祉サービスを受ける意識の欠如や情報不足などを指摘している。 社会福祉士の資格取得を目指す社会福祉学部の学生が5年前から、地域福祉実習として実施。介護保険の民間業者があまり参入していない左京区北部の中山間地域で調査している。HPのつづき・・・1月12日11時27分配信 京都新聞>「保険料を払っているのにサービスを受けられないし、受けるという意識が住民に欠けていた。介護保険の事ばかりではありませんが、やはり地域格差の縮小は、これからの高齢化社会にとっては、最も重要課題ですね!
2007.01.12
コメント(0)
-
[解説]介護用ベッド利用制限
判断基準実態と隔たり 欠かせぬ適切な供給システム 介護保険制度改正で、要介護度の低い高齢者が介護用ベッドを利用できなくなって3か月が過ぎた。一律的な利用制限には問題がある。 モーターでベッドの上半身部分を起こすことができる介護用ベッドは、起きあがりを楽にするだけでなく、介護する人の負担も減らせる。費用の1割を払えば要介護度にかかわらず介護保険でレンタル給付されたが、昨年4月の改正で、「要支援1」「要支援2」「要介護1」の軽度の人は原則、利用できなくなった。経過措置を経て昨年10月から本格実施されている。 国が利用制限に踏み切った背景には、介護費用の急激な増加がある。ベッドや車いすを含む福祉用具レンタルの総費用は、2001年4月に40・2億円だったが、昨年4月には4倍近い152・9億円に急増した。介護用ベッドは付属品も含めれば、その約6割を占める「人気商品」だ。ベッドの利用者をみると、約4割を軽度者で占めている。 安易な利用が費用の無駄を生み、高齢者の自立を妨げてきたとの指摘も介護現場にはあった。ベッドはケアマネジャーが必要と判断すれば借りられるが、「楽だから」という理由で安易に使用を勧めるケースもあった。都内の事業者が軽度の利用者約300人の利用状況を調べたところ、約半数がベッドの電源を入れずに使っていた。(2007年1月11日 読売新聞)HPのつづき・・・福祉用具については、ケアマネージャーでもあり、福祉用具のプロでもあるマリリンたちのパパさんに問い合わせてみて下さい。マリリンたちのパパさんのブログを紹介します。
2007.01.11
コメント(4)
-
移送サービス ~定年後は福祉ドライバー~
障害者や体の不自由な高齢者を車で移送するボランティア活動に、定年退職後の世代が積極的に参加している。移送ボランティアは昨年10月施行の改正道路運送法で正式に位置付けられるなど、重要性が高まりつつある。貴重な戦力 午前9時、東京都葛飾区。男子高校生(16)の自宅前に、車いす専用の福祉車両「ふれあい号」が到着した。運転する岩沢俊夫さん(61)がリフトを操作し、高校生を車いすごと車に乗せる。付き添いの母親(47)も同乗し、約13キロ離れた病院に向かった。 ふれあい号は、同区社会福祉協議会が1986年から実施しているボランティアによる移送サービス。対象は、車いすや特殊寝台の利用者だ。1週間前までに予約が必要だが、費用はガソリン代などの実費負担だけ。区民約90人が登録し、月約60件の利用がある。HPのつづき・・・を紹介します。2007年1月10日 読売新聞私も2年前までは、地域の社会福祉協議会より「移送サービス」を受けていました。しかし サービスは打ち切りになり、現在はタクシーで往復\7,000ぐらい払っています。以前は、直線距離で18kmで\1,300の負担ですみましたがね!多分 今年4月の介護報酬改定では、高齢者や障害者が通院に利用する移送サービスについて、その介護報酬の給付範囲を明確にするために、「乗車・降車の介助」という新しい介護報酬を設定して、1回1,000円(運賃は給付対象外)と決められた。 同時に、移送サービスの前後に介護事業者が身体介護を30分以上行った場合には、移送を含めた一連の行為に対して、より単価の高い身体介護の報酬(30分以上1時間未満で4,020円)を請求できるとした。(その場合は運転時間分の報酬は請求できない。)という報酬のもとではないかと思われます。 「全国介護移送協会」事務局長の山下勝久氏は、「移送サービスでもっとも大切なサービス受益者のことを考えると、安全が確保され、しかも介護に関わるNPOやボランティア団体が参入可能な、きちんとした法整備が必要。 これまで、国土交通省と厚生労働省の見解の相違から、介護タクシー業者とNPOが相対する立場に置かれていたが、今後は連携して受益者本位の移送サービスの実現と普及に取り組んでいきたい。」だそうです!
2007.01.11
コメント(2)
-
高齢者を見守る ~ご近所さんと笑顔の輪~
家族や地域のつながりが薄れ、新たな支え合いの仕組みが求められている。公的サービスには限界があり、ボランティアの役割が重みを増している。特に、時間にゆとりのあるシニア世代への期待は大きい。今月のテーマは「社会貢献」。シニアが活躍する取り組みを紹介する。高齢者が孤独死して3日間発見されなかった事件がきっかけだった。「家族や地域のつながりが薄れたことが、事件の背景にある。新たに『近隣の助け合い』のネットワークを作る必要があると考えました」と、社協の榊原昭二会長は説明する。 32人のボランティアの大半が、見守り対象者と同世代。ボランティアは、見守り対象者と付き合いのある人に、社協から依頼する。日ごろの交流の延長で活動すれば、お互いに負担にならないからだ。 これまでに、急病で倒れた高齢者を発見して救急車を呼ぶなどした例が数件ある。「ボランティアの活動を通じて、高齢者を気にかけ、支える意識を地域に根付かせたい」と、榊原会長は話す。(2007年1月9日 読売新聞)HPのつづき・・・サービス内では、介護保険でプロの介護を受ける事は言うまでもありませんが、それに伴い『近隣の助け合い』を作る事は、これからはより不可欠な時代になりますよね!
2007.01.10
コメント(6)
-
踏み台昇降 医療費半減 ニコニコペース健康法実証 お年寄り200人 福大チーム調査 1年間毎日3回で効果
踏み台をのぼりおりするだけの「ニコニコペース」という有酸素運動を続けたお年寄りは、運動をしない人に比べて1年後の医療費が半減する-。 こんな実証実験の結果を、福岡大の田中宏暁・スポーツ科学部教授(運動生理学)と白鞘(しらさや)康嗣・経済学部助教授(医療経済学)の研究チームが明らかにした。 高齢社会が進み医療費抑制をもくろむ介護予防プログラムに注目が集まるなか、研究チームは近く、この成果を学会で発表する。 ニコニコペース運動とは、生活習慣病の予防を目的に、田中教授の研究室が30年ほど前から提唱する健康法。ピアノ演奏やCDの音楽に合わせて、高さ15センチほどの踏み台を昇降するだけの簡単なステップ運動だ。 筋力トレーニングなどの激しい運動に無理して励むより、ウオーキングやランニングなど身体への負荷の軽い有酸素運動を継続することが、心臓病や高脂血症などの生活習慣病予防に効果があることは以前から注目されていた。 田中教授はニコニコペース運動を、九州を中心に各地の自治体や高齢者サークルなどに紹介し、普及に努めてきた。 今回の実証実験は2003年6月から04年11月まで、石川県能美市(旧根上町)の65歳以上の男女200人を対象に実施。うち100人は、1回十分間の踏み台昇降運動を1日3回、週に計140分間の目標で取り組み、特に運動をしない残りの100人と、半年ごとの平均医療費や通院日数などを比較した。 その結果、運動を続けたグループは、当初半年間の1人当たりの平均総医療費が約28万2900円、翌年同時期では約15万8500円と4割以上減少。 一方、運動をしなかった群は、約27万600円から約25万4500円とほぼ変わらなかった。 さらに、平均外来通院日数も、非運動集団では23・75日から24・03日とほとんど変化がなかったのに対し、運動集団は22・58日から17・87日に減った。 介護保険制度は06年4月の法改正で介護予防に重点が置かれるようになったが、どんな運動が効果的なのか各自治体は手探りの状況が続いている。 田中教授は「ニコニコペースが総合的に運動能力を高め、医療費が具体的に抑えられることが実証できた。追跡調査を続け、さらに効果を見極めたい」と話している。=2007/01/09付 西日本新聞夕刊=
2007.01.09
コメント(2)
-
ファミリーマート 店長ら介護資格を取得へ 福祉サービス拠点に
コンビニエンスストア業界3位のファミリーマートは7日、社員や店長に介護関連の資格を取得させ、店舗を福祉サービス拠点として活用する構想を明らかにした。手始めに商品の宅配制度を導入。将来的には、配達先のお年寄りらの安否確認や世話をする“福祉コンビニ”の実現を目指す。コンビニ業界は消費動向の変化や店舗増加で既存店の売り上げ低迷が続いており、各社とも若い女性や主婦、高齢者など客層を絞り込んだ新業態店展開による活性化を模索している。 同社は高齢化社会に対応したサービスを柱にすることで競争力向上を狙う。1月8日8時0分配信 産経新聞HPのつづき・・・>手始めに商品の宅配制度を導入。>将来的には、配達先のお年寄りらの安否確認や世話をする“福祉コンビニ”の実現を目指す。「ご用聞きサービス」は、すでにセブンイレブンで行われていますが、>配達先のお年寄りらの安否確認や世話をする“福祉コンビニ”の実現を目指す。これは、やはり時代の流れなのでしょうね!以前は、サービス業となるものは、「健常の人、若い人」をターゲットにしていたかも知れませんねー。私もたまたま、今週中に友人と食事に出かける事になりましたが、最近は、バリアフリーのお店も多くなりましたが、まだまだそうでもないお店も多い為、Yahoo!のグルメページを開き、電話して確認してみました。もちろん、バリアフリーのお店というのは、数少ない事も把握しています。トイレも車椅子では入れない事もです。 だけど、未だに和式というお店もありました。何が言いたいかと申しますと、ハード(建物)の問題については、「高齢者・障害者」という聞きなれた言葉で、誰でもわかるでしょう。でも「福祉」というものは、言葉だけではなく、経験があってこそ生まれて来る言葉だと思います。例えば、高齢者では膝が痛くて歩けないとか、障害者では片マヒで片手のみの飲食とか、下肢マヒで車椅子使用とか、状態・症状は人によって様々です。それぞれに合ったサービスを受ける事は、受身であった、且つ肩身の狭い障害者にとっては朗報ですね!そう言った事を お店の方にも理解してもらえる事は、より外出しやすい社会を作り出す、良いきっかけになると思いますがね!
2007.01.08
コメント(6)
-

フォト特集!(ギャル編:一部除く)
お正月は、新聞も介護ニュースもなく日記を更新していませんでしたが、今日も良いブログネタが見つかりませんでしたので、昨年撮ったギャル(一部除く)をまとめてみましたので、それで今日の日記として勘弁下さい。フォトはフォト管理に登録済みなので、あとはコピーするだけですので、私も楽です!コメントは付けていませんが、以前の日記を参照して下さい。では、ご覧下さい。今年は、昨年以上に写真(特にギャル)を撮りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくです!また、盗撮もよろしくで~す!
2007.01.05
コメント(9)
-
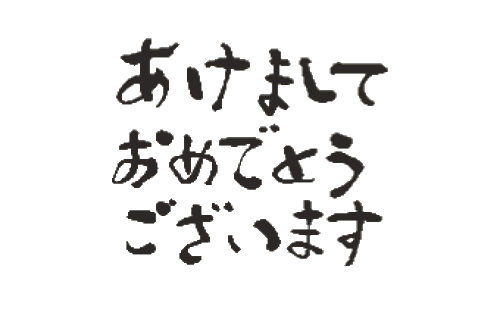
新年あけましておめでとうございます!
今年もよろしくお願い申し上げます。
2007.01.01
コメント(8)
全19件 (19件中 1-19件目)
1










