1.≪忍ぶ川≫2.≪サンダ館八番娼館≫
1.≪忍ぶ川≫
2. ≪サンダ館八番商館。。望郷。。≫
ーーーーーーーーーーーーー
1.《忍ぶ川》
早稲田大学に通う学生哲郎と上野谷中に近い山の手にある
学生寮の近くの
”忍ぶ川”という小料理屋で働いている志乃という娘の
恋物語である.
しかし二人の恋愛が本筋ではあるが、
単なる恋愛映画ではなく、日本のまた人間の
心のふるさとへの潜在的思慕を描いた秀逸な作品である。
≪忍ぶ川≫
東宝設立40周年記念作品.
にもかかわらず、モノクロでもあり映画の斜陽を
感じ始める時代の地味な作品.
だが、見応えのある熊井 啓監督作品である。
哲郎は学生寮の近くにある小料理屋忍ぶ川で働いている
志乃とお店で知り合ったことから急速に親しみをましてゆく.
ある休日に二人は深川へ行く。
そこは二人にとって共通の思い出の場所であった。
まず行った木場は哲郎の兄が働いていて、月に一度学費を
貰いに行っていた.
がその兄が親戚達からお金を借りるだけ借りまくって行方を
くらましたことから哲郎一家の運命が狂ってしまった。
借金騒ぎの件で
秋田の田舎に住む哲郎一家の長兄と次姉は
そのことがきっかけで自殺する。
遺された父と母と一番下の目の悪い姉の三人は
旧い暗い家の中で息を殺してひっそりと暮らしていて
頼り、希望は哲郎だけという重いものを背負った哲郎の
これからの人生は厳しそうだ.
一方志乃は洲崎遊郭の中で育った。
父はインテリであったが射的屋の娘に熱をあげそこに入り込んで
しまい、志乃が生まれてからも一生を遊戯場のオヤジで終わった.
父はその後栃木の村へ疎開したが、古寺のお堂に棲みついて
志乃の仕送りと弟の働きでほそぼそと余生を送っていた。
志乃も哲郎も正直に洗いざらいを話し合った。
そんな境遇が二人の心をいっそう深く強く結び付けひとつの
運命というか共通の運命の糸に繋がったような
気がしたのである。
志乃の縁談話やいろいろあるなかで、志乃の父が危篤になり
志乃は哲郎に父の死の前に逢って欲しいと一緒に栃木へ行く。
父の死後、志乃は哲郎の元へ嫁ぐ.
冷たい目を浴びせていた姉も次第に打ち解けて行った.
一家五人だけの結婚式であった。
初夜の晩も秋田は深い雪で冷えた。
秋田では夜、寝床に入るのは素っ裸だそうである。
その方が温かいというその地方の風習であった.
二人の運命がひとつに重なる...
がそれは二人がやっと安らぎの場を
見つけた夜に他ならなかった。
このシーンは当時センセーショナルであったが、これほど
美しく感動的に描かれたシーンはそれまでになかったものだ。
これは単に二人が結びついたというものではなく、
ただの愛の証だという単純なものではなく、
終に辿りついた魂の棲みかであったのだと思う。
不幸といえば不幸な身の上で落ち着く場所のない二人であったが
秋田のこの土地、風土への回帰であった.
重い鬱積したものを抱えた二人が安らぐ
雪のふるさとへの回帰が、全てが このシーンに
凝縮されていたように思えてならない。
製作 東宝 1972年度作
監督 熊井 啓
原作 三浦哲郎
主演 加藤 剛/栗原小巻/岩崎加根子
ーーーーーーーーーーーーーー
2、≪サンダカン八番娼館---望郷≫
今朝、1:00頃か、ふと、T.Vのスイッチを入れた。
B.Sで映画”サンダカン八番娼館-”望郷ー”は、
始まろうとしていた。
一瞬 ああー懐かしい」あの映画ー
私が」青春時代に、カルチャーショックをうけたあの...
(山崎朋子)さん原作のあの映画だった。
んん十年ぶりだろうか...?
当時、古代史に魅せられ、奈良や、滋賀を
めぐり廻っていた。
あるきっかけで、福岡は 太刀洗という町に
美しい教会があるというのを聞きつけ、早速カメラ片手に
訪ねた。
それは、見事な建物であった。赤いレンガ作りの
荘厳な浦上天主堂をしのぐかと思うほどにものであった。
そのころまだ、デイスカバージャパンという
流行語の流行るちょっと前で、こんな田舎に観光客など
いなかった。
ステンドグラスは、黒光りのする床に、多彩な彩りを
バラまいていて、息を呑むほどであった。
その教会に、私はいつものごとく、
忘れ物を残して帰った。
後日 神父様が、その忘れ物の手帳に美しいご本を
添えて送り返して下さった。
それはまだ、当時世間にそれ程知られていない
長崎県と熊本県に点在する美しい教会建造物を
紹介している貴重とも言える本であった。
それから、毎土曜日私と母の教会巡りの旅は、始まった。
巡るたびの中で行き会った熊本は 天草下島南端に位置する
”埼津”という町にある石造建築の教会だった。
ひなびたこの漁師町の真中にそびえ立つ教会。
何だ。。これは..表現は悪いが、生気なく見える
この町にこんなりっぱな教会が..そぐわない..
中に入ると正直、カビくさい印象を受けた。
それからも、私と母の教会巡りの旅は、2年ほど続いた。
そしてその後、たまたま本屋で、手に取ったのが、
この”サンダカン..”であった。
もう忘れたが,確か当時の芥川だか、直木賞だかであったと
思う。
この本の内容は、私にとってショックでした。
情報も溢れ、少々のことに感動も驚きも薄らいだ今と
違い、その頃の私には、若さと無知とで、
打ちのめされたことを記憶している。
それは、貧しさゆえに
遥かボルネオのサンダカンという街に、14.5歳で
娼妓として売られて行った少女 さきさんという からゆきさんを
取材する山崎さんのノンフイクションものであった。
生きてこの埼津に戻ったものの、近所から、身を
隠すように
また、子供達にも置き去りにされ 今だ町から離れた
山の中で、想像も出来ないような生活をしている事実が
そこにはあった。
おそらく、このさきさんというおばあさんの 他にも
おられたと思う。前に見たあの光景は、
隠れキリシタンという歴史と、からゆきさんを
送り出したということからくる、町のたたずまいであったのか
すぐに、もう一度訪ねてみたくなり
再度母と二人その地に足を、踏み入れた時
何故か涙が、溢れてとまらなかったことが、
この映画を観ながら、一気に甦り、
また、今朝も眠れなかった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ドラマ大好き
- 『秘密 ~THE TOP SECRET~』【ドラ…
- (2025-11-18 14:13:37)
-
-
-

- 宝塚好きな人いませんか?
- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…
- (2025-11-12 05:30:05)
-
-
-
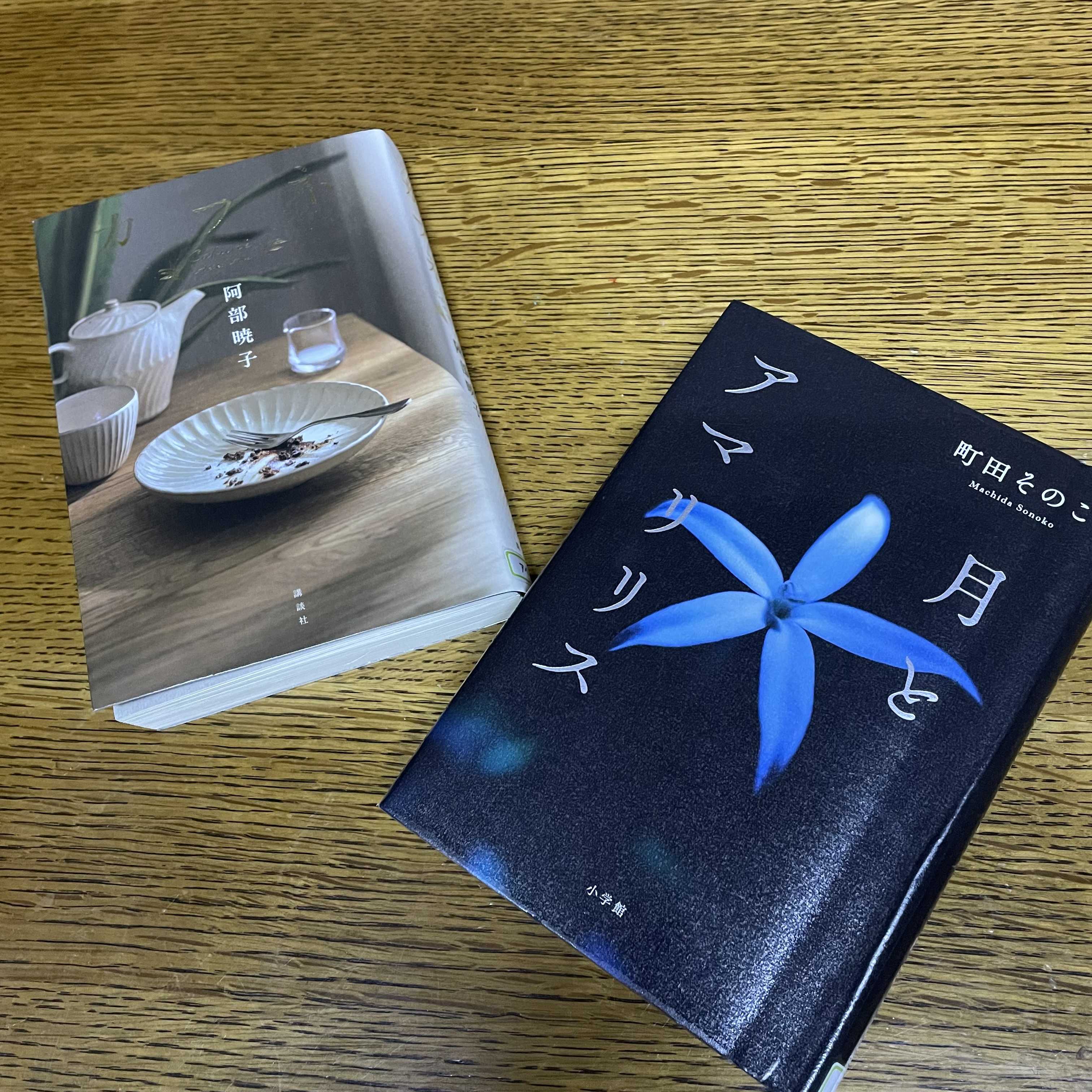
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-
© Rakuten Group, Inc.



