Halloween・Cat 2 中篇
「あの、さっきブラウンさんにご都合を伺おうと思ったのですが、何度ノックしてもお返事がなくて…。お車もありますし、お出かけの様子はないのですが」
サムがちらっと内ポケットの俺を見た。どういうことだ。外出していないのに、ノックに反応がないって?
「とりあえず、ブラウンさんのお部屋まで案内してもらえますか」
サムはそう言ってアンに道案内を頼んだ。天井の高い廊下をコツコツと靴音が響く。随分古い作りだが、がっちりと重厚な感じの建物だ。こういった建物には、古くから隠し扉や一般には公表していない地下室なんかがあるもんだが、ここはどうだろう。
「ブラウンさんのお部屋はこちらです」
アンはそういうと、すぐさまドアをノックした。しかし、やはりブラウン氏の返答はなかった。
「もしかして、中で具合が悪くなってらっしゃるんじゃありませんか」
サムが心配そうに囁くと、アンは急に不安になったのか、思い切ってドアを押し開けようとしたが、中から鍵がかかっているらしく、ドアはびくともしなかった。
「ブラウンさん、大丈夫かしら・・・。あっ、そうだわ」
アンは突然何かを思い出し、今来た廊下を駆けていった。そして、なにやらカギの束を持って戻ってきた。後からチャーリーも追いかけてきた。
「ブラウンさんの様子がおかしいんですって?」
チャーリーは心配そうにこちらに質問を投げかけたが、サムと俺は逆に面食らってしまった。
「返事がないんです。でも中から鍵が掛かっていて…。と、とにかくあけてみますね」
アンはそういいながらすでにカギを差し込んでドアを開いていた。
中に倒れているであろうブラウン氏を助けようと、チャーリーとアンが奥へと駆け込んだが、部屋の中には誰も居なかった。
サムが遠慮気味に部屋に踏み込むと、俺もそそくさとその後に続いた。
古い建物だが、重厚な家具がとてもしっくりと馴染んでいた。ドアを入って正面にメインディスクがあり、右手にはソファ、左手には背の高い本棚があった。品のいいレースのカーテンの向こうには華やかな春の草花が咲き乱れているのが見える。
チャーリーが室内を一回りして確かめたが、変わった様子もなかったので、とりあえずそこにいたみんなは外に出ようとしていた。
サムの後に続いて廊下に向かっていた俺は、ソファの下に何かが光っているのが見えた。カフスボタンだった。
前足を使ってじゃれるように転がしてサムに声をかけた。
「なんだ、グレン? こんなのが落ちてたのか?」
サムはしゃがみこんでカフスボタンを拾い上げると、デスクの端に置きなおした。
「さ、みんな外に出よう。ブラウンさんはきっと、他の用事に出かけているんだろう。勝手に部屋に入ってしまって、申し訳なかったね」
サムの言葉にアンが何か申し訳なさそうに言い訳しようとしたとき、その後ろで気配がした。ブラウン氏だった。
「君たち、どういうつもりで他人の部屋に入っているんだ!」
静かだが、圧倒的な威厳をもった声だった。アンが申し訳ありませんと事情を説明したが、ブラウン氏の機嫌はなかなか治らなかった。
「いや、本当に申し訳ありませんでした。しかし、ブラウンさんの身になにかあったのではと、心配していたのです。どうかお許しを」
サムが間に入って言うと、改めてじっとサムを凝視したブラウン氏が尋ねた。
「あなたは?」
サムは一通りの自己紹介をしたが、ブラウン氏は子どものけんかに親が口を挟むなんてと呆れたようにつぶやくと、そのまま自分の部屋に入ってしまおうとしていた。
「あ、ちょっと言い忘れてたんですが。ブラウンさん、変わったカフスボタンが落ちてましたよ。デスクにおいておきました」
サムがさりげなくそう言いながらブラウン氏の後姿を見送った。ブラウン氏がカフスボタンのことを聞いたとたん、落ち着きを失ったのは俺の目にもわかった。
「では、私はこれで。親御さんがいらっしゃらないのであれば、ご相談のしようもありませんのでね。しかし、リサさんは寂しいでしょうねぇ。娘にはその辺りの事情を話して、そっとしておくように話しておきます」
誰に言うともなくサムはそういうと、さっさと屋敷を出た。申し訳なさそうに後からついて来ようとするアンを、ブラウン氏が呼びとめ自分の部屋に入るように言ったが、サムはまるで気づかない振りで自分の車に乗り込むと、さきのコーヒー専門店の傍まで来て車を止めた。
どうやら盗聴器を仕掛けてきたようだ。サムは慌てて機械を操作し、音声がきれいに受信できるように調整した。
「すみませんっ!!」
「すみませんで済む問題ではないぞ!リサお嬢様の事を心配するのはいいが、赤の他人を屋敷に入れるとはどういうことだ。私はアイスマン家の執事なんだぞ。この部屋にはご主人様のビジネスに関する書類もたくさんあるのだ。外部に漏れるようなことがあれば、ご主人様に迷惑が掛かるやもしれんのだ!」
小さな嗚咽が聞こえていた。アンが叱られて泣いているのがわかった。
「可哀想に…」
サムは心配そうに聞きながら、車を出した。とにかくこの地域から出てしまわなくては怪しまれるのだ。
「申し訳ありません。でも、リサお嬢様のことが心配で。メアリーさんもいなくなってしまったし、リサお嬢様もあの日以来こちらにお戻りではないようですし」
「あー、うるさい。リサお嬢様もお年頃なんだ。自由に活動したい年頃なんだろう。その内飽きられてご自宅に戻ってこられるに決まっているのだ。メアリーはリサお嬢様には厳しすぎたのだろう。亡くなった奥様でさえ、メアリーの厳しさには眉をひそめておいでだったのだ。とにかく、お前はリサお嬢様がお帰りになった時、不自由なく過ごせるように万事抜かりないよう整えておくのだ。いいな」
「はい。わかりました。では、失礼します」
ドアを開ける気配がした。アンが部屋を出るのだろう。
「ああ、アン。私はこれからちょっと仕事があるので、用事は夕方から受け付ける。それまでは邪魔をしないでくれたまえ」
「はい。分かりました。では失礼します」
バタンッとドアが閉まって、ブラウン氏の深いため息が聞こえた。
「あぁ。なんだかアンに悪い事しちまったなぁ」
サムが堪らなくなって言ったが、俺にはその先のことが気になった。
「シッ! ちょっと待って!」
俺が叫ぶのと同時に、ブラウン氏のディスクの電話が鳴った。
「どうした。こちらには電話するなと言ってあっただろう」
サムと俺は一瞬言葉を失った。さっきまでのブラウン氏とはまるで別人のような口調なのだ。
「そうか、それはご苦労。ん、1万ドルぐらいになればいいだろう。欲を出すな。その辺りで手を打て。わかったな。…小娘?おい、ショーン!その小娘の名前は? ん~、分かった」
俺とサムは大きく頷きあった。やっぱりショーンたちには糸を引いている人間がいたのだ。しかしまさかそれがリサの家の執事だったとは、想像すらしていなかったことだ。
「帰ったらすぐ、ブラウン氏の過去も洗い出す必要がありそうだな」
サムはハンドルを強く握りながらつぶやいた。だが、そんなに簡単にわかるだろうか。
アイスマンとて、そう簡単に執事を雇ったりはしないだろう。それなりに調べ上げたはずだ。ブラウンという名前だって偽名の可能性もある。
その後は、書類のこすれる音やキーボードを叩く音がしているだけだった。ブラウン氏もアイスマン家の執事としての仕事はちゃんとこなしているのだろう。
その日の夜、思いがけない連絡が来た。ロイドの展示会が大成功して、新ブランドを担当する事に決定したという。マージーは自分のことのように興奮していて、電話口にいない俺でさえ、電話の内容が手に取るように分かった。
しかし、ロイドの方が落ち着いているという事は、キールとかいうインナー部門の連中は面白くないはずだ。キールとショーンが、もし繋がっているとしたら、何も仕掛けてこないとも限らない。ここは警戒が必要だろう。
俺は、すかさずキーボードに打ち込み、サムに代弁してもらった。マージーは納得した様子で、マリアやロイドにはよく話してみると答えていた。
次の週、俺は再び公園のベンチに居た。アンからの情報を得るためだった。しばらくすると、手芸屋のチェックがやってきた。
「なんだ、今日はグレンもネコスナック狙いか?」
「いやいや、そういうわけじゃないよ。もうすぐ来客かい?」
ベンチに上がってきたチェックは片目をつぶってにやりと笑った。俺はそんなチェックに場所を譲ってベンチを降りた。
「お前もご馳走になればいいじゃないか」
チェックが気を使ってくれたが、俺が欲しいのはネコスナックではない。
「気にしないでくれ。俺は今日はのんびりできればいいんだ」
そんな話をしていると、道路の方からアンが歩いてくるのが見え、さっさとベンチの後ろに退いた。アンは先日と同じく元気の無い様子で、バスケットと水筒を抱えてやってきた。
「こんにちわ、ネコ君。今日も付き合ってね」
アンはそういうと、先週と同じくベンチに腰掛けてバスケットからネコスナックを探し出してチェックに与えた。そして、またつらつらと、ささやかなグチをこぼしてみたり、チェックを抱き上げて遊んでみたりして過ごした。
「ねえ、ネコ君。私ね、ちょっと気になる事があるのよ。実はこの前ね、お嬢様のお友達のお父様がお見えになって、ブラウンさんのお部屋に入ったんだけど、ブラウンさんのお部屋の背の高い本棚が、ちょっと変だったの。
詳しくは分からないんだけど、動かしたような傷が床についていたのよねぇ。でもあんな背の高い本棚、簡単に運ぶことはできないし、おかしいわよねぇ。もしかして、お隣のご主人のお部屋への秘密の通路だったりして! あは。そんなことはないか」
アンはちょっとおどけたように笑ってみたが、心の底からの笑顔ではなかった。アンには辛い状況だが仕方ない。しかし、本棚には気づかなかったなぁ。あの時、俺はソファのカフスに気をとられて本棚のそばまで足を踏み入れてはいなかったのか。
チャンスがあれば、もう一度調べてみたい場所だな。
「それにしても、リサお嬢さんはどこでどうしていらっしゃるんだろう。。。」
すっきりと晴れたきれいな青空を仰いで、アンは大きなため息をついた。確かにリサの居所も気になるが、俺としては、なぜこんなに頼りなげなアンが採用されたのかも不思議だった。
いつものようにしばらくはぶつぶつと自分の不運を嘆いていたアンだったが、雲行きが怪しくなってきたのに追い立てられるように、早めに引き上げて行った。
チェックは、まだちょっと物足りなそうな顔をしながら、のろのろと家に帰っていった。オヤジ、家でもちゃんと食べてるんだろ? 老いてから太るとろくなことがないぜ。
俺がサムの家に戻ると、珍しくクレアより先にサムが出迎えてくれた。何かつかんだのか、サムは妙ににやけて俺に早く2階に来いと合図をよこした。
「グレン、驚くなよ。。 とうとうメアリーとコンタクトが取れたんだ。例のコーヒー専門店に、メアリー自身も客として登録していたらしい、頼み込んで教えてもらったんだ。」
サムはもう地面から数センチは浮かんで状態で、はしゃいでいた。確かにサムが喜ぶのも分かる。メアリーから直接詳細を聞き出せたら、こんなに楽なことはないのだから。
夜になって、俺はサムと一緒にメアリーの自宅に招かれた。小ぶりではあるが、きれいに整った家は、アットホームな和やかな空気に包まれていた。
「初めまして、サムと申します。実はリサさんのことで、教えていただきたくて…」
メアリーは前もってサムから用件を聞いていたのか、リサの変貌振りについて、丁寧に話し出した。
「紅茶でもどうぞ。私の知る限りのことをお話しましょう。あ、貴方がグレンね。ミルクはいかが?
リサお嬢さんは、とても素直でお優しいお子さんでした。ご主人のアイスマン氏はとても頑固なところがあって怖そうに見えるのですが、実際は仕事熱心なだけなんだと思っています。奥様もお優しい方でしたし、リサお嬢さんは充分に愛情を受け取って幸せに暮らしてらしたのです」
サムは持ち上げたカップをもう一度テーブルに戻して不思議そうに尋ねた。
「あの、無理やりやめさせられたってうかがったんですが、恨んでらっしゃらないんですか」
「うらむだなんて…。確かに突然の解雇には納得がいきませんが、私にはわかるんです。リサお嬢さんが突然解雇を言い渡されたのにはきっと理由があるんじゃないかって…」
メアリーは解雇そのものより、それを言わしめた原因に注目しているようだった。
「そうだわ!貴方は探偵さんだったんですよね。じゃあ、それを是非調べていただきたいわ。
リサお嬢さんのためにも、ジョンソンさんのためにも」
「わかりました。では、解雇の日の出来事を教えていただきますか」
メアリーはその日を思い出しているのか、じっと目を閉じて考えた。そして、おもむろに目を開けて、話し出した。
「私は、元々奥様のメイドとして、ご実家でお世話になっていたのです。まだ駆け出しのメイドで失敗も多く、奥様に助けていただく事も多かったです。その奥様がアイスマン家に嫁がれるということになって、私もご一緒することになりました。
その頃は、まだご主人様のお仕事も、そんなにお忙しいというほどでもなく、ご家庭は円満でした。
やがて、リサお嬢さまがお生まれになって、私はリサお嬢さんのお世話をするようになったのです。お嬢さんはとても愛らしいお子さんで、素直にやさしい女の子に育ってくださいました。
それが、奥様が急にお体を悪くなさって、リサお嬢さんも随分心配していらしたのです。あれはいつごろだったかしら。チャーリーさんがあのお屋敷に働きにきた後だったと思うんだけど。。 そう、前の料理人のリーさんご夫妻はとてもいい方々だったのですが、ご不幸にもご自宅が火事に見舞われて、母国にお帰りになったのです。それでチャーリーさんがこちらに来られたんだったわ。あれは、3年ぐらい前かしら。
奥様が床に伏せていらっしゃる間、リサお嬢さんは少し塞ぎこんだご様子でした。それがあまりにも哀れで、私たち…、あのジョンソンさんと私で相談して、小旅行にお連れしたこともあったんです。」
「お二人で、お嬢さんを?」
サムは遠慮のない質問をぶつけていた。
メアリーは、はっとして、顔を赤らめてつぶやいた。
「その頃、私とジョンソンさんはささやかながらお付き合いを始めておりました。いづれ結婚しようと約束していたのです。こんな形で実現するとは思いませんでしたが」
理解できずにいる俺たちに、メアリーはそっと隣のドアをノックした。しばらくすると、きゅっとタイヤのような音がして、車椅子に乗ったジョンソン氏がやってきた。
「あの日のケガで、彼は下半身の麻痺と言葉の障害を追ってしまいました。でも、彼もお嬢さんのことをうらんではいないそうです」
サムは慌てて立ち上がり、ジョンソン氏と握手した。横で見ていても、彼がしっかりと意識を取り戻しているのがわかる。
ジョンソン氏は、画用紙にすらすらと何かを書き始めた。みんなはその作業が終わるのをじっと待ち、そしてうなづいた。
『ようこそ。私はリサお嬢さんの背後にいる何かを突き止めていただきたい。あのお嬢さんは操られているとしか思えない。ブラウン氏が来て以来、アイスマン家は雰囲気が変わってしまった。』
突然、ジョンソン氏は頭を抱えた。メアリーは急いでジョンソン氏を隣の部屋に連れて行った。サムが手を貸して、ジョンソン氏は隣の部屋にあるベッドに移され、落ち着きを取り戻したようだ。
「ジョンソンさん、私でよければお手伝いさせていただきます。今は無理をしないで、安静にしていてください。」
サムの言葉にジョンソン氏は深くうなづいた。
再びもとの席に戻って、新しい紅茶を入れると、メアリーは話を続けた。
「とにかく、私たちはお嬢さんが元気を取り戻してくれる方法はないかと、よくそんな相談をしていました。
そんなある日、お嬢さんが学校の宿題で親御さんのお仕事をレポートすることになったとおっしゃいました。
私たちはもちろん、ご主人様がお帰りになるまでお待ちいただくように止めていたのです。ご主人様はその頃、お仕事で他国に買い付けにおいででした。3日後にはお戻りになると分かっておりましたし、ご主人の許可なしに、勝手にお部屋にお入りいただくことはできませんでした。
ご主人様は貿易のお仕事をなさっておいでで、もちろん、やりとりの殆どはご主人様の会社の方で全部やってしまわれるようでしたが、取引上のお付き合いなどで夜昼構わずお仕事なさっているので、合間に仮眠をおとりのようでした。ですから、ご主人様のお部屋には誰も行かないようにといわれていたのです。」
そこまで一気に話すと、メアリーは紅茶を一口飲み下し、続けた。
「ご主人様のカギは、ブラウンさんとジョンソンさんが持っていたのですが、どういうわけか、リサさんは別にもうひとつカギをお持ちだったようです。ご主人様のお部屋を出られたリサお嬢さんと、ちょうど廊下で鉢合わせになったんですが、とても顔色がお悪くて驚きました。声をおかけしたのですが、そのままご自分のお部屋に駆け込んでしまわれたのです。」
メアリーは、そのときのことを思い出したのか、深い溜息をついた。サムは、そんなことなどお構いなしで質問に入った。
「他に、その時気づいたこととかないですかねぇ。」
メアリーはじっと考えをめぐらしていたが、意を決したように顔を上げた
「実は、ブラウンさんのことなんですが。。。
ブラウンさんがアイスマン家に来るまで、ジョンソンさんはアイスマン家の執事として仕事をこなしていました。ご主人様の信頼も厚く、間柄は安定していました。一方ブラウンさんは、元々はご主人様のお仕事の関連会社の副社長だったと聞いています。出張先でばったり会って、その時随分親しくなられたと聞いています。
ご主人様がこちらにお帰りになった時、ブラウンさんも一緒にお屋敷に来られたのです。
初めは、仕事仲間としておいででしたので、来客としてもてなしていたのですが、ご主人様が、ブラウン氏も執事として働いてもらうとおっしゃって…
それ以来、ブラウンさんは事あるごとに、ジョンソンさんのやり方が古臭いと難癖をつけて、ゴタゴタしていました。
ブラウンさんが個人的にご主人様と親しいのをいいことに、物事がうまく運ばないときは、いつもジョンソンさんのミスだとご主人様に忠告していたらしくて、ご主人様も、ジョンソンさんに対して少しずつ距離を置かれるようになってしまいました。
リサお嬢さんも、なんとなくいつも苛立ち気味で、誰にも心を許さないっと言った感じでした。そして、ブラウンさんがリサお嬢さんのお世話係をもう少し若い人にてつだってもらってはどうかと提案してきたのです。
ご主人様は家のことなどすっかりブラウンさんに任せきりだったので、ことは簡単に決まりました。そして、アンという少女が雇われたのです。
アンはごく普通の少女で、勉強はあまり得意そうではありませんでしたが、気立てのいい子だったので、内心ほっとしていたのです。
ところが、その日の夜、リサお嬢さんが大変な剣幕でお屋敷に戻られたかと思うと、突然、私に解雇命令を出されたのです。
そして、憤懣やるかたない様子で階段を駆け上がられたのですが、階段の上でお嬢さんが通り過ぎるのを待っていたジョンソンさんを振り払うようにお部屋に入られたんです。
お嬢さんには悪気は無かったと思いますが、運悪く、頭を下げていたジョンソンさんはバランスを崩して階段を頭から転げ落ちてしまいました。
それ以来、私たちはあのお屋敷には足を踏み入れてはおりません。リサお嬢さんやアンのことは今でも心配ですが。。。」
サムは手帳にメモを取っていたが、なるほどっと納得したようにうなづいていた。ホントにわかったのだろうか。怪しいもんだ。
しかし、反抗期が来た年頃という事を差し引いても、リサの変貌ぶりは気になる。アイスマンの部屋で何があったんだろう。
それと、さっきから何かがひっかかっている。以前に誰かから聞いた話と、食い違っていると思った瞬間があったんだが…。
「とりあえず、私にお話できる事はこの程度です。また、何か思い出したらご連絡します。」
サムはメアリーに礼を言って席を立った。そして、思い出したように念押しした。
「あ、そうそう。くれぐれも、アイスマン家の方々にはボクが探偵だということはご内密にお願いします。」
「ええ、わかりました。その代わり、リサお嬢さんやご主人様の力になってあげてください」
サムの家に向かう車の中で、俺はずっと考え込んでいた。リサになにがあったんだろう。どうやらサムも同じことを考えているらしい、今日は随分と無口だ。
俺は突然のブレーキにサムの上着ごとシートから転げ落ちた。なんとか上着を掻き分けてシートに戻ると、サムが車から飛び出していくところだった。
「大丈夫かい? 急に飛び出しちゃ、危ないじゃないか。もうちょっとではねてしまうところだった」
サムの言葉にやっと事態が飲み込めた俺は車のすぐ前に倒れこんでいる少女を見て驚いた。リサだったのだ。どうやらサムの車には接触せずに済んだようだが、リサは意識をうしなっていた。サムが病院に運ぼうとリサを抱き上げていると、ビルの隙間からカツカツと走り去る足音がした。ビルの向こう側にでたその人物の髪に街灯があたると、ぱっと目を引く赤茶けた色が目に入った。
サムはリサを後部座席に乗せると、知り合いの外科医に連絡をとって、すぐさま病院に向かった。
「今日は随分と収穫の多い日になりそうだな」
「ふん。しょうがないだろう。漕ぎ出した船だ。ロイドの件もアイスマン家の紛争も、みんなまとめて片付けてやろうじゃないか」
まったくサムの人のよさにはついていけない。俺は大あくびで返してやった。
しかし、助手席の背もたれのすきまからみえるリサの顔は、まだまだ幼い少女のような寝顔だ。ときどき苦しそうに顔をしかめるのは、どこか具合が悪いからなのだろうか。それとも良心の呵責からだろうか。
病院に着くと、すぐさま診察がなされた。リサは足を骨折していた。頭も強く打っているらしい。体のあちらこちらに擦り傷もあるらしい。サムの知り合いだという医者は、エリックというらしいが、交通事故かなにかのような怪我だと話していた。
「サム、私は医者だから手術をするにしても保護者の承諾が必要なんだ。彼女の自宅に連絡を入れるが、君の名前を出さない方がいいのかい?」
さすがにエリックはサムの友人だけある。その辺りは心得ているってことか。エリックの配慮で、サムは名乗らないで帰った親切な男性と代わり、手術が必要なので保護者に来院を依頼した。
しかし電話の向こうでは揉め事が起こっているのか、すぐには行くといわないらしい。
「あなたは? ご両親か血縁関係の方は? 執事をなさっているだけでは駄目なんです」
電話の向こうでブラウン氏が歯軋りをしているのが目に浮かんだ。
思わぬ出来事だが、これで直接アイスマン氏に会えるかもしれない。サムと俺はしばらく病院の受付の前で待機していた。だがやってきたのはブラウン氏だった。
サムと俺はとっさに新聞で顔を隠してその場をやり過ごし、ブラウン氏とエリックとのやりとりを伺った。アンの話では、アイスマンはもう自宅に戻ってきているはずなのに、どうしてブラウン氏がやってくるんだろう。アイスマンは娘が可愛くないのだろうか。
ついさっきメアリーが話していたアイスマンの人格と、大きなずれを感じていた。
「とにかく、怪我をしている人間を放っておくことはできない。ブラウン氏には、どんな責任も取るとサインしてもらったし、手術をするよ。
サム、一旦家に戻って休むといい。もう夜も遅いしね。明日の朝には麻酔も切れて意識も取り戻すだろう」
カンカンに怒ったブラウン氏が病院から帰っていくのを見送ると、エリックは不敵な笑みを浮かべながらサムに声をかけ、看護師に指示を出していた。
翌朝、俺とサムはさっそくリサと面会するべく、病院に向かった。しかし相手は病院。俺は例によってサムの上着のポケットに押し込まれた。
サムはエリックと一言二言話をすると、すぐにリサの病室に案内された。
「やあ、気分はどうだい?」
「あんた、誰?」
子どもらしいが、とても疲れた声だった。サムがリサを助けたいきさつを簡単に話してやると、ふ~んと興味なさげな返事を返してくるだけだった。
「随分ひどい怪我をしているようだが、いったい何があったんだい?僕でよかったら、話してくれないか?」
「うるさいなあ。見ず知らずの人間に、何を話せっていうのさ。それとも謝礼でもほしいわけ?」
随分とすさんでいるようだ。とてもお金持ちの一人っ子のお嬢さんとは思えない。これは手こずりそうだと思っていると、サムが声色を変えてきた。
「そう怒るなよ。こう見えても、僕は探偵なんだよ。君がどんなことをして怪我をしたかぐらい、お見通しさ。」
「警察に連れてくの?!」
リサはやっと本当の声で話したようだ。
「まあまあ、そんなに焦るなよ。ここは取引だ。どうする?僕の質問に答えてくれるなら、君のしていたことをここの医者や警察には言わないであげるよ」
「信用できない」
サムの言葉が終わるより早く、リサはするどく答えた。どうやら、痛い目にあったようだ。サムはどうしたものかと、考えをめぐらせていたが、ふっと何かを思いついて自分のノートパソコンを引っ張り出してきた。
「いいかい。これから僕の相棒のとっておきの芸を見せてやろう。それと引き換えでどうだ?その代わり、これは他の連中には絶対に言わないでほしいんだ」
サムはそういうと、俺を内ポケットから引っ張り出し、パソコンの前に座らせた。
「何それ? くだらない。ネコがパソコンでもやるっていうの?
もしそのネコが、言葉を打ち込んだりできるっていうんだったら、信用してあげるけど?」
リサはばかばかしいといわんばかりの返事を返してきた。サムが俺に目配せしている。
しょうがない。いっちょやってやるか。
『はじめまして。ボクはグレンといいます。』
リサは唖然として俺を見つめていた。
「だ、だけど。こんなことぐらい躾けてできてるかもしれないじゃない。ねえ、私を見て、どう思うか書いてみなさいよ!」
リサはそれでも信用できない様子で、違う要求を突きつけてきた。
『君は、なんだか寂しそうだね。友達はいないの?』
リサはぐっと言葉を飲み込んだ。そして、ぷいと窓の方を向いたまま、しばらく考え込んでいる様子だった。
サムは俺にどうしたものかと合図を送ってきたが、ここはそっと待つしかないだろう。
開けたままの窓から、涼風が流れ込んでくる。それが心地よいと感じるのだから、夏は近いのだろう。
サラサラとカーテンを揺らしていた風がふわっと止まったとき、リサは居心地悪そうに体をこちらに向けなおして、観念したように話し出した。
「分かったわ。あんたたちが約束守ってくれるんなら、話してあげる。」
「そう来なくっちゃ!」
サムが俺にウインクをしてよこした。
「もうだいぶ前のことだけど、私、学校のホームワークで親の仕事について調べてレポートを書くように言われてたの。それで、パパの部屋に行こうとしたんだけど鍵が掛かってて入れなかったのよね。提出期限は5日後だったから急がなくてもよかったんだけど、パパったら仕事の事はなにも教えてくれないし、留守の間に少しでも調べておきたかったのよね。
今でも不思議なんだけど、ある日、私の部屋の前に鍵が落ちていて、家のカギって、どの部屋も同じデザインで作られてるから、家の中の何処かだろうとは思ってたんだけど、面白半分でパパの部屋の鍵穴に差し込んだら、開いちゃったのよ。」
サムはチラッとこちらに視線を送ってきた。確かに出来すぎているが、ここは聞き流すしかないだろう。
「パパの部屋は前よりちらかっていて、あちらこちらに書類がいっぱいあったわ。いろいろ見たけど、やっぱりパパに説明してもらわないとだめだってわかったの。それで、諦めてちょっと休憩しようとパパの書斎のイスに座って机に向かってみたら、真正面に小さな写真立てがあって、そこに…。」
リサは明らかに動揺した様子を見せた。俺は、キーボードに向かって言葉を打ち込んだ。
「何か、見たくないようなものでもあったの?」
リサは文章をちらっと見ると、深いため息とともに悲しげにうなづいた。
「そうよ。そこに、パパと知らない女の人の写真があったの。ショックだったわ。まだママが亡くなってからそんなに何年も経っていないのに。
それで、ちょっと引き出しも開けてみたの。そうしたら、写真立てにあった女の人のヌード写真まで出てきて、私、ショックでパパの部屋を飛び出してきちゃったわ。」
「ひどい話だなぁ。おふくろさんが亡くなって、頼りにしている父親だっていうのに」
サムは自分の娘キャシーとリサをダブらせているのかもしれない。アイスマン氏に対する怒りは相当なもんだ。
「それからは、何もかもがウソに見えて、誰のことも信用できなかった。
それで学校をサボって、街をうろうろしているとき、ショーンっていう男の人に声をかけられたの。
今から思えば、ショーンは札付きの悪だったわ。初めは私の身の上話を真剣に聞いてくれて、帰りたくないと言えば食事や宿泊の手配もしてくれて、なんていい人なんだろうって思ってた。」
「ところが、そうじゃなかったってわけか。」
サムが割って入った。
「そう。今度はお前が俺を助ける番だとか言われて、窃盗や恐喝もやらされたわ。このままじゃ危ないと思って家に帰ってた時期もあったんだけど。」
「メアリーには相談しなかったの?」
俺がキーボードに打ち込むと、リサは悲しげにうなづいて続けた。
「メアリーに相談しようと彼女の部屋まで行ったとき、私、見てしまったのよ。ジョンソンさんとメアリーが抱き合ってるところ。。。
私がこんなに困っているのに、自分たちはまるで関係ないみたいだった。私のことを心配してくれていると思っていたのに、とんだ勘違いだったわ。もう、誰も信用できなくて、部屋に駆け戻ったの。
メアリーは私の足音に気づいたらしくて、すぐに声をかけに来てくれたけど、もう、顔も見たくなかった。」
「だから、いきなり解雇命令を出したってワケか」
サムが呆れたように口を挟んだが、リサは続けた。
「それまでから、ブラウンさんにはいろいろ言われてたの。メアリーとジョンソンさんがこの家を乗っ取ろうとしているんじゃないだろうかとか。お嬢さんもあまり出歩かないで、気をつけてくださいとか言われていたわ。
それが解雇の一因でもあるけど、お母さんが亡くなって、お父さんが我が家のことを振り向いてくれなくなった今となっては、怪しい人を解雇するしか私には方法がわからなかったんだもの」
リサは孤独な立場のまま、それでもアイスマン家を守ろうとしていたのか。しかしそれをするにはあまりにもリサは無知だ。
「どうしていいかわからないまま、学校に向かおうとしたとき、ロゼッタが私を連れ去ったのよ。もう充分でしょうって、ずるがしこい大人たちに復習してやりましょうって。ロゼッタは私の味方みたいに話し込んできたわ。おろかだった私はすっかり騙されて、あたり屋の仕事を引き受けることになったの。
指定された車にバスケットボールを当てておいて、すぐそばに老婆のフリをして寝転んでいれば、すぐにロゼッタが助けだしてくれる手はずだったわ。最初にやったときは、簡単に成功したの。その場で示談が成立して、お金もすぐに手に入ったわ。2回目のときはちょっと失敗。スカーフを現場に落としてきてしまったの。あの時は大嫌いなショーンも仲間に入っていて、いやだったけど、気が動転してなにも思い出せないバカな大人を見ているのはおもしろいと思ってた。
だけど、ロゼッタたちに依頼をしてきたお客が、思い通りにことが運ばなかったと言ってお金を払ってくれなかったのよ。お客と揉めているうちに、ショーンが失敗は私のせいだと言い出して、走っている車から、突然突き落とされたの。すぐにそこからは逃げ出せたけど、家に帰りつく前にロゼッタに見つかったわ。
あんたをやらないと、私がやられるって、だから悪く思わないでねって言って、彼女、私の背中を突然押したの。そこにやってきたのがサムさんだった。
だけど、あたり屋のことを誰かにばらすとアイスマン家を放火するって言われてるの。」
「大丈夫だよ。僕たちは絶対に他言しない」
サムはしっかりとリサの目をみつめて力強く答えた。
はぁ。。っとリサは大きな深呼吸をして、ほんの少しだけ笑顔を取り戻した。
「私、助かったのかな。助かっても、しょうがないんだけどね。家に帰っても、もういる場所なんてなさそうだし」
「寂しい事いうなよ。どうしても居場所が無いんだったら、うちにでもくればいい。当面の生活ぐらいなら、面倒みてやれるよ。ただし、うちにはかみさんと娘もいるから、仲良くする事。」
俺がサムの足に爪を立てると、大笑いしたサムが付け加えた。
「ああ、すまん。 うちにはグレンも住んでる。僕の親友のペットなんだ」
リサは今までみたこともないほど、情けない顔になって、ぼろぼろと涙をこぼした。そして、ひとしきり泣いた後で、真っ赤な鼻を隠そうともしないで笑った。
「ありがとう。私、まだ生きてていいんだよね。居場所をもらえるのよね」
サムが大きな手のひらでリサの頭をそっとなでてやった。リサは思いのほか素直にされるがままになっていた。
それにしても、娘がこんな状況なのに、父親が病院にも来ないというのはおかしい。サムもどうやら同じことを考えているようだった。
「ところで、アイスマン氏はどうしてここに来ないんだろう。連絡はしてみたのかい?」
「運ばれてきたときは、病院の人が連絡してくれたそうだけど、ブラウンさんが来ただけだって言ってたわ。私、ちょっと電話してみる」
アイスマン氏に裏切られたという思いはあるだろうが、連絡が取れないというのはおかしいと思ったのだろう。リサはサムに勧められて連絡を入れることにした。
しかし、リサの電話に応対したのはブラウン氏だった。何度かアイスマン氏を出すようリサは迫っていたが、どうしても電話口にアイスマン氏を出そうとはしない。
リサも相当に頭にきた様子だったが、俺たちがみても少し不自然だ。もしかしたら、アイスマン氏は家にいないのではないだろうか。
リサは電話を切ると、すぐさまメールを打ち始めた。ブラウン氏によると、アイスマン氏は今食事中だという。それならば、食後にメールを読むことぐらいできるだろうというわけだ。
しかし、それからしばらくリサのそばについていたが、アイスマン氏から連絡はなかったようだ。
サムもどうやらその事が気になっているらしく、ちらちらとリサのケータイに視線をやっていた。
「さて、そろそろ俺たちは失礼するよ。いろいろと調べなくちゃならんこともあるんでね。夕方にまた顔を出せると思うんだ。退屈だろうけど、ちょっとゆっくり休んだ方がいいよ。じゃあね」
サムの軽口にリサはつくろった笑顔で答えた。
サムの車に乗り込むと、俺は先日サムが仕掛けておいた盗聴器をONにしてみた。するといきなり遠くでがさがさと何かが崩れ落ちるような物音が聞こえてきた。
ブラウン氏の部屋の中ではないようだが、ブラウン氏の罵声が聞こえてきた。
「まったく!どこにあるというのだ! おかしい…」
サムが運転しながらつぶやいた。
「ブラウン氏は何を探しているんだろう」
「きっとアイスマン氏のケータイなんじゃないか? リサがあんなに連絡を取りたがっているとなると、ケータイを押さえておく必要があるだろう?」
「どういう意味だよ」
サムはどうやら、本当にわかっていないらしい。俺はすべてを説明するのが邪魔くさくなった。キーボードに打ち込み始めたとき、サムのケータイが鳴った。
サムは車を路肩に止めて、顔を曇らせた。
「どういうことなんだ?」
電話の内容はかなり深刻なもののようだ。じっと様子を伺っていると、電話を切ったサムが俺に問いかけてきた。
「なあ、グレン。お前ならどう思う? せっかく新ブランドの辞令がおりたっていうのに、ロイドが無断欠勤で行方不明になっているっていうんだ。」
ロイドが無断欠勤?まず考えられるのはキールたちの仕業か、やつらに雇われた連中の仕業だろう。俺がそのことを打ち込むと、サムはすぐさま納得して、ロイドが勤務する会社に潜入すると言い出した。
この状況だ、ロイドの身に危険が迫っているとも考えられるだろう。だがアイスマン氏の方も置いていけない。俺はサムに二手に分かれることを提案して、アイスマン氏の屋敷のそばで車を下ろしてもらうことにした。
アイスマン家の門をするりと潜り抜けると、正面に古城のような塔が見える。その頂にはめ込まれた時計の文字盤に描かれているのは、湖に浮かぶ白鳥。おそらく紋章だろう。
以前この屋敷にやってきたとき、ブラウン氏の部屋で見つけたカフスボタンと同じ模様だ。はやりあのカフスボタンはアイスマン氏のものだったのだろう。
ブラウン氏の部屋にアイスマン氏のカフスボタンがあるというのは納得できない。カフスボタンをはずす理由が見つからないのだ。
俺は、アイスマン家の屋敷に入る前に、辺りをゆっくりと捜索した。古城のような屋敷の周りには花壇や噴水もあった。裏庭には納屋があり、そのすぐそばには大きなポプラが茂っていた。納屋の裏手に携帯用のパソコンを置いて身軽になると、納屋のすぐ脇にある焼却炉に近づいてみた。さっきから、いやな感じのにおいがくすぶったままになっているのだ。
焼却炉の窓は開いたままで薪が突っ込まれたままになっている。燃やしている途中で火が消えてしまったのだろう。
人の気配がしたので、慌てて納屋の裏に逃げこもうとした俺は、変な形のものを踏んで肉球に痛みが走った。振り向くと金色の中に青としろがとけた物体があった。これは、紋章と同じ配色。カフスボタンの片方だ。こんなところに落ちているとはどういうことだ。
俺は気にかけながらもとりあえず納屋のすぐそばのポプラの木によじ登り、様子を伺った。
さっきの気配はチャーリーだった。チャーリーはガーデニング用の大きなスコップをかかえて花壇までやってくると、こんもりといっぱいに花を咲かせている草花たちを乱暴に抜き始めた。一通り抜き終わると、焼却炉の様子を見て舌打ちをし、窓に突っ込まれた薪を少しだして火をつけなおしているようだった。
焼却炉の火は再び燃え、煙がモクモクと空に昇っていく。辺りに広がるいやな匂いに頭がくらくらした。
チャーリーはそのまま花壇にもどり、大きな穴を掘り始めた。そして植木の苗を数本納屋の中から取り出して穴のそばに置いた。なんだ、庭木を植えるだけだったのか。
がっかりした俺は、屋敷の中に目を向けてみた。せっかくここまで来たのに、これっぽっちの収穫じゃあ、納得できない。一通り見回したが、客室のような部屋ばかりだった。
今度は表の植木に登り、1階の様子を伺った。向かって中央やや右手側にアイスマン氏の書斎があり、その続きにある右端の部屋がブラウン氏の部屋となっている。ガラス越しに見えるブラウン氏はなにやら書類に目を通しているようだったが、興味なさ気にデスクに投げると、本棚に歩み寄り、そのまま姿を消した。初めはしゃがんだのかと思ったが、どうもそうではないらしい。ぷっつりと姿を消してしまったのだ。
そのまましばらく眺めていると、アイスマン氏の部屋に人影が動いた。ブラウン氏だった。どういうわけだ? ブラウン氏が部屋を出ていないのは、この目でしっかり確かめていたのに。これはどうやら屋敷内に進入しないと分からない事があるようだな。
俺はとりあえず納屋の裏手までもどり、サム宛にメールを送っておいた。カフスボタンのこと、紋章のこと、そして溶けたカフスボタンのことなどだ。ブラウン氏の部屋のことも少しは書いておいたが、詳細は確かめてからでもいいだろう。もし、このまま食事時になってもアイスマン氏が現れないようなら、最悪の事態も考えておかねばなるまい。
サムからはメールも届いていなかった。あちらはあちらで忙しいのだろう。しかし、今のブラウン氏の様子では、キールが動き出しているとしてもブラウン氏やショーンは関わっていないのかもしれない。前回、ロイドを陥れられなかったことで、キールも他人を雇うことをやめたのかもしれない。
俺は、そっと厨房の見える枝を物色した。もしもブラウン氏が犯罪組織に所属しているとしたら、どういう地位にいるのか、どうしてアイスマン家に居座っているのかも知っておく必要があるだろう。それにはまず、この家にどのくらいの人間がいるのか調べる必要がある。
裏庭の納屋と反対の方角にダイニングから突き出たような形の厨房がある。この2階はチャーリーやアンが住み込んでいる宿舎になっている。樫の木が生い茂って、その厨房を観察するにはお誂え向きだった。
俺は人間の目をすり抜けて裏庭に回ると、樫の木の手ごろな枝に座り込んだ。さっきまで裏庭で作業していたチャーリーが、もう厨房で食事の支度をしていた。時間的に考えて、さっきの作業は放ってきたのだろう。タマネギを剥いたり、ジャガイモを洗ったり、バタバタと忙しそうにしているのが見えた。
今、アイスマン家のいるのは、アイスマンとブラウン氏、それにアンとチャーリーだけか。朝のうち掃除にしにきていた中年女性は、昼前に帰って行った。大きな家にたったそれだけの人数とは寂しいかぎりだろう。
チャーリーがタマネギを剥き続けている。いったい何を作るのだろう。さすがに料理人だけあって、手際がいい。あっという間に大なべたっぷりのビーフシチューが出来上がった。
配膳机には3人分の食器が用意され、サラダやパンと一緒にトレイに移されていった。そして残りの大なべはさっさとふたをして、サラダの大きなボウルと一緒にコンテナに移した。その上段には一食分のトレイが置かれ、チャーリーはそのまま正面玄関を抜けて食事を運んでいった。
おかしい。まかないの料理しか作っていないとはどういうことなんだ。アイスマン氏には別メニューを出すのだろうか。しかし、使用人が先に食事をとるなんて聞いた事がない。
それにあの大なべはどういうことだ。ブラウン氏はどちらかと言えば細身な方だ。とても大食漢とは思えない。
俺は大急ぎで表の木によじ登り、チャーリーが到着するより先に部屋の観察を始めた。ドアがノックされ、ブラウン氏が不意に姿を表した。そしてそのままチャーリーを部屋に入れた。
チャーリーはブラウン氏のテーブルに食事の用意をすると、そのままコンテナを押して本棚の前まで進んだ。
俺は大急ぎで枝をよじ登った。もうちょっと高い位置からなら、本棚の前の部分がどうなっているのか見えるはずだ。
少しばかり頼りない枝ではあったが、そっと足を伸ばして本棚の前の部分が見える場所までやってきて気がついた。本棚のすぐ前には四角く区切られた場所があった。はっきりとは分からないが、地下から灯りがもれてきているようだ。
チャーリーはそこにコンテナの中の大なべや大きなボウルを運び入れると、そこかを操作した。チャーリーの乗った床はすっと滑らかに下降し、すぐさまチャーリーだけを乗せて上がってきた。
そして、チャーリーは何食わぬ顔でコンテナを押しながらブラウン氏の部屋を出て行ったのだ。
あの大なべからして、それなりの人数があの地下室にいるのは間違いなさそうだ。上下する床はチャーリーが移動して数秒後には自動的に床と同じフローリングのシートで覆われた。もしかしたらあの簡易エレベーターのようなものには、入り口が分かりにくくする細工がほどこされているのかもしれない。
そっと枝を退いて、俺は納屋に急いだ。サムの方はうまくやっているだろうか。気になるが、今はサムを信じるしかなさそうだ。俺は焼却炉のカフスボタンの件、チャーリーの食事のこと、それからブラウン氏の秘密の地下室の件をメールにまとめて送った。
急がなくては、できればあの扉の開き方を教えてもらわなくてはならない。
俺は再び表の木の枝によじ登って、辛抱強く待ち続けた。
やがてブラウン氏が本棚の前まで歩いていくと、本棚の下から3段目の辺りに右手を差し入れるのが分かった。
あそこだったのか。っと思ったとたん、足元にびしっといやな音がして、俺は足場をなくしてしまった。
ネコの癖に、着地に失敗してしまった。左足に激痛が走っている。早く逃げなくては。焦る気持ちを暗闇が覆い始める。遠くから足音が駆け寄ってくるのが分かった。あの靴は、チャーリーか。。。俺はそのまま気を失ってしまったらしい。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- まち楽ブログ
- 大垣城が秋色! (紅葉の大垣城)
- (2024-11-22 12:00:12)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 【感想あり】鷹・山川穂高が契約更改…
- (2024-11-24 00:00:13)
-
-
-
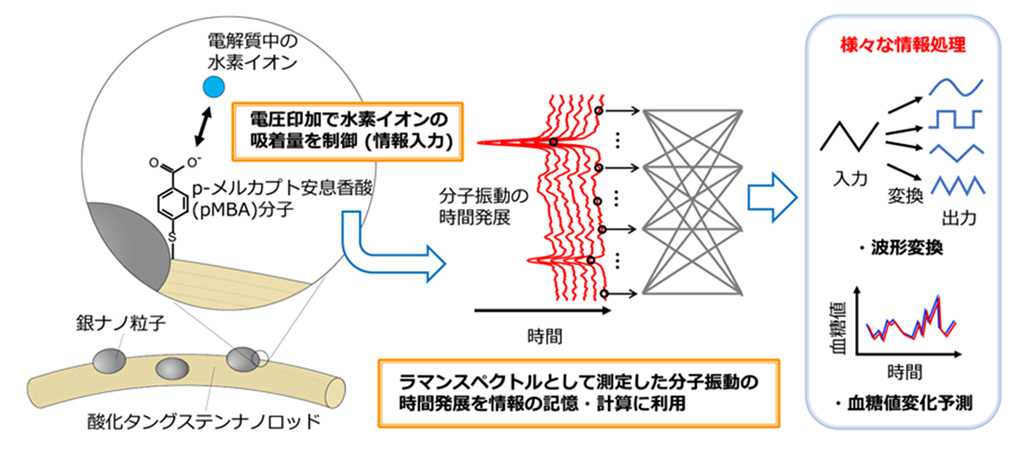
- 気になったニュース
- 理科大など、数個の有機分子からなる…
- (2024-11-23 20:13:17)
-
© Rakuten Group, Inc.



