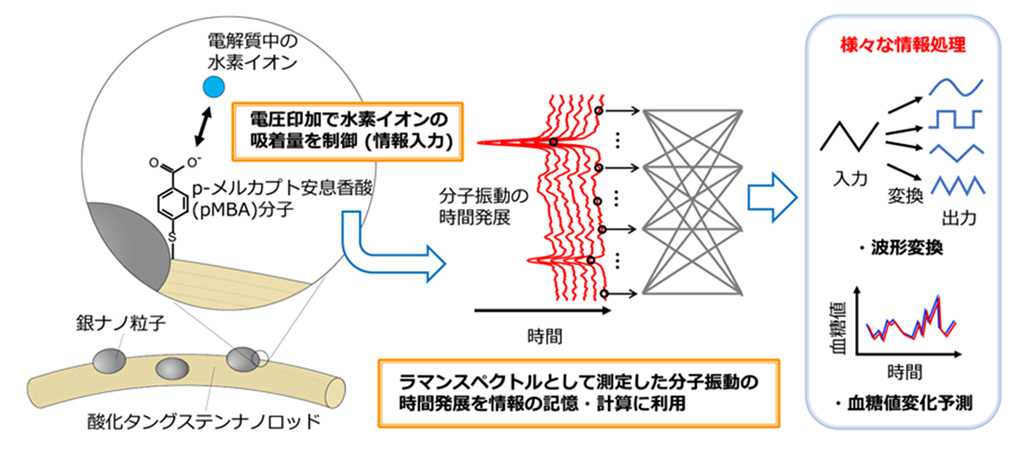[REALIZE2] カテゴリの記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
第7章 目覚めの時 5
厳かな音楽と新郎新婦を見守る人々の温かな愛情に包まれた、幸せな結婚式をまじかでみたヒカルは、はあっとうっとりとしたため息をついた。「シャルロット先生、とってもきれいだったわぁ。お父さんも幸せそうだった」「シャルロット先生ではなくて、お母さまでしょ? さぁ、あなたたちも行ってらっしゃい。そろそろダンスの時間が始まるわよ。ハワード、ヒカルをお願いね。」 ソフィアに言われて、思わず「はい」と返事を返し、二人はフロアに赴いた。 そっと差し出された手に自分の手を預けてほほ笑むと、水色の瞳がほんの少し緊張したようにとび色の瞳を捉える。何かあったのだろうか。そんなヒカルの疑問を打ち消すように、ハワードは笑顔でリードする。「あの頃、初めてダンスレッスンでハワードさんと一緒に踊った時、私ったらいっぱい足を踏んづけてたわね」「確かに。それを考えると、ずいぶん上達しましたね。」「ハワードさんとダンスの先生のおかげです」 微笑みを浮かべていたハワードが、ふいに真剣な表情になった。「ヒカル… あの…」 言いよどんでいるうちに、曲が終わっていく。もう1曲一緒にと思っていたのに、貴族たちが一斉にヒカルに詰め寄って来た。「王女様、次は私と」「いえ、次は僕の番ですよ」話しが途中になったヒカルがハラハラしているなか、アランがすっくと前に出た。「あーおほん。次は私の番です。みなさん、ご配慮を」 アランがそっとヒカルの手を取って、踊りに誘った。ギャラリーの端でシャルロットが笑っているのが見える。「ヒカル、すっかり大人になったね。お父さんからのプレゼントはどうだった?」「ふふふ、ありがとう。お父さん。私もお母さまみたいな素敵な花嫁になれるよう頑張るわ」 踊りながらほほ笑む娘に、アランは思わずステップを忘れそうになる。「え?ヒカル? 今、お母さまって言った?」「そうよ。シャルロットお母さまよ。」「ヒカル… 結婚しても、子どもが出来ても、ヒカルはお父さんの大切な宝物なんだからな」 今日の主役である新郎アランだが、この時ばかりは父親の顔になって瞳を潤ませた。「ありがとう、お父さん。だけど、私も自分の宝物を見つけたわ。」「そうみたいだな。この国の王族には、お前たちカップルを応援する大人たちがうるさくてね。」 アランはそう言ってウインクして見せた。曲が終わると、待っていた貴族がここぞとばかりに寄ってくるが、次にはシルベスタが、その次はガウェインがダンスの相手を申し出た。あっという間にラストダンスになって、ヒカルが手を取ったのは、やはりハワードだった。 会場には二人のダンスを見ようと周りを囲むように貴族が並んでいる。多くの女性を魅了し続けた麗しの騎士王ハワードと、美しい淑女に成長したプリンセスヒカルのダンスは、見ている人々をも魅了した。 曲が終り向かい合った二人は礼をする。すると突然、ハワードはヒカルの前に片膝をつき、そっと手の甲に口づけた。「ヒカル王女様、私はもうあなたしか目に入らないのです。こんなところで言うのは許されないかもしれませんが、どうか、私と結婚してください」 周りの貴族は一気にざわついた。「ウソだろ。俺だってずっと好きだったのに」「いやよ。ハワード!」「姫、早まらないで!」 周囲の喧騒はすさまじい物だったが、ヒカルはそっとアランとシャルロットに視線をやり、ガウェイン、シルベスタ、ソフィアへと順に視線を送り、そのすべての人が微笑んでいるのを確かめると、つぼみが開くようにふんわりとほほ笑んだ。「ハワードさん、よろしくお願いします」「はっはっは。ここにこの二人の婚約が成立したことを宣言する!」 ヒカルの返事を待っていたかのように、ガウェインが高らかに宣言した。恥ずかしそうに頬を染める二人の周りには、拍手と残念がる若者の声と、それを仕方ないさと慰める大人たちの笑顔であふれている。 「ねえ、シルベスタ、気になっていることがあるんだけど」「なんだい?」「この前、あと一押しとかなんとか言ってたけど、いったい何を言ったの?」「え、ああ。簡単なことさ。アランの結婚式の宴が終わるまでに答えを出さないなら、僕がお嫁にもらってもいいかいってね」「まぁ!ハワードはさぞや緊張していたでしょうね」「だろうね。普段の彼なら、あんな群衆の前でプロポーズなんて絶対しないと思うよ」「はぁ、本当にあなたっていつまでも困ったいたずらっ子ね」 呆れるソフィアの横で胸を張るシルベスタは満足げに言う。「だってほら、これで一気に貴族たちにも了承させることが出来たじゃないか。ガウェインの保証付きだよ。まさか王太子殿下の結婚式に異論を申し立てて場を悪くさせるわけにもいかないだろ?」「どうだった。私の婚約承認のタイミング、最高だっただろ?」 ソフィアたちがいる席に戻ってきて、自慢げに言うガウェインを見て、ソフィアはこめかみを抑えた。 控室に戻ってきたヒカルとハワードは、すぐさまアラン夫妻に会いに行った。「アラン王太子殿下、その、この度は急な申し入れをしてしまい、申し訳ありませんでした。」 平謝りのハワードに、アランは苦笑いだ。「大丈夫。きっとそうなるだろうと思ってたよ。だけど君があんな貴族たちの前でプロポーズするとは思わなかったから焦ったよ。どうせシルベスタさん辺りが仕組んだんだろう?」 あ、そういうことか。と、ハワードが目を見開いている。「ハワード、ヒカルを頼んだよ。」「はい!」 握手する二人の瞳には、一点の曇りもなかった。おわり
May 20, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第7章 目覚めの時 4
翌日、アイスフォレスト王国に帰るなり、厨房を借りて久しぶりにプリンづくりをしていたハワードは、ヒカルの習い事の隙間に、プリンを持ってやってきた。「王女様、久しぶりにプリンを作りましたので、お持ちしました」「プリン?まあ、久しぶりですね。 では、ハワードさんも一緒にいただきましょう」 ヒカルは侍女に合図して、紅茶を持ってこさせると、席を外すように指示した。 相変わらず、プリンを目の前にしたヒカルの瞳は輝いているが、あの屈託のない表情は見られない。「ハワードさんのプリン、やっぱりおいしいです。だけど、どういう風の吹き回しですか?」 いたずらっ子のような表情でハワードの瞳を覗き見るヒカルは魅惑的だ。ひとさじスプーンですくいながら、ハワードは観念したように語りだした。「あの旅の途中で、私がふさぎ込んでいるとヒカルにはずいぶん心配をかけてしまいました。あの時は、ヒカルに人間のドロドロしたものを聞いてもらいたくないと言いましたが、本当は子供らしくプリンを見つめて笑っていたあの頃のヒカルを自分の中にとどめておきたかったのだと思います。あの時決心したのです。こちらに帰ったら真っ先にプリンを作ろうと、そして、ヒカルに食べてもらってあの子供らしい笑顔を堪能したいと。だけど…」 少し寂しげにも見える水色の瞳が、じっとヒカルを見つめている。「あなたはもう、私が想像していた以上に大人の女性になっていたのですね。」「そうでしょうか? 今でもハワードさんのプリンは、私の最高の癒しですよ」 ヒカルが眉を下げ、申し訳なさそうに見つめると、ハワードの瞳に日が差したように幸せがにじむ。「以前言えなかった話を聞いてもらえますか? 私の異世界での家族の話です。」「聞かせてください」 水色の瞳が、まっすぐにヒカルを捉えていた。ヒカルは姿勢を正してその瞳に答えた。「私はカリフォルニアのごく普通の家の子どもとして生まれました。前にも言いましたが、年の離れた弟がいます。父とも、母とも似ていないこの水色の瞳は、私と弟だけの色なんです。街でスカウトされて、俳優になって、家族は反対するどころか、自慢の息子だと喜んでくれていました。ですが、映画に出るようになって、大金が家にはいるようになると、徐々に大人たちの生活は変わっていきました。父はギャンブルに狂い、母は現金を持ち逃げして行方不明です。そのせいで弟も心がすさんでしまって…。心配しても、スケジュールは過密でなかなか家に帰れない日々がつづきました。 やっと帰ってきたら、弟が金を要求してくるようになっていました。一番安心できるはずの家庭は無残にも崩壊いてしまったのです。あの時、ウェリントン公爵領でベランダにいたのは、懐かしい波の音がしていたからなんです。自宅でも不安なことがあるといつもベランダに出て、波の音を聞いたりしていたので…。そんな時、ヒカルがやってきたので、なんだかみっともない自分が見透かされそうな気がして、逃げ出したんです」 ヒカルはそっと席を立ち、向い側に座るハワードの隣にやってきた。そして、その悲し気な顔を両手で包んで、自分の胸に抱き寄せた。「不安だったでしょう。だけど、親のしたことで自分が恥じることはないと思います。親の身勝手を子供がどうこうできる物ではないですから。私の母も、物心つく前に男の人と出て行ったそうです。友達のお母さんたちが噂していたので知っていました。お父さんは隠しているつもりみたいだけど。だけど、ハワードさんも、私も、こうして真っ当に暮らしているじゃないですか」 ハワードは頷きながら、そんなヒカルの背中に腕を回して同じように抱き寄せ、「ありがとう」とつぶやいた。 いよいよアランの結婚式当日となった。淡いピンクのジョーゼットを重ねたドレスはその花びらのようなスカート部分のふちに輝く小さなラインストーンの粒が連なり、結い上げられた髪にはハワードの瞳とそっくりのアクアマリンの髪飾りが輝いている。これはハワードからずいぶん前にプレゼントされたものだ。それに合わせてイヤリングもチョーカーもアクアマリンでそろえている。 着付けを終えて、鏡の前で確かめていると、ドアがノックされてハワードがやってきた。今日のヒカルのエスコート役を、アランから指名されてきたのだ。その服装は、ところどころにシルバーが入ったシックな燕尾服で、胸にはピンクのジョーゼットのチーフが刺さっている。 部屋に一歩入った途端、淡いピンクのドレスを着た愛らしい姫君に言葉を失う。「王女様、お迎えに参上致しました。本日はアラン王太子殿下のご指名をいただき、王女様のエスコ―ト役をさせていただけることになりました。恐悦至極にございます」 ベスは早々に支度を片付けて、他の侍女を下がらせた。「王女様、いえ、ヒカル。本日はおめでとうございます。このままこのお二人の結婚式があってもおかしくないですね。二人とも、とっても素敵ですよ」「ベス、ありがとう。あなたも急いで着替えてきてね。ぎりぎりまで手伝わせてごめんなさい。」 ベスはふふふと笑って、「では、式場で」と言って下がった。「ヒカル、今日もとっても素敵です。」「ハワードさんもね」 ではっと、ハワードが腕を出すと、ヒカルがそっと手を添えて式場へと歩み出した。つづく
May 19, 2022
コメント(0)
-
REALIZE2 第7章 目覚めの時 3
その頃ハワードは、カリフォルニアの住宅エリアに来ていた。観光客の多い道路を避け、細い路地を抜けて長い坂道を登っていくと、緑の屋根のこじんまりした家がある。門の前までくると、スミスと書かれたウェルカムボードが置かれている。「懐かしいなぁ」 そっとウェルカムボードに触れた後、庭を覗いてみると、子どもの頃遊んだブランコが未だ健在だった。「リチャード、リンダがお庭に行きたいんだって、少し付き合ってあげて。今手が離せないの」 家の中から若い女性の声がした。そのまま庭を通り過ぎて様子を見ていると、明るい金髪を短く刈り上げた男性が、同じく明るい金髪の巻き毛を愛らしく編み込んだ幼女を連れて出てきた。「よーし、今日は天気がいいからブランコしようか。リンダ、ここにすわってごらん」 楽しそうに笑い声をあげる子どもと、目じりを下げたリチャードがブランコで遊んでいる。ああ、子どもの頃はあいつともあんな風に遊んだなぁ。ハワードは懐かしさを抑えて通り過ぎ、少し離れたところから懐かしい我が家を眺めることにした。 その時、家の中からリチャードを呼ぶ声がした。「リチャード、電話よ」「ああ、リンダ。ちょっとだけ待っててね」 リチャードが急いで家の中に入ってしまった。リンダはしばらくゆらゆらとブランコに揺られていた。お天気が良く庭でのんびりするにはぴったりの休日だ。 ハワードは、もし自分に子供が生まれたら、あんな感じなのだろうかと少し離れた場所からぼんやりと眺めていた。ヒカルの薄茶の巻き毛も捨てがたいなぁ。などと考えていると、家の裏側から不審な動きをする男が現れた。ハワードが反射的に自宅に駆け戻ると、リンダが口元を抑えられているところだった。 ハワードは夢中で庭に飛び込むと、男を蹴散らした。飛び込んだ拍子に、目深にかぶっていた帽子が転げ落ちる。突然やってきたハワードにひるんだ男は慌てて逃げ去った。ハワードは男を追いかけず、ベソをかいている幼い少女に近づいた。そして、胸ポケットにあるブレスレットを取り出して、リンダに差し出した。「怖かったね。もう大丈夫だよ。これはお守り石が入ったブレスレットだ。良かったら持っててね」「おにいちゃん、だぁれ?」 リンダはまだまるい頬に涙の粒をつけたままブレスレットを受け取ると、ハワードを見つめてはっとした。「パパとおんなじお目目」 それには答えずに微笑み返すと、「じゃあね」と立ち上がり、帽子を拾って再び目深にかぶると、そのまま庭の柵を超えて去っていった。「リンダ、どうした?大丈夫か?」 物音を聞いてやってきたリチャードに、リンダは嬉しそうにブレスレットを見せた。「あのね。怖い人が来たの。お口をぎゅってされたのよ。そしたらね、かっこいい王子様が来たの。パパとおんなじお目目の人だったよ。悪い人をやっつけてくれたの。怖かったねぇって言って、お守りだよって。」「え? 王子様だって? おんなじお目目って…まさか兄さん?」 リチャードはすぐさま道路に飛び出して辺りを探したが、ハワードの姿を見つけることはできなかった。その頃ハワードは、すでに撮影スタジオに向かっていた。手にはリンダのふわふわした柔らかな感触が残っている。ヒカルとはまた違った愛しさを覚える。「元気に大きくなってね。」リチャードがちゃんと父親として暮らしている姿を見られたのが何よりもうれしかった。 通いなれたスタジオには監督がいるはずだ。彼には一度きちんと会って謝罪しなければならない。スタジオの入り口前で、係員に監督を呼んでほしいというと、怪訝な顔をされた。仕方なく目深にかぶっていた帽子を取ると、明るい金髪がさらりと肩に零れ落ちた。「お久しぶりです」 その一言で、係員ははっとしてすぐさま監督を呼んでくれた。「ハワード!戻る気になってくれたか!」「監督、今日は、謝罪とお別れを言いに来ました。長らくよくしてくださってありがとうございました。事故に遭って、しばらく記憶をなくしていたのです。でも、もうそちらの世界で生きて行こうと決めました」 監督は蒼白な顔で嘆く。「ふう、これはえらいことだぞ。世界中の女性が号泣だ」 監督は頭を抱え、ハワードは大げさだと笑った。「あの時の子役の子、良い感じに育ってるんじゃないですか? ちょうど僕がデビューした年齢ぐらいにはなってるでしょう」「ああ、そうだ。あいつもお前に会いたがっていた。親は子役だけにさせて、他の道に進ませたいようだったが、おまえさんの演技が気に入ってずっと俳優をやると言い出したんだ」「そうですか。彼の事どうぞよろしくお願いします」 監督は残念そうに眉を下げ、名残惜し気にハワードを見つめた。「決心は固いんだな。はぁ、チクショー。どんな道に進むのか知らんが、がんばれよ!俺はいつでも応援している。うまくいかなかったら、いつでも戻ってこい」 二人は固く握手して、それぞれの道に別れて行った。スタジオを出ると坂道から海が見えた。この海を見ることはもうないかもしれない。それでも、ハワードはためらわずに水晶玉を握り締めた。つづく
May 18, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第7章 目覚めの時 2
荷物をほどいて、再び次の旅にむけて準備をしていたハワードは、ちらっと部屋の窓から見える東館の一角に目をやった。ハワードが暮らすこの部屋からは東館がよく見えるのだ。 ふんわりと明かりが広がっていた東館が、ふっと暗くなった。窓の桟にもたれて暗くなった東館をぼんやりながめる。「ヒカル、おやすみ」 胸のあたりがキュンと締め付けられる感覚は、旅の途中からずっと続いている。まさかこの歳になって、こんなに人を好きになるとは思いもしなかった。明日になれば、転移することになっている。両親はともかく、弟がどうしているか、是非確かめたい。自分が俳優になっていなかったら、平穏な暮らしが続いていたのだろうか。大切な人が出来たからか、余計に弟の今が気になった。 翌朝、早速転移省に出向いたハワードは、担当者から水晶玉を受け取り、転移室へと移動する。長い廊下を歩いていると、後ろからトトトと軽い足音が近づいて来た。「おはようございます、ハワードさん。もう出発されるのですか?」「王女様!おはようございます! はい、数日、旅人として故郷を見て回る予定です」 涼し気な水色のドレスは、ハワードの瞳と同じ色だ。そっと差し出された手に小さな石を通したブレスレットが二つ乗っている。「これを。一つはハワードさんの旅のお守りとして、もう一つは弟さんに。もし会ってお話出来たらお渡しください。お守り石を紐に通しているものです。」 ハワードは一つをその場で腕に通し、もう一つを胸のポケットに入れてほほ笑んだ。「ありがとうございます。これ、以前にリッキーを助けたというあのお守り石ですか?」「どうかしら。あの時のお守り石が消えていたのだとしたら、少しは役に立っていたのかも。」 自信なさげに微笑むヒカルに頷いて、「それでは」とハワードは踵を返した。「いってらっしゃい。よい報告を待っています」「王女様、王妃様が陛下の執務室でお待ちです。参りましょう」 侍女に急かされて、ヒカルはその場を後にした。今日はベスが休暇を取っている。 王族関係の主要なメンバーが、改めてヒカルから地方の問題や出来事について話を聞いた。地方の問題点も明らかになり、クランツ首相は早速領主から事情を聴くという。ガウェインとシルベスタは、鎮魂碑を建てることに大いに賛成した。「ヒカル、以前の王国の人々に心を砕いてくれて、ありがとう。私からも礼を言う」「そうだよね。本当なら、僕たちが気づいて真っ先にやらなければいけなかったことだ。でも、次の世代だからこそ、気が付いてくれたのかもしれないな。僕たちは、国を維持することに必死だったから」 二人からの言葉に、ヒカルは恐縮した。大人たちはみな一様に満足気だ。多くの出来事に触れ、人々に触れ、ヒカルは明らかに大人になった。公務を抱えている王子やその護衛達は、ヒカルと一緒に退室し、執務室はいつもの3人になった。「きっと何か進展があったのね。あの子の瞳に艶っぽさが見られたわ。ふふ。これからが楽しみね」 ソフィアは終始ご機嫌だ。「まあ、途中で発破をかけたからね。ハワードは真面目過ぎるんだよ。旅先でぐらいちょっとは開放的になればいいのに」「おい、まさかお前、何か仕掛けたんじゃないだろうな」 眉間にしわを深めたガウェインに、シルベスタはにんまりと笑って見せた。「あ~、これはやらかしているわね。シルベスタ、白状なさい」「やらかしたとは失礼だな。幸福の鐘を二人に鳴らしてほしかったんだよ。それだけだよ。あの土地はいわゆるパワースポットなんだよ。土地からのエネルギーを受け取って、地形的にも下から風が吹きあがってくる感じでね。高揚感とか幸福感を味わうにはピッタリなんだ」 それを聞いてソフィアが呆れたように言う。「じゃあ、ヒカルが言ってた宿の隣の旅人って、あなただったの?」「ん、気づいてもらえると思ってたんだけど、どうもそれどころじゃない雰囲気だったからさ。あの時のハワードの顔は見ものだったよ。クックック。だけど、あと一押しが足りないんだなぁ。やっぱりあの手で行くか…」 ガウェインとソフィアは盛大なため息をついた。「まったく…。アランが聞いたら卒倒するぞ」「そうだ。アランの結婚式にジュード先生を招待するのはどうだろう。せっかくヒカルたちが見つけてくれたんだ、これを機会に王政のアドバイザーになってもらうっていうのもいいんじゃない?」 諫めるガウェインの言葉をものともせず、シルベスタが提案する。ヒカルの報告会は、そのまま今後の王政についてと議題が替わり、夜遅くまで続いた。つづく
May 17, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第7章 目覚めの時 1
第7章 目覚めの時「父上、ただいま帰りました」「ふふ。なかなかいい顔になって戻ってきたね。旅は有意義だったかい?」 ヒカルは満面の笑みを浮かべて答えた。「はい。とても勉強になりました。お話したいことが山の様です」 娘の生き生きした表情を見て、アランも誇らしく思った。「では、さっそく陛下に会いに行こう。ハワード、リッキー、ベスも一緒にね」 アランが歩き出すと、フランソワが馬車の荷物をほかの侍女とともに運び出す。それをさりげなく手伝うジークが目に留まり、ヒカルが駆け寄った。「ジークさん、先日は楽しい時間をありがとうございました」「喜んでいただけて、幸いです」 ジークは片眼を閉じて人差し指で唇を抑えると、すぐさま荷下ろしに戻っていった。ヒカルはクスっと笑って、廊下で待つアランの元に駆け戻り、王の執務室へと向かった。 見聞きした多くの事を語り、その度に、王を喜ばせたり考え込ませたりした4人だったが、ハワードが「これを」と差し出した王冠を見て、ガウェインは目を見張った。「サルビィの丘の近くの谷間に埋もれていました」「よくぞ見つけてくれたなぁ。これは、父の形見だ」 王冠を見るガウェインの表情で、それが手放しで喜べない何かを孕んでいるのだということが分かる。続いて、森の奥の小屋に一人で住んでいた老人の話をすると、ガウェインが身を乗り出して尋ねた。「そのご老人は足が悪いのではないか?」「そういえば、少し足を引きづっていらしたように思います。あ、それから、陛下の事を、悪ガキとおっしゃっていました」 ガウェインは心底驚いたように目を見開いて玉座に座りなおした。「そうか、生きておられたのか。子供の頃の恩師だ。よく叱られたのだよ」 ガウェインは老人の言葉を聞き、ハワードが持ち帰った王冠を眺めながら、深く頷いていた。「この王冠は、戒めの品として保存しておこう」 ガウェインの言葉に、ヒカルはハワードに視線を送った。やっぱりハワードさんの言ったとおりだった。ハワードがそれに頷いていると、ドアがノックされてソフィアが入ってきた。「まぁ、ヒカル! おかえりなさい」 ヒカルを優しく抱きしめると、ソフィアの視線はヒカルとハワードを往復する。視線を感じたハワードがそっと視線をそらしても、耳が赤くなっていてバレバレだ。「ゴホン」 後ろに控えていたジークが咳払いをしてヒカルの傍に進み出た。「さあ、今日のところは一旦お住まいに戻られて、お休みいただきましょう。」「あら、そうなの?」 ソフィアはお楽しみを奪われたように肩を落としたが、ジークはお構いなしだ。「ヒカル王女様には、新しいお住まいが待っています。お話は後日ゆっくりと」「そうね、お楽しみは取っておくことにするわ。ヒカル、ゆっくりおやすみなさい」「はい、ありがとうございます。」 4人は新たに用意されたシルベスタの邸宅に隣接する敷地まで戻ってくると、ヒカルは仮住まいへ、リッキーとベスはその従業員宿舎へ、そしてハワードは主の邸宅へと帰っていった。 ヒカルの仮住まいは、シルベスタの邸宅の東館を借りることになった。以前の住まいと変わりなく準備が整えられているのは、フランソワの腕によるものだ。「ヒカル王女さま、おかえりなさいませ。今日は早めに湯あみを済ませて、夕食はこちらの館で召し上がっていただきます」 たった一人の夕食は、昨日までの旅の楽しさを反転させたように静かで味気ない物だった。寝室のベランダに出て夜空を見上げても、サルビィの丘のような満天の星は見えない。それでも、胸の奥がほっこりと温かい理由を、ひかるはすでに知っている。 ドアがノックされてベスが入ってきた。「王女様、そろそろお部屋にお入りください。まだ夜は冷えますよ」「ベス! 旅から帰ったばかりなのに、もう仕事?」「すみません。なんだか一人でいるのが寂しくなって、侍女長にお願いして王女様の顔を見に来ました」 ベスはちょっと照れ臭そうな笑顔を見せた。侯爵令嬢然とした凛とした姿のベスからは想像できない愛らしさにヒカルはほっこりさせられた。「ありがとう、ベス。楽しい旅だったわ。みんなが一緒でなかったら得られなかった経験だった。」「王女様、いえ、今だけは、…ヒカル、おめでとう。やっと想いが通じたのね。これからも仲良くね」「ああ、ベス!気づいていたのね、ありがとう! ベスもお幸せにね!」 ヒカルは思わずベスに抱きついて涙をあふれさせた。「あらあら、抱きしめる相手が違いますよ。 さて、紅茶を淹れます。ぐっすり眠れるカモミールにしましょうか。」 二人はしばらく旅の余韻を楽しんで「おやすみなさい」とランプを消した。つづく
May 16, 2022
コメント(0)
-
REALIZE2 第6章 宝石の原石たち 3
フレイヤたちに見送られ、ヒカルは馬車に乗り込んだ。馬車の中は華やかなホワイトローズの香りが満ちている。「わぁ、いい香り」「お気に召しましたか? フレイヤさんへのプレゼントのついでに、こちらにも少し買ってみました。ヒカルが喜んでくださるなら、何よりです」 ホワイトローズに負けない甘い微笑みを浮かべたハワードが、満足げに言う。予定していた行先がほぼ終了して、少し余裕が出てきたのかもしれない。 しばらく走っていた馬車がゆっくりと止まる。外を見ると、きれいな湖のほとりに出ていた。外から休憩しようとリッキーの声がかかる。 馬車から簡易のテーブルやイスを出し、買い込んでいたサンドウィッチを取り出す。ベスが淹れる紅茶を待っていると、気持ちのいい風が湖を渡ってきた。「リッキーとベスの結婚式はいつの予定なの?」「え、あ。まだ、日程までは決めていないけど、この旅が終わったら、両親にベスの事を紹介するつもりなんだ。王太子殿下の挙式が目の前に迫ってるから、俺たちはその後だな」 ヒカルの直球の質問にもすんなりと答えるリッキーは、語尾をベスにむけて語っている。ベスも頷いている。もうすっかり夫婦の様だ。「王城に帰ったら、急に忙しくなりますよ。新居の荷ほどきや王太子殿下の挙式の際のドレス選びも待っています。フランソワさんのお話では、新居は王城ではなくシルベスタ様の邸宅の近くになると伺っています。私たち使用人の宿舎も併設されるそうです。ただ、新築になるので出来上がるまでは、シルベスタ様の東館をお借りするそうですわ。ハワードさんは両方に行き来することになるから、きっと大変だろうって、フランソワさんも心配していましたよ」「ご心配、ありがたいことです。でも、私はこの旅が終わると少し休暇を頂く予定なんです。シルベスタ様には元々数人の執事がついていますし、ヒカルはしばらくは王太子殿下の挙式の準備に忙しいでしょうから、私が抜けても大丈夫でしょう」 ハワードがそういうと、ヒカルが急に不安げにハワードを見つめる。そんなヒカルに笑いかけて、ハワードは計画を明かした。「私を召喚した人間が誰なのかは未だ分からないままですが、とりあえず転移で元の世界に戻って、以前居た場所の様子を見に行こうと考えているのです。召喚された時点で、私の存在がどう扱われたか分からないのですが、とりあえず弟が普通に暮らしているかどうかは見ておきたくて」「ウェリントン侯爵領で話していた年の離れた弟さんのこと?」 初めてハワードの口から直接聞かされるプライベートな話にどぎまぎする。「ええ、6つ年下なので、もう大人になっているんでしょうけど、私が俳優になってなかなか家に帰れなくなる前は、まだ小さかったので。どうなっていても私にできることはないのでしょうけどね。それで、あの世界での自分とは決別するつもりです。」 ハワードの表情は晴れやかだった。もう自分の進む道は決まっているのだとその表情が如実に語っていた。ヒカルは心からの笑顔で言う。「いってらっしゃい。気を付けてね。私は、お父さんの結婚式の準備をしながら待っています」「ありがとうございます。必ず帰ってきます。あなたの元へ」 ヒカルを見つめるハワードの瞳にくもりはなかった。ベスとリッキーはそんな二人を満面の笑みで凝視している。それに気づいて、ハワードは慌てて顔をそらした。 その後も馬車は順調に進み、いよいよ懐かしい王城が近づいてきた。城に近づくにつれて、街がとてもにぎわっている。お祝いの垂れ幕や花飾りがいたるところにあるのだ。王太子殿下の結婚式を祝うものだ。カーテンを開けて街の様子を眺めていたハワードは、ふいにカーテンを閉めてヒカルに声を掛けた。「もうすぐ王城に到着します。ご準備を」「ハワードさん。あの…。私にはこの旅で一つだけ、心残りがあるのです。聞いてもらえますか?」 幸福の鐘を鳴らした時の気持ちを確かめたい。城内に入ったら、しばらくは二人きりでは会えないだろう。ヒカルは逸る気持ちを抑えて、問いかけた。改まった様子を感じて、ハワードが向き直る。「あの丘で鐘を鳴らした時、私は不思議な気持ちになりました。鳩に驚いてハワードさんにしがみついたときのハワードさんの表情が、その…、なんだかお父さんが私を見るときや、リッキーがベスを見るときの表情ととても似ていて、その…」 下を向いて言いよどむヒカルを引き寄せ、ハワードは自分の腕に抱きしめた。「こんな、顔でしたか?」 驚いて見上げたヒカルの目の前には、頬を染めて照れ臭そうに、でも幸せそうに笑うハワードがいた。「ベスから、あなたの気持ちを汲んであげてと言われました。シルベスタ様からは、さっさと告白しろと言われました。リッキーには、好きな子を守りたかったらちゃんと自分の気持ちを伝えないと誤解されると言われました。 あなたより10歳以上も年上の貴族でもない私が、王太子殿下の娘であるあなたに想われているなど、とても信じがたいのですが」「ハワードさん自身の気持ちはどうなのですか? お父さんに跡継ぎが生まれたら、私は王族を離れるつもりでいます。なんの肩書もない私をどう思いますか?」 ハワードは目を見開いて、それからはぁーっとため息をついて笑った。「私たちは、同じような気持ちで同じような隔たりにおびえていたんですね。私は、ヒカルのことが大好きです。あの丘であなたを抱きしめたとき、もう離したくないと痛切に思いました。肩書なんてどうでもいい。ただ、あなたがいてくれたなら、それだけで」 ハワードの言葉を聞きながら頷くヒカルの頬を、何粒もの涙が流れては落ちる。二人はやっと、想いを打ち明け合えた。「ヒカル…」 ハワードがそっとヒカルに口づける。その時、馬車が止まってリッキーがドアを開けかけてそのまま閉じた。「王女様、王宮に到着いたしました!ご準備をお願いいたします!」「あら!ふふふ。リッキーったら、棒読みじゃない」 ベスが察して笑っている。「おかえり。リカルド、エリザベス。ご苦労だったね。ヒカルは…?降りてこないねぇ?」 出迎えに来ていたアランが馬車に近づこうとすると、リッキーが一歩前に出て立ちはだかって、一層大きな声で言う。「王太子殿下、お出迎えくださりありがとうございます。」「いや、リッキーを迎えたいわけじゃないよ。ヒカルをね…」 不思議そうに言うアランになおも食い下がるリッキーは、「ちょっと待ってください」と言って、馬車の中にむけて声を掛ける。「開けてもよろしいでしょうか?」 すると、ドアがゆっくりと開いてハワードが降り立ち、ヒカルの手を取ってエスコートした。つづく
May 15, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第6章 宝石の原石たち 2
「なあ、それならさぁ。この辺りに休憩所でも作って、果物や焼いた魚を売るっていうのはどうだ? この峠って、西に行くのに必ず通る街道だろ? 俺だったら、この辺りで休憩をはさみたいなぁって思っていたから食べ物や果物が売られていたら嬉しいけどなぁ」「ふふ。リッキーは食いしん坊ね」「それはいいですねぇ。近くに小川があるなら、馬の水飲み場を用意してもらえたら、旅人にはありがたいですよ。」 リッキーの提案にハワードもすっかり乗り気になってきた。それを聞いていた男たちもそうだそうだとにぎわいだした。机とイスを用意しよう。雨の日には屋根がいるなぁ。などと、いろんなアイデアが出てすっかり盛り上がっていた。「では、私たちは失礼しますね。皆さんの健闘を祈ります」 ハワードが立ち上がると、4人は馬車に乗り込んだ。「待って、これを」 ヒカルは小さな袋に自分の紋章をしたため、食事代を入れてお頭に渡した。「おいしい山ぶどうをありがとうございました。もし、なにか困ったことがあったら、これを持って王城に来てください。少しはお役に立てるかもしれません。それでは、ご機嫌よう」 驚く男たちを残して馬車は走り出した。馬車を見送ってお頭が袋を確かめると、小屋を建てるのに十分なお金が入っていた。袋の紋章にももちろん見覚えがあった。国旗に描かれている剣と魔術師の杖のマークだった。「あの人たち、うまくやっていけるかなぁ」 馬車に揺られながらヒカルがぽつりとつぶやくと、ハワードはふわりとほほ笑んで答えた。「たぶん、大丈夫でしょう。あれだけ意見が言い合えるグループなら、誰かのいいなりと言うこともないでしょうし。」「そうですよね。大人が興味を示さないというのは、逆に言えば自分たちでやり切ってしまえるチャンスってことですもんね。大人の都合で振り回されるのは、いつだって子どもだもの。いい機会になるといいな」 最後は独り言のようにつぶやく顔は、王女ではなく、心細げな少女のようだった。向いに座っていたハワードは、そっと席を移ってヒカルの隣に座ると、「心細い時は、いつでも私を頼ってください」と細い肩に手を伸ばしかけて、微笑むだけに留めた。 西の果て、ライオネル子爵領に到着したのは、陽がだいぶ傾いたころだった。街中には人があふれ、みな一斉に自宅へと向かっている。この領地は、ビジネス街と住宅街が切り離されており、朝夕のラッシュは平日の定番の様だ。 ハワードは早々に宿を見つけて馬車を止めると、みんなを促してレストランに向かうことにした。宿を出ると、さっきまで街中にいた人々が嘘のように消え去り、レストランも閑散としている。「平日に外食する人は少ないからね」 店長が朗らかに笑っている。この辺りはライオネル子爵が開発した移動装置や通信機器の製造が主な産業だ。多くの人が会社勤めなので、平日の夕方はいつもこんな感じだと言う。「お客さん、週末じゃなくてラッキーだよ。週末はとんでもない混雑ぶりだし、よその土地の人には冷たい土地だから飯にありつけないところだったよ」 眉を下げて笑いながら言う店長は、やはりほかの土地からきた人間だった。 翌朝、外が騒がしいので窓から覗いてみると、街中で号外が配られていた。宿の人間に聞くと、ライオネル子爵令嬢が婚約したという。「あら。先日あった時はそんなこと言ってなかったですのに」「お祝いがてら挨拶に行ってみましょうよ」 不満げなベスもヒカルに言われると承諾するしかない。 すぐにライオネル子爵家に連絡を入れると、先日会った老執事が歓迎するという。 ハワードにお使いを頼んで、ベスには身支度を手伝ってもらい、早々にライオネル子爵邸を訪ねたヒカルたちは、調度品のない会議室のような広い部屋に通された。例の老執事がやってきて恐縮した様子で対応する。「主は先ほど工場で何かトラブルが発生したということで、帰ってくることが出来ないようです。本当に本当に失礼な事とは存じますが、お許しください。じき、フレイヤ様がお見えになります。」 執事が退室してしばらくすると、フレイヤがやってきた。眉間に深いしわを寄せてばつの悪い表情を浮かべている。「この前は、失礼しましたわ。ちょっとタイミングが悪かったのですわ」 言い訳するフレイヤの傍で、執事が柔らかく微笑みながらみなに紅茶を配っていた。ベスは呆れたような盛大なため息をついている。そんな様子を楽しげに見ていたヒカルが、そっとフレイヤに歩み寄ってその手を取った。「おめでとうございます。街で号外が出ていましたよ。婚約されたのでしょ?」 笑顔のヒカルに大きな花束を渡されて、フレイヤは目を見開いて驚いていた。「あら、あの…嫌味を言いに来たのだと思っていましたのに」「ほほほ、何を言ってるの。おめでとうを言いに来たのよ。相手はどんな方なの?」 ベスが笑って言うと、柄にもなく恥ずかしそうな顔をしたフレイヤが、こまごまと説明する。そのしぐさや表情が乙女らしくて、4人は思わずニヤニヤしてしまうのだった。「もう、笑い事ではないですわよ!次はあなたの番でしょ?」 フレイヤがベスに突っかかると、ベスも少し頬を赤らめて「そうね」と肯定した。後ろでリッキーがむせている。ヒカルとハワードは思わず声を出して笑ってしまった。それにしても、とフレイヤは不思議そうにヒカルを見る。「こんな少人数でお忍び旅とはどういうことなのですか?こんなところに来てもなにもありませんわよ」父親は研究ばかりに夢中で、領土については専門の執事が取り仕切っているから、面白みのない領土になっているという。自分が貴族らしい服装や振る舞いをするたび、無駄遣いだと文句を言うのだとも。「フレイヤさん、ご結婚されたら是非、領土の管理はあなたがやるべきだと思います。その前には、私のように、少しお忍びで領土内を散策されることをお勧めします。普段見えていないことがきっと見えてきますよ」ヒカルの言葉には実感がこもっている。つんとそっぽを向くかと思われたフレイヤは、意外にも真剣に聞いている。「実は、私も領土経営については気になっていたのです。いろいろ父には声を掛けてみるのですが、専門家にまかせておけ、の一点張りで。せっかくなので、彼と相談してみますわ」「領土経営は領民との信頼関係も重要よ。いつぞやのパーティーの時みたいな真似はやめるべきね。」 ベスの一言に、バツの悪いフレイヤは横を向いた。ヒカルたちが異世界日本からこちらの世界にきた帰還パーティーでは、王女の控室まで乗り込んできて、ベスより自分の方が侍女に相応しいと豪語したという黒歴史を持っている。「だけど、あの行動力は認めましてよ」「恐縮ですわ。また…、相談に乗っていただけないかしら。フォリナー侯爵様の手腕はこちらにもとどろいていますわ。私もお手本にしたいですもの」帰還パーティーの頃からは考えられないほど、フレイヤは大人になっていた。つづく
May 14, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第6章 宝石の原石たち 1
第6章 宝石の原石たち 再びいつもの服装に戻って、4人は旅を再開する。次は西の領土へと向かうのだ。西の果てまでは5日を要する。小川のほとりで休憩したり、木の実を取ったりしながら進んでいく。この辺りは人家のないエリアだが、食べられる果実が多く生っている「それにしても、ヒカルったら、ずいぶん言うようになったわね」「言い方はアレだけど、言ってる内容はなかなかいいアイデアだったんじゃないか?」 馬車の御者席でリッキーとベスが話している。「確かにね。なんだかとってもヒカルらしくて面白かったわ。それに、確かにあの領地経営ではだめよね。身分に固執しているくせに、どんどん先細りして、将来爵位返還もありそうな感じだったわ。」「はぁ、俺もがんばらないとなぁ。」「あら、リッキーには私が付いているでしょ?」 二人は顔を見合わせて笑った。シュルツ侯爵領での出来事は、ベスの心配事を吹き飛ばすに余りあった。そうよ。爵位になんてこだわる必要はないわ。シュルツ侯爵を見ていて気が付いた。自分の両親はあんな考えをしていない。きっと分かってくれる。 そのころ馬車の中ではお説教が続いていた。「ヒカルは自分の立場が分かっていますか?あなたはミト・コーモンじゃないんですよ!」「ミトコーって、なに?」「あれ?知らないのですか?日本の有名な時代劇ですよ。偉い人が身分を隠して旅をしてその先々で事件を解決する奴ですよ。ほら、スケサン、カクサンとか、カザグルマノヤヒチとか出てくるのです」「知らない…」 ハワードは自分が相当な日本マニアであることに気付いていなかった。「そ、それは失礼しました。だけど、もし逆恨みされて御身が狙われでもしたら大変です」「分かったわ。じゃあ、おとなしくしています。だけどさ、シルベスタ様は私の自由にしていいんだよって、言ってくださったのよ」 下を向いて口をとがらせているヒカルはまだまだ納得できていない。その時、急に馬車が止まった。外で荒っぽい男の声がしている。「命が惜しかったら、そのまま馬車を置いて立ち去れ!」「盗賊か」 リッキーが馬車を降りて身構える。ベスが馬車の扉の前に立ちはだかって二人に事情を伝えた。「ほう」 最前線にいる男が、リッキーの構えを見てにやりと笑う。その後ろで腰が引けたようになっている男が心配そうに言う。「お頭、こいつ、騎士なんじゃ…」「バカ言え、こんなところに騎士なんぞ来るはずがない。それに俺より背が低い」 リッキーはばかばかしくなって、構えていた剣を下ろして言う。「お前たち、どういう了見でこんなことをしている?」 凄みの利いた声に、お頭以外はみんなすっかり怖気づいてしまった。リッキーは早々に剣を鞘に戻してため息をついた。「おい、お前たち、ビビッてんじゃねぇ!」 啖呵を切ったところで隙だらけのお頭の腕をひねり上げ、剣を落としてリッキーがすごむ。「お前ら、いつもこんなことをやっているのか? ほかにやることはないのか?」「な、なんだよ。頭のいい奴ばっかり良い思いしやがって。俺たちだって普通の人間なんだ。仕事をもらえないなら、こうやってでも生きていくしかないだろう」 年若いお頭は、手を離されたとたん座り込んですねたようにぼやく。他の者たちもしょぼくれた様子で座り込んでいた。 外の様子が落ち着いたので、ヒカルたちが顔を出した。「ねえ、この辺りはどこの領土になるの?」「ここらあたりはヴァンサン男爵の領土だよ」 後ろで座り込んでいた一人が答えると、お頭が拳骨を食らわせた。「言うなよ!」「なんだよ。いいじゃないか。本当の事だもん。こいつはヴァンサン男爵の次男なんだ」 内輪もめを黙って聞いていたベスが不思議そうに尋ねた。「ねえ、ヴァンサン男爵って、科学の研究が熱心だって聞いてたけど、そうじゃないの?」 男たちは顔を見合わせて「そうだ」とそれぞれ頷いている。「じゃあ、それを手伝えばいいんじゃないの? 自分の親の領地でこんなことしたらまずいでしょう?」「ああ、もう!悪かったな!俺は兄貴みたいに賢くないから、役に立たないんだとさ」「僕たちは、ライオネル子爵の試験に落ちたんだ。試験に合格した者だけが仕事に就ける。あとの人間は自分たちでなんとかしろって」「大人の人たちは、あなたたちのしていることをとがめないの?」 ヒカルの質問にお頭がふっと笑った。大人は仕事が忙しくて誰も出来の悪い子供に興味がないのだという。「ま、そのおかげで自由気ままにやってるけどな。ここの森には食べられる果物がたくさん育ってるし、川魚もうまい」「これ、あげるよ。さっき採ってきたやまぶどうさ」 後ろにいた幼さの残る少年が山ぶどうを差し出した。リッキーが用心深く受け取り、一粒毒見をして、ヒカルに渡した。「大丈夫」「じゃあ、みんなで味見させてもらうね」 ヒカルはベスやハワードにも分けて、山ぶどうを堪能した。「こんなにおいしいものが採れるなら、よその領地に売りに行ってみたらどうですか? 今までめぐってきたどこの領土にもこんなにおいしい山ブドウはなかったですよ」「そうよね。他には何が採れるの?」 おいしそうに山ぶどうを食べながらヒカルが問う。「オレンジが採れる時期もあるし、あけびやほかの木の実も採れるよ」「もうちょっとしたらニジマスが釣れるんだ。あれを焼いたのが最高にうまいんだ」「山の奥の方に行ったらすももの木もあるよ」 気が付くと、みんなヒカルたちを囲んで、近くの地べたに座り込んでわいわい話し出す。つづく
May 13, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第5章 偽物 2
もやもやしたまま4人は食事を終えて早々に宿に戻ってきた。馬車で着替えて宿の入り口に一歩踏み入れると、従業員が慌ててやってきて裏口へまわれという。領主さまが王女にあいさつに向かったとのことだった。ベスは、ヒカルに頼んで再び令嬢らしくドレスに身を包み、自分も王女とやらに挨拶したいと言い出した。そして、ベスは侯爵令嬢らしく、堂々と落ち着いた所作でロビーへ現れた。「こちらにシュルツ侯爵様がお見えだと伺ったので、ご挨拶にきました」「シュルツ様はただいま王女様にご挨拶に行かれましたので、お待ちくださいませ」 従業員は焦った様子でベスを止めたが、「そうですか」と引き上げるふりをして、ベスは最初に案内された部屋に乗り込んでいく。 ドアをノックすると執事が現れ、今は面会できないと断ろうとした。しかし、ベスの顔を知っていた執事ははっとして、対応に困ってしまった。「そう、王女様というのはフレイヤのことだったのね。そこを通していただくわ」 ちらっと後ろに控えるヒカルを気遣いながらも、ベスはこぶしを握り締める。「どなたかしら。突然部屋にやってくるなんて失礼な方ね」 令嬢が鋭く言う中、ゆっくりと姿を現したベスは、にっこり微笑んで見せた。「お久しぶりですわね。シュルツ侯爵様。そして、フレイヤ・ライオネル子爵令嬢」「え?」 支配人が驚きすぎて固まってしまった。「おや、これは、これは。フォリナー侯爵家のご令嬢ではないですか。王女様と旅をされていると聞いたのですが、こちらの方ではないのですか?」「あ…。わ、私は別に王女に成りすましていたわけじゃないわ。こちらの人が勝手にきめつけていたのよ!ホントに迷惑だわ!」 支配人や従業員が混乱する中、二人のにらみ合いが続く。「ベス、もうその辺にしたら? この土地のことはよーくわかったから」 後ろから侍女の服装のヒカルが言うと、シュルツ侯爵とフレイヤが真っ青になった。「お、王女様!どうしてこんなところに!」「お久しぶりですね、フレイヤさん。私は王国の事を何も知らないから、勉強させていただいているのです。あなたも旅を? 執事さんお一人つけているだけだなんて、旅慣れていらっしゃるのですね」 フレイヤは真っ赤になって下を向いてしまった。「これはいったいどういうことだ。冗談ではないぞ」 焦るシュルツにヒカルは穏やかに言う。「こちらの領土に来てから、いろんなものを見せていただきました。今日はこのような服装ですし、明日、改めてお目にかかっても?」 シュルツは分かりましたと平伏して、その場を退散した。「フレイヤ様、この度はよい勉強になりましたね。多くの方との出会いは人生の糧になります。さて、じいは腰が痛うございます。明日には領土に帰りましょう」 執事が穏やかに言うと、フレイヤは分かったと素直に呟いた。「このお部屋は王女様に使っていただいて、私はほかのお部屋に移ります。支配人、指示を」 フレイヤに言われて、我に返った支配人が従業員に指示を出す。かくしてヒカルたちは元の部屋に戻り、フレイヤは一泊しただけでそそくさと帰っていった。 宿を出立する朝、廊下ですれ違ったハワードに、ライオネル家の老執事が言う。「本当に素晴らしい王女様ですね。うちのお嬢様にも温かい言葉をかけてくださって。これで素直に家出を解消できそうです」 その頃、ヒカルはベスに手伝ってもらって身支度を整えると、シュルツ侯爵家に出向いた。予想通りではあったが、門からずらりと執事や侍女たちが並び頭を下げる。その間をゆっくりと通り過ぎると、その先にシュルツが満足げに出迎えていた。「ヒカル王女様、本日はご機嫌麗しく、我が邸宅にお越しくださって誠にありがとうございます。さぁ、どうぞこちらへ。王女様のために特別室をご用意いたしております」 それを無表情な目で眺めていたヒカルは、おもむろに語りだす。「いえ、結構です。シュルツ侯爵様、ご存知の通り私は王女の肩書をもらいましたが、異世界から突然転移させられてきた小娘にすぎません。もとより王位を継ごうとも思っていませんから分かっていないと笑われてしまうかもしれませんが、一言お伝えしておきます。先の大きな災害は、多くの民が身分制度を緩めて怠惰な生活をした罰を与えられたのだと、こちらの領土の方々が口をそろえておっしゃっていますね。これにはいささか抵抗を覚えました」「何か、王女様にご迷惑をおかけしたのでしょうか?」 シュルツは身を乗り出して尋ねる。名前さえ聞けば直ちに投獄しそうな勢いだ。「“王女”には迷惑などかけていませんよ。皆さん身分にはとても敏感で。ですが、身分に気を取られすぎではないでしょうか。職位のない旅人にはとても冷たい土地ですね。」 ああ、そんなことかとでも言いたげなシュルツは、苦笑いを浮かべて答える。「お言葉ですが、雪深いこの地方では、お金のない旅人に施しをするほどの余裕がないのですよ。産業といえば山岳地帯の天然石の発掘ぐらいですからね。」「その天然石の発掘を一部の貴族が牛耳っているということなのね。そんなに雪深いなら、スキーやスノーボードの施設を作ったら観光客も見込めるのではないかしら。貴族だけではなくて、一般の人も来るようにすれば、土産物も売れるし、レストランも流行るでしょう。量の限られた天然石にしがみついていては、先が知れていると思うわ。まぁ、これは小娘の思い付きです。お父様に声を掛けたら、もしかしたら侯爵様のお手を煩わせずに国営のレジャー施設になるかもしれないわね。その時は、従業員として侯爵の領民の貴族以外を使う様にさせていただくわ。威張るばかりで役に立たない貴族なんて、使えないものね。ふふふ。侯爵様、あまり頭が固いと時代に取り残されますよ。」 シュルツの物言いにうっぷんをためていたヒカルは、とうとう言葉遣いも態度もすっかり王女らしさを失くして、言いたいだけ言うと、「見送りは結構よ」と言い放って、結局一歩も侯爵邸に入ることなくその場を後にする。ハラハラしながら後ろに控えていたハワードが胃を押さえていた。つづく
May 12, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第5章 偽物 1
第5章 偽物 大雨から3日が経った。ハワードの怪我もヒカルの体調も整い、4人は荷造りを始めた。次は北の領土を目指す。全体に気温の低い北の領土は、冬、雪深くなるので、温かい気候のうちに見ておかなければならない場所だ。 北の果て、シュルツ侯爵領に入ると、まずは宿をとることにした。いつものようにハワードが出向くが、どこも受け付けてはくれない。「ここもダメでしたね」「どうしてかしら。満室でもなさそうなのに」「どうも身分が高くないと泊められないと言われるのです。ヒカル、どうされますか?身分を明かしますか?」 それでは本当の姿を見ることは叶わないだろうとヒカルが考えていると、リッキーが思い付きで言う。「じゃあさ、ベスに侯爵令嬢として行ってもらおう。俺が付き人になるよ」 ベスは困惑気味だったが、とりあえずは宿を取りたい。ヒカルに手伝ってもらってドレスに着替えると、しかたなくリッキーを連れて受付へと出向いた。「こちらに泊まりたいのですが、お部屋はあるかしら」「失礼ですが、ご身分は?」「私はフォリナー侯爵令嬢 エリザベスです。それがなにか?」「いえ、失礼いたしました。それでは一番良いお部屋をご用意させていただきます。」 馬車を止めて、3人がベスに追いつこうとすると、途端にホテルマンに止められる。「あなた方はどちらの方ですか?」「私はフォリナー侯爵令嬢の侍女です」「あ~、それじゃあそこの通路を右に曲がったところに従業員の部屋があるから、そっちに行ってな」「あら、この人たちは私の旅の仲間なのよ。お部屋に入れてあげて」 ホテルマンは目を見開いて、それから呆れたように笑ってみせた。「いえいえ、この宿は高貴な方のみにご利用いただいております。だいたい、平民が貴族の方々と同じ部屋を使うなど、ありえないことです。この北の領土では、きちんと身分制度を守っているのです」 すっきりと胸を張って自慢げに言うホテルマンに、あきれ果てた。「分かったわ。でも今後の打ち合わせをしたいので、席を外していただけるかしら」 ベスは極力怒りを見せないように言うと、ホテルマンを退室させた。「随分変わった考え方ですね。」「う~ん、私、この土地では侍女のふりを通して、この土地について調べたいわ。」 ベスは承服しかねるといった顔をしていたが、仕方なくヒカルのドレスを借りて、ヒカルを侍女として従えて夕食をとり、部屋に戻ってきた。そして、ヒカルたち3人は下働きが集う店で食事を摂ることになった。 ホテルの並ぶ大通りをわきに入って、平民が暮らすエリアを歩く。大通りとは雲泥の差の古びた街並みが続いている。道行く人に、この地域は以前から身分が厳格に守られるのかと問いかければ、当然そうだと返事が返ってくる。「北の領土はあの震災でもほとんど被害がなかったからな。魔素が流れたから仕方なく移動してきたが、まだ向こうにも家が残っているよ」「ああ、サルビィの丘を見てきたのか。あの辺りは全部流されただろう?規制が緩く怠惰な生活をしていた罰が当たったんだよ」「わしらは領主さまのおかげでひどい目に遭わずに来れたんだ。旅の人も、くれぐれも失礼のないようにな」 周りを見渡すと、この土地には高齢者が多い。災害の生存率が高かったことを物語っていた。 翌朝、宿の従業員たちがあわただしく何かを用意しているのが見えた。ハワードが店員に聞くと、王女様がこちらに向かっているというのだ。「ヒカル王女さまだよ。王太子殿下のお嬢様だ。これは大変光栄なことだ」 どうやらベスが名乗ったことで、シュルツ侯爵がフォリナー侯爵家に連絡を取ったらしい。その時、派手なドレスに身を包んだ令嬢が大きな馬車から降り立ってきた。「今日はこちらに泊まります」 令嬢がちらっと視線を投げかけると、年老いた執事がすぐさま宿泊代金を差し出した。「こ、これは。多すぎます。すぐにお釣りを」「いいえ、結構よ。一番良いお部屋をお願いね」「はっ!すぐにご用意いたします」 従業員は慌てた様子でベスの部屋へと向かう。執事が受付に記帳しようとするが、こちらは支配人が丁重に辞退した。ぽかんとその様子を見ていた3人だったが、突然従業員に呼ばれてベスの客室に行けと言われた。高貴な方が見えたから、部屋を譲れというのだ。呆れながらも部屋を移った4人はどんな人物が来たのかしばらく様子をみることにした。 客人はともかく、宿側はどう考えてもヒカルと勘違いしているようだ。最高のもてなしをと、それのためにはほかの客など邪魔だと言わんばかりだった。夕食を宿内のレストランで摂りたいと言えば、王女様のためにレストランを使うので、外に行けという。4人は、馬車の中で平民の服装に着替えて下町の古ぼけたレストランに入った。 やっと落ち着いて食事ができるとほっとしたのもつかの間、乱暴にドアを開けて、店内に男たちが入ってきた。酒が入っているのか大声で乱暴にしゃべり、ずけずけと好きな席に陣取った。隣にいるヒカルたちに目をやると、ニヤニヤしながら近づいて酌をしろと言い出す。「見ず知らずの人間に酌をしろとはどういうことだ」「ほお、平民のくせにずいぶんな口をきくじゃねぇか。俺はこれでも男爵家の人間だ。言うことを聞け!」 胸倉をつかまれて、一瞬剣に手をやったリッキーをハワードが止めた。「失礼いたします。こちらにいらっしゃるのは、マイヤー子爵のご令息です。見聞をひろげるために身分を隠して旅をしているのです。お戯れはその辺りでおやめください」 執事然とした振る舞いに、男たちは驚いて勢いも一気に消え去った。途端に店内もしんと静まり、店主が慌ててやってきた。「も、申し訳ございません。大変な失礼をいたしました。我々のような店ではお口に合うものができるかどうか…」 そういいながらも、頼んでもいない料理が次々運び込まれる。「さっきからいただいていますが、こちらの料理はおいしいですよ。どうしてそんなに貴族におびえるのですか?」 リッキーが問いただすと、店主は遠慮がちにシュルツ侯爵の命令だと答えた。「王国では身分制度が緩くなり、生活が乱れている。以前のような災害が再び起こっては大変だとおっしゃって」つづく
May 11, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第4章 本当の気持ち 3
リッキーは、落ち込むベスを励ましながら、すぐさま持ってきていた魔石を使ってシルベスタに連絡を取る。ヒカルが魔素のないサルビィの丘で、天候を操ったと聞いたシルベスタはあきれ果てていた。「仕方ない。しばらく寝かせてあげなさい。2日ほど眠ったら復活するだろう。君たちも危険のないように気を付けて、2日間は休暇だと思ってゆっくりしたまえ。それで、ハワードは大丈夫なのかい?」「足をひねってしまって、シップしています。あの様子だと、激流に飲まれそうになったんだと思われ、疲労が激しいです。こちらも2日もすれば良くなるかと。それより、ん~なんていうか、いろいろあって、あ~なんていうか…とにかくじれったい感じです」 リッキーの説明に、シルベスタはブハッと噴き出して大笑いした。「リッキー、それ、ものすごく分かるよ。まったくあいつは生真面目なんだよなぁ。まあ、もう少し様子を見よう。」 シルベスタはのんきにそういうと、通信を切ってしまった。 ヒカルとハワードがぐっすり眠っているので、リッキーとベスは二人で夕食の支度を始めた。「私、もう少し魔術の勉強しようかと思うの。あんなに魔力のあるヒカルでも、治癒魔術には向いていないっていうし、私の家系なら、治癒魔術も適正はあるらしいから…」「無理はするなよ。今回の事を気にしているのなら、気にしなくていいよ。どんなにこっちが気を使っていても、ヒカルならきっとやらかしていたよ」「そうかしら。だけど、やっぱりリッキーが怪我したときとか、役に立ちたいもの」 リッキーは途端に真っ赤になって、夕食にかじりついた。 その頃、馬車の中でハワードが目を覚ました。くじいた足は熱っぽいが、ずいぶん痛みは落ち着いていた。自分でも無茶をしたと反省する。あのまま雨が降り続いていたらあるいは…。それにしても、これを発掘できたのは良かった。内ポケットに入れていた物を取り出してほっとする。 ガウェイン王の前の王は豪快な王様だったという。決して国民を蔑ろにしていたわけではないが、貴族との交流も華やかだった。その象徴のような代物が、今ハワードの手の中にあった。大粒の宝石を贅沢にあしらった王冠だ。前回、サルビィの丘で馬車を奪われた後に助けてくれたあの老人が言っていたことが頭をよぎる。アランなら、そして、その右腕にヒカルがいるというのなら、きっとそんな国にはならないだろう。これは、その時の戒めの象徴になるだろう。しばらく眺めていた王冠を片付けていて、ふいに薬箱の向こう側に人がいることに気が付いた。静かで、身じろぎもしないそれは、まるで人形のようだった。「え? …ヒカル? ヒカル!まさか…」 頭の中が真っ白になった。色素を失くした顔にはいつもの表情がなく、息すらしていないかのように横たわっている。とっさに体を起こして、足の激痛にたじろぐ。それでも気になって、足を庇いながらそっと近づき、その腕をつかんだ。細い手首に脈が打っていることが分かると、安堵から座りこんでしまった。そして、確信した。―ああ、やっぱり。やっぱりヒカルが死力を尽くしてくれたんだ。―あのまま雨が降り続いていたら、自分はきっとあの濁流に飲まれていただろう。足を掬われ、木の枝にしがみついたあの瞬間、まだ死にたくないと心から思った。まだ、自分はちゃんと想いを伝えていないと。「ヒカル、私はとんでもない愚か者です。震災の跡の大雨の話は先日あなたに講義したばかりだというのに、自分がそれに対処できていなかった。それなのに、こんな魔素のない土地で、あなたは倒れてしまうほどに力を使って助けてくれたのですね」ヒカルの手を両手で包むと、自分でも驚くほどの震えるようなため息がでた。「お姫様を目覚めさせるのは、王子様のキスよ」 不意に声がして、ハワードは驚いてヒカルを見た。ほんの少し頬に赤みがさしている。ハワードは沸き起こる喜びをどうしていいのか分からなくなって、ヒカルの唇にキスを落とした。「んん~~!ほ、ホントにするとは思わなかったー!」 慌てたヒカルが目を開けると、真っ赤になったハワードが覆いかぶさるように抱きついてきた。「ヒカル!ヒカル!気が付いたのですね!良かった。ホントに良かった」「ハワードさん、苦しいよぉ」 バシバシと背中をたたかれて、やっと我に返ったハワードは、照れ臭そうに体を離すと、リッキーとベスが顔を出した。「ヒカル、気が付いたのか?」「良かったわ。どうなる事かと思いました」「ごめんね、心配かけて。でも、まだ魔力が十分じゃないみたい。体が重くて動けないわ」 ベスから、もう2日寝てないとだめだと告げられ、素直に従った。二人分の食事が運ばれてくると、ハワードはくじいた足を引きづりながらも、甲斐甲斐しくヒカルの世話をする。「起きられそうですか? それとも、横になったまま召し上がりますか?」 ハワードに抱きかかえられながら体を起こしたヒカルは、そんなハワードを見てふふっと小さく笑う。そして、ぽろぽろと涙をこぼした。「ヒカル? どこか痛いのですか?」「ううん。ハワードさんがいつも通りだなぁって思って。ちゃんと元気にここに戻って来てくれて、本当によかったなぁって思って…」「ヒカル…。私は、何があっても必ずあなたの元に戻ってきます」 ヒカルの手を取り、膝をついて真剣なまなざしのハワードに、ヒカルもゆっくりと頷いた。つづく
May 10, 2022
コメント(0)
-
REALIZE2 第4章 本当の気持ち 2
テントの中で外の様子をうかがっていたヒカルだったが、いつまでも降りやまない雨にとうとう耐えられなくなって、丘のふちまで様子を見に行った。テントの中でもうるさく感じていた雨音は、傘を差して外に出てきてもとどまることなく続いている。ぬかるんだ丘は一足踏み出すごとに、草の中からじわっと雨水があふれ出してくる。それさえも、気にならないほどの大雨だ。昨日見下ろしていた丘のふちまで到着したが、ハワードが帰ってくる様子はない。何かあったのだろうか。胸の奥でずしっと嫌な重みを感じた。すると、ドドドっと今までとは比べ物にならない圧倒的な水音が始まった。「これは!!」昨日訪れた山の上の池の事が脳裏をかすめ、全身に鳥肌が立った。見る間に谷の上流から水煙が上がっている。途端に、過去の豪雨の喧騒が思い出された。「ハワードさんが危ない!!」 とっさに持っていた傘を振り払い、ヒカルは両手を組んで意識を集中し、風を起こす術を発動した。ここにある魔石はもしもの時に残しておきたい。ヒカルは自分の中にある魔力を出来るだけ引き出す様に意識した。「シルベスタ先生に教えてもらった一点集中の技、ここで出せないでどうするのよ!」 胃の奥がキューンと縮み上がるような恐怖と叩きつけるような大粒の雨に怯みそうになる自分にけしかける。途端に突風が噴出し、雨雲が流れ始めた。ヒカルの額には冷や汗が流れる。歯を食いしばっているが、雨雲は重く、なかなか途切れてくれない。「まだよ。まだ終わってない。お願い、雨雲を吹き飛ばして!」ありったけの力を込めて、魔力を放出した。 その少し前、ハワードは谷間の村のあとに辿り着いていた。山の斜面には崩れかけた家がそのまま放置されているが、谷に降りてしまうと、そこに人々が暮らしていたのが信じられないほどに何もない状態だった。安全なようならヒカルを連れてこようと考えていたハワードだったが、どうやら雲行きは怪しい。踵を返したところで大粒の雨が降り出してしまった。「まずいな」 獣道を登っていると、斜面に半分埋もれた物を見つけた。「これは…」 ハワードはとっさにそれを持ち帰らなければと思い立った。近くにあった瓦礫を使って掘り起こそうとするが、木の根が回っているのかなかなか掘り出せない。そうこうしているうちに川が突然増水して、ハワードの足元まで這い上がってきた。焦る気持ちを抑えて、懸命に周りの土砂を掻き出し、取り上げたところで水かさが一気に上がってきた。「うわぁ!」 恐ろしい勢いの流れに足を掬われ、とっさに近くの木の枝に手を伸ばす。近くに会ったはずの足場はあっという間に流され、あと一足踏みあがりたいところが踏ん張れない。その間にも、水の勢いは強くなり、ともすれば体ごと持っていかれそうなってきた。嫌だ、まだ死にたくない!ハワードは渾身の力を込めて腕の力だけで体を起こし、水の流れから体を持ち上げた。そのまま大きな木の枝を伝って、丘の縁まで辿り着くと、そこで意識を失ってしまった。 さっきの豪雨が嘘のようにピタリとやんで、ベスとリッキーがそれぞれのテントから抜け出して様子を見に来た。空はぽっかりとサルビィの丘のあたりだけ、青空をのぞかせていた。「ハワードさん、大丈夫だったかしら」「うん、俺も気になってたんだ。ちょっと見てくるから、ヒカルの事、頼んだぞ」 リッキーがぬかるんだ獣道を慎重に下っていく。その後ろ姿を不安げに見つめながらベスが声を掛ける。「リッキーも気を付けてね!」 リッキーが谷間を降りていくと、小川だったところは先ほどの雨で水かさが上がって、ドウドウと激しい流れになっていた。周りを見渡していると、大きな木の根元に人が倒れているのが見えた。「ハワードさん? おい!大丈夫か?」 リッキーの声に気が付いたハワードだったが、立ち上がろうとすると足に激痛が走った。「すみません、足が…」 リッキーがハワードの足に触れると「ううっ」とうめくような声が漏れる。「腫れてはいないけど、くじいてるな。肩を貸すよ。それに、全身びしょぬれじゃないか。早く着替えないと風邪をひくぞ」 リッキーはハワードに肩を貸して、なんとかベスのいるテントまで戻ってきた。「リッキー、ハワードさんが見つかったのね。良かった。うわぁ、ずぶ濡れね。早く着替えた方がいいわ。そのままだと風邪をひいてしまうもの」「ひ、ヒカルはどうしていますか?」 ハワードはリッキーに運ばれながらもヒカルが気になっていた。あんな大雨が急にやんでしまうのはおかしい。以前アランから、ヒカルが晴れのおまじないをすると聞いていたハワードには、嫌な予感がしていたのだ。「いや、まずは着替えて怪我の治療だろ。こっちでシップするから横になっててくれ」 リッキーに促されて馬車に入ると、ベスがタオルを持ってきた。リッキーに手伝ってもらいながら着替えを済ませると、そのままソファに横になるよう促された。疲れが出たのかハワードはそのまま眠ってしまった。その頃、ベスは焦っていた。リッキーがハワードを探しに行っている間に、ヒカルのテントを見に行ったのに、テントには誰もいなかったのだ。周りを探しているうちに、リッキーがハワードを連れて帰ってきたのだ。ハワードのことをリッキーに任せて、すぐさま丘のまわりを探しに行くと、リッキー達が戻ってきたのとは反対の方角に倒れてずぶ濡れになっているヒカルを見つけた。「ヒカル!!」魔力を著しく消耗してぐったりしているヒカルは、呼びかけても反応はない。「魔力がほとんど感じられないわ。ヒカル、気づくのが遅くなってごめんなさい」ベスはすぐさまずぶ濡れのヒカルを抱きかかえてテントに連れて行くと、濡れた服をはぎ取り、丁寧に体を拭いて着替えさせた。そして、リッキーに頼んでハワードと同じく馬車の向い側のソファにそっと寝かせた。一度に二人も倒れてしまったことで、ベスはしおれ切っていた。もっと、何か対応できたのではないか。他に対策が採れたのではないかと自分を責めながら、向かい合わせのソファの間に、薬品の入ったバッグをうずたかく置いて対応に備えた。つづく
May 9, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第4章 本当の気持ち 1
食料を買い込み、リッキーとベスが戻ってきた。ここから魔素のない東の果て、サルビィの丘を目指す。険しい山道をゆっくりと昇っていくと、緩やかな丘に辿り着いた。4人は馬車を降り、周りの景色を確かめる。「この辺りがサルビィの丘跡地です。案外険しい地形ですね」「お母さまに聞いたら、生き残って今のアイスフォレスト王国にいる大人は、大抵このサルビィの丘の近くに住んでいたそうですよ。この先の谷間にあった集落は全部ながされてしまったそうです」 ベスの説明を聞いて丘のふちまで進んでみると、ごっそりと足元の土が掻き取られたようになっている。これでは谷間にいた人々はひとたまりもなかっただろうとヒカルは急に足元に震えを感じた。「この先を進むと以前の避難所跡があるそうです。行ってみましょう」 ハワードに薦められて、ここからは馬車を置いて進む。魔石で結界を張ることも忘れない。木々が茂って木漏れ日を落とす山道をもくもくと歩き出す。馬車を止めた場所からずいぶんと上がってきた。ヒカルが振り返ると、緑が茂る中にミズキやヤマボウシの花が見えた。大きな災害があったなんて想像もできないような美しい景色だ。「さあ、着いたぞ。ここで一息入れよう」 リッキーの声に視線を戻せば、目の前にはきれいな池が広がっていた。「わぁ、きれぃ…」言いかけたヒカルは思わず口元を手で抑えた。池のふちに不自然に積みあがっている木片に気が付いたのだ。それは、どうやら避難所だった建物の瓦礫らしく、30年という年月よって、朽ち果て、つる草に巻かれ、少しずつその姿を失いつつあった。 不意に、ヒカルの耳に当時の喧騒が聞こえたような気がした。地震で壊れた家屋を立て直そうとしていた人々に豪雨と土石流が襲い掛かる。地面に叩きつけるような雨音、とどろく雷鳴。避難を促す叫び声さえかき消すような川の激流。ここには、懸命に生きようと奔走した人々が確かにいたのだ。心臓がドクンと音を立てる。「ヒカル、大丈夫ですか?」ハワードの声で、倒れそうになっていた自分に気が付いた。 ベスがシートを広げ「こちらへ」と促す。シートに横になって呼吸を整える。水面を渡る風に当たると、先ほどの恐怖を覚えるような喧騒は霧散した。あれはいったい何だったのだろう。「何か感じるものがあったのですね」 気が付くと、ハワードが背中をさすってくれていた。「ええ、この国の人々の声が、一斉に頭になだれ込んだように感じて驚きました。」「やっぱりここは念の強い場所なんだろうな。とりあえず馬車の所まで下りよう。そろそろ日が暮れるし」 リッキーに促されて、4人は馬車を置いた場所まで下りる、馬車からそれぞれの木箱を出し、リッキーはテントを張って、ベスは食事の準備を始めた。ハワードに促されて木箱に腰を下ろしたヒカルは、辺りを見回して大きなため息をついた。この土地はとても騒がしい。たくさんの気持ちが残ったままになっているんだとヒカルは痛感した。「大丈夫ですか? 少しは落ち着きましたか?」「ええ、ありがとうございます。だけど、あんな風に、突然昔の出来事が頭の中に飛び込んでくるなんて、今までなかったので、驚きました」「以前主から聞いたことがあります。その土地の精霊に呼びかけると、昔のことを教えてくれることがあると。だけど、こちらから聞き出そうとしていないのに訴えてくるということは、それほどまでに強い念をもっているんでしょうね。ヒカルや私は異世界から来ているのでこちらの過去には疎いですが、それでも、どこの世界にいたとしても、昔から脈々と人々の暮らしは続いていて、今につながっているのですから、無下にはできないですね」「私、お父さんに頼んで鎮魂の碑を建ててもらおうかと思うの。ここがあったから、今のアイスフォレストがあるんだものね。それから、帰ったら国の地図をじっくり見ようと思います。この国が安全かどうか今一度、確かめたくなりました」「ヒカル、それはいい考えですね」 二人が頷き合っているところに、食事ができたと声がかかった。 翌朝、小鳥のさえずりで目を覚ましたヒカルは、テントを抜け出して大きく伸びをする。すぐ近くの梢に座っていたリスが、慌てた様子で隣の木に渡っていった。カサっと木々の奥で物音がする。目をやると鹿が心配そうにこちらも伺っていた。あんな災害があった後でも、動物たちは暮らしているのだ。「ヒカル、おはようございます。早いですね」「ベス、おはよう。起こしちゃった?」「いいえ、主より起きるのが遅いなんて、侍女失格ですね」 ベスは少し困ったような顔で言うが、そんなことはない!と、ヒカルは心の中で言う。自分が視察に回っている間に、食料調達、衣類の洗濯、それぞれの場所に行く度に荷ほどき、荷造り、全部ベスがやってくれているのだ。ベスはさっそく朝食の準備にかかっている。その頼りになる後ろ姿を見ながら、ぽろりと本音がでる。「ベスはなんでもこなしちゃうから、私は甘えてばかりになってるなぁ。ねえ、ベス。結婚しても侍女は続けてくれる?」「け、結婚ですか?」 声がひっくり返って赤面するベスは、実は自分の将来についてできるだけ考えないようにしようと無意識に逃避していた。「そう、するでしょ? リッキーと。見たいなぁ、ベスの花嫁姿。絶対きれいだよね。」「か、考えてなかったです…。」「そうなの?では、ぜひ前向きにご検討ください。うふふ」 フォリナー侯爵領にいるとき、ベスの両親からリッキーに手紙が渡されたのは、どうやらベスの知らないことだったらしい。ヒカルはふざけた返答をしながらも、ベスに負担を掛けないようにしなくてはと思った。アランと二人で日本に居たときも、何とかやりくり出来ていたのだ。この旅が終われば、住まいも別館に移る。今一度気を引き締めて体制を整えなくては。「はぁ、気持ちいいねぇ。ちょっと散歩に行ってくるね」 ヒカルはこの後のことを考えながら、森の中を散歩していた。 森の奥からザクザクと草を踏みしめる音が聞こえてくる。ヒカルが目を凝らすと、何やら果物を抱えたハワードが戻ってくるところだった。「ヒカル、おはようございます」「ハワードさん、おはよう。その実はなに?」「これは、アケビという果物です。確か私たちのいた世界にもありましたよ。収穫時期は違うようですが」 差し出されたアケビはほのかに甘い香りがしている。テントまで持ち帰ってくると、ベスが木の枝を集めてかまどを作っていた。ハワードは持ち帰ったアケビを木箱に乗せると、上着のポケットから種類の違う果実を取り出した。「こんなのもありました。これは、たぶんザクロでしょう」 そう言って外皮を割ると、中から宝石のような小さな真っ赤な粒があふれ出た。「わぁ、きれい!」 ヒカルとベスは顔を見合わせて喜んだ。一粒口に入れて、ひゃぁ、すっぱい!とはしゃぐ。3人の笑い声でリッキーも起き出した。4人で山の果実を満喫して朝食を終えた。「今日は、谷間の様子をみてみようかと思います。安全が確認できるまで、ヒカルとベスはこの辺りで散策を、念のため、リッキーも彼女たちの護衛をお願いします」 そういうと、ハワードは元王国の庶民が暮らしていた谷間に向かって下っていった。リッキーは朝食のアケビが大層気に入り、もう一度森に行こうと二人を誘った。 人の手が入っていない森は果物も取り放題だ。たっぷりのアケビを収穫してテントに戻ってくると、そろそろ昼食のしたくに取り掛かる。ヒカルも枯れ枝や枯葉を集めて協力していたが、ふいに周りが暗くなって空を見上げた。「あれ?なんだか空模様が怪しいなぁ」 ヒカルの言葉にリッキーも空を見上げる。さきほどまでの澄み切った青空はすっかり雨雲に閉ざされ、続いて嫌な風が吹いて辺りは一気に暗くなり大粒の雨が降り出した。「ハワードさん、大丈夫かしら…」つづく
May 8, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第3章 アクシデントで知る想い 4
翌朝、ヒカルは教えられた平和の丘に行ってみたいと言い出し、4人は馬車に乗り込んだ。ハワードは少し不機嫌ではあったが、反対する理由はない。 ゆるやかな丘を登り頂上近くまでやってくると、美しい山々が遠くに並んでいるのが見えた。途中からは馬車を降りて登っていく。歩を進める度、美しい山々との間には大きな湖があることが分かってきた。きらきらとまばゆいばかりに湖面をきらめかせている。丘の先は断崖絶壁になっていて、その切っ先に小さな祠のような小屋があり、そこにいぶし銀の鐘が下がっていた。その上には不自然なほど高い塔が建っている。 今朝は、どうもヒカルの言動に違和感を感じる。リッキーとベスは時々目を合わせて心配そうにしていた。ハワードも同じことを考えているらしく、どこか戸惑い勝ちだ。「きっとあれがそうだわ。ハワードさん、一緒に行きましょう」 瞳を輝かせたヒカルに手を引かれて近づくと、鐘のそばにはロープが下がっていた。二人でロープを引っ張ると、祠の上につながっていた鐘が次々に鳴りだし、そばで羽を休めていた鳩が一斉に飛び立った。 思いのほか多くの鳩が飛び立ち、羽音に驚いたヒカルがハワードにしがみつく。その小さな肩を、ハワードが庇う様に抱き留めた。後ろで見ていたベスが「うわぁ、なんだか結婚式を見てるみたい」とつぶやいた。 続いてリッキーとベスも鐘を鳴らす。丘の下から吹き上がる風に煽られ、厳かな鐘の音に背中を押されて、リッキーは思わずベスを引き寄せて口づけた。「あ、ご、ごめん。なんだかたまらなく幸せな気分になって」「ううん、私もなんだかすごくドキドキしちゃった」初々しい二人は真っ赤になって、逃げるようにその場を離れた。 停車場まで戻ってくると、小さな子供がヒカルたちを指さしてはしゃいでいる。「あ、さっきのお兄ちゃんたちだ!ねえ、お母さん。あの人たちケッコンするんでしょ?」「ふふふ、きっとそうね。鐘が全部鳴って、鳩が飛び立ったものね。それにとても幸せそうだったわ」「いいなぁ。私も全部の鐘ならしてみたいなぁ」 親子の会話は続いていたが、言われた二人は真っ赤になってそそくさと馬車へと急いだ。「おーい、ちょっと待ってくれ! これは二人への記念品だ。受け取ってくれ」 丘の上の店舗の主人が、愛らしいブーケを持って走ってきた。「あの、これはどういった?」 戸惑うハワードに店主はニヤニヤしながら言う。「あれ、アンタたち知らないで鐘を鳴らしたのかい? あの鐘は、普通は1つか2つしか鳴らないんだよ。全部の鐘が鳴って、そばの鳩が空に舞い上がったら、そのカップルは結婚するって言われているんだ。いやぁ、よく見りゃ美男美女じゃないか。羨ましいねぇ。お幸せにな」 呆気にとられるハワードにブーケを手渡し、その背中をバシバシ叩いて笑うと、店主は元来た道を戻っていった。 困った顔のハワードはそのままブーケを差し出した。「ヒカル、ブーケをどうぞ」 しかし、ヒカルは受け取らない。見る見るうちに眉間に深いしわが入り、ぷいっとそっぽを向いてしまった。「ヒカル?」「…なんでもないです。これは私の心の問題です。今日の講義は欠席します!」 そのあとは、どんなに声を掛けても、ヒカルはハワードと目を合わそうとはしなかった。愛らしい花束は、そのまま水を入れた小さなカップに刺しておくことになった。 それから2日間、ヒカルはハワードの講義を受けず、窓の外をにらみ続けていた。ベスやリッキーが間に入ろうとしても、「自分が悪い」「自分が不甲斐ない」と言うばかりだった。そして、そのまま決闘を受けるため王宮に転移する日がやってきた。心配そうな3人に見送られても、ヒカルはあっさりと転移してしまう。「はぁ~」ヒカルの姿が見えなくなると、ハワードは思わず深いため息をついた。小さなブーケをさしたカップの水を替えながら、物思いにふける。あの鐘が鳴り響いたときの気持ちは不意打ちだった。自分の気持ちを抑えこむのに必死だったというのに、ダメ押しの花束が来て、まぎれもなく動転していた。一体自分はどんな顔をしていたんだろう。その様子を見ていたベスが声を掛ける。「ハワードさんは、あの幸福の鐘がたくさんなったことを不愉快に思っていたの?」「まさか!」意外な言葉に驚くハワードをよそに、ベスは続ける。「女の子って、好きな人がどんな表情をしているかすごく気になるの。たとえそれが照れ臭かったりはずかしかったりしていただけだったとしてもね。ましてや、ヒカルとハワードさんには、立場の壁も年齢の壁もあるから、不安でたまらないんだと思うの。あの子の気持ち、汲んであげてほしいな」「いや、まさかそんな。ヒカルからすれば10歳以上も年が離れているのですよ。私の事なんてなんとも…」 ドカンっと派手な音を立ててヒカルが帰ってきた。こぶしを握り締め、憤懣やるかたないと言った様子だ。「ヒカル!もう戻ってきたの? 魔術師のことはどうなったんだ?」「全部やっつけてきた! なんだかもやもやするから、当たり散らしてきたの」 あまりにも早すぎる帰還に、思わずリッキーが尋ねた。ヒカルは誰とも目を合わせようとせず、ほんの少し唇を尖らせて言い放った。「全員やっつけたのか? それで、王宮は大丈夫だったのかよ」「大丈夫、その辺は手加減したわ。でも、シルベスタ先生に荒れてるなぁって呆れられちゃった。…仕方ないもん。どうせ私は未熟者だもん。気持ちのコントロールなんて、全然できない。」 ヒカルは珍しく馬車のソファに座り込んで、顔を伏せて落ち込んでしまった。 ベスは、リッキーにそっと耳打ちして、買い物に行ってくると二人で出かけて行った。二人だけになったハワードは、どう声を掛けてよい物か迷っていた。しかし、気が付くとヒカルが寝息を立てている。ケットをそのか細い肩にかけ、そっとさすってみる。「ヒカル。あなたを不機嫌にさせたのが私の所業のせいなら謝罪します。あの鐘が鳴り響いたとき、確かに私の心に、純白のドレスを着たヒカルが微笑んでいる姿がイメージできていました。鳩に驚いてしがみついてきたあなたを抱き留めたとき、そのまま抱きしめていたい気持ちに駆られたのも事実です。ですが、あなたは気高い血筋の王女様です。どんなに焦がれても立場が違いすぎる…」 ソファからとろりと垂れ下がった手を持ち上げると、「どうか今だけはお許しを」そう呟いてその甲にそっと口づけた。召喚される前の孤独な自分が、ヒカルと出会って少しずつ過去へと変わっていることを、ハワードは実感し始めていた。この若い王女は、自分の外見ではなく本質を見ようとしてくれる。ただそれだけのことでどれだけ心が満たされることか。 しばらくしてヒカルが目を覚ました。 馬車の中はハワードと二人っきり、その彼は静かに読書を楽しんでいた。体を起こしてゆっくりと頭が冴えてくるとヒカルは「ごめんなさい」とつぶやいた。「シルベスタ先生に言われたの。今回の事で魔術師としての腕は認めると。それで、お父さんのところに跡継ぎが生まれたら、自分の後継者として修業を始めないかって。そのために陛下が計画してくれている住まいをシルベスタ先生のおうちの近くに建てればいいって。もう身分や年齢にとらわれずに自由に生きていいんだよって。私、王女様として生まれ育ったわけじゃないから、正直ほっとしたの。だけど、お父さんとすっかり遠ざかってしまうから、ひとりぼっちになるのはまだ少し不安で」 本を閉じてヒカルの話を聞いていたハワードは、そうですかとつぶやいた。「主がヒカルを認めてくださったのですね。それはすごいことです。ということは、ヒカルは次代のアイスフォレスト王国の最上位魔術師ということでしょう。ガウェイン陛下にシルベスタ様がいたように、アラン王太子殿下にヒカルがいつもそばにいて、意見を交わすことが多くなるのではないですか?」 ヒカルは驚きのあまりぽかんとしてしまった。確かにそうだ。ガウェインとシルベスタはいとこでもあるし、大親友でもある。次の世代がアランとヒカルなら、仲良し親子なのだから申し分ないだろう。「次に向かう元の王国があった場所も、じっくり見学しておきましょう。この旅で見るもの聞くものすべてが、ヒカルの将来にとても重要なものになるでしょう」「はい、がんばります!」元気に返事をするヒカルだったが、以前のような幼さはもう見られない。プリンをおいしそうに食べていた頃のヒカルを思い出して、王宮に帰ったらすぐさまプリンを作ろうと決意するハワードだった。ヒカルは、グラスにささっているブーケを見て、そっと手に取る。ブーケを差し出した時のハワードが幸せそうに見えなくて、どうにも悲しくなって受け取ることが出来なかったのだ。だけど、あの丘で、きれいな青空の下、鐘の音が鳴り響く中、ハワードの腕に飛び込んだ時、自分を庇う腕が優しくて、その表情がたまらなくしあわせそうだったことが嬉しくてそのまま離さないでほしいと願ってしまった。自分が王女でなくなったら、あの優しい腕に触れることもできなくなるのだろうか。そんな不安が、とび色の瞳に影を落としていた。つづく
May 7, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第3章 アクシデントで知る想い 3
宿の部屋に荷物を運びこんで、久しぶりにちゃんとしたレストランで食事をとることになった。ウェイターが注文を聞きながらちらちらとヒカルの様子を気にしている。ヒカルは人好きのする笑顔で会釈しているが、ハワードは心配そうにウェイターの動向を見つめていた。「こんばんは。旅の途中ですか?」 不意に隣のテーブルの女性から声がかかって、「はいそうです」とハワードが返すと、突然女性は席を立って、ハワードの傍まで来ると、親し気に話しかけてきた。「もし、こちらの宿に泊まられるなら、食事の後、一緒にラウンジにいきませんこと? お子様たちには先に休んでもらって、大人の時間をたのしみましょう?」「いや、結構です」「あら、遠慮なさらなくてもいいのよ。子供たちを連れての旅は大変でしょう?たまには羽根を伸ばさないと」「お前たち、しつこいぞ。行かないと言ってるだろ!」 堪り兼ねたリッキーが口をはさむと、女性はキッと睨みつけて言う。「あんたには関係ないでしょ。食べ終わったらさっさと部屋に帰りなさい」 あたりの雰囲気は一気に険悪になる。気が付くと、カウンターに座っている男もヒカルやベスを値踏みしている。「あの、もう食べ終わったから部屋に帰りましょうか」 ヒカルが遠慮がちに言うと、ハワードもすぐさま立ち上がった。そそくさとレストランを後にするが、行く先々で「あら、いい男」「おっと、かわいい子がいるねぇ」などと声がかかる。 それまで黙っていたハワードは「ヒカル、失礼します」と、突然姫抱っこしてすたすたと速足で歩きだした。リッキーとベスはそんな二人を見てクスクス笑いながらついていく。「え? あの…」「大丈夫です。ヒカルの事は私が守ります」 キリッとした表情でそう言い放つと、近くにいた店員から「ひゅー、かっこいい!」と声がかかる。しかし、ハワードはそんなことを気に留めることなく、いや、声がかかる度に抱き上げている腕に力を込めて、どんどん進んでいく。破壊力の強い美顔がすぐ目の前だ。耳元にその息がかかって、ヒカルはドギマギしてしまった。そして、ヒカルたちの部屋の前まで来ると、はぁっと脱力したハワードが、そっとヒカルを下ろして自分の特異な容姿について忘れていたことを謝罪した。いつもの帽子やサングラスをつけていなかったのだ。つややかに流れる明るい金髪に誰もが目を奪われる涼やかな瞳。こちらの世界に来てからは、大人の色香も出てきて、一層周りを引き付ける。「しばらく人里離れた場所にいて、すっかり忘れていました。申し訳ない。それに、ヒカルもこれからはおいそれとは外に出られませんね。これからはヒカルの服装も気を付けた方がいい…ん?」 言いながら、ヒカルが下を向いて真っ赤になっていることに気が付いて、ハワードはそっと顔を覗き込んだ。「ハワードさんのバカ!!」 ヒカルは部屋に飛び込んで内側から鍵をかけてしまった。驚いて目を見開いている美丈夫に、仕方ないなとベスが間に入った。「ヒカル、ハワードさんに悪気はなかったのよ。ちゃんとお話ししないと分からないでしょう?」 ドアの向こうからはベッドで暴れるような音がしているが、返事がない。リッキーは、戸惑うハワードを促して、隣の自分たちの部屋に落ち着いた。「私は、なにか失礼なことをしてしまったのでしょうか。あ、いえ。突然抱き上げたのだから、もちろん謝罪する必要はあると思うのですが…」「ふふ、ハワードさんって、ほんとに恋愛したことなかったんだね。好きな子を守りたかったら、やっぱり自分の気持ちをちゃんと伝えなくちゃ、誤解を生むばっかりだよ。まあ、さっきのは、嬉しすぎて混乱してたみたいだけどさ」 はははと楽しげに笑うリッキーに、ハワードの眉間にしわが深く入った。「どういうことですか? 嬉しすぎる? さっきはずいぶん気分を害してしまったように思うのですが」「なんか面白いね。なんでも完璧にこなすハワードさんが、こんなに翻弄されてるなんて」 はぁ、と深いため息をついていると、隣でもドアの開く音がして、どうやらヒカルがベスを部屋に入れたようだった。少し頭を冷やそうと、ベランダに出たハワードは、隣から人の話し声が聞こえてはっとする。「こんばんは、星がすごいよねぇ。君も旅の人?」「え?」とヒカルのためらうような声が聞こえて思わず警戒する。しかし声の主はまるで能天気な様子で、観光地の話を始めた。「もう平和の丘には行ったかい?あそこにある幸福の鐘をならすと幸せになれるというらしいよ。もしよかったら明日案内してあげようか?」「いえ、結構です!!」 気が付いたら、ベランダの柵越しに身を乗り上げて叫ぶ自分がいて、ハワードはそんな自分に驚いていた。しかし、動き出した思いは止められない。そのまま部屋を出て、ベスとヒカルの部屋のドアをノックすると、驚くベスをしり目に部屋を突っ切り、ヒカルのいるベランダに飛び込んだ。「なぁんだ。彼氏持ちか。残念。まぁ、仕方ないね。君みたいにかわいい子が一人のはずないよね。幸福の鐘は彼氏と鳴らすといいよ。じゃあね」 青年はあきらめたように部屋に戻っていった。「ヒカル、気を付けてください!今のはナンパですよ!」「ナンパ?」 まるで分っていない風なヒカルにハワードは焦りを覚える。ヒカルの両肩を掴んで、深呼吸すると、改めて謝罪を口にした。「ヒカル、さっきは私の突拍子もない行動のせいでご迷惑をお掛けしました。ですが、実際ヒカルだって多くの男たちの視線を集めていたのです。どうか、もう少し周りに気を配ってください。そうでないと…」 言葉に詰まるハワードを見つめるヒカルは困惑気味に問いかけた。「そうでないと?」 ハワードは途端に顔を赤らめて黙ってしまった。ヒカルはモヤモヤした気持ちのまま、ベランダにあるイスに腰かけて深いため息をついた。「私、今までナンパされたことなんて一度もないです。買いかぶりすぎですよ。お父さんやシルベスタ先生、ハワードさんみたいなキラキラしたオーラなんてない、ただの小娘です。さっきの人も観光地を教えてくださっただけだったし。旅に出るとみんな開放的になるのかもしれないですね」「いや…」 どう伝えたものかと考えるハワードの背後でノックが聞こえ、リッキーが入ってきた。「今、ジーク団長と連絡が取れた。どうやら王宮魔術師団を解任された何人かがヒカルを出せと騒いでたみたいだ。自分の落ち度を棚に上げて、ヒカルのせいで解任されたと思い込んで、決闘を申し込んでいるそうだ。バカじゃないのか?どこの世界に王女様に決闘を申し込む魔術師がいるんだよ」 呆れるリッキーをしり目に、ヒカルはすぐさま水晶玉を借りて、シルベスタに決闘を受けると連絡した。「ヒカル、本当にあいつらの相手をするのかい?時間の無駄だと思うけど、それで君の気が済むなら、準備しよう。では3日後にこちらに転移してきてくれ」 シルベスタは事も無げに告げた。つづく
May 6, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第3章 アクシデントで知る想い 2
一晩休むと、ヒカルもすっかり元気になっていた。朝からリッキーは老人の薪割りを手伝い、ヒカルとハワードは近くの川で魚を釣ってきた。そして揃って畑を耕したり収穫を手伝ったりした。ベスは小屋の中の掃除をがんばり、ご飯の支度を手伝った。昼食をとったあと、今まであまり目を合わそうとしなかった老人が4人の前に座って語りだした。その昔、華やかだった在りし日の旧アイスフォレスト王国の話だ。「贅沢を極めた貴族たち、商魂たくましい商人たち、平民たちも精一杯に生きていた。しかし、王族には平民の生活が見えていなかった。あの災害で最初に亡くなったのは平民たちだ。地響きを立てて襲い掛かってくる土石流になすすべもなく村ごと流されていった。今のアイスフォレストはどうだ?少しはマシになったようだが、あの悪ガキのガウェインに平民を守る意思はあるのだろうか。王太子となる青年はずいぶんひ弱だと聞くが、ちゃんと世間が見えているのだろうか」 問いかけるように一人一人に視線を送る。ヒカルは、そんな老人の視線を跳ね返すように訴えた。「陛下は、すべての国民を大切に考えています。」 老人の目がヒカルを捉える。薄茶の髪に薄いとび色の瞳。そして、まっすぐに見つめ返す強い視線にふっと合点がいった顔をした。「ところでそなたのようなまだ若い娘が、ずいぶんと過酷な旅をしているのだな」「はい、父と先生に世間をしっかり見て来いと、そして視野を広げて来いと言われました。確かに昨夜は厳しい状況でしたが、私には、頼りになる仲間がいますから、たとえ疲れて座り込んでも、また立ち上がることが出来るのです」「ほう…」 真剣な目で見つめるヒカルを、どこか懐かしさを感じるような表情で見つめ返した。そして、思い出したように告げた。「そうだな、今日の午後から薪を仕入れに若い衆が来る予定だ。それに乗せてもらえば、とりあえずは街まで行けるだろう。」 4人は荷物をまとめて、若い衆が来る直前まで薪割を手伝った。そして、老人に礼を言って、馬車に揺られて街までやってきた。そのまま市場に向かうと言う若い衆に礼を言って街を歩きだすと、早々に見覚えのある馬車に出会った。どうやら問屋に売りつけに来ていたようだ。店の前では店主と見覚えのある御者が言い合いをしている。店主は、馬車の荷台の後ろに小さく記された王家の紋章を指さして「こんなものを買い取るわけにはいかない」と恐れおののいていた。「あの、商談中のところを失礼するよ。これはうちの馬車なんだ。返してもらおうか」 言うが早いか、リッキーが御者の首根っこをひねり上げ、早々に縄で締め上げた。「食品も着替えも路銀も無事です。ご亭主、お騒がせしました。」「いや、しかし。あなたたちはいったい…」 店主が戸惑うのも無理はなかった。4人はそろってどろどろの服を着て、髪もぼさぼさだった。仕方なく、ヒカルが紋章の入ったお守り袋を見せると、やっと店主も納得した。 そこからは、リッキーが御者を務め、ベスも隣に座ることにした。街中の宿に落ち着くと、途中で買っておいた軽食を取り、ゆっくりと湯あみをして、ふかふかのベッドで横になる。生き返ったとつぶやいたのは、ヒカルだけではないだろう。 翌朝、4人は馬車に乗り込み、再び東の最果てを目指した。ベスがリッキーの隣に座ったことで、馬車の中は二人きりになってしまった。ぎこちないながらも歴史の講義は続く。「ここまでで分からないところはありますか?」 講義の終わりにハワードが尋ねると、ヒカルは少し考えてからぽつりとつぶやいた。「ハワードさん、今はもう平気ですか? 何か抱えたままになっていませんか?」 言いながらも自信のなさが瞳ににじむ。「私のような小娘に心配されるなど、不快かもしれもしれませんが、旅の仲間として、できるなら力になりたいのです」「ヒカル…。いえ、ご心配には及びません。馬車も手元に戻ってきましたし、これで安心して旅が続けられますよ」 笑顔で返すハワードをじっと見つめていたヒカルだったが、視線は徐々に下がって、しまいには首を垂れてしまった。「そうですか。私がもう少ししっかりしていればよかったのですが。不甲斐ない私で本当に申し訳ないです」「ヒカル。なぜあなたが謝るのです」「旅の仲間に信頼してもらえなかったということです。もとより王座に就く者ではありませんが、これでは王族として失格です。」「…はぁ。あなたって人は、本当に15歳なんですか?まるで大人のような発想ですね」 途端にヒカルは口をへの字にしてすねてしまった。「どうせ私はおばさん思考ですよ。友達にもよくからかわれていました。まるでお母さんとしゃべってるみたいだって」「ふぅ。殿下の教育が行き届きすぎだったのですね。その考え方は王族ならではなのでしょう」 参ったなぁと考えを巡らせていたハワードは、あきらめたように向き直って告げた。「…そうですね。白状すると、私は、もう少しだけ、少女らしいヒカルの姿を見ていたいと思ったのです。だから、その時が来たら、私の抱えているものについても聞いていただけますか?」 真摯な態度のハワードに、少しわだかまりを残したままのヒカルも「分かった」と言うしかなかった。 しばらくすると、馬車の外から声がかかった。もうすぐ次の街に入るという。今回はここで宿に泊まることになった。2日かけて歩いたあの土地を、馬車では遠回りしていくしかないのだという。窓の外は、金色の麦畑が広がっている。風になびく麦の穂が波のように美しかった。つづく
May 5, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第3章 アクシデントで知る想い 1
第3章 アクシデントで知る想い 先の御者が言った通り、別の御者がやってきた。次の目的地は東の最果て、以前の王国があった場所だ。そこまでは数日かかるため、食料を多めに積み込んで出発する。 フォリナー侯爵領を出て2日が過ぎた。馬車は牧草地を通り過ぎ、森を抜け、美しい湖のほとりに到着した。馬車の中ではハワードによる昔の王国についての講義が続いていた。馬車が止まったことで、いったん講義は中断し、テントを張る。この辺りはすでに魔素のないエリアなので魔術は使えない。それぞれが荷台から木箱を運び、自分のイスとして使う。焚火を囲んで食事をとり、旅の予定などを話し合った。 ヒカルはちらちらとハワードの様子を盗み見るが、まるでなんでもないような素ぶりだ。すっかり辺りが暗くなると、それぞれがテントに落ち着いた。一日中馬車に揺られているのも案外疲れるものだ。その日も4人はぐっすり眠っていた。 しんと静まった真夜中に、コトリコトリと小さな足音が去っていくのを聞いて、リッキーが飛び起きた。テントを出ると、馬車が森の向こうに去っていくのがかすかに見えた。御者のテントも片付けられている。どうやら御者の持ち逃げらしい。「ちくしょー、連絡がないのはおかしいと思っていたのに」 すぐさまほかの3人を起こして事の次第を告げる。食料も水も着替えも、すべて馬車の中にある。手元にあるのは朝食用の食料と当面の路銀だけだ。旅の疲れが出ているヒカルもすぐには魔力を出せそうになかった。「仕方がないですね。 こうなったら、朝までゆっくり休んでから行動しましょう」 翌朝、朝食をとると、ヒカルはすぐさま王宮に連絡を取ろうと試みた。しかし、どういうわけか繋がらない。4人がじっと水晶玉を見つめていると、微かな反応があり、シルベスタらしき声で、今はこちらに来ない方がいいだろうとそれだけが聞き取れたきり、途絶えてしまった。「王宮でもなにかあったようですね」「そうね。だけど、これじゃあ私たちもすぐには帰れないわ。」 ハワードは枕元に置いていた手帳を取り出して、何やら調べている。「ありました! もう少し北に行けば民家があるようです。ただ、馬車がないので、たぶん2,3日歩くことになりそうです。」「それじゃあ、目に留まった果物なんかは収穫しておいた方がよさそうだな」「私も気を付けておくわ」 ハワードの言葉に、リッキーとベスも腹をくくった。 馬車で通った道を、テントを背負って歩く。木漏れ日が気持ちいいと思っていたが、合間に差し込む鋭い日差しがきつい。木々の間からは羽虫が飛び出し、足元にはぬかるみもあった。「ヒカル、大丈夫ですか?」「大丈夫よ。歩いた分だけ進んでるんだもん。頑張るしかないよね!」 時々かかるハワードの声に、懸命に答えるヒカルだったが、夕方にはすっかりおとなしくなっていた。「大丈夫、ですか?」「う、うん。なんとか」 テントを張って一日目をやり過ごしても、夕食は途中で見つけた果物ぐらいだ。そのまま倒れるように眠りに落ちて、翌朝もテントを背負って歩き出す。「雨が降ってないだけマシ、獣が襲ってこないだけマシ、…」 呪文のようにヒカルがつぶやく。今朝、近くにあった小川で水を汲んで以来、水分を補給できる場所が見当たらなかった。歩いた分だけ汗は吹き出し、先ほどから頭痛がしている。それでも、前に進むしかないのだ。「ちょっとここで待ってて。水の音がするから、水筒に汲んでくるよ」 リッキーがみんなの水筒を集めて、生い茂る熊笹の中に分け入った。残った3人が座り込む。みな同じく脱水症状で苦しそうだった。 私だけが苦しいわけじゃなかったのに、気づいてあげられなかったな。ヒカルは改めてリッキーの逞しさを尊敬した。伊達に軍人をやっているわけじゃないんだ。 しばらくすると、リッキーが明らかに先ほどとは違う確かな足取りで戻ってきた。両手に4人分の水筒と、果物を抱えている。「とりあえず、水分補給をしよう。落ち着いたら、一緒に来てくれ。うまくいけば魚が採れる。」 4人は一斉に水を飲み干し、しおれた植物が持ち直すように、元気になった。「では、私がお供しましょう。ヒカルとベスには、魚を焼く場所を作ってもらうのはどうでしょう」「そうだな。あんまり離れ離れにならないようにして準備してくれ」 二人が川に向かうと、ベスとヒカルはもくもくと大き目の石を並べて魚を突き刺せそうな枝を準備した。気が付くとリッキー達が袋に魚を詰め込んで戻っていた。枯葉を集めてなんとか火をつけると、枝で突き刺した魚をあぶる。「リッキーってすごいね。やっぱり軍人なんだなぁって、思ったよ」「なんだよ、ヒカル。今まで俺を何だと思ってたんだ。これでも王女様専属の騎士なんだぞ!旅に出る前には団長からいろいろ教わってるんだ」 空腹が満たされると、みんな朗らかになる。お互いの笑い声で元気になって、再び歩き出した。「もう少しだと思われます。ヒカル、頑張ってください」「うん、頑張るよ。」 再び山道をもくもくと歩く。リッキーが先頭を切って歩きながら、余計な草を薙ぎ払っているが、それでも笹の葉や古い枝に当たって小さな傷が絶えない。日が傾いて、そろそろテントを張る場所を探そうと言う頃、木々の間から明かりが見えた。「小屋ですね。あそこまでがんばりましょう」 ハワードに促されて、みんなは小屋を目指して歩き出した。先に小屋まで駆けて行ったハワードがドアをノックすると、窓の明かり揺れて、ゆっくりとドアが開けられた。出てきたのは足の悪い老人だった。夕暮れ時に突然やってきた4人組をいぶかし気に見つめている。「私たちは旅の途中で、悪い御者に荷物を馬車ごと奪われて、ここまで丸2日歩き詰めなんです。急にやって来て申し訳ないのですが、どうか少しの水と食べ物を譲っていただけませんか?」 老人はハワードの言葉を聞いても、じっと4人を睨みつけていたが、ふとヒカルがぐったりしているのに気が付いて、「入れ」と招き入れた。「その娘は熱を出しているのではないか?」 言われて初めて気が付いたのか、ベスがヒカルの額に手を当てて驚いている。「奥の部屋で寝かせると良い。付き添いの娘も一緒に休めばいい。男たちはわしと一緒にこっちのかまどの前で。まあ、テントで寝泊まりしていたなら、似たようなもんだ」「ありがとうございます。とても助かります。」 老人に促されて小屋に入ると、疲れが一気に押し寄せた。つづく
May 4, 2022
コメント(0)
-
REALIZE2 第2章 東の地で見た忠誠 3
夜になって夕食を囲んでも、ハワードはヒカルと目を合わせることもしない。ベスはリッキーを運んだまままだ帰ってこないので、どうにもいたたまれない空気が流れていた。「フォリナー侯爵様、今までにオオカミやほかの野生動物による被害はありませんでしたか?」「いや、今まで本当に一度もなかったんです。リカルド殿には大変申し訳ないことをしてしまった。彼は、大丈夫なんでしょうか?」 ハワードが、シルベスタは治療魔術が得意だと話すと、侯爵はそれならいいのですが。とそれでもなお心配そうにしていた。「王女様、その水晶玉で、シルベスタ様ごと、こちらに来ていただくのはどうでしょうか?侯爵様も心配してくださっているし、エリザベス嬢も心細いでしょう」「分かったわ。こちらからお願いしてみます。」 突然ハワードから声を掛けられて、思わずドキっとしてしまったが、憎らしいほどにいつも通りの表情をみて、悔しさがにじむ。そっちがそういうことならと、王女としての顔で返答する。ヒカルは水晶玉を取り出し、魔力を込めてシルベスタを呼び出した。シルベスタからは緊張した様子は見られず、ちょうどこちらに二人を返そうとしていたという。一緒にこちらに来て、現場検証をしてほしいと告げると、二つ返事でOKが帰ってきた。 ほどなく、治療を終えたリッキーとベスが戻ってきた。もちろんシルベスタも一緒だ。「侯爵殿、突然失礼するよ。私は王城の魔術師シルベスタ・サーガだ。」「これは、これは。建国の立役者と言われている大英雄のシルベスタ様ではないですか」「いや、それほどでも…。せわしなくて悪いけど、現場を見に行っても?」「お言葉ですが、もう外は暗いですし、明日になさいませんか?」 シルベスタはニコニコしたまま、侯爵に答えた。「いや、今回のオオカミ襲撃の件の糸を引いていた輩を捕まえたくてね。きっと朝早くにはとんずらするつもりで今頃カバンに荷物を詰めているところだろうからね。」 まるで、今見てきたようにそういうと、ハワードを連れて外に出て行った。彼らを見送っていると、ソファで寝かされていたリッキーが目覚めた。「リッキー、大丈夫!」 急いで駆け寄るベスに、リッキーは混乱しているようだった。「はっ!ヒカルは! 俺よりも早くヒカルのところに行ってやれ!どうして俺のところに来てるんだよ!ベスはヒカルの侍女なんだぞ!」「リッキー、落ち着いて。私は大丈夫よ。」 ヒカルの声を聞いて、やっと状況が呑み込めたリッキーはうろたえて黙り込んだ。「ベスにリッキーの傍についていてあげてって言ったのは私よ。だから、ベスを責めないで。それよりも、すごく心配していたのよ。もう少し、ベスの気持ちも考えてあげてよ」 フォリナー侯爵夫妻は、執事にいいつけて、リッキーを個室に連れて行った。「ベス、あなたは王女様の身の回りのことをお願いね。」 侯爵夫人はそういうと、侯爵と目配せして、リッキーの部屋に向かった。「ベス、湯あみの準備をお願いしてもいいかしら。」 ベスはモヤモヤする気持ちを押さえつけて、ヒカルの湯あみの準備に取り掛かった。今は、何も考えたくない。ヒカルの何でもない用事が、ありがたかった。 部屋に寝かされたリッキーは、天井を睨んで考えていた。この屋敷に来て、一層強く階級の差を感じていたのだ。領民も侯爵をとても尊敬している。彼の頼みならと、今回のオオカミ狩りだって、すぐに人が集まった。そんな立派な侯爵様の令嬢で、性格もいい、顔もかわいい、スタイルもいい、しかも魔力も強い。気もよくつくし、気配りもできる。あんな素晴らしい令嬢に、他の貴族から縁談が来ないはずがないのだ。 うかつなことに、今まで考えもしていなかった。魔術学校で一緒に過ごすようになって、気心が知れて、大切な人になった。だけど、彼女は侯爵令嬢、自分は子爵の息子に過ぎない。ベスが自分にかまってくれるのを良いことに、甘えてしまっていていいのだろうか。 思いめぐらせている間に、ドアがノックされた。「リカルド殿、体調はいかがかな」「侯爵様! この度は私の不手際で、大変なご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳なく思っています」「何を言うか。我が領のために戦ってくださったのに、怪我を負わせてしまったこと、こちらが謝りたいところですよ。」 侯爵が労わるように言うと、横から夫人も声を掛けた。「リカルドさん、娘がとてもお世話になっているようですね。長い旅の間には、ケンカもするだろうし、良いところも悪いところも見えてしまうもの。それをしっかり見た上で、将来を決めてくださいね」「え、あの。だけど、彼女は侯爵令嬢だし、うちは子爵。彼女ほど優秀で美しい人なら、いくらでも良縁はあるでしょう」 珍しく弱気なリッキーが言うと、夫婦は笑って言う。「侯爵だろうが、伯爵だろうが、ましてや王子様だろうが、性格が悪い人やそりの合わない人と一緒になることほど不幸なことはないだろう。本音をさらけ出して、ケンカしあえる相手に出会えることがどれほど幸運なことか。出来がいいと思っていたうちの長男ですら、まだそんな相手に巡り合えていない。リカルド殿。これを」 侯爵が差し出した手紙には、マイヤー子爵の宛名が書かれていた。リッキーは目を見開いてそのままその手紙を大事そうに胸に抱きしめて「ありがとうございます」とつぶやいた。 シルベスタは夜のうちに森を調べ上げ、森の奥の一軒の山小屋を見つけ出して、犯人に気づかれないように逃げ出せない結界を張っていた。リッキーの傷がすっかり治るまでの2日間には、ヒカルからも炎におびえないオオカミに違和感があると聞きつけ、犯人の男を締めあげてオオカミを魔術で操って必要な物をそろえていたことを白状させた。案の定、男は王城魔術師団の元メンバーで、いったんフォリナー侯爵に見せに行くと、出迎えたベスが突然怒り出した。「あの時の変態だわ!王女様、下がってください。よくもやってくれたわね!」 この男、不正がばれて辞めさせられるのをヒカルのせいだと思い込んでいた。嫌味を言った時にヒカルの突風で身ぐるみ剥がされて、下着姿になったところをベスに目撃され変態認定されたうえ、コテンパンに叩きのめられた過去があった。ベスが怒りをあらわにすると、部屋から起き出していたリッキーが慌てて止めに入った。「ベス、大丈夫だ。もうつかまってる。安心して」 リッキーの腕に抱えられ、ベスははっとして頬を染める。それを見ていたシルベスタは満足そうに頷くと、ハワードに「後は頼んだよ」といいつつ、その耳元に何か囁いて、男を引き連れて帰っていった。 翌朝、出発する4人をフォリナー侯爵夫妻が見送った。ウィリアムがなかなか帰ってこないのだから、たまには二人で遊びにおいでとリッキーに声を掛ける夫妻に、リッキーは真っ赤になって恐縮し、ベスは涙ぐんでいた。つづく
May 3, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第2章 東の地で見た忠誠 2
翌朝は澄み切った青空で、生き生きと輝く草原の緑との対比がすばらしかった。4人は執事に案内されて、牧場を見学し、心地よい風が吹き渡るこの草原で昼食をとることになった。牧草地の端まで迫っている森の木陰にテーブルとイスが設えられている。侍女たちが手際よく食事の用意を整え、4人を迎えてくれた。「草原を目の前にしていただくのも、気持ちいいものね。」「お気に召したなら光栄です」 新鮮な空気を思いっきり吸い込んで深呼吸すると、ヒカルが進められた席についた。 4人が食事を始めたところで、遠くから鐘の音が鳴りだした。時を告げるような音ではなく、どうやら切羽詰まった何かが起こっているようだ。「失礼いたします。お食事のところ、大変申し上げにくいのですが、どうやら領地のはずれにオオカミが出たということです。念のため、邸宅にお戻りいただいた方がよろしいかと」「オオカミですって? 今までこの牧場にオオカミが出たことなんて、なかったじゃない」「俺が行くよ。どのあたりか分かるか?案内してほしい」 焦るベスを抑えて、リッキーは有無を言わせない勢いで伝えに来た下働きの男に言うと、「こちらです」と促す男について走っていった。ベスはそんなリッキーに声もかけられず、そのまま見送る事しかできなかった。「ベス、落ち着いて。今までなかったからこれからもない、なんてことはありえないわ。今は執事さんに従ってお家に戻りましょう」 困惑するベスを宥めて、ヒカルが立ち上がった。邸宅に戻ってしばらくすると、リッキーが下働きの男とともに帰ってきた。フォリナー侯爵が慌てて出迎える。「リカルド殿、大丈夫ですか?」「はい、オオカミは仕留めたので安心してください。だけど…」 そういって、下働きの男の方を見やった。男は悲壮な表情で領主訴える。「じ、実は、今日だけではなかったのです。他の仲間らも、オオカミに羊をやられたと聞いたのです。領主さま、一度全体の被害を確認していただけないでしょうか?」「なんだと! 今回だけの事ではなかったのか?!」 侯爵はすぐさま執事に伝令を出した。1時間もすれば、領民が集まってオオカミ討伐隊が組まれた。リッキーも当然仲間に加わり、出かけて行った。ベスはまたしてもリッキーに声を掛けられず、ただ窓辺から彼らが森に進んでいくのを見守るしかなかった。 刻々と時間が経つ中、ベスはずっと下を向いたまま動けないでいた。見かねたヒカルは、彼らに軽食の差し入れをするのはどうだろうかと提案する。「みなさん急いで出かけられたから、喉も乾くだろうし、お茶と軽食を差し入れるのはどうかしら」「王女様…。そうですね。準備してきます。」 ベスは気を取り直して顔を上げ、厨房へと駆けて行った。 日が傾きかけたころ、ヒカルとハワードも手伝って、屋敷からほど近いところにお茶を飲むスペースを作り上げた。王女が手伝うというので、恐縮していた執事や侍女たちも、ヒカルの手際の良さに驚き、王女様のご意志ならと、共に作業に入った。領地の外側を手分けして捜索していた何組かのチームがそろそろ戻り始めている。ベスは、みなを労って、お茶やサンドウィッチを勧めた。リッキーも戻って来て、お茶の支度に気づくと、他のチームの者たちを呼び寄せた。 領民はみな一様にオオカミの突然の襲撃に驚いていたが、これだけ見回れば大丈夫だろうというのが大方の意見だった。 薄暗くなり始めた木々の間に、まだ動いている者が見え、ヒカルが呼びに行ってくると駆けだした。すかさずリッキーがそれを追う。「おい、ヒカル。一人で行ったらあぶないぞ。まだいるかもしれないんだからな」そう言いながら追いかけて行った先で、なぜか不自然に立ち尽くしているヒカルに追いついた。「おい、どうした?」「えっとね。大きいのが1匹と小さめのが2匹いるわ」 リッキーはすぐさま剣を取り、オオカミと対峙する。にらみ合いはほんのわずかの時間だった。いきなりガタイの大きなオオカミがリッキー目掛けて襲い掛かってくる。それに合わせて小型のオオカミがヒカルにかみつこうと飛びついた。ヒカルはとっさに掌から突風を飛ばして吹き飛ばしたが、勢い余って、地面に転がってしまった。振り向くとリッキーが小型に足をかみつかれていた。リッキーは大型の牙に剣を当ててせめぎ合って身動きが取れない状態だ。「リッキー!!」 ヒカルはすぐさま突風で小型をひるませるが、なかなか離れようとはしない。森の中では炎は危険だが、このままでは埒が明かない。掌に炎を立てると、小型のオオカミに吹き付けた。「キャン!」と口を離した瞬間、突風で奥の木々の根元に吹き飛ばした。その後ろで、大型のオオカミはリッキーにのしかからんばかりに迫っている。「リッキー、伏せて!」 ヒカルは思い切って炎を大型のオオカミの脇腹に叩き込んだ。オオカミはわき腹に煙を立てながら、なおもリッキーから離れない。その時、帰りが遅いと心配したハワードが駆け込んできた。「なんてことだ!」剣など持ち合わせていないハワードは、とっさに傍にあった岩を大型のオオカミ目掛けて投げつけた。岩は頭に命中しオオカミは痙攣を起こしたが、それでもリッキーから離れようとしない。他の領民も駆けつけて、なんとかオオカミを捕獲した。 領民と一緒にやってきたベスが小さな悲鳴を上げてヒカルに飛びついた。「王女様、お怪我はありませんか?」「服はひどい状態だけど、私は大丈夫。それよりも、リッキーを見てあげて!」 気が付くと、リッキーは力尽きて倒れたまま動かない。足からの出血もひどい状態だ。「ベス、瞬間移動はできる? すぐにシルベスタ様のところに連れて行ってあげて!」「分かりました!」 ベスは覚えたばかりの瞬間移動で、リッキーを王宮に運び込んだ。それを見送ると、ハワードはヒカルを抱き上げて領主の邸宅へと向かった。「ハワードさん、大丈夫です。どこも怪我なんてしてないですから」「王女様、今日のことは大変危険な行いでした。もう少し、私やベスを頼ってください。リッキーが気づいてついて行ってくれていなかったら、どうなっていたと思いますか?」「ハワードさん、怒ってますか?」「はい、私は今、猛烈に怒っています!!」 美丈夫に姫抱っこされる王女様を目撃してニヤニヤしていた領民は、一気に背筋を伸ばした。つづく
May 2, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第2章 東の地で見た忠誠
第2章 東の地で見た忠誠 次の目的地は東の領土フォリナー侯爵領だ。エリザベスやウィリアムの実家にあたるが、そこに向かうにはルクセン伯爵領を通ることになる。ハワードにとっては苦い思い出の場所だ。リッキーの指示で足早に通り過ぎようとしていた馬車が、急に速度を落とした。 リッキーが外の様子を確かめると、一人の女性が卵をかごに入れて売り歩いているところだった。「ご婦人、馬車の前に出ると危ないですよ。下がってください」「も、申し訳ございません。卵を売っておりまして…」 馬車の中で聞いていたハワードは、はっとして馬車のドアを開けて出た。そこにはよく知った人物がいた。「ルクセン伯爵夫人! どうなさったのですか?」 娘を亡くし、夫は信用を無くして収入も途絶えたというのに贅沢癖が治らず、夫人は手元にあるわずかなお金で、養鶏場を立ち上げ、卵を売り歩いているという。「まぁ! あなたはアルフォートではないですか?! もう、怪我は治ったのですか? あの時は何もしてあげられなくて、ごめんなさいね。だけど、お元気そうで良かったわ」 ほほ笑む夫人の顔には深いしわとクマが出来ている。アルフォートとは、異世界から召喚されたとき、記憶をなくしていたハワードにルクセン伯爵がつけた名前だ。ハワードは夫人のかごの卵を全部買い取ると「少しは休んでください」といたわった。夫人はハワードの手を取って静かに言う。「ありがとうございます。外聞ばかり気にするルクセンは、決してよい主ではなかったでしょう。でも、どんな過去があろうと、あなたの本質はあなただけの物。それを見ていてくれる人は必ずいるわ。どうか、幸せになってね」 ルクセン伯爵夫人と別れ、馬車はフォリナー侯爵領へと向かう。ハワードは、夫人の温かみの残る掌を、じっと見つめていた。「ちょっとリッキー! またうたた寝している! ダメでしょう。護衛がうたた寝なんかして」「うるさいなぁ。今はみんながいるんだから、一番安全なんだよ。」「だからって、護衛騎士が居眠りして言い訳ないでしょう?」 小さな小競り合いだった二人のケンカは、どんどんエスカレートしていく。「ベス、どうしたの?」「私がいるので、お二人ともくつろいでいてくださって大丈夫ですよ」 ヒカルとハワードが間に入っても、険悪な雰囲気はなかなか収まりそうになかった。もうすぐフォリナー侯爵領だ。せっかくベスの実家に立ち寄るのに、二人がケンカしたままでは、もったいない。ヒカルはどうしたものかと考えあぐねていた。「フォリナー侯爵領に到着いたしました。」御者の声がして、ヒカルたちは馬車を降り立った。ハワードは、御者となにやら打ち合わせをしている。どうやら、ここで、御者を交代するように指示が入ったという。ハワードには連絡が来ていないままの交代だが、すぐに出発する予定ではないので、そのまま了解した。ハワードが振り返ると、未だ冷戦中の二人が黙々と降りてくる。最後に出てきたヒカルの手を取ってエスコートすると、フォリナー侯爵夫妻が出迎えてくれた。「ヒカル王女様、ようこそお越しくださいました。」「お世話になります。」 ヒカルはにっこり微笑んだ後、ちらりとベスに目をやって、眉を下げた。「あの、せっかくエリザベスのご実家に伺ったのに、なんだか揉めているみたいで。」「まあ、エリザベス! 王女様にご心配かけてどうするの。長旅でお疲れでしょう?まずはお部屋でおくつろぎください」 フォリナー侯爵夫人は、ベスに部屋に来るように指示して、荷物は執事に運ばせた。「こちらのお部屋をお使いください。殿方は向いのお部屋をどうぞ。」 執事は部下に指示を出して、リッキーとハワードの部屋へと荷物を運ばせると、ヒカルに向き直った。「王女様、御用の向きは、当家の侍女がお手伝いさせていただきます。なんなりとお申し付けください。」「エリザベスには後で会えますか?」「はい。ただ、少しお時間をいただくことになるかと…」 執事は黒ぶちの眼鏡の奥で戸惑う様子を見せた。「それは、夫人のお叱りがあるってことですね? 以前、ベスから聞いたことがあります。夫人のしつけがとても厳しいのだと。」「これは!ご明察でございます。そこまでエリザベス様と親しくしてくださっていたのですね。ありがとうございます」 堅苦しい印象だった執事の目がパッと見開いて、笑顔がにじみ出ていた。「きっと、素晴らしいお母さまなんだと思います。だから、ベスはいつだって頼りになる存在なのですね。」「お母さま」の言葉に哀愁を感じた執事は、ヒカルに母がいないことを思い出し、はっとした。「そんな風に思っていただけるとは、エリザベス様は本当に素晴らしい主に恵まれたのですね。それでは」 執事はそう言い残して、部屋を出た。 その頃、フォリナー侯爵夫人の私室では、ベスと夫人が向き合っていた。ベスはリッキーが昼間から居眠りしているのが許せないと訴えるが、夫人はただクスクスと笑っているだけだった。「お母さまったら、何がおかしいの? リッキーは護衛騎士なのよ!居眠りなんてしている場合ではないわ」「でも、あなたや執事の方がいらっしゃるのでしょ?」「そうだけど…」 憤懣やるかたないというベスに夫人は問いかける。「では、夜は誰が護衛に付くの? 護衛騎士に交代はいるの?」「いないわ。私たちは4人で旅をしているんだもの」「では、夜に神経をとがらせている人は誰かしら?」「…」 ベスはやっと気が付いたように黙り込んだ。「ベス、あなたの見ている物だけがすべてじゃないのよ。ウィリアムもそうだけど、護衛騎士の方はいついかなる時も、すぐに飛び出せるようにしているわ。それは、夜も同じでしょ? だったら、昼間のほかの仲間がいるときに、少しでも英気を養っておかなくてはいけないのではなくて? 私は感心したわ。まだ若い騎士さんなのに、ちゃんと危険度の低い時間に睡眠をとって、いつでも万全でいられるようになさっているのでしょう? しかも、どこかのじゃじゃ馬娘を大切にしてくださっているとか。なかなかできることではないわよ。ふふ。」 目を見開いて驚くベスは、夫人が楽し気に笑っているのを見て、顔がまっかになるのを感じていた。誰よ、誰がそんなこと告げ口するの?「お兄様ね!ひどいわ!」「あらあら、八つ当たり? 微笑ましカップルだから、つい助け舟を出したくなったとか言ってたわ。あなた、何かウィリアムに無理なお願いをしたのでしょう。口には出さないけど、ちょっとうらやましがってるみたいだったわ」 ベスには思い当たることがあった。そう、リッキーが初めて異世界に転移したとき、落として行った水晶玉を届けたいとウィリアムに泣きついたのだ。「マイヤー子爵家からは、以前、一度お礼状を頂いたことがあったわ。あなたが水晶玉を届けてくれたことをとても感謝してくださって。エリザベス、大切なのは、あなたがどうしたいかってことよ。お父様も私も、もちろん、ウィリアムも、あなたの想いを応援しているわ」「お母さま、ありがとうございます」 夫人はいつの間にかすっかり淑女らしくなった娘を抱きしめて、もう一度向き直ると、翌日に牧場見学を計画していると告げ、準備をしておくように言いつけた。 つづく
May 1, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第1章 南の地で気づく心配事 4
カタンっとドアが開く音がした。「こんばんわ。」 ヒカルが照れ臭そうに笑っていた。「どうしたのですか、こんな夜更けに?」「お昼寝しすぎて、眠れないのです。お隣座ってもいいですか?」 ハワードはそそくさと立ち上がり、どうぞごゆっくりと席を譲った。すさんだ世界から逃げ出してきたような感覚で、ヒカルの顔をまともに見られない。「私は、そろそろ休もうかと…。ヒカルもほどほどに。夜は冷えますよ」「あ…。そうですね。分かりました」 少し不安げな瞳がハワードの長い金髪の流れを見つめていた。その視線を感じながらも、ハワードは振り向けずにいた。ベランダにもたれて夜の海を眺めるヒカルは、これから先の旅のことを考えていた。貴族の屋敷に泊まる時ばかりではないだろう。自分が王女だと言わないで出来ればこの国の現状をこの目で確かめたい。「おや、眠れないのですか?」 ジークがベランダの人影に気が付いて声を掛けてきた。「ちょっとお待ちを」そう言って階下に下りて行ったジークはほどなく、トレイにカップを乗せて戻ってきた。「ホットミルクです。緊張を和らげたり、眠りやすくしてくれますよ」「ありがとうございます。昼間にお昼寝しすぎたのがダメだったみたいです」「あはは。じゃあ、少しお話でもしましょうか? 例えば、アラン王太子殿下の子どもの頃の話とか」「うわぁ、聞きたいです!」 慣れた様子でジークがイスに腰かけると、嬉しそうにジークの向いに座った。「アラン王子は小さいころから大変な美形でね。侍女たちが追い回していたんですよ。それはもう大変な騒ぎで、パーティなどがあると、必ず母から私に王子を守りなさいと指示がでるのです。ですから、よく二人で抜け出して、厨房や控室などに隠れて遊んでいました。」「ふふふ。楽しそうですね」「そうなんですよ。お腹がすくと見習い侍女だったフランソワがこっそり差し入れを持ってきてくれて、隠れて3人で食べたりしてたんですよ」「わぁ、いいなぁ。私も混ざりたい」 ゆっくりとホットミルクを飲みながら、今まで聞いたことがない父親の話を聞きながら、星空を眺める。いつの間にか、ヒカルはうとうとし始めていた。 ジークはそっとヒカルを抱き上げると、ヒカルのために準備しておいた部屋に連れて行く。「随分大きくなられましたね、王女様。お疲れがでましたかな」 ジークはそんな風に呟きながらヒカルの部屋のドアを開けた。その後ろ姿を、水を飲みに出てきたハワードが見かけた。大きなジークの胸に抱かれ、すやすやと穏やかな寝息を立てるヒカルからは、先ほどすれ違ったときのような不安な空気は感じられない。 ぼんやりと様子を見ていると、ベッドにヒカルを寝かせたジークが部屋から出てきてハワードと鉢合わせた。「ハワード殿、どうかされましたか?」「あ、いえ。少しのどが渇いたので、水を頂こうかと」 自分でもしどろもどろで歯がゆい。ハワードはなんとも居心地の悪い気分で台所へと行きかけた。「あの方は、まだお若いのに周りが見え過ぎてしまうのです。どう動けば穏やかにおさまりが付くか、いつもどこかで考えてしまうのでしょう。」 ジークはすれ違って後ろ向きのまま、誰に言うともなしにつぶやいた。ハワードは、つい振り返ってジークを見つめた。当のジークはゆっくりと振り返って笑みを浮かべた。「ですが、ご自分の気持ちにはなかなか素直になれない部分も多いようです。この旅の間になにかいいきっかけがあれば良いのですが。では、おやすみなさい」 そう言って通り過ぎていくこの屈強な騎士を、ハワードは茫然と見送っていた。「私は、何をやっているんだ。」 ほんの一瞬でもジークの行いに疑いを持った自分が恥ずかしかった。自分は逃げてばかりではないか。暗いキッチンで冷たい水を飲みながら先日の異世界日本でのことを思い出した。アランが怪我をして見舞いに行く途中で、ばったり「紅」シリーズの監督に遭遇していた。「ハワード?ハワードじゃないか!どうしていたんだ?」心から心配してくれていた監督に、ただ頭を下げることしかできなかった。「今からでも戻ってこないか? 俺はあのシリーズの続きがどうしても撮りたいんだ。おまえでなくちゃ、あの役は務まらない。」それは俳優にとってどれほどの誉れだろう。それでも、ハワードは首を縦には振れなかった。俳優の世界からも逃げ、ヒカルからも逃げているのだ。翌朝、領主の邸宅に戻って朝食をとっていると、ジョージが期待を込めた目で見つめながらヒカルに声を掛ける。「王女様、うちの領土は暖かで過ごしやすいでしょう? どうです。うちには一人、婚期を逃しそうなのがいるのですが、一度考えてみてはもらえませんか?」「おい、失礼なことを言わないでくれ。」 ジークは慌てて止めに入るが、夫妻はちっとも気にしない。「まぁ、ジークったら、こんな愛らしいお嫁さんなら、あなただって嬉しいでしょう?」「王女様が困ってらっしゃるだろう。まったく、好き勝手なことを言わないでくれ」「でも、父が結婚を決めたのですから、次はジークさんの番なんじゃないですか? 私みたいな子供ではなくて、ちゃんとしたいい人がいらっしゃるのではなくて?」 ヒカルまで話に乗ってきた。ジークは途端に耳を赤くして、しどろもどろになった。「はぁ、仕方がないな。まったく、ヒカル王女様はするどくて困ります。一応想い人はいる。それだけだ。」「あら?ん? ん~、もしかして…」 うすいとび色の瞳がくるりと動いてジークを捉える。その瞬間ジークの顔が真っ赤になった。「や、えっと。王女様、あの。」「ふふふ。善処します。あ、でも、チャンスがあれば、私が旅から帰るのを待たなくてもいいですからね。」「あらあら。なんだか進展がありそうですわね。王女さまからのお知らせと息子からの知らせ、どっちが先に来るのかしら。今から楽しみですわ」 食事が終わると、ジークは王城に戻り、ヒカルたちも昼前には次の目的地に出発することになった。ヒカルはハワードを誘って、砂浜に散歩に出かけた。昨夜のハワードの様子がおかしいと感じていたからだ。しかし、ハワードが家庭の事情を話すことはなかった。「ハワードさん、何かあったの?元気がないみたいだけど」「いえ、特には…」 言葉が途切れてしまう。その穴を埋めるように、穏やかな波の音が続いていた。海を見つめていたヒカルは、視線をハワードに移してその言葉の続きを待った。「王女様に聞いていただけるような物ではないのです。人間のドロドロした感情などに触れていただきたくはない」「…そうですか」 視線を落としたとび色の瞳に薄茶の巻き毛が揺れている。返事に困ったハワードは海原の向こうに目をやった。「では、帰りましょうか。リッキー達も待っているでしょうし」「はい…」 それ以上、何も言わないヒカルに、ハワードの胸中は揺れていた。つづく
April 30, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第1章 南の地で気づく心配事 3
翌朝、夜遅くに実家に戻っていたジークが、自家用船で離島の別荘に4人を案内した。「リカルド、エリザベス、今日はお前たちに休暇を与える。こっちの別荘でゆっくり遊んでくれ。王女のお世話は俺が任されよう。この島は丸ごとうちの別荘だから、自由に遊んでくれていいぞ。ただし、向こうの岩場は危ないから、気を付けてな。」「「やったー!!」」 リッキーはベスと手をつないで早速浜辺へとかけて行った。ジークはその姿を見送って、ハワードに向き直る。「ハワード殿、君も自由にくつろいでくれ。釣りをするなら、さっきの船着き場の近くに突堤がある。近くの小屋に道具も置いてあるから良かったら声を掛けてくれ。」「ありがとうございます」「私も釣りをしてみたいなぁ。ジークさん、良いですか?」 ヒカルは今まで一度も釣りをしたことがなかった。3人はさっそく突堤に向かい、釣竿を垂らすことにした。年老いた釣り小屋の管理人がヒカルにツバの広い麦藁帽を手渡す。「お嬢さんにはこれを。日差しがきついですから、日焼けしては大変ですよ」「ありがとうございます。ここには釣りのお客さんも多く来られますか?」 管理人は日に焼けて深くしわの入った顔をほころばせて、楽し気に笑った。「ここはウェリントン領主さまの別荘ですから、お客さんは領主さまのお客様だけですよ。さ、大物を狙ってくださいよ」 突堤の真下は透明度の高い海だ。波間に魚の影が見えている。朝が早いので、風が爽やかに吹き渡る。静かな波音が絶え間なく聞こえて、まるで別世界に来たような感覚だ。「うわぁ!」 突然、ハワードの釣竿がしなって持って行かれそうになる。「一気にひっぱらないで、じっくり引き寄せて」「おお、すごい手ごたえですね」 珍しく頬を紅潮させたハワードが、じわじわと魚を手繰り寄せる。年齢からは想像できないような素早さで、管理人が網で補助すると、見事な魚が吊り上がった。「さあ、ここに。」 管理人が差し出した容器には、氷が詰め込まれている。ハワードが針を引き抜いている間に、今度はジークの釣竿がしなりだし、同じく見事な魚を釣り上げた。 「わぁ、すごいなぁ。」 ぴちぴち撥ねる魚と動かない自分の釣り竿を見比べるヒカルも、「ひやぁ」と声をあげた。釣竿が引っ張られている。ぐいぐい引っ張られる感覚に心がワクワクしてくる。「ゆっくりですよ」 管理人が網を差し出そうとしたその時、釣竿が急に軽くなって、魚に逃げられてしまった。「え~、悔しいなぁ」「あははは。残念でしたねぇ。」「逃した魚は大きいってやつですな。ほっほっほ」 そんなやりとりをしながら朝の時間を過ごし、別荘に戻ってきた。ハワードとジークが釣った魚は、アクアパッツアになってお昼ごはんに登場した。 午後からも、リッキーとベスは海岸に出かけ、ヒカルは浜辺が見える別荘の庭に設えられたハンモックで木漏れ日の中、ゆっくり読書を楽しんだ。ジークは夜のバーベキューの準備をすると言って、食材の調達にでかけ、ハワードは別荘の書棚にあった植物図鑑で何やら調べものを始めた。 波の音がこんなに心地よいなんて、いままで知らなかった。木漏れ日の優しい光と、程よい海風に吹かれて、ヒカルはうとうと昼寝を始めた。 夕陽が水面にオレンジの光をちりばめている頃、ジークがバーベキューを始めた。新鮮な魚介のバーベキューに舌鼓を打って、今日はお開きとなる。それぞれに一部屋を用意してもらって、大はしゃぎしていたリッキーとベスだったが、気が付くとベスの部屋でチェスの駒を握りしめたまま二人そろって眠りこけていた。 深夜になって、それまで調べものに精を出していたハワードが、ベランダに出てきた。静かな波の音と、月の輝きが浮足立っていた気持ちを沈めてゆく。ベランダに並べられたボンボンベッドに身をゆだね、ぼんやりと星空を眺めると、まるでさっきまでの光景が夢だったかのような錯覚にとらわれる。「はぁ、ずいぶんと遠くに来てしまった」 ヒカルが転移してきたのに対して、ハワードは何者かによる召喚だ。撮影に忙しくする日々が突然途切れ、気づいたときにはルクセン伯爵に保護されていた。男色の気がある伯爵から逃れるのは手間だったが、俳優業をしていたら、監督や立場のある人物から無理な要求をされることもあったので、ハワードは難なく逃げおおせてきた。伯爵の失脚によって、シルベスタの執事へと立場を変え、それは激動の日々ではあったが、大人のハワードにとっては自由のある暮らしだ。しかし、深夜の月と波音が誘うのは、思春期の不安に揺れ動く時代への郷愁だ。家族と買い物中にスカウトされた若き日のハワードを、当時父は面白がって俳優を目指せといい、母も嬉しそうだった。映画に出るようになると、弟も友達に自慢ができると喜んでいた。しかし、「紅の騎士」の人気で、今まで以上にファンに囲まれることが多くなると、事態は一変した。ロケバスの周りにも、近くのビルのトイレにもファンが待ち伏せしていた。ロケバスのカーテンの隙間からカメラのレンズが覗いていてぞっとすることも度々だった。それでも、外に出ると、多くのファンに応援されているのが心地よかった。問題は、実家に帰った時だ。 外とは全く別の世界が広がっていた。玄関のドアを開けると、いつも弟のリチャードが仁王立ちして睨んでいた。そして、手を差し出して金を要求する。手渡しても黙ってひったくるようにして出ていくだけだ。ギャンブル狂いの父はほとんど家にはいない。母は紅の騎士の契約金が入ったとたん、家に戻ってこなくなった。金庫に入れていた契約金はなくなっていた。どんなに人気があっても、孤独だった。映画、テレビ、グラビア撮影。露出度が上がると、油断する暇もない。本当の自分はどこに行ってしまったのだろう。自分は家族に何をしてしまったのだろう。家のベランダから海が見えたので、よくこんな風に夜風に当たりながら自問自答しながら波の音を聞いていた。 執事としてシルベスタの元で働くことは、何の苦痛もない。給金も良いので、不安はない。ないのだが、この胸にぽっかり空いた空洞のような焦燥感はなんだ。ふと、すさんだ弟の顔が浮かんで、一層心を引きずり降ろされる感覚に襲われ、ハワードは深いため息をついた。つづく
April 29, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第1章 南の地で気づく心配事 2
翌朝、ヒカルはベスに手伝ってもらいながら、少しだけドレスアップした装いでミシェルと落ち合った。ウェリントン家の馬車に乗って、海岸沿いの道を進む。到着したときの、昼下がりの海辺も美しかったが、朝の空気は格別だった。 ミシェルの案内でシーグラスのお店やアクセサリーの店を見て回った。お昼になって、街中のレストランで食事を楽しんでいるとき、事件が起きた。「こら! 待て! それは売り物だぞ」 隣のベーカリーから飛び出してきた子供が、コック帽をかぶった男性につかまっている。子供は「離せ!」と暴れているが、その腕にはバケットが2本抱えられている。「まあ、どうしたのかしら」 ミシェルが驚いている傍で、ヒカルがリッキーに目配せする。リッキーはすぐに騒動の中に割って入って、お金を払ってやると、子どもを連れて戻ってきた。周りが心配そうに見守る中、ヒカルはなんでもないように声を掛ける。「こんにちは」「…」 ヒカルが声を掛けても返事は返ってこない。絶対に口を聞いてやるものかときゅっと唇が閉じられていた。「お店のものはお金を払わないと勝手に持って行ってはだめなのよ。知らなかったの?」「そんなこと知ってる!」「知ってるのに勝手に持って帰ろうとしたの?」 子どもはぷいと横を向いてしまうが、その小さな手は強く握りしめられていた。その時、ふいにハワードが子供の傍に座り込んで声を掛けた。「何か事情があるのでしょう。話してはくださいませんか?」 少し後ろに下がりながら戸惑う子どもににこりと人好きのする笑顔を向けて、尚も言い募る。「私にも年の離れた弟がいるのです。あなたを見ていると、つい懐かしくなってね。ご両親はいらっしゃいますか?」「…お母さんはいない。お父さんは病気になったからって、会社をクビになったんだ。ぼんやりして、めそめそして…。だから」「そうでしたか。病院には行きましたか」「行ったよ。行ったけど、原因が分からないって言われたんだ」「そうか。それは大変でしたねぇ。」 ハワードが子供の背中をさすっていると、ミシェルが声を掛けた。「ねえ、もしかして、あなたはグランディから来たの?」「うん」「グランディというところに何かあるのですか?」 ヒカルがミシェルに問う。ミシェルは美しい瞳に陰りを乗せて「そうなの」とつぶやいた。ミシェルは連れていた執事に声を掛け、少しの生活費を子供に渡した。「お大事にね。気を付けて帰るのよ」「あ、ありがとう。あの、お名前を聞いてもいいですか?」おずおずと顔を上げた子供に、ミシェルは微笑んだままそっと首を横に振った。そのまま皆に促されて子供は帰っていった。 邸宅に帰ってくると、ミシェルはジョージと相談して、ヒカルに事情を話すことにした。「王女様にはお恥ずかしいところを見せてしまったようですね。ミシェルが言ったように、グランディという村には今奇病がはびこっています。もう3年目になるでしょうか。この季節になると、頭がぼんやりして、鼻水がとまらなくなったり、くしゃみがとまらなくなったりする者が増えるのです。それはもう仕事どころではない様子で」 ジョージは頭を抱えていたが、ヒカルはその症状に覚えがあった。きっとハワードも。ちらりと視線を送ると、やはり同じことを考えていたのか、ハワードもヒカルに視線を送っていた。「ウェリントン公爵、私が異世界で育ったということは、もう公になっていることなので隠しませんが、その異世界にも似たような症状の病気があります」「そ、それは本当ですか!」 ジョージはしがみつくようにヒカルに問いただした。王国内のいろんな地域の高名な医者を呼んでも原因も治療方法も分からなかったのだと言う。ハワードが花粉症の症状や原因について説明すると、ジョージには思い当たることがあるようだった。「グランディの南に4年ほど前から広い畑が出来たのです。茎を干して土産物の材料にするのだとか。もしやそれでは…」「もし、可能であれば、その植物の生産をやめるか、別の場所に移した方がいいんじゃないでしょうか」 ヒカルはそういいながら、ハワードに助言を求めた。「風向きにもよりますね。花粉が飛ぶ季節の風向きを調べたら、どこで栽培するのがいいか分かってくるのではないでしょうか? 薬については、一度シルベスタ様と相談してみます。」「そうですか。ありがとうございます。分からないことだらけだったので、大変助かります」 食後、ハワードはヒカルの魔力を借りて王城に転移した。薬の調合などは専門家からも助言してもらうためだ。そのハワードが出かけている間に、ジョージの弟がウェリントン領に顔を出した。「よぉ! 今日は近くまで仕事に行っていたからちょっとよらしてもらったよ。おや、今日は客人が来ているのか?ずいぶん若くてかわいいお客さんだね。やぁ、こんにちは。これはうちの領土で採れたオレンジだ。よかったらみんなでどうぞ」 陽気な弟はどさっとオレンジの入った箱を置くと、楽し気に話し出す。ヒカルやベスが驚いているのもお構いなしだ。「今日は東部の商工会があってね、ルクセン伯爵にも久しぶりに会ったよ。まあ、あのパーティー以来ずいぶんとおとなしくなっていた。いやはや彼はずいぶんとやりたい放題だっただろ?周りもほっとしているんじゃないか? そういえば、彼は男色の気があると言われていたけど、あの美形の執事は最近見ないなぁ。あの執事も彼の毒牙にかかった口だろうかねぇ。かわいそうに」「おい、女性の前で言う話じゃないぞ」 ジョージに言われて「しまった」と顔をしかめた弟は、「では、お先に失礼するよ」と帰っていった。ハワードさん、大丈夫だったのかしら。ミシェルにオレンジを勧められて口にしたが、酸味と微かな苦みがあって、ヒカルの心を一層締め付けた。つづく
April 28, 2022
コメント(2)
-
REALIZE2 第1章 南の地で気づく心配事 1
REALIZE 2第1章 南の地で気づく心配事馬車に揺られてまだ見たことのない街にやってきた。先ほどからカーテン越しにも辺りがまぶしいのが分かる。ヒカルがそっとカーテンを引くと、目の前には春の日差しをきらめかせた海が広がっていた。 異世界日本で生まれ、父であるアラン王太子殿下とともにアイスフォレスト王国にやってきたヒカルも15歳になっていた。薄茶の巻き毛は淑女らしく波打ち、アラン譲りのうすいとび色の瞳も健在だ。日本にいるときは身分を隠し、コーヒー専門店を小学生だったヒカルと二人三脚で営んでいたアランも、今ではすっかり王太子としての仕事が板についてきた。この旅は、そんなアランと魔術の師匠であるシルベスタが、ヒカルに指示したものだ。「うわぁ、まぶしい! でもきれい」「海ですね。もうすぐ、今日の目的地に到着しますよ」 ヒカルの隣で一緒に窓の外をうかがっていたハワードが説明する。ハワードはヒカルと同じ世界から突然何者かに召喚されてきた売れっ子俳優だ。実はその人気は日本にも届いていて、ヒカルも彼の大ファンだった。腰まで伸ばしたうすい金髪を後ろで束ねた、水色の涼やかな瞳が印象的な青年だ。本来は大魔術師シルベスタの執事として働いているが、今回は主の命を受け、ヒカルの教師役として旅を共にしている。そして、アイスフォレスト王国南部のこの美しい街はアランの護衛である第一騎士団長ジーク・ウェリントンの父、ウェリントン公爵の領土だ。 ヒカルがこの世界にやってきて初めてのパーティーでも、ぜひ自分の領土に遊びに来てほしいと声を掛けられていただけあって、きれいな海岸や点在する島々、港町の家々はみな白い壁に色とりどりの鮮やかな屋根がメルヘンチックな風景だ。 ウェリントン公爵邸に到着すると、初老の執事が数人の侍女を連れて出迎えてくれた。「ようこそおいでくださいました。中でウェリントン夫妻がお待ちかねです。」「素敵なところですね。気温も暖かいし、海辺の景色も素晴らしかったです。」「喜んでいただけて光栄に存じます。ここは漁業も盛んですので、後程、おいしい魚料理を楽しんでいただきます」 屋敷の奥へと案内しながら、どうぞごゆっくりと扉を開けて促した。扉の向こうでは、ウェリントン公爵夫妻が満面の笑みを浮かべて待っていた。「よくいらっしゃいました。ジークから連絡をもらって今か今かとお待ちしておりました。」「まぁ、ワンピース姿も愛らしいわ。王女様、ぜひゆっくりしていってくださいね。」 この旅のメンバーは4人。ヒカルとハワード、そしてヒカルの護衛のリッキーと侍女のベスだ。旅の間はあまり身分を表に出さずにいようと、4人は動きやすいよう、軽装にしている。「あの帰還パーティーの時から、いつか訪れてみたいと思っていたのです。ほんとうに素敵なところですね。今日からお世話になります。」 先ほどの執事が指揮をとり、4人の荷物が運びこまれる。ウェリントン公爵は自ら客室を案内してくれる。広いベランダが設えられた客室はゆったりとして心地よい。「うわぁ、素敵!」ヒカルはすぐさま窓を全開にして、ベランダからの景色を楽しんだ。潮風が頬に当たって心地いい。「夕食は私たちとご一緒していただきます。それまでごゆっくりお寛ぎください。皆さんのお部屋は後程執事がご案内します。」 公爵は、どこかジークによく似た慈愛に満ちた笑顔でリッキー達に語り掛けると、部屋を出て行った。「俺たちの分まで一人に一部屋ずつ用意してくれるなんて、団長の家は太っ腹だなぁ。」 護衛のリッキーことリカルド・マイヤーは第一騎士団に所属していて、ジークは直属の上司だ。そのジークに指名を受けて、ヒカル王女の護衛に当たっている。リッキーが初めてヒカルに出会ったのは、異世界日本で行方不明になっていた王太子殿下を探しに行った時だった。その時の縁があって、王女様と護衛騎士、専属侍女、執事というバラバラな立場の4人は、すっかり打ち解けたお茶のみ友達でもあった。「こちらには3日ほどお世話になる予定です。夕食までまだ時間がありますし、街中を散策されますか?」 ハワードに誘われて、ヒカルも二つ返事で出かけた。美しく整えられた道路、きれいな街並み、観光地として栄えてきたのだろう、土産物屋も人当たりよく穏やかだ。美しい貝殻を拾ったり、岩場にカニを見つけたりして楽しんだ。館に帰ると湯あみを済ませ、魔術師としてのローブに着替えて夫妻との晩餐に参加した。本人にあまり自覚はないが、王城魔術師のシルベスタが恐れるほどの魔力の持ち主だが、今はシルベスタの下で修業中なのだ。「王女様は魔術師でもあらせられたのですか?」「ふふふ、あなたご存じなかったの? ソフィア王妃様から散々自慢されていたのよ?」 楽し気な夫婦の会話に王妃の名前が挙がるほど、公爵家は王族と親しいのだ。「この若さで王宮魔術師として認められているなんて、本当に素晴らしいですわ」「シルベスタ先生の教え方が上手なんです」 ジークの計らいか、4人は同じテーブルで一緒に食事を楽しむことが許されていた。「ヒカル王女様、そのペンダントはもしかして…」「ええ、お守り石のペンダントです。」「噂はかねがね伺っています。リカルドさんを守ったというお守りアクセサリ―ですよね。」ミシェル・ウェリントン公爵夫人は興味深々の様子で話していたが、ふとリカルドに目を向けて言う。リカルドは慌てて頷いた。「そういえば、リカルドさん、息子は厳しくしていない? 無理なことは言ってないかしら」「はい。団長にはほんとに良くしていただいています。面倒見がいいから、騎士団のみんなからすごく慕われているんですよ。」「そう、それなら良かったわ」とミシェルが胸をなでおろした。「あの子は気が優しいのはいいのだけど、不器用というか…。なかなかいい人にも出会えなくてね。」「ミシェル、彼らにそんな話をしても困ってしまうだろ。そうだ、君たちの事は聞いているよ。いいご縁があって、良かったね。ジークにもだれかいい人がいたら紹介してやってくれ」 ジョージ・ウェリントン公爵は、そんなに焦っている様子もなく、朗らかに笑いながらそう言った。「そうだわ。明日の夜にはジークも休暇を取って帰ってくるの。それまでに、街中にお買い物に行きましょう。今、うちの領地では、シーグラスを使ったアクセサリーが流行っているのですよ。王女様もきっとお気に召しますわ」 次々出てくる海産物はどれも新鮮でおいしい物ばかりだ。明日の買い物の約束をして、たのしい食事を終えると、それぞれ部屋に戻っていった。ヒカルは、そっと海側の窓を開ける。穏やかな波の音が心地いい。海を渡ってきた風が湿り気のある独特の空気を運んでくる。「なんだか落ち着くなぁ。海って、そう言えば行ったことなかったかも」「ヒカル王女様の以前お住まいだったところは海が近くになかったですよね」 ヒカルは、ベスが就寝の時間を言ってくるまで、波の音を聞きながら、ぼんやりと波に揺れる月の光を見つめていた。つづく
April 27, 2022
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1