[貝の鳩] カテゴリの記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
貝の鳩 その27
ジェシーは冷えたビールを男たちの前に運び出した。それに続いて料理を運び出すと、すでに庭先にはテーブルやイスがセットされていた。「待っていろよ、ミー。テーブルクロスが先だ。」 ジークが銜えたばこでクロスを広げる。隣でゴードンが楽しげに笑っていた。「懐かしいねぇ。お前さん、いつもミーって呼んでたよな」 台所でマーサがミシェルを呼んだ。かぼちゃをミキサーにかけろと言う。急いで台所に戻ったミシェルはミキサーを取り出し、やわらかくなったかぼちゃをミキサーにかけた。「まだまだ!もっとしっかりね!」 マーサに言われてじっくりミキサーにかけると、滑らかなスープが出来上がった。「さあ、みんな席について。乾杯しましょう。」マーサが残りのグラスを運びながら皆を席にいざなった。「みんなと再び会えたことに、それからいつの間にか大人になった娘に。先月、お誕生日だったでしょう?」「忘れてた!」「カンパーイ!」 久しぶりの宴は、懐かしさとほろ苦さが交じり合った優しい時間だった。ゴードン夫妻を見送って、三人は家に戻ってきた。久しぶりに自分の部屋にもどったミシェルはそっとベッドに横たわる。日向のにおいがするのは、マーサが干しておいてくれたからだろう。隣の客間でも人の気配がある。ジークだ。壁越しに聞こえてくる物音を聞いていると、あの頃の納戸での暮らしを思い出す。薄い壁を隔てても、ジークの存在は安心感を与えていた。ジークは自分との血のつながりがないことを誰かに聞いただろうか。ぼんやりと考えているうちに眠りに落ちていった。翌朝、目覚めて階下におりると、マーサが縫い物をしていた。「おはよう。あれ?叔父さんは?」「やっと起きてきたのね。デュークなら、ご両親のお墓参りに行ってくるって早くに出かけたわよ。市場に寄ってもらおうと思ってるから、帰りは夕方でしょうね。」「そう」ミシェルは紅茶を淹れてパンを焼き、自分用の朝食を作った。マーサにも紅茶を淹れて手渡すと、さっさと食べ始めた。ジークがいないと分かると、なんだか肩透かしを食らった気分だった。ミシェルが朝食を食べている間に、近所の主婦が何人もやってきては、マーサと立ち話を楽しんだ。この家にたった一人になってしまった母を孤独だと思っていたが、どうやらマーサはちゃんと自分の暮らし方を見つけているらしい。夕方、ジークが帰ってくると三人は普通に食事をして普通にその日のことをしゃべりあった。それはあまりにも自然で、まるで家族のようだった。休暇も最後の朝を迎えた。ミシェルはジークに事実を伝えるチャンスを見つけられないまま、宿舎に帰る準備を進めていた。荷物の少ないジークはすでに階下におりている。「マーサ。実は、俺は今、陸軍のある部隊の指揮官をやっているだが、ミシェルは俺のいる部隊に配属されているんだ。」「まぁ!そうだったの? じゃあ、あの子に危険がおよばないように守ってね」 マーサの願いは当然だが、ジークは首を振った。「悪いけど、特別扱いはできないんだ。でも、心配はいらないさ。俺はアイツに助けられたことがあるぐらいだから。アイツに怪我の手当ての仕方を教えたのはマーサ?」「ええ、そうよ。スチュアートは子ども相手でも容赦しなかったから。怪我をして泣いてる事も多かったのよ。きっと自分は長くないとわかっていたのね。それでミシェルには何があっても大丈夫なように鍛えていたんだわ。だから、せめて怪我の手当てぐらいは教えておこうと思ってね。役に立ったのかしら?」 ジークは苦笑いをして頷いた。「命を助けられたんだよ。ありがとう」 マーサはちょっと諦めたように笑う。「どうか、大きな怪我をしないように気をつけてあげてね。あの子が帰ってきたのを見たとき、随分大人になったと思ったの。だから、今から少しずつ縫い始めようと思ったのよ。」 そう言って隣の部屋のドアを開けると、トルソーに真っ白なドレスが着せてあった。「レースはこれから縫い付けるの。まだまだかかるけど、ミシェルに似合うと思うから」 ジークは少し耳を赤らめた。「じゃあ、そろそろ行くよ。いろいろありがとう。また休暇をとって、アイツをつれて帰るから」「そうね。気をつけて」 ミシェルが自分の部屋から降りてくると、ジークはすでに二頭に荷物を積み込んでいた。「お母さん、ありがとう。またお休みの日に帰るね」「気をつけてね。」 マーサは微笑んで見送った。丘を下り、広い草原の道を進む。振り返るとマーサが佇んでいるのが見えた。二人は大きく手を振ると、再び宿舎へと馬を走らせた。 途中の川原で馬を休ませる。そこは二日前に初めて二人が心を打ち明けた場所だ。今日はというと、さっきまで振り向きもしないで前を走っていたジークがのんびりとタバコをふかしている。今、自分たちに血縁がないと知ったら、ジークはどんな顔をするだろう。ミシェルはくすっと笑う。「ジーク。一昨日、母から聞いたんだけど、私たち…」「知っている」 ジークは視線を馬に向けたままつぶやいた。「ホントに?」「ああ、ゴードンさんが教えてくれた」 ミシェルはその続きが聞けるのかとじっと待っていたが、ジークはそのままタバコをふかすばかりだった。「どうかしたか?」「だって、せっかく障害がなくなったのに」 ジークは立ち上がると指笛で馬を呼んだ。「俺は職業軍人だ。またリュードのような危険な任務がやってくるかもしれない。もしものとき、お前はマーサのようにしっかりとしていられるのか?一人ぼっちになるかもしれないんだぞ」「リュードから死亡通知が来たとき、とても辛かったわ。だけど、信じてた。絶対帰ってくるって無事でいるって、信じてた。」 ミシェルは馬に乗り込むと、勝気に言う。「私が王女の身代わりでマルコス王子と会っていた時、ジークは絶対私情を挟んでた。これから先、私を放っておいて、またあんなふうに男に言い寄られても冷静な判断が出来るのかしら。」 ジークはそれには答えずにさっさと馬を進めた。「さっさと来い! 俺は亭主関白なんだぞ。」 その言い合いは宿舎に戻るまで延々と続いていた。終わり
September 13, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その26
「お母さん、ただ今!」 玄関を開けると、おいしい匂いが漂ってきた。「お帰り、ミシェル!元気にしてた?」「ええ、おかげさまで!」 マーサは娘をぎゅっと抱きしめて再会を喜んだ。「マーサ、お久しぶりです。」「まあ! デュークじゃない!ほんとに久しぶり!すっかり男らしくなっちゃって、さあ、中に入って。今、お茶を淹れるわ。」 勧められるまま、ミシェルとジークはリビングへとすすんだ。窓辺には車椅子が置いたままになっている。 二人はそれをじっと見つめていた。 お茶を淹れたマーサが、二人の前に差し出すと、恥ずかしそうに笑った。「おかしいでしょう?だけど、あの場所にこれがないと、さみしくて。パンプキンパイはいかが?あの人が元気だった頃は、ちっとも実をつけなかったかぼちゃ、今年はいっぱい実をつけているのよ。」 マーサの眼差しはやさしいままだった。「ミシェル、まずはお母さんに言う事があるでしょう?ゴードンさんから聞いてるわよ」 娘の目をまっすぐに見つめるマーサに嘘はつけなかった。「ごめんなさい。だって、お父さんの病気が心配だったし、早くこの家に帰りたかったんだもの」「だからって、女の子が一人で男の人たちの中に飛び込んでいくなんて!」 表で人の気配がした。「あははは。やってる、やってる。マーサ、そんなに叱らないでやってくれよ。ミシェルちゃん、がんばってたんだからさ」「まあ、ゴードンさん。ジェシー。いらっしゃい。」 ゴードンと女房のジェシーがやってきたのだ。「ミシェルちゃん、この度は大活躍だったねぇ。」「そうさ。マーサ、聞いて驚くなよ。この子は王女の代役をしてたんだぜ。」「ええー!ミシェルが?」 マーサはめまいを起こした。「冗談でしょう? マナーもなにも教えてないし、男か女かわからないような子なのに」 一同はわっと笑った。「何言ってるんだい。ちゃんとしたドレスを着て、カツラをかぶっていたら、ほんとうにきれいな王女さまだったよ。デューク、お前も見ただろ?」「ああ、馬子にも衣装だな」 ジークはさらりと言ってのける。ミシェルはちらっとその姿を見て、唇を尖らせた。 軽快は会話が弾んでいた。随分前にもこんな風にみんなでわいわい話をしていたような気がする。父がいて、母がいて、仲間がいて。ミシェルはぼんやりと昔の事を思い出していた。 昔の仲間がそろったので、皆でスチュアートに会いに行こうということになった。みんなが順番にスチュアートに声を掛ける。姿は見えないが、まるでそこにいるかのようだ。 スチュアートの墓前に花を手向けると、ジークは静かにつぶやいた。「兄さん。今の俺の姿、見てもらいたかったよ。兄さんのお陰で今の俺がある。そう言ってもいいほどなんだ。ありがとう、兄さん。また来るよ」 一行は墓地を抜けマーサの家に帰ってきた。 ゴードンとジークは庭先でのんびりと話している。その間にマーサとジェシーは夕食の準備にかかっていた。「あら、ミルクが足りないわ」「じゃあ、ちょっと買ってくるわ。ちょうどうちの人にビール買ってこいって言われてたのよ。」 ジェシーは慣れた様子で出かけていった。「ミシェル、お皿を出して。」 マーサの指示で宴の準備はどんどん進んで行く。 「ミシェル、かぼちゃのスープの作り方を教えるわ。いらっしゃい」 ミシェルにかぼちゃの下ごしらえをさせながら、マーサは他の料理を作り始めた。そうしながらふと手を止めてつぶやいた。「ふふふ。今日、あなたが帰ってきた時、一緒にデュークがいたでしょ?私、びっくりしちゃった。」「どうして?」「あなたはもちろん、覚えていないだろうし、デュークも忘れてしまっただろうけど、あなたは幼い頃、デュークが大好きだったのよ。いつも抱っこしてもらっていたわ。寄宿学校に入学が決まった時、ミシェルったらこの世の終わりみたいな顔をして、部屋に閉じこもって号泣したのよ。」 マーサはその頃のミシェルを思い出したのかいとおしそうに言う。「だけどいよいよ出かけるという時に、あなたの宝物だった貝殻の鳩を握り締めて出てきたの。これをミシェルだと思って大切にしてねって言ってデュークに手渡したのよ。」「随分ませてたのね」 気恥ずかしい気持ちでいた。そんな頃から、私はジークのことを大切に思っていたんだ。「ふふ。貴方が徴兵に行ってから、よくスチュアートが話していたわ。デュークはきっと軍で頭角を現わすだろうって。ミシェルがもし軍人として働いていたら、向こうで出会うかもしれないって。それで、向こうで出会って二人が結婚したいって言ってきたら、素敵だねって。だから、二人が一緒に帰ってきた時、心臓がドキドキしたの。あの人の夢がかなうんじゃないかってね」 かぼちゃを切る手が震えていた。「でも、叔父さんと姪じゃ、結婚は無理よ」「普通はそうよね。でも、デュークはスチュアートの継母の連れ子だったらしいから、血はつながってないのよ。デュークはまだ赤ちゃんだったから覚えてないだろうけど。だから、そうなれば素敵なのにねって、思っていたの。ほら、早くかぼちゃをなべに入れてちょうだい」 心臓がドキドキ音を立てた。叔父さんじゃなかったんだ。慌ててかぼちゃをなべに入れてスープで炊く。玄関ではジェシーの声がしていた。「ミルク買ってきたわよ。」 慌てて返事をして玄関に飛び出すと、ジェシーが驚いた顔をした。「あら、ミシェルちゃん。なんだか顔が赤いわよ。大丈夫?」「う、うん。ちょっとのぼせちゃったのかな。」
September 6, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その25
「ミシェル。いろいろありがとう。お陰で邪魔の入らないうちにアーノルド王とじっくり話をすることができたよ。」「おめでとうございます。もう王様の貫禄ですね」 驚いたような顔でミシェルを見つめると、王子はちょっと寂しそうに答えた。「ごめん。前にも同じ言葉を姉から言われたんだ。あれは、大学を卒業した時だっただろうか。レイチェルに認めてもらった気がして、ものすごくうれしかった。それなのに…」「ハドソン王子。美しく賢い王女さまのこと、いつまでも忘れないでいてあげてくださいね」 ハドソンは静かに頷いた。「今朝、リュードのフォレスターという人物から連絡をもらった。レイチェルの遺骨を返してくれるということだった。近いうちに、レイチェルの葬儀をしなければならないな」 その沈痛な胸の内はミシェルにも痛いほどわかる。「ハドソン王子。これで私の任務は終了いたしました。もう、お目にかかることは敵わないかもしれませんが、どうかお元気で」「ミシェル、君もな」 ミシェルは静かに敬礼した。王子もまた、それに答えた。 宿舎の車が王室の敷地に入ってきた。ジーク、ミシェル、スキャットマンの三人が乗り込むと、ロザーナが慌てて駆け寄ってきた。「ミシェル。元気でね。」「ありがとうございます。ロザーナさんも。ハドソン王子にお妃様が来られた時は、くれぐれもコルセットを閉めすぎないでくださいね」 明るい笑い声が響いた。 馬車が動き始める。見送る人々に手を振って、ミシェルはまたいつもの宿舎に戻ってきた。「隊長。申し上げにくいのですが、2,3日休暇をいただきたいです。任務の途中で父を亡くし、母のことも心配なので。」 ミシェルは帰還報告と同時に、休暇を依頼した。「いいだろう。ゆっくりしてこい。それから、偶然だが、私も休暇と取る予定だ。ディック、悪いが緊急連絡の時はよろしく頼む。フィル、出動の時は鳩をとばしてくれ」「イエス、サー!」 部屋に戻って夕食の支度を始める。先日ジークが持ってきた食料はどれも一人分で、分けて食べるには少なすぎた。 もう、一緒に食事をしようとは言ってもらえないのだろうか。コーヒーには口も付けずに机を叩いて出て行った後姿がまだまぶたに焼き付いている。 黙々と事務的に食事をしても、おいしいはずもなかった。 リュードに持って行った荷物を整理していると、貝殻の鳩が出てきた。 これは、あの時の! ミシェルの瞳から一気に涙が溢れ出した。頭の中をジークの言葉が次々に響いている。「どうだ、これから一つチェスでもやってみるか?」「独り者は俺たちだけだ。まあ仲良くやろうぜ。」「お前…。きれいだな」「だれがこんなところに来いと言った。お前は王女の身代わりになっていろと言っただろ」「あれほどそこにいろと言ったのに!」「そういうことじゃないだろう!」 あの手紙は、なんだったんだろう。自分の中に芽生えてしまった気持ちをどう打ち消したらいいのだろう。 目が覚めると早朝だった。どうやら泣きながら眠ってしまったらしい。肩にケットが掛けられている。いったい誰が掛けてくれたのだろう。 周りを見渡すとメモがあった。-鍵も掛けずに寝てしまうとは、何事だ!疲れは特殊部隊の天敵だぞ。3日間の自宅謹慎を命ずる!その間は絶対に自宅から出るなよ!-「隊長…」 ミシェルは急いで支度をして、早いうちに宿舎を出た。馬はもちろんハドソン王子から譲り受けたあの馬だ。朝靄の中を走り、途中の牧草地で休憩を入れる。木陰に座り込んで馬が草を食む姿を眺めていると、もう一頭の馬が現れた。「なんだ。お前だったのか」「隊長!お休みを取られたと伺いましたが」「俺の実家にはもうだれも住んでいないが、この先に兄貴の家があるんだ。」 ジークはミシェルの隣にどさっと座ると、馬たちの様子を眺めながら話し出した。「俺には年の離れた兄貴がいてな。親とはどうも意見が合わないが、兄貴はいつだって俺の味方だった。頭のいい兄貴はおれにチェスを教えてくれたし。武道の基本も教えてもらった。そんな兄貴が結婚して独立すると、おれは両親とケンカして家を飛び出したんだ。 それからは寄宿学校に入った。それも兄貴が金を払ってくれて実現したんだ。学生時代はよく兄貴の家に遊びに行ったもんだが、軍人になってからはすっかりご無沙汰していたんだ。ところがそんな兄貴が病気で亡くなっていたらしい。だから、今日は墓参りだ」「それって、もしかしてうちの父のことですか?でも名前が…」 ジークは足元に視線を落として頷いた。「そういうことだ。第三部隊にお前が来た時、まさかとは思っていたが、宿舎の部屋にあった写真を見て確信した。俺の名前はジーク・D・グロウ。デュークっていうのはセカンドネームだ。あの頃の仲間がそっちの方がかっこいいだろうって言って、ニックネームにしてたのさ。」「隊長、それじゃあ、隊長は私の叔父さんなんですか?」 ジークはポケットからタバコを引っ張り出して火をつけた。「どうもそうらしい」 さわさわと心地よい風が吹き渡っていく。きれいに晴れた草原と木漏れ日の煌き。それなのに、二人の距離を縮めることはできなかった。 不意にジークの腕がか細い肩をつかんだ。「そんな顔をするなよ。マーサが心配するじゃないか」 白い頬を流れる涙を拭って、ジークは寂しげに笑った。「お前が兄貴の子どもだってことが分かっても、自分の気持ちをとめることが出来なかった。だから、リュードに単身潜入すると決まった時、どうしても自分の気持ちを伝えたかったんだ。それなのに、お前はあんな危ないところに一人で飛び込んできて、おまけに俺の命を救ってくれた。」 ミシェルはたまらなくなって、大きな胸に飛び込んだ。ジークの腕がしっかりとミシェルを抱きしめる。このまま時がとまってしまえばいいのに。そんな思いは、二頭の嘶きに遮られた。「ミシェル。マーサに会いに行こう」 ジークは気持ちを引き剥がすように立ち上がると、自分の馬にまたがった。ミシェルもすぐさまそれに続く。二人は草原の風のように、丘の上にある懐かしい家を目指した。
September 5, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その24
握り締めた手に力がこもり、あっという間に腕の中に抱きとめられた。「ふふふ。お戯れを。前にも申し上げましたが、私はマルコス王子さまと結婚するつもりはございません。」「困ったお姫様だね。僕がこんなに愛しているっていうのが、分からないの?」 ミシェルはするりとその腕から抜け出して微笑んだ。「私の理想の殿方は強いお方です。自分の夫が女性を口説いてばかりで一人も幸せにできないような方では困るのです。」 言いながら、ゆっくりと歩き出した。「強い男? 僕はこう見えても腕には自信があるよ」「まあ、ホントに? じゃあ、私を捕まえられるかしら?」 ほほほと笑いながら、ミシェルはするすると歩幅を広げ、薔薇園へと向かった。宮殿の中の石畳より地面の方が倒されたときの衝撃は少ないだろうと考えたのだ。 女などすぐに捕まえられると踏んでいたマルコスは焦っていた。ミシェルは微笑んでいるが、するりと体をかわし、どうしても捕まえられないのだ。「マルコス王子、こちらですわ」 次第に額に汗がにじみ、その表情から笑顔が消えていく。「いい加減にしろよ。僕の気持ちが変る前に降参した方がいいんじゃないか?どうせハドソン王子だけじゃ、こんな国など簡単に僕の物になってしまうんだからな」 イライラした表情を隠そうともせず、ドレスの裾をわしづかみにして怒鳴った。「ふふふ。捕まえた。これ以上僕を困らせたら、あとでひどい目に会うぞ!大人しく僕の物になれよ」 ミシェルのあごを乱暴につかみ、マルコスは覆いかぶさろうとした。「うわぁぁぁ!!ああ、失礼!いやぁ、申し訳ありません」 黄色いバラの花束をマルコスの頬に押し当てて、男が倒れこんできた。「これは!マルコス王子さまではございませんか。もうしわけございません。」 土下座して謝る男にマルコスは目を血走らせた。「なんだ、お前は!」「ははぁ。王子様にこの花束を届けるように、そこにいらっしゃるレイチェル様から言われておりまして」 マルコスはシルクのハンカチで頬に伝う血を押さえながら、ミシェルを振り返った。「ええ、そうですの。黄色い薔薇の花言葉をご存知?」 マルコスはやや気をよくした様子で答える。「花言葉? 愛の告白かい?」「黄色い薔薇の花言葉は不貞。もっとも、マルコス王子のお国では、そんな考え方はないのかもしれませんね。この国が狙いだったんですね。でも、それは無理ですよ。」 ミシェルは微笑みながら近寄り踊るようにマルコスの腕を取ると、軽やかに投げ飛ばした。「何をする!」砂を払っていきり立つ王子にもう一度近づくと、今度は軽く足払いをした。「王女である私にこんなにも簡単に倒される王子さまの国が、そんなに強いのかしら?」「なんだと!」 つかみ掛かるマルコスの腕を片腕でねじ上げ、なおもやさしい微笑を浮かべてミシェルは言う。「マルコス王子。もっと痛いのはお好き?」 その細腕に力がこもると王子はうめき声を出した。「だ、だれか! この女を!」「だれも来ませんわ。ここはザッハードではないのですから。それに、あんなに優しいお妃さまがたを離縁なさって、貴方に王子としての居場所はあるのかしら。王家の結婚はそのまま国交の象徴でしょう?アーノルド王は認めていらっしゃるのかしら?」 マルコスの顔は次第に青ざめた。「僕を脅すのか?」「あら、脅していたのは王子様のほうではありませんの?」 さきほどの男が立ち上がった。「レイチェル王女様、今日のところはその辺で許してあげてください。男としての面目は充分つぶれてしまったでしょう。今頃は、ハドソン王子もアーノルド王との会談を無事に終えられているでしょうし。」 ちらっと見上げた男の目が「やりすぎだぞ」と語っている。ミシェルはそれには答えず、マルコスの腕を放すと、静かに言った。「今日のことは、聞かなかったことにして差し上げましょう。ですが、お忘れにならないでください。どんなに恵まれた境遇に生まれ落ちたとしても、それはあなた自身の功績ではないのです。あなた自身の功績は、これからご自分の手で築き上げていかなければならないのです。アーノルド王はご立派です。貴方にもその素質はあると思いますよ。さようなら、マルコス王子。」 ミシェルはそのまま宮殿に帰って行った。マルコスが呼び止めても振り向く事もなかった。救いを求めるマルコスの視線に男は静かに言う。「王子、王たるものがしなければならないことが何か知っているか?今からすぐザッハードに戻って、アーノルド王に教えを乞うんだな。それと、まだこの国を狙うというなら、お前の命なんぞあっという間に俺が奪ってやるぜ。」 男もまた、さっさとバラ園の中に消えて行った。一人残ったマルコスは白い衣装についた砂埃を払い、だまって黄色い薔薇の花束を見つめると、深いため息をついた。そのまま宮殿の中央玄関までぼんやりとした様子で向かう。近衛兵がどうしたものかとおろおろしている中を進み、乗ってきた馬車に乗り込んだ。王子の変りように戸惑いを見せながらも、ザッハードの近衛兵たちは一礼して馬車に続いた。 入れ違いに入ってきたのはハドソン王子の一行だった。隣国への挨拶を終え、少しずつ自信をつける王子は著しく成長していた。 ロザーナから事の次第を確認したハドソンは満足げに頷くと、すぐさまミシェルの部屋に向かった。「レイチェル王女、私だ」 扉を開けると、嬉しそうな笑顔が飛び込んできた。
September 3, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その23
王室への帰還は華々しいものだった。リュードにいた期間をハドソンはレイチェル王女が入院したことにしていたのだ。大きな羽根飾りのついた被り物をつけられた馬はミシェルと旅をした仲だ。ミシェルを馬車に乗せると、堂々とした足さばきで宮殿へと進む。 沿道には多くの国民が国旗を振って王女の退院を祝った。 跳ね橋があがり、馬車は宮殿の中に入る。一番に迎えてくれたのは、ロザーナだった。「王女さま!おかえりなさいませ」 ほろほろと伝うものはうれし涙に違いなかった。ロザーナに手を取られて、しずしずと中に進んで行くと、正装したハドソン王子が待っていた。「レイチェル王女。よくぞお元気になられました。心よりお喜び申し上げます。」 近衛兵のラッパが鳴り響き、ハドソン王子とレイチェル王女がベランダから国民に手を振ると、そのまま二人は奥へと入って行った。元気になったレイチェル王女を人目見ようと集まっていた人々は一様に嬉しそうに手を振り、満足げに帰って行った。「任務、ご苦労。それから、無事に帰ってきてくれてありがとう」 ハドソンに握手を求められ、ミシェルは笑顔で答えた。「君のお陰で、僕は変わったよ。君が、本当に、君が本物の女性だったらよかったのにと、君が出て行った日からずっと思っていた。しかしそれは敵わない夢だな。」王子のまぶしそうな視線が痛々しい。「だけど、今回はザッハードの王子をギャフンと言わせてやりたいんだ。」 気持ちを切り替えて王子は拳を握る。「なにかあったんですか?」 ハドソンにしては随分熱くなっていると思われた。「君は隣国に外交に行った事があるから知っているだろう? あの国は一夫多妻制。だけど、飽きたと言う理由だけで今までの妻を全部実家に帰らせたというんだ。もちろん、離婚と言う形をとってだ!」 あのパーティーで優雅に微笑みあうマルコスの妻達がまぶたに浮かんだ。彼女達はどうしているだろう。 ドアがノックされて、新しい執事が現れた。「申し上げます。先ほど、隣国ザッハードのマルコス王子さまより連絡が参りました。明日、レイチェル王女さまにお目にかかりたいとのことです」 ハドソンはため息をついた。「今日退院したばかりだというのに、随分失礼ではないか。丁重にお断りしてくれ。」「いいえ、大丈夫です。ご希望通り、明日お目にかかりましょう。」 ミシェルは覚悟を決めて了解した。「まったく、君の勇ましさには驚かされるよ」 執事が出て行ってから、王子は苦笑いを浮かべた。 部屋に戻ってドレスを脱ぐと、早々にアーミースタイルに着替えて調理室に向かった。「ミシェル!ミシェルじゃないか!よくぞ無事で帰ってきたなぁ!」 ゴードン夫婦はわが子のように喜んだ。「ミシェルちゃんの居ない間にいろんなことがあったんだよ。王様がニセモノだったりしてさぁ!」「おれはうすうす気付いてたんだ。王妃が亡くなった頃、王様は何も口になさらなかった。それなのに、翌日には平気な顔でモリモリ食事を摂っていたんだからな。」 賑やかな二人を見つめながら、もう国民にはこの事件が伝わっているんだと実感した。「そうそう、今朝、懐かしいやつに会ったよ。デュークだ。元気そうにしていたよ。スチュアートが亡くなった事はやはり知らなかった。随分驚いていたよ。それにしても、随分男らしくなっていたなぁ。今のミシェルちゃんを見たら、びっくりするだろうなぁ。あははは」「レイチェル王女様!レイチェル王女様!」 ロザーナの声がしてきた。ゴードンは苦笑いして手を振った。「お仕事だね。がんばっておいで。」 ミシェルはそっと会釈すると、すぐさま廊下に飛び出して行った。「レイチェル王女様、大変です。マルコス王子さまが、こちらに向かっているのだとか。すぐにドレスに着替えてください」 ロザーナは有無を言わさずミシェルを王女の部屋に引っ張って行くと、ドレスの準備を済ませ、カツラをつけながらつぶやいた。「気をつけてくださいね。ザッハードに行ったメイド仲間の話によると、マルコス王子は結婚と言いつつ婚礼の際に王女に付けて贈られる高価な品々や周りからのお祝い金が目当てだという噂がまことしやかに流れているそうです。それが証拠に、3年以上マルコス王子と婚姻関係にあった女性はいないということです。あなたは元々王女ではないのだし、しっかりと断りを入れて戻ってきてくださいね。ウイリアム王がなくなった今となっては、ハドソン王子だけでは脆弱だと見られてしまいます。もしかしたら、この国ごと乗っ取るおつもりかも…」「ロザーナ、ご心配かけてばかりですね。でも、マルコス王子には諦めていただきますわ。」 ミシェルは涼しげに笑って中央ホールに進み出た。ホールにはすでにマルコス王子が待ち構えている。真っ白の軍服には多くの勲章が輝いている。「これは、これは、レイチェル王女。ご機嫌麗しゅうございます。」「マルコス王子さま、しばらくご無沙汰しておりました。」 静かに会釈するミシェルにマルコスは熱っぽい視線を送る。そのままヘビのように視線をそらさずするすると進むと、すぐさまミシェルの手をとった。「あなたは罪な人だ。僕は貴方に出会って以来、他の妻との結婚生活ができなくなってしまった。もうあなたしか見えない。 レイチェル、君のせいだよ」
September 2, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その22
数日後、ツィン大佐は逮捕され、ツィンとラングレイの二人による、二国乗っ取りという恐ろしい計画も全て明るみになった。世間が大騒ぎしている中、任務を終えた特殊部隊のメンバーはそろって船に乗り込む。「お前、どこに行ってたんだ?」 ディックが慌てて船室に戻ってきたミシェルに声をかけた。「馬をあずかってもらっていたんです。だから、返してもらいに行ってたんです。」「馬?」 ジョージが不思議そうに聞く。「ええ、ハドソン王子が私に譲ってくれたんです。リュードに行くと告げた時に」 当たり前のように答えるミシェルに、部隊のみんなは声を上げた。「冗談だろ! 王家の馬って言ったら物凄い値段がするらしいじゃねえか。そんな馬をこんなおんぼろ船に乗せてつれて歩いていたのか?」「え? ダメなんですか?だけど確かにいい馬です。良く走るし、言う事もきちんと聞くし。」 男達のため息がこぼれた。「王子がくれるって言うんだったら、もらっておけばいい」「そうですよね」 ジークは殆ど諦めたような言い方だが、ミシェルはそれで納得ができたようだ。 ノースポートに港が見えてくると、誰かがじっとこちらを見つめているのに気がついた。「スキャットマンさん!リュードには行かなかったんですか?」「俺は後発隊として武器を持っていく予定だったんだが、どういうわけか王子が特殊部隊の人間と面会したいと軍上層部に頼んだらしい。仕方なく残っていた俺が対応したら、一緒に王室の安全を守ってくれと懇願された。お陰でウイリアム王が影武者だったこともわかったし、裏で糸を引いているのがラングレイだということも証拠をつかんだ。そっちの方はリュードでもいろいろ暴かれたらしいから、ラングレイに助かる道はないな。 まあ、フィルからは現地で対応できると連絡をもらったからよかったものの。急に張り切りだして、あの王子、どうなっちまったんだ?」 スキャットマンはちらっとミシェルを見た。「ミシェルの王女姿は随分と美しかったらしいからなぁ。もしかして、男として目覚めたのか?」 フィルが含み笑いで答える。ミシェルとジークは頬を赤らめた。「お前達、くだらない話をしていないで、さっさと荷物を下ろせ!スキャットマン、今日はこのまま王室に戻ってくれ。ツィンたちは逮捕されたが、連絡が取れなくなればラングレイが動き出すかもしれない。サンタリカの近衛兵が動く前に逃亡されても困る。それと、王子と連絡を取って、ミシェルを王室に戻すべきかどうか確認してくれ。他のものはひとまず宿舎にもどるぞ」「イエス、サー!」 宿舎には軍から車の迎えが来ていた。港の馬小屋に頼んで馬を預かってもらい、ミシェルは軍の車に乗り込んだ。 宿舎では隊員の家族が出迎えてくれた。デイジーの手料理でもてなされ、やっと肩の荷を降ろすことが出来た。 階段を上がり、久しぶりに自分の部屋に戻る。振り向いてもジークが上がってくる気配はなかった。部屋に入るとよどんだ空気に苦しくなる。窓を開け放ち空気を入れ替えて、自分もシャワーを浴びた。 冷蔵庫を開けても飲み物すらない。仕方なくミシェルはコップに水道の水を入れた。かすかなノックが聞こえた。ジークだった。「お疲れ。長いこと留守にしていたから、食料も何もないんだろう?」 そう言って抱えていた大きな紙袋をテーブルに下ろした。驚いたように見つめるミシェルを見ようともせず、ジークはさっさと指示を出す。「早く冷蔵庫に入れないか! それが終ったら、うまいコーヒーを淹れろ。」「はい、隊長」 ミシェルは慌てて冷蔵庫に食品を並べた。お湯を沸かし、コーヒーを淹れる。ふくよかな香りが部屋中に充満した。カップに注いでテーブルに置くと、ジークはどかっとイスに座り込んで砂糖を一つ、放り込んだ。その姿を見ながら、向かいの席にすわると、自分でも気付かないうちにミシェルはつぶやいていた。「隊長の死亡通知が来た時、すごくショックでした。もう何もかも放り出して、直ぐにでも飛んでいきたかった。」 ジークは何も言わず、ただカップの中をかき混ぜているだけだ。「だから、ジャンキーのアジトで隊長に会えた時は、すごく嬉しかったです。」「あれほど…」 うなるような擦れた声だった。「え?」「あれほどそこにいろと言ったのに! リュードは危険な場所だった。政府側の人間とジャンキー側の人間が入り混じり、監視しあうような場所だったんだ。無事でいられたからよかったようなものの。もしも…」「でも、ちゃんと切り抜けました!」「そういうことじゃないだろう!」 ジークは突然立ち上がってテーブルを打ち鳴らした。カップの中のコーヒーが大きく揺れている。ミシェルにはもう返す言葉がなかった。圧倒的な威圧感が部屋に満ちている。 しかし、ジークはそれ以上攻めることはなかった。「疲れているのに、悪かったな。」 暗い声でぼそりと言うと、ジークはそのまま部屋を出て行った。カップを片付け、こぼれたコーヒーをふき取った。どんなに洗っても、コーヒーのしみが取れない。ミシェルは向きになって洗ったが、かすかに残ったしみは、消えなかった。 翌朝会議室に向かうと、ジークが待っていた。「他のみんなは?」「今日は休暇だ。お前には任務の続きが待っている。今朝スキャットマンから報告があった。ハドソン王子はこのまま王位に着くことになりそうだ。昨夜遅く、ラングレイが王室の金塊をカバンに詰めて、逃亡を試みようとして捕まった。後は近衛兵と王室諮問委員会に任せることになった。ところで、隣国ザッハードのマルコス王子とやらとはどういう関係なんだ?」 言葉尻にかすかに私情が加わる。ミシェルはそれには気付かずげんなりした顔で答えた。「ああ、レイチェル王女に熱を上げている王子さまで、一夫多妻制のお国柄なので、自分が望めばみんな妻になると思っていらっしゃるようすです。何度かお断りしていたのですが。替え玉とは気付かずに偽の王の命令で外交を続けていました。」「そうか。しかしハドソン王子はもう一度だけマルコス王子に会って欲しいとのご要望だ。そして、マルコス王子にガツンと言ってやってくれと、そう申されている。」 ミシェルは目の前がクラクラするのを禁じえなかった。しかし任務とあらば仕方がない。今回はジークも護衛に付くということなので了解した。
August 31, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その21
その頃、ロイは山の頂上で様子を窺っていた。見下ろせば、街からの侵入者も牧草地の様子も全部見渡すことが出来る。そこから山の反対側の斜面を使って点滅信号で連絡を取り合うのだ。 ミシェルは合図をもらいながら、マイクに囁いている。残る兵隊はモーグ率いるCグループのみだ。ちらっと木の陰から覗くとモーグのすぐ後ろにディックがいるのが見えた。 ロイから次の合図が来た。雑木林の影から一斉にスポットライトがモーグ達を照らし出した。闇になれた目は一気に視力を失う。そして、ここぞとばかりにミシェルが甲高い笑い声を響かせた。「やっとここまでやってきたの? 理不尽なやり方で私腹を肥やし、とうとう隣国にまでその汚れた手を伸ばす悪党め! 姿を失っても、私は絶対に許さない!」 セリフと同時にミシェルが立ち上がり、スポットライトを浴びながら雑木林の前へと躍り出る。「皆のもの!怯むな!これは正々堂々とした魔女狩りだ!私たちが正義だ!」 震え始める兵隊達に檄を飛ばし、モーグは自ら傍にいた兵隊の拳銃を奪い、ミシェルめがけて引き金を引いた。ミシェルはひらりとかわし、再び仁王立ちで姿を見せる。 他の兵隊たちは恐怖のあまり、狂ったように撃ちまくる。それでも甲高い笑い声が続いた。狂っているのは兵隊なのか、魔女なのか、兵隊達の中にあるのは、ただ助かりたいという気持ちだけだ。やがて兵隊の弾が尽き果てると、魔女の姿はぱたりと倒れ、辺りは静寂に包まれた。 暗闇の中に硝煙の匂いだけが漂っている。かすかに聞こえるのは怯えきった兵隊達の吐息。「バ、バカめ! 私に勝てると思ったか。」 震えを押さえながら、モーグは強がった。「モーグ中尉。魔女は本当に死んだんでしょうか」 兵隊達が狂ったように撃ちまくっている間、後方に下がってタバコを吸っていたディックが及び腰の中尉の耳元でぼそりとつぶやいた。「ふ、ふん。コレだけやられて生きている奴がいるものか。おい、お前。ちょっと見て来い! 隣にいた兵隊を小突いた。哀れな歩兵は腰が引けたまま恐る恐る前へと進んだ。 かすかな朝の気配が広がり始めた静かな山の中腹に恐ろしい爆音が轟いた。地雷が作動したのだ。政府軍の兵隊達は狂ったように叫びながら何処かへ逃げて行った。しかし、動乱の中にあってもミシェルはモーグの脱出を許さない。煙のたなびく人型の戸板の上に押さえ込んだ。「よぉ!やっぱりお前も来ていたのか!ミシェル!」「ディック! お疲れ様」 ミシェルに変ってモーグをひょいと片腕でねじり上げ、ディックは山から駆け下りてきたロイに手渡した。「貴方がディックですね。ご協力感謝します」「ロイか。なかなか面白かったぜ。」 二人は拳をぶつけ合って笑った。「よーし!戦闘班。移動だ」 ロイの掛け声でメンバー達が先ほど爆破させた雑木林のすぐ隣のイチョウの木を横にずらすと、人一人通れるだけの狭いトンネルが現れた。その中に、一人ずつ滑り込む。滑らかに加工されたトンネルは快適だ。しばらく行くと荷物の並んだ建物の中に降りた。山の斜面を利用して建てられた宅配便の倉庫だ。そこからは配達の車に乗って移動する。荷台に居れば、外からは気付かれないというわけだ。 目的地の工場の施設内に車ごと乗り入れて、シャッターを閉めてから車を出た。 モーグは目隠しをされたまま引っ張られていた。そのまま建物の奥に入って行くと、小さな部屋から老人が顔を出した。「よくがんばったな。こちらにモーグを」 心なしか寂しげな表情の老人は、それでも気丈に振舞っている。「長老。申し訳ありません」 ロイは遠慮気味に言う。「お前が謝る事ではない。謝らなければならないのは私の方だ。まさかこんなに腐りきった人間になっていたとは、思いもしなかった。」「ふん。オヤジが。アンタみたいに辛気臭い事やってたら、世の中は思うように動かないんだよ」 突然平手が飛んで、モーグは目隠しされたままイスごと吹き飛んだ。「自分の思うように動かそうとは、どこまで愚かなんだ。ここまで来たら、全部吐き出してもらうぞ」「ちっ!」 悔しげに吐き捨てるモーグだったが、不意に目隠しを外されて想像以上の人間に囲まれていると知って驚いた。 ミシェルはスタスタとモーグの元に近づくと、そっとその腕をとって立たせ、イスを立て直した。そんな姿を見たモーグはガタガタと震えだす。「お、お前は…。間違いなく首を落としたのに。あの時も何度も撃ったのに。どうして…」「幽霊は何度殺されても死なないんだよ。それに、アンタを殺しても罪にもならない。どうする? ツィンとラングレイの計画を話す気になったかい?」 モーグは腰が抜けたように座り込んでしまった。「分かった。分かったから、殺さないでくれ。頼む!」 モーグは自分の知る限りの情報を全て吐き出した。モーグの上司、ツィン大佐とラングレイはお忍びで出かけたザッハードの高級クラブで偶然であっていた。そこで同じ匂いを嗅ぎ取った二人はそれぞれの思惑が成就するように計画を立てた。 その頃のリュードは不景気の真っ只中にあったがそれでも贅沢をやめられない一部の貴族を守るため、税率は上がる一方だった。一般の国民は学校に行くのも困難になり、生活するのがやっとの状態で政治を監視する余力はなかった。それをいいことに汚職、賄賂、天下りと言った政治家に甘い環境がはびこり、富を極めたツィン大佐は貴族への道を模索していた。 同じ頃リュードの腐敗を払拭しようと立ち上がった国民運動はじわじわと力をつけ、少しずつだが政府に意見をするようになった。しかし、それも軍によって悪者に仕立て上げられ、対立することになった。ツィンはそこを狙ったのだ。 ジャンキーを倒し国を守ったということになれば、伯爵の称号も自分の物になると考えたのだ。 そしてラングレイは兄であるウイリアム王の安定した政治でのんびりと過ごせていたが、それとて、自分の虚栄心を満足させる事はできず、玉座を狙っていたということだった。「あのラングレイという男は恐ろしい男だ。レイチェルと言えば、ウイリアム王の娘じゃないか。それを身代金を奪っておきながらあっさり殺せと命令してきたんだ。俺だっていやだったが、ツィン大佐は逃げる事を許さなかったんだ。王様になるのと、浮浪者になるのとどっちがいいと詰め寄られて、しかたなく…。俺だって辛かったんだ、うわっ!」 懸命に言い訳するモーグの胸倉をねじり上げたのはあの老人だった。しわの深く刻まれた腕が震えていたのは、モーグの体重のせいだけではなかった。 老人はそのまま拳でモーグの頬を殴りつけた。「お前のような性根の腐ったやつに、うちの名前を継がせることはできない。30年の投獄と家への立ち寄りを禁止する。もちろん、別荘も何もかもだ!じきにお前の仲間も投獄されるだろう。老後はあいつらと仲良く思い出話でもするがいい。」 老人はそのままゆっくりと廊下へ出た。「パパ! それはないよ。ひどいじゃないか! 僕はこれでも第2位王位継承者なんだよ!」「わがフォレスター一族も私の代でおしまいだな」 ぼそりとつぶやいて後ろ手にドアを閉める。ジャンキーのメンバーは誰一人、老人を慰める事ができなかった。「隊長。あのご老人はどなたなんですか?」「ああ、あの老人はジャック・フォレスターと言って、今のリュードの王様の従兄弟になるらしい。ところが王様の身内が数年前の飛行機事故で一気に亡くなった。他の用事で飛行機に乗り損ねたフォレスター氏が犯人ではないかと随分ゴシップネタにされたようだ。 身内が亡くなったのに、犯人呼ばわりで葬式にも出られなかったらしい。もう、イヤになったんだろ。ぷいと家を出たきり、行方不明になっていたんだ。ぼんやりと森の中に座っているやせこけた老人を見つけたのはロイだ。アイツが見つけなかったら、もうこの世にはいなかったんだろうな」 ミシェルはそっと部屋を出て、老人の後を追いかけた。
August 30, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その20
「隊長、ミシェルです。失礼します。」 カーテンを引くと、顔色の悪いジークが横になっていた。右腕に巻かれた包帯が痛々しい。息の浅いジークはゆっくりと向きを変えて、驚いた様子でミシェルを迎えた。「だれがこんなところに来いと言った。お前は王女の身代わりになっていろと言っただろ」「隊長! 亡くなってしまった王女の身代わりなんて、おかしいです。王妃もなくなられて、王様のなさりようにも違和感を覚えます。王子には、しっかりと気をつけるように話してきました。」そこまで一気に報告すると、ミシェルは堪らなくなってジークの傍に駆け寄った。「隊長の死亡通知が来ているのに、ドレスを着て微笑んでいるなんて自分には出来ませんでした!」 ジークはいとおしげに見つめゆっくりと左手をあげ、ミシェルの頬をやんわりと打ったが、そのまま苦しそうに腕を下ろした。その様子にミシェルは何かを感じ取った。「ここにはどれぐらい薬がある?」「そこの戸棚にあるのが全部だ」 ロイは部屋の隅にある戸棚をあごで差した。すぐさま戸棚を開け、中から消毒液と化膿止めになりそうな薬をみつけると自分も手を洗ってすぐさまジークの右腕に取り付いた。 傷口の化膿はひどく、周りの腕も腫れ上がっている。ミシェルはすぐさま処置に入った。桶に氷の入った水をもらい、タオルを絞って額にのせると、あっという間にタオルが乾燥するほど、ジークは熱を出していた。 ミシェルは夜を徹してつきっきりで看病した。その間、ジャンキーの連中は決して口を挟まなかった。翌朝、ロイが顔を出して、二人に食料と水を届けた。「どうだ、ジークの熱は引いたか?」「うん、だいぶ引いてきた。よかった。もう少し遅かったら、危なかったかもしれない」 ほっとした表情にも疲れが見えた。「そういえば、昨日の。悪かったな。大丈夫か?」 ロイは白い頬がかすかに赤みを差しているのに気を使った。「ううん、気にしないで。ホントに打たれないと回りに怪しまれると思ったんだ」「ロイ、気にするな。こいつはこれでもサンタリカの陸軍特殊部隊のメンバーだぜ」 いつの間にか意識を取り戻したジークが自慢げに言った。ミシェルはすぐさまベッドに飛びついた。「隊長!気がついたんですね!」「泣くな!サンタリカで何かつかんできたか?」 ミシェルは急いで涙を拭くと、ハドソン王子から受け取った写しを手渡した。すぐさま黙って読み終えると、納得するように大きく頷いた。「まさかあの甘えん坊の王子様がそこまで調べてくるとはな。お前、なにか吹き込んだのか?」「人聞きが悪いです。ちゃんと状況判断してくれと訴えただけです」 にやりと笑うジークの瞳には、いつもの自信家の光が宿っている。 夕方になると、ジークはもう戦略会議に出来るまでに回復していた。「ロイ、やっぱり俺たちが睨んだ通りだ。ラングレイとツィンは繋がっている。そしてその下にモーグがいるというわけだ」「隊長、他のメンバーはここにたどり着いていないのですか? 自分より先にサンタリカを出たはずなんですが」 ジークは不敵な笑みを浮かべる。「俺たちはただの陸軍ではないだろ?それに、ラングレイの手先でもない。そうだろ?」 その言葉の意味を理解して、ミシェルは笑顔になった。 突然、駆け足が近づき、慌てた様子で少年が入ってきた。「ロイさん!大変です! 政府軍がこちらのアジトを見つけ出したらしく、先ほど軍に出動命令を出しました!」「なんだと! 詳細を。」「フィルさんが傍受した情報によりますと、明朝夜明け前に出動予定です。指揮官はモーグです。」 ロイは指の関節を鳴らしてにやりと笑った。「とうとう出てきやがったか。確実に俺たちを捕らえられると踏んだな。それで手柄を独り占めってわけか。よし、戦闘班は会議室に集合だ。情報班は引き続き情報収集を怠るな」 すっくと立ち上がるロイに、ミシェルも従った。「ミシェル、お前の今まで学んだ事を全部出し切ってやれ!」「サー、イエッサー!」 ミシェルの敬礼にロイが眉を上げて驚いた。「ジョー!お前はけが人を第二基地に誘導しろ!皆が出たのを確認したら、証拠隠滅だ」「はい!」「隊長も、退避しておいてください。まだ完治とは言えません。」「ふん、わかったよ。せいぜい暴れて来い。」 ジークは楽しんでいるようだ。「ロイ!自分にいい考えがある。ちょっと手伝って欲しい」 ジークが元気になったとわかると俄然勇気が沸いてくる。ミシェルもまた、自分のペースを取り戻した。 ミシェルはすぐにロイと一緒に飛び出していった。 日が落ちるまでの間、メンバーは散り散りに手分けして作業を急いだ。落とし穴や獅子脅しのトラップを仕掛け、近隣の住民には工事と偽って立ち入りを禁じた。日が落ちた頃、ミシェルは黙々と穴を掘っていた。ここが最後の場所になるのだ。 ライトのセッティング。武器の配置。そしてスピーカーを樹木に隠した。やがて静かな夜が訪れ、星の瞬きと共に薄れ始めた頃、ぞろぞろとモーグの軍隊が森を取り囲んだ。「Aグループ、Bグループ、後方から距離を詰めておけ!Cグループは私の後に続け!」 Aグループに潜り込んだリチャードはため息をついた。「バカか、アイツは。トランシーバーなど傍受されているに決まっているのに」「ふふふ。そう怒るなよ。あれでもうまい事やってるつもりなんだ」 ジョージはリチャードをなだめながら、我先に進んで行く他のメンバーの様子を伺った。一部の人間以外はつましい生活をしているこの国では、手柄がそのまま金になるというので、歩兵には貧困層が多い。そして無茶をする者が多いのも事実だ。 突然、歩兵達の悲鳴が聞こえた。ざざざと斜面をすべる音、折り重なって倒れる音。全ては夜の闇の中の出来事だ。これに恐怖を覚えないのはよほど戦いに手馴れた者だけだろう。そして止めを刺すように小さな声が聞こえてくる。「どんな陰謀もいずれ暴かれる日が来る!覚悟はできたんだな」 じわじわとボリュームが上がるその声は、どうやらBグループの方でも聞こえているらしい。狂ったような叫び声を上げて、後方の兵隊たちは散り散りに逃げ出した。
August 27, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その19
「何てことするんだ!」 ミシェルが立ち上がるのを合図に、男は直ぐに殴りかかってきた。周りにいた客も加勢して、ミシェルはあっという間に捕まってしまった。「離せ!お前達の目的は何だ!」 カウンターから出てきたバーテンダーの平手が飛ぶ。いつもなら簡単にかわせるが、両手をつかまれていてはどうすることもできない。「どうする?」 男はバーテンダーに指示を乞う。「例の場所に連れて行け」 落ち着いた声で指示が出ると、男はさっさと店の奥にミシェルを連れて行った。両手首を縛って猿ぐつわをはめると、より奥へと進み、ミシェルを押し出して店の裏側に出た。店の裏口には車が止まっていて、有無を言わさずねじ込まれた。助手席には先ほどのバーテンダーが乗っている。 こうなったら大人しくしているしかない。ミシェルは黙ったまま、車の向きだけをしっかりと見据えていた。どうやら海岸沿いに北西へ向かっているようだ。サンタリカから見ると、ちょうど裏側になる。入り組んだ路地を今度は山に向かって進み、山の中腹にある牧草地まで進んだ。牧草地にはこんもりとした丘があり、辺りは雑木林でうっそうとしてる。「下りろ」 ドアを開けられて素直に車を降りると、雑木林のどこからか扉が開いた。中に入ると扉は閉まり、再び何事もなかったように見えるという仕組みだ。 中はコンクリート張りだが、きちんとした建物のようだ。小さな部屋に誘導され、猿ぐつわを外されるといすに座るように言われる。意外にも、こちらが歯向かわなければ乱暴なことはしてこない。 しばらく待たされた後、老人が部屋に入ってきた。一目見て人格者であろうと思われるその老人は、落ち着いた様子でミシェルに問うた。「名前は?ダリーの知り合いか?」「名前は、ミシェル。ミシェル・グロウ。ダリーと言う人は知りません。お年寄りが若い男達に殴られているので止めただけです。」 老人は表情を見せないまま頷いた。「お前は旅行者のようだが、この国に何をしに来たんだ?」「人を探しに。ジークと言う大柄で野生的でうるさくて恐くて、でも」「でも?」 老人は全てを知っているかのような顔つきだ。「でも、優しい」 満足げに頷くと、老人は先ほどの男に声をかけた。「ミシェルとやらをアイツのところに連れて行ってやれ」「わかりました」 男はミシェルの手首のロープを外し、ついて来いと促した。長い廊下を歩きながら、男はぼそりという。「お前、本当は女だろ?」 ミシェルの背中に嫌な汗が流れた。先を歩いていた男はくるりと振りかえり、目深に被っている帽子を奪い取った。驚いて見上げるその顔を見て「やっぱりな」とつぶやいた。「アイツは、ジークってやつはたいした男だよ。一人でふらりとこのリュードにやってきて、あっという間に政府軍の幹部たちの恐ろしい計画を暴きだした。 サンタリカの王女は誘拐されてすぐに長い髪をばっさりと切り落とされて、まるでお前そっくりだった。その髪とティアラをサンタリカに送りつけて俺たちジャンキーの名を語って脅迫したのは政府軍だ。」「どうしてそんなことを?」 男はため息をついて再び歩き出した。「俺たちジャンキーは今の政府の汚職や私腹を肥やす天下りに憤った仲間で構成されている。だから、間違った事をしている政治家やその構成員に制裁を下しているんだ。もちろん、そんな俺たちを抹殺しようと政府は軍を使って躍起になって探している。しかし、緩みきった軍の連中に俺たちを捕まえる事はできなかったのさ。だから、サンタリカの悪人と手を組んだってわけだ。王女の長い髪と引き換えに莫大な資金が入ったリュードの政府はもう用済みになった王女をスパイと偽って断崖絶壁の処刑場で堂々と公開処刑したんだ。 ジャンキーに肩を持つとこういうことになると大々的に広告していたさ。」「ひどい!!」 ミシェルは唇をかみ締める。亡くなった王妃やハドソン王子が聞いたら、どんなに悲しむだろう。しかし、ウイリアム王やラングレイは資金を送ったことなど微塵も見せなかった。ラングレイはともかく、ウイリアム王にとっては許せない話のはずなのに。「アイツはその公開処刑を見てしまったんだ。髪が短くなって、おまえそっくりな王妃は最後まで気丈に涙も見せずに政府の連中を睨みつけて叫んでいた。『どんな陰謀もいずれ暴かれる日が来る!覚悟しておきなさい』と。処刑はあっけなく終わった。国民は誰一人、悲鳴すら上げられなかった。ただ、その亡骸をじっと見つめていた。 その時、一人の男が政府軍の中に身を投じたんだ。次々と政府要人をなぎ倒し、軍の要人も何人か倒れていた。ものすごい戦闘能力だった。だけど、一人では何千という軍隊とは戦えない。そのうちに腕を切られ、そのまま海に落ちた。俺たちは、すぐさまアイツを救い出したんだ。」「そんな…」 ミシェルの声は涙に震えていた。「ところがだ。アイツは驚異的な速さで体力を回復させ、祖国に知らせるといってここを飛び出して行ったんだ。まだ傷は癒えていないし、政府が血眼でアイツの遺体を捜していたんだ。それで、あの店で無理やりアジトに引きずり戻し、保護している。」「だから、死亡通知が来たの?」 男は振り向いてにやりと笑った。「そっちに届いていたか。身代わりに大物政治家が口封じに殺した秘書の遺体をちょうだいして、アイツの服を着せて海に投げ込んでおいたんだ。念のため、岩で顔をつぶしておいて正解だったな」 この国の現実を突きつけられたようで涙も乾いてしまった。「ところで、お前、ここまで一人で来たのか?」「ああ、隊長の死亡通知を見ても、どうしても納得できなくて」「ふふ。たいした奴だな、お前も。俺はロイ。よろしくな。さて、ここだ。まだ状態はいいとはいえないが」 男が体をそらせて、ミシェルを先に通した。白いカーテン越しに人の影が見える。
August 26, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その18
表通りから細い路地を抜け、しばらく西に進むと小さな集落があった。決して豊かとはいえないその村の長屋の端に、老人たちの住まいはあった。「大丈夫ですか?」 古いベッドに老人を寝かすと、老人は申し訳なさそうに礼を言った。「うちの息子は、勉強ができる方でな。政治家になるんだと言って都のあるメガドに行ったんだ。ときどきよこす手紙には、上司にも可愛がられてがんばっていると書いてあった。それなのに、1年ぶりに帰ってきた息子をジャッキーの連中が連れ去ったんだよ。あの日、息子が帰るというのでワシは嬉しくてうまいものを食べさせてやろうと表通りの市場に寄った。その帰り、わしの前を息子が歩いているのに気がついた。随分りっぱになって、洋服や持ち物も、高価なものを身につけていた。よほどがんばったんだろう。嬉しくて声をかけようとしたら、あの店から出てきた連中が、あっという間に」 悔しさで歯を食いしばる老人に、ミシェルはどうしてやることもできなかった。「あなた、そんなことを旅の人に言っても…。今日はありがとうございました。ところで、今日はどちらにお泊りですか?」「いえ、まだ宿は取っていなかったので」 老女は勤めて微笑むと、知り合いの宿を紹介してくれた。ミシェルは礼を言って立ちあがり、老女に見送られて宿に向かった。 表通りを一筋それたその宿はにぎわっているようには見えなかったが、それでも見晴らしのいい場所に建っていた。馬を小屋に連れて行き、部屋に案内してもらう。じきに宿の主人がやってきた。「いらっしゃいませ。私はこの宿を切り盛りしておりますサーガと申します。さきほど、ダリーの両親から話は聞きました。今日は、友人の両親がお世話になりました。」「ダリー?ああ、ジャンキーに連れて行かれたという人ですか?」 主人はお茶を淹れながら答えた。「ええ、そうです。ダリーは私の幼馴染なんです。頭がいいのはいいのですが、お調子者なところがあって危なっかしくて。アイツがメガドに行くって言ったとき、私は反対していたのです。」「よかったら、教えていただけますか? ジャンキーはどうしてそんな悪いことをするんですか?」 ミシェルの質問に、主人は直ぐには答えられなかった。そっと立ち上がり、廊下の人気を確かめると、再びミシェルの前に座って小声で言う。「実は、私にはジャンキーが悪者なのかどうかわからなくなっているのです。確かにジャンキーはテロ集団と言われていますが、ジャンキーが何か騒ぎを起こした後には必ず政府側に汚職や裏工作があったことが明るみに出て、大騒ぎになるのです。ダリーの両親には申し訳ありませんが、ダリーが久しぶりにこの街に戻ってきたあの日。アイツは高そうな車に乗って、まがまがしい金のネックレスやごつい指輪をして、なにより目つきがすっかり変ってしまっていました。」 ミシェルはサーガの話を聞きながら、貧しい村の長屋に住む老夫婦を思い出していた。「うちに寄ってくれたのですが、話題は麻薬の話ばかりでした。ここを連絡場所に使わせろというので、丁重に断りました。ダリーはメガドなんかに行かせるべきじゃなかった。すっかり毒されて別人になっていたのです。あのまま放っておけば、いずれは麻薬の売買の元締めになって、とんでもない奴になっていたでしょう。ジャンキーはダリーをどこに連れて行ったのか、それは分かりません。ですが、あのままではどうせダリーは悪い人間になっていたでしょう」 宿の主人はしゃべりすぎたと思ったのか、慌てて話題を変えた。「ところで、お客さんはお一人で観光ですか?」「いえ、私は叔父を探しに来たのです。この国に行ったということしか聞いていないのですが、喧嘩っ早い人だから、心配になって。ジークって言う人です。背が高くて」 ミシェルの言うジークの特徴で、主人は思い出したように言った。「もしかして、結構野生的な人ですか? 確か、3ヶ月ほど前にここにお泊りでした。そう、この部屋です。ですが、その方は、例の「I+1」で派手にケンカして、どこかに連れて行かれてしまいましたよ」「ええ!じゃあ、ジャンキーに捕まっちゃったってことでしょうか?」 主人は肩を落としてため息をついた。「言い難いですが、そうでしょうね。あなたはまだお若いようだし、体も華奢だ。ジャンキーに一人で立ち向かうのは無理があります。悪いことは言わない。この街で観光したら、そのままお帰りになった方がいい。」「叔父さん…」 主人はミシェルの肩に手を置いて労わるように撫でると、そっと部屋を出て行った。 翌朝、ミシェルは散歩に出かけた。みやげ物屋はきれいな貝がらや加工品が並んで、ミシェルには珍しいものばかりだ。しかし、ミシェルは緊張を溶かない。ずっとつけてくる気配があるのだ。 何食わぬ顔で貝殻を眺めて歩く。そして、何軒か立ち寄るうちに、貝殻の加工品を扱う店にたどり着いた。乳白色にかすかな虹色がかかる貝をいろんな形にくりぬき、ボタンやペンダントトップに仕上げていく。「これは、隊長の…!」 気がついた時には買い求めていた。公園の木陰に座り、袋から貝の鳩を取り出す。女性用なのか茶色のヌメ革の紐がつけられていた。首に回して、できるだけ見えないように長めに結ぶ。 夕方にはあの店に向かわねばならない。のんびりと景色を楽しむように座っていると、いつの間にか妖しい視線はなくなっていた。 日が傾いてきた。ミシェルは一旦宿に戻り、一泊分には充分な代金を支払い、馬を預かって欲しいと頼んで宿を出た。行き先は決まっている。迷うことなく店内に入って行った。 ドアを開けると、賑やかな音楽とあちらこちらのグループが楽しげに酒を酌み交わしている光景が広がった。想像していたのと違っていて、ミシェルはなぜかほっとした。「ご注文は?」 カウンターでグラスを磨いていた男が声をかけた。「じゃあ、ビールを。」「わかりました」 静かに差し出されたビールは良く冷えてうまかった。「お前、昨日爺さんを助けた奴だろ? 今頃のこのこと何しに来た?」 昨日老人を殴り倒したグループの一人だろう。カウンターに寄りかかって睨みつけている。「ビールを飲みに来た。それだけだ」「よく言うよ。ここがどこだか分かってるんだろう?小さい割にはいい度胸だと褒めてやるよ。だが、ここには政府の犬に飲ませるビールはねぇんだよ」 男はミシェルが一口飲んだビールをザーっと床にぶちまけた。
August 25, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その17
調理室に行って、ゴードンに事の次第を告げると、馬小屋の世話役に声をかけてくれた。裏の勝手口はゴードンの女房がすでに開けてくれていた。ロザーナも一緒だった。「ミシェルちゃん、これを!」 飲み物と食料が入った袋を渡され、ミシェルは敬礼した。「皆さんの優しさに感謝します。では、いってきます!」 夕日が差し込む王室の森を走った。うっそうと茂る木々の間から、時折オレンジ色の光が剣のようにミシェルの目を刺した。油断は許されない。今一度、気を引き締めて森を抜け、ミシェルは無心で突き進んだ。サンタリカは大陸の西の端に位置し、東にマルコス王子のいるザッハード。西は海峡を渡って島国リュードがある。海岸は北にノースポートという大きな港があり、南には漁港がある。王室宮殿がある中央やや東の位置からこのままノースポートまで行けば、今夜の連絡船の最終便に間に合う。それに乗れば翌朝早くにリュードに上陸できる。 途中の小川で馬に水を飲ませ、草原の草を食む時間を与えた。その間に自分も腹ごしらえを済ませる。できるだろうか。仲間との連絡手段もなく、隊長の安否も分からない中で、自分にこの状況を解決することが、本当にできるだろうか。草原の草が風になびいて一斉に波打った。「自分を信じろ! ミシェル、自分を信じて突き進め!」それは心に響く父の声だったのかもしれない。それともジークの言葉か。ミシェルは立ち上がり、再びノースポートを目指した。 港の明かりが見え始めたのは、町が暗闇に沈む直前だった。ミシェルは慎重に馬を進め、連絡船の受付を済ませて小屋に馬を休ませた。動物はみんな小屋ごと船に乗せられ運ばれる。持ち主は客室で思い思いに体を休める。 ミシェルも窓際を陣取って、出発の時刻を待った。特殊部隊のメンバーはどうしているだろう。最後の連絡では、すでにリュードに潜入しているはずだ。しかし、ジークの死亡通知はもしかしたら彼らには伝わっていないかもしれない。彼らからジークの件で連絡がないことには違和感を覚える。 がたんとふいに床が動き、出航したことがわかった。ゆったりと2,3度左右に揺れた後、船は港を離れた。 ミシェルの心にはもう曇りはなかった。ジークの死亡通知はでたらめかもしれないという可能性に気がついたからだ。特殊部隊のメンバーからの報告でない限り、なにか裏があると見るべきだと踏んだのだ。 目覚めると、すでに船はリュードの港ムンバに到着していた。館内放送が流れ、他の乗客も下船の準備を始める。ミシェルはすぐに馬を引き取り、リュードの街を歩いた。言葉は少し方言があるだけで、ほぼ同じだ。車より馬車の方が比率が高いところから考えて、母から聞いた昔のサンタリカのような感じだろう。 朝早くに到着したのでまだ商店は開いていない。のんびりと街の中を歩いていると広い公園に出くわした。「仕方ない。ここで時間をつぶそう。」 ミシェルは公園の噴水で顔を洗うと、馬にも水を与え、林の中に手綱をくくった。サンタリカを出るときもらった袋からリンゴを取り出し、朝食にした。空気がおいしい。緑も清々しかった。こんな美しい国に、本当に恐ろしいテロリストが隠れているのだろうか。 木陰の芝生にごろりと横になって、ミシェルはぼんやりと考えていた。 日が高くなってきた。ミシェルは市場やみやげ物屋を冷やかしながら、それとなく探りをいれるが、反応は面白いほど二つに分かれた。 政府を支持してジャンキーを憎んでいるものと、ジャンキーを応援しているものだ。いずれにしても、ジャンキーは今のところ政府に反旗を翻しているという形になるので、おおっぴらに応援するものはいない。「お前、どこでジャンキーの名前を知った? 不用意に余計なことを探っていると政府の連中に投獄されるぞ」 あるみやげ物屋の主人は小さな声でするどく言った。「僕は、海の向こうのサンタリカから来たんだ。ある人からジャンキーが叔父さんをさらっていったって言われて、叔父さんを探しにきたんだ」「叔父さん? どんな人だ?」 ミシェルは不安そうな表情でぽつりぽつりと話し出す。「背が高くてね、髪をぼさぼさに伸ばしていて、筋肉質な感じ。えばってばかりで怖いんだけど、だけど本当は優しい人なんだ」 最後に優しい人だと言っている自分にはっとして、思わず唇をかんだ。「ん~、そういえば、随分前にそっちの表通りを北に上がったところにある「I+1」って店で揉め事があったと聞いたなぁ。旅行者が絡んできたとか言っていたが。まあ、そんなに簡単に見つかるものでもないだろうが、気をつけてな。」 主人に礼を言うと、ミシェルは素直に表通りを北上した。確かに「I+1」と言う店はあったが、こちらは飲み屋で夕方からの営業だ。「仕方ない。他の情報を集めておくか」 そのまま北上を続け、カフェに入った。 店の中は真っ白な壁に囲まれ、所々に貝殻が埋められている。店先の白いテーブルにつくと目の前に海が広がってすばらしい眺めだ。潮風を胸いっぱいに吸い込む。サンタリカの内陸に暮らしていたミシェルには新鮮な感動だった。 夕方まで待って、「I+1」の向かいのレストランイに入ると、すぐさま窓際を陣取った。軽い夕食を摂りながら眺めていると、仕事帰りの男達がぞろぞろと店に入って行く。一見しただけではテロリストには見えないがまだまだ気は抜けない。 食事を終えて、店を出ると、なにやら通りが騒がしくなってきた。あの店の前だ。人だかりができて、どうにも事情がわからない。ミシェルはするすると人の間を掻き分けた。「この、人殺しめ! ワシの息子を返せ!」「言いがかりだ! さっさと帰れ!」「ワシは知っているんだぞ。お前達はこの店の中で悪巧みをしているんだろう。お前達があのジャンキーというテロ集団なんだろ!」 老人は、有無を言わせず殴りかかって行く。男達は始めこそなだめようとしていたようだが、気がつけば老人を囲んで殴りだしていた。「ちょっと、通してください!」 後ろから来た老婆が慌ててその老人の前に走りより、男達からかばおうと身を投じた。「なんてこと?」 見渡しても、誰もこの騒動を止める者は居ない。ミシェルはたまらなくなった。「いい加減にしないか! たった一人の老人相手に、大勢で殴ったり蹴ったりするなんて、どうかしている!」「なんだとぉ?」 集団の中の一人が一歩ミシェルににじり寄った。ミシェルの後ろでは、老女が懸命に老人を抱き起こしている。「お前、見かけない顔だな。旅人か?」「そうだ。事情はわからないけど、大勢で一人を傷つけるのは間違ってる!」「ごもっともなご意見だな。旅人なら仕方がない。見逃してやる」 男はふっと失笑すると、仲間に合図して店の中に退いた。ミシェルはまだフラフラしている老人に肩を貸すと、家まで送り届けてやる事にした。
August 24, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その16
「ミシェル。大丈夫? 私が悪かったんだわ。本当にごめんなさいね」 冷たいタオルを額に乗せられて気がついた。 キツイ匂いがしなくなったので、自分がどこかに運ばれた事を知った。「ロザーナ?」「ええ、そうです。私が、張り切りすぎて、パニエのウエストを強く締めすぎたんです。だから貧血を起こしてしまってあなたは倒れてしまったの。でも、マルコス王子は素敵でしたよ。貴方を抱きかかえてご自分のお部屋で休ませて下さっていたんですって。だけど、どうしても気がつかないので、そのまま馬車でサンタリカに戻ってきたんですよ。」 ミシェルは急いで体を起こしたが、まだフラリと視界がゆれる。「もう少しじっとしていてください。ですが、今回の外交は大成功です。ザッハードの国王様も王妃もとても貴方を気に入ってくださったし、あんなに一生懸命な王子は見たことがないって、おっしゃっていたそうですよ。」「ロザーナ。それでも私には軍の特殊部隊の仕事があります。今はラングレイ殿下の命でこのようなことをしていますが、これではザッハードの王室を馬鹿にしているのではないですか?」 ミシェルの訴えにロザーナは頷いた。そして声を落として言う。「私には、わかります。貴方がどういう理由で男として軍に入ったのかは分かりませんが、あなたは本当はお嬢さんでしょう。マルコス王子はサンタリカの王女がほしいのではなくて、貴方自身に恋をしているのです。あなたが王子を嫌いでないのなら、そのまま流されてもいいのではないの?」「ロザーナ…!」 真意を探ろうとしても、ロザーナの誠実な瞳にはかなわない。ミシェルはしばらく考えて意を決して告白した。「私には心に決めている人がいます。これからの私の行動はご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうしても真実を知りたいのです。」 ロザーナは悲しげな表情になった。「ジークさんですね。」「どうしてそれを?」 ロザーナはミシェルの額のタオルを絞りなおしてそっと乗せた。ひんやりと心地いいタオルの感触がミシェルに落ち着けと囁いている。「貴方達の視線を見たとき分かりましたわ。何か強い絆で結ばれているんだと。ですが、ジークさんはリュードに向かわれたまま。実は、死亡通知がリュードから届いていると伺いました。貴方に知らせるのは忍びなくて。」「嘘!」 ミシェルはすぐに立ち上がると、まだふらつく体を無理に奮い立たせて自分の部屋に向かった。ハドソンが部屋の入り口に座り込んでいたが、今のミシェルにはどうでもよかった。ハドソンを押しのけるようにドアを開け、崩れるように部屋に入った。 部屋の外からハドソンがノックする音が聞こえている。続いてロザーナの声も。そうだ、今はまだ泣いている場合じゃない。まだ任務は終っていないのだ。ミシェルは頬を拭って立ち上がり、そっとドアを開けた。ロザーナはすでにハドソンに下がるように言われたのか、姿が見えなかった。ミシェルはすぐにハドソンを引っつかんで部屋に引き入れると、有無を言わせず捲くし立てた。「いいですか!この国はとても危険な状態にいる。今、貴方が立ち上がらなくてどうするんです! レイチェル王女を陥れた人物はどうやら特定できているようだけど、どうしてリュードのジャンキーが絡んでくるのかが分からない。私はこれからそれを調べてみます。場合によってはリュードまで調べに行かなければならない」「ラングレイは、叔父はどうやらリュードのツィン大佐と交流が深いようなんだ。何度か連絡が入っているのを聞いている。ツィン大佐はあまりいい噂のない人物だ。どうにも胡散臭い。」 ミシェルはハドソンの告白に目を見張った。「分かりました。後は私が動きます。でも、王様とあなた自身の身の安全が保障できない。充分に気をつけて。食事が心配なら、調理室のゴードンさんに相談して。ミシェルの紹介だと言ってくれたら分かってくれます。ハドソン王子、絶対に生き残ってくださいね!では、着替えさせていただきます」 ミシェルの言動を驚いたように聞いていたハドソンだが、そっと廊下に出た。 ミシェルはそのままジークからの最後の手紙を開き、静かに読み始めた。『ミシェル、この手紙が読まれているということは、俺の命がすでにないということだな。だから、思い切って告白しておこう。 お前が入隊して来た日。おれは随分と戸惑ったものだ。か弱い体で精一杯男の振りをして、危なっかしくてしかたなかった。しかし、お前は強かった。誰よりも戦略的で誰より冷静だった。納戸にお前を押し込んだのは悪かったと思う。しかし、そうでもしなければ飢えた男たちのことだ。すぐにお前が女だと気付いてしまうだろう。 特殊部隊に配属が決まったときは随分迷った。お前を連れて行って危険な目にあわせてしまうんじゃないかと思ったんだ。だが、ラミネスに言われたんだ。お前の頭脳は俺を凌駕している。絶対連れて行くべきだと。あいつはうすうす気付いていたらしい。 今もまだ。王女として孤独な戦いをしているだろうか。俺がいなくなっても、不安に思って泣いたりするな。お前には仲間がいる。それに、父親にしこたま鍛えられた技量と頭脳がある。どうか任務をやり遂げ、両親の元に元気に帰ってくれ。 俺の宝物、ミーへ ジーク・D.・G.』 手紙を持つ手が震えてうまくたためない。知っていた。女性だという事も。そしてなぜか、ミーという幼い頃の呼び名も。 ミシェルはすぐさまドレスを脱ぎ捨てた。ティアラやネックレスも全て外し、ハイヒールを脱いで入隊したあの日のスタイルに着替えた。カバンから細長いナイフを取り出す。「これは、ジークにナイフ投げを教えられた時のもの。」 そのナイフを内ポケットに忍ばせる。バンダナで、ぎゅっと頭を縛った。これでいい。後は、馬を準備しなければ。 急にノックがして、身を硬くする。「俺だ。ハドソンだ。」 ミシェルはそっと扉を開けた。ハドソンはリュードの地図と、ラングレイの電信の一部を傍受し、そのコピーを手渡した。「やっぱり行くのか。」「ええ、私は軍人ですから」 ハドソンはそっと右手を差し出した。そして、ミシェルと握手すると寂しそうに言った。「俺は、はずかしいよ。何も知らない世間知らずの坊やだったんだな。お前は、目の前の宝石だらけのティアラもネックレスも置いていくんだな。惜しいとは思わないのか?」「惜しい…」「え?」 ハドソンはミシェルの表情を伺おうと顔を上げた。すると、その首筋にミシェルが飛びついた。「ハドソン王子、あなたがそんなにすばらしい人だったと今まで気付かなかったこの時間が惜しい! あなたや仲良くしてくれたロザーナや他の王室の人々と別れなくちゃならないのが惜しい!」 ハドソンはミシェルの肩をぐっと抱き寄せた。「馬小屋に行け。俺の馬を一頭譲ってやる。話はついているから、すぐに出してくれるだろう。気をつけていくんだぞ。俺もがんばる。絶対に、ラングレイの思い通りにはさせないさ」 ミシェルはハドソンの肩をつかんで無理に離すと、敬礼をして部屋を飛び出した。
August 23, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その15
日曜日の朝は今までにないほどの豪華なドレスとティアラが用意されていた。ずっしりと重いティアラに耐えながら中央玄関に向かうと、大きな羽根のついた被り物をつけた白馬の馬車が待っていた。 シンデレラじゃあるまいし。状況が派手になるほどに心が冷え切る。 馬車に乗り込むと、ウイリアム王が駆け寄った。「レイチェル。隣国の方々に失礼のないようにな。これを、マルコス王子へのお祝いの品として渡してくれ」「分かりました。では、行って参ります」 馬車が動きだし、ウイリアムは満足げに頷いていた。一体向こうでどんなことが起こるのだろう。沿道で国旗を振る人々に手を振りながら、ミシェルは無理に微笑んで見せた。 王室の敷地を出ると、木漏れ日を浴びて馬車がゆっくりと進む。この道は、ジークの表彰の時に一緒に通った道だ。清々しい風が吹き渡り、あの日のことが思い出される。ジークはどこにいるんだろう。当たり前のように連れまわされたり、食事時にやってきて翌日の分まで食べられたり、怒ってばかりの自分だったが、あの頃が無性に懐かしかった。「レイチェルさま。どうかなさいましたか?」 ロザーナが声をかけてきた。国外への単身での外交がはじめてのミシェルに付き添ってくれたのだ。ミシェルはなんでもないように微笑んた。 ザッハードの国境では、門兵が身分証明の確認を行い、早速トランペットが吹き鳴らされた。国賓の入国の知らせだ。 馬車は悠然と沿道を進み、しばらく行くと大きな門の前に行き当たった。美しい小川を超える跳ね橋がゆっくりと下がり、同時に門が開いた。 高い城壁に包まれていた中の敷地は花々の咲き乱れる美しい世界だった。宮殿の前で馬車が止まると、ロザーナがそっと先に降り立ち、ミシェルの手をとった。 目の前には赤い毛氈が敷かれ、その先に笑顔のマルコスが待っている。「よく来てくれたね。さぁ、こちらへ」 マルコスはミシェルの手をとると、来賓の間へと案内した。来賓の間には美しい女性が数人で穏かに談笑していた。「あら、マルコス様。新しいお妃候補の方ですの?」「まぁ。愛らしいお嬢様ですこと。わたくしはマルコス王子の第2夫人のサマンサです。どうぞよろしく」「初めまして。私は、隣国サンタリカのレイチェルです。どうぞよろしくお願いします」 あまりの優雅さに戸惑ってしまう。どんなに優雅に振舞おうと、生粋の貴族である彼女達の優雅さには敵わない。「緊張なさっているのね。大丈夫よ。わたくしたち、みんなマルコス王子の妻なんです。でも、みんな仲良くしているのよ。その包みは王子に?先にお渡しになったら?」「あ、はい。」 住む世界の違いをまざまざと見せられ、気後れしていたミシェルはウイリアム王からの預かり物をすっかり忘れていた。「マルコス王子、本日は誠におめでとうございます。これはわが父、ウイリアム王より託された贈り物でございます」 マルコスはうれしそうに受け取ると、目の前で開けて見せた。中には乗馬をするマルコス王子をモチーフにしたクリスタルの置物と手紙が入っていた。「やったー!ウイリアム王の了解が得られたよ!レイチェル、おいで!」 意味が分からないまま、手を引かれて進むミシェルは宮殿の3階にある大きなホールへと連れて行かれた。「マルコス。お客様を放っておいて、どこに行っていたの。」 まだ若そうな貴婦人がマルコスを嗜めた。「申し訳ありません。今日は大切はなご報告がありまして。母をご存知ありませんか?」「アンジェラなら、さきほどアーノルド王にお会いになるとかでホールの控え室に向かわれましたわよ。貴方も早く向かうことね。」「ありがとうジュリア。 あ、紹介しておくよ。こちら、サンタリカのレイチェル王女。僕の妃になる人だよ」 ミシェルは面食らっているがジュリアには興味のない話題のようだ。「まあ、そうなの? 私はアーノルドの第三夫人のジュリアよ。よろしくね、レイチェル。」「どうぞよろしく」 口ではそう言ったものの、ミシェルには驚きの連続だ。「さあ、急ごう!」「マルコス王子、私は貴方と結婚するなんて一度も申し上げていませんわ」「いいから、いいから。」 マルコスに手を引かれて控え室に到着すると、さすがのマルコスも身だしなみを整えた。「お父様、お母様。ご機嫌麗しゅう。本日は、僕の為にこのようなすばらしい宴を催してくださり光栄に存じます」「はっはっは。随分とませた事が言えるようになったな。マルコス、こっちにおいで」 どっしりと落ち着いた体形にワインレッドのマントとかんむりが良く似合っている。傍にいるきれいな女性はマルコスの母親だろう。それにしてもむせ返るようなバラの香りだ。これはアーノルド王の好みなのだろうか。ミシェルはそっとそこに佇んでいた。「マルコス、こちらのお嬢さんは?」「ああ、紹介するよ。こちらはサンタリカのレイチェル王女。このたび、ウイリアム王の許可が下りたので、彼女を妻に迎えようと思うんだ。」 アーノルドは満足げに頷き、母アンジェラは微笑んだ。「あの、私まだ結婚するとかそういうこと伺っていなくて、その…」「レイチェル。大丈夫よ。この国の結婚はそんな大げさなものじゃないの。自由な暮らしが約束されたと言うことなのよ。」 困り果てるミシェルにアンジェラは優しく語りかけた。しかしそれは余計にミシェルを混乱させた。「レイチェル。どうしたの?顔色がすぐれないよ。レイチェル!」 マルコスの声が遠くで聞こえていたが、ミシェルにはもう立っていることすら出来なかった。
August 20, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その14
「俺だ!開けろ!」ハドソンだ。そっとドアを開けると、かすかに鼻の頭が赤いミシェルをみて逆にぎょっとしているのがわかった。しかし、勢いは無くさない。後ろ手にドアを閉めると、いきなり胸倉をつかんできた。「お前、どういうつもりだ!もしかして、ザッハードのスパイか!マルコス王子と結婚して、この国を乗っ取る算段なんだろう!」 どんなに脅しをかけてもミシェルには効かない。さっきまでの不安な気持ちは、一気に消え去った。自分にはこの状況を打破する任務がある。小さな胸元をつかむ腕は微妙に震えてか細い。何の躊躇もなく、あっという間に後ろ手にねじ上げた。「王子。お戯れはおやめ下さい。私は任務を遂行しているだけ。マルコス王子と仲良くするように勧めていらっしゃるのはウイリアム王ご本人なのですよ」「ちくしょー!みんなで俺を無視しやがって! 人を呼ぶぞ!いいのか!」 ミシェルはげんなりした。「どうぞご自由に。お姉さまに腕をねじ上げられている王子なんて、みっともないんじゃないですか?」「クッソー!離せ!」「離して欲しければ、一つお答え願いたい。本当のレイチェル王女はどうして誘拐されたのか、ご存知の部分だけでいいので教えてください。」「ちっ!またレイチェルか!」 唇を噛む仕草はあまりにも幼い。「あなたは王様のご長男でしょう。この国を正しく導く人でなければならないのですよ!自分のプライドばかりに振り回されていてはいけないのです!」「ふん!おまえもどうせ、ラングレイと同じ考えなんだ。俺がレイチェルを殺したと思っているんだろ」 幾分、気弱な表情で、ハドソンはつぶやいた。「いいえ、私はそんな風には思っていません。私の推測では、たぶんハドソン王子とレイチェル王女はいつものように単純な兄弟げんかをしていた。王子はどうしても超えられない出来のいい姉が目障りだった。だからちょっと懲らしめてやろうと思ってレイチェル王女のティアラを取りあげ、窓から捨てた。」 ハドソンの腕から力がぬけた。「もちろん、レイチェル王女は大切な宝石がちりばめらているので急いで建物の外に取りに行った。その後ろを追いかけて行って、締め出したんだ。ほんの少し仕返ししたかっただけなんのでしょう」「それが殺した事になるのか!」 ミシェルはすっかり手を離して、その代わり呆れたようにため息をついた。「王子、何度言わせるのです。私はそんなこと言っていないでしょう。あなた方のケンカをいつも傍で見ていた人物がいるのです。その人物が、もし頭のいいレイチェル王女を消したいと思っていたら。そして同時に王子の権力も奪いたいと考えているならば、やるべきことは簡単だったのです。貴方が締め出した王女を部下にさらわせて命を奪い、その責任を王子に押し付けてしまえばいいのです」「まさかっ!」 振り返った王子をキッと睨みつけ、ミシェルは言う。「王子、いつまで甘えているおつもりですか!レイチェル王女が誘拐され、王妃までも亡くなってしまった。あの日、図書館でお調べになっていたのは薬物中毒ではなかったですか?私は、すでに裏を取りました。王妃はご病気でなくなったわけではない。王子も充分にお気をつけください」 王子はほんの一瞬何か言いたげは表情を浮かべたが、すぐにきびすを返して部屋を飛び出した。 そのままミシェルは部屋を出た。王子を追うのではなく、図書館へと向かったのだ。 リュードという国は、サンタリカの西にある島国だ。サンタリカの北西にあるノースポートと言う港から連絡船が出ている。もしも、一人で向かうとなれば、それを使うしかないだろう。ミシェルは唇をかみ締めた。「レイチェルさま! レイチェルさま!」 ロザーナだ。ミシェルは急いで地図を棚に戻すと、すぐさまロザーナの前に飛び出した。中年の婦人は大層にふうと安堵してみせると、すぐに正装に着替えよと急かした。「今日はどんな行事ですか?まだ何も伺っていない」「マルコス王子さまですよ! ふふふ、随分とご執心ですこと。」 ご機嫌だが、ロザーナとてミシェルが『特殊部隊』から派遣されていると分かっているはずだ。しかしそのことはすっかり忘れ去られたように、みなが娘として扱った。 すぐにドレスに着替えると、バラの香水が振りかけられた。「今日は力が入っていますね」「ほほほ。当たり前ですわ。もしもマルコス王子とのご結婚が決まったら、サンタリカにとって大きな利益になりますもの。ザッハードは豊かな自然と鉱山に恵まれた裕福なお国ですよ」 驚いて反論しようとするミシェルをロザーナは許さない。「とにかく、今はこの流れに乗って。後はこちらに任せてくださいな」 そのまま中央広間を抜けて、テラスへと連れて行かれると、王室自慢のバラ園の噴水に大きなパラソルが設えられてあるのが見えた。 テラスを出ると、すぐにマルコスが声をかけてきた。「やぁ、今日もきれいだね。」「今日はどういうご用ですか?」 マルコスはやや小首をかしげるようにして、それから急にミシェルに顔を近づけた。「君に会いたくて、やってきたんだよ。」 とまどうミシェルを救い上げるように片腕に抱くと、バラ園の中へと誘う。「今までいろんな人と会ったけど、君ほど頭のいい人は見たことがない。それに乗馬もうまい。君は、僕が嫌い?」「そんな…、嫌いだなんて。」「じゃあ問題はないだろ? 今度うちの庭園にも遊びにおいでよ。君には見せたいものがたくさんあるんだ。一緒に馬に乗って散歩もしてみたいし、チェスもお手合わせ願いたい。どうだい?」好奇心に満ちた瞳に自分が映し出している。その肩ごしにラングレイが注意深く見つめているのがわかった。「わかりました。じゃあ、次の機会に。」「もう次の機会はある。実は、次の日曜日は僕の誕生日なんだ。国を挙げて祝福してくれるんだよ。君にもぜひパーティーに出席してもらいたいんだ」 ここは受けておくしかないだろう。ミシェルは首を縦に振った。マルコスは満面の笑みを浮かべると、急に顔を寄せる。「うれしいよ。僕のお姫様」 あっという間に頬にキスをされ、不覚にも頬を赤らめたミシェルは腕を引かれてテラスに戻ってきた。「じゃあ、日曜日に。約束だよ。」 それだけ言い残して表に出ると、マルコスは馬にまたがって颯爽と帰って行った。追いかけたミシェルは、ウイリアム王とラングレイが並んで見送っているのを目撃する。 この二人、グルなのか? いやな予感が広がっていく。
August 19, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その13
約束どおり、勝手口は開いていた。そっと馬を下りてゴードンたちと合流する。「お帰り。マーサは元気だったかい?」「ええ、思ったより元気そうだった。ゴードンさんたちのお名前を聞いて、すごく懐かしいって、言ってたわ。あ、そうだ。デュークって人、知ってる?」「デューク?ああ、スチュアートの弟だろ?年が離れていたから、スチュアートは随分可愛がっていたんだ。デュークも来たのかい?」 ゴードンは懐かしそうに言う。「いいえ、音信不通になってもう何年も経つんですって」「そうか。それは寂しいなぁ。」 しんみりとしたところで、ロザーナがやってきた。「まあ、こんなところにいたの。早く着替えてちょうだい。隣国の王子さまが急にこちらに見えることになったの。急いで!」「今日はお休みを頂いているんですが」 ミシェルの言葉など何の効果もなかった。「何言ってるの!王女さまにお休みなんてありません!」 ロザーナはミシェルを無理に引っ張って耳元でしかりつけた。ミシェルは諦めてレイチェル王女の部屋に急いだ。すぐさまドレスに着替え、カツラを被り、メイクを整えて部屋をでた。「おお、レイチェル王女、探したんだよ。今日は隣国ザッハードのマルコス王子がお越しになる。急に決まったのでおどろいただろうが、先方からの申し出だ。喜んでお受けしなさい。」 休みはキチンと許可されているのに、随分と好き勝手してくれるじゃないかと心の中で毒づいた。「ラングレイ殿下、ザッハードのご一行がお見えです。」 近衛兵の連絡を受け、ラングレイはにんまりと笑った。「うまくやれよ」 すれ違いざまそんな言葉を残し、ラングレイはすかさず中央の広間へと急いだ。ミシェルは戸惑った。何をどううまくやれと言うのか。 しかし、状況は待ってはくれない。すぐさまメイドたちに急かされて、広間へと連れて行かれた。「レイチェル王女。この度は、私のわがままにおつきあいくださり、感謝しております」「マルコス王子さま。わざわざこちらにおいでくださるとは、光栄でございますわ」 ロザーナに仕込まれたとおり、ゆっくりと顔を上げるとそこにはつい数時間前に川辺で話をした青年が立っていた。「やはり君だったか! あえて嬉しいよ!」「あなたはあの時の!」 ラングレイはすかさず鋭い視線を送っていたが、問題がなさそうだと分かると、さっさと退室を申し出た。「本日はレイチェル王女にご用とのこと。我々は、席をはずしておきますゆえ、御用の向きはベルでメイドをお呼びください」 一行が席をはずすのを待って、マルコスはパッと嬉しそうに笑った。「驚いただろ? さっき出会ったときは気付かなかったんだけど、別れてから思い出したんだ。先日ここで見かけた人だってね」「私は全然気がつかなかったわ。あの時はショックで…」 マルコスはそっとミシェルの肩に手を掛けた。「ごめんね。君を悲しませるつもりではなかったんだ」「気になさらないで。あの時は気が動転していたんだわ」 そのまま二人は馬の話やチェスの話で盛り上がり、時間の経つのも忘れていた。 小さなノックで二人が黙ると、ウイリアム王が入ってきた。「これは、これは。王様にお目にかかれるとは感激でございます。」「そんな風にかしこまらなくてもいい。今日はよくぞレイチェルに会いに来てくださったな。ザッハードとわがサンタリカはしっかりとした同盟で結ばれた同志。これからも我が家のように行き来してくだされ」 ウイリアムは満足げにそういうと、メイドにお茶とお菓子を用意させた。「わが王室は王妃をなくしたばかりだが、これからは若い世代が賑やかに盛り立てて行ってくれるのが一番なのだ。レイチェル、粗相のないようにな」「まあ、いやですわ!」 穏かに会話が弾む中、なぜか違和感を覚えるミシェルだった。 翌朝、ウイリアム王とラングレイはご機嫌で朝食を摂っていた。相変わらずハドソンは無口なまま食事をすると、さっさと部屋に帰ってしまう。それを目で追うラングレイが、近衛兵の一人に何かを耳打ちしている。 気付かない振りをしながら、ミシェルはその近衛兵の動きがきになった。早々に食事を切り上げ、自分の部屋に戻ると、小窓に鳩がいるのに気がついた。「ありがとう」 はとの足の手紙を開く。そこには急いで書いたらしい慌てた様子の文字が並んでいた。「ミシェル。落ち着いて聞け。先ほど軍上層部から連絡があった。隊長が消息を絶ったそうだ。俺たちは今週中にリュードに潜入する予定だ。スキャットマンもこちらに戻っている。お前の任務が終わっていないので、連れて行くことは出来ないが、無事を祈ってやってくれ! F」 堪えていたものがわっとあふれ出してしまった。ベッドに突っ伏して、声を殺して泣いた。嘘だ、嘘に決まっている。自分の目で確かめない限り、私は何も信じたくない!「どうかご無事で!ずっと祈っています!」はとの足に手紙をつけ、そっと抱きしめたあと、窓の外に放った。そのままその白い翼の上に乗って飛びだしてしまいたい! ミシェルは唇をかんだ。まだ諦めない。部隊のみんなが行ってくれるのだから。ミシェルが気持ちを落ち着ける前に、ドアがノックされた。
August 18, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その12
黒いワンピースに身を包み、静かな列に続いた。親の葬式に出るのは2度目だが、何度経験してもむなしい寂しいものだとミシェルは思う。たとえ偽りの母であったとしても、その笑顔を知っている以上、ミシェルには悲しい別れだったのだと、今、自分の父の葬儀に参列しながら考えていた。 親戚や知人を見送って母と二人になった。まだまだ若いと思っていた母の背中は、いつのまにかか細く年老いたものに変っているような気がした。「ほら、そこに座って。今、お茶を淹れるわ。向こうでの暮らしはどう?」「なんてことないわ。退屈な事務仕事よ」 紅茶を差し出しながら、そう答えるミシェルを見て母はほっとした表情を浮かべた。「ミシェル。もうしわけないんだけど、お父さんが亡くなったと管理局に連絡したら、今までの仕事で使っていたほかの研究費用も対象になることがわかったとかで、貴方の任期が延長になりそうなんですって。」「そんなぁ。お父さんが本当にその費用を全部使っていたの?一緒に研究していた人たち、どうしているのよ」 母に言っても仕方ない事だったが、つい突っかかってしまう。「実は、お父さんとも話していたんだけど、どうも何か記録を改ざんされているんじゃないかと思うんだけどねぇ。私たちでは調べる事もできなくて」 申し訳なさそうな母にこれ以上言い返すことは出来なかった。「とにかく、私は今の仕事をがんばるのみだわね。お母さんのところにはちゃんと生活費が届いてる?」「ええ、ちゃんと届いているわ。貴方のお陰ね。ちゃんと結婚資金も貯めてあるから、いい人が見つかったら連れていらっしゃいね」「お母さん…」 両親のことだ。そういう話はみんな相談済みなのであろうと推測できた。自分のいない日々に、両親がどんなことをどんな風に話し合いながら暮らしてきたのだろう。主の居ない車椅子は寂しげに窓の外を向いている。 この家に、自分も誰かと帰ってくることがあるだろうか。そんなことを思いながら、ふとジークのことが思い出されて、耳たぶが熱くなった。「じゃあ、私はそろそろ行くわね。お母さん一人で大丈夫?」「大丈夫よ。今までもそうやってお父さんを支えてきたんだもの。次は貴方が素敵な知らせを持って帰ってくれる日を楽しみにしているわ。お父さんといつもそんな話をしていたんだもの。ねぇ…」 そういいながら振り返った母は、誰も居ない車椅子を目の当たりにした。「はぁ、私も年かしらね。」 苦笑いを浮かべながらさっさと行きなさいと追い立てる母に急かされて、ミシェルは再び馬にまたがった。「ほら、これ。途中で食べなさい。クッキーと紅茶よ」「ありがとう! あ、そうだわ。職場の近くにゴードンさんたちご夫婦が働いているの。お母さんにヨロシクって、困った事があったら知らせてくれって」「まあ、ゴードンさん。懐かしいお名前ね。そういえば、あの子、来なかったわねぇ。」「あの子って?」 少し寂しげな顔で母は言う。「覚えてないの? デュークよ。貴方の大好きだった。仕方ないわね。もう長いこと音信不通なんだもの。」 母は無理に笑顔を作って手を振った。それに答えるように、ミシェルは手綱を持った。「いってらっしゃい!気をつけるのよ」「はい。お母さんもね」 頼もしい笑顔が帰ってくるのをみて、母は娘の変化に気付いていた。 そのまま馬を走らせて、中間地点の河を渡ったところで、馬を休ませた。馬が水を飲んでいる間に、母にもらったクッキーを広げてみた。はらりと何かが落ちて拾い上げてみると、それは父からの手紙だった。「ミシェル。この手紙を読むころ、私はもうこの世にはいないのだろう。しかしお前にはどうしても伝えておきたい事がある。」 やはり父は死期が迫っている事を知っていたのか。寂しさが不意に襲ってくる。それでもミシェルは読み続けた。父はミシェルの取る行動など全てお見通しだった。男として軍に紛れ込むなら、毎晩基礎トレーニングを続けろと記してあった。「無理よ。あんな狭い納戸の中じゃ、何も出来なかった」 そして、読み進むうちに驚くべき事実が書かれていた。父は野菜の研究をしていると言う事になっていたが、実は戦略司令部に配属され、国内の内紛や海外からの圧力を抑えてきたというのだ。そして、そこで新たなる武器の開発にも関わっており、ミシェルへの徴兵期間が長くなってしまっていると言う事だった。 父は最期まで自分を信じて生きよと綴り、信頼できる仲間を得よと励ました。その手紙をそっとカバンに納めて、空を仰ぐ。「父さん、ありがとう。」 不思議なことに、寂しさはなかった。父は自分の心の中に生き続けている。ミシェルにはそんな実感があった。 馬のそばに寄ると、青年が同じく馬に水を飲ませていた。「やあ、こんにちは。 君の馬?」「いいえ、友人に借りてきたの。急な用事があったものだから」「へえ、いい馬だね」 青年は馬をなでながらミシェルに振り返った。「君はこの辺の人?」「いいえ、普段はこの先の森の奥にいるの。また、仕事に戻らなくちゃ」「忙しいんだね。」 穏かな物腰、決して派手な服装ではないが、品の良さそうないでたちの青年は人懐っこく話してくる。「あなたは?」「僕はちょっと遠乗りしてきたんだ。本当は隣の国に住んでる。ホントは違反だよね。」「ふふふ。見つからないように気をつけてね」 なぜかほっとするその人柄にミシェルも打ち解けていった。二人はひとしきり話をして、名残り惜しそうに手を振った。「じゃあ、そろそろ行くわ。仕事が待ってるの」「仕方ないね。僕もそろそろ行かなくちゃ。じゃあ、また何処かで会えたら」「ええ、さようなら」 映画で見たような別れをして、ミシェルは王室の敷地まで止まることなく走り続けた。
August 16, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その11
宴が終わり王が退室するとミシェルはそっと舞台の裾に向かい、ツボを抱えてレイチェル王女の部屋へと戻った。ロザーナがやってくる前にツボの中を片付け、着替えておかなければならない。バタバタと着替えを済ませ、カツラの上のティアラを外しているところにロザーナが戻ってきた。「お疲れ様。あ、そのティアラはそっと扱ってくださいな。まったく。これだから殿方は困るのです。女性ならもっと丁寧に扱ってくれるんでしょうのに。」「すみません」 ミシェルは心の中でだけ口を尖らせた。この状況はなかなか難しいのだ。ドレスと宝石の類を片付けると、メイドたちはさっさと引き上げ、ミシェルにもほっとする時間がやってくる。レイチェル王女の奥の間に戻ると、鳩が小窓の縁で鳴いていた。「ありがとう。」 ミシェルは鳩を抱き寄せて頭を擦ると、そっと足に付いた手紙を解いた。「調査結果だ。王妃はもともと健康体であったのに、どうやら鉄過剰症に陥れられていた様だ。スキャットマンに会っただろう?弱ったところを見計らって王女の失踪、そして犯行声明と王女の死を思わせるティアラ返還だ。巧妙なやり方だが犯人ははっきりした。ミシェル、気をつけろよ。詳細はツボの中だ。 それと、隊長のチェロはどうだった?すばらしいだろう? しかし惚れるなよ。お前の女装に隊長はすっかり調子を崩している。隠そうとしているのが痛々しいぜ。早く元の姿に戻ってもらわないと、こっちもえらいことになりそうだぜ。F」 ミシェルは驚きのあまり倒れそうになった。あのチェロを弾いていた紳士が隊長?あのボサボサ頭に無精ひげを生やしたむさくるしくも厚かましいジークだったとは。 それでも心臓がドキドキしているのをとめることは出来なかった。 急いで自分の頬を手のひらで叩き気合を入れなおすと、つぼの中にある資料を取り出した。その厚みはツボを移動する時に気付いてはいたが、短期間に多くを探り当てる仲間のすごさに改めて尊敬の念を覚えた。 夕食を終えて自室に戻ってくると、ミシェルは本格的に資料に読みふけった。ジークに出された指令は、国交のないリュードという国のテロ集団、ジャンキーに潜入してレイチェル王女誘拐の犯人を捕まえる事。そしてレイチェル王女を救い出すことだという。 確かにレイチェル王女の失踪は国民には内密なので、長い髪やティアラが送りつけられた事も公表はされていない。しかしそれが送りつけられた時点で、王女の生存は絶望的と言えるのではないのか。それとも、その亡骸を連れ戻せと言うのか。 ミシェルはラングレイの影の人格に恐れおののいた。 しかし、レイチェルも王妃も亡くなった今、次に狙われるのは誰なのか。冷静に考えてウイリアム王に間違いないだろう。ミシェルは自分の打った手でどこまで防げるのか、心もとない気分だった。 気を揉んでいるうちに三日はあっという間にすぎた。ジークはラングレイの元に呼び出され、正式な命を受けた。ミシェルはジークに会うチャンスを与えられず、小窓に寄りかかって外の様子を眺めていた。 ふいに鳩が飛び込んできた。足の手紙を解いてやると、鳩はすぐさま大空に飛び立つ。手元の手紙には「開けるな」と書かれてあり、もしも帰って来なかったなら、これを読むようにと記されてあった。窓に飛びついたミシェルは先ほどの鳩がジークの乗った車の上を飛んでいるのが見えた。「私にも、翼があればいいのに!」 ミシェルはその車が見えなくなるまでいつまでも見送っていた。 それからしばらくはただ黙々と王女の振りをして外交をこなす日々が続いていた。それが落ち着いたある日、ミシェルに軍から連絡が届いた。訃報だった。 ミシェルはラングレイに休暇を申し入れ、1日だけの休みを手に入れた。すぐさまアーミースタイルに着替えると、調理室へと急ぐ。「ゴードンさん、お願いがあるの! 父が、今朝亡くなったって、連絡が来て」「なんだって!そうか、スチュアートの奴…」「それで、どうしても今日一日で実家に行って戻ってこなくちゃならないの。」「今日一日でか?!厳しいなぁ。ここは警備の関係もあるから公共の乗り物には簡単にありつけないよ。そうだ!お前さん、乗馬は得意だったな。野菜を運んでくるオヤジに頼んでやるよ。もうすぐ来るころだ。」 言い終わると同時に勝手口のドアが開いた。「俺になんかようか?」 ゴードンはすぐさま事の次第を伝え、馬を一頭借りる事に成功した。「ゴードンさん、ありがとう。」「奥さんにヨロシク言っておくれ。俺も行きたいが仕事だからな。」 寂しげな顔はゴードンには似合わなかった。そんなゴードンの肩をごんと荒っぽく叩いて押しのけ、ゴードンの女房が包みを差し出した。「ミシェルちゃん、コレをもって行きな! どうせ昼には着かないだろう。途中で食べるんだよ。それから、あんたのお母さんに伝言しておくれ。困った事があったら、いつでも言ってきてってね」 ミシェルはゴードンの女房のふくよかな胸に顔をうずめた。「ありがとう。じゃあ、時間がないのですぐでかけるわ」「裏門は夕方の仕入れの時間には開いているよ。それに間に合わなかったら夜まで待っておくれ。そうすれば朝食の材料を届けに業者が来る。それに紛れて入ればいい」 こういう時は女の方が肝が据わっているらしい。帰りの段取りもしっかりとつけて、ゴードンの女房は勝手口の扉を開けた。「さあ、早くお行き!」「ありがとう、おばさま!では、行ってきます」 軽やかなひづめの音を立て、ミシェルはふるさとを目指した。
August 15, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その10
「アンタ!あれじゃないの? ラングレイ殿下が持ってきたあのお薬!」「ああ、そうだ!」 横から声をかけたのはゴードンの女房だ。ゴードンの話では、彼らがここに仕事に来た頃にラングレイ直々に調理場にやってきて手渡したものだという。「これは東洋の秘薬で、貧血気味の王妃に飲ませると体調がよくなるというものだが、王妃がお飲みにならないので、粉砕して料理に入れてくれと」 ミシェルはすぐさまその薬を確かめた。「これは、鉄剤…?」「まあ、そんなものだろうなぁ。しかし、東洋の秘薬ってやつはたいした事ないのかねぇ。この国にだってもっと少しでもちゃんと効く薬があるだろうに。随分沢山いれなきゃならん」 それはおかしい。いくらよその国のことといっても違和感がある。ミシェルはゴードンから1回分の量を確認すると、すぐさま部屋に戻り鳩を飛ばした。ジークの出発は3日後。他のメンバーもまだ待機しているはずだ。 そのままじっとしていることができないミシェルは、自らも王室図書館へと足を運んだ。もしかしたら、何か見つかるかもしれない。静まり返った図書館の中を音を立てないように歩くのは至難の業だ。そっと医学書のコーナーに近づいたところで、司書と思しき細身の男に出会った。「これは、これは!レイチェル王女。この度の王妃さまのこと、心よりお悔やみ申し上げます。それにしても、こんなところにおいでくださるとはめずらしいですな」「なにか気持ちを紛らわせるものが欲しかったのです」 視線を下げ、悲しみに暮れる姫君を装うが、どうもこの男全てを分かっているような顔つきだ。「それならば、これなどいかがですか? さきほどハドソン王子も読んでいらっしゃいました。難しい本の方が気が紛れるとかで」「そう、ではそれをお借りするわ」 何気なく受け取ったその分厚い本は薬学に関する資料だった。はやりハドソンもなにか気付いたのか。それにしても、とミシェルは男の後姿を眺めた。敵なのか見方なのかさっぱりわからない。ただ、挑むようなその目に、見覚えがあるような気がしてならない。 窓辺に座り分厚い本をめくると、インクの独特の匂いが鼻を突いた。この匂いは父の部屋の匂いと同じだ。ミシェルは遠い日に父に見せてもらった百科事典を思い出していた。 ぱらりとページをめくると思わぬ文字が目に飛び込んだ。 『鉄過剰症』 鉄剤の過剰摂取により内臓に支障をきたすというものだ。もしもラングレイがこれを使ったとしたら。リュードへの潜入にもなにか裏があるかもしれない。そうなればジークも無事ではすまないだろう。ミシェルは唇をかみ締めた。「レイチェル王女、そろそろお部屋にお戻りになったほうがよろしいのでは?先ほど近衛兵がレイチェル王女を探しているようでしたよ」「え?」 顔を上げたミシェルはやっと気が付いた。ひげを蓄え銀縁の眼鏡をかけているが、その瞳に覚えがある。そうだ!スキャットマンだ!「ご親切にどうも。」 ミシェルは満面の笑みを浮かべて答えた。スキャットマンは控えめな微笑みを浮かべ。何食わぬ顔で机にあった分厚い本を手に取った。「レイチェル!そんなところにいたのか! もうすぐ王妃を偲ぶ会が開かれる。早く支度をしなさい!」「わかりました」 ミシェルは席を立ち、司書に一礼して部屋を出た。「新しい司書か。こちらに挨拶もせず、無礼な奴だ」 ラングレイは口の中でもごもごと文句を言いながらミシェルを追いかけた。ミシェルが部屋に戻るとすでにロザーナがドレスや宝石を準備して待っていた。「今日は隣国の王子さまもご出席くださるので、正装していただきますよ。さあ、これを身につけてくださいな。準備が出来たらカツラをセットしますので」 ドレスを身につけるのはすっかり板についた。さっさと着替えを済ませると、ロザーナを呼んでカツラをセットしてもらう。「はぁ、何度見てもレイチェル様に瓜二つだわ。どうしてあなたは女性に生まれなかったの。もったいないわぁ」「ロザーナ様。それは内密にとラングレイ殿下が」 メイドたちが楽しそうにロザーナを嗜める。ここの女性達は本当のことを知らないのだろうか。ミシェルは一層気持ちを引き締めた。 王妃を偲ぶ会は、静かな音楽と共に始まった。王妃が好きだった花がいたるところに飾られ、王妃の好みの紅茶とケーキが振舞われた。正面に飾られた美しい肖像画は見るものの涙を誘っていた。ウイリアム王はそれでも隣国の王子と穏かに言葉を交わし、懸命に堪えている様子だった。ミシェルはただ寂しげに下を向いたまま時が過ぎるのを待つしかなかった。ちらりと隣を見ると、ハドソンが何か考え込んでいるのが見える。睨みつけるその視線は会場のあちらこちらに飾られた花だ。「王子、お花がどうかしましたか?」 ミシェルが小声で尋ねた。「お前には関係ない。お前はラングレイの手下なんだろ? 今度は誰を殺す気だ!」 声を潜めていても、その激情は伝わってくる。ミシェルはどうにもやりきれない気持ちでいた。「王子、私ども特殊部隊は王室を守る為に派遣されております。どうか、ご理解ください。」 王子は何も答えない代わりに、父親に似た大きな瞳でじっとその真偽を確かめるように睨み付けた。その視線に耐えられなくなったミシェルは飾られた花を眺めた。 王妃が好んで飾らせた真っ白な胡蝶蘭と一緒に飾られているのは赤い西洋ツツジだ。王子は何かに気付いているというのか。 周りの拍手で演奏家が変るのが分かった。次に出てきたのはタキシード姿の男性だった。髪を後ろに撫でつけ、うやうやしく頭を下げると、そっと舞台脇からチェロを持ち出してきた。 居住まいを正し、奏でるメロディは低く厳かに王室の人々を癒していった。「なんて慈愛に満ちた響き」「お前なんかに私や父の気持ちなど分かってたまるか!」 ハドソンは吐き捨てるように小さく言った。しかしその視線は滑らかに動く弓をただひたすら見つめていた。 ミシェルはもうへそ曲がりな王子に構わず、じっとその音色に身を投じた。そっと目を閉じると、実家の庭に縁台を並べて木漏れ日を浴びながら座っている自分がいた。両親とその仲間たちが集まり、料理をつまみ、酒を酌み交わす。その風景の中にこの音楽が流れていたような気がした。 穏かな笑い声の中、自分はなぜかドキドキして何かを握り締めている。まだ幼くてふっくらとしたその手を広げると乳白色の鳩が翼を広げている。そう、それを誰かにプレゼントしたのだ。 不意に思い出した記憶に懐かしさがこみ上げる。ミシェルが目を開けると、拍手の中、演者が深々と頭を下げているところだった。顔を上げたその瞳は、ちらりとミシェルを見やりチェロを抱えて舞台から下がってしまった。 たったそれだけのことだったが、ミシェルは心臓をつかまれたような衝撃をうけた。これはどういうこと? どうしてこんなに動悸がするの? ミシェルは何事もなかったように座っているのがやっとだった。
August 12, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その9
「レイチェル!」 鎮痛な面持ちで膝間づくラングレイにウイリアム王は本当なのかと詰め寄った。だがその後ろではかなく倒れこむ王妃を見ると、その勢いは消えうせた。側近に助けられ、そのまま退室する王妃に続いてウイリアム王もかけていった。 しかし、ハドソンは冷ややかにラングレイを見ていた。この王室で何かあれば、それはラングレイの仕業に違いないとでも言いたげな瞳だ。ラングレイもその辺りは察しているのか、憔悴した様子でハドソンの肩に手を掛けた。「ハドソン、お前は心配ではないのか? 同じ王家の人間として、お前の人格を疑うよ」 ミシェルは耳を疑った。これはラングレイの宣戦布告とさえ取れる。黙って見つめる視線に気づいたのか、ラングレイはミシェルに退室せよとあごで指示した。「失礼します」 そっと席を立ち、ラングレイに背中を見せながら、ミシェルはしきりにハドソンに注意を促したが、もとよりミシェルの言う事など聞く気はないハドソンに、そんな些細な言動は届かなかった。 部屋を出て廊下を歩く足音だけ少しさせてそこに留まっていると、思わぬ言葉が聞こえてきた。「ハドソン、お前がやったんだな! いくら仲が悪いと言っても、命までとるとはどういうことだ!説明してもらおうか!」 あまりにも大きな声に、違和感すら覚える。「冗談じゃない!そんなことするわけないだろう!」「じゃあ、どうしてレイチェルを城の外に追い出した!お前がレイチェルのティアラを窓から投げ捨てるのを、私は見ていたのだぞ!」 緊迫した空気がドアの隙間からもじりじりと漏れ出ている。そっと柱の影に身を潜めていると、いきなり激しい音と共にドアが開き、ハドソンが駆け出してきた。 廊下の途中にいる人影に気付いたハドソンは気まずい表情でそのまま走り去っていった。呆然と見送るミシェルをドアの隙間からじっと見ていた男は、満足げに口角を上げた。 国民には何も知らせないまま、一月が過ぎた。王妃の体調が優れず、ウイリアム王は付っきりになった。しかし、ラングレイの動きはあわただしかった。執務を預けられたのをいいことに、犯行声明の送り主である西の国リュードのテロ組織・ジャンキーにむけて特殊部隊を送りこむことを決定したのだ。ハドソンにも執拗に尋問を繰り返した。ある朝、起き上がることも出来なくなっていた王妃は、王の献身的な介護もむなしくそのままあっけなく亡くなってしまった。 王妃の葬儀は国を挙げて盛大に行われ、国内外の貴族が集まった。ミシェルも黒いドレスに身を包み、その列に並んだ。葬儀が終わり、部屋に戻るミシェルに声を掛けるものがいた。「ミシェルちゃん、じゃないか?」 ゾクリと背筋に冷たい汗が流れるのを覚える。「どなたでしょう?」「調理の手伝いでやってきたゴードンと言う者だ。スチュアートは元気かい?」「父…、スチュアートさんをご存知なんですの? わたくしはレイチェル。ということになっております。どうかお許しを!」 小太りの男は何かを察したのか、そっと頭を下げたまま告げた。「了解した。しばらくは王室の調理室にいる。何かあったら連絡してくれ。」「わかりました」 ミシェルはそっと頭を下げ、優雅に歩き出した。ゴードン、その名前に覚えがあった。父スチュアートの幼馴染で料理上手なゴードンは、ミシェルが幼い頃にはよくご馳走を抱えて遊びに来てくれたものだ。 その夜、ミシェルの窓に鳩がやってきた。足にくくられた手紙を開くと思わず笑みが漏れる。明日、王家の人々を慰める演奏会があるので、紛れこむというのだ。少し厚い資料を渡すので舞台の末席につぼを置くように指示があった。また、ジークを見つけても、絶対に知らぬ振りをせよとのことだった。 見つけても知らぬ振りをするというのはどういうことだろう。ピエロにでもなるつもりか。 しかし、その笑みもすぐに消えた。最後に書かれた一文が緊張を強いたのだ。「リュードに単身潜入の任務が来た。特殊部隊も後日動員されるだろう。」 そんな日が来るかもしれない事は分かっていた。それでも目の前のこの文字を違うものに摩り替えたい気持ちをとめられない。 その夜、ミシェルは手紙を握り締めたまま眠った。ジークならきっとうまくやり遂げる。もう何度も自分に言い聞かせているが、王室に身を置いてこの密室の中で行われているやり取りを目の当たりにすると、あまりにも大きな影の動きに恐れを覚えてしまう。 翌朝、早くに目覚めたミシェルは頃合のツボを見つけ、中に自分の手紙を潜ませた。王妃がなくなった今となっては、あの和やかな朝食の時間は望めない。ウイリアム王は別室に食事を運ばせ、ハドソンは朝食の間に顔を出したものの、食事も摂らずに調べ物をすると言って姿を消した。ラングレイと二人、広いテーブルを挟んで食事をする。なんとも味気ない食事になった。 紅茶を口に運んだとき、ささやかな違和感を覚えた。嫌な予感がする。何食わぬ顔で食事を終えると、ミシェルは部屋に戻った。すぐさまカツラを脱ぎ捨て、兵士の服に着替えると、近衛兵の目を盗んで調理場へと急いだ。 調理場の中では朝食の支度が終って一段落している様子だった。そっと中を確かめ、見慣れた顔を見つけてほっとする。「おじさん!」「おお、お前さんか。昨日とは随分違うな」 朗らかに笑うゴードンだったが、ミシェルの顔は緩まなかった。「おじさん、教えて欲しいことがあるの。おじさんはいつ頃からここのお手伝いをしてるの?」「ええっと、半年ほど前かなぁ」「じゃあ、何か気に成る事はなかった? 特に王妃の食事について。何か特別なものをつけさせられたとか」 ゴードンは腕を組んで黙り込んだ。
August 11, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その8
王女としての身のこなしにも慣れてきた頃、王様と王妃に謁見できることとなった。あまりに似ているミシェルを見た王妃の取り乱し様は大変なもので、多くの者の涙を誘った。しかし、にこりともしないで睨みつけている者がいる。ハドソン王子だ。王子はレイチェル王女の弟にあたり、普段からあまり仲がよくなかったというのがメイドたちの噂だ。 王室にやってきて2週間が過ぎた頃、王女に面会のものがやってきた。ジークだ。「王女さま、ご機嫌麗しゅうございます。」 うやうやしく頭を下げるジークを見て、ミシェルは笑いを堪えるのに苦労した。しかし、周りには近衛兵やラングレイも同席している。うかつには表情が出せない。 その時、王室の庭の向こうで小さな爆発音が聞こえた。「今の音は?」 驚くラングレイにすかさずジークが叫んだ。「ご心配には及びません。我ら特殊部隊がすぐに解決して参ります!」「いや、おそらく城内であろう。私の率いる近衛兵の方が手馴れているのだ。者ども、急げ!」 ラングレイはとっさに兵を率いて飛び出して行った。その隙をついて、ジークはミシェルに駆け寄った。「気をつけろ。リチャードはお前から隔離されている。こちらに近づこうにもガードが固いのだ。これからの通信には鳩を使おう。ラングレイ殿下はどうも裏の顔をお持ちのようだ。もう少し内偵してみないと分からないが、俺の勘では、次に狙われるのはウイリアム王かハドソン王子だ。気をつけろ!」 そこまで言うと、ふいにミシェルの顔をまじまじと見た。「お前…。きれいだな」「え?!」 遠くからどやどやと足音が近づいてきた。「大丈夫だ。下らん仕掛けに過ぎなかったよ。私の部下にかかればあんなものは恐るるに足らずだ」「さすがはラングレイ殿下!」 ラングレイは鼻息を荒くして笑って見せた。「ところでジークとやら、このたびは西部の動乱を見事に治めてきたようだな。おって陛下より褒美が出るようだ。」「はは。有難きお言葉。」 ジークは跪き、頭を下げる。満足げな殿下は近衛兵を所払いすると、鋭く言う。「業務連絡は控えめに願おう。近衛兵たちにすら、ばれないように心がけてもらいたい。今後数年はミシェルに代役を頼むことになるだろう。ジーク。君にも近々遠征の命が下る。心して当たりたまえ。」 そういうと、さっさと部屋を出た。「隊長。今の言葉、どういうことですか?」「ん、確かにおかしい。お前の任務が長期にわたるとは聞いていない。本物の王女が見つかればすぐに終る話だったはずだ。近衛兵にも伝えず探そうともしていないとは、随分なめられたもんだな」「おかしいです。陛下には懸命に捜索していると伝えていたのに」 ミシェルは唇をかんだ。「気をつけろよ。これはちょっと大掛かりな仕事になるかもしれない。お前に一つ任務を与える。陛下のお抱えの仕立て屋か音楽家を調べてくれ、返答は鳩で。じゃあな」 か細い肩に大きな手がどんと乗った。不満は言わない。今はこの仕事をこなすのみだ。ミシェルは決意を新たにした。 ミシェルの任務は簡単に終った。おしゃべりなメイドたちにかかれば、王室の情報はいとも簡単に流れだす。夕食を終えると、ミシェルはすぐさま自分の部屋に戻り、待機していた鳩の足に手紙を結びつけた。「頼んだよ。」 そっと夕暮れの空に解き放つと、白い翼を広げてさっそうと飛び出していく。後は隊長からの指示を待つのみだ。 遠く日の暮れるのを眺めていると、乱暴にドアをノックするものがいた。ハドソンだ。「ハドソン王子!どうかなさいましたか?」「シッ! その口の利き方はおかしいだろ!とにかく中に入るぞ!」 ハドソンはミシェルを押しのけるようにしてレイチェルの部屋に入ると、じっと奥の壁を見つめていた。ふいに胸いっぱいに息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す。「お前の目的はなんだ。レイチェルの陰謀か!」「ご存知とは思いますが、私はラングレイ殿下のご依頼で派遣されたまでです。レイチェル王女の陰謀とはどういうことですか?」 ハドソンは目をそらし、ちっと舌打ちした。「男のくせに女の格好させられて、お前は恥ずかしくないのか?」 苦し紛れに怒鳴るハドソンに、冷たい返事が帰ってきた。「大変失礼な事を申し上げるようですが、我々一般国民はみな、徴兵制によってお国の為に何年間か軍に身を置かねばなりません。私はまだ未成年ですが、病身の父の身代わりで勤めているのです。どんな屈辱的な仕打ちにも耐えなければ成りません。王子、貴方の生活はそんな国民たちの努力によって守られているのです。そのことを、どうかご理解いただきたい」「ふん!一般階級ごときが!」 やりたい放題の生活しか知らない王子には、理解できない言葉だった。自分の苛立ちの矛先が見つからず、王子はぷいと部屋を飛び出して行った。 翌朝、王室の朝食に招かれたミシェルは、食事の後の歓談会にも出席するようにと呼びたてられた。 初めのうちは緊張のあまり何を食べたのかも分からなかったにせ王女だったが、日が経つにつれ、王家の人々の性格も分かり、それなりの立ち位置を理解した。王家の人々だけの歓談会は打ち解けた雰囲気のなかに始まった。しかし、近衛兵の耳打ちにラングレイが退席して再び戻ってきた時、全ては変ってしまった。「王様に申し上げます。レイチェル王女の髪とティアラが、先ほど犯行声明と共に門前に置かれていたとの報告が入りました。」
August 10, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その7
翌日からは厳しいトレーニングが始まった。午前は走りこみとジム。午後からは爆発物の仕掛け方やトラップの仕込みを習い、その後は射的やナイフ投げの腕を磨いた。 射的はスキャットマンが熱心に教え、ナイフ投げはジークが担当した。爆発物やトラップの事は、フィルが得意だ。素質のあるミシェルは面白いように知識を吸収した。 休日は何もなければ週に2日。ディックの妻、デイジーは世話好きでよくバーベキューをしようとメンバーを招待した。リチャードの妻はまだ若く、ミシェルと変らないほどだ。仲間に冷やかされてさすがの堅物も頬を染めた。ジョージの妻とフィルの妻は意外なことに幼馴染だという事が分かり、一層家族ぐるみの付き合いが増えていった。このまま、何事も起こらなければいいのに。心のどこかにそんな思いが芽生え始めていた。 明け方、なにか赤いものが動いているので目が覚めたミシェルは、すぐさま服を着替えて飛び出した。転がるように階段を上がり、司令室に向かう。すでにフィルがコンピュータを操作していた。他のメンバーも次々やってくる。「そろったか?」 最後に入ってきたのはジークだった。司令室の奥で幹部と連絡を取っていたらしい。「では任務を発表する。西部動乱の鎮圧と王室警護の2つだ。初めてのミッションだが同時進行でやってもらう。王室からはミシェル、お前が指名されているぞ。あとは、リチャード、ミシェルに同行してミシェルの後方支援と俺への報告を頼む。」「イエス、サー!」 二人はそろって敬礼する。「残りのものは西部へ向かうぞ。こちらは数日は帰ってこられないだろう。家族に声をかけておいてくれ。出発は午後2時だ。」 一気に張り詰めた空気で満たされた。それにしても王室からの要請とは腑に落ちない。それに、自分が名指しされているのも気になる。 部屋に戻って武器の装備をしていると、ドアがノックされた。ジークだ。「今回は目立つ武器は持っていくな。極力目立たないように装備するんだ。お前の護衛はリチャードに任せてある。」「どういうことですか?」 隊長は机の上に置いたフォトフレームを見つめながらつぶやくように言う。「どうも王室の様子がおかしい。今回の依頼はラングレイ殿下からのものなんだ。軍上層部でも踏み込んで確認できないところなんだが、ラングレイ殿下については以前からおかしな噂も流れている。心して任務を遂行するように。西部の動乱が落ち着いたら、俺もすぐ王室の情報を集める予定だ。それまでなんとか持ちこたえていろよ。」「王室への派遣は対外的なものではないってことですか?」 詰め寄るミシェルにふっとため息をついた。「まあ、そういうことだ。だが実際には行ってみないとわからない。無理のない情報収集を心がけろよ。依頼主はラングレイ殿下だが、俺たち軍は祖国サンタリカの王、ウイリアム陛下のものだ。そこのところ、忘れるなよ。」「イエス、サー!」 ふふっとジークは笑った。「プライベートな時まで言わなくていいさ。気をつけろよ。じゃあな」「隊長も、お気をつけて!」 慌ててかけた声に不敵な笑みが振り返った。「ふっ、西部のバカどもなんぞ、あっという間に木っ端みじんにしてやるさ」 いつもの自信家の顔を見て、ほっとするミシェルだった。それにしても、王室内部はどうなっているのだろう。武器を吟味しながら、翌日に訪れる新たな事態を想像できずにいた。「ラングレイ殿下のご依頼の元、ミシェル・グロウ、リチャード・カーターの二名、ただ今参上いたしました。」「うむ」 優しげなその表情からは悪意は窺えない。直立不動で並ぶ二人をラングレイはまじまじと見つめると、静かに説明を始めた。「実は、レイチェル王女が行方不明なのだ。対外的に問題になっては困るので、どうしても伏せておきたい。王女捜索は近衛兵に命じてあるので、君たちには王女に成りすます事と、王女役の警備を担当してもらいたい。ミシェル君、だったね。君の容姿はすばらしく王女に似ているのだ。しばらくは王女にふさわしい立ち振舞いを学んでもらおう。リチャード君は、彼が王女として外交に出たときに護衛を頼みたい。但し、普段は近衛兵と内密のうちに王女の行方を捜してもらいたい。」「イエス、サー!」 ほどなく近衛兵の密偵のリーダーがやってきた。リチャードとニ、三言葉を交わすと、連れ立って部屋を出た。ラングレイはメイドたちを呼び、ミシェルにあうドレスを選んで着替えさせることを命じる。 自分が女性である事がばれないかとヒヤヒヤしていたミシェルだったが、女性たちも席をはずし、ミシェルを男として扱った。アーミー模様のカーゴパンツと特殊部隊の上着を脱いで、シャワーを浴び、コルセットやパニエをつける。レースと宝石がちりばめられたドレスに袖を通す。忘れかけていた女性としての喜びに思わず顔がほころんだ。ヒールの高い靴を履き、鏡の前に立ったミシェルははっとした。短くカットした髪があまりにも不釣合いだったのだ。「男が変装しているんだ。不満げにしなくちゃ」 自分に言い聞かせ、わざと仏頂面でメイドたちの待つ部屋に出向いた。「まあ。お似合いですわ。本当に王女さまにそっくり」「男の方だなんて、思えないわ。もったいないほどの白い肌!」 メイドたちは口々に感嘆の声を上げた。「静かに。騒ぎすぎですよ。」 カーテンの奥からカツラを持った年配の女性が現れた。おそらくこの女性がお世話係の長を勤めているのだろう。「私は、お世話係長のロザーナと申します。ミシェルさん、このカツラを被ってみてください。」「こう、でしょうか?」 女性は寂しげに微笑んで、髪の乱れを整えた。「レイチェルさまにそっくりだわ。本当にどこに行ってしまわれたのかしら」「ロザーナさん、王女様はきっとわれわれがお助けしますよ!どうか元気を出してください」 ロザーナな無理に笑って頷くと、そのままミシェルをつれてラングレイの元を訪れた。「殿下、いかがでしょう」「レイチェル!いや、違うのだな。ロザーナ、しばらくはミシェルを王女として代役に立てることにする。外交にも出てもらうことになるので、礼儀作法はしっかりと教えておくように」「承知いたしました。」 それからしばらくは、人が変わったようにスパルタ教育をするロザーナを相手に悪戦苦闘の日々だった。そんな中でわかったことは、王女が行方不明になった事を知っているのは王家の人々と王女の世話係、それと近衛兵の一部のみということだ。 ミシェルの部屋はレイチェル王女の部屋の一つを間借りする形で作られた。そうすることでミシェルが王女として自分の部屋を行き来できるように考えられたのだ。
August 9, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その6
「他に質問は?」「そこにいるミシェルという人物は、どうしてここにいるのですか?」 抑揚のない冷たい声がミシェルを突き刺した。チャーリーだ。「こいつか?こいつは以前俺のいた部隊の掃除係だ。見た目は役に立たなさそうだがいろいろと使い勝手がいい。少なくとも、実戦では対等だと思うが。」「まさか…」 呟きと同時にチャーリーは小さな胸倉をつかむ。ミシェルはくるりと体勢を変えて投げ飛ばす。すぐさま立ち位置を変えて平手が飛んでくる。ギリギリのところを払い落とし、後ろから飛んでくる回し蹴りを交わしながら軸足を蹴り倒した。「うっ…」「あ、すみません。大丈夫ですか?つい、勢いで…。」 むっとするリチャードの肩をぽんと叩いて、ジョージが笑った。「そんなにとげとげするなよ。ここに選ばれているんだから、なにかしらの特技があるってことさ。ミシェル、気にするなよ。なかよくやろうぜ」「はい、よろしくお願いします」 ジョージはすばらしいムードメーカーだ。一気に場の雰囲気が和らいだ。「いい動きだったぜ、ミシェル。どこで覚えた?」「父に教えてもらいました。」「いいお父さんだな。俺が後で指導してやるよ。少し筋肉が足りないんじゃないか?」 ディックが細い腕を振りながら言う。「いや、こいつにはこのままの体形の方がいいんじゃないか?俺とおんなじだ。筋肉質にならずに俊敏に動く。力仕事はディック、君に任せるさ。そうだろ?」 スキャットマンはさらりと笑って見せた。任しときなと力瘤を見せるディックに一同がわっと笑った。「では、今日の会議はここまでだ。昨年の西部の暴動の後始末がすっきりしていない。あの時は第3部隊で鎮圧したが、首謀者は逃亡したままだ。近いうちに出動要請があるかもしれん。休みの間に家族とのんびりしておいてくれ。もちろん、トレーニングは欠かすなよ」 ジークが言うと、一同は席を立った。会議室は最上階、そこから中央の階段を使って下りる。一フロアに二軒が暮らしている。ベランダを広く取ってあるので、家族が多いほど部屋数の多い下の階に下りる事になる。ジークは踊り場を出て部屋に向かいながら、珍しくミシェルに声をかけた。「どうだ、これから一つチェスでもやってみるか?」「いいですねぇ。」 答えながら、前から気になっていたことを聞き出してやろうと考える。ジークに続いて部屋に入ると雑念と荷物がならんであった。「どうだ、あまりに汚くて掃除したくなっただろう。」「隊長。それが目的ですか?」 むっとするミシェルににやりと返すジークだったが、さすがにミシェルも黙っていなかった。「わかりました。私が負けたら掃除しましょう。でも、もしも勝ったらその貝の鳩のペンダントをつけている理由を聞かせてください」「ん?これか? いいだろう」 ジークはそっと柔らかな光を放つ鳩を指でなでた。「いやぁ、助かったよ。また部屋が汚れたら一戦交えよう。ご苦労」 楽しげなジークに見送られて、ふくれ面のミシェルは部屋を出た。掃除どころか洗濯までさせられたのだ。自分の部屋の片付けもまだだというのに。 それでも、今までのようにみんなが寝静まってからのシャワーからも介抱されるのだ。気持ちは弾んでいる。さっぱりと荷物を片付け、シャワーを済ませてはたと気が付いた。食事の用意が何もない。前の宿舎と違って食堂がないのだ。 仕方なく服に着替えて部屋を出ると、ちょうどジークも部屋を出てきたところだった。「なんだ、今頃。」「ちょっと散歩です」「偶然だな。俺もそうだ」 ぎこちない空気が流れる中、二人は階段を下りる。フロアごとにおいしそうな匂いが漂い、恨めしくさえ思える。建物の外に出ると、街は夕焼けに染まっていた。 少し歩いたところにスーパーがある。閉店ギリギリに滑り込んである程度の食材を買い込むと元来た道を戻った。気が付けばジークも何かを手に提げてのんびりと歩いている。「隊長!今日の分しか買ってないのですか?」「おお、お前か。なんだ、俺の分まで準備しているとはたいした奴だな」「いえ、余計なものは買っていません!」 足を早めてさっさと通り過ぎようとするが、あっという間に袋を奪われた。「ほう、バケットがあるじゃないか。それにコーヒーもある。朝はそんなに食べないからコーヒーとトーストだけでもがまんしよう」「いい加減にしてください!」 いきり立つミシェルの肩にジークはそっとその手を乗せて静かに言った。「ミシェル、お前はちっとも自分のことがわかってないなぁ。俺がどうしてお前を特殊部隊に連れてきたのかまだわからないのか?」 その真剣な眼差しに、ミシェルは動揺した。いつも勝手ばかり言う上司が、こんな風に真摯な態度をみせるなんて。胸の辺りがぎゅっと締め付けられる。もしかして、この人は自分を女だと見抜いているのだろうか。どぎまぎしながらジークの言葉を待った。「掃除洗濯とくれば残るは一つだ。」「炊事? ですか」「大当たり。他の連中はみんな家族がいるんだよ。独り者は俺たちだけだ。まあ仲良くやろうぜ。」 何が仲良くだ。ほんの一瞬でも何かを期待した自分が悔しかった。さっさとその場を離れ、宿舎まで帰ってくると、かわいい子どもの笑い声が聞こえる。ディックの家は小さい子どもがいるのか。中央の階段を上がって行く。 ビーフシチューの香りが漂ってきた。これは相当おいしそうだ。フィルの奥さんは料理上手らしい。 自分の部屋にたどり着くと、調味料をセッティングし、急いで料理に取り掛かる。やっと食卓についたところで、ベルが鳴る。「ミシェル、皿は2枚あるか?」「隊長!お皿はそれぞれの部屋の食器棚にあると思いますが。」 ジークは満足げに頷くと、さっさと部屋に入ってきた。「なんだ、肉とサラダだけでは寂しいだろう。これを持ってきてやったぞ」 差し出したのはケースに入ったパンプキンスープだった。さっさとスープ皿を2枚取り出すと、まだ充分にあたたかいスープを皿に移した。「なにをぼんやりしてる!早くもう一皿準備しろよ!うまいスープが冷めちまう!」 言うが早いか、ミシェルが準備していた料理を頬張った。「そんなぁ…」 膨れていても仕方がない。再びフライパンに肉を乗せると手早く自分の分を作り直した。「悪くないが、もう少し胡椒が効いている方がいいな。」「御代、頂きますよ」 ふてくされて言うミシェルにジークはなるほどと納得した。「いやぁ、悪かったな。そうだなぁ。俺の分の材料費は払ってやらねばな。よし、とりあえず今日の分を払っておこう。次回からはそのやり方でいこう」「え?」 あっという間に食事を平らげると、じゃあなと言って隊長は帰って行った。皿を洗いながら思う、今夜のことは全て計画されていたのだと。考えてみれば、この特殊部隊の宿舎での生活については何も教えられていない。他のメンバーの様子からはとまどったところを見かけないからジークが伝えておくとでも言ったのだろう。 洗い物を終えると、どさっとベッドに横になる。疲れと緊張で、あっという間に眠りに落ちた。
August 7, 2010
コメント(4)
-
貝の鳩 その5
「いやぁ、王室の食事はうまかったなぁ」 第3部隊に戻ったジークはご機嫌だった。堅苦しい軍服は早々に脱ぎ、肩につけられていた勲章はケースに戻した。「ミシェル。聞いてるか?」 薄い板を挟んで隣の部屋から声がしている。いつもの作業着に着替えたミシェルは軍服を片付けているところだった。「お前はなにも感じなかったか?」「何を、ですか?」「どうにも胡散臭い視線を送っているやつがいたのに、気付かなかったのかと聞いているのだ」 思わずため息が出る。ミシェルには分かっていた。しかしわざと気付かない振りをして別荘地を出た。パーティー会場の隣にある建物の最上階から、ずっと嫌な視線を感じていたのだ。「パーティー会場でおもしろいことを聞いた。ウイリアム王の実弟ラングレイ氏はどうやら玉座を狙っているらしい。まさかわが国にもそんな骨肉の争いがあるとはね。それともう一つ。おもしろいことに気が付いた。お前によく似た人物があのパーティーにいた。」「私に似た人物ですか?」 思わず聞き返した。「ああ、残念ながら見た目は似ても似つかない。麗しの王女だからな。しかし、顔かたちや雰囲気が似ている。これは役に立つかもしれんな」 最後の一言はミシェルには聞こえない。ジークは何かに没頭するように黙り込んだ。こうなれば何を尋ねても返事はない。ミシェルは自分の任務に戻った。 それから半年が過ぎた頃、ジークは多くの内乱を治めた功績が認められ、特殊部隊への配属が決まった。「お呼びでしょうか?」「引越しだ!さっさと荷物をまとめて10時に特殊部隊宿舎前に集合!それまでにお前の今までの任務を第4部隊のトムにきっちりと引き継いでおくように。」「あの、私も引っ越すんでしょうか?」「命令に従え!駆け足!」 部屋にやってきたミシェルに、いきなり言いつける。ミシェルには質問の余地がなかった。仕方なく、住み慣れた納戸の荷物を集めると、自宅から持ってきた大きなカバンに詰めた。 そのまま急いで第4部隊の宿舎へと走ると、トムの部屋を訪ねた。トムはまだ状況がわかっていない様子だったが、もう時間がない。とりあえず、ミシェルがしてきた掃除の手順を伝える。違和感を感じることは事細かに指揮官に報告することも言い忘れなかった。 ワケがわからないまま、説明を受けているトムの部屋に、仲間が声を掛けてきた。「トム、指揮官がお呼びだ!」「はい!」「そこの小さい奴も一緒に来いだとさ」 ミシェルは不審に思いながらもトムに続いて指揮官の下に向かった。「ミシェル、よく来たな」「あ!ラミネスさん!」「ジークはもう準備を進めているのか? 寂しくなるなぁ。たまにはここに顔を出せと伝えてくれよ。」「ラミネスさんはご存知だったのですか?」 事情を知らないトムの前を言葉が飛び交うばかりだ。「ああ、すぐにジークから連絡が来たよ。お前も行くんだろ?」「でも、どうして私まで付いていくんですか?昇格したのは指揮官であって、私には関係ないはずなのに」 ラミネスはにんまりと笑いながら、そんなミシェルを見た。「とりあえず、付き合ってやれよ。いいコンビだと思うぜ。」「ミシェル。ジークさんは乱暴そうに見えるけど、いい人だよ。僕も何度か助けてもらってる。君を連れて行くってことは、きっとこの先に君が活躍できる場所があるってことさ。」 それまで二人のやり取りを聞いていたトムが口を開いた。「まあ、そういうことだ。がんばれよ。」「ありがとうございます!では、失礼します!」 迷っていた心がすっと開けたような気分だった。任期はあと1年と8ヶ月のはず。そんな短期間でどれだけ活躍できるのかわからないが、父に鍛えてもらった拳法の腕があれば、何とか凌げるかもしれない。ミシェルは覚悟を決めた。特殊部隊はこの度新設された部隊で、内乱や自然災害、近衛兵でまかなえない王室関連の事件にも出動する。メンバーは職業軍人ばかりで宿舎に家族と共に移り住むということになっている。さすがに宿舎は先の第3部隊とは比べ物にならないほどきっちりとした建物だ。それぞれの部屋はマンションのように独立し、建物の外を歩いただけでは、そこが特殊部隊の宿舎とは到底思えないほどおしゃれなつくりになっている。ただ一つ違うのは、緊急出動時の赤色燈とスピーカーが各部屋に設置されているということだ。隊長を命ぜられたジークに与えられた部屋は最上階、ゆったりと広い2LDK。一人暮らしには広すぎるほどだ。その隣に併設されたワンルームがミシェルの部屋になる。ワンルームにバストイレ、キッチンがついているだけ。それでもミシェルには最高の居心地だ。転居してきたメンバーはさっそくミーティングを開く。特殊部隊に配属されるだけあって、みんな個性的な顔ぶれだ。いかにも腕っ節の強そうなディック、クールでスレンダーなスキャットマン、熱血漢のジョージ、メカに強いフィルはぱっと見医学生に見える、優等生タイプのチャーリーは絵に書いたように軍服をパリっと着こなしている。「新設された特殊部隊のメンバーは見ての通りだ。俺はジーク。この部隊の隊長だ。これからはここが我々の基地ということになる。フィル、司令室の状態はどうだ?」 フィルは銀縁のめがねを少しずらして親指を立てた。「よし。外観はどこかの社宅を装っているので、普通に暮らしてもらって構わない。だが、一旦戦闘態勢に入ったら、いつ帰ってくることができるかわからない。それと、なにかの手違いで情報が漏洩することも念頭において、地下に避難通路が設置されている。覚えておいてくれ。」「地下通路の途中にあるトレーニングルームは自由に使っていいのか?」 スキャットマンはすでに通路を確認済みのようだ。「ああ、自由に使ってくれ」 ディックとジョージがにやりと笑った。
August 6, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その4
「お前ら、いい加減にしないか?」 ジークだ。こんなところにのこのこやって来るなんて!ミシェルは唇をかんだ。「あれ?あのチビは一緒じゃないのか?それとも血まみれで動けないのか?」「悪いが、俺には男をはべらせて連れ歩く趣味はないんでね。今頃トイレ掃除でもしているんじゃないか?」 ざっと今にも踏み出しそうな足音がした。「もういいジェラール!ここに指揮官を連れて来ただけで充分だ」「どういうことだ、グレゴワール。割れたガラスの入った雑巾では掃除が出来ないだろう」 相変わらず落ち着き払った声だが、ミシェルは思わず首をかしげた。窓拭きをしていた雑巾にはなにも異常はなかったのだ。「チビはどうした。お前のかわいいペットなんだろ?」「なんだ、ヤキモチか。下らんな。奴はあれでも軍の役に立っている。流行り病が第3部隊に流行しなかったのは奴の功績だ。体力がなくても役立つことはできる。お前も指揮官を目指しているなら、そういうことに気付くべきだな。」「くっそ!そんなことを言っていられるのも今日までだ!」 グレゴワールの怒声で、一気にしんと静まり返った。建物の影からそっとのぞくと、グレゴワールの拳銃が見える。なんとかしなければ!ミシェルは足元にあった小石を拾うとすぐさまグレゴワールの手元をめがけて投げた。金属に当たった小気味いい音が響く。手元が狂ったグレゴワールは青い馬に風穴を開けた。「誰だ!」 駆け寄ってくるマッド・ジェラに足払いをかける。すぐさま起き上がったジェラはその小さな影を睨みつけた。背後ではジークがグレゴワールの拳銃を奪い取って組み臥していた。「どうする?まだやるのか?」「このチビが!ふざけやがって!」 くまのように両手を振りかざして襲い掛かるジェラをかわして後ろに回ると、後頭部に一撃を与え、太い腕をねじ上げた。「なんだ。もう終ったのか?」 宿舎からやってきたラミネスはたいして急ぐ様子もなく歩み寄ってきた。「遅いぞ」 ジークの言う事など気にする様子もない。楽しげに笑いながらミシェルの頭をなでた。「まあいいじゃないか。面白いものを見せてもらったよ。しっかしコイツにこんな力量があったとはね。いい相棒になりそうだな」「ふん」 ジークは否定も肯定もしなかった。グレゴワールとジェラはラミネスが連れて来た第1部隊に捕獲され、連行されていった。 それを見送るミシェルの後ろでラミネスが悲鳴を上げた。「なんてこった! この前新調したばっかりの国旗が!ちくしょー!もっと早く来てとめるべきだったー!」 下ろされた青い馬は頭の上に穴が開いてたんこぶを作っているようだった。 年が明けてすぐ、王室では新年を祝うパーティーが開かれ、毎年活躍した兵士たちが招かれる。今回はジークもその一人として招待を受けた。ジークは軍服に身を包み、髪を整えてミシェルを呼び立てた。「用意は出来たか?」「は?指揮官。、私は招待されておりません」「ばか者!王室に招かれるときに武器など持っていけないだろう。ギリギリまで護衛をするのがお前の務めだ」 ムッとしながらも急いで軍服に着替えると、ジークと共に迎えの馬車に乗り込んだ。馬車は思いのほか快適で、木漏れ日のもれる森を眺めていると思わず笑顔になる。「お前が招待されているわけではないぞ。気を引き締めろ」 指揮官の檄が飛ぶ。同乗していたほかの部隊の男達の失笑にへそを曲げそうになる。 パーティーの会場は王室の持つ別荘地で行われた。広い庭は芝生で覆われ、美しい小川や鮮やかな緑がすばらしい。王室に招かれた兵士たちは別室に呼ばれて王室からの勲章が授与される。ミシェルや他の護衛たちは、庭の外を警備するよう命じられた。「軍人たちはそろったのか? ウイリアム王が見える頃だ。危険のない様に警備を怠るな」 ウイリアム王の実弟ラングレイは神経質に警備の近衛兵に命じる。「はっ! 本日は表彰される軍人の警備を担当する兵もおりますので、警備は一層厳重かと」「よし、抜かりないようにな」「はっ!」近衛兵を退室させ、ラングレイは庭園の周りを双眼鏡で偵察していた。「ん?あれは? まさか、王女?」 ラングレイはすぐさま先ほどの近衛兵を呼びつけたが、意外な返事が返ってきた。「あれは、本日の表彰軍人の警備兵です。確か、陸軍の小隊でジークという者に伴われてきておりますが」「陸軍か、なるほど。それで、ジークという者の功績は?」 近衛兵が慌ててメモを取り出し、読み上げる。その間もラングレイの視線はミシェルに注がれていた。
August 5, 2010
コメント(1)
-
貝の鳩 その3
「随分とお気楽な仕事じゃねぇか。まったくジークの野郎、どういうつもりだ!」 磨かれたばかりの床につばを吐いて、マッド・ジェラは立ち去ろうとした。「部屋に戻るのはそのつばを拭いてからにしてもらおうか」「なんだと?」 静かだが一歩も引かない物言いに、大男が足を止めた。にらみ合う二人を見つけ、他の連中も寄ってきた。いい娯楽になるというわけだ。「いい加減にしとけよ、ジェラ。こんなやつに怪我させたらお前が掃除係をさせられるんじゃないか?」「うるせー! コイツだけは、どうにも気に入らないんだ。ここらへんで、口答えできないようにしっかりとつぶしておかないとな。」 言うが早いか、ジェラはミシェルの後ろに回りこんだ。すぐさまその細い腕をねじ上げようとしたが、ジェラの腕は空を切る。それと同時に強烈な足払いに巨体が派手な音を立てて床にたたきつけられた。 周りがその状況を理解する前に大きな足は細い腕にしっかりと動きを止められ、想像を絶するような力にひきづられ、不意に放された。 ミシェルは身なりを整えると、なんでもなかったような顔で言う。「拭き掃除ご苦労。じゃ、俺は掃除の続きがあるんで、失礼するよ。」「なにっ!」 慌てて起き上がったジェラの背中には、さきほど自分が吐き出したつばがしっかりとふき取られていた。 ギャラリーは大喜びで事の顛末を見ていたが、突然水を打ったように静まった。「騒ぎを起こしたのはお前か!?」 指揮官補佐のグレゴワールだ。ジークとは対照的な冷徹漢だ。すぐさまジェラの首根っこをわしづかみにすると自分の部屋へと引きずっていった。 ミシェルは動く事ができなかった。通りすがりに放たれた一言が心を揺さぶったのだ。「ジークの番犬め!」 グレゴワールの部屋の扉が閉まると、嫌な汗がつーっと背中を流れた。そっとポケットに手を突っ込んでみる。先ほどの紙切れがカサリと指に触れた。誰が、何の為に、いったい何をするというのだろう。嫌な予感がして、ミシェルは早々に掃除を引き上げた。 こういう場所では勢力争いがあるのが当たり前。それを今さら驚いたりはしない。だけど、どうにも胸騒ぎがする。悶々と考え込んでいると、薄い壁越しに不意に声がかかった。「掃除はどうした?」 ジークだった。一瞬言葉につまる。でも、伝えておいた方がいいかもしれない。ミシェルは立ち上がり、ジークの部屋の扉をノックした。 拾った紙切れを差し出し、今日の出来事を淡々と説明する。指揮官はそれを受け取ってじっとその話に耳を傾けていた。「青い馬か…」 つぶやいて向けた視線の先に、窓の向こうの長いポールがあった。今はただ銀色の棒のように見えるそれは、式典のときだけ旗が掲げられ、一身に注目を浴びるのだ。 青い馬、それはこの国の国旗に描かれた馬の事ではないのか。ミシェルの思考を読んだのか、ジークが深く頷いた。 つかみどころのない不安がこみ上げてくる。ふと見上げると、何か白いものが見えた。この荒々しい指揮官には不似合いなもの。貝がらを削って形作った鳩のペンダントだ。軍隊の指揮官が平和の象徴である鳩のペンダントとは。ミシェルはそのペンダントに関わる物語を想像して、少し気持ちが楽になるのを覚えた。 その日の夜中、ミシェルは妙な気配に目を覚ました。明らかに忍び込んでいるような足音が、隣の部屋から聞こえるのだ。「何の用だ!」 指揮官が分かりきったように言い放っている。足音はぴたっと止まり、小さなため息とともに誰かの声がする。「少し、相談に乗ってもらいたい」「こんな夜中に、か?」 聞き覚えのない声だ。ミシェルは思わず耳をそばだてた。「すまない。他の連中に見つかると、統率力がないなどと言われかねんからな。俺の部隊でどうにもおかしな動きをしている奴がいるんだが、どうやってしっぽをつかもうかと思って…うっ!」「夜中にこっそり忍び込んでか? その手の中にあるものは毒薬か?それともビタミン剤か?」「び、ビタミン剤だよ。手ぶらで相談もないだろう」「じゃあ、自分で飲んでもらおう。気持ちは有難いが疲れているのはお前の方だろ?」「勘弁してくれよ…」 ミシェルはそこまで聞くと、寝返りを打って眠った。寝入りばな、転げ落ちるように逃げ出す足音が聞こえていた。 翌朝、ミシェルは窓拭きをしていて自分の目を疑った。青い馬が風を浴びて翻っているではないか。おかしい。今日は式典の予定などないはずだ。 気が付いたときには、雑巾を握り締めたまま、ジークの部屋をノックしていた。しかし、何度ノックしても、中からの応答はなかった。司令室で第3部隊のスケジュールなどを調べてみたが、屋内トレーニング中の部隊の中にもその姿は見当たらない。 途方にくれたミシェルは宿舎の裏を回って、そっと青い馬の旗の元に近づいた。ポールは道具入れの建物のすぐ前に立っている。風をはらんだ旗が揺らめいて引き上げ用のロープがポールとぶつかり、カランカランと乾いた音をたてている。建物の後ろから、そっと様子を伺っていると、数人の気配が近づいてきた。「奴はまだか」「もうすぐです。ちょいと仕掛けをしてありますんで、すぐに引っかかってくるでしょう」「ふん」 ミシェルには聞き覚えがあった。しかもとても身近にだ。心臓がバクバク音を立て、彼等に聞こえてしまいそうな気分になる。
August 3, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その2
想像はしていたが、あまりの汚さに嗚咽すら覚える。自分に振り当てられた部屋はこともあろうに指揮官の部屋の隣にある薄汚い小部屋だった。 母に作ってもらったサンドウィッチを慌てて食べ、指示された宿舎の前に駆け出した。運の悪いことにさきほどからかってきた男もどうやら第3部隊のようだ。ミシェルは自分の運の悪さを呪った。 部隊での生活の説明を受けた後、一人ずつ名前を呼ばれ、配属される課を振り分けられた。「ミシェル、お前はこの部隊の掃除係だ。宿舎内の全ての部屋の掃除をするように!お前達は貴重品を金庫に入れて置くように。こいつに取られても、文句は受け付けないぞ!」「ひどい!どうしてオレが掃除係なんです!部屋だって他の連中みたいにちゃんとした場所を与えてもらっていないのに!」「うるさい!」 ミシェルの抵抗はあっさり却下された。他の連中は楽しげに笑っている。「そんなに言うなら、俺と勝負しろ。俺に勝ったなら、戦略指令部に入れるように進言してやる。」 ジークはチェスを持ち出し、にやりと笑った。「今からはレクレーションタイムだ。それぞれ隣にいるやつとチェスをするんだ。上がってきたやつがオレと勝負できる!わかったな!」 ミシェルは心の中で小躍りした。チェスなら幼い頃から父に鍛えられている。その辺の大人にはまけたことがなかった。 一通りの相手とやりあい勝ち残ったミシェルはジークの前に躍り出る。「ほう。お前が残ったのか」「約束です。コレに勝ったら掃除係は無しにしてください」 ジークは楽しげに頷くとさっさとコマを進めた。勝負がはじまってまもなく、ミシェルは大きな手ごたえを感じていた。 強い…。この男は父と同じぐらい強い! うろたえているうちに勝負はついてしまった。「コレで気が済んだだろう。じゃあ、さっそくやってもらおう。他のものは服を着替えてトレーニングだ。集合は3時。以上!」「3時だって?! あと5分しかないじゃないか!」 皆はバタバタと駆け足で宿舎に戻った。一人残ったミシェルをジークが呼びつける。連れて行かれたのは先ほどの小部屋だ。ジークはそのドアを開いて、キッパリと言う。「お前の場所はここだ。元々は納戸だが、とりあえず電器があるからいいだろう。ここにある荷物は…」「これは何ですか?」「これは掃除道具のはずだが?」 ミシェルは意を決して言い放った。「上官!こんなもので掃除をしたらばい菌をばら撒いているようなもの!疫病を流行らさないためにも、掃除道具は新調してください!それと、掃除係を言い渡された以上、銜えたばこはご遠慮願いたいです!」 ジークは思わずミシェルの表情を確かめた。そして、堰を切ったように笑い出した。「あははは。そうか、なるほど。いいだろう。お前の希望は聞いてやろう。その代わり宿舎全体の掃除は手を抜くんじゃないぞ!」「はっ!」 ミシェルは覚えたばかりの敬礼をして、風化しつつある掃除道具をゴミ袋に詰め始めた。 数日が過ぎた。訓練の時間に合わせて掃除をするので、他の隊員たちにからかわれることもない。ただ黙々と掃除をするのみだ。訓練に参加できないのは少し肩透かしな気分だったが、女であることを隠している以上、接触は少ない方がいいに決まっている。 初めのうちこそ遠慮気味だった隊員たちの部屋の掃除にもなれ、手順もすっかり出来上がってきた。ミシェルは黙々と掃除を続けた。その頃、他の部隊では困った問題が起きていた。胃腸の病気が蔓延し始めていたのだ。 軍の上層部からは手洗いの徹底を促していたが、広がりを止めることはできなかった。しかし、第3部隊だけは無事だった。その部隊だけどうして感染しなかったのか。上層部ではいろんな説がでていたが、ジークはにんまりと笑いながら困惑する上司たちに言い放つ。「指導力の差、じゃないんですか? つまり、第3部隊は病気に負けるほどたるんではいないんですよ」 これには他の部隊の指揮官たちもむっとした。しかし、事実を変えることはできない。そしてその直後に起こった内乱をあっさりと鎮めた第3部隊は一躍英雄として注目を浴びた。 元々きれい好きだった母にしっかりと仕込まれていたミシェルは、部隊の連中の不潔な服装、タオルなども納得がいかない。次々に新しいことを提案し、宿舎内はすっかりきれいになっていった。文句を言う隊員もいたが、ジークの言葉は絶対だった。そのうちに部隊の連中もその状態に慣れ、しまいには清潔な環境を当たり前と感じるようになっていた。 ある日、ミシェルはどうにも気になるメモを拾った。廊下の片隅に落ちていたその紙切れには『3日後、青い馬の元にて決行』とある。 決行と記してある以上、なにかの計画が実行されようとしていることに他ならない。三日後といわれても、このメモが書かれたのがいつか分からない以上、日にちは特定できなかった。 ミシェルは床を磨きながら頭の中でそのメモのことに集中していた。「何をやっているんだ!邪魔だろう!」「すみません」 うっかりモップの先を誰かの足にぶつけたらしい。慌てて顔を上げると、入隊の日にからんできたあの男が睨んでいた。この男、ジェラール・ブロシェという。マッド・ジェラというニックネームをつけられるほど粗暴な男だ。 あの入隊の日の失態は単に油断していたからだと、周りには言いふらしていた。
August 2, 2010
コメント(2)
-
貝の鳩 その1
貝の鳩 「それでは、行ってきます」 ミシェルは駅に向かって歩き出した。歩き慣れた道を突き進む。振り向くと車椅子に乗った父とそれに寄り添う母が手を振って見送っているのを目の当たりにするだろう。しかし、ミシェルは振り返らなかった。 ミシェルの父は新種の野菜を開発する研究員で、国からは多額の研究費用が出されている。しかしその研究成果が出る前に病に倒れてしまったのだ。成果の出なかった研究費用は何らかの形でその一部を返還しなければならない。大方は現金で返納するか徴兵に出るかだ。研究費用を使い果たしていた父は一人娘のミシェルに代役を依頼した。女性なら期間は長くなるが楽な仕事が回されると考えたのだ。 駅に着くと、さっそく電車が来た。急いで飛び乗って開いた席に座る。窓を見やると、懐かしい我が家が丘の上にかすかに見えたところだった。 風になびく長い髪を、そっと後ろで束ねると、ミシェルはある決意を新たにした。 都に行ったらどんなことが待っているだろう。 ミシェルは大きなバッグを胸に抱いて考える。人をあやめなければならないこともあるのだろうかと。 ミシェルに不安はなかった。父は研究員でありながら武道にも長け、一人っ子のミシェルには幼いうちから多くのことを教え込んだ。暴漢の一人、二人ぐらいなら、素手で戦えるほどの腕前だ。 激しい稽古に耐えてこられたのには理由があった。稽古の後、水浴びをして出てくると、父は決まって、東洋のチェスを出してきて、相手をしてくれる。 これがことのほか楽しくて、勝てそうで勝てないもどかしさにミシェルは夢中になっていった。目的の都につくと、駅舎の裏にまわって長い髪をばっさりと切り落とした。もともと引き締まった口元が一層強調され、少年のように見える。袖口を無造作に巻くり上げ荷物を肩から引っさげると、さっそく管理センターに足を運ぶ。女性と男性では仕事内容が異なるので、受付の場所も分かれていた。女性の文字をちらりと目に留めながらも、ミシェルはきびすを返した。父に課せられた年数は3年。しかし、それを女性が代わるとなると5年を必要とする。自分の実力を試すため、そして、さっさと終らせて自宅に帰るため、男に成りすます事を選んだのだ。同じ方向にむかっている者はほとんどが一般人のようだが、中には腕に自信がありそうな男もまじっている。徴兵制度として以外にも、仕事としてやってくる連中も少なくないのだ。案の定、受付の前には長蛇の列が出来ている。その最後尾に並ぶと後ろからきた男にぶつかられて倒れそうになった。「よお、すまねえな。ちっこくて見えなかったんだ。許せ」「別に、いいけど」 ぶっきらぼうに答えてみたが男はあからさまに楽しんでいた。むっとする気持ちをぐっと堪えて受け流そうとするが、どうもそうはいかないらしい。いきなり荷物を顔面に投げつけてきた。「ぼうず、今日からお前はおれの家来にしてやるよ。ほら、荷物を持ってろ」「家来? 冗談じゃない」 言い終わる前に胸倉をつかまれる。「ぼうず、威勢だけはいいようだが、ここではそんなもんは通用しないんだよ。」 男はか細い体を面白そうに揺らしてにやりと笑うと、不意に開いた腕を振り上げた。 ドスっという鈍い音と共に、周りに人だかりが出来てしまった。野次馬は驚いた様子で事の成り行きを見つめ、役員たちはバタバタと駆け寄ってきた。「救急隊!こいつを担架で救護室まで運んでやれ!関係のない者は静粛に、列を乱すな!」 指揮官らしき男がてきぱきと指示を出す。その様子をぼんやりと見ていたミシェルは不意に目の前に突きつけられた指に驚く。「おまえ!事情聴取だ。こっちへこい!」「あ、はい」 せっかく半分ばかり前に進んだところだったが、これは避けられそうにない。ミシェルは指揮官の後に続いた。別室に入り始末書に名前を書かされ、事の次第を詳細に説明する。指揮官はほうっと言いながらミシェルの細い腕と、始末書を見比べると、叱る事もなくいとも簡単に釈放した。 まったく、今日はついていない。 ミシェルは諦めて列に従った。もう後ろに並ぶものもない。どこからか、おいしそうな匂いが漂ってくる。どうやら昼食の時間になっているようだ。きゅるると小さく腹の虫が泣いている。「次!書類を出して!」 やっと順番が回ってきた。書類を提出して指示を待っていると、後ろからさっきの指揮官がやってきた。「ラミネス! 飯にしようぜ!」「ああ、ジーク!こいつが最後だ。先に行っててくれ」 そこで初めて先ほどの騒ぎを起こした張本人だと気付いたジークは、ちらっとミシェルを一瞥して邪魔臭そうに言う。「ああ、コイツか。まだまだ体力がなさそうだし、オレの部隊の掃除係にでもしてやってくれ。」「だとさ」 ラミネスと呼ばれた役員は呆れたような、でも実は楽しんでいるような顔でミシェルに言った。「あいつはジーク。第3部隊の指揮官だ。軍の宿舎はこの地図を見ればわかる。午後からはそれぞれの上司との面談があるから、1時にはそれぞれの宿舎前に集合だ。急げ!」 言うが早いか、役員はさっさとその場を後にした。さっきの男が上司になるとわかると、どうにも気分が滅入る。しかし時計を見ると1時まで15分しかなかった。ミシェルは慌てて荷物を抱え、宿舎へと走った。
August 1, 2010
コメント(2)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-
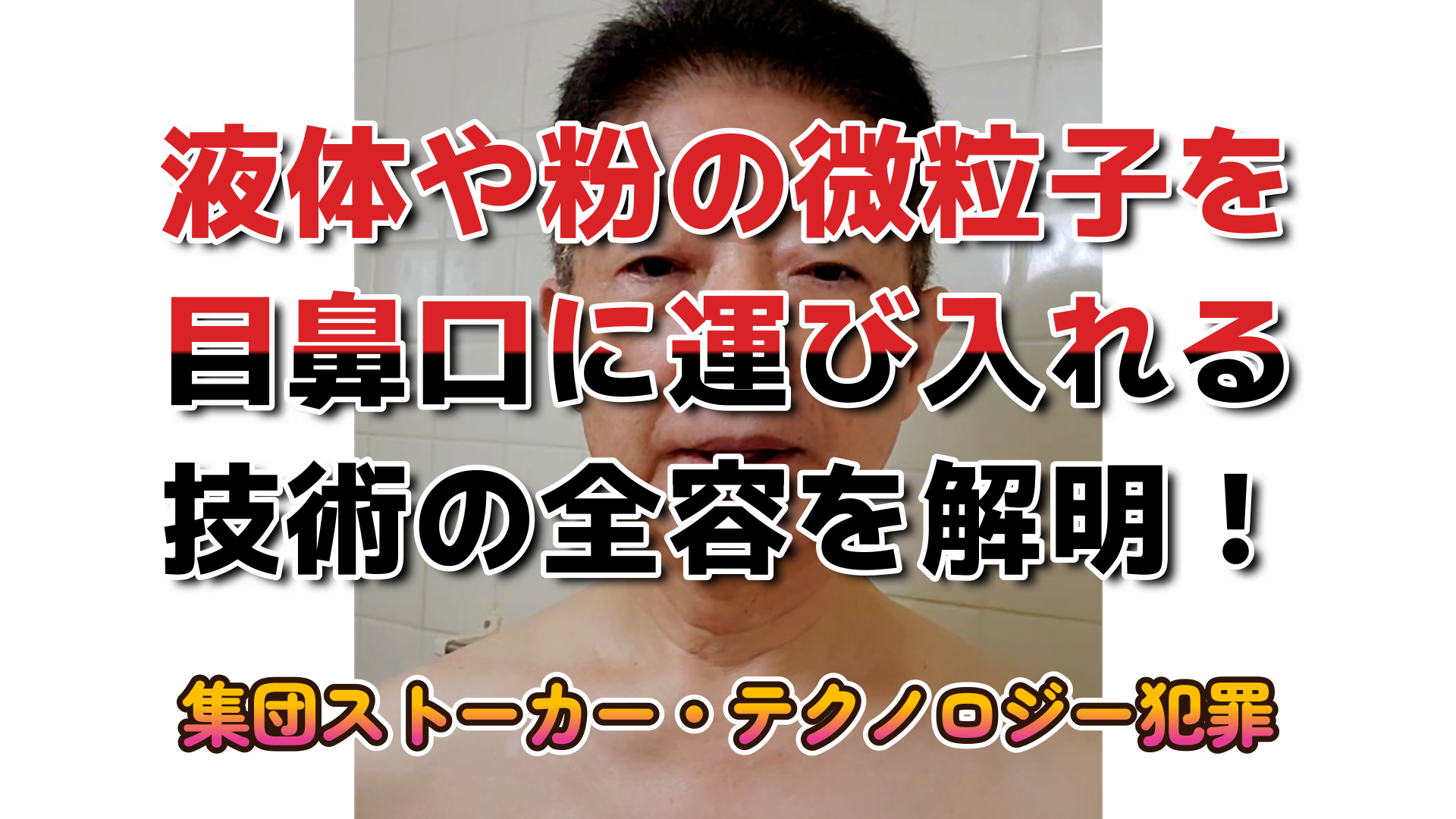
- 政治について
- 液滴や粉の微粒子を目鼻口に入れる技…
- (2024-11-23 21:26:45)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 2024 株主総会 ほぼ日株主ミーティン…
- (2024-11-24 00:28:06)
-
-
-

- 楽天市場
- #レトルトカレー 罪なきチキンカレー…
- (2024-11-24 02:00:18)
-







