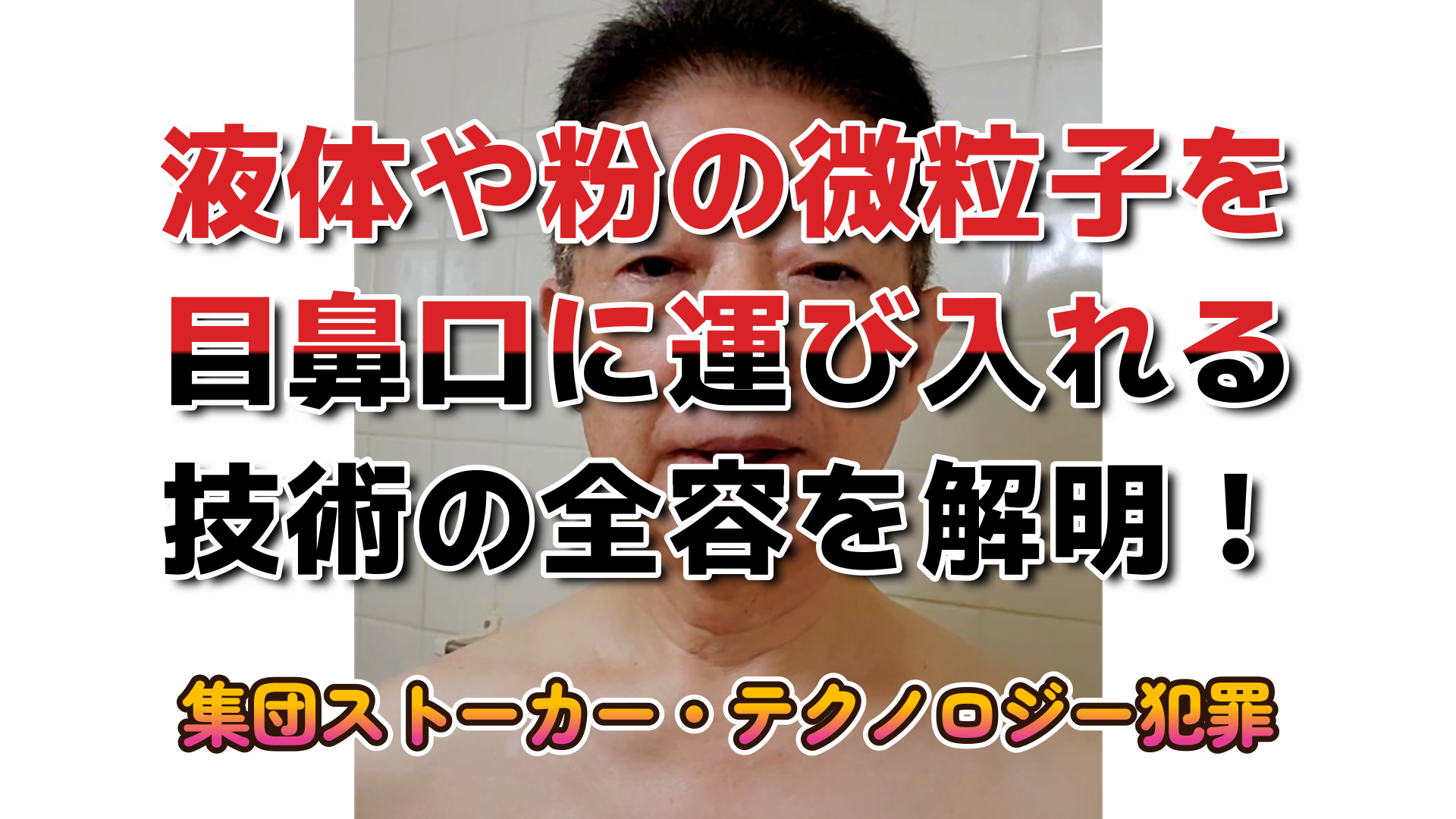全917件 (917件中 201-250件目)
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 >
-
あ、え? うそ!
みなさん、お気づきでしょうか。今日から12月なんですって。。。この仕事始めるまで、私は結構計画的に年末年始の家事をこなしていたのです。ええ、大掃除も、場所を決めて少しずつ、いつもより丁寧に。ところが、去年の年末は、慣れない仕事に追われ、もういいや!と疲れ果てていてとりあえずやっつけた感の大掃除でした。じゃあ、今年はがんばるんだろうと思われた方、いやいやいや、まだ私という人間を理解していないですね。ふっふん♪ (←いばるところじゃない)今年もたぶん、ぎりぎりにやっつけるぞー!的な大掃除になりそう。。一人暮らしを目指している娘たちに、練習だと言って、やってもらうっていう手もあるか…などと、悪だくみだけは浮かんできます。さてと、今日はお休み!という名目の、水面下でのあれやこれやをこなしてきます。今月前半に、大きなイベント複数件あるのです。お願い!コロナ、来ないでー!!
December 1, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 26
エピソード 26 地下のショットバーに男が入ってきた。静かに流れるジャズに満足げに頷くと、慣れた様子でカウンターに座る。「やぁ、久しぶりだね。藤森君。」「ミスターK、今日はご足労頂いて申し訳ないです。ちょっと調べてもらいたいことがあって…」 藤森がバーテンダーに目配せすると、すぐに別室が用意された。二人は席を移動して、向かい合う。「アメリカ国籍の企業のことなんです。スリーピングベアという寝具専門店をご存知でしょうか?」「ああ、よく知っているよ。各国に支店を広げているね。いや、待てよ。そういえば、何か最近聞いたような気がするな。」 瞼を閉じて少し考えた後、見開いた瞳はエメラルドのように輝いていた。「思い出したよ。そう、スリーピングベアは今、要注意企業だ。先月ちょっとした事件があってね。経営陣が総辞職して顔が挿げ変わったんだ。ところがどうも今度の経営陣の方がキナ臭い。寝ているくまを起こしてみたら、くまのプーじゃなくてグリズリーだったって訳さ」「前の経営陣が退陣したの理由は?」 藤森は、いきなり身振り手振り説明するこの金髪のイケオジにやや引いてしまった。「うむ。それなんだが、実は今、捜査中なんだ。日本支社でもなにか動きがあったのかな」「いや、はっきりと掴んだわけではないのですが、ちょっといろいろありましてね。また、動きがありましたら報告します。そちらの情報もいただけると助かります。」「了解だ。時に、本田君はどうしている?」 ちらっとイケオジの様子を伺いながら、ふっと思い出し笑いをして、脳科学者は水割りに口をつけた。「随分とお気に入りの様ですね。そういえば、しばらくお目にかかっていないですね」「いやぁ、いつ飲みに行っても言いがかりをつけてくるんだよ。負けん気が強いというか、なんというか。だけど、あのやり取りがまた楽しくてね。そうだ。今回の事を調べさせようか。少なくとも彼ならスリーピングベア・ジャパンの事なら嗅ぎつけそうだと思わないか?」「その辺りはミスターKにお任せします。先輩なら、警察関係にも友人がいるらしいので、うまく調べてもらえそうですしね。」 二人はそのまま杯を重ね、それぞれに帰っていった。 自宅まで戻った藤森は、美月に連絡を入れた。突然の体調不良案件で、うまくこなせているのか気になったのだ。「美月、仕事は大丈夫だったか?」「ええ、榊にいろいろと教えることになったけど、まあ、彼にとってもいい機会だっただろうね」「そういえば、食事はどうしてる?デリバリーもできなかっただろ?」「ああ、それなら大丈夫。新人の三田村さんにお願いして、届けてもらってるんだ。」 藤森は、美月のビルの前で心配そうに立ち尽くしていた志保を思い出していた。「そうか、あの人にまで迷惑かけてしまっているんだな。」「まあね。それがなかなか素朴でうまいんだよ。白和えとか、サバの味噌煮なんて、食べたことなかったしね。」「じゃあ、彼女と一緒に食べているのか?」「はぁ?どうして? 作ったものを持って来てもらってるだけだよ。材料費もこちら持ちだし、時間外労働として賃金も払ってる。それがどうかした?」「そうか…。」 心配そうに、寝そべっている美月を見守る姿が思い出されて、どうにもやるせない。「しかし、急に頼まれて、食事の支度をしてくれる女性なんて、なかなかいないぞ。秘書の仕事内容に社長の食事の支度は含まれないんだろ?報酬を支払えばいいという問題ではないんじゃないか」「ん、まぁ、感謝してるよ…。」「そうか。まあ、あと2日だ。がんばれよ」 電話を切ると、美月はしばらく考え込んでいた。あと2日。そうか、あと2日分しか、あの食事が届けられないのか。どこかに家庭料理の店はあっただろうか。そんなことを考えながら眠りについた。 2日後、秘書室にやってきた志保を待ち構えていた榊が、声を掛けてきた。「ねえ、三田村さん。もしよかったらなんですけど、今日の晩御飯は私の分も一緒に作ってもらえないでしょうか?この1週間、私たち良く頑張ったと思うんですよね。だから、打ち上げをしたいと思ったんです。1週間も毎日おいしそうな匂いばかりかがされて、よく耐えたと思うんですよね。あ、もちろん社長が嫌だっていうなら、私たちだけで打ち上げしましょうよ。私もワインか何かを買ってきますから。」「あの、榊さんって、奥さんがいらっしゃるのかと思っていたのですが…」「いえ、独身です。毎日コンビニ弁当ですよ。そう、家庭料理に飢えていますとも!」「そうだったんですね」 その時、秘書室に美月が現れた。「おはよう。なんの話?」「おはようございます。あの、榊さんが、この1週間の私たちの頑張りを労って、打ち上げをしようと提案してくださったのです。社長は、こちらでご一緒に晩御飯を召し上がるのはいかがですか?」「え?ここで?3人で?」 眉間にしわが入り、腰が引けている。志保はまずかったと後悔した。「あの、すみません。余計な事でした。社長の分は、ちゃんと一人分作ってお渡しします。」「そうですね。じゃあ、私たちはここでお疲れ様会をしましょうか」 榊の嬉しそうな顔に、胸がチクりと痛んだ。確かに二人には負担を掛けたが、社長の自分を抜きで二人だけで打ち上げとはどういう了見だ。美月は、自分でも何が嫌なのか分からないまま反対を唱えた。「社長!いくら社長でも、私たちが一緒に食事することに反対する権利はありませんよ。この1週間、おいしそうな匂いばかりかがされてきたんですから、最後ぐらい、私にも食べさせてほしいのです。三田村さんの了承はいただいています。」 いつになく真剣な顔で訴える榊に驚いた美月は、仕方なく秘書室でお疲れ様会をすることを許可した。「しかたがないなぁ。じゃあ、僕も参加するしかないだろう」 拗ねたように言う美月を見て、志保は恥ずかしそうに俯き、榊はにやりと口角をあげた。つづく
November 30, 2022
コメント(0)
-
やばい!
今日からの1週間、イベントが怒涛の如く並んでおりまして、キャー えらいこっちゃ!!なのですが、今朝の強風にあおられて、妙にワクワクしているおかしなしんたです。ええ、準備は着々と進めてきましたから、抜かりなし!といいたいところですが、だいたいそういう時って、「なんでやねーん!」なことが起きるので、油断大敵なのです。小説もぼちぼち続けておりますが、すぐに追いつかれちゃって、毎日の更新がままならない状態。ほんますみません。汗今回の小説、バブル期の日本が舞台なせいか、それとも毎日更新できていないからか、あ、そうか! おもしろくないからか!とにかく、閲覧数は伸びず。。。はぁ、またがんばって精進いたします。今年、クリスマスツリーもまだ出してない。。明日、父の誕生日なのに、プレゼントも用意できてない。。とりあえず、この1週間を乗り越えたら、フォローに走ろう!
November 29, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 25
エピソード 25「社長、お昼ごはんはどうなさいますか?こちらにデリバリーするのは危険な気がするので、何か買ってきましょうか?」「そうだな。三田村さんはどうするの?」「私は、お弁当を持ってきました。」 ぽかんとした美月には、お弁当を持ってくると言う発想がなかった。「それ、僕に譲ってもらえない? その代り、好きなランチを食べてきていいよ。僕がごちそうする」「え? 私のお弁当なんて、社長のお口に合うかどうか…」 戸惑う新人秘書に、社長は両手を合わせて頼み込む。「お願い!これから一週間外食出来ないんだよ。ステーキでもなんでも食べてきてくれていいから、ね!」 志保はしぶしぶ自分の弁当箱を差し出した。女性らしい小さな箱に、美月は驚いていた。「さすがに女性のお弁当だけでは足りないか。食後でいいから、大きめのサラダを買ってきてくれないかな」「分かりました。では、出かけてきます。」 新人秘書が出ていくのを見送りながら、ふと今まで気づいていなかったことに思い至った。「そうか、これじゃあ晩御飯もデリバリーできないな。」 志保はコンビニの前で途方に暮れていた。あふれんばかりの会社員がコンビニの外にまで並んでいたのだ。「あら、新しい秘書さんですよね。どうされました?」「あ、受付の…」「はい、受付嬢の七瀬です。この前はありがとうございました。例の吉川さんの件」「あ~、困りますよねぇ。」 そのまま一緒にコンビニに入ると、慣れた様子の七瀬と共にコンビニ弁当とサラダを購入した。「私、ずっとお弁当だったので、こんなに混雑しているなんてしりませんでした。」「そうなんですか? 近くのレストランも混んでいるので、私はコンビニ派なんですよ。じゃあ。」 社屋内に到着すると、それぞれの持ち場へと別れていく。志保は、仲良くなれそうな人が一人増えて、ご機嫌で秘書室に戻ってきた。「ただいま戻りました。社長、こちらのサラダでよろしかったですか?」「ああ、ありがとう。あれ、外で食べて来たんじゃないの?」「はい、どちらもいっぱいで…。」 外食に気後れしたと言うのは、なんとなく躊躇われた。自分の席で食事を終えて、片付けていると、美月が給湯室にやってきた。「ごちそうさま。おいしかったよ。家庭的な味は久しぶりで、なんだか泣きそうになっちゃったよ」「お口に合いませんでしたか?」「ああ、そうじゃなくて。うちは、両親とも忙しい人たちで、子どものころから親子でそろって食事することなんてほとんどなかったんだ。母も家事をしない人だったしね。だから、家庭料理には縁がなかったんだよね。おいしかったよ。ありがとう」「あ、あの…。私の料理でよろしければ、作ってきます。この1週間、社長はここにいないことになっているんですよね。デリバリーもできないのなら…。もちろん、どなたか作ってくださる方がいらっしゃるなら、いいのですが」 きょとんとした顔の美月を見て、しまった、っと後悔する志保だったが、次の瞬間には両肩をガシっと掴まれていた。「それ、ナイスアイデア! だけど、三田村さんの負担が増えてしまうけど、いいのかな?」「大丈夫です。一人分も二人分も手間は同じですから」「そうか、じゃあ、お願いするよ。好き嫌いはないし、食べられない物もない。食材を買ったら、レシートは全部こちらに回してくれる?」早速、食事の手配を頼むことにした。これで食事の心配も無くなった上に、高級レストランにはない、ほっこりとした料理が食べられる。美月は上機嫌だった。 その日、美月が体調を崩した話は、瞬く間に広がり、事務所内にはお見舞いの電話が続いていた。受付にも、お見舞いの品なども届き、美月の人気の高さを物語っていた。 5時の退社時間を過ぎた頃、志保は一旦会社を出て、いつものようにスーパーに寄り道した。「メニューはいつも君が食べている物でいい。いや、そっちの方がいい!」 妙に力説する社長を思い出して、ふと笑みがこぼれた。あの会社に入社して、あっという間の出来事だったが、今まで持っていたイメージをことごとく覆されている。 料理をタッパーに詰めながら、ふと、美月の食事の量を確認しなかったことに気が付いた。「仕方ないわ。少し多い目に入れておこう。」 カバンに出来立ての料理を詰めて、志保は再び会社へと向かった。秘書室前まで来ると、エレベータを乗り換える。そこで、秘書室にまだ明かりがついていることに気が付いた志保は、中を確かめることにした。「あの、どなたかいらっしゃるのですか?」 そろりと覗くと、美月と榊が打ち合わせしているところだった。「ああ、悪いね。助かるよ」「え? 社長、どういうことですか?」 明らかに戸惑う様子の榊に、にやりと笑って志保のカバンを指さした。「僕の晩御飯だよ。外食もできないし、三田村さんにお願いしたんだ。今日のメニューは何?」「えっと、豚肉の生姜焼きとほうれん草の白和え、それに具沢山のお味噌汁です」「うわ、うまそう。それ、社長の分だけにしては多くない?」 榊の目が爛爛と輝いている。「社長がどのぐらい召し上がるか分からなかったので、少し多い目にお持ちしました」 そういいながら、カバンの中身を少し開いて見せると、香ばしい生姜焼きの匂いがふわっと広がった。榊は思わず生唾を飲み下す。「うん、いい匂いだ。大丈夫、全部食べるよ。さて、榊。さっさと終わらせよう。三田村さん、そこに置いててくれる。ありがとう。帰り、気を付けてね。」「はい。では、失礼します」 志保はカバンごとソファの横のテーブルに置くと、そっと秘書室を出た。エレベータを出て家路につく中、なんとなく物足りなさを感じていた。何を期待していたんだろう。社長が食べているところをじっと見ているわけにもいかないのに。自分の中の妙な期待が外れて、不思議な感覚に陥っていた。つづく
November 28, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 24
エピソード 24「奥平先生。あの…。ちょっとお伺いしたいことが。」「中野さん、どうかしたのか?」 声を掛けてきたのに、なぜか言いよどむ中野は、美月の手術の時、麻酔医として参加した一人だ。今日は、美月の手術に関わった麻酔医二人が勤務する病院に顔を出していた。もちろん、偽情報を流すためだ。先日の美月拉致事件には触れずに、相手の意向を促すと、じっくり考えた末に、吐露した。「少し前になるのですが、小山さんが、どこかの会社幹部に仕事中呼び出されていて、私が飲み物を買いに廊下に出たとき、ちらっとデータをインプットできるという言葉が聞こえてきて。その、もしかして、あの手術のことをばらしてしまったんじゃないかと心配になっています。」 目が泳いでいる。指先をせわしなく重ねたりさすったりするのは、まるで嘘をついていますと言わんばかりだ。「ああ、あの手術、どうやら上手くできてなかったらしい。ちょっと前から美月が調子を崩していてね。データのやり取りは出来ないみたいなんだ。やっぱり難しい手術だったから、ミスが出たのかもしれないな。まあ、大丈夫だ。普通に生活は出来ているし、意識もはっきりしていた。もうしばらく様子を見る予定だけど、まあ、仕方ねぇーな」「え…、失敗だったのですか?」「ん、どうやらそうらしい。なかなか難しいな」 ざっくりと束ねた頭をガシガシと搔きむしって笑って見せると、麻酔医はほっとしたような顔になって、退室していった。奥平は大きく息を吐いて、気持ちを切り替える。もう一人にも同じ情報を流さなくてはならないのだ。 休憩室でくつろいでいた小山を見つけると、奥平は声を掛ける。「小山君、久しぶりだね。コーヒーでもどう?」「奥平先生!お久しぶりです。」 人懐っこい笑顔が帰ってくる。場所を移して二人が座ったのは、病院内にあるコンビニのイートインだ。ここは中野の部署からも見える。楽し気にコーヒーを飲みながら他愛ない話で盛り上がっていたが、外科医がぼそりと例の手術が失敗だったらしいと告げると、目を見開いて絶句した。「で、あの、美月さんの様子はいかがなんですか? なにか麻酔でまずいことがあったのでしょうか?」「ああ、ちょっと具合悪くしていて、様子見なんだが、どうやらデータのインプットやアウトプットが出来ないみたいでな。せっかく力を貸してくれたのに、悪かったな」「そうでしたか。美月さんといえば、有名な起業家だし何かあったら大変ですよね。」「まぁ、そうだなぁ。倒れたときは驚いたが、まあ、今は普通に生活できそうだし、あいつも手術され損ってところかな。さてと、ちょっと院長に呼ばれてるんだ。じゃあな」 奥平は振り向かない。そのまますたすたとその場を離れた。小山は手元に残った冷めたコーヒーを一気に飲み干して、はっとした。「院長、今週は出張のはずだ…。じゃあなぜ?」 小山の背中を冷たい汗が流れた。この若い麻酔医には気がかりなことがあった。あの手術の時、もしかしたら薬を間違えたかもしれないと、どこかで不安に思っていたのだ。あるはずのない薬品の空ケースを術後に見つけたのだ。もしかして、あれが原因ではなかったのか。それで、奥平が自分の様子を確認するためにきたんではないか? 小山は大きく深呼吸した。美月が普通に生活できているだけでも、喜ぶべきか。何かおかしなことがあれば、あの有能な奥平の事だ。すぐに原因を突き止めてくれるだろう。そこで、自分にミスがあったなら、その時は正々堂々と謝罪しよう。 大きく息をついて、小山は仕事に戻っていった。***** 美月が体調を崩したことになった初日。念のため、大き目のパーカーのフードをかぶってカジュアルな服装の男が秘書室を訪ねた。「社長、おはようございます。」「ああ、おはよう。今日のスケジュール表、出してくれる?」 志保が書類を持ってくると、榊が資料を持って集まってきた。今日から美月に変わってクライアントに指導を行うことになっている。今回は、急な体調不良ということで、休めそうなところは休みを取っている。それでも、至急の案件や、事態が急変しそうな案件は放置できない。美月が細々と説明を入れながら、榊を指導する。「今の説明で分からないことは?」「何とかなりそうですね。もし、どうしてもこちらで判断できない場合は、後日のお返事ということでよいでしょうか?」「そうだね。僕の体調が少し落ち着いたときに聞いてきたということにして、回答を伝えればいいよ」「分かりました。では、そろそろ出かけてきます。」 書類をそろえると、口元を引き締めた榊が出かけて行った。「社長。吉川さんとおっしゃる方が、度々お越しですが…」「ああ、スナックのママだろ? 何年か前に麻薬取締法違反で捕まったはずなのに、もう出てきたの?関わらない方がいい。」「分かりました。」 一通りの指示が終わると、美月は社長室に向かう。いつもはブラインドを開けると明るい陽射しが入る室内も、今日は暗いままだ。電器をつけようとして、一瞬考える。この部屋は外から丸見えになる。そのままそっと部屋を出ると、ソファに腰かけて考え込んだ。 昨夜も一通り海外のニュースをチェックしてみたが、スリーピンベア本社で何かが起こっているという情報はない。一体何があの会長をあそこまで追い込んだんだ。 ふいに、気配を感じて顔をあげると、志保がお茶を運んできていた。「社長。余計なことかもしれませんが、少し、休憩を挟まれてはいかがですか?」「ああ」 ふと時計を見ると、ソファに座ってからすでに2時間が経過していた。「もうこんな時間か…。」つづく
November 26, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 23
エピソード 23 コーヒーを飲み終えると、藤森が美月の肩を抱えるようにして、車に乗り込み美月の事務所に向かった。そう、ここから演技は始まっているのだ。「敵を欺くにはまず味方から、ってやつ?」「ああ、そういうことだ。美月、座席を倒しておけ。どこでだれが見ているか分からないからな」「了解」 ぼんやりと車の天井をみつめてため息をつく。「なんだ、そんなにスリーピングベアのことがショックだったのか」「え、ああ、それもあるけど、他にもね…」 信号待ちで車が止まった。ちらっと美月の様子を確かめて、藤森が言う。「私は、美月みたいに女性慣れしていなかったが、傍にいて落ち着く女性に勝るものはないと思ったよ。」「それが、例の彼女?」「ああ。彼女は、特別美人というわけでも、何かの才能があるというわけでもない。だけど、私を気遣い、癒そうとしてくれる。そこに見返りを求めるところがないんだ。」 信号が変わり、車を発進させながら、藤森の表情は優し気だった。確かに、今まで自分に近づいてくる女性たちは、何かしらの見返りや見栄えなんかを求めていた。上辺だけの関係だ。だからこそ、余計に隙のない鎧を着て、日々を過ごしていた。「ん? 美月のビルの前に女性が立っているけど、知り合いか?」 そろっと頭をあげて確かめると、志保が心配そうに立ち尽くしているのが見えた。「ああ、新しく入った秘書だ。彼女には本当のことを話しておくつもりだ。」「じゃあ、車に乗ってもらって、地下の駐車場まで行こう。美月、上着で顔を隠しておいてくれ。通行人がいる」 速度を落として女性の前に車を止めると、藤森は真剣な顔で志保に声を掛けた。「すまない。美月が体調を崩してね。悪いがこのまま車に乗ってくれるか?地下の駐車場から運んでやろうと思うんだ」「分かりました。では、失礼します」 一瞬で顔を曇らせた志保は、すぐさま車に乗り込んで美月の様子を伺った。「社長、大丈夫ですか? またお風邪がぶり返したのでしょうか?」「大丈夫だ。事情は社長室内に入ってから話そう。榊君は秘書室にいるかい?」「はい、榊さんは、今日のスケジュールの調整と電話対応中です」「ふむ、では、美月、もう少しの辛抱だ」「ああ、分かったよ」 志保は驚いたように美月にしがみついた。「社長、気が付いておられるのですか?! 良かったぁ。あの、どこも痛くないですか?」「ああ、大丈夫だよ。詳しいことは部屋で話そう」 人気のない駐車場に降り立ち、そっと美月に肩を貸しながら歩く藤森に、志保も手助けする。エレベータは、ラッキーなことに誰にも出くわさず、あっさりと秘書室に辿り着いた。「社長!御無事で何よりです!」 榊が駆け寄って支える。 秘書室に鍵をかけると、美月はふうっと大きく息を吐いた。「榊、もう大丈夫だ。ありがとう。」「社長。どういうことですか?」 心配そうな榊と志保を見つめた後、改めて今回のことを美月が語りだした。昨夜の拉致に始まり、某所での監禁、説得によって解放されたこと。そして、藤森、奥平と共に決めたこと。「しばらくは、君たち二人には重荷を背負ってもらう形になるが、堪えてくれる?」 一点を見つめたまま語り続けていた美月が、榊に目をやると、口を真一文字に結んで頷く姿が目に留まった。そして、志保に視線を送って、ギクリとする。声を殺して、ボロボロに涙をあふれさせていたのだ。「わ、分かりました。私に出来ることでしたら、なんでもおっしゃってください。だけど、だけど…ご無事で良かったです。」「ああ、ありがとう。心配かけたね」 ふいに口調がやわらかくなって、藤森は驚いたように美月を振り返った。「いろいろと、なんとかなりそうだな。」 脳科学者のつぶやきに、美月が疑問を感じて問う。「いろいろ?いろいろって何?」「ん?まあ、いろいろだ。これから何やら起こりそうな予感がしたんだよ。だけど、美月には頼りになる仲間がいる。大丈夫だ。榊君、それから…」「あ、三田村です。今日からこちらに勤務させていただくことになりました。」「そうか。じゃあ、榊君、三田村君、美月の事、よろしく頼むよ。」 そういうと、藤森は帰っていった。「榊、今日のスケジュールを。」「はい。」 いつも通りてきぱきと仕事を確認する美月は、体調に問題なさそうだ。榊はほっと胸をなでおろした。「今日から1週間は、僕の代わりに榊がコンサルに行ってもらう。社長体調不良で伝言という形を取ってくれたらいい。それから、とりあえず、僕はここには毎日来るから、三田村さん、電話番で困ることがあったら、伝えてくれる?」「分かりました」 秘書たちがそれぞれの仕事を始めると、美月は社長室に向かった。「さて、この案件、どうしたものか…」 スリーピングベアの動きはどうもおかしい。嫌な予感に唇をかみしめる。つづく
November 25, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 22
エピソード 22 榊の元に美月の無事が伝えられたのは、その日のお昼前だった。「三田村さん、社長が無事、見つかりました。いやぁ、焦りましたね」「それで、社長はどこも悪くないのですか?倒れていたとかじゃ、ないのですか?」 勢いよく迫ってくる志保に、榊は苦笑いで答える。「ああ、大丈夫ですよ。落ち着いて。」「あ…。すみません。昨日、辛そうになさっていたので、し、心配しました」 俯いて、耳を赤く染めている志保を励ますように指示を出す。「さーて、無事と分かった以上、働いてもらいます。三田村さん、今日の社長の予定を見て、必要な資料を準備しておいてください」「分かりました。え、でも、そんなにすぐにお仕事されるのですか?」「あの人は、仕事していないと死んでしまう質なんですよ。」「えっ?!まぐろ…ですか?」 ぷっと噴出して、志保の肩をよろしくと言って叩くと、榊は自分の仕事に戻っていった。***** 奥平の事務所に、脳科学者と外科医、そして美月の3人が顔を突き合わせていた。今回の事は、確かに可能性として考えられることではあったが、詰めが甘かった。「う~ん、じゃあ、美月の手術は実は失敗だったってことにしよう」「ええ? それじゃあ仁の経歴に傷がつくじゃないか。」「そもそもこの手術は公にしていないんだ。なんてことないさ。それより、あの手術に関わった麻酔医の小山君と中野さん、それから、彼らの勤務する病院で噂が広がっている可能性がある。それならいっそのこと、実は失敗だった。経過が悪くて臥せっているってことにしようぜ。」「ああ、なるほど。それなら同じ経路で噂が広がるという事か。美月、しばらく寝込んでくれ」 呑気な外科医に同調する脳科学者があっけらかんと言い放つが、当の本人は渋り顔だ。「冗談でしょ。そんなに仕事を開けたことなんてないよ!」「まあそう言わずに。榊君だったか、あの有能な秘書に言付けて代わりに伝えてもらうやり方にすればいい。ある程度は対応できるだろう。これは情報漏洩の後始末だ。諦めてくれ」「そうだ、別に外に出るわけじゃないなら、事務所には顔を出してもいいんじゃないか?指示だけだして、表向きは寝込んでいることにしよう。あ、その間は女の子を侍らせるなよ!」「仁!一緒にしないでくれる?!」 ふくれっ面の美月だが、今回の事件は穏便にすませたい。そして、第2、第3の事件が起こらないよう予防線も必要だ。しぶしぶ承諾してため息をついた。「それにしても、随分なことをやるもんだな。美月、犯人は分かっているんだろ?」「ええ、もちろん。スリーピングベア・ジャパンだよ。僕は取引がないけど、ライバル会社の東野寝具にはコンサルに入っている。あとは、深山家具かな。この2社は、業務提携するべく動いていて、画期的な新商品を企画しているんだ。」 浮かない顔の美月を、脳科学者が覗き込む。「なにかひどいことでもされたのか?」「いや、僕としては、スリーピングベア・ジャパンは優良企業だと思っていたから、ショックだったんだ。そろそろアメリカ籍の本社から独立してもいいんじゃないかってぐらい業績を伸ばしていたのに。」「本社からの軋轢があったんじゃねぇのか? 俺にはよく分からないけどな」 そういいながら、部屋の外に顔を出して、冴子に声を掛けた。「悪いけど、コーヒー淹れてくれないか?」「分かりました」 戻ってきた奥平を美月がキッと睨む。「おい、どうした?」「どうしたじゃないよ。さっさと籍を入れたりしてさ。僕だけ残されるなんて、屈辱だよ」「あれ?この前まで女優と付き合ってなかったか?」「あ、あれは! 後腐れない関係なんだよ。お互い了解済み。性的興奮は極上の美容液って言うぐらいなんだ」「なんだ。ちゃんと相手がいるんじゃないか」「違うよ!彼女たちにはほかにちゃんと正式な相手がいるんだ。」 二人の会話を黙って聞いていた藤森は、すっかり傍観者になっていた。「僕の事より、涼さんの方はどうなったの?」 急に話を振られて反応が遅れた藤森は、少し言いよどんでにんまりと笑った。「あ、いや。まあ、つきあうことになった」「おい、本当か? で、相手はどんな子なんだ?」 奥平が食いつくように問いただす。「ん、夜の海に浮かぶ月の光を、一緒に眺めてくれる子なんだ」「うわぁ、見たくないよ。涼さんのそんなデレた顔。」 ドアをノックして、冴子がコーヒーを持ってきた。「美月さん、今朝から何も食べてないんでしょ? 焼き菓子だけど、良かったらどうぞ」「ありがとうございます。はぁ、気が利くなあ。仁にはもったいない」「なんだと?! 悔しかったらお前だけを大切にしてくれる人を見つけて来い」「僕だけを大切にしてくれる人…?」 美月の脳裏にふいに浮かんだ顔に、思わず赤面する。「ん? 何か心当たりがあるようだな。」 脳科学者は、コーヒーを楽しみながらじっくりと観察し始めた。「もう!涼さんまで! とにかく、僕は1週間、寝たきりってことにするから!みんなもその線でよろしくね!」 つづく
November 24, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 21
エピソード 21 ここは、どこだろう。気が付いたときには、目隠しされて腕を縛られていた。しんとしているのは、誰もいないからか。 美月は出来るだけ耳に意識を集中させて、情報を得ようとしていた。微かに香る皮製品の匂いと、悪趣味な葉巻の匂い。急に音が聞こえたと思えば、救急車のサイレンだった。微かにぼやけて聞こえくる音は、普段の仕事場に似ているな。 肌がひりひりと痛むのは、暖房のない場所にいるからか。しばらくすると、微かな人の気配が、階下から聞こえたが、すぐに出かけたのか再び静かになった。 昨日、事務所を出る前に、風邪薬を飲んでおいたのがよかったのか、今朝の体調は空腹以外、万全だ。それにしても、いったい誰がこんなことを…。 遠くから足音が近づいて、美月はとっさに眠ったふりをした。「こちらでございます。とりあえず拉致しただけですが、これからしっかり調べ上げる予定です」「変な薬など使っていないだろうな。普通の状態ではないのだから、うかつなことはするなよ」「はい。承知しております。もうすぐ検査官が来る頃ですので、しばらくお待ちを。」 美月のすぐ近くに顔を寄せて、何かを確かめているのがわかる。先ほどからの葉巻の香りが一層強くなった。「いやぁ、それにしても、まさか本当に脳神経とデータをつなぐことができたなんて、私には想像もできませんよ」「余計なことをいうな!」「いや、こいつ、まだ寝てますよ。呑気なもんですね。」「手荒なことはするなよ。問題はどうやってそのデータを抜き出すかだ」 美月の眉が思わずピクリと動いて、二人は口を閉ざした。その時、ドアをノックする音が聞こえ、もう一人部屋に入ってきた。「お待たせしました。」「どうやら起きてしまったようなので、気を付けて確認してください」 従者と思しき男が後からやってきた検査員らしい男に言うと、検査員は、つかつかと近くまで来ると、いきなり美月の髪をねじ上げた。「うっ!」「ああ、失礼。あなたの脳にデータを入れられると聞いたのでね。どこかに差込口があるはずですよね」 検査員は含み笑いをもらして、美月の髪をバサバサとひねり上げて調べた。「誰ですか。こんな失礼な真似をするのは!」「すまないね。君はいろんな会社のコンサルをやっているじゃないか。その小さな頭の中に、いろんなデータが詰まっているんだろ?独り占めしないでちょっと見せてもらいたいんだよ。」 やっぱりか。美月にはうすうす分かっていた。あの手術を受けてから、どうも周りに視線を感じるようになった。貴絵が生きていたら、他の人間を手術室に入れることはなかったのだが、どんなに調べて選んだ人間も、後から金を積まれたり、誰かを人質に取られたら、口を割ってしまう。「おかしいなぁ。脳にデータを送るなら、頭部にインプットする先があるはずなんだが…」「残念ですが、あなたたちには見つけられないですよ。もし、見つけたとしても、今の一般的な技術では対応できない。諦めて解放してください」「なんだとぉ!」 従者らしき男が、いきなり美月の胸倉をつかみ上げた。「やめないか! いや、失礼した。君が素直に私の希望するデータを掲示してくれると言うなら今すぐにでもやめさせるんだが」「こんな手荒な真似をするぐらいです。当然、真っ当な仕事に使うわけではないでしょう?」「まったく、憎らしいほど頭がいいね、君は。」「申し訳ないですね。バカなふりをするのは僕のプライドが許さなくて。はっきり言いますが、絶対に見つけられないようにしているので、この行いは徒労に終わります。僕が作った特殊な装置がないと、アウトプットできない仕組みです。 それから、この手術に関わった脳科学者や外科医以外にも、弁護士や警察とも連携されていますので、あまり長く僕を拘束すると、彼らはあっという間にここを嗅ぎつけてしまうでしょう。」 目隠しされていても、その場にいた人間の緊張が伝わった。「どうです。ここで取引しませんか? このまま僕をどこかの公園にでも座らせてくださったら、今回の事はなかったことにしましょう。僕だって、簡単に拉致されたとなると、管理能力を問われかねない。そして、あなた方の顔も分からないし、今僕がどこにいるのかもさっぱり分からないので、あなた方を特定するのは不可能です。」 きっぱりとした発言に、辺りは静まり返った。奥歯をかみしめて、悔しそうにこぶしを握っている姿が、目に浮かぶ。あと一押し。「ああ、そろそろ皆さんが出社される時間じゃないですか? 今、目の前にいらっしゃる方、それなりの肩書をお持ちですよね? 早く連れ出さないと、一般社員の目に触れてしまいませんか?」 しばしの沈黙の後、男は観念した。「分かった。だがせっかくなので、少しだけ悪あがきさせてくれ。おい、あと10分だけ調べてくれ。それでも見つからなければ、公園まで連れて行ってやれ」「え、会長!?いいんですか?」「彼の言うことももっともだ。私が浅はかだった。」 そのまましばらく体中を調べていたが、時間が来たのかその作業はすっと終わった。「会長、私は、会長の判断が正しかったと思います。誓って、今日の事は口外いたしません。では、私はこれで失礼します。」 検査官が退室していった。「では、公園まで連れて行ってやれ。君にも嫌な仕事をさせたな。」「いえ、ではお連れします。」 従者は美月の体を支えて立たせてやると、そのまま部屋を出てエレベータへと進んだ。美月の頭の中で、エレベータの速度と時間が計算される。32階、辺りか。。 ひんやりとした人気のない空間にでて、しばらく歩くと、車のドアを開く音がした。従者は意外にも丁寧に美月を座らせ、車を走らせた。「会長さんに、お伝えください。もし、お困りでしたら、次はコンサルタントとしてお会いしたいと。この手術を受けるときに開発した仲間で話し合ったのです。絶対に悪用されないように、十分に気を付けること。もし、技術が進んで暴かれそうになったら、命を絶つ覚悟でいること、と。」「そうでしたか。うちの会長は従来そんな悪いことをする人ではないのです。こんな仕打ちをされて、すんなり信じられないでしょうけどね。あなたの聡明さに我々は救われました。」 車を止めて、美月をベンチまで誘導すると、従者は後ろ手に縛っていたロープを緩めた。「すみません。痛い思いをさせて。ですが、どうか私が去るまでは目隠しのままでお願いします。では、失礼します。」 そう言い残して従者は車に戻っていった。ほどなく車が去る音がして、美月はそっと目隠しを外した。「まさか、あの会社がこんなことするなんて…」 美月には、すでに会社が特定されていた。ビルの階数、車の移動方向、そして、現在地。それだけで十分だった。つづく
November 22, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 20
エピソード 20「そうだ!」 すぐさま馴染みの相手に電話を入れる。「もしもし、三木さんですか? あの、うちの社長はそちらにおじゃましていませんか?」「いえ、こちらにはお見えではないですよ。あ、ちょっと待ってください。今、所長が来られたので聞いてみます。… 所長もご存知ないようですね」「そうですか。いや、お邪魔しました」 受話器を置いて、じっと考え込む。三木は藤森の第一秘書だ。藤森の事務所にもいないし、藤森本人も行方を知らないという。もちろん、美月の関連店舗には姿を出していないことは確認済みだ。 それからもあちらこちらに連絡を入れるが、どうにも足取りが掴めない。 時間は刻々と過ぎ、コンサルティングのアポイントの時間が迫っていた。自由人の美月でも、仕事だけはきちんとこなしていたのだが、今回はそういうことではなさそうだ。榊は再び藤森の事務所に連絡を入れた。「美月がいない?」 事態を知った藤森は、すぐさま美月の通信機器を取り出したが、やはり連絡は取れなかった。奥平や本田、篠原にも連絡を入れてみたが、みな、会っていないという。「榊君、昨日、美月の様子はどうだった? たぶん二日酔いになっていたと思うんだが」「ええ、それはひどい顔で。でも、秘書の面接にも対応していましたし。そういえば、風邪をひいていたみたいで、熱が出て、しばらく医務室で横になっていました。」「榊君、忙しいだろうが、一度美月のマンションに帰っていないか確認してみてくれないか」「分かりました」 電話を切って、しばらく考え込んでいた榊が、思い切って行動することにした。「三田村さん、急で悪いけど、私と一緒に社長宅に来てくれるかな」「はい」 志保はすぐさまコートを着込んで準備する。事務所を出る前に、思い出して、昨日の残りの経口補水液をカバンに入れた。もしかして、どこかで具合が悪くなっているかもしれないと思ったのだ。「あの、社長のご自宅に伺うのではなかったのですか?」 戸惑う様に榊を見上げる志保に、第一秘書は慣れた様子で微笑んだ。「そうですよ。このビルの最上階が社長のご自宅です。何軒か抱えているバーを見回ったりするので、社長はここに住んでいるんです。ちなみに、このビル丸ごと社長の持ち物です。」「このビル、全部ですか…」「ええ、他の階は貸事務所がほとんどですが、一部簡単な宿泊施設になっています。出張で来た人が利用しやすい構造なんですよ。」 橘製薬もそれなりに大きな会社だったが、まるで規格違いだ。驚いている志保をしり目に榊はポストを見てうなった。「社長、ここには帰ってないな。昨日の夕刊からの新聞が溜まっていますね。いったいどこに行ったんだろう。」 榊は昨日の美月の様子を思い出していた。志保が帰った後、しばらくはベッドでおとなしくしていたはずだ。しかし、その後電話が入っていた。そう、美月はその電話で少し困惑した様子を見せていた。今日一日連絡が付かなかったら、警察に連絡しよう。警察なら、電話の履歴も探れるはずだ。 事務所に戻った榊は、今日の午前のアポイントを美月の体調不良を理由にキャンセルして、出かけることにした。「三田村さん、着任早々で申し訳ないですが、電話番をお願いします。社長あての電話は体調不良ということで、私あての物は、出先からこちらに電話を入れるので、その時教えてください。社長のスケジュールの詳細は端末に入れてありますので、後でご確認を」 榊の様子で何かが起こっていると察した志保は、頷いて榊を見送った。 しんと静かになった秘書室にポツンと一人取り残された気分の志保は、そっと窓際まで歩いてみた。ビジネス街のど真ん中、高層ビルの35階は見晴らしがいい。振り向いたその部屋には、ゆったりとした応接セットと秘書たちの机が並んでいるだけだ。そしてその奥に社長室の扉がある。 ここはなんて贅沢な空間だろう。この階にあるのは、あとは応接室と医務室だけだ。一つ下の階は総務部のフロアで、その下は営業部のフロアで、そちらにも小さな会議室が何部屋か並んでいた。 端末で、社長のスケジュールを確認すると、それこそ分単位で組まれている。「ありがとう。今日、君がいてくれて、良かった…」 橘製薬に来られた時の自信に満ちた表情からは、想像できないほどの弱弱しい声だった。彼をよく知る第一秘書の榊でさえ、あれほど焦っているのだ。きっと何か良くないことが起こっている。どうか、無事でいてください。志保は両手を握り締めてそっと祈った。 突然、内線電話が鳴って、慌てて取り上げた。「受付です。今日、社長とお約束があると、吉川様とおっしゃる方がお見えです。」 志保は、すぐさま端末の予定を確認するが、今朝の来客はキャンセルになったコンサルの仕事が入っていただけだ。「今日、社長は体調不良でお休みです。お約束もこちらでは伺っていないようですが」 受付嬢が、ほっとしたのが電話口からも分かる。「分かりました。失礼いたします」「あの、対応が終わりましたら、こちらにご連絡いただけますか?」「承知しました」 受付嬢はそつなく受け答えして電話を切った。そして、その数分後には、再びかかってきた。「今、お帰りになりました」「ありがとうございます。私は、今日から秘書になりました三田村です。どうぞよろしくお願いします。あの、先ほどの方はどんな感じの方でしたか?」「それが…、以前にもこちらに来られたことがあるのですが、クラブを経営なさっている方で、社長が対応されたことはありません。いつも榊さんに帰ってもらう様にと言われていました。」「そうでしたか。ありがとうございました。」 いつも面会を断る相手など、志保の経験からは想像できなかった。そうか、優秀で目立つ美月は多くの者と戦ってもいたんだ。それに気づいたら、なおさら昨日の気弱な姿が痛ましく思え、胸を締め付けた。つづく
November 20, 2022
コメント(0)
-
訂正
先ほど、じっくり「エグゼクティブ・チーム」を読み返していたら、登場人物の名前を間違えていたようです。きのう、今日とアップロードしたエピソード 18,19で出てきた秘書として面接に来ていた三田村志保さんは、以前、橘製薬で受付嬢をしていた鈴木志保さんでした。ややこしいので、鈴木 ➡ 三田村 に訂正いたします。失礼いたしました。 (≧◇≦)ひえ~
November 19, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 19
エピソード 19「いつも気取っているのに、不細工で笑っちゃうでしょ?」自棄っぱちの美月が言うと、きゅっと眉を寄せ、それでも美月の状態を確かめようと、志保はすっと席を立ち、美月の傍に駆け寄った。「失礼します。 あ、やっぱりお熱がありますね。少し休まれた方がいいですよ。それと、アルコールが早く体の外に出てしまう様に、お水も飲まれた方がいいかと。」「ああ、大丈夫です。それより今は、君の面接を…」 迫ってくる志保を遮ろうとする美月の手を、志保ががっしりと握りしめて、真剣な顔で言う。「私の面接なんかより、社長さんの体調の方がずっと大切です!お顔の色もよろしくないですよ。榊さん、こちらには社長がお休みになれる場所はありますか? 絞ったタオルと経口補水液などあればいいのですが」 結局、美月はあっという間に医務室に寝かされた。榊が経口補水液を買いに行く間、志保に社長を見ていてほしいと頼まれ、退室する機会を失ってしまった志保は、自分のタオルのハンカチで美月の額を冷やした。「ごめんね。こんな失態、初めてだよ」「社長さんのご自分をプロデュースする力は見事です。周りの人もみんな美月社長のいつもの隙のないかっこよさに憧れていらっしゃいますよね。だけど、体調の悪い時は無理をなさらないで下さい。社長だって、一人の人間なんです。」 熱が上がってぼうっとした頭のままでも、その言葉は美月の心にしみ込んだ。新たなタオルを乗せる手をそっと捕まえて、夢うつつでつぶやく。「ありがとう。今日、君がいてくれて、良かった…」「あ…。」 不意に手を握られ、志保は驚いたが、美月はそのまますやすやと眠ってしまった。 しばらくして、静かなノックの音と共に、榊が入ってきて、絶句する。「!!」 その表情を見て、握られたままの手に思い至った志保が真っ赤になった。「あ、あの。相当お辛かったようで、ありがとうとおっしゃったときに手を掴まれて、そ、そのままお休みになってしまわれました」「ふふ。うちのわがまま社長が申し訳ないです。きっと入社決定ですね。もし、今日これからお時間があるようでしたら、もう少し社長の傍にいてあげてもらえませんか?」 美月は夢を見ていた。幼いころから、その容姿のせいで目立ってしまい、誉めそやす者もいれば、妬んであらぬ噂をたてる者もいた。人を蹴落として見栄を張りたい者のなんと多いことか。 外見だけがいいと言われるのが悔しくて、必死で勉強した。そうしているうちに、気の合う先輩たちにも巡り合えた。そんな先輩たちが、それぞれ人生のパートナーを見つけて自分から離れて行ってしまう。自分はまた、子どもの頃のように一人ぼっちになってしまうのか。「そうだなぁ。隙を作るのもいいのかもな。美月は隙が無さすぎなんだよ」 不意に昨夜の藤森の言葉を思い出す。涼さん、僕は今、隙だらけだよ。こんな姿、周りの人間が見たら、あざ笑うのが落ちさ。 冷たいタオルが額に乗って、ふいに意識を取り戻した。目の前には心配そうな瞳があった。「あの、大丈夫ですか?タオルが落ちそうだったので、直してみたのですが。」「あれ? ごめんね。看病までしてもらってたの? 榊はどうした?」 足元から榊の声がした。「社長が彼女の手をしっかりと握りしめているから、帰るに帰れなかったんですよ。社長、いい加減、彼女を解放してください」「ん?! あ、ごめん!」 美月が自分の手元を見ると、しっかりと小さな手を握り締めていた。慌ててその華奢な手を離して、謝った。「では、私はこれで失礼します。社長、どうぞご自愛ください。」「ああ、すまなかったよ。君の入社は決定だから、明日、9時までに出社してね。みんなに紹介するよ」 志保は丁寧にお礼を言って、部屋を出た。美月はまだ熱の残る頭でぼんやりと部屋の天井を見ていた。「いい子ですね。真面目だし、変な色目を使ったりしないし」「ん、そうだね」 予想外のそっけない返事に、榊は思わず美月の表情を確かめた。いつも自分が最強だと強気な生き方をしてきた社長が、ぼんやりと考え事をしている。それは風邪熱のせいだけではなさそうだと、榊は思いを巡らせていた。 翌日、美月の事務所に新しい秘書として志保が出社してきた。榊が皆に紹介して、一通りの朝礼が終わった。ただ、社長の席に美月は顔を出していない。「おかしいな。社長は間違いなく出社すると思ったのに。」「あの、もしかして、まだ体調が優れないのでしょうか?」 志保は空室になっている社長室の扉を見つめている。先ほどから自宅には電話を入れているが、コールだけが響いている。いったいどこに行ったんだろう。どんなに自由にしていても、こういう場面は外さない人なのに。榊の心に、じわりと嫌な予感が広がる。つづく
November 19, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 18
エピソード 18「美月、さっきは悪かったね」「え~、涼さん、ホントひどいよぉ」「美月?もしかして酔っている?」「これが飲まずにいられますか? 仁も入籍するっていうんだよ!」 珍しい美月の醜態に、ふっと口角が上がる。らしくない美月もなんだか親近感がわくというものだ。「美月、今どこにいるんだ?」「自分ちだよ。外じゃ絶対見せられないじゃない、こんな姿」 酒におぼれて絡んでくるなど、今までの美月には考えられない。藤森は、この可愛い後輩をなんとかしてやりたいと思っていた。「不思議だな。3人の中で一番モテる美月が残ってるなんてな」「涼さん、あのね。モテるからって、最愛の人に出会えるとは限らないんだよ。」 さすが美月、達観している。脳科学者には到底出せない真実だった。「そっか。そうだよな。あ、でも、私は美月に出会えてよかったと思っている。今の私は美月にプロデュースしてもらったようなものだからな」「何言ってるの。ちょっとアドバイスしたらすぐにおしゃれになっちゃって。元々のセンスが良かったんだよ。それよりさぁ~。僕も彼女がほしいよぉ。おしゃれでスマートな美月君の殻を脱いでも許してくれるような子、いないかなぁ」 話しながら、藤森はすでに自室に戻っていた。マンションのベランダからも月は美しく輝いて見えた。「そうだなぁ。隙を作るのもいいのかもな。美月は隙が無さすぎなんだよ」「ええ~、それは僕のプライドが許さないよぉ」「その姿そのままを誰かに見てもらえたらいいんだがな。今なら隙だらけなんだが。明日も仕事だろ?酒はその辺にしておいて、ちゃんと睡眠を取れよ。」 通話が終わった機器を見つめながら、美月はふくれっ面でつぶやいた。「もう、涼さんでいいから彼女になってよ」 翌日、見事なまでの二日酔いで腫れぼったい顔の美月がいた。「やばい。こんな顔では出社できないじゃない。」 慌てて蒸しタオルを作ると、しっかりと顔に当てながら今日の予定を思い出す。「店舗は榊に頼めばいいけど、コンサルが1件入っていたっけ」 何度かタオルを取り換え、少しは落ち着いてきたのを見計らって、大き目のマスクと眼鏡をかけて、しぶしぶ出社した。ここは以前橘製薬の社員が見学に来たビルだ。やってきた美月に、秘書からの予定変更の連絡が来た。「社長、今日のコンサル案件ですが、クライアントに急用ができたとかで延期の申し出がありました。」「ホント? そっか、それは良かった。日程はそちらに任せるよ。じゃあ、今日はこのまま一旦帰宅してもいいかな」 美月はまだ社長室にも入らないまま、じわっとUターンし始めるが、榊によってきっぱり断られる。「いえ、それは困ります。」 妙に嬉しそうな第一秘書に違和感を覚えた美月は、眉間にしわを寄せた。「榊、僕が珍しく二日酔いだからって、からかうのはどうかと思うよ」「いえ、先日産休に入った神谷さんの代わりに、秘書課の補佐を探していたのですが、今日、よさそうな方が面接に来られることになっています」 美月はじっと榊の表情を凝視している。含みのある表情は、何か隠しているか、自分を驚かそうとしているかだ。「こちらが履歴書です。10時の予定になっていますので、あと10分ほどでお見えかと」 差し出された履歴書には見覚えのある写真が貼られていた。「この人は、橘製薬の受付嬢?」「はい、会社倒産後、自分磨きをしたいとのことで、アルバイトしながらうちの秘書講座を受けていたのですが、この度検定に合格されたとのことで、お礼に来られたのです。」 美月の腫れぼったい目が一層細くなって、片方の眉が器用に上がっている。「で、おせっかいな僕の秘書が、そんな律儀な彼女を神谷さんの代わりにと声を掛けたんだね」「おっしゃる通りでございます」「それで今日、僕に面接をしろと。こんな顔なのに」「あ、いや。申し訳ございません。まさか美月社長がそんな不細工な…、あ、失礼しました。体調を崩されているとは知らず…」「榊!」 美月が攻めようとしたところで、控えめなノックが聞こえた。「ああ、来られたようですね。どうされますか?」「はぁ~~~~、通してくれ」 美月は観念してソファに座り込んだ。 それを確認すると、榊がそっとドアを開ける。「失礼します。三田村志保です。先日は、お声かけくださりありがとうございました。」「社長の美月です。どうぞ、座って」 ぺこりとお辞儀をして、志保はそそと近づきソファに座った。榊はそっと隅に控え、空気のように気配を消した。「秘書検定、合格したそうですね。」「はい、今一度、きちんと学びなおそうと思いました。以前の勤務先では、きっとこんな風に自分を磨くことなんて、考えられなかったと思います。あの時、美月社長がコンサルタントとしてお見えになって、私には大きな衝撃でした。」「そうか、そんな風に影響を与えられたなら良かったです。」 話をしながら、志保がちらちらと美月の顔を見るので、軽く咳払いをした。「失礼しました。あの、今日はお体の具合が優れないのかと思いまして。今日の面接のために無理をしてくださっているのだとしたら、申し訳なくて」「はぁ、本当は、こんな姿誰にも見せたことがなかったんですけどね。色々あるんですよ。まぁ、気にしないで。ただの二日酔いですから。」つづく
November 18, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 17
エピソード 17「あの、良かったんですか? お仕事の呼び出しでは?」 心配そうに見つめる詩織の頭を、藤森はぽんっとひと撫でしてほほ笑んだ。「酒の誘いだから気にしなくていい。それに、こっちが先約だからね。」 何度か海岸で月を眺めていた二人は、この日、初めて一緒に食事に出かけていた。夜の街でしか会っていなかった彼女は、明るい店内に入ると、一層その美しさが際立った。はにかんだように話すその表情にも好感が持て、顔には出さないが、藤森は上機嫌だった。 幼いころから脳科学に異常な興味を持ち続いていた藤森は、女性と恋愛を楽しむという感覚がよくわからなかった。女性の尻を追いかけて楽し気に笑う奥平や、浮名を流しながら、次々女性との関係を楽しむ美月を見ていても、ぴんと来なかったのだ。 あ、これは…!ドーパミン、アドレナリンが大量に分泌されている感覚だ。そうか、これが恋に落ちるということなのか。 詩織の潤んだ瞳や微かに赤らんだ頬に、自分の中の変化を感じながら、その感触を味わった。「何が好き?」「え…?! あの…」 急に尋ねられて真っ赤になる詩織を見て、聞き方を間違えたと藤森は慌てた。「いや、失礼。何を食べたい?」「あ、すみません! あの、なんでもいいです」「ここのステーキは絶品だよ。試してみる?」「はい、お願いします」 しどろもどろの詩織に、さりげなく助け舟を出しながらオーダーを告げる藤森は、大人の男性の品と色香に満ちていて、小さな胸がどきりとはねる。と、藤森は再び詩織に向き直った。「これ、私の名刺なんだ。渡しておくね」「ありがとうございます。 あの、私は名刺を持っていないので、名前と連絡先を書いてきました。」 名刺代わりに渡された小さなメモは、ふちに小花模様が入っていて脳科学者の頬を緩めた。「篠原詩織さん、というんだね。看護師なんだ。仕事はどう?」「まだまだ先輩のお世話になってばかりです。でも、患者さんが元気になって退院されるのを見送ると、頑張ってよかったって思えるので、辛くはないです」「そっか。」 目を細める藤森に、遠慮がちに詩織が質問する。「あの、脳科学者さんって、どんなお仕事をされるのですか?」「ん~、人間の脳はまだまだ分からない部分も多いからね。そういうのを解明するのが仕事なんだ。」「…もしかして、藤森さんは祖父をご存知ですか?篠原賢三というのです。大学院の研究所に勤務しているのですが、祖父の口から、藤森さんのお名前を聞いたことがあって…」 食前酒のグラスを持ち上げたまま、藤森は固まってしまった。「教授のお孫さん?」「はい、そうなんです。やはり、お知り合いだったんですね。祖父がよく自慢しています。」 手元のグラスをテーブルに置きながら、動揺を押し殺す。まさか、教授の親戚だったとは。やばい。教授には、脳科学に執着しすぎて、ボロボロの服装やボサボサの頭に分厚い眼鏡姿を見られている。これだけは、彼女の耳に入れてほしくないのだが。「それで、教授は私の事をなんと?」「え…あ、あの。とても優秀で穏やかな方だと。それで…」「そ、それで?」 詩織の視線が泳いでいることに、藤森はまったく気づいていない。言いにくそうに俯く詩織に答えを促した。「け、結婚するなら、彼のような人にしなさいと…」「け…え!? そ、そうか。参ったな。」 顔をあげた詩織は、耳を真っ赤にした藤森を目の当たりにして後悔した。「あの、ごめんなさい。祖父の言ったことなので、気にしないでください。その、余計なことを言って、申し訳ありません」「いや、そ、そうじゃないんだ。私があまりにも経験不足なもので…」 そういうと目の前の水をゴクゴクと一気に飲み干して、大きく深呼吸をした。そうして、目じりを下げて告白する。「いい歳をしてみっともないだろう? 私は、若いころから脳科学にしか興味のない変人だったんだ。だから、本当におかしなくらい女性と関わったことがなくて。だけど、君と水面に浮かぶ月を見るのが、とても心地よくて。仕事の合間にも、ふとあの時の波の音や風の匂いや君の笑顔を思い出したりして…。あ、いや、申し訳ない。私は何を言ってるんだ。ちょっと混乱しているね」 一息にそこまでしゃべってしまって、藤森は自虐的に笑った。さっきまでの大人の品はすっかり霧散して、女性に不慣れな素朴な男がそこにいた。そんな姿に、詩織は親近感を覚えずにはいられなかった。「つまり、もしよかったら、私と付き合ってほしいんだ。もちろん、結婚を前提として」 目の前の彼女は、目を大きく見開いて固まっている。藤森は即座に失敗したかと後悔した。海岸で数回会って、今日は初めて食事に誘ったところだというのに、いきなりプロポーズまがいの告白になってしまった。 『涼さん、それはダメだよ。彼女にだって心の準備は必要だよ!』 呆れたような美月の顔が浮かんだ。「いや、すまない。突然すぎて驚いているよね」「あ、いえ。あの。…そうなったらいいなって、ずっと夢見ていたので、びっくりしすぎて…。あの、ホントに私なんかでいいのでしょうか?」「それは私のセリフだよ。これから、お互いの事を知っていこう」 強張っていた詩織の顔がふわっと緩んで微笑みに変わった。気持ちが通じ合うと、緊張は一気に解けて、二人は他愛ない話で盛り上がった。 食事が終わると、すっかり定番になった夜の砂浜へと足を運び、のんびりと月を眺める。 いつもの交差点まで見送ると、マンションまで歩きながら、ふと美月に連絡を取ってみようと思い立った。つづく
November 17, 2022
コメント(0)
-
やっちゃった。
明日の朝にUPするつもりだった小説、あげてしまいました。。。良かったら、読んでください。小説家になろうの「ブルーフォレスト」は今も約34件の閲覧がありまして、どうしてでしょう。。よくわかりませんね。ホントに気に入って、読んでくださってるならいいんだけど。エグゼクティブ・チームはなかなか着地点が見つからず、まだまだ悪戦苦闘です。あ~~~~~!!そうこうしているうちに、お仕事が忙しい季節に入って来て、ここからやばい感じです。そしてそして、このブログ。随分放置機関が長かったのに、皆様のおかげで、閲覧数がもうすぐ10万!もし、自分がキリ番踏みましたー!というのがあったら、是非お知らせくださいね。もうちょっとかかりそうですけど、自分で踏まないように気をつけようっと!
November 15, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード16
エピソード16 週末のクラブはにぎわっていた。美月は今日もカウンターに座って、水割りを楽しんでいる。若い女性客が2人、そっとカウンターに歩み寄り、美月に声を掛けた。「あの、美月さんはどんな女性がタイプなんですか?」 瞳をキラキラさせてためらいがちに尋ねる彼女に、くるりと振り向くと、サラサラの淡い金髪が後ろに流れ、ブルーグレイの瞳が露わになって、営業スマイルが炸裂する。「控えめな子が好きかな。それと、下品な子と押しの強い子は苦手なんだよね」「あ…すみません。厚かましく声を掛けて…」 声を掛けた彼女は、あからさまにしゅんと肩を落とした。そんな女性客を純粋にかわいいと感じていた。「君たちの事じゃないよ。いつもお店に来てくれてありがとう。ねえ、この子たちに合うカクテルをごちそうして。」 美月が目配せすると、バーテンダーが愛らしい色合いのカクテルを手早く作って、彼女たちの席に届けた。 女性たちは感激してお礼を言うと、嬉しそうに席に戻っていった。 これは、いわゆる営業だ。下品な客、押しつけがましい客は必要ないと、暗に宣言して、まとわりつく客を席に座らせる。本人たちは気をよくして、口コミを広げてくれるのだ。 彼女たちの後に続こうとする他の客は、近寄れなくなる。 遠巻きに美月を眺める客たちをしり目に、今日も美月は水割りの氷が解けていく様を眺めていた。「美月、帰ったぞ!」「仁! ここは君の家じゃないし、僕は君の奥さんでもないんだけど」「いいじゃねーか。日本が俺の家なんだから」 がははと笑う奥平に、美月は小さくため息をついた。さっき下品な客や押し付けがましい客が嫌だとけん制したばかりなのに。これでは示しがつかない。「ねえ、仁。久しぶりに涼さんに会いに行こうよ」「お、いいね!そう言えば、あの立てこもられ事件から、ゆっくり話せてないんだよ」 二人は、さっそく店を出た。 いつものショットバーを覗いたが、藤森の姿はなかった。「おかしいなぁ。久々これを使おうか」 美月は、自作の通信機器を取り出した。これを作ってすでに1年が過ぎている。巷ではポケベルなるものが出回り始めた。藤森を呼び出すとほどなく応答があった。「どうした?」「涼さん、今どこ? こっちは仁が帰ってきたから一緒に飲もうかと思って」「悪いけど、今日は遠慮しておくよ。」 美月はその言葉の向こう側で女性の声が聞こえてはっとした。「そ、そう。じゃあまた」 機器を片付けて、じっと考え込んだ美月に、不思議そうに奥平が声を掛ける。「おい、どうしたんだ? 涼はなんて?」「ああ、今日はやめておくって」「なんだ、また論文書いてるのか?」「いや、そうじゃないみたい…」 美月の戸惑った様子にピンときた奥平は、ふっと笑い出した。「そうか、さては涼にも彼女ができたのか」 瞠目する美月を楽しそうに眺めながら、奥平が爆弾を投入する。「そうそう。俺も、籍を入れることにしたんだ。」「は?どういうこと?」 焦る美月に、奥平は妙に余裕な様子だ。「ん、女の子の後を追いかけるのが、邪魔くさくなったんだよ。それと、あの人質事件の時、意識を失くす直前に冴子が気絶させられるのが見えて、体中から血の気が引いたんだ。聡明で気が利くけど、気が強くて偉そうで、何があってもどんとそこに居座っていると思っていた。それなのに、あっけなく倒れていく姿を見て、たまらなくなったんだ」「ねえ仁。冴子さんって、6つ年上の本田先輩の、お姉さんだよねぇ」「ああ、そうだ。俺の事務所にいる冴子だ。」 何かが理解できない。納得できないというか、受け入れがたいと体中の細胞が訴えている。しばらく目を泳がせていた美月は、そっとその視線を奥平に戻した。「それで、冴子さんはOKしたの?」「ん?それがな。意外なことにあいつ、こんなこと言うんだ。やっと気が付いたの?ほんとに世話が焼けるわね、だと」 はぁ~っと大きなため息をついて、美月は手のひらで顔を覆った。「僕には理解できないよ。ああ、だけど、おめでとう、だよね」「ああ、ありがとう。次は涼からの報告待ちだな。美月、先に飯にしようぜ」 さっさと歩き出した奥平の後を追いながら、ふと街中を眺めると、そのカップルの多さにはっとする。そうか、もうすぐクリスマスなのか。キリスト教徒でもなんでもない日本人が、好んで楽しむこのイベントは、恋人たちにとっても盛り上がれる行事だ。美月は根拠のない焦燥感に襲われていた。つづく
November 15, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 15(後半)
エピソード 15後半 藤森が奥平の事務所に到着したのに気づくと、美月はすぐさま駆け寄って報告した。「つい今しがた、警察が来たよ。どんなに説得しても日本語も英語もフランス語も通じないし、もう僕ではお手上げだよ。」「仁はどうしてる?」 美月は、はぁっと大きなため息をついて嘆く。「それがさ。いきなり事務所にやってきて、何か薬品を噴霧されたみたいで、意識を失ったまま人質にされている。犯人は3人で、若い男だよ。僕もたまたま事務所前に来ていたんだけど、様子がおかしかったから事務所に入らずに通り過ぎて様子を見てたんだ。それで、早速通信機器を使ってみたんだ。」「そういうことか。仁が無事ならいいんだが…。とりあえず、私が通訳に向かおう」 OSO事務所はビルの25階にあった。エレベータで現場に向かうと、ちょうど警察が突入するところで、その場は騒然としていた。「おい、いきなり突入して人質は大丈夫なのか?」「え?女性なら、気絶させられていたので保護しましたが、他に人質なんていたんですか?」 傍にいた警官が驚いていた。焦ったところで、すでに部隊は突入している。藤森は眉間にしわを寄せた。 聞きなれない言葉で男たちは叫び声をあげているが、こちらには理解できない。警官がゆっくりと日本語で話すが、まったく意味をなさなかった。 藤森が立てこもっている部屋の中をそっと覗くと、3人はすでに拘束されていたが、奥平の姿は見つからない。「ここは、仁の私室に使っているところか?彼らの言葉なら私が通訳できる。中に入らせてもらうよ」 室内は事務所というより仮眠室に近い。よく見ると、部屋の奥に男が転がっていた。藤森はふっと肩の力を抜いて、捲し立てる男たちに声を掛けた。『君たちはノーザンディから来たのか?』 ふいに意味の分かる言葉が聞こえ、男たちはそこに注目する。男は3人組で、主に何かを叫んでいる男とその手下らしい男2人だ。『ここは奥平の事務所だろ?奥平という男を出せ!』『なぜだ?』『あいつのせいで、父が失脚させられたんだ。父は、ノーザンディのために懸命に努力してきた人だ。新しい薬を開発して、多くの人を救うんだって言っていたのに』 男は歯を食いしばって悔しがっているが、後ろ手に縛られて、なすすべもない。『もしかして君は、エルアルド氏の息子なのか?』 つばをとばして叫んでいた若い男は、瞠目して藤森を見つめた。そして、探るように尋ねた。『父を知っているのか?!』『ああ、以前ノーザンディに滞在したとき世話になったよ。』 若い男はじっと藤森を値踏みする。身なりは良く、口ぶりも落ち着いている。この人物は何かの要人だと、彼の直感が示していた。幼いころから父親に高い教育を施された。父を訪ねてやってくる客人の多くは、目の前の人物のように落ち着いている。一部の怪しい連中を除いて。『あなたは、誰ですか?』『私は藤森という。脳科学を研究している者だ。ノーザンディには、サイエン王国の研究所に行った際に、アルバーニ大統領を表敬訪問させてもらいに行ったんだ。その時世話になってね』 若い男は、サリエルと名乗った。さっきまでの殺気は失せて、すっかり落ち着きを取り戻していた。『残念だが、ここは君の言う奥平の事務所ではないな。人違いだ。そこにいる男は、私の部下だ。ここに資料を渡しに来ていたんだ』 サリエルはすぐ後ろに転がっている男を見た。『日本人はみんなよく似ている。人違いは仕方ない。だが、騒ぎを起こしたことはちゃんと説明してくれ』『そう、だったんですか。』 茫然とするサリエルに、他の二人もどうしていいのか分からない様子だった。その時、グガッと大きないびきをかいて、奥平が寝返りを打った。「ふう、寝てるだけだったか。」「あの…。彼を隣の部屋に寝かせてあげてもいいですか?」 ほっとしている藤森の横から、美月が声を掛ける。「あなたが藤森さんですね。弁護士の本田から聞いています。あ、奴とは大学の同期でして…。私は、明智署の山田と申します。彼らの言葉が分からなくて、困っていたのです。取り調べに協力いただいてもよろしいですか?」 本田とは対照的な人懐っこい顔をした男が、あからさまにほっとした様子で声を掛けてきた。やっとゆっくりできると思っていたが、どうやら今日はそうはいかないらしい。藤森はあきらめたように頷いて3人の若い男たちに説明し、山田に続いた。警官が藤森とサリエルたちを連れて行くと、美月がふう、っと大きなため息をついた。「嘘も方便とはいうけど、涼さんも人が悪いよ。」つづく
November 15, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 15(前半)
エピソード 15 静かになった空間に、キーボードを叩く音だけが響いていた。残業しているという感覚はない。しいて言えば、四六時中仕事をしているとも言えるし、四六時中趣味の事をしているとも言える。まとまった論文を前に、ふうっと大きなため息をついて、藤森は背もたれに背中を預けた。 論文をまとめている間に、奥平はラバリー帝国に向かったが、何もできないまま帰ってきた。「戦争真っただ中に乗り込んでいくもんじゃねーな。命がいくつあっても足りんぞ。うまい具合にサイエン王国の護衛騎士にばったり会えて、保護されたのはラッキーだった。なんでも、例の第2王子からカームリーの王女に自分の国の軍隊が勝手をしていると情報が流れたらしくてな。カームリーの王妃はサイエン王国から嫁いでいるので、母国に助けを求めたらしい。俺が帰国の準備をしている間に片が付いたよ。」「いや、待てよ。サイエン王国にそんな強力な軍隊なんてあったのか?」「いや、やったのは化学部隊だ。押し寄せてくる軍隊を無味無臭のガスで眠らせて、コンテナに詰め込んで送り返していたそうだ。何度やっても同じ状態になって、とうとうラバリー帝国の軍部も諦めたそうだ。」 のんびりした奥平の声に安堵するとともに、参加できなかったことが悔しくもあった。ノーザンディのデ・ボーノは復権し、エルアルドが建てた乳製品の工場に見立てた麻薬工場は摘発された。こちらは、ミスターKからもたらされた情報だ。エルアルドはインターポールに捕縛され、罪状はこれから明らかになるだろうとのことだった。「今頃先輩が走り回っている頃か。」 窓の外を眺めると、きれいな月が出ていた。しんと静まったオフィスには音楽は流れていない。それなのに、藤森は小さな音で「月の光」が聞こえたような気がした。あれから随分と時間が経ってしまったが、あの時の情景がふいに蘇って、思い立ったように席を立った。 今夜の月はことさら大きく見える。きっと波間にうつる姿も美しいだろう。藤森は車を走らせて、海沿いの道を行く。 車を路肩に停めて、外に出ると、潮の香りを乗せた夜風がすっと頬を撫でた。防波堤の先まで行くと、思った通り、美しい月の光が波間を揺れていた。目を閉じて、心の中でドビュッシーのメロディーを再現する。「こんばんは」 控えめな声がして振り返ると、いつか出会った彼女が、微笑んでいた。「やぁ、こんばんは。今日の月は大きいね」「そうですね。あの、…先日は危ないところをありがとうございました。おじいちゃんにも、遅い時間に外に出ないようにって、注意されちゃって…。でも、どうしても先日のお礼が言いたくて。」 気恥ずかしそうにそういうと、ふと海沿いに並ぶマンション群を振り返る。「寮の休憩室から、あなたがこちらに来られるのが見えたので、急いで来てしまいました。」 そういうと、そのまま隣に佇んで海を眺めている。そして、ふいに何かを思い出したのか、カバンの中を弄って、小さな機器を取り出した。「小型のスピーカーを見つけたんです。」 嬉しそうに微笑むと、ウォークマンに接続した。途端に、「月の光」が流れ始め、二人は微笑み合った。「いいね。」 波の音、少し湿り気を含んだ潮風、静かに二人を照らす月光とピアノの繊細なメロディ-。名前も知らない二人が寄り添うには、それで十分だった。 静寂を破ったのは、美月の通信機器だ。「どうした?」「涼さん、今どこ? すぐに仁の事務所に来て!外国人の男たちがが立てこもってるんだ」「分かった。すぐ行く!」 彼女は、心配そうに藤森の横顔を見つめていた。事態の急変に戸惑う彼の背中にそっと手を添えて言う。「何か、大変なことが起こってるのですね。すぐに向かってください。でも、気を付けて…。」 その瞳が心配そうに揺れている。藤森はゆっくりと頷くと、彼女を以前であった交差点まで送り届けた。「あの、詩織です。私、詩織と言います」「私は藤森という。あわただしくてすまないね。気を付けて帰るんだよ。じゃあ」 そのまま車に乗り込むと、藤森はすぐさま奥平の事務所に向かった。それを見送りながら、詩織は茫然と呟いた。「藤森、涼…。あの人が…。あれ?私、ちゃんと名乗ったかしら…?」つづく
November 14, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード14
エピソード14「時に本田君、最近狩野君とは仲がいいそうだね」「狩野さんですか? どなたでしょう?」「おや?もう何度も酒を酌み交わしていると聞いているんだが、違ったの?」 教授と弁護士は頭の上にはてなマークを浮かべて見つめ合う。それを見ていた藤森がくくっと笑う。「ミスターK、と言ったら分かるんじゃないですか?」 途端に本田の目つきが変わった。「なっ!あんのキツネじじい…。まさか教授と繋がりが?」「ああ、私の親友だよ。言ってなかったかなぁ。彼はIPIEOと言って、汚職や不正を働く国や政府を摘発する国際的な組織の一員なんだよ。まあ、その手伝いというかね。趣味だな、これは。はっはっは。」 眉尻を下げて楽しげに笑う教授は、本田には狸に見えていただろう。「藤森君も知っていたのか?」「ええ。私もお手伝いを。推理小説を読むよりリアルで、体験型アクションゲームって感じがよくて。研究詰めになると、どうも視野が狭くなるのでね。リハビリですよ」「!!」 目を見開く本田を見て、しれっという藤森は、ふと何かを思い出したように奥平に声を掛けた。「仁、どこの病院? 後で結果が聞きたいな」「ああ、僕もそれを頼もうと思っていたんだ。学生の彼に薬物がかかわってるなんて、恐ろしいよね。最近、身近でも聞く話なんだよ」 美月も顔をしかめて言う。「ああ、知り合いの病院だから頼んでおくよ。」「まさかとは思うが、エルアルド辺りから流れてきているとしたら問題だな」 誰に言うともなく藤森がつぶやくと、奥平はじっと考えを巡らせてはっとした。「もしかして、あの工場か?」「私の推理が正しければね。ここはミスターKの力を借りよう。それから、もう一度ノーザンディに行くことになるかもしれないな。デ・ボーノ氏と情報共有しておこう」「あのぉ…」 応接室にそろりと顔を出した牧野が、申し訳なさそうに声を掛けた。「藤森さんにお電話です。」「あ、うーん、そうか。」 藤森が出ると、第一秘書の三木から淡々とした声が聞こえてきた。「本日午後には出社されると伺っておりましたが、ご予定は変更ですか?すでに、各方面の会議への欠席は連絡しましたが、本日中に仕上げていただく論文と各方面からの質問への回答の期限が迫っております。本日はご帰宅いただけない可能性がでてきましたが…」 藤森は瞑目し、三木の流れるような説教を受け入れると、すぐに帰ると答えた。「藤森君、また無茶なスケジュールを組んだんだろう?」「涼、あきらめろ。ノーザンディへは来月にも行く予定だから、様子を見てくる」 軽く肩を落として、藤森は席を立った。「美月、例の通信機器、早急に作ってくれ。このままでは身動きが取れん」「分かったよ。あと少しなんだ。出来たら届けるよ」 名残惜しそうに帰っていく後ろ姿を、くすっと笑いながら見送ると、美月はその場にいたメンバーにも、通信機器について説明を始めた。「美月君、それ、私の分も頼みたいんだが」「ええ、もちろんです。牧野君の弟のこともありますから、存分に働いてもらいますよ」 さらりと金髪を揺らして微笑むが、ブルーグレイの瞳は笑っていない。本田はそれに気付いてゾクっと背筋を凍らせた。「では、私も狩野君と連絡を取っておこう。他国の事だから、私たちにとやかく言う権利も義務もないんだけどね。いやなんだよねぇ。こういうやり方をする連中は。」 世間話でもするように、篠原は軽くため息をついた。「美月さん、お電話です」「ああ、見つかっちゃったか。」 電話口でスケジュール調整をする美月は、先ほどの藤森と同じパターンだ。どうやらこちらも秘書にいろいろ指摘されているらしい。本田は取り澄ましてはいるが、自分より忙しい彼らの趣味に、驚いていた。 美月と入れ替わるように玄関で人の気配があった。研究員が対応すると、女性がやってきた。冴子だった。「やっぱりここだったのね。直接現場まで送るわ。」「あ、冴子か。仕方ねーな。じゃあ、教授、先輩、お先に」 部屋を出る奥平に続いて、冴子がドアノブに手をかけて、すぐに振り返る。「新之助、例の件は?」「ああ、直接奥平君に伝えたよ」「そう、たまには役に立つのね。ふふ」 そう言って、悔しがる本田を置いて、さっさと部屋を出た。つづく
November 12, 2022
コメント(0)
-
うわ~ん
小説!!どうなってんねん!!と、自分に突っ込み入れながら日々過ごしております。ええ、ホントになかなか進みません。ごめんなさい。小説を書くって、心に余裕がないと書けないものなんですね。原稿の続きを開いても、「・・・」あのイベントの準備、大丈夫だっけ?とか今度の会合の資料、抜けてないかな?とか去年はコロナの影響でほとんどできなかったイベント系のお仕事。夏ごろに、やりませんかぁ~って営業していたのが花開いて・・・というと聞こえはいいけど、自分で自分の首を締めましたね。はい、その通り。今月来月はえらいこっちゃになりそうです。だけど、そういう時ほど、新しいアイデアが浮かんだりするしなぁ。。。なんて、勝手な期待もしちゃったりして。。 まぁ、がんばって隙間狙って書き進みます。どうか、見捨てないでぇ~~
November 11, 2022
コメント(0)
-
ひえ。
やばいです。とうとう執筆が追い付かれてしまいました。うう~~、ここからの掲載は、カタツムリ並みになると思われます。気長にお待ちください。。
November 8, 2022
コメント(2)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 13
エピソード 13「いい子だね。」「仲のいい姉妹だったんでしょうね」 しみじみと見送る篠原に相槌を打っていた本田が、自分もそろそろと席を立とうとした。「先輩、ちょうどいいじゃないですか。これから情報共有をしようと思っていたんです。先輩の手持ちのカードも出していただけませんか?」「え?私はなにも持っていないよ。」 うそぶく本田の肩に手を回して、微笑む藤森がそのままソファへと本田を誘う。「君、副業でホストかなにかやってる? 誘い方がうますぎるよ」「なんとでも。貴絵の事件で萌絵さんからもう聞き出す必要が無くなったって話でしたよね。その辺り、詳しくお願いしますよ、先輩」「本田先輩、冴子からもある程度聞いていますよ。あ、申し遅れました、俺、冴子さんの勤務先であるOSOの代表兼医師の奥平です。」 滑稽なほどに驚く本田を二人の後輩がにやにやと笑みを浮かべて見つめていた。「ああ、本田君は奥平君とは初対面だったね。」してやったりとニヤつく老人を、本田が睨む。そこに、軽い足どりの美月がやってきた。「ごめんね、遅くなっちゃって。あれ?老人にコーヒーを淹れさせる先輩じゃないですか?お久しぶりです」 ここぞとばかりにきらびやかな笑顔を見せる美月に、本田はあきらめたように腰を下ろした。「それでどんな情報をお持ちなんですか?」「そういえば、先輩はあの一宮製薬社員殺しの事件を担当されているんですよね?あの犯人、分かったのですか?」 藤森と奥平がジワリと詰め寄ると、本田は居心地悪そうに咳払いした。「君たちだから言うが、こういうことには秘守義務というものがあってだね…」「ああ、分かっています。この研究所ではそういうの無しでお願いしますよ」 弁護士としてあろうとする本田に、美月が邪魔くさそうに言い募ると、深いため息とともに本田は語り始めた。「まあ、私が担当していた嘉村実里の事件が元だったんだが、その被害者である佐藤静流が一宮製薬社員殺しの犯人だった。どうも薬物死に以前から興味を持っていたそうだ。そこは藤森君が知っているだろ?」「ええ、そうでしたね」 藤森が頷くのを見て続ける。「冴子から、つまり姉から勤務先の、これは奥平君の患者のことでよかったのかな?調べてほしいと連絡が来て、それがカームリーの王女のことだったんだが。そこから近隣の国についても少し調べてみたんだ。すると、どうもきな臭い状態だと分かってきてね。先日藤森君から、佐藤がサイエン王国に留学していたと聞いていたんで、ノーザンディあたりと佐藤が繋がっていなかったか調べてもらったんだよ。まあ、ここはいくつかある可能性を潰していくぐらいの気持ちだったんだが。すると、ノーザンディの政治家の息子と繋がりがあったことがわかった。どうやら諜報員として活動していたらしい。」 奥平が藤森に視線をやると、納得したような顔が返ってきた。その横で、いつになく真剣な表情の篠原が頷いている。「だけど、どうしてノーザンディの諜報員が製薬会社の一社員を狙うんだろう」 これまであまり関われていなかった美月が首をかしげる。「ああ、それなら、一宮の新薬って言うのが、患者を一時的な脳死状態にしながら、細胞を維持できる薬だったからだ。ノーザンディはまだまだ内紛が続いていてな、先日私も行ってきたが、王宮内が大統領派と側近派に分かれていて、予断を許さない状況だった。あんな薬を手に入れたら、証拠も残さずにあっという間に今の政府を転覆させるだろう」 確かめるように見つめる後輩に、深いため息で返事をすると、藤森は美月からの情報を促した。「僕からの情報はさっき電話で話した通りだよ。橘製薬の社長の息子があの街中での通り魔事件の犯人さ。しかも、本当に狙っていたのは貴絵一人だ。自分との縁談に乗ってくれなかったというのが理由だそうだ。調べてみると、慣れない株に手を出してしくじった挙句、会社の金に手を付けてあっさりすってしまったってことだったよ。まさかとは思うけど、結婚したら相手の財産も食いつぶすつもりだったんだろうか。まったく、生産性のかけらもないね。」「そんな奴にあの子は殺されたのかい?」 篠原は、すっかり冷めたコーヒーをじっと見つめていた。場の空気がぐんと冷え切ったその時、急にバイクの音が聞こえてきた。研究所の前でエンジン音が止まって、一同がドアの方を見ると、ライディングスーツに着替えた萌絵が興奮気味でやってきた。「あの、さっきの研究員の人を呼んでください」 隣の研究所から見えていたのか、牧野が慌ててやってくると、萌絵はバイクの後ろを指さした。「あれです!迷惑ですので、お引き取りください!」「健二?! あの、いったい何があったんでしょう?」 後ろ手に縛られ、膝を曲げ蹲るように縛られて、バイクの荷台に荷物のように括りつけられた男が窓越しに見え、牧野はうろたえて尋ねた。「ずーっとストーカーされていたんですが、今日、私を拉致しようとしたので、逆に拉致仕返ししてみました。」「拉致だって?なんでまた…」 驚きすぎて頭が回らない牧野に、いらだった様子で萌絵は言う。「ああ、なんでも新薬のデータがどうとか言ってましたよ。親の家業だからって、なんでも知っているわけないのに。」 それを聞いた藤森たちは一斉に立ち上がった。「で、そいつはまだ生きているのかい?」「そこのバイクに括り付けてきました。たぶん生きてると思うけど…」 大胆な割にアバウトな彼女に苦笑いして、奥平が駐車場に向かうと、さるぐつわされた口からうーうーと何か文句を言っている健二がいた。「それで、君の弟君は、サイエン王国辺りに渡航歴はあるのか?」「ええ、高校生の時に交換留学で行ってましたが、それが何か?」 状況が呑み込めないうえ、意図が分からない質問に牧野が答えると、、藤森は納得したように頷いた。その時、駐車場から奥平が牧野に声がかかった。「あ~、大丈夫だな。で、牧野君、どうする?警察を呼ぶ? それとも、病院に連れて行く?」「薬物やってそうだから、まずは病院がいいんじゃない?」 ちらっと後ろから様子を見ていた美月がアドバイスすると、ロープをほどきながら、牧野も困り果てたまま頷いた。「もし、伝手がありましたら、お願いします。それにしても…」 改めて健二を見ると、あちらこちらに殴られた後があった。そっと萌絵に視線をやると、萌絵はぷいっとそっぽを向いた。「い、いきなり私を誘拐しようしたんです。正当防衛だと思います!」「ん?まえに貴絵が自慢してたよなぁ。妹は黒帯なんだって。いつでも守ってくれるんだって…」「コホンっ、気のせいです。とにかく、そちらに引き渡しましたから。被害届は出さないでおきます。私からのお願いは、二度と私の前に顔を出させないこと。それだけです。では、失礼します。」 それだけ言うと、萌絵はさっさと帰ってしまった。再び見送る篠原は、眉尻を下げてつぶやいた。「貴絵さんも魅力的な人だったけど、彼女もとても興味深いね。」「俺の知り合いの病院を紹介しようか。」 しんみりする老人をよそに、若者たちは動き出した。奥平の紹介で健二の行先は決まり、背後の状況を調べるため、明智署の山田と本田が連携することになった。牧野が病院に弟を連れて行くと、研究所は落ち着きを取り戻した。つづく
November 8, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 12
エピソード12 笑い合う二人が日本に降り立った時、呆れたニュースが飛び込んできた。「なんだって? じゃあ、貴絵たちを殺した犯人は橘製薬の2代目だったのか?」「ああ、そうなんだ。しかもお見合いの話を蹴られた腹いせだっていうじゃないか。温厚な僕でさえ、久々に殺意を覚えたよ。もちろんコンサルの話はお断り。もうすぐ倒産だね。あのバカ、父親の会社の金で株をやってたらしいが、大損を喰らった挙句に、貴絵との見合い話が流れたもんだから、自暴自棄になってやったって自白したらしいよ。本田さんが、警察の知り合いから聞いてきたから間違いないって話だよ。はあ。」 電話の向こうでは、珍しく息の荒い美月が盛大なため息をついている。「ちょっと情報の整理が必要だな。美月、今から時間はあるか?」「ああ、時間なら作るよ!最優先事項だ!」「では、いつものバーで…、いや、この時間なら、まだ教授がいるかもしれないな。研究室に行ってみるか」「分かったよ。今から向かうね」 研究室の扉を開けると、若い院生が顔を出した。「あ、もしかして、藤森先生ですか?! この前テレビで見ました!」「はは、涼は有名人だな。」 藤森は、少したじろいだ様子を見せたが、すぐに教授を呼び出した。場慣れした様子で応接室に向かう二人を見て、院生はそそくさとコーヒーを淹れて持ってくる。「あの、お二人はここのOBなんですよね? 僕、すごく尊敬しています」「ははは、牧野君、今日はラッキーだったね、憧れの人に会えて」 後ろから篠原が楽し気にやってきた。「教授! コーヒー淹れますね」「ああ、頼んだよ」 嬉しそうに給湯室に入っていく後ろ姿に、貴絵を重ねてか、篠原はふと寂しげな表情になる。「教授、お久しぶりです。貴絵のことで新しいことが分かったというので、ここで情報整理をしたいと思ってやってきました。お時間、ありますか?」「ああ、時間は作るものだよ。で、犯人が分かったということかな?」「もうすぐ美月もやってきますので、お待ち…」 藤森が言葉を途切れさせたので、みなはその視線を追った。「貴絵…いや、失礼。一宮萌絵さん、ですね。」「失礼します。あの、今日は本田弁護士とお会いすることになっていて…。」 たじろいだように言葉を紡ぐ萌絵に、藤森は穏やかに微笑みかけた。「私たちは、貴絵さんと一緒に研究を進めていた仲間なんです。葬儀の時は、ゆっくりお話もできなくて、失礼しました。 私は、藤森と言います。ちょうどいい、どうぞこちらに座って。」「俺は、奥平。俺も貴絵と同期だ。もうすぐ一年後輩の美月も来るぞ。俺たち4人でチームになって研究していたんだ」「そして僕がここの研究所の所長をしている篠原です。よく来てくれたね。貴絵さんはここのマドンナだったんだよ。真面目で誠実な彼女は、みんなに愛されていた。本当にどうしてこんなことに…」 教授が肩を落とす姿はあまりにも寂しかった。萌絵はどう振舞っていいのか、途方に暮れていたが、その哀れな姿を放置できなくて、とっさに肩をさすっていた。「やはり姉妹だな。気遣いが貴絵とよく似ているね」 意外な言葉に声の主を改めて見る。有名ブランドのスーツに髪を後ろに流した藤森という男は、きっと姉の想い人だ。姉から聞いたことなど一度もなかったが、萌絵にはすぐに分かった。研究室をゆっくりと見まわし、萌絵は大きく深呼吸してみた。「ここに来るとき、姉さんはいつも楽しそうでした。そっか、こんなに素敵な人たちに囲まれていたんですね。やっぱり姉さんって、すごいな」「彼女がいるだけで、この空間がとても居心地よくなるんだよ。ここが彼女の席だ」 教授がそっと席に寄ってそのイスをさすっている。それを見つめながら、萌絵の視線は遠くを見つめていた。「君だって、きっとそんな風になれるよ。まずは夢中になれる物を探してみるといい」「ああ、そうだ。貴絵はああ見えてオタクだったからな。大好きな物はものすごい勢いで調べまくっていたな。特に甘い物にはうるさかったなぁ」「そうだったね。彼女のフィナンシェは最高においしかった」 奥平が茶化すと、篠原も思い出したように懐かしむ。「そうだ、牧野君、彼女にもコーヒーを淹れてくれないか?」「はい、了解です」 通りかかった研究員に声を掛けると、萌絵はその人物を見てはっと体をこわばらせた。「どうかしたの?」 篠原が気遣うが萌絵はうまく言葉を発せられない。ここは姉の通っていた大学院だ。自分の通う大学ではないのに、どうしてあの人がいるの?混乱する萌絵に牧野は笑顔でコーヒーを差し出した。「あの、もしかして弟の知り合い? 3つも年が違うのに、よく双子かって言われるんだよね。弟が迷惑かけてるなら、僕に言ってね。しっかり言い聞かせるから。まあ、あいつコミ障だから、声もかけられてないだろうけど」 牧野は軽く笑って退室した。入れ違いに入ってきたのは本田だった。「今日は随分にぎやかだな。あれ、藤森君たちも来てたの?」「ええ、まさか本田先輩がおいでになるとは知らず。お陰で貴絵の妹さんとも話が出来て、今日は有益でしたよ。」 遅れて来たらしい本田は、すっかり出鼻をくじかれた様子で肩を落とす。「一宮さん、今日はこちらに足を運んでもらって悪かったね。調査が急展開してね。君に聞き出そうとしていたことが概ね分かったから、今日はお詫びにこちらを案内しようと思っていたんだが、どうやら私はすっかり出遅れてしまったようだね。私の優秀な後輩が君にいろいろ説明していたようだし」 めげずに弁護士らしく言い訳するのを見て、萌絵は思わず笑っていた。「はい、そうですね。こちらの皆さんにいろいろ教えていただきました。本田さん、今日こちらに呼んでくださって、本当にありがとうございました。姉がどんなふうに亡くなったかということより、どんな風に生きていたか知ることが出来て良かったです。」 萌絵は着た時とは別人のように明るくなって帰っていった。つづく
November 7, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード11(後半)
翌日は、エルアルドがつきっきりで工場見学を行った。大規模工場の割にお粗末な生産ラインに、なにも気づかないように感動して見せる藤森に、奥平は笑いをこらえるのに必死だった。「いやぁ、今日は感動の連続だったよ。まさか大統領の側近であられるエルアルド氏自らご招待くださるとは思わなかったな。」「さっきの試食もうまかったな。さすが酪農の国だ。ん?ああ、失礼。」 すっと顔をそらす奥平を冷静な顔で見つめる藤森は、そのまま奥平の首筋に手を当てて驚いた。「おい、熱があるぞ。どうした?」「いや、少し疲れが出たのかもしれん。今日はこのまま部屋で休ませてもらってもいいだろうか」 エルアルドはとっさに距離を取るが、何事もなかったように了解した。「何か、必要な物があればお申し付けください」「悪いな。では、氷枕とタオルを。それから水をピッチャーに多めにお願いしたい。日本で蔓延しているあの病気でなければいいんだが…」「承知しました」 エルアルドは早々に引き上げていった。後でやってきた侍女に、夕食を部屋で食べたいと申し出て、念のため部屋には入らないようにとくぎを刺す。「了解いたしました。私は、アルバーニ大統領より直接指示を頂いておりますベスと申します。お出かけの時間が決まりましたら、外への通路をご案内します。」「なるほど、それは有り難い。早々に行動したいので、今からいけるか?」 ベスはすぐさま頷いて、二人を客室のウオークインクローゼットへと案内した。大きな棚を手前に引くと、扉が現れた。その奥はどうやらクーデターなどがあった時の避難路になっているらしい。「こちらへ」 足早に案内するベスは、侍女らしい服装ながら、どうやら護衛のようだ。しばらく細い通路を行くと、小さなドアが見えてきた。そこをくぐると、貴賓館の北側の庭園のガーデニング倉庫へと続いていた。「この時間でしたら、ここが一番人気がありませんので、お気をつけてお出かけください。こちらは感染症かもしれないと伝えて侍女共々遠ざけておきます。おかえりは先ほどの通路をお通りください。」 それだけ言うと、ベスはすぐさま客室へと戻っていった。それを見送った藤森がぼそりと呟いた。「できるな」「うん、可愛かったな」「え?」「え?」 相変わらずの奥平に、笑いが漏れる藤森だった。 デ・ボーノの邸宅へは、意外にもすぐに到着した。ベスからも連絡があったのか、二人はすぐに中に通された。「奥平先生!よくぞお越しくださった!」 ドアが開くなり、実直そうな中年男性が歩み寄り、奥平の手をヒシっと握り締めた。そして、早速に奥の間へと案内した。「急な申し入れですまなかった。こちらは俺の大学院の仲間で脳科学者の藤森だ」「よろしく」 すんなりと握手するのは、奥平の信頼が厚いことに他ならない。「デ・ボーノさん、体調が優れないと聞いたが、その後どうだ?」「あちらではそういう事になっているのですか。体調など、問題ありませんよ。すべてはエルアルドによって仕掛けられたこと。そんなことより、もし、お二人が自由に他国を移動できるのであれば、どうかカームリー小国とラバリー帝国の様子ご教えていただきたいのです。エルアルドはどうやらあの2国を戦わせて相打ちにさせ、弱ったところを狙っているようなのです。」 座るなり矢継ぎ早に語られた内容に、奥平が眉を顰める。「あの野郎、一枚噛んでいやがったか」「ラバリーの第二王子、ホルガ―だったか。彼には一度会ってみないといけないな」「今度はナイフを向けられないようにしないとな」 二人の言葉に驚きながらも、デ・ボーノは続ける。「ほかにも、我が密偵の探ってきたところに寄りますと、先生方の国に手を回していたという話もありました。なんでも新しく開発された薬を狙っていたようで、日本人留学生をうまく利用しようとしていたようです。ただ、そちらはその後の進展がないようなので、失敗に終わったのかもしれませんが。」「新薬か…。思い当たる事件はあったな」「たぶん、その新薬を手に入れることはできなかったでしょう。しかし、十分に注意してください。健闘を祈っています。」 デ・ボーノはこれから大統領と密談しながら復帰を目指すと笑った。二人はあまり時間をかけられないこともあって、早々に引き上げたが、充実した時間となった。 飛行機が飛び立つ。高度を上げて安定したところで、奥平が尋ねた。「ずっと気になっていたんだが、どうしてエルアルドは慌てて会談の場を離れたんだ?」「え?ああ、極弱い威力の花火を仕込んだ手紙を自宅に送ったんだ。開封するとぼふんと煙が出るようなおもちゃだな。まぁ、疚しい奴ほどそういう事には敏感だったりするからな」「… 涼、なかなかやるな」 奥平はククッと笑いをかみ殺した。「それにしても…」と藤森は呆れたようにつぶやいた。「まさかあのエルアルドが日本に手を回していたとは驚いたな」「一宮製薬の新薬が狙いだったんだろ?あんなものが奴なんぞに渡ったら、あっという間にこの国は牛耳られてしまう。」「まったくだ。まぁ、そのあたりは本田先輩辺りが調べていそうだな。ミスターKは適材適所がお得意だ。」「そうだ、前から聞こうと思っていたんだが、そのミスターKとはどういう人物なんだ?」「IPIEOつまり、国際的な政治的不正を暴く組織のメンバーだ。篠原教授の親友だそうだ。」「だけど、涼は脳科学の第一人者になっているわけだろ?そういえば趣味で不動産も扱っていたよな。その上この仕事か?」「いや、これは趣味だ。研究室だけでは新しい発想は出てこないからな」 奥平は以前藤森のマンションに寄った時に見た、奇怪なオブジェの数々を思い出した。「つまり、この仕事を理由に研究を抜け出して、交通費向こう持ちで珍しい国々をめぐるというご褒美をもらっているのか」「仁、最近察しがよくなったな。うん、脳内がよく活性化している。シナプスも増えているんだろうな」「おいおい、俺の脳みそをおもちゃにするんじゃない!」つづく
November 6, 2022
コメント(0)
-

淡路島
今日は、家族で淡路島まで行ってきました。コスモスが咲き乱れるここは「花さじき」というところです。お花の向こうには瀬戸内海、そしてその向こうには本州も見えています。どこまでも青い空ぽっかりうかんだまんまるの雲がキュートでした。さて、小説の続きを書かねば…
November 5, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード11(前半)
エピソード 11乾いた荒野に西風が吹き渡る。枯れた牧草の束が、ころころと風に流されていった。街を行き交う人々がバンダナを口に当てたり、日傘を持つのは、この西風による砂埃を防ぐためだ。サイエン王国の北に位置するこのノーザンディという国は、元は酪農と農業が盛んな国だった。のんびりとした風土で、山も美しく四季を彩っていた。しかし、30年ほど前に数年続いた干ばつとそれによって税の取り立てが厳しくなったラバリー帝国からの難民という名の野盗によって、この国はすっかり様変わりしてしまった。なんとか国としての体裁は保っているものの、現れては蹴散らされる反逆者や暴動で、酪農も農業も廃れていった。ノーザンディの首都に近いターランという空港に、藤森は降り立っていた。数年前、サイエン王国に研究所を建築中にも一度この国には来ていたが、その荒廃ぶりは着実に進んでいると言える。「ミスター藤森か?」 背後から、フードを目深にかぶった怪し気な男が声を掛ける。振り向くと男はフードを外す。口と鼻をバンダナで隠し、サングラスをつけた男の目じりが笑っていた。「仁!脅かすなよ」「はは、ちょうどカームリー小国の手術が終わって一息ついたところなんだ。ついでにノーザンディの大統領の経過観察に寄ったら、補佐官から涼が来ると連絡をもらってね。こっちだ」 奥平は慣れた様子で車の送迎スペースへと進む。しかし、その後ろ姿からは何かを伝えたくてうずうずしているのが分かり、藤森は水を向けてやることにした。「仁、車内で話を聞いてもいいか?」 振り返った奥平は、待ってましたと言わんばかりの笑顔だった。 待たせていたリムジンは防音設備が整った動く会議室の様だった。車が走り出すと、奥平はさっそく今回のカームリー小国の手術の話を始めた。「まずは最近俺に入っていた手術のスケジュールについて話しておこう。先月はとある国、とりあえずLという国としよう。ここの要人の性転換手術の予定があった。男性から女性へというやつだ。そして、先日終えたのがK国の要人の中絶手術。この二つ、ほぼ同じころにオーダーが来た。」「どちらも要人ってことは王族とか…」 藤森が探るように言うと、奥平は視線だけで肯定した。「それが、隣接する国で、しかもにらみ合いしているって状態だとしたら、どう思う?このLって国…ああ、もうじゃまくせー!」「ははは、ラバリー帝国だろ?」「ご名答!あの国は今、内紛も起こっている。カームリー小国にサファイアの鉱脈が見つかったのは知ってるだろ?あの山岳地帯がぎりぎりラバリー帝国との国境に位置するんだ。ラバリーの軍部は侵略を狙っていて、王族は戦争より穏便に血縁を進めようとしていたんだ。ラバリー軍は血の気が多い。王族と対立してもう随分になるらしい。王様にも面会したが、憔悴しきった様子だった。」 黙って聞いていた藤森は呆れたように言う。「で、王太子はすでに結婚しているはずだから、第2王子あたりが先走ってカームリーの姫君にちょっかいかけたってことか?」「だろうな。軍を出し抜いてやろうとカームリー小国の夜会にこっそり参加して、その気にさせるつもりだったらしいが、本人と会ったら、ずいぶんと自分好みでがまんできなかったとかじゃねーの。」「… サルか」「サルだな」「くだらん!…で、余計な事をした王子が犯罪者と言われるわけにはいかないから性転換手術なのか?それはあまりにも稚拙な考えじゃないか?」「だよな。そうでなくてもまだ確立されていない手術を、本人の了承無しにやらされるところだったんだぜ?当の本人がおかしいと気付いて看護師を問い詰めたらしい。で、俺が手術室に入ったら、いきなりナイフを突きつけられた。まったく、ヤバかったなぁ」「仁、仕事は選んだ方がいいぞ」 奥平ははぁっと大層なため息をついた。仕事の選択はほぼ冴子に握られているのだ。「まぁ、依頼主に成功する確率が低い手術だと伝えたときに、失敗したらそのまま亡き者にしろと言われたって話したら、随分ショックを受けていた」 安定した国を持続させることは、簡単な事ではないのだろう。藤森は窓の外に広がる青い空と砂埃の舞う荒野を眺めながら、哀れな王子の行く末を想った。「ところで、このノーザンディも落ち着かない状態なんだろ?」「ああ、そうだな。だが、このところ暴動もないし、大統領が大けがをしたことで、少し鎮静化しているようだ」 それを聞いても、藤森の表情は曇ったままだ。「そもそも内紛を起こしているのはどういう勢力なんだ?」 奥平は再びため息をついた。その辺りはさっぱり分からないらしい。話しに夢中になっている間に、車はノーザンディの貴賓館に到着した。この建物は、外交関係の来賓の宿泊施設兼応接ホールになっている。 車を降り立った二人を出迎えたのは、大統領の側近、エルアルドだ。無表情なエルアルドは、ちらっと奥平の隣に立つ男を盗み見たが、そのまま二人を客室に案内した。「滞在中はこの部屋でお過ごしいただくよう、言われております。しばらくこちらでおくつろぎを。外出されます際は、お申し出ください。護衛をつけさせていただきます。夕刻には大統領との面会を予定しておりますので、お知らせに上がります」 そういうと、侍女に指示を出して、そっと退室していった。その後ろ姿を見送ると、侍女たちはすぐに二人に紅茶を淹れ、控えの間へと向かった。「ねえ、君。ちょっといいか」 客人に急に声を掛けられ、侍女の一人が向き直った。「さっきの人は、大統領の側近だと聞いたけど、もう長いことその職務についているのか?」「いえ、2年前からになります。」 藤森の落ち着いた風貌から安心したのか、侍女は素直に答えた。「俺は、数年前の暴動で大けがをしたアルバーニ大統領を治療した奥平だ。あの時の側近はどうしている?あ、いや、とても世話になったんでね。今日は会えると思っていたんだが」 一瞬怪訝な顔になった侍女も、話の流れが悪くないと分かると、穏やかな笑顔で答える。つづく
November 5, 2022
コメント(0)
-
どうしてでしょう。
10月後半、私はこのブログでつぶやいていました。小説家になろうというサイトで、自分の小説の閲覧数が1つの作品に限りですが、毎日35名ほどが同じ時間に見に来ると。それが不思議だと呟いたのです。そうしたらね、どういうわけか、このサイトの閲覧数がガタ下がりしているのです。いや、そりゃね、そんな大したものを掲載してるわけじゃないし、見に来てくださるだけでうれしいのですよ。ああ、まだ読んでくれる人もいるんだ。。なんて思いながら、小説書き書きするわけですよ。だけどこれもまた不思議なんですよね。あ、ちなみに、小説家になろうの方はまだ続いています。閲覧数の多い作家さんなら、気づくこともないんだけど、私のような弱小物書きの場合は目立っちゃうんですよねぇ。
November 4, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード10(後半)
「まだ、わが社との契約をしているわけではないので、皆さんに教えて差し上げることはできませんが、今日見られたこの現場で、もしなにか得る物がありましたら、幸いです。」そう締めくくると、そっと立ち上がった。「では、地下のショットバーにお連れします。今日はお金を頂きませんから、カクテルでも飲みながら、店内での準備の様子なども見て行ってください。」「おお、やった!」 とたんに勢いづく男性社員に、地味な受付嬢は小さくため息をついていた。 ショットバーはまだ開店前ということで、テーブルやイス、家具などが丁寧に掃除されていた。今日は特別という事で、すでに掃除の終わったバーカウンダ―に彼らを座らせ、バーテンダーが希望のカクテルなどを提供した。 静かに飲み物を提供するバーテンダーとは別に、他の店員はいまだグラスの一つ一つを丁寧に磨き上げている。橘製薬の地味な受付嬢志保は、その仕事ぶりに感動していた。「私、お客様には誠心誠意丁寧に対応しようと思っていましたけど、まだまだダメでした。ここに呼んでいただいて、本当に勉強になりました。ありがとうございます。」「はは、志保ちゃんはまじめだねぇ。こんなの社長からの福利厚生だと思えばいいのに」 志保とは反対に、楽し気に過ごしていた営業の多田が、カクテルを飲み干して笑い飛ばす。そして、さっさと次のカクテルを注文すると、したり顔でしゃべりだした。「うちもさ、新薬が出せたらいいんだけど、くそ真面目な研究員はうちのアットホームな雰囲気になじまなくてね。みんな辞めちゃうんだよ。何が気に入らないんだろうね。だいたいは、一宮製薬に流れてるんだ。あいつら、うちで新薬作ればいいのに、ちゃっかりあっちで新しい薬を作ってやがった。国の許可も下りたらしいし、また一宮に出し抜かれたよ。しかもヤバい薬なんだろ?どこだっけ、外国のノーザンなんとかってところも狙ってたって話でさ。俺、社長がどこかと電話してるの聞いちゃったんだよ」「でもさ、若が一宮のご令嬢と結婚してたら、うちも万々歳だったのに、あんな事件で死んじゃうなんて、残念だったよね。若だったら絶対落とせたと思うのに」 バーに行き慣れているのか、リラックスした様子で答えるのは、もう一人の受付嬢だ。酒が入ると、饒舌になる二人はわいわいと居酒屋トークに花を咲かせる。「あの、そういう話はやめませんか?今日は他社さんにお邪魔しているのだから、まずいですよ」 まだ若い男性社員が、心配そうに声を掛けるが、二人は小ばかにする。「さぁ、そろそろお開きにいたします。こちらの店も本格的に開店準備に入りますので。もしご希望でしたら、開店後にお客様としていらしてください。」 榊は爽やかに微笑んでいるが、バーテンダーに目配せする。バーテンダーは軽く頷くと、次々目の前に水の入ったグラスを置いていく。「本日はお疲れ様でした」 店員の一人がドアを開け、彼らが退店するのをじっと頭を下げて待っている。それに気づいた志保が、大急ぎで会社の仲間の背中を押した。「榊様、本日はお忙しい中お時間を頂きまして、ありがとうございました。また数々の失礼がありましたこと、お詫びいたします。」「いえ、お気になさらずに。失礼ですが、お名前を伺っても?」「はい、受付嬢をしています三田村志保といいます。」 榊は初めて本当の笑顔になって、志保の耳元でささやいた。「もし、転職を考えられるなら、いつでもお声かけください。本日は誠にお疲れ様でした」 驚いた顔の志保を、橘製薬の仲間が早く来いと呼んでいる。それを確かめた後、榊はそっと店内に戻っていった。*****「もしもし、林君? 美月です。涼さんの行先、もしかしてノーザンディだったりする?」「えっ、な、なぜ?」 うろたえる声にクスっと笑みが漏れた。林は藤森の第2秘書だ。真面目で良くも悪くも素直なところが美月に気に入られている。「ねえ、それって篠原教授からの依頼?」「いえ、教授の古いお知り合いだとかで…。あっ!」「ふふふ。気にしないで。どうせ教授から吐かせるつもりだったから」「吐かせるって…」 焦る林をよそに、目まぐるしく思考を回す美月は、瞑目する。やはり彼らに無線機かポケベルだけでも持たせるべきだったのだ。榊から橘製薬の社員の話を聞いて、一宮製薬を狙っていたのは橘製薬だけではないということはすぐに分かった。マンションで一宮製薬の社員が殺害されたニュースで気が付くべきだったのだ。いや待て。それなら次に危険なのは貴絵の妹ではないだろうか?「もしもし…、美月さん? どうされました?」「あ、いや。失礼。涼さんから連絡があったら、こちらにも連絡をくれるように言っておいてね」つづく
November 4, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム 10(前半)
エピソード 10「失礼しまーす。このお茶、おいしいんですよ。今日は営業の田中さんのお土産付きです」「せっかくですが、私は商談に来たのです。親戚の家に遊びに来たのではありません。こちらに構わず、ご自身のお仕事に戻ってください」「はぁ…。」 谷村は、驚いてそのままおずおずと部屋を出た。「どうされますか?」「いや、すまない。君が緊張するかと思って、軟弱な姿を見せた。失礼したね。」「橘製薬は、ここ数年で業績は悪化しています。新薬の発表もありませんね」 鋭い指摘にわずかにため息をついて橘は答えた。「まさにその通りだ。優秀な研究者を入れたのに、数か月でみんな違う会社に行ってしまう。社屋を新しくして、研究室も最新のものにした。どんなに温かく迎えても、この会社に落ち着いてはくれないんだ。新薬なんてとても手が届きそうにない状態だ。だが、ここまで一緒に頑張ってきた社員を切り捨てることもできないんだ。」 ふっくらとした手を握り締めて訴えるが、美月には響かない。「だれも切り捨てろとは言っていません。ただ、教育もしていないですよね。これは経営者の責任ですよ」 その時、後ろに控えていた榊が控えめに声を掛けた。「社長、申し訳ございませんが、お時間です」「そう。では、今後、どうされるか再考してください。僕はこれで失礼します」 橘が驚いていると、榊が申し訳なさそうに言う。「橘社長、申し訳ありませんが、美月社長は予定が詰まっていますので、これで失礼します。契約については、後程事務所にご連絡ください。」「そ、そうか」 会議室を出て1階に戻ると、一気に女子社員が騒ぎ出す。「橘社長、もし良ければ一度どなたか数名、うちの店に見学に来てもらうのはどうですか?僕もスケジュールが詰まっていてそんなにこちらに頻繁には来れないでしょう。自ら学びたいという気概のある社員さんなら歓迎しますよ。」 美月の言葉に、わぁっと女子社員たちが色めき立つ。「あ、ちなみに僕はその場にはいませんよ。榊がご案内します」「検討するよ。」「では、失礼します。」 女子社員たちのじっとりとした視線をものともせず、美月はさっさと車に乗り込んだ。「コンサルなんて言うからどれだけ経営に長けているのかと思えば、ちゃらちゃらしやがって。誰も行くわけがないだろう…」 車が去るのを見送りながら、好々爺の顔を残したまま橘は毒づくが、振り向いた先には、意欲満々の社員たちが手をあげるべく待ち構えていた。 数日後、じゃんけんで勝ち取ったという数人が、美月の店にやってきた。時間は開店前の午後1時。中には、昼間から飲めると張り切っている男性社員もいた。「いらっしゃいませ。私は、美月社長の秘書の榊と申します。皆さんもご存知でしょうが、会社には秘守義務というものがございますので、すべてを見ていただくことはできませんので、ご了承ください。」「あの、飲み屋を経営されているって聞いたんですが、ここは事務所ですよね。」 戸惑い勝ちに聞いたのは、酒好きな若い男性社員だった。榊はにっこりとほほ笑んでいるが、目が笑っていない。「そうです。皆さんには、会社とはどういうところかを再度見ていただきたいと思いまして、こちらにご案内いたしました。今日は特別に、こちらにスツールを置きましたので、こちらでしばらく社内の様子をご覧ください。」「え?ただ見てるだけでいいの?」 のんびりとした様子で女性社員が問いかける。「ええ、それで結構です。ただし、私語は謹んでください」「う~ん、そんなんで何が分かるの?」「まあ、会社なんてどこでもいっしょだろ?飲みまでの時間つぶしじゃないの?」 難しいことをさせられないと分かって、一様に肩の力をぬいた社員がわらわらとしゃべりだす。すると、事務所内の社員から冷たい視線が飛んできた。「あ、すみません…。みなさん、お静かに」 慌ててとりなしたのは、受付にいた地味な女性だった。気後れしたように黙り込み、事務所内の様子を見ることに専念していた橘製薬の社員たちは、息を飲んだ。 くだらない私語はなく、もくもくと仕事をこなす。連絡を取り合い、老若男女関係なく、物おじせず意見を戦わせる。電話のコールもワンコールで取られるのでとても静かだ。「30分ほどでしたが、御社との違いが分かりますか?」 応接室に移動した橘製薬の社員に、榊が問いかける。反応は様々だ。「おしゃべりなしなんて、ちっとも楽しくないじゃない」「あなたは会社におしゃべりをしに来ているのですか?そういう存在は会社にとって必要でしょうか?」 受付で美月に遠慮のない視線を送っていた女子社員が頬を膨らませて言うと、まるで他人事のように、榊がさらっと言い放った。「あ、そうだ。喉が渇いていませんか?飲み物はここを出て左のエリアにありますので、ご自由にお取りください。」「あ、では、私が取りに行きます。トレイをお借りできますか?」「トレイはありませんね。うちは、個人が自分で好きな飲み物を取りに行くので、各自で行ってください」 男性社員たちが鼻白む。つづく
November 3, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 9
エピソード9 大通りに面したビルの2階の一室は、今日も電話の音や話し声でにぎわっていた。「所長、明智警察署からお電話です。」「分かった」 明智署の山田警部は大学の同期だ。昔のよしみで時折こうしてこっそり捜査してもらっている。「新之助、お前の予想通りだったよ。やはり佐藤は木戸殺しの犯人だ。例のラインストーンが外れていた服も佐藤の部屋で見つかった。殿村のバイクに手を加えたのもヤツだった。不自然に店の奥に向かう佐藤を見ていた客がいたんだ。」「ほう、それは良かった。」 本田は満足げに顎を撫でる。「で、佐藤はやはりどこかの国と繋がっていたのか?」「おお、そうだった! あんなおとなしそうな顔して、ノーザンディの革命軍の諜報員だった。どうやら留学中につながりができたようだな。それにしても、よくそんなことが分かったなぁ」「ふふ、まあな。大学院の後輩に優秀な外科医がいてね。そいつがノーザンディの大統領の大けがを治療したと聞いて、もしやと思ったんだよ。あの国はもう長いこと内紛が続いている。そこに来て、殺された木戸は新薬の開発に携わっていたと聞いたんだ。脳の手術をするために、一時的に全細胞を仮死状態にする薬だと聞いた。だれが殺したのか分からないまま、死因も特定できないまま消すにはとても都合がいいだろ?」「ひえぇ、薬も使いようだな。ま、これで、木戸の事件は犯人死亡で書類を出せる。佐藤の事件にも情状酌量が見えてきたな」 山田は満足げに電話を切った。しかし、本田は再び考え込んだ。一宮製薬は狙われていた。それは新薬を開発した木戸にむけられたものだけだったのか?もう少し、調べる必要がありそうだ。本田は部下の木村に指示を出すと、受話器を手に、一瞬ためらった。「ちっ、またあいつから情報をもらうことになるのか」 金髪をさらりと後ろに流して、小ばかにしたような顔で笑うイケオジの顔を思い出し、イラっとする。しかし、本田の真実を知りたい欲がそのためらいをあっさりと飛び越えた。「おや、本田君じゃないか。先日は楽しい酒の席をありがとう。姉上にもとても世話になったね。よろしく伝えてくれたまえ。それで、今日も私の力を貸してほしいということかな?」 眉間にはこれでもかと深いしわをよせて、本田が口を開く。「例の店に19時」「おや、悪いね。その時間、ちょっと女の子と約束があるんだよ。20時まで待ってくれる?」「はぁ?」「クックック。そんなおどろくことじゃないだろ?まあ、一緒にお茶でもしてくれるかわい子ちゃんがいないなら、一人侘しく居酒屋でやけ酒でも飲んでいてくれたまえ」「…20時、遅れるなよ!」 ガチャンと乱暴に受話器を置くと、「ちょっと出てくる」と言い捨てて事務所を飛び出した。*****「榊、涼さんとの連絡、まだ取れないの?」「申し訳ございません。秘書の方によると、しばらく休暇を取られているとか。その、例のご友人が亡くなってから、元気を無くされているようで…」 痛々し気に秘書の榊が言葉を途切れさせた。「そう」 視線を下げたブルーグレイの瞳は物憂げだ。今回の事故はあまりにも衝撃が大きい。海外で要人の手術に当たっていた奥平も、美月からの連絡に言葉を失っていた。「なんでだよ!俺が日本に居たら、絶対に死なせなかったのに!!」 やっと絞り出した言葉は、慟哭に近かった。 だけど、と美月は思う。藤森はそんなに感情的になるだろうかと。「で、実際はどこにいるの?」「え?…ああ、なんでも、サイエン王国に向かわれたと聞きました。」「そっか。分かった。」 美月は気を取り直して、出かける準備を始めた。自分の会社の経営よりも、最近はコンサルティングの依頼があわただしい。「今日は、橘製薬でしたね。お車、準備しております」「ありがと」 橘製薬は、先日急に依頼が来た企業だ。一宮製薬とも取引があったことをぼんやりと思い出しながら、美月は車に乗り込んだ。 真新しいビルに一歩入ると、受付嬢だけでなく、一階にいるほとんどの人間が、驚いたように客を見つめている。「社長と14時にアポイントを取っています。コンサルタントの美月です。」「い、いらっしゃいませ」 磨き上げられたフロアに不似合いな、地味な女子社員がおどおどした様子で、内線を使って社長に来客を告げる。その間、隣にいたもう一人の受付嬢が、遠慮のない視線を寄こしていた。美月にとって、見慣れた光景だが、話を聞く前から、ため息が出るような自覚の無さだ。『そんなに外国人が珍しいのか?』 不快感を微塵も見せず、薙いだ瞳でフロアの社員たちを見回した。その時、好々爺然とした社長がパタパタと階段を下りてきた。「いや、すまないね。今、エレベーターが壊れてて、明後日には修理に来るんだけど。」 好々爺はなぜか照れたように笑っている。それを無表情な美月が静かに見下ろしていた。会議室に通されて改めて向き合うと、開口一番、こう言い放った。「橘社長。こちらの会社のコンサルティング契約をする前に、お伺いしたいことがあります。」「なんだ?遠慮せずに何でも聞いてくれ。 おーい、谷村さん。お茶持って来て。おいしい方ね。ははは。」 社長のやりとりを黙って聞いていた美月は、おもむろに問いかける。「社長。あなたは多少の犠牲を払っても会社を立て直したいですか?それとも、社員と仲良く泥船に乗りたいですか?」「どういう意味だね?」「あなたは、社員にとても愛されているようですが、愛される必要なんてないのです。このままなれ合いの状態を壊したくないと思うのであれば、僕は契約を辞退します。」 断られるなどとは思ってもみなかった好々爺は、その愛想を崩すこともできず固まってしまった。「職場が居心地の良いぬるま湯であってはならない。常に向上心を持って、今より上を目指そうと個々が自ら努力する会社。僕が目指すのは、そこです。」 ぐっと言葉を詰まらせたままの橘の元に、谷村がお茶を運んできた。つづく
November 2, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 8
エピソード 8新緑のワインディングロードを、一台のバイクが走り抜ける。そして、目的の場所に近づくと、徐々にスピードを落としていった。坂の上には展望台とささやかな公園がひろがっている。ヘルメットを脱ぎ、エンジンを止めると、海からの爽やかな風が吹き付け、萌絵の髪を、頬をくすぐった。自販機で缶コーヒーを買うと、ゆっくりと一人の時間を楽しむのだ。あの事件以来、母は自分の行動に一段と口うるさくなった。だけど、どんなに言われても、自分は一宮貴絵にはなれない。萌絵は再びヘルメットを装着すると、バイクにまたがってイグニッションを回す。なめらかなボディは、もう自分の体と一体化しているかのようだ。下り道を走りながら、ふと、このまま目の前の壁にぶつかったら、母はどんな顔をするんだろうと頭に浮かんだ。姉を亡くしたときの狂ったような号泣を思い出し、ハッと我に返る。まずい! 腰をぐんと左にずらし、身体全体で車体を傾け、鮮やかに弧を描く。駆け抜けた後ろで、はやし立てる声と拍手が聞こえた。そうか、今日は日曜日。ギャラリーが多いようだ。ん? なんだか見たことがある人物がギャラリーの中に紛れている。軽そうなヘルメットに大き目の眼鏡。手には薄いグローブ。ロードレーサーを従えたその人物を頭の中で着替えさせるが、どこで見かけたのかが思い出せない。「どうしてこんなところに?」 微かな違和感を覚えながら、萌絵は帰路についた。バイクにカバーを着せて玄関の扉を開けると、母が待ち構えていた。「萌絵、またバイク?! 出かける時は、どこに行くか声を掛けてって言ったでしょ?まったく、あなたときたらまるで私の話を聞こうとしないんだから」「もう、いいでしょ。レポート仕上げたいから。」 言うが早いか、萌絵はさっさと自室に閉じこもって、ベッドにごろんと横になった。チェストの上には、姉妹で出かけたときの写真が飾られている。思えば、いつも貴絵は自分を庇ってくれていた。自分を悩ます母の小言も、きっと今に始まったことではないんだろう。だけど、それは貴絵という防波堤のお陰で、自分を煩わせることがなかったのだ。 あの事件以来、大学に行ってもどうにも居心地が悪い。顔も知らないたった一人の自分勝手な行動のせいで、ここまで影響が出るのかと、萌絵は途方に暮れた。 午前の講義が終わると、学生たちはほっと緊張を解いていた。「萌絵、ランチに行こう」「ええ、行きましょう。沙希と美玖は?」「沙希は午後からの講義がないから、バイトだって。美玖はもうすぐ来るよ。カフェで待ち合わせしてるの」 二人が席を立って歩き出すと、少し離れた場所で、同じように移動を始める男がいた。萌絵からは死角になっていて、気づいていないようだ。「愛結花もバイトじゃなかったの?」「うん、今日はバイト休みなの。ちょっと、気になる人が、今日の午後の講義を聞きに来るっていうから…」 愛結花は微かに頬を赤らめて、落ち着かない様子だ。萌絵はその異変に気付くと、はぁっと深いため息をついた。「いいなぁ。どうやったら好きな人に巡り合えるんだろ。私、一生誰とも恋愛しないような気がしてきた」 眉を下げて嘆いて見せているが、今が一番おだやかだと萌絵は実感している。愛結花や沙希、美玖は、自分をしっかりと持っていて、噂に流されないところが有り難かった。だから、萌絵もこんな風に自分を素直に出すことができるのだ。一日の講義を終え、友人たちと別れた萌絵は、一人電車に飛び乗る。ドア際にもたれて通り過ぎる景色を眺めながらぼんやりと考えていた。 友人とのランチが楽しいのも、彼氏が欲しいのも、嘘ではないけど、ふと目を閉じると、山間のひんやりした空気を思い出す。4ストロークのエンジン音、全体重をかけて車体と共に流れるようにカーブを描く快感、バイクが自分の体の一部のように感じる瞬間だ。あれを一度味わったら、やめられない。最寄り駅を出るころには、今日の走行経路を頭に描いていた。 ライダーズスーツに着替えて、フルフェイスをかぶり、グローブの感触を確かめる。その頃には、家族の事も、友人の事も、全部放り出してバイクと意識を一体化する。今日もいつもの峠を攻めよう。エンジンが温まったのを見計らって、萌絵はスロットルを回した。 お気に入りの峠を走っていると、またあの人物が目の端に移った。「危ない!」 石垣への激突は免れたが、ギリギリのところをなんとか立て直して、バイクは疾走する。そのままどんどん走っていくが、背中には冷や汗が流れた。 展望台でバイクを止めて、少し気持ちを落ち着かせていると、不意にあの人物が大学にいることに気が付いた。「そうだ。あの人、同じ学部の人だ!だけど…」 同じ趣味だというならそんなに気にも留めないが、相手は自転車だ。そしてそれよりも萌絵に不安を与えたのは、その表情だった。狂気にも似た笑顔でじっと彼女を凝視していた。「次からコースを変えよう。」 妙な人物に目をつけられたものだ。萌絵はため息をついて、帰路についた。 翌週は貴絵の法要があった。さすがにその日は母の言いつけを守って、萌絵も参列していた。たくさんの人がやってきて、手を合わせる。みんな身なりがよく、知性的だ。これは貴絵の生き方をそのまま表したようなものだと、萌絵は思っていた。「あの、失礼ですが、君は一宮貴絵さんの妹さんですか?」 振り向くと、そこには上品に身なりを整えた若い男が立っていた。やや吊り上がった切れ長の目を細め、さっと名刺を差し出している。「弁護士さんですか? あの、私に何か?」「ええ、私は貴絵さんの大学院の先輩にあたるのですが、少し彼女の死に気になることがありまして、お話を伺いたいと思っていたのです。」 とたんに萌絵の眉間にしわが入る。姉は通り魔に襲われて亡くなった。そこに彼女を狙っていたという意味は含まれていないと思っていた。だけど…。「貴絵さんのあの功績から考えて、彼女の死因はあまりにもあっけない、そう思われるでしょ?」 心の中を見透かされたようで、思わず警戒してしまう。「こんな場所ではなんですので、一度、お姉さんが仕事場にしていた大学院の研究室に来ていただけませんか?」「…分かりました」 見知らぬ弁護士の事務所なら、断っていただろう。本田と名乗る男を見送りながら、萌絵はその場にたたずんでいた。姉は、仕事に行くとき、いつも楽し気だった。彼女の仕事場など、行ったこともないが、そこに行けば、姉のことが何か分かるような気がしていた。そして、こんなにも自分は姉のことが大切だったのかと、今頃になって気づいていることに愕然としていた。
November 1, 2022
コメント(0)
-

はろうぃーん
このところ、何かと忙しいのです。仕事も趣味の事も、そしてプライベートも。。。これから年末にかけて、恐ろしいイベントや楽しいイベントが目白押し!!思えば今年の8月9月は案外暇してたんですよ。仕事でも、秋以降忙しいとは見込んでいたので、早めにできる資料作りなんかはやっていたぐらいなんです。ところがね、なぜかPCが調子悪く作っていた資料のデータが出せなくなり、そのままPCは買い替えることに。。。えっと、9月の私の努力はどこへ…そして、コロナで止まっていた趣味の活動がいよいよ再開しようとしているのです。喜ばしい。。。はずなんだけど、次のコロナの波はインフルの波と同時進行だとか。この年末までのイベント、どうなるの?!そんなこんなで、気持ちばかりが焦っている私です。
October 31, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 7
エピソード 7 隠れ家のような小さなショットバーに、本田がやってきた。この店は顔を思い出してもムカつく相手と待ち合わせする場所だ。カウンタ―を陣取って、あごを手に乗せて瞑目するが、眉間のしわが本田の気分を如実に表している。「やぁ、久しぶりだね。君から会いたいだなんて。あははは。どうしたんだい?」「ちっ、だから嫌だったんだ。冴子の奴…」「ふふ、姉上からの依頼だね。そんなに拗ねていないで、まずは一杯どう?」 楽し気に笑うこの男、60をとっくに過ぎたイケオジだ。金髪、緑の瞳、整った知的な顔立ちで、いつも身なりを気にしている本田でさえ、見劣りするようなハイブランドで固めている。「はぁ、仕方ない。今日は付き合ってやるか。」「ほっほっほ。相変わらずだね。それが依頼先に対する態度なのかい?だいたい君は人とのコミュニケーションの仕方が分かってないんだよ。冴子君にも注意するように伝えておいたんだが、どうやらこの坊やには人の意見を聞く能力が備わっていないようだね」「ミスターK、今、なんと?」 穏やかな口調でありながら、二人のにらみ合いは熱い。「あの、お飲み物はいかがいたしましょうか?」 バーテンダーがさりげなく抑えに来たが、この二人に聞く耳はない。「おや、坊やは耳が遠くなったのかい?」「ほう、やはり耄碌してしまったようだな。私の耳は正常だ。ミスターK、バーテンダーを待たせている。まずはオーダーを」 いきなりの応酬にもすっかり慣れっこのバーテンダーが、二人に水の入ったグラスを差し出した。「いや、まったく。よく気が利くよね、君。この坊やに爪のアカをわけてやってくれ」「ミスターK!バーテンダーに爪のアカなどありえない。君、このおいぼれが失礼した。私には山崎12年ものをワンフィンガー、ロックで」 バーテンダーが頷いてミスターKに目をやると、こちらも「同じものを」という。「さて、本題に入るが、カームリー小国でなにが起こっている?」「ふむ、あの国は、面積は小さいが裕福な国だ。王族と国民の信頼関係もある。ルビーやサファイアの鉱脈が見つかって、一層豊かになっている。」「つまり、問題は何もないと?」 ふふっとミスターKは笑みを漏らす。「何かあるから確認しているのだろ?確かに国内は問題ないが、それだけ裕福になれば、どうしても他国から狙われる。それが世の常だ。」 カランと小気味良い音を立てて氷が踊る。グラスに口をつけて、ミスターKは目を見開いた。「ほう、日本のウイスキーもうまいねぇ」 それには答えずに、本田は自分のグラスの中を見つめながら問う。「なにか、心当たりがあるのか?」「ん、ラバリー帝国の王族がどうも落ち着かない。地理的には、サイエン王国を挟んだ形で西と東になるが、サイエン王国の北側の山岳地帯の北で、2国はほんの少し隣接している。そして、カームリー小国の宝石の鉱脈もこの山岳地帯にあるんだよ。そして、その両国の細い国土をはさんで、ノーザンディという国がある。こっちもごたごたしていてね。」「なるほど。それで、ミスターK、あなたが日本に来ている理由を聞いても?」「ああ、篠原君に声を掛けてもらったんだよ。彼の優秀な教え子たちが、すごい成果を発揮したと聞いたものでね。あ、そういえば、君も彼の教え子だったね。」 緑の瞳を細めて、意地の悪い笑顔を見せる。カームリー小国やその周辺国の状況は分かったが、彼が日本にわざわざ来たことと関係があるのかと質問したことを、本田は心から後悔した。 カランとグラスの酒を一気に飲み干した本田を見て、やれやれとイケオジが呆れる。「君、酒の飲み方も知らないのかい?12年ものだろ?その熟成年数に敬意を表してじっくり味わいたまえよ」「フン、年寄にはできない飲み方でしょうね」「君、私を老いぼれ扱いするのか?」「おや、自覚がなかったんですか?」「なんだと?」 ミスターKは自分のグラスを握り締めると、ぐいっと一気に飲み干し、カウンターにグラスを置いた。「いやぁ、うまい酒だ。君、もう一杯いただけるかい?」「はい」 バーテンダーが2杯目を作り始めると、本田も負けじとオーダーする。そうこうしているうちに、大人げない酔っ払いが2体できあがるのであった。「ほら、しっかり立って!佐々木君、悪いわね。ホントにどうしようもないわね、いい大人が」「あはは。いえ、大丈夫ですよ。こうして回収してくださる方がいらっしゃるお客様はマシな方ですから。」 細身な割に力のあるバーテンダーの佐々木は、いとも簡単にミスターKを抱えて車に乗せる。一方冴子は本田に肩を貸しながら引きずるようにして駐車場までやってくると、後部座席に荷物のように放り込んだ。 佐々木に礼を言って車を出すと、自宅マンションへと向かう。「まったく、どういうことかしらねぇ。手伝ってもらおうと思ったのに、とんだお荷物だわ。あら?」 信号待ちをしていると、反対車線の歩道を見知った後ろ姿が角を曲がっていったのだ。あれは、教授の研究室で見かけた女性だ。以前、教授を訪ねたとき、おいしいコーヒーと焼き菓子をごちそうになった。 信号が青になって、進み始めるのと同時に、後ろの方で女性の悲鳴と男性のさけび声が聞こえた気がした。しかし、後ろの車に急かされる形で、冴子は車を進めるしかなかった。「大丈夫だったかしら、彼女」 妙に落ち着かない気分だった。いそいで自宅マンションまで帰ると、二人を客室用の部屋に放り込み、急いでたテレビをつけた。画面に映っているのは、さっき通ったばかりの幹線道路だ。赤色灯でギラギラした街は、さっきとはまるで違う場所のようだった。 画面の右上は死者8名、重軽傷者14名と激しい字体で記されている。画面上ではアナウンサーがさっき分かったと思われる被害者の名前を読み上げている。そして、その中に、あってはならない名前を耳にして、冴子は愕然とする。「うそ…」 冴子は、震える指を抑えながら、篠原や仁に連絡を入れた。つづく
October 30, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 6
エピソード 6「悪いね、私の事務所に来てもらっちゃって。良かったら、適当に飲み物でも入れてくれ」「いえ、結構です。それで、どういう案件だったのですか、本田先輩」 本田の事務所のソファに座って、笑って見ているのは藤森だ。美月も呼ばれていたが、予定が合わなかった。「この女性なんだが、僕が弁護を担当しているんだ。君のデータの中にあるかい?」 差し出された写真を見るなり、名前が出てきた。「嘉村実里 25歳。関東文具販売(株)勤務。ですね」「ああ、さすがだね。そう、この女性が殺人犯として捕まっていて、私が弁護士としてついているんだが、どうしても彼女の動機が分からないんだ」「被害者は?」「こっち、佐藤静流。同じ会社の同僚だ。警察の聞き込みでも、二人は仲が良かったということだった。半年前に嘉村の恋人が何者かに殺されて、動揺しているときも、甲斐甲斐しく世話をしていたらしい。それなのに」 じっと話を聞いていた藤森は、ささっとメモに名前と住所を書き記した。「ここ、その恋人木戸ってやつでしょ?その前後の足取りで立ち寄った場所です。ここでなにか聞いてみてもいいかもしれませんね。」「スーパーと花屋と喫茶店か。君、行ってみない?」 藤森はふっと笑って、断った。「いえ、お断りします。そんなに暇ではないんですよ。大方、嘉村に執着しすぎて消されたんじゃないですか?それ、僕のデータ必要あります?僕はおもちゃじゃないですよ。」「う~ん、そうか。いや、せっかくだから木戸についても教えてくれる?」「木戸ですか? えっと、一宮製薬の社員で、木戸テックの社長の息子ですね。ついでに佐藤も調べます? 嘉村と同じ関東文具の社員です。あれ? 警察のチェックが入ってる。どうやら、犬猫の薬物死に関与しているみたいですね。佐藤は元々理系の大学を出ていて製薬会社志望だったみたいですよ。サイエン王国にも留学していましたし。あ~、これは調べ甲斐ありそうですねぇ。」 藤森は席を立つと、上着を整えてにっこり微笑んだ。「では、せいぜい頑張ってください、先輩」「ええ、そうか。君、なかなか頭がいいね。さすがは私の後輩だ。まあ、がんばるよ。」 笑いながら後輩を見送って、仕方なく、自分でコーヒーを入れた。「それにしても、なかなかのデータ量だったな。あのデータ、クレジットカードからの情報漏洩だろ?こんなセキュリティの低さじゃ、やばいよ、日本」 ソファに腰を下ろすと、あごに手を当てて考えを巡らせる。やはり彼らには、この程度の事件では物足りない。もっと入り組んだ案件を考えてやらねば。 ほんの一瞬、嫌な顔が頭に浮かんだが、本田は慌てて打ち消し、コーヒーをひと飲みした。 木戸が一宮製薬の社員であることは、すでに掴んでいた。その木戸がどうして殺されたのか。コーヒーを飲みながら、本田はもう一度嘉村と佐藤の写真を眺めた。「犬猫の薬物死か…。嘉村さん、知らずにいい仕事したのかもしれませんねぇ。ここは、全部吐き出していただきましょう」 にやりと笑って、写真を片付けると、さっさとコーヒーを飲み干した。*****「え、何が気に入らなかったの?会えなくて寂しかった?来週はデートできるよ?」 受話器にしがみつくこの情けない男は、奥平仁。世界的に名前を知られている外科の名医だ。だというのに、このざまだ。「ふふふ。また振られたの?」「うるせー」「女の子の選び方、間違えてるのよ。見ていて可哀そうになるわ。モテないわけではないのにねぇ」 大雑把にまとめられた長い髪をガシガシとかきむしり、奥平は盛大なため息をついた。ここは彼の個人事務所だ。目の前の姉御肌の女性は、本田冴子。奥平が独立するとき、篠原が紹介した人物だ。彼女の管理能力と多言語の堪能さのお陰で、手術だけに専念できている。 冴子はゆっくりと紅茶を淹れながら、奥平を宥めにかかる。「まあ、これだけ忙しいと、じっくり女の子に構ってなどいられないわね。それでも待ってるって言ってくれるような女の子を探さなくちゃだめなんじゃない?」「ええ?じっと待ってるとか辛気臭せーなぁ」 自分用のカップにも紅茶を注ぐと、優雅に席について楽し気に言う。「じゃあ、しばらくはあきらめるのね。明後日には美月君の手術が入ってるわ。その後、ラバリー帝国の第二王子の性転換手術、その翌週にはカームリー小国で中絶手術…。あら。どなたかしら。カームリーにそんな年齢の要人いらしたかしら。」「分かったよ。とりあえず美月の手術の日程は確保できたんだな」 カップをテーブルに置くと、奥平は席を立った。「あら、どちらに?」「寝る。16時には起こしてくれ。美月の術前検査がある」「了解」 プライベートルームに入る奥平を見送って、冴子は小さなため息をつく。「結構モテるのに、自覚がないのよねぇ」 そういいながらカームリー小国の依頼主に連絡を取る。要人専門の医療を謳っているOSO(奥平サージェントオフィス)としては、患者の年齢性別、既往歴などは確認事項だ。 ドアをノックする音で、奥平は目を覚ました。いつになく、おとなしめのノックに違和感を覚えた彼は、すぐさまオフィスエリアに顔を出した。「どうした?」「時間よ」「それだけじゃないだろ? 何があった?」 冴子はすぐには答えないが、目が泳いでいる。そのままじっと見つめられることに耐えられなくなって、眉間にしわを寄せた。「仕方がないわね。例のカームリー小国の患者、王女様だったわ、15歳の」「え?!…」 眠気に覆われていた頭が、一気に覚醒した気分だった。穏やかな国政、国土は広くないが、誠実は国民性で工業がとても盛んな国だ。最近は希少価値の高い宝石が取れることで、より豊かな暮らしが成り立っている。国民が王族をとても慕っているという、おとぎ話に出てきそうなとして有名な国だ。そんな国の幼いお姫様が中絶? これはとんでもない醜聞だ。「裏がありそうだな。」「ちょっとこちらでも調べておくわ」「よろしく頼むぜ。じゃ、美月に会ってくるか」 奥平を見送ると、冴子は受話器を手に持った。「新之助? ちょっと調べてくれない? カームリー小国のことよ」つづく
October 29, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 5 (後編)
1週間が過ぎた。木戸の遺体は検察に回され、未だ遺族の元に帰っていないという。もとより母親のあの権幕なら、葬儀には呼んでもらえそうにない。会社に申請していた有給もあと1日でなくなってしまう。どんなにつらくても、お金を稼がなくては食べていけないのだ。実里は意を決して部屋着を着替え、街に出た。「しっかりしなくちゃ。 もう、彼はいないのだから」通いなれた木戸のマンションまでの道。途中の花屋で小さな花束を買った。「あ、先日のお客さんですよね。あの花束、大丈夫でしたか?」「あ…先日はありがとうございました」「それはよかった。大きな花束だったし、注文してくれたお客さん、めちゃくちゃ照れ臭そうだったから、どうしてもきれいな状態で届けなくちゃって思ってたんですよ。」 花束を配達した若者は、ここの店員だったようだ。思いがけず木戸の様子が聞けて、張っていた気がぐらっと崩れそうになる。「そうだったんですか。素敵な思い出の品になりました。ありがとう」 実里はそう言って、店を出た。そして、木戸のマンションまでやってきたのだ。立ち入り禁止のテープは張られたままだが、警察の姿はどこにもなかった。ドアの前にそっと花束を置くと、通路にしゃがみ込んで手を合わせる。そして、立ち去ろうとエレベータに乗ったとき、箱の隅に何かが光っているのが見えた。 直径2㎜程度のラインストーンだ。赤黒い汚れがついている。「まさか…」 困惑しながらも実里はそっとティッシュでそのラインストーンをつまむと、大切にポケットにしまった。「木戸さん。会いたいです…」 エントランスを出て振り返ると、実里はじっと木戸の部屋のあたりを眺めてつぶやいた。そして、そのままいつもの喫茶店に立ち寄った。「いらっしゃいませ。実里ちゃん!もう、大丈夫なのかい?」「店長さん、その節は、ありがとうございました。ずっと家の中に閉じこもっていたんだけど、それじゃだめだと思って、思い切って出てきたんです。明日からは仕事も再開します」「そっか。よく決心したね。でも、辛くなったら、いつでもここにおいでよ」 店長の穏やかな笑顔にほっとさせられた。その時、実里はいつもの声が聞こえないことに気が付いた。「あの、いつもの店員さんは?」「ああ、殿村君? 彼、バイクで通勤しているんだけど、どうやらいたずらされてたらしくて、事故っちゃってね。足の骨を折って入院中。でもおかしいよね。従業員の駐車場は店の裏側にしているのに、わざわざそこまで来ていたずらするなんて。彼、あれでモテるから、変に逆恨みされたのかもね。」「そうだったんですね。次、会われた時に、お大事にって伝えてください。」 少しずつではあるが、実里は気持ちを立て直す。しばらくすると、店を出て、自宅に向かった。さっきの花屋の前を通ると、店員が声を掛けてきた。「あの、実はさっきその、事件の事を知って…。えっと、あの、大丈夫ですか?」何と言って切り出せばいいのか、迷いに迷った様子で、しどろもどろの店員が言う。実里には、その気持ちが有り難かった。いつの間にか、知らない人にまで心配かけているんだ。しっかりしなくちゃ。「ありがとうございます。」 実里は心を込めて礼を言う。頭を下げたその時、グラっと平衡感覚を失った。ここ数日の出来事でほとんど眠れていなかったのがいけなかった。 そのまま店員に突っ込む形で倒れこみ、その腕の中に納まっていた。「だ、大丈夫ですか?! あの、俺…。同じ男として、あの人と話した人間として、力になりたいです! 事情もある程度わかってるし、ほっとけないです!俺で良ければ、泣きたいときはいつでもここで泣いてください!」「何をやっているの! 実里から離れて!この子に変なことをしたら承知しないわよ!」 突然降りかかった常軌を逸した叫び声は、静流のものだった。「違うの。私がふらついたから、支えてくださっただけよ」「実里は黙ってて。いいこと。彼女が傷ついているからって、こんな時に自分の物にしようなんて、考えないことね」「いや、そういうつもりは…」 静流は、実里の腕をつかむと、グイっと自分の方に引き寄せた。「しばらく私のマンションで過ごしましょう。一人になるよりいいよ」「静流…。ありがとう。でも、そろそろちゃんと自立しないとね。明日からは会社にも行くから。」「何を言ってるの。無理しちゃだめよ」 細い腕に食い込んだ静流の指をはがす様に離し、落ち着いた声が言う。「本当にもう大丈夫だから。」 心配する静流を残して、実里は、花屋の店員に会釈すると、そのまま帰っていった。それを見送った店員は、静流に目をやってぎょっとする。唇を嚙み、思いつめたような表情は、とても心配している様には見えなかった。「あなた、誰に頼まれたの?」「え?…な、何をでしょう?」 あまりに狼狽する店員の姿にはっとして、なんでもないわと言い捨てて、慌てた様子で去っていった。***** カーテンを閉め切った真っ暗な部屋の中、その人物は頭を抱えていた。自分の中の衝動と好奇心をどうしても抑えられなかったのだ。「あれはやるべきではなかった。だけど、あの小動物のようにおびえる目を見たら、どうしても答えてやりたくなる。どんな風に逝きたい?何を使ってほしい?」 その瞬間自分の手の中の感触を思い出し、恍惚感に浸ってしまう。「ああ、そうじゃない!なんとかリカバリーしなければ。やはりあの子を取り込んでしまおう。盗まれて困るような情報は、娘や恋人にひそかに持たせていることも多い」 半年前、久しぶりに留学時代の友人から連絡が来た時は驚いた。サイエン王国の隣にあるノーザンディから留学していると話していたが、まさか政治家の息子だったとは。思わず笑みがこぼれる。この仕事を終えたら、彼とは結婚が決まっている。こっちでどんな汚れ仕事をやっても、向こうに行けばノーカウントだ。だからこそ、どうしても成功させなくては。つづく
October 26, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 5(前編)
エピソード5「どうし、て…。」 そんな言葉を残して、木戸は崩れるように通路に倒れた。腹部に刺さったナイフをえぐるように抜き取ると、さぁっと血だまりが広がる。それを無表情なままみていた人物は、足音を消してその場を離れた。 ぼんやりとカウンターの隅に座って、実里は生きた屍のようになっていた。時折店員の殿村が様子を伺っている。実里は、この店の常連だ。いつも仕事帰りに立ち寄っては、友人と楽し気にお茶をして帰るのだ。うら若き女性とは思えない今の姿は、誰の目にも異常だった。 しばらくして、店長が実里に声を掛けた。「実里ちゃん、どうしたの? 大丈夫?」「え?ああ、はい」「話して楽になるようなことなら、話してごらん。ほら、実里ちゃんのお気に入りのプリン、ごちそうするからさ」 目の前に愛らしいプリンアラモードが置かれ、空洞のようになっていた瞳に、ほんの少し光が戻る。そして、はたと思い出したように胸元のペンダントを握り締めた。「店長さん、ありがと。彼がね、彼が…。」「え?もしかして、浮気ですか!?」 寄ってきたのはウエイターの殿村だった。「その方が良かった…。今、ニュースになってるわ。おとといの夜から連絡がつかないから、風邪でも引いたのかと思って様子を見に行ったら、警察がいて…」「それって、もしかして、道向かいのマンションの事件のこと?」 実里の瞳にわっと涙があふれた。その時、一人の客が飛び込んできた。「実里!やっぱりここにいた!大丈夫?!」「静流ぅ…。どうして? どうして彼があんな目に遭うの?」「実里、辛かったね。私、ずっと実里の傍にいるからね。」 静流がぎゅうっと実里の肩を抱き寄せると、実里も耐え切れなくなって、静流の胸で号泣した。「ああ、その役、僕がやりたかったのになぁ。」 他の客のオーダーを運びながら、殿村が残念そうにぼやく。その後ろ姿をぎっと睨む静流のことなど、気づきもしない。 実里が少し落ち着いたところで、店長がそっとココアを置いた。「少しは落ち着いたかな?ホットココア、どう?気持ちが落ち着くよ。お友達も一緒にどうぞ」「ありがとうございます。実里、いただこうか」 頷いてカップに手を掛けたところで、スマホが鳴りだした。警察からだった。「静流、心配かけてごめんね。警察から、もう一度事情を聞きたいから来てくれって。店長さんも、ありがとうございました。」「とりあえず、ココアだけは飲んでいきな。外は冷えてきてるし。」 実里は頷いて、両手でカップを包み込むように持ち上げる。まだまだ気持ちはどこか遠くにあるような妙な気分だ。それなのに、ココアの温かさだけは、身体の中に広がっていく。「じゃあ、失礼します。」 静流が付きそうと言ったが、それは辞退した。今は、甘えてしまってはいけない。そう思って、そっとペンダントを握り締めて一人店を出たのだ。「実里ちゃん、大丈夫だろうか。芯の強い子だと思うけど、だから余計心配だよ」 殿村が閉じられたドアを見つめてつぶやく。 それから数日。実里は帰ってこなかった。警察の尋問は続いている。まるで彼女が犯人であるかのようだ。 あの日、再び取り調べ室に向かった実里は、木戸の両親と対峙した。息子の突然の死に取り乱していた母親は、いきなり実里を捕まえて、「人殺し!」と叫んだのだ。「あの子が他の女性と付き合うはずはないわ。だって、ちゃんと許嫁がいたのよ。主人の会社の取引先の社長のお嬢さんよ。それなのに…。あなた、息子に振られて、腹いせにこんなことをしたんでしょう?!息子は私たちにはとてもやさしい子だったのよ。返して!あの子を返して!」「やめないか!」 取り乱す母親を宥めていた父親が、実里の胸元に光るペンダントに目を止めた。「君、そのペンダントは息子から?」 急に問いかけられて、戸惑いながらも実里は答えた。「はい、なんでも、自分の気持ちを特別な方法で閉じ込めてもらったから、ずっとつけていてほしいって言って…」「嘘よ!そんなもの、渡すはずがないわ!」 再び取り乱し始めた母親を父親が叱る。「いい加減にしないか!この人だって、あいつのことを想ってくれていたんだ。あいつは、それだけ多くの人に愛されていたってことなんだ。若い娘さんが、あんなに目の下に隈を作ってやつれているんだ。それ以上責めるもんじゃない」ようやく修羅場が落ち着くも、そのまま警察の尋問は続くのだ。 やっとアリバイがはっきりして、開放された時には、もう、何もかもがどうでもいいとさえ思っていた。 自分のアパートに帰りつくと、ちょうど配達の若者がうろうろしているところだった。「あの、嘉村実里さんですか?」「はい」 若者は、ほっとした表情で、大きな箱を手渡した。「何度か伺ったのですが、お留守で…。これ、中身が花束なので、焦りました。じゃあ」 若者はあっさりと帰っていた。そのまま鍵を開けて、久しぶりの我が家に戻ると、ぼんやりと大きな箱を見つめながら、ここ数日の事を考えていた。 壁にかかっているカレンダーには赤いハートマークがついていた。あれは、何のマークだっけ。そう思った時、不意に思い出した。あれは彼が遊びに来た時に付けたマークだ。そう、自分の誕生日だった。出張で当日は会えないけど、帰ったらお祝いしようって、笑っていた。 テーブルに置かれた大きな箱には木戸の名前が記されていた。「そんな遠くに出張なんて、行かないでよ…」実里は重い腰を上げて、箱を開いた。中から出てきたのは、大きな花束と手紙だった。木戸らしい角ばった文字が便箋いっぱいに記されていた。「帰ったらプロポーズするつもりだから、覚悟しておけだなんて…。お母さまのお見合い話は断ってる。そっか。」 実里は手紙をそっと封筒に戻すと、胸に抱きしめた。つづく
October 24, 2022
コメント(0)
-
言い訳? 解説?
始まりました「エグゼクティブ・チーム」ですが、実はまだ執筆中です。いつもはある程度完成させてから推敲しながらのアップロードなので、今回は、ドキドキしながら上げております。で、次回のエピソードから場面がガラッと変わります。藤森や美月は出てこないで、他の場所で起こった事件を描いていきます。もちろん、後々彼らに繋がっていくお話ですが、あれ?っと思われるかもと思い言い訳しております。wところで、今、不思議に思っていることがあるのです。「小説家になろう」というサイトにも小説を掲載させていただいているのですが、夏ごろ掲載していた「ブルーフォレスト」というお話が、未だに毎日35名ぐらいの方に閲覧してもらっているのです。私のような弱小物書きにとって、掲載した小説が何か月も経ってるのに、こんなに読んでもらえるのは、奇跡のような出来事です。でも、多少の違和感を覚えています。しかも、いつも1時間のうちに一気に35名。(アクセス解析で閲覧数を時間ごとにチェックできるのです)そうなると、なんだか不安になってきて、どういうことなのか知りたいなぁなんて、思うわけです。あ、もちろん、ブックマークも評価もされてないので、ランキングに入るわけもなく。。。だれかこのカラクリをご存知の方がいらしたら、教えてください。
October 22, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 4
エピソード 4「教授、本当に脳神経とデータの記憶装置を接続することなんて、できたんですか?」「ああ、まったく彼らには驚かされてばかりだよ」 大学院の研究室に、コーヒーの香りが立ち込めていた。来客用のソファに腰かけ、長い足を組んでくつろいでいるのは、本田新之助。弁護士だ。切れ長の目に髪をさらりと後ろに流し、上質なスーツを着込んだ彼は、藤森の数年先輩にあたる。「いや、しかし。そんなことが可能なのか?」「ははは、悔しいんだろ? だが、君は生まれてくるのが少しばかり早すぎたんだ。同学年だったら、どうなっていたことやら…」 カップに淹れたてのコーヒーを注ぎながら、篠原は含み笑いをする。「ところで本田君、君、こんな高齢の師匠に珈琲を淹れさせてふんぞり返っていることについて、なにか謝罪はないの? せめて、スイーツでも差し出してもらいたいもんだね」「ああ、お気遣いなく。私は甘いものが苦手でして」「だれが君に食べさせると言った。まったく、相変わらずちゃっかりしているな」「ふふふ。お褒めの言葉と受け取っておきますよ」 ばかばかしくなったのか、篠原は自分のカップにもコーヒーを注いで、本田の向い側に座った。「一宮君がいてくれたらなぁ。この辺りですっとひと口フィナンシェあたりが出てくるんだけどなぁ」「一宮、君ですか?」「ああ、例のチームの一人で一宮製薬の社長令嬢だよ。頭がよくて、センスもある。そして、なにより気が利くんだよ。君とは大違いだな」 大きなため息をつく篠原は、一宮の名前に本田の目が鋭くなったことに気付かない。「今度そのチームの面々と会わせてくださいよ」「ああ、彼らは神出鬼没だから、運が良ければ会えるんじゃないか?海外に研究所を設立して3年。ここに顔を出したのは数えるほどだ。」 コーヒーを飲み干すと、本田はあっさりと帰っていった。やれやれとカップを片付けていると、聞き覚えのあるエンジン音が聞こえてきた。「おや、入れ違いになってしまったようだね」 篠原は、ふふっと笑いながら、やってきた若者たちを招き入れた。「教授、お久しぶりです。」「やぁ、藤森君。君の活躍は聞いているよ。」「いや、あれは美月の知識のお陰ですよ。私は脳神経のことしか分からないので。」「しかも、天才外科医と極上の麻酔医兼助手がいる。君たちでないと成しえなかった。本当に尊敬するよ。」 藤森が振り向くと、美月、一宮も一緒にやってきた。「教授、お久しぶりです。今日はコーヒーのお供にひと口フィナンシェをお持ちしました」「おや、そう?! それは、それは。」「あれ、篠原教授、なんだか含みのある笑顔ですね」「美月君、話せば長い、わけでもないが、聞いてくれる?」 篠原は、さっきまで来ていた本田の話を聞かせた。まさか冗談で話した一口フィナンシェが本当に手元に来るとは思ってもみなかったのだ。「奥平君はどうしてる?」「サイエン王国の北側のノーザンディという国で、暴動が起きたとかで、大統領が命に係わる怪我をしてしまい、そちらに出向いています。」「そうか、相変わらずだな。」 研究室の給湯コーナーに行った一宮が声を掛けてきた。「教授、さっきコーヒーを飲まれたのですか? 紅茶にします?」「いや、君の淹れてくれるコーヒーが飲みたかったんだよ。お願いしてもいいかい?」「ふふふ。了解です。」 明るい声に篠原は目を細める。「いや、まったく素晴らしい女性だね。お嫁さんになってほしいよ」「教授!」 貴絵の声が咎める。「だって、ねぇ。こんなに気が利く女性、なかなかいないよ。本当はあちらこちらから引く手あまたなんだろう?」「やめてくださいよ。先日まで家業の関連会社の人がしつこくて大変だったんですよ。ホントにいい迷惑です。そんなことより、藤森君、美月君、今回のこと、説明しておいてよ」「ああ、分かった」 藤森は、自分の耳の後ろ辺りの髪をかき上げ、教授に見せた。「こんなところに接続部分を作ったのかい」「ええ、脳に近いですし、髪の毛でカモフラージュできますしね。」「それで、データはすんなり頭に収まるのかい?」「はい、そもそも人間は一生のうちに使える脳の記憶力のほんの少ししか使えていないのです。だから、データの蓄積には問題ないようです」 藤森と美月が今回の研究成果を説明しているうちに、コーヒーとフィナンシェが運ばれてきた。「ああ、やっぱり一宮君の淹れてくれるコーヒーはいいねぇ。香りが上品だよ」「あら、本田先輩は淹れてくれないのですか?」 一宮が尋ねるとこの老人は、両肩をきゅっとあげ、拗ねたような顔で嘆いて見せる「聞いてよ。あいつ、この僕にコーヒーを淹れさせて、自分はソファでくつろいでいるんだよ。だけど、持ってる人間は違うよね。こうやって、ちゃーんと希望の物がやってくる。」 おちゃめな一面を見て、3人は思わず噴き出した。と、その時、再びドアがノックされた。「教授、報告を忘れていたんだけど…。あれ?お客さん?」「ちぇっ、こいつも持ってる奴だったのか」 篠原は眉をしかめて言う。「彼が、さっき話した老人にコーヒーを淹れさせた男だよ。本田君、君の会いたがっていた若者たちだ。ラッキーだったね」「それはどうも」 本田は、にやりと取り澄まして微笑むと、3人に向き直った。「僕は本田新之助、弁護士だ。篠原教授のもとでしばらく研究していたんだけどね。弁護士の仕事も気になっていて、今はそちらに注力している。それで、君たちが素晴らしい成果を上げたと聞いて、会いに来ていたんだよ。ところがどこかの偏屈がなかなか会わせてくれなくてね」 ぐふっと教授がむせている。 研究成果を詳しく聞いた本田は、身を乗り出していた。まるで自分がすでにその手術を受けると決まっているかのようだ。「来週、僕も手術を受ける予定です。仁が空いていれば、ですが」「まったく素晴らしいね。じゃあ、今度そんな君たちに活躍できる案件を持ってくるよ。その成果をぜひ目の当たりにしたいんでね」 美月の言葉にすっかり乗り気の本田は、それだけ言うと、再びにやりと笑って部屋を出ようとした。「おい、本田君。君、報告があって戻ってきたんじゃないの?」「教授、その報告、彼らと手を組んで一仕事してからにさせていただきます。では」 今度こそ、本田はあっさりと飛び出していった。「なにが、では。だよ。まったく」 篠原は、さっさと出て行った教え子の後ろ姿を見送りながら、一宮特製のフィナンシェを頬張った。つづく
October 21, 2022
コメント(2)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード3
エピソード3 料亭を思わせるような純日本家屋の一室に、微かな香の香りが漂っている。竹細工の細い花器には、りんどうの花が生けられていた。茶室には、名だたる会社の重鎮たちが静かに座っている。 おもむろにふすまが開いて、美しい髪を結い上げた着物姿の若い女性が現れた。「一服さしあげます」 丁寧に頭を下げ、そそとした様子で茶器の前に座ると、優雅な所作でお茶を点て始める。そこに年配の女性がそっと入室してきた。「皆さま本日は、お忙しいなかお越しくださってありがとうございます。どうそ、お菓子を召し上がってください。」 そう言うと、出来立ての抹茶を小袱紗に乗せ、目上の者へと運んでいく。若い女性はすぐさま次の器を取り出し、また、流れるようななめらかな所作で次の抹茶を点て始めた。 一通りの客人に抹茶が渡されると、年配の女性は、主に目配せしてそっと退室した。「こちらのお嬢さんは、会長の?」 好々爺然とした客が目じりを下げて問うた。「ああ、上の孫娘だ。貴絵という。結婚より研究だなどとぬかしおって、まったく。」 口は悪いがまんざらでもない様子の老人に、茶道具の始末をしていた手を止めて、若い女性が主をキッと睨む。「これ、客人の前でそんな顔をするでない。ははは」「一宮製薬の会長を睨みつけるとは、これはなかなかの大物でいらっしゃいますね」 楽し気な客人にそっと頭を下げると、若い女性はさっさと退室していった。 控えの間に入ってくると、すぐさまお手伝いの佳子が茶道具を受け取り片付ける。「お疲れ様。いつ見ても貴絵のお点前は優雅よね」「もう、せっかくの休日だったのに、急にお茶を点てろとか言い出すんだもの。おじいさまにも困ったものだわ」「ふふふ。あれでもあなたの事を自慢したいのよ。さっきのお声を掛けられた客さん、橘製薬の会長さんなんだけど、どうやらお孫さんのお嫁さんを探しているらしいのよ」」 ご機嫌な母に、あきれ顔の貴絵はため息をつく。「やめてよ。着替えてくるわ。午後から調べ物がしたいの。次は萌絵に頼んでね。」「あら、萌絵はダメよ。休みになれば早朝からいなくなるわ」「何してるのかしら?」 母はここぞとばかりに大きなため息をついた。「大きなバイクの免許、いつの間にか取っていて、勝手にバイクまで買ってたのよ。女の子なんだから、もっとおしとやかに…」「お母さま、自分の理想を押し付けたら、可哀そうよ」 貴絵はそういいながら、部屋を出て行った。「うん、もう!」 文句が言い足りない母は、残念そうに娘を見送った。 艶のある長い髪を下ろし、パンツスーツに着替えた貴絵は、早速院内の図書館で専門書を借りてきた。そして、その数冊を取り出すと、研究室の片隅を陣取った。調べ物をするなら、ここと決まっている。カバンから取り出した水筒には、淹れたてのグァテマラが入っている。お茶を点てる貴絵は、珈琲も大好きなのだ。マイカップに注いでいると後ろから声がかかった。「おや、一宮君、来てたのかい。」「お久しぶりです、篠原教授。」 篠原は、この大学院の研究所の所長だ。御年72歳。そして、珈琲に目がない一人だ。「教授、ご一緒にグァテマラ、いかがですか?」「いいねぇ。実は匂いにつられてやってきたんだよ。わはは」 教授の手には、ちゃっかりカップが握られていた。貴絵がカップに珈琲を入れている間に、篠原はぽつりとつぶやいた。「もう、声はかけられたかい? やつら、また新しい悪だくみをしている様だよ」「ええ、脳の電気信号の世界的権威のボルドー氏が協力してくださるとかで、脳神経先進国のサイエン王国に研究施設を作るそうです。 はい、どうぞ」「ああ、ありがとう。いい香りだね。 向こうに行ったきりになるのかい?」「いいえ、みんなそれぞれ活動しているので、いける時だけになりますが、常に取り組める場所があるのはありがたいですから。」 受け取った珈琲をうまそうに飲んで、篠原はちらっと貴絵に目を向けた。「気を付けるんだよ。君たち、やりだしたら絶対成果を上げてくるんだから。目立っちゃうと、妬んだりつぶしたがるような輩も出てくるんだからね。 それじゃ。」 軽快な会話だが、中身は重い。山高帽をぽんと頭に乗せると、篠原は帰っていった。それを見送った貴絵は、再び調べ物に没頭する。アメリカの発明家によって、メディアCDはすでに実現しているが、サイエン王国では、まったく違う分野でデータの記憶媒体が開発されつつあるという。「まさか、人間の脳とその記憶媒体をつなごうって言うんじゃないでしょうね。」 はたと思い当って、その場にいない誰かを叱るように呟く。目の前のカップを手に取ると、冷めかけた珈琲を一気に飲み干して、あきれたようにため息をついた。「あの人達ならやりそうだわ」つづく
October 20, 2022
コメント(2)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード 2
エピソード2「ねえ、見て見て! ほら、今入ってきた人!彼が美月さんよ。 はぁ、いつ見てもかっこいいわねぇ。」「へぇ。金髪なんだ。」「そ、イギリス人のおばあさんがいるって聞いたよ。ウォーターなんだって」「かっこいいー!」 着飾った女たちが目を潤ませて見つめる先にいる男は、美月司。金髪にブルーグレイの瞳が目を引く。すらりとした体格で、少女のような長めのボブスタイルにしているが、一度その瞳に射抜かれたら、逃げられないと噂になるほどの美丈夫。もちろん、そんな彼に射抜かれるような女は、ほんの一握りだ。ビジネス街と観光地が隣り合ったこの都市は、夜も眠らないと言われている。腹に響くような重低音でカルチャークラブが鳴り続くクラブハウスは、危険な夜遊びの相手を探す若者であふれていた。美月は慣れた様子でカウンターに腰かけると、ブランデーをロックでオーダーする。細目の葉巻をくゆらせて、ふわっと煙を吐き出すと、スツールをくるりと回して店内をゆっくり見まわした。色気だだ洩れのそのしぐさに、女たちのため息があふれる。「どうぞ」 すーっとカウンダ―を滑らせて、グラスが掌に届く。 カランっと氷が転がる音が小気味好い。美月は葉巻を消して、ゆっくりと氷の解けるさまを鑑賞した。「ねえ、今日はお一人?」 前髪をとさかのように巻き上げ、ソバージュヘアに胸の広く開いた肩パット入りのワンピース、煽情的な上目遣いで一人の女が声を掛けた。「ああ、そうだけど」 その姿を目の端に捉えつつ、ブランデーの香りを楽しんだ。その様子を見て、口角を微かに上げた女は、ぐいっと距離を詰める。「ねえ、私のお店に来ない? ここじゃ女の子の露出も少ないし芋っぽい子が多いじゃない?」「マスター、これ、ヘネシーじゃないね。レミーなの?」「はい。ちょっとお客さんの反応見てみようかと。いかがですか?」「うん、悪くないね」 美月はグラスを傾けながら言う。「ねえ、聞いてる? もっとおいしいお酒、あるわよ」 隣のスツールに座り込んで、尚も続ける女をちらっと眼の端にとらえ、ふっと笑った。「遠慮しておくよ。ここは僕の店なんだ。お客さんを悪く言われるのは不愉快だ」「え?」 女はしなだれかかっていた体をすっと離した。「あ、あら。ごめんなさい。」「それに、違法薬物を扱う店になんて出入りしたくないからね。君、気を付けた方がいいよ。ここは警察官立ち寄り店だからね」 女の眉間にしわが入るのと、肩を叩かれるのが同時だった。「2丁目のスナック「粋」のママ、吉川忍だな」「え?そ、そうよ」「違法薬物所持、および強要の疑いで逮捕する」 女はすぐさま立ち上がり、美月を睨みつけたが、相手にされることはなかった。「ご苦労さんです」「ご協力、ありがとうございました。」 客を装った警察官が、女を連行していった。その様子はまるで客が帰っていくような手際の良さだった。「美月―!久しぶりだな」「やあ、仁!」 ずかずかと近寄って、遠慮なく隣にドカッと座り込んだ男は、ご機嫌な様子で同じものをオーダーする。「いつ帰ってきたの?」「ん、さっきだ。羽田から直行だよ。美月、お前に会いたくて!」「寄るな、触るな。僕は女の子しか相手にしないから。」 仁に抱きつかれた腕をメリメリとはがしながら言う。「ふふ、今回はちょっと面白い情報が手に入ったんでな。藤森も呼んで、作戦会議だ」「じゃあ、貴絵も呼ばないと。彼女、メスは持たないけど薬物は好きなだけ手に入れる人だからね。」「やだー。俺、突然死は嫌だ」 おどける仁、こと、奥平仁は、がははと笑う。奥平の専門は外科手術だ。都内の病院に勤務していたが、他国からの依頼が多くなって、今ではフリーの外科医となっている。無造作に伸ばした髪をオールバックにまとめている。ワイルドな風貌だ。 一方、美月は大学時代の後輩にあたる。時代の流れに敏感で、いくつかの企業を立ち上げている起業家だ。この店もその一つなのだ。 二人がそっと席を立つと、女性客たちが寄って来て声を掛ける。「美月さん、もう帰るの? 一緒に飲みたかったわ」「ごめんね。急用ができたんだ。またここに来るよ。じゃあね」 美月は女たちを軽くあしらうと、カウンター内のバーテンダーに目配せして、そっと店を出た。****** 大通りに面したビルを小さな路地へと曲がり、勝手口のような小さなドアを開くと、細い階段を下りていく。まるで隠れ家のようなこの店は、藤森のお気に入りの場所だ。薄暗い店内には、静かなジャズが流れていた。「あ、やっぱりここにいた。んー、ジャズもいいね。これ、ビル・エバンス?渋いね。」「涼、久しぶり!」 二人はするすると階段を降りると、藤森をはさんでカウンターに座った。「仁、いつ帰ってきたんだ?」「はは、今日だ。で、ちょいと相談があるんだ。ねえ、部屋、空いてる?」 仁は、今夜二度目の質問に笑いながら答え、後半をバーテンダーに向かって言った。無駄のない動きでVIPルームへと導かれると、オーダーもそこそこに、いきなり本題に入った。「涼、ついにボルドー氏から了解を取り付けたぜ。」「え、本当に?」「ああ、ヤツからの条件は、本人の住まいの近くに研究施設を建てること。医療機器なんかは、向こうが提供してくれるらしい。」「僕が調べたところによると、サイエン王国の国立病院の隣に製薬会社が撤退した跡地があるから、そこが有力候補だね。」「なるほど。で、国立ってことは、サイエン王国の王室の許可が必要ってことだろうけど」「ああ、それは俺が手を打ってある。今回の海外遠征は、なんとサイエン王国だったんだ。王室にもしっかり恩を売ってきたから話は早いだろう」「篠原教授と貴絵にも連絡は取ってあるよ。教授からは、慎重に動くようにって指示が来てる。まあ、ちょっと技術的に、一般の企業とは大きくかけ離れるからね」「了解した。仁、王室の許可が下りたらすぐに連絡してくれ。土地と建物の売買については、こちらで手配しよう」 美月の報告に頷いていた藤森は、それだけ言うと満足気にゆったりとソファに体を沈めた。 一通り話が付いたところで、酒が運ばれてきた。3人はそれぞれグラスを手に取ると、「チア!」と声を掛けて酒を煽った。つづく
October 18, 2022
コメント(3)
-
言い訳
えっとですね。この「エグゼクティブ・チーム」の時代背景は1980年前半ぐらいから始まると思ってください。世の中は、バブルに向かているころ。まだケータイ電話もありません。音楽機器は、ウォークマンが最新です。そう、まだテープレコーダーに録音していた時代です。CDだってまだ巷には出回っていません! どうだ、驚いただろう~。。。ま、そんな時代のお話だと思ってください。ま、言い訳ですけど。
October 17, 2022
コメント(0)
-
エグゼクティブ・チーム エピソード1
エグゼクティブ・チームエピソード1 静まり返った深夜の街を、男を乗せたタクシーが進んでいく。この男、藤森涼という。学生時代、バスケットをしていたからか、手足が長く、すらりとした体形だ。前髪をかきあげ、アルマーニのスーツを軽く着崩している。子どもの頃から脳科学に異様な興味があり、留学先から帰っても、そのまま大学院の研究室にとどまっている。 その日は、難問だったプロジェクトが無事終了したことで打ち上げに参加していたのだ。窓を少し開けると、夜風が酒で火照った頬に心地いい。藤森を乗せたタクシーは、マンションに近い海沿いの道を行く。月が波間に光を躍らせていた。「そこの角でいいよ」「分かりました」 タクシーを見送ると、吸い寄せられるように波打ち際までやってきて、水面に輝く月の光を眺めた。長らく外を歩いた記憶がない。そういえば、気に入って観ていた大相撲も、先の夏場所でだれが優勝したのかさえ知らない。こんなに集中して仕事をしたのは、久しぶりだ。 ゆっくりと深呼吸をすると、藤森は街中に向かって歩き出した。月の光は水面に限らず、住宅の屋根にも降り注いで、すっかり街の風景を変えている。異世界に来たような不思議な感覚を味わいながら進んでいくと、小さな足音が聞こえてきた。 不安げなその足音の主は、月の光を浴びてふわりと空から降り立ったように、交差点の角から現れた。ふんわりとしたシフォンのブラウスにひざ丈のチェックスカート。いわゆるハマトラファッションだ。出会いがしらにぶつかりそうになった女性は、「ごめんなさい」と丁寧に頭を下げると、再び何かを探す様に歩き出した。 こんな夜更けに大丈夫なのか? 藤森の脳裏にそんな言葉が浮かぶ。そのまますれ違って数歩も行かないうちに、車のブレーキ音とズカズカと派手な音楽があふれ出した。「ねえねえ、彼女。どうしたの? これから一緒に夜のドライブなんてどう?」「え? いえ。結構です」「なんだよ。冷たいこと言わずに。こんな遅い時間に一人じゃ危ないよ」「い、いや!離して!」 異変に気付いた藤森はすぐさま踵を返す。「おい、なにやってるんだ!」「ち! 男連れかよ」 車はすぐにその場を去っていった。「あの、ありがとうございました。」「いや、それはいいんだが、さっきから何か探しているのか?」「そうなんです。カバンに入れていたはずのウォークマンが無くなっていて…防波堤で音楽を聴いていたので、そこまでは確かにあったんですが」 困り果てた様子は迷子のようだ。藤森はとりあえず海岸まで付き合うことにした。「今日は月が大きく見えるね」「そうなんです!だから、波に輝く月の光をゆっくり堪能したくてつい遅くまで居座ってしまって…。 あ!ありました!」 見ると、防波堤の手前にぽつんとシルバーに輝く機器が見えた。「ちゃんと動くか試した方がいいな」「はい。」 ヘッドフォンを耳に当ててスタートボタンを押すと、静かなメロディが流れだした。「ありがとうございました。ちゃんと動いています。ほら!」 女性は、藤森の耳にヘッドフォンを当てた。「あ、この曲は…。ドビュッシー?」「ええ、月のひかりです」「少し、いいかな」 繊細なメロディーが目の前の情景に同化していく。ん、悪くないな。1フレーズ聞いたところで、少し名残惜しいとさえ感じながら、ヘッドフォンを返す。「さて、では自宅まで送ろう。もう、落とし物はないか?」 何気なく言う藤森に、女性の頬がほのかに赤らんで、恥じらうような笑顔になった。「何から何まで、ありがとうございます」 彼女が出てきた交差点の角まで送ると、羽衣がフワっと流れるように微笑んで去っていった。 自宅マンションまであと数分、藤森は頭の中でドビュッシーの月の光を再現しながら月夜の街を楽しんだ。つづく
October 17, 2022
コメント(0)
-

イッチョコマエ!
再び、雨と共に涼しく…、いえ、寒い空気がやってきました。このしとっと潤った空気も割と好きなしんたです。ところで、毎年、少しずつ花開いていくうちの金木犀は、どういうわけか、今年は、せーの!で花開いてきゅんとするような甘い香りを広げております。ん、いい香り♪♪ なんて、家族はご機嫌ですが、これって、パッと咲いてぱっと散るヤツじゃ…。いやいやそこは揃えなくていいのよ。ぼちぼち咲き始めて、なが~く楽しみたいじゃない。ところで、我が家の水菜たちは、すくすく育っております。もうイッチョコマエに水菜らしいはっぱまで出しちゃって。うふ。こんなふうに、自然は豊かにそして着実に季節を進めているのですが、私は…あ~~~!! 進まん!でも出したい。駄作ばっかり書きやがって!もうちょっと実のあるものを書きやがれ!というお叱りの声が聞こえてきそう。。。でも、少し出してみようかな。連日のアップロードは不可です。1話の長さもまちまちです。それから、まだ修正掛けないとなので、完成品を読みたい方は、小説家になろうにUPするまで待っててください。あー-----、完成したら、ですが。。。つまり、まだ書き終わってない。すんません。困ったやつです。
October 17, 2022
コメント(0)
-
時の流れ
子どもたちがすっかり成長してしまうと、動画って撮らなくなるんですね。今度、仕事でたまたま動画を撮って配信することになりまして、もちろんカメラは公的機関の物をお借りするのですが、念のため、自分ちのビデオカメラでも撮っておこうということになりまして…。一体、何年使ってない?? そういえば、こういうの使ってたよねぇ~って感じで出してきまして、動作確認。良かった、ちゃんと撮影できてる♪と、安心していたのですが、なんせ古いのです。データはHDにも入るのですが、公的機関のカメラからも、SDカードでデータをもらってこちらでDVDに焼いて業者に提出という段取りなので、SDカードリーダーを引っ張り出してみたのですが、これ、反応してない。。。我が家のビデオカメラに、以前使っていたスマホのマイクロSDカードを差してデータ保存させたのですが、どうやらそのデータ量にカードリーダーが対応できない様子でした。う~~ん、難しいですね。ちょっと前までちゃんと動いてたやん!しっかりしろ!なんて声かけてみても動かないものは動かない。(ま、この時点で、ちょっと前っていつの話ってことなんですが…)差し込んでるマイクロSDは64GB。そういえば、このカードリーダー買った頃は、ギガ なんて言葉あったかしら。。。という時代物。あえなく買い直しとなりました。皆さんにとって、【ちょっと前】 って、いつ頃のことになります??
October 16, 2022
コメント(2)
-
ひげ抜き士
突然ですが、ひげを抜かれました。。。痛かったまさか本当にやられるとは…!!あれ?しんたさんって、男だったの?いえいえ、違います。どういう訳かあごの先に一本だけ生えてたんです。それをね、うちの娘(ミニしんた)がすごく気にしてて、毎夜あごチェックに来ていたのですよ。ひげなんて、抜いたことないし、怖いから、ずっとはさみでカットしてもらってたんだけど、とうとう、さっき。「お母さん、ちょうどいい感じに伸びてるわ! 今が NU・KI・DO・KIよ!!」と、迫ってきたので、うっかり許可したら。。。ブチっとやられました。はぁ、痛かった。
October 12, 2022
コメント(2)
-

芸術の秋!
本日は10月10日スポーツの日。え? 体育の日じゃないの??う~ん、祝日の呼び名が替わったり、日にち自体が替わったり、昭和生まれには戸惑うことの多い今の制度。だけど、やっぱり秋めいてくると、【芸術の秋】は外せない。ということで、昨日は兵庫陶芸美術館に行ってきました。今は、ルネ・ラリック アール・デコのガラス展をやっていて、なかなかの見ごたえでした。下の画像は、途中で寄った播州清水寺で咲いていた「10月サクラ」です。4月の桜のようにたくさん花をつけているわけでもなく、ハラハラと雪が舞っているかのような楚々とした風情でした。ところで、これ。何かご存知ですか?子どもの頃、ご近所のおばあちゃんにもらって、食べたことあるんですよ。中の実はルビーみたいにきれいで、すっぱくて、かすかに甘い。。。これも、播州清水寺で見つけました。この後、パラパラ降り出した雨は、土砂降りになって、美術館には行ったけど、窯元めぐりはあきらめたのでした。さて、さっきの画像、知ってる人、いるかなぁ。。。柘榴です。ザクロ♪
October 10, 2022
コメント(2)
-

寒い!
昨日から、ぐんと気温が下がって秋らしくなってきました。そろそろお鍋の支度かな。。。あ、お鍋と言っても、材料を植えるところから。w数日前に種をまいておいた水菜です。最初は、サラダに入れて。株が大きくなってきたら、お味噌汁の具にしたり、お鍋に入れたり♪去年プランターに植えてると、とっても便利だったので、今年もやっております。そう、辺りが暗くなったころ、こそこそと庭先のプランターに水菜を引っこ抜きに来る不審者出没!はい、私です。きちんと二列に種まきしたのですが、種まきの翌日に強い雨が降ったせいか、ばらばらに芽が出てしまいました。ま、食べる分には関係ないけどねぇ~実は秋茄子も順調に育っています。 wお漬物にしようか、甘辛く煮付けてもおいしいかな。田楽にしてもおいしいよねぇ。。。あ、夏にやってた輪切りのナスにとろけるチーズをのせて、オリーブオイルで焼くの。ひっくり返してチーズをカリカリにしてぱらっと塩コショー…ん、あれもおいしいかも♪やばい、痩せる気がしない。
October 6, 2022
コメント(0)
-
寂しい。。
昨日、ある人の訃報の聞いた。その人は、私にとっては大叔母。御年100歳!!実家のご近所に住んでいたので、我が実家にもよく顔を出してくださって、子どもの頃の私が大好きな「おばちゃん」だった。我が実家に来るとき、いつも子供の喜びそうなおやつを持って来てくれる人で、笑顔が絶えない人だった。病気でご主人を亡くし、その後、一人娘(母のいとこ)も病気でなくした「おばちゃん」は娘婿と孫たちと、それでも元気にいつも笑顔で暮らしていた。晩年は、耳が遠くなって、電話しても聞こえないのに、私が電話すると、ちゃんと電話に出てくれて、「しんたちゃん、元気~? おばちゃんは元気でやってるよ。耳が聞こえないから勝手にしゃべるけど、ごめんね~」なんて言いながら好きなだけしゃべって電話を切るおちゃめな人だった。先月、コロナ陽性者になって、救急車で運ばれたけど、無事に治ったって聞いてたのに。。お葬式、誰も参列できない。これが現実なんだなと、痛感した。おばちゃん、安らかに…
October 3, 2022
コメント(4)
-

無事、咲いています
先日買っていたトルコ桔梗。無事、根付いてくれたようです。涼し気に咲いております。トルコ桔梗 雅というらしいです。だけど、ネットでは1年草扱いなんですよねぇ。今日は久しぶりに奈良の実家に顔を出しました。高齢な両親ですが、とっても元気!コロナで行くのを控えていたので、おしゃべりしたくてうずうずしていた母は、ずーっとしゃべり続けておりました。あは。。。近いうちに子供たちも連れて行かなくちゃ。
September 29, 2022
コメント(0)
-
逃げだと言わないで。
今日は珍しく短編を掲載しました。え、先日言ってたバブルの小説は?あ~、あれも書いてるんですが、プロットが定まらなくて苦戦中。ということで、気分転換に書いていた短編を掲載することにしたのです。「笑子さんの一日」この笑子さんとは、実在の人物をモデルにしています。その名もずばり笑子さん。(笑) 本名です!実は、私の叔母です。笑子おばさんへのオマージュなのです。若くして病気で亡くなったので、私はおろか、母ですら会ったこともないのですが、生前、祖母から聞いていたエピソードを基に、イメージを膨らませて書いたものです。ん、会いたかったなぁ。。。
September 26, 2022
コメント(0)
-
笑子さんの一日
笑子さんの一日 笑子さんは僕の同僚。朝は8時30分には出社していて、ホットコーヒーを飲みながら経済新聞を読む。僕が出社すると、「おはようございます」と笑顔で挨拶してくれるんだ。え?そんなこと普通だろって?いえいえ、よく周りを見てよ。僕の「おはようございます」に答えてくれるのは、「うっす」「おお」「はよ」「ども」。ちゃんとした挨拶が帰ってくるのは笑子さんだけだ。 そんな笑子さんのことを、僕はこっそりにこちゃんと呼んでいる。だって、いつだって穏やかな笑顔だし、名前もね。笑子さんは、とても誠実で丁寧な仕事をしている。取引先が間違ったことを言っても、責めたりせず、根気よく説明しているので、結局物事は穏便につつがなく進むんだ。だけど、最近、僕はあることに気が付いた。笑子さんには、いろんな人からプレゼントが届くのだ。昨日も、取引先の営業さんがシュークリームをどっさり持ってきた。もちろん、みんなに配れるように配慮してくれていたけれど、渡し方がね。「笑子さーん。今日はスイーツを持ってきました。いやぁ、先日の書類、助かりましたよ。たまには甘い物でも食べてゆっくりしてくださいね」「まぁ、気を使わせてしまって、ごめんなさい。お仕事の事はお互い様じゃないですか。うふ。でも甘いもの大好きなので、嬉しいです」「でしょ?きっとお好きなんじゃないかと思ってたんですよぉ」「まぁ!美味しそう♪ ご一緒にどうですか?」「いやいや、私はこれで失礼します。」 話しながら中身をチェック。ああ、その笑顔。可愛すぎ!!「笑子さんばかりずるーい」 若い社員の佐伯さんはそういうけど、それとて、決して本気で妬んでるわけでもなく、ともすれば、おすそ分けが欲しいだけだったり。「ふふ。みんなでいただきましょう。」「やった! じゃあ、お茶入れてきますね。」 そうやって、営業さんの前ですぐに中を確かめる辺り、計算ずくかな? みんなが営業さんにお礼を言うので、なんだか嬉しそうに帰っていった。うん、次もなにか来るな。 みんながお茶タイムする10時。それぞれがビル内の自販機やコンビニで飲み物を買って一息入れる頃、笑子さんは夢中で仕事をしている。その真剣な横顔を見るのが好きなんだなぁ。「寺島くん、今日も笑子さんに見とれてるのね」 一瞬で顔が熱くなった。え、そ、そんなつもりはなかったのに。 そっと笑子さんの様子をうかがうと、なにやら険しい顔でモニターとにらめっこ中だった。こんなに傍で話していても、てんで聞こえないんだよなぁ。はぁ。「よっし!!」 突然笑子さんが声をあげて、僕らはひっくり返りそうになった。「ねえ、寺島君。見て! A-トレイドの輸出分、船が見つかったのよ! この値段なら、採算が合うわ」 僕の手を取ってご機嫌で話す笑子さん、うう、可愛すぎる!!「やりましたね! じゃあ、お祝いを兼ねて帰りにお茶でも…」「さぁーて、忙しくなるわね。うふふ。私、ちょっと飲み物買ってくるわ」 ご機嫌で席を立つ笑子さんの後ろ姿には音符がいっぱい飛び交っている。「あ~、今日もダメだったか。寺島君、がんばれ」「佐伯さん…。他人事だと思って」 佐伯さんはぷはっと噴出して笑っている。ちぇっ、何とでも言ってくれ。だけど、笑子さんを見ていると、もうそれだけで幸せな気分になるんだよな。 午後になって、仕事に集中していると、目の前にトンっと珈琲が置かれた。驚いて顔をあげると、笑子さんが笑っていた。「今やっと、一区切りついたんだけど。さっき、何か言いかけてなかった?」「え? あ、あの。」 ああ、すっかりタイミングを逃してしまって、お茶に誘える雰囲気じゃないなぁ。おろおろしていたら、意外な言葉が聞こえてきた。「もしよかったら、今日の帰りお茶でもどう?」「ええ!いいんですか?! じゃあ、よろしくお願いします!」 僕の返事に満足したように、ニコッと笑うと、笑子さんは仕事に戻っていった。「ちょっとちょっと、寺島君! さっきの笑子さん、なんだって?」「え? ん~、秘密です!」 好奇心の塊みたいな佐伯さんが、椅子ごと転がって聞いてきたけど、僕は本能的に言わないことを選んだ。 「ちぇ~、じゃあ、明日、どんな感じだったか教えてね! ふふふ」 え?なんだ、分かってたんじゃないか。だけど、そんなこと、気にならないくらいテンションが上がってる。うわわ。時計は4時を少し回ったところ。あと1時間、嬉しすぎて仕事に集中できないよ。 あっという間に時間が過ぎた。5時ぴったりに佐伯さんは帰っていった。僕の後ろを通るとき、「がんばれ~」なんて言いながら。 机の上を片付けていると、席を外していた笑子さんが戻ってきた。後ろにまとめていた髪を下ろして、お化粧直しもしている。「寺島君、帰れそう?」「はい、もう大丈夫です!」「そう。隣のビルに新しい店舗が入ったの。ちょっと行ってみたかったんだけど、どう?」 ふふ、笑子さんの目がキラキラしている。僕らは早速隣のビルに出かけてみた。 オープン早々という事もあって、お店の前には行列ができていたけど、そんなこと気にならないくらい、笑子さんは話上手だ。気が付くと、窓際の席に案内された。高層ビルの最上階ということもあって、見晴らしが良い。「いいお席ね!」「見晴らしがいいですね」 二人で話していると、ウエイターがそっとメニューを差し出した。「ありがとう」 笑子さんはすかさずお礼を言ってる。「あ、いえ」 ん、このウェイター、ちょっと照れてる? そっと表情を確かめると、見知った顔だった。「あれ?城之内?」「え?あ、寺島? 久しぶりだなぁ」 驚いた。大学時代の友人がこんなところで働いていたとは。二言三言懐かしい話をして、オーダーを取ると、彼は「じゃあな」と言ってカウンターに戻っていった。 その間、笑子さんがニコニコしながら僕らを眺めていた。「お友達?」「ええ、大学時代の友人です。」「いいわねぇ。 ちょっと羨ましくなっちゃったわ」 笑子さんの目に、ほんの少しだけ寂しさがにじんでいる。「笑子さん?」 僕が彼女の瞳を覗き込むと、いつもの笑顔を見せて、それから、一瞬真面目な顔になって忠告された。「あのね、友達が、いつだって傍にいるとは限らないじゃない? 地球上にさえいてくれたら、ネットを駆使していくらでも交流できる時代だけど、星になっちゃったら、さすがに会えないし、声も聞けないでしょ? だから、今のうちに、いっぱい友達とは交流することをお勧めするわ」 それじゃまるで、笑子さんは友人を亡くしてしまったみたいじゃないか。そんな風に聞いてみると、笑子さんはゆっくり頷いた。「もう随分経つけど、学生時代からの親友を亡くしてしまったの。病気だった。いつも明るくて、仕事が大好きな人だった。だからつい、お互い仕事に夢中になって、連絡するのを忘れていたの。」 静かにそういうと、オレンジから紫へ色を変えていく空を眺めていた。「そうか、だから…」 僕の中で、何かがストンと心に収まった気がした。言葉を止めたのは、笑子さんの心が遠くの友達に向いていたから。 僕はそっと席を立つと、城之内にこっそりスイーツをオーダーした。城之内に言わせると、メニュー表を持って行って、きちんと目を合わせてお礼を言われたのが初めてだったんだとか。「かわいい人だな。俺も思わずキュンとなったよ。」「え、おい!」 焦る僕を見て、楽しそうにニヤニヤしていた城之内は、「がんばれよ」と言って、仕事に戻っていった。ほどなくして、最初にオーダーしたコーヒーが運ばれてくると、笑子さんはいつもの笑顔に戻っていた。「いい香りね!」「そうですね。城之内は昔からコーヒーにはこだわりを持っていましたから」「失礼します。こちらをどうぞ」 話していると、城之内がにんまり笑って笑子さんの前に特大プリンパフェを差し出した。「まぁ!どうしたの、これ。」「寺島をこの店に連れてきてくださったお礼です!またいつでも来てくださいね!」 スプーンが二つテーブルに置かれる。これは、二人で食べろってことか?そういうつもりではなかったんだけどなぁ。 焦っていると、笑子さんの楽し気な笑い声が聞こえてきた。「わぁ、ホントにいただいてもいいの?じゃあ、遠慮なく! 寺島君、いただきましょう」「あ、え? は、はい!」 にやりと笑う城之内をむっとして睨んでいると、ご機嫌な声でスプーンを握り締める笑子さんがいた。「寺島君、いい仲間がいるのね。なんだか、安心したわ」「え? どういうことですか?」 聞き返す僕には答えずに、笑子さんは「さあ、食べよう!」とトッピングの生クリームを頬張っていた。 彼氏でもないのに、同じカップのパフェを分け合うなんて、まずいかな、なんて考えていた自分が馬鹿らしくなるほど、笑子さんは楽しそうにパフェを食べ進める。「ほら、寺島君もがんばって食べないと、私が太っちゃうわよ」「そりゃ大変だ。あ、このメロン、もーらい!」「じゃあ、私はこっちのサクランボ、もらっちゃうわよ」 気が付くと、隣の席の女子がこちらを指さしてオーダーしている。向こうのカップルも…。 楽しい時間はあっという間だ。駅まで他愛のない話で盛り上がって、僕は焦っていた。僕の気持ち、いつ切り出そう。「笑子さん、あの…」「ん?どうしたの?」 キラキラした瞳が僕を捉えている。うう、かわいい! 思わず見とれていると、急にその瞳が掲示板に移ってしまった。「あら、もう電車が来ちゃうわ。ごめんね。続きは明日、会社でね。今日は楽しかったわ。ありがとう。じゃあ、また明日ね!」いつもの笑顔のまま、笑子さんは電車に飛び乗った。 ホームに残ったまま手を振ると、いたずらっ子のようにニカっと笑う笑子さんを、電車があっさりと攫って行く。 駅のホームの端まで歩いてみた。ふうっと、ため息が漏れる。笑子さんの乗った電車は、とっくに見えなくなっていたけど、なぜか僕の心の中は、ほっこりと暖かだった。 きっと明日も、8時30分には笑子さんは出社している。よーし、明日もがんばろう!おしまい
September 26, 2022
コメント(2)
全917件 (917件中 201-250件目)