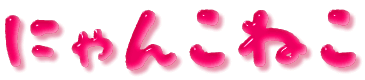命名・由来
~* みなさんは一生名乗る子どもの名前をどのように決めますか? *~名前は、貴方から赤ちゃんへの最初のプレゼントです。
いろんな理由で名前をつけていると思いますが、
私は苗字に合った字画から考え、その画数にある漢字を探し
音の響き(音運)や漢字の意味を当てはめました。
(/(@_@)\ 8ヶ月に及ぶ大変な作業だったわん~)
字画なんていうと【古いっ!】なんて思うかもしれないけど、
私にとっては、たとえそれが迷信でもなんでも、
赤ちゃんにマイナスの要素を与えたくなかったんです。
最高の名前をつけてあげて それでも不幸が襲ったら・・・・
それはそれで、諦めもつくと云うもんですっ! はいっ!(結構いい加減)
それと、将来娘がグレた時の言い訳用でもあるんだなぁ~♪(爆)
娘「私はどうしてこんなに不幸なのぉぉぉっ!!!」
母「なに言ってんだぃっ!
あんたの名前は将来成功を掴む立派な名前なんだよっ!」
娘「ママァ~~~ごめんなさ~~い~~」
・・・・・なわけないか。( ̄- ̄) シーン・・・・
ちなみに、候補に上がっていた他の名前に「琴音(ことね)」「りの」「ゆうり」など
思いっきり古風か今風かで考えてたのよね・・・。
【命名】 ○○○
いつも健康でいて、どんな苦難があっても前に進んで行けますように♪
▼ 姓名判断 占い ▼
◆ 21世紀の姓名判断命名navi 一番のおすすめ。音運も調べられるよ
◆ 「名付けと姓名判断」 こちらもおすすめ。参考になります!
◆ 姓名判断の力 数字や音の響きの意味が画数・あいうえお順に調べられます。
■○○○(苗字)の字画■ 21世紀の姓名判断命名navi より引用
○○○ ○○
○○● ○●
7 3 12 9 6
総運37○ 独立心強く、誠実で努力家。周囲の信頼を得て成功をつかむ。家庭運○。
人運21◎ 抜群の行動力を持ち、仕切り屋でリーダータイプ。
外運16◎ 他人に良くすることが幸運を呼びます。臨機応変な対応が得意。
伏運36◎ 可愛がられて成長しますが、甘やかしは禁物。
地運15◎ 上昇、調和、幸福運。
天運22△ 目の前の幸福を逃しやすい家柄。(家柄が、ガンなのね・・・)
陰陽 ◎ 理想的な配列です。
★各運数の意味
上から順に重要な運数です。
☆総運(人生の象徴:姓の画数と名の画数全部を合計した数)
その人の人生に大きく影響します。一番影響の大きい運です。
例えれば、その人の歩んで行く「道」です。
☆人運(性格の象徴:姓の一番下の文字の画数と名の一番上の文字の画数を合計した数)
社会的協調性を示します。職業の成功に大きく影響します。
吉数なら社会での出世昇進が期待できますし、
凶数なら自営業や学術、芸術等、社会とあまり関わらない仕事に向きます。
2番目に影響の大きい運です。
☆外運(生活の象徴:総運の画数から人運の画数を引いた数。姓・名が一文字の場合は例外)
その人の人生に影のように寄り添って微妙な影響を与えます。
主に生きていく環境を表します。凶数の場合不運に見舞われる可能性があります。
例えれば、総運の道を外れないよう作られたガードレールのようなものでしょう。
☆伏運(宿縁の象徴:人運の画数と名前の画数を合計した数)
他の運数が吉数でもこの運が凶数だと、災害や犯罪に巻きこまれる可能性があります。例えれば、ガードレールの隙間の予期せぬ災害から守ってくれる運でしょう。
☆地運(本能の象徴:名前の画数の合計)
成人するまでの性格形成に影響します。
名前に関しては画数より音運のほうが影響が大きいようです。
☆天運(家風の象徴:姓の画数の合計)
家柄、家系の持つ運を表し、祖先からの宿業が影響します。
★陰陽配列
各文字の画数を奇数は陽、偶数は陰とし、その配列で吉凶を占う方法です。
全部が奇数、または偶数になる名前は大凶名で、
順風満帆だった人生が、突然の不運に見舞われたりする例が多数みられます。
奇数、偶数、どちらかに片寄った名前は命名の際、避けて下さい。
■音運■
○○○
×○(調和名)
主音○ やさしくおとなしそうな性格ですが、内面はしっかり者で強情な面さえ。
次音○ 自分本位に見えるが、本当は面倒見が良い人。
助音○ 先のことを考えている。
頭音AU 一見温厚で優柔不断に見えるが、シンは太く行動力もある。
秘数11 まわりの声など気にもせず、目標に向かって突き進む。
音運判断の説明
調和名・不調和名
不調和名は、主音の性格を消極的にし、悪い面を増長する傾向があります。
ただし、女性で「あかさたな」等あ行で始まる名前の場合、
強すぎる性格を抑え、家庭的な性格になります。
次音・助音
主音の性格にプラスされる性格です。
次音は2番目の音、助音は基本的に名前の最後の音ですが、
4文字名以上で、最後が「う」「い」の場合、その前の音になります。
頭音
姓と名の最初の音を「あいうえお」の5行に分類して組み合わせたものです。
秘数
姓と名をローマ字に変換し法則にしたがって数値化したものです。
濁音
濁音の入った名前は個性が強調されます。
■音の意味■ 姓名判断の力より引用
○ 容貌、スタイルに優れた人が多く、そのためにもてすぎて
自身過剰となり、鼻持ちならないという人もいます。
つまらない小細工をして身を滅ぼすこともあるので、
十分に注意することが必要です。
○ 集まった金をよく散ずる運で浪費癖もあり、ルーズな性格です。
しかも、自分の欠点を棚に上げてしつこく他人を恨むという
困った点もあります。(濁点なので強調)
○ 頭が鋭く、立ち回りも早いので、どの方向に進んでも
ひとかどの成功を収めます。しかし、他人を利用して
あとは省みないという計算高さが他入の根みを買う結果とも
なりますから、注意が大切です。
女性は、芸術家、芸能人として成功します。
ママの独り言「( ̄◇ ̄;) げっ! なんか、良くないじゃない・・。」

【▼柚/▼柚子】
カン科の常緑小高木。中国、長江上流原産といわれる。枝にとげがあり、葉は卵形で柄に翼がある。初夏、白花を開く。果実は径4~8センチメートルの扁球形で、でこぼこがあり、淡黄色に熟す。香気が高く、果汁は酸味が強い。香味料、マーマレードや菓子の材料にする。ユウ。ユ。[季]秋。〔「柚子の花」は [季]夏〕
【柚湯】
冬至の日、ユズの実を入れてわかす浴湯。この湯にはいると風邪を引かないという。[季]冬。
【帆】
風を利用して船を進ませる船具。帆柱にあげて風をはらませ、推進力を得る
【帆掛(け)船】
帆を張って走る船。帆船。ほかけ。
【帆船】
帆を張って風の力で走る船。風帆船(ふうはんせん)。帆前船(ほまえぶね)。ほぶね。
「三本マストの―」
世界大百科事典
【柚・柚子】
[かんきつ類(柑橘類) かんきつるい citrus fruit]
ミカン科の常緑樹で,日本の代表的調味用かんきつ類。果面が粗いことから古くはオニタチバナと呼ばれた。直立性でかなり大木になる。葉は小さく翼葉がある。花は単生で 5 弁花が 5 月に咲く。新芽,花はわずかに紫色を帯びる。果実は扁球形で 100g前後。黄色で芳香がある。果肉は柔軟多汁だが,搾汁率は果実重の 15 ~ 20 %。酸味強く,約 6 %の酸を含み,その大部分はクエン酸である。糖分は 2 ~ 3 %。
ミカン科の常緑小高木。枝にとげがあり、葉は卵形で柄に翼がある。初夏、白花を開く。果実は径4~8センチメートルの扁球形で、でこぼこがあり、淡黄色に熟す。香気が高く、果汁は酸味が強い。香味料、マーマレードや菓子の材料にする。
ユウ。ユ。[季]秋。〔「柚子の花」は [季]夏〕
[分類]
酸味と香りが日本料理に珍重される。皮は薄く切りとって汁物の吸口とし,せん切りにして焼物や煮物にのせ,あるいはおろし金でおろして,みそに加えてユズみそにつくる。果汁はダイダイ,スダチなどと同様,刺身のつけじょうゆに加えたりする。また,果肉をくり抜いて柚釜 (ゆがま) として,中に酢の物やあえ物を詰め,あるいはゆべしをつくる。 10 月下旬ころの 7 ~ 8 分着色期の採収果が果汁が多い。 8 ~ 9 月の未熟の緑色果も香り,酸を利用できる。完全着色は 11 月中下旬。寒さで落果しやすい。また,ふろに入れてユズ湯とし,とくに冬至のユズ湯に入ると,ひびやあかぎれを癒すとか,風邪をひかないといわれ,冬至にはこのための需要が多い。かんきつ類の大害虫であるヤノネカイガラムシの抵抗性因子をもつため,かんきつ類の育種上も利用価値が高い。
[起源と伝播]
ユズは長江 (揚子江) 上流地域で,キンカンは東南アジアから中国南部で生じたと考えられている。
中国での栽培史は古く,ユズ,カラタチは原生していた。前 10 世紀にはタンゼリン tangerine とユズの記録がある。
日本には古くからタチバナが自生していたが,垂仁天皇の時代にトキジクノカクノコノミ (ダイダイだろうといわれている) が導入されたといわれ,中国,朝鮮半島との交易により,かんきつ類が栽培化された奈良時代には橘 (たちばな),甘子 (こうじ),柚子 (ゆず),阿部橘 (あへたちばな) (ダイダイ),枳 (からたち) が知られていた。
[栽培]
日本ではカラタチが用いられ,矮性台で病気にも強いため他の諸国でも普及しつつある。 4 ~ 5 年生より結実し始め,20 ~ 40 年生が盛期。日本では冬季の寒さが最大の限定要因である。耐寒性はシトロン,ライム,レモン,ブンタンはひじょうに弱く,イヨカン,オレンジ,ナツミカンも弱い。ハッサク,清見,スダチ,ウンシュウは強い。ユズ,カラタチはきわめて強い。
[利用]
中国でかんきつ類の果皮は陳皮として古くから薬用にされていた。日本でも古くから生薬として,凍傷,外傷,風邪,解熱,神経痛などに用いられてきた。また,古代インドなどではかんきつ類の果実が銅製品の洗浄,洗髪,食酢に利用されていたし,大航海時代にはビタミンの補給源として重視された。クエン酸の工業用原料になったこともある。強い酸には,味の調整,栄養的効果のほかに殺菌効果もあり,料理によく添えられる。ほかにマーマレード,凍結果肉,七味唐辛子,それに砂糖漬,ゆべしなどの菓子類の原料にされる。ダイダイは果実が落果せず 2 年にわたり結実し続けるため,子孫繁栄の縁起物として,正月のお飾りにされる。キンカンなどは鉢物,庭木としても利用される。香りと色を楽しむミカン酒や 8 ~ 9 月の幼果を搾ったジュースも一利用法である。
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-

- 中学生ママの日記
- クリスマスパーティーはしなさそう?…
- (2025-11-25 11:05:04)
-
-
-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…
- (広告の愚痴)と1~3店舗目 scope半額…
- (2025-11-25 23:38:11)
-