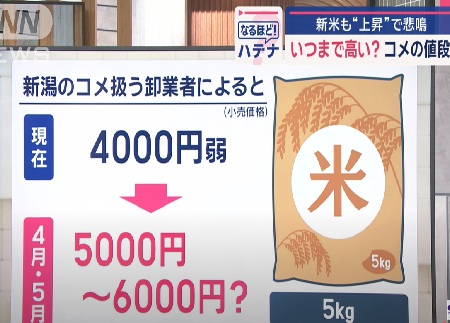第三章 助左衛門、堺に帰る
第三章 助左衛門、堺に帰る (1)今日は天正七年五月十日、南蛮暦(ユリウス暦、1582年10月4日の翌日を10月15日として10日を足してグレゴリオ暦に改めたのでこの時点ではまだユリウス暦)では、1579年6月4日である。五月一日に堺の港に着いてから昨日までは、目が回るほどの忙しさだった。
荷揚げの監督は船頭や脇船頭がしたのだが、助左衛門は人に任せる事が出来ず、あちこち飛び回って声をかけた。荷を船外に下ろす時は、船の帆柱に、斜めに柱を取り付け、柱の先に滑車を付けて、クレーンのように荷を船底から引っ張り上げ、柱を外に振り出して、荷を下ろす。陶磁器の時は特に慎重にゆっくりとやった。
「そらそらそーら、ゆっくり綱をひいて、ひいて、ひいて、止め!、よーし、ゆっくりおろして、おろして、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、そおや、ゆーっくりと、よーおっしゃ、止め!」
身振り手振りよろしく、熱が入る。首無しの吉兵衛はニヤニヤして見ながら、「人にまかされへん性格は、直らへんなあ」と呟く。
助左衛門が一番心配するのは、コーチ(ベトナム)、ルソン(呂宋、フィリピン)、朝鮮、そして明国(景徳鎮などの官窯や民窯のもの)製の磁器や陶器の破損の状況だった。船は横揺れ、縦揺れが激しく、嵐もあり、丁寧な梱包をしないと破損してしまう。
明国の陶磁器の船積みの仕方は、一風変わった積み方である。それは、箱に粘土を敷き、豆をまく。その上に陶磁器を並べ、その上に粘土をかぶせ豆をまくというやり方である。こうすれば、豆が根を出して陶磁器を包み込み、隙間をなくし、あるいはクッションにもなり、大きな衝撃にも耐えるというわけである。明国では古来、このやり方で成功してきた。ただ、この方法で、問題があるとすれば、匂いである。豆の根が腐り始めると、船の中にその匂いが充満し、船室では息も出来ないほど、臭いのだ。助左衛門はそれが嫌で、堺から荷師(にし)を連れていき、陶磁器を藁縄(わらなわ)で梱包するやり方を、あちこちの港で教えて、日本式の梱包で、陶磁器を船に積んだのだった。米が主食の国々なので、稲藁はふんだんにあり、材料に事欠かなかった。どんなに丁寧に梱包したとしても、それがどうなっているか、いつも港に着くと心配になる。荷を開けて、一つひとつの品を取り出し、割れていないのを確かめては、ほっとするのだった。
(続く)
© Rakuten Group, Inc.