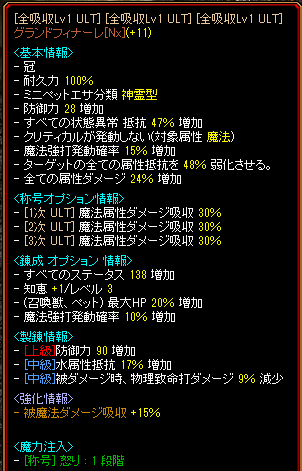置き場
車窓から見える街並みはほんの僅かでしかなかったが、それでもその秀麗なる概観を捉えさせるには十分すぎる程だった。赤土のレンガは建造物を華やかに彩り、白亜の石柱は自らの光彩を惜しみなく際立たせ、石畳は踏み締められたその数だけ人の想いを刻み込んでいた。
馬車の扉が何の前触れもなく開かれる。
絢爛な馬車に相応しく、扉が開いたにも関わらず擦過音は一切ない。馬車のことには詳しくないし、初搭乗ではあったが、そんなボクにもこの馬車がどの階級の人間を乗載させるため存在しているかくらい検討はつく。恐らく今後一生涯、ボクがこれと同等の車乗を利用することはないだろう。うん、きっとそうだ。
「どうでしたか? この乗り心地は?」
扉の向こう側でボクを待ち構えていたのは、案の定ウサギだった。ウサギといったってタダのウサギじゃない。礼装した二足起立のウサギ。人狼という言葉を拝借するなら、人兎となるのかな。その人兔ことピーターが相変わらず表情の読めない面相でボクに恭しく首を垂れる。
「悪くなかったよ。ちょっと暇だったけどね」
「左様ですか。まあ、そこはそれ。今回は少々転送位置がずれてしまいましたから、何卒ご容赦の程を」
あれからボクはこのピーターと旅に出ることになった。その経緯については追々話していこうと思うけど、兎に角ボクはピーターの提唱する取引に応じてみることにしたんだ。理由は単純に「ボクの求めるものを彼が探させてくれる」から。その代わり色々制約も付くんだけどね。まあ今の所関係もないし、その辺はその時が来てから考えようと思ってる。むしろ問題だったのは
朝靄に薄らと浮上するシルエット。
それはこの街を模る存在。精緻なる建築技術によって、優麗に築き上げられた街並み。
レンガを精巧に組み合せた軒蛇腹を冠するルネッサンス調の建造物。木造と石造とを、利便と端正の見地から程よく調和させた橋梁。それらは、未だ靄を貫き切れぬ陽光に対して不満すら洩らさずただ只管に朝を待つ。
石畳は己が上に昨日塗付けられた想いを、また人が踏み拉く前に乾かし固めてしまおうとその身体に落ちる陰影を必死に退かそうと試みている。
大都市だろうと、寒村だろうと変わらぬ夜明けが近付いていく。
朝靄の中。
誰も口にすることこそないが、そこに息づく全ての存在が朝日照る今日を心から待ち望む瞬間。ボクは一足先にその躍動を開始していた。
ボクは少し身を燻らせると、大きく息を吸い込んだ。
例え人類が繁栄する裏に大気の濁りが取り糺されようとも、朝とも夜とも呼べぬ世界。その世界に充満する命の吐息は生まれたての赤子のように芳醇な鮮度を誇る。
まるで妖精のたおやかな悪戯のよう。なんて言ったら「夢見すぎ」とか返って来そうだけど、でもきっとここに立って一つ胸を撫で下ろせばわかるはず。これは当の昔に人が文明との対価に支払ってしまった見得ない宝物だということが。
「早起きは三文の得」なんていうけど。
この揺蕩う息吹がもし一文で手に入るなら安いものだと思った。
残りニ文もきっと素晴らしい使い道があるに違いない。期待も膨らんでくる。
この世界を知らない人々は、「三文」中一文だとて貯金するばかりで使うための意思表示をするのはいつになることやら。貯金したとて三文までしか使えないことに変わりはないというのに。
大通りの路肩を少し跳ねるように歩く。
車道にはまだ早朝とも呼べぬ時間なのに、時折思い出したかのように馬車の宣揚が響く。幾らその存在を示しても、まだ誰も彼を必要とするはずがないのにご苦労なことだ。ちょっと呼び止めて驚かしてやろうか、なんて思ったけど、あまりの吃驚に車輪を外されても困りもの。思うだけで止めておく事にする。
道すがらふと、露店の準備をする光景が目に入った。
さすが要衝と呼ばれる大都市だけのことはある。大通りは車道だけでなく、すでに路肩ですら目を覚まし掛けているらしい。忙しく店内から店外に運搬される売り物。その手際の良さから、この店がこの街と古くからの付き合いであることが窺えた。ただただ開店準備の手際の良さが裏目に出て、早朝から客待ちで欠伸を噛み殺さない事を祈るばかりだ。
そろそろ目的地が見えてもおかしくないハズなんだけど。
ボクは先程から引っ切り無しに辺りを落ち着きなく見回していた。
それもこれも兎人ことピーターの奴が悪いのだ。
ことは一日前に遡る。
ボクはピーターに出会い、そして旅に出ることを承諾した。
その経緯とかは追々話していこうと思うけど、簡単に今言ってしまえば「ボクの望み」を叶えてくれる。そうピーターが言ったからに他ならない。
「信じるか信じないかはあなた様次第です。ですが、ここで立ち止まる事に何の意味がありましょう? などと言うと、殆どの方が訝しげな瞳で仰りますね。『あ、今ちょっと立て込んでるんで』と」
うまい煽り文句だったと気が付いた時には、もうこっちの世界に来ていたんだからしょうがないけどさ。中々にボクはそうした駆け引きにまだまだ疎いようだ。気を付けないと、次はどんな誘導に引っ掛かって見知らぬ街を徘徊させられるかわかったもんじゃない。
「おっと、失敬。ワタクシ、約束事をしておりましたのをすっかり忘れておりました。甚だ欠礼にて詫びる言葉もございませんが、明日はお一人で出向いて頂く事お許し下さいませ」
「ちょ、え? どういうこと? 拒否権とかってないってこと?」
「面白い事を申されますね。まあ、在り来たりにお答えするとすれば「Non」。御座いません。もしこれが和気藹々とした旅行ツアーでしたらば、ガイド不在など許されぬ所作でしょうとも。ですが、これは云い得て妙ながら、全てが自由行動・自由意志の上に成る旅行。あなた様にその権利は発生なさらない、というのが理で御座いましょう」
「ん……それだと、ボクはおまえの言う通りにする必要はないんじゃないの?」
「なるほどなるほど。相互の主張に食い違いがあったようですな。ワタクシが申したのは、『ワタクシがあなた様』
小さい頃からこういう臭いには殊更敏感だった気がする。
饐えた臭い、というヤツだろうか。
人間独特の腐りかけた血肉の芳香。
他の動物の死骸だと、決してこんな生理的嗚咽を齎すほどの悪臭は生じない。特にボクは人間以外の動物の死臭をそこらにいる若者より嗅ぎなれていることもある。間違えようもなかった。この場所で死んだ人がいる。それもこれだけの腐敗臭を、死んでも尚この場に刻み留めるだけの恨みを抱いて死んだ人が。
鬼火の目撃件数と事故の発生率は比例する、と日本社会には古来よりどこから持ってきたのか、そんな決まり文句が存在する。が実際に事故原因と死霊とが関わっている事例はそうそうないと言っていい。中には引きずり込む程に怨の念を辺り構わず飛び散らかす不届き者もいることはいるが、大概の者は無害である。時々「なにをしてるの? 楽しそうね」と興味本位で近づいてきた姿が目撃される程度で、呪い殺されるなど稀も稀。むしろ、そうした要因で死に至ったと安易に思い込み宣揚する人間。その浅はかさの方がボクは怖かったりする。もし事故が多発するのだとしたら、霊媒師を呼ぶ前にその土地の検証を隅から隅まで徹底することをまずオススメしたい。
でもたぶん、ここにはいる。
負の粒子を塊にしたような奴が。
死が鼻腔を擽る場所程度なら、その気になればどこにでも見出すことができるだろう。人間なんて例え車に引かれただけでも、その身も知らぬ相手に壮絶な憤恨を募らせる生き物なのだ。だからそれだけだったなら、ボクは何も気にしないでこの場所を早々に歩き去っていただろう。それだけだったなら。
指が震えるのだ。
右手の親指が。繊細に揺らぐ羽虫の跳梁のように。
ボクのこの親指は小学二年の春、一度だけボクから逃げていった。
親友の小刀がその仲を引き裂いたからだ。
ボクは、ボクという器から暗褐色の蛆虫が幾重にも這い出していくことよりも、ただ逃げていく親指のことが気掛かりだった。親友の「こんなつもりじゃなかったんだ」と喚き叫ぶ声が無償に腹立たしい。ちょっと静かにしててくれないか。逃亡中の親指を探してるんだ。あいつだけ解放されるなんてあり得ない。あっちゃいけないことなんだ。探さなくちゃ。許されないことだ。「先生、わざとじゃないんです」「ど、どうしましょう。せっかく臨時で雇ってもらえたっていうのに」「先生、ボクは悪くないんです」「ああ、やっぱり図工は断っておくべきだったんだわ」「小刀がなんだかそんな感じだったんです」「あの校長のことだから、きっと私に責めよって……」ちょっと。煩いぞ。逃走経路の割り出しに集中してるんだ。邪魔をするならこの世から出てってくれ。
それからボクの右手の親指は動かなくなった。
一つの例外を除いて。
ボクの親指は一足先に冥府の扉を叩いてしまったのだろうか。
「たけしくーん、もう帰りなさーい」
一人校庭のブランコでボクがたそがれていると、用務員の小池さん(齢48歳、独身。実は夢見る乙女だが、そんなに美人ではない。ボク談)がいつものように声を張り上げてきた。ということは、もう四時になるってことだ。
小池さんはまるで時計のアラームのように、毎日毎日四時きっかりになると、校庭のボクに声をかけてくるんだ。何て律儀で時間にしっかりした人なんだろう、と最初こそ子供心に尊敬の念を抱いていたのだが、残業という言葉を覚えた辺りから大人の意地汚い皮裏が見え隠れして敬意もくそもなくなった。だから、大人ってキライだよ。ほっといてくれってんだ、ビス……噛んだからいいや。
とは言うものの、実際問題、小池さんはボクが重い腰を上げるまで、あの金切り声を止めないのもわかってること。本当はもっとここにいたいけど、っていうか家になんて死んでも帰りたくないんだけども、まあ、しょうがない。四時になっちゃったんなら、とりあえず学校は出よう。
そう思って、ボクは軽く揺れ動くブランコから立ち上がった。
校門の向こうに果てしない赤がよく見えた。きっとボクの半身も、焼け付くように紅に染まっていることだろう。辺り一面の大地がそうなのと同じように。
ボクは一日のうち一番この光景が大好きで、それでいてこの時間が一番イヤだった。なぜかって? なんでだろうね。よくわかんないや。子供だから。
この「子供だから」って凄く便利な言葉だと思う。
子供っていったって、世の中わかってるヤツはそこらにいる大人よりよっぽどわかってるってのに、子供として一括りされちゃえば「まだまだ子供」「まさかこんな子供が」扱い。どんなことをしたって、精神未成熟による適切な判断力の欠如とか見なされて大したお咎めもない。もう頭のイイ奴にはして良いことと悪いことの分別なんてとっくのとうに身についてるし、それを逆手に取る頭脳だって備わってる。なのに大人は気が付かないんだ。いいや、フリをしてるのさ。子供はか弱い存在で、自分たちに牙を向けるなどあり得ないって思わないと、不安で手元に子供を置いておくことが出来なくなっちゃうから。
だから子供が図に乗るんだ。
それが少年犯罪の起因ってワケ。
大人はまた気が付かないように、見ないようにしてるけどね。
「うちの子に限って」とか「なぜこんなことに」とか「子供のことがわからない」とか。そんなことよくテレビで目にするけど、そんな時ボクは内心こう呟いてうやるんだ。
違うだろ? そうじゃないだろ? おまえらがさ、意図的に目にしないように背けてただけだろ? わからないんじゃない。わかろうとしないんだ。そうすればすぐわかるさ。あんたらの子供も立派な犯罪者なんだってことがね。
もちろん、テレビに出てる「犯罪者になってしまった子供」の親だけがそうじゃない。どの親もその危険性を内包しているにも関わらず、そんなニュースを目にすると「ウチはこういうことはないから、安心よねー」なんて鷹を括る。括る余裕なんて本当にあるのかどうかなんてわからないのにさ。親は子供のことを知ってるようで何も知らない。その事に子供が気が付いてることすら知らないんだ。だから子供は牙を向く。
まあ、ボクはそんなことしないけどね。
今の少年法はそんなに甘くないって聞くし、何より一年だって自由を奪われるのはご免だ。社会奉仕とか、慈善実習とか。あんなことしたって殆ど救いにもなりゃしない。得られるのはせいぜい自己満足が関の山。まあ、仮にそれで一人辺り一万人の難民が救えるっていうならやってもいいかもね。偽善という称号は持っておくに越したことはないし。
ボクはそんな考え方から、今期学級委員にもなった。
地盤作りの第一段階には丁度いいかな、なんて思ってただけだったんだけど、意外にもボクを形容する言葉の一つに「品行方正」なんて言葉まで飛び出すようになった。思わぬ展開だったけど、首尾としては上々を補って余りある成果だと思う。このまま行けば、色々な恩恵に与れるのもそう遠くないかもしれない。兎にも角にもこの世の中、何が己を語るかって、他者からの見られ方ほど社会的に己を雄弁に語るものもない。ボクは子供だけど、それは知ってる。それを知ってるのと知らないのとでは雲泥の差だってことも知ってる。だから何も知らない他のヤツラと一緒にバカをすることは出来ない。
悪循環だな。なんて思う。
出来ないから、また自分を装って。装った自分が社会では本当の自分として認識されるから、また出来ないことが増えていく。きっとこれはもうレールの上なんだ。誰かがボクのために敷いてしまった――強いてしまった。だからボクは下手にメッキが剥れないようにいつも一人で居るし、また家に帰って仮面の自分を演じるのが面倒だから、こうしていつまでも学校に残ってたりする。
燃えるような夕日が好きなのも、きっと誰でもない真実のボクを一日の終わりに地面に黒々と焼き付けてくれるからだと思った。本当のボクはここにいるよ。ボクは今この時だけ確かな存在を感じることが出来るんだ。
それすらも小池さんにはわからないのだけれど。
「たけしくーん、お家の人心配してるわよー」
うるせぇなババァ。
とつい叫びそうになり、ボクは口を両手で抑えた。
いけないいけない。あの人にとってのボクはきっとこんなことを言わないはずだ。
そう、こうだ。
「うーん。今帰ります。小池さん、さよーならー」
「はい、たけしくん。さよーならー」
それに安心したのか、小池さんはボクに背を向けると、校舎の中に戻っていった。
けれど、ボクはもうブランコに戻ろうとはしなかった。
また小池さんがやって来て、同じやり取りをするのはイヤだったし。
そろそろ戻らないと、母親が心配する時刻だったからね。
だから、むしろ小池さんには感謝している位なんだ。だって、この毎日寸分も違わぬ日常が送れるのも、彼女がきちんとボクに定時を教えてくれているからに他ならないんだから。さっきはババァなんて思ってごめんなさい。とかね。
ボクはブランコの軸柱に立てかけておいたランドセルを背負うと、もう一度ゆっくり日の光を全身に浴びる。だんだん頭の中が真っ白になってくる。そうして、ボクは学校での出来事を全てリセットするんだ。無用なものをいつまでも溜め込んでおくほど、ボクの脳内の皺は本数も長さもあるわけじゃないからね。必要なものはどうするのかって? 学校なんて檻の中での出来事に本当に必要なものがあると思ってるの?
ボクはブランコを後にする。
「もしもし、坊ちゃん」
それは丁度ジャングルジムの前を通り過ぎた時だった。
急に背後からボクは声をかけられ、振り向いた。首だけ捻ったっていうほうが近いかも。とにかく相手を見定めようとして、その人の方を見たんだ。
だけど逆行になってて、その人の姿はよく見えなかったんだ。何て表現すればいいんだろ。うーん、まるで真っ黒い影がボクを追いかけてきた。まさにそんな感じだった。というのも、その影――人は、夕日に引き伸ばされ引き千切れんばかりの大きさになったボクの影と同じくらい大きな身体をしてたんだもん。一瞬我が目を疑っちゃったよ。
まだ子供だしね。
「あの、何か?」
「坊ちゃんはこの学校の生徒さん?」
「ええ、そうですけど」
「丁度良かったわ。探してたのよ、小学生を。でも最近の小学生って帰るの早いのねぇ。どこ探しても一人もいないんだもの。困っちゃったわ。こっちは薄暗くなるまで、隠密行動も出来やしないから待ちぼうけてたってのに」
「あの、何を言ってるんですか? ボクに用があるんですか?」
正直、この瞬間に地面を思いっきり蹴ってないといけなかったんだけど、情けないことにボクの足は目の前の闇に射竦められてしまっていて、うんともすんとも動かなかったんだ。それに心構えもなかった。まさか自分が変質者に襲われるなんて夢にも思ってなかったんだ。後悔先に立たず、なんて諺が思わず頭に浮かんだけどホントどうでも良かった。
「あら、震えてるの? 可愛いわね。あなた、自分がどういう立場にあるかわかっちゃったのね。ま、それくらい利口な方がこちらとしてはありがたいのよね。というわけで」
そう闇が笑ったかと思ったその刹那。
闇が歪な音色で蠢き始め、少しずつ一つの形に集束していった。
「へ、へ?」
なんと間抜けな声だろう、と聞いていた人がいれば思っただろうが、ボクにはその時自分の体裁などに構っていられるほど余裕なんてあるはずもなく。だって闇が模ったその姿は紛れもなく。
「!?」
おっきな動物だったんだ。
「ふふ、お気に召したかしら。あ、そうそう。ご紹介遅れましたわね。私、秘密結社ツブウドコッベタが怪人。その名をサイ・キック・ラ・ヴァァァァァァァァア! 今後ともご贔屓にお願いしますわね」
いや、ヴァァァァァァって言われても……てかだっさ。
ボクは口をあんぐり開けながら、これは正直やっちゃった系だろうと冷静に心の中でつっこんだ。しかし、そんな呆然とするボクを後目に――
「あら、怖くてぐぅの音も出ないみたいね。ま、普通そうだわねぇ。」
ないない。
心の声だけが空しく木霊するけど、声は出せない。
いくらかなりマサルさん臭(なんだろう、突然出た言葉だけど)がするといっても、目の前にいるのは正真正銘、二足歩行のおっきな動物。そう野獣なんだ。もし何か物理的手段にでも出られた日にゃ、か細いボクは胴体ごと夜空の塵と化す事やぶさかではないのだ。やぶさかじゃないのか。
こんな良いキレのノリツッコミをしても、声を出せないのがもどかしい。
「完全人型ベースのクロサイ怪人様に、たかが地球産のお子チャマが恐れを為さないワケがないわよねぇ。サイサイ」
尚も続けるラヴァーさん。もはやボクのことなんて眼中にもないようだ。というかサイサイってなんだ。てゆーか……
ああ! もう言わせてくれ! 頼む!
拷問なんだよ! こんな展開!
「さて、じゃ大人しくついてくるサ――」
「……じゃねぇ……ん」
「ん、どうしたのかしら? お腹イタイの?」
「おめぇはサイじゃなくて、カバだろがああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!」
ああ、スッキリした――のはいいとして、どうしよう。
ラヴァーさんプルプル震えてるし。というか、今にも突進して来そうだし。
なんかすっごくやっばい予感。というか悪寒。
もはやこうなっては小学生のボクには一縷の望みもないままに身構えることしか出来ない。自分の非力がとにかく恨めしいが、まあ、子供なんてのは頭は発達してても、所詮身体は出来損ない。外部からの弾圧に屈するを得ないのは世の摂理。とか言ってないで考えろ~、考えろ~。さすがにここで死ぬのはまずいぞ。まずいぞまずいぞキクゾウラーメン。ん、何か?
こういう時ほど冷静な判断力が試されるというのに、もはやボクの頭はパニックになっていた。というか、カバの化け物にサイだなんだと言われた時点で絶叫して卒倒しなかっただけでも実は凄いことなのかもしれないけど。それでも何でも現状を打破するだけの確固たる打開策は一向に思い浮かばないことに変わりはないワケで。
最終的にボクが出来たことといえば――
まるで妖怪道中記のボス戦よろしく、手を合わせ目を瞑ること位だった。
にしても、あんまりいい人生じゃなかったなぁ。と記憶が走馬灯のように浮かんでは消え、消えては浮かび。なぜ齢十数年で、こんな人生のほろ苦さを味わわなければならないのかとか、ぶっちゃけどうでもいいけど。にしても、浮かんでくる走馬灯の内容が酷い。これまた目も当てられないほど――いや、実際目はつぶってるんだけどね――酷すぎた。いいのか、ボク。こんなんで。
そんなだったから、正直死ぬ覚悟なんて出来るワケもなく。
それでも、そんなボクを待ってくれるカバはいないわけで、ボクは大空へと高らかに……あれ? 舞ってない。大空に高らかに舞い上がってませんけど。
ボクはきつく閉じていた目を薄ら開いてみる。
刹那、目の前にカバの顔がアップであったらどうしようとか色々イヤな妄想したりもしたんだけど、そんなことはなかった。まあ、あったらあったら楽になれそうな気もしたから、それでも良かったのかもしれない。
けれど、ボクのまなこが網膜に焼きつけた光景は、その陰惨たる妄想のどれをも反映してはいなかったんだ。むしろ、なんだろ。この光景は。
「え……泣いてんの……」
見れば、先程の立ち位置で膝を抱えシクシクとしょげ返るカバが一頭。いやこの場合、怪人なんだから一人、となるのかな。と思わずのことに頭の思考回路もちょっと適当処理中。だって大のカバが(こんな表現あるんだろうか?)校庭で一人泣いてるんだよ? そんなの見たことある人がかつていたんだろうか。いや、いないだろー。
「ええと、あの、ですね」
「なによぅ」
嗚咽に混じるような形で返答が返ってくる。
このカバ本気で泣いてる! という内心の動揺は隠せないものの、ボクは至って冷静なフリをして次の言葉を選ぶ。なんだか色々ありすぎて、もう本当はどうでもいい気もしてたりするけど。
「いやボクが尋ねるのも何なんですけど、泣いてるんですか?」
「泣いてなんかいないわよぅ。ほっといてよぅ」
「え……じゃ、じゃあ。ボク帰っちゃってもいいんですかね?」
「勝手にすれば? こんなか弱い乙女の純情を弄んでおきながら、なんて残酷な子なのよぅ。酷い、酷いわよぅ。サイサイ、サイサイ」
涙声もサイサイなのかよ……じゃなくて!
どういうことだよ。純情を弄んだって?
「あの、その、ですね。意味が測りかねるんですけど……も」
ここまで謙った敬語を使うのも初めてだといわんばかりの言葉遣いでボク。
「人の心に土足で踏み込んでおいて、その言い草はなんなのよぅ。バカバカ」
と女々しく泣き喚くサイ科のクロサイ怪人ことラヴァーさん。
「ボ、ボク何かしましたかね? ラヴァーさん?」
地雷を踏まないように、細心の注意を払うボク。
「そんなの自分の胸に聞いてみるといいのよぅ」
とナリはでかいがとてつもなくウザいクロサイのラヴァーさん。
ってなんでボクがこんな恋愛関係のもつれよろしく会話をしないといけないんだ。危ない危ない。もうちょっとで「ボクはこんなに君を愛しているのにかい?」まで辿り着くところだった。小学生でサイの恋人持ちなんて考えただけでも鳥肌ものだ。
危機を寸での所で回避出来たことにボクは安堵の溜息を洩らした。
「なによぅ、その溜息は。私がまるで悪いみたいじゃないのよぅ。あなたがカバって言ったのよぅ? 反省の態度くらい見せたらどうなのよぅ!」
憤るサイ。いや、カバ。
じゃあなんですか。それであなたは泣いていらっしゃるわけですか。ええと、あなたカバですよね? どこからどう見ても黒いカバですよね? 硬い皮に覆われてもいないですし。というかですね、あなた角がないじゃないですか。角のないサイなんてそんな不サイ工なサイいないんですよ! それにこんな子供に本当のこと言われて凹んでるなんて、なんて了見の狭いお人だ、あなたは。こういうときは大人の、いえ怪人の器量ってもんを見せるもんなんじゃないんですか? そもそもサイをカバと正されることがそんなに不愉快なんですか? むしろ間違えて自称しちゃってる方がよっぽど不愉快で最悪で恥の上塗りのような気がしますけどね! ええ、どうなんです? この豚ヤロウ!
なんて言えなぃし。
どうしよ、これ。そろそろお母さんの堪忍袋も切れちゃう時間だし。
ボクは正直このまま帰っちゃおうかなって本気で思い始めてた。だて帰っちゃってもこのカバは問題なさそうだったし、何より絶対今なら逃げ切れたからだ。それなのになぜそう踏み切れないでいたかといえば、正直なんでだかわからなかった。やっぱり思考能力が限りなく停止状態に近くて、最善の判断ってのが出来なくなってるのかもしれない。ただ死に物狂いで家まで走ればいいだけなのに。
ボクはすっかり撫で肩になってしまったカバの肩に、そっと労わりを込めて手を置いた。ああ、ボクは何をやっているんだろう。でもこのカバはきっとボクがいないとダメかも。なんて気分になってるのは、捨て猫を拾うときの心境と同じなのかな。
「優しくしないでよぅ」
こうしてボクらの間に友情が生まれ――と思ったその刹那、プァンという耳を劈くような快音が辺りの大気を震わせた。
「天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ! 悪を倒せと轟き叫ぶ!」
メガホン――朝礼のとき禿げた(禿げてないかも。50vs50)校長が口につけるけたたましい過去の遺物――から風に乗り運ばれてくる甲張り声。その声音のする場所――校舎の屋上に目を向けると、佇む四つの影。いつの間にそこにいたんだろう。日の光に照らされ炎を纏うかのように聳えるその姿は、人型をしていてもボクに何か異形を思わせた。けれど、そのとき抱いた感情は恐怖とかそういうんじゃなくて、なんていうか憧れに近かったと思う。たぶん――その時だけだったけど。
「っておい、イエロー。こっちこいって! もう決め台詞叫んじゃったって!」
「リーダー早すぎるんだって、だから。オレが着替えるの遅いの知ってるじゃんか。だから五分待ってって言ったのにさ。無視するからだよ」
「てか、だったら着替えて来いよ! マ・ジ・デ! あの少年が今にもあの、なんだ、あれ。うんと、アルマジロ?」
「リーダー。あんた前々から思ってたけど、脳使って生きてるの?」
「だぁれが、山崎邦正じゃ! 使っとるわい。失礼な!」
「じゃ、あれがアルマジロなの?」
「え、違うの?」
「違うだろ……どう見ても……」
「次郎は黙ってろよ!」
「ちょ、名前で呼ぶなよ! 何でボクだけ名前でいっつも呼ぶんだよ! ブルーって言えばいいだろ! 何のためにこんな派手な変身してると思ってんだよ!」
「バッカ。そりゃ五人もいたら、みんな名前にすると覚えてもらいにきーからに決まってんだろ?」
「そう思ってるのは、リーダーだけかもねぇ」
「コォラ! グリーン! いっつもいっつも揚げ足取るようなことばっか言いやがって。大体だな。いっつもテメーはリアルんときオレを見下したような目で見やがって、正直気に入らねーんだよ!」
「はは、やめてくれないか、そういうの。見苦しい」
「なんだとぅぅ」
「ちょっとちょっと! そんなことしてる場合じゃないでしょ! 何のためにここでこうやってると思ってんの? てかリーダーふざけ過ぎ」
「いやピンクさん。オレは別にふざけてるわけじゃないんですけど……ってそうだった! 少年、今助けるぞ!」
「ていうか、今までの会話、全部メガホン通して聞かれてるしね」
「おわっ。イエロー、着替え終わったんなら言えよ。おまえ存在感薄くて、いきなり背後に立たれると怖ーよ」
「それも入ってる」
「ああ、すまん。一旦スイッチ切るわ」
「いや、もう切らなくていいだろ」
「だから、次郎は黙ってろよ」
「何でだよ」
「だーからだかーら! そんなことしにここに来てるんじゃないでしょ!」
「む、そうだな。次郎、この勝負は一旦お預けだ」
「ケッ、逃げやがって(ボソ」
「聞こえてるぞォォォ! コノヤロー」
「何だよ、リーダーらしくしろよ、バーカ!」
「うるさい、ブルーの代わりなぞごまんとおるわ! 死ね! ここで死んでしまえ!」
「おまえこそ死ね! ボクがレッドを代わってやるから!」
「おまえになんかなれるもんか!」
「すでにおまえがなりきれてねーだろが!」
【ゴッ】【ゴッ】
乾いた音がメガホンを通さなくても、はっきりくっきりと校庭中に響き渡る。
そしてそれを皮切りに、ボクの人生史上、最も劣悪な記憶の幕が切って落とされることになった。続くかも。
© Rakuten Group, Inc.