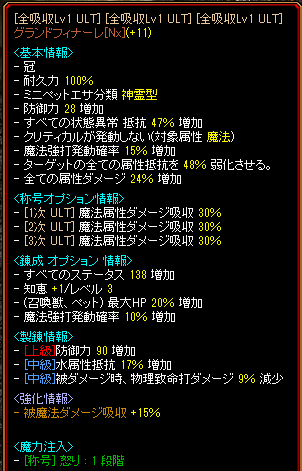Ragnarok Memories~サイドストーリー~
Ragnarok Memories
サイドストーリー
サンドウィッチ
大道芸 というのは、道端や街の一角でちょっとしたショーを開くものであり、そこを通行するお客は自由にそれを鑑賞し、面白ければ報酬としてチップを投げ入れるものである。このロード・オブ・デスが君臨する物騒な世の中でさえ、否。こんな世の中だからこそ、安定な収入の得られぬ者は大道芸人へとシフトするのだろう。これは、ジュノー生まれのとある大道芸人のお話である――
ソレーユたちがオーク村で奮闘しているのとほぼ同時期、オーク村―ゲフェン間の道端(ややゲフェン近郊)に、2人の大道芸人が芸をしていた。ひとりはまばゆい金色の髪を長めにそろえ、顔にはオペラ座の怪人よろしく、仮面をつけ、頭にはシルクハットをかぶったマントの少年。もうひとりは、やや蛍光色の強い緑色をベリーショートに切りそろえ、顔には仮面、頭にこれも同様シルクハットをかぶった法衣の少女。2人は雲ひとつない晴天の青空の下、道端に集まった数人の老若男女の目の前で、火の輪を出したり、氷の壁を出したり、水の湧き出る泉を出したりしては、拍手を受けていた。そう……男はウィザード、女はセージなのである。
「さてさて、本日はこの"イテフェンとネフェティのどきどき魔法Show"をご覧いただき、真にありがとうございました!数々のマジック、いかがでしたでしょう?どのマジックが一番よろしかったでしょうか?炎の輪を出現させ、その間を私がくぐるものでしょうか?はたまた、氷の壁を出して、みなさまにカキ氷を作っていただいたものでしょうか?それとも、木筒をポリンに変えるものでしょうか?」
「ポリンポリン!びっくりしたよ!!」
「あれはきっとあの筒の中に入ってたんだよ!俺は炎の輪が良かったぜ!あのドキドキ感がたまらねぇ!」
「わたしはアイスー!初めにずっとそこに置いてあったシロップが気になっていたんだけど、まさかカキ氷とは!」
「僕は水かな。しかし、あれが飲めるとは……」
最前列で見ていた子供たちが口々にあれだこれだと言うのをイテフェンもネフェティも嬉しそうに見ていた。イテフェンは小さく礼をして、一歩前に出て手を上げた。
「さぁ、ショーもいよいよ大詰め!次がラストマジックでございます。それではみなさま、これは少々危険ですので、10mほどお下がりください。」
10m?!と一瞬聴衆がザワザワした。しかし、2人はニヤリと笑い、慣れた口ぶりで観客を10m先へと移動させた。どうやら、いつもこういう反応のようだ。
「さて、それでは参ります!マジック最終章! "龍の舞" !!」
10m先まで聞こえる大声でイテフェンが叫ぶと、2人は詠唱を開始した。そして、まずはネフェティが魔法を放つ。
「デリューシ!」
すると、彼女の前の大地が急にボコボコと音を立て始めた。そして、次の瞬間にはパンッという破裂音の後、そこから水が滾々と湧き出てきた。
「いいわよ、イテフェン!」
今度はイテフェンがその水場に重ねるように魔法を放った。
「ロード・オブ・ヴァーミリオン!!」
突如、凄まじい雷鳴の後、水場からビリビリビリッと水柱ならぬ電気柱が宙へ舞った。その姿はなるほど龍が昇るようで、空中で旋回し、やがて放電しきったか、消えていった……
2人のショーは大成功だった。拍手喝采の後、山ほどのチップとビンの蓋(子供たちはお金がないので)をもらった。
その夜、2人はゲフェンへと続く道の上で野宿する事にした。
「今日も大成功だったね。」
仮面を外すとつぶらな瞳が愛らしいイテフェンは、ネフェティに笑いかけた。
「これで、ゲフェンに着いたら必要なものが買える!薬品も新しく調合しないとだし、食料も買わないとね。」
「君はよく食べるからなぁ。サンドウィッチなんか特に…」
ゴチンという音と共にイテフェンは頭を抱え込んだ。
それからしばらく2人は会話を楽しみ、床につくことした。寝袋に入り、焚き火を消した。途端に真っ暗な闇があたりを包み込み、虫の鳴く声が小さく響く。
「じゃぁ、お休み、ネフェティ。明日はゲフェンだね。」
「うん。しばらくは街の広場でショーをしてお金稼ぎましょ。おやすみ。」
疲れていたのか、すぐに2人は寝息をついた。ネフェティはなぜか、昔の夢を思い出した――
――それは彼女が10歳だった頃。ジュノーで生まれた彼女は魔法学校に通っていた。
彼女はまだ魔法が使えなかった。他の同じぐらいの年の子はもういくつかの魔法を使いこなし、闘争心丸出しで技を競っていた。しかし、彼女だけは魔法が使えなかった。当然、そんな彼女は学校で笑い者になり、 誰が呼んだかあだ名は"マホナシ"。 既に名前の原型すら留めぬこの呼び名で幼い彼女は傷つき、学校も休みがちになった。
しかし、彼女は別に引きこもりになったわけではない。昔、有名な魔法使いだった叔母のところへ行き、魔法の手ほどきを受けたのだ。
幸い彼女は魔法の力が全くないわけではなく、詠唱が下手なだけだったようだ。叔母の家に行って数週間、なんとかペンに、名前を書かせる魔法だけは使えるようになった。
彼女は嬉しくなり学校へ戻った。先生は褒めて彼女を抱きしめてくれたが、既に炎を出す魔法を使いこなす同世代の子たちからは冷ややかな視線を浴びた。 彼女のあだ名は"サイン(学校のあちこちに自分の名前を書いたから)" になった。
けれども、彼女はあきらめなかった。日が出ている時は 学校でサインを求められながら 、暇さえあれば図書室の知識書を読み漁り、日が沈めば叔母の家に行き、一人こっそりと魔法の練習をした。
そんな彼女を見ていた叔母はある夜、高台の上で必死に魔法の詠唱をして薪に火をつけようとしているサインのところへ暖かいミルクを届けた。
「ネフェティ、魔法の調子はどうだい?」
「マァマァデス。」
「一人で寂しくないかい?」
「できればミルクじゃなくて、同じぐらい魔法が下手なお友達が。」
苦笑いして2人は長いすに腰掛け、夜空を見ながらミルクを飲んだ。
「叔母さん、どうやったら魔法上手になるかな?」
「心に強く念じるんじゃ。魔法は心と直結しておるからのう。ほしいと思ったものを強く念じれば、必要に応じて出てくるはずじゃ。炎!と念じれば……」
ポンと叔母の手にライターの火ほどの炎がついた。
「ファイアーボルト!」
ネフェティも負けじと詠唱したが、彼女の眉間に眉が寄るだけで何も起きなかった。
「ホッホッホ。単に詠唱をするだけではないのじゃ。それは言葉に過ぎぬからのう。魔法とは心に直結しておる。」
「それ、さっきも聞いたよ!それに学校でも何度も!」
「ホッホッホ。まぁ、お前は練習すればいつかできるようになるじゃろう。この言葉の意味がわかるようになればの。じゃぁワシは行くよ。邪魔したね。」
叔母が去った後、彼女はミルクをぐっと一気に飲み干し、再び練習した。もちろん、火はつかなかった。
それから数日後、いつもどおり彼女が練習をしようと高台へ向かうと、そこに人の姿があった。ネフェティは恐ろしくなったが、こっそりと近づくと、その人は薪に向かって何かぶつぶつ言っていた。
「ファイアーボルト!」
彼女は耳を疑った。
「何してるの?」
彼女は勇気を持ってその人に話しかけた。その人は一瞬たじろいだが、くるりと反転して彼女を見た。それはネフェティと同じぐらいの金髪の少年だった。
「おっと、ごめん。実は僕、最近この町に来たんだ。魔法使いになりたくてね。でも、魔法全然使えないから、練習しようと思って歩いてたんだ。そしたら丁度良く薪があったもんで。ところで君は魔法使い?」
「えぇ、そうよ。私、ペンに名前をかかせられるの。言っとくけどね、魔法使いになりたいって思うだけじゃなれないのよ?きちんと魔力があって、ちゃーんと勉強しないとなれないの。だから、いくらあなたがなりたいと言っても……」
「僕もそれぐらいできるよ。でも、これってこっちの子は3歳ぐらいでもうできる魔法なんでしょ?でもまぁ、7年のハンディがあると思えば!」
彼女は再度耳を疑った。
「何ですって?」
「それより君は僕と同じぐらいだね!ねぇ、魔法見せてよ?お願い!」
「今は……練習中。」
「へ?」
彼女はこの少年を恨んだ。学校でいくら馬鹿にされても構わないが、絶対にこの時間まで人にこけにされたくはなかった。しかも、なんでこんなどこから来たかわからないような男が、私と同じ魔法を使えるの?彼女はそう思った。
「だから、今練習中って言ってるでしょ!私もできないのよ!」
(笑え、笑うがいいわ!この純粋なジュノーの子供が、あんたの言う3歳でできる魔法しかできないのよ!)
彼女は海に投げ出された樽のような気持ちになった。しかし、彼は嘲笑せずに、サインの手を握った。
「じゃぁ一緒に練習しようよ?」
彼女は耳を疑った。
「え?」
「だって2人で練習した方が楽しいと思わない?一人でこんな夜に練習するなんてさ、つまらなすぎるよ。」
そのつまらなすぎる事を私は今までしてたの!という言葉が頭に浮かんだが、彼女はそれを口に出さなかった。
「いいわ、私があなたに教えてあげるからね。まずはそこに座りなさい。」
少年は言われるまま長いすに座った。
「まず、魔法っていうのは心と直結してるの。だから、強く念じるのよ。心に火のイメージをね。やってみて。」
コクリと頷き、少年は薪に手を向けた。
「ファイアーボルト!!」
しかし、何も起こらない。
「あー、だめだめ!"ファイアーボルト"はただの言葉よ?お分かり?イメージよ、イ・メ-・ジ!」
「魔法って難しいんだね。」
「そうよね……じゃなくて、早くやりなさい!」
こうして2人は一晩中薪に呪文を投げつけた。もちろん、一度も火はつかなかった。
それから毎晩、この少年とサインは共に練習した。少年の名前はイテフェンというらしかった。学校は手続きを踏んでいないらしく、まだ行けないらしい。でも、サインはそんな事を気にしなかった。気がつくと、 毎晩、彼と会うのが楽しみになっていた。
「叔母さん、行ってくるねー。」
「ホッホッホ。最近はいつもに増して気合が入っておるな。 弁当の量も2人分ぐらいになったしのう。 良い事じゃ良い事じゃ。がんばっておいで。」
「ネフェティは、学校に行けていいなぁ。」
2人は長いすに腰掛けて、叔母の作った弁当を広げていた。薪はほとんど使われていない。
「どうして?」
ウィンナーを口に頬張りながらサインは聞き返した。
「だって、学校にはたくさん友達がいるんでしょ?一緒に魔法の勉強をしてさ。楽しそうじゃん。僕なんか、ペンで名前を書いたらみんなからバケモノ呼ばわり。」
ふぅとため息をつき、目を伏せるイテフェン。そんな彼を見てネフェティは、サンドウィッチを彼の目の前に差し出した。彼はありがとうと言って受け取った。
「私は真逆よ。紙にペンでいくら名前を書いても、みんなから馬鹿にされる。」
「何かさ、僕たちって逆だけど、似てるよね?」
くすくすとイテフェンは笑ったが、ネフェティは顔を真っ赤にした。
「そんな事なーい!一緒にしないでよね!!」
「はいはい。」
イテフェンは笑いを堪え、彼女の目の前に半分食べたサンドウィッチを差し出した。彼女はありがとうと言って受け取った。
「さてとっ。お腹もいっぱいになったことだし……始めますか。」
口に入ったサンドウィッチの残りをかみ締めながら立ち上がると、イテフェンもそれに続いた。もちろん、いつも通り火は出なかった。
「ファイアー!」
「うおおおおお!!」
いつも通り、二人の声だけが高台に響いた。もはや彼らには"ファイアーボルト"という言葉が意味を成さない事などわかっていた。
「ねぇ、ネフェティ。」
ふと、イテフェンが彼女に向き直った。しかし、ネフェティは集中を切らさないようにずっと薪を見ながら応じた。
「なに?」
「君は将来素敵なお嫁さんになれるよ。」
一瞬、彼が何を言ったのかわからなかった。口をぽかーんと開けたまま、薪を、いやそっちの方をぼんやりと見つめた。
「何言ってるのよ!練習しなさい!」
「君は素敵だよ。」
イテフェンはいつになく真面目な顔で彼女を見つめていた。しかし、ネフェティは彼を見ずに頬を赤らめるだけだった。
「わけわかんない!早く練習!」
「ネフェティ。僕は君の事が……」
「うるさあああああい!」
その瞬間、彼女の心の中に赤いメラメラとした何かが姿を現した。情熱か何かか。抑えきれないその衝動は、彼女の中からあふれ出した。と、その時。
「ビューン!」
彼女の手の平から小さな火が出て、薪に直撃した。すると、薪は風を受けて瞬く間に成長し、立派な焚き火になった。
「で、できた……」
彼女は自分の両手を見た。生暖かい火の感触。それは彼女の心の中に火を呼び出す感覚を叩き込んだ。
「できた……できたあああ!」
あっはっはと笑い声を上げるネフェティ。そして、勝ち誇った顔でイテフェンのいた方を向いた。
「どう?やっぱり私の方が上だった……ってあれ?」
しかし、そこにはイテフェンの姿はなかった。
「イテフェン?」
呼んでも返事はない。
(怒っちゃったかな?)
高台から隈なく下を探すが彼の姿は見当たらない。まるで魔法のように、彼は消えてしまった――
それから数日間。ネフェティは夜高台で一人待った。最初はただ怒ったと思っただけだったが、日にちが立ってもイテフェンは現れず、だんだん焦りが出てきた。
「そんな事しないよね?イテフェン?私を置いてどこ行くの?ねぇ?一緒に練習しようよ?私……ちゃんと教えてあげるから。今度はきちんとできるんだよ?ね?」
高台で独り言のように呟きながら、長いすに腰掛けて顔をくしゃくしゃにして泣いた。それでも彼は来ない。
「ねぇ、イテフェン?ほら、サンドウィッチもあるし、ウィンナーもあるよ?ホラホラホラ。また半分こしよう?」
隣にあったバスケットには、あの日からずっと置きっぱなしの弁当の残りがあった。虫がたくさんついている。それでも、ネフェティはそれを手にとって半分に分けた。
「ほら、叔母さんが作ってくれたお弁当。おいしいって言ってたでしょ?叔母さんが……」
そこで彼女ははっとなって叔母さんの顔を思い浮かべた。そして、ミルクを持ってきてくれた日の事を思い出した。
"ほしいと思ったものを強く念じれば、必要に応じて出てくるはずじゃ"
"できればミルクじゃなくて、同じぐらい魔法が下手なお友達が"
・
・・
・・・
・・・・
あっ!
私、魔法でイテフェンを出したんだ
そう……彼女はあの時、心で同じぐらいの友達がいてくれたらと強く思った。それが形となった。つまり、 彼女はあの時既に魔法を使っていた のだ。
溢れる涙を塞き止めることもできず、彼女はただただ泣いた。彼女が一番ほしかったものは "友達"と"魔法制御" 。この両方を叶えるために、彼女は友達を作り出し、その友達と頑張ることで魔法制御の力を得たのだった――
彼女はその後、この日の思いを胸に、数多くの魔法を習得した。それも驚くべき速さで。そして13歳になる頃には、学校のどんな子よりも、場合によっては先生よりも高度な魔法を使いこなすほどになっていた。もちろん"サイン"などというあだ名などはあった事すら否定される。 彼女のあだ名は"ネフェティ"となった。 どんなに悪い奴も、ネフェティの前では猫に追い詰められた鼠のような顔で降参する。けれども、彼女は満足せずに、さらに高度な魔法を求め、 サインを求められながら 毎日図書室で本を読み漁った。
その後彼女は、14歳という史上類を見ない若さでセージ(教授)の称号を手にする。だがその計り知れぬ魔法への貪欲さからか、ある 禁断の魔法 を使い、ジュノーを追放され現在に至る――
「おーい、ネフェティ。早く起きろよ。もう朝だぞー。」
イテフェンの声で彼女は目を覚ました。イテフェンは既に寝袋をたたみ、出発の準備を完了していた。
「ちょっと!何でもっと早く起こしてくれなかったのよ?!」
慌てて仕度するネフェティに、彼は笑いかけた。
「だってなんかとっても良い夢を見てたみたいだから。起こすの悪いかなって。」
そう言って、彼女にサンドウィッチを半分にして差し出した。ネフェティはありがとうと言ってそれを受け取った。
「あら?随分素直に取るんですね。叩き落とすかと……」
「そんなわけないでしょ。大切なものだもの。さぁ行くわよ!!」
「 君のサンドウィッチ好きにはまいったなぁ。しかも半分は結局僕が食べるんだよね…… 」
「つべこべ言わずにきりっと歩く!もうすぐゲフェンなんだからね!!」
荷物整理を終えた彼女は、イテフェンの背中を押して歩き出した。
「妙にハイテンションだなぁ。さてはサンドウィッチをたくさん食べる夢だな……」
日が心地よい今日この頃。風は東。追い風となるこの暖かい風が、2人の背中を優しく押した。
――彼女はジュノーを追放された事を後悔していなかった。なぜなら、「生命倫理」という禁断魔法で、再びイテフェンを生み出したのだから――
Qこの二人の名前のカラクリがわかるかな?(・∀・)答えは↓
ネフェティ→NEFETI イテフェン→ITEFEN
ローマ字逆さ読み!そこ!!古いとか言わない!!ヽ(゚∀゚)ノ
© Rakuten Group, Inc.