キルハイル編~悲しみの生み出ししキエル~
~ROクエスト小説~キルハイル編~悲しみの生み出ししキエル~前編


エルメスプレート――ルーンミッドガッツ王国とシュバルツバルト共和国の国境(とは言っても調停によりシュバルツバルト共和国に属するのだが)にあたるこの地は、険しい山々で隔てられた山地である。草もほとんど生えない無機質な岩肌がこれでもかと露出している。そんな黄土色のこの地の上空は常に、白とも黒ともつかない色の雲に覆われているため、まだ昼だというのに辺りはほの暗い。しかし、こんな薄気味悪い場所とは対照的な、それだけに異質な建物があった。それは外見的にという意味ではなく、どちらかと言うと精神的なものであるが――つまり、ここに"学院"がある。もちろん、アインベフ鉱山でユミルの心臓が見つかってからというもの、シュバルツバルト共和国の科学的な進歩には目を見張るものがある。同国お抱えの研究機関レッケンベルを携え、工業都市リヒタルゼンを中心に、神の領域への挑戦をしていた。それは、一定の材料から生体を作り出すホムンクルスや、24時間城の警護など、仕事を可能にしたガーディアンの生成等々、枚挙に暇が無いものである。そのため、巷では人間の生体研究も行われているのではないかと、実しやかに噂されていた。リヒタルゼンの貧困街から、金欲しさに自分の体を売り、そのまま行方不明になる――というケースも少なくない。話が逸れたが、もちろんこのようなシュバルツバルトが有する学院なので、見た目も警備もかなり立派ではあるのだ。しかしながら、先ほど精神的なと言ったのは、やはりここが 学院 だからである。学院生たちの笑い声がこの空しい土地に響く時、感じるのはやはり"異質さ"。なぜ、このようなところに学院を作ったのか―― まるで、人目をはばかる様に 。なぜ、この機械のような無機質の土地で子供を教育するのか―― まるで彼らも機械である様に。
ところで、この学院を作った者がいる――それが、 キル・ハイル だ。彼は20歳という若さでレッケンベル社の専門研究員に抜擢されるほどの才能を持っていた。彼はユミルの心臓が見つかってから兼々、それを応用できないだろうかと考えていた。つまり、ガーディアンのようにある一定の命令をインプットさせ、同じ仕事をやり続けさせるというのはありきたりだ(一般人から見ればそれでもセンセーショナルなのだが)と考えていた。できればもっと複雑な――人間のように考え、行動する、AI(人工知能)を発達させる事はできまいか……そう考え続けた。
そして、彼の願いは成就した(どういった方法でそれに至ったかというのは、難しい論理と数千に及ぶ計算式を用いて説明しないといけないため、ここでは割愛する)。彼はまず、ガーディアンのような巨体(小さくても15メートルはあるもの。これは中にユミルの心臓を入れなければならないため、どうしても大きくなくてはいけない)を人型まで縮小する事に成功した。そして、少々の事は自分で考え、臨機応変に対応できるように改造を施した。これが俗に "第一世代" と呼ばれるAIロボットである。とは言っても、臨機応変と言えば聞こえはいいが、結局教えられた事しかできないのには変わりが無かった。それでも、この機械人形は従来のガーディアンと比べ、圧倒的に低コストで実現かつ、人間の姿に酷似しているため(注文によっては好きな性別、顔、スリーサイズに変更できる)、シュバルツバルト内の金持ちはこぞって買いあさり、別荘のメイドや遊び相手、さらには自慰人形等々、様々な用途を開拓していった。だが、もちろんこのようなガーディアンのまがい物で満足するキル・ハイルではなかった。もっと人間的に考え、自分で行動し、成長する――そんな機械人形を作り出したかった。しかし、彼に資金提供をしてくれるレッケンベル社に頼まれ、彼が次に作り出したのは、 "第二世代" と呼ばれるものであった。これは簡単に言えば第一世代と逆、つまり、人型まで圧縮したガーディアンである。ガーディアンの本来の目的、モンスターや悪党から主要都市を守ったり、重いもの(t単位)を運ぶ言わば、兵器兼産業用ロボットだ。これも金持ち連中の間ではヒットした。一日中引っ張りまわしても疲れない、衰えない上に、買い物袋100や200程度は軽々と持ち上げる力を持ち、買い物症候群のマダムに特に人気があった。
しかし、この第二世代の開発は第一世代のように順調にいかなかった。やはり焦点は、人間のサイズでどうやって百人力を実現するかである。これにはさすがのキル・ハイルも頭を抱えた。というのも、彼はもともと兵器とか産業とか、そういうチープな事に使う機械を開発したいのではなく、あくまで人間性に固執していたため、気が進まない研究ではあったからだ。しかし、決してサボタージュをしていたわけではない事は、本人の名誉に配慮して付け加えておく。そのあたりは、やはり技術者と言えども人間性を重視するだけあって、レッケンベルへの義理通しという意味合いが強かったようだ。
そういうわけで、第二世代に思った以上に時間をとられ、気づけば彼も50間近。あまり時間があるとは言えない。次の研究で終止符を打とうと、自身の全身全霊をかけて研究に没頭した。レッケンベルもそれを知ってか、彼にはあまり関心を寄せなくなった。第二世代で用済み――というわけでない事を祈る。そして丁度50の時、彼は完成させた。それが "第三世代" と呼ばれる機械人形だ。最低限のAIと成長するAIを兼ね、感情を持たせる事にも成功し、能力外見も初期値は第一世代同様人並み。この成功が彼をして、あらゆる技術者の神に至らしめた。唯一残念なのは、あまりに精密なので、一般普及は当分できそうにないという点である。しかし、彼はもともと売るとかいう
陳腐な考えは持ち合わせていなかったので、これを機にレッケンベルを退職し、たんまりともらった退職金をはたいてエルメスプレートに第二世代が警備する学院を作り、彼自身は近場に別荘をたて、第一世代をこき使いながら、穏やかな老後を過ごした。
そう――もうお分かりだろう。この "キルハイル学院"は、第三世代を養育するための施設なのだ。 とは言っても、第三世代自体は2人しかおらず、後の子供たちは正真正銘人間の子供である。こういった子供と触れ合うことで成長し、大人になっていく第三世代の完成をぜひとも見てみたいと思うまま生き続け、気づけば還暦も過去の事、62歳に。そして、その歳から、彼は腕利きの冒険者を雇うようになった。
「ここがキルハイル学院じゃないか?」
背の高い青い髪の、ハイプリーストの格好をした男が学院の前で建物を見上げていた。
「こんなところに立派なものがあるのねぇ。」
その隣にいたこちらも青い髪を肩ぐらいで切ったモンク格好をした女は、ふぅとため息混じりにそう言った。
「でも、こんな学院が冒険者を求めるって事は、何か事件があったのかな?」
青髪の男が呟くと、その後ろにいた栗色の髪の、ウィザードの格好をした男が、背負っていたリュックを下ろし、パンフレットのようなものを出す。
「"我がキルハイル学院は、腕に自信のある冒険者を求めている。興味のあるものはエルメスプレートにある我が学院まで来られよ。試験に合格すれば仕事を依頼しよう。報酬は全て後払いで100000000z、現金でお払いする。では勇気ある冒険者の諸君、ご検討を。 キルハイル学院長キル・ハイル"。って書いてあるさね。この大枚に引かれて来たはいいけど、思ったほど参加者は少ないみたいさね。」
「レンちゃん。少ない……と言うより、俺たち以外誰もいないんじゃないか?ここまで歩いてきたけど、誰とも会わなかったぞ。」
「匂う…匂うわ!」
その隣で女が声を上げた。
「ど、どうしたんだよ、コトさん。俺がそんなに匂うか?そういえばここ数日歩き続けて風呂にも入ってなかったからな。」
「違うわよ、アコル。あなたじゃなくて、あれが匂うの。」
そう言って彼女はレンの方を指差した。
「え?俺かい?」
一瞬にこっと笑い、すぐに真顔になって二の腕辺りをかいでみる。
「違うって!これよ、これ。」
レンの近くまで歩いて、ひょいとパンフレットを取り上げた。
「100000000zよ?こんな大金見た事ないわ。でも、参加者は異様に少ない……これって危険な匂いがぷんぷんするわ。」
「確かに!」
2人とも首を「うんうん」と縦に振った。
「じゃ、帰ろうかね。」
そう言い出したのはレンだった。さっさとリュックを取り上げ、回れ右した。しかし、前に進まない――コトが彼の首根っこをつかんで離さなかった。
「だいたい、この話をプロンテラの酒場に持ってきたのはレン。あなたでしょ?今さら逃げるの?それでも世界一のウィザードって言ってた男?」
「でも、話に乗ったのはあんたらさね。俺は、着いてきてくれる人を探してた、それだけ!それにまさか、こんなに少ないとは思ってなかったさね。100人ぐらいでどどどっとやってしゃしゃしゃっと片付けて、ぱっとお金を頂くのを予想してたさね。」
「そんな楽して1億zももらえるわけないでしょ!」
それでもじたばたする彼をぐいぐい引っ張る。さすがモンク。肉弾戦でウィザードが叶うはずない。
「さぁ、行きましょ。まずはキル・ハイルさんに会わなくちゃ。」
そう言って、 アコルのいた方 へ顔を向けた。いた方、と描写したのは、そこに今彼がいないからだ。
「あ、あいつ!逃げてくぞ!」
今度はレンの方から声がした。キルハイル学院とは逆方向にどんどん小さくなるアコルが見えた。
「ふぅ。」
コトはため息をつき、レンを離すと、屈伸伸脚をし始めた。
「あいつとはかれこれ10年の付き合いになるけど、あなたは昨日一昨日一緒になった臨時パーティですもんね。私から逃げるって事が無意味だって教えてあげる。」
ゴクンと唾を飲むレン。彼女は一通りストレッチを終えると、大きく深呼吸してその場で駆け足した。
「じゃ、レンさん。ここにいてね!逃げちゃだめよ?」
そういい終わるか終わらないかのうちに、彼女はレンの視界から消えていた。空気がふわっと移動したかと思うと、まるで空気と一体化したように見えなくなった。そして……
「ぎゃあああああああああ!」
もう見えなくなったアコルの方から悲鳴が聞こえた。本当に恐ろしいものを見た時に出るような、心からの叫びだった。それを聞いたレンは、「やれやれ……」とその場に腰を降ろし、ポケットに入っていた青いクリップを取り出した。
「コトさん、ヒール覚えてるかねぇ……」
それから数分としないうちに、アコルが足をつかまれて引きずられる形で戻ってきた。それでいて抵抗しない彼に、レンはもの哀しさと深い同情を寄せた。彼の顔は2倍に膨れ上がり、頭にはタンコブ。目の辺りからは流血、そして鼻血、しかし他の体の部分は無傷だった。背中の服が少々黒ずんだだけだ。
「す、すびばぜんでじだ……」
やっと搾り出した言葉がこれだ。「すみませんでした」と言っているようである。
「普通、こういうのって目立ちにくい腹とかやるんじゃないのかい?」
梅干を食べたようなすっぱい顔でレンがアコルにヒールをかけた。傷が一つ一つ塞がっていく。本当に一つ一つ……
「いつもの事だから大丈夫よ。ほれ。」
そう言うと、コトはアコルに手をむけ、ヒールをかけた。一気に彼の顔の傷がなくなり、元に戻った。
「モンクとは思えないヒール量ですな。」
「私がいくら殴っても死なれちゃ困るからねぇ。自然と回復量が増えたのよ。」
はっはっはと、笑うコト。しかし、レンもアコルも笑う気にはなれなかった。それを察知してか、彼女は頬を赤らめ咳払いをして、2人を立たせた。
「じゃ、早速行きましょっか。それに私、今日はついてるのよ?」
3人は元気よく(?)キルハイル学院に向かう。
学院の入り口は大きな門になっていてその奥にさらにドアがあった。門の前には堅固な鎧を身に纏った2人の警備らしき者が立っていた。ぴしっと伸びた背中が妙に凛々しい。
「ご用件を承ります。」
愛想笑いもせずに気をつけの姿勢を続ける2人。
「あ、これを読んで来たんですが……」
アコルがパンフレットを見せると、警備は眼球だけ動かしてそれを見た。
「ソレハソレハ……ヨウコソ"キルハイル学院"ヘイラッシャイマシタ。」
片言のように敬語で話すと、回れ右をして後ろにあったインターホンを押した。
「はい……」
奥から聞こえたのは澄んだ女性の声。
「キル・ハイル様への用件で3名確認。」
ここだけ妙にかつ舌が良かった。
「わかりました。お通しください。今門を開けますので……」
「了解シマシタ。」
すると、ごごごと大きな音を立てて門が開いた。
「ソコノドアノブヲ回セバ中ニ入レマス。デスガ、授業中ナノデ静カニオ願イシマス。部屋ハ突キ当アタリヲ右ニ曲ガリ、一番奥ノ部屋デゴザイマス。」
そう言うと警備はまた元に戻り、気をつけの姿勢になった。その横でアコルが言われた通りドアノブを回すと、ドアが開いた。中からなにやら楽しげな音楽と子供たちの歌声が聞こえる。アコルに続いて2人も中に入り、ドアを閉めた。
中は思った以上に広かった。めまいがするほど真っ白な中央廊下はゆったり2mはあり、真っ直ぐ奥まで続いていて、雪の中にいるような錯覚を覚えた。
「目がちかちかするさね。」
レンがたまらず目をぱちぱちさせる。
「こんなところで子供なんか育てて、頭おかしくなりそう。」
2,3部屋を通り過ぎると突き当たったので、右に折れ、一番奥の部屋に入る。中には大きなデスクが一つと、壁には本棚がびっしり並んでいた。デスクの上では、まだ15歳ぐらいのメガネをかけた赤いショートヘアの少女が何かに目を通していた。そして、その隣に黄金に輝く長い髪のメイド服装を着た綺麗な女性が立っている。アコルは感覚的に、先ほどのインターホンの相手はこの女性のような気がした。
「……」
しばらくの沈黙。少女は気づいているのかいないのか、いっこうにデスクから目を離さない。
「エリー様。お客様がお見えになっております。」
隣のメイドが傍によってそっと耳打ちすると、エリーと呼ばれた少女はびくんと肩を震わせ、初めて前を見た。タレ目が可愛らしい人懐っこそうな少女である。
「はっ!ごめんなさい…!ちょっと研究課題の論文を書いていて……あなたたちが おじいちゃん のパンフ読んできてくれた人?」
立ち上がり、メガネの淵を親指と人差し指で持ち上げたり降ろしたりしながら興味深そうに3人を観察した。
「そうです、お嬢さん。それで、キル・ハイルさんはどこに?」
右に左に体を動かし、いろいろな角度から3人を観察するエリーを目で追いながら、アコルが尋ねると、また「はっ!」となってデスクに戻った。
(あの子、やっぱり頭おかしくなっちゃったのかしら?)
コトが小声で隣のレンにささやくと、彼も苦笑いしながら頷いた。しかし、メイドがじっと2人を睨んだので、すぐに口元を絞めた。どうやら地獄耳のようだ。
「それなんですが……」
エリーは腰に両手をあててうな垂れてみせる。少々演出過剰じゃないか、とアコルも思ったが、今はそれより早く依頼人に会わなければと何も言わなかった。
「これは実はユイ……」
「ユイ」と言ってから彼女は口をもごもごさせた。何度も「ユイ」と言うがそこから続かない。どうやら言葉を度忘れしてしまったらしい。
「”遺言"。」
隣のメイドがきっぱり答えると、エリーの顔は明るくなった。
「ありがと、エリシア!そう、それ!あれは遺言なの!」
そう言ってから彼女はまたうな垂れた。つまるところ、「遺言」などという言葉を楽しげに語るのは財産目当ての子孫だけで十分なのである。
「え?じゃあ、依頼人は……」
アコルの次の言葉を予測したかのように、首を横に振るエリー。
「あれは確かに遺言なんだけどね、でもまだおじいちゃんは生きてるし、遺言じゃないんだけど遺言なんですよ。」
ますます頭がおかしくなったとコトがレンとさっきよりも小さな声で話すが、再びエリシアに目で喝を入れられて黙った。
「だからつまり~……簡単に言っちゃうとね、おじいちゃんは拉致されたの!」
それからの彼女の話を分かりやすく要約すると、以下のようになる。
彼女のおじいちゃんキル・ハイルは用事で、付近にある息子キエル・ハイルの家に行く前、エリーに「もしもワシが2週間経っても戻ってこなかったら、これをばら撒いてくれ」と言って大量のパンフレットを渡した。そして、もう一品。「そのパンフレットで来た人間の中で信用できる者を選び、ワシを探しにキエルの家までよこしてくれ」とキエルの家のカギを渡した。なぜこうなったかはエリーにもよくわからないが、何でも2人は顔を合わせればいつも口論になるほど仲が悪かったらしい。
「その信用できる人を選ぶのが試験ってわけね!」
コトがこれ以上印象を悪くしてはいけないとさも興味ありげに声を張り上げた。エリーも自分の話が思った以上に伝わって嬉しそうだった。
「そう!でね、私決めたの。あなたたちにする!」
あまりに自然の流れのまま言ったので、3人とも聞き流すところだったが、エリーがカギを見せると急に現実味が湧いた。
「ほ、本当に俺たちでいいんですか?」
「うん!私、信用できると思う!キエルさんの家はここから2,3km北に向かったところにお墓があって、その隣にあるから行けばわかるよー。」
3人はエリーとエリシアに別れを告げると、頭のおかしくなりそうな廊下を歩いて、キルハイル学院を後にした。
「ね、言ったでしょ?今日はついてるって!」
くるりと2人を振り返り、勝ち誇った顔をするコト。
「でも、こんなんで1億zももらえるなんて何か裏がありそうさね。」
「確かに、家に行くだけって事はなさそうだな……キエルって奴の事、もっと聞いとけば良かった。」
「もっと前向きに考えなさいよ!」
それからしばらく歩くと、エリーの言うとおり墓地があった。しかし、その隣にあるのは、便所ほどの小屋である。
「これはこれは……豪華な家に住んでますこと。」
レンが茶化すと、2人も笑った。
「ここで合ってるよな?」
アコルが隣のお墓を確認しながら不安げにもらした。
「ここみたいね。」
ミニアはすぐに小屋の近くに行って周りを調べると、ドアに鍵穴があった。エリーからもらった鍵を入れてみるとしっかりとはまり、まわすとガチャリと音を立てて開いた。
「さぁ、何があるのかしら!」
勢いよくドアを開ける。しかし、中は一瞬カラに見えた。見た目どおりの狭い、しかも悪い事にキルハイル学院の廊下同様真っ白な四角い小部屋だった。しかし、底に目をやると、階段が地下へと続いていた。ガセネタでは?と一抹の不安を抱えていた一行だったが、思った以上のリアリティに、この仕事は本物だと感じる。3人は気合を入れなおし、吸い込まれるような闇へと勇んでいった。
中は真っ白ではなかった――真っ赤だった。自分が写るほどに磨かれた赤いタイルを床壁天井に貼り付け、内部構造はどこかキルハイル学院に似ていた。
「ハイル一家は1色にこだわる人なのかねぇ。」
目をぱちぱちさせながらレンが乾いた笑いを立てる。
「さて……キル・ハイルさんを探さないと。」
3人はどこにいるかわからないので、とりあえず中央廊下を歩くことにした。しかし、突き当たったところで目を疑う光景が飛び込んできた。
「おい!大丈夫か!?」
そこでは2人の男が全身から血を流して倒れていた。一人はローグ、もう一人はプリーストだ。2人とも体に深い切り傷と、大きな錐で開けたような穴があった。そしてその血は、赤いレンガと同化して、まるで最初からこうだったような自然さである。
「ダメさね……もう死んでるさね。」
レンは脈がない事を確認して手を合わせた。
「やっぱり何かあるのか…」
「ちょっと待って、おかしくない?だって、エリーは私たちにだけここに来れる様にカギをくれたのよね。この2人はもう死んでるわ。って事は侵入者よね?どうやって入ったのかしら?」
「 最初から選んでなんかなかったのか? 」
「あの子が嘘をつくようには見えないけど、でもそれ以外には考えにくいわ。」
「また、侵入者。今日は多いネ。キエル様がいないというのに……留守を仰せつかった私たちの身にもなってオクレヨ。」
どこからともなく声が聞こえ、3人はすかさず戦闘態勢に入る。
「どこだ?!」
「あら、私たちの事が見えないの?」
今度は女の声がした。
「まったく、人間はこれだから困るわ。目に暗視スコープも入ってないなんて、不便な体。せめてサーモグラフィぐらいは入っててほしいわ。」
そう言って姿を現したのは、白い学ランをきた少年と、白いセーラー服をきた少女だった。先ほどの話を聞く限り、相手は人間じゃないと思っていた3人は拍子抜けする形になる。
「そう言うあなたたちも人間じゃない。」
コトの言葉に2人とも、ケラケラと笑った。
「聞いたカイ、エリセル?フフフ……」
「聞いた、エリオット?さっきの2人も同じ事言ってたわね。ふふふ……」
しかし、次の瞬間、コトは前言を撤回した。なんと2人の腕が伸びてみるみる研ぎ澄まされていき、鋭いナイフになった。背中からも庭用ハサミのようにクネクネと巨大なハサミが出てきた。

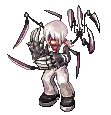
「何なの、こいつら!?」
ジョキン!エリオットのハサミがコトの首を切り落とそうと襲い掛かる。
「私たちは、キエル様の天才的な改造によって生まれた、機械人形!」
シャキン!今度はエリセルの腕のナイフがレンとアコルに襲い掛かった。間一髪で避けると、レンはすかさず魔法の詠唱を始めた。
「エ、エリセル、こいつ魔法使いダヨォ!」
エリオットが動揺の声を上げる。
「怖がらなくても大丈夫よ、エリオット。先に殺せばいいの。」
しかし、レンに突進しようとするエリセルをコトが捕まえた。
「お人形さんなら大人しくしててちょうだい!」
そしてそのまま見事に一本背負いを決める。ドーン!という音が廊下を包んだ。
「ヨクモ、エリセルをやったナ!」
しかし、今度はアコルがエリオットを捕まえた。そして、それと前後してレンの詠唱が終わる。
「タイムアップだ。」
アコルとコトは2人の傍を離れ、レンはそこに焦点を定めた。
「サンダーストーム!」
レンの両手から稲妻が飛び出し、エリオットたちの体に命中する。
「ウワアアアアアアア!」
「キャアアアアアアア!」
後には黒コゲになった2つの首だけが残った。
「ゲフゲフ……ウェェッ!キエル様……苦しいヨォ。」
「だ、大丈夫よ、エリオット。キエル様がまた直してくれるわ。ふふふ……」
「そうダネ。フフ…フフフフフフフッ」
まだ息がある。2人は不気味に含み笑いを続けた。
「何なの…これ……」
「本当に生きてるみたいだ……」
その異様な光景に3人は息を飲んだ。一思いに踏み潰してやりたいが、それができない。とその時、ギイイと奥のドアが開く音がして、再び戦闘態勢をとる。
「キル・ハイルさん。こっちです。」
しかし、部屋から出てきたのは、紫色の髪のアサシンと、白髪と皺の割に筋骨がしっかりした老人だった。この男がキル・ハイルである。
(しまった!まだ他にも契約者が!先を越された!)
悔しそうな顔でアサシンを見つめるコト。すると、その視線に気づき、彼は眉をひそめた。
「君たちがエリオットとエリセルを倒したのかね?」
キル・ハイルはその隣にある人間の死体には目もくれず、ふふふふと未だに不気味な笑い声をあげる2つの頭を見て少し興奮している様子だった。
「いやはや……すばらしい!まさかキエルの造った第三世代を倒すとは。」
「あの、キル・ハイルさん。こいつらは一体……」
アコルが聞こうとするのを隣にいたアサシンが止めた。
「後にしよう。キエルが返ってくる前にここを出ないと。」
「そうだな、バーネットさん。聞きたい事はたくさんあるだろうが話は学院でしよう。」
そこで、みなは急いでキルハイル学院に向かった――
赤色から白色に――結局は極端な単色仕様の場所移動でしかないのだが、一度目のような感覚は不思議となかった。慣れというものは恐ろしいと実感する。最初にエリーがいた部屋に戻ると、エリーはいなかったが、代わりにエリシアが迎えてくれた。彼女はテキパキと奥から長テーブルを出し、イスを並べ、紅茶を運んでくると、キル・ハイルの隣でひと段落した。
「まずは、礼を言おう。バーネットさんに…えーっと。」
「私はコト。青いのがアコルで、栗色がレンです。」
なんとか報酬のおこぼれでも頂戴できないかという下心でついてきたわけだが、いっこうに1億zの影すら出てこない。
「そうかそうか。3人とも。ありがとう。そして、エリーの事は許してやっておくれ。人間の心理的に、"だけ・限定・あなたのため"というものに強い興味を示すと書いてあってな。是が非でも来ていただくために、わざと自分たちだけだと思わせたんだ。そのお侘びと言ってはなんだが、すぐに2億zは用意しよう。」
「に、2億?!」
眼球が飛び出そうなほど驚く3人。キル・ハイルはそれをにこやかに笑うと、エリシアにそっと耳打ちした。
「かしこまりました。」
そのまま、4人に一礼をして部屋を後にする。
「バーネットさんに1億。そちらのお三方に1億でよいかの?」
やった!今の3人には、すでに先ほどキエルハイル邸で起きた出来事は忘れ去られ、その金で何をするかを想像していた。しかし、バーネットは首を横に振る。
「キル・ハイルさん。金はいらないから、一つ質問に答えてもらっていいですかね?」
「ほう……」
途端にキル・ハイルの目が鋭くなった。心の深くまで詮索するような眼光が、バーネットを捕える。しかし、バーネットも負けてはいなかった。その目のやりとりを3人は静かに見守っていた。1億を棒に振ってまでしたい質問とは……やがて、キル・ハイルはふっと笑った。
「いいだろう。何が知りたいのかね?」
「 なぜ、そこまで息子を恐れるのか? 」
その明らかに挑発的な、それでいて深層まで見透かすような鋭い声でバーネットが尋ねると、キル・ハイルは若干顔を引きつらせた。
「ワシが?……息子を恐れている……だと?」
その言葉には、腸が煮えくり返るような思いが込められていて、すごみがあった。
「ええ。今回の事に関して、1億という法外な賞金を出しているのも納得がいきませんし、ただの親子喧嘩では話に収集がつかなそうです。私自身キエル君に話をききたいのですが、彼はかたくなに人と会うことを拒むようで、よほどの事が無い限り、外にも出ないそうじゃないですか。それで、あなたにお話をと思って。」
しばらくキル・ハイルは黙っていた。その間もバーネットから視線を外すような事はない。そして、またふっと笑った。
「残念だが、ワシとキエルはただの親子。それだけの事だ。」
「……そうですか。それならいいんです。俺の思い違いにこした事はないですから。では。」
そう言ってバーネットは部屋を後にした。気まずい雰囲気だけが部屋に残った。
「ワシは仕事柄、いろいろな奴に情報を握られる人間でね。」
ひとりでに語りだすキル・ハイル。3人はうんうんと頷いた。
「危ない仕事をしてるみたいですね。」
「ほっほっほ。ワシを知らないとはシュバルツバルトの人間じゃないな?」
「全員ルーンミッドガッツ出身です。」
「そうかそうか……ワシは、42年前からレッケンベル社の生体研究部門に所属していたのだ。そこで、人間のような機械人形を造ることに我が青春を費やしたのだ。」
彼は紅茶を一口啜って続けた。
「言っておくが、さっきのようなキエルが作った兵器ではないぞ?人間のように考え、行動し、成長する機械人形を作ったのだ。 エリーとかエリシア のような。」
「エ、エリーとエリシアが機械人形?!」
3人が同時に叫ぶと、彼は満足そうに笑った。
「その顔からして、気づいていなかったようだな。いやはや、結構結構。実際、彼女は本当の人間と変わらないからな。」
「でも、おじいちゃんって……」
「ほっほっほ。本当は父親のようなものなんだがな。彼女が独自にワシぐらいの歳だとおじいちゃんと呼ぶように覚えたんだろう。」
そこまで言ってもう一口紅茶を啜ると同時に、ドアが開いてエリシアが戻ってきた。手には大きなトランクケースが2つ握られている。
「ただいま戻りました、キル・ハイル様。お客様、一つお取りください。中を開けて、間違いないかどうか確認してください。」
しかし、3人は1億zよりもエリシアに目がいっていた。白い肌、透き通った目、金色の髪。どれをとっても、人間に違いなかった。
「何か?」
それでも顔色一つ変えずにいるあたりがわずかに人形を思わせる。はっとなってコトがトランクケースをとり、確認した。
「確かに1億zいただきました。」
「うむ。それではワシは仕事に戻るとするか。エリシアよ、デスクの上を綺麗にしておいておくれ。」
「かしこまりました。」
もう1億zを持ったまま、デスクまで移動して上に散らばった消しカスやくしゃくしゃになった紙を丁寧に取っていった。
3人はまた白い廊下を抜けると外に出た。日は沈みかけて仄かに赤みがかっている。
「さて!面白いものも見れたし、お金も手に入ったし!ジュノーまで行って何か食べてホテルにとまろ。」
「そうさね。俺お腹ぺこぺこさ。」
「俺は眠みぃ。」
キルハイル学院を後にして、一行はジュノーに向かい歩き出す。その5,6メートル後方には、紫色の髪のアサシンが物音立てずについていた。
「彼らに協力してもらうしかない。」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 鉄道
- 【2025/10/30】江ノ島電鉄線 1502‐1…
- (2025-11-24 13:16:57)
-
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 多摩動物公園 今日のビクラム 泥パ…
- (2025-11-23 16:30:04)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…
- (2025-11-22 20:32:53)
-
© Rakuten Group, Inc.



