2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

(画像アリ)楽天、三木谷社長とのツーショット
楽天、三木谷社長とのツーショットです。昨夜、阪急ホテルインターナショナルでご一緒しました。■以下二人の会話アキ:ボクは明宏だから“アキ”と呼んでくれー社長:ボクは三木谷だから“ミッキー”と呼んでくれーアキ:そんじゃ、ミッキー!今夜は朝まで飲むぜー社長:ガッテンだい!アキ!最後までつきあうぜーなんて会話があったような、なかったような。
2005年01月27日
コメント(12)
-

(画像4枚)イカとアスパラのシンプル炒め
イカとアスパラ炒めを作ってみました。材料を丁寧に下処理して、一手間かけると、お家でつくっても驚くほどおいしく出来上がります。シンプルな塩味で簡単にまとめるので、素材は新鮮なものを選びましょう。■材料イカ・ねぎ・ふくろ竹・アスパラガス塩・紹興酒・ウイパー(練りタイプの調味料) アスパラガスを斜めカット・イカを四角に切って、切れ目をいれる・ネギも斜めカット イカとアスパラガスを塩を入れた湯の中で、湯通しする。この一手間があとから効いてきます。余熱で中心まで熱が伝わりますし、あとで炒めるので軽く湯通しします。 フクロ竹とねぎを油で軽く炒めたら、さきほどの湯通ししたイカとアスパラを鍋に戻して強火で炒め、ウイパーと塩で軽く味を整える。 シンプルでおいしいです。簡単ですので、皆さんもどうぞ。
2005年01月25日
コメント(9)
-

(画像4枚)国立国際美術館
大阪中ノ島に出来た国立国際美術館へ行ってきました。これは万国博美術館を新築・移転したものです。昨年11月3日にオープンしたばかりです。今日はイベントがなく、常設展だけを見てきました。ポップアートを見る機会があまりなかったので面白いものに沢山ふれてきました。 これは「煉瓦の壁」です。すごく目を惹いたので写真を写してみたくなりました。もし、だめっだったら何か言うだろうと思って、学芸員のすぐ前で写しましたが何も言われませんでした。作品を写してもいいのですね。これ自体に驚きました。これは一階から地下ホールの大空間に設置したミロの陶壁画「無垢の笑い」です。モビールはアレクサンダー・コールダーの「ロンドン」です。この広い空間にピッタリです。 地下から一階に上るエスカレーターの雰囲気がよかったので写しました。美術館の外観の一部です。どこを見ても結構楽しめます。たまにこういうところに来ると気持ちにゆとりが出ますね。いい一日でした。
2005年01月16日
コメント(5)
-

(画像4枚)お正月に門松を自作しました。古いネタですみません。
20分で出来る超簡単門松です。最近は伝統的な門松を飾る家を見ることがなくなりましね。マンションではクリスマスリースのようなおしゃれな門松リースが流行っています。でもチョッと工夫するだけで、もう少し本格的で、しかも簡単に作れる方法があります。簡単にできるのでボクは毎年、自作しています。■用意するもの 青竹130cm位 赤・白の和紙 赤・白・金のロープ 松の先端 椿 糸ノコ ドライバー(先端がマイナス型)■写真1.竹の一部をくりぬく為に上と下に切れ目を入れる。 間隔は約13cm■写真2.上下の切れ目の延長線にドライバーを置き、金づちで 思いっきり一撃を加える。 “ピッ”と音がして、綺麗に裂けます。 竹を割った性格そのものです■写真3.断面をカッターで綺麗に整える。■写真4.あとは赤・白の和紙を巻きつけ、赤・白・金のロープを巻きつける。最後に松と椿を差して出来上がり。(水を差しておくことを忘れずに)ね、簡単でしょ。お暇な方は来年はお試しください。誰かが言っておりました「自分は不器用なので、竹踏みが一杯出来てしまうかも…」いいではありませんか、竹踏みは健康てきですから。
2005年01月13日
コメント(6)
-

(画像3枚)自家製焼き豚でチャーシュー麺を作りました
自家製チャーシューに挑戦です。(NHKきょうの料理を参考)ボクは町のラーメン屋さんで納得のゆく焼き豚を食べた経験がすくないので、いっそのこと自家製に挑戦することにしました。たまたま「きょうの料理」2005年1月号に煮豚の作り方が書いてありましたが、初めから煮るより、一度フライパンで表面を焼いたほうがおいしいと思ったので、自分流にアレンジして作りました。実際、焦げ目が出来て、おいしかったです。■材料豚肉肩ロース(塊)…500g長ネギ…半分しょうが…2かけ固ゆでたまご…2個酒カップ…2/1醤油カップ…3/4キビ砂糖…大2八角…1個 1.豚肉をタコ糸で全体をグルグル巻きにする。2.フライパンに少量の油を敷き、強火で肉の表面だけ全体を焼く。3.鍋に上記の材料を全部入れ、水を1Lを加えて沸騰させる。4.沸騰したらネギ・肉・ゆで卵を入れて弱火で約40分煮たら、肉と卵をとりだす。 5.残り液体をフライパンに移し変えて、水分を飛ばして煮詰める。6.煮詰まったら、肉と卵をふたたびフライパンの中へ戻しいれ、煮絡める。 チャーシューを好みの厚さにカットして、卵も添えて出来上がり。八角をつかったので、いかにも中華らしさがでました。コツは最後の調味液をよく煮詰めてから肉を絡めることです。しっかり煮詰めるまで根気よく煮詰めます。ただし、やりすぎて水分を蒸発させすぎないこと!!家庭でも簡単につくれますので、皆さんもいかがですか。
2005年01月11日
コメント(11)
-

(画像4枚)信楽の陶芸家、奥田美恵子展に行きました
友人の中で唯一の陶芸家、奥田美恵子さんの陶芸展に行ってきました。第15回秀明文化基金賞受賞記念展です。昨年はご夫婦でイタリアに渡り、イタリアでの創作活動で忙しい中、見事受賞された記念の展覧会です。なんと!!世界で初めて雪のように仕上がる釉薬とその温度を発見され「雪結晶シリーズ」を発表されました。今後の創作活動が期待されます。期間:1月8日~1月19日場所:GALLERY陶園(滋賀県甲賀市信楽町長野883-1)電話:0748-82-1495 一番下段の器を購入いたしました。題名は「月見で一杯」うさぎがお月さんを見ながらお酒をのんでいるところです。こういうユーモラスなところを持つ作家さんです。これに何を盛るか、考えるのが楽しいです。 題:月見で一杯参加しています!応援お願いいたします。人気Webランキング
2005年01月10日
コメント(3)
-

(画像5枚)お正月に伊達巻を作りました。
おせちの一つとして、今年は伊達巻に挑戦しました。ボクは伊達巻が大好きなので、いつか自分で作りたいと思っていたので、大満足です(味を除けば)作り方はオレンジページの「お正月料理と鍋」にありました。■材料(1本/4~5人分)卵…3個はんぺん…50g(一個の7分の1くらい)砂糖…大さじ2酒…大さじ1薄口醤油…小さじ半分塩…少々サラダ油…少々■作り方1.はんぺんを2cmくらいにカットしたものと砂糖をフードプロセッサで良くかき混ぜ、ペースト状にする。2.卵・酒・薄口醤油・塩をいれてから、再び15秒くらいかくはんして、卵液をつくる。3.これをこし器を通して、なめらかにする(ゴムベラでこし器をこするとよい)4.玉子焼き器をよく熱してからサラダ油を薄く敷いて余分な油はペーパータオルでふき取る5.卵液を流し込み、極弱火でじっくり両面焼く。6.周囲が固まってきたら、アルミホイルをかぶせて弱火で5分焼く。裏返して、さらに3分焼く。7.焼きあがったら、“鬼すだれ”という特殊なすだれで巻いて、左右を輪ゴムできつく固定する。※熱いうちに巻くことがポイントです。 つくるのは簡単でした。写真を撮る方が、大変でした。三脚を立てて、自分に限りなく近づけ、セルフタイマーをセットし、シャッター半押しでピントをあわせ、シャッターが切れる寸前に手のポーズをつけたり…でも料理写真をとるのが大好きなので楽しかったです。最後まで読んでいただいてから、このような事を書くのは気がひけますが、このレシピ、あまりおいしいというほどではありませんでした。すこし、工夫を加えればよくなると思います。
2005年01月09日
コメント(4)
-
かつぎ桶太鼓の練習に初参加しました
昨年、かつぎ桶太鼓のコンサートに行って、感激したのがきっかけで、今日、初めてこの練習会に参加しました。場所は奈良県天理市です。参加者約25名先生は林田博幸さんです。かつぎ桶太鼓では日本を代表する方との事。確かに、先生の一打ちを聞いただけで「これは凄い!!」と思わせる一打です。どこが違うかというと、音に切れがあるんです。その先生について、10時から19時までみっちりトレーニングです。腕はいたくなるし、マメはできてすりむけるし、それはそれは厳しかったです。一番ショックだったのは、音符が全く読めなかったことです。音符が読めないなら、音だけで聞いて真似ればいいかと思いましたが、とても長い(自分にとって)フレーズなので、覚えきれず、全く自信をなくしました。「タカタ・タカタ・タカタカタン」といわれても右と左の順が良く分からないまま授業は進みます。苦痛でした。それでも、連打を打っているときは、音の洪水の中で自分がそのリズムと一体となってとても気持ちいいものでした。結局、適当に打っても気持ちいいものであることは確かなので、みんなと合っていなくても、ともかく腕を先生と同じくらい上げて、思いっきりテキトーに打ちまくりました。先生に、自分には難しすぎてつづける事が無理かもしれないと正直に話すと「今日のレッスンは初めての人には少しレベルが高かったかもしれないので、京都にある太鼓センターの初心者用の講習を受けた方がいいかもしれない」とのアドバイスをいただく。これから、続けようか早めに見切りをつけるか悩んでいます。ともかく、今夜はゆっくり休みます。
2005年01月08日
コメント(8)
-

(画像付き)土鍋でご飯を炊きました
ボクは土鍋で炊いたごはんが大好きです。だから、炊飯器なるものを持っていません。毎回、お米を研いで、水につけて…これが実に楽しいです。自分で炊いたお米は鍋底にはりついていた最後の一粒まで掻きだして食べてしまいます。愛着がわくんですね、お米に。1年かけて育ててくださった農家の方にも感謝の気持ちが自然と沸いて来ます。■炊き方土鍋にも色々癖があるとおもいますが、自分の土鍋の場合で記載します。1.米を研いで水に30分浸漬する2.ザルに移して10分放置する3.土鍋に米を入れ、水を(体積で)同量いれる4.沸騰するまで中火で過熱5.沸騰したら、その時点から3分そのまま加熱しつづける6.時間がきたら火を止める7.そのまま10分蒸らし、よくかき混ぜる、あと3分蒸らして出来上がり。■ポイント5.の沸騰とは、穴や、フタと本体の間から勢いよく水蒸気が出た状態)初めから最後まで中火のままです料理の本に、水は米の1.2倍と書いてありますが、浸漬したときに約0.2の水分を米が吸っているので、後から入れる水は同量である1でよいのです。また、火力についても、料理の本によっては、強火で5分とか書いてありますが、そんなことをしたら、焦げてしまいます。(おこげが食べたいのなら別ですが…)皆さんが持っている土鍋と土鍋の癖が違うので、必ずしも上記方法で上手く炊けるとは限りません。但し、自分の経験では、鉄鍋でも同じやり方で成功しております。皆様の経験、ご意見をいただければ幸いです。 (投稿者撮影)
2005年01月07日
コメント(3)
-

画像あり 年越し蕎麦を手打ちで作る
年末に年越し蕎麦を打ちました。やや太めに切り、これを鴨汁仕立てでいただきました。蕎麦打ちは2年前に初め、月に1回、大阪は寝屋川へ練習しに行きます。出来の悪い蕎麦でも、自分で打った蕎麦は格別です。ざるにこびりついたコマ切れの蕎麦でも、いとおしくて捨てられず、すくって食べてしまいます。昔からいいますね「バカな子供ほどカワイイ!!」蕎麦も一緒です。 (三脚を立てて、セルフタイマーで撮影しました)
2005年01月06日
コメント(4)
-

(画像有り)黒豆を煮ました
おせちに黒豆は欠かせませんね。水に17時間漬けて豆をふやかし、10時間かけてじっくり煮ました。■材料黒豆…(丹波大納言)カップ2杯鉄くぎ…8本(ガスコンロで焼いて冷ましたもの)重曹(炭酸水素ナトリウム)…耳かき2杯蜜…水カップ5と白砂糖330gを溶かしたものブランデー…少々■作り方1.鍋に、豆を体積で3倍以上の水に漬け、釘をガーゼに包んで一緒にいれて17時間くらい浸す。2.鍋ごと加熱(強火)し、沸騰したら極小の弱火にして重曹を入れて10時間煮る。3.アクが大量に出るので、丁寧に何回もすくう。(アクが出なくなるまで根気よくやる)4.この間に水分が蒸発して湯が少なくなるので、何回か熱湯を注ぎ足す。5.10時間したら、蜜を沸騰させた別の鍋に豆だけをすくって移しかえる。6.移し終えたら、すぐに鍋ごと流水につけて、粗熱をとる。7.冷えたら、ブランデーを小さじ1杯いれて、甘さの切れをみる。味の変化を見ながら2杯~3杯を好みで入れる。8.タッパーに写して保存しても、鍋ごと寒い部屋で保存してもOK■ポイント1.沸騰後に弱火にしても、フタをしていると、ゴボゴボ沸騰してきて、豆が壊れやすくなるので、フタを半分ずらすといい。2.煮込み温度は90度くらいをキープ (自分で撮影しました)
2005年01月05日
コメント(8)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-
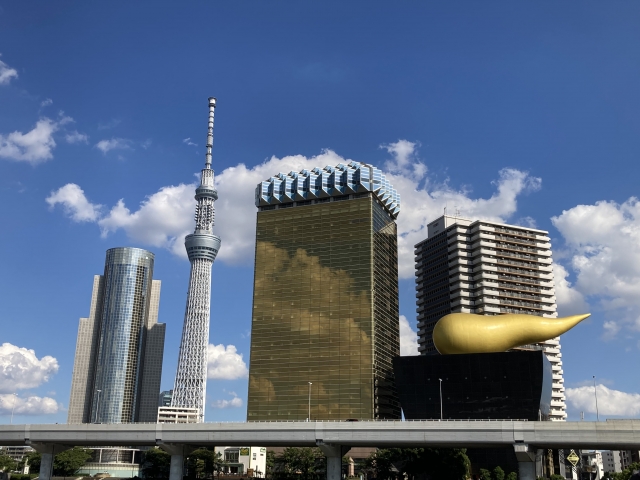
- ◆パチンコ◆スロット◆
- 東京都小平市 低貸スロット(2.5円…
- (2025-11-15 00:00:08)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 石切神社 参拝
- (2025-11-14 21:00:05)
-
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-







