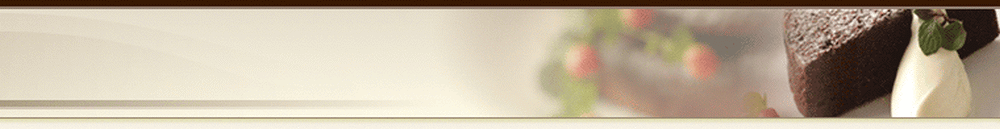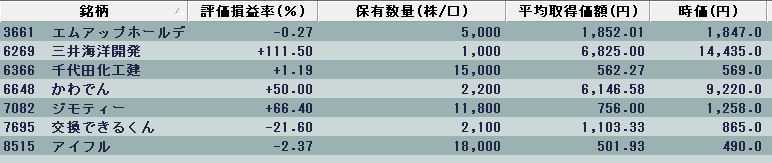2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
確定申告情報その19~必要経費とは?
よく尋ねられることですが、「必要経費と家事費の境目ってどこにあるんですか?」 営業関係の方のスーツや靴は必要経費なのか、自家用車兼営業車の必要経費は? 法令や通達を見てもあいまいなことしか書かれていないので私はこう考えることにしています。 「この商売をしていなかったらこの支出はあったかどうか」 この商売をしているからこそある支出が必要経費だと思います。私の例でいうと、税理士事務所を自宅と別に構えていますからこの事務所の固定資産税や自治会費などの支出は100%必要経費です。この仕事をしていなかったらこの事務所もない訳で、これらの支出もない訳で・・。 この考え方にも限界はありますので例外を2つほど。 私の自家用車兼営業車はこの商売をしていなくても持つことになる訳ですが、これは仕事に使っており収益を上げるのに貢献しています。よってその減価償却費や自動車税・保険料などは家事部分を見積もりそれを控除した額を必要経費にしています。 また、私もスーツを着て仕事をしていますが、確かにこのスーツは仕事に貢献しています。しかし私用に使えることも事実なので必要経費とはしていません。もっとも、会社名入りの作業服など仕事にしか使わないようなものは必要経費性が高いと思います。人気blogランキングへ
January 31, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その18~源泉分離課税
所得税は原則として総合課税といい全ての所得を合計してその金額が大きくなれば税率も高くなるという考え方が大前提にあります。 しかし、所得の種類に応じて他の所得と分離して単独で課税することになっているものもあります。こういうものを「分離課税」と言っています。 その分離課税の中でも所得の発生時に源泉徴収して課税関係が終わってしまうものを「源泉分離課税」と言っています。 その代表選手が利子所得。銀行などの利子を確定申告したことがある人は殆どいないと思います。無論、申告書には記載する箇所がありますがここに記載している人は見たことがありません。 何故かというと利子はその利息の支払い時に銀行側で所得税15%住民税5%を源泉徴収しそこで課税関係が終わっているからです。 外国の金融機関の利子も日本の銀行にその金額が振り込まれる際にその日本の銀行で源泉徴収することになっていますから、総合課税の利子所得というのは外国の金融機関の利子を直接小切手か現金のようなもので送付されてきたもののみになります。 総合課税で税額がゼロになった人も利子については税負担を強いられるというのも変な話ですね。人気blogランキングへ
January 30, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その17~上場株式等にまつわる地方税
上場株式等にまつわる所得というと配当所得と株式譲渡所得がすぐに浮かびます。これらの共通点(?)は所得税・住民税とも源泉所得税率が同じということ。 配当・譲渡差益に対しそれぞれ所得税7%、住民税3%で源泉徴収されます。 また、配当は金額にかかわらず所得税では選択により申告しないことができますし、譲渡差益分についても源泉徴収ありの特定口座に入れておくと申告しなくてもいい点も共通しています。 ところで、確定申告書第2表の右下の方にある住民税に関する事項のところに1.「配当に関する住民税の特例」、2.「配当割控除額」、3.「株式等譲渡所得割額控除額」なる欄があるのをご存知でしょうか? 1.は上場株式等以外の株式・出資からの配当は年10万円以下であれば所得税は申告不要を選択できますが、住民税は申告しなければならないので所得税で申告しなかった上場株式等以外の配当を書いて下さいということです。これは去年か一昨年の税制改正でそうなったのですが、事実上課税モレが星の数ほどあると思われます。 2.と3.は上場株式等の配当や譲渡所得を申告した場合、源泉徴収されている住民税部分の3%の金額を書いて下さいということです。ここに書いておくとその金額が翌年分の住民税から差し引いて課税されてくるので是非記載モレがないようにしたいものです。 今日はちょっとマイナーな箇所にスポットを当ててみました。人気blogランキングへ
January 29, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その16~社会保険料は必要経費ではありません
国民年金の掛け金、国民健康保険の保険料などの社会保険関係の支出は必要経費から除かれています。 しかし、これらの支出は社会生活を営む上でどうしても出てくる公共的なものですから所得控除という形で支出した額全額を所得控除として所得から差し引くこととされています。この取り扱いは所得税でも住民税でも同じです。 支出した金額が所得から差し引かれるのだから必要経費にしたのと税額は同じじゃないか、という声をよく聞きます。 ここのところが税法をややこしくするのかもしれません。 必要経費と所得控除はどう違うのでしょうか。 所得税の申告には2つの意味があると考えます。一つはもちろん税額を確定させることですが、もう一つその年の所得を確定させることです。 所得は税金以外にもいろんなところに影響があります。公営アパートの家賃とか、国民健康保険の保険料とか、公立保育園の保育料とか、高額医療費の算定とか・・・。 社会保険料を必要経費としてしまうと所得がその分だけ小さく出てきます。ですから所得税の金額は必要経費でも所得控除でも結果は同じになりますが、所得計算ということを考えると必要経費とすることはできないと言うことになります。人気blogランキングへ
January 28, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その15~医療費控除を誰につけるか?
医療費控除は世間によく知られる所得控除となっており医療費の領収書を細かく集め保存されていると思います。 この医療費控除の特徴は 1.同一生計の親族分であること 2.10万円又は所得金額の5%のいずれかの足切り額があること が上げられると思います。足切り額というのはある程度の金額に達しない場合その達しない部分の金額は控除の対象としないという金額のことで医療費控除の他寄付金控除と雑損控除にあります。 この2つのことを考えると次の法則が浮かび上がってきます。1.同一生計分の医療費は全部まとめて誰かにつけると足切り額が1回で済むのでトクになる2.ただし医療費があまりにも大きく、一人の控除では控除額が余ってしまう場合に初めて2人目にその余る部分を分けてつける(この場合、足切り額は2回となりますが全体では税金が安くなります)3.所得控除なので基本的に課税所得の一番大きい人につけるとトク4.ただし足切り額は所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく所得金額の5%となるので医療費が10万円以下の場合でも所得金額が200万円未満の人につけると控除額が出てくることがある よく医療費が10万円ないと「控除が受けられない」と考える方がいらっしゃいますが、所得金額が200万円未満であれば控除額が出てくることもあるので注意が必要です。人気blogランキングへ
January 27, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その14~無料申告相談会
私の所属している北陸税理士会高岡支部では今日から無料申告相談会を当番制で始めます。 毎年の恒例行事で3月上旬まで続くのですが、今年は消費税の納税義務者の増加と年金受給者の申告増加でかなり日数も増えています。 税務署の方にお聞きすると今月20日に開設した相談所(税務署の1階部分)が例年になく盛況で1日当たりの来署者数も多いそうです。 無料税務相談所も同様に利用者が多くなりそうです。利用される方はもう申告書も届いていると思いますから資料を揃えて早めに相談された方がいいと思います。 所得税の確定申告は2月16日から・・・となっていますが、実務上それ以前でも受け付けてくれるところは多いと聞きます。2月15日以前ならまだ利用者も少ないと思いますのでお早目に申告されるとすぐ終わると思います。今年は例年に増して「お早めに」ということになりそうです。人気blogランキングへ
January 26, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その13~長期譲渡と短期譲渡
この前頂いた相談できわどいのがありました。 どうきわどいかというと短期と長期ぎりぎりだったのです。 土地付き建物の譲渡をいつすればいいかということで登記簿謄本を見ながらお話させて頂いたのですが、取得日が平成12年4月。 「これ、もう譲渡されたんですか?」「いえ、今から譲渡するのでいつの譲渡にすればいいかと・・・」 譲渡なさる前にご相談に来られてよかったです。 実は、土地や建物の短期と長期は譲渡した年の1月1日まで遡って、その時点で5年を超えているかどうかで判定します。 ですから、本件の場合平成17年中に売却されたのであればたとえ暮れに売却があり実所有期間が5年を超えていても平成17年1月1日時点では所有期間が5年を超えていないため「短期譲渡」になってしまう訳です。 長期譲渡の税率は国税15%地方税5%。長期譲渡の税率は国税30%、地方税9%。税額がほぼ倍になるので注意が必要です。 ちなみに、平成17年分の所得税で長期譲渡となるのは平成11年以前取得分の土地・建物となります。人気blogランキングへ
January 25, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その12~確定申告用紙を送ってこない?
毎年申告をなさっている方にはそろそろ確定申告の用紙が送られてくる時期となりました。 しかし、待てど暮らせど送ってこない。こんな方もいらっしゃいます。 去年、電子申告で申告なさった方には確定申告用紙を送らないことになっています。今年も電子申告でお願いね、ということなのでしょう。 無論、税務署などで用紙を入手するか国税局のHPからダウンロードするかして紙の申告をすることも可能です。 この場合予定納税の額はどこで調べるのかということですが、電子申告のメッセージボックスでお知らせが来るようです。 消費税の新規課税事業者も増えることですし、この際電子申告にチャレンジされるのもいいのではないでしょうか。人気blogランキングへ
January 24, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その11~配当は申告した方がトクか(下)
今日は結論です。 まず、総合課税の税率が30%、37%になる方は上場株式等、年10万円以内のその他の配当ともに申告しない方がトクです。7%、20%の源泉所得税で済むからです。これらの高所得者層の方は定率減税も頭打ちになってますし、配当控除を考えても源泉所得税の方が安くて済みます。 では、総合課税の税率が10%、20%の方はどうでしょうか。 まず、上場株式等について。源泉は7%ですから総合税率20%の方は申告しない方がトクです。20%(税率)×90%(配当控除後)×80%(定率減税後)=14.4%となり7%より大きくなるからです。同様に総合税率10%の方で税額の出てくる方は10%×90%×80%=7.2%となるので申告しない方がトクです。ただし、所得より所得控除の方が大きいという方はもともと所得税がかからないので申告して源泉所得税の還付申告をされた方がトクになります(ただし、この配当を申告することによって所得金額が38万円を超えてくる場合、自分が他の人の扶養親族等になれなくなるので注意が必要です)。 また、上場株式等以外の配当はどうでしょうか。源泉所得税率が20%ですので総合税率10%の方は申告した方がトクなのは一目瞭然です。総合税率20%の方でも配当控除があるので実質税率は18%となり申告した方がトクということになります(所得控除後の所得金額が3,212,999円までの方はさらに20%の定率減税があります)。《結論》総合税率10%の方⇒上場株式等は申告しない方がトク(税額が出てこない人は申告で還付を受ける方がトク) 上場株式等以外は申告した方がトク総合税率20%の方⇒上場株式等は申告しない方がトク 上場株式等以外は申告した方がトク総合税率30%、37%の方⇒上場株式等、上場株式等以外ともに申告しない方がトク なお、来年、再来年と定率減税の縮小、撤廃の道筋ができています。この有利不利はそれに応じてまた変わってきますのでまた来年考えることにします。人気blogランキングへ
January 23, 2006
コメント(1)
-
確定申告情報その10~配当は申告した方がトクか(中)
昨日の続きです。 いろんなところから受け取る配当。上場株式や年10万円以下の配当について申告してもしなくてもいいというのは昨日述べた通りです。 さて申告した方がいいかどうかですが、まず所得税の税率と配当の源泉税率をおさえておく必要があります。 所得税(総合課税分、配当も総合課税)の税率は所得控除後の金額が330万円までの部分が10%、330万円超900万円までの部分が20%、900万円を超えると30%、37%と上がっていきます。 また、配当所得には配当控除という税額控除があります。これは大雑把にいうと所得控除後の金額が1,000万円までなら配当所得の10%、1,000万円を超えていると配当所得の5%を税金から差し引くことになっています。 配当の源泉所得税の税率は上場株式の分は7%、それ以外の分は20%です。 ちょっと複雑ですが、上場株式の分とそれ以外の分に分けて明日、結論を述べていきます。人気blogランキングへ
January 22, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その9~配当は申告したほうがトクか(上)
最近インターネット取引を行う個人投資家が増え、株式にまつわる所得申告も増えていると思います。 株式にまつわる所得として考えられるのはまず株式譲渡の所得。そして配当所得。今日はこの配当所得について考えてみます。 配当所得は株をやってなくても例えば信用金庫とか農協の出資配当がある方など幅広く出てくる所得です。しかし、税法では少額不追及ということと配当所得は源泉徴収の制度があるということから上場株式等の配当については金額にかかわらず、それ以外の配当については1銘柄当たり年配当10万円以下のものが納税者の選択により申告してもしなくてもよいこととなっています。 そこで気になるのが「配当所得を申告した方がトクなのか、ソンなのか」ということです。明日以降、これを上場株式等とそれ以外の株式等に分けて考えてみます。人気blogランキングへ
January 21, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その8~青色申告特別控除
不動産所得と事業所得、山林所得の青色申告者の特典として青色申告特別控除という制度があります。 このうち、不動産所得のうち事業的規模のものと事業所得については記帳体制を整えることにより控除の上乗せがあります。 これまでの控除額は原則10万円、上乗せ適用分が45万円か55万円となっていましたが今年の申告分から原則10万円、上乗せ適用分が65万円となりました。 どうすれば65万円控除の適用になるかということについてはFPステーションさんから2本のテープを出させて頂いているのでそちらに譲るとして、上乗せ適用分の控除額が大きくなったということから帳簿をきちっとつけている人については税の恩恵を与えるという税務当局側の姿勢が見てとれます。 やはり10万円の控除より65万円の控除の方が税額が安くなるので是非チャレンジしていきたいところです。 また、不動産所得と事業所得の両方がある方は不動産所得が事業的規模ではなく事業所得が赤字という場合でも事業所得の帳簿体系が65万円の要件を満たしていれば不動産所得から65万円控除することができますから(納税者有利)注意が必要です。人気blogランキングへ
January 20, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その7~雪害に逢われた方へ
去年の暮れから降り続いた雪も現在は小康状態を維持しているようですが、雪おろしや雪による居宅の破損など大きな被害が報道されています。 このようは雪害関連の費用は雑損控除という制度があり、給与所得者であっても還付申告をすることができます。 手続きとしては医療費控除に似ていて、支出した金額のうち一定の金額を所得控除として確定申告するといったものです。ただし今回の申告の対象になるのは平成17年に支出した分のみで年明け以降の支出分は来年の申告の対象となります。 是非、雪害費用の領収書などは保存しておき還付申告に使って頂きたいと思います。人気blogランキングへ
January 19, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その6~所得控除が減りました
所得税が複雑で分かりにくいという原因・・・10個の所得、8個の課税標準、15個の所得控除、8個の課税所得金額と習いましたが正にそれだと思います。 そのうち15個の所得控除が平成17年分の確定申告から14個に減りました。老年者控除というものがなくなったのです。 老年者控除とは年齢65歳以上で合計所得金額が1千万円以下の人に一律50万円を所得から控除するというもので年金所得者などはこのためにかなり税額軽減されていたものです。 これが今回の確定申告からなくったことにより他の所得控除にも影響が出ています。寡婦(寡夫)控除です。 寡婦(寡夫)控除は老年者控除とダブルで受けられない控除項目だったのですが、今回老年者控除がなくなったことによりつれあいに先立たれた人などは何歳であっても寡婦(寡夫)控除が受けられるようになりました。 ですから、去年まで老年者控除を受けており寡婦(寡夫)控除を受けていなかった人は今回から寡婦(寡夫)控除が復活しますから権利の上に眠らないよう注意が必要です。人気blogランキングへ
January 18, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その5~還付の申告書はいつ出すか
ウチの事務所にもいよいよ繁忙期が訪れました。事務所を開いてからずっと「確定申告は1月からやりましょう」とお客様に触れて回っていたのがようやく結実し、既に決算ができている方を含め6,7人くらいのお客様が1月中に上がる予定です。前倒ししていかないと今年は消費税の関係でどうなるか分かりませんから大変有難いです。 さて、今日は所得税の還付申告の話です。 還付申告は5年の時効はあるものの、いつ提出してもよいことになっています。ですから、2月16日の受付開始を待たずに今日提出しても受領してくれます。我々の業界も報酬の10%を源泉徴収されていることから通常、還付申告となります。この還付申告をいつするかによって還ってくる金額に差が生じる場合もあります。 まず、早く出す(一応、2月16日以前を早く出すということと考えて頂いていいです)ことのメリットは早く還ってくることです。まだ大多数の国民は確定申告期に入ってないと思ってるうちに出す訳ですから当然税務署の処理も早くなります。 では、遅く出す(大体3月10日過ぎと考えて頂いていいです)ことのメリットは何でしょうか?還ってくる税額がある程度大きい場合に利息(還付加算金といってます)がついてくることです。この利息は年14.7%と破格の率で計算されますのでいい資産運用となります。この日数は3月16日から実際の還付命令があるまでの日数で計算します。なお、この還付加算金はその年分の雑所得となりますので翌年確定申告する際に注意が必要です。 いずれにせよ、確定申告の準備だけは早めに進めた方がよいと思います。
January 17, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その4~節税するか否か(下)
現在のように所得税が増税基調にあるときの節税には積極的に進めればよいものとそうでないものがあるということがお分かり頂けたと思います。 今までも業績が年々上昇して所得が増えていく場合には所得税は超過累進税率(所得が増えるほど税率も上がるということ)を採用していますので積極的に進めないほうがよい節税もあったということになります。 まとめますと1.国民年金基金や小規模企業共済への加入などその年にしか影響しない節税は積極的にしてもよい。2.引当金の計上や特別償却など経費の前倒しとなるような節税は積極的にやらない方がよい、むしろ経費を翌年以降に繰り延べる方向で ということになります。 ここで勘違いしてはならないことは「経費をなるべく今年は少なくすればいいのか」と思って店主勘定に振替える額を多くすればよいということではないということです。店主勘定に振替えた額はその年限りで終わりですから翌年以降に経費を繰り延べるということにはならないので意味がありません。 3日間に渡って節税対策を施すかどうか検証してきましたが、無論、これに当てはまらない人もいらっしゃいます。決算対策で平成17年の経費とすることにより平成17年の税額がゼロになる人です。この人たちを除けば所得税の実効税率はここ何年かで上がっていきますので節税の内容に応じてやればいいのかやらない方がいいのか判断することになります。人気blogランキングへ
January 16, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その3~節税するか否か(中)
昨日の続きです。 まず、積極的に節税した方がいいものを考えます。それは来年以降の申告に影響を及ぼさない必要経費なり所得・税額控除です。 例えば業務用自動車を買うとか国民年金基金や小規模企業共済に加入するとか社会保険料控除を税率の高い人につけるとか税額控除とかいうものです。これら自体は今年の申告にしか影響がないのでこういった性質のものは積極的に取り組めばよいということになります。 では、どのような節税を見合わせるべきか。上記とは逆に来年以降の申告に影響のある必要経費なり所得控除です。 例えば特別償却とか引当金とか地代家賃・社会保険料・小規模企業共済などの年払いとかいったもので来年以降の必要経費や所得控除を本年に前倒しする効果しかないものです。 国民年金を1年分12月に前払いして平成17年分の社会保険料控除が16万円増えることを考えてみましょう。 平成17年の税率が10%だったとすると平成17年は16万円×10%×0.8=12,800円だけ所得税が減ります。しかし、これは平成18年分の所得控除を前にもってきただけなのでもともと平成18年の所得控除とできるものです。もしこれを平成18年分の所得控除としていたならば・・・16万円×10%×0.9=14,400円となり1,600円分節税効果が大きくなることになります。 さらに平成19年には定率減税が全廃されますし、所得税率の区分も細かくなるということなのでここで実効税率が上がると見込まれる人にはこういった節税を今回してしまうとこの先何年かの合計税額を考えた場合不利になるということになります。 この考え方は明日まとめてみます。人気blogランキングへ
January 15, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その2~節税するか否か(上)
個人の確定申告でも法人同様、決算対策などにより節税を図ることができます。 ただ、個人の場合には各種所得、家事関連費、所得控除、超過累進税率(課税所得が大きくなるほど税率も大きくなること)といった法人にはない概念がありますので少し事情が異なってきます。 今現在決まっている改正事項と去年の暮れに発表された与党税制改正大綱を見ていますとどうやら所得税は増税の方向にあると判断せざるを得ません。 違った言い方をすれば、平成17年分の所得税について何が何でも節税ということでやってしまうと18年、19年で余計な税金がかかってくるということが予想される時代になってきたということです。だって、同じ所得でも後々税率が上がると税額は多くなるのですから・・・。 そこで、個人事業者の節税方法をいくつかに分けて平成17年でやっても後々影響のないものと、どちらかというと平成17年ではやらない方がいいものを明日からご紹介していこうと思います。人気blogランキングへ
January 14, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その1~申告期限
そろそろ今年も確定申告の時期になってきました。 所得税の確定申告は大きく3つに分けられます。一つ目は納税の出る申告。二つ目は損失を次年度以後に繰り越す申告。三つ目は還付を受けるための申告。 納税の出る申告と損失を繰り越す申告は2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。 それでは、還付を受けるための申告はいつからいつまでにするのでしょうか? これは決められていません。ですから平成17年分の所得税の還付申告期限は平成18年1月1日から時効期限である平成22年12月31日までとなります。 ですから、還付になる方は早く還付を希望する場合今日にでも申告を受け付けてくれます。まだ混雑期に入ってませんからかなり早く還付されてくるものと思います。 また、年末調整だけで申告してない過去の年分(例えば平成14年とか15年とか)の所得税について例えば扶養控除が抜けていたとか医療費控除が抜けていたとかで還付になる場合、今からでも確定申告により還付を受けることができます。私も去年、お客様の義母の扶養控除が抜けていたので5年分の申告をして還付を受けていただきました。人気blogランキングへ
January 13, 2006
コメント(0)
-
確定申告期に入ってきました。
いよいよ今年も個人の確定申告期の足音が聞こえてきました。 先日、ちょっと早いですが事情があり税務署に確定申告書と決算書の用紙をもらいに行ってきました。 決算書はいつも通りなのですが、確定申告書は我々実務側からすると大変に大きな変更点があります。 第一表に(平成十七年以降用)と書いてありこれは老年者控除がなくなったことなどから記載内容が変わったことを意味してるんだな、と思いきや用紙の穴の数が変わっています。また、この変わり方が中途半端。 所得税の確定申告書の用紙はどれも3枚複写になっていて一番上が税務署保存、2枚目は市町村役場保存、3枚目が納税者控えになっています。今までは1枚目と2枚目が15穴、3枚目は無穴だったのが今年から1枚目のみ4穴となりました。これにより1枚目4穴、2枚目15穴、3枚目無穴とそれぞれ穴の数が違うことになります。 ほとんどの会計事務所ではプリンタで出力することになっていると思いますが1枚目と2枚目で穴の数が違う(=用紙が違う)ものをどうやって用紙セットしていくのか・・・と疑問が出てきます。 ウチの事務所でも15穴の白紙用紙はまだ在庫が数百枚あります。消費税の申告書に変更はないようなので消費税の申告書と2枚目にしか使えません。うーん、どうしようか・・・。これでは申告書を受領する税務署の現場でも旧申告書で出てきた場合など綴るのに一苦労だと思いますよ。人気blogランキングへ
January 12, 2006
コメント(0)
-
眼圧?なんのこっちゃと思ってました。
今眼科から帰ってきました。 暮れに受けた人間ドッグで眼圧が異常値を示しているということで眼科の受診を勧められたからです。 眼圧って・・・?目の圧力・・・・?何でも、放っておくと緑内障を引き起こし失明の危険もある症状らしいのですがこれは一大事ということで事務所近くの眼医者さんにいく運びとなりました。 今日の検査では多少高めではあるものの、異常値ではなく視野もそんなに狭くなっている訳ではないとのことで診療は不要とのことでした。 ほっとしましたが、去年入院してから何か妙に病院に縁が近くなったような気がします。一病息災とはいいますが以前では考えられなかったくらい医療費の領収書がたまっていきます。 何はともあれ、疑いのあった箇所が一つ減って何よりです。※眼圧・・・眼球の硬さのことだそうです。硬くなりすぎると眼球の後ろ側にある視神経を圧迫し、視野が狭くなる緑内障を引き起こすということでした。人気blogランキングへ
January 11, 2006
コメント(2)
-
氷の世界
昨日は誕生日のことをここに書きましたが皆さんにお祝いの言葉を頂きました。有難うございました。 誕生日が祝日になったのが嬉しくて自分で国旗を家の前に立てたりしてましたが、実は昨日一日雪かきでした。 午前中は家の前でお昼から事務所の駐車場。娘と二人で事務所で雪と戯れていました。 久しぶりのいい天気だったので駐車場のアスファルトを出してやろうとスコップで雪の下をゴリゴリやってました。すると白い雪の下は厚さ5~10センチの分厚い氷の世界。その氷の上に3センチくらいの雪の層。 雪国にいるので白い雪の下は氷だというのは知ってますがここまで分厚いのが事務所の駐車場にあろうとは・・・。降り始めからかなり雪かきをサボっていたのが分かってしまいます。 実はウチの事務所の駐車場のうち2区画を近所の方(どちらも若いお姉さんです)に貸していてそこはきれいにアスファルトが出ていますがそれ以外の部分が分厚い氷の世界だったと知るととても恥ずかしい思いをしました。 今日も高岡は雪。朝来たら昨日顔をみせてくれたアスファルトが再び雪の下数センチのところにもぐっておりました。 今度こそ分厚い氷の世界をつくらないぞ!人気blogランキングへ
January 10, 2006
コメント(0)
-
ハッピーマンデーのお陰で・・・
今日は私の誕生日です。毎年1回訪れる誕生日ですが今年はちょっと事情が違います。 まず、12年に1回の年男の誕生日だということ。ああ、あと2回りで還暦か・・・などと思ってしまいます(同じ戌年の母が今年還暦なので)。 もう一つは子供のころから夢見ていた(?)祝日になったということです。 私の近所にいた従兄弟の誕生日が4月29日で当時天皇誕生日でした。子供ながらに「何で順ちゃんの誕生日だけ皆で日の丸上げるがけ?」などと親に聞いていた覚えがあります。それだけに祝日に誕生日のある人をうらやましく思っていました。国民皆で旗を上げて祝ってくれるのですから・・。 それが幾星霜もの年月を経て今日、ついに自分の誕生日が成人の日という祝日になりました。 夢といっても自分の努力でかなうという性質のものではありませんが、何かいい気分です。人気blogランキングへ
January 9, 2006
コメント(12)
-
人的課税と物的課税
たまには本職のアカデミックな話題を。 税金にはいろんな分類の仕方があります。国税と地方税、直接税と間接税、所得課税、消費課税と資産課税など・・・。 そのような分類の仕方として「人的課税と物的課税」という見方があるそうです。 人的課税は今の日本でいうと所得税と個人市県民税だけ、それ以外は全て物的課税です。 どういうことかというと人的課税は所得控除があることに特徴があります。同じ所得を挙げている二人の人がいるとします。このうちAさんは健常者で未婚、扶養すべき人もおらず生活には何の支障もないのに対しBさんは夫に先立たれ扶養すべき子供が3人もいらっしゃるとするとこの二人に同じ金額の税負担を設けるのは理不尽であるとする考えのもとに成り立っています。 これを是正すべく所得控除なるものを規定してその人の置かれている現状に応じて税負担を調整しようというのが所得控除の意味合いです。 これが税を複雑にしていると言われることもありますが、言い方を変えれば少しでも人間味のある血の通った制度だと言えます。 これに対し物的課税はそういったことを考慮しません。個人事業税などはその代表例です。所得から年290万円を引いて残った金額の5%。扶養人数が多かろうが少なかろうが、障害者であろうがなかろうがこの金額で課されます。ある意味、血も涙もない税金です。消費税もそうです。 これまで国の歳入はこの人的課税である所得税が税目としては一番大きなものでした。それが消費税の納税義務者の拡大とこれから上がるであろう税率のアップにより消費税が一番になるのはもう時間の問題です。 血の通った人的課税が後退し血も涙もない物的課税が台頭してくることに一抹の寂しさを感じます。人気blogランキングへ
January 8, 2006
コメント(0)
-
雪で遊びました。
高岡は今日も小雪がちらついています。 こちらは先月から降り続いていた記録的な雪も小康状態となっています。今なお大雪に見舞われている地域の方々には同じ雪国からお見舞い申し上げたい気持ちでいっぱいです(今朝も富山市で84歳のおじいさんが屋根の雪下ろしで転落死したそうです)。 一方で子供達は雪が大好き。裏山までそり遊びをしに行ってきました。ここでもそりのコースをつくるのにスコップで一仕事。2人とも楽しくて楽しくてしょうがない様子で家族4人で楽しみました。 家に帰ってくると今度は庭の例年にない積雪に穴を開けてかまくら作り。これもお父さんの仕事。かまくらって、作るの大変だけど完成したら子供が入って楽しんでごく短い時間で終わるんですよね。 それはそうと、そりもかまくらも子供達に楽しんでもらえて大変よかったです。私も久しぶりに童心に帰って夢中でスコップ作業をしました。子供の遊びに親が夢中になるというのを実体験しました。しかし、明日の筋肉痛が心配・・・。人気blogランキングへ
January 7, 2006
コメント(0)
-
電子申告に思う
一昨年から始まった電子申告。法人・個人ともとても普及が進んでいるという状態ではありません。 昨日税理士会の会報で税理士会が政府に電子申告に関する要望を提出したとの記事を読みました。 やはり今のままでは普及は難しいとの立場です。 電子申告とはインターネットで国税局のサーバにアクセスし申告内容を送信するだけのものですが、なりすまし防止のため納税者の電子認証(インターネット上の実印)が必要となります。 実際にやっていると会計事務所側は作業が楽になります。税務署に提出に行かなくていいんですから。納税者の方には若干の負担が生じます。電子認証は無料ではないですから。税務署はどうでしょうか。電子申告のデータは見にくいですよ。 そこで、税理士会は税理士の電子認証のあるものについては納税者の電子認証は不要ということで何とかならないかと申し出た訳です。お隣のIT先進国、韓国では税務士(韓国の税理士に相当)の電子認証のあるものは納税者の電子認証は不要です。既に電子申告の普及率は8割に達しているそうです。 これが日本で通るかどうかは分かりませんが、電子申告や消費税を見ても我々税理士の業務に関するモラルや責任がこれからますます問われる世の中になっていくと感じました。人気blogランキングへ
January 6, 2006
コメント(0)
-
今年の税務支援
今日から対外的には営業開始となっているので朝から年末調整の資料集めに奔走してました。 その帰りに北陸税理士会高岡支部の事務局に寄り今年の確定申告期の税務支援の作業をしてきました。 今年は老年者控除廃止に伴う年金所得者の相談の増加や消費税の課税事業者の増加により今までにない忙しさとなることは明らかなのですが、事務局でちょっと仕事をするつもりがあれこれやることが出てきて大変でした。 商工会や商工会議所でも同じような悲鳴を上げていると聞いていますが、とうとう来るべきときが来たという感じでこれからの超繁忙期を迎えます。 何分、無理は禁物。早め早めの対応で乗り切りたいと思います。人気blogランキングへ
January 5, 2006
コメント(0)
-
なつかしい貧乏学生の帰省
昨日、東京と名古屋から帰省していた妹と弟が帰っていきました。今日からまた普段の日常に戻っていると思います。 私も10数年前は東京の大学に行っていたので盆・暮れには帰省をしていました。当時は(今も)お金もなかったのでよく「急行能登」や甲府・松本回りの普通列車乗り継ぎで帰ってきていたものです。 この貧乏旅にも大変な楽しみがあって、急行能登では座れないので一番後ろの運転席(?)の前に新聞紙を引いて友人とオール宴会。車掌さんも大声を出さなければ見逃してくれました。午前6時のアナウンス開始(夜行列車では11時半くらいから翌朝6時まではアナウンスが休みで停車案内もありません)のときに「皆さん、明けましておめでとうございます」と車掌さんの第一声。今でもいい思い出です。 松本経由で普通列車を乗り継ぐコースは朝5時半に中央線の東小金井を出発します。高尾と松本、糸魚川で乗り換える9時間コース。まだ真っ暗なうちに出発、松本に着くと少し時間があるので駅の周りをぶらぶら。大糸線に乗ると雄大な白馬岳が迎えてくれます。南小谷を過ぎてトンネルを超えると一気にカラーの世界からモノクロの世界。このギャップにびっくりしたもんです。山が水墨画の世界になるのですから。 今では帰省自体することがなくなりましたし、旅行といっても時間のかからない飛行機が主となりました。新幹線や特急の旅もいいのですが、また機会があればこのような貧乏旅をしてみたいな、と妹と弟が帰っていくのを見て思いました。人気blogランキングへ
January 4, 2006
コメント(0)
-
我が母校
昨日、今日と2日連続で箱根駅伝をテレビで見ています。 去年に続き今年も我が母校が厳しい予選会を勝ち抜いて出てきました。 今さっき平塚中継所を通過していきましたが、トップの順天堂大学と12分余り遅れの17位。またひとつ順位を落としていますが、考えてみれば140キロ余り走ってきてたったそれだけの差。やはり選ばれた人達が走っているんだなぁと感じます。 最近の我が母校は六大学野球も優勝から遠ざかっているし、お家芸のラグビーも去年は目も当てられない惨状でした。 せめて新春の箱根路をあと3区でトップに7分以上の差を引き離されず1本のタスキでつないで欲しいと願っています。人気blogランキングへ
January 3, 2006
コメント(0)
-
元旦営業に思うこと
今から10数年前、ダイエー高岡店(現在は既に撤退)が元旦営業を行うということで地元商店連盟が大きく反対運動に出ました。 まだコンビニのように24時間365日というのが一般化してなかった時代の話です。 何でも、正月の一日くらいは仕事を休んで家族親戚縁者と、ということです。 昨日の夜、東京と名古屋から帰ってきている妹と弟、私、家内、子供2人で焼肉のさかいに行ってきました。案の定、若い人でいっぱいでした。 その帰りに寄ったファミレスも若い人でいっぱい。やはり飲食関係は元旦営業で都会から帰ってきている人をもてなす場となっていることを確認しました。 今では元旦に働くというのはそんなに珍しいことではなく、単なる365分の1に過ぎないのでしょうか。 子供の頃の年末年始というと店がやってないので年末に買いだめをするとかあったと思うのですが、それはそれで不便でもなかったような気がします。日持ちのするお節料理は少し飽きがきますが、みんなで同じ料理をつつき合うというのもよかったかもしれません。特に今年のように雪の多い年は移動だけでも時間がかかるのでウチでじっとしてるのもいいのかもしれません。皆で花札をしたのもなつかしい思い出です。 今では市民権を得てしまった元旦営業も、反対運動があった頃を思い出すとなつかしく感じます。人気blogランキングへ
January 2, 2006
コメント(0)
-
頌春
新年明けましておめでとうございます。 今年は戌年。十二支の中では一番人口が少ないそうです。 何を隠そう、私も戌年、年男です。 私は1月生まれなので年が明けるとすぐに年をとってしまいます。 今年は年男ということもあり十何年ぶりかで二年参りに行ってきました。 年が明ける5分前くらいに地元の神社に着いたのですが、午前十二時になると港から船の汽笛が鳴り参拝客の列が動き出しました。 それにしても夜の参拝客が少ない。十数年前は午前二時くらいまで千人くらいの人の列がついていたものでしたが昨日あの時間で百人いたでしょうか。でも並んでいたのが高校生など若い人達ばかりで元気な姿を新年から目にできてよかったです。 今ほど地元の賀詞交換会に行ってきました。市長さんと市議会議長さんも来ておられましたが今日は最近にない快晴。議長さんはその初日の出の朝日を元旦マラソンで浴びて来られたそうです。 いつも元旦は晴れるのですが、今年も雪の多い中晴れてくれました。雪があるととても明るくまぶしい光景になります。すがすがしい年の幕開けとなりました。 戌年はドッグイヤーといわれ変化の早い年と言われますが、地に足つけて頑張っていこうと思います。 皆さんにも幸多き一年でありますように。人気blogランキングへ
January 1, 2006
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1