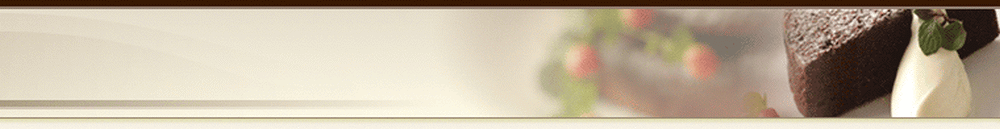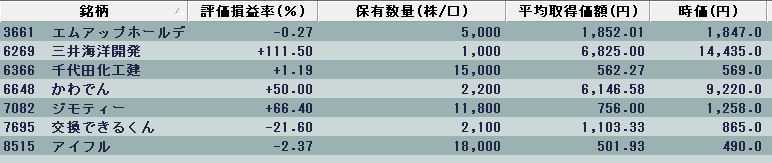2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
確定申告情報その47~無料税務相談
今日で2月も終わり。当初予定にはなかったのですが、先週末に先輩から折り入っての頼みということで税務署の無料税務相談を一日やることになりました。 無料相談には本当にいろんな方が来られます。大半は年金の方なのですが、事業者の方が来られることもあります。 こういった中で毎年無料税務相談が行われている訳ですが、相談に来られる方にいくつかお願いがあります。1.決算の必要のある方は分かるところはできるだけ書いてきて下さい。2.国民健康保険税などの社会保険料については支払った金額がわかる資料をお持ち下さい。3.国民年金の納付証明が今年から必要ですのでお忘れなく!4.自書申告が原則です。私達も書きたくなくて書かない訳ではございませんのでご理解をお願いします。5.多くの納税者の方がお待ちですからあまり長時間を取らないようご配慮下さい。 税金に対していろいろ言いたい方とかも見受けられます。お気持ちはよく分かるのですが、また別の機会にして頂ければと思う方も毎年いらっしゃいます。お待ちの方がいらっしゃらなければいくらでもお付き合いさせていただくのですが、後ろで年金申告のおばあさんがお待ちだとついつい急いでしまいがちになります。 税務署の税務支援は今日が最後。いってきます。人気blogランキングへ
February 28, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その46~医療費控除
よく知られている確定申告の所得控除に医療費控除があります。 雑損控除と医療費控除、寄付金控除は年末調整では受けられない控除なので給与所得者の方も確定申告にて控除されることとなります。 医療費控除で注意すべきことをいくつか掲げてみます。1.その医療費は全て平成17年中に支払ったものかどうか2.診断書の料金など(文書料などと記載されていることが多いです)が控除対象から除かれているかどうか3.健康増進費用が控除対象から除かれているかどうか4.予防接種の料金が控除対象から除かれているかどうか5.親族に対する世話代が控除対象から除かれているかどうか6.かぜ薬なども控除の対象となります。 他にもいろいろあるのですが、対象の範囲など複雑です。これはどうかな?と思われるものについてはタックスアンサーなどで調べてみられることをお勧めします。人気blogランキングへ
February 27, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その45~扶養控除をつける時期
扶養控除、配偶者控除はその年の所得が38万円以下の同一生計親族を対象とします。 では次のような場合、扶養親族や控除対象配偶者になるのでしょうか?1.平成17年12月31日に子供が誕生した場合2.平成17年1月1日に父が死亡した場合(平成17年中の所得はゼロ)3.専業主婦であった妻が平成17年4月29日に死亡した場合4.専業主婦であった妻と平成17年4月29日に離婚した場合5.平成17年12月29日に結婚し、妻となった人の所得がゼロの場合6.平成17年12月3日に里子と養子縁組をしその養子の所得がゼロの場合 扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかはその年の12月31日の現況により判断します。死亡した者については死亡した時の現況により判断します。 よって、上記の6つの例で扶養親族・控除対象配偶者となるのは1,2,3,5,6でならないのは4(12月31日において配偶者ではないから)ということになります。人気blogランキングへ
February 26, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その44~分離課税と源泉分離課税
お客様によく聞かれることです。「定期預金の満期などで利息の欄に『分離課税』いうて書かれとるけど、これちゃ何け?」「利子所得は受け取り利息の20%(所得税15%と住民税5%)を差し引かれて課税関係が終了するんです。確定申告でも取り戻すことができません。」「じゃ、何で『分離課税』いうていうがけ?」「給与所得とか事業所得などはいろんな所得を合算して税率をかけることになっています。これを『総合課税』と言っています。利子などはそれに加えずに単独で税額を計算するから『分離』なんです。」「ふーん、なら、土地とかどうなんがけ?」「土地も総合課税には含めず単独で税率を適用しますから分離課税です。でも利子と違うのは源泉徴収されないので申告で精算するということです。これは株の譲渡なんかも一緒です。」「何やら、複雑なことになっとるがいね。なら、利子も土地も税金の掛け方は一緒のようなもんや?」「決定的な違いは所得にカウントするかしないかです。利子は源泉徴収されて終わりなので申告書には出てきようがありませんが土地は申告書に出てきます。だから同じ金額の所得でも利子なら所得に加算されませんし、土地なら所得に加算されます。」「それちゃ、どっちが有利ながいね?」「当然、所得に加算されない方が有利ですよ。国民健康保険や公営住宅の家賃なども所得が低い方が安いですからね。」「あっちゃー、税金は変わらんでも所得ちゅうもんが変わってくるがいね。同じ分離課税でも源泉されとったら所得にならんから有利やいうことや。」「そうです。例えば年1千万円の利子だけを受け取って生活している人がいるとしましょう。この人、所得はゼロですよ。他の親族の扶養にもなれます。」「何か、変な制度になっとるね・・・。」 国内に住む人の源泉分離課税は利子だけとなってしまいましたが、やはり変な制度だと思います。このあたりが所得税を複雑なものにしているのかもしれません。人気blogランキングへ
February 25, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その43~「事業」って何?
所得税や消費税の申告の手引きなどを見ているとよく「事業」という言葉が出てきます。 所得税ではその収入が「事業的規模」かどうかで取り扱いが違ってくることがあるので不動産所得、事業所得、山林所得では事業的規模のものとそうでないものに区別が要ります(事業所得は全て事業的規模です)。 私も「事業」と聞くとこの所得税でいう事業を連想するので不動産所得、事業所得、山林所得以外の収入分の消費税は課税対象にならないと思っていました。消費税の課税対象の要件の中に「事業者が事業として」というものがあるからです。 しかし、よくよく調べてみると消費税でいう事業とは継続・反復的に行われるものということだそうで、所得税では事業とはされない雑所得なども事業者が継続・反復的に行っていれば課税対象となってくるそうです。 同じ日本語でも税目によって意味がちがってくるということを改めて知る機会となりました。人気blogランキングへ
February 24, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その42~税込み経理と税抜き経理
以前ここで書いた内容ですが、税務相談もたけなわとなったこの時期にもう一度おさらいをしようと思います。 消費税と所得税の関係ですが、税込み経理(全ての取引を消費税込みで経理すること。税抜き経理はその逆。)をしている場合、消費税は必要経費として計上することになります。一方で税抜き経理をしている場合には必要経費という形では現れてきませんが、売上などに消費税が込まれていない分利益が納付する消費税分だけ少なく現されますから結果は原則として税込み経理と同じ数字となります。 さて、この納付すべき消費税について税込み経理をしていると平成17年分の所得計算に必要経費として計上することもできますし、実際の支払いをする平成18年の経費とすることもできます。 平成18年の所得がどうなるか今から知る由もありませんが、税率が17年と同じに納まりそうなら今回の申告消費税は納付した時、つまり平成18年の必要経費とすることをお勧めします。 ご存知のとおり、平成18年分の所得税では定率減税が今の20%から10%に引き下げられます。つまり、8掛けの税金でよかったものが9掛けになるということです。 何を言いたいかというと、必要経費も今は8掛けの効果しかないけど来年は9掛けの効果が出てくるということです。同じ経費でも税額に与える影響は大きいほどいいですよね!? 税抜き経理だとこういうことはできませんが税込み経理ならではの節税(?)の方法だと思っています。人気blogランキングへ
February 23, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その41~公示制度
通例、3月31日までに申告書を提出されたものについては納税額が1千万円を超えていると5月にその申告書を税務署の前に貼り付けられ、新聞にも掲載されることになっています。いわゆる長者番付というものです。 これは高額納税者についてその申告内容が適正であるかどうかを広く地域住民に図るという意味で戦後行われてきました。 しかし、この制度の本来の趣旨から外れ寄付のお願いや営業にその情報を利用したり、はたまた強盗に入るという不逞の輩もいることは事実です。事実、神戸ではこの公示制度で高額納税者の住所を調べて強盗に入り家族が殺害されるといった事件もおきているようです。 個人情報の保護が叫ばれるようになってからこの公示制度がどうやら今年からなくなりそうです。芸能界やスポーツ界、政治家などの一種ランキングのような取り扱いもされてきましたがやはり時代にそぐわなくなったということでしょう。 私も以前、お客様の申告で長者番付に載りたくないということで期限内にある所得を抜いて申告、納付は適正額を納付して頂き4月1日に修正申告をすることによりノーペナルティで公示を免れたこともありました。 そんなことを今年からする必要がなくなりそうだということはいいことだと思っています。人気blogランキングへ
February 22, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その40~還付加算金の申告
所得税や消費税の還付申告をすると還付金とともにその利息として還付加算金が振り込まれてくることがあります。 これは源泉所得税や予定納税、中間申告の還付について、国が預かっていたことになる訳ですから国が国民に利息を支払うという意味合いでついてくるのですが、これはその受領した年分の雑所得になります。 どの税金の分とか考える必要はなく、所得税分であれ、消費税分であれ、還付加算金は全て雑所得です。この分の必要経費はありません。 これは支払い元が国税当局ですから当然、税務署側も分かっています。金額の大小を問わず申告漏れに注意が必要です。人気blogランキングへ
February 21, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その39~災害関連支出
居宅などの生活に必要な財産に災害・盗難などの被害があった場合に雑損控除という制度があります。 雑損控除はその被害により資産の価値が目減りした分と災害の復旧などにかかった金額の合計から計算します。 この復旧などにかかった金額のことを「災害関連支出」と呼んでいます。 この災害関連支出には腑に落ちないところがあります。それは災害がやんだ日から1年以内の支出に限られているところです。 大規模災害が起こった場合、復旧工事などが遅れたり地盤の変化を待ったりすることがあるため1年を超えて支出することが度々あります。しかもその遅れが行政側の予算の都合だったりすることもあります。 こういった支出は災害関連支出の性格は100%帯びているものの、1年以内の支出ではないため雑損控除の対象になってきません。 大規模災害には県や市からの補助などがあると思いますが、何か「使えない制度」になっているような気がしてなりません。人気blogランキングへ
February 20, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その38~住宅借入金等特別控除
居住用の住宅、その敷地を金融機関などの借り入れによって購入した人については10年間の住宅借入金等特別控除が受けられます。 これは給与所得しかない方でも初めてこの適用を受ける年は確定申告をしなければなりません。給与の他に所得がなければ還付申告になると思います。2年目以降は年末調整で受けることができます。 この制度は住宅の借入金残高の○%を所得税から差し引くというものなので借入金がないと控除は受けられません。 また、所得制限もあり、その年分の所得が3千万円を超える年は受けられません。 もし、1年目に所得が3千万円を超えて受けられないとしても確定申告で控除ゼロの申告をしておくと2年目以降、楽になります。人気blogランキングへ
February 19, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その37~税金以外への影響
お客様の確定申告を毎日やっているとその度にいろんな気づきがあります。中でも今日は確定申告の税金以外のところに及ぼす影響です。 お客様のAさんは個人事業者で奥様を青色事業専従者として給与を支払っておられます。奥様はこの給与について年末調整で税金の精算をしておられるのですが、例年通りお子さん2人を奥様の扶養として源泉所得税の還付をされていました。その結果、奥様の税率10%での税額ありとなりました。 翻ってご主人のAさんも締めてみると3人目のお子さんを扶養とし、税率10%で税額ありで予定納税との差額を納付するということになりました。 普通ならここで終わるところですが、今回はあえて奥様につけた2人のお子さんをご主人につけかえて奥様は納付、ご主人は予定納税の還付の申告とするようお勧めしました。 お二人合わせて考えてみると扶養をそのままにしておいても税額は変わりません。こうお勧めした理由は2つ。 一つは予定納税の還付額に還付加算金がつくかもしれないこと(せこい?)。これよりも大きな理由の二つ目は児童手当の受領ができるかもしれないと思ったからです。 私の住む市では児童手当は1人目と2人目は各5千円、3人目以降は一人1万円になります。主たる扶養義務者の所得と扶養人数によってもらえるかどうかが判断されます。 現況届というのがあるので必ずしもご主人に扶養をつけてないともらえないというものではないのですが、税申告において扶養をつけてあれば漏れがない。所得制限内に入ってこれば必ずもらえる手続きがとられます。 税金以外にもこういったところに影響がありますので特にお若い事業者については気を配ることにしています。人気blogランキングへ
February 18, 2006
コメント(7)
-
確定申告情報その36~100円未満切捨て
原則としてほぼ全ての税金は計算の際、税率を掛ける前に1000円未満を切り捨て、納付税額は100円未満の端数を切り捨てることになっています。 しかし、所得税には分離課税を合わせると8つ(でしたっけ?)の課税所得があり、それぞれに税率を掛けて計算するため1000円未満の切捨てはその度に行い税率を掛けます。つまり、1000円未満の切捨ては出てきた課税所得の数だけ行うことになります。 では、100円未満の切捨てはその都度行うのか?という声を確定申告会場で聞いたことがあります(とはいえ、課税所得がいくつもある人はそんなにいらっしゃるものでもないのですが・・・)。 答えは「100円未満の切捨ては1回だけ」ということになります。それぞれの税率をかけて出てきた数字はあくまでそのままとして他の税額と合算、定率減税や源泉所得税を差し引いたところで1回だけ100円未満を切り捨てることになります。 もっとも、消費税の申告書は上と下で100円未満を1回ずつ計2回切り捨てていますが、あれは税目が違うため。上は国税である「消費税」の計算で下は道府県民税である「地方消費税」の計算をしているからそれぞれに100円未満切捨てがあるのです。人気blogランキングへ
February 17, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その35~必要経費になる税金もあります
商売をしていると誠にいろんな税金が課せられてきます。私も開業4年、つくづくそれを実感しています。 さて、これらの税金の中でも必要経費として計算できるものもあります。 一般的なものを並べてみると・・・・(商売用資産の)固定資産税、個人事業税、延納分の利子税、印紙税、消費税(税込み経理をしていれば)、営業車の自動車税など・・・。 逆に考えると必要経費にできない税金は所得税、住民税、延滞税などのペナルティくらいでしょうか。 個人事業税については、税務調査などで追徴が来た場合、その追徴された本税部分は支払った年の必要経費にできるので注意が必要です。人気blogランキングへ
February 16, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その34~予定納税
事業所得や不動産所得など経常的に発生する所得で源泉徴収のないものにかかる所得税が一定額を超えるとその次の年分の所得税の前納め分として7月と11月に前年の3分の1ずつの予定納税をすることになっています。 この一定額というのがいくらかというと15万円以上なのですが、定率減税の影響でこの金額が下がりそうなのです。 今までは単純に15万円以上の年税額があった場合に「今年は夏と秋に予定納税が来ますね」などといっていたのですが、平成18年は定率減税が10%になります。 ですから、今年14万円の納税となった人は来年も同じ所得・所得控除だったとすると定率減税が下がった影響で年税額が15万円以上となってくるのです。 ぱっと計算すると平成17年分の年税額が13万4千円以上の方が予定納税となってくるようです。人気blogランキングへ
February 15, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その33~減価償却費の計算
確定申告期の無料税務相談で不動産所得や事業所得のある人が大体空欄にしてこられるのが減価償却のところです。 減価償却とは、2年以上に渡ってその効果を発揮する10万円以上の資産についてその取得価額を効果の及ぶ期間に配分して経費とすることといえるでしょう。例えば営業用の車両とか建物とか機械などが上げられます。 この減価償却も計算の仕方がいくつかあって、特に届出がない場合個人事業者は定額法(取得価額×0・9×耐用年数に応じた償却率×事業供用月数÷12)で計算することになっています。 無論、今年の税額を少なくしようと思ったら経費を多くすることになりますから減価償却費は多く計上できればその年の税金は安くなります。 そこで青色申告の特典として平成17年に取得、供用した30万円未満のものについてはその年の経費とすることができるようになっています。決算書の減価償却の備考欄に注意書きは必要ですが、平成17年に大きく利益が出た方などにはいい方法だと思います。人気blogランキングへ
February 14, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その32~消費税の申告
平成17年から消費税の免税点が引き下がり、平成15年の課税売上高が1千万円を超えている事業者に申告義務が課されています。 消費税は2種類の税額の計算の仕方があって、原則課税と簡易課税に分かれています。この選択はその課税期間に入る直前までに届け出ることになっており、平成17年、18年分については今から選択することはできません。 また、簡易課税は一旦選択したら2年間は強制適用になりますので注意が必要です。 消費税の申告書は所得税の申告書とは別に送付されてきていると思いますが、原則課税の申告書と簡易課税の申告書は違うのでどちらが送られてきているか確認してみるとよいでしょう。申告書の右上に簡易課税の「簡」を○で囲んであるのが簡易課税用、ないのが原則課税用です。 消費税の申告書や付表は所得税と違い2枚しかありません。申告書は複写になっていますが、これは控え用で提出することはありません。 手計算してみると分かりますが、全て税込み価格から計算することになっています。しかも国税部分(4%)と道府県民税部分(1%)を分けて計算することになっていますのでちょっと分かりづらいかもしれません。 消費税は単純な税金なのに制度が複雑で申告書もかきづらいところがあるのでこの免税点の引き下げを期に消費税の改善要望の声が大きくなればいいと思っています。人気blogランキングへ
February 13, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その31~申告内容を間違えた場合
今年はまだ確定申告書を出しておりませんが、毎年還付申告になるので1月中に出しております。 確定申告の際間違えて計算した場合には申告期限内であれば「訂正申告」として同じ様式の確定申告書に記入・押印の上、上部に「訂正申告」と記載して提出します。申告書は後から提出したものが優先して取り扱われることになっています。 申告期限が過ぎてしまうと、対応は2種類に分かれます。間違えた申告を訂正すると税額が多くなる場合と少なくなる場合です。 多くなる(追徴)場合には「修正申告」として第5表をつけて提出し速やかに不足額を納付します。あとから延滞税がかかってくることがあります。 少なくなる場合には「更正の請求」をします。これは更正の請求書というのがあってこれに計算資料などを添付して提出します。これは本来の確定申告の申告期限から1年以内に限り認められていますので平成16年分の確定申告が多く納めすぎたという場合、今年の3月15日までに請求することが必要です。 なお、特別償却や税額控除など「訂正申告」では盛り込むことができても「更正の請求」では使えないというものもありますので注意が必要です。人気blogランキングへ
February 12, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その30~株式譲渡の繰越損失
インターネット取引が牽引する空前の個人投資ブーム。しかし株式で損失を出している方も少なからずいらっしゃると思います。 上場株式等については譲渡損失を3年間繰り越すことが認められています。つまり平成17年に発生した損失と平成18年、19年、20年で発生した譲渡益を相殺することができるというものです。 この譲渡損失は他の所得と相殺することはできませんが、株の取引を続けていく方には是非繰越の制度を利用して頂きたいと思います。 これは特定口座でも一般口座でも上場株式等であれば繰越OK。ただし確定申告が必要です。 確定申告においては第1表、第2表、第3表と株式譲渡の付表(黄色い紙)を提出することになります。また、一度損失の申告をして次の年に利益が出て相殺、さらに次の年に繰り越す損失が残るという場合でも確定申告しないとその損失は次年度以降に繰り越すことができなくなるため注意が必要です。人気blogランキングへ
February 11, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その29~みなし譲渡にご注意
先日、税務署からお客様のところに届いた確定申告書の用紙を確認したところ、第3表と土地・建物の譲渡の明細書が入っていました。 普通は第1表と第2表(AタイプとBタイプのいずれか)が送られてくるのですが、土地や建物の譲渡や株式譲渡の繰越損失があったりすると第3表と所定の明細書が送られてきます。 そのお客様に「土地の譲渡がありましたか?」と確認すると「いいや、そんなことしてないよ。」との返事。 数十分してからそのお客様から電話があり「そういえば神社の境内地を寄付したな・・・。でもお金はもらってないよ。」 この件は今から調べていかなければならないのですが、法人に土地や建物などを寄付・贈与するとその時の時価での譲渡があったものとみなされることになっています。お金をもらってないところに課税されてしまうのです。 今回の件についてもこの神社が宗教法人だとしたら時価によるみなし譲渡課税が行われます。 なぜお金をもらってないのに課税されるのかということについては長くなるので省略しますが、なんともやりきれない思いのする規定です。人気blogランキングへ
February 10, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その28~電子申告
確定申告の仕方には従来の紙の申告書で提出するやり方と電子申告で申告データをインターネット経由で送信するやり方があります。 紙の申告書は申告自体には何の準備も要りません(強いていえばハンコを買うことくらいでしょうか)が電子申告にはいくつか準備するものがあります。 まずパソコン。それに電子世界でのハンコの代わりとなる公的個人認証(市役所で発行している住基カードが多いと思います)、それを読み取るカードリーダライタ、電子申告ソフト、こういったものが必要になります。 パソコンはなるべく新しいものの方がトラブルが少ないような気がします。公的個人認証は私の住んでる高岡市では1,000円でとれます。全国似たような金額と思います。この際、2つの暗証番号を指定することになりますが忘れないようにメモしてくるとよいでしょう。 リーダライタはNTTやサクサというところが出しております。1万円前後でしょうか。電子申告ソフトは税務署に「電子申告利用開始届出書」を提出すると2週間後位に郵送されてきます。 このソフトで申告データを作成して公的個人認証で電子署名した後に送信すれば自宅に居ながらにして申告完了です。ただし源泉徴収票や保険料控除の証明書などの添付書類は別途郵送することになります。 なお、国税庁のHPで申告書を自動作成するコーナーがありますがあれは電子申告ではありませんのであしからず。人気blogランキングへ
February 9, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その27~同一生計に関する控除
確定申告もたけなわの時期を迎えつつありますが、所得控除について感じることをいくつか。 所得控除には同一生計の人に関するものがいくつかあります。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(生命保険料控除と損害保険料控除もありますが難しくなるので割愛します)。 これらに共通するのは「同一生計の人であれば誰につけてもよい控除」ということが言えます(給与や年金から控除される社会保険料は除きます)。 ここがミソ。確定申告で事情により事業主の所得が赤字になったとします。すると「ああ、所得税がゼロか・・・」で終わる方が多いかもしれませんが、次の2つに気をつけてみると意外と戻る金額が出てくるものです。1.この事業主に付けようとしていた所得控除で、誰に付けてもいいものがあればその事業主ではなく奥さんや他の同一生計の方に付けてその奥さん達の確定申告を行うことにより源泉所得税の還付を受けられませんか?2.この事業主自身が扶養親族になりますからこの事業主を奥さんや他の同一生計の方につけてその奥さん達の確定申告を行うことにより源泉所得税の還付を受けられませんか? 「所得税ゼロ」で終わらない、さらに還付を受けることも一家全体で考えてみるとよくあるのではないでしょうか。 事業主さんの所得が38万円を超えていても76万円未満であれば配偶者特別控除が奥さんに付けられるのでこれも見落としがちですが、注意するといいでしょう。人気blogランキングへ
February 8, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その26~所得税の計算の仕組み
所得税は複雑で分からないという方がいらっしゃいます。一方でそんなに難しいものでもないので自分で申告書を書くという方もいらっしゃいます。 両者の違いは何なのでしょうか? 所得税の計算の仕組みをひもといてみます。 所得税の計算は大きく5段階に分かれています。1.各種所得(10個の所得があります)の金額の計算 2.課税標準額の計算 3.所得控除額の計算 4.課税所得金額の計算 5.納付税額の計算 所得税が難しいか否かの鍵を握るのはやはり1.の各種所得の数がいくつあるかでしょう。 これが一つないし二つくらいで計算も単純な給与所得とか年金の所得だけだとそんなに難しく感じません。 一方で土地や建物の譲渡所得があったり株式譲渡など複雑に入り組んでいるものがあったりするととたんに申告書の枚数も増えて分からなくなったりします。 10種類も所得の数がありそれぞれに所得の計算の仕方がある訳ですからやはり難しいものなのでしょう。 因みに私の平成17年は利子所得を含め6種類の所得がありました。人気blogランキングへ
February 7, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その25~個人事業税
個人事業の所得にかかる税金の代表格は所得税ですが、他にも住民税と個人事業税があります。 中でも個人事業税は事業的規模の不動産所得と事業所得(医業など一定の事業は除かれます)にのみ課される道府県民税で税率は奇しくも消費税と同じ5%。所得税や住民税と違い、課された年分の必要経費になるのも特徴です。 この計算方法は誠に簡単で、青色申告特別控除を差し引く前の事業的規模不動産所得の金額と事業所得の金額を足します。そこから290万円(事業主控除といいます)を差し引いたものに5%を掛けて100円未満の端数を切り捨てればその翌年にかかってくる事業税額になります。 ただし年の中途で開廃業した場合、所得から差し引く290万円は月数按分されますので注意が必要です。この場合には所得税の確定申告書の第2表の右下の事業税に関する事項のところに「開廃業・月日」とある欄に忘れずに記入します。人気blogランキングへ
February 6, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その24~所得税と住民税
個人の所得にかかる税金の代表格が所得税ですが、これと並んで地方税である住民税(市町村・道府県の税金の総称)があります。 以前、所得税の申告の目的は2つあるとここで書かせて頂きました。つまり、「税額の計算」と「所得の計算」です。 このうち「所得の計算」については所得税と住民税は全く同じです。違うのは所得控除と税額控除。 所得控除でも社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除のように所得税と住民税で取り扱いが同じものもありますがこれは少数派。住民税の所得控除は所得税より控除額が少ないのが普通で所得税では38万円の基礎控除が住民税では33万円になるなど課税所得が住民税の方が大きく出る仕組みになっています。 もう一つは税額控除。こちらは所得税にあっても住民税にないというのが多いような気がします。例えば住宅借入金等特別控除。これがあると所得税がかからない人は多いですが住民税にはこの控除がないので嫌に住民税が大きく感じてらっしゃる方も多いと思います。 ただし、税率は所得税より住民税の方が小さく設定されていますから住宅借入金等特別控除などの税額控除がなければ所得税より住民税の方が小さくなるのが一般的です。 所得税の確定申告書はそれぞれの表が複写になっていますが2枚目が住民税の申告として住所地の市町村に回されることになっています。市町村はこれを基に市町村民税と道府県民税を計算して一括して納税者に納税通知を行うことになります。人気blogランキングへ
February 5, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その23~農業の収支計算
平成17年分の所得税から全ての都道府県において農業所得は収支計算により所得を申告することになっています。 これまでは小規模農家については市町村の方から「農業所得のお知らせ」ということで標準的な収穫高を見積もり概算経費を差し引いたものを郵送しこれを農業所得として申告していました。 消費税の免税点引き下げということもあるのだと思うのですが、「農業所得のお知らせ」では所得金額がぽつんと書いてあるだけで収入が分かりませんからやはり本来あるべき姿で申告しようということになったのだと思います。 さて、平成17年分の所得税の農業所得を収支計算でやっていると殆どのお客さんが「農業所得ちゃ、こんなに少ないがけ?」とか「農業所得ちゃ、マイナスなったけど損して仕事しとんがけ?」とかおっしゃいます。 これは私が予想したとおり従来の「農業所得のお知らせ」は標準的な収穫高で計算されているため割高の所得金額が通知されてきていたのです。 農業所得は小規模農家の方の中にはマイナスになる人も少なくないと思います。これで農業経営にやる気をなくす人が出てこなければいいのですが・・・。人気blogランキングへ
February 4, 2006
コメント(2)
-
確定申告情報その22~間違ってました。
いきなりですが、申し訳ありません。 先日配当所得の申告の有利不利を書いておりましたが、一部間違いがあることに気づきました。 どこが違うかというと所得税の税率10%の方の上場株式等です。 結果からいうと税率10%の方は税額がある、ないにかかわらず申告した方がトクになります。 一旦、税額が配当額の10%出てきますが配当控除の10%で消されるため源泉所得税の先納めになっている分だけ税額が少なくなるということになります。 参考にされた方には大変申し訳ありませんが、ここに訂正してお詫び申し上げます。人気blogランキングへ
February 3, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その21~振替納税
今日は納税の話を。 所得税と個人事業者の消費税には期限内申告分の納税について振替納税という制度があります。 これは期限内に確定申告した分について本来所得税なら3月15日、消費税なら3月31日までに現金納付すべきところそれぞれ4月中旬~下旬頃に本人指定の口座から自動振替になるというものです。 振替日は国税庁と日銀の話し合いによって決められるので毎年変わるのですが、今年は所得税が4月20日、消費税が4月27日です。 法定の納付期限より1ヶ月くらい遅い訳ですが延滞税などはかかりません。ただし残高不足などで引き落としできなかった場合には3月の法定期限に遡って延滞税の計算が行われます。 この振替納税は所得税の期限内申告の本税分、延納分、予定納税分と消費税の期限内申告の本税分と中間申告が振替の対象となります。 この振替納税は申告期限のその日に銀行口座から引き落とすということがシステム上不可能なので時間的メリットがある訳ですが、振替日の案内などは来ませんので注意が必要です。人気blogランキングへ
February 2, 2006
コメント(0)
-
確定申告情報その20~消費税はいつの経費か?
平成17年分の申告から消費税の免税点が1千万円に引き下がり、納税義務者が大幅に増加することになりました。 さて、ここで納付することになる消費税はいつの必要経費とすればいいのでしょうか。 所得の計算方法に消費税込みで売上げや経費を計算する方法(税込み経理といいます)と消費税抜きで計算する方法(税抜き経理といいます)があります。 まず、税抜き経理をしている場合には必然的にその年の必要経費となるようになっています。つまり、平成18年3月に納める消費税は平成17年分の経費となります。 また、税込み経理をしている場合には平成18年3月に納める消費税は平成17年(発生した年)の経費とすることも平成18年(納めた年)の経費とすることもできます。 何か変な話のように思いますが、このような決まりになっています。人気blogランキングへ
February 1, 2006
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1