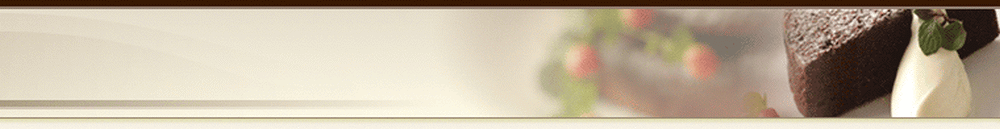どこかで書いたような気がするが、前回もおさらいだったので今回も(もし、以前どこかで書いていれば)おさらいということで少し内容を加えたものを書くこととする。
サミットなどを見ているとよく分かるが、日本という国は国際舞台での発言力が比較的弱いとされる。それは先の大戦で負けたから・・・というのもあるが、イタリアやドイツはどうなのだろうと考えた場合、それだけではないような気がする。今や世界の一部となっている「日米関係」の主従関係のうち「従」の国だから「主」を差し置いて大きな発言をすることができないから?それもあるだろう。
先日、面白い本を読んだ。日本人というものは世界でもかなり特殊な価値観をもっているというのだ。それが世界の常識とはかけ離れているからなかなか外国人とは話がかみ合わないのだとか。その特殊な価値観というもののうち、私が特に興味を持った部分は2つあって、いずれも今日の日本社会・日本人を考えるとなるほど、と膝を打つものであった。
まず一つは国境である。世界地図を見るとよく分かるが、普通、国境というのは陸地にある。それが川の上だったり分水嶺(つまり、山)であったりする訳であるが、これらに共通しているのは「人為的にラインを引いたこと」と「人が作ったラインだから何かのもつれで移動することがあり得る(=国境が侵害される)」ということだ。だから洋の東西を問わずどの国も軍隊が国境を必死に守っている。しかし、我が国はどうか。我が国は言わずと知れた島国だ。国土を自分達の力で勝ち取ったものでは決してない(私が唱える、日本人の大陸からの移動説の後のこととして)。その後の国境も19世紀頃からの戦争により取ったり取られたりした島々は別として、古来より本土は侵されていない。つまり、侵略の危機という目に遭ったこともほとんどない。
ということは、日本人の価値観による「国」というものと世界の標準的な価値観による「国」というものとの間には大きな隔たりがあるのではないか。日本人のそれは「神から与えられしもの」で世界のそれは「自分達の力で一度は勝ち取った、又は創り上げたという歴史のあるもの」。この差は大きい。金満な家庭に育った子が考える「お金」というものと、今日明日食うにも困る貧乏な家庭に育った子が考える「お金」というものが違うように、日本人は安定した国土があることを当然と信じて疑わず、世界中の国々についても同様だと思っているだろう。このような国についての価値観が異なる人たちが例えば世界平和について協議したとき、果たして本当に実のある話合いができるのだろうか?
もう一つは意外であるが、「家畜の肉を食べるかどうか」だそうだ。我が国に獣の肉を食してきた歴史は殆どない。歴代の為政者がそれを禁じてきたからだ。我が国は粗食を基本とし、穀物や野菜などの植物と魚、せいぜい肉は鳥しか食する機会がなかったといえる。余談ではあるが、ウサギを一匹、二匹・・・ではなく一羽、二羽・・・と数えるのはウサギの肉を食べると獣の肉を食したということで罰せられるため、「これはウサギではなく、鳥の肉でございます」とごまかすために鳥と同じ単位で数えるようになったとか・・・。実際、ウサギと鳥の肉は脂分が少なく白身なので似ていると聞いたことがある。さて、これが民族の価値観にどう影響したのか。
ちょっと宗教を持ち出して恐縮ではあるが、キリスト教の聖書に「さまよえる子羊たちよ・・・」という一節があるのはよく知られているところだと思う。ここでいう「子羊たち」というのは一般民衆というか、今現世に生きている人間のことを指しているのは容易に想像がつくが、我々日本人には今ひとつピンとこない表現である。なぜか。日本人は羊を飼いならす習慣がないから。
世界の大部分の国々では羊を家畜にしているそうだ。羊は毛が洋服になり乳と肉は食用になる。大変飼いならしやすくおとなしいので長年人間とともに暮らしてきた。さて、この「飼いならしやすい」ということであるが、どうしてかというと「群れのリーダーさえ手下にしてしまえばあとのその他大勢はそれについてくるから」。アルプスの少女ハイジなどを見ているとよく分かるが、年端もいかないペーター少年(おそらく小学校低学年~中学年くらい)の家での仕事は羊の群れを操り草を食べさせたり小屋に誘導したりすることである。何故年端もいかない少年に何百匹もの羊を操ることができるのかというと、リーダーをてなづけてしまえばその他大勢はそのリーダーの後を何も考えずに追うからだ。「さまよえる子羊」というのは人間をこのことに例えているのだ。
しかも、飼い主は最後はその羊(全部ではないにせよ)を食ってしまう。草や魚などと違い、四本足で歩き人間と同じく毛で覆われた動物、しかも毎日行動をともにした半ば家族ともいえる家畜を最後は殺して自分の腹に収めてしまう。この感覚は我が国では養豚業者や肉牛を育てる業者を除いては今でも我々には想像だにできないことである。この羊の群れを国家、それぞれの羊を国民と考えたとき、「人間というもの」に対する価値観が異なったものとなる。国益をかけて複数の国家間で揉め事があったとき、発言力の強い国家が他の国家に不利益を与え、これでもかとばかりの制裁を行うことがあるが、我々からすると「何もそこまでしなくても・・・」と思うのであるが、昨日まで家族同然だった家畜を今日は殺して食ってしまう世界の常識ではそういったこともありなのだろう。我々はこういう意味でも違った価値観を持っている。そして、外のことや世界の常識を知らない。
かつてアインシュタインが来日したとき、我が国を「一つの由緒ある家系に守られた神の国」と評したらしい。彼も祖国ドイツを追われ、人種のるつぼといわれるアメリカで生涯を過ごすこととなった運命を持っていたため、このような国をうらやましく思ったのであろう。帰るべき田舎がない人が田舎がある人をうらやむのに少し似ている。私も我が国は歴史的に「恵まれた国」だと考える。神から国土を与えられ、さしたる侵略の危機も数度しかなく、侵略された歴史がない。資源は乏しいかもしれないが、ないならないで節約する精神を身につけ不平不満は言わない。何といっても世界標準(と私が勝手に思っている)羊のような殺伐とした価値観がない。このような、いい意味で一種独特の環境下にあるのが我が国だといえるだろう。
さて、いつもの「お上について考える」のコーナーとなるが、このような国を支配してきたお上が恐れることは何だろうか?
国土は神から与えられ、常に変わらぬ状態で「ある」のが当たり前とお上も下々も思っている。さらに侵略者もそうそういないとする。そういう状況にあってお上が恐れるものは「他国からの異なる価値観の人が領土に入ってくること」であろう。これは今でもそうだと思う。
お上に属する人の境遇を考えてみる。私の住む富山県では「お上」になるルートはごく、限られていておおよそ次の通りである。1.御三家プラス2と言われるTY高校、TC高校、TA高校、UO高校、TN高校のいずれかを卒業する 2.東京大学(文科1類⇒法学部)に入学する 3.国家1種か外交員試験に合格する 4.入省式で大臣のお言葉を聞いてその後「大過なく」過ごす こんなところであろう。
ここで強調したいのは、「お上」の人となるには上記のいずれをも突破しなければならない(もちろん東京大学OB以外にもたくさんいるが、いずれも難関大学)ということだ。つまり、1~4全てをパスする必要があり、そこから外れた時点で「落ちこぼれ」となるということだ。「お上」にとって「お上」になれなかった人は全て下々の者であり、お上の仲間ではない。ゆえにお上は必ず強いエリート意識を持っている。
かく言う私は一応、1.は該当したのであるが、そこでこのルートからは外れてしまった。頭が悪いのだから仕方がない。お上にはなれない人間であったということだ。しかし、私も高校生のときはいわゆる「御三家」と言われる進学校であったこともあり、勉強にそれなりに必死だったからはっきり言うとエリート意識が当時はあった。他の高校生とは違う、選ばれた人達なんだと恐らく皆そう思っていたと思う。
私は2.には進むことができなかったためエリート意識というのは社会人になって割とすぐにギャフンと言わせられたこともありなくなっていったが、そのまま2.に進んでいたらどうたるのか。おそらく、私の高校時と同じように周りの連中は皆仲間兼ライバルだろう。そして、自分達以外の人は下に見えることだろう。すなわち、ずっとエリート意識を持ったまま自分との戦いに明け暮れることとなる。こういう法律を作ったら国民がどうなるかではなく、自分の出世がどうなるかとか、自分の省益がどうなるかとかしか考えられなくなるのではないか。つまり、社会人になってもずっと学生の状況のままだ。
この国ではエリートは強い。下々がそう思っているからだ。こう考えると、30代の某〇〇省の職員がホテルに連泊し、100万円近くの宿泊料金を払わないという事件が起こったのも何となく分かる。彼らの意識の中では先ほどの1.~4.の全てをパスした人が偉いのであり、パスできなかった人とは違う。ゆえに偉い人は何をしてもいいから金は払わないと。
また、お上は国会議員より偉い。国会議員は下々の者の代表であり、選挙に落ちればただの人だし、何といっても1.~4.を全てパスすることができなかった「落ちこぼれ」だ。国民の代表という都合のいい立場を逆利用してお上が自分達に一方的に都合のいい法案を作って自民党の議員(=下々の者)に言い訳をさせ、何か悪いことがあっても罰せられるのは国会議員であり、お上の自分達は顔すらさらすことがない。「くやしかったら1.~4.を全てパスしてお上になればよかったんじゃない」これがお上の本音であろう。
ちょっと余談が長くなったが、お上が恐れるものという話。下々の多くはあまり海外に出ることはない。旅行に行くことはあっても諸外国の政治やものの駆け引きという場面に出会うことはまずない。しかし、外務省に限らずキャリアと呼ばれるお上は留学や海外出張により外の世界を知っている。これがまたエリート意識を強くさせるのであるが、せまい島国で仲良く暮らしている国民を支配するのは「我が国で起こっていることは世界の常識」とばかりにお山の大将を気取っていれば「大過なく」過ごすことができる。お上は予想外の変化が起きて自分の立場が危うくなるのをとても恐れるのでこの島国がずっと今の状態を維持し続けてくれることが彼らの願いである。しかし、そこに外の世界を知る人が入ってきたらどうなるか。その人達がお上自身の立場を危うくさせる存在となる可能性がある。だから外人とか帰国子女を厄介もの扱いしたくなるのだろう。
留学生や帰国子女は大学の入学に際して特別枠があるのはご承知の通りだと思う。それは日本の(無駄に厳しい)教育を受けられなかった人にも大学で学ぶ機会を与えようということだと思うが、本音は、「お上の立場を危うくする可能性のある存在には先に恩を与えておいても損はないだろう」というところではないだろうか。だって、この国では「疑問に思うこと」はお上がよしとしないことだから何かにつけ疑問に思ううるさい人達がギャーギャー騒ぎ出したらお上も支配がしにくくなるでしょ?そして彼らは「お上」が世界標準では一番偉いものとされていないということを知っている。
私が勝手に思うには、我が国はお上神話があり官僚支配の国である。しかし、このお上の本当の上層部は今でも学生と同じ競争社会を生きており、それが必ずしも国民のためとはなっていない部分がある。何といってもこの人たちの舵取りが間違えたとき、誰もその間違いを正すことができないシステムとなっている。このお山の大将を気取り続けたい人達も間違いはあるのだからそれを自覚させ、優しく導いてやる組織が必要だ。それが我々の代表である国会議員ではないのか。
カレンダー
 New!
保険の異端児・オサメさん
New!
保険の異端児・オサメさん『今時の勉強方法』 所税仲間さん
キャッシュフロー 社… 公認会計士天野隆さん
10年後の自分に向け… taka-maruさん
輝く私であるために にゃこ姫さん
コメント新着