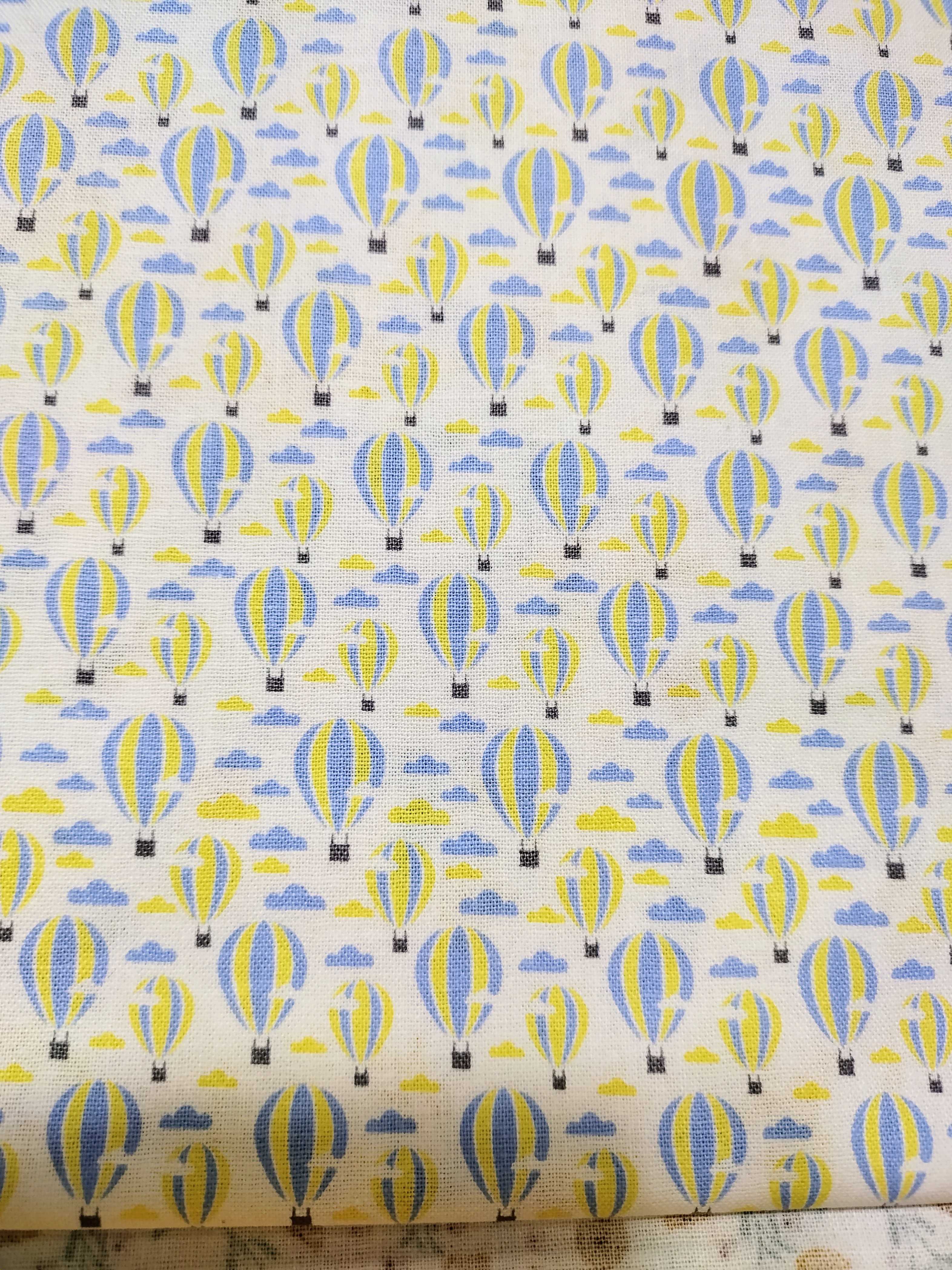特に体癖の説明や、頚椎〜胸椎〜腰椎〜仙骨までと、骨盤・骨盤底部の説明は、実際の骨格標本でも見ながら読まないと分からないと思う。
だけど、とても興味が湧いて仕方ないので、何度も繰り返し読んでいる。
今日は、自分の体癖は11種の過敏型タイプなのではないか?と気付いたことを書き記す。
まず、体癖とは、
『野口晴哉さんは、身体の基本的な緊張−弛緩の偏り=エネルギーの集中の偏りの型を整理して、開閉(9・10種体癖)、左右(3・4種体癖)、前後(5・6種体癖)、上下(1・2種体癖)、ねじれ(7・8種体癖)という運動傾向、身体構造の要素を基にして分類し、「体癖」と呼んだ。さらにそれぞれのタイプの中で、エネルギーの発動が内発的か、外発的かによって、エネルギーの発動が自主的・内発的な場合を奇数系(1・3・5・7・9種)、エネルギーがこもりやすく、外的条件下を契機として発散する場合を偶数系(2・4・6・8・10種)に分けている。またそれ以外に身体の反応全体の傾向として、過敏(11種)と遅鈍(12種)傾向を付け加えている。』
整体。共鳴から始まる/片山洋次郎/ちくま文庫より
本書を読まないとよく分からないと思うので、詳しく知りたい人には購読をお勧めする。
私の場合、自分が何種なのか色々当てはめて考えてみたところ、右脳型の2種、消化器型の4種、呼吸器型の6種、泌尿器型の8種、骨盤型の10種になんとなくそういう要素はあるけど、どれもなんか違う人のことのような…という感じで、どれも時と場合によってその型に当てはまる気もするなぁという感じだった。
それで、片山さんの本を何気なく思い出していたら、あれ?もしかして私って11種の過敏型に近いことやってない?と思い出したのだった。
例えば、
・人から道を聞かれやすいが地図の説明が苦手
・職場で、他の人は言われてないのに、自分は人から色々注文を言われやすい(あけすけに物を言われやすい)
・駅などで前の人から距離を自然と空けている
・美術館が好きなのに絵を観るのがくたびれるので行くのに気合いが要る
・好きな相手と一緒に住むよりも、自分だけで過ごせる空間が欲しい、離れて暮らすほうが楽
・人と会うスケジュールがとにかく苦手。緊張したりして止めたくなることが多い
・イベントに行く前は億劫になるが、行って帰った後のほうが良い記憶がまとまって思い出されてくる
・考えがころころ変わりやすい
・執着が少なく、遠い未来のことを決めにくく考えるのも苦手
・人から言い寄られやすく、自分の思考に入られやすく、混ざってくるので断れない。だから人が集まる場所には行きたくないことが多い
・自分で決められないことが多く、人に決めてもらうほうが多い
・同席している人が、気づいたら無防備にイビキをかいて寝ていることがよくある
・同年代よりも歳が離れた人たちのほうが緊張せず接しやすい
・子供や幼児から仲間?のように接される、ちゃん付けして呼ばれたり、初対面なのにすぐ打ち解けられる、泣かれることがない
・幼いときから時折、教師や身近な人から当てつけのようなキツい言い方をされたり、いじめられたり、のけものキャラに貶められたり、勝手なレッテルを貼られやすい。その都度、それって私のせい?私に何かを投影してるんじゃない?と客観的になっている。
・一生懸命言っても相手に伝わらないのに、後々になって相手から自分の思いのように聞くことがある。
・様々な場面で、部屋や広場などにずっと居たのに気付かれないことがある。気付かれたとき、「居たの?!何してるの?!」と驚かれる
などなど
つい最近まで、こういうことが多かったことを思い出した。
そして、それでは生きづらいと知り、生き方を変えよう、つまり「断る」ことを覚えよう、と思い至って、「自分で決め、決めたことを取り敢えず一つずつでいいから小さくても実行していく」ということを実行していた途上だったのだ。
だけど、片山さんは本書のなかでこう書いていた。
『過敏体癖の発見、共鳴性の高い人
共鳴力の高い人たちというのがある。
“自己”が希薄で「存在」を照らすような鏡のような存在であり、無欲で透明性が高く、存在感は薄い。別に何の標識を持つわけではないので、誰にも存在価値を認められない場合も多く、気的に果たしている役割が大きいのに、それは目に見えないので、無理解にさらされやすい。そういう人たちを気的過敏(共鳴)体癖と呼んでいるが、誰でも程度の差はあるが、そういう傾向は持っている。ただ、自己の“存在感”を重視する近代社会にあっては、そういう傾向は押し殺されてきたといってよいわけで、そういう傾向を“価値”として認めにくいので、自己の中にそれが見えない人もいるし、認めたがらない人もいる。私にとっては過敏体癖の発見は“救い”だった。一つは自分の中にもそういう傾向を発見して、
多くの自分の欠陥だと思っていたことが、どうでもいいことになったこと、もう一つは、「個の自立」という自分にとっての強迫が少なくなったということである。』
まさに!
まさに私もそう感じたのだ。
片山さんのこの気持ちをなぞるように、私も彼の思いに共鳴した。その後、人と集団で過ごすときに何気なく「自然体」で居られる自分に気が付き、気持ちが楽だったのだ。
私の疑問としては、私の体癖の身体と思考のタイプは偶数系に多く該当する気がしたので、11種というのは奇数だから、それ(過敏体質)は思い過ごしなのかな?ということだ。
ま、どうであれ、私に必要なのは身体が楽になれたら気持ちも楽に過ごせると留意して、日々を過ごすことなので、体癖の何種かに自分を無理に当てはめるのに労を費やすことを目的にしたくない。
私は気持ちよく過ごせたらそれでいいのだ。
-
片山洋次郎さんの本 2025.10.07