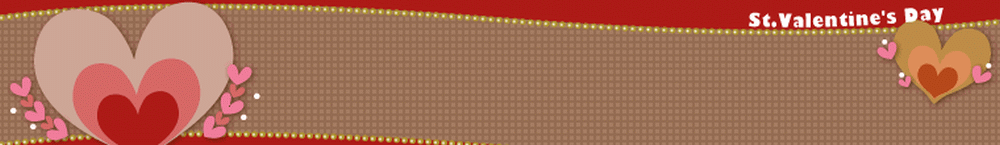2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年10月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
自分らしい色彩
自分らしい色彩マイホームを買ってから、とても気になっていたのは、デザインのことだ。デザイナーに頼まないで、今回は自分でデザインをして、内装業者に内装工事をしてもらった。デザインすることなんて、初めてだから、大丈夫かなぁ~てまったく自信がなかった。最初のチャレンジは壁だった。ペンキを塗るのか、壁紙を張るのか、どちらのほうがどのような部屋に似合うのかという問題だ。また、色の相性も視野に入れなければならないことだ。せっかくのマイホームだから、自分らしい色を大胆に使ってみよう!って思って、姉とわたしは変な色合い(いろあい)を決めた。リビングは抹茶のような緑で、天井はライム(lime)の薄い黄色。キチンは黄身のような色。また、開放感が広がるように、ひとつの部屋のリビングに向かう壁を取り除いて、細い木が格子に組まれていてそれに白いガラスを張ったもので、左右に引いて開けたり閉めたりできる引き戸を仕切りにした。この部屋の壁はオレンジにする。寝室のほうは、壁は明るいピンクの壁紙で、天井は紫のペンキだ。結果は親戚や友たちに「派手すぎじゃないか、やはり間違いないのは白!」と言われた。ペンキ業者も「けばけばしくすると、しつこく感じさせますよ。もう一度考えてください」と言っていた。「家を面白くできれば、いいじゃないか」とずっと思っていたわたしは、周りの人たちの意見を聞いた後、ちょっと不安になった。迷っていた。「白はきれいだけど、活気のある色をつけると、気持ちを生き生きとさせられるようになるじゃないか」と自分に言う。「部屋の色を変えると、そこに住んでいる人の様子や性格まですっかり変わってしまう」という話もある。台湾人の知人たちの家を欧米の友たちの家と比べると、面白い違いに気づいた。台湾人の知人たちのほとんどは薄い色を使い勝ちだが、外国人の友たちは、鮮やかな色づけが好きなようだ。ヨーロッパに住んでいた際に、常にヨーロッパ人の家や博物館を訪ねに行った。けばけばしい壁紙や鮮やかなペンキを使う人は少なくない。大胆だけど、和やかさや優しさを伝えるという印象も残っている。ヨーロッパ人はカラーにセンスがすばらしいなぁと感動させられたわたしは、「自分の家があったら、自分らしさを表現できる色をつけたい」と時々自分に言っていた。個性を大切にする雰囲気が溢れるフランスで暮らすうちに、芸術の鑑賞力も変わるようになる。さらに時々旅に出るから、知らず知らずのうちに、わたしはカラーセンスも変わるかも。何気なく色をつけると、何気なく自分らしさが描けるたどろうか。色彩そのものは人間に影響を与えるものだ。心地とか、情長とか、色によって、効果もそれぞれ。または、色彩も様々な感情が表現でき、物事を連想させることがあるという話もある。というわけで、色合いの選択を通して、人の人柄, 個性や本心が見抜けるかも。「きっと恐ろしい感じになるだろう」!と母に言われたのに、結果はやはり自分の望みどおりに、家を色づけた。やっと出来上がったね。胸がどきどきしていた。ドアを開けた瞬間に、びっくりした。鮮やかだけど、意外に柔かいバランスが作られた!一言でいうと、Sandyの味がいっぱい!Sandyの味とは?下記の色に対する一般的なイメージを参考すると、Sandyの味とはどんな味なのか分かるようになる。(笑)白 善(主にキリスト教圏)、雪、無、清潔、純粹、無罪 など 黒 悪(主にキリスト教圏)、死、男、武勇、汚濁、夜、有罪 など 褐(茶) 土、豊穣、糞 など 赤(赤) 血、生、火、力、女、情熱、危険、熱暑 など 橙 温暖、快活 など 黄 太陽、穀類、金、注意、臆病、色欲(中国) など 緑 植物、自然、安全、幼稚、嫉妬(アメリカ)など 青 水、冷静、知性、憂鬱、寒冷 など 紫 王位、高貴(中国)、貴重 など
2006.10.20
-
脳死者の生きがいとは
日本には、「本人が拒否していない限り、家族の同意により脳死判定と臓器提供ができる」とする臓器移植法改正案にほぼ合意したという報道を読んだ。脳死とは、脳波がとまり、人工呼吸によって心臓だけが動いている状態を呼ぶ。患者に意識はなく、体中に器具を取り付けられ、ただベッドに横たわっているだけだ。植物人間と呼ばれる状態で、身内に大きな負担をかけているばかりでなく、社会全体にとって、大変な重荷になっているかもしれない。そうな状態になってしまうのは患者側から見るときっと悲惨な運命に決まっている。何もできるという切ない気持ちや自分の人生を決められないという無力感を持って、日々を送っている。可哀相ではないだろうか。本来、法律とは、権利と義務を守ることを目的になされるべきものではなかったのだろうか。生まれつきの人権を保障すべきの法律は今、逆に法律上認められた権利を奪うようだ。あるい人たちの命をはつる傾向にあるようだ。今、ある部分の利害関係者を妨害しないために、利害関係者に有利な法律を定めるでしょうか。意識のない患者は自由を奪われるだけでなく、自己決定権を失ってしまう。誰でも生きるという基本的な権利を持っているはずだ。呼吸さえできれば、生き物と見られる。脳死は一律に人の死と認められる野か、家族の意思によるだけで、患者本人の思いを判明できるのか、脳死と判定された人は人権があるのか。もう一度考え直すべき問題だ。第三者の立場からすると、医療とは、患者の苦しみを最大限取り除くということだし、それに脳死者が臓器を提供してくれるのは純粋な善意だから、移植を待ちわびる人にとって、いいかなと思われている。だからといって、もし、自分に万一のことがあったら、そんな状態になったら、「脳死は一律に人の死」という点について、全然違う考えを持つだろうか。生命倫理と死生観にもかかわる問題だ。だから、立場によって、考えも変わるということだ。法律を定める人、臓器を与える人、臓器をもらう人、家族、病院、保険業者、政府、国民、及び社会全体などいろいろの利害関係者にかかわる複雑な問題だ。現在の先端医療の水準や、医の倫理問題などと合わせ、国民的な論議に高めるきっかけにすべきだ。生命倫理を規定する法体系が存在しなてはならないのだ。
2006.10.08
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 日本全国のホテル
- 【千葉】日和(ひより)ホテル舞浜
- (2025-11-14 14:08:13)
-
-
-
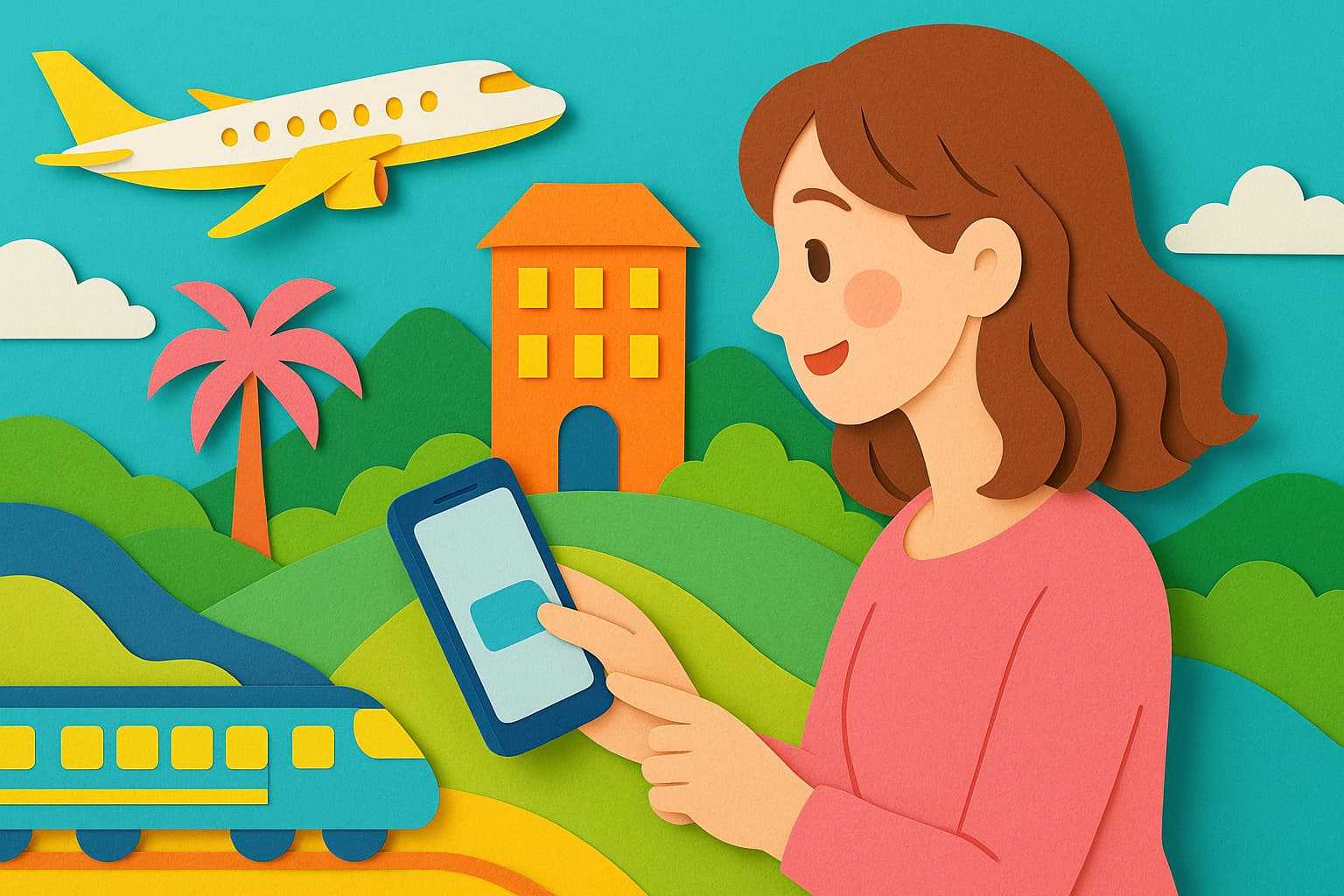
- 国内旅行どこに行く?
- 旅好きの私が“宿を逃さない”ために選…
- (2025-11-14 21:30:04)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- シャカサインで感じるハワイの風
- (2025-07-28 18:59:01)
-