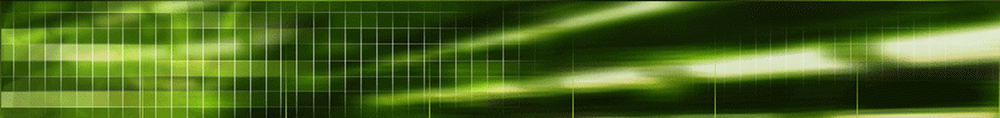第三話「なくしたモノ(前編)」
中東・旧サウジアラビア/リアド近郊
日付も変わり、夜も更けた深夜。風に舞う砂塵を避けるよう、大きな岩陰に暖を取る二人の姿があった。
寒暖の差が激しいこの砂漠では、夜ともなると0℃を下回る事さえまれではない。
切り立った岩壁の小さな溝は、砂嵐を避けて一夜を過ごすに十分な環境だった。
「…………………」
静寂の支配下にあって、焼けた枯れ木のパチパチと鳴る音だけが星の瞬きに調和していた。
まだ日のある頃に集められた薪を手に取り、焚き火の中へと放り込むタクマ。だが、その瞳はどこか虚ろで、何か思い悩んでいるようにも見えた。
「…何を…考えてるの…?」
「ん…?」
戦闘時以外で、彼女の方から話しかけて来る事など初めてだったのかも知れない。
珍しい事もあるものだ。と、少し驚いた顔で振り向いたタクマは、小首を傾げて尋ねるティリアを見た。そして、もう一度正面に向き直り、焚き火の柔らかい炎を見つめながら、少し間を置いて小さく答えた。
「…エド・ランバルト…。アイツと、その部下の事を思い出していた…」
「…どう…して…?」
「………………………」
そう聞き返され、正直どう答えるべきか迷っていた。
長い沈黙…。それは、彼女に語った所で、どれ程の意味を成すのかという自身への疑問と葛藤していたからだった。
無機質な感情しか持たないティリアに、何を求めているのだろう。そんな事を考えながらも、彼はゆっくりと口を開くのだった…。
「…あの男は…どうして、笑って死ねたんだろうな…」
アルベルト・ゲルンシュルト伍長。エド・ランバルト中尉率いる「ミヅチ隊」所属の新人パイロット。
彼は、あの戦闘より一月ほど前に配属され、隊内では最も若い20才だったそうだ。
その事実は、破壊された彼のクリムレアから回収したデータボックスに記されていた。
これらの記録の他にも、幾つか画像データが見つかり、最後の1ページに残されていたのが、死を目前にした彼の姿だった。
「あの戦いを振り返ると、いつも思い出してしまうんだ…。アイツの事を…」
この二週間、ずっと同じ事を考え続けてきた。
自分にもかつて、あの男と同じように、優しい笑みを残して死んでいった人がいた。
その人は、どんな思いでこの世を去ったのだろう。
二ヶ月前のあの日、彼女が自分に残していったのは、悲しみと寂しさ。そして、悔しさだけだったというのに…。
【0020/03/29/10:30】
メイス公国/月面都市セレス
資源衛星OP2の恩恵に与り建造されたこの都市は、月面のクレーターを利用した特異な形状の城塞都市である。
ここを本国とするメイス公国は、その内に公国軍本部を置き、様々な重要拠点や研究施設を内包させた。
公国民至上主義を唱える彼等と守人との関係は冷え切り、その摩擦熱もピークに達していたこの頃。独立宣言を翌日に控え、俄かに慌しくなり始めた公国軍内部では、同時決行される侵攻作戦、「オペレーション・シューティングスター」に参加する兵士の最終選考が行われようとしていた。
【公国軍第一特殊技能研究院/地下試験場】
非公式に造られたこの試験場は、地下200メートルの深さに存在する。
そもそも、このプロジェクト自体が非人道的であった為、そのような処置が施されたのだそうだ。
プロジェクトTAC。…それは、遺伝子操作によって生み出された強靭且つ圧倒的身体能力を持つ兵士の育成を目的とした計画で、誕生した子は培養液の中に入れられた後、あらゆる戦闘技術と知識を植え付けられながら数ヶ月という驚異的な速度で成長を遂げる。
正式に兵士として運用されるのは、個人差があるものの平均して通常16歳~17歳程度にまで成長した個体の最終試験に合格した者だけである。
「…もうすぐだね。最終試験…」
「ああ…」
テストパイロット用の控え室。その壁際に置かれたベンチに腰掛けた二人。
静かな室内には、清涼飲料が並べられた自動販売機の嫌な音だけが響いて耳に残る。
「あ~…ねぇ、何か飲む?アタシってば、なんか緊張しちゃって…タハハ」
立ち上がり、そわそわした様子で強張った笑みを浮かべる少女。
しかし、もう一人の少年の方はというと、至って落ち着いた風で、ぶっきらぼうに首を横に振っただけだった。
「ぁあ…、そう…。ゼンッゼン平気なワケね…」
「…相応の技術と経験を積んできた筈だ。今更、何が起きようと問題ない…」
少年は、目の前に立つ少女と目も合わせずにそう言い放った。
すると、ハァ~ッと小さな溜め息を吐きながら、少女は再びベンチに腰掛けた。
「流石だね、タクマは。…それに比べて、アタシと来たら…」
言い掛け、そこで言葉を止めた彼女は、肩を落としてまたも溜め息を吐く。
ダランと降ろされた両腕をベンチに置き、脚をパタパタと動かしながら天井を見上げる少女。
試験を目前に控え、酷く緊張している事は明白だった。
「…緊張は…その、決して悪くない。むしろ、この状況では必要なファクターと言っていい…と、思う…」
「…えっ?」
驚き、目を丸くした少女は、タクマの顔をじっと見つめた。
「な、なんだ、顔が近過ぎるだろうっ」
目と鼻の先にまで急接近した端麗な顔立ちに、タクマは慌てて視線を逸らした。
「…珍しいぃ~…。タクマがフォローしてくれるなんて。ちょっとカンドー」
「馬鹿を言うなっ。オレはただ、事実を言ったまでだ…っ」
「ふぅ~ん…」
紅潮した顔で怒り、反論したタクマ。だが、少女の方はフフンと笑いながら座り方を元に戻した。
そして、ソッポを向いたままのタクマに、囁くような小さな声で告げた。
「ありがと」
「ん…?」
「ううん、なんでもっ♪」
さっきまでとは違う明るい笑顔を振り撒き、鼻歌まで飛ばしだす少女。
それに安堵したのか、タクマはまた腕を組んで黙り込むのだった。
そして、数分。
11時を告げる予鈴の後に、院内放送でスピーカーから女性の声が聞こえて来た。
『…これより、TAC最終試験を行います。各TAC。及び、研究員の方々は、所定の位置に…』
その放送が鳴り止む前に、二人は顔を見合わせ、真剣な眼差しで言葉を交わす。
「…負けるなよ?」
「大丈夫。勝って…必ずタクマといっしょに地球に降りる」
「フッ、その意気だ」
そう言って微笑むと、タクマは彼女に背を向け、先に控え室のドアノブに手をかけた。
「あ…待ってっ」
唐突に呼び止められ振り返ると、少女は少しだけ間を空けてから、心を決めたように口を開いた。
「…絶対、いっしょだよ」
その言葉に、背を向けた彼は右手を上げて親指を立てた。
最終試験の合格者は、地球降下作戦に参加する事が出来る。それは、戦う為だけに生み出された彼等TACにとっての存在意義であり、唯一無二の目標であった。
必ずや合格し、彼女との約束を果たす。それだけを心に刻み、少年は控え室を出るのだった…。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『汐風と竜のすみか』1~2巻
- (2025-11-30 00:00:12)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- ガールクラッシュ 4巻 読了
- (2025-11-29 07:10:34)
-
© Rakuten Group, Inc.