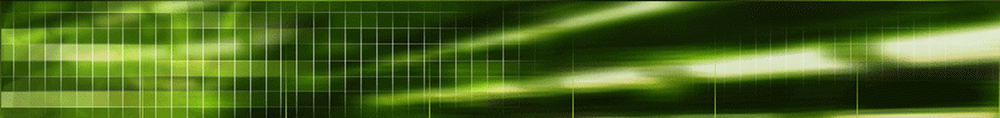第三話「新姫生誕」
尽きる事なく、日一日と無限の広がりを見せる永遠の大陸。
三大軍事国家として名高い「グランスレイ」「シュルノベーレ」「チュウキュウ」を筆頭に、この大陸には多くの国々が混在する。
その数、約三百。
強調すべきは、共和制や民主制を掲げる国は極僅かで、大半が君主制の軍事国家であるという事。
現世で時代に名を残した英雄達が、こちらへと落されて尚も天下の覇権争いに躍起になっているからだ。
ナポレオンやアレキサンダー、織田信長や徳川家康、果ては、かの有名な三国志に登場する劉備や曹操に至るまで、歴史に名高き猛将達がここには五万と居る。
知と武を振るい、彼等は何時果てるとも知れぬ争いの歴史をこの世界でも繰り返しているのだ。
そんな乱世の只中にあり、共和制を主張し続ける数少ない小国の一つが、ここ「ゲンシュウ」である。
無限に広がり続けるこの世界では、それほど貧困に喘ぐ国は無い。
際限が無いから、資源も食料も豊富なのだ。
裕福な満たされた環境。だが、それが戦国武将達の欲望を余計に煽る。
この世界で名を上げようと考える者が後を絶たないのだ。
そんな彼等…周辺大国が真っ先に狙うのが規模の小さな軍備の整わない小国。
このゲンシュウも、遥か昔から、何度となくそんな戦乱に巻き込まれながら存在し続けている。
だが、小国でありながら、何故それだけの侵略を退け続ける事が出来たのか。
その答えは簡単だ。
…そう、抗うだけの「力」が在ったからだ。
ゲンシュウ国、首都ケイクン。
共和制を主張するこの国には、他国と異なり君主が存在しない。
しかし、何故この国が共和制を掲げる事となったのか、その経緯には、嘗ての君主という存在の説明が必要不可欠だろう。
遥か古の時代。この国には「千年王」と謳われる君主の存在が在った。
彼は「ヴァルシード」という名の剣を振るい、降り掛かるあらゆる災厄からこの国を守り抜いた。
だが、何時の頃からか、その矛先は自国の防衛だけでなく、他国への侵略にまで向けられるようになる。
本来、現世では、他国を侵略し、自国の領土を広げる事で国を富ませる。
それを目的とする侵略行為だからこそ、歴史もまた勝者を賞賛するものだ。
しかし、この世界においては、どんな国であっても豊かな暮らしが約束されている。つまり、他国への侵略理由はそこにないのだ。
他国へと侵攻する理由。それは、個の存在と武勇を他に知らしめる事。
それが世界そのものの存在意義とも通じているのだから、また困り物である。
だから、千年王と呼ばれた嘗てのこの国の君主は有能であったとも言える。
そして、生涯に一度の敗北を喫する事もなかった彼は、後の世に、その偉業を伝える事となった。
ところが、突如として彼が姿を消したのは数百年も昔。時の流れと共に広大なこの国の領土は、新たに生まれた他国によって脅かされ、今となっては、大国であった頃の見る影もない
そこで、この国の民衆は考える。
彼の偉業を誇り、共和制を掲げ、その再来を待つ事としたのだ。
だが、力を持たずしては国土を守り切る事は出来ない。だからこそ誕生したのが「ドルゥ・ヴァン」という名の自警武装集団である。
「ドルゥ・ヴァン」とは、この国の古い言葉で「聖王の剣」を意味する。
つまり、彼等は遥か昔からこの国の存亡を脅かす者と戦い、王の帰還を待ち続ける、まさに千年王が残した剣なのだ。
「…お初にお目に掛かります。姫…」
ゲンシュウ国の首都ケイクンにあるドルゥ・ヴァンの本拠。その居城は、まるで日本の戦国時代に遡ったかのような…時代劇に登場するお城のような、そんな形をしていた。
石垣に囲まれた城壁には幾つもの四角い穴が開いている。学校で習った事がこの城にも適用出来るのなら、この穴は外敵からの侵入を阻止する為の物だろう。
この穴から弓で矢を放ち、熱した油を注ぎ、敵を退ける。
こんな城に、人が本当に住んでいるんだから、実感せざるを得ない。
私は、本当に戦国の世に立っているんだ。
「ちょっ、…そ、その、頭を上げて下さい…っ」
私の目の前には、頭を垂れ、傅くように跪いた男が一人。
その背後には、十数人の鎧兜を身に纏った兵士らしき者達も同様に跪いていた。
私の隣には、彼等の長であるヴァンも立っているから、最初は彼に対しての敬意だとも思った。
だが、姫と口に出されている以上、これは私に対しての出迎えである事は言うまでもない。
慌てた私は、状況も理解出来ずにそんな言葉を口にして、両手を左右にフリフリしていた。
「ご命令とあらば…。皆、面を上げよ」
先頭に立った男がそう指示すると、背後の男達も同様に立ち上がる。
これじゃあ本当に、自分がお姫様にでもなった気分になってしまう。
そんな混乱した私に助け舟を出してくれたのは、隣で堂々と立ち尽くすヴァンだった。
「待たせたな、ローレンス」
「…全くだ。だが、まさかヴァルシードとその操り手まで連れてご帰還とは、少々驚かされたよ。ヴァンハルト」
二人は顔見知りなのか、打ち解けた会話を交わしていた。
城門の手前。城を囲う深い堀に架けられた長い橋の入り口で、私達は盛大な出迎えを受けていた。
「クーヤンが落ちたと聞かされた時は、正直、肝を冷やしたよ…。けど、無事で何よりだ」
「丁度本陣の移動を完了した直後だったのでな。幸い、被害も殆ど出ずに済んだ」
どうりで…なんて話しをしているヴァンとローレンス。
その脇で、私はローレンス・アーンスラントというその男の容姿をまじまじと観察していた。
透き通るような青の腰程までもある長い髪。
ヴァンとは系統が違うが、整った顔立ちには高貴ささえ感じる。
彼自身の髪に良く似た瞳は、まるで清水の湖面を覗き込んでいるかのような、そんな錯覚を覚えた。
背の高さはヴァンと同じくらいだろうか。しかし、その体は華奢で、身に纏う物も鎧ではなく、古代中国の文官が着ているような服だった。
「キトラの一件では苦労をかけたな」
「なぁに、ショウコのお陰で、それほど人民に被害はない。ただ、家屋には相当なダメージを受け、もはや人の住めるような状況じゃないがな…」
「あぁ、流民の受け入れはコチラに任せてくれて構わない。既に準備も整え、私の隊に収容を任せてある」
「そうか。助かる」
キトラでの戦いで、街は甚大な被害を被った。
皆は私のお陰で助かった。なんて言うけど、聞けばグランスレイの目的は、あの鎧甲機…ヴァルシードだったというじゃないか。
今のアレの持ち主は私だ。そう考えると、やはり罪の意識も芽生えてくる。
そんな事を悩んでいると、ローレンスの目が私に向けられている事に気付いた。
「…え、とっ…私が、何か…?」
「…っと、これは失礼。お気を害してしまったのであれば、お許し願いたい。…ただ、貴方のようなうら若いお嬢さんが、今や「救国の姫君」などと噂されるヴァルシードの操り手であるとは、どうにも信じ難かったもので…」
内心、だろうね…なんて、肯定してしまう。
何処からどう見たって、私はただの一女子高生だ。
着ている物だって、街で良く見かけるセーラー服だし、剣を持っているワケでもなければ、鎧を身に着けているワケでもない。
まして、人心を引き付けるような何かが有るワケでもないんだ。
でも、私の自分を見る目と他人が私を見る目とでは、大きな食い違いがあるらしい。
「…しかし、皆が姫と呼びたがる理由も頷ける」
「…?」
「その陽光を照り返す艶のある長い黒髪。そして、整ったお顔立ち。…正直、女の私から見ても、貴方は美しいと思えますから」
お、女っ!?…と、心の中で大きく叫んだ。
確かに、言われてみれば男の人にしては華奢な体付きをしてるし、顔だって整い過ぎてる。
名前が男の人っぽかったから、まんまとそれに騙されてしまっていたんだ。…というか、誰も彼…ううん、彼女の事を男だなんて言ってないんだから、私が単に早とちりしてしまっただけか…。
「ご、ごめんなさいっ」
咄嗟に謝ってしまっていた。
自分の心の中の失言に対して、贖罪の気持ちがあったから。
でも、そんな事をこの人が知る筈もなく、ん…?っと小首を傾げられてしまった。
「…まぁ、予想はつきますがね」
そう言って苦笑したローレンスは、更に言葉を続けた。
「ともかく、今日はお疲れでしょう。質素な物ですが、部屋と食事を用意させて頂きました。どうぞ、ごゆるりとお体を休ませて下さいませ」
「あ、ありがとう…ございます…」
ローレンスはそう言うと、半身振り返って背後の兵士達に向かい、指示を飛ばす。
「サラ、ユイ、姫様を御部屋へご案内してさしあげなさい」
「はいっ」「はっ」
同時に声を上げ、私の前に歩み出たのは、私よりも少し年下といった感じの二人の少女。
「姫、コチラへ」
「お荷物などございましたら、私めが」
丁寧な口調でそう言うなり、彼女達は私を案内するように歩幅をあわせて歩き出した。
ヴァンとはここでお別れ?そんな不安に後ろを振り返ると、まだ仕事がある、とばかりに微笑んで手を振ってくれた。
そんな事を望んでたワケじゃないんだけど…。
とはいえ、ここで駄々を捏ねるのも何だか情けない。だから私は、そのまま黙って彼女達について行く事にした。
城門を抜け、塀に囲まれた長い長い道のりを歩き、ようやく城内へと通された時には、私はもうヘトヘトに疲れ切ってしまっていた。
こんな造りも、敵の侵入を妨げる為の物なのだろうが、最近運動不足だった私には、ちとキツかった。
でも、城内に入って、私は疲れていた事も忘れて声をあげたんだ。
「はわぁぁ………っ」
ポカ~ンと大口を開けたまま、それ以上何も言えなくなる。
だってそこは、信じられない程広くて、綺麗で、この世の物とは思えないような光景だったから。
ココの建築様式とか、そういうのは難しくて良くわからないし、それが何なのかも理解出来ない。でも、眩いキラキラした白い金って表現がそのまま適用出来てしまいそうな空間。
西洋の建築様式でいうなら、そこはエントランスっていうのかな。正面には開けた大広間があって、広さは私の住んでた家…お屋敷がスッポリそのまま入ってしまうくらい。
数十本の金と銀で装飾された柱が全体を支えるように両端に並んでて、その向こうには二階建てくらいの高さまで階段が続いてて、そのまた向こうには高さ五メートル以上もありそうな大きな扉が聳えてる。
外見は日本のお城みたいだったけど、中はまるで、西洋のお城みたいだった。
「…姫?」
「どうかなさいましたか?」
唐突に御付きの二人に声をかけられ、はたと我に返る。
「ご、ごめんっ」
私は、足が止まっていた事にようやく気付き、数歩前方で不思議そうにコチラを窺っている二人の所まで早足で駆け寄る。
すると、一人が私に半身反らして背中越しで続けた。
「姫のお部屋は最上階にありますので」
そこまで言われ、何となく想像してしまう。
最上階?こういう場合、お城の天辺にある部屋は…
「…や、やっぱり…」
想像した通りだった。
ここは地上数十メートルもある所に位置する最上階。この城の主が住まう場所。
ここに至るまで、この世界には似つかわしくない奇妙なエレベーター?に乗せられてやってきたから疲れなんてなかった。けど、その光景に私は苦笑を浮かべる。
何故って、簡単な事。
私の目の前には、広さ二十畳くらいの…だだっ広い、一国一城の主が住まうような私室が広がっていたんだから。
しかも、その装飾品や調度品の数々ときたら、一階にあったエントランスの比ではなかった。
更に言わせてもらえるなら、その部屋はわざわざ私の為に用意されたような、そんな感覚がある。
だって、その部屋は、とても男の人が住めるような部屋ではなかったから。
窓には淡い桃色のカーテンが敷かれ、絨毯も同じような色。壁は清潔感のある白だけど、何より驚いたのは、ぬいぐるみがそこかしこに置いてある事だった。
「こ、これって…」
私が以前、ヴァンに話した内容そのもの。
そんな部屋に住んでみたい。…なんて、軽い気持ちで言った言葉が全面に反映された部屋だった。
この分だと、隣にあるっていう寝室のベッドも、きっとお姫様仕様なんだろうなぁ…と、そう思い、また苦笑する。
「気に入って頂けましたか?」
「ヴァン様にお願いされて、私達がご用意させて頂きました。いかがでしょうか…?」
もう笑うしかない。
年下…かどうかは判らないけど、そんな女の子達が上目遣いで尋ねてきて、それを無下にあしらう事なんて出来るわけがないし。
「ありがとう。嬉しいよ、とっても」
私がそう言って微笑むや否や、二人はパァ~っと花が咲いたような笑みを浮かべる。
でも、二人にそれぞれお礼を言おうと思って、やっと気付いた。
そういえば、どちらがサラで、ユイなのか、名前もまともに聞いてなかったんだ。
「…そういえば、二人の名前、まだ聞いてなかったね」
と、言うと、喜び覚めやらぬまま、二人は慌てた様子で向き直ってペコっと頭を下げた。
「も、申し訳ありませんっ」
「申し送れましたっ」
すると、右に立っていた桃色に髪を染めたツインテールの少女が一歩前へ出た。
「私が、今後、ショウコ様の身の周りのお世話をさせて頂く事に相成りました、ユイ・ギョコウと申します」
ユイと名乗った少女は、私よりも小さな体だっていうのに武官なのか甲冑を身に纏っていた。
しかし彼女は、そんな勇ましい姿とは対照的に、表情が柔らかく、話し方なんかもおっとりしていて、きっと大人しい性格なんだと思える。
対して…
「私が、サラです。サラ・チョウイ。ユイと同様、ショウコ様の侍女として働かせて頂く事になりました。どうぞ、お見知りおきを」
ユイと名乗った少女の隣に、同じく一歩進み出て名乗ったのは、赤茶色に染めたポニーテールの子。
言葉は丁寧だけど、ユイとは対照的で活発的な印象を受ける彼女は、同じく武官なのか、鎧兜に帯剣といった勇ましい格好をしている。
雰囲気は対照的だが、どちらにも言える事が一つだけある。それは、とっても可愛いって事。
世が世なら、学園のアイドル。なんて言われてもおかしくないほど可愛らしい。
きっと、男の子の間でも人気があるんだろうなぁと思える。
って、そこまで考えて、改めて彼女達の言葉を反芻し、気付く。
「身の周りの世話…?侍女…?」
「はいっ」「はっ」
にっこり笑顔で答えるユイと、ビシッと背筋を伸ばして返事をするサラ。
私の耳はそれを聞き逃さなかった。
そして、目で見た物と、耳にした事を基に情報を脳内整理してみる。
「…………………………………………………」
まるで将棋を打つ人みたいな長考。
自身の右手は顎に添え、その右肘を左手で支えるような体勢で考え込む私。
では、整理してみよう。
ここは、ゲンシュウ国の首都ケイクン。
ドルゥ・ヴァンと呼ばれる自衛組織の総本山。
そして、嘗てはこの国の君主が根城としていたこの城の最上階に位置する城内で最も豪勢な装飾が施されているであろう一室を、私は与えられた。
加えて、侍女とは、上位の位に位置する人間の身の周りの世話をする人達の事。
そして、私の呼び名は「姫」。
…と、いう事は…
「こ、このお城の城主って、もしかして…っ」
ハッとなって自身を指差しながら尋ねた私に、サラとユイは笑顔で「ハイ」と答えた。
「な、な、ななな、何ですとぉぉ~っ!?」
我ながらベタな驚き方をしたものだ。でも、事情はどうあれ、こんなのおかしいに決まってる!
だって、私はただの女子高生で、偶然にもヴァルシードっていう鎧甲機を動かせただけの、か弱い一女の子に過ぎない…って、自分で、か弱いなんて言ってたら世話ないけど。
そりゃあ、この組織のリーダーであるヴァンと仲良しで、客人として私を丁重に持て成すというのは理解出来る。でも、こんなの過大評価も良いところだ。
この前の戦いの時だって、キトラの人達を助ける事に頭が一杯で無策で飛び出した挙句、敵軍の隊長格に良い様にあしらわれちゃって…。そんな私が、こんな待遇を受けるなんて絶対何か勘違いしてるんだ、この人達は。
けど、この人達の事情を考えると、そう口にするのが恐くなった。
何百年もの間、彼等は何時現れるとも知れない「君主足る人間」の再来を心待ちにしていたんだ。
そして、嘗ての王の遺産であるヴァルシードを操れる私が現れた。…そりゃあ、そう思いたくなる気持ちだって分からなくない。
でももし、私が千年王の跡継ぎでも生まれ変わりでもないって知ったら、彼等はどう思うだろう?
そんな事を考えていた私は、剣呑とした表情でも浮かべていたんだろう。サラとユイに内心の不安を見抜かれ、心配そうな顔で覗き込まれてしまった。
「…あっ、だ、大丈夫!べ、別にこの部屋に不満があったとか、そういう事じゃないからっ」
慌てて両手をフリフリしながら苦笑する私に、彼女達は「そう…ですか?」と答えて互いに顔を見合わせる。
でも、少なくとも、今は黙っておこう。
こんな考えが彼等に伝わってしまったら、それこそどうなるか分からないんだから。
後で、ヴァンに相談してからでも遅くない。先の事は、それから考えよう…。
サラとユイに「とりあえず、今日は疲れたから休ませて貰うね」って、そう伝えて、今は一人、隣の部屋のお姫様ベッドの上。
フリフリのカーテンが付いたピンク色のふかふかスプリングベッド。
ヴァンが用意してくれたその上に、ドサッと大の字で寝そべり、深く沈んで行く自分の体の感触を確かめながら、その心地良さを噛み締めて瞼を閉じる。
「…はぁ~…、なんか、大変な事になってきちゃったなぁ~…」
深い溜め息の後、疲労から来る睡魔に太刀打ち出来なくなった私は、何時の間にか寝息を発ててしまっていた…。
グランスレイ王国、王都ベルキニア。
無機質な質感の街並み。
多くの人間が行き交う街路の喧騒は、そこが大都市の中心地である事を如実に語って見える。
この国に住む者達は、皆、鉄の家に住み、定められた一生を送る。
…適材適所…。そう言えば聞こえはいいが、王であるドルマ・レ・ウル・グランスレイの命令通りに動く、いわば駒のような存在だ。
逆らおうなどと考える人間は、いないのだろうか?…否、いないのだろうな。
恐怖政治によって支配されたこの国では、従う事に至高の喜びを感じる者の方が多いのだ。
灰色の空気漂う機械仕掛けの都。その中心で、私は唯一人、そんな事を考えていた。
「…色の無い世界…か」
眼下に広がる働き蟻達を眺め、私は哀れみにも似た視線を向けていた。
「言い得て妙ですなぁ。ドレイク将軍」
「…立ち聞きとは悪趣味だな、ゲイル」
グランスレイ王国国王ドルマ・レ・ウル・グランスレイの居城。つまりは、上位権力者達が集うこの国の中枢。
鋼の城とでも形容すべき姿を持つこの巨大な城の上層部。その一室の壁一面を担うガラス窓から外界を見下ろしていた私の背中に唐突にかけられた言葉だった。
薄暗く、何も置かれていない無機質な四角い空間。そんな場所で一人物思いに耽る私もどうかしていたが、現れたこの男の立ち居振る舞いも悪趣味と言わざるを得ない。
「随分な物言いだ。…これでも、数少ない親友が悩み事でも抱えているのかと心配しての配慮だったのだが…ねぇ?」
「フン、心にも無い事をツラツラと…。何用だ?」
何が親友であるものか。
隙あらば互いの命を狙い合う。そんな関係を親友と言うのであれば、それは間違いではないのだろうが。
そんな皮肉染みた言葉を思い浮かべ、背を向けたままである事を得策でないと判断した私は、半身振り返って背後の男に射抜くような視線をぶつけた。
「おぉ~恐い…。何時もながら、ゾクゾクとする良い目だ。その視線に射抜かれただけで、悶死してしまいそうですな…。クックックッ」
気味の悪い男だ。だが、これで私と同じ四柱将の一角を担っているというのだから油断ならない。
ゲイル・ウルガン。それが、この不気味な男の名だ。
彫りの深いこけた頬。その無骨な体に似合わない小さな丸渕眼鏡。
前髪だけ解けたオールバックの黒い髪は、整髪料でも使っているのか、テカテカとした艶を放っている。
文官と呼ぶには抵抗さえ感じる体格で威圧するその男は、薄ら笑いを浮かべながらコチラを見つめていた。
「…用が無いのなら、これで失礼させてもらう。貴公の戯れに興じていられる程、私は暇ではないのでな」
「ツレないお言葉だ…フフフッ。ですが、用ならありますぞ?」
ん?と目で聞き返した私に、ゲイルはまた気味の悪い笑みを浮かべて続ける。
「陛下がお呼びです。まぁ、例の件に関してでしょうがね」
「…わかった。直ぐに行く」
例の件。そう言われれば、察しが付くというものだ。
ドルマ王は、「アレ」に酷く御執心らしい。
正直、面倒な事この上ないが、陛下直々のお呼び出しとあれば、無碍にも出来ん。
私は部屋を出ようと扉の前に立ち、自動で開かれるのを待った。…すると
「…勝敗は兵家の常。あまりお気になさいますな…。クックククッ」
皮肉のつもりなのだろう。
キトラでの一戦で我が軍が敗退した事を言っているのだ。…馬鹿馬鹿しい。
個の真意も読めぬ男に将の価値があるとは思えんが…、それでも、機嫌を損ねたフリでもしておいてやれば満足するのだ。ここは乗せられてやろう。
「………チッ」
軽く舌打ちをしてみせ、勝手に開かれた扉から廊下へと歩き出す。
すると、閉じられた扉の向こうから、満足気な笑い声が響いてきた。
「…下らん男だ…」
小声でそう呟きながら、鋼造りの広い廊下を行く。
謁見の間直通の転送装置を経由し、大広間へと出た私は、目の前に浮かぶ巨大な観音扉の前に立つ。
警備の兵がその両翼を固めてはいるが、私にとって、それは何の意味も成さない。
私は「四柱将」と呼ばれる、この国最強を誇る将の一人。
警備兵など、恐れをなして自ら声をかけようとさえしない。
ただ、敬礼し、私の到着を室内の門兵に伝える事しか出来ないのだ。
「…………………」
程無くして開かれる扉。薄暗いその先へと堂々と進んだ私の前に、ぼんやりと浮かび上がる玉座。
この部屋の広さは熟知している。だが、光りの差し込まないそこは、得体の知れない淀んだ空気に包まれている。
無論、部屋の端から端までなど見渡せる筈もない。
在るのは、ただ静寂。
その最奥に、玉座は在った。
「…ヴェイル・ドレイク。参りました」
黒い鎧は闇に溶け込んでしまう。だからという訳でもないが、私は自身の到着を言葉にして告げた。そして、その御前に外套を翻して跪く。
すると、闇の奥底から響き渡る、重々しい威厳のある初老の男の声。
「…アレの捕縛に失敗したそうだな、ヴェイル…」
「弁明の余地もありません。…ですが、不測の事態に陥り、陛下より頂いた大切な精兵を失う訳にも行くまいと、早々に退却を命じた次第にございます」
「…不測の事態…とな?」
「は…っ」
私は、陛下に事の顛末を伝えると、再び押し黙る。
「…ふむ…。…よもや、アレの操手がヴァンハルトの下に居ようとはな…」
陛下は、何かを考え込んでいるのか、そのまましばしの沈黙が続いた。
そして、再び開かれたその口からは、私が想像していなかった意外な言葉が飛び出す。
「…塵塚に鶴とはこの事か…。しかも、操手の娘は相当な美の持ち主と聞く。捨て置くには惜しいな…」
「と…、申されますと?」
言いたい事など分かっていた。だが、あえて聞き返した私に、言葉を返したのは女の声だった。
「陛下は、その娘ごと、ヴァルシードを献上しろ。…と、そうおっしゃっておられるのだ。ヴェイル」
「…シュウラン…か」
玉座の裏手から、和服にも似た紫電柄の着物の乱れを正し、簪を刺し直しながら現れた紫髪の妖艶な女。
キョ・シュウラン。
その美貌と戦場における鬼神の如き槍捌きから「戦女神」の字を冠する四柱将が一人。
その紫の瞳に魅入られた者は、ただそれだけで我を失い石像と化し、その艶やかな肌に触れた者は、死して尚も彼女の忠実なる下僕と化す。
敵味方から、魔女とまで噂される絶世の美女。だが、その一方では色欲魔と呼ばれる程、あらゆる男をその美貌と肉体で手玉にとってきた女だ。
おそらく、アレの情報を陛下に与えたのも、この女の仕業だろう。
余計な真似をしてくれる…。
だが、そんな思いを口に出すような愚行を私は好しとしない。
これもまた、我が大儀の為と喉の奥に仕舞い込む。
「御意」
陛下の肩へ甘えるように寄り掛かったシュウランに一度目を合わせ、その妖艶な笑みに応えもせず立ち上がった私は、深々と陛下に向かって腰を折り、命を実行せんと立ち上がる。
「必ずや、吉報をお持ち致します」
「…うむ。期待しておるぞ…」
振り返り、外套を翻し、陛下に背を向けて歩き出す。
その間際、陛下とシュウランの濃密な接吻を見せ付けられ気分を害するも、今の私にそれをどうこう言う理由はない。
今の所は、黙って従っておこう。そうでなければ、ここまで築き上げた物が全て水泡と化して消えてしまうのだからな。
だが、この状況は大いに利用させてもらう。
ヴァルシードを手に入れるのは、千年王が直系たる、この私なのだからな…。
「フッ…」
闇の中へと溶け込む私の背を見つめる視線。それは、陛下ではなく、おそらくはシュウランの物だろう。
だが、その真意になど興味はない。
私に必要なのは、力。
ただ、それだけなのだから…。
ゲンシュウ国、首都ケイクン。
自室のベッドの上で何時の間にか眠ってしまっていた私は、けたたましい声に目を覚ました。
「ちょ…っ、それホントなのッ!?」
ビクッとなってベッドから飛び起きた私は、何があったのかと慌てて部屋を飛び出した。
バタンッ
扉を蹴破るような勢いで開け放つなり、目の前に立っていたサラとユイに大声で尋ねる。
「ど、どうしたのっ!?」
そんな風に飛び出せば、彼女達も驚いて…
「ショウコ様っ!?」
でも、その視線が、何故か少しずつ下がって行って…
「…お、おっきい…」
「へ…っ?」
二人が凝視していたのは、私の胸の辺り。
目線を追ってみて気付いたのは、自分が今、上半身裸だったって事。
「はぅあっ!」
…と、自分のソレを慌てて腕で抱え込み隠してはみるけど、考えてみれば女同士。何も慌てる必要性はなかった。
だから、そのままの格好でもう一度尋ねる。
「…そ、それより、何かあったの?」
「あ、あ…あぁ、はい。つい先ほど隣国のガカクに放っていた間諜が戻りまして…」
ユイの話しによれば、隣の国「ガカク」をグランスレイ軍の鎧甲機部隊が襲い、太守であった「織田信長」が討ち取られたというではないか。
正直、半信半疑だったのだが、本当にこの世界には、そういった歴史上の人物が今も尚生かされているのだと実感させられる。
私は、ホントに居たんだ…。なんて口に出しそうになったけど、そこはあえて飲み込んで話しを進める事にした。
「それって、かなり不味い状況なんじゃ…」
考えてみれば、単純な話し。
グランスレイ軍は他国侵略の為に遠征軍を派遣し侵攻してくる。だからこそ、今までは対処のしようもあったんだ。
何故かっていうと、コチラは城…というより、都に篭っての篭城戦になるわけで、グランスレイはそれを相手に戦う事になる。
昔から言われている事だけど、篭城する敵を打ち破るのに必要なのは、篭城する相手の三倍の兵力だって言われてる。
如何に小国といえど、篭城した相手を討ち取るのはそう容易い事じゃないんだ。
それに、小回りが効き、足の速いうちの軍隊は、遠征軍…つまり、グランスレイの補給線を断つという策にも向いている。
だから、今までは、グランスレイも本腰を入れての侵攻作戦を行えなかったんだと思う。
小国だから…なんて、そういう考えもあったんだろうけど…。
でも、隣国を陥落させられたとなると、話は別だ。
今までは遠征軍として兵力の導入にも限界があったけど、そんなに近くに拠点を構えられてしまうと、溜め込まれた兵力を一気に吐き出すような作戦も取られてしまう可能性が大きくなる。
この国の状況は、正直に言って芳しくないのである。
「彼我戦力差は甚大…。このままじゃ、圧倒的な兵力の差でジリ貧に追い込まれちゃう…」
…と、そんな事を口にすると、サラがポカ~ンと大口を開けたまま、唖然とコッチを見ていた。
「ど、どうしたの…?」
気になった私は、そんな彼女に尋ねた。
すると、思い掛けない言葉が返って来る。
「あ…っ、いいえ、スゴイなぁ~…って、ついつい感心してしまって…」
え、何が?と言わんばかりに小首を傾げると、ユイが続けた。
「隣国が落ちたとお話ししただけで、そこまでのご高察をなされるなんて…。まるで、ローレンス様みたいでした。尊敬しちゃいます…」
どうやら、さっきの説明は口にも出てしまっていたらしく、彼女達はその事に感心しているようだった。
でも、そんなに難しい推察ではなかったように思うんだけど…。なんて、そう思っていた時だった。
ギィ~…パタン
…と、私室のドアが開けられた音がして、振り返った私達と、侵入者の目がピタリと合う。
「あぁ、ショウコ。話し…が………」
瞬間、部屋の空気が凍り付いた。
「……………………………」
「……………………………」
全員の時間が止まってしまったかのような錯覚を覚える中、ただ一つ流れる物。それは、侵入者…ヴァンの鼻から伝い落ちる、赤い物だけだった。
「…ひぅっっ!!」
…と、私が声にならない声を発し、両腕で胸を隠してしゃがみ込んだ時、目の前に居た筈のサラとユイの姿はパッと消えていた。
「こぉんのぉ…ド変態ぃぃぃぃーーーーーーーーーーーーーーーっ!!」
「…死ね…っ」
ちょっ、今、ユイの顔が一瞬鬼に見えたんですけどっ!?
っていうか、信じられない言葉が発せられた気も…。
ゴキッ!
直後、もの凄い音(骨が砕けたような)が響いて、ヴァンの体が宙を舞っていた。
鼻から噴出された血飛沫が、まるで噴水みたいにキラキラ輝いて…。
一瞬、綺麗だなぁ~…なんて、思ってしまった。
「ぐぎゃっ!!!!」
あ…、床に落ちた。
「女性の部屋に入る時くらい、ノックして下さいっ!」
「不謹慎ですよ、ヴァン様!」
私の前で仁王立ちするサラとユイ。その眼下には、地に横たわる哀れな骸…って、まだ死んでないけど。
「…ご、誤解…だ………」
チ~ンッて音が聞こえてきそうな感じで、ヴァンの救済を求める手が力なく床に落ちる。
ちょっと可哀想な気もするけど、これはこれで仕方ない。うん。
まぁ、そもそも、ノックもせずに部屋に入って来た彼が悪いんだし…。
大人しく成仏して下さい…。
…なんて、ヴァンが目を覚ました後、どうして私を訪ねて来たのか聞くと、やはり織田軍失墜の件についてだった。
私が推察したのと同じ事をローレンスさんも考えていたようで、午後から軍議を開く事になったのだそうだ。
そこで、私にも出席して欲しいとの強い要請があった事を聞かされ、渋々ながらも参加する事になった。
元々、私もヴァンについて行くと決めた時から軍属になる事を覚悟していた。
状況は少し変わってしまったけど、折角得られた力だ。誰かの役に立てたい。
でも、私が考えていたよりも、この国は切所に追い詰められていたみたいで、戦争をしているんだなぁと、また気付かされる。
簡単じゃないんだ。
数万っていう人の命がかかってるんだ。
私は、改めて、その軍議の中で自分が置かれている立場という物を思い知らされた。
そして、同じ頃。
城の地下にある格納庫では、あの子にまた変異が始まっていた事に、私は気付いてあげられなかった。
ブゥオン…ブゥオン…ブゥオン…
暗がりの中で一人、目を輝かせる巨人。
ヴァルシードは何かを予見していたのか、私に警告を発し続けていたっていうのに…。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
- 楽天ブックス
- [楽天ブックス 年間ランキング 2024…
- (2024-12-03 03:14:30)
-
-
-

- 経済
- 2024.9.3.財界オンライン:2024-09-03 元…
- (2024-11-12 00:09:27)
-
© Rakuten Group, Inc.