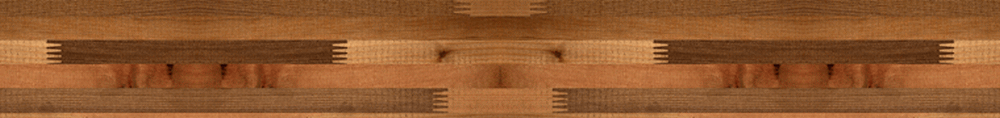シンデレラ
王宮で、盛大なダンスパーティーが行われるのだ。
おおっぴらに謳われている訳ではないが、そのパーティーで王子の妃が決まるのではと、もっぱらの噂だった。
それで、国中の年頃の娘を持つ貴族は、ここが正念場と盛り上がっていたのだ。
「行ってらっしゃいませ」
「お留守番よろしくね、お掃除とお洗濯おまかせしたわ」
「はい、お母様。セシリアお姉さま、行ってらっしゃいませ」
「ごめんなさいシンデレラ。あなたも行ければいいのに」
「私はいいのよ。サンドレド家代表としてセシリアお姉さまがんばってくださいね」
セシリアはにっこりと微笑んだ。
屋敷から馬車が見えなくなるまで見送ると、シンデレラは腕まくりをした。
「さあ、のんびりしてられないぞ。やることは山ほどあるからね」
張り切って厨房のバケツを持ち上げた時、黒い影がさっと動いたのが見えた。
「キャッ!!」
驚いたシンデレラの手からバケツが落ち、その音が屋敷じゅうに響き渡った。
シンデレラが動く影をよく見ると、バケツの音に驚いて転んでいるネズミがいた。
「ひゃー、びっくりした」
なんとネズミがしゃべった。
「なによ、びっくりはこっちよ。なんでネズミがしゃべるの?」
「それは、私が、魔法使いだからだよ~」
煙がモクモクと湧いて、現れたのは太っちょのおばあさんだった。
「ひひひ~。驚いたかい?」
「そりゃあ驚くわよ!なによ勝手に人の家に入ってきて!」
「おやまあ、そう怒りなさんな。迷惑はかけんよ」
「もう充分迷惑してるわ。いたずらだったらもう出てって頂戴。あなたと遊んでる暇はないの!」
「はいはい、えろうすんませんでしたー」
再び煙がモクモクと湧き、ネズミが外に出て行くのが見えた。
シンデレラはふーと大きな息をつき、気を取り戻したようにバケツに水を汲み、手馴れた動作で掃除を始めた。
テーブルを拭き、椅子を拭き、戸棚も一段一段丁寧に拭き、雑巾をすすいだ。
シンデレラの額には汗が吹き出ている。
その表情はいつの間にか楽しそうに輝いていた。
よいしょっとバケツを持って振り返ったとき、いつの間にか、魔法使いの太っちょばあさんが拭いたばかりの椅子に座って頬杖をついていた。
びっくりしてまたバケツをひっくり返した。
「やめてよ!いったい何なの!」
「おやおや、また驚かしちゃったかね」
「もう、床がグチョグチョだわ」
「すまんすまん」
と言いながら魔法使いは短い杖を懐から出すと、呪文を唱えだした。
「トエロンテレロン~!」
すると、部屋の隅のモップが勝手に動き出し、床を吹き始めた。
魔法使いがリズムに合わせて杖を振ると、今度は雑巾が空中を飛び、隅から隅まできれいに磨いて行った。
呆然とするシンデレラを尻目に、あっという間に厨房は隅々まできれいに片付いてしまった。
「ほっほっほ。驚かしたおわびじゃ。礼はいらんよ」
満足そうな魔法使いとは裏腹に、シンデレラは眉を吊り上げていた。
「冗談じゃないわ。お礼なんて言うもんですか。私の楽しみを奪っておいて!」
「楽しみ?」
「そうよ。お掃除が私の楽しみなの。私、お掃除大好きなの。みんなが出かけるこの日は、思いっきりお掃除ができると思ってたのに。それを―、なんなのあなたは。人の気も知らないで!」
「掃除が好き?変わってるのう~」
「いいでしょ。人には人の好みがあるの!!」
シンデレラはますます怒り出した。
魔法使いはすまなそうに話し出した。
「実はな、お前のことは、昔から見てて不憫に思ってたんじゃよ。
姉さんはいつも着飾ってパーティーなのに、お前は掃除ばかり。
それで、わしの魔法の力で、今日はお前さんもダンスパーティーに連れてってやろうかと思ってのー」
「おあいにく様。私はダンスパーティーなんてぜんぜん行きたくないわ。
お姉さまはダンスパーティがお好きだけど、私はそうじゃない。
家に残って掃除をしたい人なの。それを、魔法なんかで、こんなにしちゃって―」
魔法使いは首をすくめて聞いていたが、ちょっと悪戯っぽく訊いた。
「でも、行けるんだったら、お前も行きたいじゃろ、ダンスパーティー?」
「だから、行きたくないってば。着ていくドレスもないし」
「ドレスがあれば、行きたいか?」
「えっ…。ドレスがあっても、お城へは馬車がないと行けないわ」
「ドレスと馬車があればいいんじゃな」
太っちょばあさんは、呪文を唱えて杖を振った。
「シャバランドレンド~!」
杖の先から煙が立ち上がり、その中から出てきたのは、美しいドレスを身にまとったシンデレラだった。
「ほほ~。なかなか美しいじゃないか。外には馬車も用意してあるぞ」
うれしそうに魔法使いは言った。
「ちょっと、やめてよ。私本当にダンスパーティーなんかに興味ないの!」
それまで怪しげな笑みをたたえていた魔法使いの表情が、本性を現すように変わった。
「魔法使いには出来ないことはないんだよ!
わしが、お前をダンスパーティーに連れて行くって言ったら、絶対連れて行くんだ!」
眉間にシワを寄せて、かっと見開いた眼に睨まれて、シンデレラは動けなくなった。
魔法の杖が奇声とともに振り下ろされると、部屋の景色がぐるぐる回りだし、まるで竜巻に飲み込まれたようにシンデレラの体は空中へ飛ばされた。
ぐるぐるまわっていた景色がだんだんと落ち着いてくると、大勢の着飾った人たちの姿が見えてきた。
そこはお城のダンスパーティの会場だった。
大勢の貴族たちがこちらを見ている。
「あの美しい方はいったい誰だ?」
「あんな美しい人は見たことがない」
ざわざわと声がきこえる。
だんだん目覚めてきたシンデレラは震えだした。
『困ったわ、どうしよう。早くここから逃げないと大変なことになるわ』
どんな大変なことが起きるかわからなかったが、とにかく大変なことになると思った。
すると、人ごみの中に、姉のセシリアの姿が見えた。
「お姉さま~!セシリアお姉さま~!」
シンデレラは喜び勇んでセシリアのもとに駆け寄った。
セシリアは一瞬訝しげな表情をしたが、声の主がシンデレラだと判ると大きく目を見開いた。
「まあ、シンデレラなの?―驚いたわ。どうして、あなたがここにいるの?」
「悪い魔法使いに悪戯されたの。良かった、お姉さまに会えて。私どうしようかと思ってて…」
「シンデレラ、あなたとても綺麗よ。はじめはあなただと判らなかった程だわ」
「だから、悪い魔法使いに、魔法をかけられたの。ひどいわ!」
「シンデレラ、あなたあの鏡でご自分を御覧なさい」
セシリアに連れて行かれて、シンデレラは鏡に映った自分の姿を初めて見た。
そして、呆然とした。
「…これが、私?」
自分でも見違えるほど、美しい女性に変わっていた。
「いつもあんなかっこうしていたから、あなたがこんな綺麗な人だったなんて気がつかなかったわ」
シンデレラ自身もそう思った。
「もし―、よろしければ、私と、踊っていただけないでしょうか」
ふいに声をかけてきた男がいた。
ひときわ高貴な服装の、美青年だった。
「まあ、王子様!」
セシリアはこの方が、この国の王子であることをシンデレラに耳打ちした。
シンデレラは硬直した。
「だめよ。私、踊りなんか知らないわ」
すると、シンデレラの頭の中に声が響いた。
『ほっほっほっ、安心をし。あんたは魔法が掛かってるんじゃ。踊りでも何でも出来るようになっちょる』
シンデレラは緊張で泣きそうになりながら、王子の手に引かれて行った。
すると、不思議なことに、習ったことも、見たことすらない宮廷の踊りが、自然と踊れていた。
「おお、美しい人よ。なんと素晴らしい踊りなのだ。よほど高貴な方でしょう。どうぞお名前を教えてください」
踊りながら王子は尋ねた。
シンデレラは夢見心地で揺れていたが、その声にはっとわれに返った。
「申し訳ございません。ゆえあって、名前は申し上げられません」
王子の手を離すと、逃げるように駆け出した。
心の中で、自分がいけないことをしているという気がした。
とにかく、ここにいてはいけない。
庭に出ると、カボチャの形をした馬車が止まっていた。
無我夢中で飛び乗った。
「お願い、魔法使いのおばあさん。私を家に帰して!」
両手を握って、ぎゅっと目を閉じ、必死に祈ると、また竜巻が起こった。
次に目を開いたところは、元の厨房だった。
シンデレラの服も元通りに粗末なものに戻っていた。
目の前には太っちょ魔法使いがいる。
「なんだい、もう帰ってきたのかい」
緊張の糸が切れたシンデレラの目から、涙がぽろぽろ流れ出した。
「どうだった?おもしろかったじゃろ?」
シンデレラは首を横に何度も振った。
「おやまあ。楽しくなかったかい」
少し落ち着いてから、シンデレラは言った。
「突然だったから、驚いたわ。―でも、本当は、うれしかったかもしれない…。私が、あんなに綺麗になれたなんて…。まさか、王子様と踊れるなんて…」
「そうかい、じゃあ良かったのかねえ。年寄りの悪戯も」
「ええ。あんな経験、魔法じゃなければありえないもの。それについては、お礼を言うわ」
シンデレラはきっぱりと言った。
「喜んでもらえたなら、もうひとつ言うが、実は、今、お城のものがお前を探しておる」
「えっ、どうして?」
「王子がお前を気に入ってしまったらしい」
「王子様が、私を気に入った?」
「今日のダンスパーティーは王子の妃を決める催しだったんじゃよ。それで、お前に決まったんじゃ」
「妃?私が?ありえないわ。それに、私の名前も知らないのよ」
「それが、お前は馬車に乗るとき、靴を落としてきたじゃろ。あのガラスの靴を頼りに探しておる。
靴にぴったりの足を持っている娘が妃になる。あの靴は、魔法が掛かっておるから、他の誰が履いても、あわない。
おまえだけじゃ、履けるのは。今、順番に回っているから、何れここにも来る。いくら汚い格好をしていても、お前が履けば、ぴったりじゃ」
「私、どうすればいいの?」
「な~に。靴を履いて、妃になればいいのじゃよ。妃になれば毎日楽しいぞ~」
「…」
「毎日、綺麗な服を着て、おいしいものを食べて、家来にモノを言いつけて―」
「違うわ!」
「何が?」
「それは、私じゃない」
「どういうことじゃ」
「さっきの私は、魔法にかけられた私だから、本当の私じゃないわ。
王子様の気に入られているのは、うその私だから、それで私が選ばれるわけに行かないの」
「選ぶのは向こうだからいいじゃないかい」
「だめなの。うその私は、結局うその私よ。本当の私のままで生きないと、苦しむのは私の方だわ」
「せっかくのチャンスだぞい」
「チャンスでもなんでもないわ。私は私のままで人生を送りたいの」
魔法使いは首をかしげて少し考えた。
「せっかくお前のためにと思ったんじゃが」
「ありがとう。でもいいの」
「ほんとに、いいんだね」
「いいわ」
「このまま、一生掃除と洗濯の下働きだぞ」
「お掃除もお洗濯も、私大好きだって言ったでしょ。私は私の楽しみ方をするわ」
「そうかいそうかい。そうまで言うのなら―」
ふとっちょ魔法使いは、杖を振り上げた。
「ガラリンパ~!」
シンデレラの家の前で、ガラスが割れる音が響いた。
今まさにドアをノックしようとしていた家来の持っていたガラスの靴が、呪文とともに粉々に砕けて消えてしまった。
シンデレラは元のシンデレラの戻った。
一夜の冒険を、思い出の扉にしまって。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 日常の生活を・・
- トイレットペーパーおすすめ!
- (2025-12-04 11:13:20)
-
-
-

- 運気をアップするには?
- パワーお香をプレゼントします。福岡…
- (2025-12-04 23:49:59)
-
-
-

- φ(._.)主婦のつぶやき☆
- どれか欲しい半額チーズケーキ(地元…
- (2025-12-04 20:00:04)
-
© Rakuten Group, Inc.