2023年02月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

山口県山口市 長沢ガーデンの長沢定食
○長沢定食牛焼肉、鯛とマグロの刺身、野菜の煮物、おからの煮物、サラダ、ご飯、味噌汁、香の物牛焼肉とサラダ。デザートのオレンジ付き。さっぱりとした鯛とマグロの刺身。国道2号線沿い、長沢池のほとりにある旅館&ドライブイン。長く営業を続けているようで、全体的に昭和レトロな雰囲気が漂う。レストラン、売店、温泉、宿泊施設の全てが揃っており、ドライバーや旅人にとってはまさしく、最高の休息地といえるだろう。今回いただいた長沢定食は、長沢ガーデンオリジナルの定食。肉、魚、野菜の三拍子が揃った、ボリューム満点のメニューだった。また、他の定食は全てお皿に盛られていたのに対し、なぜかこれだけは大きな弁当箱に盛られていた。国道2号線沿いを走っていると目に留まる、いかにもサービスエリアといった感じの大きな看板が目印。小さな旅館が隣接しており、宿泊ができるようになっている。価格も3500円~と安価。温泉の日帰り入浴もでき、入浴料は大人400円、小人160円(レストランで食事をすると割引あり)。店内は昭和のレトロな雰囲気が漂う。ちなみに売店では長沢ガーデンオリジナルのグッズも販売されている。食堂入り口にズラリと並ぶ食品サンプル。食欲をそそる。メニューも非常に豊富で、定食、寿司、鍋物、喫茶メニューまである。うどん・そばのレトロ自販機もあり。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.02.27
コメント(0)
-

岡山県岡山市 『備前国総社宮』
備前国百二十八社の御祭神が祀られている神社。市指定文化財に指定されている。御祭神は大己貴命(オオナムチノミコト)、須世理姫命(スセリビメノミコト)、神祇官八神。加えて備前国128社の御祭神が祀られている。大己貴命は大国主命(オオクニヌシノミコト)の別名で広く知られ、病気平癒、商売繁盛、縁結びの神として信仰されている。須世理姫命は、大己貴命が素盞嗚命(スサノオノミコト)から受けた様々な試練を助けたことから、厄災削除の御利益があると言われている。後に大己貴命と須世理姫命は結婚したことから、夫婦円満、家内安全、子孫繁栄の御利益があるとも言われている。また、備前国128社の御祭神が祀られており、当社にお参りするとこれらの神すべてに参拝したことになり、様々な御利益を得られると言われている。総社というのは、国司が巡拝しなければならない各神社が、国内各地に分散していて不便であるため、国内の御祭神を国府の近接一ヵ所に合祀し、参拝を略式化するために設けられたもの。当社はその内の備前国の総社に当たる。創建の時期は定かでないが、平安時代に成立したと推定されている。律令制崩壊後は、氏神として地域の信仰を集めた。1992年(平成4年)に放火の被害に遭い、社殿が焼失。2010年(平成22年)に本殿が、2015年(平成27年)に拝殿が再建され現在に至る。元日に歳旦祭、2月に節分祭、4月に春季例大祭、8月に夏越大祓祭、10月に秋季例大祭、大晦日に晦日大祓祭が行われている。石鳥居。参道。訪れた時は正月で、参道脇には露店が並んでいた。社務所。随身門。今上天皇聖蹟の碑。手水鉢。非常にこじんまりとしたもの。摂末社。舞台。例大祭の時にここで獅子舞の奉納や、和太鼓の演舞が行われている。拝殿。木造の社殿で、2015年(平成27年)に再建されたもの。本殿。2010年(平成22年)に再建されたもの。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.02.24
コメント(0)
-

岡山県岡山市 『吉備津彦神社』
古くから神の山として崇敬されている吉備中山の北東麓に鎮座し、吉備津神社と同じく大吉備津彦命を祀る神社。「朝日の宮」とも称される。本殿は県指定重要文化財に指定されている。御祭神は大吉備津日子命(オオキビツヒコノミコト)。厄除け、五穀豊穣、武運長久、延命長寿の御利益があると言われている。相殿に吉備津彦命(キビツヒコノミコト)、孝霊天皇、孝元天皇、彦刺肩別命(ヒコサシカタワケノミコト)など大吉備津日子命の子孫や兄弟、金山彦大神(カナヤマヒコノオオカミ)、大山咋大神(オオヤマクイノオオカミ)が祀られている。吉備中山の北西麓に位置する吉備津神社と同じく、温羅と呼ばれる鬼神を退治し、吉備国を平定・統治した大吉備津日子命を主祭神としており、吉備国を治めた屋敷跡に社殿が建てられたのが当社の始まりと言われている。843年(承知10年)には一品爵位を贈られ、一品宮、一品吉備津彦大明神とも呼ばれ、吉備国が分割された後は備前国一宮として崇敬された。江戸時代に入ると岡山藩主池田氏から篤い信仰を受け、1677年(延宝5年)に300石の社領を寄進、1697年(元禄10年)に社殿が再建された。1930年(昭和5年)に不慮の火災で随神門と本殿以外が全て焼失し、1936年(昭和11年)に社殿が再建され現在に至る。年間を通して様々な祭事が行われているが、中でも毎年8月2日、3日に行われる御田植祭が有名で、岡山県指定重要無形文化財に指定されている。正面参道の石鳥居。鶴島神社。神池の北側に浮かぶ鶴島にある。御祭神は住吉神(底筒男命(ソコツツオノミコト)、中筒男命(ナカツツオノミコト)、表筒男命(ウワツツオノミコト)、神功皇后)。亀島神社。神池の南側に浮かぶ亀島にある。御祭神は市寸島比売命(イチキシマヒメノミコト)。随神門。1697年(元禄10年)に備前岡山藩2代目藩主で、後楽園を造営したことでも知られる池田綱政公が造営したもの。安政の大石燈籠。高さは11mあり、笠石は8畳の広さを持つ、日本一大きな石灯籠。1830年(文政13年)から1857年(安政4年)に渡って寄付が寄せられ、1859年(安政6年)に天下泰平、国家安全を祈願して建立された。御神木の平安杉。樹齢は1000年以上。1930年(昭和5年)に火災が起こった時に火にあぶられ、老朽化が進み倒木が懸念されていたが、多額の寄付が集まり、2004年(平成16年)に治療が行われた。拝殿・祭文殿。社殿は夏至の日に正面鳥居から日が差し込み、祭文殿の鏡に当たる造りになっている。そのため、「朝日の宮」と呼ばれている。本殿、渡殿。県指定重要文化財に指定されている。檜皮葺の流造で、現在の本殿は1668年(寛文8年)に備前岡山藩主の池田光政公が造営に着手、1697年(元禄10年)に完成したもの。稲荷神社。御祭神は倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)。五穀豊穣、商売繁盛の神として知られる。卜方神社。備前岡山藩主の祖である池田伸輝公と池田輝政公の霊神を祀る。祖霊社、牛馬神社、十柱神社、温羅神社。温羅神社は大吉備津日子命が退治した、温羅の和魂を祀る。7つの末社。伊勢宮、幸神社、矢喰神社など。天満宮。御祭神は菅原道真公。901年(延喜元年)に道真公が大宰府に赴く途中に当社に寄られたという由縁があり、学問の神として境内に天満神社が建立された。社殿の老朽化により1909年(明治42年)以降は末社に合祀されていたが、2005年(平成17年)に現在の場所に再建された。子安神社。御祭神は伊邪那岐命(イザナギノミコト)、伊邪那美命(イザナミノミコト)、木花佐久夜姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)、玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)。縁結び、子授け、安産、育児、家庭円満の神として信仰されている。慶長年間に備前岡山藩の池田利隆公が子宝に恵まれなかった際、ここで祈願後に光政公が誕生したという逸話が残っている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.02.21
コメント(0)
-

岡山県岡山市 『吉備津神社』
吉備中山の北西麓に鎮座し、桃太郎伝説の原型になったとされる、吉備津彦命と温羅にまつわる伝説が残る神社。本殿、拝殿は国宝に指定されており、南随神門、北随神門、御釜殿は国指定重要文化財に指定されている。主祭神は大吉備津彦命(オオキビツヒコノミコト)。この地で蛮行を重ねていた温羅を退治した後、吉備国の人々の為に殖産を教え仁政を施し、281歳まで生きたことから、必勝祈願、学業成就、延命長寿などの御利益がある。また、相殿神として御友別命(ミトモワケノミコト)、倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトヒモモソヒメノミコト)など、大吉備津彦命の子孫や兄弟も祀られている。かつて恐ろしい風貌の巨漢で、百済の国の王子とされる温羅がこの地に渡来し、城を構えて蛮行を重ね人々を困らせていたという。そこで大和朝廷は温羅退治のために、孝霊天皇の子で四道将軍の1人の大吉備津彦命を吉備国に派遣。大吉備津彦命は吉備の中山に本陣を張り、温羅と激しい戦いを繰り広げ、ついに退治した。これらの伝説が、おとぎ話「桃太郎」の原型になったと言われている。大吉備津彦命はその後吉備国を統治し、281歳で亡くなり吉備の中山に葬られたという。創建の年代は不詳。社伝によると、仁徳天皇が吉備国に行幸された際に、大吉備津彦命の業績を聴かれ、その徳を偲び吉備国の祖神として崇め奉斎されたと伝えられる。古くは「吉備津彦神社」と称されていた。朝廷からの篤い崇敬を受け、927年(延長5年)成立の延喜式神名帳では明神大社に列し、940年(天慶3年)には最高の一品の神階を贈られた。かつては神仏習合の場だったが、江戸時代中期に分離。明治維新後に「吉備津神社」に改称し、現在に至る。毎月1日に月旦祭、13日に月次祭が行われており、その他にも毎月様々な祭事・神事が行われている。また、釜の鳴る音で吉凶を占う、古くから伝わる独特な神事「鳴釜神事」も金曜日以外に行われている。手水舎。初詣に参拝。多くの参拝客で賑わっていた。矢置石。大吉備津彦命が温羅と戦う時に、温羅に向けて放つ矢を置いたと伝えられる大きな石。毎年正月三日にここで矢立の神事が行われている。北随神門。北の参道に位置している。1542年(天文11年)に再建。国指定重要文化財に指定されている。本殿・拝殿。どちらも国宝に指定されている。現在の建物は室町時代の1390年(明徳元年)に足利義満が造営を開始し、1425年(応永32年)に再建されたもの。建築様式は、入母屋造の屋根を前後に2つ並べた比翼入母屋造と呼ばれるもので、全国的に見てもここだけの様式であることから、吉備津造とも呼ばれている。授与所。神札や様々な種類のお守りなど、授与品が揃っている。隣にある五角形の建物は桃太郎おみくじが引けるところで、種類もよろこびみくじ、こどもみくじなど5種類ある。社務所。祈祷殿。一童社。御祭神は菅原神、天鈿女神(アメノウズメノカミ)。学問、芸術の守護神として信仰されており、受験の合格祈願に参拝している人が多かった。南随神門。廻廊の途中に位置している。1357年(延文2年)に再建されたもので、吉備津神社の中では最古の建造物。国指定重要文化財に指定されている。廻廊。1579年(天正7年)に再建されたもの。全長360mもあり、本殿・拝殿から本宮社まで一直線に伸びている。えびす宮。商売繁盛、家業繁栄の神様を祀る。正月9日、10日、11日にはえびす祭が行われている。岩山宮。吉備中山の中腹にあり、吉備国の地主神を祀る。周辺はあじさい園となっており、6月下旬になると1500株の色とりどりなアジサイが辺りを彩る。祖霊社。祖先神を祀る。水子慰霊社。幼くして亡くなってしまった子供の御霊を祀る。三社宮。左から春日宮、大神宮、八幡宮。周辺は梅林となっている。瀧祭神社。吉備中山を流れる細谷川のほとりにある。宇賀神社。神池の中央の島に位置し、吉備津神社最古の稲荷神を祀っている。本宮社。廻廊の南端に位置する。御祭神は孝霊天皇、吉備武彦命(キビノタケヒコノミコト)、百田弓矢比売命(モモタユミヤヒメノミコト)。いずれも大吉備津彦命の親族の神にあたる。安産、育児の神様として信仰されている。御竃殿。古くから行われている神事「鳴釜神事」が行われている場所で、大吉備津彦命が退治した温羅を祀る場所とも伝えられる。伝えによると、大吉備津彦命は温羅を退治し首をはねたが、それでも温羅は大きな唸り声を上げ続けたという。髑髏になっても声は止まず、ついにはこの地に埋めてしまったが、それでも唸り声は止むことなく周辺に響き渡ったという。大吉備津彦命が困り果てていた時、夢の中に温羅の霊が現れ、ここで竈を使った神事を行うよう告げる。そして実際にその神事を行ったところ、唸り声は治まり平和が訪れた。これが鳴釜神事の起こりとされる。神事の内容は、釜の上にせいろを置いてその中に玄米を入れ、蓋を乗せた状態で釜を焚いた時になる音の大小長短で吉凶を占うというもの。なお、吉凶であるかどうかはその音を聴いた本人が判断するようになっている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.02.20
コメント(0)
-

小倉城カラフルナイト
撮影地:福岡県北九州市 『小倉城、小倉城庭園』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.02.14
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 金沢旅行 4日目
- (2025-11-12 17:42:15)
-
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-
-
-
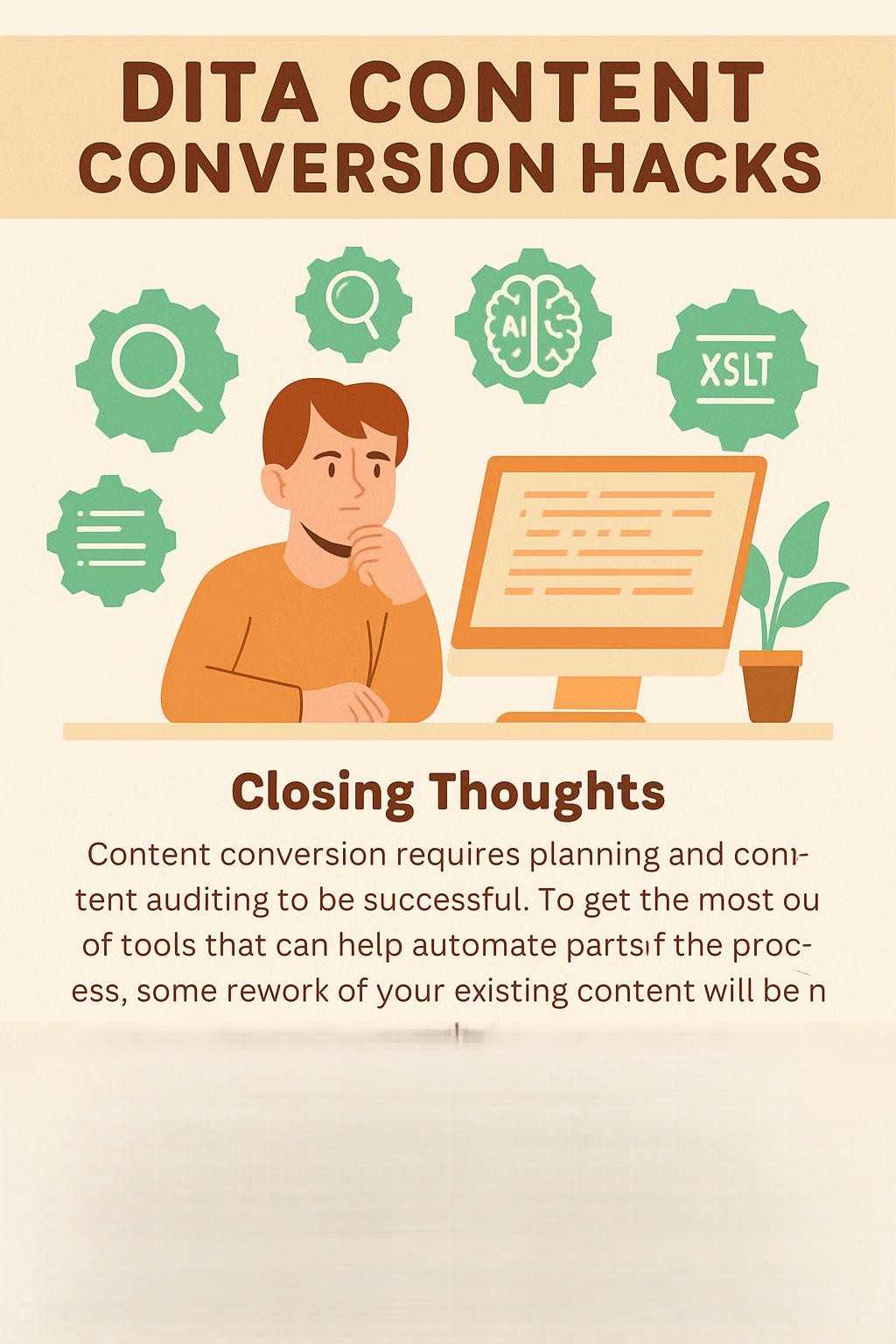
- 英語のお勉強日記
- DITAコンテンツ変換の裏技(DITA Con…
- (2025-11-14 15:01:12)
-







