2023年10月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

夕方の秋桜
撮影地:福岡県田川郡大任町 『道の駅 おおとう桜街道』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.31
コメント(0)
-

宮崎県延岡市 辛麺屋 桝元本店の元祖辛麺
○元祖辛麺元祖辛麺(15辛)まるで地獄のような15辛のスープ。麺はこんにゃく麺、中華麺、ちぢれ麺、うどん麺から選べるようになっており、今回はこんにゃく麺を選んだ。延岡市にある、九州を中心に全国に店舗を展開する辛麺屋桝元の本店で、宮崎のB級グルメである宮崎辛麺の発祥の地。桝元の辛麺は唐辛子、ニンニクの効いた秘伝のスープにニラ、卵、ひき肉の具材を加えたもので、辛くて美味しく、やみつきなるような味わい。スープの辛さは0辛~30辛まで選べるようになっており、3辛で中辛、15辛で激辛の度合い。今回は初見ながら30辛中真ん中の15辛を注文してみた。めちゃくちゃ辛かったが、無事完食。食べきった頃には体中が汗だくになっていた。店舗の外観。「桝元」と書かれた大きな看板が掛けられ、辛麺発祥の地と書かれた立て札もある。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.26
コメント(0)
-

宮崎県延岡市 『愛宕山展望台』
延岡市中心部に位置する愛宕山の山頂付近にある展望台。そこから見える夜景は日本夜景遺産、夜景100選に認定されている。愛宕山は標高251mの小さな山で、古くは「笠沙山」と呼ばれていた。古事記によると天孫ことニニギノミコトとコノハナサクヤヒメが出逢い、結ばれた場所とも言われ、山麓には愛宕神社をはじめとしたいくつかの神社が鎮座する。元々は女人禁制の霊山とされていたが、江戸時代に徳川家康のひ孫で延岡藩主夫人の日向御前が禁制を破って登ったという逸話が残る。山頂付近の展望台は約300°の大パノラマを展望でき、特に夜の市街地の光景は絶景。ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメが出逢った地であることから、出逢いの聖地として注目を集め、出会いの鐘や錠かけモニュメントなども設置されている。出逢いの聖地の碑。公園。錠かけモニュメント。片方のモニュメントには、ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの小さな像が上部にある(何者かがこっちにも南京錠をかけているが…)。出逢いの鐘。ちなみに、階段から出逢いの鐘まで続く道は蛍石が埋め込まれていて、夜になるとかすかに光り輝く。愛宕山展望台。3階建ての構造で、延岡の街を約300°見渡せるようになっている。展望台から見た夕暮れ時の延岡市の景色。延岡の街並みに日向灘、大崩山や行縢山も見える。天気が良いと、海の向こうの四国地方も見える。ちなみに2枚目の奥の方に見える祝子川は、山幸彦が生まれた時にコノハナサクヤヒメが川の水を産湯に使ったという伝えが残る。夜。出逢いの聖地延岡の立て看板。展望台から見た夜景。住宅街の灯りや夜の工業地帯が、無数に散りばめられた星のように煌めく。条件が良ければ、満月の光が日向灘の大海原に反射して"月の道"が浮かび上がり、夜景をより幻想的にする。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.25
コメント(0)
-

宮崎県延岡市 『港神社』
五ヶ瀬川・北川の河口付近、延岡港の対岸に鎮座する小さな神社。御祭神は底筒男命(ソコツツオノミコト)、中筒男命(ナカツツオノミコト)、表筒男命(ウワツツオノミコト)。所謂住吉三神。海の神様として広く知られ、海上安全の御利益がある。1700年(元禄13年)に延岡藩主三浦明敬公がが東海神社の場外末社として、住吉三神の分霊を勧請したことに始まる。地元の航海安全の神様として大事にされており、年明けの乗り初めの時に、漁船は大漁や安全を祈願して出港するそう。青い鳥居の神社として知られる。SNSを中心にテレビなどでも紹介され、最近はSNS映えのスポットとして若い人も訪れている。満潮時には神社に近づけなくなるので注意。海岸沿いには車を停められるスペースがいくつかあり、港神社のある海の方に降りる道も同じようにいくつかある。海沿いに歩いて行くと、青い鳥居の神社が見えてくる。港神社の青い鳥居。元々は色が塗られていなかったそうだが、海の神様を祀る神社ということで後に青色に塗られたんだとか。現在の鳥居は2020年(令和2年)に新築されたもの。全国的に見ても珍しい色の鳥居なのだが、宮崎県西都市の速開都比売神社にも同じ青色の鳥居があったりする。石段の鳥居は水色で、稲荷神社のように連なっている。こじんまりとした拝殿・本殿。拝殿右手にあるソテツ。鳥居新築記念の碑。鳥居と同じく青色になっている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.24
コメント(0)
-

【観光スポット紹介】九州の紅葉名所
10月下旬。肌寒くなってくると同時に、モミジの葉も色付き始め、紅葉シーズンも間近。北部日本では既に見頃を迎えているところもあるそう。と言うことで今回は、自分が行った九州の紅葉スポットの中でも、素晴らしいと思ったところをピックアップ。有名なスポットから穴場まで、紹介したいと思います。ちなみに宮崎県と鹿児島県はまだない。ごめんなさい。○福岡県朝倉市 『秋月』"筑前の小京都で過ごす秋"秋月城の城下町の景観が残り、筑前の小京都とも呼ばれる秋月。中でも秋月城跡黒門周辺はカエデの木が沢山あり、秋一番の見どころとなっている。見頃:11月中旬~下旬詳細はこちら→福岡県朝倉市 『秋月(秋)』○福岡県福岡市 『曲渕ダムパーク』"福岡市郊外のモミジ狩りスポット"曲渕ダムの真下にある公園。福岡市きっての穴場の紅葉スポット。園内の紅葉も綺麗だが、国道から公園までの道まで続く、燃えるように色付いたモミジの並木も素晴らしい。見頃:11月中旬詳細はこちら→福岡県福岡市 『曲渕ダムパーク』○佐賀県武雄市 『御船山楽園』"水面に写る紅葉と、圧巻のライトアップ"御船山の麓にある、国の登録記念物にも登録された日本庭園。園内の鏡池を囲むようにしてモミジの木が連なり、池が水鏡となって紅葉景色を写し出す。夜間はライトアップが行われ、圧巻の景色に。見頃:11月中旬~下旬詳細はこちら→佐賀県武雄市 『御船山楽園(秋、昼)』、佐賀県武雄市 『御船山楽園(秋、夜)』○佐賀県鳥栖市 『大山祇神社』"わずか2日間だけ映し出される、幻想的な紅葉夜景"鳥栖市の郊外にある神社で、隠れた紅葉名所。境内はイチョウやモミジの木が群生していて、11月の2日間(2023年は11月11日と11月12日)だけ夜間にライトアップがされ、大変幻想的な光景となる。見頃:11月上旬~中旬詳細はこちら→佐賀県鳥栖市 『大山祇神社(鳥栖市)』○長崎県雲仙市 『雲仙仁田峠』"山肌一面に染まる感動の秋景色"雲仙を代表する景勝地の一つ。駐車場から妙見岳の頂上まで雲仙ロープウェイが運航しており、ゴンドラから見える山肌はまるで珊瑚礁のように鮮やかで美しい。登った先の視界が開けた場所で見える、紅葉の大パノラマも必見。見頃:10月下旬~11月上旬詳細はこちら→長崎県雲仙市 『雲仙仁田峠』○大分県玖珠郡九重町 『九重"夢"大吊橋』"秋色に染まる九酔渓を空中散歩"鳴子川渓谷に架かる、日本一の高さを誇る歩行者専用橋。空中散歩を楽しみながら、日本の滝百選に選ばれた震動の滝と共に、九酔渓の秋の絶景を一望できるようになっている。見頃:11月上旬~中旬詳細はこちら→大分県玖珠郡九重町 『九重"夢"大吊橋』○大分県豊前高田市 『富貴寺』"九州最古の木造建築×イチョウの絨毯"九州最古の木造建築で、国宝にも指定された大堂がある天台宗の寺院。仁王門の燃えるようなモミジの紅葉に始まり、大堂の周辺はモミジの葉で埋め尽くされ、まさにイチョウの絨毯に。見頃:11月中旬~下旬詳細はこちら→大分県豊前高田市 『富貴寺』○熊本県阿蘇郡南小国町 『マゼノ渓谷』"秋と春の2つの期間だけ開放されている、隠れた紅葉名所"秋と春の数日間だけ開放されている、秘密の渓谷。モミジの木々に包まれた渓谷で、人の手がほとんど付けられていない自然の中、紅葉狩りを満喫できる。マゼノ滝周辺の紅葉もコントラストが美しい。見頃:10月下旬~11月上旬詳細はこちら→熊本県阿蘇郡南小国町 『マゼノ渓谷』○熊本県阿蘇郡小国町 『遊水峡』"一枚岩の渓谷で紅葉狩り"マゼノ渓谷と同じく阿蘇郡の紅葉スポット。巨大な一枚岩の渓流沿いをモミジの木が彩り、遊歩道は見事なモミジのトンネルになっている。渓谷の一番奥にあるかっぱ滝の目の前にある岩もみじも必見。見頃:11月上旬~中旬詳細はこちら→熊本県阿蘇郡小国町 『遊水峡』○熊本県八代市 『五家荘』"八代の秘境で様々な秋景色を楽しむ"八代市の東部にある、滝や渓谷が見られる秘境。五家荘までの道では車窓から美しい秋の山が見え、せんだん轟の滝、樅木の吊橋、梅の木轟公園吊橋、五家荘平家の里などの見どころがあり、様々な秋景色を一度に楽しめるようになっている。紅葉期間中は道の一部が一方通行・通行止めになっていることがあるので注意。見頃:11月上旬~中旬詳細はこちら→熊本県八代市 『五家荘』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.22
コメント(0)
-

宮崎県延岡市 『行縢神社』
日本武尊にまつわる伝説が残る、行縢山の麓に鎮座する神社。御祭神は伊弉冉命(イザナミノミコト)、事解男命(コトサカオノミコト)、速玉男命(ハヤタマオノミコト)で、3柱の神を総じて行縢嶽三所大権現と号する。他に日本武尊(ヤマトタケルノミコト)をはじめとする23柱の神を合祀する。鎮座する行縢山は古代より神の宿る山として信仰されており、雄岳と雌岳の主祭神とされる面足命(オモダルノミコト)と惶根命(カンコネノミコト)のご託宣により、718年(養老2年)に紀州(和歌山県)の熊野大権現を御勧請し社殿が建立される。日向国内では有名な神社だったそうで、代々藩主の崇敬が篤かったと言われる。1164年(長寛2年)には鎮西八郎為朝が当社に参篭し、武運長久を祈願しており、社域には為朝腰掛石が保存されている。毎年11月19日に例祭が行われている。一の鳥居。かなり新しいもの。行縢山登山口。登山ルートは他にも複数あり。二の鳥居。さざれ石。国歌「君が代」の歌詞にもある、長い年月を経て小石が固まり、大きな岩になったもの。参道。参道脇にある鯉が泳ぐ池。手水舎。銭洗い所。賽銭を神域の清水で清めるところ。御神門。御鎮座千三百年を記念して、2018年(平成30年)に竣工された。拝殿。正面や柱には、鳳凰や獅子などの立派な彫刻が彫られている。独特な容姿の狛犬。普通の狛犬と並ぶようにして配置されている。ポーズは普通の狛犬と同じだが、顔だけがまるで猿のようになっている。どちらも明治時代に造られたもの。本殿。軒下には立派な龍の彫刻が彫られている。授与所。鎮西社。御祭神は源為朝公(鎮西八郎為朝)。平安時代末期の武将で、強弓の使い手で剛力無双と謳われた。平安時代末期に当社に参篭し、武運長久を祈願したという伝えが残る。門守社。バクチノキ。樹高35m、樹齢200年。夫婦杉。行縢神社の御神木。根元が一体となっており、神様の宿り木として祀られてきた。推定樹齢300年。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.18
コメント(0)
-

宮崎県延岡市 『行縢の滝』
延岡市の西部に位置する行縢山に懸かる滝。日本の滝百選の一つ。落差は77mで、幅は30m。行縢山の雄岳と雌岳の間、垂直に切り立った崖をさらさらと静かに流れ落ちるのが特徴。その姿から「布引きの滝」と呼ばれている他、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の故事から「矢筈の滝」とも呼ばれる。水量は少なく、時期によっては水が流れ落ちていないことがある。滝までは行縢山を登っていく必要があり、最短ルートの行縢の滝駐車場からのルートであっても、高低差のある山道を片道で30分以上登っていく必要があるため、健脚向け。行縢山の山麓にある宮崎ひでじビール。宮崎県のクラフトビール「ひでじビール」の醸造所。ひでじビールの販売は勿論、BBQビアテラスもあり(冬季は除く)。行縢山の雄岳と雌岳の間、視界の開けた場所に行縢の滝があり、宮崎ひでじビールの場所からも、流れ落ちている様子が観測できる。行縢の滝駐車場。ここから案内板に従って、行縢の滝目指して山道を登っていく。自然豊かな山道。澄みわたる行縢山の渓流。道中にある滝見橋。そこから、行縢の滝の上部が見えるようになっている。滝見橋を渡れば、行縢の滝まであと少し。駐車場から山道を歩いて30分、ようやく滝に到着。疲れたけども感激。滝の全景。ほぼ90°垂直に切り立った崖を、少ない水量でさらさらと水が流れ落ちている。間近から見れるようになっており、滝のスケールは写真1枚に収められないほど大きい。足場が少し滑りやすくなっているので、観測する際は足元に注意を。岩肌に描かれた水の流れは、一部がまるで魚の鱗のようになっている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.16
コメント(0)
-

滋賀県大津市 近江ちゃんぽんビエラ大津店の近江ちゃんぽんと肉汁餃子
○近江ちゃんぽんと肉汁餃子近江ちゃんぽん、肉汁餃子野菜たっぷりの近江ちゃんぽん。一口食べると、じゅわっと肉汁が溢れ出る肉汁餃子。大津駅にある、近江ちゃんぽん発祥の店。ちゃんぽんと言えば、九州の長崎ちゃんぽんを思い浮かべる人が多いと思うが、滋賀県の近江ちゃんぽんはそれとは全くの別物。まず、スープは豚骨でなく、魚介系のダシに薄口醤油で仕上げた和風のものになっていて、あっさりとした味わいが特徴。具は魚介類を使用せず、様々な種類の野菜と豚肉だけ。外見こそまさしく、これぞちゃんぽんそのものだ!といったところだが、九州在住で長らく長崎ちゃんぽんばかり食べてきた自分にとっては、全く味わったことの無い新鮮な味だった。ちゃんぽんの新境地、ここに開かれり。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.09
コメント(0)
-

滋賀県大津市 『近江神宮』
近江大津京跡に鎮座する、かるたの聖地として知られる神社。境内の多くの建造物が登録有形文化財に登録されている。御祭神は天智天皇。舒明天皇の第二皇子で、中大兄皇子の名で広く知られ、大化の改新を行ったことでも有名。667年(天智天皇6年)に飛鳥から近江大津宮に遷都した後は、日本の憲法の源となる近江令の制定、学校制度の創始、戸籍制度の制定、土地制度の改革などを行った。また、中大兄皇子の時代には漏刻を作り、時報を始めたとされている。これらの事績から、時の祖神、開運・導きの大神、文化・学業・産業の守護神として崇敬されている。滋賀県、大津国の発展は飛鳥から近江大津宮に遷都されたことに始まるとして、1897年(明治30年)頃に滋賀県民の間で天智天皇を祀る神社の創建運動が始まる。1938年(昭和13年)に昭和天皇の御聴許を賜り、皇紀2600年に相当する1940年(昭和15年)に創建。日本の神社の歴史の中では比較的新しい部類に入る。小倉百人一首の第1首目「秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」を天智天皇が詠まれたことに因み、毎年1月に競技かるたのチャンピオンを決める名人位・クイーン位決定戦が開催されている。この他にも数多のかるた大会が開催されており、かるたの聖地としても知られ、漫画・アニメ・映画作品「ちはやふる」の舞台にもなっている。大津宮に遷都がされた4月20日に例祭が行われている。他にも1月上中旬の日曜日にかるた祭、6月10日(時の記念日)に漏刻祭、7月7日に燃水祭、8月に献書祭、11月7日に御鎮座記念祭、12月1日に初穂講大祭が行われている。一の鳥居。木造の大きな鳥居で、神額はない。正面右手にある社号標は近江神宮奉賛会初代会長だった近衛文麿元首相の筆によるもの。緑に包まれた参道を進み、石段を登った先に二の鳥居がある。手水舎。楼門。朱塗りで、青もみじとのコントラストが美しかった。楼門の両廻廊に掛けられている小倉百人一首かるたの額。時計館宝物館。日本最古級の懐中時計や和時計など古今東西の時計の他に、奉納された絵画や陶器なども展示されている。入館料は大人300円、小中学生150円(団体割引あり)。時計館宝物館のそばにある2基の日時計。漏刻。三層に分かれた枡から漏れ落ちる水の量から時間を測定する、日本最初の時計(レプリカ)。日本書紀によると天智天皇が初めて造られた時計と言われ、近江朝から平安朝末期まで全国の国府や鎮守府に置かれていた。古代火時計。約4000年前に中国で使われていた時計。龍の背に等間隔14個の銅球を吊り下げ、その糸の下を線香の火が燃え進んで糸を焼き落として銅球が落下し、下に設けられたドラが鳴って時間を知らせるというもの。自動車清祓所。1890年(明治23年)に建築された旧大津地方裁判所の本館車寄だったもので、1971年(昭和46年)に全館取り壊しが行われる際に、この地に移築された。神座殿。結婚式や祈祷が行われる他、かるた祭などの祭典も行われている。社務所。外拝殿。登録有形文化財に登録されている。1940年(昭和15年)建立。内拝殿。後方に本殿が見え、本殿の造りは「近江造」と呼ばれる独特なもの。どちらも1940年(昭和15年)建立で、登録有形文化財に登録されている。外拝殿の廻廊。轟太鼓。昭和天皇御在位五十年の年に、有志1000名の浄財を以って奉祝寄進されたもの。栖松遙拝殿。有栖川宮家の祭祀を継承された高松宮宣仁親王が、宮廷内に創建した御霊屋。高松宮家廃止に伴い、2006年(平成18年)に高松宮家と縁の深かった近江神宮に移されることとなり、有栖川宮家の"栖"と高松宮家の"松"を取って栖松遙拝殿と名付けられた。神座殿中庭に掲げられているかるた額。中村北潮氏揮毫のもので、百人一首の下の句だけ書かれている。近江勧学館。一般財団法人天智聖徳文教財団によって創設された研修センター。林間学校やかるた関連行事が行われ、漫画・アニメ・映画作品「ちはやふる」の資料が展示されている他、名物のカルタくじも販引ける(1回300円)。近江時計眼鏡宝飾専門学校。1969年(昭和18年)に創設され、時計・眼鏡・宝飾の技術を合わせ学べる唯一の学校。善庵。境内にあるそば処。創建当時から参拝者休憩所として建てられた建物で、登録有形文化財に登録されている。予約制だそうで、そば粉十割の本格手打ちそば「宮そば十割」が名物。天智天皇御製の百人一首の碑。小倉百人一首の第1首目の句である"秋の田の刈穂の庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつゝ"が記されている。他にも、境内には弘文天皇、松尾芭蕉、春日真木子など13の歌碑、句碑がある。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.07
コメント(0)
-

島根県松江市 『八重垣神社』
素盞嗚尊と稲田姫にまつわる伝説が残り、縁結びの神社として信仰されている神社。板絵著色神像(本殿板壁画)3面が重要文化財に指定されている。御祭神は素盞嗚尊(スサノオノミコト)、稲田姫命(イナダヒメノミコト)、大己貴命(オオアナムチノミコト、大国主命)、青幡佐久佐日古命(アオハタサクサヒコノミコト、八重垣神社宮司の先祖)。素盞嗚尊と稲田姫命がこの地で結ばれたという伝説が残り、また大己貴命は縁結びの神様として知られ、縁結び、恋愛成就、子孫繁栄、安産、夫婦円満の御利益がある。素盞嗚尊と稲田姫命の、八岐大蛇退治にまつわる伝説が残る神社として知られる。高天原から斐の川上に降り立った素盞嗚尊は老夫婦(脚摩乳命、手摩乳命)とその娘の稲田姫命が泣いている様子を見て、訳を聞き、八岐大蛇を退治することを決意。その際、素盞嗚尊は佐久佐女の森に大杉を中心に八重垣をお造りになり、そこに稲田姫命をお隠しになったという。素盞嗚尊が八岐大蛇を退治した後、「八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を」と喜びの歌をうたい、老夫婦の許しを得て結ばれ、この地にお宮を造ったのが始まりと言われている。1872年(明治5年)に境内社の佐久佐神社を合祀して佐久佐神社と称し、1878年(明治11年)に八重垣神社に改称して現在に至る。同県の出雲大社と共に縁結び、恋愛成就のパワースポットとして知られ、境内には縁結びにまつわるスポットが見られる。中でも、奥の院の鏡の池で占い用紙を浮かべてその上に硬貨を乗せ、紙が沈む早さやどこに流れていくかで縁を占う「鏡の池の縁占い(恋占い)」が有名。毎年10月20日に例祭が行われ、12月15日に新嘗祭・還幸祭が行われている。また、5月3日には素盞嗚尊が八岐大蛇を退治する際に、稲田姫命をお隠しになられたという社伝にちなんで行われる身隠神事があり、本殿から奥の院の夫婦杉に向かって神輿による神幸三列が行われる。境外にある夫婦椿。連理玉椿とも呼ばれ、昔稲田姫命が二本の椿の枝をお立てになられ、それが芽を吹き出して一心同体の椿になったんだとか。愛の象徴と言われている他、東京資生堂がこの木を神聖視し、発展を遂げたことから、美容調整の御神徳があるそう。木造の鳥居。手水舎。随神門。狛犬。出雲構え型と呼ばれる特殊な構え方をしたもので、松江市神宍道町で産出された来待石を使って造られた。社務所、神札授与所。縁結びの御守や御札、神札などがあり、鏡の池の縁占いに使う用紙もここでもらえる(一枚100円)。拝殿。1964年(昭和39年)に再建されたもの。本殿。江戸中期に再建。参集殿。宝物収蔵庫。893年(寛平5年)に宮廷画家の巨勢金岡が描いた、板絵著色神像(本殿板壁画)3面が保存・公開されている。神社建築史上例のない貴重な壁画とされ、国の重要文化財に指定されている。拝観料は中学生以上200円、小学生100円、幼児以下は無料。三日月の彫られた石灯籠。山神神社。八重垣神社の末社で、明治時代頃に境内に遷された。山、農耕の守護神、夫婦和合の他に、安産、子宝、下半身の病に霊験があり、お社の左手には手作りの男根が供えられている。水の神様を祀り、稲荷神社の倉稲魂命も併せ祀る貴布禰神社と、手摩乳命(稲田姫命の母神)を祀る手摩乳神社。脚摩乳命(稲田姫命の父神)を祀る脚摩乳神社と、天照大御神を祀る伊勢宮。社日社。農耕に関わる五柱の神様(天照大神、倉稲魂命、埴安姫命、少彦名命、大己貴命)を祀る。山陰中央新報社が東宮殿下御結婚記念に建立した碑。素盞嗚尊の歌碑。"八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣つくる その八重垣を"と記されている。八重垣神社の由来とされる和歌で、素盞嗚尊が八岐大蛇を退治して、須賀の地にて詠まれた日本最初の和歌ともいわれる。松尾芭蕉の句碑。"和歌の跡 とふや出雲の 八重霞"と記されている。芭蕉が遠くからこの地に思いを寄せて詠んだ歌と言われている。松平雪川公献碑。"木枯れや 神のみゆきの 山の跡"と記されている。松江藩七代藩主、松平治郷の弟である松平雪川公が詠んだ歌。夫婦椿。乙女椿とも呼ばれている。境外にある連理玉椿が枯れても、境内には同じような二股の椿(夫婦椿)ができると伝えられており、奥の院の方にも同じように夫婦椿がある。少なくとも2回、あの椿の木が枯れたということなのだろうか?奥の院の夫婦椿。子宝椿とも呼ばれている。奥の院、古くは佐久佐女の森と呼ばれた場所へ。素盞嗚尊が八岐大蛇を退治する際に、稲田姫命をお隠しになったと伝えられるところで、緑に包まれた森の中には夫婦杉と呼ばれる2本の杉の巨樹がある。松江の俳人として知られる前田圭史の碑。"笹鳴や 縁占ひの 神の池"と記されている。前田圭史の妻の碑。"そうこうの 妻に悔いなき 初鏡"と記されている。裏面に昭和四十九年金婚記念と記されており、その時に建立されたものといわれる。鏡の池。稲田姫命が佐久佐女の森(奥の院)にお隠れになられた際に、水を飲料水とし、水面に姿を写され美容調整されたと伝えられ、姿見の池とも呼ばれる。稲田姫命の御霊魂が深く浸透していることから、縁結び占いの池として信仰され、「鏡の池の縁占い」が行える。占い用紙に硬貨を乗せて水に浮かべ、用紙の沈む早さや沈む場所で縁を占うというもので、用紙が早く沈む(15分以内)と良縁が早く、遅く沈む(30分以上)と縁が遅いと言われ、また近くで沈むと身近な人と、遠くで沈むと遠方の人と結ばれると言われている。天鏡神社。鏡の池を望む場所に鎮座しており、稲田姫命を祀る。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村
2023.10.04
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-
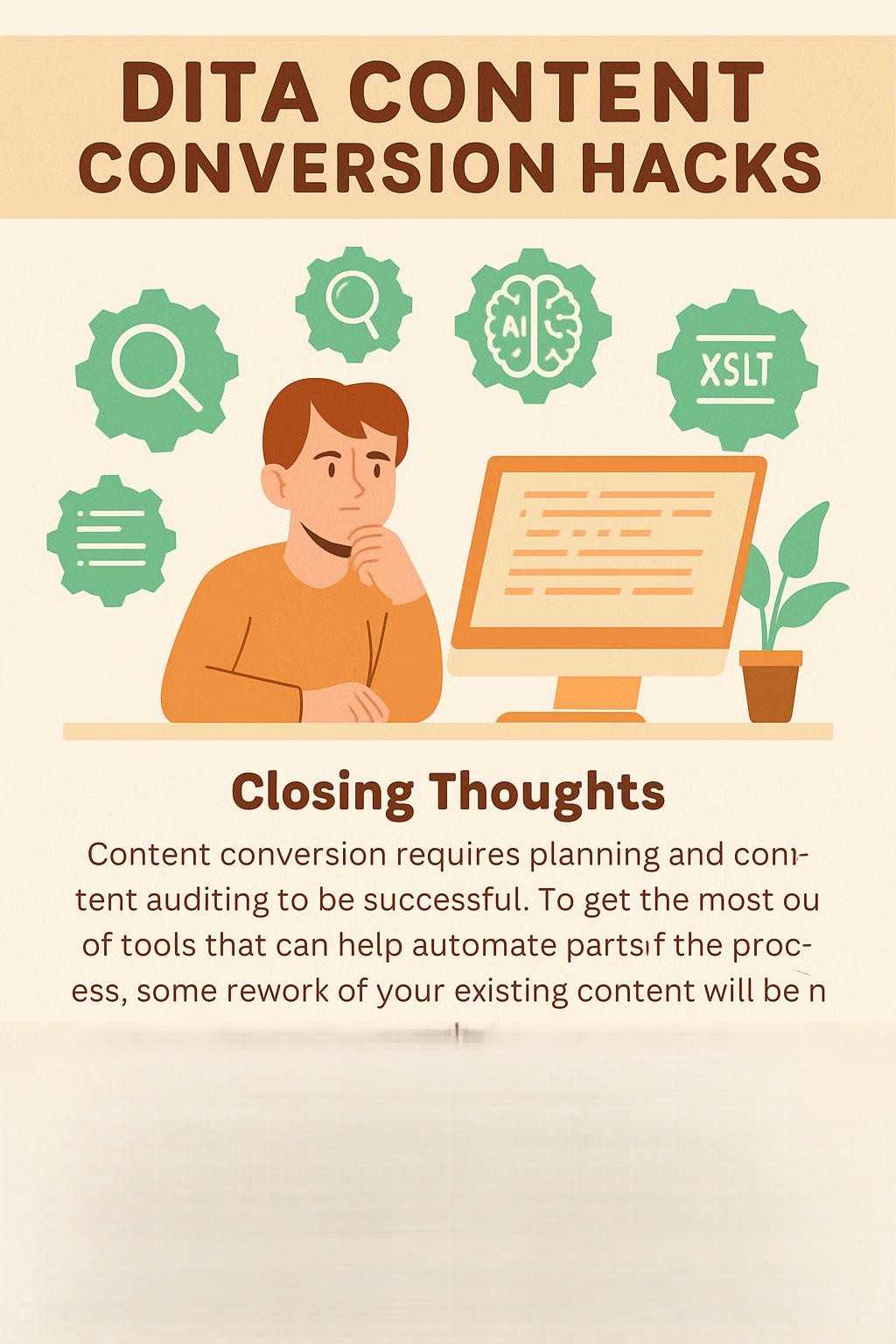
- 英語のお勉強日記
- DITAコンテンツ変換の裏技(DITA Con…
- (2025-11-14 15:01:12)
-
-
-

- 温泉旅館
- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…
- (2025-11-13 06:46:38)
-
-
-

- 海外旅行
- 【イタリア】ヴァチカン市国サン・ピ…
- (2025-11-14 15:00:07)
-







