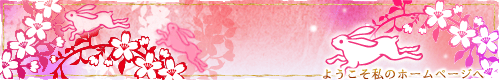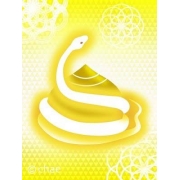キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
・2025年11月
・2025年10月
・2025年09月
・2025年10月
・2025年09月
・2025年08月
・2025年07月
・2025年07月
コメント新着
カテゴリ: 節供・雑節と北海道の季節だより
令和4年2月1日 旧暦新年 謹賀新年
旧暦新年、あけましておめでとうございます。謹んで、新年を年に2回もお祝いできるお慶びを申し上げます。今年は2022年2月1日が旧暦の新年、本来の日本のお正月の日でした。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本年も皆様にとって良い年でありますように🍀
2月4日 こんにちは。昨日2月3日に、冬と春の節目の「節分」。昨日で冬も終わり、今日から春の入り口「立春」の入りました。まだまだ寒いですが今日から早春、春はもうすぐです🍀

画像:無料イラストなら「イラストAC」 作者:ゴートゥーさん より
雑節の一つ「節分」は、季節の節目を表し、本来は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日が節分でした。春の節分と言えば「豆まき」。古代中国の、季節の変わり目に、病疫や邪気を追い祓うための儀式「追儺(ついな)」が元で、平安時代に伝わって来たそうです。春の節分が重視され始めたのは室町時代からで、「春の節分」で二十四節気や七十二候が一巡し、一年の節目となっているからだそう。それが現在に引き継がれているそうです。
節分の日に夜に炒った豆を「鬼は外、福は内」と唱えて炒った豆をまくのは、夜は鬼がやってくる時間。大きな声や音は魔除けになるのだそう。炒った豆は、生の豆だと拾い損ねた豆から目が出ると「邪気が目を出す」し縁起が悪いとされ、発芽を防ぐためだそう。蒔いた豆は、拾い集め、無病息災と、自分の歳と同じ数の福を体に取り込むために自分の年齢の数に1個足した数だけ豆を食べます。因みに、節分の日の夕暮れに柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を刺したものを戸口に立てる風習もあるそうです。
参考・引用資料
・ POCKE.INC お天気.com「2015年2月3日は節分です」より: https://hp.otenki.com/290/
・ こだわりのもり、おいそさのもと PATISSIER morimoto INFORMARION「2022年の節分はいつ?豆まきの由来やお勧めのお菓子も紹介!」より:
https://www.haskapp.co.jp/news/16255/
・ ウィキペディア「節分」より: https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E5%88%86
帰り道のお散歩 写真スケッチ 旧北海道庁本庁舎前 札幌市北三条広場にてスナップ 1月28日 OMデジタルソリューションズ OMD-E-M10 markⅡ

昨日は節分。冬と春の境目でした。節分を過ぎると、季節は暦の上では春の入り口「立春」。季節も一巡し、今日で季節も春に入りました。旧暦で新しい新年が始まるのも、何日か前後はしますがこの頃から。今年は2月1日が旧暦でいう「新年」でした。節分の豆まきは、季節の変わり目には邪気が生じやすいとされることから行われている、中国から平安時代に伝わってきた伝統行事。


節分にまく豆は、「大豆」派と「落花生」派の地域があるようで、北海道・東北・信越地方・鹿児島・宮崎は落花生派。その他の地域は大豆派だそう。私の故郷、静岡県では「大豆」、札幌の大学に来てからは「落花生」を蒔いていました。

北海道では、もともと大豆でしたが、落花生の国内生産が拡大した昭和30~40年代に大豆から落花生に変化したそう。北海道や東北などの雪国では雪の中にまいた大豆を拾う場合、大豆より落花生の方が楽で、後で拾って食べるのにも殻が付いていて衛生的という理由があるそうです。因みに鹿児島や宮崎で落花生を蒔くのは、鹿児島や宮崎は落花生の産地だからだそうです。

雪国や鹿児島・宮崎などは、有名なビールやウイスキー、日本酒、焼酎の産地ですから、落花生をまいた後に豆を拾って、それをおつまみに一杯というのもあったかもしれませんね。まぁ、それもいいではありませんか。体内に入った武漢肺炎のウイルスも、日本の酒のアルコールで消毒、豆まきの豆と柿ピーも付けておつまみに(昔はお米をまいていたそうです)無病息災。そして、新しい春を迎えるのも良いかもしれませんね。
旧暦新年、あけましておめでとうございます。謹んで、新年を年に2回もお祝いできるお慶びを申し上げます。今年は2022年2月1日が旧暦の新年、本来の日本のお正月の日でした。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本年も皆様にとって良い年でありますように🍀
2月4日 こんにちは。昨日2月3日に、冬と春の節目の「節分」。昨日で冬も終わり、今日から春の入り口「立春」の入りました。まだまだ寒いですが今日から早春、春はもうすぐです🍀
昭和25年 歌会始 お題「若草」
天皇陛下御製:もえいずる春のわかくさよろこびの いろをたたへて子らのつむみゆ
皇后陛下御歌:とりがねもとほくきこえてあけそむる みそのうつくし若草のいろ
引用資料 宮内庁ホームページ「皇室に伝わる文化 歌会始 お題一覧」より: https://www.kunaicho.go.jp/culture/utakai/odai.html

画像:無料イラストなら「イラストAC」 作者:ゴートゥーさん より
雑節の一つ「節分」は、季節の節目を表し、本来は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日が節分でした。春の節分と言えば「豆まき」。古代中国の、季節の変わり目に、病疫や邪気を追い祓うための儀式「追儺(ついな)」が元で、平安時代に伝わって来たそうです。春の節分が重視され始めたのは室町時代からで、「春の節分」で二十四節気や七十二候が一巡し、一年の節目となっているからだそう。それが現在に引き継がれているそうです。
節分の日に夜に炒った豆を「鬼は外、福は内」と唱えて炒った豆をまくのは、夜は鬼がやってくる時間。大きな声や音は魔除けになるのだそう。炒った豆は、生の豆だと拾い損ねた豆から目が出ると「邪気が目を出す」し縁起が悪いとされ、発芽を防ぐためだそう。蒔いた豆は、拾い集め、無病息災と、自分の歳と同じ数の福を体に取り込むために自分の年齢の数に1個足した数だけ豆を食べます。因みに、節分の日の夕暮れに柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を刺したものを戸口に立てる風習もあるそうです。
【「節分(晩冬の季語)」の例句】
節分の 辻々雪を 残しけり 鈴木真砂女(すずき まさごじょ)
節分の 何げなき雪 ふりにけり 久保田万太郎(くぼた まんたろう)
引用資料 ジャパノート ー日本の文化と伝統を伝えるブログー「節分の俳句 25選 ー鬼外福内ー」より: https://idea1616.com/setsubun-haiku/
参考・引用資料
・ POCKE.INC お天気.com「2015年2月3日は節分です」より: https://hp.otenki.com/290/
・ こだわりのもり、おいそさのもと PATISSIER morimoto INFORMARION「2022年の節分はいつ?豆まきの由来やお勧めのお菓子も紹介!」より:
https://www.haskapp.co.jp/news/16255/
・ ウィキペディア「節分」より: https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E5%88%86
帰り道のお散歩 写真スケッチ 旧北海道庁本庁舎前 札幌市北三条広場にてスナップ 1月28日 OMデジタルソリューションズ OMD-E-M10 markⅡ

昨日は節分。冬と春の境目でした。節分を過ぎると、季節は暦の上では春の入り口「立春」。季節も一巡し、今日で季節も春に入りました。旧暦で新しい新年が始まるのも、何日か前後はしますがこの頃から。今年は2月1日が旧暦でいう「新年」でした。節分の豆まきは、季節の変わり目には邪気が生じやすいとされることから行われている、中国から平安時代に伝わってきた伝統行事。


節分にまく豆は、「大豆」派と「落花生」派の地域があるようで、北海道・東北・信越地方・鹿児島・宮崎は落花生派。その他の地域は大豆派だそう。私の故郷、静岡県では「大豆」、札幌の大学に来てからは「落花生」を蒔いていました。

北海道では、もともと大豆でしたが、落花生の国内生産が拡大した昭和30~40年代に大豆から落花生に変化したそう。北海道や東北などの雪国では雪の中にまいた大豆を拾う場合、大豆より落花生の方が楽で、後で拾って食べるのにも殻が付いていて衛生的という理由があるそうです。因みに鹿児島や宮崎で落花生を蒔くのは、鹿児島や宮崎は落花生の産地だからだそうです。

雪国や鹿児島・宮崎などは、有名なビールやウイスキー、日本酒、焼酎の産地ですから、落花生をまいた後に豆を拾って、それをおつまみに一杯というのもあったかもしれませんね。まぁ、それもいいではありませんか。体内に入った武漢肺炎のウイルスも、日本の酒のアルコールで消毒、豆まきの豆と柿ピーも付けておつまみに(昔はお米をまいていたそうです)無病息災。そして、新しい春を迎えるのも良いかもしれませんね。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[節供・雑節と北海道の季節だより] カテゴリの最新記事
-
令和6年1月8日 新年のご挨拶 昨日1月7日… 2024年01月08日 コメント(8)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.