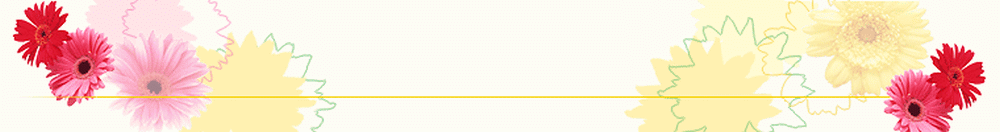T君の3学期
T君もこの頃より少し筒落ち着いてきていた。保育室で、健常児たちと一緒に居る時間も長くなっている。他児がカルタをしている時ははじめの少しには参加する。長続きはしない。部屋を飛び出そうとすると子どもたちがT君の興味の持てる遊び方に変更してくれたり助けてくれたりして少しでも長く一緒に遊べるように工夫をするのだ。再び同じ遊びが続けられる。3度目くらいに投げ出しかけた時には保育者がT君だけの遊びを同じ室内で提供する。「カルタ」は出来なくても、図鑑を見る。などの工夫をする事によって、他児と同一場所で同一時間過ごす事ができるのだ。学校に行けば1時間=45分は「授業」を受けなければならないことから言っても大事な事だ。外遊びの時も同様の工夫をした。そして、クラス全体が「T君も自分と同じ学校に行く」事を望みそのための「工夫」を受け入れてくれていた。自分の存在が認められる保育園であり楽しい保育園として、卒園していって欲しいと思った。そんな気持ちが通じたのかどうかは解らないが、少なくともT君の意欲は引き出せたと思っている。
2月には園生活最後の「生活発表会」練習の時は「チョコチョコ参加」だったが、本番では「激遊び」私は黒子になり、T君と共に参加した。台詞も言えたし、身体表現も見事にできた。終った時は涙!!お母さんの目にも光るものがあった。「歌」も「合奏」も壇上に並んで出演した。一瞬足りともじっとしていられなかったT君が、健常児ですら緊張する「発表会」を見事に終えることが出来たのだ。
「卒園式」が間近に迫ってくると、私の頭の中は1年前の「入園式」の事が思い出され不安と緊張が増していった。「練習」の苦手なT君は「発表会」の時と同様逃げ回ったりわざとヘラヘラ笑いながら他児の練習を見ていた。正に「高見の見物」だった。私自身「練習」を強要したくなかったから其れでもいいのだが、周囲の目が有った。「卒園式」まで後2・3日となった頃には「高見の見物」ではなかったことを証明するかのように、椅子に座れるようになってきた。お母さんも「Tは本番に強いから」と楽観する発言が出るまでになっていた。子どもの成長が親も成長させお互いの自信になってきているなあと思った。T君の「就学」先が2月の中旬になって、ようやく、決まった事も幸いだった。
卒園式当日にT君がパニックを起こさない事に最大の神経を注いできた。健常児にとっても、必要以上の緊張感を与えてまでのやり方は考え物である。一人一人が「希望」に満ちた気持ちの中で「式」を迎えたかった。
しかし、当日は開式前から私はt君以上の緊張をしていた。この緊張をT君に悟られないようにと努力をしたが、・・・
で、二人してビンビン!!ピリピリ!!緊張のしまくり。
いよいよ、開式。T君は私に体をピタリとくっつけて「式」に臨んだ。「一心同体」だ。座ってる間は「向き合い抱っこ」。T君は胸元のネックレスやコサージュを触って時を過ごした。立つ時はしっかりと手を繋いで肩を抱き寄せていた。
卒園証書は左手でT君の右手を繋ぎ、右手で肩を抱き寄せながら二人で授与した。
閉式後涙が溢れ出た。お母さんの目も真っ赤。同級生の保護者の皆さんも、我が子同様、T君の「卒園」を喜んでくれた。
この年の5歳児は9名。保育士3名。と恵まれた環境だった、よいうのも、T君のほかに、重度麻痺のMちゃんが居た。T君とMちゃんにそれぞれ各1名ずつの加配がつきメインクラス担任1名というわけだ。
私たち3名の保育士は、9名の子どもを真の意味での平等精神で保育に取り組んだと思っている。9名一人一人の保育をどうしていくか?をいつも3名の保育士が考え相談しながら進めてきた事が、9名それぞれの成長を促してきたのだと思う。その結果子どもも職員も保護者たち全員が迎えた「卒園式」だった。
今思うに、T君やMちゃんだけでなく、保育園にきている子どもたち全員の成長を考えられる「保育者集団」があったればこその、1年間だった。
「保育士」でよかった。と 思わずに入られない。
T君有難う。お母さん達有難う。子どもたち有難う。職員の皆さんありがとう!!
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 子連れのお出かけ
- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…
- (2025-11-07 07:53:33)
-
-
-

- シングルマザーの子育て
- もうどうしたらいいか分からない
- (2025-11-14 23:09:22)
-
-
-

- ♪~子供の成長うれしいなぁ~♪
- 学生かばんをミニにリメイクしていま…
- (2025-11-26 05:15:56)
-
© Rakuten Group, Inc.