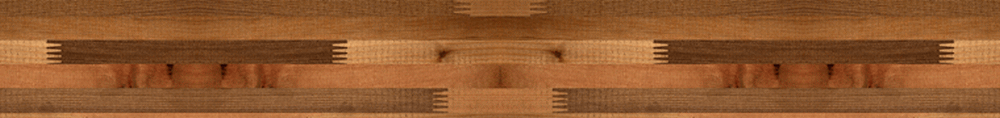テーマ: 最近、読んだ本を教えて!(24647)
カテゴリ: 読書
もう去年のことになってしまいましたが、このブログで 堀江敏幸『おぱらばん』を取り上げたことがあります



で、そのときのブログにも少し書いたことですが、『おぱらばん』を読んだときの印象は、それまで僕が堀江敏幸の作品から得ていた、「上手いけれど、どこか硬い」というのとは随分違ったものでした。『おぱらばん』を読んでいたときは、きっと自分が変ったのだろうと思い、ブログにもそう書き、もっと早くこの魅力的な作家を読んでおけばよかったと嘆息していたものです。ところが、よくよく調べてみたら、どうも変ったのは僕だけではないようなのでした。
出版されたばかりの『子午線を求めて』や『本の音』を買ったとき、僕はそれが最新の文章集だと思っていたのですが、実のところ『子午線を求めて』は大半が1996年以前に書かれたもので、『本の音』も幾つか古いものが混じっている。そして『郊外へ』は1994年から1995年に書かれたものです。それに対して『おぱらばん』は1996年以降に書かれたものが中心で、さらに『いつか王子駅で』や『熊の敷石』は1999年から2001年にかけてのものばかり( 「堀江敏幸教授のレミントン・ポータブル」 というサイトも参照させてもらいました)。つまり僕は今まで比較的早い時期に書かれたものばかりを読んでいて、今頃になってようやく、「その後」の堀江敏幸に出会ったというわけです。
そして今になって『郊外へ』などをきちんと読んでみると、やっぱり間違いなく文章が硬い。
「町を包み込んでいる空気、若者たちの表情、建物の外観には、おのずと滲みでてくる現在と過去があって、これはどうにも隠しようがない。歴史の爪あとを処理できずに、今日にいたるまで過去と媒介なしに結ばれている土地も少なくないのだ」
「私は不覚にも、一瞬のあいだ視界が曇るほどの感動に襲われてしまった。著名な写真家が作品にとどめているとの説明書きや碑文があるわけでもないこんな家が、よくも生き延びられたものだという感慨にふけったのではない。ひとが家を建て、そこに住み、食事をし、眠る、この単純な反復のただならなさを、かいま見たように思ったからだ」
その変化は一体何なのだろうと考えました。単に文章が上手くなっただけ、というのもあるでしょう。でも僕は、この変化の最大の理由は、おそらく堀江敏幸が他人の経験というものを取り込むようになったからではないかと思うのです。実際『郊外へ』で主に語られるのは「わたし」個人の想念ばかりで、その想念に引っかかったかぎりで他人が出て来るだけで、しかも想念の中心を占めるのは作家や写真家ばかり。それに対して、『おぱらばん』以降の堀江作品では、他人の経験の占める範囲が圧倒的に増えているような気がします。もっと言えば、他人の経験を自分の想念の中に引きずり込むのではなく、自分の想念を一旦棚あげにして、他人の経験に寄り添ってみる、いやもしかすると他人の経験に振り回されてみる。そういう類いの柔らかさが伺える。そして「場所」に対する堀江敏幸のまなざしも、その「場所」が自分だけではなく他人にも経験されているものとして捉えることで、さらに奥行きと広がりを増すのです。その結果、「おのずと滲みでてくる現在と過去」とか「反復のただならなさ」が、他人の経験や言動を通じて具体的に、はっきりとした内実を伴って、しかし「私」の想念に回収しきれない形で浮かび上がってくるのではないかと。
『おぱらばん』には既にそうした要素が幾つも伺えますが、おそらくその最たるものは『いつか王子駅で』でしょう。主人公が生きる場所に暮らす多くの人々の生活が重なりあっているというだけではなく、例えば下手すると印鑑職人の「正吉さん」よりも印象に残ってしまう中学生の「咲ちゃん」との融通無碍な交流は、まさに振り回されているという名にふさわしい。だって中学生の女の子相手に、抽象的な思考を繰り広げたところで、仕方ないですから。実際、短距離走者である「咲ちゃん」はしばしば、「私」の想念を軽やかに「抜き去って」いってくれるのです。その爽快さ、心地よさ。もちろん、そうした軽やかさではなく、自分の経験と他人の経験のズレを執拗に見つめ、その果てしもなさに驚きつづける『熊の敷石』も、『いつか王子駅で』とスタイルは異なるものの、やはり他人の経験に出来る限り想像力を向け、そこで戸惑うことを形にしていると言ってよいでしょう。
そして実のところ、こうしたことを堀江敏幸自身も意識していたのではないかと思います。上述したようなことを考えながら『郊外へ』を読み、いよいよ終わりにさしかかろうとしたところでこんな文章に出会いました。
「異国の郊外で私がどれだけ幸福な散策を繰り返したにせよ、畢竟それは、他者の視線をたくみに回避しつつ、こちらの視線だけを地名や書物にぶつけて、その『言表』のクッションボールを架空の物語に仕立てあげていたにすぎないのではないだろうか」
そう、そして回避していた「他者の視線」を、おそらくは意識的に取り込むことで、彼の「架空の物語」はもっと豊かなものとなったのでした。もちろん堀江敏幸がこの文章を書いてからもう10年以上が経過し、『いつか王子駅で』や『熊の敷石』からも6~7年がたっています。きっと「その後」の堀江敏幸はまた変わっていくのでしょう。僕の目の前には、つい最近某新古書店にて100円で手にいれた単行本版の『雪沼とその周辺』が積んであります。2008年の堀江敏幸までまだまだ先は長い。楽しみです。

 ←もしよろしければclickを!
←もしよろしければclickを!



で、そのときのブログにも少し書いたことですが、『おぱらばん』を読んだときの印象は、それまで僕が堀江敏幸の作品から得ていた、「上手いけれど、どこか硬い」というのとは随分違ったものでした。『おぱらばん』を読んでいたときは、きっと自分が変ったのだろうと思い、ブログにもそう書き、もっと早くこの魅力的な作家を読んでおけばよかったと嘆息していたものです。ところが、よくよく調べてみたら、どうも変ったのは僕だけではないようなのでした。
出版されたばかりの『子午線を求めて』や『本の音』を買ったとき、僕はそれが最新の文章集だと思っていたのですが、実のところ『子午線を求めて』は大半が1996年以前に書かれたもので、『本の音』も幾つか古いものが混じっている。そして『郊外へ』は1994年から1995年に書かれたものです。それに対して『おぱらばん』は1996年以降に書かれたものが中心で、さらに『いつか王子駅で』や『熊の敷石』は1999年から2001年にかけてのものばかり( 「堀江敏幸教授のレミントン・ポータブル」 というサイトも参照させてもらいました)。つまり僕は今まで比較的早い時期に書かれたものばかりを読んでいて、今頃になってようやく、「その後」の堀江敏幸に出会ったというわけです。
そして今になって『郊外へ』などをきちんと読んでみると、やっぱり間違いなく文章が硬い。
「町を包み込んでいる空気、若者たちの表情、建物の外観には、おのずと滲みでてくる現在と過去があって、これはどうにも隠しようがない。歴史の爪あとを処理できずに、今日にいたるまで過去と媒介なしに結ばれている土地も少なくないのだ」
「私は不覚にも、一瞬のあいだ視界が曇るほどの感動に襲われてしまった。著名な写真家が作品にとどめているとの説明書きや碑文があるわけでもないこんな家が、よくも生き延びられたものだという感慨にふけったのではない。ひとが家を建て、そこに住み、食事をし、眠る、この単純な反復のただならなさを、かいま見たように思ったからだ」
その変化は一体何なのだろうと考えました。単に文章が上手くなっただけ、というのもあるでしょう。でも僕は、この変化の最大の理由は、おそらく堀江敏幸が他人の経験というものを取り込むようになったからではないかと思うのです。実際『郊外へ』で主に語られるのは「わたし」個人の想念ばかりで、その想念に引っかかったかぎりで他人が出て来るだけで、しかも想念の中心を占めるのは作家や写真家ばかり。それに対して、『おぱらばん』以降の堀江作品では、他人の経験の占める範囲が圧倒的に増えているような気がします。もっと言えば、他人の経験を自分の想念の中に引きずり込むのではなく、自分の想念を一旦棚あげにして、他人の経験に寄り添ってみる、いやもしかすると他人の経験に振り回されてみる。そういう類いの柔らかさが伺える。そして「場所」に対する堀江敏幸のまなざしも、その「場所」が自分だけではなく他人にも経験されているものとして捉えることで、さらに奥行きと広がりを増すのです。その結果、「おのずと滲みでてくる現在と過去」とか「反復のただならなさ」が、他人の経験や言動を通じて具体的に、はっきりとした内実を伴って、しかし「私」の想念に回収しきれない形で浮かび上がってくるのではないかと。
『おぱらばん』には既にそうした要素が幾つも伺えますが、おそらくその最たるものは『いつか王子駅で』でしょう。主人公が生きる場所に暮らす多くの人々の生活が重なりあっているというだけではなく、例えば下手すると印鑑職人の「正吉さん」よりも印象に残ってしまう中学生の「咲ちゃん」との融通無碍な交流は、まさに振り回されているという名にふさわしい。だって中学生の女の子相手に、抽象的な思考を繰り広げたところで、仕方ないですから。実際、短距離走者である「咲ちゃん」はしばしば、「私」の想念を軽やかに「抜き去って」いってくれるのです。その爽快さ、心地よさ。もちろん、そうした軽やかさではなく、自分の経験と他人の経験のズレを執拗に見つめ、その果てしもなさに驚きつづける『熊の敷石』も、『いつか王子駅で』とスタイルは異なるものの、やはり他人の経験に出来る限り想像力を向け、そこで戸惑うことを形にしていると言ってよいでしょう。
そして実のところ、こうしたことを堀江敏幸自身も意識していたのではないかと思います。上述したようなことを考えながら『郊外へ』を読み、いよいよ終わりにさしかかろうとしたところでこんな文章に出会いました。
「異国の郊外で私がどれだけ幸福な散策を繰り返したにせよ、畢竟それは、他者の視線をたくみに回避しつつ、こちらの視線だけを地名や書物にぶつけて、その『言表』のクッションボールを架空の物語に仕立てあげていたにすぎないのではないだろうか」
そう、そして回避していた「他者の視線」を、おそらくは意識的に取り込むことで、彼の「架空の物語」はもっと豊かなものとなったのでした。もちろん堀江敏幸がこの文章を書いてからもう10年以上が経過し、『いつか王子駅で』や『熊の敷石』からも6~7年がたっています。きっと「その後」の堀江敏幸はまた変わっていくのでしょう。僕の目の前には、つい最近某新古書店にて100円で手にいれた単行本版の『雪沼とその周辺』が積んであります。2008年の堀江敏幸までまだまだ先は長い。楽しみです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書] カテゴリの最新記事
-
「雪沼」とどこにもない場所 2008年03月28日
-
読書の水先案内人 2008年03月17日
-
働く場所へのまなざし 2008年03月11日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年07月
2025年06月
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.