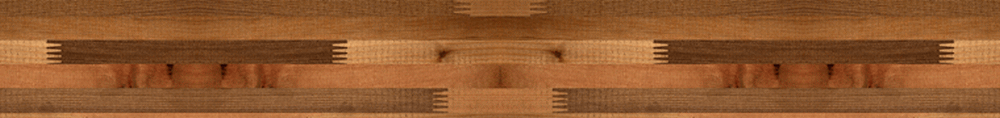テーマ: お勧めの本(7885)
カテゴリ: 読書
(三木清『読書と人生』新潮文庫)


そもそも僕が最初に読んだ高橋源一郎の著書は新潮文庫版の『ぼくがしまうま語をしゃべった頃』で、その本は当時の僕にとって本とマンガへの道標のようなものだった気がします。ピンチョン、バース、バーセルミなど、そこで紹介されているポストモダン作家たちの作品は今に至るまで一冊も読んでいませんが、現代文学の世界ではそういうことが起きているんだなあと、ぼんやりとイメージすることができたし、ガルシア=マルケスやブローティガンの名前もこの本で最初に知ったのではなかったかと思います。清原なつの、吉野朔実、松苗あけみ、岩館真理子などが書いた素晴らしい少女マンガに出会うことができたのも、やっぱりその本のおかげ。
自分の読書量に比べて本に関する知識だけが肥大化するという弊害はあったものの、その後も高橋源一郎の書評集は僕にとって読書の道標というか、「ナビゲーター」であり続けました。実際には彼の勧めている本の十分の一も読んでいないとは思うのですが、それでも、少なくとも自分の頭の中の「読みたい本リスト」は、高橋源一郎の書くものを参考にしながら作っていたのは確かです(ついでに、高橋源一郎が書評を書くときの文体にも随分影響されたなあ)。
それが変ったのはいつだったか。まず待ちに待った『ゴーストバスターズ』を発売後すぐさま読んで、ああ僕はもう高橋源一郎の小説は読まないだろうなあと思ったことがまずあって、その後も週刊朝日の書評欄の立ち読みと、小説以外の単行本の購入は続けていたものの、『もっとも危険な読書』を最後にそれも止めてしまいました。その後は、高橋源一郎に代わる「ナビゲーター」を捜さなくてはと、色々読んでみましたが、坪内祐三にせよ、堀江敏幸にせよ、池澤夏樹にせよ、それぞれ決して悪くはないし、自分の読書計画の参考にもさせてもらったのですが、それまでの高橋源一郎ほどに入れ込める「ナビゲーター」とはなりませんでした。


で、たまたま去年『ニッポンの小説 百年の孤独』を読んで、数年間ぶりに高橋源一郎と「再会」し、つい先日も『人に言えない習慣、罪深い愉しみ』をふと買ってしまい、現在読み途中なのですが、ひどく懐かしさを感じつつ、自分にとってやっぱり高橋源一郎はもう「ナビゲーター」とは成り得ないのだなあと再確認しているところです。そこで紹介されている本で、「あ、読んでみたい」と思う本が無い訳ではない。だから読書案内としては十分な筈なのですが、でも何かが違うのです。ではその「何か」とは何なのか。そんなことを考えている最中に、ちょうど必要があって徐京植の『子どもの涙』を読み返すことになり、それを読んでいたら、ふと答えが見つかったような気がしました。


徐京植の本は、 前にも少しだけ触れたことがありますが 、少年時代から大学時代までの彼の読書遍歴を振り返った本で、言わば本を通じた自己の形成史のようなものです。従って、彼のその時々の生活の風景と密接に関連した形で本が紹介される。そもそも彼が他に書いている美術関係の本にしても、徐京植は、やり過ぎではないかと思われるくらいに自分の経験に作品を引きつけるのですが、殆ど自伝のような『子どもの涙』の場合、その傾向はますます強まります(ただ、この本については、どんなに引きつけてもやり過ぎと思えることは無いですが)。その結果どうなるかというと、徐京植がそれぞれの本にどんな印象を持とうとも、読者である自分が持つであろうそれとは決定的に違うのだろうなあと思ってしまうのです。

通常、というか多くの書評は、取り上げられる本を、著者と読者がある程度まで同じような受け止め方をするであろうということを前提としていると言ってよいでしょう。少なくとも、対象となる本から誰でも読みとれるであろう要素を紹介することが多い。けれども徐京植の場合、自身の生の固有な文脈に徹底的に引きつけて本を読むために、彼が読みとるものはどこまで行っても彼だけのものであって、他の誰一人として、同じ本から彼と同じものを受け取ることは無い筈なのです。
そもそも、どんなに「一般性」を目指した書評であっても、どこかにその著者の固有性というものは見え隠れしているわけであって、おそらく無意識にであれ、それによって読者はその書評が信頼できるかどうかを判断している。そしてつまるところ僕が書評に求めていたのは単なる本の紹介ではなくて、その著者が本を読む姿勢、ないしは技術のようなものだったのだなあと考え、高橋源一郎のその姿勢ないし態度に共感できなくなったからこそ、高橋源一郎の書評本を読むのを止めたのだと思い当たったのでした。そういえば、僕が現在最も好きな書評家は詩人の荒川洋治なのですが、彼の本を読むのは、そこに紹介してある作品を読んでみたいとからではなく(もちろんそれもありますが)、彼の本に向かう態度を知りたいからなのだと、これを書いていて気付きました。
もちろん荒川洋治の態度にしても、それが自分の態度と必ずしも一致するわけではない。最終的に本に向かう態度、そして本を捜す姿勢というのは、自分自身で作り出すもので、それは徐京植がそうであるように、他の誰とも似ていないもの態度であるべきなのかもしれません。ちょっとカッコつけたことを書いてしまうと、その態度ができあがるまでは、「ナビゲーター」は必要なのかもしれませんが、いつか自分自身が自分の「ナビゲーター」になる時がくる、ということです。僕の場合は高橋源一郎を読まなくなったときがきっとそうだったのでしょう。とても余談になりますが、ブルーハーツの歌で「ナビゲーター」という名曲があって、その中に「ナビゲーターは魂だ」という歌詞があるのですが、それは要するにそういうことなのだと、これを書いていて気付いた次第です。なんか魂とかいうと、ちょっと自己啓発っぽい方面に流れてしまいそうで危険ですが、でもやっぱりそういうことですよね。このブログにしても、「オススメです」とか書きながら、本の紹介ブログとしては相当不十分だと思うのですが、きっとそれはそれで良いのだと、自分を正当化してみたりもしているのでした。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書] カテゴリの最新記事
-
「雪沼」とどこにもない場所 2008年03月28日
-
働く場所へのまなざし 2008年03月11日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年07月
2025年06月
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.