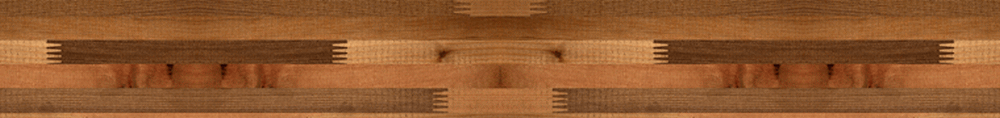全43件 (43件中 1-43件目)
1
-

人がそこにいることの重み~植田正治写真美術館にて
今回は写真の話です。数日前まで鳥取にしばらくの間滞在していたのですが、その間に、去年その存在を知って以降ずっと行きたかった植田正治写真美術館をようやく訪れることができました。美術館そのものについてはHPを見てもらうとして、写真を見て考えたことなどを少し書くことにします。 池澤夏樹の『海図と羅針盤』の表紙に植田正治の写真が使われていることは、以前このブログでも触れましたが、それ以上に有名かつ印象に残るのは、やはり鷲田清一と植田正治のコラボレーションでしょう。かくいう僕も、鷲田清一の名著『「聴く」ことの力』に添えられた写真で初めて植田正治という写真家を知り、その後植田正治の写真に鷲田清一の文章を添えた『まなざしの記憶』を見つけてそれをうっとりと読んでいたりもしたのでした。 ただ当然ですが、そうした本に収められているよりもサイズの大きな写真そのものを、それも何の添え物も無しで見ると、印象はやはり違ってきます。まずもって、気になる写真が全く違ってきました。鷲田清一の本を読んで印象に残っているのは、砂丘に立つ人物の写真など、植田正治の中でも比較的スタイリッシュな写真なのですが、美術館で目を惹かれたのは、もっと風景写真に近いものでした 桜庭一樹の『砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない』の舞台である境港に生まれた植田正治は、鳥取砂丘以外にも、島根・鳥取の風景を撮った写真を沢山撮っているのですが(ちょうど「山陰抒情」という企画展を開催中でそういう写真が数多く展示されていました)、その多くは、写真の上半分は空、そして下半分は駅や工場や畑といった構図のものです。その中に人もポツンと写ってはいるのですが、空や風景に比して大変に小さい。しかしそれでもなお、惹きつけられるのは、風景や構図の美しさではなく(それも勿論ありますが)、そのポツンと心細く立っている小さな小さな人に対してなのです。 風景の一部と化した人間ではなく、あくまでその全存在の重みをかけているかのようにそこに存在している人間。風景のなかにポツンと写っているというよりは、むしろ全身でその広い広い空を含めた風景全てを背負っているような人間。そういう風に見えるというのは、やはり構図の妙であるとか、色々技術的な理由もあるのだろうとは思いますが、さしあたり僕にわかるのは、そこに写っている人にも風景にも、土地の匂い、生活の匂いがしっかりと染み付いていること、だからこそ人が「モノ」となっておらず、同時に風景ともしっかりと関係を持っているということだけです。それでも、ああ、植田正治というのはこういう写真を撮る人なのだと、しみじみ腑に落ちたのでした。 そして同時に、鷲田清一が植田正治の写真を使った理由も、よりはっきり判るような気がしました。なぜって、鷲田誠一の哲学とは、人を「モノ」として扱うことを徹底的に拒否し、人がただそこに存在しているだけで持っている重みを何よりも大事に考え、それを思考の軸に据えようとすることなのですから。きっと植田正治の写真は、鷲田清一の哲学の実践であり、もっと言えば彼の哲学を触発するものなのでしょう。つまるところ、鷲田清一の本を読んで写真のスタイリッシュさばかりに目を撮られていた僕は、そもそも写真をきちんと見ていなかったということになります。コラボレーションということの意味も全然理解せずに、文章の添え物としてしか写真を見ていなかったということです。僕は多分、『「聴く」ことの力』をもう2回は読んでいる筈なのですが、どうも、もう一度読み返さなくてはいけなくなりそうです。深い自戒を込めて。追記:恥ずかしながら、この文章を書いた後で、一昨年に鷲田清一『「待つ」ということ』という本が出ていて、その表紙も植田正治の写真であることを知りました。うわあ、これも読まなくてはいけません・・・・。 ←もしよろしければclickを!
2008年04月03日
コメント(0)
-

「雪沼」とどこにもない場所
「分解して組み立てられるくらいの、単純だが融通のきく構造が、機械にも、社会にも、人間関係にも欲しい、と田辺さんはいつも考えていた。息子や娘とも、もちろん妻ともそんなふうにつながっていられれば、どんなに健全か。単純な構造こそ、修理を確実に、言葉を確実にしてくれるのだ」(堀江敏幸『雪沼とその周辺』) 以前「地図にない場所」というエントリを書いたとき、地図にない場所=どこにもない場所=ユートピアだなあと思いつつ、そのことについては書きませんでした。けれども、ファンタジー作品に限らず、多くの小説作品は、ユートピア小説と銘打っていなくともユートピア的な要素を持っているとは思います。例えば北村薫、加納朋子、坂木司等の書くソフトミステリは、作者及びその作品の愛読者たちにとって、「こうであってほしい人間関係」や「こうあってほしい場の雰囲気」のようなものを書いていると思うのです。ライトノベルであれ何であれ、戦闘/戦争ものが好まれるのは、話が作りやすいということもあるでしょうが、そこに必然的に伴う規律のある秩序だった人間関係の場に対する憧れという要素もある筈。そういえば藤本和子さんも、リチャード・ブローティガンの『西瓜糖の日々』をユートピア小説と書いていたような。 冒頭に掲げた言葉が示しているように、堀江敏幸の『雪沼とその周辺』もまた、おそらくは、そうしたユートピア的な願望を内に秘めています。「雪沼」がおそらくは架空の、「どこにもない場所」であるというだけではありません。その題名通り、雪沼の周辺に住む人々をめぐる7つの連作短編からなるこの小説が全体として描き出すのは、ゆるやかで押しつけがましくはなく、けれどもどこかに確かなものを持っている人間関係なのです。1つ1つの短編がそういう話なのですが、また短編同士が、かすかな、気をつけなければ見落としてしまいそうなほどの、うっすらとした関係でつながっているという構成も、またそうした人と人との関係のあり方のアナロジーであるようにも思えてきます。つまりは、「単純だが融通のきく構造」を持った小説。描かれる1つ1つの人間関係は、決して矛盾や葛藤を排したものではなく、むしろ無骨でごつごつしたようなものですが、少なくともそこには、そうしたものをそうしたものとして引き受けつつ、同時に「言葉を確実にしてくれる」ものを持とうとする意志が見えるのです。 こんなことを考えながら『雪沼とその周辺』を読んでいる最中に、ふと思い出したのはムーミン谷のことでした。僕はムーミン谷のシリーズもまた優れたユートピア小説だと思っているのですが、そこでいう「ユートピア」とは、やはり矛盾や葛藤のない世界ではありません。しかし、雪沼と同様、ムーミン谷にも、「単純だが融通のきく構造」が確かにある。この連想はおそらく決して突飛なものではないと思います。実際、『おぱらばん』に収められた「のぼりとのスナフキン」で、堀江さんはムーミン谷の住人についてこんなことを書いているのです。「スナフキンが独立不覊の存在であることは疑うべくもないけれど、旅をつづけて少し顎のあがりかけた彼にもっとも適した濃度の酸素を吹き込んでやる仲間たちの振る舞いの方にこそ、じつはムーミン谷の秘密が隠されているのだ。感情のじかの接触におぼれず、それをゆっくり育てたり修復したりする時間の使い方に、あの連中はいかにも長けている」 この文章を見つけて、ああ、きっと「雪沼」というのは、堀江さんにとってのムーミン谷なんだな、と僕は一人で得心していたのでした。
2008年03月28日
コメント(0)
-

風景のざわめき~ミステリの風景・再び
色々と文句をつけつつ、日本のミステリは依然として折に触れて読んでいます。いきなり新しいものから読むのは何だか抵抗があるのでどうしても少し古いものになってしまうのですが、最近読んだものとしては真保裕一『ホワイトアウト』と高村薫『照柿』があります。 かたやミステリというよりは冒険小説、かたや地味な警察小説と、全く似ていない2作ですが、無理を覚悟で言うと、どちらもそれなりに「場所」にこだわった作品という共通項がないでもありません。そしてそう考えると、日本のミステリには場所性が希薄であると以前書いた手前、それぞれのミステリの内容はともかく、その点については何か書いておかなくてはと思ったのでした。 まず『ホワイトアウト』からいきますと、多くの人がご存知の通り、冬山でのダムをめぐるテロリストと職員の攻防戦というお話で映画化もされました(当時その映画の評価をめぐって『キネマ旬報』で立川志らくと高島某との間で論争が繰り広げられていて、ひどく面白かったのですが、それはともかく)。とにかく雪やら氷やらの描写が凄まじく、それが冒険小説を構成する重要な要素となっています。つまり、少なくとも物語が展開する「場」の存在感は少しも希薄ではない。ただ問題は、その雪やら氷やらのいわゆる「自然」が、その「土地」から完全に切り離されてしまっていることです。外界から完全に遮断されたダムが舞台という設定なので、仕方のないところもあるのですが、甲信越のどこかにあるらしいそのダムは、正直言って、雪さえ降っていればどこにあってもいいダム。登場人物にしても、テロリストとダム職員と警官以外には、人質になったダム職員の家族がお情け程度に登場するだけで、例えば麓の住民など影も形も見えない。 真保裕一は現代日本を舞台にした本格的冒険小説が書きたかったそうで、その試みは実のところテロリスト像にあまりにリアリティがないという点で相当つまづいているのですが(日本の左翼の過激派にこんな優秀な人たちは多分いません)、もう1つの問題としては、極端な話、これが日本を舞台にする必要すら殆ど感じられないということもあります。少なくとも、日本でなければ成立しなかった冒険小説とは言い難く、そしてその理由の一部は、周りから切り離されてしまったが故に、その舞台が「場所性」というか「風土性」を失ってしまったことにあるのではないかと思うのです。 一方『照柿』はどうかといいますと、話は主に青梅線沿線で進み、時折大阪の西成が顔を出します。どちらもそれなりに丁寧な描かれており、主要登場人物の一人が働く工場の描写があるのもなかなか悪くない。ただそこに住んでいる、ないしは働いている人たちの具体的な様子が見えてこないという点は、これまで僕が読んできた日本のミステリと基本的には大差ありません。描写が丁寧と書きましたが、実のところ描写の殆どは、2人の主要登場人物が、周りの風景やら人やらに投影する一方的な自己意識についてなのです。そこに住んでいる人の気配、ざわめきのようなものは殆どない。何というか、外側から見ている人の視線なのですね。それが悪いとは言いませんが、それだとその場所に棲息している、ないしは育まれた色々なものは決して見えてこないのです。 それからこれはどちらの作品にも共通することなのですが、とにかく作者が色々とよく調べていることは間違いないと思います。ダムの内部についての説明も、工場の労働過程の説明も、実に詳しい。ただそうしたものを詳しく書いたからといって、その場の雰囲気が立ち上がってくるかというと、そう言う訳ではないと思うのですね。むしろそれは外側からの視線を強化してしまうような気がしてなりません。それからこれは小説であれ何であれ言えることですが、調べたことをもっと物語の中に上手に織り込んで欲しいなあと思います。読んでいる方が、それと知らぬ間に、その場所やその職場の空気に触れることができるような。もちろんきちんとした取材もしていないような作品に比べれば遥かにましなのですが。 こうして文句ばかり書いているのも何なので最後に1つ。上述したようなことも含め、高村薫の描写はとにかく、ありとあらゆる意味で執拗なのですが、その執拗さは、簡単に片付けるわけにはいかないような「何か」を持っているような気もしています。彼女の描写は明らかに過剰ですが、その過剰さは、おそらく彼女がミステリの枠に収まりきらない「何か」を書こうとしているからではないかと、『マークスの山』と『照柿』と二冊しか高村作品を読んでいないにもかかわらず、そんなことも思うのです(実際、『照柿』は殆どミステリとは言い難いですし)。そしてだからこそ彼女は『晴子情歌』『新リア王』などを書いたのではないかとも。その「何か」は少なくとも『マークスの山』や『照柿』では実現していないようですが、それが実現したとき、彼女がどんな「風景」や「場所」を立ち上がらせてくれるのか、それはそれでちょっと楽しみだったりもするのでした。
2008年03月23日
コメント(0)
-

読書の水先案内人
「読書法は各人においてめいめい性格的なものである。それ故に各人にとって自分に適した読書法を発明することが最も大切である。読書の技術においてひとはめいめい発明的でなければならぬ」 (三木清『読書と人生』新潮文庫) 高校生から大学生にかけての頃、僕の一番好きな作家は高橋源一郎でした。『さようなら、ギャングたち』とか『虹の彼方に』とか、作品が含意しているものなどは殆どわからないままに、ただただ文章の静けさと独特のリリカルな雰囲気が心地よくてたまらず、何度も読み返した記憶があります。確か当時は『ゴーストバスターズ』が発表される前の長い長い空白期間だったので、とにかく高橋源一郎名義のものは、競馬関連以外は全て読みました。もちろん『文学がこんなにわかっていいかしら』に代表される書評・文学論集も。 そもそも僕が最初に読んだ高橋源一郎の著書は新潮文庫版の『ぼくがしまうま語をしゃべった頃』で、その本は当時の僕にとって本とマンガへの道標のようなものだった気がします。ピンチョン、バース、バーセルミなど、そこで紹介されているポストモダン作家たちの作品は今に至るまで一冊も読んでいませんが、現代文学の世界ではそういうことが起きているんだなあと、ぼんやりとイメージすることができたし、ガルシア=マルケスやブローティガンの名前もこの本で最初に知ったのではなかったかと思います。清原なつの、吉野朔実、松苗あけみ、岩館真理子などが書いた素晴らしい少女マンガに出会うことができたのも、やっぱりその本のおかげ。 自分の読書量に比べて本に関する知識だけが肥大化するという弊害はあったものの、その後も高橋源一郎の書評集は僕にとって読書の道標というか、「ナビゲーター」であり続けました。実際には彼の勧めている本の十分の一も読んでいないとは思うのですが、それでも、少なくとも自分の頭の中の「読みたい本リスト」は、高橋源一郎の書くものを参考にしながら作っていたのは確かです(ついでに、高橋源一郎が書評を書くときの文体にも随分影響されたなあ)。 それが変ったのはいつだったか。まず待ちに待った『ゴーストバスターズ』を発売後すぐさま読んで、ああ僕はもう高橋源一郎の小説は読まないだろうなあと思ったことがまずあって、その後も週刊朝日の書評欄の立ち読みと、小説以外の単行本の購入は続けていたものの、『もっとも危険な読書』を最後にそれも止めてしまいました。その後は、高橋源一郎に代わる「ナビゲーター」を捜さなくてはと、色々読んでみましたが、坪内祐三にせよ、堀江敏幸にせよ、池澤夏樹にせよ、それぞれ決して悪くはないし、自分の読書計画の参考にもさせてもらったのですが、それまでの高橋源一郎ほどに入れ込める「ナビゲーター」とはなりませんでした。 で、たまたま去年『ニッポンの小説 百年の孤独』を読んで、数年間ぶりに高橋源一郎と「再会」し、つい先日も『人に言えない習慣、罪深い愉しみ』をふと買ってしまい、現在読み途中なのですが、ひどく懐かしさを感じつつ、自分にとってやっぱり高橋源一郎はもう「ナビゲーター」とは成り得ないのだなあと再確認しているところです。そこで紹介されている本で、「あ、読んでみたい」と思う本が無い訳ではない。だから読書案内としては十分な筈なのですが、でも何かが違うのです。ではその「何か」とは何なのか。そんなことを考えている最中に、ちょうど必要があって徐京植の『子どもの涙』を読み返すことになり、それを読んでいたら、ふと答えが見つかったような気がしました。 徐京植の本は、前にも少しだけ触れたことがありますが、少年時代から大学時代までの彼の読書遍歴を振り返った本で、言わば本を通じた自己の形成史のようなものです。従って、彼のその時々の生活の風景と密接に関連した形で本が紹介される。そもそも彼が他に書いている美術関係の本にしても、徐京植は、やり過ぎではないかと思われるくらいに自分の経験に作品を引きつけるのですが、殆ど自伝のような『子どもの涙』の場合、その傾向はますます強まります(ただ、この本については、どんなに引きつけてもやり過ぎと思えることは無いですが)。その結果どうなるかというと、徐京植がそれぞれの本にどんな印象を持とうとも、読者である自分が持つであろうそれとは決定的に違うのだろうなあと思ってしまうのです。 通常、というか多くの書評は、取り上げられる本を、著者と読者がある程度まで同じような受け止め方をするであろうということを前提としていると言ってよいでしょう。少なくとも、対象となる本から誰でも読みとれるであろう要素を紹介することが多い。けれども徐京植の場合、自身の生の固有な文脈に徹底的に引きつけて本を読むために、彼が読みとるものはどこまで行っても彼だけのものであって、他の誰一人として、同じ本から彼と同じものを受け取ることは無い筈なのです。 そもそも、どんなに「一般性」を目指した書評であっても、どこかにその著者の固有性というものは見え隠れしているわけであって、おそらく無意識にであれ、それによって読者はその書評が信頼できるかどうかを判断している。そしてつまるところ僕が書評に求めていたのは単なる本の紹介ではなくて、その著者が本を読む姿勢、ないしは技術のようなものだったのだなあと考え、高橋源一郎のその姿勢ないし態度に共感できなくなったからこそ、高橋源一郎の書評本を読むのを止めたのだと思い当たったのでした。そういえば、僕が現在最も好きな書評家は詩人の荒川洋治なのですが、彼の本を読むのは、そこに紹介してある作品を読んでみたいとからではなく(もちろんそれもありますが)、彼の本に向かう態度を知りたいからなのだと、これを書いていて気付きました。 もちろん荒川洋治の態度にしても、それが自分の態度と必ずしも一致するわけではない。最終的に本に向かう態度、そして本を捜す姿勢というのは、自分自身で作り出すもので、それは徐京植がそうであるように、他の誰とも似ていないもの態度であるべきなのかもしれません。ちょっとカッコつけたことを書いてしまうと、その態度ができあがるまでは、「ナビゲーター」は必要なのかもしれませんが、いつか自分自身が自分の「ナビゲーター」になる時がくる、ということです。僕の場合は高橋源一郎を読まなくなったときがきっとそうだったのでしょう。とても余談になりますが、ブルーハーツの歌で「ナビゲーター」という名曲があって、その中に「ナビゲーターは魂だ」という歌詞があるのですが、それは要するにそういうことなのだと、これを書いていて気付いた次第です。なんか魂とかいうと、ちょっと自己啓発っぽい方面に流れてしまいそうで危険ですが、でもやっぱりそういうことですよね。このブログにしても、「オススメです」とか書きながら、本の紹介ブログとしては相当不十分だと思うのですが、きっとそれはそれで良いのだと、自分を正当化してみたりもしているのでした。
2008年03月17日
コメント(0)
-

働く場所へのまなざし
日本の小説について常々抱いている不満の1つとして、人が「働く」という経験、及びその場所が十分に描かれていない、ということがあります。アルバイトも含め、大多数の人々は何らかの仕事をして、それでお金を貰って生きている筈なのですが、その人々の人生の大部分を占めている「仕事」ないしは「労働」というものが、日本の小説では不均等に少ない場所しか与えられていない、と。 もちろん「サラリーマン」が主人公の小説なんかは沢山あります(咄嗟に思いついた例で言うと黒井千次の『群棲』とか、古井由吉の『櫛の火』とか)。でもそこですら、仕事の場面、職場の場面は殆ど描かれずに、話の中心になるのは仕事外の人間関係なのです。最近手にとった柴崎友香の『フルタイムライフ』にしても、仕事の場面については大変おざなりで、作者が書きたいのはどうも個人的な人間関係であるような気がしてしまい、途中で読むのを止めてしまいました(まあ、小説としても余り面白そうではなかったし)。 むしろこの点で言うと、マンガの方がまだマシかもしれず、現在ひどく評判のいい安野モヨコの『働きマン』や、『働きマン』の元ネタではないかと勘ぐってしまうほど良く似ている逢坂みえ子の『ベル・エポック』などは、恋愛の問題を扱いながらも、仕事の過程を相当丁寧に書いていたりもします(そもそも逢坂みえこは、『9時から5時半まで』にせよ『火消し屋小町』にせよ、仕事をよく書きます)。『おたんこナース』と『Heaven? 』の佐々木倫子に至っては恋愛のことすら書かず、ひたすら仕事の話ばかり。 ただ『働きマン』や『ベル・エポック』は編集者、『火消し屋小町』は消防士、『おたんこナース』は看護師、そして挙げるまでもない医者、料理人、スポーツ選手を主人公にした数々のマンガ・・・と、マンガで対象となる職業は華やかなイメージがあるものや、一般に良く知られている専門職がどうしても多い。それはきっとポジティブな意味づけがしやすいからでしょう。けれどもそれは無数にある仕事の中のほんの一部にすぎず、世の中には、あまり人の目にも触れず、やりがいはあっても決して華やかではない仕事に携わっている数多くの「名もない」人々がいるわけです。そして以前取り上げた『リチャード・ブローティガン』を書いた藤本さんの文章を借りれば「物語を書くことの目的の一つは、『名もない』と一括される人びとの名を固有名詞にして呼びもどし、かれらの声を回復することにある」筈なのです。桐野夏生の『OUT』が、お弁当を作る工場のパートの女性たちを主人公にしたというのは、確かに驚くべきことでした。個人的に『OUT』には不満が多々ありますが、少なくともそうした「名もない」人々の仕事の場を書くことで、小説世界は実際に豊かで広がりのあるものになりました。それはもちろんミステリに限った話ではなく、前回取り上げた堀江敏幸の『いつか王子駅で』にしても、それが素晴らしい理由の1つは、例えば町工場の職人に目をむけ、その世界を立ち上がらせているような、そうした視線の広さにあるだろうと思うのです。それはまさに「他者」と出会うための回路としての小説、ということにもつながる事。 そういうわけで、一時期そういった小説・マンガを意識的に探していた時期もあります(念のために言っておくと、これはプロレタリア小説云々とは、ひとまず関係ないです。というか、僕は恥ずかしながらブロレタリア小説なるものを一冊も読んだことがないのでよくわからんのです)。有名なところからいくと、例えば宮崎誉子の小説。独特の文体で「フリーター」の仕事について書く彼女の小説は、多くの人が知っているつもりで実は殆ど何も知らない世界を、その世界を描くのに必要な言葉で描くということを見事に成し遂げた作品と言ってよいでしょう。数ある中でも『日々の泡』は特にオススメ。女性のフリーターを扱ったものとしては、さとうさくら『スイッチ』なんてのもありました。もっと男臭い世界を描いたものとしては、秋山鉄『ボルトブルース』という自動車工場のライン労働を扱った小説があります。話がほぼ職場での出来事に終始し、恋愛の話もほぼゼロに近いのに、小説としてきちんとして成り立っていて、しかも読後感もとても良い。同じような読後感を持った小説としては、映画化もされたらしい辻内智貴『青空のルーレット』というのがあって、これは窓拭き労働を扱ったもの。ちなみに窓拭き労働を扱ったものとしては、清田聡『染盛はまだか』というマンガもあったりします。これもなかなか。それからちょっと毛色の違うものとして、夏石鈴子『いらっしゃいませ』は大企業の受付嬢が主人公。目の付けどころも素晴らしいし、一人の女性の仕事・生活に対する期待と不安を実に丁寧に書いてあって、僕は『働きマン』なんかよりずっとこの作品の方が好きです。 こうして探してみると意外とあるものなんだなあ、と思いもしましたが、それでもやっぱり量としては全然不十分。それに、上に挙げたような作品群は、今度は仕事のことばかりを描いていて、それ以外の経験、ないしはその仕事の外側にある世界とのつながりが見えにくいという難点も抱えています。贅沢な要求かもしれませんが読者は贅沢で良いのです。きっと僕は、働くこと、生活することの細々としたことの描写から、ある特定の地域、ないしは共同体の全体が浮かび上がり、しかもその地域・共同体をすら越えるようなテーマを扱おうとするような小説に出会えることを夢見ているのでしょう。そう、ちょうど中上健次の一連の小説のような。
2008年03月11日
コメント(0)
-

堀江敏幸・その後
もう去年のことになってしまいましたが、このブログで堀江敏幸『おぱらばん』を取り上げたことがあります。その後堀江敏幸にすっかり参ってしまった僕は、この間、『いつか王子駅で』と『熊の敷石』を読む一方、読みかけのままになっていた『郊外へ』も無事読了しました。ちょっとした堀江敏幸ブームです。 で、そのときのブログにも少し書いたことですが、『おぱらばん』を読んだときの印象は、それまで僕が堀江敏幸の作品から得ていた、「上手いけれど、どこか硬い」というのとは随分違ったものでした。『おぱらばん』を読んでいたときは、きっと自分が変ったのだろうと思い、ブログにもそう書き、もっと早くこの魅力的な作家を読んでおけばよかったと嘆息していたものです。ところが、よくよく調べてみたら、どうも変ったのは僕だけではないようなのでした。 出版されたばかりの『子午線を求めて』や『本の音』を買ったとき、僕はそれが最新の文章集だと思っていたのですが、実のところ『子午線を求めて』は大半が1996年以前に書かれたもので、『本の音』も幾つか古いものが混じっている。そして『郊外へ』は1994年から1995年に書かれたものです。それに対して『おぱらばん』は1996年以降に書かれたものが中心で、さらに『いつか王子駅で』や『熊の敷石』は1999年から2001年にかけてのものばかり(「堀江敏幸教授のレミントン・ポータブル」というサイトも参照させてもらいました)。つまり僕は今まで比較的早い時期に書かれたものばかりを読んでいて、今頃になってようやく、「その後」の堀江敏幸に出会ったというわけです。 そして今になって『郊外へ』などをきちんと読んでみると、やっぱり間違いなく文章が硬い。「町を包み込んでいる空気、若者たちの表情、建物の外観には、おのずと滲みでてくる現在と過去があって、これはどうにも隠しようがない。歴史の爪あとを処理できずに、今日にいたるまで過去と媒介なしに結ばれている土地も少なくないのだ」「私は不覚にも、一瞬のあいだ視界が曇るほどの感動に襲われてしまった。著名な写真家が作品にとどめているとの説明書きや碑文があるわけでもないこんな家が、よくも生き延びられたものだという感慨にふけったのではない。ひとが家を建て、そこに住み、食事をし、眠る、この単純な反復のただならなさを、かいま見たように思ったからだ」 どちらも『郊外へ』からの引用です。ここに書いているスタンスというか、町や家に向ける視線自体は、まさに堀江敏幸ならではのもので、それ自体は『いつか王子駅に』『熊の敷石』などにも引き継がれてはいます。けれども、そうした作品では、「おのずと滲みでてくる現在と過去」とか「反復のただならなさ」とかいった硬い言葉を直接に使うことなく、そうした事象が描かれているように思うのです。その結果、フィクション性が増しているとか、舞台が日本のこともあるとか、そういう変化以上に、明らかに文章がまるく柔らかになっている。そう、つまるところ、1990年代後半のどこかで、堀江敏幸の文章はその質をはっきりと変化させていたのでした。 その変化は一体何なのだろうと考えました。単に文章が上手くなっただけ、というのもあるでしょう。でも僕は、この変化の最大の理由は、おそらく堀江敏幸が他人の経験というものを取り込むようになったからではないかと思うのです。実際『郊外へ』で主に語られるのは「わたし」個人の想念ばかりで、その想念に引っかかったかぎりで他人が出て来るだけで、しかも想念の中心を占めるのは作家や写真家ばかり。それに対して、『おぱらばん』以降の堀江作品では、他人の経験の占める範囲が圧倒的に増えているような気がします。もっと言えば、他人の経験を自分の想念の中に引きずり込むのではなく、自分の想念を一旦棚あげにして、他人の経験に寄り添ってみる、いやもしかすると他人の経験に振り回されてみる。そういう類いの柔らかさが伺える。そして「場所」に対する堀江敏幸のまなざしも、その「場所」が自分だけではなく他人にも経験されているものとして捉えることで、さらに奥行きと広がりを増すのです。その結果、「おのずと滲みでてくる現在と過去」とか「反復のただならなさ」が、他人の経験や言動を通じて具体的に、はっきりとした内実を伴って、しかし「私」の想念に回収しきれない形で浮かび上がってくるのではないかと。 『おぱらばん』には既にそうした要素が幾つも伺えますが、おそらくその最たるものは『いつか王子駅で』でしょう。主人公が生きる場所に暮らす多くの人々の生活が重なりあっているというだけではなく、例えば下手すると印鑑職人の「正吉さん」よりも印象に残ってしまう中学生の「咲ちゃん」との融通無碍な交流は、まさに振り回されているという名にふさわしい。だって中学生の女の子相手に、抽象的な思考を繰り広げたところで、仕方ないですから。実際、短距離走者である「咲ちゃん」はしばしば、「私」の想念を軽やかに「抜き去って」いってくれるのです。その爽快さ、心地よさ。もちろん、そうした軽やかさではなく、自分の経験と他人の経験のズレを執拗に見つめ、その果てしもなさに驚きつづける『熊の敷石』も、『いつか王子駅で』とスタイルは異なるものの、やはり他人の経験に出来る限り想像力を向け、そこで戸惑うことを形にしていると言ってよいでしょう。 そして実のところ、こうしたことを堀江敏幸自身も意識していたのではないかと思います。上述したようなことを考えながら『郊外へ』を読み、いよいよ終わりにさしかかろうとしたところでこんな文章に出会いました。「異国の郊外で私がどれだけ幸福な散策を繰り返したにせよ、畢竟それは、他者の視線をたくみに回避しつつ、こちらの視線だけを地名や書物にぶつけて、その『言表』のクッションボールを架空の物語に仕立てあげていたにすぎないのではないだろうか」 そう、そして回避していた「他者の視線」を、おそらくは意識的に取り込むことで、彼の「架空の物語」はもっと豊かなものとなったのでした。もちろん堀江敏幸がこの文章を書いてからもう10年以上が経過し、『いつか王子駅で』や『熊の敷石』からも6~7年がたっています。きっと「その後」の堀江敏幸はまた変わっていくのでしょう。僕の目の前には、つい最近某新古書店にて100円で手にいれた単行本版の『雪沼とその周辺』が積んであります。2008年の堀江敏幸までまだまだ先は長い。楽しみです。 ←もしよろしければclickを!
2008年03月05日
コメント(1)
-

主人公の条件
「文学は、ぼくたちがよく知っている世界とは異なった風景を見せてくれる。だが、同時にあまりに異なった風景を人は本能的におそれる」(高橋源一郎『人に言えない習慣、罪深い愉しみ』) Amazonのレビューや、ブログのレビューなどを読んでいて、最近気になるのが、「主人公に共感できない」という評、ないしは感想を、しばしば否定的な評価の理由として見かけることです。主人公(もしくは登場人物の誰か)に感情移入して読むというのは、確かに1つの小説の読み方だし、それを要求している小説もあるでしょう。でも、何も世の中そういう小説だけではないだろうと思うし、そういう小説に「共感できない」と言うのは、少し的外れではないかと。 かつて高橋源一郎が、小説を読むというのは、「別の人生」を生き直すことだと、どこかで書いていました。主人公が自分が思いもよらないような思考を展開したり、自分にはとても縁のないような経験をするのを読んで、それを読者自身が「生きてみる」こと。「共感」とか「感情移入」が、主人公を自分に引き付けることだとすれば、別の人を「生きる」というのは、むしろ自分を主人公に引きつけてみることではないかと思います。それは言い換えれば、自分以外の「他者」に出会うことと言ってもよいかもしれません。少なくともそういう小説の読み方というのもある筈。 ただ一方で、全く馴染みのないもの、全く理解できないもので埋めつくされた小説というのは果して可能なのだろうかとも考えます。以前『ネシャン・サーガ』について触れたとき、その世界が読者にひどく馴染みのあるものから出来ていると書きましたが、最初から最後まで本当に全く想像もつかないようなものしか出てこない小説というのは、おそらく存在しているのでしょうが、読むのも書くのもひどく困難なものになるような気がしてなりません。 その後、『ラナーク:四巻からなる伝記』を読んでいるときに1つ気がついたことがありました(ちなみにラナークは読みかけのまま中断しています)。『ラナーク』の第一部は、私たちが馴染んでいる世界とは相当かけ離れた、加えて通常のファンタジーやSFでも余り出てこないような、とても異質な世界が描かれます。つまり、ファンタジーとしての「純度」が高い世界。そこの世界に住んでいる人々の行動も、今ひとつ理解不能です。ただそれでも、主人公の行動だけは、共感できるかどうかはともかく理解はできるようになっています。主人公はその異質な世界に馴染んでいないという設定のために、その世界を「おかしな」世界と感じることができ、読者もまた主人公を通じて、その世界が「おかしい」ことを再確認できるのです。おそらくそうすることで、読者は異質な世界と関係を持つことができるのでしょう。 ファンタジーやSFに限らず、例えば外国を描いた日本の小説が、しばしば主人公を日本人に設定するのも同じ理由なのだと思います。須賀敦子、堀江敏幸、堀田善衛等、自分の海外での経験を基にして、エッセイともフィクションともつかないものを書く人たちはもちろんですが、完全なフィクションでもそういうものがしばしば見受けられます。思いつくままに挙げれば、加賀乙彦の『フランドルの夜』もそうだし、辻邦夫の『夏の砦』もそうだし、今たまたま読んでいる、多和田葉子の「ペルソナ」(『犬婿入り』所収)もそうです。小説ではないですけど、浦沢直樹の『MONSTER』もそうですね。あれなんか、どうして主人公が日本人でなければならないのかさっぱりわからないのですが、多分そうしないと、読者が物語に付き合ってくれないということなのか。 そこまで考えて思い出したのが、カフカの『城』。あれは、小説の舞台となる町と城が、何かある論理に従って機能しているようなのに、その論理が判らず、従って町や城に住む人々の行動も理解できないというだけではありませんでした。主人公たる測量技師Kは、読者と同様、一応その町の仕組みや人々の行動が「理解できない」ことを表明してくれるのですが、そもそもそのKの行動自体も、行き当たりばったりで何がしたいのだか、読者には(少なくとも僕には)さっぱり「理解できない」のです。『審判』とか『変身』は、もう少し主人公の行動や感情が理解できた気がするのですが、ともかく『城』は、そこに出てくる登場人物の誰一人として理解も共感も出来ないという恐ろしい小説なのでありました。いやあ、読みにくかったわけです。一応最後まで読みましたけどね。 それでもまだ『城』に出てくるのは人間であって、理解はできないにせよ、一応人間らしい行動はしてくれる。これが人間以外の生物だったらどうなるんでしょう。人間とは全く違う論理で動き、全く違う事を考え(そもそも考えるのか?)、全く違うことを行う生き物しか出てこない小説って可能なんでしょうか。『ウォーターシップダウンのうさぎたち』とか『冒険者たち』とか、基本的に動物しか出てこない名作もありますが(どちらも大好きです)、そこでは動物を擬人化して描いているわけで、何もうさぎ的思考、ねずみ的思考を追求しているわけではない。せいぜい私たちが普段馴染んでいるものについて違った視点を提供してくれるくらいです(それはもちろん夏目漱石の『我が輩は猫である』、及びそれへのオマージュである井上ひさし『ドン松五郎の生活』も同様)。そうではなくて、全く異質な思考を人間の言葉に翻訳したような・・・。そんなことを夢想していたら、昨日ブックオフでたまたまベルナール・ウエルベル『蟻』という小説を発見してしまいました。何でも「主人公はアリ」とのことですが、まあ、パラパラ見た限りでは、人間も出て来るようだし、多分そんなにラジカルな小説ではなかろうと思いつつ、つい購入(上下で200円だったし)。いや、もしかすると、出来ればそんなにラジカルな小説でない方がありがたいのかも・・・。
2008年03月02日
コメント(0)
-

語るに忍びざるもの~『本泥棒』をめぐって・その2
「彼女は女の子だった ナチ政権下のドイツで。 そういう状況で言葉の力を発見したのはなんとふさわしいことか」 (マーサーク・ズーザック『本泥棒』) (今回は、前回の続きになっていますので、もし読んでいないという方がいましたら、一つ前のエントリから読んで頂ければと思います)『本泥棒』の語り手は「死神」です。この突拍子も無い設定と、その「死神」による、スラスラと流れるような語りというよりは、どちらかというとランダムでゴツゴツとして語りは、最初ひどく戸惑いました。けれども読んでいくうちに、その純粋な一人称でも純粋な三人称でもない不思議な文体が、語られる対象との絶妙な距離感を生み出していることに気付き、全く違和感が無くなるとともに、むしろこの小説はこの語りの形式でなくてはならなかっただろうとまで思うようになってしまいました。一人称や三人称であれば、おそらくこの小説はもっと感傷的でべたべたしたものになっていたでしょう。それがこの形式によって、「優しく突き放す」ような適度にウェットなリアリズムが実現している。またおそらくこの形式は、全知の神のような存在による語りという形式で書かれた19世紀小説のパロディなのでしょうが、19世紀小説の「全知の神」が実のところ作者の化身であるのに対して、『本泥棒』の死神は作者ではない。そのため、作者にすら語りにくいことを、「死神」が代わって語ってくれるということになるのです。本の帯には、『タイム』誌からの引用として「すごみのあるブラックユーモアを使って、一見暗く暗鬱な主題を耐えられるものにしている」という評が載っていて、「暗く陰鬱な主題」を「耐えられる」ものにすることが果して必要なことなのかどうかよくわからないのですが、少なくとも、「死神」でなければ語れないことを語っていることは事実だと思います。何より「死」をその重みをきちんと保持したまま、それでも尚単なる「死」として捉えるという。小説は、主人公の女の子が(盗んだ)本を通じて「言葉」を覚え、「言葉の力」を獲得していくという筋立てになっており、それぞれの章は、そこで重要な役割を果たす「本」の題名になっています。これは本好きにはたまらない仕掛けでしょう。実際、この小説はとにかく本を読む喜びに溢れています。漫然と本を読んでいる日常をもう一度振り返させられるような。ついでに言えば、子供が本を通じて成長していくというのは、とってもジュナイブル的なのですが、それにもかかわらず、物語の最初から、最後はアンハッピー・エンドになることが示唆されており、それがまた物語に緊張感を与えることになっています。もちろんこの仕掛けが無理なく成立してしまうのは、語り手が「死神」であるからに他なりません。 ・・・と褒めちぎってみた訳ですが、実は『本泥棒』を読んでいる間ずっと、こうした巧みさに感心しつつ、一方で何か納得のいかないものを感じ続けていました。それは、なぜこのっマーサーク・ズーザックというオーストラリア人はナチス・ドイツを小説の舞台として選んだのだろうかという疑問です。「訳者あとがき」によれば、作者は最初現代のシドニーを舞台に書こうとしたのですが上手くいかず、ドイツとオーストリア出身の両親から何度も聞かされた2つの話に、「本を盗む」というモチーフを合体させたところ、話ができあがったとか。けれども、前回書いたように、「ナチス」とは何なのかということをグダグダと考えていた僕は、もしその選択が、単に一つの極限状態を設定することで話をもっともらしくするためだけの選択だったらイヤだなあと感じていたのです。確かにベルリン五輪のエピソードや、ヒトラーの誕生日の描写、ホロコーストへの言及等々、物語の背景もとても丁寧に描かれてはいます。でもそれにしても、下手すると世界史の授業のようになりかねない気もして、やっぱこの物語がどうしてもナチスドイツでなくてはいけないのかどうかが納得できなかった。 物語を残すところ後4分の1程度、というところで、突然そのことが腑に落ちました。詳しく書く訳にはいかないのですが、これは単に「言葉の力」について書いているだけではなく、「ことば」による支配に抗するための「ことば」の力について、さらには同時にその無力についても書こうとしているのだと気がついたのです。いや、小説のテーマを1つに絞ってしまうのは危険なことなので、言い換えますと、これが「ことば」をめぐる支配と(しばしば無力な)抵抗についての物語だと捉えることで、僕にはこの小説が一挙に説得力のあるものになったのです。ナチスを「言葉による支配」と捉えること。そしてそれを丁寧に描き出すことを通じて、「言葉による支配」は今もなお、決してなくなってはいないということを示唆すること。現代と歴史的出来事を無理矢理に結びつけるのではなく、一つの歴史的事例を丁寧に描ききることで、そこから現代にも連なるようなテーマを掘りおこしてくること。この小説がしていること(の1つ)はそれなのだと。それはまさに、「ナチス」とはそもそも何かと考えている僕に、何か手掛かりを与えてくれるものでもありました。 そうすれば、上で褒めちぎったような技巧の数々も、単なる技巧のための技巧ではなく、そのテーマを生かすために何より必要な要素に思えてきます。つまり、小説としての楽しみを十分に備えつつ、なおかつその楽しみを通じてさらに多くのものを掬いだしてきている、と。うーん、実に見事です。読み終えたときの充実感は相当なものがありました。小説にはまだまだこんなことが出来る。いや、「言葉」にはまだまだこんなことができる。陳腐な表現になってしまいますが、本当に「全ての本好きに贈る」です。追記:昨夜、ブログを書き終えた後、本棚の奥からH・マウ/H・クラウスニック『ナチスの時代――ドイツ現代史――』(岩波新書)が発掘されました。ひとまずこの本でも読んでもう少し勉強したいと思います。なお、1つ豆知識を。『本泥棒』の冒頭には、「死神」が赤・黒・白の3色について語るシーンがあり、「訳者あとがき」では、その3色がナチスの鉤十字の色でもあると説明しているのですが、『ナチスの時代』によると、そもそも赤・黒・白というのは、1918年以前の帝政ドイツの旗の色でもあり、1918年以後も、それを誇示することが、黒・白・金で出来たワイマール共和国の旗に対する敵意を表現することだったそうです(そしてその敵意を、ヒトラーは利用した、というのが『ナチスの時代』の作者たちの主張のようです)。 ←もしよろしければclickを!
2008年02月27日
コメント(0)
-

語るに忍びざるもの~『本泥棒』をめぐって
マーサーク・ズーザック『本泥棒』は、本の宣伝文句を見ればすぐさまわかるように、舞台がナチスドイツに設定されています。今年に入ってクラウス・コルドンのベルリン・シリーズを読むことで20世紀前半のドイツに一層の興味を持つようになり、その一方で去年はクリストファー・プリーストの『双生児』やサラ・ウォーターズの『夜愁』など、たまたま第二次世界大戦時を扱った本を幾つか読む機会があった僕としては、その2つがちょうど重なる時期を扱ったこの本に、とても良いタイミング出会えたなと思って最初は手に取りました。小説としての楽しみを期待することはもちろんですが、同時にナチスというドイツ史上、いや世界史上類いまれなる重要性を持った事象について、その同時代的な文脈で考えるヒントが得られるであろうとも思いながら。 さてナチスについて考える際に、しばしば重要なのが、ナチズムというものが何故実現してしまったかという問いです。これはつまるところ、以前書いた「ワイマール期」の評価にも関わることで、実際クラウス・コルドンは、1919年の王制廃止に始まる一連の事態が、ナチスの台頭を阻止するべきであった筈の勢力を分断してしまい、その結果として1933年にヒトラーが政権を取ることを許してしまったと考えているようです。いやそこまで楽観的ではないかもしれませんが、少なくとも組織立った抵抗運動が出来なかったということは強調しています。だからこそ彼は『ベルリン1919』と『ベルリン1933』を書いた。 多少(僕が)単純化してしまっているにせよ、ともかく、反対勢力がきちんと結集していればナチスを阻止できたかもしれないという、それなりにポジティヴなこの観点に対して、もっと徹底的にネガティブな観点ももちろんあります。例えば歴史家のホブズボームは、以前にも紹介したLondon Review of Books(vol,29, no.16)のエッセイで、ワイマール政府が、ナチスではなく、もっと伝統的な保守政権によって取って代わられたほうがまだ良かったかもしれないという議論に対して、それは「ヒトラーの台頭を、包括的な反ファシスト連合によって防ぐという展望と同じくらい非現実的だ」と指摘し、さらに続けてこう書いています(下手な翻訳ですが許して下さい)「右派であれ左派であれ中道であれ誰一人として、ヒトラーの国家社会主義という、それまで誰も見た事が無く、その目的は理性的に考えると想像もつかないようなものであった運動を見定めるための現実の基準を持っていなかった、というのが事実である」 これはこれでなかなかに陰鬱な凄みを持った主張です。同じような見解を、文化史家のスチュアート・ヒューズが書いた『大変貌』の中にも見つけました。ジュゼッペ・アントニオ・ボルゲーゼという歴史家がこんなことを言っているそうです。「一世紀以上ものさまざまな予言の時代の間にも、一人の予言者も……ファシズムのようなものを想像しなかった。来るべき未来のうちには、コミュニズムやサンディカリズムやその他諸々はあった。アナーキズム……戦争、平和、大洪水、汎ゲルマン主義、スラヴ主義はあった……。だが、ファシズムはなかった。それは誰にも意想外に出現した……」こうして見ると、ナチズムがなぜ登場したかについて考えることは、そのままナチズムそのものについて考えることにつながるということになります。しかしここまで来て、僕は立ち止まってしまうのです。ナチズムについて考えるためにヒントと最初に書きましたが、ではそもそも、その考える対象そのものについて一体僕は何をどこまで知っているのだろうかと。教科書的な知識は一応あるつもりです。ハンス・リヒターの『あのころはフリードリヒがいた』やフランクルの『夜と霧』といった「定番」は読みました(ただ『アンネの日記』は読んでおらず、『本泥棒』の宣伝コピーが『アンネの日記』+『スローターハウス5』となっていたので、慌てて『アンネの日記』も買うだけは買いました)。ランズマンの映画『ショアー』も観たし、それと同時期にプリーモ・レーヴィの『溺れるものと救われるもの』も読みました。去年は偶然に、河島英昭『イタリア・ユダヤ人の風景』という素晴らしい本に出会い、その流れでかねてから読もうと思っていた徐京植の『プリーモ・レーヴィへの旅』も読むことも出来ました。 しかし、実のところ、こうしたものに触れてわかることは、圧倒的なまでの「言葉にならなさ」です。『ショアー』を観た後の感覚は今でも忘れません。何というか、自分が普段生きているのとは全く関係のない世界に一人投げこまれてしまい、その世界では誰ともコミュニケーションが出来ないし、かといってその世界について現実に周りにいる人に話そうとしても、どういう風に話したらよいのかさっぱりわからない・・・という。とにかくたまらなく淋しくて、その日はずっと誰かに何かを話をしたかったのですが、どうせ話しても通じないだろうなあと思いつつ結局何も話せずじまい。比べるのもおこがましいですが、その後で読んだプリーモ・レーヴィの本では、強制収容所から帰還した人々が、そこで起ったことが余りに信じ難く、また言葉にすらならないので、その経験を誰に話しても信じてもらえないだろうと考えたという話が書いてありました。そして徐京植の『プリーモ・レーヴィへの旅』に詳しく書いてあるように、アウシュビッツからの生き残りであるプリーモ・レーヴィは、それでもなお強制収容所について書き続けたものの、ある日身投げをしてしまうのです。ホロコーストは、そうしてひたすらに理解されることを拒もうとし続ける。 そしてさらに言えば、こうした「言葉にならなさ」にしても、さしあたり「ホロコースト」に限ったことであって、ナチズム全体についてではないのです。つまり「ホロコースト」について仮に何かをつかんだとしても、それを生みだしたナチズムについては、まだまだ全然手が届かないということ。「ホロコースト」というのが、ナチスが行った想像力を絶するようなことの1つであるのは確かです。でもそれがナチスの全てではない。アドルノが論文「文化批判と社会」(『プリズメン』に所収)に書きつけた「アウシュビッツ以後、詩を書くことは野蛮である」という有名すぎる言葉にしても、それが何を意味するにせよ、「アウシュビッツ」という言葉が、それを生み出したもの、そしてそれを生み出したものを支持したもの全てを指しているのは間違いないでしょう。そしてそれこそが、まさに「それまで誰も見た事が無く、その目的は理性的に考えると想像もつかないようなものであった運動」というわけです。しかしその運動の全体について僕が一体どれだけのことを知っているかと言えば、まあ殆どゼロといってよいでしょう。しかしそんな状態で、果して「ナチズムについて考える」などということが出来るのか・・・。今のところ僕に思いつくことは、ようやっとエーリッヒ・フロムが『自由からの闘争』を書いた理由が腑に落ちたとか、ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』を今更だけど読んでみなくてはとか、ひとまずそのくらいなのです・・・。『本泥棒』の感想を書くための前置きのつもりだったのですが、すっかり長くなってしまいました。『本泥棒』そのものの感想については、次回に回したいと思います。すみません・・・。
2008年02月26日
コメント(0)
-

こことは違う場所、こことは違う時間
以前、アメリカの古生物学者スティーブン・ジェイ・グールドの『ダーウィン以来』を読んでいたら、ほ乳類が一生のうちに呼吸する回数はみな同じだと書いてありました。ちょっと驚いて、念のために動物学者の本川達夫さんが書いた『ゾウの時間 ネズミの時間』を確認してみると、やっぱり、殆ど全てのほ乳類は、一生をトータルで見ると同じ回数だけ呼吸し、同じ回数だけ心臓を動かしていて、その呼吸の間隔や心拍数は、体重に比例して変わっていくのだとなっている。つまり小さな動物(そして寿命の短い動物)ほど、それだけ速く呼吸し、心臓を動かして生きているということ。だから猫を見て、のんびりしているなどと思うのは、人間の単なる思いこみで、猫は猫なりに、人間なぞよりはるかに猛スピードで生きていて、むしろ人間の方がずっとゆったりとして生きているということになる。もちろん、これは時計の時間で比べるからそういうことになるのであって、むしろ猫と人間は、比べるのもバカバカしいほどに、違った時間の中を生きていると言ったほうがいいのかもしれませんが。 もちろん、違った時間を生きているのは、動物だけではないでしょう。呼吸の間隔や心拍数はそれほど違わないかもしれませんが、同じ人間でも、子供と大人では、違った時間を生きているだろうと思います(「子供の時間」なんて言い方をよくしますね)。もっと言えば、時間の違いは子供と大人だけでもない筈。以前、インドネシアを旅した人のこんな話を聞いたことがあります。彼が田舎を歩いていると、とてもゆったりしたペースで農作業をしているお婆さんたちを見かけ、普段は自分でも農業をしている彼は、そのペースなら簡単についていけると思い、作業に参加したそうです。けれども、いざ参加してみると、作業はものすごい速さで進行していて、彼は全くついていけなかった。相変わらず、お婆さんたちの作業はゆったりのんびりに見えるのに。 よく、どこそこでは時間がゆっくり流れているなどといいますが、簡単にそういうことを言ってはいけないのだと、その話を聞いて思いました。速いとかゆっくりとかではなく、そういうところでは多分、流れている時間の種類が全く違うのだろうし、そもそも同じ速さの基準で比べることができないのだと。 以前このブログでもちょっと名前を出した森田裕子さんの書いた『内側の時間――旅とサーカスとJ・L・G』という本を読みながら考えていたのはそんなことでした。森田さんは、以前フランスのサーカス学校に留学して、サーカスの研究をし、そして日本に戻った後に『サーカス そこに生きる人々』を書いた人で、彼女はそれからしばらくして、またフランスに行き、今度はサーカスを手伝いならが、一緒に旅をして生きていく生活を始めました。『内側の時間』はそのことを綴った本です。題名にも「時間」という言葉が使われているように、森田さんはサーカスに流れている、別の「時間」にこだわります。それはショーが行われている間に流れている「曖昧な」時間のことだけではありません。キャラバンで巡業していくサーカスのカンパニーは、日々の生活そのものが、独自のテンポで動いているし、ヨーロッパ中を旅するキャラバンは、行く先々で違う時間に出会う。「内側」の時間というのは、ショーの「内側」であり、またショーを演ずる人の「内側」なのだけれど、森田さんはショーの「外側」の時間も随分強調しているように見えます(巻末には森田さんが撮った何枚もの写真が収めてありますが、ショー自体の写真は一枚もないのです)。 森田さんはさらに、そうした違う「時間」を生きることの難しさについて、主にサーカスと文化政策の関係を通じて、所々で考察を展開しています。残念なことにこの考察の部分は、抽象的なのに舌足らずで非常に読みにくく、ときに単純すぎで、あまりほめられたものではありません。ただ少なくとも、違った「時間」を生きることが、フランスであれどこであれどんどん難しくなっているように感じるのは確かだと思います。もちろん日本でもそれは同じこと。違う時間が流れる違う場所には、多分違う言葉があって、違った人間関係がある筈で、違う時間が難しくなっていくということは、そうしたものも難しくなっていくということだから、それは考えてみればひどく息苦しく、そしてひどく寂しいこと。いや、本当は寂しがっているだけではいけないのでしょうけれど。
2008年02月23日
コメント(0)
-

ジプシーの音楽地図
確か一昨年の11月くらいだったと思うのですが、関口義人『ジプシー・ミュージックの真実』という本を読みました。ルーマニア、マケドニア、ブルガリア、ハンガリー等々、東欧諸国を巡って、それぞれの国のジプシー(ロマ)とジプシー音楽について説明するという内容の本。そのずーっと前に、クストリッツァの映画『アンダーグラウンド』を観て衝撃を受け、思わずファンファーレ・チォカリーアのアルバムとゴラン・ブレゴヴィッチのアルバムを一枚ずつ買ってしまいつつも、その後はジプシー音楽のCDを買うこともなく、クストリッツァの映画『黒猫・白猫』やトニー・ガトリフの映画『ラッチョ・ドローム』『ガッジョ・ディーロ』なども見逃してしまった僕としては、改めて東欧のジプシー音楽と出会い直さなくては!と思い、関口さんの本を手に取ったのでした。 そして本はまさに期待通り。文章自体にはやや不満が残ったものの、それを補って余りある丁寧で豊富な説明には大満足でした。ジプシーが元々インドの辺りから旅を続けて東欧の方にまでやってきたこと、そしてその行く先々でその地の音楽に影響を与えて来たことなどはぼんやりと知っていたのですが、そのインド発祥説にも疑義が呈されていることや、東欧のジプシーと一口にいってもその辿って来た歴史も、そしてもちろん音楽も、国によって、さらには一国内の地域によっても全然違うこと等々、全く知らないことばかり。安易に「東欧のジプシー音楽」等とひとくくりにしてはいけなかったという訳です。もちろん東欧以外にも「ジプシー音楽」はあって、それらもまた実に雑多であることは言うまでもないありません。 本を読んだ後、巻末に紹介されているCDを何枚か買い、いつの日か関口さんのように生で演奏を聴きたいなあとか、やっぱりガトリフの映画は何としてでも観ないとなあ、などとぼんやり考えつつそれから1年。映画『ジプシー・キャラバン』公開を知り、これは何としてでも観に行かなくてはと思い、早速劇場に足を運んだ次第です(そういえば今年になって劇場で映画を観るのは初めてだ)。 映画は2001年にアメリカで行われた、ジプシー音楽のコンサート・ツアー(そのツアー・タイトルが『ジプシー・キャラバン)の様子を記録したドキュメンタリー映画です。コンサートの出演者はルーマニアのタラフ・ドゥ・ハイドゥークフ、マケドニアの「ジプシー・クイーン」ことエスマ、インドのマハラジャ、スペインのアントニア・エル・ビバ・フラメンコ・アンサンブル、そしてルーマニアのファンファーレ・チョクルリーア(CDと日本語表記が異なりますね)。 映画の半分はツアーの様子ですが、ツアーの映像の合間合間に、ツアー後に収録されたそれぞれのミュージシャンの出身地の映像やそこでのインタビューが挟み込まれます。その編集はなかなかのものだし、何よりミュージシャンたちの言葉や行動は、ツアー中でも地元でもとても魅力的でとてもおかしい。なので音楽に全く興味が無い、という人には辛い映画かもしれませんが、ジプシー音楽にさほど親しんでいない人でも楽しめる作りにはなっています。というか、ジプシーの迫害の歴史や、彼らの音楽に込められたものについて、簡単なコメントは幾つか聴かれますが、そうしたことについての詳細な説明はあまり無いので、コアなジプシー音楽ファンの人には少しもの足りず、むしろジプシー音楽の入門として最適かもしれません。 僕にとっては、ミュージシャンたちの地元をちゃんと紹介してくれるこの映画を見ることは、関口さんの本と合わせて、自分の頭の中にジプシー音楽の「地図」を作り上げることでした。ジプシー音楽発祥の地(ということになっている)インド、ジプシー音楽と密接な関係を持つスペインのフラメンコ、そして東欧のそれぞれスタイルの異なるジプシー音楽。そもそもジプシー音楽に限らず、音楽は人と一緒に旅をし、そこに音の痕跡を残します。その痕跡を確かめて行けば、そこには1つの「地図」が出来る。以前、知り合いのウード(アラブの弦楽器)奏者に、弦楽器の「旅」の話をしてもらったのですが、それはまさに音楽で地図を描くことでありました。そうした地図をも沢山自分の中で持っていたいと、とてもとても思うのです。もちろんその作業はまだまだ始まったばかり。ジプシー音楽以外にも聴きたいCD、読みたい音楽関係の本は沢山あるのですが、ひとまずやっぱりジプシーの歴史をもっとちゃんとおさえたいなあ。関口義人さんの本もまだまだ他にあるし、『立ったまま埋めてくれ』なんていう切ない題名を持った本も読みたい本リストの上位に位置したまま。何とか時間を作って、読んだ報告をまたこのブログでしてみたいと思っています。 追記:ジプシー音楽初心者がエラそうに何ですが、買ったCDの中で一枚だけ紹介を。ハンガリーのバンド、Romano Dromの『Ando Foro』は、聴きやすいけど、ジプシー音楽の持つ音の緊張感がしっかりと込められている良いアルバムでした。興味はあるけど何から聴いてよいかわからないという人にはぜひオススメ。 ←もしよろしければclickを!
2008年02月20日
コメント(0)
-

ある町の記憶
「今日あるがままのザイラを描きだすということにはまたザイラの過去のいっさいが含まれておるはずでございましょう。しかし都市はみずからの過去を語らず、ただあたかも掌の線のように、歩道の縁、窓の格子、階段の手すり、避雷針、旗竿などのありとあらゆる線分と、またさらにその上にしるされたひっかき傷、のこぎりの痕、のみの刻み目、打った凹みといったなかに書きこまれているままに秘めておるのでございます」 (イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』)以前、このブログで『ベルリン1919』を取り上げたときに(「ベルリンの傷跡」)、「痛ましい記憶が傷跡のように残っている」とか何とか書きました。その後、上に引用したカルヴィーノの文章を見つけ、上手いこと書くもんだなあと感心することしきり。僕が書きたかったことを、もっと暗喩的に、かつより普遍的で的確に表現するとこういうことになります(何も記憶は「痛ましい」ものだけではないですものね。さてさらにその後、松山巌『手の孤独、手の力』を用事があって読み返していたら、その中の「河口の舟に視入る影」という短いエッセイに、少し形は異なるのですが、やはり似たような「都市の記憶」についての記述がありました。東京は多摩川の河口にある羽田の町を、松山さんが1975年頃に訪れた頃の話です(尚、羽田市とか羽田町とかいった地名はありません。羽田空港のある辺り一帯のことを指している模様) 何でも羽田空港の駐車場には、神社も無いのに鳥居だけがポツンと立っているらしいのですが、その鳥居について松山さんは色々な「うわさ」を耳にします。やれ鳥居を動かそうとした米兵が痺れたとか、熱を出したとか、はたまた鳥居を動かしたら飛行機事故が増えたので元に戻したとか、とにかくその町の色々な人が色々なバージョンの「うわさ」を教えてくれる。さらに松山さんが調べてみると、この町には他にも昔から色々な「うわさ」が伝わっていて、大正時代には、近くの「味の素」の工場では蛇の粉を使って「味の素」を作っているという「うわさ」まで流れたとのこと。松山さんはそこからさらに筆を進めて、「味の素」の「うわさ」の奥に、工場の排水によって漁師たちが仕事を奪われたという経験を、そして鳥居をめぐる「うわさ」の奥には、進駐軍によって町の一部が接収され飛行場に変えられてしまった経験を見て取ろうとします。もちろん松山さんは、漁師たちが意図的に「うわさ」を流したとか、米兵に対する反感から「うわさ」が作られたとかいいたいのではありません。ただ、工場や進駐軍をめぐって様々に積み重なった複雑な思いが、「うわさ」の中には込められているのではないか、と。そして彼はこう書きます。「戦後にはこのほかにも、羽田では昭和29年(1954)の重油流出事件(東京ガスの二十トンもの重油が海面に流れ、海苔にも大被害を与えた)や昭和39年(1960)の学生闘争、ハガチー事件など数多くの事件が起きている。にもかかわらず、これらのことを語る方は少なくとも私が聞いた範囲ではいなかった。尋ねなければ答えようもない、遠い話のようだ。海を埋め立てたコンクリートが彼らの口を閉ざしている。 しかし厚いコンクリートを剥がせば、羽田の、いやどの町においても呟きが聞こえて来はしないだろうか。ただ、私たちはいま彼らの黙して語らぬことの重さをこそ噛みしめるべきであろう」 エッセイを読み終えて思ったのは、これで1つミステリが書けそうだな、ということでした。いや何も必ずしもミステリである必要はないし、そもそも「厚いコンクリートを剥がす」というのは小説に出来る重要なことの1つだとは思うのですが、ミステリというのはとりわけそれに適したジャンルだと思うのです。トマス・H・クックがやっていることなんてまさにそうした「記憶」の掘り起こしと言えるでしょう。ただ残念ながら、僕は今のところ日本のミステリで、そうした作品に出会ったことはありません。以前触れた芦辺拓の『時の誘拐』はそうした意図を持っていたと思うし、ある土地の伝承を利用するというのであれば、例えば米澤穂信の『犬をさがせ』なんかがそうでした。でもどちらも、上に書いたような重く積もった複雑な「土地の記憶」を掘り出すまでは到底行っていないのです。もちろん僕が単に知らないだけで、きっとどこかにはあるのでしょう。そうした優れたミステリに出会うことを夢見るというのも、それはそれで悪いことではない筈です(そういえば浦沢直樹の『MASTERキートン』の中に、まあまあいい線を行っているエピソードがあったなあ)・・・。追記:なお、上に取り上げたエッセイだけでなく、『手の孤独、手の力』は、同じ「松山巌の仕事」シリーズ『路上の症候群』とともに、とても良い本です。またこのブログで取り上げることもあるかと思いますが、ともかくオススメですよー。 ←もしよろしければclickを!
2008年02月17日
コメント(0)
-

桜庭一樹と「歴史」の感覚
「歴史的瞬間に立ち会う」とか「その時歴史が動いた」といった言葉を僕は好みません。理由は至って単純。歴史はいつだって「動いて」いるし、私たちが生きている刻一刻が「歴史的瞬間」だと思うからです。「歴史的瞬間に立ち会う」といった発想は、大きな「歴史的」出来事をつないでいく歴史観を根拠にしています。そうした歴史観ももちろん必要ではあるのですが、そうした「歴史的」出来事にしたって、その前後に営まれている日々の生活の積み重ねの上にあるという、別の歴史観も大切にしたい、と。 こう書くと、何だか、以前の「文化史としての歴史小説」と同じようなことを書いていると思われる方もいるかもしれませんが、その通りです。というか、その後桜庭一樹の『青年のための読書クラブ』『少女七竃と七人の可愛そうな大人』を立て続けに読みまして、少し桜庭一樹が持っている「歴史意識」のようなものについてもう少し書いてみたいなと思ったのでした。 読んだ方はご存知の通り、『青年のための読書クラブ』は、都内のとある女子高を舞台にした短編がオムニバス形式で並んでいて、それが全体としてその女子高の100年の歴史を描き出しているという構造になっています。ただ『赤朽葉』とは異なり、基本的に歴史はその高校の中で閉ざされており、高校の外で動いている歴史の流れについては簡単に触れられるくらいです。ですから1910年代から2019年までの100年を扱っているといっても、日本の二十世紀を描く!などという壮大な野心を持っているわけではない。それでも感心してしまったのは、たとえ閉じた世界についてのことであれ、こまごまとした歴史の積み重ねとして「現在」というものがある、という感覚が伺えるからです。これは、大きな「歴史的」出来事と現代とをアクロバティックに結びつけるようなやり方(いくらでも例はありますが、例えば村上春樹の『ねじまき鳥』にもそういう技巧的なものを感じました)よりもずっと繊細な歴史感覚ではなかろうかと思うのです。 『赤朽葉』以前に書かれた『少女七竃と可愛そうな七人の大人』(そういえばこれは「ミステリ」ではありませんでした)の場合は、舞台は現代から動きません。描かれるのは旭川の小さな町の狭い血縁関係。共同体のどろどろした血縁関係を書くというのはミステリに限らず日本の小説の大好きなテーマですが(僕は根拠なく、これは19世紀フランス自然主義の悪影響ではないかと思っています)、桜庭一樹は、そうしたどろどろした血縁関係を描くというよりは、少女七竃が、その血縁関係を知ることを通じて、自分という存在を作り上げて来たものをきちんと見定め、そうして成長していく様を描いているように思えます。単に血縁関係だけにこだわるのではなく、一緒に住んでいる祖父、時々一緒に住む母、そして七竃という3世代のそれぞれの生き方を意識的に比較しているのもおそらくはそういうことで、これもまた歴史意識といって良いのではないかと。実際この「3世代」というテーマは『赤朽葉』にも引き継がれるわけですしね。 そしてつまるところ桜庭一樹は、『砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない』『少女には向かない職業』等で、殺すか殺されるのかのギリギリのところで生きながら、それでいて(だからこそ?)生の感触が乏しい現代の少年少女たちを描き出した後に、どうすれば今の世の中で、より肯定的な生の感触を取り戻し、誰も殺すこともなく生き延びることが出来るかを考えようとし、それをまず「現代に歴史的に捉える」ことを通じて行おうとしたのだと思うのです。『七竃』『赤朽葉』『読書クラブ』の全てに共通しているのは、過去が常に未来へと開かれている、ないしは開かれようとしていることです。そしてついでに言えば、未来へと開かれている過去というのは、必然的に「老い」という問題とも直面しなくてはいけないのですが、『七竃』や『読書クラブ』のもう1つの重要なテーマはまさにその「老い」。桜庭一樹の少女趣味というか少女好きははっきりしていますが、彼女は少女を少女のままに留めておくことを拒絶します。それもまたもしかすると、歴史と向き合う以上避けられないことだったのかもしれませんが。 こういう筋の通し方をする作家って、いるようでいない気がします。少なくとも僕はそういう現代の日本人作家を殆ど知らない。相変わらずほめ過ぎな気もしますが、僕にはかなり稀有に思えるこの作家を、もう少し読み続けてみたいと思うのでした。うーんまずは『ブルースカイ』と『私の男』を読まなくちゃ、ですね。 ←もしよろしければclickを!
2008年02月14日
コメント(2)
-

地図にない場所
「地図にない場所をさがしたくて 地図ばっかり眺めてた」(知久寿焼『地図にない場所』)「どこに意識をむけても、肉体と意識をもった人たちがうろついているのが見えた。どんな地図にも載っていない情報だ」(スカーレット・トマス『Y氏の終わり』) 言葉と現実の関係というのは、哲学や文学の世界では、昔からずっと最重要の問題の1つです。存在している現実に言葉をあてはめているのか、それとも言葉で認識するから現実が存在するのかという大問題がまずあって、それに関わって、例えば詩人や芸術家といった特殊な人だけが認識できる高次の現実があるという考え(ロマン主義)とか、言語というのは現実に恣意的に対応する記号のシステムでしかないという考え(構造主義)とか、言語は現実に対応しないで勝手に意味を作り出すシステムだという考え(ポスト構造主義)だとか。 いや、こんなことを書いたのは、何も生半可な知識をひけらかすためではありません。今朝読み終えたばかりの『Y氏の終わり』が、まさにこういったことをテーマにした小説だったからです(『Y氏の終わり』はshovさんのブログで知りました。shovさんに感謝!)。何しろ、このお話自体が、人間の意識の世界を飛び回るというもので、主人公はデリダが大好きな英文学専攻の大学院生。そしてその主人公のモノローグや他の登場人物との会話の中では、やれ宇宙の発生はどう解釈できるかとか、相対性理論とはいかなる「物語」かといった、およそ「認識」をめぐる議論が次から次へと出て来るのです。「思考実験」という言葉が小説の中には頻出するのですが、この小説自体、一つの思考実験といってもよいかもしれません。人間の意識の世界というものが存在するとすればそれはどんなものであるか?という。 そもそも小説というのは、高次の現実云々は脇においておくとしても、言葉だけで世界を構築するという特異な性質を持っていて、その点では思考実験にぴったりと言えます。本には書いてあるのは(挿し絵がついていることはありますが)基本的には黒い文字だけ。それなのに、私たちはそれを読んで様々なイメージを作り上げるのですから。おそらく「わかりやすい」とされる小説というのは、そのイメージを作りやすい本のことを言うのでしょう。自分が生きている現実にとても近い世界を描いていればイメージはしやすいし、子どもの本に挿し絵がついているのも、イメージを作るのを手助けするため。でも、到底想像のつかないような世界を言葉で作り出してしまうというのも、小説の大切な1つの役割の筈です。そして『Y氏の終わり』は、少なくとも「意識の世界」という捉え難いものを描き出すということには、結構成功しているように思います。 さて、『Y氏の終わり』を読んでいる最中、急激に普通の「ファンタジー」小説を読みたくなってしまい、ラルフ・イーザウの『ネシャン・サーガ1・ヨナタンと伝説の杖』を図書館から借りてきて、『Y氏』と並行しながら読んでいました。この本は、数年前のハリー・ポッターの大ブームに便乗して雨後の筍のように出版されたファンタジーの1つで、訳者が『ベルリン』シリーズと同じ酒寄進一さんであるという理由で、僕も途中までは読んでいたものです。改めて読みたくなったのは、一応ファンタジー作品(ミステリ仕立てのSF風ファンタジー?)である『Y氏』がどうにも頭を使って疲れてしまうので、もう少しわかりやすいファンタジーも読みたいなあと思ったからでした(どうも僕自身疲れていたようで、『ネシャン・サーガ』を借りてきた数日後に風邪を引いてしまいました。まだ治りません)。実際、『ネシャン・サーガ』はとても読みやすく、『Y氏』よりも先に読み終わってしまい、今は次を読もうと思っているところです。ただ1つ気になったことがあって、それは「わかりやすい」「読みやすい」ファンタジーというのは一体何なのかということでした。 ファンタジーと言っても色々あるでしょうが、基本的には「どこにもない場所」を描いたもの、もしくは普通の世界に「考えられない事」が起こるもの、のどちらかでしょう(『Y氏』はその両方をやっています)。『ネシャン・サーガ』はもちろん、主に「どこにもない場所」を描いたものです。ただその「どこにもない場所」はやけに想像がしやすい。もともと西欧のファンタジーの多くは、アーサー王に代表される中世騎士物語から素材を取ってきていますし、日本のRPGゲームなどがそれを再生産しているため、私たちが剣とか魔法とか竜とかをイメージしやすいのは当然なのですが、それだけではありません。「ネシャン」という架空の世界に出て来る山は、私たちが普通に想像する山とどうも余り違わないし、それは食べ物や服装にしてもそうです。見た事もないような動物や植物も出て来るには出て来るのですが、それも普通の動物や植物を少し加工すればイメージが作れるようなものばかり。何と言うか、基本的に「想像の範囲」で書かれているのですね。さらには、最近のファンタジーの多くがそうであるように(これはゲームの影響もあるのですが)、ちゃんと地図までついている。だから少なくとも読者は主人公たちがその世界の「どこにいるか」はわかるのです。つまり「どこにもない場所」ではあるけれど「地図にない場所」ではない。 それに比べると、『Y氏』で描かれる意識の世界は、少なくとも私たちが通常思い浮かべるような「地図」で描ける世界ではありません(一応その世界なりの法則はあるようですが)。なので主人公たちがその世界の「どこにいるか」はさっぱりわからない。その意味では、『Y氏』の方がファンタジーとしての「純度」は高いのかもしれない(良い悪いは別として)と思っていたのです。そしてついでに言うと、カルヴィーノの『見えない都市』に描かれた数々の都市は、「どこにあるか」がわからないだけではなく、存在するのかしないのかも、もちろんそれぞれの関係もさっぱりわからない、完全に言葉だけで構築された都市で、その意味では最高純度のファンタジーなのかもしれないなあ、と相変わらずちょびちょびと齧りよみをしながら考えたりもするのでした。
2008年02月10日
コメント(2)
-

喫茶店で読むべき本
今日はちょっと番外編みたいな感じで。 バイト先に新しい古本屋が出来たので、先日あまり期待せずひやかしに入ってみたところ、少なくともいい加減な古本屋ではなく、それなりのこだわりを持ったお店で、何冊か欲しい本が目に留まりました。その時は持ち合わせが殆どなかったので、高橋康也『ウロボロス』にするか寿岳文章『わが日わが歩み』にするか迷った挙句、寿岳さんの本を購入。寿岳さんの名前は、冨山太佳夫の『書物の未来へ』で知ったような気がしていたのですが、帰って確かめてみるとそれは勘違いで、しかも寿岳さんは英文学者であることは確かなのですが、民芸運動などにも関わっていることまで判明し(知らなかったのです)、ウィリアム・モリスと日本の民芸運動とのつながりについての文章まで書いている。そうすると、小野二郎さんの本で名前を知ったのかしらん。いずれにせよ嬉しい誤算でした。それより前にたまたまブックオフで100円で購入したばかりのW・H・ハドソン『はるかな国 とおい昔』の訳者である寿岳しづさんが、寿岳文章さんのお連れ合いであることもWikipediaで知ってますます嬉しくなってみたり。 で、買って返る電車の中や、家に帰って来て珈琲なぞをいれながらパラパラ読んでみたのですが、つくづく思ったのは、ああこういう本は家ではなく喫茶店で読みたい、ということでした。おそらく寿岳さんの本は学問的には殆ど「新しさ」はないのだとは思うのですが、それでも一世代前(二世代前?)の学者が書くようなふるめかしい文章で書かれた短いエッセイの数々はひどく心地よく、そしてこれは、頭をフル回転させてぐいぐいとのめり込むように読んで行く本ではなくて、頭の中に沢山の隙間を作って時々ぼんやりしながら読むような本で、それにはおそらく喫茶店が一番だろうと。 ただ、最近は色々あってそういう時間がとれません。たしか長田弘さんの『風のある生活』という本の中にあった、一日に一回は喫茶店で本をゆっくり読むような時間があるべきだという意見は全くその通りだと思うのですが・・・・。それにしても何故喫茶店なのだろうかと考えてみると、おそらくそこが時間的にも空間的にも「切り離された」場所だからだろうと思います。自分に関わりのある全てのものから、さしあたり距離を取ることができる場所。そうすると頭の中にうまいこと隙間ができるのです。そういう場所って実はなかなか無い。マンガ喫茶もそれに近いですけど、最近はインターネットなんぞがありますので、どうしても外部の世界に「接続」してしまう(開かなければいいだけなんですが)。そうするとせっかくの隙間が本とは関係のない余計なもので埋まってしまうような気がするのです。 後日、別の古本屋で今度はイタロ・カルヴィーノの『マルコ・ポーロの見えない都市』を購入しました。カルヴィーノは高校生のときに『木のぼり男爵』を読んで、何が面白いのかさっぱり判らずに、それ以来ご無沙汰になっていたのですが、『見えない都市』の最初の数頁を読んだだけでその面白さに愕然。そしてこれもまた、寿岳さんの本とは少し違う意味で、喫茶店で読むべき本だなあ、と思ったのでした。隙間が必要な本という意味では同じ。ただその隙間に入ってくるものの密度がすさまじい。寿岳さんの本は、文章の隙間に合わせるように自分の頭の隙間を作って、その隙間自体を楽しむような感じですが、カルヴィーノの場合は、十分な隙間を作っておかないと書いてあることが満足に自分の中に入ってこないという感じ。今度は高橋源一郎のとあるエッセイを思い出しました(書名は忘れました)。彼が作家デビュー前に肉体労働をしていた頃、時々仕事を休んで喫茶店に出かけてモーニングセットを食べながら吉田健一の本を読み、読んでいると余りに多くのことが頭の中に入ってくるので時々窓の外に目を向けてぼんやりしなくてはいけなかった・・・という。 ああ何て贅沢な時間の過ごし方だろうと思いつつ、やはり喫茶店に行く時間は当分作れそうにないので、仕方なく時間の合間にちょびちょびと寿岳さんの本とカルヴィーノの本を読んでいる今日この頃なのでした。カルヴィーノの本については、また触れる機会があると思います。あー、でも喫茶店に行きたい!!追記:冒頭の写真は僕の家のすぐ近くにある、まさに読書にうってつけの喫茶店です。昔は週に2~3回は行ってたのになあ・・・。
2008年02月07日
コメント(0)
-

文化史としての歴史小説~『赤朽葉家の伝説』を読んで
香月洋一郎さんという人が書いた『記憶すること・記録すること』という地味だけど素敵な題名の本があります。香月さんというのは確か宮本常一の鞄持ちとして、宮本さんと一緒に色々歩いて回った方で、現在は神奈川大学日本常民文化研究所に属している筈。つまりはフィールドワークを行う民俗学者。その本を読んだのはかなり前なので内容についてもあやふやなのですが、確かどこかの山奥で農業を営んでいたおじいさんが、戦前から戦後にかけて、彼が働きながら見ている風景がゆっくりとゆっくりと変わって行ったという話を引き合いに出して、そういう歴史的な変化(ここでは近代化)がどのように「経験」されたかこそ自分が知りたいことだというようなことが書かれていたように記憶しています。桜庭一樹の『赤朽葉家の伝説』を読んでいて、ふとそのことを思い出しました。 『赤朽葉家の伝説』の舞台は、作者の生まれ故郷である米子市、ないしは、米子の市街からかつてたたら場があったという伯耆のあたりまでを一つの村にぎゅーっと押し込めたような架空の村です(以前このブログで桜庭一樹の生まれ故郷を境港と書きましたが大間違いでした。恥ずかしい)。その村は海から山まで全部詰まっていて、基本的にその海から山へ向けてスロープになっているというか、階段状になっているという設定。ついでに一人目の(そして実質的な)主人公である赤朽葉万葉は千里眼であったりするので、この小説では、彼女の目から見た村の風景、ないしは村の風景の変化がしばしば説明されるのです。三世代に渡るこの物語は1953年から始まり現代で終わるので、おおよそ日本の戦後50年が、1つの地方都市という定まった地点から観察されている(つまり定点観測)といってもよいでしょう。 「近代化」とか「高度経済成長」とか、そういったものに関する教科書的な説明はいくらでも転がっているのですが、それが現実に生きる様々な人々によって様々に経験される様子というのはなかなか捉え難い。それがある程度長期的な変化となると尚更です。もちろん香月さんのような民俗学者や、いわゆる民衆思想史と呼ばれる分野の研究者の人たちなどは、まさしくそういった作業をしているわけですが、実のところ小説というのも、フィクションではあれ、いやフィクションであるがゆえに、そうした経験を捉えるのに最適な方法の1つなのではないかと今回改めて思ったのでした。そもそも考えてみれば、小説はこれまでもそうしたことをしてきた筈で、例えば『赤朽葉家』もそれなりに意識していると思われる、トーマス・マンの『ブッテンブローク家の人々』などはまさに、19世紀ドイツの変化を、1つの家族が四世代に渡って経験したことから捉えようとしたわけです。『ベルリン1919』に始まるシリーズにしても、今度は20世紀前半を、やはり三世代に渡る1つの家族の視点から描こうとしたものですし。 何というか、桜庭一樹という人はつくづく正統的な小説家だなあと思ってしまうわけですが、もう1つ『赤朽葉家』が面白いのは、その歴史変化を描くにあたって、文化史、とりわけ若者文化の戦後史に焦点をあてていることです。日本の戦後文化史というのは、大塚英志のものなど僅かな例外を除けばあまり優れたものがなく、最近になって論文集『オカルトの帝国』や坪内祐三の『1972』とかいった興味深い本も出てきましたが(宮沢章夫の『80年代地下文化論』はぱらぱらっと見た限りではそれほど面白くなさそうでした)、それらは一般的に、時代が限定されているということはさておいても、どうしても東京中心になってしまうのですね。若者文化、とりわけ1970年代以降のそれが全国的な広がりを持っているのはもちろんですが、地域によっては当然タイムラグもあるだろうし、受け止められかたもそれぞれ違うでしょう。獄本野ばらが名作『下妻物語』で書いたように、ロリータを茨城でやるのは東京でやるよりずーっと大変なのです。そういうわけで、鳥取という場所からの若者文化史という意味でも『赤朽葉家』はなかなか楽しめました。特に、どうしても紋切り型になってしまいがちな「高度成長」だとか「公害」だとかの記述に比べ、1980年代の不良文化の描写などは、おそらく作者自身の青春時代とも重なっているせいか、なかなか鋭いことも書いてあるのです。まあ文化史のパートについても、ちょっと年代的に?なところも無いではないのですが、ともかくその心意気やよし、でしょう。 ちょっとほめ過ぎな気もしないでもないので最後に一つ。この小説は、第三部に入って突然ミステリ仕立てになるのですが、果してそれが本当に必要だったのか。「謎」を解く過程で、それまでの歴史がまた姿を変えて現れるくるようであれば、ミステリ仕立てにする意味もあろうと思うのですが、そういうことも(僕が読んだ限り)ないし。桜庭一樹がミステリ好きなだけなのか、それとも東京創元社の意向なのか、わかりませんが、何か付けたしみたいなんですよね。別にミステリが悪いといっている訳ではないですが、無理にミステリにするくらいなら、いっそ全くミステリの要素がない作品をぜひぜひ書いてほしいなあと思います(あ、もちろん桜庭一樹のラノベにはミステリじゃないものもありますよ)。せっかくこんなに書く力があるんだからさ。 ←もしよろしければクリックして頂けると嬉しいです。
2008年02月03日
コメント(0)
-

イギリス風俗小説の伝統?
先日、イギリスミステリ作家のスティーヴン・ブースが書いた『死と踊る乙女』という作品を読みました。前作『黒い犬』に続くシリーズ第二弾なのですが、人間描写もより繊細になっているし、会話も洒落てきたし、格段にレベルアップしていてビックリ。前作と合わせて、ヨークシャーの風景がますますくっきりしてきたのも嬉しいところです。ただ、今回書きたいのはそのことではありません。 このブログでは、過去1、2回ほど、ミステリ評論家の書く「解説」なるものにケチをつけたことがありますが、今回読んだ『死と踊る乙女』の巻末についた関口苑生さんの解説が、なかなか面白かったのです。内容をごくごく簡単にまとめると、吉田茂元首相がかつて、愛読書を尋ねられて『銭形平次』と答えたことに関して、英国通の吉田茂はイギリス的な風俗小説に当たるものとして『銭形平次』を挙げたのだという中村真一郎の説明を紹介し、その上で、生活や人間を丁寧に描写するイギリスミステリは、『トム・ジョーンズ』やジェーン・オースティンなどのイギリス風俗小説の伝統に連なっているのに対して、アメリカや日本のミステリは謎と論理に特化していってしまった・・・・というものです。 それほど数をこなしている訳ではないですが、僕がこれまで読んできたミステリを振り返る限り、この「解説」はとっても腑に落ちますし(もちろん例外はありますよ)、以前「ミステリの風景」で書いたことも要するにそういうことなのだと思います。ついでに言えば、僕がアメリカや日本のミステリに比べてイギリスのミステリを好む理由もわかった気がしました。何というか、僕は謎解きを楽しむというよりは、「場」か「風土」とかそういうものを知りたくてミステリを読んでいるんだろうなあと。その「解説」によれば、吉田茂は『銭形平次』には江戸の市民生活が描かれているのに、最近の小説はいくら読んでも生活が浮かび上がってこないと言ったらしいですが、そのことはおそらくイギリスの現代文学にもあてはまってしまう。最近の流行りである、理知的で論理的で、しばしば「ポストモダン」などと称される小説は、それはそれで読めば面白いし、遠ざけている訳ではないのですが、現代のイギリスの生活とか人々の感情とかいったものはどうも見えにくい。そこに不満を感じてしまうと、どうしてもミステリに向かってしまうのですね。 もちろん、そうした風俗小説の伝統を受け継いでいるのはミステリに限るわけではなく、デイヴィッド・ロッジなどがそうした要素を取り入れているのはもちろんのこと、『トレインスポッティング』に代表されるアーヴィン・ウェルシュの作品などはとても見事な風俗小説だと思います(『トレインスポッティング』は映画も悪くないけど、小説はさらにずっと面白いです!!)。それから読んでいないのですが、ニック・ホーンビーなんかもその系列に入るのかもしれませんね(あと『ブリジット・ジョーンズ』も?)。そうそう、どちらかといえば「ポストモダン」な小説を書いているグレアム・スウィフトが、1つとっても風俗小説的な佳作『最後の注文』を書いているというのも、そう考えるとなかなか興味深いです(まあ、『ウォーターランド』にも風俗小説的な要素はもちろん入っているのでしょうけど・・・)。 ちなみに我が家には、以前新古書店で見つけ、イギリスの小説であるという理由だけで(そして全部100円だったので)買ってきた、いかにも読みやすそうなイギリスの現代小説が何冊か転がっています。一応名前を挙げておきますと、ニッキ・フレンチ『メモリー・ゲーム』、J・J・コノリー『レイヤー・ケーキ』(また映画の原作。この映画も結構面白かった)、フィル・アンドリュース『オウン・ゴール』、それからセリーナ・マッケシー『テンプ』。『テンプ』以外は、ミステリないしはスリラーという体裁を取っているようですが、さてこれらは優れた風俗小説であってくれるのでしょうか。いつになるかわかりませんが、読んだら(そして面白かったら)またここで報告できればと思います。
2008年02月01日
コメント(0)
-

ベルリンの傷跡~『ベルリン1919』をめぐって
「ワイマール文化」と称されるものがあります。簡単に言えば、1919年から1933年にかけてのドイツのワイマール憲法時代に形づくられた文学・芸術・演劇・音楽等々の総称ということになるでしょうか。代表的な人物・運動としては、ブレヒト、トーマス・マン(とハインリヒ・マン)、クルト・ヴェイル、マックス・ヴェーバー、バウハウス、表現主義、ワールブルグ研究所等々。いや、僕自身、せいぜい脇圭平の『知識人と政治』を読んだくらいで、ピーター・ゲイの『ワイマール文化』や海野弘『1920年代の画家たち』は読みかけでほっぽりだしたままという状態なので、ワイマール文化について何かきちんとしたことを言えるわけではないのです。 ただ、昨晩、クラウス・コルドンの『ベルリン1919』を読み終えてふと思ったのは、ワイマール文化のスタート地点について、ワイマール文化そのもの以上に何も知らなかったのだなということでした。London Review of Booksというイギリスの書評紙の最新号に載った、歴史家ホブズボームのエッセイの中の表現を使えば、その「残虐な生誕期 murderous birth-period」について、です。もっとも自分の勉強不足を棚にあげるわけではないですが、ワイマール文化のその「生誕期」については、一般にあまり言及されていないようです。『ベルリン1919』という小説は、まさにその時期を扱ったものなのですが、原題は『赤い水兵あるいは忘れられた冬』。訳者の酒寄さんが書いているように、ドイツ人にとってすら1919年は「忘れられた」時期なのです。確かに、僕が読んだ数少ないワイマール文化についての文章も、第一次世界大戦との関わりについては多少言及があったような気がしますが、戦後、というか戦争が終る前後のドイツ国内の状況については、殆ど書いていなかったような気がします。そして上述のホブズボームによれば、ワイマール時代に対する歴史研究者の注目は、それがヒトラーの政権奪取といかなる関係にあったのか、ワイマールはヒトラーを防ぎえたのか、ということに集中しているらしい。つまり、もっぱらワイマール時代の始まりではなく終わりへの関心。 そういうことを考えただけでも、1919年という時代を、それもあのスパルタクス団を中心にして描こうという『ベルリン1919』が、並々ならぬ意図を持っていることはわかります。その意図を僕がどこまで汲み上げることができたかは心もとない限りですが、少なくともベルリンという町の持つ歴史的奥行きだけは感じとることができたのではないかと思います。『ベルリン1919』は題名通り、ベルリンが舞台で、ウンター・デン・リンデンやら、ブランデンブルグ門やら、ティアガルテンやら、観光客にも馴染みの名前が次々に出てきて、ありがたいことに地図までついてます。僕もその辺りを少なくとも一回は通過している筈なのですが、当時は東西に引き裂かれたベルリン時代に思いを馳せはしたにせよ、よもや1919年のことなどは一切考えませんでした。ただ、その時代が忘れさられ、当時の具体的な痕跡が一切無くなっていたとしても、『ベルリン1919』に描かれているような痛ましい記憶の数々は、傷跡のようにして残っているのではないかと思うのです。もしくはその傷跡をそこに投影することはできるだろうと。それは多分、現在のベルリンの地図に過去のベルリンの地図を重ねてみることと言ってよいかもしれません。そしてそれは、物語を未来に向けて開かれたものにしようとしているクラウス・コルドンの意図とも、それほどかけ離れていないのではないかなとも思うのでした。もちろんそれはベルリンを観たり歩いたりする側の問題であって、次にいつベルリンに行くともしれない僕も、もう少し立体的なベルリンの地図を作っておかなくてはいけません。当時の写真が豊富に載っている『ベルリン・嵐の日々 1914~1918』なんかも役に立ちそう(『ベルリン1919』に引きずられるようにして、とりあえず図書館から借りてきたのですが、これは買わないとなあ)。それからもしその時がくれば、ベルリンのどこかにある筈のローザ・ルクセンブルクのお墓にも立ち寄ってみようかなと思います。なお、この『ベルリン1919』は『ベルリン1933』『ベルリン1945』と続く歴史大河小説です。一応児童文学というのが驚くような分厚い内容(確かに噛んで含めるような文章は児童文学っぽいですが)。作者の政治的・社会的なスタンスが非常に明確なので、それに合わない人はもしかすると読むのがしんどいかもしれませんが、でもこの重厚で貴重でそしてわかりやすい歴史小説を読まないのは勿体ないですよー。シリーズ全体についても、また機会があったら何か書きたいと思います。追記:ついでにオススメのCDを。上述のクルト・ヴァイルがブレヒトの芝居のために作った音楽を、イタリア人のおじいさん2人(クラリネット奏者とアコーディオン奏者)が演奏しているものです。タイトルはRound About Weill。まるで薄暗いベルリンのキャバレーの夜の深く深くに潜り込んでしまったような音楽。素晴らしいの一言です。ついでにライナーノートを書いているのはウンベルト・エーコ!!(トップの画像はそのジャケットです。ジャケットもカッコいいです)。
2008年01月26日
コメント(0)
-

イギリス人のユーモア
2年程前に、英文学者の冨山太佳夫さんが『笑う大英帝国』という本を出しました。これは、イギリス人がいかに冗談が好きかというのを、だいたい18世紀くらいまで遡って跡づけたものです。冨山さんの文章自体は「笑う」とまではいかなかったものの、そこで紹介されている幾つかの「ネタ」は確かに相当おかしい。 イギリス人(厳密にはイングランド人ですが)が独特のユーモア感覚を持っているというのは、現代でももちろんそのままです。いや、どの国にもどの地域にもどの集団にも独自のユーモア感覚というのはあるのですが、イギリス人の場合、何と言うか「笑い」に対する物凄いオブセッションすら感じてしまうのですね。冗談を言わない奴は馬鹿だ、とでも言わんばかりの。『前代未聞のイングランド』という、邦題にはあまりセンスが感じられませんが、中身は確かに面白い本の中で、著者のジェレミー・パクスマンは「ユーモアのセンスをもっていることを、これほど高く評価する国がほかにあるだろか?」と書いています。 例えばこのブログでも何度かとり上げているイギリスのミステリも、ちょっとした「笑い」は満載です。ラヴゼイのダイヤモンド警部シリーズも、会話でかなり笑いを取っているし、ウィングフィールドのフロスト警部シリーズに至っては、「ちょっとした」なんてものではなく、僕が今まで読んだ中で多分一番「笑えた」本ではないかと思うくらい。別にミステリに限らずとも、デイヴィッド・ロッジのような、かなり洒落たユーモア小説を書く人もいます(それから僕は読んだことが無いのですが、冨山さんの紹介を読む限り、スパイク・ミリガンという作家のおかしさは相当です)し、ロッジともおそらく知り合いの文芸評論家テリー・イーグルトンの真面目な研究書も、とにかく冗談で一杯です。そもそも、ジェーン・オースティンとかディケンズとか、日本では「文豪」とされているような人たちの小説だって、冗談ばっかなのです。時代が離れているということ、それから翻訳の問題で、どうしても「笑える」とまではなかなかいかないのですが、例えば中野康司さんの訳するオースティンは相当「笑え」ます(ちなみに同じく中野康司さんの訳している『大学のドンたち』『手のひらの肖像画』もとてもおかしい。彼の翻訳書を読んでいると「笑い」を翻訳できるって凄いことだとつくづく思います)。映画にしても、会話は相当練ってあります(話自体が単純なので見くびられがちな『ブラス!』なんかも、会話は相当笑えますよ)。さらにさらに一昨年のニュースになりますが、イギリスの高等法院で行われた『ダヴィンチ・コード』の盗作疑惑を巡る裁判の判決文の中に、暗号を忍ばせたなんてこともありました。何もそこまで・・・と思いますが、イギリス人はそのくらいしないとむしろ落ち着かないのです、きっと。 さて、イギリス人の好むユーモアというのは、多分大雑把に分けると2種類あって、1つはモンティ・パイソンのような、とにかくベタでスラップスティックな笑い。もう1つは、かなりひねった、しばしば自虐的で陰鬱とも言えるような冗談。先のパクスマンによれば「昔からよく言われるとおり、『イングランド人はもともと陰気に生まれついているから、景気づけにスコッチをダブルで飲む』ので、自分の国が不幸な宿命を背負っていると思うと、かえって安らぎを覚えるのだ」とのこと。イギリスは雨ばかり降っているという定番ジョークはその中に入るでしょう。そしてどちらにも共通しているのは、とにかく真面目くさった顔で下らないことを言うということでしょうか。冗談を言われた方も、それとわかっても笑わない。やはり無表情に気の利いた答えを返さなくてはいけません。モンティ・パイソンも、役者たちがニコリともしないのが、またおかしさをかもし出しているような気がします。BBCがエイプリル・フールに「嘘のニュース」を流すというのは有名ですが、それもまたおそろしく馬鹿げたことを皆で真面目な顔でやっているという・・・・歴史的な名作として語り継がれている「スパゲッティの収穫」なんか本当に傑作です(「スイスのとある村では、今年もスパゲッティが豊作で・・・」というナレーションが流れる中、木から何十本もぶらさがったスパゲッティを、女性たちが収穫し、乾燥させている映像が流れる。文末の画像はその一部) で、そんな伝統の中に、かの有名なジェローム・K・ジェロームの『ボートの三人男―犬は勘定に入れません』があります。これは、上述したような2種類のユーモアをどちらも上手く取り入れた佳作で、丸谷才一の翻訳もとても良く、多少古めかしい感はあるものの、今でも結構「笑える」小説です。アメリカのSF作家コニー・ウィリスが、この本を下敷きにして『犬は勘定に入れません』という、素敵なタイムトラベル物(そんなに「笑え」ませんが)を書いたのもご存知の通り。きっと今でもファンが多いんだろうなあと思っていたら、実はピーター・ラヴゼイもこの本を下敷きにしたミステリを書いていることを発見しました(ただし原書が出たのは1976年ですが)↓ この本が、もうそれこそ爆笑につぐ爆笑、であれば話にうまくオチが着いたのですが、残念ながらミステリとしてもユーモア小説としても中途半端な感じ。クスリとさせられるようなところはあるのですが、ダイヤモンド警部のような辛辣さもあまり見られず残念でした。ただ元祖の『ボートの三人男』にしても、ウィリスやラヴゼイのものにしても、とにかくのーんびりしていて気持ちのいい本であることは間違いないので、良かったら三冊まとめて読んでみて下さい。追記:さて、イギリスのユーモア小説といえば、それこそP・G・ウッドハウスを挙げるべきなのですが、実はまだ一冊も読んでいません。それなのにイギリス人のユーモアについて語ってしまうとはお恥ずかしい限り。様々な紹介から想像する限り、ジーヴス執事というのは、それこそ表情一つ変えずに陰気で辛辣な冗談を言う人の典型のようなのですが・・・・。はい、なるべく早く読みます。(リンク先を訂正しました。すみません、ブログの操作に慣れていないもので・・・)
2008年01月22日
コメント(1)
-

ミステリの「風景」
僕は日本のミステリを普段殆ど読まないのですが、『このミステリがすごい!』なんかを読んでいると、やっぱり日本のミステリも読んでみようかなあという気になってくるし、そもそも明らかにイギリスに偏り過ぎな自分のミステリ趣味をもう少しバランスを取ってみようかしらんとも思います。そんなわけで、今年に入ってからひとまず芦辺拓の『時の密室』と逢阪剛の『百舌の叫ぶ夜』の2冊を読んでみました。結果としては、芦辺拓にはがっかり、逢坂剛はまあまあ、だったのですが、それはさておいて。 2冊を読んでいて、今回とても感じたのは、地方性というか、場所性というか、物語が進行している「場」の把握がとても弱いということでした。そして、それは思い返してみると、これまで読んできた日本のミステリに大体当てはまるんじゃないかなあと。例えば芦辺拓の『時の迷宮』なんかは「大阪」という土地を前面に押し出したミステリであるにも関わらず、それがどこまでいっても道具立てに過ぎず、行ってみれば書き割りの背景のようなのです。大阪に関する蘊蓄はさんざん披露されるものの、そもそも主人公が大阪という固有の街を歩いているという感覚が非常に乏しい(同じ芦辺拓の『時の誘拐』はもう少しましだったような気がするんだけどなあ)。それは逢阪剛の『百舌の叫ぶ夜』にも言えます。舞台が現代の東京なんだから場所性が希薄なのも当たり前という意見もあるかもしれませんが、それが短絡的なのは、例えば堀江敏幸の『いつか王子駅』にでも読めばすぐにわかることです。そういえば、僕は内田康夫を読んだことがないのですが、ミステリに詳しい知人が、内田康夫に出て来る「場所」は観光客の「場所」でしかないと書いていたことも思い出します。 堀江さんについてはまた書くとして、要するにこの日本のミステリの「場」の希薄さは、過剰なまでのプロット・トリック重視の結果なのだと思います。つまりは、プロットやトリックが、それが起る場所から切り離されて突出し、その結果として、人が生活を営む場所としての感覚が限りなく後退してしまっていると。日本のミステリにおいて、主要登場人物以外がおざなりな描写しかされないのも、そのことのあらわれの1つだと言えるのではないでしょうか(ついでにアメリカのミステリもしばしばそういう傾向のものが見受けられるのですが)。ミステリだから仕方がないという訳ではない筈です。イギリスのミステリ(ウィングフィールドのフロスト警部シリーズでも、イアン・ランキンのリーバス警部シリーズでも、ピーター・ロビンスンのアラン・バンクス警部シリーズでも何でもいいです)なんかを読んでいると、その「場」の感覚はびっくりする程ですし、魅力的な周辺的人物もごまんと出てきくるのですから(特にフロスト警部シリーズは一つのコミュニティ全体を描いているといっても言い過ぎではないと思います)。プロットと「場」はきちんと書けばきちんと結びつくのです。そしてそれは日本のミステリ作家の多くが勘違いしているように、風景描写を徒に積み重ねればいいというものではないのです(日本のミステリを読まない理由の1つとして、この過剰で無意味な描写の連続が苦痛で仕方ないというのがあります。始めて小説を書く高校生じゃないんだからさ)。そうそう、また「場」を作者の思い入れだけでプロットとはあまり結びつかない形で過剰に押し出すと、今度は坂木司みたいに、何だか嘘くさいというか、鬱陶しくなるんじゃないかなあ。 そこまで考えて、ふと思ったのが桜庭一樹の『砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない』や『少女には向かない職業』が持っている濃密な「場」の感覚についてでした(実のところ一年程前に始めて彼女の作品を読み、未だに『私の男』はおろか、『赤朽葉~』も『少女七籠~』も読んでいないものとしては、桜庭一樹について云々するのは憚られるのですが、まあ直木賞受賞のご祝儀ということで)。『砂糖菓子~』の舞台は、冒頭に触れられているように、桜庭一樹の出身地である米子市のすぐお隣の鳥取県境港市。『少女には~』は下関(らしい)。どちらも街の様子についてそれほど書き込まれている訳ではありません。『砂糖菓子』などは、舞台がどこであろうと関係ないのではないかというくらいの構成になっています。けれども、そこに描かれている、主人公の少女たちが感じているヒリヒリするような生(ないしは死や暴力)の感覚、息苦しさというのは、確実に特定の「場」と結びついたものであり、その点において「場」は単なる書き割りや風景ではなく、人によって経験され生活される「場」となっているのです。 ミステリではありませんが、そういえば依然読んだ吉川トリコの『「処女同盟」第三号』にも同じような感想を持ちました。桜庭も吉川も、どちらも広い意味での(つまり「大衆小説」と呼ばれるものを含めた)「文壇」の外部から出て来た人達で、しかしその人達の方が、既成の枠組みで物を書いている人達よりもずっと「場」やその「経験」について鋭敏な感覚を持っているというのは、面白いというか、意味深長だなあと思ってしまいます。実際、ラノベ出身者の作品の中には、橋本紡の『ひかりをすくう』みたいに、桜庭とは違う意味で、やはり「場」に敏感な人達がいますね。彼ら・彼女たちにしても、その場が主人公たち以外の人間によって経験されるという感覚は未だ薄いのですが、それでも何か期待できるとすれば、この人達じゃないのかなあ、と日本ミステリをろくに読んでいないと宣言している僕は図々しくも思うのでした(もちろん引き続き日本ミステリをきちんと読んでから判断し直そうとは思っております)。 追記:なお、「場」に対する感覚が弱いというのは、日本ミステリに限らず、1980年代以降の現代日本文学の主要な特徴の一つだと思っていて、上述の「期待できる」というのは、そこまで含めてなのですが、それについてはまたいつか。
2008年01月19日
コメント(0)
-

「不安」のアメリカ
ここ数年のアメリカについて考える際の自分なりのキーワードと言えば、さしあたり狭い意味での「暴力」で、それはクックの一連の小説や、一昨年大評判になった『あなたに不利な証拠として』(これが何であんなに大評判になったのかは結局わからなかった。悪い小説ではないんだけど)、昨日読み終わったばかりのグレッグ・ルッカ『わが手に雨を』などを読みながらいつも思い浮かべていたことでした。もちろん犯罪小説が暴力と結びつくのは当然なのですが、何というか上述したような小説は、話の中心にある犯罪のみならず、話の隅々にまで暴力が浸透していて、登場人物の多くがその遍在する暴力に蝕まれているようなのです。そして『フリーキー・グリーンアイ』のような全く毛色の違う児童文学などにも、その暴力の気配は常に漂っている。 だから「暴力」をキーワードとすること自体は決して間違っているとは思っていません。ただ、現在のアメリカが全体として抱えている矛盾をつかまえるための言葉として、もしかすると「暴力」というのは少し表面的なのかもしれないと、『ニッケル・アンド・ダイムド』によって日本でも有名になったバーバラ・エーレンライクの新作、『捨てられるホワイトカラー』を読みながら考えていました。 「暴力」というつかまえかたが表面的だというのは、そこで終ってしまうと、「暴力」を生みだすものが何であるのかという視点がさしあたり必要無くなってしまうからです。言い方を返れば、暴力というのはもっと大きな矛盾の1つの現われに過ぎないのではないかと。そういえばマイケル・ムーアは『ボウリング・フォー・コロンバイン』で銃社会の原因を「恐怖」に求めていましたし、去年やはりそこそこ話題になったジョック・ヤングの『排除型社会』(イギリス人の書いたものですが、アメリカの例が非常に多く出てくる)では、犯罪の原因を「剥奪感」に求めていました。 エーレンライクの本について少し書いておくと、一応『ニッケル・アンド・ダイムド』のホワイトカラー版ということになってしまうのでしょうが、そのまんまの期待で読むと肩すかしを食わされることになります。『ニッケル・アンド・ダイムド』はまさに労働現場そのものについての本でしたが、『捨てられる~』は労働現場というよりは、アメリカの労働文化、ないしは企業文化についての本であり、さらに言えば、そうした文化を生みだしているアメリカのメンタリティーについての本なのです。だから見るべきは、本の中に出て来る数々の失業者・求職者たちが抱える「恐怖」と「剥奪感」でしょう。それは、マイケル・ムーアが指摘したようなメディアによって煽られる「恐怖」よりももっと広く、もっと人の内側にまで染み込んでくるような「恐怖」であり、ジョック・ヤングが説明するよりも、もっと切実で具体的な「剥奪感」です。 そうした「恐怖」や「剥奪感」などをまとめる言葉として、もし「不安」という大雑把な言葉をあえて使うのであれば、その「不安」が銃社会を生みだし、増加する犯罪を生みだすとも言えるでしょう。銃規制への反論として言われる「家族を守る権利」とやらも、その「不安」に対するマッチョな応答と言えなくもありません。ジョック・ヤングの議論はその「不安」が犯罪や暴力に結びつくメカニズムを説明したものとして読むこともできます。ただ、エーレンライクの本に出てくる「不安」に満ち満ちた失業者たちは、別に積極的な銃の推進派でもなければ、犯罪予備軍でもありません。むしろその「不安」は外に出ることなく、彼らの内側に溜まり、そして内側から彼らを蝕んで行く。そしてエーレンライクはそれがどこから来るものなのかを、はっきりとではありませんが、決して企業文化に収斂させることなく描き出しているように思うのです。 正直に言うと、アメリカのミステリを殆ど読んでいない僕は、これからもアメリカの犯罪小説を読み続け、そこに暴力の気配を感じ取り続けるでしょう。もちろん犯罪小説に限る必要もないし、『性と暴力のアメリカ』なんて本も読みたい本のランキング上位に位置しています。でも、上述したようなことを考え、そして「不安」という言葉で大雑把に捉えたものを、もっと構造的に、そして歴史的に捉えた上で、犯罪や暴力を見て行かないと、単純化になってしまうだろうなあとも思うのです。犯罪や暴力が「不安」の象徴の1つであることは確かですが、「不安」を犯罪や暴力に還元してはいけない。 アメリカでは大統領選挙の予備選挙が始まりましたが、あの国をあげてのお祭り騒ぎも、「不安」と向き合うというよりは、「不安」から目をそらすための大イベントのように思えてなりません。そしてさらに言えば、例えばアメリカのショー文化なども・・・いや、あまり言い過ぎるとまた別の単純化になってしまいそうなので、ひとまずここら辺にしておきます。
2008年01月15日
コメント(0)
-

ロシアという豊饒
「フォルマリストは、プーシュキンとその世代の功利的・社会的伝統を単に攻撃するだけで、彼らの作品については、特権的対象としてみずから文学的分析や再評価を彼ら独自の方法で行なった。このようにして、フォルマリストはロシア文学におけるこの偉大な形成期を、否認するというよりはむしろ、自分たちの目的のために再利用する傾向がある。この時期というのは、文学的激動期であっただけではなく、政治的にも変動期であって、大作家たちの多くは失敗に終った十二月革命、『ペテルスブルグ元老院前の広場におけるロシア史のかの有名な休止』に共感を寄せていた」[フレドリック・ジェイムソン『言語という牢獄』46頁]。 別にこの程度のことでジェイムソンなんてものものしいものを引用する必要もないのですが、たまたま読んでいる最中に眼にとまってしまいました。以前に感想を書いた『真説ラスプーチン』を読んで以来、20世紀初頭のロシアという場所が何とも気になって仕方がなくなっています。思えば、19世紀ロシア文学の豊かな遺産を受け継いだり、変形させたり、ぶっ壊したりするロシア・アヴァンギャルドやロシア・フォルマリストがうごめき、エイゼンシュテインとスタニスラフスキーが活躍する時代というのは確かに魅力的に決まっていて、そこにロシア革命という無茶苦茶なエネルギーが加わればもう言うことなしなのです。 昨年出版された佐藤亜紀の『ミノタウロス』を読んでみようと思ったのも、実のところ、それが20世紀初頭のロシアを舞台にしていると知ったからでした。時代はおそらく1900年から1920年くらい(小説中には正確な年号は一切出てきません)。舞台は、小説の時代ではロシア帝国とソヴィエト連邦に属する現在のウクライナ。都市の描写は殆どなく、出て来るのは農村ばかりで、アヴァンギャルドともフォルマリストともさしあたりは無縁な土地。政治的な動きは、もちろん農村とは密接な関係を持っているわけですが、『ミノタウロス』はそれとも慎重な距離を取ります。描かれるのは「壮大なる歴史とは断固として無関係」と言い切る一人の若い悪党の、諦念と粗暴さと愚かしさと知性がごちゃ混ぜになった短い一生。 もちろん「断固として無関係」というのは主人公の主観であって、物語後半からはロシア革命後の内戦に思いっきり巻き込まれるのですから、「歴史」とは無関係ではないのですが、赤軍にも白軍にもつかずに、ただただ乱暴狼藉と殺戮を繰り返す主人公たちは、少なくとも英雄的な「壮大なる歴史」とは無関係なのでしょう。実際、『ミノタウロス』を何よりも魅力的なものにしているのは、ひたすらに反英雄的な無意味さです。成り上がり地主のお坊ちゃんとして生まれた主人公は、物語が進めば進むほど、「どこで誰が死んでも誰も知らないし気にもしないのらくろの国」で、どんどんどんどん、匿名の存在になっていきます(実際、主人公が名前で呼ばれることは、小説中1回しかない筈です)。「たぶんもう、誰が誰であるのかなどどうでもいいことなのだろう。ほんの暫くは残っていた記憶も、感情も、すぐに消え去ってしまうだろう」というのは小説の終わり近くでの主人公の独白。 ただし、『ミノタウロス』が魅力的であると同時に小説として優れているのは、そうした無意味さで世界を塗りつぶしてしまわないことです。上に政治と慎重に距離を取ると書きました。それは作者の姿勢でもあり主人公の姿勢でもあるのですが、何かと距離を取るというのは、その何かの存在を認めて、その存在と自分との関係を自覚するということです。だから主人公は、例えば自分が行き交うに農民たちが、一見無意味と見える生活を頑なに守る確かな存在であることを認め、それとの比較で、自分たちの徹底的な無意味さを自覚するのです。上にロシアのエネルギーと書きましたが、実のところそのエネルギーというのは、様々な場所の様々な集団がそれぞれに持っているエネルギーの重ね合わせの筈。そして『ミノタウロス』は、場所はそれほど動かずとも、その中の複数のエネルギーを描くことで、重層的なものになり、そのおかげで(少なくとも僕の中では)『真説ラスプーチン』ともつながることになったのでした。 加えて、暴力に満ち満ちたこの小説が露悪的になっていないのも、おそらくこの「距離」に対する自覚のためでしょう。無意味な暴力への没頭を描けばそれだけで「何か」を書いたと勘違いする小説家は多いですが、『ミノタウロス』では、主人公も作者も、中心的な暴力を常に他との「距離」において相対化するために、そうした悪趣味さを免れています。ついでに、文章のスピード感と描写の簡潔さも、この小説が悪趣味な暴力への開き直りに陥るのを救っているような気がします。佐藤亜紀の小説はデビュー作の『バルタザールの遍歴』しか読んだことはなく、『バルタザール』については、その仰々しい文体と物語の空疎さ(もちろん意図的なものなのですが)をどうしても楽しめず、ファンタジー大賞受賞時の審査員のコメントにも全くうなずけなかったのですが、少なくとも『ミノタウロス』はそうはなっていない。仰々しさというか、想像力を過剰なまでにふくらませるような比喩は残っていますが、あくまで警句のような短い文章をリズム感よくつなぎ合わせることに徹することで、しつこさが一切無くなっています。暴力に淫することもない。『バルタザール』と『ミノタウロス』の間の小説も読んでみなくてはいけませんね。 20世紀初頭ロシアについては、岩波現代文庫のサヴィンコフなぞも現在パラパラ読んでいるところなのですが、そうなると、彼がロープシンという筆名で書いた『蒼ざめた馬』も読みたくなってきます。依然古本屋で買って読まないうちに人に貸して返ってこないまま(そしておそらく二度と戻ってこない)だなあ。エレンブルグの『わが回想』やパステルナークの『ドクトル・ジバコ』も読み返したい。うーん、ロシア熱はまだまだ続きそうです。そうそう、『ミノタウロス』を読んでいる最中に、ふと思いついて、リチャード・ブローティガンが大好きだったという、バーベリの『騎兵隊』(これは長田弘さんが『20世紀書店』で勧めていたのを見て以前買っておいた)を読み始めてみたのですが、案の定雰囲気がとてもよく似てる。これについてはまた回を改めて何か書いてみたいと思います。 追記:ちなみに『このミステリがすごい!』の2007年度版では、何度かこの『ミノタウロス』がとり上げられているのですが、これをミステリと呼ぶのはどうかなあ。何と言うか、ミステリ評論家たちのコンプレックスに基づく自意識過剰だと思うのですが、それは言い過ぎかしらん。 ミノタウロス
2008年01月08日
コメント(0)
-

また読んじゃったー今度は"聖遺骸”
「フランスを旅行される人は、本当にどこへ行ってもという言い方が通るほどに、Saint Martin 聖マルタンの名を冠した教会にぶつかる筈である。そうして言うまでもなく、その他数百にものぼる筈の聖人、聖女の名における教会があり、それらのうちの少しは格式が高いとされるものには、必ずや何かの遺品、遺骸がある。 それらは四世紀、五世紀頃から始まっていたもので、たとえばこの巡礼の通る道筋の一つであるスペイン北部の大都市の一つオビエドには、次のようなものがある、あるいは、あることになっている。 キリストの首を包んだ手ぬぐい(聖骸布)、イバラの冠の八つの部分、最後の晩餐のパン切れ、聖処女の乳汁、髪の毛、ユダがキリストを売ったときの30デニエの古銭の一部、キリストの足を拭いたマリア・マグダレナの髪、モーゼが紅海の水を分けたときの棒の木切れ、聖ペテロのわらじの片っぽ、等々。…… たいへんなコレクションである。 異教徒としての私は要するにそういうがらくたの詰まった宝物室なるものを見せられ、茫然として、人間の為す、あるいは仕出かす業の振幅、あるいは芸の細かさに感服をしているだけなのである。しかも誰もそれを笑いとばすわけには行かないであろう。そこに籠められている執念の深さを思えば」 堀田善衛『スペイン断章』(集英社文庫版)の下巻の(ないしは岩波新書の『情熱の行方』の)最初の方に書かれた文章です。僕が以前、「うさんくさいもの」について書いたことは、多分、ここに引用したことに集約されてしまっているでしょう。殆ど滑稽なまでに見えてしまう闇雲な情熱。12月から1月にかけて、ジェームズ・ロリンズ『マギの聖骨』とフリア・ナバロ『聖骸布血盟』という、まさに「聖遺骸」を扱ったキリスト教歴史ミステリを読んでいたのですが、当初期待していたのは、まさに、こうした歴史に裏づけられたヨーロッパの途方もない情熱の姿を垣間見ることでした。 けれども残念ながら大きく大きく期待はずれ。『マギの聖骨』はしょっぱなから、アメリカ特殊部隊の戦闘シーンから始まってぎょっとしたのですが、その後もひたすら派手なアクションシーンが続きます。以前、高橋源一郎がマイケル・クライトンの小説を評して「映画化を前提とした小説」と書いていましたが、まさにそんな感じ。ああ、きっとこんなシーンになるんだろうなあ、と映像が浮ぶような文章です。映画化はまだ決まっていないようですが、竹書房がこの小説のために作ったサイトは殆ど映画のサイトのよう。何だか何だか。正直言って、そこでかなり萎えそうになりつつ我慢して読み進むのですが、正統ローマン・カソリックの権威を疑う姿勢は露ほどもなく、出て来る登場人物は超人めいた人ばかり。つまるところ権威づくしで、少しも「うさんくさく」ないのです。何と言うか、本来「うさんくさい」筈のものに、色々な要素をくっつけて箔をつけているというか。 上巻まで読み終えた後、下巻が回ってこないため(図書館から借りてました)、それまでの間の埋め草に、買い置いていた『聖骸布血盟』をスタート。スペイン人作家の書いたものなら、派手好きなアメリカ人とはひと味違うものを書いてくれるのではないかと思ったのですが、これまた話にならないお粗末さ。文章はスカスカ。歴史記述と現代の冒険の記述が並行して進んで行くというスタイルもひどく単調でご都合主義的。そして次から次へと出て来る「セレブ」な人たちにも鼻白んでしまう。ここでも「うさんくささ」は影も形もない。というかひどく世俗的な権威で飾り立てられている。カバーに書いてある「衝撃の結末」というのも、どこを捜しても見つからず。何というか、もさーっとした小説でした。何でも映画化が予定されているそうですが、どうなんでしょうねえ。 『聖骸布血盟』が読み終わった頃に、ようやく下巻がやってきた『マギの聖骨』は、殆ど義務で再会。最初の方は、まだ物語が動いて行くので何とか読めたのですが、話が進めば進むほど人物描写がどんどん薄くなっていって、展開も単調になってくる。アクションシーンが上手いのはまあ分かりますが、それ以外の謎の部分は重さが全然無い。うーん、この人アクションシーン以外の語彙が極端に貧弱なのですね。そしてクライマックスはもう目を覆いたくなる程の安っぽさ。作者は獣医ということなのですが、文系の物事の探究の仕方というものが果してわかっているんだろうか。というか、歴史とか哲学とかに対する物凄いコンプレックスを感じてしまい、それが安っぽい記述につながっていると思えて仕方ないのですが、それはうがちすぎかなあ。でもそう考えると、次から次へと繰り出される科学的な知識の数々も、やっぱり権威付けにしか見えず。そうした知識が全て「事実に基づいている」のが自慢らしいですが、正直言って、事実に基づいていようといまいと、面白ければ何でもいいんですけどね・・・。どちらも、こういう類いの小説が殆ど全てそうであるように、イタリアを中心にしてヨーロッパをあちこち移動します。ついでに『マギの聖骨』の原題はMap of Bones。実際に地図が謎解きに大きな役割を果たします。でもその移動というか地図的想像力は少しも魅力的ではないのです。簡単にあちこち飛び回っちゃうからか、それとも行く所がみな観光名所ばかりだからなのか。読み終えた後はつくづく疲弊しました。いや、読むのが悪いのは分かっています。なので、これが終ったら読もうと思っていた、リチャード・ベン・サピア『キリストの遺骸』は自粛して、大人しく堀江敏幸でも読んでいようと思うのでした。次回は悪口じゃない書評を書きたいものです。追記:なお冒頭に引用した堀田善衛は、「あの」カタリ派を扱った小説を書いています。これはとてもとてもオススメ。 追追記(1月8日):その後、ジェフリー・ディーヴァーの『コフィン・ダンサー』を読んだのですが、このリンカーン・ライムのシリーズも、超人的にプロフェッショナルな人がざくざく出て来て、知ってても知らなくても人生には大した違いがないような「科学的」トリビアが満載という点では、『マギの聖骨』と一緒ですね(もちろんディーヴァーは『マギの聖骨』と違って少なくとも楽しめますが)。アメリカでベストセラーになる小説って、そういうもんなのかなあ、と思ってみたり。
2008年01月03日
コメント(0)
-

堀江敏幸のパリ
パリは嫌いだと話す女性にこれまで2度くらいあったことがあります。その口ぶりに何か疎ましいものを感じてそれ以上話を聞かなかったので、パリの何が嫌いだと言っているのかはついぞ分からずじまい。それでも、「パリ素敵!」と無邪気に言い放つような女性とは、私は違うのよ、という屈折した自己顕示欲のようなものがあるのはわかりました。世の中にはパリに一生行くことすら覚束ない人もいれば、生涯の記念に一度だけようやくパリに行くような人もいるだろうに、意図的にではないにせよ、結果としてそういう人たちの思いを足蹴にするような言葉はどうしても受け入れ難い、とそのときも思ったし今もそう思います。そして堀江敏幸の『おぱらばん』を読みながら、ふとそのことを思い出し、そして、パリは嫌いだという彼女たちは、果して堀江敏幸の描くようなパリを知っているのだろうかとひとりごちていました。 ただ、自分自身、そんな偉そうな感想を抱くほど「堀江敏幸のパリ」を知っているわけでは実のところありません。ずっと前、おそらく出たばかりの『子午線を求めて』を書店で手にとって購入し、その視線には強く惹きつけられながらも特に理由もなく四分の三ほどを読んだ時点で放り出しておき、その後、書評本ばかりを読んでいた頃、今度は『本の音』を購入して、今度は文章が硬すぎるのではとか、短い文章に少し詰め込み過ぎではないかとか、賢しらな感想を抱いてみたり、その後で古本屋で目についた『郊外へ』を購入してこれまた全部読まないままに、本の中のエピソードを真似してバスに乗って「郊外」(といっても僕の住んでいる場所自体「郊外」ですが)に行ってみたりと、何だか堀江さんとは中途半端なつきあいが続いていました。 ただ、今回もまた特別の理由もなく図書館で『おぱらばん』を手に取り(三島賞を受賞していたことも、その瞬間は忘れてました)、一つ一つの作品をゆっくり読んでいると、自分の中に入ってくるものが、これまでとは随分違うことに少し驚きました。別に『おぱらばん』が、『郊外』や『子午線』とそれほどスタイルが違っているわけでもないでしょう。おそらくは、場所に関する個人的な記憶の断片と重なり合い、そこに文学的な記憶と記録、さらには歴史的な記録を織り重ねていく堀江さんの手法が、ようやく自分の腑に落ちた、ということでしょうか。考えてみればこのスタイルはまさに「読書地図」とも言うべきようなものなのでした。あくまで個人的な、「それぞれのパリ」に対する関係から語り起こし、それをまた多様で入り組んだ歴史と結びつけて行く手際にもひどく共感を覚えます。そう、そうすると、これだけ「パリ」とは様々であるのだから、そんなに簡単に「パリ」が好きだとか嫌いだとか言ってどうするのだろうということになるのです。もちろんそうした態度だって、「パリ」との関係の1つの取り方であると言えばそれまでですが。それからもう1つ、彼が狭い意味での「文学的」なるものに拘泥せず、例えば普通であれば「政治的」なものとしてくくられてしまうようなものなどにも、万遍なく目を向けようとする姿勢も個人的には好きです。もっともこのことは既に気がついていたことで、2005年にパリ郊外で異なる国を出自に持つ若者たちが暴動を起した際、ふと思いついて『子午線を求めて』を読んでみたら、そうした暴動が既に1980年代から頻発していることが、移民の歴史についての丁寧な説明とともに書かれており、そこでの説明は、他のニュース解説などよりずっと参考になったということがありました(尚、冒頭に掲げた写真は今年やはりパリ郊外で起こった同様の暴動の写真です。日本では殆ど報道されてなかったような気がしますが)。もちろんそうした「文学的」なものに収まらない事柄についての記述はとりわけて強調されている訳でもなく、読みとばすこともできるくらいのものですが、それでも個人と社会の様々な関わりの中に、そうしたものが避け難く含まれているということを、堀江さんはきっちりと理解しているのだなと、今回『おぱらばん』を読みながら、そのことも確認していました。 本そのものについて、読んだことのない方のために少しだけ紹介めいたことを書くと、『おぱらばん』という不思議なタイトルの意味は、最初の物語を読むとすぐにわかるようになっています。そして、それを読めば、その不思議な言葉がタイトルにならざるを得なかった理由を理解できるでしょう。その物語の終盤近くで、その言葉が作者によって高らかに口にされる瞬間は、上述したような堀江さんの姿勢が、奇妙な人物とのユーモラスな関係の中に織り込まれつつ、清々しく宣言されているようで、ひどく幸せな気分になったのでした。
2007年12月23日
コメント(0)
-

どこにもいけない―『制裁』のこと
さて、ようやく『制裁』について書いてみます。 この前たまたま本屋で目についたので(そして安かったので)、『このミステリーがすごい!』の2008年度版を買いました。『制裁』はベスト40の中にすら入っていませんでしたが、たった一人だけ個人的なベスト5に挙げている人がいました。まあ、そんなもんだろうなと思います。先に書いたように、『制裁』はちょっとミステリとは言い難いので。 確かに『制裁』はミステリの体裁で書かれてはいます。でも実のところ、多くの人がミステリから期待するであろうものに、この本は殆ど応えてくれないのです。例えば前半のプロット。まず残虐な性犯罪歴を持つペドフィリア(幼児性愛者)の男性が、施設から施設への移送中に逃げ出します。たいがいのミステリであれば、ここで、その男性が次の犯罪を犯す前に何とか捕まえようとする警察の必死の操作を事細かに描くでしょう。でも『制裁』ではあっさり一人の少女がその男に誘拐されてしまいます。そして、警察の追跡が殆ど進まないうちに、犯罪を食い止めることも、少女の命を救うこともできなかったことが明らかになるのです。性犯罪者と彼に捕まってしまった少女との行き詰まるような攻防、そして警察の必死の追跡を描いた、キャロル・オコンネルの『クリスマスに少女は還る』などを読んだ人間からすると、この展開の異常な早さは呆気に取られてしまうほどです。 未読の人のためにこれ以上は書きませんが、主な犯罪の過程は前半でさっさと終ってしまい、後半はその過程に対する司法の場での出来事、そしてそうしたこと全体に対する人々の反応について描かれることになります。「謎解き」の要素なんて微塵もありません。 ちなみに、著者の1人、アンデシュ・ルースルンドさんは刑務所に関するドキュメンタリーを作ったというジャーナリスト、もう1人のベリエ・ヘルムストルムさんは刑事施設・更正施設評論家という肩書きの持ち主です。著者2人のこうした経歴からして、刑務所や犯罪者の更正に関する問題点を指摘しつつ、何らかの積極的な提言を行うような物語なのかな、と最初は思ってました。でもそれはとんでもなかった。彼らはおそらく現行の司法制度の理念を否定するつもりなど全くないと思うのですが、それでも、そこで描かれる性犯罪者の像は、他人と最低限の意志の疎通を行うことすら殆ど出来ず、そしてそれが大きく変化する見込みは殆どないというもの、つまり更正の余地など殆ど期待できない存在です(もちろん「サイコパス」などといった安易な用語は使われませんが。余談ですが、ピーター・ラヴゼイのある著作では、一人のプロファイラーの口を借りて、「サイコパス」という用語に対する批判が述べられています。さすがはラヴゼイ)。 一方ではまた、性犯罪者、とりわけペドフィリアが何故ここまで徹底的に憎悪され、特別な監視の対象となることが許されているのか、という問題についての、多少批判的なコメントも見られます(正確には知らないのですが、アメリカやイギリスの少なくともある部分では、ペドフィリアの犯罪者は、その後も住所等が一般に公開されている筈です)。以下は、刑務所内でのペドフィリアの扱いについて述べたものですが、これは何も刑務所内に限ったことではないでしょう。「囚人たちは皆、恥辱や自己嫌悪の念を抱いている。そのはけ口が必要だ。塀の外の社会で馬鹿にされるのには、とても耐えられない。だから代わりに、自分とはちがう罪を犯した囚人を馬鹿にしてやる。自分よりも醜く、もっと傷つき、もっとのけ者にされているやつがいる。みんなでそう決めてしまえば安心する。それが、世界中の刑務所に昔からある、暗黙の了解だ。……他人の生きる権利を奪った俺は、ペニスであそこをずたずたに突き刺したおまえよりも、価値ある人間だ。他人を踏みにじったのは同じだが、俺のほうがだんぜんましだ」。これは明らかに矛盾です。しかし話はそこまで。『制裁』は、現在の司法制度・犯罪対策が明らかな矛盾を抱えていることを丹念に指摘していくのですが、その解決を示そうとはしません。むしろそうした矛盾を、もしくはその矛盾から生まれかねない新たな矛盾の可能性を、これでもかといわんばかりの迫力で1つ1つ丁寧に描いて行くだけ。例えばスウェーデンには死刑制度がありませんから、更正不可能と思われる犯罪者も一定刑期を満了すれば刑務所を出られます。著者たちはだからといって、死刑制度復活を主張するようなそぶりは全く見せません。ただ「更正」という近代的な理念が明らかにあやうくなっている事態を読者に突きつけるだけ。またそうした矛盾に対する市民の反応も描かれます。その反応というのは、まさに性犯罪者(ないしはその恐れがあるもの)を自らの手で罰することで、犯罪を未然に防ごうとするもので、少なくとも近代的な司法制度の理念からすれば決して許されないことです。しかし、そこにはまた現代の司法制度に対する不信、そして現代の犯罪に対する不安感というものが潜んでいることもまた事実であり、その事実を著者たちは決して否定しません。もちろん市民による制裁という考え方を決して肯定はしませんが。そしてその先には、性犯罪者だけが他の犯罪者に比べても劣等な処遇を受けることが公式に認められている、という別の矛盾が続いてくるわけです。もちろんそうした事態を認めるような市民感情が確実に存在することを(ある程度批判的に)認めつつ。 とにかく出口が見えない。解決の糸口を示すどころか、事態がより深刻になるのではないかという懸念すら伺えます。だから話はとにかくひたすらに息苦しい。最近のミステリは読んでいて苦しいものが少なくないですが、ここまで息苦しいものは正直初めてです。話には救いがこれっぽちもなく、ラストも悲惨。もちろんこうまで行き詰まり感に溢れているのは、著者たちが死刑制度の復活とか、「サイコパス」の隔離とかいった、安易で扇情的な解決策を提示せずに、何とか近代的な司法理念の内側に留まろうとしているからこそだとは思います。そうでなければ、そもそも矛盾など生まれないのですが。でもそれでも、そのどうしようもない矛盾には身体が締め付けられるような思いがします。せめてもの救いというか、驚きなのは、これがスウェーデンのベストセラー・リスト(何位まで載るのかわかりませんが)に14週連続でランクインしたということ。とにかく矛盾を矛盾としてきちんと向き合おうという人たちがそれなりにいるということなのだと思います。出口は見えないままにせよ。
2007年12月18日
コメント(0)
-

ハーブと革命
以前『真説ラスプーチン』を取り上げたとき、歴史の大きな動きが見えにくいという感想を書きました。その時念頭にあったのは、ここ数年で読んだ、伝記的な社会史とでもいうべき、幾つかの優れた作品です。 例えば、サイモン・ウィンチェスターの『世界を変えた地図』。これはイギリス地質学研究の草分け的存在であるウィリアム・スミスという人の伝記なのですが、むしろ、スミスについて語りながら、当時の地質学、そして博物学の発展、そしてちょうど同時代にあたる産業革命との関り合いを、全体として描く優れた作品になっていたのでした。毛色は少し違いますが、サイモン・シンの書いた『フェルマーの最終定理』も、基本的にはジョナサン・ワイルズという、フェルマーの定理を解いた数学者を中心に話が進むのですが、その過程を通じて最終的には、ギリシャから現代に至るまでの数学の歴史、そして現代における数学業界の様子などが明らかになるという構成を取っていました。どちらにも共通しているのは、ある個人を軸にして、そこに関わる人や物事を書き込んでいくうちに、1つの時代、ないしは1つの領域が全体として浮かび上がってくるという点です。そもそも社会史というジャンル自体、歴史の中で今まであまり重きを置かれなかった領域や主題に光を当てることで、歴史全体を違う角度から眺めることを可能にするものですが、上記の2冊は伝記というスタイルを取ることで、その点をさらにはっきりさせていたように思います。そして、つい最近読んだ、ベンジャミン・ウリーの『本草家カルペパー』もまた、そのような作品といってよいでしょう。 ちなみにカルペパーというのは、17世紀のイギリスで、当時使われていた薬草の類いについて、その効能を英語で説明する本を始めて出した人です。それまで薬についての知識はラテン語でしか書かれておらず、従ってラテン語を読めない多くの民衆は、薬についての正確な情報を持つことが出来なかったのですが、カルペパーの本によって、薬の、ひいては医学に関する知識をようやく普通の民衆でも手にいれることができるようになったのでした。原題は『ハーバリスト・カルペパー』。つまり多少大袈裟な言い方をすれば、現在日本人の私たちですら何気なくハーブティーを飲んだりしているという事態の、その出発点に彼がいるという訳です。実際ネットで調べてみると、イギリスには「カルペパー」の名を冠したアロマオイルの会社もあるようで、そういうことに詳しい人はもしかするとその名前を聞いたことがあるのかもしれません(最初に掲げた写真はそこのロゴだと思います。例えばにこんな製品も↓)。 ただ、ハーブに興味のある人が、イギリスのハーブの本?と思って手にとると多分びっくりするかと思います。何せカルペパーが活躍した時代というのは、イギリス市民革命(世界史で「清教徒革命」とか「名誉革命」とかいう名前で習うあれです)の真っ只中。そしてカルペパー自身も、市民革命に巻き込まれるどころか積極的に参加していたため、本の三分の一以上が、市民革命についての、そして市民革命期のロンドンの様子(カルペパーはロンドンに住んでいた)の描写に費やされているのです。もちろん戦争に従軍して王党派と戦うことと、民衆向けのハーブの本を書くことは、カルペパーの中ではしっかりつながっており、そのつながりを説明するのがこの本の眼目ですからそうなるのも当然。そしてそのおかげでこの本は、そこからハーブについての知識はそれほど得られないにせよ、イギリス市民革命という途方もない歴史的事件を当時の医学・薬学の世界から眺め、そうすることで革命の過程自体を非常にわかりやすく、かつ生き生きと描き出すことに成功することになったのでした。もっとも、カルペパーについて書かれた文書が殆ど無いので、そういう社会史的なアプローチを取らないと、そもそも何も書けないという事情もあるにはあるようですが、それはまあさておき。ちなみに、やはり17世紀イギリスという大変な時代を、スコットランドという「辺境」から眺めた物語として、ローズマリー・サトクリフの『はるかスコットランドの丘を越えて』があります。サトクリフについては、アーサー王物語や、ローマ時代のイギリスを扱った作品で知っている人も多いかと思いますが、優れた歴史文学作家。一応「児童文学作家」ということになっていますが、大人が読まないのは勿体ない。ついでに言えば、『アイヴァンホー』で有名なサー・ウォルター・スコットの『ウェーバリー』なんかも、まさにサトクリフと同じ題材を扱ったものらしいのですが(というかサトクリフはスコットに対するオマージュとしてその本を書いたようです)翻訳は出ていないようです。そうそう、スコットやサトクリフほど偉大ではないですが、ロス・キングの歴史ミステリ『謎の蔵書票』も、17世紀「革命後」のイギリスを扱ったものでした。これもまあまあオススメです。 最後にもう1つ。『カルペパー』を書いたウリーという人は、これより前に、エリザベス一世のお抱え占星術士だったジョン・ディー博士という人の伝記も書いているそうです。カルペパーもまた占星術にそうとう入れ込んでいたようで、そうした今から見れば「うさんくさいもの」を、彼がどういう風に利用したかというのが『本草家カルペパー』のサブテーマでもあったことを考えると、非常に非常に興味深いです。翻訳、出ないもんでしょうか。お願いします、白水社さん。
2007年12月15日
コメント(0)
-

いくつものアメリカ・その2
(『制裁』について、ではありません。それについて書けるまでもうしばらくかかりそうです) 前回、クックの作品について書いたときのタイトルは「いくつものアメリカ」でした。そのタイトルについてきちんと説明をしていなかったのですが、つまるところ、「アメリカ」という言葉で多くの日本人がイメージするであろうものとは全く違うものをクックは書いている、ということが言いたかったのです。ただ「もう1つのアメリカ」とか「アメリカの光と影」というような言い方はしたくなかった。そういう二項対立ではこぼれ落ちてしまうほどに、一人一人のアメリカ人にとっての多様な「アメリカ」の経験があって、それぞれが、その様々なアメリカの土地で、様々な記憶を抱え、様々な物語を生きているということ。そのことを忘れないように「いくつものアメリカ」というタイトルをつけたのでした。 おそらく、クックが場所と記憶に執拗にこだわるのも、そうしたことなんだろうと思うのです。クックの小説の登場人物たちの多くは、成功者というほどではないにせよ、少なくとも生まれ育った土地と、そこでの境遇からは距離を取り(抜け出し)、それなりに安定している人が多い。そして彼ら・彼女らはその場所の記憶を懸命に忘れようとしたり隠そうとしたりするのですが、それはふとしたことで現れてきては、現在の自分の足を引きずり、悩ませ、時に振り回す。きっと、過去を鷹揚に振り返り、時に美化し、そしてあの過去があったから今の自分があるんだ云々と満足げに語るのが、「正しい」アメリカン・ドリームなんでしょう。けれども、クックの登場人物たちは、そうした大きな「アメリカ」の物語には頼ることができません。どこまでもどこまでもローカルな過去の記憶が、いつでも現在の安定を脅かし浸食しようと待ち構えている。もちろん、過去がそのようなものとしてあるのは、「成功」はもとより、「安定」にすら縁のない数多くの人々の「現在」があるからです。そこにもまた、非常にローカルな「たくさんのアメリカ」がある。そもそもアメリカン・ドリームという大きな「物語」は、「成功」できなかった様々な人々を見捨てることを正当化したという側面もあるのですから(そこにアメリカの社会保障の貧困があります)、そうした「物語」が、排除した人々によって復讐されるというのは当然のことかもしれません。もっとも、多くの「成功」の物語はそんなことを気にかけていないのですが、少なくともクックは、そうした事態を強く意識している作家の一人だと言ってよいでしょう。そして、同じことを、おそらくクック以上に痛切に意識していたのが、リチャード・ブローティガンという作家でした。今回取り上げる藤本和子『リチャード・ブローティガン」は、まさにそのことを書いた作品です。ちなみに藤本和子という人は、ブローティガンの小説の多くを見事な日本語に訳して来た人で、実際にブローティガンとも親しい友人だったようです。以下は主にその本から。 実の父親は母親の妊娠中に姿を消し、その母親は家を飛び出したり帰ってきたりを繰り返しつつ生活保護でかろうじて暮らしていたという少年時代を持つブローティガンは、生まれ育ったオレゴンを抜け出してカリフォルニアへと向かい、そこで様々な仕事をしながら小説を書き、1967年に出版された『アメリカの鱒釣り』という小説で一躍有名人になります。そして彼もまた、死ぬまで一度も生まれ故郷に戻らず、母親にも妹にも会うことはありませんでした。けれども「逃げるつもりで出奔した故郷はかれを追いつづけ、ついにその束縛の手をゆるめなかった。それはかれにもよくわかっていた」[64頁]。だから彼はそれ以上逃げようとはしませんでした。むしろその過去を決して忘れまいとし、そしてその過去の経験を、そして少年時代の彼が置かれていたような境遇に今も生きているような人びとのことを書き続けた。「働きづめで報われることもなく死んだ女たち、不幸だった酔いどれの、あるいは、やさしかったが間抜けだった親爺たち、非業の死をとげた若者たちの」[24-25頁]アメリカを。藤本さんはそのことをこんな風に説明しています。「呪詛のような風景。ブローティガンはそこで言葉という道具を手にして戻っていく。風景から逃亡するためではなく、それを葬りさらないための行為だ。オレゴンをあとにしてサンフランシスコへ、いわば逃亡したはずのかれは懲りもせずに、『呪われた土地』の原風景を語ることで、そこへもどる。いや、いまだにそこに佇んでいる」[162頁]。「語られなければ過去は時間の屑籠にすてられたままである。語られることで、記憶が掘りおこされる。埋もれた時間はときに、呪われた時間でもあるが、それでも語られさえすれば、傷ついたこころが休息を得ることはある。いや、呪われた時間こそ、語られなければならない。それではじめて、悲傷や失意や屈辱に威厳があたえられるだろう」[140頁]。それは彼がどんなに有名になっても、そしてその後再び忘れ去られてしまっても、ずっと一貫して変わらないことでした。1982年にモンタナ州立大学で創作講座を持っていた頃のこんな話が紹介されています。「授業のあとは、バーへ行った。過去を忘れてしまいたい人びと、あるいは現在をどうにかやりすごす力を得たいと願う人びとがバーに集まっていた。『これこそ、偉大なるアメリカの楽しみの追求さ』とかれはいった。『人生は壮絶だ、残酷だ、人びとは苦しみ嘆いている』」[27頁]。もちろん、カリフォルニアの陽光の下で生きながら、「陽光の土地の、石や建物や樹木の蔭にひそんでいる人々の挫折や悲哀が、太平洋北西部の原風景に重なってみえてしまう」ようなブローティガンに、心の平安が訪れることはありませんでした。「彼は引き裂かれていた」と藤本さんは書いています。ブローティガンは20歳の時に精神病院に強制入院させられて以来、何度も何度も抑鬱に苦しめられ、酒量は増える一方、そして何らかの救いを求めて訪れた日本でも結局安らぎを得ることが出来ませんでした。きっと彼は、本当にぎりぎりのところを綱渡りのようにして生きていたのだと思います。それほど土地の記憶、土地の呪縛は強かった。もちろんいつでも目に入ってしまう「苦しみ嘆く」人々の姿も。おそらくブローティガンにとっての「アメリカ」とはまさに、自分の知る「いくつものアメリカ」に引き裂かれ続けることだったのでしょう。そうして、酒場のエピソードの2年後に、彼は自ら命を断ちます。44口径マグナムで、頭を撃ち抜いて。 追記:ブローティガンの本は、数年前に文庫が出て手に入りやすくなりました。喜ばしいことです。
2007年12月10日
コメント(0)
-

スウェーデンのミステリを読む
まずとても私的なことを書きます。今思い出すと不思議なくらいですが、中高生の頃は「北欧」という言葉にひどく思い入れがありました。別に福祉がどうとかそういうことではないのです。ただ単にムーミンが大好きだったのですね。とりわけ『ムーミン谷の冬』は小学校の時に一回読んだくらいだったのですが、圧倒的な印象を自分の中に残していました。もっとも当時は、トーベ・ヤンソンがフィンランドの出身であることすら知らないくらいで、思い入れといってもひたすらに抽象的なものでした。そういえば高校一年生の時、地理の授業で国を1つ選んで壁新聞を作れという課題が出た時があって、そのとき「一国ではなく北欧三国で作っては駄目か」と先生に絡んだこともあったなあ。意味不明な情熱。ダメと言われて仕方なくスウェーデンについての壁新聞を作っていたら、そのときヤンソンさんがフィンランド人だと気付き、随分恥ずかしい思いもしたのでした。そうそうちょうどその頃、当初は原作にひどく忠実に作っていたムーミンの新作アニメも放映中だったっけ(放映後半はみるも無惨なことになってましたが)。 その後も北欧に対するファンタジックで一方的な思い入れは続き、大学生の時には念願かなって冬の北欧旅行(そしてムーミン博物館見学)という無謀な夢もかなえることが出来ました。その後『ムーミン谷の冬』を再読して、ますますその素晴らしさを確信もしました。ただそれでも、北欧の国々について具体的なことは殆ど知らないという状態は依然として変わらず、漠然と好印象を持ってはいたものの、いつしか「北欧」という言葉は自分の中で薄れていってしまいました。 それが変わったのはここ数年。スウェーデンの研究をしている友人が出来たり、北欧音楽を少し聞くようになったり(ヴェーセンとトリアケルくらいですが)、そして何より、ヘニング・マンケルのクルト・ヴァランダー・シリーズに出会ったのが大きかった。おかげで北欧に対する、とりわけスウェーデンに対する興味がぐんと広がりました。そして気付いてみれば、マンケルさんの邦訳が2001年に出て以来、数は少ないですが、スウェーデンのミステリがぽつぽつと定期的に出版されるような状況も生まれていたのでした。 長い前置きになりましたが、ここからが本題。最近立て続けに2冊のスウェーデンのミステリを読みました。リサ・マークルンドの『爆殺魔』とアンデシュ・ルースルンド/ベリエ・ヘルストレムの『制裁』です。以前最近のミステリの傾向について少し書きましたが、スウェーデンにおいても基本的にはそれは変わらず、犯人は誰か、トリックは何なのかといった「古典的」な問いはどちらのミステリにおいても殆ど問題になりません(もっとも僕はスウェーデンミステリの名作マルティン・ベック・シリーズを読んでいないので、それとの比較はできないし、いわゆる「古典的」なミステリも翻訳されていないだけで存在しているのかもしれませんが)。むしろ2つのミステリで中心的となるテーマはスウェーデンとはいかなる社会であるのかという問いかけであって、あくまでその1つの視点として犯罪を描いているという印象を受けます。マンケルさんの場合は、まだ警察小説という性格が色濃いですが、それでもやはり同じ傾向を持ってますね。だからマンケルさんもそうですが、この2冊のミステリでも、スウェーデンについての様々な事柄が細々と描かれることになります。 例えばスウェーデン人はシナモンロールが大好きで、あちらこちらで食べているとか、冬にはグルッグと呼ばれるホット赤ワインに香料を混ぜた飲み物を飲むとか、そういう日常の風俗がわかるのはとても楽しい(特に『爆殺魔』はクリスマス前の数週間が描かれているので、スウェーデンのクリスマスについてよくわかります)。正直、ここまで日常的なことをきちんと書き込んでいる小説というのは(特に現代文学では!)そんなにないと思います。残念なのは、スウェーデン人であれば説明せずにわかることが、こちらにはわからないこと。例えばある登場人物がある地域の出身であると書かれていれば、スウェーデンの人はそれだけで何らかの印象を持つのだろうし、作者もそれを分かって書いているのだろうなと思うのだけれど、日本人には全くわからない。ただそうしたことを補ってあまりあるほどに、スウェーデンの、おそらく観光しただけでは決してわからない日常の風景が、くっきり浮かび上がってきます。 そしてもちろん、その日常の風景というのは、楽しいことばかりではない。例えば『爆殺魔』の訳者あとがきでも触れられていますが、スウェーデンには個々人に社会保険番号というものが割り振られています(日本の住民基本台帳のようなもの?)。そして他人の番号も、普通の市民が簡単にわかるようになっているらしく、つまりは他人の住所・電話番号・職歴等々のいわゆる「個人情報」が簡単に手に入ってしまうのです。知り合いのスウェーデン研究者によれば、スウェーデンの人たちはみんな「便利で良い」と言っているらしいですが、『制裁』にはこんな文章もありました。「赤の他人であっても市民番号さえあれば、どんな人生を送っているか、細かく調べ尽くすことができる。なんと便利なことだろう。なんと異常なことだろう」。 実のところ、マンケルさんの作品も含め、これらの現代スウェーデン・ミステリから浮かび上がってくるのは、スウェーデン人が社会に対して抱えている漠然とした不安だったりします。スウェーデンの社会保障制度が非常に発達しているのは間違いない。それはスウェーデン人もはっきりわかっていることだと思います。彼らは自分たちが便利で快適で安心できる社会システムを作ってきたという自信を持っています。いや少なくとも持っていた。けれども、それが本当は上手くいっていないのではないか、もしくは便利で快適なのは確かだけど、その裏側には何か「異常」なものが隠れているのではないかという不安が、どちらの作品にも強く伺えるのです。 正直ミステリとしては強くオススメするようなものではないかもしれません。『爆殺魔』は悪くはないけど地味。そして『制裁』は殆どミステリとは言い難い。でも、ミステリとしての楽しみはそんなに期待できずとも、ある1つの社会と、そこに生きる人間の姿を多層的にきちんと捉えているという点で、やはり優れた小説であるとは思うのです。とりわけ『制裁』は本当に凄い小説です。 なお、『爆殺魔』の方は原作が 年に出版されて邦訳は2002年。訳者あとがきによれば、その2002年の時点で、『爆殺魔』と同じ主人公の物語が既に2冊出ているらしく、ぜひ読みたいと思うのですが、今の時点で翻訳されていないということは、もう出ないんでしょうねえ・・・。売れなかったんだろうなあ。これが英語であれば、よっしゃ原作で読んでやると思えるのですが(実際に読むかどうかは別として)、スウェーデン語だともう手も足も出ません。今年邦訳が出たばかりの『制裁』も、同じ作者2人による作品が数冊出ているそうで、こちらも激しく読みたいですが、どうかなあ。『制裁』の売れ行きによるのだろうと思いますが、『爆殺魔』以上に期待できません。なぜ『爆殺魔』以上に期待できないかというと・・・・。これはまた回を改めて書くことにしましょう。
2007年12月08日
コメント(0)
-

「うさんくさいもの」たち・その2
上手く続きになるかどうかわかりませんが、前回の続きです。 「うさんくさいもの」というタイトルからすると、超能力者であるとか超常現象であるとか、そういったものをネガティブに捉えていると思われてしまうかもしれませんが、実のところ、基本的にそういう「うさんくさいもの」は大好きです。ただ「うさんくさいもの」はあくまで「うさんくさい」から素晴らしいのであって、それが色々な意味を付与されすぎてしまうのは良くないと思うのです。前回の『職業欄はエスパー』に絡めて言えば、例えばスプーン曲げは是非見てみたいと思います。でもそれが、「人類の新たな能力」を発露であるとか、「物理法則を覆すもの」であるとか、そういう意味づけは正直どうでもいい。多分、そういう過度な意味づけをするから、今度は「トリックがあるに違いない」とかいった「否定派」が活気づくのです。不思議なこともあるもんだ、とそのくらいでいいではないですか。「うさんくさいもの」は「うさんくさいもの」のままにしておきましょう。理由がわからなくてもいい。いや、理由がわからないからこそ面白いのです、きっと。だから極端な話、「超能力」にトリックがあっても全然かまわない。僕の中では手品もスプーン曲げも、そして大道芸も「うさんくさい」ことにおいては変りないです。もちろん、手品だろうとスプーン曲げだろうと、パフォーマンスとして素晴らしければ、賞賛を送るべきなのは言うまでもありません。 とても極端な言い方をすると、「うさんくさいもの」とは「無意味だけどとにかく凄い」もの」と言い換えてもいいです。例えばあらゆる「見世物」は全て「無意味だけどとにかく凄い」ものでしょう。反発を覚える方もいるかもしれませんが、僕にとってはスポーツもまた、その「見世物」の部類に入ります。だって100メートルを9秒台で走ろうが、49.195キロを2時間ちょいで走ろうが、昔ならともかく現代においては全く意味がないのですから。スポーツから何か人生の教訓を学ぼうとか、そういう態度はとても苦手です。イチローにしたってちっとも面白いことを言っているとは思いません。それよりパフォーマンスに徹している野村監督の方がずっと面白い。小沢昭一という俳優なんかは、「役者というのは所詮、河原乞食である」という意味のことをよく言っています。極めて肯定的な意味において。その段でいくと、スポーツ選手もまた、河原乞食の類いでいいではないかと。だいたい、身体能力の高さ、とか自己管理能力の高さ、という点で言えば、中国の雑技団とかサーカスの人たちなんかすごいですよ。でも誰も彼らから人生の教訓を学ぼうなどとはしないわけです。 身体能力のことばかり書いていますが、実のところ、人間の想像力の中にも「限りなく無意味だけど凄いもの」というのはあると思います。そしてそういう想像力のあり方を、実のところ「オカルト」というのではないかと。例えばレイラインというものがあります。考古学的ないしオカルト的に重要なものが同一線上にある、という考え方です。正直、同一線上にあるから何なんだ、と思いますが、少なくともそういうことに気付いてしまう想像力というのは凄いと思うのです。もちろん人間の想像力のすることですから完全に「無意味」にはなりえない。でもそこに付与された意味は限りなく「無意味」です。少なくとも、僕たちが日常的に生きている世界においては「無意味」。僕は『ダヴィンチ・コード』とか、それに続いて出版された数々のオカルトチックな長編冒険小説の類いをそれなりに読んでいますが、その理由もまた同じです。アーサー王の墓を捜すとか、聖杯の正体を突き止めるとか、そもそもいつになっても達成できないとは思うのですが、そういう限りなく「無意味」なものに向かう想像力というのは、とても魅力的だと思うのです。「荒唐無稽」っていいではないですか。 あと、そういう「うさんくさい」想像力を一挙に集めたマンガ『イリヤッド』も、話の大雑把さと合わせてとても好きです。もちろん『イリヤッド』と同じく長崎尚志の原作による『MASTERキートン』も。 「オカルト」的想像力は、確かに厄介なものにもなります。とりわけ宗教的なものと結びついた時には、意味が膨らみすぎてしまう。リン・バーバーというイギリスの社会史家が書いた『博物学の黄金時代』という本には、18世紀から19世紀にかけて続々と登場する地質学的な証拠が聖書の記述を否定するのに対して、教会側が用意した涙ぐましいまでに荒唐無稽な説明が書いてあります。それは今読むととても微笑ましいけれど、同様の事態が、現在のアメリカのように「進化論を教えるな」という話になってしまうと笑うに笑えない。やはり『博物学の黄金時代』に書いてあったと思うのですが、ネス湖のネッシーというのは、科学者の間で「想像上の動物」と「実際に存在する動物」との区別がほぼ完全になった19世紀後半から生まれてきた話だそうです(ちなみにそれ以前には、グリフィンなどという動物まで「実際に存在する」と考えられていたらしい)。言うなれば、常識では説明のつかないものが存在してほしい、ないしは常識ではどうにもならない事に説明をつけてくれるものがほしいという思いが「ネッシー」を生み出した訳です。そういう思いをむげに否定したくはない。だからこそ、そういう思いは「ネッシー」くらい「うさんくさい」ものであってほしいと思うのです。そして「うさんくさい」という言葉を何度も使ったのはそういう訳だったのでした・・・。 まとまったようなまとまってないような、でもいい加減長くなったのでこの辺にします。最後に「うさんくさいもの」を、正しく「うさんくさいもの」として扱った「博物学」の本。荒俣宏の『怪物の友』を紹介しておきます。本当にこのくらいがちょうどいいんですけどね(あ、これはリンク張ってません)
2007年12月05日
コメント(0)
-

「うさんくさいもの」たち
前回取り上げた『真説ラスプーチン』を読んでいると、どうしても、ロシア人の超常現象好きということが頭に浮んでしまいます。確か米原万里さんも、どこかでそのことを書いていました。19世紀後半に降霊会などが盛んだったのはともかく、20世紀の米原さんの友人の中にも、そういった類いのことに熱心な人がいたとか。ついでにいえば、あのオウム真理教は、ロシアではそれなりの勢力を獲得していたのでした(実際『ラスプーチン』を読んでいると、麻原彰晃など、ミニ・ラスプーチンのように思えてくるほどです)。「ロシア人は超常現象が好き」という一般化は現に慎むべきではありますが、少なくとも『真説ラスプーチン』は、なぜ当時のロシア人の一部が「超人」を求めてしまうのかということについてかなり説得的に書いていて、それはロシア人に限らず、ある状況に置かれた時にある種の人が「超越的なもの」を求めてしまう心理についての、それなりに普遍的な説明にもなっていたと思うのです(同じようなことは沼野さんの解説にもちょこっと書いてあります)。もう1つ、『真説ラスプーチン』は、ラスプーチンが完全ないかさま師でもなければ、かといって現世を超越した聖者でもないという立場を一貫して守っており、そこには好感が持てました。ラスプーチンのような人は、自ら誇張していたかもしれないにせよ、確かにある種の「能力」は持っていたのでしょう(それを超能力とか霊能力とか言うかどうかは別にして)。例えばここにアップした写真を含めて、ラジンスキーも書いているように、彼の写真は全てその「目」が凄いです。でも、そうした凄さや「能力」は、彼が何も現世を超越していたということにはならない。そんなことよりずっと重要なのは、そうした「能力」の持ち主と、その周りの人たちが、その「能力」を、特定の歴史的・社会的状況においてどう利用するか(ないしは利用されるか)、ということなのだと思います。ラスプーチンの場合は、おそらくありとあらゆる意味において、その「利用」は悲劇的なものになってしまった訳ですが(そして付け加えると、『石のささやき』もそうなのですが)。そうすると思い出すのは森達也の名作『職業欄はエスパー』(単行本時の題名は『スプーン』)。職業欄はエスパー元スプーン曲げ少年の清田益章、UFO・宇宙人評論家の秋山真人、ダウジングの堤裕二という3人の「超能力者」の「日常」を追ったドキュメンタリーを制作する中で、森達也は、自分の目の前で説明のつかない事態が次々と起こるのにも関わらず、最後まで「超能力を信じるか」という質問に「わからない」(時に「信じない」)と答え続けます。彼らはある種の「能力」を持っている、でもそれが「超能力」なのかどうかはわからない、と。それは、彼らが単なるいかさま師でもなく、けれども特別な人間でもないという立場と言ってもいいでしょう。森達也の関心が、「超能力者」という肩書きを(ある程度までは本人たちも不本意なままに)与えられてしまった人が、そもそもどういう「人間」であるかを探ることにあった以上、「超能力」があるかないかという議論には加わらないというのは全く正しい。そしておそらく彼にしてみれば、「超能力」は存在するかどうかという議論の設定自体が、彼らのもつ何らかの「能力」をメディアが「利用」する1つの仕方なのでしょう(もちろん秋山さんのようにその「能力」を「利用」して生計を立てている人もいるわけですが)。そして彼は「超能力者」たちを「人間」として描くことによって、その「利用」に批判的に対置させようとする訳です。・・・もう少し書きたいことがあるので、次回以降に続きます・・・なお、森達也がテレビ用に撮ったドキュメンタリー『職業欄はエスパー』はYoutubeで見れます↓ あと関係ないけど、森さんはこの頃が一番面白かったなあ・・・。http://www.youtube.com/watch?v=IRYHfNU1rws
2007年12月01日
コメント(0)
-

伝記と歴史と物語
11月11日だったかの朝日新聞の読書欄に、エドワード・ラジンスキー『アレクサンドル二世暗殺』の書評が載っていました。何でも19~20世紀のロシアを扱った四部作の最後の作品だそうで、かなり高い評価。ちょうどヨーロッパ関係の歴史書を探してもいたし、19~20世紀のロシアという歴史的に非常に興味深い時期についても知りたいことは沢山あったので、ひとまず四部作の中で最もとっつきやすそうな、『真説ラスプーチン』から読むことにしました。書評では、ラジンスキーの文章の「読みやすさ」を強調していました。他の作品は知りませんが、少なくともこの本は確かに非常に読みやすい。それは何故なのか。まず、いちいち謎を提示してはそれを解決していくという手法が1つあるでしょう。ラジンスキーは、自分がこれからどんな謎を解こうとしているのかをいちいち書いてくれるので、読者はその後の文章から何を読みとればいいのかが非常にクリアになるのです。ついでに言うと、謎の「解決」を余りにきっちり書こうとするので、どうしても推測が交じってしまい、それが多すぎるというのがラジンスキーに対する一番の批判になっているそうですが、まあ基本的には誤解を招くような書き方はしていないのでよいのではないかと思います。あと、このこととも少し関連するのですが、背景説明的な記述が最小限に抑えられている、ということもあるでしょう。例えば最初の方に、ラスプーチンの出生について簡単な記述があるのですが、そこで彼の出身地であるポクロエスコフ村については、殆ど説明がなされない。たいがいの伝記であれば、村の規模くらいは書くでしょうし、もっと詳しいものになれば当時のロシアにおける農村の状態一般についても記述するでしょう。しかしそうしたものは一切無し。基本的に万事がこの調子で進みます。それが悪いと言っている訳ではないです。結果としてラジンスキーは、社会的な文脈よりも個人的な人間関係を中心にラスプーチンを描き、「謎」もたいがい人間関係によって説明する訳ですがそれはあくまでスタイルの問題。それに、ラスプーチン関係の本は沢山出ているので、そうした情報はそれらの中に十分書いてあると思っているのかもしれないし、もしかするとラジンスキーがほぼ同時代を扱って書いている『皇帝ニコライ処刑』に書いてあるのかもしれません。また(あとがきで訳者の沼野さんがしているように)そこに書かれていることを自分でより広い文脈の中に埋めこむという楽しみもあるのでしょう(残念ながら僕にはその知識がないですが)。ただ一方で、この本だけだと、ラスプーチン、皇帝夫妻、貴族たち、そして一部の国会議員や聖職者等々の「偉い人」の手によってのみ歴史が動いているという印象を与えてしまうのも確かです。さらには、人間関係の幅がどうしても限られてしまうため、次第に同じ事の繰り返しになってくるという問題もあります。正直、ラスプーチン暗殺までの数年を扱った下巻は、終盤の暗殺場面の記述以外は少々だれました。人間関係の構図自体は殆ど変化せず、ただ新しい人物が繰り返し現われては消えていくばかり。せっかく第一次世界大戦とロマノフ朝の危機という、世界史的な背景があるのだから、それをもっと利用すれば良いのになあ・・・とやっぱり思ってしまったのでした。ちなみに同時代的な文脈と言えば、『アレクサンドル二世暗殺』では、ドストエフスキーについてそれなりのページが割かれているそうですが、この『ラスプーチン』にもドストエフスキーへの言及が幾つかあります(他にもレーニンとかトルストイとか有名人への言及が時折挟まっているのはちょっと嬉しい)。実のところラジンスキーを読もうと思った理由の1つは、ドストエフスキー読解の手助けになるかなと期待してのことでした。もちろん古典新訳文庫の『カラマーゾフ』を読むことを意識しつつ(まだ買ってもいませんけどね)。でも、全く助けにならないとまでは言いませんが、少なくともこの本は期待したほどではなかった。それはもちろん以上のような理由、そしてそもそも時代が違うという僕のミスによるものです。時代的なことを言うと、むしろレーニンなんかを読むのに役立つのかもしれません。って今どきレーニンもないかもしれないけど(あ、でも古典新訳文庫のシリーズからレーニンも出てたっけ)。ドストエフスキー読解に向けては、改めて19世紀ロシアについての良い本を探さなくてはいけないですね。何かいいの無いかな。 カラマーゾフの兄弟(1)
2007年11月29日
コメント(0)
-

いくつものアメリカ
石のささやき 遅まきながら、トマス・H・クックの新作『石のささやき』を読みました。クックについては書きたいことが山ほどあるのですが、まずは本の終わりについている「解説」のことから。 どの本だったか忘れてしまいましたが、クックのある作品の解説を読んでいた時に、ミステリ評論家の誰かさんが、「ミステリと文学の区別など存在しない!!」(つまりそれほどクックは素晴らしい!!)と息巻いているのを見て、うんざりしたことがあります。今どきいったいどれだけの人が、そんな区別を真に受けているだろうかと。いわゆる「文壇」の人たちが何を考えているかは知りませんが、多くの本好きは、ミステリだろうと何だろうと、重要なのは面白いか面白くないかであって、それが「文学」だろうと「文学」でなかろうとどうでもいい筈です。文化研究が盛んになった現在、多くの「文学」研究者たちですら、そういう区別をどうでもいいものと思い始めているのくらいですから。何というか、「ミステリと文学の区別など存在しない」と叫ぶミステリ評論家というのは、その人の度し難いコンプレックスの現われなんじゃないかと思ってしまったのでした。 で、そういうコンプレックスは今回の「解説」にも出てきます。『石のささやき』の解説には、何と佐伯一麦やら福永武彦までが持ち出されて、クックとの類縁性が示唆され、クックが描くのは「真正の人間ドラマ」なのだと主張されるのです。つまりそれくらい「普遍性」があるのだと言いたいんでしょうね。でも、人間の持つ「普遍性」を描くのが「文学」だという、この途方もない勘違い自体、彼のコンプレックスを裏書きしているように思えてなりません。というか、そういう我田引水を、果してクックは喜ぶのかな。 わざわざ人の悪口を書き連ねて来たのは、クックの「解説」はいつも、やれ人間の心理の奥深さだの人の心の闇だの、そういう似非心理学的なな抽象的価値に還元することに終始しているように思えてしまうからです。けれども、クックを読めば読むほど感じてしまうのは全く違うのは、彼が描きたいのは、そんな得体のしれないものではなく、まずもって「アメリカ」というものなのではないか、ということなのです。 例えば、『熱い町で死んだ少女』や『蜘蛛の巣のなかへ』、そして僕が一番大好きな『過去を失くした女』など、とりわけて歴史的な題材に特化した作品を読めば、彼が「アメリカ」の歴史に並々ならぬ興味を抱いていることは一目瞭然でしょう。それも公民権運動ならまだしも、わざわざ1930年代の労働運動などというおそろしくマイナーなトピックを選んだりもするのです。また舞台の多くはアメリカ南部。そして描かれるのはその共同体の息苦しさ。モルモン教を中心に持ってきた『神の街の殺人』など、アメリカでしかあり得ないような話ではないでしょうか。 しかし僕がとりわけ、クックの「アメリカ」に対する強いこだわりを感じたのは前作の『緋色の迷宮』でした。読んでない人のために詳述は控えますが、あらゆるものが不安定で疑わしく思えてしまいつつ、かつその疑わしいという感情すらが次第に疑わしくなっていくという心の動き、罰されるべき人が罰されていないとのでないかという社会(ないし共同体)に対する強い不信感などなど、この作品はまさに、扱われる事件の暴力性も相俟って、現在のアメリカが抱える深刻な「症状」を描いているように思えたのでした。すなわち、暴力に対するパラノイア的な恐れ、不安、そしてそのパラノイアそのものが暴力と化してしまうという矛盾。緋色の迷宮 そして振り返って見ると、上述したようなテーマは、それ以前のクック作品にもチラホラ見受けられる。ちょっと心理的な問題に深入りしすぎでは・・・と心配していた、いわゆる「記憶」シリーズ(このシリーズ名を勝手につけたのは日本の出版者ですが)にしても、アメリカの抱えるそうした「症状」の極端な現われを描いたものではないかと思えるようになってくるのです。そして、再び「記憶」シリーズへの回帰か?という気がしないでも無い今回の『石のささやき』もやはり、一貫したテーマは同じです。今回はそれに『神の街の殺人』と同様、超常的なものに対する執着というテーマが絡んできますが、その執着自体、そして執着が結局暴力に帰結してしまうという事態も、また極めてアメリカ的と言ってよいでしょう。 ただまあ、作品として見ると、今回のは少し落ちるかなあ・・・。二人称で描かれる刑事との対話シーンと、一人称で描かれる回想シーン(もちろん二人称の「おまえ」と一人称の「わたし」は同一人物)の繰り返しという構成は、どうも単調にすぎるし、かつてなかったほどにもってまわった(「文学的」な?)記述が多い気がします。文学作品からの引用も少しくどい。いや、最後まで読めば、そうしたものにもそれなりの理由があることがわかるようにはなっているのですが、わかるまではつらいのです。ただまあ、色々な手法を試してみようとするのはいつものことですから(『孤独な鳥がうたうとき』とか)、今回はそれほど上手くいかなかったかな、ということで、次回を期待することにしましょう。追伸 最後に、ここに書いたような「アメリカ」を強く感じてしまった映画を1つご紹介。一応刑事物ですが、全くカタルシスがなく、ひどく気の滅入る映画です(いや、良い映画なんですよ)。これを見た時も、アメリカはこんなにも行き詰まっているのか・・・と思ったものでした。ご参考までに。プレッジ スペシャル・エディション(期間限定)(DVD) ◆20%OFF!
2007年11月26日
コメント(0)
-

歴史映画を作るということ
最近、読書が滞っておりまして、また「読書」で日記が書けませんでした。今回は「映画」です。8月の末に試写会を観た『君の涙、ドナウに流れ』が現在公開されているようなので、それについて書いてみます。 歴史映画を撮るにあたって、たいがい誰でも知っていそうなトピックを選ぶ場合と、それほど知られていないものを選ぶ場合があると思います。誰でも知っていそうなトピックで再三映画化されているのは、やはりナチスについての映画でしょうか(日本人にとっては太平洋戦争かな)。これは何より観客がとっつきやすいという利点を持っていますが、同時にまたこの話?と思われてしまうために、新たな切り口がどうしても必要ともなります。例えば手軽な方法としては子供の観点から描くとか。ちなみに、僕はボランスキーの『戦場のピアニスト』をちっとも面白いと思わなかったのですが、その理由の1つは、何故あそこまで類型的なホロコースト映画を今さら撮らなくてはいけないのかが少しもわからなかったからです(唯一評価できるのは、ワルシャワ・ゲットーでの蜂起を撮ったことでしょうか。説明なかったけど)。 反対に、マイナーなトピックはリスキーです。『君の涙、ドナウに流れ』は、1956年のハンガリー動乱を扱ったものですが、ハンガリー人であれば誰でも知っている出来事であるにせよ、他の国の人で歴史にさして興味が無い人にとっては、それ何?でしょう。背景説明を詳しくするというのも1つの手ですが、そうすると映画的な面白さは大概半減してしまいます。実際この作品も、余計な説明は殆どありません。なのでハンガリー動乱について全く予備知識なしに観に行くと、所々意味がわからないという事態になるのではないかと。個人的にはこういうマイナーなトピックを扱った歴史映画をじゃんじゃん作ってほしいと思うので、この映画自体は歓迎なのですが、さてどれくらいお客が入るでしょうか。ちなみに日本人にとってはあまり重要なことではないかもしれませんが、全編ハンガリー語です(登場するロシア人はもちろんロシア語を話す)。パンフレットによれば、英語で作れば?という意見もあったらしいですが、監督があくまでハンガリー語にこだわったそうです。これも「取っ付きやすさ」と関係あるのですよね。つまりアメリカ人にとっての。『戦場のピアニスト』は全編英語(そして何故かナチスはドイツ語を話す)で、これもまた幻滅した理由の1つでした。 さてその上で、映画そのものについて。大国の圧制に苦しむ小国の悲劇、それに抵抗する市民、そしてその抵抗そのものが孕んでしまう悲劇・・・というテーマは、どうしても今年始めに観たケン・ローチの『麦の穂を揺らす風』を思い起こしてしまいます(尚アイルランド問題についての映画は数多くありますが、内戦そのものを描いた映画はあまり無いのでは。僕は『マイケル・コリンズ』くらいしか思いつきません)。麦の穂をゆらす風 プレミアム・エディション小グループに焦点をあてているというのも似てますね。ただ大きな違いが2つあります。まず1つは、『麦の穂~』が地方の小さなグループの話に限定しつつ、常にアイルランド全体の動きを意識させるように作っているのに対し、『君の涙~』は、学生たちのグループ以外の動きが今ひとつ見えないこと。例えば、ハンガリー動乱を扱った2つの著作、ビル・ローマックスの『終りなき革命 ハンガリー1956』やアンディ・アンダーソン『ハンガリー1956』がどちらも、労働者たちの作った工場評議会の役割を強調しているのに対し、映画はその存在すら感じさせません(もちろん他の知識人の動きなども)。ハンガリー1956そのため、何だか下手すると、主人公たちが、若さの余りつっぱしった学生たちの群像、みたいに見えてしまうのです。もう1つは、その小グループの人々が、大国の圧制に対して何を守ろうとしているのか、何を獲得しようとしているのかが、『君の涙~』では今ひとつはっきりしないことです。「独立」はもちろんなのですが、それ以上の価値。「民主主義」というのもあまりに茫漠としています。そして『麦の穂』は、その点も実にはっきりさせていたと思うのです。 ただし、こうして書くと『君の涙~』はたいした映画では無さそうに思えてしまうかもしれませんが、良く出来た歴史映画であることは間違いないです。ハンガリー動乱の推移と、オリンピックにおけるハンガリー水球チームの活躍の過程を、同時並行で追って行くという手法は、ありがちといえばありがちですが、見事なスピード感を生み出していますし、悲劇性を際立たせることにも一役かっています。また戦闘シーンのリアルさも特筆すべきでしょう。あまりにリアルなので、例えばソ連軍の戦車が爆発するシーンなどではカタルシスを感じてしまいそうになるほど。もちろん、リアルな戦闘描写の最大の目的は、現実の人間が戦い傷つき、死んでいったという生々しい現実を強調するためでしょうし、その目的は十分に達成されていると思います。おまけに監督はまだ39歳。これだけのものを撮れれば大したものでしょう。これからも良い映画を撮ってくれることを期待したいと思います。 追伸:尚、来年の春にはチャウシェスク大統領時代のルーマニアを舞台にした映画が日本に来るようですね。東欧関連ということでこれも楽しみ。ちなみに題名は『4ヵ月、3週と2日』です。
2007年11月24日
コメント(0)
-

舞台のマッピング
「読書」地図ではありますが、今日は舞台の話。先日、大阪の劇団「維新派」の公演を観に行ってきました。場所はさいたま彩の国芸術劇場。今年の夏に大阪で上演した新作『Nostalgia』のツアーの一貫です。実は公演開始数日前まで埼玉でやることを知らず、慌てて予約して観に行ったのでした。維新派を見るのは2003年の『ノクターン』以来、久しぶり。無理に「地図」と結びつける訳ではなく、この劇団は実際「地図」が好きです。確か以前「Map」と題した小公演もあったくらい(この公演自体はぐだぐだでしたが)。生演奏と打ち込み音に合わせてラップのように切れ切れのセリフを発するというのが維新派のスタイルなのですが、中でも世界各地の地名を役者たちが代わる代わるに口にするというシーンが多いです。単純と言えば単純なのですが、様々な響きの地名が舞台上に投げ出されることで、それがいつの間にか空間を広げ、そこにぼんやりと「地図」を浮き上がらせるのが不思議です。声で「地図」を描くというか)。今回の舞台は南米が舞台だったため、南米の地名や河の名前がひたすら連呼されるシーンがあり、最近南米に興味しんしんの私としてはそれだけで嬉しくなってしまう(ただ今回は映像で実際に地図を映し出すという効果があったのですが、それが逆に地図的な想像力を減退させてしまったような気も)。舞台そのものの感想はもし機会があれば後に詳しく書くとして、20世紀前半の南米の歴史をトータルに描こうとするその姿勢にはとにかく感激しました。まさに地図的な想像力と歴史的な想像力の結合。興味しんしんと言いつつ、南米の歴史についてはあまりに無知な私ではありますが、こういう想像力の広がりの中でもう少し読書を深めていかねばと思うことしきりなのでした(一応、そのわずかな知識の中で一冊だけ、上野清士『南のポリティカ』という本をオススメしておきます)。尚、公演自体は来年の2月に京都であります。演劇に親しんでいない人でも十分楽しめる舞台だと思うので観てみて下さい。維新派「カンカラ」南のポリティカ~誇りと抵抗
2007年11月16日
コメント(0)
-

本のマッピング
このブログのタイトルの由来というか、ヒントを得ているのは、池澤夏樹の書評本『海図と航海日誌』です。この中で池澤さんが、「地理的」な読書と「歴史的」な読書という話をしていて、前から、読書というのは、自分なりの世界地図と歴史年表を作るようなものでもあると考えていたので、そのことがとても腑に落ちたのでした。同時に、自分の読み方はどちらかというと「歴史的」だなあ、と思い、それからは「地理的」な読書も意識するようになったのでした。要するに、それがいつ書かれたか、いつの時代を扱ったものか、だけではなく、それがどこで書かれたもので、どこについての本なのかということを常に頭において、地図帳は必携、そして出来るだけ沢山の場所についての本を読むと、まあ、そのくらいなのですが。 一応、「地理」に対応する「地図」だけではなく、「歴史」に対応する言葉も織り交ぜたかったのですが、「年表」だと何か本当に社会科みたいだし、「歴史地理学」とかするとカッコいいのかもしれないけど、それほどのものではないし、ということで「読書地図」に収まりました。なので今のところ圧倒的にイギリスが多いのですが、本当はもっと色々な地域の本を読み、そして書きたいのです。どうしても気がつくとイギリスの本を読んでいることが多いのですが・・・。 尚、植田正治の写真がとても素敵なこの『海図と航海日誌』、池澤夏樹の書評本の中では一番好きなものです。リアルタイムの書評というよりは、これまで彼が読んできた本を振り返る自分史的なもので、彼自身書いているようにひどく「個人的」です。でもそれが彼の一時期の文章の特徴であった硬質なところを少し和らげていて、僕にはちょうど良かった。スパイ小説や冒険小説を読む楽しみを教えてくれたのもこの本です。まあ、もしかすると、読書を通じた自己形成という類いの本を僕が好きなだけかもしれません。同じような本としてとりあえず思いつくのが徐京植の『子どもの涙』と須賀敦子の『遠い朝の本たち』。自分の貧しい読書歴を振り返って切なくなるという副作用はありますが、本との対話という、ひどくシンプルで個人的な行為が、どれだけの豊かさと広がりを持ちうるのかということを、確認させてくれるありがたい本たちです。子どもの涙遠い朝の本たち
2007年11月13日
コメント(0)
-

古典ミステリへのオマージュ
大鴉の啼く冬処刑の方程式以前、最近のミステリは読者による「謎解き」を重要視しないと書きました。それを否定するつもりはないのですが、もちろん例外もあります。ただしその「例外」も、古典ミステリの基準からすれば、おそらく随分と「例外的」なのですが。今年評判になったらしい(そしておそらくは年末のベストにも必ずや入ってくるであろう)『大鴉の啼く冬』は、スコットランドのシェトランド諸島の1つの島が舞台になっています。イギリス本島からはもとより、近くの島同士ですら相当に行き来の不便な島における殺人は、実のところある種の密室殺人です。もちろん密室殺人にお馴染みのトリックなどは問題にならないのですが、例えばある屋敷の中の一室の殺人がそうであるように、容疑者は必然的に絞り込まれるわけです。事件当時にその島にいた人は限定されていて、他の容疑者がふらっと出てくる可能性はほぼ皆無ですから。読みながら、ふと、しばらく前に読んだヴァル・マグダーミドの『処刑の方程式』を思い出しました。これは島ではないですが、イギリスの中のある隔絶されたコミュニティを舞台にした作品。そこでは他所者が入ってくるとすぐさま村中に知れ渡るという、ひどく閉じたコミュニティで、いわば陸の孤島。そしてそこに住む人間は、上記の島に住む人間よりも遥かに少ないのです。もちろん陸の孤島とはいえ、他の場所から犯人がやってくる可能性はわずかながらありますが、読者はどうしたって、そこの住人の誰が犯人なのだろうかと考える訳です。ネタばらしはしませんが、どちらのミステリも、後半以降に突然新たな容疑者が出現するようなことはありません。その意味ではひどく「古典的」であり、実のところ、プロット上のトリック(つまり誰が犯人かという設定)も、非常に「古典的」です。もちろんそれを大胆な形でアレンジしていますし、またそのアレンジの仕方が非常に「現代的」であるところに、2つのミステリの醍醐味があるのですが、こういうささやかな「古典」への「オマージュ」のようなものを読むのもなかなかいいものです。
2007年11月12日
コメント(0)
-

二項対立と文学
コーデックスロックンロールミシン随分前のことになるけれど、「ゲンダイブンガク」を読もう!!と、鈴木清剛の『ロックンロールミシン』を読みました。これまた三島賞受賞作。けれども全然面白くなかったので、何が面白くないのだろうと考え込んでしまったのでした。読みやすいし、鼻につく感じもあまりないのだけど。その後すぐ読んだ、レヴ・グロスマン『コーデックス』のあとがきを読んでいたら、つまらなさの原因が少しだけわかったような気がしました。ちなみに『コーデックス』というのは、『ダヴィンチ・コード』以来(ないしは『薔薇の名前』以来)流行っている、知的エンタテイメントに属するような作品。イギリスの企業に移るアメリカ人のエリートサラリーマンが、イギリスの貴族が所有する稀覯本をめぐるミステリーに巻き込まれるというもので、本をめぐる現代の謎解きという設定だけなら、ゴダードの『眩惑されて』やバイアットの『抱擁』にも似ています。全然期待はずれでしたが。ただ訳者あとがきの中で、「アメリカ」と「イギリス」の対比、証券会社のビジネスマンと古い貴族の対比、コンピューター・ゲームと「本」というメディアの対比がこの本のポイントだ云々と書いていて、ああ、それがどちらの本もつまらなかった理由なのだと。『ロックンロールミシン』もまた、「二項対立」のお話です。軸になるのは、自分の仕事に疑問を感じつつ地味に働くサラリーマンと、自分の好きな服をつくることに命をかけるデザイナー一歩前、くらいの若者(2人は確か同い年)の対比。何が問題かというと、まずその対比があまりに単純すぎること。若者のある層に属する人なら誰もが一度は考える悩みですよね。ちょっとだけ流行ったらしいマンガの『FINE』もまさにそういう対比(これもつまんかったなー)。好きなことだけで生きていくか、多少のつまらなさや縛りを我慢して生活の安定を得るか。そこにまつわる色々な複雑なことがすっぱり捨象されてしまっている。さらにはその単純さは同時に視野の狭さでもあるということ。あえて「若者のある層」と書きましたが、そもそもそんな選択肢自体許されない人もいれば、悩むことなくバリバリ働いている人もいる。そういう広がりの中に、物語を置くのならいい。けれども、その二項対立だけしか書いていないために、世界がすっぽりその単純な二項対立で覆われてしまうのです。なお付け加えると、三島賞でこの作品が選ばれた理由の1つには「働くこと」が(日本の現代文学には珍しく)描かれていること、があったのですが、それを言うなら、例えば、伊井直之とか青野聡とか笹山久三とかいるだろうよ(そして鈴木清剛の後には、秋山鉄とか宮崎誉子とか、鈴木とは比べ物にならないような素晴らしい作品があるのです)。おまけに主人公の仕事は全然描かれていないし。『コーデックス』も同じです。これは二項対立をうるさいほどに強調するために、そこに収まらないものがきれいさっぱり取り除かれてしまっている。だから物語がものすごく平坦でぺったりしたものになっています。というか、最初に二項対立があってそこから無理矢理話を作っているような・・・。コンピューターゲームが大きな役割を果たすのですが、殆ど必然性を感じないのです。仕掛けとしても陳腐だし。一応、最後にフォローじみたことを書いておくと、『ロックンロールミシン』は、後味の良い青春小説を読みたい、という人にはオススメです。読んで嫌な思いをすることはないと思う。でも、『コーデックス』は誰にもオススメできないなあ。
2007年11月10日
コメント(0)
-

またラヴゼイ
殺人作家同盟ダイヤモンド警視シリーズ最新作!!かと思って読んだのですが実は違いました。三分の一くらい読んでからあとがきをちょっと除いてようやく気付くという情けない始末。おまけに、ダイヤモンド警視(邦訳)最新作である『漂う殺人鬼』で新たに登場した女性警部が物語の後半から出て来て事件を解決するといういわばダイヤモンド警視シリーズの番外編みたいな作品で、これは『漂う殺人鬼』を先に読んだ方が良かったなあ、と思ったものの、そこで読むのを止めるのも嫌で結局最後まで読み切りました。最初の方、ちょっと人物がごちゃごちゃしていて読みにくいのですが、それさえクリアすれば、後は見事なプロットと人間関係の描写の上手さに引き込まれるでありましょう。正直、ラヴゼイについてはこれだけでいいのですが、それだけでは何なのでもう1つ、2つ。物語の後半がかなり過ぎてから、新たな容疑者が出現します。ここで例の女性警部がこんなことをつぶやきます。「わたし、暇を見つけてはアガサ・クリスティーのテープを聴いてるでしょ。デイム・アガサはね、物語がこんなに進行したあとで犯人を登場させるようなことは、けっしてしない人なのよ。だから、わたし、カリビエット[注:その新たな容疑者]が犯人でないことを願っているの」。こんなことを実際の警察官が言うかどうかはともかく、こういうお遊びが隠れてるのもラヴゼイの魅力なのでしょう。近年のイギリス・ミステリを読んでいる方はご存知の通り、最近ではそういう古典的ミステリの「お約束」は滅多に守られることはありません。真犯人はしばしばかなり後になって出てくるし、もしそうでない場合も、決定的な証拠となるような事実が最後まで明かされないことも当たり前。つまり読者が犯人を「当てる」ことはかなり難しいのです。もちろんそれが悪いわけでは全然なくて、ミステリの楽しみ方が代わったということです。ただそれを分かりつつも、こうしたことを書いてしまうラヴゼイはお茶目だなあ、と思うのでした。実際に犯人がその警部の願望通りに言ったかどうかはさすがに書きませんが、余計なことと思いつつ付け加えると、優れたミステリがそうであるように、読者を惑わすのが上手な作品であることは確かだと思います。つまり、真犯人に行き着く伏線も用意しつつ、そこから目をそらさせるような伏線もたっぷり張ってあるということです。警部の独り言も、ちょっとした読者の攪乱ですね。最後に書いておくと、この題名と表紙何とかならないかなあ。何も知らない人が見たら、どんなにおどろおどろしい作品かと思ってしまいますよ。おまけに「サークル」という原題の含意が全然生かされてないし。本当にこんなにどぎつくしないと売れないのでしょうか。むしろこの本に見合った読者を逃しているような気がするんですけどね。
2007年10月23日
コメント(0)
-

ラヴゼイの『最期の声』
ピーター・ラヴゼイのダイヤモンド警視シリーズ第7作にあたる『最期の声』を読了。多分、先日書いたエイミスの『リヴァーサイドの殺人』があまりにつまらなかったため、その反動できちんとしたミステリが読みたくなってしまったのだと思われます。 ラヴゼイはダイヤモンド警視シリーズしか読んでいないのだけど、とにかく話を作るのが上手い人だなあ、と読むたびに関心します。今回も、裁判の場面から始まる的確な導入、そして最初の殺人の後のダイヤモンドの苦悩で前半を読ませ、後半はアクションも交えた急テンポの展開で読者を引っ張る。最終部はちょっと強引な話の展開と思わなくもないですが、最終部をもっと丁寧に書いてしまうと多分読者は飽きてしまうのでしょうね。そういった気配りも見事です。 最新作(今年出たばかり)の『殺人作家同盟』も読むのがとても楽しみですが、唯一心配なのは、ハーグリーヴズに続きステフまでいなくなってしまった事で、ダイヤモンドが軽妙で毒のきいたウィットを発揮する場面が少なくなってしまうのではないかということ。会話の巧みさこそイギリス・ミステリの本骨頂だと思っているので・・・。まあハーグリーヴスの再度のゲスト出演と、新たな登場人物の出現などを期待しましょう。 おそらくそんな人余りいないと思うのですが、イギリスの刑事小説(ウェクスフォード警部とかモース警部とか・・・)が好きな人で、万が一このダイヤモンド警視シリーズを読んでいないという人がいましたら、もうそんなにもったいないことはないのでぜひぜひ読んで下さい。
2007年10月09日
コメント(0)
-

ニッポンの現代文学
いわゆる「現代文学」とカテゴライズされる日本の小説を読むようになったのは確か高校生のときでした。一番最初に読んだのが何だか忘れてしまったけど、かなり始めの頃に高橋源一郎の『さようならギャングたち』を読んで、内容というか作者の意図は多分殆どわかっていなかったのだけど、言葉の選び方、構成、全てがあまりにしっくりして、小説の言葉言葉1つが身体に滲み渡るような気がしたものです。それ以来高橋源一郎は『ゴーストバスターズ』までほぼ全て(競馬エッセイ除く)読みました。あと高校生から大学生にかけて読んでいたのは平中悠一を数冊、小林恭二と島田雅彦と松村栄子と辻仁成(辻仁成は中学生のとき?)のデビュー作、長野まゆみを何冊か、それからまあお約束ですが村上春樹と吉本ばなな。村上春樹は大学時代の2度マイブームがやってきて『ねじまき鳥』までは多分全部(それも2回)読んだように思います。吉本ばななは『アムリタ』までは全部。 その後、いろいろあって同時代の日本文学に対する興味が急速に失せてしまい、本当に時々文芸雑誌を手にしてみたりするくらいで殆ど読んでいなかったのですが、最近ふとしたことで笙野頼子を読み始め、それがなかなかに面白かったので、もう少しニッポンの現代文学を漁ってみようかなあと考えているところです。高橋源一郎の『ニッポンの小説:百年の孤独』も久しぶりに読んだら案外悪くなかったし。そもそも考えてみれば、同時代の同じ国に生きている作家の中で、共感できる人が全くいないというのは随分淋しいことだと思うのです。ニッポンの小説 ひとまず自分と世代は全然違いますが、以前数冊読んだ古井由吉を最初の頃から読んでいこうと、まず『行隠れ』を読み、現在は『櫛の火』を読み途中。全然同時代じゃないじゃん!!なのですが、せっかく現代文学を読むのなら、まず近代日本文学なるものをある程度読んで、その文脈の中で考えたいとか思ってしまうのです。その上で『野川』なんかを読みたいなあと。そうやっている内に結局どこにも行き着けないというのはよくある話ですが、『二百回忌』『何もしていない』を読んだのに続いての笙野頼子『居場所もなかった』も手元にあるし、小野正嗣『水に埋もれる墓』鈴木正剛『ロックンロールミシン』も図書館から借りて来たので多分大丈夫かと。 全然関係ありませんが、小野さんと鈴木さんの名前は、三島由紀夫賞で見つけてきました。第一回が高橋源一郎だったんですよね。あと『二百回忌』もとったっけ。三島賞から「現代文学」を捜してくるんだったら中原昌也と舞城王太郎じゃないの?とも思うのですが、暴力的なものは苦手なのです。いつか読むと思いますが、しばらくは遠ざけつつ。その前にまず町田康を読みたいなあ。笙野頼子三冠小説集
2007年10月08日
コメント(0)
-

双生児
本好きの人にとっては何をいまさら、だと思いますが思いますが、数日前にクリストファー・プリースト『双生児』を読了しました。いやあ、すごかった。これほど充実した読後感を持った長編小説は久しぶりです。 物語を前に運んで行くための小道具、部分的な謎明かしなどを実に実に丁寧に配列して、最後まできちんと読者を連れていく。読みながら、これは自分が気付いている以上に綿密な構成で書かれているんだろうなあと思って、大森望さんのあとがきを読んでみると、その綿密な構成の一部に気がつかされてまた呆然。本当は数回読むべき本なのでしょうね。 もちろん文章も会話もとてもきちんとしているし翻訳も良い。そして主たる舞台が第二次世界大戦時のイギリスというのも良かった。第二次世界大戦を題材にした「改変歴史モノ」というのは「定番」らしいですが、僕は読むのが始めてで、なおかつイギリスに限って言えば、第二次世界大戦の経験を描いた小説というのはそんなに多くないと思います。同じプリーストの『魔術師』は、いかにも19世紀後半のイギリス、という雰囲気が強すぎて十分に楽しめなかった記憶があるのですが(もちろん面白かったけど)、『双生児』はそういう点でも新鮮なところがたくさんありました。あとちょうど最近読んだサラ・ウォーターズの『夜愁』と比べてみたり。そういえば、『犬は勘定にいれません』のコニー・ウィリスの新作も第二次世界大戦時のイギリスだそうで、早く翻訳でないかな。 これがSFなのかファンタジーなのか歴史小説なのかというジャンル分けなど本当にどうでもいいとは思うのですが、こういう優れたSF(ないしはSFとされている小説)をもっと読みたいなあと思って、今日はついついスティーヴ・エリクソンの『彷徨う日々』を図書館から借りてきてしまいました。さてさて。
2007年10月05日
コメント(0)
-
エイミスとフレミング
たまたまイギリス人の書いたミステリとスリラーを一冊づつ立て続けに読みました。キングズリイ・エイミス『リヴァーサイドの殺人』とイアン・フレミング『カジノ・ロワイヤル』。 『リヴァーサイド~』を読んだのは、エイミスが書くミステリってどんなんだろ、と思ったためで、存在を知ったのはピーター・クラーク『イギリス現代史1900-2000』の記述より。 『カジノ~』は言わずとしれた007の第一作(今年も映画化されましたね)。イギリスにおける大衆小説の代名詞みたいな作品で、誰か構造主義者がテキスト分析までやっている。なのでいつか読まないとなあ、と思っていてようやく第一作が読めた。 この2つを比べても仕方ないのかもしれないけど、立て続けに読んでしまったためひとまず比べてみると、『リヴァーサイド~』の方が圧倒的につまらない。翻訳も悪いけど、プロットもいい加減だし、設定にも相当無理がある。ミステリとしては二流。昔のミステリだから荒いのかなあと考えてみたけど、この作品が書かれた頃(1973年)には、既にルース・レンデルなんかが今読んでも十分面白いミステリを書いていた訳で。 では「小説」としてどうかというと、無茶苦茶ご都合主義的な「少年の性の目覚め」などが書かれていてこれまたお粗末。 訳者小倉さんによると、エイミスにとって小説家の目的とは「普遍的な人間性を描くことにある」のであって、それはどんなジャンルを書こうが一緒、なのだそうだ。きっとつまらない原因はここにある。 つまりエイミスは人間のことだけ書けば「人間性」が描けると思っているんだろう。でも本当は、人間の周りにある細かいことを丁寧に書かないと「人間性」なんて浮かび上がってこないのだ。もちろんミステリを書くならミステリとして一流のものを書いた上でその「人間性」とやらを書いてくれとまず思うのだけど。 一方フレミングは「人間性」なんてもちろん考えていない。ボンド以下、登場人物の単純さといったらないのだけど、それでも彼は最低限の決まり事を守ってスリラーを作りその中で書くべきことは書いている、と思う。だから(まだ)面白い。そして皮肉なことにエイミスよりも人間味のある人物描写が出来てしまっているのでした。 さてひとまず次は『ムーンレイカー』かな。
2007年10月01日
コメント(0)
-

河島英昭
数日前から河島英昭『めぐりくる夏の日に』を読んでいる。河島さんのことは前から知っていたけれども、きちんと読んだのは7~8月にかけてゆっくりと読んだ『イタリア・ユダヤ人の風景』が始めて。それがとても素晴らしかったので、ちょうど新刊で出たばかりだったこの本も手に取った。 まだ半分しか読んでいないのだけど、東京の大森を散策する彼の視点とイタリアの都市のユダヤ人街を散策する彼の視点とが色々なところで重なるのがとても腑に落ちる。もちろん「流刑」という言葉への親近感なども含めて。 それにしても、ちょっと内容とはずれるのだけど、河島さんは1933年生まれ。70代になって、ようやくこうしたエッセイ集を出すというのはかっこいいというか正しいよなあ、と思う。優れた研究者がどういう背景を持ってその専門に取り組んでいるのかというのはもちろんいつも興味あることだとは思うけれど、それを軽々しく文章にしてしまってはいけないのだとも同時に思う。そんなことしている暇があったらもっと研究を進めなさい、と(もろろん誰かさんのように研究者をとっくにやめて唯のテレビタレント兼雑文書きになってしまったような人は論外)
2007年08月28日
コメント(0)
全43件 (43件中 1-43件目)
1
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 218冊目「氷の宰相閣下をうっかり助…
- (2025-11-29 22:00:06)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月15日分)
- (2025-11-29 01:10:07)
-