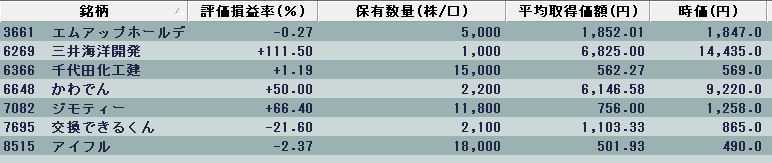2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年12月の記事
全61件 (61件中 1-50件目)
-
良いお年を。2006年の感謝。
あ、そんなDJ OZMAの話を書くつもりじゃなかった…。本年も、訪問いただいた皆様、コメントを下さった皆様、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。ただいま、自由にPCが使いにくい環境下におり、ゆっくりコメントのお返事などできませんが、新年に改めまして、お返事したいと存じます。 さて、いよいよ来年は、出版をはじめ、楽しみ&不安なことも山積していますが、このブログでの皆様とのご縁と、応援をエネルギーに頑張って行きたいと思っています。どうぞ、宜しくお願いいたします。皆様も、素敵な新年をお迎え下さい。そして、来る年が素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 2006年、ありがとうございました!!(了)
2006/12/31
コメント(4)
-

オズマ、紅白でやらかしました。
えー、実況中継です。紅白歌合戦において、DJ OZMAが、先ほどやらかしてしまいました。うーん、チャレンジャーです。NHKも変わったなぁ。しみじみ。(了) DJ OZMA/アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士【CD+DVD】
2006/12/31
コメント(0)
-

ふぞろいのリンゴたち、そろわず。~『ロシアン・ドールズ』、観ました~
この時間に記事アップ。所謂、裏番組です(笑)。購入から随分と経ちましたが、ようやくゆっくりとDVDを観る時間が。そう、『ロシアン・ドールズ』。 前作『スパニッシュ・アパートメント』から5年。お堅い仕事を蹴って、作家志望の物書きになったグザヴィエ(ロマン・デュリス)。いやぁ、このグザヴィエの仕事ぶりが、なんともリアルで、私自身とかぶるんです。で、その5年前のスペインでの留学経験を基にした作品を書き上げるも、出版の宛てもなく、原稿を大事に抱えて、日々納得のいかない仕事にも精を出す。 前作が、まさに日本で言う「ふぞろいの林檎たち」から「愛という名のもとに」「白線流し」的、大人一歩手前の青春群像ドラマで、パリからバルセロナに訪れた青年が、雑多な人種的ルーツを持つ同世代の若者が混在するアパートで共同生活をする中で、自分探しをする物語だったワケですが、その続編たる今作は、完全な大人が主人公の恋愛ドラマ。恋愛映画、ではなく。 実際、前作にあったような、青臭くも甘酸っぱい、なんともいえない不安だけど能天気な若さ独特の活気はなく、どちらかと言えば、日本でならテレビ対応のドラマ的作り。映画にもなりません。しかも、完全にグザヴィエと、まさかの相手との意外な恋の行方を中心にストーリーが展開し、そろうはずの“林檎たち=アパートの仲間たち”は、ほとんどがちょい出演のみ。 じゃぁ面白くないのか、というと面白いんです。続編というより、スピンオフした再度ストーリーみたいな味わい。加えて、内容はありきたりなのに、カットの切り方、音楽が格好良かったです。それから、グザヴィエと、必然性なく結ばれてしまう(ま、愛ってそんなもの…かな?)ウェンディの弟・ウィリアムが大化けしましたね。ま、何かやらかすと思っていましたが、相変わらずのバカっぷりに、笑いを禁じえません。 ウィリアムのみならず、人種的なネタをジョークに挟み込みつつも、ただのジョークにせず、時代性を限りなくリアルに反映した、“って感じ”ってなフィーリングで表現しながらも、それがある程度正確性を有していたのが『スパニッシュ・アパートメント』だったわけで、そのあたりのケレン味のなさが、今作にもうまく踏襲されていたのには好感が持てました。 しかし、オドレイ・トトゥ、損な役だなぁ。今回も。(了) ロシアン・ドールズ スパニッシュ・アパートメント2
2006/12/31
コメント(0)
-
“福袋”、だからありがたいのかな。
年末です。でも、街中は結構賑やか。お店もみんなオープンしているし。季節感、ないですよね。ありきたりな表現ですけれど。こんなコト言われるようになったのは、コンビニが一気に全国にひりがり出した時期から。15年前くらいからでしょうかね。 で、考える。毎年、なんで福袋が売れるのか。中に何が入ってるかも分らないのに、並ぶ、並ぶ。新春早々、並ぶ。価格以上のモノが入っているから?いろんなモノが入っているから?限定品が入っているから?まぁ、それもそうでしょうけれど、やっぱり別のところに魅力があるような気がします。 つまり福袋だから。なんかよく分らないけど、めでたい感じ。福の袋ですもん。いまや年中お祭りやイベントで予定ギッシリの日本にあって、年始だけシーンとしてるのは、もう受け付けないんでしょうね。やっぱり祭りが欲しい。で、“福袋争奪戦”祭り。 もう一つは、日本古来の美意識、世阿弥の心と申しますか、闇鍋の真髄と申しますか、中に何が入っているか分らない。ここに萌えるんでしょうね。「秘すればこそ、福」。 今年は、いっちょ福の詰まった袋でも、戯れに買ってみようかしら。(了)高級アイテムが新春特価で!【ブランド 福袋】新春おみくじ付き総額60万円以上
2006/12/30
コメント(3)
-
DSからWii、PS3まで。史上最安値って・・・。ホントか?でもスゴいなぁ。
DSからWii、PS3まで。史上最安値って・・・。ホントか?でもスゴいなぁ。どれも在庫一台限り、とかだけど、確かに安ないなぁ。先日DS Liteを購入した知人がいたので、試しに値段を見てみたら、まぁあるわ、あるわ。ピンからキリまで。個人的には、今は何が欲しいかなぁ・・・。特にないですね。ホント。奇麗な絨毯が欲しいかな。(了)史上最安値 ニンテンドー Wii (本体)史上最安値 プレイステーションポータブル(PSP) ブラック [PSP-1000]史上最安値 PlayStation3 HDD20G プレステ3史上最安 ニンテンドーDS lite アイスブルー*アイ・アイってお店が安いみたいです。 ↓
2006/12/29
コメント(0)
-

『皮革あ・ら・か・る・と』
見出し:日本で読める最高の皮革文化本の一つ。出口公著『皮革あ・ら・か・る・と』(解放出版社) 皮革文化は奥が深く、各国様々なようであり、以外と海を隔てて類似点があったりするきわめて興味深い文化である。もっとも、このような特徴を持つのも、人間にとって最初の衣類であり、防具であり、寝床であった、きわめてプリミティヴにして、普遍的なテーマであるからにほかならない。この普遍性は相当に強く、人類誕生から21世紀の御代まだ、未だに皮革文化そのものが持つモードや形式、基本的なエッセンスは大した変化を必要としていない。 皮革、と言わずレザーと書くと、これはもうどこか遠い国のきらびやかな世界の話になってしまいそうだが、実際日本には、世界に誇る特に二つの皮革文化が存在している。すなわち姫路の金唐革と、山梨の甲州印伝である。こうした、日本における皮革文化や産業の歴史など、普段なかなか知ることのできない世界について、読みやすく、過不足なく、まとめてある。また、皮革文化が抱えて来た様々なバックボーンにも意識を向けておきたい。(了)皮革あ・ら・か・る・と
2006/12/29
コメント(0)
-

『殉教カテリナ車輪』
見出し:試みは斬新なれど、宣伝の一人歩きに本質が霞む“図像学ミステリー”。飛鳥部勝則『殉教カテリナ車輪』(創元推理文庫) まず断っておくが、これは断じて図像学(狭義にも、広義にも)を取り入れたミステリー小説ではない。これは、図像学的フレーバーを取り入れ、図像学的と思い込ませることを意図したミステリーである。この点では、『ダ・ヴィンチ・コード』とて同じである。著者自身による油彩作品などを実際に作中に織り交ぜながら、妖しい雰囲気を演出する試みは斬新である。インタラクティブで、立体的なミステリーでもある。しかし、いささかストーリーが紋切り型であり、展開はあまりに幼稚で、私のような遊びでミステリーを読む者ならまだしも、ミステリーに一家言ある向きには、ちょっと甘口過ぎるかもしれない。もともと、私の守護聖人(今はローマ教会からは除外)がタイトルに入っていたため、私は思い入れを持って読めたのだが。(了)殉教カテリナ車輪
2006/12/29
コメント(0)
-

『「玉砕総指揮官」の絵手紙』
見出し:戦火の勇気。栗林 忠道 著、 吉田 津由子 編集『「玉砕総指揮官」の絵手紙』(小学館) 戦争体験はないが、戦争追体験のある私は、とかくこうした類いの資料から得られるリアリティに対しては、少々懐疑心を抱いていた。戦争は悲惨、と皆異口同音にいうが、一体全体、何が悲惨で、どこまでが感情論で、どこまでが憐憫なのか、まったくわからないのである。これこそが、時代の経過という“緩慢な悪魔の計画”なのであるが、ふと手にした本書は、確かに戦時下、それも往きて戻らぬ玉砕覚悟の精神状態の中で、父の安否を気遣う家族に宛てた言わば“日めくり遺書”でありながら、どこか達観したユーモアを感じる。家族を安心させるためのやせ我慢ともどこか違う、もうこの世の者でなくなってしまったかのような、ふうわりとした抒情を偲ばせさえするのだ。 戦争は悲惨だ。こんなステレオティピカルな言葉を、ここで挙げることは愚問だ。しかし、本書には、戦争体験をユーモラスに語ってくれた祖父の飄々とした面影が重なって、素直に対峙してしまう。家族愛は、戦火においても最大の勇気なら、今、この平和時にもさらなる勇気になるものと信じたい。(了)「玉砕総指揮官」の絵手紙
2006/12/29
コメント(0)
-

『「キムラ式」音の作り方』
見出し:あるマエストロの曲芸的飛躍的音作り。木村 哲人 著『「キムラ式」音の作り方』(筑摩書房) 古来より、音は有機的な存在であった。というのも、音は、自然と密着しており、発信する場合には、身体性との親和力が強固であった。ボディタッピングは、今で言う携帯電話のルーツであるし、奴隷制下のアメリカ南部で、打楽器が禁じられたことは、互いに太鼓で連絡を取り合い、謀反を起こされることを防ぐためであった。もっとも、打楽器を取り上げられたことで、ワークソングやボディタッピングが深化し、さらに教会でのゴスペルに発展し、トタンに糸を張ったブルースギター(もともと、アメリカのプロテスタントの教会には、オルガン以外の楽器を使う文化がないし、ましてや弦楽器の文化もアメリカ大陸にはほとんど存在しない)が誕生して、ブルースやR&Bが誕生するのである。話が逸れた。ともあれ、今や音は、デジタルで合成すれば、どんなものでも再現可能である。もちろん、擬似的なレベルにおいて、であるが。数値とサンプルの合成。編集。調節。これを、アナログなソースでやってきたのが、まさに著者である。音響の世界で、効果音の神様とも呼ばれる著者は、単にその技術の高さだけでなく、奇想天外な方法で求められる音を作るという、曲芸的飛躍的イマジネーションでもって評価されるべきである。かつては、素晴らしいマエストロがいたものだ。(了)〈キムラ式〉音の作り方
2006/12/29
コメント(0)
-
ご挨拶に感謝。
年の瀬、お忙しい時期にご挨拶コメントを寄せて下さった皆様、ありがとうございました。一つ一つにはお返事いたしませんが、この場を借りて、改めてお礼と感謝を。改めて読み直すと、一年間支えて下さった皆様の当ブログとの関係が見えて来て、本当に味わい深いコメントの数々でした。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 と言って、年内、まだまだ記事は書く予定ですが、いくつか、この場で補足を。1:プロフィール写真、変えました。これ、リンクスに参加されている方は仕掛けを楽しんで下さい。2:今年は忘年会はなかったのか?もしくは忘年会絡みの記事はなかったのか?というご意見も出そうですが、実は記事の中で、忘年会の話を書いたモノがあります。これも仕掛けですが。ヒントは、記事一本丸ごとが仕掛けになっています。ということで、忘年会、ありました。 さて来春は、まずはいよいよ出版に向かって邁進あるのみです。出版社が諸手を上げたのですから、著者自身は納得です。腹も決めました。あとは、納得してくれた出版社の方に反響で恩返しをし、かつ内容を評価(というより一言、出してよかった、と言ってもらうこと)していただき、かつ拙いとは言え、私のこれまでの仕事の一つの集大成的な意味で、読者の皆様に、理解/無理解していただけることを楽しみに待つばかりです。引き続き、どうぞ応援、よろしくお願いいたします。(了)
2006/12/29
コメント(1)
-
大掃除をすると、ヘンな落書きが出てくる。
まぁ、だいたい大掃除と言っても、大してすることなどないのですが、溜まったゴミや、書類の整理、雑誌や資料の整理が大半です。そんな中、毎年恒例の作業がありまして、カレンダーの付け替え。いや、どこのご家庭でもそうでしょうけれど、私の場合は、カレンダーにちょこっと落書きするのが趣味なんですよ。その落書きで、だいたいその時期何していたかが分かってしまう(笑)。今年も大量の落書きを、スクラップブックに貼り移し作業しました。大収穫です。その中の一枚をご紹介します。えぇ、多分、映画『V・フォー・ヴェンデッタ』を観た時期でしょう。V八先生にされちゃってますけど。(了)Vフォー・ヴェンデッタ 特別版
2006/12/29
コメント(4)
-

『類似ヴィトン』
見出し:すべてのブランドは偽物である。 すべてブランドなるものは、偽物といわないまでも、実体のないものである。だからして、偽物のブランド品を掴まされたからと言って、目くじらなど立てては野暮というモノだ。いや、冗談ではない。ブランドとは、バックストーリーや、メッセージ、コンセプト、歴史が刻まれているとはいえ、結局は蜃気楼のようなものなのだ。世にブランド力なる言葉が流行るほどに、日本人のブランド意識も少しは成熟したようでもあるが、果たしてこのような意識が一人歩きして成熟したところで、今度最後に掴むのは、泡でなく、空気である。 ともあれ、ブランド品に興味にある方は是非ともご照覧あられたい。その恐るべき、真贋虚実の境目の摩訶不思議なるに、目からクロコ、いやウロコが落ちること必定である。 そして最後に、「これからは、堂々とブランド品=偽物を買おう!!」と呵々大笑して買い物に出かけていただきたい。(了)類似ヴィトン
2006/12/28
コメント(2)
-

『夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録』
見出し:表紙を、5秒眺めて網膜に歴史を刻め。V.E.フランクル著、 霜山 徳爾訳 『夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録』(みすず書房) この本について、どれだけの事が書かれ、そして、どれだけのことが言い残されているのか。 第二次世界大戦下、ドイツ、ナチズム、強制収容所…死以外の何も訪れない場所で、ありうべくもない生を見出した奇跡の男の、戦慄のドキュメンタリー。そこに、人間の生の尊さや、実存的意味が溢れている。 そんな紋切り型のコピーや感想なら、いらない。中身を読む必要もない(嗚呼、幼き日に足を運んだ『ナチス展』の心の傷、“処分されるだけの身長”しかなかった私の弟!!)。ただ、刮目して表紙の写真を5秒眺めよ。そして、歴史を、人間の本性を、しかと網膜に焼き付けるがいい。(了)夜と霧
2006/12/28
コメント(0)
-

カムバック、エディ!!~サタデー・ナイト・ライブでの才気、何処へ~
大好き。だったんですよ、正確には。エディ・マーフィ。ギラギラしてた頃の。リチャード・プライヤーにも平気でディスできちゃうのはエディしかいないだろう?ってなほどの、あの生意気で、嫌みで、気障で、ワガママで、でも無茶苦茶面白いエディ。どこ行ってしまったんでしょう? 映画でファンになった方も多いかと思います。アクセル刑事、うーん、良かったねぇ(ビバリーヒルズ、って響きも今じゃちょっと恥ずかしいけれど)。『48時間』では、パート1では脇役扱いだったのに、パート2になったら主役になってた。あと・・・何があったっけ?『ゴールデン・チャイルド』?どうしちゃったの、エディ?『星の王子 ニューヨークへいく』…、まぁ、あったような。『バッド・ボーイズ』、いや出てないから!!『ホーンテッド・マンション』、だから出てないって!!え?出てた?あ、そっか。。。『ドクター・ドリトル』…あ、太るヤツだ!!違う、これはホーム・ドラマ。エディがホームドラマ?なんか、どれも違うよなぁ…。 個人的には、『ブーメラン』『ナッティ・プロフェッサー』は評価したいですけどね。でも、唯一、エディが出た最高の映画がありまして、お題を『ザ・ロウ』と言います。ナマってコト。これ、結局日本未公開でビデオのみ、なんですよね。惜しいなぁ。ま、内容が過激、って理由なんですけど、いま観ると別に過激でもないし、何より、ステージでのライヴパフォーマンスを録ったドキュメンタリー映画なので、もう勢いがスゴい。本当に格好いいです。私、これ観てファンになったクチなので、他のが甘口に思えて仕方がない。エディ・マーフィの、モノマネとかギャグばっかり入ったCD(輸入版です、もちろん)まで持ってるくらいですから。 今は、このサタデー・ナイト・ライヴ時代の映像に、銀ラメのスーツも着こなしちゃう、エディの想い出を探すのみです。(了)ポニーキャニオン エディ・マーフィ/サタデー・ナイト・ライブ ベスト・オブ・エディ・マーフィ
2006/12/28
コメント(5)
-

『グーグル・アマゾン化する社会』
見出し:周縁の無化と、一極集中はどう和解するのか。森 健 著『グーグル・アマゾン化する社会』(光文社) 著者自らが述べるように、いわゆる“グーグル本”ではない。ただ、リリースのタイミングから誤解もあろう。丁寧な情報収集と理路整然とした筋立てに定評のある著者が、この本で本当に伝えたかったことは何なのか。“アマゾン”や“グーグル”の話ではない(もっとも、その手のシステムの話に疎い私にはありがたい内容ではあったが)。アーキテクチュアやシステマチックなインフラストラクチュアによって、我田引水的に、一つの田畑に、恣意的に最高の水が集まること。つまり、現代的な一極集中の様相を地図化して見せているのである。 音楽のシングルヒットを例にすれば一極集中の話は分かりやすい。つまり、松田聖子伝説は超越されない、ということである。松田聖子の時代は、チャートアクションのソースもメディアも基本はシングルパッケージのみ、流通経路もそれほど複雑ではなく、また付帯する副次的サービスの数も多くはなかった。露出の最大のメディアはテレビの歌番組。そのような、一極集中せざるを得なかった70年代後期から90年代初頭までの日本の音楽産業は、勝つ者がいつも勝つ、まさに一極集中の牙城であった。だからこそ、アルバムはほぼすべてがベスト盤、アイドルが歌手よりセールスを獲得し、ワンヒットワンダーも多々生んで来た。一極集中して、周縁は浅かったのである。 今音楽業界では、まさに逆転現象が起こっている。多極拡散である。一人勝ちのルールはある程度残しつつ、しかし流通経路、メディア、再生媒体、レーベル、クオリティ、すべてにおいて多岐/多様化し、ある意味ですべてのアーティストがワンヒットワンダーになってしまっている。お分かりであろう。今、アーティストでシングル5万枚売れるということは、一極集中時代の松田聖子のミリオンにも匹敵すると言って過言でない。 本書で一極集中について考えれば、周縁が浅く、薄く、いつかは無化されていくことに気づくだろう。音楽を例に採った本評が適切かどうかは措くとして、しかし逆に、論理的法則によって音楽産業が一極集中から逆行したようなことが、あるいは他の生活世界に起こらないとも、言えなくはないだろうか。(了)グーグル・アマゾン化する社会
2006/12/28
コメント(0)
-

『ザ・マン盆栽』
見出し:箱庭は人を癒すのか。パラダイス山元著『ザ・マン盆栽』(文芸春秋) 箱庭療法というもともとユング派の心理分析の技法で、縦57cm×横72cm×高さ7cmの、砂の入った木箱の中に、いわゆるフィギュアのようなものを並べたり配置したりして一つの世界を作り、そのクライアントの心理状態を診たり、自由作業によって非言語的なメッセージを受信しようとする試みである。 日本には古来から盆栽という素晴らしいアートワークがあり、しかし同時に、それは一つの“老後の楽しみ”というせまい嗜好に直結されて来た。 マンボと盆栽にどんな関係があるのか知れない。また、それを結びつけるに、こじつけ以上の必然的な意味があるか知れない。しかし、この一冊に収められた箱庭=小宇宙の数々は、どこかほのぼとするのみならず、まさに自由という名の無意識で、思わず心象風景を再現してしまいそうな危うい罠を感じる。実に、危険で洒脱な試みである。(了)ザ・マン盆栽
2006/12/28
コメント(1)
-
嘘評:そこは、夢と熱気の集う“巣箱”。
菊池良寛著『夢の巣箱』(だうと舎) あるいは夢に敗れ、あるいは夢を追い続け、あるいは永遠に夢物語ばかり語り続け、あるいは、夢と夢を闘わせる。高級クラブが軒を連ねる東京の一角で、一国一城の夜の主となった“マスター”の視点から、訪れるお客の“夢”にまつわるエピソードが12篇のショートストーリーで綴られる。秀逸なのは、「第12夜 放念会」。たいてい常連ばかりになる忘年会で、小さなお店に一年分の熱気を抱えたお客が繰り広げる珍騒動の数々。夢はまだ終わらないのだ。あたかも、ロンドンのパブの様相を呈する猥雑さと、破天荒な老若男女の客人が、すべてを忘れて白む都会へと帰途につく姿を見送る“マスター”の男気溢れるクールでホットな視線にもほっこりさせられる。年末にふさわしい一冊と言える。(了)
2006/12/28
コメント(0)
-
処女作、共著のお相手はスピリチュアルの大家。
近藤裕(こんどうひろし) 教育学博士(臨床心理)・マリッジカウンセラー・サイコセラピスト1928年(昭和3年)千葉県に生まれる。日本で神学・心理学を学び渡米。カリフォルニア州バークレー市の病院においてサイコセラピスト(心理相談室長)、精神衛生コンサルタントとして12年間の 臨床・教育に従事。日本人で最初の米国マリッジ・ファミリー・セラピイ協会の臨床会員として多くの結婚・家族の病理の心理療法を行う。また、がん患者とその家族に対する心理療法にも携わり、日本にサイモントン療法(イメージ療法)を紹介。現在、東京を拠点に「癒し」の専門家としてカウンセリング、各種セミナー、企業向け研修、執筆活動などを行う。著書は80冊以上にのぼる。〔学歴〕・早稲田大学専門部 政治経済学科中退(1945)・西南学院大学文学部卒業(1957)・九州大学教育学部教育心理学研究室(1960-1961)・米国ニューオリンズバプテスト神学大学院、教育学部臨床心理学科、ドクターコース卒業,教育学博士(1971)〔結婚・家族病理〕・結婚・家族問題も診断・カウンセリング・コンサルテーション〔精神衛生〕・企業内メンタルヘルス体制の企画・推進・ストレス・マネジメント向上・「やる気」の向上・職場におけるリーダーシップ、人間関係トレーニング・CMSコース(カウンセリング マインド スキル)〔海外人事〕・海外要員・家族のメンタルヘルス予防と対策プログラム・異文化コミュニケーション、異文化適応教育〔医療心理〕・全人的健康教育・医療における人間学・病人学教育・医療における人間関係教育・ガン患者とその家族の心理療法〔そのほか〕・西南学院大学文学部非常勤講師(1962-1967)・米国カリフォリニア州バークレー市のヘリック・メモリアル病院心理相談室長(1971―1982)・昭和大学医学部・藤が丘病院非常勤講師(1991-1995) ・東京女子大学非常勤講師(1984-1996)・帯津三敬病院 非常勤サイコセラピスト(1993―現在)・(株)コンサルティング アソシエイツ、顧問コンサルタント・(株)日本能率協会マネジメントセンター、顧問コンサルタント・(株)セコム、顧問コンサルタント・(株)JTBモーチベーションズ、顧問コンサルタント ・(株)パーソナルライフズエデュケート、嘱託コンサルタント ほか企業研修多数(以上、公式HPより抜粋)
2006/12/27
コメント(0)
-
処女作は共著。
さて、不定期な出版のPRです。来春地湧社から出版される私の処女作は、共著です。共著の相手は大御所・近藤裕氏。もともと、自身の幅を広げるためと、その前に学会で訪れた沖縄文化の吸収のために、同氏が沖縄にて沖縄文化を中心とした心身の健康を考えるNPO法人の立ち上げを行うに当たって、そのお手伝いをさせていただいたのがご縁。そのとき、心の問題について自身が何も知らないがゆえに、大したお手伝いができなかった悔しさがきっかけとなって、後にカウンセラーの資格取得を目指して勉強をすることになるのです。 さて、処女作が大御所との共著、というと、大抵みな「やめておけ」といいます。一つは、結果いい本になっても、「権威主義だ、権威に寄った」と過小評価するでしょうし、いい本でなければ、「権威の尻馬に乗って本を出した」という評価を受けるからです。 しかし、私はそういうことは意に介しません。文章を書き始め10年。頑固に、仕事を選びながら、苦しみながら、真摯に仕事に取り組んできました。ましてや、文章を書くことこそが悦びなれば、本を出すことそのものにすら興味がなかったほど。 ですが、こうなった以上ガチンコ勝負です。相手が大物であれ、ルーキーであれ、文章に関して勝負は常にガチンコです。まぁ、結局権威に寄るだけなら、その後苦しむのは自分自身ですしね。ガチンコ勝負でも負けないという気迫と覚悟あればこそ、あえて共著にこだわったのはほかならぬこの私。師匠も生ぬるいお友達感覚ならそれは望まないでしょうし、仮にキャリアの浅い私と共著するほうが、彼にしてみれば面倒なわけですから「一緒にやろう」とはいわないでしょう。 処女作、このあたりの新旧世代の仁義はあるけど容赦ないガチンコ勝負の火花にも注目していただきたいものです。(了)
2006/12/27
コメント(4)
-

武士の一分、コント三分。
映画『武士の一分』、意外にもかなり評判になっていますね。それもコアな映画ファンからも。私ね、心配なんですよ。主演が。木村氏、巧すぎるの。器用で努力家なんでしょうね。でも、それが時として仇となることもあるのかな、なんて思う次第。というのも、SMAP×SMAPなんかで、よくコントやるでしょう?ああしたコントの演技も、一番こなれてるんですよ、木村氏(逆にアドリブが痛い)。だから逆に、重厚な映画に出演した時、あのコントのイメージがかぶって来てしまって、虚心坦懐で鑑賞できないんじゃないかな、って思う。一方、ドラマだと、素の木村氏と役者の木村氏の虚々実々を見せることで、比較的すんなり違和感なく観れたりするんでしょうけど。現代劇と時代劇。違いますよ~。カツラ乗せて、コントが思い浮かんだら、もうアウトですから。 ほかのメンバーを見て行くと、あくまで個人的な感想ですが、中居氏は、まずもってまさに器用な人。芸能人、って感じです。ドラマも評判よかったけど、役者として巧いかどうか、は別かな。大物アイドルが、クサいほどに演じても嫌みがない、という点では評価高いです。対照的なのが草?氏と香取氏。草?氏は、まず地声が良いです。前から、ナレーター向きだなぁ、と思っていましたが、最近はご活躍で。で、演技も、なんか雰囲気がいいんですよ。何演じても。ある意味、古いスタイルの日本人俳優の佇まいがある。ただし、コントは下手ですね。素でしか笑いが取れない。一方香取氏は、何やってもコントになってしまう。きっと頭の回転が速い人なんでしょうけれど、それがかえって、即興性に依るところの多いコントでしか発揮できないのは、なかなか悩ましいところではないでしょうか。 評価が難しいのが、稲垣氏。演技派、アート担当、という感じはありますが、正直演技は下手です。ドラマではね。過剰なのかなぁ。中居氏で許されることが、稲垣氏では許されない感覚。ただ、この方舞台での評価は高いですから、それを観てみないと何とも言えませんね。 と、ファンを前にして、勝手な意見を述べましたが、私はSMAPは日本の芸能文化の宝だと思って来ましたし、ある意味で、もうあとはその縮小版かフォロワーしか出てこないでしょう。そういう意味では、完成してると絶賛して来ました。ここでは、あえて、『武士の一分』をお題に、彼らの演技について、ちょっと分析してみた次第。(了)一分 TAKUYA KIMURA SPECIAL BOX(30000セット完全限定生産)(DVD) ◆20%OFF!
2006/12/25
コメント(2)
-

『カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』
見出し:嗚呼、純真は残酷な夢の悪夢を見る。マックス・エルンスト著、巌谷國士訳『カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』(河出書房新社) 『百頭女』『慈善週間または七大元素 』と三部作をなす、マックス・エルンストのコラージュ・ロマンである。既に知られているように、三部作の中でも最もエロティックな要素を持っているというが、なるほど、やがて鳥類の長=ロプロプ、つまりエルンスト自身が惑乱される“妹”の原型が見出され、その内容は、プロローグからして、何とも“後味”の悪い、愚昧なる純真を犯す?神的な、しかし至高のエロティシズムの種とも呼べるシーケンスで始まっている。 『百頭女』『慈善週間または七大元素 』に比して、現状を肯定し、連続性の中で“置き換え”ていくシュルレアリスムの手法を駆使した、虚無的な攻撃性、つまりは諧謔精神がトーンダウンしている。そのためか知らぬが、得意のコラージュも他の二作に比べると、意図的か知らぬが、緻密さを排除され、いささか乱雑な印象を受ける。もっとも、ロプロプとともにコラージュ・ロマンの主軸をなす、“妹”の誕生と変容を謳うのが主たる目的であれば、コラージュはその補足的、あるいはオルタナティヴな表現であるから、あまり気にすることもないのであろう。無論、エルンストのコラージュが本作でも素晴らしいことは言うまでもないのだが。 後半に付された自身によるマックス・エルンスト伝により、ロプロプの源流(鳥類もしくは嘴固着である)も解き明かされた。まさに、この一冊なくしてコラージュ・ロマンは完成し得ない。 日本人の視点からならば当たり前かもしれないが、随所に楳図かずお的な匂いが漂っているのも、見逃したくない。(了)カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢
2006/12/25
コメント(0)
-
藝術としての事業承継について。
・竹中半兵衛重治が、あえて数名(わずか16名、そのうちには弟も含まれていたとも伝えられているが)にて、国を憂いて、居城の稲葉山城をたった一日で簒奪したのは、実際は義侠心からである。だから、これはアルテなのである。智謀と実践、正義の心の三位一体たる藝術なのである。したがって、たとえ小さな城でも、この半兵衛の三位一体のみをもって事務所を手に入れたのは、私自身の藝術的根拠からなのである。(いつかのメモより)
2006/12/25
コメント(0)
-

『スーパーマン・リターンズ』観ました@DVD。
ようやくDVDリリースされた『スーパーマン・リターンズ』、観ました。スーパーマンへの思い入れは、過去の日記に譲るとして、とにかく良かったですねぇ。あのテーマ曲が流れて来た瞬間に、「おーっ!!」って感動しました。しかも、オープニングでは全然新生スーパーマンが登場しない。ロゴの周りを飛んだりしない。引っ張ります。 で本編。まぁ、ケビン・スペイシーの気色悪いこと。なんか、ジーン・ハックマンのレックス・ルーサーより粘着質で、嫌だなぁ。ケイト・ボスワースのロイス・レインは、ちょっと違うかなぁ。マーゴが演じた時とは。ただ、キャリアウーマンの現代女性像そのものが、きっと変貌しているせいなんでしょうね。これ、隔世の感。 肝心のブランドン・ラウス@スーパーマン。思ったよりあどけない。横顔や、雰囲気、クラークとスーパーマンの時で巧みに変える声の調子などは、なかなかいい感じ。しっかり先代を継承してます。ただ、やっぱりクリストファー・リーヴの時と同じ心配が出て来ますね。この人、スーパーマン以外の役、大丈夫かなぁ、と。体と顔のバランスが、普通のドラマだとちょっと障害になるかな、なんて心配もしました。スマートさ、ジェントルさでは先代に軍配があがりますが、人助けをして、さりげなく「グッナイっ」ってゆっくり飛び立つ様は、まさに“スーパーマン再生”です!! いいですよ。文句なしでしょう。惜しくも急逝したクリストファーも喜んでいることでしょう。まさに、子は父になり、父は子に還る、ですね。 ライフワークである『X-MEN』最終作を蹴ってまでメガホンを取ったブライアン・シンガー監督の意気込みもまた。随所に見られる、彼独特のダークな雰囲気が、青い空と完全な正義との対照をなして、美しかったです。でも、やっぱりこの人、疎外感を描きたがるんだよなぁ。まぁ、理由はいろいろあるでしょうけれど、先代スーパーマンが、全人類の憧れお頂点として、人間の中にいるヒーローだとすると、ブライアンの描くスーパーマンは、人類とは違うがゆえに、大きな責任と義務を引き受けさせられた、“異星人”になっています。人類と同じ目線に立たせないところに、スーパーマンの描き方の違いを感じました。新生スーパーマン、今後が楽しみですね。(了)*写真は、過去記事でも書いた件のスーパーマンの衣装(母の手作り)。いやぁ、ポーズも決まってますね(照)。史上最強のヒーローが帰ってきた!スーパーマン・リターンズ
2006/12/24
コメント(0)
-
今日見た夢に懊悩する。
行き違いがあった。残したメモか手紙のために、$は目の前で私と行き違い、回転ドアのようなところ越しに、私の進行方向と反対に駆けて行った。その後、$は実に短い幸せをつかむが、なぜかまた独り身になり、私は$と夜の遊園地のようなところで再会し、夢の中でも嬉しかった。そして、私と$は結ばれた。やっと、本当に幸せを手に入れたような幸福感と、夢の中でさえこの幸せを夢と知っているような空しさを感じて目を覚ました。そんな夢を見た。(了)
2006/12/24
コメント(4)
-

今年もクリスマス会@実家、ドンピシャな景品が廻ってくる。
昨年同様、今年も家族で集まってクリスマスパーティを開きました。普段それぞれバラバラに頑張っている一族が、集合する貴重なイベント。会場は実家。今回は、シンガポールから従兄が駆けつけ、その弟で来春結婚する従兄弟カップルも参加。総勢11名。もともと家族の少ない当家としては、かなり高い出席率。次第に家族が増えるのもまた、喜ばしいことです。 集合時間はアバウト3時のおやつ。順に各方面から集まってくるのがなんとも楽しいです。次は誰か?みたいな。 私は、週末に荷が重いプレゼンを済まし、少々ぐったり目で参加。でも、二番目でした。最後は、仕事を持ち帰っていた弟が夫婦で駆けつけ、モエ・エ・シャンドンを抜いてパーティがスタート。飲んで、しゃべって、歌って(なぜかそこここで歌が自然発生)、慌ただしいながらも、存分に時間をかけてチキンをたいらげ、やがて、恒例のプレゼント交換へ。今年は参加人数も多いので、6種の景品があみだくじ(!)で、交換されることに。プレゼントの条件は、どんなに行っても予算2000円以内。その中で、22歳から88歳までの誰に当たっても喜ばれるプレゼントを考えるのは、非常に難しくてスリリング。 しかし、フタを開けてみると、今年は6組それぞれが、まさにピッタリのプレゼントに当てはまった模様。最後はキャンドルの中で、写真を撮り、ケーキを食べてそれぞれ解散。とても賑やかで楽しい会となりました。実家で準備をしてくれた両親に感謝です。ちなみに、今年私が頂いたのは、弟夫婦の選んだ目覚まし時計!!うーん、私に早起きして欲しい、という執念が、6分の1の確率に勝利したようです。無念。(了)*ちなみに私が選んだプレゼントはコレ。海外に住む従兄弟に当たりました。丸善で買ったんですけど…。 ↓レターオープナートロイカ(Troika) ・ エルバンディード・ LOP72/MA(sotr180) (レターオープナー)
2006/12/24
コメント(4)
-
波乱万丈の歴史を刻む銀山温泉は、大正ロマンとともに蘇る。(銀山温泉/山形県)
康正2年(1456年)、金沢の儀賀市郎左衛門という人物が発見したといわれるのが、延沢の銀山。銀の採掘が盛んだった頃には、島根の石見銀山、兵庫の生野銀山とともに三大銀山と呼ばれました。2万5000人の鉱夫を抱えていた延沢の銀山に温泉が発見されたのが1600年頃といわれています。採掘にあたっていた鉱夫が偶然に見つけたと伝えられ、最初は鉱夫たちの間で利用されていました。それが、銀の塵の減少、元禄2年(1689年)の大崩漁をきっかけにこの延沢銀山が廃山になり、その後享保年間からは湯治場として栄えるようになりました。 大正2年(1913年)の大洪水により、あたり一面の温泉街が被害を受け当時の面影はありませんが、銀山温泉は大正ロマンあふれるモダンなたたずまいに一新されました。また昭和60年に国指定史跡となった「延沢銀山遺跡」も、銀山温泉の歴史を物語ってくれます。波乱万丈の銀山温泉に想いをめぐらせながら、ガス灯ともるロマンティックな温泉街散策にでかけませんか。(了)お問い合わせ:尾花沢市商工観光課 TEL:0237-22-1111山形県尾花沢市銀山新畑アクセス:JR山形新幹線大石田駅から銀山温泉行きバスで40分、終点下車効 能:神経痛、筋肉痛など
2006/12/23
コメント(0)
-

『シュルレアリスムとは何か』
見出し:シュルレアリスムとは何か。巌谷国士著『シュルレアリスムとは何か』(ちくま学芸文庫) 書評のタイトルには、あえて書名を付さず、キャッチコピーで内容に興味を持ってもらうことを信条としてこれまで記事をアップしてきた。しかし、である。この一冊は、そのものズバリなのである。というのも、これほどタイトルと内容が見事に合致した本はそう滅多にないからである。事実、結果として記事のタイトルと書名が一緒であったからこうなったのであって、もし仮に書名が違っていたとしても、私は書評のタイトルに、躊躇うことなく「シュルレアリスムとは何か」とつけたことであろう。 話し言葉で綴られ、教科書的展開であるとはいえ、だからこそ、誤解や早合点をしがちなシュルレアリスム理解の基礎を、順序良く整理立てて、分かりやすく説いてある。 私自身が、結局リアリストだから、シュルレアリスムのことはある程度、感覚的には分かっていたのかもしれない。というのも私は何につけ、現実との連続、必然的接点、リアリティがないものには主義だからである。夢と現に、時間軸的な、あるいは生体的な境目はあっても、実存的な意味での生から見た場合には切れ目はないように、私がロマンティシズムへと傾斜するときも、別世界への没入ではなく、実世界の連続としてのめり込んできた。つまり、シュルレアリスムの何たるかを知らずに、心のどこかでは分かっていたと言うことである。いや、ある意味では、これまでの生き方そのものが、真の意味でのシュルレエルだったと言えるかもしれない。 日本で使われるシュールという表記そのものの誤謬の言及は興味深い。「シュール・レアリスム」では、「シュール」と「レアリスム」のくっついた言葉になってしまうから、語感から現実離れした異様な世界をイメージしてしまうが、もともとは、もし切るとすれば、「シュールレア(エ)ル」と「イスム」なのである。「シュール」が「レエル」にかかっているのではなく、「イスム」に「シュルレエル」がかかっているのである。 もともと、語の作りから、それが英語でいうsuperrealであることももちろんわかっていた(フランス語は解さないが)。つまり、著者が指摘するように、超現実は、現実とはほかの場所にある世界だという意味とは、私は思っていなかった。これは、心理学を学ぶ際には、スーパーエゴ=超自我という言葉に出会うが、この“超”の使い方とシュルレアリスムにおけるシュルレエルに近似しているということを既に知っていたからである。 著者曰く、日本では辞典ですらシュールの意味を間違えているというから、気をつけたい。これからは、シュルレエル、もしくはシュルレアリスム、と切らずに表記しなければ、せっかく意味を知っていても、知らないのと同然になってしまう。(了)シュルレアリスムとは何か
2006/12/22
コメント(0)
-
経営理念。いたって、シンプル。
さて、ひょんなことからの経営者への就任。当然、ビジョンはなければならないのです。ただ、私の場合は、公私共に、考えていることが年々同じになって来ているので、あらためて考える必要は何もなく…。 もともと、話ベタなことも物を書く仕事への遠因ともなっているわけで、したがって、所信表明は文書にして、その場でスタッフに話しました。それが下記の内容です。***************************【新体制について―経営方針および理念】1:自社営業にこだわると同時に、営業して恥ずかしくないだけの自分を創る。2:個々人の継続的スキルアップに基づく少数精鋭集団たること。3:当社が企業であるという意識は捨て、個性あるフリーランスが集う工房と考えて欲しい。4:とは言え、法的には企業なので、 最低限の生活の保障は企業責任としてする。 それ以上を望むなら、自己研鑽を怠らず、かつ仕事でお客様に「魅せる」こと。 それなき場合は、右肩上がりは期待しないこと。ただし、故無く見捨てはしない。 『いつまでも、あると思うな会社と給料』5:新旧世代がうまく噛み合い、相互に補完しながら共生できる制作会社を実現する。6:「武士は食わねど高楊枝」、「勝って武士の情けを知る」。そういうやせ我慢を厭わないで欲しい。やせ我慢は、その人に誇りと知性を与える。中途半端な我慢ならいらない。7:文章を書く、言葉を扱う、これ、最高の仕事と自覚する。優雅に仕事をして欲しい。8:仕事の道、金儲けの道、出世の道、すべての道の前に、人間の道があることを忘れるなら、すぐにほかの仕事を探すべし。9:奉仕の精神を忘れない。恩には恩を。10:自分の仕事を愛する。自分の仕事を家族に見せ、誇る。 あとは自由。仕事人間にならず、人生そのものを、めいっぱい楽しみ、哀しむ。それを、仕事に、プライベートに反映し、凸凹はあっても、豊かな人間になって、死んで欲しいです。*************************** 以上です。結局、一番大事なことは、自分を恃むだけの努力を怠らない、ということと、人生そのものを喜怒哀楽で受け入れる、ということなのです。それ以上については、私も責任を取るつもりはないし、取るだけの義務も才覚もありませんから。覚悟がなければ生きていけませんし、覚悟があれば、大抵のことは乗り越えられる。それに、私の座右の銘は「人間は誰でも闇を抱えている」ですから、誰かに完全を求めることも、ガチガチの統制をすることも不可能だと思うのです。その不可能という制限の中で、少しの虚無感をもって、生々しく生き延びていく。これがリアルな人生ではないかと考えるのです。 ちょっと真面目になってしまいましたが、甘い言葉や上手い話はいくらでも作れるし、聞く側も心地いい。でも、それで人の人生を台無しにするなんてことはしたくないので、やっぱり少なくとも私が真実だと思うことを説明し、着いて来てもらう方が、最終的には善意なのかな、なんて思います。(了)
2006/12/22
コメント(4)
-
企業、ではなく発業(後編)。
さて、経営者。さっぱり分かりません。ただ、業界が業界ですし、もともと私の動き方をよく熟知したスタッフを、フリーランス稼業の合間に育ててきましたから、従来の神出鬼没な動きは変わらないと思うんですけど。業種は、まぁ制作会社ですね。 私の父はサラリーマンでしたが、40代半ばからは社長業を転々として来た、いわば経営のプロにして、傭兵隊長。私、父のことは「我がフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ」と呼んでいますが、結局、創業以来の経営方針が時代性にマッチしないとか、新しい業務展開を見据えて、適材としてのトップを求めている企業(大小に関わらず)から請われて、社長として赴くのです。ただ、どれもオーナー会社ですから、実質的には、まさに傭兵隊長なんですね。その上でも、以下でもない。 父と私は、父の自由主義的な教育方針もあって、互いに敬意を表する仲でありましたが、それゆえにか、私は父とはまったく別の世界へと進み、かつ父もそれを応援しこそすれ、眉をひそめるようなことをしませんでした。やっぱり遺伝子かなぁ。でも、私の場合は小さな組織ですからね。因果かなぁ。 さて、なぜ経営者に?自分でも分かりません。ただ、ある会社の人事採用からキャリアコンサルテーション、若手育成、コネクションの整理から経営体質の改善、制作現場での作業で外注ながら切り盛りするうちに、「任せたい」という要請を受けました。 私は、一度も勤め人をしたことがなく、学生から研究生、そしてフリーランス、と渡り歩いて来ましたから、もともと組織に依存することにこだわりがないんです。否定はしないし、拒絶はしませんが、肌に合わないのだと思います。なので、受けるべきか戸惑いましたが、もともと経営者になっても、飽くまで個々のスキルで生きて行く覚悟のある社員を育てて来たつもりですし、私自身も会社の大小は関係なく、今や組織に依存する姿勢自体が甘え(雇用者側は思いのほかドライですから)だと思って来ましたので、経営者にはなるけれど、会社がなくなってもフリーでやっていく自信があるだけの努力をスタッフにしてもらうことと、オーナーにならせてもらうことで引き受けました。私が経営ドップリだったら、すぐ潰れますからね。むしろ、ゲリラ的に動いて、仕事を増やすことの方が、私には求められていると思いますし。 そんなこんながありまして、ちょっと慌ただしかったりもしましたが、まぁ面倒や困難は、得てして固まってやって来ますし、それなら一気に集中して取り組む方がいいだろう、なんて思い、せめて仕事納めまで踏ん張ろうと覚悟している次第です。(了)
2006/12/21
コメント(2)
-
企業、ではなく発業(前編)。
過日、何故にプロフィールの変更を再告知したのか…。それには理由が二つあります。1:もともと、ライターという言葉が好きでなく(変に誤解されて華やかとか派手に見られますが、地味な仕事です)、ただ自分の文筆に対する思いやこだわりをいちいち説明するのが厄介なので、便宜上ライターという肩書きを使って来ました。しかし、文筆家でないけれど、多数の本を出されているプロフェッショナルな方と、文筆家としてコラボレートすることが決まったことをもって、ちゃんと自分を形容できる職業名に変えようと思ったのです。つまりライター→文筆家。別に、文筆家が格式高そう、なんて下心はなく、書く内容より表現にこだわる私としては、文筆家ないしは文章家の方が適切だろうと思うのです。事実や事象の言い換えが大事であって、その言い換えの術に“らしさ”やスタイルを出したいのです。また、作家でない私は、海外の友人に仕事を聞かれてライターと答えると、まず「作家」と思われてしまいますから。ジャーナリストとも違う、創作的感性を除外した文章表現の専門家、という意味では、やはり文筆家なのです。2:そして。あろうことか、ひょんなことから、経営者になってしまいました(気づいた方、いらっしゃいましたでしょうか)。本当に、ひょんなことから。自然発生的ともいえる展開は、起業でも開業でもなく、ふっと湧いた幻の城、一夜城、つまり発業と呼ぶべきではないでしょうか。(つづく)
2006/12/21
コメント(0)
-
正義と公平。
これ、よくあるコトなんですが、「紳士さんは文学部出身ですよね」「紳士さんはデザイン系の出身ですか」と質問されます。特に、“紳士=文学部出身”説は結構頑固に蔓延していまして…。 ですが、私、法学部、しかも、堅いほうの法学を勉強してました(逆に、実用的なのが、例えば六法絡みです)。文学とは無縁の畑にいた人間。実際、文学、全然分かりません。我流なんです。美術も我流だし…。 でも、ふと自分が法学部出身であることを思い出すと、いつも自分の行動基準に現れる一つのモードがあることに気付きます。それが、リーガルマインド、というものです。学生当時は、特にほかにすることがなかったので、結構勉強したとは思いますが、その時に、生得的な感覚と、後天的な学習によって得た一つの価値観が、正義と公平についての判断基準です。 法の女神ユスティティアは、Justice(正義)の語源ですが、 持っているのは秤(と裁きの剣)。振り返って、私の考える正義は、所謂正義(法的正義)ではなく、公平感なんです。つまり、Equalityの方なのです。 私の正義感や義侠心は、自分ないし誰かの公平が損なわれた時に、損なわれた側の損失をカバーする ために発動する、ということに自分で気付いた次第。今もどこかで起こっている戦争の数々を見れば分かるように、現実の世界での正義と言うのは、きわめて主観的です。だから、主観的正義をぶつけ合って持ち分を逆転するのではなく、あくまで公平というバランスを取り戻すための正義なのです。こうした正義感(正義観)は、やっぱり法学部的だなぁ、と感じますね、自分でも。(了)
2006/12/21
コメント(6)
-

『ダンディ ある男たちの美学』
見出し:現代日本のダンディ、ここにあり。ロジェ・ケンプ 著、桜井哲夫訳『ダンディ ある男たちの美学』(講談社現代新書) あえて言おう。「ダンディとは、ダンディになるのではなく、ダンディに生まれるのだ」。そう、ダンディズムとは、畢竟生得的な資質である。だから、ダンディの基準は、ダンディか、ダンディでないか、しかない。そこに、曖昧な線引きもグレーゾーンも存在しない。明快。 本書は、おそらく10年以上前に手に取って読んだ本だが、改めて読み返すとなかなか興味深い。生田耕作の『ダンディズム 栄光と悲惨』と対比してみると、生田の“ジョージ・ブランメル支持、バイロン不支持”に対して、本書は“バイロン支持”を採っていて、私にとってはありがたい話である。その理由は、過去の書評を参照されたい。 ダンディを日本語に訳す時、それが名訳であるかどうかは別として、伊達男や洒落者とされる。しかし、傾き(かぶき)と婆娑羅が異なるように、外在し、展示され、顕示されて行くダンディズムは、婆娑羅の悪趣味や歌舞伎の饒舌な過剰装飾に他ならない。原始的な意味での傾き(かぶき)とは、やせ我慢である。沈黙である。孤高である。迎合や取り入りには無縁である。和して同ぜず、である。憂鬱であるが不愉快でなく、むしろ愉快である。自ら恃むを恐れず、批判を受け流す(受け入れるかは別として)人である。集合や体制と絶縁することで被るあらゆる負債を、覚悟を持って、己の美意識のために甘受する人である。決して、世に見かける華やかな誤解されたダンディズム(お洒落や装飾)とは無縁の人たちである。 ダンディズムとは、畢竟、類い稀なるを、あるいは希有たるを、沈黙するやせ我慢を、作り笑いと純粋な渋面で受容する人である。 訳者は冒頭で、終末論的な悲嘆と、無策の義憤を込めて、現代日本にダンディはいない、と憂いてみせる。心配はいらない、ダンディはここにいる。(了)ダンディ
2006/12/21
コメント(0)
-

最近の大量読破はホンモノです。
最近、やけに読書の勢いに拍車がかかっておりまして、ついつい気がつけば読書に耽ってしまっています。以前、当ブログで自身を指して“遅読の徒”と評しましたがこれは本当で、しかしながら最近の連続書評分は、まったくもって本当に、一気に読んでいるのです。まぁ、それでも速読なんて芸当とはほど遠いワケですが。 ひと昔前は文庫なんていうと、スノッブからは「岩波じゃないと…」的な見方をされましたけど、最近は結構ハードな内容の本も文庫化されているので、読書の幅が広がりありがたいことです。(了)【上質革のブックカバーMinerva Box】ソフトレザー文庫サイズブックカバー
2006/12/20
コメント(1)
-
今日見た夢に戦慄する。
鼻の近くに小さな白いできものができた。一日もすれば枯れてしまうニキビのような、小さなできもの。気になって、いじっていると、やがてそれはイクラ大の大きさになった。驚いて、痛みをこらえて潰そうとすると、それはイクラ大の目玉であった。叫びたいほどの痛みに耐えて、それを指先で潰すと、ぷつ、と音を立てて洗面台に落ちた。その目玉は、ジッとこちらを見ていた。そんな夢を見た。(了)
2006/12/19
コメント(8)
-

『慈善週間または七大元素』
見出し:考えるな、感じろ!!マックス・エルンスト著、巌谷国士訳 『慈善週間または七大元素』(河出文庫) ファンクとは何か?ソウルとは何か?ロックとは何か?こうした問いがナンセンス、もしくは一問一答的な陳腐な皮肉のきっかけでしかないように、シュルレアリスムとは何かを問うても、よほどの専門性がない限りは、厳密な分析など不可能である。だから、ただ「考えるな、感じろ」なのである。 描かれているものより、描かれているものの“向こう”が、タナトス的でエロティックでネクロフィリアである。この世の欺瞞をすべて、切り取り、残ったものを貼りあわせるロプロプ=エルンストの手作業の残滓は、かえって清清しい。いつわりのない姿。シュルレエルによってリアルを映す姿、まさに慈善の鑑である。 各図版中の肖像画や鏡の使い方が効果的で、そこに注目していくと、あらぬ想像ないしは正確な読解への妄想が促進されていく。(了)慈善週間または七大元素
2006/12/19
コメント(0)
-
再告知:初の本、出版します。
再度告知です。 “出版冬の時代”、最初の一冊目は、文筆家として、自費出版でない商業出版にこだわり、結果につなげました。脱稿から約10ヶ月。 一時は出口なしか、と思われましたが、自分の信念を曲げず、世に問うて恥ずかしくない一冊と信じて、ぬか喜びと落胆を重ねて来ました。 もともと生涯一文筆家、出版にはそれほど興味はなかったのですが、いざ必然性を感じると、とことんまで行ってみたくなるのが性分。また、本来出したい(テイストや出版社のカラーの面で)出版社にこだわり続け、出版契約に至ったことも、書き手としては嬉しい限りです。 この本、キーワードとしてはズバリ、“現代の赤本”。つまり読み捨てされないで、困ったり、疑問にぶつかったときに、都度読み返して欲しい本です。その度に味わいが変わるでしょう。 出版は来春(遅くとも3月)予定。厚かましいお願いですが、興味関心のある方、ぜひお気に入りやリンクにご登録いただき、これから本が出るまでの旅程を、ご一緒下さい。(了) *サンタクロースにお願いすること。今は、“わが子”が無事生まれ出てくれることだけです。
2006/12/18
コメント(8)
-

『悪女入門』
見出し:悪女入門=馬鹿な男の見本市。鹿島茂著『悪女入門』(講談社現代新書) 悪女入門と名付け、著者ならではのファム・ファタル論を展開して行く。事実、随所に「ファム・ファタル=悪女になるにはここがポイントです」的お節介なコメントが挿入されるが、この女性に向けて書かれた“男心からみた「命をまるごと吸い取られる女」論”は、他の著作では見られない妙に慇懃な文体が、かえってシニカルで読んでいて面白い。 鹿島氏の文章を読んでいると、氏がどうも女性的である、と思える時がある。というのも「これでもか」とばかりに、ファム・ファタルに翻弄される男の惨めさを、サディスティックなまでに描き倒すのだが、馬鹿な男のサンプル提示の数々に、鹿島氏の、ファム・ファタル自身であるかのような倒錯的な陶酔を嗅ぎ取ってしまうからである。 もっとも、うら若い女性を相手にする仕事の故かもしれないが…。ともあれ、悪女入門とは、すなわち馬鹿な男の見本市であり、悪女への近道は、馬鹿な男を数多踏み台にすることである。(了)悪女入門
2006/12/17
コメント(4)
-
訪れれば、北の自然の魅力が満載。一日かけて散策したい山花温泉リフレ。(北海道/山花温泉リフレ)
今どこでも人気のスーパー温泉やスパ。山花温泉も、そんな最新のリラクゼーション・スポットです。ただ、この山花温泉が、コアな温泉ファンにも人気の理由は、ここは釧路ではじめて湧き出た温泉だという点です。近海に火山帯を持ちながら、釧路市内にはこれまで温泉は存在しませんでした。この山花温泉はまさに、待望の、そして湧くべくして湧いた温泉といえるかもしれません。 泉質はナトリウムをメインにしており、水温も43度、と優しい温泉です。山花温泉は、「山の湯」「花の汲」の二つの露天風呂を有し、北海道の自然に囲まれながら、のんびりゆったりとくつろげます。 山花温泉の周囲には、釧路のシンボル、丹頂鶴が遊ぶ“釧路市丹頂鶴自然公園”、シマフクロウのいる“釧路市動物園”、乗馬の楽しめるホースパークや家族でアウトドアを満喫できるキャンプ場などがあり、一日かけてゆっくりと自然と触れあいたい温泉です。山花温泉には、宿泊施設もありますので、時間を気にせず、都会の喧騒を忘れてリフレッシュに訪れたいものです。お問い合わせ:釧路市農村都市交流センター 電話:0154-56-2233山花温泉リフレ〒084‐0928 釧路市山花14線131番H P:http://www6.ocn.ne.jp/~refre1/アクセス:JR 札幌-釧路 3時間45分効 能:神経痛、疲労回復、筋肉痛、関節痛、冷え症など
2006/12/17
コメント(0)
-
湖水豊富な宍道湖のほとりに湧き出た地域密着型でもある温泉(島根県/松江しんじ湖温泉)
牡丹の花や、小泉八雲の物語で知られる松江はまた、水の豊富な土地柄としても有名です。市内を縦横に走る旧城下町の名残の川の数々がそれを物語っています。そして、松江を“水の都”たらしめているのが、豊かに湖水をたたえ、その夕陽の沈む様は絶景とされる宍道湖です。この宍道湖のほとりに広がるのが松江しんじ湖温泉です。松江しんじ湖温泉は、宍道湖の北岸に位置し、昭和46年の掘削によって、76度という高温の温泉が湧き出したことに始まります。この温泉が、神経痛やリウマチなどに効能があることが認められて、翌年昭和47年より、近隣の温泉旅館に配湯が開始されました。その後は松江温泉として愛されてきましたが、平成13年に全国から名前を募集し、現在の「松江しんじ湖温泉」に改称しました。温泉街の多くの宿からは、小泉八雲がこよなく愛した宍道湖や、川に囲まれる松江の市内を望むことができます。温かい水の恵みに浸かりながら、“水の都”を眺めるというのも、一風趣向の変わった贅沢ではないでしょうか。(了)お問い合わせ:松江観光協会 電話 0852-27-5843松江市観光文化課 電話 0852-55-5214アクセス:JR米子駅下車山陰本線特急 松江駅下車効 能:リウマチ、神経痛、慢性湿疹など
2006/12/16
コメント(4)
-
幕末の志士たちが壮大な維新の夢を語り合った「白狐の湯」(山口県/湯田温泉)
幕末の日本を動かした優秀な志士たちを多数輩出した山口県を代表する温泉である湯田温泉は、井上馨の像や、長州藩の重臣周布政之助の碑などを抱え、勤王の志士たちが維新への夢をこの温泉で語り合ったという逸話にも頷けます。72度のお湯が、毎日2000トン湧きだし、訪れる客を楽しませている湯田温泉には、およそ800年前に湯田の権現山の麓のお寺の境内にあった小さな池に毎晩傷を癒しに訪れた白狐が、この温泉を教えたという伝説が残っています。和尚さんが、その池を掘ってみると、温泉が噴きだすとともに、薬師如来の金像が姿を現したというのです。以後、この仏像を拝みながら湯浴みをすると難病も治るという「白狐の湯」の評判が立つようになったということです。天才詩人中原中也の生誕の地としても愛されている温泉です。(了)お問い合わせ:湯田温泉旅館協同組合 TEL:083-920-3000山口県山口市湯田温泉アクセス:JR山陰新幹線小郡駅から山口駅方面行きバスで20分、湯田温泉下車効 能:神経痛、筋肉痛ほか
2006/12/16
コメント(0)
-

“火を使わないロウソク”は、私の情緒をやさしく刺激する。
最近、照明に関する本を読んでいて、かつて照明デザイナーの石井幹子氏に取材した時のことを思い出しました。やっぱり、自然光が一番なんだ…。でも、自然光ったって、実際家でアロマキャンドル立てる、なんてよっぽどの時ですよね。むしろ、異例のこと。自然光、それも暖かい明かり、蝋燭の焔のような明かりを、手軽に、しかも洒脱に生活に取り入れる方法、ないかなぁ…と思っていましたが、ありましたよ。コレ。N.Y.ののMOMAでも扱っているこのキャンデラ・ホワイト vesselは、当然デザインもシンプルにしてお洒落。 ロウソクのような温かでほのかな明かりなのに、火を使わず安全。充電方式、ランプはフル充電(約16時間)で、約5時間の使用が可能。もう、毎晩これで本読んでますよ。その影が天井に揺れる様が、またゴシックな感じです(つくづくシチュエーション・マニアだなぁ)。 様々な形状やサイズで、買い足しも出来るので、楽しくつき合って行けそうです。ちなみに、充電中に停電になるとライトが自動的に点灯するので、防災的な役割も。うーん、ホント、これ持って、湿った暗い階段とか降りてみたいものです(笑)。(了)■送料無料■キャンデラ・ホワイト2本セットcandela vessel 充電式ワイヤレスランプ【送料無料】VESSEL/ヴェッセル Candella aqua terra(キャンデラ アクア・テラ)
2006/12/15
コメント(4)
-

『明日は舞踏会』
見出し:“古今東西の乙女の夢”も、また易きにあらず。鹿島茂著『明日は舞踏会』(中公文庫) 1991年に、サントリー学芸賞に選ばれた『馬車が買いたい!』は、いわば“19世紀パリの“男性”の、ステイタス、欲望、野心、浮き名などといった価値の獲得の象徴、あるいは立身出世で男を上げる、ないしは有閑的嗜好に耽るための“夢の箱船”たる馬車をモチーフに、現代人が高級車に憧れる物欲のドライバを、社会的/文化的な視点から分析し、かつ同時に読み物として楽しめるように綴られた、バーチャルなモノ・マガジン的一冊であった。著者は、今度は『明日は舞踏会』の冒頭で言う。「女性の夢の仮想体験の実現に貢献する視点は、『馬車が買いたい!』にはなかった。だから、その女性版を書いてみよう」と。 著者自身も述べているように、男性の憧れが「馬車(=サクセスの証)」であるならば、女性の少女的発想からなる夢は、古今東西、「舞踏会」の華やぎときらびやかさ、そしてロマンスにあるという。舞踏会の文化がきわめて些少なここ日本にあっても、である。その夢を、やはり舞台を世紀末パリに移して、限りなく実現可能なノウハウを再現してみた、知的冒険心からなる一冊は、思いのほか資料が不足し難航したと言う。 だが、私自身は、資料のなさに、かえって間接的資料を補い、かつバルザックの『二人の若妻の手記』の主人公を案内役に立てることで、見事にパッチワークに成功し、スリリングにも“明日の舞踏会”への手ほどきを復元してみせている。加えて、挿入される図版が美しく、当時の服飾文化が垣間みえるのも愉しい。 夢はつねに陶酔と引き換えに困難を伴うものであるが、“古今東西の乙女の夢”も、また易きにあらず、である。社交界とは実に、面倒な場所である。(了) 明日は舞踏会
2006/12/15
コメント(0)
-
書評:沖縄の元気を伝える亜熱帯マガジン、『うるま』を読んでみよう!
「うる=珊瑚」、「ま=島」、つまりは沖縄を意味する呼称をタイトルに冠した元気な情報誌をご存知ですか?沖縄のその時その時の最新の情報を満載し、沖縄から発信している雑誌『うるま』は、その読者の半数が沖縄県外の人たちだそうです。ガイドブックにない沖縄を、定評ある美しい写真とともに紹介する『うるま』は、沖縄が好きな人も、沖縄に詳しい人も、これから沖縄の魅力に触れたい人にも是非おすすめしたい情報誌です。沖縄の春はもう始まっています。夏もすぐそこ。沖縄を訪れる前に、一度手にとってみてはいかがでしょう?●お問い合わせ 雑誌うるま編集部(有)三浦クリエイティブTELO98-833-9051 FAXO98-836-4140HP:http ://www.u-r-u-m-a.co.jp/uruma/uruma.html
2006/12/15
コメント(0)
-
プロフィールに、手を入れてみる。
ブログ開設から随分経って、様々な変更を加えて来ましたが、案外野放しになっていたのがプロフィール。ということで、久しぶりにプロフィールを更新してみました。ま、基本はあまり変わらないのですが、少しだけリアルタイムに近づけてみました。(了)
2006/12/14
コメント(4)
-

永遠の恋人、タミー・テレル。
タミー・モンゴメリー。後にタミー・テレルと呼ばれ、モータウンの仲間入りを果たし、ヒットに恵まれないマーヴィン・ゲイと、デュエットという架空の世界で、永遠の恋人同士を演じ、謳い、讃え合った女性シンガー。マーヴィンのミューズ。そして、遠い恋人。 早くもそのパンチのある歌唱力を認められ、ジェイムズ・ブラウンのバンドで歌手兼愛人。舞台をデトロイトに移したタミーは名前を改め、活動を開始。 実は、もう10年くらい前になるだろうか、レコードショップで彼女がモータウンから出したソロ・アルバムのアナログ盤が飾ってあり、値札には目の飛び出るような価格が付いていた。欲しかった。でも、買えなかった。 ソウルフル一辺倒ではなく、さわやかでメロディアスなポッピズムを組み入れた、洗練されたサウンド・オブ・ヤング・アメリカを追求していたモータウンにあって、タミーのような唱法は、果たしてマッチしたのだろうか? したのである。それも、モータウンの社長の姉と結婚し、モータウンのプリンスと呼ばれるも、まだまだその有り余る才能を開花させられずにいたマーヴィン・ゲイを、持ち前の明るさと飾らない人柄、チャーミングな容姿、何より、シャイなマーヴィンをグイグイと導くエネルギーで、一躍“理想の恋人”にまで押し上げてしまったのである。 マーヴィンは、数々の女性シンガーとデュエットをしているが、タミーとの相性は抜群である(最悪の相性なのがダイアナ・ロス)。本来、スムースな歌い方にこだわるナット・キング・コールやシナトラ好きなマーヴィンと、モータウンの歌手にしては少々アーシーなタミー。この二人が組むと、まずはパンチのあるタミーが、敢えて三歩下がって、マーヴィンを強く前に立てる。そうすると、途端に、マーヴィンが誠実な青年らしい青臭いまでのシャウトで弾む。よしよしと頷きながら、確かで力強いタミーの声が、不安定なマーヴィンの声を支え、かえって自由に遊ばせてあげる。 二人が組んだ瞬間、それまでにない自分を引き出し合うことで、完璧なカップルとなったのである。ジェントルだけど押しの弱いマーヴィンは、やがてタミーをリードし、本来快活なタミーは、自我を抑えることでマーヴィンに安心感を与え、今度はマーヴィンのエスコートを受けて光り輝く。スタジオに入り、二人が声を出した瞬間、立ち会ったミュージシャンたちは、思わず鳥肌が立ったと言う。 しかし、である。互いに、音楽活動の中では恋人同士であっても、スタジオを離れれば、マーヴィンは妻の元へ、そしてタミーは、恋人であるテンプテーションズのスター、デイヴィッド・ラフィンの元へと、それぞれ別の道を帰途につく。実に切ない。その実生活の二人のロマンスが、上手く行ってなかっただけに。 後に、マーヴィンは、タミーに対して好意と敬意はあったけど恋愛関係はなかった、と述べたという(マーヴィンとのデュエット=疑似恋愛の美しさに嫉妬したデイヴィッドが、タミーに暴力をふるったという真しやかな噂は、さりげなく某再現ドラマにも描かれている)。本当だと思う。恋愛関係はなかった。だが恋愛感情はあったのではないだろうか。マーヴィンは、タミーを愛していただろう。だが、愛しているからこそ、深入りしなかった。後に、セックス・シンボルとなり、ポルノの権化のようにさえ道化てみせるマーヴィンは、反面過剰に潔癖な男であったのだ。 その証拠は、タミーの死にある。1970年、タミー・テレルは、ステージ上でデュエット中のマーヴィンの胸の中に倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。脳腫瘍。20代、美しい盛りであった。以後、マーヴィンはステージ恐怖症、対人恐怖症となり、人気シンガーへの階段を放棄して一年以上も音楽活動を休止してしまった。これは、よく言われるマーヴィンの繊細さのゆえのみならず、タミーへのプラトニックな愛のゆえではないだろうか。私は、そう信じたい。(了)タミー・テレル/THE BEST 1200 タミー・テレル
2006/12/13
コメント(4)
-
嘘評:ハーレム・ルネッサンスを“再生”させた憂愁の詩人
ヒューゴ・ロングストーン著『儚き夜の想い』(白昼書房) 20年代のニューヨークは、まさにローリング20’Sのまっただ中。ハーレムにも、新たな文化と芸術の爛熟の刻がやってきていた。自らの肌の色を誇り、アフリカン・アメリカンがそのアティチュードによって、自分たちのルーツを再発見(白人によって、文明化論的に“発見”された“アメリカの黒人”を、人種主導で積極的に再発見して行ったのだ!!)したこの時代は、後にハーレム・ルネッサンスと呼ばれ、華やかなノスタルジーを喚起する魔法のキーワードとして、アメリカの黒人たちや、進歩主義的な文化人ら記憶されることになる。 一方70年代アメリカ。公民権運動、ベトナム戦争、ヒッピー・ムーヴメントの時代に多感な時期を過ごした詩人は、ハーレム・ルネッサンスではなく、「ブラック・パワー」、「ブラック・イズ・ビューティフル」をスローガンとする気風の中に身を置きながらも、遠く20年代のブラック・カルチャーに郷愁と共感を抱きながら、自身の人種的アイデンティティを模索していった。同時代のアイコン、マーヴィン・ゲイの心情を代弁した作品“タミーは死んだ”は、詩人のセンシティヴィティと、モチーフのナイーヴさがマッチした珠玉の一篇である。(了)“タミーは死んだ” ヒューゴ・ロングストーン タミーは死んだ永遠に。 俺の、腕の中ではなかったが。 タミーは死んだ永遠に。 ステージの上で、 歌いながらではなかったが。 俺とタミーの関係は、 いわゆる結ばれた恋仲ではなかったが、 ほんの僅かの間でも、 二人でいると良い歌声をかなでた。 その瞬間は完璧に、 二人だけの暖かな世界になった。 演じ、演じあう恋人も、 それぞれ帰りは別の道。 腕に抱くのは別の人。 タミーは死んだ永遠に。 死んでタミーは永遠に、 遠い遠い恋人になった。(『儚き夜の想い』より)
2006/12/13
コメント(2)
-

パウロ・コエーリョと地湧社。~地湧社ってどんな出版社~
ようやく決まった初の出版。その出版社が地湧社さん。なぜ地湧社にこだわったのか。そして、相思相愛のもとで出版に達したのか。 それは、一つには、*地湧社さんは、書籍にこだわり、地味ながら真面目に本を作ってきた出版社であること。*もともと書き始めたときから、地湧社さんをイメージして執筆開始していたこと。*他の出版社に持ち込んだところ、異口同音に「地湧社さんがぴったりじゃないか」というアドバイスをいただいたこと。 そして何より、一人の作家、それも、私が住み愛したブラジルの作家であるパウロ・コエーリョを日本に紹介した出版社だったからです。パウロ・コエーリョは、つい最近も、FIGAROjapon(フィガロジャポン)9/20号で特集が組まれていましたが、その作風の特長は何といっても、子供っぽいプロットに大人向けのメッセージを入れる点や、寓話性に富んだ現代小説を描き出すところです。 私の本は、実は共著なのですが、その相手との出会いのきっかけこそが、パウロ・コエーリョの故郷・ブラジルで200万部突破、世界23ヵ国語、47ヵ国で出版された『アルケミスト』だったのです。 こうした縁から、何か必然性のようなものを感じ、どうしても地湧社さんから出したいな、という強い思いがありました。地湧社さんの設立趣意書は次のように言います。 「私達は有史以来初めて体験する、さまざまな大きな危機に直面しています。その最も切実な問題が、世界的な規模で廃絶が叫ばれている核兵器であります。核兵器を使用するという事態が勃発すれば、人類は間違いなく滅びることでしょう。 私達が直面している危機は、一つ核兵器の問題のみではありません。産業の近代化にともなう大気汚染と、そして河川や海の水質汚毒は、私達の生命を、じょじょに、しかも確実に蝕んできています。また私達の生命の源は食物でありますが、現実に直面している食品禍は、おそるべきもので、これまた私達の生命を蝕んでいます。日本の農地は農薬と化学肥料によって瀕死の状態であります。私達の健康と生命を脅かしている食品は、農産物だけではありません。工業的に作られた有害添加物を含む、偽りの食品が氾濫し、それを口にする私達は、生命の根から断たれた浮き草のような状態になりつつあります。現実的には、ガン、脳卒中、心臓病等々の文明病は、いよいよ増加の一途をたどっています。これは、肉体のみにとどまらず、私達の精神を確実に腐敗させています。 私達をとりまく大自然の中で、自然と人、社会と人、人と人とが触れあう環境が、世界中の一人一人に対し例外なく、次第に生命を滅ぼす方向に進んでいることは、誰の目にも明らかです。 さて、人間の没落に歯止めをかけるには、どうすべきかという問題であります。 政治家や経済人など現代の指導者的立場にある人が、人類未曾有のこの危機を救ってくれるでしょうか。答えは残念ながら否であります。彼らがこんにち担っている役割を突然変えることは、かえって社会を混乱させるだけのことでしょう。 では、学者、教育者、医師、その他文化人が私達の生命を守る役割を果たしてくれるでありましょうか。学問や職業を極度に専門化し、私達を当たり前の生活から遠ざけた彼らも、残念ながら私達を育ててはくれないでありましょう。 それならば、宗教家は私達を救ってくれるでしょうか。しかし、これほど大きな問題に直面した宗教者は、いまだかつてなかったのです。すなわち、宗教は私達を救う原理を内包しているはずですが、では世界的な規模に拡がっている危機をどのようにして救うかという具体策の点では、まだ私達と同じ入り口で模索しているのが実状でありましょう。 すなわち、私達は今まで、私達の指導者として仰いできた人々を、もはや頼りにはできないということに気づいたのです。 つまり、私達は、科学だとか文化だとか言って、表層の感覚や知的営みばかりをあてにしてきたのです。 既成の文化が人間にとってまったく無意味だったというわけではありません。しかし生命の深い根を見つめた観点に立てば、そうした知的営みは、人間に秘められた能力のごく一部分に過ぎなかったのではないかということであります。人間は、もっと大きな智慧に支えられているのではないでしょうか。 私達は地球誕生以来の進化の産物です。私達の生命の中には、地球と同じ歴史を圧縮して宿しています。すなわち、実際的な年令とは別に、私達は三十数億年という年令を持っていることになります。たかだか数千年の文化を誇ったりしてみても、私達の生命に宿る歴史から眺めれば、部分に過ぎないわけです。 私達誰もが、現在の文化から得た智慧以上の、魚であったりサルであったり、あるいは宇宙そのものであったときの智慧を、潜在的に持っていると考えられます。 これまで、この深い智慧に到達した人々は、特殊な境遇に出会った、ごく一部の人々でありました。ところが、このまったく行き詰まった現代になって、自らあてにしてきた人知の舟をおり、いのちの再生へと進路を取りはじめた人々が、洋の東西を問わず、増えはじめています。 これを自覚の人々と呼びましょう。 彼らはとりたてて指導者的立場にある人ではなく、大地に根を下ろした実践をもった人々です。彼らは百姓であったり、庭師であったり、家庭の主婦であったり、市井の医師であったり、あるいは宗教者であったりします。 彼らは、生命に根ざした生き方をいち早くした人々といえます。次の時代を担う人達です。にもかかわらず、彼らは、そのことをはっきり意識する必要のない世界に住んでいます。ですから、彼らはお互いに連絡を取り合うこともなく、自己との対話の中で、内面から聞こえてくる声を頼りに生活しています。 彼らとは、それはあなたなのです。 深い智慧の井戸を掘りつつある、あなたなのです。 生命に根ざした生き方をしている、あなたを含めたその人達は、社会の表面に露われていませんが、しかし一本の地下水脈でつながっています。この地下水脈はやがて地表に湧き出し、人類の生命の根源の水となり、人々を潤し、旧い人々が想像するような激しい変化ではなく、もっと静かに、しかし確実に、この世の変革をとげるに違いありません。 自覚の時代は始まっています。(地湧社設立趣意書より)」 この趣意に沿う内容の本になっているか。大丈夫だと思います。皆さんの目と知性で、ぜひ確かめてみてください。(了)アルケミスト
2006/12/12
コメント(2)
-

『パリ五段活用』
見出し:“鹿島アンソロジー”の鬼っ子。鹿島茂著『パリ五段活用』(中公文庫) 評価の難しい本である。ひとたび気になると、周辺の著作を一気に読み漁るのは私の悪いクセであるが、そうであれば当然、似たような話を複数の本で散見する破目になる。案の定、前半は著者の他の著作の使いまわしのような、代わり映えのない文章が綴られて退屈である。 ところが、5章辺りからいきなりトーンががらりと変わる。そもそも、この章を境に、まったく別の本が合本になっているような感じなのだ。少々回りくどくはなるが、前半の軽妙だが浅薄な使いまわしとはまったく異なる、冴え渡る分析的記述が押し寄せてくるのだ。ベンヤミンの“パサージュ論”などを軸に、パリという都市そのものが持つ五段活用、つまり言語的・物語的行為が生き生きと展開されるのだ。 それもそのはず、巻末の初出一覧を見れば、あちらこちらの媒体に寄稿したエッセイらの数々をまとめた本書、あとがきには編集者の妙、つまり、このつながりにくい固有のテーマを、“五段活用”というタイトルで括ったクリエイティヴィティに対して、著者からの敬意が表されているが、実に、こうでもしなければ一冊として成立はしなかっただろう。 実に、“鹿島アンソロジー”のキマイラ=鬼っ子的著作である。(了)パリ五段活用
2006/12/12
コメント(2)
-

加湿器で、バーチャルすき焼き。
このテーマに合うかどうか、いささか心配ですが。実は、今住んでいるマンション、築年数が新しいこともあって、やたらに密閉性が高いんですよ。ま、暖かくていいですし、結露などもしないので、便利なのですが、とにかく乾燥する!!朝起きると、喉カピカピなんです。で、加湿器、買いまして。 もともと数年前にこのプラスマイナスゼロの加湿器が出たときは、いやはや、なかなか興味をそそられる逸品だなぁ、と思っていたのですが、いかんせんまだニーズもあまり感じることなく、またちょっとビビッドな色彩が、もう一つ…という感じだったのですが、気がつけばVer.3なんてのが出てたんですね。 今年は、ニーズと、さらにシックになったカラーリングを見て購入を決意。で、ここからが本題。もう、これだけ人気商品ですから、いまさらスペックは言うことなしでしょう。 さて、これまで加湿器なんぞ使ったことのなかった私。これが、寝室で使ってみると、なんともしっとり、いい感じなのですが、音がですね…すき焼き鍋のような音がするんですよ。よりによって真夜中、若干空腹気味な時間帯。 で、試しに、頭の中でバーチャルすき焼き、してみました。いや、空しかったですね。この加湿器、一定の時間を置いて、無音になったりグツグツと煮立つような音がするんですが、無音の時に、頭の中で、「まずは豆腐、豆腐。あ、端っこのしらたき、もう煮えてるよ」なんて突っ込んで、さらに煮沸音が聞こえて来たら「肉、肉!!もう肉、オッケーだって!!」と想像してみるのです。すると不思議と、鼻先に、あるはずのない醤油とみりんと砂糖の煮詰まった甘く香ばしい薫りが…。 もっとも、メーカーさんもこんな使われ方してるとは夢にも思ってないでしょうけれど、ほかにもそういう人、いるんじゃないかなぁ。どうでしょう?(了)送料無料/昨年発売のモデルからカラー変更と共にバージョンアップしての登場。プラスマイナスゼロ加湿器
2006/12/10
コメント(2)
-
“粒ぞろいな秘密”を出版します!?
いやぁ、『ふぞろいな秘密』話題になってますねぇ。あれだけPRすれば、印税暮らしも夢ではないかも。もっとも、本業の方はご無沙汰なので、“貧すれば貪す”。プライベート、それもデリケートなプラベートを切り売りするしかなかったのが本音でしょうけれど、ちょっと見苦しいですね。私はああいうジャーナリズムには否定的です。勿論、人の秘密や噂ほど、吸引力を持つネタはないのですが、ちょっといただけないですね。 先般、長い折衝の末、初の本を出版するご報告をしましたが、こちらにはその手の目引きは一切ないです。でも、心身の健康問題、異文化コミュニケーション、スピリチュアリティ、スローラーフなど、粒ぞろいなテーマを、なるべく丁寧に扱い直した一冊になっています。そう、こうしたキーワードも、あっと言う間に使い古されてしまっていますが、こうしたまだまだ価値があるけれど、消費されてしまったテーマについてもう一度深め、敢えて意味を問い直すことが、企画段階での私の目論みでした。 果たして、“粒ぞろいな秘密”を自認する一冊に込められたメッセージは、皆さんに伝わるでしょうか?(了)
2006/12/09
コメント(4)
全61件 (61件中 1-50件目)