2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年06月の記事
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-

『必殺シリーズを創った男 山内久司』
見出し:実録、一撃必殺の仕事人。山田誠二構成『必殺シリーズを創った男 山内久司』(洋泉社) かつて、大坂万博・三菱未来館人気の立役者であり、『ゴジラ』の生みの親にして黒沢映画のプロデューサーであった田中友幸氏の右腕として、現場面で辣腕を大いに振るった、田中友幸氏の興した企画会社の現会長にインタビューをさせていただいたことがあり、その後も公私にわたってあたたかい厚誼をいただいているのであるが、その会長とのお話の中でも、戦後日本のエンタテイメント文化は、激変に継ぐ激変の繰り返しであったことを教えられる。 刊行当時に買ったまま、棚で眠っていた一冊が、突然私を刺激した。ユーザー(視聴者)、現場(スタッフ・俳優)、そしてさらにもっと大きなもの、つまりは、局の上司であり、他局の人気番組であり、そして社会の動きの真ん中にあって、既存の時代劇のイメージを覆すのみならず、完全に革命を起こしてしまった“必殺シリーズ”のプロデューサー・山内久司氏に、必殺オタクを自認する山田誠二氏が、丁寧に、かつ鋭く切り込み、熱気溢れる後日談を引き出すのに成功している。 制作のことは、現場に身を置かなくてはいいものは作れない。このインタビューの底に流れるメッセージは、最大公約数的にまとめれば一言になってしまい、それも大づかみとしてはながちはずれていないが、その最大公約数にたどり着くまでの試行錯誤、いや、山内氏独自の理念と哲学、姿勢に裏打ちされた覚悟は並々ならぬものであったことがうかがえる。 文中、ハッとさせられるやりとりがある。恨みはらす裏稼業のストーリーに、臨終の時が迫っている時代感覚をさして、山内氏は「人々が腹立たなく、怒らなくなってきたんだな」「細かい不満はあるけど、現在の生活にみんな満足しているんです。内的にね自分のイメージの中で殺してるんですよ。バーチャルの中で」と述べているが、必殺シリーズ誕生が1972年、本書刊行が1994年。2007年の現在の社会状況を考えると、大看破である。 怒りや恨みを抑圧し、内的(および、内的な納得をもと)に殺す。それが心の時代を誘い、反社会的行為や暴力事件の遠因となり、やがては現実逃避的な精神世界への追従へと向かわせる、などという紋切り型の筋をつけるつもりはないが、やはり、ブラウン管の向うでスカッとできたからこそ、人がお金をもらって人を殺す、という、勧悪懲悪にエンタテインメント性を視聴者は鋭く感じ取ったに違いない。四方八方を丸く収めるインテリジェントな勝負勘を持つ、現場主義プロデューサー・山内氏の“アンテナ”の精度は、時代を超えてなお、強烈に高いと知れる。まさに、一撃必殺の仕事人その人である。(了) ■著作です:何のために生き、死ぬの?必殺シリーズを創った男
2007/06/30
コメント(0)
-
嘘評:おいしい空気、あります!!かたちなき悦びへの賛歌。
島田マサノリ著『空気はおいしい』(ゲッツ・パブリッシング) 気鋭の作家の風刺小説である。「おいしい水」、「体にいい水」。水、水、水!!なんで、ただの水がこんなに売れるのか?一過性のおいしい仕事以後、実体のない虚業のゆえに元の貧乏暮らしに戻ったアキラは、ある商売を思いつく。元手のいらない、おいしい、おいしい商売。 空のペットボトルを大量に集め、あたり構わず振りかぶってはキャップを閉じていく。夢中になって朝を迎えると、何もなかった安アパートの畳には、『おいしい空気』の詰まったボトルの山が!! かつての人好きのする営業トークで、この貴重な空気の入ったペットボトルを売りに出歩くと、これがアキラ自身も信じられないほどのバカ売れに。あっちでもこっちでも、注文が引きもきらない。毎日毎日空のペットボトルを虚空で振り回し、肩を壊し“生産”も追いつかない。やがて、この『おいしい空気』はネットで話題になり、通販の代理店契約の依頼で携帯電話が鳴りっぱなし。TVやラジオの取材、関連商品の企画の持込。空気を売って、財布は重たくなる一方。 「俺は夢を見てるのかな?いや、前もITで一山当てたんだ。みんながこの空気を欲しがってるんだ!!」。しかし、やはり虚業は長く続かない。的外れなやっかみ、そして真相。狂気の沙汰の夢の中で、己を失ったアキラは、ついに全てを捨てて社会から消え去ることを選ぶ。濡れ手の泡は文字通り気化し、“まずい”空気と消えたのだった。(了)■著書です:何のために生き、死ぬの? 意味を探る旅
2007/06/29
コメント(0)
-
沖縄。魂は、この海から飛び立ったか。
6月22日、夕方。突然の電話。沖縄で、浅からぬ縁のある恩人が急逝した。あまりに急な話。翌朝、キャンセル待ちでかろうじて那覇へ飛び、そのまま北部の港へ直行。お通夜は、島で行われる。午後の最終便の船で、島に到着。大きな家の居間に、その人はいた。突然死だったので、遺体は綺麗なままで表情も穏やかである。長患いと闘病生活の果ての死ではなかったのが、唯一の救いである。 島は暑い。遺体に、遺族が手ずから入れた氷も、すぐに溶けてしまう。大家族の主を支えた女性として、その家族や親戚、知人から愛された故人を、偲び、涙を捧げる人が家を埋め尽くす。 一晩明け、火葬する。小高い場所にある島に一つの焼き場へ、集まった弔問客の車やバイクが列をなす。 最後の別れ。焼いて、肉体を捨てたとき、人間はこの世から旅立つ。2時間後、肉体の残り、つまりは骨だけを遺して故人の魂は、無事虚空へと旅立ったようだ。このタイミングで、今度は文化の違う場所で、ふたたび“死と舞踏”することになるとは。 霊柩車の代わりに、バンに骨壷と遺影を載せ、黒い日傘を立てて、先祖代々の墓へとまた、弔問客が列を作る。黒い傘が、魂の旅立ちの御旗である。この列に、パトカーが途を譲る。魂を送り出したこの一行は、同じ道を通らずに、一筆書きのようにして、焼き場からお墓へ、お墓から故人宅へと移動しなくてはならない。 あまりに有名な、あの石造りの沖縄のお墓の中に、親族は集まり、せっせと墓掃除や花の設置をしている。 私は、仕事の都合で帰京せねばならず、いとまを請うてここから船着場に戻り、午後の便で本島に戻り、一路空港へ向かった。 思い返すに、常々生と死の問題は私のテーマであった。生と死は違うのか?はたまた、つながった環なのか。どちらかが入り口でどちらかが出口の、一つの世界なのでは…。そして、『何のために生き、死ぬの?』を書き上げた。 しかし、その原稿の時と今では、また死生観に関する私自身の想いも日々、少しずつ変わっているだろう。だが、離島から港に降り立ったとき、足下を潤す沖縄の海と、通り雨でよく湿った木々から発するミストに、ほんの一瞬身を浸して、水が、水の風土がこの世とあの世を結び、雨が、雫が、波が、あるいは気化を通じて魂を運んでいるのではないか、としみじみ感じた。 一種、知識や経験とは違う、特別な感覚でもって、魂を、この海から無事見送れたような、神秘的であると同時に、安堵の念が湧いた。 冥福を、よき旅路を、心の底から祈り念じたい。(了)
2007/06/27
コメント(0)
-

マッチポイント。
今日、久々に夕飯のあとたまっていた映画を一本観ましてね。『マッチポイント』。ジョナサン=リース・マイヤーズを推し続け、スカーレット・ヨハンソンに疑問符をつけてきた私。この作品では、ジョナサンは、『アメリカン・サイコ』のクリスチャン・ベールを思わせる業の深い役柄。うーん、やっぱり闇から光を臨むのは、かくも人を狂わせるものか…と。で、スカーレット。いいですね。これはハマり役です。 なんか、『真珠の耳飾りの少女』以降は、彼女がしっとり演じると逆にカマトトぶってる感じがしてイヤだったんですけど、こういう激しくて、ちょっと生々しい女性を演じると合うなぁ、と。生々しい、というのは、セクシーという意味ではなく、口汚く罵ったり、不安定な態度を見せたり、ちょっとテンパってる感じ。真相はともかく、素のスカーレットはすごくクールと言われるだけに、こういうギャップのある演技を観ると、やっぱり巧いのかなぁ、と思います。 全編にオペラが流れるんですよ。物悲しい、場面で。あ、そういえば『マッチポイント』、よく考えればあまりにもオペラ的な内容ですね。 で、重要なのは、これ、DVDですから。そのまま本編終わってしまうとメニュー画面に戻ります。本編観て、一服なんぞして戻ると、このメニュー画面で、あたかも映画の意外な余韻のように、ずっとリピートでオペラが流れてるんです。これが、イヤぁな意味で耳についてしまって、後味が悪い。投げた指輪はネットに当たって、どちらのコートに転がり落ちるのか…。いやはや(汗)。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?【ポイント2倍】マッチポイント(通常版)/ジョナサン・リース・マイヤーズ[DVD]
2007/06/26
コメント(0)
-

尽きぬ恨みの数々を、晴らす仕事の表稼業。
チャララ~…です。喇叭なんです。必殺仕事人。私、そんなに詳しくないですけど、個人的に中条きよし氏のファンなので。ついでにバラしますと、芸能界で取材してみたい俳優さんベスト3に入ってます。1位は草刈正雄氏ですね。もう永遠のアイドルですから。マルベルのブロマイド、机の上に貼ってますからネ。さて、 どこかで誰かが泣いている 誰が助けてくれようか この世は人情紙風船 耳をすませた奴は誰 泣き声目指して走る影 この世は闇の助け人 世の中の善と悪とを比べれば 恥ずかしながら悪が勝つ 神も仏もねえものか 浜の真砂は尽きるとも 尽きぬ恨みの数々を 晴らす仕事の裏稼業 ま、私、裏家業でも助け人でもない(闇ですらないですね)ですが、必殺シリーズのナレーションにひっかけて、 世の中、 事実がドラマよりも奇なるもので、 役所の不手際、企業の不祥事、 破廉恥漢に、こそ泥まがい 声なき声が啼いている 全ての道のその前に、 人倫の道がございます その道渡る六文を、 もたぬ弱きにうち変わり、 恨みを晴らす表稼業。 と嘯いてもみたくなるものです。三味線屋さんでも始めようかなぁ。まずは。■著書です:何のために生き、死ぬの? 意味を探る旅*我ら兄弟のバイブルです。邦題は無茶苦茶ですが、原題は“聖人”ですから。ま、我ら兄弟 は聖人の足元にも及びませんけど…。 ↓処刑人マイスタージャパン 必殺仕事人 BOX販売(予約:7月下旬発売予定)
2007/06/26
コメント(0)
-

スパイダーマン3は、Bすれすれの泣けるヒーロー映画。
ブログで顔を出しているほどには余裕がなく、結構タイトだったここ数週間。いまさらですが、ちょっと前にようやく『スパイダーマン3』、観てきました。 なかなか豪華でしたね。えぇ、キャラクターが。ま、“バトルロイヤル”とパンフにも謳ってありましたし、アメコミの世界って、もう作品名も何もかも、垣根を越えてバトルロイヤルしてしまうところが、一種読者にとってはカーニバル的な魅力があるわけで。 しかし幼少時代、ブラジルでテレビで見ていた“オーメン・アラーニャ(スパイダーマンポルトガル語)”ことスパイディー、すっかりダークで苦悩するキャラクターになってますね。ただ、X-MEN、バットマンらと比べると、基本コンセプトである“隣のお兄ちゃん的”な感じと、青春ドラマ的な要素はしっかり今回も踏襲されていて、スパイダーマン映画らしさ満載。 さて、バトルロイヤル。今回はコミック初期からの強敵・サンドマン、グリーン・ゴブリンjr.、そしてそして、ファン待望のヴェノム!! 結論から言うと、バトルロイヤルになっちゃうと、各キャラの個性が散漫になってしまうのが惜しい。そして、この手の映画の永遠のテーマ。X-MENもしかり、でしたけど。 特に、アメコミ全ジャンルを通じても、膨大なファンを持つヴェノムの扱い&登場シーンが少なく、今回は“オマケ出演”って感じでしょうか。あの黒い生命体が、今度は誰かに寄生して、スパイディーとがっぷり四つでバトルしてくれることを祈ります。だって、4、絶対あるでしょう??? 全体としては、130点のエンタテイメント映画で、雨後の筍のごとく公開されてきたヒーロー映画の中で、回を重ねるごとにクオリティをアップさせてきた唯一のシリーズと言えるでしょう。特に、スパイダーマン1、2は100点であえて止めてサム・ライミ監督も、今回は十八番のBテイストをふんだんに盛り込み、深刻なテーマの中にもユーモアや遊びゴコロもたっぷり。3でたたき出したプラス30点は、サム・ライミ節の分ですね。 サム・ライミ監督は、キャラクターに恵まれました。サムが好きなBすれすれのアクションもアイディアも、スパイダーマンならオッケーなんですよね。作り手と受け皿の甘い関係、というヤツでしょうか。 個人的には、アルフレッド・モリーナ演じたドック・オク、あの哀しげな黒い瞳が、ストーリーと相俟って、3を観た後でも2がフェイヴァリットですが、とにかく、さわかに泣けてしまうヒーロー映画。なかなか作れるモノじゃないです。(了)■著書です:何のために生き、死ぬの? 意味を探る旅SPIDER-MAN 3/ SPIDER-MAN vs VENOM & SANDMAN DIORAMAスパイダーマン3 ダイアモンドセレクト版 ミニバスト:ベノム カートン(仮予約)
2007/06/26
コメント(0)
-

iPhoneか、Phoneか。それが問題だ。
iPhone、プレスに露出し始めた頃から気になってました。いやぁ、すごい。デザインも勿論申し分ないし。ただ、私は様子見、かなぁ。 一つには、私はiPod第一次世代からのユーザーであり、miniもシャッフル現行モデルも使ってないんです。欲しいけれど、いかんせん容量が・・・。 もう一つの足踏みの理由は、昨今携帯電話の競争もひとまず落ち着きを見せたとして、MNPの勝負のピークも、予想していた時期ほぼぴったりに終わりました。 その結果、サービスはほぼ均一化し、電話会社側がいくら斬新なサービスを矢継ぎ早に出してきても、そうそう、乗っかる人は激減するでしょう。で、あとは機種レベルで、使いたいモデルがあるから携帯会社乗り換える、といったような可能性はあるとしても、ユーザー側の機動力はどんどん下がってくるのではないかと見ています。 今、プロバイダ契約不要のポータブルPC/電話が市場でしのぎを削っていますが、実際ミニPCとして使うユーザーはいても、それを電話としてまで、という人は少ないとか。結局、PCはPC、携帯は携帯、で使い分けているのが現状のようです。 新しもの好き、デジタルライフ好きの人でない限り、iPhoneを文字通り電話との併用にメリットを感じて利用する、というユーザーは国内では案外少ないのでは? iPhoneか、Phoneか。それが問題だ。(了)■著書です:何のために生き、死ぬの? 意味を探る旅WILLCOM(ウィルコム) PHS W-ZERO3[es](WS007SH) Premium version 機種変更(6ヶ月未満ご利用)WILLCOM WS004SH(W-ZERO3)《機種変更10ヶ月以上ご利用》
2007/06/23
コメント(2)
-
ビリー、もうワンセット!!
またまたビリーですよ。いやね、先日も書きましたが、本気で気になってる。それがまた、来日騒動があったものだから、なおさら気になってしまって。で、今度は弟が薦めるんですよ。「買いなよ」って、やたらに。おかしいなぁ・・・と思ったら、スポーツ続かない私が、すぐに飽きて“おさがり”してくれるのではないかという、淡い期待があったようで(笑)。そうは行くか!!さぁ、もうワンセット!!・・・あ、そうですよ、彼がもうワンセット買えばいいだけじゃないか!!(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?今だけポイント10倍!ビリーズブートキャンプ ビデオ版(ビリーバンド×1セット)
2007/06/22
コメント(2)
-
備忘録:本当に在った怖い男、再認識。
ユイスマンス。その存在そのものが変態的でフェティッシュな眼差し。錯乱すれすれな複雑にして神経質、几帳面な美の審判者。闇についてのその莫大な知の財産は悪魔からの贈り物と疑っていたが、そうではなかった。 あなたは、自己犠牲によって地獄の凍土に触れてきた、神の使いだった。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?
2007/06/20
コメント(0)
-
ビリー語録。~ここをどこだと思ってるんだ!!~
またビリーですよ。なんか、あの宣伝が目に焼きついて離れません。なんでも、器具はもちろんとして、付属のビデオだけでも十分楽しめるとか。収められた映像には、テカテカ汗で光りながら、“優しい鬼軍曹”が、次々と名言を吐くそうで、それが“ビリー語録”として話題になっているとか。なんか、痩せる、とかそういうことよりも、“優しく叱られたい”。そんなソフトなマゾヒズムを刺激してやまないのが人気の秘訣なのか、などとエロティシズム論や欲望論的観点から傍観しているのですが、もはや私も傍観してるだけでは我慢が出来なくなってきました。語録、聞きてぇ~ッッ。ビデオだけ見たいなぁ。本気で。(了)追)なんか、こんなイメージでしたっけ???■著作です:何のために生き、死ぬの?
2007/06/19
コメント(2)
-
元祖、ビリーズブートキャンプ。
はい、写真が我が家に伝わる元祖・ブートキャンプ。その名も“親父のブートキャンプ”。これは、スポーツ大好き、筋肉鍛えるの大好き、通販大好きな父が使っていたグリップで、相当ハードなもの。それを私が譲り受けまして、今日まで使ってまいりました。スパルタ教育。 20年以上は使っているのでしょうか、さすがに傷みが激しく、とくにカバー部分は完全に破損。おまけにプラスチックが溶けて来て大変。それをセロテープで巻き付けて使っていたのですが、このたびお別れすることに決めました。 痩躯な割に、握力ではあまり負けたことのないワタシ。その、アンバランスな握力を養ってくれた、“親父のブートキャンプ”に感謝を込めつつ、さらなる父の健勝を祈るのでありマス。なんか、父のことなので、ビリーズブートキャンプ買ってそうだけどなぁ。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?
2007/06/18
コメント(2)
-
子曰く、「仁者先難而後獲」
論語に〈「 子曰、「仁者先難而後獲、可謂仁矣。」(子曰く、「仁者は難きを先にして獲るを後にす、仁と謂うべし。」 )〉、というのがあったような。 この真髄を、ある企業の会長からうかがって以来それを、「美しいやせ我慢」と表現を変えて肝に銘じています。苦労が先で、収穫は後。当たり前だと思いますけど。 実際よく使われるこの“先難而後獲”、出来てない人の方が多いような。腹が立つ、というより野暮だなぁ、と思いますね。ニュース見てますとね…。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?
2007/06/18
コメント(0)
-
ルルドの泉。~奇跡と誤解と~
ヨーロッパでは、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステラと並んで、カソリック最大の巡礼地とされるフランスはオート・ピレネー県のルルド(正確にはルールド)の泉が、朝日新聞の奇想遺産というコーナーで、編集委員の竹内敬二氏によって、大々的に紹介されているとの報告が実家よりあったのが、およそひと月ほど前でしょうか。 記事の主旨としては、この奇跡の泉湧くルルドの聖域に聳える、大聖堂(H・デュラン、1972年完成)をソースに、ルルドの「明るい癒しの場」としての紹介でした。 その記事は、愛用のスクラップ・ブックに、カラーコピーしてファイリングしておきましたが、折しも、幸か不幸か、サイコセラピストである近藤裕氏との共著の出版のタイミングと重なっていたのでした。 何が幸か不幸なのか。それは、出版した共著は、ルルドへの旅をきっかけとした著書80冊以上のサイコセラピストと、私、文筆家/カウンセラーによる人生論、次世代的価値観の検討、そしてスピリチュアリティについて、ガチンコで取り組んだ一冊だったからです。しかし、ルルドというカソリックの聖地をフックとしながらも、宗教や信仰、信条を超えて、昨今のスピリチュアル・ブームとはまた違った視点に於いて、著者二人自身と、読者を、生きて死ぬこの生命の意味を問う旅に誘い、自問することをコンセプトとした一冊であっただけに、逆にメディアで採り上げられたルルドがきっかけとなった我々の共著が、特定の宗教に寄った閉鎖的な内容と受け取られることで誤解を受けたくなかったのです。 しかし最近、宗教とは関係なく、ルルドへの憧れや、一種の希望のようなものが、様々な場面で散見されるようになっている事実をまた別のルートで知って、今なら、むしろルルドから始まった拙著が、誤解されることを恐れるよりも、それを求める読者の方々にとって何らかのヒントになるのであれば、躊躇うことなくルルドと拙著の距離を公にしても良いのではないか思ったのです。 もはや、世に出てしまった一冊。あとは、読者の皆様が育てて下さるものです。この一冊が、誰かにとって奇跡となるか、誤解となるか。恐れることよりも、時勢に身を委ねることにしたいと覚悟を改めた次第です。(了) ■著作です:何のために生き、死ぬの?
2007/06/17
コメント(0)
-

エアギターもスゴい。
なんなんですか、コレ。エアギター・・・だけど。コードを押さえると、赤外線の弦が出るそうで、そこを弾くと音が出るとか。いやはや、巨大なキターケースは空間の無駄ってコト?(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?AIR GUITAR PRO エレキギター(レッド)
2007/06/17
コメント(6)
-

『パイレーツ・オブ・カリビアン』を、いつかこの…
最近忙しくて、飛行機の中でしか映画が観れていません。辛いです。今年見逃した&見逃してる大作系映画リスト。■『スパイダーマン3』:アメコミ好きな私。しかも、アメコミ映画では白眉の作り。甘酸っぱくて泣けますもん。でも、観れてない。■『ハンニバル・ライジング』:レクター博士、というよりG.ウリエル観たさ、だったんですけど。原作先に読んで、これは作品はダメだ。きっと映像の方が楽しめる、と直感したのに観れてない。■『300』:マッチョはどうでもいいけれど、『シンシティ』が良かったからなぁ。観たいですね。映像美的な意味から。私の親父は好きだろうなぁ。古代ローマ・ギリシャネタ大好物。■『パフューム』:もうこれはDVDで。香水マニアを自称する私には欠かせない一作です。そして、■『パイレーツ・オブ・カリビアン』:単純に、スカーンと楽しめる映画って、細菌減ってるし、しかも続くとコケるけれど、これは好きだなぁ。子供の頃の夢が海賊だったし。でも、観れてない。 と、書いたところで、コレご存知ですか?あ、そうですか。私、知りませんでした。すごいなぁ、ジャックの船の操舵を模したDVDプレイヤー。しかも、リモコンがあの北を指さない羅針盤ですと!!参りました。マニアックです。 スター・ウォーズマニアでもある私でして、SWグッズに関してはかなりディティールにうるさい私(リアリティとか、精密さだけでなく、遊び心の面でのシーケンスやコンセプトの落とし方などについてです)ですが、このDVDプレイヤーも相当なもんだ。もし『パイレーツ~』も見逃したら、このプレイヤーで観ることにします。。。(了)追)余談ですが、先日一度チャンスがあって、新宿三丁目のマルイ新装オープンも素見そうとシネコンに行きましたが、まぁ、観客導線がまったくなってないですね。あれじゃ、映画目的の人は行かないですよ。映画別に並ばせればいいものを、全部ひとくくり。その日は『パイレーツ~』目当ての人ばかりだったのに、『スパイダーマン3』を観に行った私まで、チケット買うだけで一時間待ちです、と平気で言われました。アタマに来たなぁ~、流石に。「次回の上映まで、お買い物でもされては?」とでも言うつもりでしょうか。導線は考えた方が良いですね、ああいうチケット売り場を広く確保できない施設では。パイレーツ・オブ・カリビアン DVDプレーヤー【パイレーツオブカリビアン ジャックスパロウ方位磁石】パイレーツオブカリビアン デッドマンズ・チェスト(Limited Edition) 【デイヴィ・ジョーンズの宝箱】
2007/06/16
コメント(0)
-

『健康問答』
見出し:健康に答えはない。笑いはある。五木寛之・帯津良一著『健康問答』(平凡社) とにかく、笑える一冊だ。可笑しくて可笑しくて仕方がない。健康問答。肩肘張って、病因渦巻き、病院難民迷えるいまの世の中である。酒は百薬の長か?メタボリックは?岩盤浴は?塩分の採り過ぎは?マクロビオティックって? およそ世の中は健康に対して神経質になり過ぎているのかもしれない。その答えを、名文家と名医が組んで書いた本なら、きっと明確な長生きの秘訣が書かれているに違いない、と思うことだろう。 その期待は気持ちよく裏切られる。我々を脅かす健康情報に冷や水を浴びせかけ、捏造された情報を笑い飛ばす。 しかし、である。帯津氏の、愛嬌たっぷりの発言の中に、しっかりとした経験値と医学的見地からの鋭い意見もあり、だからこそこの和やかな“深刻本”に信頼という名の重みが備わってくる。 今、健康について迷っている人は、是非一読し、まずは気の病から治そうではないか。健康の尺度は人それぞれ。健康である、というジャッジは、結局医師のアドバイスを受けて、自分が決めるものなのかもしれない。近頃食欲不振だった私は、早速パン二枚にヨーグルト、チーズ3片に、自らベトナム珈琲を湧かして満腹になり、朝の一服を愉しんだ。 “心気症社会”に効果覿面の一錠。ただし、「これ一つしかない」「これだけで解決だ」という売り文句に疑問符を付ける「中道の五木流」に倣うならば、気になる本をもう一冊手に取って、自分なりの健康観を養うといいだろう。 全体が対話式になっているのは読みやすく、はからずも帯津氏に推薦文をいただいた拙著にもダイアローグを盛り込んだことは奇縁であり、必然という名の偶然というしかないが、同時に、こちらが健康問答なら私たちの著作はその合わせ鏡、生き方問答と言えるかもしれない。(了)追)まったくの偶然だが、下記の三冊は異なるチャンネルから作られ、結果的に一つの環となった三巻本と言ってまったく嘘はない。健康、心の問題、生き方。三冊揃えて、是非ともトータルに生きる意味を問う旅を続けていただきたい。
2007/06/16
コメント(1)
-

四角い赤ら顔の電波時計。
たまには力の抜けた記事も。ちょっとキッチンの時計が調子悪くなったので、手頃で見やすい時計を探していました。それも電波時計で。25センチでほぼ正方形、大きさもバッチリ。無機質になりがちなキッチンに、赤い文字盤がアクセントになって、色気が出て来ました。四角い話がまぁ~るくなるかどうかともかく、“四角い赤ら顔”、なかなか素敵です。(了)電波掛時計「アトリエM431」リズム時計 8MY431AT06
2007/06/15
コメント(0)
-
嘘評:嗚呼、素晴らしき哉、嘘のない世界。
星野一路著『この素晴らしき正直社会』(ムーア新書) 時は2056年、地球。IT社会と呼ばれた時代は遠い昔となり、引きこもりが当たり前の時代。21世紀前半に問われた社会の嘘や倫理の逸脱、信頼の欠如を一掃するため、日本が旗ふりとなって推進した「正直な地球・構想」は、急ピッチで進められた。今や、ホログラム搭載の最新式コンピューターが各国民に配られ、セル(現代の自宅)を一切出ることなく、社会生活が営めるように配慮されている。セルから出れば、いかなる嘘に出会うか分からないからである。 このライフスタイルは、嘘のないグローバリズムを一気に実現し、もはや国境そのものが意味をなさず、したがって戦争も格差をも解消してしまった。 一点、このセル社会=「正直な地球・構想」の中で生きるには、すべての個人情報は開示されなくてはならない。虚偽のプロフィールで籍を得たものは、直ちに「特別治安維持エージェント」によって逮捕されてしまう。裏返せば、嘘のない社会実現は、個人情報の一元管理システムにほかならなかった!! しかし、である。この世界では、相手が誰か、善人か悪人か、男性か女性かを勘ぐる必要などない。すべてのメッセージには真実が溢れ、そこで得られる情報や関係に、嘘は一片もないのである。 コミュニケーションの技術のいらない社会。疑心暗鬼から自由な社会。誰もが正直な世界。嗚呼、素晴らしき哉、嘘のない世界。痛烈な社会風刺小説である。(了)
2007/06/15
コメント(0)
-
書評:“おしゃれ”という記号が生んだ珍事
北山晴一著『おしゃれと権力』(三省堂) 人がイチジクの葉で裸体を隠してから、“衣装”がファッションになるまでには相当な時間がかかった(無論、人類の歴史の中で、ではあるが)。このことは洋の東西を問わないようであるが、ことファッションとモードの街・パリにおいては、美的センスが特殊にして洗練されていた日本のそれと比べると、はるかに長大な時間を要したことを知る。 そこには、パリの闇にねっとりとこびりつく汚物の神聖化、汚物崇拝というスカトロジーやネクロフィリア的メンタリティーの伝統があったことは、“おしゃれ”が記号化していく前夜の珍事である(だからして映画『パフューム』は、何も荒唐無稽な作品ではなかったのだ)。 やがて、主に衛生学の観点から、衣服は衣装になり、衣装はおしゃれ=ファッションとなり、豊かさと権力の記号へと変貌していく。ファッションを消費文化の動力にしたのは、デパートの発明であるが、同時に、既製服の誕生で、オーダーメイドが当たり前だった服飾文化の衰退を誘引した。何しろ、“デパート以前”では、女性よりも男性の方がファッションにお金を費やしていたのだ!! 貴族階級および新興ブルジョワの奥方たちが生み出すモードはすぐに、ハイライフに憧れる中流階級の憧れの象徴となり、安価な既製服がデパートという劇場装置で多売されていく。この大量生産、大量消費、それも、ハイクラスではなく、ハイクラスの模倣を志向するミドルクラスの欲望を駆り立ててやまない見えざる実効力(タイトルの“権力”とは、おそらく記号が発効する拘束的な行動を規定するものとしての“権力”と解されるべきだ)が、莫大な儲けをもたらすと知ったからには、門外漢が投資し抱え込んで、一山当てようと躍起になったのも頷ける話しだ。現に、こうした他人のまわし、ならぬ土俵に靴も脱がずに上がりこんで相撲を取ろうとする破廉恥な新興成金の恥図は、今もって後を絶たない。 “ポスト・デパート”の珍事としては、この権力化した“おしゃれな記号”が、上流階級の女性による万引きのルーツとなったことや、デパートという欲望実現の伽藍が、痴漢(あまりにフェティッシュでここに書くことかなわぬのが残念だ)の発祥の場となったのは実にさかしまで面白い。 全体に読みにくく、思わず目を剥く一節もない代わりに、資料的価値は高く、実に、質実剛健、誠実無比な一冊といえる。特に、服飾業界に身を置く方にはぜひとも手にとっていただきたい文献である。(了)
2007/06/15
コメント(0)
-

別に、欺瞞でもイイじゃないか。
クリック募金は長いこと何となく気になってはいた。しかしそうしたボランティアや寄付行為を、偽善だ、欺瞞だといった知人の言葉が10年以上頭に残っていて、どうしても次のステップに踏み出せないでいた。 しかし、これからは豊かさの価値観も変わる。一部のなりふり構わぬ拝金主義を除けば、みんな物的な豊かさとは違う豊かさを求めることになるのではないか。いや、そうならなければ、結局苦しむのは自分自身だろう。 ノーブレス・オブリジュという言葉が死ぬ。いや、意味を変えて生き返る。物質的豊かさとは違う豊かさ(その答えはそれぞれだろうけれど)を持った“美しく尊いクラス”の人々が、高貴な慈しを支えていく時代が来る。だから、今は欺瞞や偽善でも何でもいい。とにかくまずは私自身の価値観を転換するため、アクションを起こしてみようではないか!!(了)
2007/06/15
コメント(2)
-

本に登場する映画『ガッジョ・ディーロ』
毎日本のこと書いてると、私としては心苦しいのですが。今日は著作『何のために生き、死ぬの?』に出てくる映画を一本紹介します。 作品は『ガッジョ・ディーロ』。父の意思を継いでロマ(ジプシー)のある歌を求めてパリからやってきたステファン(ロマン・デュリス)が、ロマの老人・イジドールと生活する中で、触れ合い、気づき、出会うのは果たして・・・。その答えについて本の中で私流に解釈して採り上げているのですが、この映画はサントラも素晴らしいんです。入手困難なのが惜しいです。トニー・ガトリフ監督作品は、なぜか縁があってどれも観ているのですが、特にこの『ガッジョ・ディーロ』は好きな一本です。(了)ガッジョ・ディーロ(DVD) ◆20%OFF!【送料無料選択可!】ルパン / 洋画
2007/06/14
コメント(0)
-

『七宝の魅力』
見出し:目にも艶やかな七宝の世界。菊池昌治『七宝の魅力』(小学館) ここ数年の高級時計ブームにあやかれば、クロワゾネ、と書いた方がピンと来るのだろうか。勿論、これ七宝焼のことである。 海外を旅していて、日本で七宝焼を見かけるより、クロワゾネを施した少々高価な工芸品や作品に出会うことがあった。その、色とりどりの飴が溶け込んだような、何ともいえぬ鮮やかさ。そして、色彩の水溜まりを思わせる何とも艶っぽい魅力は、いつしか、心の、ほんの片隅を占めるようになっていた。 私は、文章を書くのが仕事だが、やはり時々実験をしてみたくなるものだ。これまでは、五感で味わう文章を目指して来たが、ふと、今度は文章に七宝の要素を採り入れてみたいと思いついたのである。果たして、それがどのような方法で、どのような形で、いつ実現するか、まったくもって未知数であるが、なんとか奮闘して形にしてみたいものである。 本書は、豊富で美麗な写真が多用され、日本に於ける七宝焼の歴史と現在が概観できる。お茶器からジュエリーまで、幅広く収めたヴィジュアル・ブックであるが、白眉は、何と言っても赤坂・迎賓館の箇所である。(了)備忘録:工芸技法のひとつ。などの金属製の下地の上に釉薬(ゆうやく:鉱物質の微粉末を水とフノリでペースト状にしたもの)を乗せたものを高温(800度前後)で焼成することによって、融けた釉薬によるガラス様あるいはエナメル様の美しい彩色を施すもの。中近東で技法が生まれ、シルクロードを通って、中国に伝わり、さらに日本にも伝わった。大勲位菊花大綬章(副章)など日本の勲章は、七宝焼きの物が多い。(Wikipediaより抜粋、引用、一カ所のみリライト)七宝の魅力
2007/06/14
コメント(0)
-

著作、ネット販売開始。
寝耳に水と申しますか、共著のネットでの取り扱いが開始しました。書店にも足を運べていない状態。なんと珍しいことに、先にネット上で自著を発見することになるとは…。ネット上ではピックアップされるのに時間がかかると聞いていましたが、こんなに速いとは。感謝感謝。これからは、書店のみでなく、ネットでも購入できます。(了)何のために生き、死ぬの?
2007/06/13
コメント(2)
-
著作、反応それぞれ。
過日上梓しました『何のために生き、死ぬの?-意味を探る旅』(地湧社)。予約注文分および謹呈献本分より配本と相成りまして、今週には書店でも目にすることが出来るかと思います(ネット系書店では少し遅れるとも…)。 先にご一読いただいた方からは、様々な反響や感想をいただいております。その詳細をここでオープンにすることはかないませんが、「対話部分が馴れ合いになってないのがいい」、「対話する同士の年齢が大きく離れているのが新鮮」、私のパートに関しては「本来意識しない死生観に取り組んだ4章が、なぜか身近に感じられた」、などご意見をいただきました。今後この本がどのような旅に読者を誘い、また本自身が旅をしていくのか、楽しみになってきています。(了)
2007/06/12
コメント(1)
-

迷うための占いならイラナイ。
なんなんでしょう、ベトナム帰国以来、三週間も咳が止まらないのでして、周囲では様々な憶測と疑惑が渦巻いていますが、原因は明瞭。お気に入りのジャケットを現地で紛失、現地の気候を考えて薄着しか持っていなかった私は、バッチリ機内で風邪引いた、という案配。その後は、いくつ顔があれば足りるんだ?というほど慌ただしい毎日でして、ちょっとブログから遠ざかっていました。と言っても、一日か。 唐突ですが、占い大好きです。これは過去記事にも書きましたね。で、良いことだけ信じるのもムシがいいってんで、一応悪いことも信じて自分なりに公平感を保ってみたりなんかして、なんて話も書きましたよね。 最近、ふと思ったこと。占い、多いに結構。でも、本気でのめり込んで、迷うための材料にするなら、占いはイラナイってコト。無論、私はげんはかつぎますけど、占い崇拝者ではないので、占いの結果で迷ったり躊躇ったり、なんてことはないのですが、結局、それが天命であれ運命であれ、導きであれ、最後に選択するのは自分自身ですし、頭から妄信して優柔不断になるくらいなら、占いなんかしない方がいい、って思いますね。 ちょっと迷ってる人がいて、そんな話を聞いたので、自分にあてはめて考えてみた早起きは三文の徳。(了)*とか嘯いて、結構この本、好きだったなぁ。 ↓ 誕生日事典
2007/06/12
コメント(0)
-

『何のために生きるのか』
見出し:何のために生きるのか。五木寛之、稲盛和夫著『何のために生きるのか』(致知出版社) どこかで見たようなタイトルである。さておき、蔵書のうちの数パーセントにも満たない、140本足らずの書評をざっと一覧いただければ分かるように、私が、こうしたジャンルの本を手にすることは実に稀である。一つには、まだまだこうした人生哲学や実業ジャンルの本を手にするにはあまりに若すぎると言うことと、本来自身が割かねばならない読書時間は他のジャンルのためにあるという思いもあった。 と、同時に、サラリーマンを経て経営者にもなった父の本棚には、ありとあらゆるこの類いのジャンルの本が所狭しと並んでいたので、その気になって実家に戻れば、最新のベストセラーが常に揃っているという理由もある。 ふたたびタイトルである。そう、私たちの共著とニアミス寸前のタイトル。無論、この本の存在を知って、著者二人の一存(二存)でつけたのでなく、出版社との編集会議の中で、多数の候補から絞り込んだのではあるが、つくづく、今、生きる意味を問うテーマの本が、引きも切らず読者へと発信されているのだと痛感する。 この、滅多に手にしないジャンルの本をあえて手にしたのには二つの理由がある。一つには、私たちの近著とどのようなシンクロがあるかを確かめたかったこと。いま一つは、どう違うのかを把握しておきたかったこと、の二点である。 いくつかその結果を挙げてみると、●五木氏、稲盛氏が、仏教を拠り所に“情(こころ)”と呼んでいるものを、私たちの共著では、近藤氏は“スピリチュアリティ”と呼び、私は“知性”と呼んでいるが、根底に在るスタンスは一致していた(無論、本書で否定される頭でっかちなインテリジェンスと、私の考える“知性”の全く異なることは、著作を読んでいただければ分かるであろう)。●五木氏が「現代日本には歌がない」と述べている点は、音楽業界の片隅にもいる私としては、納得のいく部分と、複雑な感情との両方を抱いた。●本書が、同じ年代生まれの対談形式になってる内容については、逆に私たちの共著が約半世紀の年齢差のある二人が書き対話している点、赴きと視点が違って、遠慮がなく面白いかもしれない。とりわけ、どうしても現代人の情操面での枯渇が、テレビゲームの罪に帰されている点は、テレビゲーム世代で育った私としては、若干結論と断罪への飛躍を感じてしまったが、そこもまた世代間の意見があってしかるべきであるし、私の意見は共著にしっかり盛り込んだつもりだ。●本書における“利他”の思想、および慈しみの精神が、私たちの近著において私のパートで述べた、自己愛とどう違い、どう絡むのか(私としては、ほぼ同じ意味と考えているが)、これは私自身が深堀していきたい。 さて、『何のために生きるのか』を読んだ。次は、近藤氏との共著『何のために生き、死ぬの?-意味を探る旅』(地湧社)が、いよいよ週明け半ばから書店に並びだす。この二冊が、個人的には合わせ鏡のように感じられてならないのは、著者故の思い入れのみには非ず、である。(了)何のために生きるのか
2007/06/10
コメント(0)
-

『デパートを発明した夫婦』
見出し:経営者に教えたくない一冊。鹿島茂著『デパートを発明した夫婦』(講談社現代新書) 論語に、〈子曰、「仁者先難而後獲、云々…」〉という言葉が出てくる。つまり徳のある人は、先に困難に臨み、見返りを後とする、ということである。 さて、また鹿島茂本か、と言われてしまいそうであるが、そうなのである。アタマのなかの情報シナプスがそう支持したのだから仕方がない。 パリにはじめて近代的なデパートを作った(発明したというべきだろう)のみならず、当時の中産階級に対して、常にモードや流行、洗練されたハイライフへのヒントを、天賦の才に裏打ちされた、入念なアイディアによって提供し続け、消費文化および消費行動そのものに大革命を行った〈ボン・マルシェ〉のブシコー夫妻の“経営戦略”を学べる一冊である。そうした点、著者自身があとがきに特別な思い入れを記しているように、読み手としても他の鹿島本とは違う視点でページを繰ってしまう。 この消費の劇場たる〈ボン・マルシェ〉の役割は、「誘惑」→「消費願望」→「消費」という消費資本主義の構造そのものを作ったことにああるが、実際には、最終段階である「消費」そのものは添え物とさえ思わせる、「〈ボン・マルシェ〉に足を運ぶこと、そして、〈ボン・マルシェ〉が発信する流行に敏感でいること」というステイタスを獲得する場に仕立てたことこそが、結果的に商売の大成功につながったようである。 この消費願望の刺激と、消費劇場の誘惑は、上流階級夫人をして万引きせしめたというから、その欲望装置の精度たるや、端倪すべからざるものがある。 さてしかし、はたしてこのデパートを発明したブシコー夫妻が、「売らんかな」一点張り、成功体験やブランドや肩書きだけで、平気な顔して「粗悪なサービスを高く売りつける」金の亡者であったかと言えばまったくその逆である。 お客様を楽しませ、満足させ、徹底して接客から内装まですべて落ち度のないよう細心の注意を払ったばかりでなく、従業員の待遇、ルールの設定、そして慈善活動まで、「売名」でなく志で行ったことがまた特筆すべき点である。夫唱婦随の美しいモデルとしても記憶しておきたい。まさに、「仁者先難而後獲」である当時に、あまつさえ“「後獲」の後”にも施しをしている。経営者の鑑というべきか。 この一冊には、今後淘汰される運命の足音を耳にし始めている現代の企業には手遅れだが、まだまだ手の施しようがあるいささかの善意の在る企業の経営者にとっては、虚業から実業への転換への大きなヒントとなるだろう。少し、意地悪な言い方をすれば、だからこそ経営者に教えたくない一冊なのである。(了)デパートを発明した夫婦
2007/06/08
コメント(0)
-

帯津良一先生にご挨拶。
今日は、著作に推薦文をいただいた帯津三敬病院名誉院長の帯津良一先生に御礼かたがたご挨拶にうかがいました。帯津先生とお目にかかるのは今日で二度目。かつては読み手として、今回は書き手として。 帯津先生は、ホリスティック医療(全人的医療、つまり身も心も丸ごと見ていく医療のあり方)に取り組まれておられる方で、現在五木寛之氏との共著『健康問答 本当のところはどうなのか? 本音で語る現代の「養生訓」』はじめ、著書が常にベストセラーにランクインする“人気の語り部”でもあります。 本日お顔を拝見して、私の学生時代の恩師(謹呈に対して本日コメントをいただいたのですが…)が、「あの先生は、患者が顔を見るだけで病気が治ると言われている先生」とメールで仰ったのを改めて痛感。 医療について門外漢の私が、先生のホリスティック医療の要である“ヴァルネラビリティ”というキーワードを、まったく快筆紳士的に解釈し繙いてみせたことに対して、齟齬がなければいいが、と心配しつつ、きっと私の意図したことは汲んでいただけるのではないかという、希望的にして確率の高い予測を抱きながら、素敵な推薦文に感謝してきた次第です。(了)健康問答
2007/06/07
コメント(0)
-

『ベル・エポックの肖像』
見出し:M男を束ねるドS女優、その激しい生き様。高橋洋一著『ベル・エポックの肖像』(小学館) 実に真面目な一冊である。例えば、たびたび書評で採り上げて来た鹿島茂氏の文体や、本そのものに掲げるコンセプトには遊び心が溢れて(ときに溢れかえって)いるが、同じベル・エポックを描写させても、本書は、実に真面目。丁寧に、丁寧に、サラ・ベルナールという希代の名女優、ベル・エポックのミューズを軸に、彼女の生き様を通じて、人間関係および時代との関わりを記述していく。個人的には、サラの南米公演では、ブラジル帝国皇帝ドン・ペドロ二世との接点があったことが、今度は私と伯仏関係を整理するクリップとなったのはありがたかった。 さすがに図版も贅沢で、書名は『ベル・エポックの肖像』となっているが、実際は副題である“サラ・ベルナールとその時代”をテーマとした一冊として資料的価値も高く良書である。 さてしかし、いかにサラが、抗いがたい魅力を持った女王だとしても、私はきっと惚れることはなかっただろう、と格の違いを無視して、一組の男女の目線で考えてみる。 彼女の生涯を振り返って、その人生に影響を与え、彼女を磨きあげたのは、彼女自身以外はすべて、M男だからである。敬慕するM男でドSなモンテスキュー伯爵が、彼女とは良好な交友関係を続けたことは、何とも嬉しいことである(艶っぽい噂もあると聞くが、私は二人に関係はなかったという説を勝手に支持している)。 とまれ、芸術への貢献は不動にして至高なれど、“ドラキュラ作家”B・ストーカーをして「女吸血鬼だ」と言わしめる、傲岸不遜、ドSの女王、その繊細にして大胆な気まぐれの生涯はあまりにはた迷惑で、亭主関白でもない私でさえ、あまり懇ろになりたくないものだ。などと感じてしまったが、サラとの関係を夢想している時点で、あるいは、もう彼女の魔力にとらわれているのかもしれない。 全体的には駆け足の一冊であるが、むしろそれが良い。かように、テーマが濃密で過激に過ぎるからである。(了)追)親切ではあるが、注釈とページのレイアウト上のズレが若干大きく、読みづらい感があるのは残念だ。ベル・エポックの肖像
2007/06/06
コメント(0)
-
嘘評:コメディなり、腹黒き夜会。
小野田丸作著『人間模様、喜劇』(月蝕書院) 人間の集まるところには、輝きとともに汚泥が渦巻いて仕方がないようだ。宴会好きで“コネクション大好き”なフィクサー部長が作る通称「社交サークル」に、幹事補佐(つまりは体のいい追廻である)として巻き込まれた新入社員・雄悟。この「社交サークル」には、企業のトップから政治家、物売り、似非芸術家やら、ちやほやされたい淑女が集まってくる。 雄悟は、連日の宴会の店探しから、案内告知、予算から会費の回収まで、こまごまとした作業をしながら、実は、この不思議な人間関係を、時には間近で、時には鳥瞰で冷静に分析できることに気づき、やがて、そこで繰り広げられる腹芸や失態を、愛おしい気持ちも込めて、喜劇として楽しむようになる。 やがて雄悟は、何もかもが喜劇的にバカらしくなって、早々に退職し、田舎へと帰って行くのだった。(了)
2007/06/06
コメント(0)
-
著作は予約分から…。
過日地湧社より上梓しました共著『何のために生き、死ぬの?-意味を探る旅』が、まずは予約注文分・謹呈分から配本スタートしました。発行日が6月10日になっておりますので、書店などでは今週末から来週半ばにかけて著作が並び始めることと存じます。 発売中、でも本屋で見つからない!!という読者の皆様へのご連絡でした。どうぞよろしくお願いいたします。(了)
2007/06/06
コメント(0)
-
画家からもらった「どこでもドア」。
幾度か旅を共にし、「騎士道精神を捧げるにふさわしいレディ」と呼んで敬慕する、画家のY女史から、このたびお祝いに一枚の絵を譲っていただいた。 小柄な躯から発する快活なエネルギー、ユーモアのセンス、姉御肌の気っ風の良さ、何より、誰にも悟られることもなく、細部にいたるまで心配りの出来るこの“大先輩”(失礼!!)は、先頃銀座の文芸春秋社のギャラリーでも個展を催された。 そのY画伯(ここからは画伯と呼ぼう)の展覧会で、数ある作品の中から一番気に入った作品を、心底絶賛したところ、その作品を惜しげもなく下さったのである。 そろそろ書店にも並び始めるであろう著作を一読いただければ、このスペイン情緒溢れる街路を、市街から5キロも離れたカンポの丘を拠点に、画伯自身が惚れ込んで描き上げた作品は、ただ作品として素晴らしいだけでなく、私自身の生得的な郷愁を激しく刺激して止まなかった。 その作品を、壁に飾ってみた。するとどうだろう。あたかも、そこが血なまぐさい戦争があったとはいえ、巧みに怨敵の長所を柔軟に吸収したスペインの、イスラム文化を融合した美しい街路に、この額縁をくぐり抜けて、すぐにでも訪れることが出来そうな想像を膨らませずにいられないのである。 パパからもらったクラリネットではないが、この記念すべきタイミングに、敬愛する画伯より賜った私にとっても思い入れ深い作品は、さながら「どこでもドア」のように、いつまでも、この愉しいイマジネーションを掻き立てて止まないだろう。(了)追)私が撮った写真が、失礼ながら画伯の作品の価値を貶めているとしたら、これは無礼に当たるが、この場では何とぞご容赦いただきたい。
2007/06/04
コメント(2)
-
ZARDが遺したイメージ。~思わず走りだしたくなる曲~
ZARDらJ-POPが次々とヒットチャートを賑わせていた頃、私は、日本では到底その真髄に手が届かない音楽、つまり今でこそ音楽ビジネスのマーケットの中心にあるR&Bやレゲエ(特に、レゲエに至っては、当時殆ど日本国内で情報がなかった)に心酔し、実際、日本の音楽シーンにじっくり対峙し耳を傾けるだけの財力も時間もなかった。 ZARDと言えば、年に一度のテレビ番組で、芸能人の24時間マラソンの最後にかかる音楽、応援ソングとしてのイメージしかない。 そこで考えたのが、走ることと音楽の関係。高橋尚子氏が、HITOMIの曲をイメージトレーニングに愛聴していた逸話すらすでに随分昔のことのように思える今日この頃であるが、「思わず走りだしたくなる曲BEST3」を、拙い知識ながら挙げて見る。「思わず走りだしたくなる曲BEST3」1:“RUNNER”(爆風スランプ)2:“トレイン・トレイン”(THE BLUE HEARTS)3:“負けないで”(ZARD) あまりに貧困なイメージかもしれないが、異論はあまり出そうにもない、とも思う。いずれにせよ、何かの形で、永きにわたって“あるイメージ”を設定した時、想起される一曲を遺したZARDの、日本のミュージック・シーンへの足跡は様々な意味で大きかったのではないだろうか。 遅ればせながら、冥福を祈りたい。(了)
2007/06/03
コメント(0)
-
パトグラフィー(病跡学)と伝記。この難しさ。
誰か(特に、一般に天才や英雄などと呼ばれる人物)の行動や行為、メンタリティなどに垣間見える特殊な要素を、生育歴の中でも、特に病に関することについて分析する。これをパトグラフィー(病跡学)と言い、ドイツの精神科医メビウス(メービウスとも。“メビウスの環”で有名)が二十世紀に提唱した。 伝記を読むに際して、このパトグラフィーが諸刃の剣となる。とかく伝記の感想や書評ほど難しいものはない。人物の紡ぐ歴史は、角度によって様々な文様を見せるからで、その伝記の、さらにまた感想を述べると言うことは至難の業に等しい。 一方で、伝記から立ち上がる、「ある人物」の行動が幼少時の体格や健康状態、あるいは精神的な健康状態に影響されていることを頭に入れて読むことで、納得と同時に前提条件を受け入れた形でのミスリードを誘う可能性がある。 特に、書簡集などは、伝記でないにしても、「ある人物」の思考や行動を知るにあたって貴重な資料となるわけだが、これを、テクストとして読むか、パトグラフィーを通じた言語的サインと読むかによって、文章化された情報そのものが大きく左右に揺れることになる。 文学にせよ、伝記にせよ、パトグラフィー的に文章を読む癖が昔からあり今も抜けない私は、「ある人物」が登場する書物を手に取るたびに、なんとも複雑な気持ちになるものである。(了)
2007/06/03
コメント(2)
-

『怪帝ナポレオン三世』
見出し:皇帝は、辣腕オタク・プロデューサー。鹿島茂著『怪帝ナポレオン三世』(講談社) 総ページ数478ページ。晩酌ならぬ晩読にはいささか手首に負担の大きいこの一冊、なかなかどうして、その筆力と切り口の意外さで、あっという間に読ませる。 ルパン三世を知っていても、偉大なる皇帝ナポレオン・ボナパルトの甥、ナポレオン三世について知っている人がどのくらいいるだろう。それも、著者が一般的な誤解を指して「バカで好色なダメ皇帝」と表現する以上のことを。 私は、ナポレオン三世のみならず、お洒落な、憧れの街パリの現在をこの過小評価された皇帝の右腕として作り上げた知事ウージェーヌ・オスマンの業績と二人の関係を知りたくて手にした本書であったが、この怪帝は、花の都(怪帝以前のパリは、映画『パフューム』のそれ、つまり鼻梁も曲がらんばかりの汚臭と汚物の“博覧会場”であった)のみならず、さまざまな分野において、現在喝采を受ける潮流を生み出した辣腕のプロデューサーであったことがよくわかった。つまりは、ファション、低所得者への福祉政策、そして美術界では当時酷評されていた印象派の大きなうねり…。あるいは、彼のメキシコ介入で、南北戦争直後のアメリカとフランスがつながり、もって私自身の仏米関係にも接点が生まれた。 「皇帝民主主義」、「弱者のための帝政」という、なんとも綱渡りのような曲芸を、わずかな期間とはいえ実現させた、著者が頻用するところの「端倪すべからざる」皇帝ナポレオン三世、その複雑怪奇でファンタジックな思想と行動、つまり天下百年の計は、一種の徹底した誇大妄想から生まれた実践と知ると、彼の躯に流れる英雄の血脈は決して薄くはなかったと知ることになるだろう。 300年先に生まれた、辣腕でないオタク・プロデューサー、ルドルフ二世との違いは、筆者の「実質的にフランスのために伯父以上の実績を成し遂げた」という締めくくりの怪帝評に集約されている。(了)怪帝ナポレオン3世
2007/06/03
コメント(0)
-

袱紗にバカラ。
ここ一年くらい、ブルーと渋金のカラーの組み合わせの可能性に魅力を感じ、取り憑かれておりまして、この色の組み合わせのものには片端から目が行ってしまうのです。 で、古袱紗。茶会で器を拝見する時に敷いたり、特別なお茶碗でお点前をいただくときに使う小さな袱紗ですが。このダークブルーと、まさに渋金の刺繍がなんとも風雅で、思わず購入。 ちょっとした器、たとえば和風でも洋風でも、下に敷しいてあげて飾るとなかなかいいカンジなのです。ヴァーチャル・オリエンタル、ってカンジですかね。 和洋の組み合わせも、思いつきだけでトライすると部屋の統一感が無くなって、なんだかガラクタ置き場みたいになってしまうのですが、色々試して行くと、さりげない落ち着きと自分で「好きだなぁ」と思えるポイントが掴めてくるようです。まだまだ途上、精進精進。 このように、茶道具をインテリアに取り入れるのもまた面白いかも知れませよ。(了)龍村美術織物裂地 稜華文錦
2007/06/01
コメント(0)
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…
- (2025-11-14 19:41:15)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 2026年福袋!数量限定🧦選べる 靴下…
- (2025-11-14 21:17:02)
-
-
-
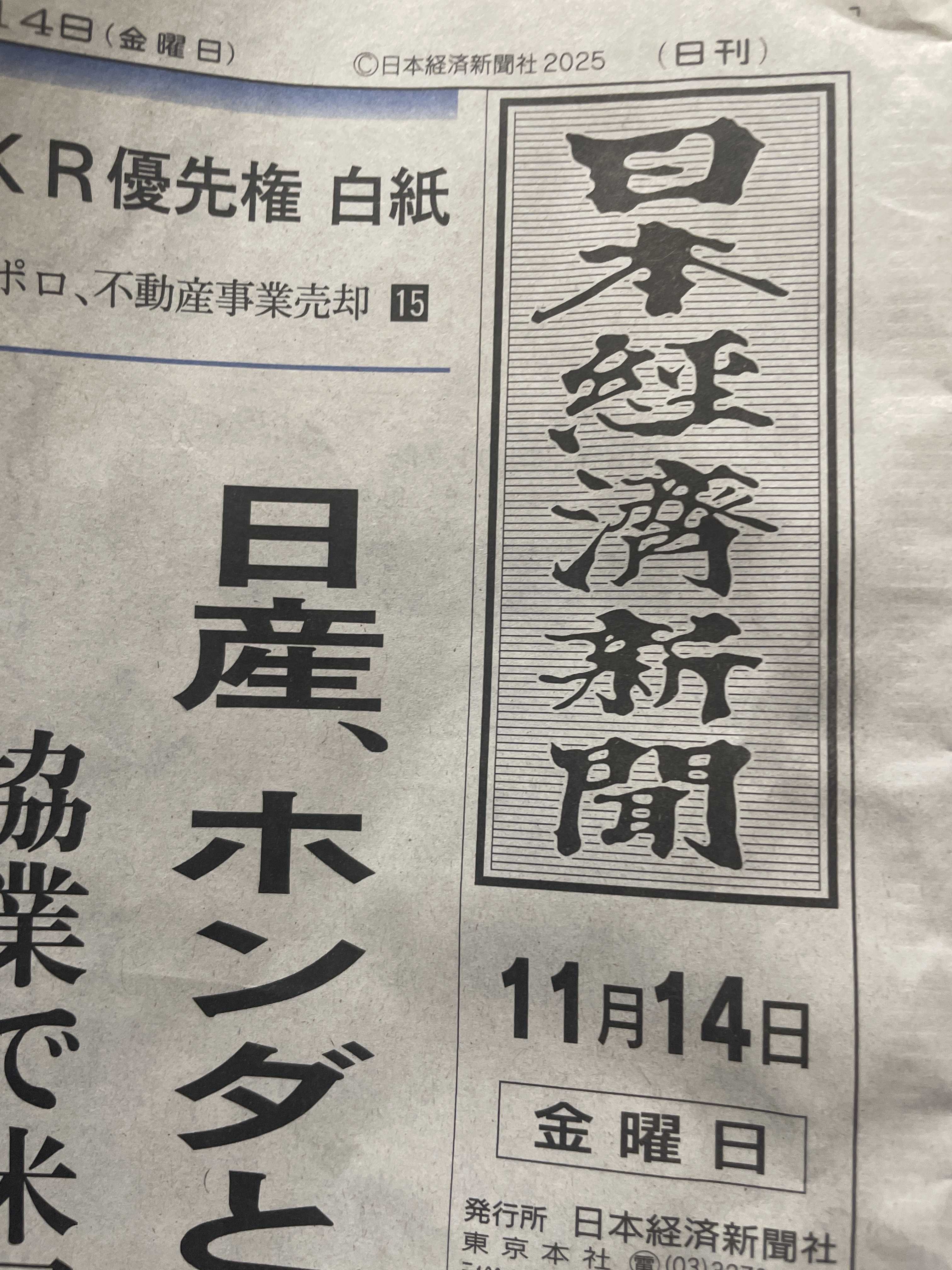
- ★つ・ぶ・や・き★
- 戦争やりたきゃ、てめえがやれ
- (2025-11-15 01:07:19)
-






