2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年06月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

インディ・ジョーンズ、“洞窟の少年”。
『インディ・ジョーンズ』最新作、まだ観に行けていないです(涙)。でも、いろんな雑誌や特集で過去作を振り返っているのを見ると、酷評された『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』の少年・ショート・ラウンド、通称・ショーティ、人気高いですね。アジア系っていうのが、また親しみを覚えさせるのかな。あるいは、時代的に言うと、“ジャッキー・チェン風味”が日本で大ウケした時代だったから、ほんのり香港映画を醸し出すショーティの存在感はインパクトがあったのかも知れません。インディ最新作でも、ショーティの復帰出演を望む声が多かったとか。 そのショーティことキー・ホイ・クワン、大人になった姿を『インディ・ジョーンズ』DVDのBOXセットのメイキング映像で見かけましたけど、そのまま大人になってた。でも、何してるのかよく分からなかったんですけど、武術指導とかしてるらしいです。ちゃんと業界に残ってるんだなぁ、としみじみ。『グーニーズ』…というより、やっぱり『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』でのイメージが強いキー・ホイ・クワンですが、両方とも洞窟つながりだ…。洞窟の少年…。なんか、インディ映画のサブタイトルみたいだなぁ。(了)★最安値★コトブキヤ ARTFXシアター インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説【9月予約】▲コッチも出たか…。トロッコにショーティが乗ってるし…。[DVDソフト] アドベンチャーズ・オブ・インディ・ジョーンズ コンプリートDVD(生産完了)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/30
コメント(0)
-

アッシャーと私。
アッシャーと私。関係、ないです。方やR&Bの枠を飛び越えてしまった、男性シンガー部門待望にして、事実上現在のプリンスなわけで。 アッシャーと私。関係、ないです。方やR&Bの枠を飛び越えてしまった、男性シンガー部門待望にして、事実上現在のプリンスなわけで。 そのアッシャー、実に四年ぶりに新作発表。事前情報などでは、ヒゲをたくわえたベイビーフェイスのアッシャーがメディアで露出していましたが、「うーむ、君もやはりマーヴィン・ゲイを目指すのか」と思っていたら、ホントにそうだったという。 そう、スターの座に甘んじることなく、シンガーとして、アーティストとして、自身のアイコンと真摯に対峙すべきときが来たのでしょうね。 新作には、多分にマーヴィン指向を盛り込んだご様子。飽くまで、シーケンス的に…と言いつつ、この人もまた、自分自身の心の声に命がけで耳を傾けるステップまで到達したのか、と感無量。そう、内省的な経験は、誰もが通る試練です。 そんなわけで、今月発売中の『BMR』7月号(No.359)の特集記事を読みますとね、書いてあるんですよ。何がって?ヴァルネラブルという語への言及が。記者によれば、「17分の取材でこの日本に馴染みのない言葉を三度も使った」とのこと。そう、本当に日本語にしづらい言葉&概念です。 で、アッシャーと私。というコトになるのですが、私は共著『何のために生き、死ぬの?-意味を探る旅』(地湧社)の中、4章において、まさにこのヴァルネラブルという語(ホリスティック医療で使われるヴァルネラビリティをソースにしてはいますが)について、なんとマーヴィン・ゲイを引き合いに出して書いているのです。しばらくは、冗談半分で「ホリスティック医療におけるこの難解な言葉を、マーヴィン・ゲイで解いた、いまのところ最初にして唯一の文章じゃないかな」なんて言ってましたけど(笑)、別に“言ったもん勝ち”になりたくて書いた訳ではなく、少なくとも私には、ヴァルネラブルという言葉を説明し、考察するにはマーヴィン・ゲイの力を借りる(マーヴィンに共感する)ことが一番自然だったわけで、こうして出版から一年、アッシャーを通して、多分異論反論はあれど、あれはあれでヴァルネラビリティについての読み方の一つとしてはアリだったのかな、と改めて自信を抱いたのでありマス。(了)ヒア・アイ・スタンド/アッシャー[CD]■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/27
コメント(0)
-

『ゾロ:伝説の始まり』(上・下)
見出し:怪傑ゾロ誕生までを描いた、オフィシャル「成長小説」。 イサベル・アジェンデ著、中川紀子訳『ゾロ:伝説の始まり』(上・下)(扶桑社) ドン・ディエゴがいかにして黒いマスクを着けるにいたったか?愛馬・トルネードに跨り、片手に鞭、片手に名剣・フスティシアを携え、颯爽と荒野を駆ける“カピストラノの疫病神”怪傑ゾロ誕生のいきさつは?あの黒装束の伝説のヒーローの「ビギンズ」と来れば、これを読みたくない人が果たしているだろうか。 本書は、中南米文学では必ず名の挙がる、ペルーはリマ出身、『精霊たちの家』で知られる名手・イサベル・アジェンデによるオールドファッションな冒険小説へのオマージュ的一作である。しかも、『怪傑ゾロ』原作者ジョンストン・マッカレーの版権に意見できる筋から、正式にオーソライズされたオファーによって書き上げられた作品なのである。 滅法面白い。ゾロ誕生までの道のりを目の当たりにした謎の伝記作者が、思い出を語っていくという仕掛けも、このあまりに有名な伝説的英雄の誕生秘話を客観的にする点で奏功している。「マスク・オブ・ゾロ・ビギンズ」なんて、誰だって飛びつきたくなるはずだ。 とはいえ実はこれ、作者の目線から(そしておそらく読者による、なにか「ビギンズ」のようでそうでないような、微かな違和感から)すれば「ビギンズ」ではない。一応、ビルドゥングスロマン、つまり成長物語という位置づけになっている。昨今「ビギンズもの」が流行だが、ビルドゥングスロマンとなると、これは話が違う。いかにしてドン・ディエゴがゾロになりし哉、という筋書きに相違ないが、厳密には「ビギンズもの」と「成長物語」では両者は違うからだ。なるほど、これは「ゾロ版青春グラフィティ」か、はたまた「ゾロ版青春白書」か。 内容としては、やや荒唐無稽の感もあり、説明的に過ぎる部分も散見され、あまりにたくさんのアイディアを背負わされた(および、原作との整合性を意識させられすぎた)作品、という印象は否めない。しかし、怪傑ゾロのサイドストーリー、あるいは一種のスピンオフとしては相当に読ませる正統派冒険小説だ。 また、この作品が「ビギンズもの」でなく「青春グラフィティ」だと分かれば、ディエゴ少年がヨーロッパでサーカスをしたり、ジプシーと恋したり、秘密結社に入ったり、などといった武勇伝があったら確かに面白いには違いない、と理解できる。だが、この武勇伝には楽しい話ばかりが出てくるわけではない。そこに着目すると、今度は、本作で描かれるドン・ディエゴが、後の怪傑とは結びつかない。どんなに事実の裏付けが語られても、これだけの悲喜交々を経験した男が、あれほどからりとした快男児にはならないのではないか、という疑念が湧いてしまう。実際人格とはそういうもので、それはフィクションにおいても同じことだ。パーソナリティ造形という意味では、このジェットコースター小説と原作との接点には首を傾げざるを得ない。 加えて、ディエゴ少年がやがて青年となり、ドン・ディエゴ=ゾロとなるまでの成長物語でありながら、実は作中、ディエゴ自身が一番退屈な人物である。逆に、その脇を固める人物達が、大物からちょっと出のカメオ級まで、非常にいきいきと豊かに描かれているのが特徴的である。 なにしろかの名高きゾロだ。だから、大作家の力量をもってしても、十分に描くことは躊躇われたのか、という勘ぐりとともに、「そうか。この個性的で素晴らしい人たちが、のちのゾロを生んだのか」というさわやかな納得も抱いてしまうのである。いずれにしても、ヒーローの種明かしは、畢竟、伝説をミステリアスでなくしてしまうということだろうか。 怪傑ゾロ誕生の物語。読者諸氏はどのように読まれるであろう。(了)ゾロ(上)ゾロ(下)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/27
コメント(0)
-
『水野竜生展 タヒチ』@銀座、見てきました。
昨日は、「銀座 ギャラリー桜の木」にて画家・水野竜生氏の『タヒチ展』を見てきました。ひょんなご縁から、私の文章を氏の作品解説として採り上げていただき、以来公私にわたってのお付き合い。とはいえ、実は再会は半年ぶりでした。 フランスに学び、同地をはじめ新潟・柏崎、中国、と活動の場を広げてきた水野氏は、今年の一月にタヒチに取材に行かれ、かの地を描写してきた由。それが、今回の『タヒチ展』として結実した次第。 鮮やかなブルーを使った楽園図も素晴らしかった(水野作品定番の「人・シリーズ」もいつも楽しみでして…)ですが、私はむしろ色数少ない作品の幾つかに、まだ見ぬタヒチの水の音や風の声を聞いたような気がしました。 水墨画を採り入れた水野氏が描く作品は、“間”が強力な仕掛けになっているんです。描かれているものを引き立たせ、立体化する、強力な余白。この“間”の感じが、あくまで想像上の、ですが、私の中のリラクシングなイメージにぴったり来てしまった。あるいは、たとえば一本の木が強風に揺られている絵が、余白によって本当に目の前でたわんでいるように錯覚してしまう。筆に勢いをつける手が、そのまま風になったような、そういう感じなんでしょうか、描いているときは…。 やけに目線が低くて、絵の中に踏み入れれば細かい砂が足に感じられそうな浜辺の作品も気に入りまして…。後でうかがったら、コレ、実際に地面にキャンバスを置いて描いたそうです。 その後近くでランチをご一緒し、作品それぞれのバックストーリー、タヒチでのお土産話までいただきました。 モノ作りのスタンスというか、哲学や美学のような部分は、互いに共感できる部分が多いので、水野氏との時間はいつもエキサイティングです。(了)■開催場所:銀座 ギャラリー桜の木■開催期間:6月14日(土)~6月28日(土)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/24
コメント(0)
-

鼠先輩。
音楽にかかわる仕事をしていても、必ずしも全方位型という性分ではなく、好きなジャンルの幅はかなり広い方ですが、やっぱり偏りがあるワケで、常に流行の歌を完全網羅しているわけではないのです(本当はしなきゃいけないのかもしれないのですが)。 これ、飽くまで今この時点での話ですが、鼠先輩の『六本木』が頭にこびりついてます。そうだなぁ、さわやかにループしてるとか、じわっとリフレインしているとかではなく、ギトッとこびりついてますね。 意味不明の歌詞、本気か冗談か分からないPV、使い古されたようなメロディ。でも、これぞまさに、日本歌謡史が連綿と継承してきた、理屈でなく、身体の記憶として反応してしまう、王道絶妙メロディなんですね。ある大御所は、この王道メロディの存在が日本の音楽を拘束してしまっている、と話していましたが、それはここでは措くとして、やっぱり耳に付いてしまうんですね。歌詞の面白さ、ナンセンスさ、あるいは歌手のイメージ。これらも大事。でも、この曲はメロディなんでしょうね。 私、名前しか知らなかったのですが、弟に薦められて、今ではすっかり頭の中が「ぽっぽぽぽぽぽ」で埋まってます。仕事に集中できないので、やめて欲しかったです(笑)。(了)《メール便なら送料無料》【6/18発売 新作CD】鼠先輩/ 六本木~GIROPPON~<2008/6/18>■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/23
コメント(2)
-

『アーサー王と円卓の騎士―サトクリフ・オリジナル (サトクリフ・オリジナル)』
見出し:西欧世界のキング・オブ・ネタ帳。ローズマリ・サトクリフ著、山本史郎訳『アーサー王と円卓の騎士―サトクリフ・オリジナル (サトクリフ・オリジナル)』(原書房) 正直言って、アーサー王伝説について、それも物語を読むということは、私にとってはダンテの『神曲』を読むようなもので、できればいつまでも手を付けず、この世のあらゆる愉しみがなくなった頃に手繰りたいテーマであった。そして、アーサー王伝説については、意外にも必然的な“読むべき時”が早く訪れてしまったというわけだ。 そういうことで、実は私は、活劇的な意味でしかアーサー王と円卓の騎士たちの物語について何も知らなかったし、これに踏み込めば、また大きな森に彷徨うことになるという重圧感があって遠ざけていたので、サー・トマス・マロリー『アーサー王の死』に行く前に、この壮大にして複雑な物語の糸玉に手がかりを見出したいとの思いから本書を手に取った。 しかしまぁ、サトクリフ・オリジナルと冠するのだからすごい。ツクダオリジナル並みにすごい。それだけこの著者によるシリーズが、本テーマを扱ってステイタスと読者を獲得しているということだろう。 事実、サトクリフ・オリジナルには、古き良き英雄をテーマにした物語が日本でも7巻出ていて、どれもこの分野における名著として長く親しまれているようだ。 まずは、かの名高き円卓の騎士について、ざっと読みたい。そういう私のニーズにも応えてくれるからこのシリーズは素晴らしい。何重にも折り重なったアーサー王とその騎士たちの物語の中で、ハイライトとなる物語やテーマをうまく整理し、短編集的に編集しながら記述して一巻の物語としたところがこのシリーズの特徴なのだ。 文章は読みやすく、ちょっと児童書のような印象もありながら、しっかり大人の読者をも満足させてくれる(それなりに読書好きな子供たちにとっても、比較的読みやすいのではないだろうか)。 しかし改めて、アーサー王伝説というテーマは、特に西欧世界の、あらゆるジャンル、あらゆる文化にとって、時代を超越したネタの宝庫なのだと痛感。 アーサー王と円卓の騎士たちの名誉を証す旅は、形を変え、メディアを変え、今も、明日も、続いているのだ。(了)アーサー王と円卓の騎士■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/22
コメント(0)
-

『インディ・ジョーンズ』最新作、初・舞台裏。
いよいよ、『インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国』、一般公開です。今回は、過去三部作はもちろん最新作ノベライズも読破・準備して、この予期せざるお祭り(ここが、予めストーリー数が早くから明らかになっていたスター・ウォーズにおける“祭り”との違いですね)を楽しもうと、腰のムチに油を注したりなんぞしているワケですが(ワケ、ない)。 ところで、先立って『メイキング・オブ・インディ・ジョーンズ』なる豪華本が刊行されたのですが、さっそく購入、読みました。いやぁ、貴重です。作品によって、資料の質や量にバラつきがあるものの。さらには、DVDコンプリートBOXの特典ディスクと重複する資料が含まれていたりするものの(私が持っているのは、昔出た方のBOXセットで、最近のセットの特典映像には、『クリスタル・スカル』絡みの情報も盛り込まれているようですね)。 でも、ですよ。実は、それこそこのコンプリートBOXくらいしか、ファンが手元に置いて堪能できる資料がないのですよ、インディ・シリーズでは。 これがスター・ウォーズとなると、もう玩具系に関しては、大ファンの私でさえちょっと食傷気味になるほど無茶なリリースしまくってますし、書籍・文献系資料にしても、フォローできない(かぶってるネタ多そうで、したくない)ほど出ているのに、ルーカス・フィルム仲間であるインディ・ジョーンズに関しては、これまで全くと言ってよいほど関連グッズにしろ、資料がなかったのです。そういう意味で、スティーヴン・スピルバーグ×ジョージ・ルーカスが、この“古典的ヒーローに着想を得たニュー・ヒーロー”インディに、どのような想いやコンセプト、アイディアを盛り込んできたか、その制作秘話や裏話を、プロダクションノートを閲覧するかのように目撃できる『メイキング・オブ・インディ・ジョーンズ』は非常に価値が高いと思うのです。 で、タイミングずらして、出てるんですよね。スター・ウォーズの『メイキング・オブ~』も(笑)。(了)メイキング・オブ・インディ・ジョーンズメイキング・オブ・スター・ウォーズ▲うーん、『クローン大戦』はあるけどさ、この内容はちょっと今さら過ぎないか???【予約】超特大、最安値!!SideshowToy社1/4 スケール・プレミアム・フィギュア/インディ・ジョーンズ レイダース/2009年1月)【送料無料】【10%OFF】ARTFX インディ・ジョーンズ/「レイダース 失われたアーク」【送料無料】【10%OFF】ARTFX ヘンリー・ジョーンズ/「インディ・ジョーンズ最後の聖戦」インディージョーンズ 鞭プロップレプリカインディージョーンズ なたプロップレプリカインディージョーンズ レプリカ帽子 レギュラーエディション Mサイズ■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/20
コメント(0)
-

『花咲ける騎士道』、観ました。
『花咲ける騎士道』、観ました。古い雑誌を読んでいて、急に観たくなったので。ちょっと前にヴァンサン・ペレーズとペネロペ・クルスでリメイクもありましたね。 しかし、ジェラール・フィリップ、本当にイイ男だなぁ。一筆書きで、簡単に絵に出来そうなイイ男=シンプルなお面相。パーツがイイ証拠なんだなぁ。 ジェラール・フィリップとアラン・ドロン。もうこの二人の対比って、飽きるほど見たり読んだりしてますよね。で、団塊世代の継承者としては、フランス映画は知らなくても、とにかくアラン・ドロン=ダンディ、猫も杓子もアラン・ドロン、どっぷりお茶の間化したアラン・ドロン、で育っているので、ジェラール・フィリップのシンプルな男振りがなかなか分からなかったんですよ、ずっと。特に同性としては。コテコテに作り込まれたアラン・ドロン、ちょっと確信犯的なアラン・ドロンにまんまと説得されていたと言うか…。 そんなダークさがまたアラン・ドロンの魅力なんでしょうけど、ギミックなしでスカッとしたジェラール・フィリップ、やっぱり素敵です。 肝心の映画の方ですが、これはもう、オールド・スクールな冒険活劇。騎士道が軽佻浮薄になった時代の典型的ロマンスがスジです。騎士道に一言ある私としては、ちょっと軽く思えてしまうのですが、それはそれ。ただただ、シーンを追うだけの映画。これまたシンプルの美。それでもしっかり面白い。恋と夢に生きる“チューリップ坊や”を、こんなに軽やかに、自然に演じて、まったく違和感がない役者、ジェラール・フィリップ。そりゃ、役名がニックネームになるワケだ。(了)花咲ける騎士道(DVD) ◆20%OFF!花咲ける騎士道(DVD) ◆20%OFF!■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/18
コメント(0)
-
『浜村博司 油彩画小品展』、観てきました。
先日、銀座の長谷川画廊さんで、『浜村博司 油彩画小品展』を観てきました。浜村先生は、恩人も恩人、学生時代にお世話になったのをきっかけに、その後今日にいたるまで、公私にわたってご縁をいただいている方。 意外性のあるビビッドでパキパキッとした色使いの向こうに、ライフワークであり、ご自身のルーツ、創作活動の原点である長崎の原爆被害という重厚なテーマを描き出す浜村先生、昨年は長崎県美術館にて、『~ナガサキ考~』なる集大成的個展を大々的に催しました。 浜村先生の作品には長崎原爆を大きな柱に、いくつか別のテーマがあるのですが、私は、それらを扱った先生の小さな作品もとても好きで、いつも「可愛らしいなぁ」と思って鑑賞するのです。そう、「可愛らしい」と思って知らず愛でてしまう、そういう作品群に魅力を感じてしまうのです。 長谷川画廊さん。オープン時、こけら落としにと、まさにこの場所で、若き日の“浜村博司とその仲間”が、展覧会を開いた場所。 うーん。故郷にてライフワークに一つのピークを作った先生が、今度は画廊という“場”のルーツに凱旋する。新たな創作的旅路の暗示…と符号を見出そうというのは、ちょっと考えすぎでしょうか。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/17
コメント(0)
-
岩手・宮城内陸地震に想う。
この手の話をブログで扱うのは、個人的には気が進まない。黙して、ただ被災者の一日も早い救助・救援、日常の回復を祈るよりほかにあまりに非力だからだ。ただ、岩手・宮城内陸地震を前に、様々な想いを抱かずにはいられなかった。 私は、震災後の神戸、小千谷も取材した。人生を一変してしまう天災への怒りや悲しみはどこへ向ければいいのだろう、という無力感しか残らなかった。それから学ぶこともあったのだ、などと酷薄なことをどうして言えるだろう? ある者は、震災後の、国や然るべき組織の対応力の弱さに矛先を向ける。ある者は、全世界的に天災が各地で頻発する昨今、それを地球規模での環境の変化、地球環境からの警鐘と語る。高度に利便性を追求した人工都市の被害は、むしろ人災ではないかという人もいる。 しかし、間違いなく言えることは、いま目の前で被害に遭っている人ひとりを前に、メタな議論や教訓などまったくの意味はない。そしてただ想う。それが、命のリアリティというものではないだろうか、と。(了)
2008/06/16
コメント(0)
-

『一九三四年冬―乱歩』
見出し:書けない乱歩と、妖しい四日間を極上のホテルで。久世光彦『一九三四年冬―乱歩』(新潮文庫) 嫌い嫌いと言いながら、やっぱり読んでおきたかった本書。読後、「うーん、すごい」。それしか出てこない。タイトル通り、1934年、一月の寒風が旋毛巻く東京、江戸川乱歩四日間の物語である。 何がすごいって、その文学的意味(たとえば小説言語など)については、解説で井上ひさし氏が述べている。単純に、こんな、何もない、平凡な四日間を、ここまでの作品に仕上げたな、ということ。まず、この作品、江戸川乱歩の伝記になってしまってはいけない。飽くまで江戸川乱歩を主人公とした小説なのである。 そこで久世は、スランプに陥った乱歩―巷間知られるあの大探偵作家、怪奇の帝王の看板から逃げ出す為に、文字通り世の中からコソコソと逃げ隠れて来た乱歩―を登場させるのである。 世の喧噪と好奇の目(もう、乱歩は書けない…のか!?)から逃れるために偽名で飛び込んだ洋館のホテルで、書けない乱歩が、過剰な怯懦と過敏なデリカシー、過度な煩悩で独り相撲を取る中、虚実綯い交ぜになった、怪しの話が展開していく。そして(久世が描く)乱歩が、崇高なことから卑俗なことまで、気まぐれに摘まみ上げては、それについていちいちボヤき、自問自答し、懊悩し、いけない妄想を先走らせるとのと並行して、この異様な、隔絶した、孤立した、奇妙な四日間で『梔子姫(くちなしひめ)』という作品を書き上げていく。書けない乱歩が、書くのである。 無論、この『梔子姫』は、久世流の粋な仕掛けであって、つまり作中作、“久世による乱歩”の贋作なのであるが、乱歩は久世の操り糸を借りて、ともかく『梔子姫』を書き上げるが、要するにこれは一種のカタストロフィーであり、書くことで模糊とした自身を乱歩は整理したのである。整理したから、『梔子姫』は世に出ない。つまり、幻の作品ということになる。こんなオチも洒脱である。もっとも、『梔子姫』、どう考えても久世光彦の作品で、乱歩はこうは書かないだろう、などという指摘は野暮だろうか。 とまぁ、実に筋はシンプルだ、作中作を書かせることで、世間から隠れた乱歩が四日間でスランプに一応の結着をつける。それだけの話し。ミステリらしい要素は何もないのに、妖しく、かつ面白いのは、数々の仕掛けや選ばれた言葉の一つ一つの相乗効果もさることながら、やっぱり久世による乱歩像の徹底的かつ精密な作り込みが素晴らしいからだ。文字通り、手抜かりがない。窮屈な拘束儀のように、息苦しいほど周到なのだ。 だから実在した大作家を狂言回しにしても、荒唐無稽にならない。誰よりも乱歩を知っている風に、この人は書く。だ から、我々も、乱歩を身近な、昔からよく知っている近所の風変わりな物書きのおじさん(失礼)のように感じてしまう(蛇足ながら、この究極に練り上げられた久世の乱歩像に触れて、久世のユーモラスな一面を垣間見ることが出来たのは何よりで、私の“久世恐怖症”が少々緩和されたのである)。 先に、「虚実綯い交ぜ」と書いたが、一歩間違えば正統・乱歩伝としても通用しそうなほど、江戸川乱歩についてはてっぺんからつま先まで、徹底的にディティールが描き尽くされ、もし当の乱歩自身が「私はこんな人物ではない」と言い張ったとしても、小説の中の乱歩の方が真実のような気さえして来る。加えて、乱歩周辺―文壇や文化、あるいは社会、 交遊-の差し込み方も秀逸である(これは、半分は乱歩自身の、半分は久世の思い入れや意見が、乱歩を通じて述べられているのだとしても)。読者諸氏においては、このおどおどした、小心で几帳面、臆病で見栄っ張りな大作家とともに、美青年の笑顔が迎えるホテルで、極上に耽美な四日間を満喫していただきたいのである。(了)一九三四年冬ー乱歩 ■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/11
コメント(0)
-
初めての読者へ。
ここのところ。この枕詞は止めよう。とにかくブログは更新がやっとで、ろくにメンテナンスもしていなかった。記入率が65パーセントに落ちた。 要するに、PCの前に座っている時間が確保できなかったということなのだが、このブログを始めた数年前、開設まもなく(まさに間髪入れず!!)読者になって下った方が、ブログを閉じていたことに今ようやく気がついた。 デスクトップの中でのご縁ではあったが、それ以上のつながり、それ以上の応援もいただいた。同じ、文筆に使命を抱く同志でもあった。 あの方のことだから、閉鎖前に丁寧な挨拶をアップしていたかもしれない。理由、そしてその後、そんな野次馬的なことはどうでもよく、今はただ、この半年というもの、何度かしか訪問も出来ず、区切りに言葉を寄せられなかったことをとても悔いている。これが早合点ではないか、とまだ信じられないのだ。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/11
コメント(0)
-
菊亭で痛飲。
過日記事にも書いたように、恩人の自費出版の書籍が完成した。タイトなスケジュールであったが、現場の多大な協力と連携、そして著者自身の思い入れと入念さによって、恩人の記念日に無事労作を届けることが出来た。 そのお祝い…となるはずが、逆に慰労会を一席設けていただく運びとなり、丸の内で創業から55年、江戸前天ぷらの老舗菊亭さんで、久しぶりに痛飲。 もともと若輩の私にもフランクに接してくださる方だが、この日はさらに打ち解け、実に楽しい夜となった。海峡を越えて直送される山海の幸はどれも胃袋に染み渡り、ウイスキーで酔った頭で語り合う詩論や映画論、本について…。極上の料理に、腹六分目を旨とする私も、ついつい箸が止まらない。 美味しいお酒を飲む、とはきっと、こういう時間のことを言うに違いない。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/11
コメント(0)
-

『乳房論』
見出し:乳房は誰のものか?マリリン・ヤーロム著、平石律子訳『乳房論』(ちくま学芸文庫) 現在のところ、日本語で読める乳房論の最も信頼できる一冊ではないだろうか。テーマは一貫して、「乳房は一体誰のものか?」「乳房は本来誰のものか?」そして「乳房を取戻せ」と、はっきりしている。 古来、豊穣のシンボルであった神代の時代から、女性の女性らしさが、いかに男性中心主義・ファロセントリックな制度や装置の中に取り込まれ、欲望と消費、暴力と束縛の拷問ペンチに挟まれ、そしてコルセットの中に押し込まれて来たか、米国、ヨーロッパ諸国の各風土や文化、宗教観それぞれについても取りこぼすことなく、逐一検討考察を重ねて、乳房奪還への道のりを丁寧に論じていく(欲を言えば、東洋的価値観の下における乳房の考察が、表面的に、あるいは図版扱いのようにしか登場しないのは残念だが、これはまた同時に日本においてこの種の議論が盛んでない、あるいは成熟していないことも示している)。 ふたたび本書は、先に述べたよう、テーマが一貫しているため、この硬派な縦糸が存分に暴れ回り、その鋭い矛先(本書では、乳房は攻撃的たるべしと述べられているから)は、神話、宗教、セクシュアリティ、衛生学や階級論、教育論、道徳や倫理、さらには心理学、文学、芸術、医学までをも貫いていく。乳房および乳房の記号的な意味や役割(それが、女性にとって不都合な、押し付けられた制度の結果であっても)を通して、様々な分野に分け入り、疑問符を投げかけてみるというのは実にスリリングであり、また男性として教えられることが多々あった。 もともと、私自身が社会学の世界に身を置いていたこともあり、また差異の問題、さらには身体の問題(まさに「黒い、白い、黄色い肌は誰のものか?」であるとか「アティテュードはステレオティピカルなボディラインを超越するか」などなど)も多少テーマに組み入れていた手前、実は本書で語られる、きわめて社会学的な発想や問題提起の道筋や論調そのものには、それほどの驚きを感じたわけでもなく、むしろ当たり前―つまりは、どの権利闘争や異議申し立ても必ず通る闘争史―として読め、また受け取れてしまった。と同時に、いやだからこそ、竹を割ったような著者の記述に対して、「乳房が、その本来の所有者に戻ったとして、今度は、肉体を所有することと解放されるということは一致するのか?人間/人格は自らの肉体の所有者なのか?所有する主体は、どこに(例えば、心脳問題でもいいが)存在するのか?」などと、つい素直になれない癖も出てしまう。 結局、私は社会学者が宿命的に背負う「闘う」というスタンスに、どうも馴染めない性質なのだ、ということに改めて直面させられてしまう。これはもう、向き不向きの問題、適正の有無の問題なのだが。 本書で特に着目すべき箇所は、個人的には中世絵画における聖母子の描かれ方の分析、ファッション史、乳房とその政治的役割を論じた箇所、さらに後半、一種の運動としてアート化された武器としての乳房たちの影響力、そして個人を離れたところでは、乳ガンについて、特別に入念かつ真摯にページを割いて、この人類の脅威との闘い、そして共存への積極的可能性を、使命感を込めて論じた箇所であろう。発表が1997年、と10年以上も前でありながら、一部の箇所を除いてきわめてリアリティに富んでいるのは、それだけ社会が、人類の知性に成長(進歩とは言うまい)が見られなかったからだと反省すべきかも知れない。(了)乳房論 ■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/10
コメント(2)
-

トニー・ガトリフ監督作品『ガスパール 君と過ごした季節』を観ました。
トニー・ガトリフ監督作品『ガスパール 君と過ごした季節』を観ました。棄てられた老婆、青年、家族を失った中年男、病む子持ちの薄幸な女。彼らが擬似家族を形成しながら、やがて人間的な絆を回復していく(というよりも、家族よりも濃い絆を“創出していく”)物語。ヒューマンタッチの優しいコメディ。 うぅ、なんだろう。別に、トニー作品じゃなくても良いんじゃないか?なぜならこの作品、従来のように、監督自身のルーツでありテーマであるロマ(ジプシー)を扱っているワケでもなく。パッケージには、そんな関連を匂わせるコピーがついていましたけど、主人公が、いわゆる既存の共同体と絶縁してしまっていることと、それぞれの「自由」を求めているという以外に、ロマ的な要素は皆無ですし。ラストにしたって、あまりにベタ(トニー作品は基本的にはベタが多いのですが、その分かり安さの向こうに必ずディティールがまぶされてるんですけど)で、ちょっと驚いてしまうくらい。 私はこの『ガスパール』は、これまでのトニー・ガトリフ作品の童話的な要素を目いっぱいに拡大して一本にした、そういう作品ではないかと思いました。もともと童話的な要素を持つ作品を撮ってきたトニーが、あえて作りたかった「真の童話」(『トランシルヴァニア』は大人の童話でしたね)。 本当に、感じのいい小品、という印象。描かれる事実や背景は、シリアスだったり重かったりしますけど、それを深読みさせる作品じゃないなぁ。シンプルに観る。それがいいみたいです。 あとになって振り返ると、この作品って、ハリウッド的な感覚とは違う意味で、親子で見たい映画、親子で観れる映画なのかも。そういう作品を作りたかったのかな。なんだか、絵本の読み聞かせを。親と子、両方が一緒に読み聞かせを楽しめる絵本のような作品、かな。 その感触に大きく貢献しているのが、画面を埋め尽くすポップでカラフルな、色、色、色!!砂浜に並べられたガスパールたちの“夢の象徴”が、なんだか胸の奥の懐かしい部分を刺激します。 そしてこの映画の決め手。いわば、勝ちが決まった瞬間。これはもう、冒頭、ジャンヌおばあちゃんとロバンソンが出会うシーン。あの互いの満面の笑顔。これで決まりですね。『ガスパール 君と過ごした季節』の良さはあのシーンで決まり、あのシーンに尽きた、そんな気がしました。(了)ガスパール~君と過ごした季節(DVD) ◆20%OFF!■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/05
コメント(0)
-
出版から一年が経ちました。
6月1日をもって、共著『何のために生き、死ぬの? 意味を探る旅』(地湧社)が出版一周年を迎えました。その間、たくさんの読者の方に、感想メールやコメントを頂き、著者として非常に嬉しく、またありがたく思っています。 振り返ってこの一年は、本当に短かったようで長く感じ、どのような反響があるだろうか、どれくらい読者の心に届いているだろうか、などと、透明人間を追いかけるような独り相撲の期間でもありましたが、今年に入って青少年向けの推薦図書に選んでいただいた辺りからまた別の動きも見せ始めたようで、改めて「“もう一周年”、ではなく“まだ一年”だったか…」と、少しだけ肩の力が抜けたような気がします。 出版から一周年を迎え、そうした心境にも至ったところで、今年も一冊…という予定で書き上げたものを、この週末自分でご破算にしました。本を出すだけなら意味が無いわけで、いくら形が整っていても、自分で「描ききれた」という気がしないな、と感じていたところ、ようやく方向性が固まったので、もう一度全部書き直すことに決めました。慌てて出すような類のものでもないので、じっくり壊してじっくり作り直そう、と考えています。(了)■著作です:何のために生き、死ぬの?。推薦文に帯津良一・帯津三敬病院名誉院長。
2008/06/03
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- 株主優待コレクション
- 3玉がオトク!旨辛豚つけ汁うどんを…
- (2025-11-15 00:00:05)
-
-
-
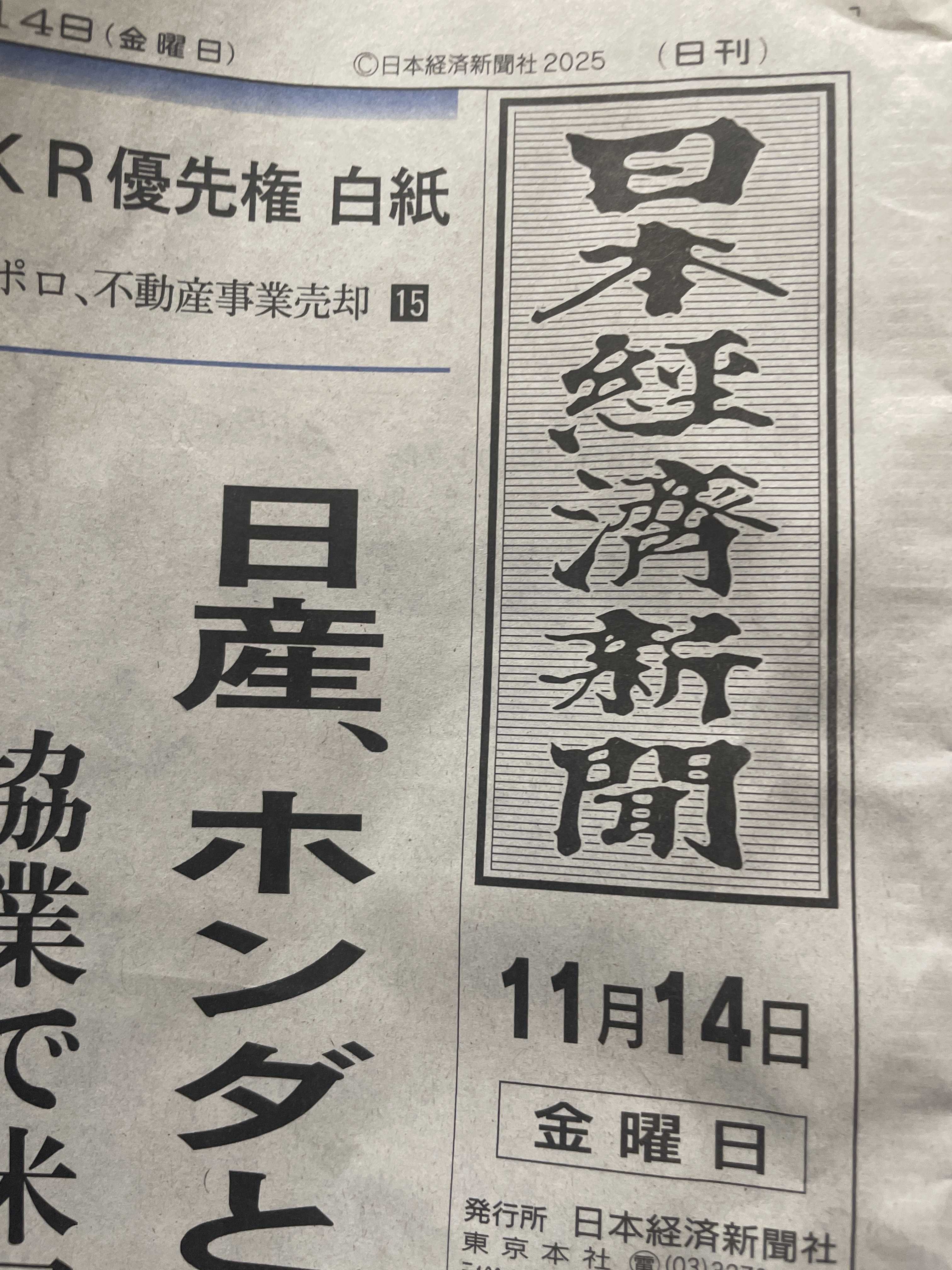
- ★つ・ぶ・や・き★
- 戦争やりたきゃ、てめえがやれ
- (2025-11-15 01:07:19)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 2026年福袋!数量限定🧦選べる 靴下…
- (2025-11-14 21:17:02)
-






