2008年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

3月24日(月)から3月30日(日)までに読んだ本
ユビキタス・コンテンツ・ビジネスのすべて前坂俊之・野口恒PHP研究所あなたが私を好きだった頃井形慶子ポプラ社憲法第4版 芦部信喜 著高橋和之 補訂岩波書店挑めばチャンス 逃げればピンチ樋口廣太郎PHP自分ブランドで勝負しろ!藤巻幸夫オーエス出版社
2008.03.31
コメント(0)
-
もう一つ何か欲しい
今ブログでコメントしている本、映画、日記にもう一つ分野が欲しくなってきた。基本的なスタイルは変えないが週に一回くらい何か決まったことを取りいれたい。ハッキリ言うと、情報誌など決まった雑誌を毎号読むことを習慣にしたい。それからその雑誌の気になった記事についてまとめやコメントを残しておきたいなあと。なんとなくだけれど、月刊誌を4冊ほど決めて、週に1冊ずつ、その中の話題をとりあげて何か書く、みたいな。そうすれば、定期的に4つの分野について触れられるからワクワクできていいなあと。ただ、4つの分野っていっても、どれにするかはまだ決めていない。たまに読んだ本として触れるビジネス系、飲食系もいいけど、音楽、芸能、ファッション、遊び、モノ関係など自分があまり関わっていない分野でもいいし。やってみないとわからないが、4つはきついかな・・それはまた考えていくか。どっちみち時間は限られているから絞らないといけないが、興味があって続けられそうな分野がいいよなあ。何がいいかな。しばらくは様子見ということでいろんな雑誌を立ち読みしてみよう。なんだか楽しみになってきた。
2008.03.30
コメント(2)
-
結婚か・・
先日、地元沖縄で高校時代の友人の結婚式があった。お呼ばれしていたが、断ってしまった。当日友人が写メールで様子を何カットか送ってくれたが、とても幸せそうだった。素敵な笑顔だ。もちろん直接会ってお祝いしたかったというのはあるが、いったん帰って地元で落ち着いている同級生軍団に囲まれたら、きっと自分もはやく落ち着きたいという方向に流れるだろうなあということと、あと10年もすれば県内の主要な企業や県庁などで主力メンバーになるだろうなと思われる人間たちばかりだから、今の自分ではたぶん後ろ向きな気持ちになる気がしたからだ。まだまだ克服すべきところはたくさんあるなあ。まっ、しょうがない。上京して一から始めていくと決めたのは自分だし。成長していくしかない。最近読んだ本で、住友銀行時代の頭取の堀田庄三氏が常々口にしていた「お・い・あ・く・ま」の心得(おこるな・いばるな・あせるな・くじけるな・まけるな)というのがあってそれを自分にひたすら言い聞かせている。そんな時代もあったなあと笑い飛ばすためにも今、ここでがんばろう。
2008.03.29
コメント(2)
-

最近読んだ本232
本は10冊同時に読め!成毛眞知的生きかた文庫マイクロソフトの日本法人の元社長が考える読書法について書いた本。「自分の価値」は読書量で決まる。結論から言うと、どんなに忙しくても読書だけは欠かさず、しかもひたすら量を読みなさいということだろう。すきまの時間を使って読む本、部屋にいるときに読む本などいろんな状況で読める本をそれぞれもち、しかも仕事関連の本というような一つのジャンルにこだわらずありとあらゆるものを同時並行で読みなさいと。この著者は言葉がかなり過激だ。本を読まない人間はサルだと言い、本を読む人間と読まない人間との差をはっきりと区別し読まない人間には近づくなと強く主張している。あとは、読書メモや3色ボールペンで線を引きながらする読書はやめろとも言っている。まとめている暇があるならもっと本を読みなさいとのこと。読書とはあらゆるジャンルのものを自分の頭のなかにいれていき、それらが融合されて新しいアイデアを生み出すことでもあるので、整理していくことで柔軟な考え方ができなくなるらしい。さすがに自分がやっていることを否定されるようで、耳が痛かったが、自分の行動を常に批判的に見る自分も必要かなと思った。確かに、メモするしないはこれから考えないといけない問題だが、少なくとも今の自分にとっては、現在のスタンスを崩そうとは思っていない。だが、次の段階に行くには変化をしないといけないのかなと自分に対しての問題提起になった本。自分の中の引っかかり・自分の周りに本嫌いの人がいるのなら、そういう人とはつき合わないほうがいい。 足を引っ張るだけで、自分の人生に何ももたらしてくれないからである。 ・・本を読んでいない人たちの会話とは、上司のグチ、会社の待遇への不満、 女房のグチ、しょうもない自慢話など、生産性のない話ばかりだ。知識ゼロの 人間が何人集まっても、ゼロ。2倍や3倍になることはないのである。・「生きた証」を残せなければアリと変わらない。・経営者になってから経営論や戦術論に関する本を読んでいるようでは、遅すぎる。・本は、大きな決断のときの判断材料になる。
2008.03.28
コメント(2)
-

感銘を受けた本167
中谷巌の「プロになるならこれをやれ!」中谷巌 日経ビジネス文庫タイトルの通りプロになるために必要なことについて書かれた本。プロになる第一歩は自分の人生をもう一度原点に返って考え直してみることから入っていくことが必要である。それからプロが共通している人生観というのが、・自分の仕事に命をかけている。自分の時間やお金をプロとしての技量を磨くために 決して出し惜しみをしない。・少しでも高いところに到達したいと常に高い目標を自らに課している。・少々の困難があってもプロは必ず結果を出すということ。・自分はまわりの人たちに支えられてここまで来ることができたという感謝の気持ちを 強く持っている。・地道な努力は必ず報われるという信念を持っている。ことであり、一流のプロが持つこれらの特有の人生観を身につけるためにはどうすればいいのかということについてそのヒントとなるようなことがこの本に書かれている。この本はかなりためになった。プロとして生きていくためにはある程度の時間をかける必要があること、どんなことであれある一定の段階まで行くとどの分野に共通の境地に立つことができること、これから鍛えていくべきところなど今まであまりと意識したことのないことをはっきりと意識させてくれて、自分の専門分野に関して、自分が命をかけてもいいと思えることに関して、もっと深く入って行こうという気持ちがより強固になった。今の自分にとってはかなり響いた本だった。自分の中のひっかかり・心に秘めた熱き志がチャンスを呼び寄せる。・ノウハウの前に人生のビジョンを定めることが大切。・「直感」を「概念化」する能力を磨け →リーダーの「直感」を誰にもわかる形に変換(「概念化」)しないと、 リーダーの直感は部下には伝わらない。・リーダーは本質を見抜いて、瞬時に言葉に変える能力が求められる。・普通の能力を持った人が一つのことに一万時間、禁欲的に自己投資すれば、スペシャリスト になれる。 →一日八時間勉強すると(土日除いて)一年で約2000時間。五年で一万時間になる。 さらに1万時間を費やして造詣を深めた人は、ある共通の境地に立つことができます。 自分の専門分野をどんどん掘り下げていくと、地下に流れる鉱脈に行き当たる。 その鉱脈はすべての分野につながっていて、一つの鉱脈を掘り当てると、不思議と 他の分野のことも見えてくるようになるのです。・プロになるには、それぞれの分野のスキル・技術を極めることが前提になるが、 どんな分野でもそれが可能になるのは、本人の「心構え」や「人生観」が しっかりと確立しているときに限られるということです。・
2008.03.27
コメント(0)
-

感銘を受けた本166
ガイアの夜明け闘う100人テレビ東京報道局日経ビジネス人文庫 テレビ東京の「ガイアの夜明け」に出演した人たちの言葉を中心に編集した本この本は日本経済に影響を与えた100人の人生哲学を名言という形で述べており、そのあとに各々がやってきたことなどが軽く紹介されていている。どの分野であれ、ある一定の段階まで行った人しかだせない言葉というのがある。どの言葉も本人たちの経験を踏まえた上で出てきた言葉なので、どれも力を感じるし、その言葉から裏には本人たちの成功や挫折などいろんな経験がつまっているのがよくわかる。書物を読むことを否定するわけではないが、どんな書物よりも人の生き方から出てくる言葉はとても影響を受ける。背中でものがいえる人間になりたいものだ。いろんな人たちのやってきたことのダイジェスト版のようなもので、一人に割いているページ数は少ないものの熱く生きてきたことだけは充分伝わる。読んでいてかなりワクワク出来た本。自分の中の引っかかり・退屈な人間にはリーダーは務まらない。 リーダーは魅力的なビジョンやブランド戦略を持ち、それを魅力的に語れなければならない。・自分が感動した良いものを、俺だけが知っているのはもったいない。 世のみなさんに紹介したい。それがビジネスの基本。・勝算はやってみないとわからないが、初めから負けるなんて思ってはいない。・エリートなき会社は滅びる。21世紀のエリートとは、一番困ったときに先頭に 立って動ける人。トップが決定能力を欠いたとき、国も会社も衰退する。・今の日本は、勉強しなくても一応は生きていける社会。 しかし、これからの20年後、30年後にこれがいいかというと、いいとは思わない。
2008.03.26
コメント(0)
-

最近見た映画31
死ぬまでにしたい10のこと出演: サラ・ポーリー(Sarah Polley)/マーク・ラファロ(Mark Ruffalo)/スコット・スピードマン(Scott Speedman) ほか 監督、脚本: イザベル・コヘット(Isabel Coixet) 収録時間: 106分 制作国:カナダ制作年:2002年アンは23歳。家族は失業中の夫と二人の娘。すぐ側にママも住んでいる。パパはもう10年も刑務所にいる。ある日突然、腹痛に倒れて病院で検査を受けると、「あと2ヶ月の命」と宣告される。家族にも誰にも話さない。そう決めたアンは、深夜のカフェで独り、「死ぬまでにしたいこと」リストを作る。それは10項目のリストになった。その日から始まったアンの死ぬための準備。それは同じことの繰り返しだった毎日を生き生きと充実した瞬間に変えていった。しかし、最期の時間は刻一刻と近付いていた・・・。とてもいい作品だと思った。ストーリーは余命2ヶ月と死を宣告され、その間にしておきたいことを実行していくというまさしくタイトルそのものなのだが、病気のことを誰にも言わず、主人公ひとりで抱え込みながら自分で決めたことを実行していく様子がとても痛々しい。でも応援せずにはいられない。気になったこととして、リストの「夫以外の人間と恋愛をすること」という項目。10のリストの中に、「夫以外の人間と恋愛をすること」という項目があって、家族ともうまくいっているのにどうしてなんだろうと思っていたが、17歳で今の夫と出会い子供ができて、他の人たちが青春を送っていた頃に、子育てをしていた主人公は、自分のやりたいことや経験したかったことをすべて犠牲にして、子供や夫に尽くしてきたと。決して子供や夫を愛していないわけではないが、他の人たちと同じように恋をしたり、やりたかった仕事をしてみたかったというのを見て、想像でしかないがなんとなくわかるような気がした。あとは、家族や関わりのある人間たちと少しずつ別れの準備をしていくのを見るのも結構つらかった。しかも誰にも言わずにひとりこっそりと行なっていくわけだし。女の人は追い込まれたときにとても強いなと感じる。この作品は「死」という重たいテーマを扱っているが、重苦しく感じない。おそらく役者や脚本や撮影が素晴らしいのだと思うけれど、美しい感じのまま終了していた。自分的に結構印象に残った作品だった。
2008.03.25
コメント(4)
-

3月17日(月)から3月23日(日)に読んだ本
プロ論。B-ing編集部徳間書店まったくわからない人のためのパソコンの常識貝原典子・加藤多佳子・樋口由美子新星出版社本は10冊同時に読め!成毛眞知的生きかた文庫一瞬で「自分の夢」を実現する法アンソニー・ロビンズ 著本田健 訳いつも楽に生きている人の考え方ウィンディ・ドライデン 著野田恭子 訳ディスカバー21
2008.03.24
コメント(0)
-
ひたすら続けているとやってくる感覚?
書道で今日が3月分の作品の提出日なのでひたすら書きまくった。今回結局休憩入れずに4時間くらいぶっ続けで書いていたのだが、その書いている最中に突然切れる瞬間というのがあった。しかも後半のけっこう疲れてきたときに。客観的にはまだまだうまくはないけれどただ自分的にイメージしている筆使いがうまくいったぞと思えた瞬間があった。ほんの一瞬だけだったけれどこういうことがあるんだなあと驚いた。書いて書いて、はやく帰りたいなあと思って、でも提出できる作品を書けてないからもう少し書かないといけないと踏みとどまってさらに書き続けているときに来た。なかなか伝えづらい感覚けど不思議な感じだった。毎回その感覚があるといいけど毎回ヘトヘトになるのもなあ。まあ書道は細く長く続けるイメージなので軽い気持ちでいこう。
2008.03.23
コメント(0)
-
千鳥が淵の桜 2008
今日は、九段下に行って桜を見に行ってきた。昨年、一昨年と毎年見に行っていたから今年も絶対千鳥ヶ淵に行くと決めていたので、予定を立てて行ってきた。満開の時に見に行こうと思ったけれど、でもなんとなく花が開く前の桜を見たいなあと思って少し時期は早かったが今日にした。公園の道を普通にランニングしている人もいるくらい人がいなくて、とても静かだったので、今までの出来事を思い返したり、これからの事を考えたり、自分と対話をしながらゆっくりと歩いていた。満開の一番美しい時を見るのはもちろん楽しいが、そうでない時を見るのもまたおもしろい。来年見に行くのが楽しみになる。それから靖国神社、市ヶ谷から四ッ谷にかけて散歩をした。今年は一人で行ったのだが、気持ち的にかなりリフレッシュできた自分がいた。自分であまり意識しないようにしていただけなのかもしれないが、結構お疲れモードに入っていたのかしら。毎日のように人と会って、話して、「がんばっていきましょう」と自分や相手を鼓舞し熱くなっていくのも嫌いではないが、こんな風にゆったり自分と向き合うことも求めていたようだ。今回どうしても行きたいと思っていたから、知らず知らずの内に自分で精神的なバランスをとっていたのかもしれない。ドンピシャのタイミングだった気がする。今年は去年の感動とはまた違うがすごく満足できた。来年はどんな気持ちで行くのかなあ。楽しみだ。P.S.早稲田の大学院に行く君へ本当は直接会っていろんな思いを分かち合いたいけれど、お互いになかなか時間があわないからとりあえずこの場を借りてこちらの気持ちを伝えるよ、自分の思いに少しでも近づくことができてよかったね。本当にうれしい。こういう話を聞けるのはなんともいえないくらい幸せな気持ちにさせてくれる。ここ最近はずっと会っていなかったから近況はよくわからなかったけれど、いい流れを引き寄せたんだね。俺が約1年前に東京に出てきて底辺の生活をしている頃に出会って、夢、希望、悩みなどいろんなことを話し、励ましながらお互いやってきてこうしていいところでバチンと結果をだせたのはやっぱりカッコいいなと思う。いろんな意味で自信もでてきたんじゃない?これからやりたいことの幅がもっとひろがっていくだろうし、またできるだろうしよりいい男になるなあ。自分の信じる道をひたすら進んでいってね。次は俺か。まあ近いうち時間つくるよ。語らおう。
2008.03.22
コメント(8)
-

感銘を受けた本165
変人力樋口泰行ダイヤモンド社日本のマイクロソフトのCEOが思うリーダーシップ論について書かれている。ダイエーの前社長として泥沼にはまっていたダイエー再建の礎を築き、その後マイクロソフトに移っているのだが、これまでの経歴を見ると、松下電器、ハーバード大学院、ボストンコンサルティンググループ、アップル、HPなど超エリート街道まっしぐら。しかし、実際にトップとしてとりかかったことなどに触れてみると、もちろん改革などの絵はしっかりつくっているのだが、何よりも現場を重要視しているなあと思った。この本ではまずダイエー時代に経験したことが書かれていて、その後にリーダーとして著者が大事にしていることを「現場力」「戦略力」「変人力」と3つの分野にわけて著者なりの見解を述べている。ちなみに、「変人力」とは、周囲が何を言おうとも自分の信念を貫き通す力、底知れない執念で変革をやり遂げる力、とのこと。著者は、まず現場ありきですべてがあてはまるわけではないが、ハーバード時代に経営判断における何百ものケースを疑似体験してきたことが知識的な土台となっているとも言っていた。「現場と学問の融合」をうまく行なって結果を出しているのかなあ。ダイエーだったりマイクロソフトだったりとやってきたことの規模はデカすぎてあまりピンとはこなかったのだが、そのマインド的な部分で勉強になりとても刺激を受けた。著者の熱さがとても伝わってくる本だった。自分の中の引っかかり・それまでの私は、大企業で名をなした経営者が再建途上の企業や国策会社などに 身を投じたという報道に接するたび、「なぜ安定を捨てて、わざわざ火中の栗を 広いに行くのだろう?」と疑問を感じることが多かった。しかし、今ならその 理由が何となくわかる気がする。それは、計算を超えた、誰かのために貢献したい という純粋な使命感だろう。・現場の風土こそが企業発展のベースになるということだ。戦略や戦術はあくまで その上に乗せるものである。・本来的に言えば、構造改革と営業力強化策は同時に進めるべきではない。 まず構造改革を終わらせてから、営業力強化策に着手するべきだろう。 なぜなら、組織が後ろ向きの改革を進めている間は、社員のマインドも否応なく 後ろ向きになる。その状態で前向きな改革に取り組んでも、十分な成果を見込み にくいからだ。・自社にとって最適な戦略を構築しようとすれば、その前に「ビッグ・ピクチャー (全体俯瞰図)」を描くことが何より大切となる。将来にわたる競争環境や 社会環境などの絵柄をきちんと想定しなくては、精度の高い意思決定はできない ということだ。・専門家からの情報やアドバイスを自分自身で評価できるだけの最低限の知識が 必要となる。ファイナンスであれ法務であれM&Aであれ、専門知識がまったく わからないと、外部のアドバイスを右から左へ伝えるだけの伝書鳩になってしまう。 外部の専門家から提案された知識や知恵を自分の頭で咀嚼し、それを現場の 「共通言語」に翻訳する力がリーダーには欠かせないのである。・変人力の二つの資質 第一の資質「ぶれない軸を持つ」 第二の資質「異様なほどの実行力を持つ」
2008.03.21
コメント(0)
-

最近読んだ本231
自信加藤諦三知的生きかた文庫本物の自信をつけるためにはどうすればいいのかについて書かれた本。避けることからは、いかなる自信も生まれてこない。さまざまなことに挑戦し、自分を試し、実際の自分を知りさえすれば、たとえ実際の自分がどのようなものであっても、人は本物の「自信」を得る。だが、いきなり「自分を知る」「自分から逃げない」「現実から逃げない」といっても難しい。心理学者の立場から、まず自信のない人は、あやまって現実を解釈し、その解釈にしがみついて生きてきた人、と定義し(たとえば、まわりが泳げる人間ばかりで「あなた泳げないの?」と、泳げるのが当然でしょみたいな感じで言われて、「泳げない=悪い」と間違った意識を植え付けられるような)、しかし、そういった解釈は正しくなく、自分の思い込みだということをわからせていき、その後自分を変えていくためには勇気が必要であることを段階的に説いている。読んでみて、事前に人間の心理を知識として知っておくだけでだいぶ精神的な状態は変わる気がするなあと思った。何もわからない状態で落ち込むとふさぎ込んでしまうだけだが、ある程度心理などの流れを知っている状態で落ち込むと自分を客観的に見られるから次の対応が見えて来る分、立ち直りもはやいのかなと思う。こういうことも一つの自信につながるのかもしれない。自信のない人に見られる共通点や具体例などを挙げ、一つずつばらしていきながら、対応策について述べている本で読みやすくて理解しやすい本だった。勉強になった。自分の中の引っかかり・自信のない人が自信をもつためには、自分の周囲にいる人間の正体を見破ることが 必要である。・他人に好かれることを目標にしてしまっている人は、自分の以外の人なら誰にでも よい顔をする。したがって、さまざまな性格の人と付き合っているが、本当に親しい人 はできない。 人間はいろいろな種類の人がいる。すべての人と深くつきあう必要などない。 そんなことをしようとしたら、ノイローゼになってしまう。・まわりを一切考えずに「浮かんだ気持ち」を大切にする。・高慢になる人は、もう勝負に負けている。・断ち切らない限り、「依存」はますます強化されていく。・相手が大きく見えすぎたりするのは、自分の錯覚だ。・できることをやっていくうちに「個性」がでてくる。
2008.03.20
コメント(0)
-

最近読んだ本230
ウサギはなぜ嘘を許せないのか?マリアン・M・ジェニングス 著野津智子 訳山田真哉 監修アスコムコンプライアンス(法令遵守)についてのビジネス小説。コンプライアンスとは、一般的には法令遵守と訳され、企業活動において、法律や規則、社会規範などに違反せず、それらをきちんと守ることをいう。この本の物語自体は、コンプライアンスがどうとか難しい言葉が使われているわけではなく、小さな嘘をついて世の中をその場その場でうまく渡ってきた人間と正しいことを貫くことでそのつど集団からはじきだされてきた人間、それぞれの生き方で最後はどうなっていくか、という感じの話。コンプライアンス体制のための手続きや細かい法令などは書かれていないが、そのもとになる個人の心の持ち方についてどうあるべきかが書かれている。言うまでもなく最後は正しいことを貫く人間が最終的な成功を手にするのだが、結構考えさせられた。「正しい」とは結局何なのかというところに行き着くと思うが、自分の行動に後ろめたさがなくて胸を張れるようなことと定義すればいいのかなあ。なかなかすべてにおいて正しく行くというのは厳しいが、今までの意識よりは「正しいこと」をしようとする意識づけにはなった。自分の中の引っかかり・問題を解決する方法は目の前の手段以外にきっと何かある・短期間で手に入るものに惑わされないこと。 「短距離走者」たちはいずれつまずく。彼らに追い越されても自信をなくさないこと。・問題を克服しなければ、結局はすべてを失う。
2008.03.19
コメント(0)
-

最近見た映画30
ロスト・イン・トランスレーションプロデューサー・監督・脚本:ソフィア・コッポラ プロデューサー:ロス・カッツ エグゼクティブ・プロデューサー:フランシス・フォード・コッポラ/フレッド・ロス 撮影:ランス・アコード 音楽プロデューサー:ブライアン・レイツェル 出演:ビル・マーレイ/スカーレット・ヨハンソン/ジョヴァンニ・リビシ/アンナ・ファリス/林文浩制作国:アメリカ制作年:2003年受賞履歴:2003年:アカデミー賞脚本賞ウィスキーのCM撮影のため来日したハリウッドスターのボブ。妻とあまりうまくいっていないため逃れる口実と200万ドルのギャラのために、なんとなく仕事を引き受けて東京へやってきた。しかし言葉も通じず次第に疎外感を強めていく・・・。フォトグラファーの夫に付き添って来日した新婚のシャーロット。しかし、夫は仕事に明け暮れるばかりで、行くあてもない彼女はホテルの部屋に取り残されてしまう・・・。「自分の居場所がない」同じように心に空洞を抱えた二人が、同じホテルで偶然出会った。急速にうちとけた二人は、トーキョーの街の目も眩むようなネオンと雑踏の中に繰り出していく・・・。とても美しいストーリーだった。監督もおそらく日本がとても大好きなんだろうなと思う。だが、主人公たちに疎外感を感じさせるというストーリー上、日本(特に東京だが)のあまりよくないイメージが取り上げられている。京都で結婚式の白無垢姿の花嫁さんがあるいている姿など日本風の美しさも取り上げられているのだが、選挙カーで街をまわるうるさい感じや人ごみ、眼鏡をかけたサラリーマンの集団、常に仕事に追われてさっさとすませようとする広告代理店の人間など、東京は疲れるなあと感じさせる映像が多かった。外国の人から見た日本のイメージはこうなんだろうなあという感じ。でも全体のストーリーはすごくいい。主人公の二人が少しずつ近づいていく流れはとても自然で、見ているこちら側も感情移入しやすかったし、シーン一つ一つがしっかり構成されていて、とてもいい流れで話が進んでいるなあと思った。東京の見慣れた街並みというのもあったが、見ていてかなり印象に残る作品だった。結構おすすめ。
2008.03.18
コメント(2)
-

3月10日(月)から3月16日(日)に読んだ本
ウサギはなぜ嘘を許せないのか?マリアン・M・ジェニングス 著野津智子 訳山田真哉 監修アスコム自信加藤諦三知的生きかた文庫中谷巌の「プロになるならこれをやれ!」中谷巌 日経ビジネス文庫ビジネスマンのための「数字力」養成講座小宮一慶ディスカバーIT業界資格と就職ガイドブック高作義明 加藤多佳子新星出版社
2008.03.17
コメント(0)
-
フォーシーズンズホテル椿山荘東京
今日は、フォーシーズンズホテル椿山荘東京に行ってきた。フォーシーズンズホテル椿山荘に関して、フォーシーズンズ・ホテルズ&リゾーツは「中規模でラグジュアリーなホテル」をビジョンとして世界各国に展開している国際的なホテルチェーンで、1992年1月にアジア進出第1号として開業したのが「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」(運営は藤田観光に委託)。結婚式場として老舗だった椿山荘と同じ敷地内に建てたことから「フォーシーズンズ」の後ろに「椿山荘」の名がついている。都内のホテルは高層ビルや、東京タワー、ウォーターフロントに立地するホテルが多いが、ここは広大な庭園に囲まれており、名前の通り四季折々の自然の景観が楽しめ、どちらかというとお若い方よりも、40代以上に人気が高い、とても落ち着いた雰囲気のホテル。結婚式場として非常に人気もある。とのこと。初めて行ってきたがかなり感動した。ホテルの建物自体高級感漂う感じだったが、なんといってもすごいのが椿山荘庭園。2,30分くらいで全部をまわれるくらいの広さで、池を中心として土地の起伏をつくり、そこに庭石や草木を配し四季を鑑賞できるようになっており、またところどころに茶室や三重塔など、文化財的なものもあったりこれが日本らしさなんだなと感じることができるとても美しい日本庭園。おそらく三月下旬から四月頭は桜のソメイヨシノがあたり一面に咲き広がってかなり美しいんだろうなとイメージされる。庭園のところどころに食事やお茶をするところがあり、なんだか大人のテーマパークみたいだなと思った。年齢層はやや高めな気がしたが、「ゆっくり歩いて、ゆっくりお茶しながら景色を楽しむ」ことが嫌いでなければきっと満足すると思う。ちなみにレストランでの食事はランチでもいい値段だった。桜をテーマとした食事を食べたが、料理自体もおいしく、雰囲気もよかった。ホテル内のレストランだけでなく、庭園内にある店を回るというのもありだし、ホテルに泊まって、部屋から庭園を見るというのもあるだろうし、機会があればまた行きたいなと感じたところだった。満足度はかなり高かった。
2008.03.16
コメント(2)
-
すまん
先日弟の誕生日だったからそのお祝いということで、弟のリクエストもあり新宿のパークハイアットで食事に行こうと思ってそのように準備していた。で、今日「Lost In Translation」というDVDを見ていたら、偶然にも新宿のパークハイアットが舞台の中心的な場所になっていて、作品を見れば見るほど自分の学生の頃のパークハイアットでの思い出がよみがえってきて「まだ行ってはいけない」と行く気がまったくなくなってしまった。今までで最も自分の弱さ、ふがいなさを感じた日。その日を境にいろんな場所に行って、いろんな経験をしてもっともっと強くなろうと決意した今でも忘れられない日。今回のこの機会にさらりといってやるかと思ったが、やっぱりダメだ。今の自分ではまだ行ってはいけない。行きたくない。自分の中のひとつの壁だがまだだめみたいだ。堂々と胸をはっていけるまでもう一段階自分のレベルをあげたい。最近調子にのっていた自分がいたからいい意味でへこまされたわ。謙虚に、ひたむきに自分のレベルをあげていこう。それしかない。ごめんな
2008.03.15
コメント(2)
-

最近読んだ本229
男性を見る目が今夜から変わる本トレーシー・キャボット 著青木雅子 平形澄子 訳KKベストセラーズ女性の立場から最高のパートナーを見つけるための考え方、方法について書いた本。自分自身の理想の男性像を知り、出会い、相思相愛の仲にになるためには、ほんのちょっとの努力と観察力、実践力があれば、日常のあらゆる空間、時間で効果を発揮できる方法があるということで、いろいろなやりかたが書かれている。まずこういう男には近づいてはいけないということで、あなたに無関心な偉大な達成者、精神世界に生きる教祖、時限爆弾のような人、優柔不断の人、傲慢な上司タイプ、母性本能をくすぐる居候タイプ、ワイルドだが実はやくざの極道タイプ、何かあるとすぐ病気になるタイプ、過去に固執するタイプ、夢を語るものの何一つ達成できないタイプなど・・を紹介し、その後自分自身の本当に望むタイプを知るチェックテストのようなものがあり、それから男性を目に映ったことから反応する視覚系、耳でとらえるのがどの感覚より俊敏な聴覚系、感情あるいは情緒というように心に響き残ったもので語ろうとする触覚系にわけて、それぞれのタイプに向けてのアプローチ法を展開している。確かに恋愛経験が豊富な人はやっているだろうなと思ったが、ここに書いてあることをできる人は、恋愛に限らず、仕事での人間関係も含めてかなり優秀な人間かなと思う。そこまで意識的にできるのか?と感じた。まあ女性向けに書かれている本で、読んでいる自分が男で別に男に恋愛としての興味があるわけではないので、ちゃんとは理解できていなかったというのがあるかもしれない。でも読んでいて、恋愛の悩みというのは男も女も似たようなものだなあと思った。どちらも人間だし、人間関係の悩みは基本的には男女同じようなものか。だが、この本にはさほど触れていなかったが、女性の場合は(場合によっては男性も)相手の社会的地位、経済力なども判断材料に入るだろうが、その場合の気持ちとのバランスってどうなんだろう、どちらを重視するのだろうか?悩んだらきりがないな。また機会があれば考えよう。男性へのアプローチを知りたい女性にとってはためになる本なのかなと思う。
2008.03.14
コメント(2)
-

最近読んだ本228
本番で最高の力を発揮する法ステファン・ロング 著山本一羊 訳日本実業出版社メンタル面を強化し、結果をだすための方法について書かれた本。数々のオリンピック選手の実例をあげながら、その運動競技における成功法則を、人生にも当てはめている。「勝つために学ぶ」「勝つために準備をする」「勝つためにプレーする」とテーマを大きく三つにわけて書かれているが、実際に読んでみて、とことんまで自分自身を信じることを強調しているなと思った。すべての土台になるのは自尊心であると。周りに左右されず好きなことだけをひたすらやればいい。なかなか難しいことだけれど大事なのはそれを貫けるかどうかということなのか。やはり最後は自分がやりたいのかどうかということにいきつくのかな。あと、結果を出したとき全て自分の努力の成果だと思えというのは面白いなと思った。その反面失敗も責任転嫁せずすべて自分のせいだと考えるということも書いてあったが、自分がやったという自己認識が自分の精神面をよりタフにしてくれるらしい。まわりのおかげ、運のおかげというのもあるとは思うが、自分の精神を強くするという意味ではそういうものの考え方もありかもしれない。勉強になった本。自分の中の引っかかり・行動という種をまけば習慣を収穫し、習慣という種をまけば人格を収穫し、 人格という種をまけば運命を収穫する。・成功するために有効な原則をもつ 「原則=どうすれば最もうまくいくか」・自らの個性を大事にしましょう。その結果、自分自身を信用するようになるのです。 自分をどう思うかということをコントロールするところから始めて、考え方を 変えることで自己認識を強め、他人の望む人間になろうとすることをやめて、自分自身 の夢、希望、恐れ、誤りを心から受け入れましょう。あるがままの自分を受け入れるのです。・自分の弱さを無視する。・パフォーマンスの後、メンタルの強い人間が最初にやることは、結果がどんなものであれ、 成功したことは自分の手柄だと考えることです。こういう人たちが極めて忍耐強くいられる のは、何といっても、まずは自分がきちんと達成できたことに注目するからなのです。・単純化する・最後までやり遂げられないと勝ちはない。
2008.03.13
コメント(0)
-

最近読んだ本227
週1時間の集中力があなたを変える!デイブ・ラクハニ 著島村浩子 訳ソフトバンククリエイティブ集中力、時間の使い方について書かれた本。生活の質やビジネスの価値に本当の差が出るのは、時間の使い方によるのであり、また自分に「変化を起こすには1時間あれば十分である」ということについて効果や実践方法、多くの人が失敗してしまいそうな部分に対してのアドバイスなどが書かれている。最終的にはマラソン級の継続を意識せよというが、まずは1時間。1時間というのはほとんど誰でも忙しい生活のなかから時間を見つけ、変化を起こすために投資できるからであるとのこと。自分がどのように変わりたいかを明確にイメージし、しっかりと準備をしてから物事にとりかかる。ということだったが、ビジネスに関していうと必要なことだと思うが、自分に変化を起こすということが目的であれば、そこまでこだわる必要はないかなと思う。「とりあえずやってみる」でいいのでは?少なくとも今の自分においては行動がすべての始まりかなという気がする。特定の分野を徹底的にやり抜くのはやはり必要だと思うが、たとえ3日坊主になったとしても、そのとりかかった分野に関しては、今後は自分の視野の中に入ってくるから、程度の差はあれ、今まで拾えなかった情報をキャッチできるようになる。飽きっぽいといってもその飽きた分野が3つ4つでなくて、100や200もあればそれだけ視野が広がっていくから必ず自分にしっくりくる分野に出会えるだろうし、逆にそれだけ移れる行動力は賞賛に値すると思う。行動が変化の源であると言いたかっただけだが、この本に関してはややハードルが高いかなという気がした。でもこの本にあるように明確なビジョンを描き、なぜそうありたいのかを徹底的に考え抜き、準備をしてから、行動することで華々しい結果がでるのかなとも思った。こういう考え方もあると頭の片隅に置いておこうと思う。自分の中のひっかかり・週1時間でプライベートやビジネスを一変させるには、批判的な考え方(クリティカルシンキング) を学んで使えるようにしなければならない。クリティカルシンキングは問題点を見つけ、 効果的な解決策を練る確かな基礎となる。 批判的に考えるというのは、問題点について一番合理的で納得のいく結論に到達するため、 情報、アイデア、状況を検討する過程のことだ。・自分自身やビジネスに変化を起こそうという試みが失敗するのは、目標を達成するための 準備がしっかりできていないからだ。成果をはっきり定義するというのは最も効果的な ステップだ。 準備のための3つのステップ 1.目標をはっきり定義する。 2.実行することを具体的に定義する。 3.目標達成の判断基準を決める。・重要なことを成し遂げる人は、ほとんど全員が他人から批判されるリスクを冒している。 それも二度。最初は初めに自分の努力をあざ笑われるとき。二度目は当人の成功を見た 人たちが、自分の行動力のなさを棚に上げて批判するときだ。 批判については、くよくよ考えなくていい。新たに身につけたスキルと知識の実践に ついてだけ考えよう。・自分を成長させるうえで忘れてはならないのは、続けようと努力することだ。 どんなことでもエキスパートの域に達するには、1000時間の練習が必要だということを 覚えておいて欲しい。 週に1時間だけ投資すると、あなたはこれから19年間忙しくなる。毎日1時間の場合は これから2.74年。どれくらいの速さを選ぶかはあなたしだいだ。 しかし実践は任意ではない。・いいアイデアに出合うためには積極的な「心の休日」が必要。
2008.03.12
コメント(0)
-

最近見た映画29
地下鉄(メトロ)に乗って 出演:堤真一/岡本綾/大沢たかお/常盤貴子 ほか監督:篠原哲雄脚本:石黒尚美原作:浅田次郎制作年:2006年いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降りて駅の階段を上がると、そこはオリンピック開催に沸く昭和39年の東京だった。真次(堤真一)に突如訪れた、現実とも夢とも信じがたいタイムスリップ。真次は恋人みち子(岡本綾)とともに過去へ遡り、そこで若き日の父(大沢たかお)とその恋人(常盤貴子)に出会う。時空を超える旅を続けるうちに明らかになる、父の真実の姿。そして真次とみち子との間に隠された、驚くべき秘密。それは二人の愛に過酷な選択肢を突きつける、あまりにも切ない運命だった・・・。 自分のイメージとしてはDVDの表紙が「ALWAYS/三丁目の夕日」に似ていて、堤真一がでているから昭和3,40年代の暖かい感じの作品だろうなあと思って見ることにしたのだが、いい意味で裏切られた。危篤状態になっている父親に会いに来てくれと言われている主人公は、兄の死の原因を作ったうえに、汚いやり方でお金を稼いでいる父親を憎み、会いに行く気などさらさらないのだが、ある日、地下鉄に乗って外にでると、タイムスリップしてしまい、そこから若き日の父親の姿に触れていく・・という感じで話は進んでいくのだが、結構重たい話だった。自分の亡き父親とダブらせてしまったということもあるが、父親が子供たちに示す厳しい態度とその裏にある本心と両方が描かれていて、その複雑な思いというものはとても共感できて、作品とは別次元だが、もっと父親にいろいろしてあげたかったなあという気持ちになった。この作品は時代が2つ以上にまたがる上に、登場人物が主人公、兄、弟、父、母、奥さん、子供、愛人とかなり多く、過去の時代の行動が現代に反映されるため、最初は登場人物を把握できるまでは集中していないとつながりがわからなくなるかもしれない。だけどつながりがわかると、親が子を思う気持ち、愛する人を思う気持ち、など胸に残るシーンが多いのでかなり泣けた。さわやかという感じではないが、印象に残るとてもいい作品だと思う。自分的にはかなり好き。
2008.03.11
コメント(0)
-

3月3日(月)から3月9日(日)に読んだ本
変人力樋口泰行ダイヤモンド社週1時間の集中力があなたを変える!デイブ・ラクハニ 著島村浩子 訳ソフトバンククリエイティブ本番で最高の力を発揮する法ステファン・ロング 著山本一羊 訳日本実業出版社ガイアの夜明け闘う100人テレビ東京報道局日経ビジネス人文庫 男性を見る目が今夜から変わる本トレーシー・キャボット 著青木雅子 平形澄子 訳KKベストセラーズ
2008.03.10
コメント(0)
-
自分勝手な話
人の話を聞くというのは難しい。人から連絡があったとき、こう考えて、こうした方がいいんじゃない?っていいたいけれど、相手はそれを求めていない。人が話す相手に求めていることって、結局は「自分の中にたまっているものを話すことで発散させる。」もしくは「自分の中でほぼ決まっている答えに対して背中を押して欲しい。」ということにいきつくのではないのか?今までの自分の人生ではありえないくらいいろんな方向から、悩みなどの話をされるようになって(今年に入ってから特に)、自分の人生でこんなに受けに回ることなんてなかったからなかなかとまどっていて、でもいろんな話を聞くうちに、相手の方で自分の悩みを解決する方向は決まっていて(もしくはわかっていて)、解決策を求めているんじゃなくて上記のようなことを求めているというのを実感した。こちら側としては経験したことないことに対して、なんて言えばいいのだろうか?と結構自分なりに考えて出した言葉もあっという間に吹き飛ばされる。でも、自分を出すというのはとてもやりずらいことなのに、それでも出してくれるというのはありがたい。信用されていると感じることができるから。ただ、自分の言葉で傷つけた人もいるので、自分の言葉や行動はよかったのかといわれるとはなんともいえない。人はそうやってずっと悩みながら生きていくのか・・何が言いたかったのかしら?自分の悩みプラス人の悩みまで自分で勝手に抱えていたから、「自分の中にたまっているものを話すことで発散させる。」か?だけど直接の役には立たなくても、誰かの気持ちが少しでも前向きになるために何かをすることは好きなんだよなあ。まあ、自分の悩みだろうが、相手の悩みだろうがどんと来いといえるくらい自分のレベルを上げていけよってことなんだろうな。さて、すっきりしたので、明日からまた戦っていきますか。
2008.03.09
コメント(4)
-

最近読んだ本226
大抜擢される55の方法中谷彰宏PHP文庫自分を相手に印象づけるためのヒントを紹介した本。オーディションは役者やモデルの選考だけでなく、就職試験、日ごろの出会いなど、自分をアピールする機会はどの人間にも訪れるわけで、この本は、誰にでもやってくる人生のオーディションの場面で、どうすればいいのかということについて書かれている。人との出会いはほぼ一瞬で決まるといっても過言ではないだろう。自分の中でも無意識的にあうあわないの振り分けをしてきたのかなと思う。自分の中で人間関係を振り返ってみると、すべては一瞬で決まっている気がする。自分は余計なかけひきなどせずまっすぐいく人間なので、敵味方(というよりは自分とあうあわない)の差はかなり激しい。自分のような人間とはあわない人(こちら側もそうだが)は確実にいるわけで、だけど、年を重ねていくうちに、あわない人もそれぞれの生き方をして自分なりの価値観をもっているし、部分で見ると尊敬できる部分も見えてきたり「あわない=嫌い」ではなくなってきたかも。距離のとり方を覚えたのか。あくまで以前の自分よりはだけど。一緒に食事などはしないと思う。それはともかく、この本を読んで思ったのは結局は毎日の積み重ねと外見の清潔感が大事なのかなということ。やっぱり人は第一印象が大きく左右するのは間違いないし、ただ第一印象は、戦いのリングに参加する権利が与えられただけで、そこから勝ち続けるには、日ごろからのトレーニングで自分の引き出しをたくさん作るしかないんだろうなあと思う。自分のあり方について自分と対話できた本だった。自分の中の引っかかり・オーディションはほぼ一瞬で勝負がつきます。 それは、あなたの生き方が一瞬で出てしまうからです。 オーディションや面接は、そんなに短い時間で本当にわかるのか、 と批判する人がいますが、わかるのです。 面接で斜に構える人は、仕事を与えられても一生懸命やることはありません。 仕事に真正面から向かうことを恥ずかしいと考えているからです。・相手がのってこない話は、はやくやめる。・「会ってみたい」と思わせたら、勝ちだ。・たった今、オーディションがあっても受けられるようにしておこう。・1度来たワイシャツは、気合いが抜けている。 →オーディションのような「ここ一番」の時にはケチってはダメです。 ケチることによって、気が抜けるというマイナスが出てきます。 気に対しては、絶対にお金をケチらないことです。 クリーニング代だけの小さな問題です。しかし、一番迷うところでもあります。 日々の生活は、すべての時間がオーディションのつもりで気を張っていなくては なりません。1回そでを通したものは、それがたとえ10分であっても、 クリーニングにだしましょう。
2008.03.08
コメント(0)
-

感銘を受けた本164
成功する男はみな、非情である。角川いつかPHP研究所数々の成功者たちとの関わってきた著者が成功者たちが持つ要素について書いた本。なかなか過激な本だと思う。己のみを信じ、邪魔するものを排除し、とことん結果を出すことにこだわる。孤独とつきあい、決断し続ける。モノサシはつねに自分の中に置き、とにかく勝ち続ける。この本は、日本国内にとどまらず、海外も含めていろんな成功者に触れてきた著者が成功者たちの持つ要素というものをとりあげ、コメントをしているのだが、自分自身あまり使わない言葉、考えにくかったことを引っ張りだしてきているので、結構刺激を受けた。ただ、成功している人たちの「生のことば」というのは、いいまわしがどうあれ、説得力があるのだけは間違いない。あとは、成功する人間たちはひたすら「結果をだす、勝つ」ということにこだわっている。執念といってもいいのかもしれない。「勝つ」と執念をもって戦いひたすら勝ち続けていく・・単純だが最後は「勝ちたい」という気持ちが強い方が勝つのだろう。成功するためにはということで、様々な本が出ているが、この本は闘争本能を刺激されるような本だった。自分の中のひっかかり・成功をし続けるためには、汚れる仕事はしないこと。・成功者は初めから違っている。語るべき将来プランがとにかく面白いのだ。 ・・世界中どこでも人は興奮したいし、笑いたいし、喜びたい。そんな物語を 持っているのだ。・男の闘争本能に従うこと 成功するには、つねに勝たねばならない。・人をあてにしない。いざというとき、自分で解決する力を持つ。・上位二割になれる人間は、覚悟がいる。平凡な幸せに拘泥しないこと。・無能な人、役に立たない人、戦略に合致しない人、文化を共有できない人、 を排除すること。・成功を「予行演習」すること。成功することに慣れておくこと。 できるだけ高いレベルでイメージする癖を身につけていくこと。 ・辛抱強くチャンスを待つ。やみくもに動くばかりが能ではない。・リーダーは、自分自身の人生で経験した生の素材をもとに、自分のスタイルを つくらなければならない。・悪い言葉は口にしない。 成功者は、負ける人間とはかかわらない。 負ける人は負けを選ぶとわかっているから。
2008.03.07
コメント(0)
-

最近読んだ本225
「がんばらない、うまくやる」サラリーマン保身術社会人サバイバル研究会小学館文庫サラリーマンが会社、社会でうまくやっていくための知識について書かれた本。法律学、社交術、キャリアアップ術、貯蓄学、健康学について、それぞれの専門家が一般的な常識的なことから、一歩抜け出すためのアドバイスなどサラリーマン向けの視点から書かれていて、学生時代には「知らなかった」で済んだ事も社会にでたらそうもいかないよということで、自分の身を最低限守るための知恵を教えてくれる。自分的にはそんなに真新しいことはなかったが、落とし穴にはまらないように確認というような感じで攻めの本というよりはどちらかというと守りの本だった。自分の中の引っかかり・ゆったりとしたきれいな挨拶がコミュニケーションの第一歩 →頭の下げ方一つで、その人の人生観が透けて見えてしまう。・「いい人だ」という第一印象の刷り込みがビジネスを成功させる、・謙虚に他人を観察し、学び取ること。それが自分を確実に成長させる秘訣である。・人生においては、会社より自分自身を優先させるべきである。 この当たり前のことがわからない人が多い。私は、自分の価値観を曲げてまで 会社に迎合することはないと思う。・「つくられた不安」に振り回されないで生きよう。
2008.03.06
コメント(0)
-
最近読んだ本224
マーフィー 最高の自分になれる法植西聰成美文庫マーフィー理論による「夢実現」への考え方について書かれた本。あなたは本当に幸せな人生をおくっていると自信をもっていえるのだろうか。「生きがいは何か」と聞かれたときにはっきりと答えられるものを、もう、見つけただろうか。幸せな人生を送るために、真にやりたいことを見つけるために、自分と向き合い、自分自身に本当にやりたいことを問う。この本は、「生きがい」をテーマにマーフィーの言葉を集めているのだが、著者が人生の様々なシチュエーションを読者に投げかけて、読者自身が想像していくことで、自分自身と向き合い、それからマーフィーの考え方を持ってくるというスタイルで書かれている。自分のことを考えると、人生において今が一番おもしろいかなあ。自分が忘れていたことを思い出したりして自分の気づきになったので自分を見つめるという意味ではとても勉強になった本だった。自分の中の引っかかり・人生の楽しみや生きがいを見失ってしまったら、幸福感を満喫していた 過去の自分を振り返ってごらんなさい。どんな遠い過去の出来事でも かまいません。 楽しかった自分、何かに夢中になっていたことを思い出してみるのです。 そうすると、思わぬ解決策が得られるはずです。・ハンディや悪条件はあなたという人間を大きく発展させるチャンスであり、 生きがいを創造していくうえでの起爆剤となります。言い換えれば、 生きがいとは何かを達成した瞬間に生じるものではなく、悪条件を克服 しつつあるプロセスにおいて生じるものなのです。・夜明け前が一番暗い。でも朝は必ずやってくる。 どんな困難な問題に直面しても、最終的にはハッピーエンドになることを信じなさい。 それは潜在意識が実現してくれます。
2008.03.05
コメント(0)
-

最近見た映画28
フラガール監督:李相日『69 sixty nine』脚本:李相日、羽原大介『パッチギ!』出演:松雪泰子、豊川悦司、蒼井優、山崎静代(南海キャンディーズ・しずちゃん)、岸部一徳、富司純子 制作年度 2006 日本 収録時間 120分 昭和40年のとある炭鉱町。石炭から石油へとエネルギー革命が押し寄せ、町は風前の灯だ。この危機を救う為に炭坑会社が構想したのが、レジャー施設「常磐ハワイアンセンター」だった。北国をハワイに変えるという、起死回生のプロジェクト!目玉となるのはフラダンスショー。しかし、炭鉱を閉じて”ハワイ”を作る話に人々は大反対。残ったのは、紀美子(蒼井優)、早苗(徳永えり)、初子(池津祥子)だけだった。そこに、大柄な女の子・小百合(山崎静代)が連れられてくる。そして娘達にフラダンスを仕込むため、東京から平山まどか先生(松雪泰子)が招かれるが・・・。廃れゆく炭鉱町をフラダンスショーによって復活させようとする人々を描く、実話ベースのヒューマンドラマ。盆踊りしか知らなかった炭鉱娘たちがひたむきな熱意によって強く美しく、そして華やかに成長する姿を生き生きと映し出している。かなりおもしろかった。素人の娘たちがフラダンスを踊るためにひたすらがんばって最後にうまく踊るというストーリー自体はとてもわかりやすいが、「常磐ハワイアンセンター」オープンまでの過程、レッスン中でのやりとりなど熱い人間ドラマがあってそれらを知った上でダンスを見るとなんだか泣けてきた。この作品で、フラダンスの動き一つ一つには意味があるということや、ゆったりした曲、アップテンポの曲などいろんな種類があることなど、自分が考えている以上に奥が深いもので、今までフラダンスというものをちゃんと見ていなかったんだなあと申し訳ない気持ちになった。自分も最初は作品にでてくるハワイアン計画に反対の側と同じような気持ちだったのかもしれない。でも何かに一生懸命な姿というのは人の心を打ち、周りを変える力をも持つわけで、見ているこちら側も胸を熱くさせられる。クライマックスのフラダンスショーはとてもすごくてつい見とれていた。笑いあり、涙ありの見ていてとても気持ちのいい作品だった。本当によかった。
2008.03.04
コメント(2)
-

2月25日(月)から3月2日(日)に読んだ本
成功する男はみな、非情である。角川いつかPHP研究所ヒルズな人たち佐々木俊尚小学館「がんばらない、うまくやる」サラリーマン保身術社会人サバイバル研究会小学館文庫大人失格松尾スズキ知恵の森文庫マーフィー 最高の自分になれる法植西聰成美文庫
2008.03.03
コメント(0)
-
まいった・・
一時間くらいかけて昨日の講演会のことを書いていたが、いざ、「公開する」を押したら、画面に期限切れみたいなことがでて、結局今まで書いたのが全部消えてしまった。気持ち入れて作成していたので、ショックが大きい。これからは本の記事書くときみたいにメモ帳に書いてからにしよう。直接書き込むとこういう形で失敗する可能性があるのか・・気をつけよう。かなりまいった。今はふたたび書くのは厳しい。ごめんなさい。
2008.03.02
コメント(0)
-
中谷彰宏講演会
中谷彰宏の講演会に行ってきて、本人を直接見てきた。自分の中でこういう大人になりたいと思う数少ない人。やっぱりカッコいいわ。一般的な50前の人間には全然見えない。と講演会の話をしたかったが、大学時代の親友が就職を決めたということで、これから行かなきゃならない。これまでの苦労を知っているから、直接声をかけたいし、今のこの瞬間を逃すと、次に会えるのはおそらく半年後かそれ以上かもしれない。一緒に喜びをわかちあってきたい。本当によかった。イベントが重なるときというのはとことん重なるものだなあ。朝までかしら・・中谷さんの話も含めてまた明日ということで。
2008.03.01
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-
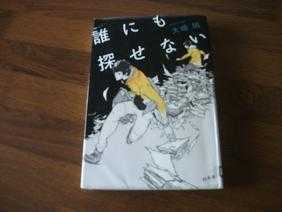
- 本のある暮らし
- 《画像》シナモン食パン 作りました…
- (2025-11-14 18:04:17)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 日々の贈り物・10月
- (2025-11-14 17:49:04)
-







