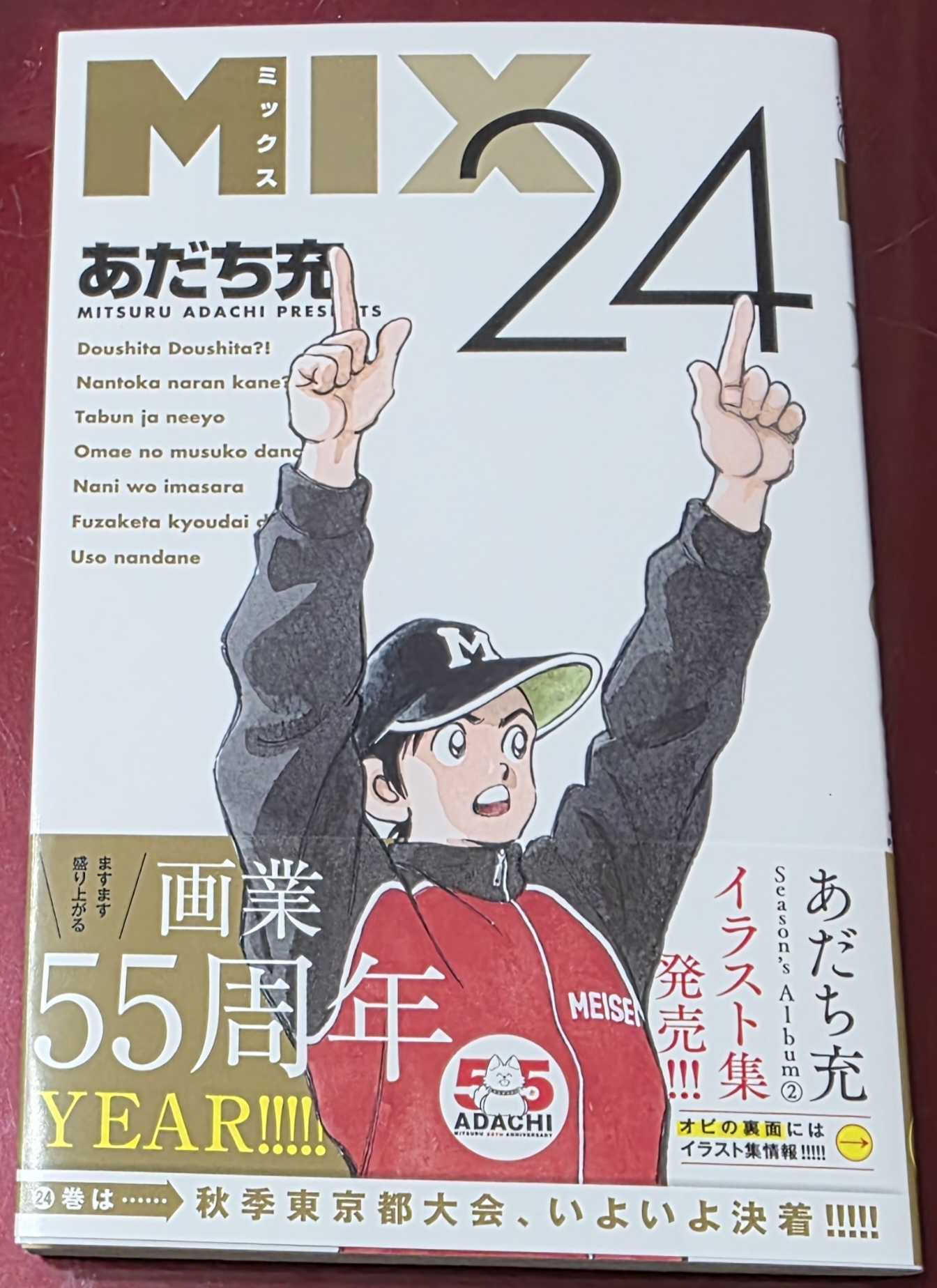2015年01月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
1/18に読んだ本
誰にでもできる「交流会・勉強会」の主催者になって稼ぐ法 安井麻代同文館出版4時間半熟睡法 [ 遠藤拓郎 ]フォレスト出版成果主義時代のリーダーになれる人なれない人 梅森浩一IBCパブリッシングお金が貯まる人の思考法横山光昭講談社頭の回転数を上げる45の方法 [ 久保 憂希也 芝本 秀徳]ディスカヴァー
2015.01.18
コメント(0)
-
ワインの基礎知識
ワインの基礎知識アカデミー・デュ・ヴァン監修田中清高 奥山久美子 梅田悦生 著時事通信社ワインの基礎知識について書かれた本。2013年にワインエキスパートの資格をとって、個人的な仲間でワイン会などを行ってきたが、もっとちゃんと勉強したいと思って手に取った本。これは個人的な思い込みだが、ワインスクールのアカデミー・デュ・ヴァンでの初級に近いクラスの教科書だったのではないかなと思った。それくらい、ワインをちょっと踏み込んだ人用の知識が載っているなという気がした。どうだかわからないが・・まあ、読んでみて、とくに印象に残ったのがエピソードの部分。たとえば、ドンペリの愛称で親しまれるシャンパン ドン・ぺリニヨンだが、もともとは修道僧で、シャンパーニュ地方にあるオーヴィエール修道院の酒倉係に任命されていたが、1668年の春、酒倉を見回っていると、「ポーン」という音とともにコルクが自然に吹き飛んだワインを見つけた。(理屈としては寒さのために発酵が止まっていたワインが春になって温度が上昇したため、ボトルの中で再発酵し、できた炭酸ガスの力でコルクが吹き飛んだということ)その後ぺリニヨン修道僧はワインをブレンドしたり、ボトルを強化したり、コルク栓を使うなど研究を重ねて今のシャンパーニュができたとのこと。あとは、フランスでブルゴーニュがワインの王様、ボルドーのワインが女王となぜ言われるようになったかというと、もともとブルゴーニュ地方は交通の中心であり、ボルドーと比較するとパリに近いしフランス王朝が支配していたため、ブルゴーニュの素晴らしいワインは古くからフランス王朝御用達であったため「ワインの王様」と言われるようになった。一方ボルドーは、もちろん素晴らしいワインは作っていたものの、港町であり、パリやベルサイユから遠いという地理的事情、百年戦争が終わるまで、イギリス領であったという歴史的事情のため、ボルドーワインがフランス王室に知れ渡るようになったのは、ブルゴーニュワインより後となり、このとき既にブルゴーニュは、「ワインの王様」と言われていたため、ボルドーワインは、「ワインの女王」と言われるようになったと言われているとのこと。また、フランス王室は男子系相続が王位継承の原則だが、イギリスは女子系相続があり、ボルドーはイギリスのワインであり、女王陛下のワインであるため「ワインの女王」と呼ばれる説もあるらしい。こういうストーリーを知るとさらにワインが面白くなってくる。近いうちにワインに関するブログでもたちあげようかなという気にさせてくれる本だった。ワインの基礎知識
2015.01.18
コメント(0)
-
ブレインダンプ
ブレインダンプ [ 谷澤潤 ]東洋経済新聞社脳の機能を活用するための手段について書かれた本。成果を出せない人というのは、1優れたアイデアを出すことができない。2アイデア実現のために何をすればいいのかわからず、 行動の優先順位がつけられない。3実行力に乏しく、アイデアを実践できない。これらを克服する手段をこの本「ブレインダンプ」で紹介している。ブレインダンプとは、「あなたの脳の中にあるものを、すべて出し尽くす」という意味で、「もうこれ以上は出てこない。私の頭の中はからっぽだ」とあなた自身が観念するくらいに、すべて紙の上に書き出す。そして脳が身軽になり、前に進むために必要な次のアイデアや、次の行動イメージをどんどん出してくれるとのこと。確かに紙に書くことで、頭はすっきりするし、やりたいことを書き出していったら、どんどん膨らんでいくなと思う。今回特に印象に残ったことは、頭に浮かぶアイデアということをとても大事にしているなということ。アイデアは一瞬だけ浮かぶもので、すぐ逃げていくので、この瞬間を絶対に逃してはいけないとのことで、必ずメモをとる習慣とシステムを整えなさいとかいてあった。今後は自分なりのメモの方法をさがして、かつシステム化する意識を持っていこうと思った。脳をいい意味でもっと使っていこうと思った本だった。自分の中のひっかかり・結果を出すことができる人とできない人との差は、脳の機能を最大限に 活用できるかできないか。ただそれだけなのだ。・革命的なアイデアは、連想からしか生まれない。 ・・連想を誘発する行動をとること。あなたの脳は、どんな場面を みせて、どんな音を聞かせ、どんな感覚をもたせたときに、いま あなたが追求しているテーマに関して、アイデアを出してくれるか を考える。そしてそれを実行する。あなたが力をいれるべきことは、 ただこれだけだ。・アウトプットする場をつくる。・私たちは、イメージができあがってはじめて行動を起こすことが できる。頭にイメージが浮かばないまま、行動を起こすということは できない。・時間に追われ短期的な成功を得なければならないときには、脳は プレッシャーとしてではなく、ストレスとしてそれを受け止めて しまう。 →短期的な目標は、周囲に宣言しない。 長期的な目標はできるだけ周囲の人に話した方がよい。 自分に対するアファメーションにもなるし、まわりのほとんどの人が 応援してくれる。・1つ上のレベルに上がったときや独立起業を果たして一国一城の主に なったときには、いつまでもタイトなスケジュール表とにらめっこを しているようではいけない。 そのときあなたに期待されるものは、与えられたたくさんの仕事を 効率よくこなすことではない。価値を生み出す源泉そのものを 創出することだ。・得意な方法で実績を作れば、苦手を克服できる日が必ずやってくる・あなたの得意なところで、全力で勝負に挑めば、必ず次のステージ に上がることができる。そうなったときにもう一度、苦手だった ことに向き合ってみると「以前はどうしてもできなかったのに、 今ならできる」ということに必ず気づく。そのようなときが 必ず来る。それを信じて、今、あなたが最もやりやすい方法、 いまのままのあなたが、自然体でできるやり方に、全力を投じて いただきたい。ブレインダンプ [ 谷澤潤 ]
2015.01.16
コメント(0)
-
ボクのインプット&アウトプット法
ボクのインプット&アウトプット法 [ 千田琢哉 ]アイバス出版大量インプット&アウトプットのやり方について書かれた本。著者が行っているインプットとアウトプットの方法について書かれているが、まず根本的な考え方として、出し惜しみせずにアウトプットすることで、大量のインプットができるということ。呼吸と同じように、息を吐ききることで、自然と大量の息を吸うことができるのと同じだと。確かにその通りだなと思う。あとは、特に印象的だったのが、著者は、読み終わったら即処分する習慣にすると、たくさん読める。と考えていることが、気になった。どんどん読んで、どんどん処分していくと、読書が質量ともに大幅にアップしていくとのこと。自分はブログに残してからと意識はしているが、今まで捨てるという意識はなく、少し抵抗があったが、著者ももちろん捨てるときは「今までありがとう」と合掌して捨てているというのを見て、一期一会の精神で、どんどん読んで、どんどん処分してみようかなと思う。自分の読書のやり方を変えるきっかけになった本だった。自分の中のひっかかり・1000回繰り返し読める本に出逢うために、たくさん本を読む。・時間を忘れて没頭できるものが、本当にあなたに向いている本なのだ。・独りで汗をかいていると、ある日振り返ったら誰かいる。・人脈は拡げるのではなく、深める。・人脈が長続きしないのは、あなたが勉強不足だから。 ・・相手をドキドキ、ワクワクさせるためには、まずあなたが勉強することだ。・本を読む人脈は、年齢とともに謙虚になって富んでいく。・後輩に教えると、自分は何もわかっていなかったことに気づく。・今のプロジェクトが終わるまでに、次の企画を仕上げる。・間接的に詐欺に遭ったら、その人の周辺すべての人脈を整理する。・成金が落ちぶれるのは、固定費を上げるから。 ・・固定費を”急激に”上げてはいけないのだ。・自力で地獄から這い上がると、将来のネタになる。・成功に直結する遠回りとは、1%でも夢とつながっていると確信できることだ。ボクのインプット&アウトプット法 [ 千田琢哉 ]
2015.01.15
コメント(0)
-
起業家10000人から見た「結果を残す人」のたった1つの行動習慣
起業家10000人から見た「結果を残す人」のたった1つの行動習慣 立石剛フォレスト出版自分の強みを生かすヒントについて書かれた本。現在、人との出会いや自己啓発の本やビジネス書などで、結果をだす様々な考え方が出ている中で、著者のいう結果を出し続けるために大切な、たった一つの習慣とは何か?それは、自分の「強み」に気づくということたとえ仕事と関係がなくても、自分の「強み」を伸ばしていく過程で、必ずどこかに自分の仕事との接点がでてくるはずで、その接点を少しずつ広げていくと自分だけしかできない仕事、名誉、お金をもたらすとのこと。自分の強みを生かすということについては、自分の興味があるところから徐々に広げていけばいいかなと漠然とした思いはあるが、ただ自分の部下の強みを知っていますか?と問われたときに、あまりわかっていないことに気がついて、自分自身の管理能力の甘さを痛感するとともに、日頃からコミュニケーション、信じることを意識しつつ、自分だけでなく、相手の強みなどももっと考えていかなきゃなと思った。自分の部下に対する接し方に反省するきっかけをもらった本だった。自分の中のひっかかり・大切なことを、同じように大切にする人と付き合う。・いい目的に出会うと人は変わります。・選ばれる人になるために、自分をブランド化しよう・「社員や部下の強みを知っていますか?」 ・・なぜ気づかないのでしょうか? ・・「リーダーが部下と向き合えていない」ことが原因・褒める、叱ることよりもっと大切なこと ・・「信じる」こと起業家10000人から見た「結果を残す人」のたった1つの行動習慣 立石剛
2015.01.11
コメント(0)
-
1月8日に読んだ本
シャンパンの教え [ 葉山考太郎 ]日経BP社シャンパンについて他のジャンルの芸術(宝塚とか映画など)でたとえながら書いた本。「やる気」と「成果」が出る「最強チーム」の成功法則 山谷拓志東洋経済結果の出るチームの作り方について書かれた本社長のノート [ 長谷川和廣 ]かんき出版著者の経営における考え方などについて書かれた本ワインの基礎知識アカデミー・デュ・ヴァン監修田中清高 奥山久美子 梅田悦生 著時事通信社ワインの基本的なことについてかかれた本人材育成の超プロが書いた気づく人気づかぬ人 佐藤英郎アチーブメント出版人を育てるためにはどのようにすればいいか書かれた本
2015.01.09
コメント(0)
-
一流秘書だけが知っている信頼される男、されない男
一流秘書だけが知っている信頼される男、されない男 能町光香10年間エグゼクティブの秘書を務め、様々な人たちを見てきた著者が、信頼されるための方法について書かれた本。信頼今の自分に必要というか、意識しているキーワードであり、この本にそのキーワードが書かれていたので手に取ってみた。一番印象に残ったのは、「相手を信頼することなくして、人の信頼を得るのは難しい」ということ。まず、こちらから信頼するからこそ信頼されると。シンプルでとても簡単に思えるが、これまでを振り返って裏切られた、裏切ったこと、両方あったので、こちらからまず信頼するのは、なかなかためらう部分もあるが、でも、これは心に余裕をもっていれば、自然とできることであり、正しいことなんだろうなと思う。意識していこうかなと。あとは、状況を一瞬にして把握するセンサーを磨くということも書いてあって、空気を読むことは大事でそこも常日頃から意識する必要があるなと感じた。ほかには信頼される男は歩き方が美しいというのもあり、外見の重要性なども説いており、信頼される人間というのがどういうことをしているのか?ということがいろいろと書かれている。人間関係について勉強させてもらった本だった。自分の中のひっかかり・「信頼される上司」のもとで働く部下や同僚は、とても幸せそうです。・時間をかけて「信頼」は生まれてくるものです。 ・・「信頼」は、言葉に出した瞬間に偽物となる・「言い訳」の数だけ「信頼」が失われていく・「信頼される男性」は、ただ「ありがとう」と機械的に伝えるのではなく、相手の心の機微を読み、 相手の気持ちに寄り添いながら「ありがとう」を言葉にして伝えています。 この違いが、「ありがとう」という言葉に深みが増すかどうか、より伝わりやすくなるかどうかを 決めているように思います。・信頼される男は、ネガティブな言葉を発しない・「自信」はまわりの人が運んできてくれるもの・無邪気な遊び心を持つと、まわりからの期待が高まる・信頼される男は、笑顔のときに目も笑っている・経験の積み重ねが「人としての色気」を醸し出す・「男のロマン」をロマンで終わらせない人がかっこいい・信頼される男は、「人生哲学」を持っている・自分自身を「信頼」し、自分自身の人生を生きる一流秘書だけが知っている信頼される男、されない男 能町光香
2015.01.08
コメント(0)
-
仕事は6倍速で回せ!
仕事は6倍速で回せ! [ 石塚孝一 ]祥伝社「時間がない」「仕事が多すぎる」とあれこれ不満を抱えている人は、効率の悪い働き方をしているのではないか?という視点から著者の時間の使い方について書かれた本。人と同じことをやっていては生き残れないということで、著者は6倍速ということを提唱しており、著者がやってきたことを読んでみるとかなりすごい。休みなく走り続けている印象をうける。かといって現実離れしているかといえば、そうではなく、誰でもやろうと思えばできるが、やらないだけということをひたすらやっている。一番大事なのは勉強し続けようという意識を持ち続けることなのかなと感じた。そこからすべての行動が始まるのかなと。話題はやや違うがこの本でとくに、残ったのが、リーダーは「アメとムチ」の本物のアメを上手に使う。ということ。飴を食べながらカッカする人はいないとのことで著者は部下に渡すようのアメがデスクにあるらしい。これは面白いと思ったので、自分も取り入れようと思う。時間の使い方の意識し、学び続けることの大切さを学んだ本だった。自分の中のひっかかり・ポストがない企業には未来はないと思う。・出会いの機会を増やす。そうすれば、見識の高い人と知り合える。・人生のどこかで人の2倍働いていたほうが、50代以降に楽をできる可能性が高い。・大きなチャンスを引き寄せる成功法則 ・・「誰もしたがらない仕事を引き受ける」・3年でこの会社のすべてを吸収し、辞める」くらいのつもりで 行動する。・「わかりません」と言ってはいけない。仮定でもいいから、答えを 出して前進せよ。・鏡の前で「優秀そうに見えるか?」と自らに聞く。 優秀そうな人を演じられれば、ビジネスの武器になる。・2つ上のポジションで考える。・リーダーは部下の尻を叩くのが役割ではなく、部下が最大限の能力を 発揮できるような環境をつくるのが役割ではないかと思う。
2015.01.07
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1