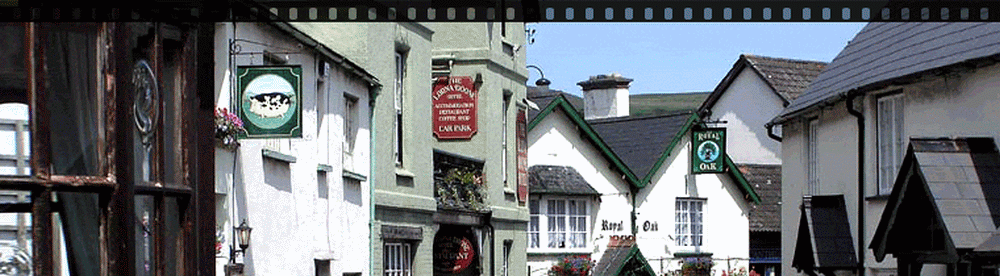2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年03月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
ちょっとした感動
送別会の居酒屋でのこと。開始時間が遅かったので、帰りの電車の時間もあり、途中で退席する女性が2人いました。コース料理があと2品と最後のデザートのみとなったところで、電車の時間が気になる女性2人はそろそろ帰ろうか…と話をしていました。料理を運ぶお店の人がその会話に気付き、「お二人分だけ先にデザートをお出ししましょうか」と親切に気を使ってくれました。コース料理も非常においしく、デザートも食べることができ、お店の人の心配りにも感激して、女性2人は喜んで帰宅しました。コース料理の順番通り、普通に料理を出せば、「おいしかったね」で終わり、特に感動もなかったかもしれませんが、お店の人の心配りがスパイスになってさらに料理をおいしく食べることができ、女性2人も感動したように思います。客の会話を聞いて、頼まれてもいないのに、とっさに自分で判断して、自分のできる範囲で最大限にお客さんをもてなそうとするスタッフの姿勢に感動しました。お客さんが喜ぶサービスって、何もお金をかけなくてもできるんですね。
2005年03月30日
コメント(5)
-
プラスマイナス
「この人の一生ってすてき!」と思える女性の有名人ってなかなかいないよね…と同僚の女性が話をしていました。例えばタレントなどは、人気のある旬な時に一時期にあこがれる人はいますが、「この人の一生みたいに自分の人生も過ごしたい」と思える女性はいないとのこと。言い換えれば、どのタレントに対しても、「いいなぁ、あんな風になれたら幸せ」と思える期間が短いということです。今は輝いていても、一生そうであるとは限らないということでしょうか。お金を稼いでいても孤独そうだったり、有名だけど悪い評判だらけだったり、(もちろん直接会ったことはないので想像で)輝いて注目を浴びている時は、幸せだと思うのですが、輝くときもあれば、そうでない時もあり、案外、人の幸せって、プラスマイナスで全体のバランスが取れている気がします。
2005年03月29日
コメント(0)
-
できるリーダー
できるリーダーは分類することがうまいそうです。売上が上がらない…客単価が減った…みんなのモチベーションが下がっている…いろんな好ましくない結果があります。なぜ好ましくない結果になったのか?いろんな人に相談すれば、いろんな原因が次々とあげられます。それらの原因を分類して意味のある単位にまとめ、その単位で対応するのです。分類した単位で対応すれば、そこに含まれる各項目も同時に解決することも多々あります。「分類」ができないリーダーは、根本的な改善センスがないかもしれません。そういえば、いつも細かいことばかりを指示、指導するリーダーっていますよね。
2005年03月25日
コメント(2)
-
年の功
満席の新幹線、お昼時で乗客のほとんどはランチタイム。そんな中、マニキュアを塗る女の子がいました。けっこう強烈なシンナー系のにおいを車内に充満させていました。会社の研修なんかでよくあるコミュニケーションゲームの一種で、ちょっと複雑な図形を自分だけが見ながら、言葉だけで指示して相手に描いてもらうゲームがあります。どれだけ早く描けるかを競うのです。このゲームのポイントは、こちらがこう言葉にすれば、相手はこう描くだろう…と予想しながら、どう話せば相手は思った通りの図形を描いてくれるのか?を考えることです。要は相手の思考を予測するということです。何十社もの社員にこのゲームをやってもらい結果を見てきた人の話しによると、ゲームの結果には、ある傾向があるそうです。若い社員ほど時間がかかるそうです。例えば新入社員です。つい最近まで学生だった彼らは、考え方や行動が似通った、同世代の中で生活していました。相手がどう考えているか、を考えるのではなく、自分がこう思うから、相手も同じように思っていると考える傾向があるのだと思います。思い込みは、どんな年齢の人にもあると思いますが、周りの人の気持ちを考えられるようになるには、年の功しかないんでしょうか。席に座れず、立っていたおばさん2人が、「年を取ったら、味を感じないのよねぇ」「鼻も弱くなって、においがよく分からなくなるのよねぇ」みたいなことを話していたのですが、今になって思えば、それって、さりげなくマニキュアの子に注意してたのか??さすが、年の功??
2005年03月24日
コメント(0)
-
100%大丈夫
現実をどう伝えるかで、聞き手の印象は変わります。「○△□予備校では、90%の人が東大に合格」「○△□予備校でも、10%の人は東大に入れない」どちらも現実で、同じこと言っていますが、聞き手の印象はかなり違います。受験生がこの予備校で、がんばろうと思うのは、きっと「90%の人が東大に合格」だと思います。「10%の人は東大に入れない」より、勉強にかけるエネルギーが全然違うはずです。会社でも、部下への言葉の投げかけ方ひとつで、社内に流れる空気やエネルギーが変わります。デジタル的な管理も大切ですが、人を動かすには、アナログ的な、感覚的な感じさせ方も大事だと思います。目標までまだまだの時は、「90%の人が~」と自信を持たせ、合格確実になりそうな時には「10%の人が~」と気を抜かないようにする。そして、受験当日には、「100%大丈夫」と安心させて平常心で受験に挑んでもらう。部下指導とちょっと似てますね。
2005年03月23日
コメント(0)
-
言葉の温度
新婦側の親戚として、神戸では一番歴史が古いと言われるある教会に行ってきました。ですが、式が始まる40分前になっても新郎が現れません。式のお世話をして下さる教会の女性が、「何時くらいにご到着のご予定でしょうか?」「今、どのあたりまで来られているんでしょうか?」と何回も何回も新婦に尋ねていました。新婦は携帯で連絡するのですが、山奥に教会があるせいか、つながらないようでした。「渋滞かなんかでしょう」と新婦はあせってもいない様子でしたが、お世話係りの女性は、どうしよう…というような表情でボク達の前をうろうろしていました。式まで、あと30分…その時「遅れてすみません!」と新郎が飛び込んできました。どうも事故渋滞に巻き込まれたようでした。新郎の登場に、お世話係りの女性は、「ドタキャンじゃなくて、ほんとに良かったぁ!わーん!」と安心したのか泣き出しました。そして、その言葉を聞いて、一同ドッと笑い出しました。というのも、まさかドタキャンなんて誰も考えていませんでした。結婚式で「ドタキャン」なんて、思っても口に出せないとは思うのですが、思ったことをストレートに口に出しても、嫌味になるどころか、場を和ますことがあるんですね。口に出してはいけない言葉が思わず出ちゃうほど、限界ぎりぎりまで心配してくれている心の温かさを感じて、場を和ますんだと思います。言葉に温度を感じたんだと思います。冷静に、真顔で「ドタキャンかと思った」と言えばきっと嫌味になったと思います。ひと騒動ありましたが、式も無事終わり、新郎の遅刻騒動も良い思い出になったようです。
2005年03月22日
コメント(0)
-
感性
両手に大きな荷物を持った人がエレベーターに乗り込んで来ました。どうやら行きたい階のボタンを押すのが大変なようです。あなたは操作ボタンの近くにいます。どうしますか?3連休の真っ只中、昨日あった出来事です。最近、新幹線乗り場への改札が自動改札に変わったJR某駅。小さな子供を連れた若い親子3人が、ヨタヨタと歩く感じでやって来ました。お父さんとお母さんは両手に大きな荷物を持っていました。お母さんの方はどうやら妊婦のようです。小さな子供は3~4才くらいでしょうか。親子3人は、たくさんの人があわただしく通り過ぎる改札をとてもスムーズに通過できる状況ではないと思い、自動改札すぐ脇の係りの人がいる改札を通ろうとしました。そこには、20代前半くらいの女性の駅員が一人、手を前に組んで立っていました。親子3人を見て不思議そうに「はいっ??」と挨拶をしたかと思うと「自動改札をお通り下さいませ」と手でジェスチャーをしました。「えっ?」と困った表情で一瞬、お父さんとお母さんはお互い顔を見合わせたのですが、「これを…」と、お父さんが手に持った切符を女性駅員に見せました。すると女性駅員は「自動改札で通れますので、切符をお通し下さい」と一言。何か言いたそうでしたが、むっとした表情で、若い夫婦は改札機の方へ向かっていきました。例えば、エレベータの中で、ボタンが押しづらそうな人がいれば、全くの他人なのに「何階ですか?」とたずねて代わりに親切にボタンを押してくれる人がいます。「ボタンを押したら、その階に停まりますよ」なんて、言わないと思います。仕事として働いている駅員が、とても改札をスムーズに通過できそうにない人に、「自動改札で…」と案内するのは、経験とか教育とかの問題より個人の感性の問題のような気がします。趣味にしても、仕事にしても、スポーツにしても、感性がある人はできる人だと思います。接客で定評のある、某スーパーは、社員の選考基準として、サービスマインドがあるかどうかを基準にしています。入社前に店で実際にアルバイトをしてもらってサービスの感性があるかないかを見るそうです。感性のある人が入社するため、社員教育はほとんどしないそうです。それだけ、感性が大切だそうです。感性…どうやって身につけるのか知りたいところです。
2005年03月21日
コメント(3)
-
当たり前の幸せに感謝
今の自分って、幸せ?お金があれば幸せ…家族がいれば幸せ…友人がいれば幸せ…好きなことができれば幸せ…でも、人って欲張りです。何でも好きなものが買えるほどお金があるのに、今度は好きなことができる自由な時間が欲しくなります。あったかい家族、心の安らぐ場所を手に入れたのに、今度は欲しいものが何でも買えるようにとお金が欲しくなります。何かを手に入れるために、目的を持って頑張ることは非常にいいことだと思います。ただ、今ある幸せへの感謝って忘れてはいけないですよね。アフリカでは世界で一番平均寿命が短いといわれる国があります。平均寿命は男性で約33歳、女性で約35歳です。日本ではつい60年前、戦争をしていました。いつ戦地へ駆り出されるかわからない時代です。ちょっと大げさかもしれませんが、この時代に、この国に、生まれたこと自体が幸せなような気がします。あまりにも当たり前すぎて忘れがちですが。
2005年03月18日
コメント(2)
-
100万円あったら
先日の新聞記事より10代の女性に聞きました。「100万円あったら何に使う?」一番多かった答えは、「貯金」。7割もの人がそう答えたそうです。何に使う?と聞かれて、貯めると答えているのです。彼女達の将来、過去に先送りされてきたいろんな問題と直面しなければならず、(例えば自分達の老後には年金もらえないとか)貯金することで安心という保険をキープしたくなるのだろうと新聞では分析していました。未来は明るくない、そう考える若い人が多いようです。不安があると人って、限定的な行動をとる気がします。仕事でも、新しいことにチャレンジして、失敗して評価を落とすくらいなら、チャレンジしないで、今の評価をキープする。評価を落として給料が下がっちゃう不安があるなら、自分ができる仕事の範囲でしかチャレンジしなくなる。失敗がない人は、新しいことにチャレンジしなかった人。毎年、年度はじめにそう思って、意気込むのですが…
2005年03月17日
コメント(1)
-
できる上司
「おしい!」昔の上司がよく使っていた言葉です。部下が自分の意見を述べる、部下がトラブル対応を報告する、例えそれらの意見や対応が間違っていても、上司が最初に発する言葉は、「おしい!」でした。もちろんきちんとしたトラブルの対応方法や、意見も聞いてくれアドバイスもしてくれます。最初に「おしい!」と言われて、自分の意見を否定されるのと、「お前それ、全然違うじゃん!」と頭ごなしに言われて否定されるのとでは全然違います。頭ごなしに怒られてばかりでは、大切な情報すら報告しづらくなります。ましてや、好ましくない報告、例えばトラブル報告等も一層話しづらくなります。仕事の情報でもプライベートな情報でもできる上司は自分のところに情報が集まるようです。ボクの周りを見回しても、情報が集まる上司と、集まらない上司っています。部下の結婚話を一番最後に聞くような上司では情報が集まらない上司かもしれません。
2005年03月16日
コメント(2)
-
コミュニケーション
かんたんに次の絵を描いてみましょう。「海の上にヨットを描いてください。」かんたんに横線を引いて、その上にヨットを描くと思います。たぶん、誰が描いても同じような絵になると思います。では、「屋根の上にカラスを描いてください。」絵心があるかないかは別にして、この時、2種類の描き方があると思います。ひとつは、屋根の「上」にカラスがとまっている絵。もうひとつは、屋根の「上」をカラスが飛んでいる絵。どちらも屋根の「上」です。伝える側の意図と伝えられた側の解釈が違うことってたまにあります。仕事でもこういうことが起きます。コミュニケーションが足りない状態とでも言うんでしょうか。コミュニケーションといえば、見た目の第一印象も立派なコミュニケーションです。案外、人って見た目で判断します(特に初対面の場合そうなのではないでしょうか)。スーツをぴしっと着て、髪型も清潔に整えていれば、信用できそう人と思いますが、だらしない服装で、無精ひげだとちょっと警戒してしまいます。(嫌味にならない無精ひげでいい味出している人も中にはいますが)人に感じさせる何かを与えるという意味では、見た目も立派なコミュニケーションだと思います。もちろん言葉もコミュニケーションです。簡単に使えて、簡単に理解できる手段です。ですが、伝える人の伝える力と、伝えられた人に理解する力がないと正確には伝わりません。「屋根の上にカラスを描いてください。」では、伝える側の意図する「上」と伝えられた側の「上」が一致しないかもしれなかったということです。屋根の上にとまっているのか、屋根の上を飛んでいるのか、伝える方も、伝えられた方も同じ事を相手も考えている…答えはひとつ…と思った時にコミュニケーション不足が発生しているような気がします。あわただしく仕事をしている中で、上司の指示の意図、もしくは自分の指示した内容について「こうだよね」「あってるよね」という確認って以外にしないのかもしれません。
2005年03月15日
コメント(2)
-
若くて知識と経験がある人
年を取ってから、気力、体力が充実していた若い時に戻れたらなぁなんて思うことが誰でもあると思います。あの時に戻れたら、こうやったのに、ああやったのに…って。でも、気力、体力は当時に戻っても、頭の中、知識は今のままという条件を誰でも勝手につけて空想していると思います。若くなる代わりに、知識も若い頃当時に戻る、となると、それだったら今のままでいいやとなってしまいます。(それって、ボクだけ?)結局、年をとって何事も恐れないパワーや体力などは減っていっても、引き換えに知識や経験が増えていってるんでしょうか。若い時には、経験、知識に乏しく、年をとってからは体力、気力が続かない、人って上手くできていると思います。最近話題の堀江社長。若くて行動力ありそう。知識、経験も豊富そう。(もちろん自分に知識や経験がない分野は、優秀なブレーンがいるのでしょうけど)若くて、経験、知識もある。自分にないものを持っている自分ができなかったことをやっている結構、世の中の経営者はうらやましがっているかもしれない。
2005年03月12日
コメント(1)
-
お客様アンケート
近くの(地方では)大手スーパーの話。お客様の声を反映したお店にしよう!お客さん第一主義!と頑張っているのですが、最近少々やり過ぎのようです。“お客様の声をお聞かせ下さい”とアンケート用紙が設置されています。さらに、お客様から寄せられた主な質問と店側の回答が貼られているボードがあります。このボードに、「○○メーカーのペットボトルのお茶はおいしくない。店で売らないで。」「テナントのハンバーガーショップのアルバイトの子ににらまれた。あの子を辞めさせて。」こんな自分勝手なクレーム?に対する店側の回答もていねい貼って載せています。しかも、お客様の声ありがとうございました…と大きくボードに書いてあります。そんなお客さんの声を載せるほうもどうかとは思うのですが、お店の人もアンケートがあるから仕方なくボードに載せているような気がします。本当に他のお客さんに有益なアンケートを載せるための判断をしないで、形式的に仕事をしているような気がします。もちろん、お茶がほんとうにおいしくないか、バイトの子の態度に問題はないかくらいは調べるべきだと思います。そのスーパー、レジの人達はみんな、「私達は笑顔で接客します」と書かれた大きなプレートを胸につけていますが、やらされているから仕方がないなぁという感じが否めません。そんなプレートをつけさせられた時点で笑顔が消えるような気がします。
2005年03月11日
コメント(2)
-
就職活動の最近の傾向
不景気な世の中ながらも、就職市場は売り手市場の気配が強いそうです。会社説明会など求人活動を支援する某企業の担当者から聞きました。複数の企業が何十社も集まり、各企業がブースで区切られたコーナーで説明会を実施するいわゆる会社合同説明会でもその傾向が現れているそうです。5~6年前は、学生一人当たり何社も各企業のブースを訪問していたそうです。しかし、2~3年前から、学生一人当たり2社程度になったとのこと。たくさんの企業が説明会会場に来ているから、「できる限り多くの企業と接触しよう」という風潮から、自分が興味のある企業が参加するなら「その企業の話だけを聞けばいいや」に変わっているそうです。就職できるならどの業界どの企業でもいい…という傾向から働くならこの業界、この会社で…と選り好みする傾向がだんだん強まってきているそうです。また売り手市場になると、学生さん達は、ホワイトカラー方面への希望者が一層多くなるそうです。そのため、小売業などが求人活動ですでに苦戦し始めているそうです。予定の採用数に達しない小売業が昨年は結構あったそうです。労働人口がますます減っていく将来を考えれば、何もしなくても人が集まる会社、いくら募集しても人が来ない会社の2極化現象もより鮮明になってきそうです。
2005年03月10日
コメント(0)
-
時間の価値
高校に入学したAくんとBくんの2人がサッカー部に入学しました。中学時代からサッカーを続けているAくん。高校ではじめてサッカー部に入ったBくん。高校卒業後2人はバラバラになるのですが、同窓会で久しぶりの再会をしたそうです。当然サッカー部時代の話題で盛り上がりました。Aくんは、「練習キツかったなぁ。つらい思い出しかないよ。いっぱい走らされて。ほんと、しんどかったよなぁ。」とハードな練習に耐えた昔を懐かしんでいました。Bくんは、「いろんなことが経験できて、俺は毎日が楽しかったよ。」と好きなサッカーに打ち込めた3年間を懐かしんでいました。中学時代からサッカーを続けてきたAくんは、レギュラーでたくさんの試合に出場し、スポットライトがあたる3年間でした。はじめてサッカー部に入ったBくんは、補欠メンバーで試合にも数えるほどしか出場していません。中学時代からサッカーを続けてきた人と比べれば、サッカーの技術も体力も知識もなかったはずです。練習について行くこともきっと大変だったはずです。きっと影で練習以上に大変な努力をしたに違いありません。そんなBくんが、「楽しかった」なんて…Aくんは驚いたそうです。サッカー部で過ごした同じ3年間ですが、今では、Bくんにとって3年以上もの価値のある時間だったのです。
2005年03月09日
コメント(2)
-
人が怒るとき
人が怒る時って、生命や財産、権利などが奪われそうになった時くらいで、普通はなかなかないと思います。たとえ、気に入らないことがあっても、相手が真剣に自分のことを思って行動していてくれたら、そうそう怒らないと思います。知人が、最後に「ア」をつけたらヨーロッパの国名になる(ヨーグルトもイメージする)ブランドの腕時計を買いました。2年で動かなくなって、5万円もかけて修理しましたが、それから1年たたないうちにまた故障し、3年で2回故障したのです。(ちなみに腕時計を買った店はそのブランドの直営店ではありません)2回目の修理のために腕時計を預けたあと、店から電話があったのですが、費用がいくらくらいかかりそうですという連絡だけでした。そこで知人が、前回の故障は、どこが悪くて、今回はどこが悪かったのか教えて欲しいと頼みました。せっかく高い腕時計を買って気に入っていたのに、こんなに故障するのは残念だ。扱い方や保管の仕方に問題があるのかどうか、今後故障させないためにもぜひ教えて欲しいということでした。するとその店の店員は、専門家でないと詳しいことは分かりませんとこたえるだけだったそうです。腕時計を買った店では、そのブランドの修理工場から詳しい状況など聞かず、金額だけを事務的にお客さんに伝えているだけのようでした。さらにその店員も、どこかにぶつけたことがあるのでは?落としたことがあるのでは?とまるでこちらが悪いことをしたかのような口調だったとのこと。そんな対応だったので、ついには知人の怒りも頂点に達して、電話口で怒鳴っていました。知人が怒ったのも無理はないと思います。工場に問い合わせて調べようとか、連絡をとろうとか、相手のことを思って行動する雰囲気が全くなかったからだと思います。今この電話で済ませてしまいたい…という店員の雰囲気を察したのだと思います。店員にとっては、たくさんある時計のひとつだったかもしれませんが、知人にとってはたったひとつのお気に入りの時計だったのです。そのあたりことを店員はわかってないように思いました。
2005年03月08日
コメント(0)
-
食料がなくなる時代
今の日本は、世界中のどの国より、歴史上のどの時代より、どんな貴族より、贅沢な食生活だそうです。ちょっと話はそれますが、近い将来、世界的に「水」が足りなくなるかも…というような内容が先日目にとまりました。先進国でさえ将来、水が足りなくて困るかもしれないそうです。幸い日本はまだ水に恵まれている方だと思いますが、それでも安心はできないそうです。日本の食糧自給率は40%程度だそうですが、ほとんどの食料を輸入に頼っています。野菜、果物、魚、鶏肉、牛肉…などたくさんの食料を輸入しています。そして、それらの食料を育てる為に、生産国では「水」を使います。植物はもちろん、家畜を育てるのにも水が必要です。つまり、食料を輸入するということは、生産国の「水」を消費するということだそうです。世界中で「水」が枯渇すれば、生産国は食料を育てることができず、日本のような食料輸入国に影響を及ぼすわけです。うそかほんとか知りませんが、日本ではホームレスも糖尿病にかかるとのこと。そのくらい今の日本は飽食だそうです。エネルギー問題、環境問題、食料問題…大きな時代の転換期が近い将来迫っているような気がしてなりません。
2005年03月07日
コメント(0)
-
時間を「過ごす人」「無くす人」
今日、あなたが何気なく過ごした1日は、昨日亡くなった人が、一生懸命「生きていたい!」と願った1日です。去年、知人関係の葬儀に参列した際、お坊さんがお話をされていました。その場に居た誰もが「はっ」としたようで、そのあとでも知人同士の間でその話が話題になり、自分の生き方、習慣、態度などさまざまなものを見直すきっかけになりました。お金を無くしたら、買い物ができない…手帳を無くしたら予定がわからない…定期を無くしたら電車に乗れない…鍵を無くしたら家に入れない…世の中、無くしたら、すぐに自分が困ってしまうものばかりです。でも、時間だけは無くしても今すぐには困らないんですよね。勝手に無限にあるもののように感じて、ずっと後になって無くしたことに気付くのかもしれません。病気と闘い先日亡くなられたプロウィンドサーファーの方のニュースを聞き、ふと冒頭の言葉を思い出しました。と同時に、時間を「過ごしている」のか、「無くしている」のか生かされていることに感謝し「一日一日を一生懸命生きる」ことについてあらためて考えさせられました。
2005年03月05日
コメント(4)
-
就職活動で有効な質問
また採用活動ネタです。就職活動って大変ですよね。特に面接って緊張します。学生さんも前もっていろいろ考えて面接にのぞんでいるようです。面接で、「何か質問はなないですか?」と学生さんに聞いた時に、「良くうちの会社のことを調べたなぁ」と感心する質問もありますが、大抵は、「とりあえず何か質問してアピールしておけばいいか」というような質問が多いです。どうせ質問するなら、今後の就職活動のためにも、「伸びる社員と伸びない社員の違いは何でしょうか?」と質問してみましょう。面接というのは実際に働く前から学生さんを選別する場です。要は面接官はこの伸びる要因を学生さんが持っているかどうかを見ています。伸びる社員の特徴を聞き出して、それを次回の面接で(他社の面接でもいいと思います)アピールすれば良いのです。何社かで同じ質問をして答えを研究すればもっといいのではないでしょうか。
2005年03月04日
コメント(0)
-
いいとこ探し
車選びって人によって基準が全然ちがうものなんですね。デザインを重視する人燃費や経済性を重視する人パワーを重視する人操作性を重視する人人それぞれに優先させるものがあるんだと思います。デザインは良いがちょっと燃費が悪い車多少経済的ではないけどパワフルな車全てにおいて満足いく選択は難しいと思いますが、自分が優先させるものに魅力を感じれば、多少マイナス面があっても受け入れられるんだと思います。逆にマイナス面も愛嬌で愛着を感じることもあると思います。ちなみにボクはデザインは良いがちょっと燃費が悪い車を買いました。同僚が今、たまたま求人担当をしていますが、学生に会社の何をアピールすれば良いのか思案しております。若い社員が多いなんでも自由にチャレンジさせてくれる教育制度が充実している初任給が高い学生の会社選びの基準も人それぞれ違いますが、短所、マイナス面をカバーできるほどのアピール点が見当たらず、うちの会社って「これだっ!」という魅力に乏しいね…と話していました。案外社員は気づいていなくても、学生は魅力に感じることがあるかもよ。と、いいとこ探しをやってみました。これが結構おもしろく、プラス発想でいろいろ考えて、やや強引ですがたくさん列挙してみました。うんうん、うちの会社も捨てたもんじゃないなぁと妙に会社が誇らしくなったりしました。みなさんも、人やものやってみてはどうでしょうか。ちなみにいいことしか言わないというルールでやりました。
2005年03月03日
コメント(2)
-
効率と雰囲気
お世話になっている車屋さんがあります。受付の女性や、なんでも教えてくれる修理のおっちゃん。結構きさくな人達でした。ですが、最近、なんか雰囲気が変わったような気がしました。むだ話をするくらいなら、さっさと切り上げて仕事に戻りたい…社員の人達がそんな感じで働いているように思えました。その車屋さんに見慣れない人がいました。その人は、お客には元気に声をかけているのですが、口は笑っても、目が笑ってないような眼光鋭いやり手の営業マンって感じでした。一般のお客さんを相手にするならもっとソフトな人のほうが受けがいいのにとも思い、受付の女性に話を聞くと、どうもその人が営業のおえらいさんだそうでした。そのおえらいさん、タイムイズマネーではないですが、社員の動きを監視しているとのこと。お客さんが集まって会話するゆとりの時間も、むだな時間と考えているようでした。そのおえらいさん、異業種からの転職らしいですが、規則やルールで縛りきれない、客商売というか、人情の部分も効率化という枠の中に当てはめているような気もしました。効率やコスト意識も大事ですが、そういったやり方よりも、お客に雰囲気が変わったと思わせない社員のあり方を先に考えなくてはいけなかったような気もします。
2005年03月02日
コメント(4)
-
成功者
夢が叶う、目標が達成できる、成功する…といった感じの本が最近多いように思います。世の中の成功者の思考を紹介するスタイルの本です。成功者の表面的な部分(言葉や行動など)だけの記載でも結構面白い内容の本も多く、考え方を真似すれば自分も成功者の一員になれるかも…と思わず本を買う人が多いのだと思います。「へぇ~、成功した人ってのは、こんな考え方するんだぁ」「やっぱりプラス発想で何事にも挑戦だねっ」と読んだ時には感心したり、妙にポジティブになったりもします。ですが時間の経過と共に、成功者が本当に成功の秘訣をみんなに教えるわけもなく、成功した理由もきっと人と違ったことをしたからで、本を読んで本の通り実践してもすでに過去の成功ルールにありがたくしがみついているだけのような気もします。でも、やっぱり、あなたも金運がつく!とか成功○○の法則!とか魅力的な本のタイトルに惹かれてついつい本を買っちゃうんですよね。やっぱりやめられません。
2005年03月01日
コメント(2)
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- つぶやき
- 今シーズンの冬は寒くなりそうだから…
- (2025-11-14 20:56:19)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 「届くのが遅すぎて使えない…」楽天…
- (2025-11-14 22:00:05)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…
- (2025-11-14 19:41:15)
-