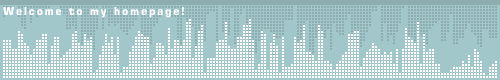音円盤アーカイブス(5月)
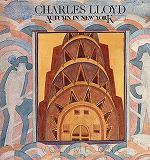
初めて聴いたのはクラブの研究会でK原君がかけた時だった。
チャールス・ロイドは「JOKE」でキース・ジャレットの参加したATLANTIC盤をよく聴いていたけど、今一かったるくてこれなら本家のコルトレーン聴いた方が数倍いいわと思っていた。
ストリングスの調べにのってヒュルヒュルと舞い降りてくるかのようにロイドのテナーサックスが1曲目の「オータム・イン・ニューヨーク」を奏でた瞬間、落雷に打たれたようなショックを受けた。
いままでの印象を覆すかのような引き締まった余計なものを殺ぎ落とした潔い演奏に、その演奏が本当にロイドによるものなのかレコードジャケットを確めたくらいだった。
次にこのレコードを見たのは、ジャズ批評「ジャズレコード蒐集学」の中で滝口さんがこの作品を紹介していた時で、これはどうにかして手に入れたいと思った。
出会いは突然やってきた。しばらくして中古レコード屋で発見したのだ。
このレコード実際、コルトレーンの「バラード」のロイド版みたいな形で引き合いにだされるが、私にはロイドの新たな決意表明に聴こえる。
バラードナンバー集を吹き込んだのは、コルトレーンの場合、マウスピースの不調やボブ・シールのサジェスチョンとか言われているが、ロイドの場合は今一度シーンに駆け上がる為の原点回帰としてこのアルバムを吹き込んだように感じられてならない。
時代はとっくにロイドを追い越してフュージョンミュージック真っ盛りの70年代後半、今一度やる気になったロイドは手始めにこの原点ともいえる手垢のついたバラード演奏を試してみたのではないか?マイナーなレコード会社(DESTNY RECORDS)からの再スタート。
やがて、ミッシェル・ぺトルチアーニとの出遭い、ブルーノートレーベルとの契約とジャズシーンに再浮上するチャールス・ロイド。
その後の活躍は書くまでもないだろう。
そんなことを夢想しながらここで演奏されているバラードナンバーを聴いていると本当のことなんじゃないだろうかと錯覚に陥りそうになるほど、ここでのロイドのテナーサックスは凛々しくて限りなく優しい音色をしている。
曲目は「AUTUMN IN NEW YORK」「AS TIME GOES BY」「WAIT TILL YOU SEE HER」「NANCY」「NAIMA」「STELLA BY STARLIGHT」「BUT BEAUTIFUL」「PENSATIVA」
メンバーはCHARLES LLOYD(TS)TOM GRANT(P) KEVIN BRANDON(EL-B)
KIM CALKINS(PER) SUZANNE WALLACH(VO)with STRINGS 1979年作品

トロンボーンのワンホーンものということで、たぶん買ったのではないかと思う。
コンラッド・ハーウィッグだから出来は保証されているし・・・
そんなところだと思う。今メンバーを見てみるとピアノがBERNARDO SASSETTIなのだ。
買ったときは無名のピアノトリオがバックだったのでそこがちょっと不安だったはず。
FESTIVAL DE JAZZ DE GUIMARAESでのライブ録音で、このシリーズは他にもGROOVEレーベルからリリースされている。
ハーウィッグのトロンボーンはデイブ・リーブマンが参加したデビュー作を買って以来結構買い込んでいるが、この作品ライブという事もあっていつもにまして張り切ったパワフルな演奏が聴かれる。
「24 FOR FRANK」「AMULET」「RED ON BLACK」など以前のオリジナルの選曲も硬派であるが、楽曲と演奏のバランスがしっかり取れたパフォーマンスなので、聴いていて冗長だとは感じない。
ハーウィッグのトロンボーンは、テクニック面(テクニカルなフレーズ、ハーモニクスの処理、ハーモニーの解釈など)も素晴らしいと思うが、音色が私にとって一番魅力に感じる。
3曲目ではスティーブン・ターレかアルバート・マンゲルスドルフの様なハーモニクスを駆使したソロを披露。ドラムとのデュオからカルテットに以降する瞬間がカッコいい。
急速調の「AMULET」に続く名曲「RED ON BLACK」はたゆとう感じで演奏される。
ドラム奏者の力量がやや格落ちなのが惜しい。バックのつけ方が無神経すぎるのではないか?アップテンポでもパワー不足を感じる。
BERNARDO SASSETTIは、ポルトガルの人々がもつ目の奥に潜んだ哀しみという様な深い情緒を感じさせるピアノソロをスペースを生かした方法で披露。
6曲目がこのアルバムの白眉、「MUSICA CALLADA N1」。
ハーウィッグのこんな情緒的で情熱的なテイストのプレイは初めて聴いた。
ポルトガルという土地でのライブと楽曲がハーウィッグのプレイに歌謡性、ラテン性を目覚めさせたのだろう。
ラストはモンクの「I MEAN YOU」で締めくくられる。
録音は1993年11月 FESTIVAL DE JAZZ DE GUIMARAES

2000年の秋、大阪出張の時ワルツ堂EST1店で買ったCDで、リーダーのJAN ZUM VOHRDEの名前はその時初めて知った。
サイドメンがTHOMAS CLAUSEN,JESPER LUNDGAARD,ALEX REALなので明らかにバックのミュージシャンの名前で買ったのだと思う。
選曲もスタンダードナンバー中心なので、無難な一枚だろうとあたりをつけたのだろう。
この予想少し外れてしまったようだ。
1曲目「酒とバラの日々」から結構骨太のトーンのアルトサックスのサウンドが飛び出してくる。大きな個性はない。いやむしろ地味と言っていいのかもしれない。
ジャケットのインナースリーブを覗いてみるとビッグバンドに在籍していたそうだ。
70年代からパレ・ミッケンボルグ、先頃逝去したニールス・ペデルセン、トーマス・クローセンらビッグネームと演奏したというからデンマークのジャズシーンではそれなりに名の知れた存在なのだろう。
VOHRDEのサックスは決して悪くはないのだが、如何せん今一歩の個性に欠けるのだなぁ。
聴く耳はどうしてもクローセンの煌びやかなタッチのピアノやアレックス・リールのシャープでパワフルなドラミングを追ってしまうのだ。
4曲目はトム・ハレルの「LITTLE DANCER」をフルートで演奏。
ワルツテンポの小品で、サポート隊もジェントルな伴奏をつけていてVOHRDEのフルートが映える仕掛けになっている。
この曲なんか等身大の声が聴けているようで中々いい感じです。
スタンダードに戻るともとの調子に戻ってしまって実際VOHRDEのサックスがすんなり耳に入ってこない。
プロデュース面でもう少し工夫して選曲やアレンジを主役のVOHRDEがもっと生きるようにすべき。スタンダードを普通に演奏すれば百戦錬磨のベテラン勢の強烈な個性が際立つのは充分予想されたはずだ。
とここでプロデュースのクレジットを見たらこれが、VOHRDE本人なのですね。
本人はスタンダード演りたかったんだろうね、きっと。
メンバーはJAN ZUM VOHRDE(AS,FL)THOMAS CLAUSEN(P)JESPER LUNDGAARD(B)
ALEX RIEL(DS)
録音は1998年9月1,2日

GWなのでもう一本!
いやぁー。このレコード探している人多いでしょ。
そうなんです。私も長いこと探していたのです。
有りそうで中々見つからないスティーブ・キューンの「ラストイヤーズワルツ」。
厳密には今から約10年程前、買い逃した事がある。
JR福山駅の構内で中古市、レコードだけじゃなく古本なんかも含んだごく普通のセール。
ジャズのエサ箱も3箱くらいあったので暇つぶし程度にチェックしていた。
あったのだ!この盤が・・・こんなのだったらもっと珍しいブツが見つかるかもと隣のエサ箱に移動。レコード探していると隣に人影が・・・。
なんとさっきのキューン盤を手にとっているではないですか。
お願いだから、戻してくれ、エサ箱に。こちらの期待むなしくその人はレジに・・・。
天国から奈落の底に突き落とされた瞬間だった。
結局それ以外目ぼしいブツもなくスゴスゴと退散するのでした。
それ以来見つけたブツは絶対足元に置くようにしている。
皆さんもこういう悔しい経験されたことないですか?
それから月日は流れ昨年の秋、N山亭での研究会でレコード棚をチェックしていた時のこと。なんとなくKの棚をチェックしていた。
何十回と棚を見ているのに何故かそこだけはチェックしていなかったのだ。
あったのだ!この「LAST YEARS WARTZ」が。
思えば、トリオレコードがECMを配給していた80年代、この作品の広告をSJ誌で見て以来欲しいと思っていたのに何故か縁がなく聴いた事なかった自分にとっての幻の作品が・・・。
早速かけてもらう。
キューンの柔らかなピアノのイントロに導かれてシーラ・ジョーダンのあの声が流れてくた。
これだけでこのレコードに関しては自分の中で完結している。
B面1曲目ハービー・シュワルツの「MEXICO」はキューンの甘口の部分が日本企画のわざとらしい部分なしに自然発生的にでた名曲、名演だと思う。
メンバーはSTEVE KUHN(P)SHEILA JORDAN(VO)HARVIE SWARTZ(B)BOB MOSES(DS)
録音は1981年4月 FAT TUESDAY`S NYC
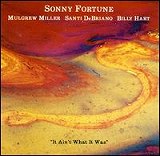
最初に言っておくが、ソニー・フォーチュンは決して一流のミュージシャンではない。
二流と決めつけては言いすぎだけど、出す作品、出す作品すこしピントの外れているものが少なくないのである。
でも愛すべき二流なんだなぁ、音楽に対する真摯な態度、マッチョで肉付きのよいパッショネイトで艶やかなアルトの音色は一度聴いたら結構耳に残るのではないか。
ただしアルバムつくりはさっきの様に決してうまくないのだ。
90年代の初め、KONNEXというドイツのレーベルからソニー・フォーチュンのCDが立て続けに3枚リリースされた。これはその中の2作目にあたるもの。
ソニー・フォーチュンというとサイドマンではマイルスの「アガ/パン」で来日した時のサックス奏者、マッコイの「サハラ」に参加プレイヤーというのが最も一般的な認識だろうが、リーダーアルバムも70年代中頃からHORIZONやATLANTIC数枚吹き込んでいるがどれもが、中途半端な作品が多かった印象を持っていた。
80年代中頃にWHY NOTレーベルの新録でセンチュリーレコードからソニーの新録がリリースされたはずだけど、見聴のままであった。
そんなときにKONNEXから新録がリリースされたのであった。
確か3枚とも岡山の「LPコーナー」で買ったと思う。
それからBLUE NOTEと何故か契約できて3枚リリース、日本企画でもゲイリー・バーツとのツーアルトでの企画作品がGDでリリースされて少しは話題になった。
アルバム自体は日本企画の悪趣味性が諸に出たチープなつくりだったが・・・
結局いい時代はそんなに続かないのである、フォーチュンに。
このアルバムはそんなフォーチュンが最も自然体でレコーディングしたと思える一枚で、
作品として粒揃いの選曲、演奏が収録されていて個人的に最もよく聴くCDなのです。
2曲目「GENTLE RAIN」5曲目「STRAIGHT STREET」はフルートを使用。
ややヘタウマの気があるフルートも意外と聴き物で音楽テクニックだけじゃないことがよく分かる。
エルビン・ジョーンズ・ジャズ・マシーンの公演で出番待ちの間ずっと虚無僧のようにフルートでスケール練習していたフォーチュンの姿が今でも記憶に残っている。
サイドメンでは、マルグリュー・ミラーのピアノも輝いてソロにサポートに非凡な才能がうかがえる。
実のところ、私はアルトよりフォーチュンの無骨でワイルドなテナーが好きなので、今度はテナーとフルートでこのような等身大であるながらピリッと引き締まったところのあるアルバムを出してくれないだろうか?
PADDLE WHEELから出た「コルトレーンの魂」はちょっと力の入りすぎ、重たいものだったので。
メンバーはSONNY FORTUNE(AS,FL)MULGREW MILLER(P)SANTI DeBRIANO(B)
BILLY HART(DS)
録音は1991年12月 NYC

レーベルブルーのCDは昔も現在もどちらかというと手に入りにくく、この作品も94年5月、東京出張の時に一日滞在を伸ばしてライブハウス、ジャズレコード店巡りを敢行した時に入手した。確か今は無き六本木WAVEで買ったと思う。
このCDの凄い所は1曲目の「STOLEN MOMENTS」のメロディーが鳴り響いた瞬間にたちまちジャズを聴いている幸福感、満足感を与えてくれるところだ。
それはさておき、
以前にも書いたと思うが一年間に何百というピアノトリオのCDがリリースされている。
その中で演奏に必然性のあるピアノトリオはいったいいくつあるのだろう?
一歩譲ったとして、5年後、10年後聴き続かれていく演奏はいくらあるのだろう?
中には売らんが為のメーカーのお仕着せ、企画ものもあるだろう。
使える制作予算、販促予算、営業経費が決まっている中、比較的低コストでリスクの低いそして収益が望めるピアノトリオの録音ほど、都合の良いものはないのである。
そして売れるものはどんどん仕入れて全面にフェイス出しする販売店。
もういい加減そんな見えすいた仕掛けに踊らされ、バカの一つ覚えのようにピアノトリオのCDばかり買うのは止めようではないか。
ピアノトリオというフォーマットはベースとドラムの技量が素晴らしかったらそこそこのピアノでもそしてイージーな企画でもそれなりに聴こえてしまうところが怖い。
実際たいした演奏でもないのに・・・。
そして、そのようなCDが売れてしまうためにもっと陽があたって聴かれるべき作品が闇に埋もれていくかもしれないのだ。いや、作品をリリースするチャンスさえ、廻ってこないのかもしれない。勿論全部聴いたわけではない、そんな暇はない。
こんなにピアノトリオのCDばかり次から次へとタケノコみたいに出る国は世界的にみても日本だけだと思う。
メーカー、マスメディア、ショップ、も考えてもらいたい。
そして、リスナーのほうももっと耳を鍛えなければならないと思うのだ。
私は決してピアノトリオが嫌いなわけではないし、実際結構聴いている。
しかしピアノトリオ=ジャズの主流ではなくあくまでも一つのジャンルと考えている。
どうもピアノトリオを題材にすると苦言が多くなるけれども、このHENRI TEXIER TRIOの出来は120%私が保証いたします。
この10年に吹き込まれた何千(そんなにないか?)という中でベスト3にはいる仕上がりだと思う。
曲目は「STOLEN MOMENTS」「THE SCENE IS CLEAN」「ARRIVAL」「SKATING IN CENTRAL PARK」「SOUL EYES」「LOTUS BLOSSOM」「LONELY WOMAN」「MINORITY」「STABLEMATES」「LAMENT」全10曲。
メンバーはHENRI TEXIER(B)ALAIN JEAN-MARIE(P)ALDO ROMANO(DS)
録音は1991年1月26,27,28日
捨て曲なしのピカイチ盤として大推薦します。
さあーって、パソコンで疲れたからケニー・ドリューの北パリ終着駅なんやらかんやらでも聴こうっと・・・

KIETH OXMANの名前は知らなかったが、テナーのワンホーンものだし、通好みの選曲で悪い事もなかろうと買ったのだと思う。
一番の決めては「FUNK IN DEEP FREEZE」を演っていたから。
ハンク・モブレーのこの曲に目が無いのです。
実は今もフィル・アーソがこの曲を吹き込んだCDを出しているので迷っているところ。
はやく入手しなければと思っている。
初めて聴いたのはチェット・ベイカーのCTI盤だったと記憶しているが、それ以来好きなジャズマン・オリジナルのひとつになっている。
KIETH OXMANは1978年、20歳の時に住んでいた町に演奏しにやって来たソニー・スティットと共演する機会を得る。スティットに勇気付けられマウスピースを貰ったとライナーにある。忘れられない一生の思い出になった貴重な経験だったそうで、このOXMAN,プレイヤーとしての側面と同時に大変なジャズマニアとしての顔も持っている。
家の自室はパーカー、マイルス、トレーン、デクスター、にナバロのポスターが壁にかかっていてCD、LPレコードの山らしい。レスター・ヤングやバド・パウエルのインタビューテープまで所有しているというから相当のマニアだ。
ヴィジュアルも充実していてホーキンスからドルフィーまでのジャズジャイアンツのビデオテープもコレクションしているらしい。
ジャズミュージシャンでマニアとして、ケニー・ワシントンやボブ・ベルデンなんかが有名だけれども、OXMANも相当なものなのではないか?
そんなOXMANだからジャズファンの心理がよく分かっているのか、かゆいところに手が届く実にツボを押さえたプレイ。
自身のアーティスティックなところ、ミュージシャンとしての主張を殺さずに伸び伸びと吹いているようで、聴衆に見事なエンターテイメントを提供するまさにプロミュージシャンとしての鏡みたいな存在だ。
豊富な知識と経験に裏づけされたプレイはぽっと出の若手テナー奏者など足元にも及ばないだろう。
あまり有名じゃなくてもこういうオーソドックスなスタイルで素晴らしい演奏をするプレイヤーが山のようにいるアメリカはやっぱりジャズ村の中のメイジャーリーグなんだと思う次第。
ピアノのANDY WEYLも素晴らしいプレイをしていると付け加えておこう。
メンバーはKIETH OXMAN(TS)ANDY WEYL(P)MARK DIAMOND(B)MIKE WHITED(DS)
録音は1996年6月27日 COLORAD

一昔以上前にもうなるのだなぁ。
このEERO KOIVISTOINENのCDを買ったのは。バックのメンバーの豪華さに惹かれて岡山
のLPコーナーで買ったと記憶している。
RANDY BRECKER(TP)CONRAD HERWIG(TB)DAVE KIKOSKI(TB)JOHN SCOFIELD(G)RON MCCLURE(B)JACK DEJOHNETTE(DS)まさにキラ星の如く現代ジャズ界の雄が一同に会したパーソネルで、この時点でリーダーのEERO KOIVISTOINENの名前だけ全く初耳だった。
フィンランドジャズ界の重鎮として活躍しているのを知ったのは、ずっと後の事。
EEROは、実際、60年代後半から30年以上フィンランドジャズ界のリーダー的存在としてUMOジャズオーケストラはじめ各種セッション、ライブ活動に活躍しているのである。
このCDはそんなEEROが本場NYの一流ミュージシャンと腕合わせしたスペシャルセッションと言えるだろう。
末聴なのだが、こういう録音はEEROにとってこれが初めてではなく、1983年に録音された「PICTURE IN THREE COLOURS」というアルバムをジョンスコ、マクルーア、デジョネットはそのまま、TPにトム・ハレル、Pにジム・マクニーリーというメンバーで吹き込んでいる。これも是非聴いてみたい一作。
問題の中身なのだが、アレンジメントと個々のアドリブプレイがバランスよく噛みあったスタイリッシュでクールな当時最先端だったと思われるニューヨークサウンドが展開されているといった感じで、EEROのサックスプレイも天才的のひらめきや爆発力は感じられないが、メンバーと違和感なく溶け込んでおり、充分合格点だと思う。
このCDで展開されているサウンドは実際EEROの音楽の一部分であり、その後1995年に発売されたアルバムはもっと思索的、観念的な要素の強いサウンドであった。
もうひとつ書くことが、あった。
表にはクレジットされてないのだが、このアルバムのは若き日のBUGGE WESSELTOFTがシンセサイザーで3曲参加しているのだ。
録音は1991年9月25,26日 CLINTON STUDIOS, NY

所有しているのは、2000年にHALF NOTE RECORDSから再発されたセカンド盤なのですが、
この作品もバックの豪華メンバーにつられて買ったもの。
JACK DEJOHNETTE(DS)EDDIE GOMEZ(B)GEORGE GAZONE(TS)DAVE LIEBMAN(SS)NANA VASCONCELOS(PER)
MORDY FERBERはイスラエル北部の生まれで、ギター小僧によくあるように、最初はロック少年であったが、17才の時にラジオで聴いたジャンゴ・ラインハルトのギタープレイに衝撃を受けて、ジャズにのめり込むようになる。
チャーリー・クリスチャン、ジョー・パス、ウェス・モンゴメリー、ジム・ホールなどのギタリストを研究、やがてバークリー音楽院に入学、やがてジャズ界とのネットワークを拡げていって、1990年にはNYへ移住する。
今までに3枚のリーダー作をリリースしているが、本作は2作目にあたる。
MORDY FERBER自身の演奏は決して悪くではないのであるが、正直いって強者揃いの現代ギター界においていささかインパクトが弱く、薄味というか、強烈な個性にかけるのだ。
ジョン・スコフィールド、マイク・スターン、ビル・フリゼル、パット・メセニー、カート・ローゼンウインクル、ベン・モンダーなどと比べるとどうしてもFERVERの演奏はスタイルの指向性がにかよっているので、不利は避けられない。
作曲の方に私は才能を感じる。1曲目のジョンスコ調の「MR.X」自身のアコギとガゾーンのテナーが黄昏時の寂しさを表現しているかのような3曲目「A MINOR TUNE」など結構いいけるのではないか。
そんな訳でFERBER自身コンポーザー型ミュージシャンだと思うので、豪華ミュージシャンもどちらかというと、その音楽を表現する一部分としての役割にベクトルが傾いているようで、あまり奔放なアドリブプレイはリーブマンもガゾーンも展開していない。
そんなところが、少し物足りなく、活かしきっていない気がするのは私だけだろうか?

彼らのHPで全曲試聴できたので、聴いてみたところゴキゲンなサウンドが流れてきたので、早速中南米音楽に注文して手に入れた。
一言で言ったら、ゆるーい感じのカルロス・サンタナのような口ずさめる哀愁歌謡調メロディーが展開されているのだ。
1曲目からジャンピーで活気ある親しみやすいリフナンバー、ギター(サンタナ調)とホーン隊のコールアンドレスポンスもいい感じ。
FLAVIO NAVESのハモンドオルガンも適度にファンキーで楽しい雰囲気を盛り上げている。LANCASTERのギターは曲調に応じて、ノリノリのロックテイスト、ブルージーなブルース調、ファンキーなジャズ調、哀愁度高めのラテン調と器用に立ち回る。
4曲目「ITAMARA」は美メロ、サンタナがいかにも演っていそうな曲調。
バックのホーンリフがサウダージ感覚をうまく増幅していてプロフェッショナルな仕掛け(アレンジ)!座布団3枚!
5曲目でゴーゴーダンス(古るっ!)踊ってもらって、6曲目はソファに戻ってトゥワイライトタイム。
7曲目「BLUESAMBA」いかにもっていう感じの70年代後半風クロスオーバーメロディー。
ベタでゆるーい感じが逆に快感、前頭葉をもろ刺激してくれるというか、こういうところも計算されたプロフェッショナルの仕事なんだと思う。
彼らのHPで全曲試聴できるので、聴いてみてはどうでしょうか?
www.lancastereflavionaves.com.br
録音は2004年1月~8月

1992年に発売されたNY「バードランド」でのライブ録音盤で、日本盤で一緒にパキート・デリベラ~クラウディオ・ロデッティー、ドナルド・ハリソン~マーロン・ジョーダンのライブ盤が徳間から発売されたものを岡山のLPコーナーで買った。
このチェンバース盤は、ボブ・バーグが参加していたので買ったのだと思う。
他にメンバーはフィリップ・ハーパー(TP)ジョージ・ケイブルス(P)サンティ・デブリアーノ(B) 1991年3月8,9日 バードランドとクレジットされている。
JOE CHAMBERSのドラムは60年代のブルーノート録音でよく聴いていたが、70年代リアルタイムでリリースされていたスーパージャズトリオなどで、その繊細なドラミングがクリアにレコーディングされていたので、より親しみがもてるようになった。
90年代以降はその顔のひろいネットワークを活かしてミュージックコーディネーターみたいな役割も多くなってきたけれども、まだまだ現役バリバリで本業の方でも活躍している。
そういえば、10年程前、広島の中古レコード市でチェンバースの自費出版のLPを手に入れたけど、ウェイン・ショーターの「RIO」なんかを演っていて中々聴き物だった。
いつかこの日記にもアップしようと思っている。
ジョージ・ケイブルスは2年半ほど前に、アーチー・シェップのピアニストで来日した時に見たけれども、杖をついて出てきたのに驚いた。
どこか健康を害しているのだろうか?
フィリップ・ハーパーを初めて聴いたのはもうテープを無くしてしまったがNHKFMのセッション(何年だったかな)で今は亡きトコさんが、自分のバンドで紹介した時だったと記憶する。
そして、ボブ・バーグ・・・突然の事故死は本当にショックだった。
一度はステージを生で見たいテナー吹きだった。
生粋のニューヨーカーの会話のような畳み掛けるようなスピードでファナティックに謳い上げるプレイがまさにボブ・バーグの真骨頂だったと思う。
このCDはそんなメンバーが新生CANDIDレーベル復活の際、バードランドの連続ライブレコーディングで組まれたセッションを収録したものだが、彼らの普段着のライブセッションが有りのまま収録されていて、それが逆に彼らの底力を垣間見れる結果となっているのである。

2000年にREDから発売された素晴らしいビッグバンド作品。
我が国の一国一城、リーダー級のミュージシャンがボビー・ワトソンの指揮のもとに集まって繰りひろげたスーパーセッション。
1曲目ボビー・ワトソンのナレーションから始まるのだが、この曲のリフというか、テーマがカッコイイ。なんかとてつもない演奏が目の前で起こりそうな予感を感じさせる曲といったらよいだろうか、メンバーのやる気と集中力を呼び起こす気合の1曲といったところか?
このライブ録音がおこなわれた「SOMEDAY」はボビーにとって約10年前にも自身の日本のミュージシャンとのセッションが録音された縁ある場所。
このセッションでも誰よりも情熱的で熱いソロを展開している。
ボビーの場合、BLUE NOTEやCOLUMBIAのような大手レーベルより古巣REDみたいなマイナーレーベルの方が奔放な自然な姿のような気がする。
実際ソロに関しても伸び伸び吹いているような印象を受けるのだ。
次に印象に残るのは(勿論全員、素晴らしいソロなのだが)佐藤達哉。
昔のようなブレッカーライクなソロをぶちかましてくれている。
初めて佐藤のプレイを見たのは、合歓ジャズインで早稲田モダンジャズ研究会が出演した時のこと。
度肝を抜くくらい素晴らしいテクニックを伴った圧倒的なテナーソロに、思わず目を見張った。
次に見たのは新宿PIT INN昼の部に出演していた吉田正治カルテットだった。
高野正幹とのツーテナーで「インプレッションズ」や「ナーイマ」を聴いたのを昨日のことのように覚えている。
とにかくこのセッション、ミュージシャン全員がどんどん気分が高揚して音楽のマジックが起こって、高みに登りつめる興奮の様が見事に収録されている。
これは、やはりリーダー、ボビー・ワトソンのカリスマ性、統率力に他ならないと思う。
メンバーはROBERT"BOBBY"WATON(AS&LEADER)SHIRO SASAKI(TP)MITSUKUNI KOHATA(TP)
KEIJI MATSUSHIMA(TP)YOSHIRO OKAZAKI(TP)HIDEAKI NAKAJI(TB)HARUKI SATO(TB)
MASAHIKO KITAHARA(TB)MASAKI DOMOTO(BTB&TUBA)SEIJI TADA(AS)ATSUSHI IKEDA(AS)TATSUYA SATO(TS)KOSE KIKUCHI(TS&FL)ATSUSHI TSUZURANO(BS)MASAAKI IMAIZUMI(P)KOUICHI OSAMU(B)TAPPY IWASE(DS)11日YOSHINOBU INAGAKI(DS)13日
BOBBY WATSON&TAILOR MADE WITH TOKYO LEADERS BIG BAND
録音は1999年2月11日、13日 SOMEDAY TOKYO
こんなライブだったら、どんなことしてでも駆けつけたい。

2000年にJHMからリリースされたスイスの若手テナー奏者のカルテット作。
大阪出張の時、ワルツ堂EST1店で買ったもの。
モノクロの写真ジャケットに赤色の名前の印字がなんとなくフリージャズの作品を連想させるが、全くそういうものではなく、ストレートなメインストリーム路線の作品。
LANDOLFのサックスの音色はソプラノもテナーも芯の太さを感じさせるコアの部分は引き締まった印象を受けつつ、表面は、柔らかなブランケットに包まれているような保温性を感じさせるモダン系サックスとしては理想的な音色をしているのではないか?
3曲目のバラード曲なんか、その成熟したダークネスを感じさせる表現なんか、結構やるなぁという印象を受ける。
作曲はウェイン・ショーターに一番影響を受けたそうだが、なるほどこの「PARTHENOPE」という3曲目の曲を聴いているとその影響度がよく分かる。
このCD、録音も非常によい。特にドラムのシンバルやスネアの音がとてもリアルに収録されていると思う。
4曲目は唯一のスタンダード「IF I LOVE AGAIN」。その他はLANNDOLF自身の作品が5曲、カルテットのピアニスト、JEAN-PAUL BRODBECKが2曲という構成。
アルバムを通してLANDOLFのストレートで活きのいい吹奏と一体化したバンドサウンドが楽しめる水準作だと思う。
最近、ドイツの新興レーベルから久々に新作をリリースしたので、成長ぶりをチェックしなければと思っている。
メンバーはDOMENIC LANDOLF(TS,SS)JEAN-PAUL BRODBECK(P)FABIAN GISLER(B) DOMINIC EGLI(DS)
録音は1999年9月1,2日 ZURICH SWITZERLAND
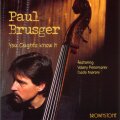
NYのベーシストの1997年録音作。このBROWNSTONEというレーベル、すごく下町のカラーが出ているレーベルだと思う。
NYで活躍するほぼ無名のミュージシャンの等身大の演奏が記録されている作品中心のレーベルカラーといったところか?
この作品も快適なハードバップセッションといったところだ。
メンバーの中ではVALERY PONOMAREVとDADO MORONIの二人が目を引く。
さすがにこの2人はベテラン、中堅だけあり、自分の持ち味を活かした素晴らしい演奏を展開している。
テナーのGEORGE ALLGAINERはセロニアス・モンク・コンペティションでジョン・ゴードン、ジミー・グリーンに続き第3位に入賞した経歴の持ち主で、このアルバムでも、オーソドックスなハードバップテナーを披露してくれている。
ベニー・ゴルソンとジョニー・グリフィンのテイストがそのプレイからは感じられる。
PAUL BRUSGERはロングアイランドに生まれ、ハイスクール時代にジャズとウッドベースに出会い、チャーリー・パーカーやコルトレーンの音楽にのめり込む。
社会学を学ぶ為フロリダの大学に移ったBRUSGERはアイドリス・シュリーマンやケニー・ドリューJR,ジョン・ハートと共演する機会を得る。
1997年にNYに戻ったBRUSGERはロン・ブレイクのレコーディングに参加したり、ヴァレリー・ポノマレフやダグ・レイニーのサイドマンをつとめながら、自身のバンドを結成、活動する。
このような楽歴の持ち主BRUSGERのデビュー作は素晴らしい楽曲とサイドメンの好プレイによって非常に満足できるハードバップセッションが記録された一枚になったと思う。
メンバーはPAUL BRUSGER)B)VALERY PONOMAREV(TP)GEORGE ALLGAINER(TS)
DADO MORONI(P)JOHN JENKINS(DS)
録音は1997年9月8日 SOUND ON SOUND STUDIOS NYC
 フランスの偉大なベーシスト、ジャン-フランソワ-ジェニ-クラークの完全ベースソロの収録されたCDで、彼の死後2003年秋にリリースされた。
フランスの偉大なベーシスト、ジャン-フランソワ-ジェニ-クラークの完全ベースソロの収録されたCDで、彼の死後2003年秋にリリースされた。JEAN-FRANCOIS JENNY-CLARKを初めて聴いたのは確か今から四半世紀ほど前、富樫雅彦「セッション・イン・パリvol.2」だったと思う。
新譜ででたばかりのLPを何度も聴いてすっかりファンになってしまったのです。
アルバート・マンゲルスドルフのトロンボーンにも魅了されてけど、アルバム全体を通して鋼の様に硬質でありながら変幻自在に適応していくフレキシブルなプレイに強烈な印象をもったのだ。
この人、リーダーアルバムはほとんど残しておらず、CMPからヨアヒム・キューン、クリストフ・ロウアーと一緒に録音したアルバムが生前残された唯一の作品ではなかろうか?
それまで、ゲイリー・ピーコック一番だった私にまだまだ素晴らしいベーシストは探せばいりのだなぁと気付かせてくれた存在がジェニー・クラークだと言える。
それから、サイドメンで入っているCDをいろいろ探して手に入れていった。
そして、2003年秋にこの完全ソロ作品が突然発売された。
ベースソロの作品は何作か聴いているけれども、こんなに飽きることのない全編に渡って無駄のない素晴らしいストーリー性を感じさせる作品は聴いた事がない。
アルコ奏法やパーカッシッブな奏法に逃げることなく全編ピッチカートで押し通している事がまずもって素晴らしい。
そしてこれが重要なんだけど音の繋がりにストーリー性が感じられるのだ。
まるでJEAN-FRANCOIS JENNY-CLARKが音楽のマジックによって空間から必然性のある音の粒子を抽出して演奏という行為によって具現化しているというような妄想を抱かせるくらい自然であり、作曲されたエチュードを聴いているかのようなハイブロウでありながら、メロディアスであり緩急自在でスリリングな音楽が展開されているのだ。
そして断片的に様々なメロディーを引用するユーモアも持ち合わせていて、堅苦しさも感じられない。
是非、J・F・JENNY-CLARKのベースの旅に付き合ってみる事をお薦めする。
録音は1994年 AVIGNON

去年から気になっていたトミー・スミスの新作をGWにタワーレコードでようやく手にいれた。この作品オールスターメンバーでおまけにジョー・ロバーノとのツーテナーなので、凄く聴いてみたかったのです。
TOMMY SMITHを初めて聴いたのはゲイリー・バートンのECM盤(小曽根真も参加)だったが、何故かそれ以来縁がなく、一枚もリーダー盤を所有しておらず、ちゃんと聴いたこともなかったので、このCDがほとんど初めての試聴と言って過言でない。
すでにリーダーアルバムを10枚以上リリースしていて、中堅といってもよいポジションだと思うが、このような超豪華メンバーでの録音はスミスにとっても初めての経験ではなかろうか?
1曲目「WOODSTOCK」曲調は題名通り、アメリカの中西部というか、ロック~カントリーテイストのするメロディーをもついかにもジョン・スコフィールドが演奏しそうなテーマをもつ曲。そのスコフィールドが昔の感じでバンドの一員といったギタリストに徹したプレイを展開していて聴き物だ。
後半に展開されるスミスとロバーノのバトルは両者のスタイルの違いがよく分かって、迫力のあるソロ交換がおこなわれる。
一言で言うならば、スミスがスタイリッシュ、クールで端正なスタイルなのに対し、ロバーノは男性的で豪放と言える。
3曲目「LISBON EARTHQUAKE」は複雑なテーマをもつ曲だが、メンバー全員の協調性あるプレイにより破綻なく素晴らしい出来になっている。テーマ部分に対してアドリブはストレートな4ビートで展開されているので、白熱した仕上がりでロバーノ、スコフィールド、スミス、テイラーの順でソロが取られる。
5曲目「SPUTNIK‘STALE」もクールなテーマをもつ曲だが、聴き応えのあるアドリブの応酬が繰りひろげられる。スミス、スコフィールド、ロバーノ、テイラーの順。
全6曲、普通これだけのメンバーが揃うと誰かがエゴの強いプレイを展開してバランスを崩したり、顔見世的セッションに終わってしまうことが少なくないのであるが、全員の協調性溢れる、そしてソロの場では100%持ち味を存分に発揮したプレイを展開することによって大変聴き応えある一作に仕上がったと思う。
メンバーはTOMMY SMITH(TS)JOE LOVANO(TS)JOHN SCOFIELD(G)JOHN TAYLOR(P)
JOHN PATITUCCI(B)BILL STEWART(DS)
録音は2003年4月 AVATOR STUDIOS NYC

オーディオファイルから1998年にリリースされた未発表ライブ作で、2000年に福岡のキャットフィッシュレコードから手に入れた。
このアルバム、私的には最高の曲の流れでとても気にいっている。
アルバム3曲目から11曲目の流れが、まるで自分のために選曲してくれたんじゃないかと思うくらいツボにはまった選曲なのです。
録音は1977年、まさに歌手として絶頂期を迎えていた時で、このアルバムのプロデューサーであるDICK PHIPPSの自宅で録音されたものなので、非常にリラックスした雰囲気の中で唄われた事が推測される。
全部で22曲が収録されているのであるが、3曲目「EMILY」から「WHEELERS AND DEALERS」「WHAT ARE YOU DOING THE REST OF YOUR LIFE?」「MAD ABOUT THE BOY」「THE UNDERDOG」「YOU WERE THERE」「A CHILD IS BORN」「THE SHADOW OF YOUR SMILE」11曲目「A TIME FOR LOVE」が白眉だと思う。
録音はテープの劣化の為所々歪があるが、聴けないほどではなく許容範囲内だと思う。
勿論スタジオの正規録音ほどのクオリティーは望めないが・・・
5曲目の「これからの人生」ひょっとしてクラールは自身の残された時間をこの録音の時点で悟っていたのかもしれないと思わせる様なとても深くて寂しい表現をさりげなく唄に織り込む。この名曲の3本指にはいる名唱だと思う。
7曲目アル・コーン作曲の「負け犬」は隠れ名曲だが、こういう淡い色調のバラードを独自の解釈で表現できて初めて一人前の歌手ではないか?
何故こんなにアイリーン・クラールを好きになってしまったのか自分でもよく分からないのだが、まず声質、聴き取りやすい発声、歌詞の真意を真っ直ぐに自身の唄に表現するシンセリティー、ストーリーテリングの巧みさ、そこはかとなく漂ってくる情感、気品といったところだろうか?
こんな歌手居そうであまり居ない、亡くなってからその存在の大きさを感じて喪失感に心が痛む素晴らしいジャズボーカリストだったと思う次第。
クラールは私の心の中で、いまでも生きつづけているのだ。

リリース情報を当時通販で買っていた大阪の「ライトハウス」のカタログで知って直ぐに注文したはず。同じ頃、NHKFMのジャズ番組で本多俊夫がこのCDをオンエアしたのを思い出す。
買った時は全く知らなかったのだが、メンバーはピアノ、LARS JANSSON, テナーにJOAKIM MILDERという今から見ればとても素晴らしいサイドメンが参加。
ストックホルムのレッド・ミッチェルの自宅で録音されたものなので、いつになく寛いだ雰囲気のするレコーディングとなった様だ。
部屋のアコースティックもよいので、録音状態もとても良い。
ミッチェルのベースは通常の調弦ではなくてチェロの調弦がなされている事は前にも書いたと記憶するが、その独特な音色でうたいあげるベースプレイは70年代以降まさにワン&オンリーなものとなった。
ブラインドで聴いても直ぐにそれだと分かる印象的なプレイはこれまた癖がありすぎて評価の分かれるロン・カーターと双璧をなすと言ってよいだろう。
私はどうかって?
どちらも大変好きです。ロン・カーターの事を最悪のように言う人が結構多いけど、あの音色も結構好きなんです。ピッチが悪いだ、ゴムが伸びたような音色だ、ボロクソ言う人が見受けられるが私自身は音的に決して悪くないと思うし、あの音色はロン・カーターが作り上げたオリジナルなものだと思うので、評価している。
レッドもロンもそういう意味で個性のかたまりのようなベーシストであるし、その特徴ある音色と奏法でソロイストとしての地位を築きあげたのだと思う。
このアルバムはスタンダード「THERE IS NO GREATER LOVE」「枯葉」「MY ONE AND ONLY LOVE」「LIKE SOMEONE IN LOVE」「ON GREEN DOLPHIN STREET」と3人のオリジナル作品がバランスよく選曲されていていつまでも飽きのこないスルメ盤としてお薦めする。
録音は1990年2月18,19日 RED MITCHELL`S APARTMENT IN STOCKHOLM

イタリアの中堅ピアニストが1998年に吹き込んだカルテット作。
2000年5月に大阪出張の時、梅田のワルツ堂EST1店で買った。
決して手を抜いていると言う訳ではないのだけれど、全般的に今で言うマッタリしたリラックスした雰囲気に溢れている。
テナーサックスの新鋭FRANCESCO BEARZATTIは最近の若手にしては珍しくハスキーなサブトーンをうまく取り入れてこのアルバムでは非常にオーソドックスなプレイに終始している。
実際自身の最近のアルバムではフューチャージャズを意識した新らしめのサウンドを展開していた。
リーダーのGIOVANNI MAZZARINOはレギュラーグループでクインテットも結成していて、そこにはファブリッジオ・ボッソも加入している関係上この人のリーダーアルバムは自然と増えていったのであるが、正直ピアニストとしては極めて中庸の線で、特に特筆するようなピアニストではないと思う。
サイドメンにボッソやBEARZATTIのような有能なメンバーが集まるのは、人望や統率力があるためかもしれない。
このアルバムではスタンダードやジャズメンオリジナルのバラードナンバーがつながりよく選曲されていて完成度が高く、何度も聴いてみる気になるつくりがなされている。
ミルト・ジャクソンの「NIGHT MIST」とアラン・ブロードベント「DON`T ASK WHY」がこんなに素晴らしい曲なのは、このアルバムで初めて知った。
他に「EVERYTHING HAPPENS TO ME」「I`M THROUGH WITH LOVE」「STARWAY TO THE STARS」「PORTRAIT OF JENNY」「SPRING IS HERE」「I THOUGHT ABOUT YOU」「ALONE TOGETHER」など全11曲。
メンバーはGIOVANNI MAZZARINO(P)FRANCESCO BEARZATTI(TS)STEFANO SENNI(B)
PAOLO MAPPA(DS)
録音は1998年9月10日 CATANIA(SICILY)
 このアルバムはソニーのOPEN SKYレーベル第一弾として確か発売されたはずで、発売当日に買ったのを覚えている。
このアルバムはソニーのOPEN SKYレーベル第一弾として確か発売されたはずで、発売当日に買ったのを覚えている。確か1979年夏だったと記憶している。
いきつけのジャズ喫茶「JOKE」でもEAST WINDの「EIGHT MILES ROAD」やギル・エバンス・ビッグバンドでのギタープレイをよく聴いていたし、前年に買ったMPSからリリースされた隠れ名盤「NATURE`S REVENGE」(いつか紹介しようと思っている)を買ってすっかり川崎燎のファンになった大学生の私は相当期待してこのアルバムを買ったのだと思う。
渡辺香津美、増尾好秋と並んで三大ジャズギタリストだった川崎燎だが、BETTER DAYSの渡辺(コロンビア)、ELECTRIC BIRDの増尾(キング)に比べて人気の点で、やや劣っていた。これで多くのファンを獲得してシーンの前面にでてくるなぁと溜飲を下げたものだ。
実際OPEN SKYのアーティストのプロモーションコンサートで帰国した川崎には音楽誌だけでなく一般誌のインタビューが朝から夜遅くまで殺到してまさに人気爆発は頂点に達していたと思う。
このアルバムは今から25年以上前に録音されたフュージョンに分類される音楽だと思うが今の耳で聴いても古臭く感じない点にびっくりする。
その頃の他のフュージョンアルバムを聴くと懐かしさと同時にどうしてもリズムやアレンジの古さを感じるのに、この川崎のアルバムはそんな事は微塵も感じさせない、新譜といっても信じそうになるくらい完成度の高いオリジナルな音楽が展開されていることに驚異を感じる。
このアルバム、90年代に入ってから、
UKのクラブシーンで火がつき、(ジャイル・ピーターソンだったかがプレイした。)それが川崎の再評価につながったのも元はといえばこの作品の音楽としての新しさ、完成度の高さ、魅力からくるものであろう。
この後同レーベルから2枚アルバムをリリースするが、もともとポップス性を志向していなかった川崎はよりインドの旋法やロック色を強めたサウンドを展開していき大衆性、人気という点からはこのアルバムを頂点に再び遠ざかっていくのである。
そして、あまり名前を聞かなくなって、風の便りにコンピュータープログラミングで大もうけして、それで一生遊んで暮らせるほど稼いだというような話を耳にした。
90年代に入って再び音楽活動が活発になるのであるが、スムースジャズというオブラートにパッケージングされていても川崎のギターはさすがに鋭い輝きを維持している。このアルバムのカヴァーバージョンのCDも製作された。
一ファンの願いとしては、原点に返るというか、オーソドックスなギタートリオかカルテットの編成でライブハウスツアーしてほしいと思う。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- 還暦とは思えない!
- (2021-02-28 20:19:39)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪遠藤さくら『のぎおび◢』S…
- (2024-11-23 05:24:10)
-
-
-

- ラテンキューバン音楽
- アナログミキサーの整備 7 sept. 20…
- (2024-09-07 00:00:12)
-
© Rakuten Group, Inc.