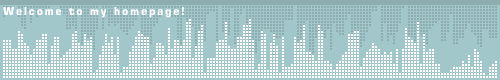音円盤アーカイブス(2005年8,9月)

CELLAR LIVEから最近リリースされたRYAN KISORとIAN HENDRICKSON-SMITHがフロントの現代ハードバップ作品。
名付けてTHE UPTOWN QUINTET。
ニューヨークというと、ブルックリン派やアンダーグラウンド派、シアトル派の動向にどうしても目がいきがちだけど、昔も今も変わらずこういうオーソドックスなストレートジャズは、日常的に様々なスポットで演奏されているわけで、そういう風景は世界中どこでも見られNYでも勿論変わりはない。
一番大事なのは演奏しているミュージシャンが本当に演りたい音楽なのかどうかだと思う。
ミュージシャンは、ファン心理の一途な思いとは離れて様々なトライアルを試みて挑戦して常に変化を好むタイプもいるし、一つのスタイルを何十年に渡って極めるタイプもあって、一概に言えないのだけれど要は本当に好きで演奏している音楽かどうかなのだと思う。
このアルバムに集ったTHE UPTOWN QUINTETのメンバーが本当にハードバップスタイルが好きで演奏しているのは聴けば直ぐに分かるだろう。
目を輝かせながら楽器を持ってプレイするのが楽しくてたまらない様子が音から自然と溢れ出てくる。
フロントのRYAN KISORとIAN HENDRICKSON-SMITHの活気に溢れたソロの応酬も賞賛に値する聴きごたえのあるもので、こういうストレートなジャズにおけるアメリカ=メイジャーの強みを感じる。
メンバーのオリジナルも佳作揃いなのだけど、1曲選ぶとすれば、やはり「BLUE MINOR」に留めをさす。
ライブの現場で実際耳にしたらジャズファンなら素直に感動すると思うのだ。
メンバーはRYAN KISOR(TP)SPIKE WILNER(P)IAN HENDRICKSON-SMITH(AS)BARAK MORI(B)CHARLES RUGGIERO(DS)
録音は2004年4月26日 SMOKE, NYC

このアルバムが発売された1994年当時はリーダーは勿論、ピアノのERIC REEDやベースのMARK SHELBYも全くの無名の存在だったはず。
ドラムのBILLY HIGGINSのみ有名。しかし、このCD,結構話題になって売れたようで
最初にWAVEに注文したときは品切れで、何ヶ月か経ってから手に入れたブツなのを覚えている。
ROBERT STEWARTのテナーの音色はスタンリー・タレンタインやジョン・スタブルフィールドの様なアーシーなトーンで、厚いリードに腹の底から息を吹き込んでいるのが分かるようなサウンド。
いわゆる、遠鳴りする音で、瞬発的よりむしろ持続的なパワーを感じさせる。
エッジの聴いた鋭い音ではなくて、鉈のような音といったらよいだろうか?
そういう音を武器に楽曲をストレートに吹奏する様が聴いた当時とても新鮮に感じたことを覚えている。
メカニカルなフレーズやスケールアウトすることなしに、あくまでも伝統的にストレートに実直にテナーを吹く姿勢に好感を抱いたのだ。
オリジナル作も良い曲が多いけれども、1曲選ぶとすれば「INVITATION」でしょう。
数年前NHK-FMの「オールデイ・ジャズ・リクエスト」のなかでA&Fの大西さんが同曲をリクエストしてオンエアされたのだが、嬉しそうに誇らしげに紹介されていたのを思い出す。
まさに、ジャズ喫茶のほの暗い空間で聴いたら最高の1曲だと私も思う。
メンバーは、ROBERT STEWART(TS)BILLY HIGGINS(DS)ERIC REED(P)MARK SHELBY(B)1994年作品

昨年NAGEL HEYERからリリースされたDONALD HARRISONのサックストリオもの。
テレンス・ブランチャードとの双頭コンボを結成していた頃はリアルタイムで追いかけていたけれど、最近のアルバムはほとんど聴いていなかった。
80年代初頭のデビュー当時のハリソンは、切れ味鋭いアルトサックスを武器に八面六臂の活躍をしていたけれども、やがてケニー・ギャレット、グレッグ・オズビー、スティーブ・コールマン、ジェシー・デイビス、ヴィンセント・ハーリングなど新たな人材が出てきてハリソンの影は次第に薄くなってくる。
アルバムはコンスタントにリリースしていたのだけれど、これがハリソンサウンドだというものに欠けて、インパクトの強さや訴えるものが弱かったと思うのだ。
レコード会社も頻繁に移籍して、アルバムの指向性もその度に路線変更が行われ、一体どれが本当にハリソンの演りたいことなんだ?とファンもその度に振り回されたのではないか?
いろいろなことに手を出しすぎて墓穴を掘った例のように思えてならない。
厳しいことを書くようだが、ハリソンにもう一度ブレイクすることを期待してのこと。
NAGEL HEYERに移籍してからストレートジャズに方向性を見据えたようで、レーベルカラー自体はとても保守的だけれど、このまま突き進んでいけば良いのではないかと思う。
このアルバムはロン・カーター、ビリー・コブハムのサポートを得てアルト一本で全11曲を録音している。
正直、今のハリソンの演奏で70分はちょっときつい。
サックストリオで飽きさせずに通すにはあまりにも語り口が一本調子すぎるのだ。演奏にもっと山あり谷ありの起伏がないと聴いている方は飽きてしまう。
使用楽器やアレンジ、構成面でもう少し変化をつければもっと良い出来になったと思う。
演奏がけっして悪いというのではなくプロデュース面のそういう不味さがあったのは結果として残念である。
まだまだ老け込む年でもないのだから、ハリソンには思いきった演奏を録音したアルバムをリリースすることを期待したい。
メンバーはDONALD HARRISON(AS)RON CATER)B)BILLY COBHAM(DS)
録音は、2002年12月1,2日

「ライトハウス」から毎月送られてくる通販カタログに大プッシュされていたので、1990年当時直ぐに発注して聴いたレコード。
未だにMONICA BORRFORSの最高傑作だと思っている。
1曲目ラルス・ガリンの「HAPPY AGAIN」。この美曲を情感込めて丁寧に表現する語り口に私は一聴して惹かれてしまった。
スモーキーな成分が含まれるヴォイスを活かしてそこはかとない情緒を歌に感情移入できるバラード歌手としてのスキル、と同時に軽快で快活な表現にも長けているジャズボーカリストとしての柔軟性、テクニックも持ち合わせたボーカリストだと思う。
今でこそ結構有名になったけど、このレコードがリリースされた1990年当時は知る人ぞ知る存在だつたはずで、スウェーデンの女性ボーカルでモニカと言えば、100人中100人が先日亡くなったモニカ・ゼッタールンドと答えたのではないだろうか?
長年、女性ボーカルを聴いている方ならば、この「HAPPY AGAIN」を聴いてもらえば直ぐに気に入ってもらえるのではないかと思う。
2分23秒の短い曲だけど、モニカの魅力が凝縮された1曲だと思うのだ。
ピアノのGOSTA NILSSON,テナーのBERNT ROSENGREN(このアルバムではアレンジのみ)によるアレンジも素晴らしくこのレコーディングに参加したミュージシャン全員がモニカの為に一肌脱いでやろうという心意気が表れていて聴いていてとても気持ちの良い暖かく家庭的な雰囲気のセッションだったのが窺がわれる。
選曲も「ROUND MIDNIGHT」「HOW DEEP IS THE OCEAN」「WHEN SUNNY GETS BLUE」「ALONE TOGETHER」「OLD FOLKS」「THAT OLD BLACK MAGIC」「TWISTED」などモニカの持ち味が存分に発揮できる曲がセレクトされており、アルバム一枚捨て曲なしで楽しめる仕上がりとなっている。
未聴の方は是非一度聴いてみられることをお薦めする。
メンバーはMONICA BORRFORS(VO)STEFAN ISAKSSON8TS)GOSTA NILSSON(P)PER NILSSON(B)MAGNUS OSTROM(DS)他
録音は1990年3月 STOCKHOLM
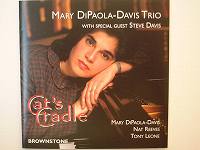
1997年にBROWNSTONEからリリースされた女性ピアノトリオの一枚で、旦那はトロンボーンのSTEVE DAVIS。
このMARY DiPAOLA-DAVISの作品にもそんな訳で数曲スティーブが加わってトロンボーンのワンホーンセッションが展開されている。
アルバム前半はピアノトリオの演奏で、MARYの女性的な穏やかで抒情感溢れたタッチによる演奏は日常的に聴くピアノものとして丁度いい塩梅。
圧倒的な演奏では決してないが、オリジナル曲とプレイのバランスがどちらが競り勝っていると言うわけでなく良い具合に均衡を保っているのでゆったりと身を任せて演奏を楽しむことの出きる作品となっているのだ。
1曲目「CAT'S CRADLE」も良いが、3曲目の「LITTLE BOY'S BOSSA」が特に良い。
6曲目「BEAUTIFUL FRIENDSHIP」からSTEVE DAVISが加わり、トロンボーンカルテットの演奏となる。
ソロイストとしてやはり華があると言うか演奏の雰囲気がそれまでの叙情的でしっとりした感じから、一転ジャージーで活気に溢れたものになる。
DAVISが入っているトラックでもテーマはMARYが弾いているものもあり、そこら辺がゲスト扱いなのが見てとれる。
ピアノトリオでも収録された「EASY LIVING」のカルテットヴァージョンはややテンポを速めて演奏される。
ラストは「DARN THAT DREAM」をしっとりと演奏してアルバムは終了。
道端に咲いた小さな色の美しい花のような見過ごすには勿体無い、ちょっと歩を止めて見ていたい様なチャーミングで可愛い作品というところか・・・
メンバーはMARY DiPAOLA DAVIS(P)NAT REEVES(B)TONY LEONE(DS)STEVE DAVIS(TB)
録音は1996年10月7日 BROOKLYN, NY

発売当時、岡山の「LPコーナー」で買った一枚。
入荷して値付け前のものを目ざとく発見し、H井さんに売ってもらったはず。
FRANCOIS JEANNEAUは70年代後半ジャズ喫茶でよく聴いていたが、特にマークしていた訳ではなくてこの時偶然に衝動買いしたもの。
LABEL BLEUだし、悪いことも無かろうと精算前のもう一枚に選んだのだ。
編成がオーソドックスなカルテット編成で、ジャノーの演奏も結構直球一本勝負で、コルトレーンしている。
さざ波の様に繊細でパルシィブなアーロン・スコットのシンバルワークの中をJEANNEAUのテナーがフレーズをつむぎだし増幅していく3曲目など、気迫のこもった吹奏ぶりで迫力がある。
ソプラノも数曲吹いているが、テナーの方が圧倒的に私はいいと思う。
5曲目「VALSE」も名演、カルテットの一丸となった演奏が聴ける。
最近のチャールス・ロイドのカルテットを思わせるところがないではないが、ジャノーのテナーの方がシャープで切れ味鋭くエッジが立っている。
ANDY EMLERやMICHEL BENITAの名前はこのレコードを買った1988年当時馴染みがなかったけれども、今聴いてみていいプレイを行っていると思う。
メンバーはFRANCOIS JEANNEAU(TS,SS)MICHEL BENITA(B)ANDY EMLER(P)AARON SCOTT(DS)
録音は1988年5月24,25,26日

昨日無事到着しました。
HMVから入荷遅れのメールが何日か前に送られてきて不安になり、クレームのメールを入れようかどうしようか迷っている矢先、すんなりと送られてきました。
このレコード、オリジナルは美品のコンディションなら一体いくらするのだろう?
おそらく20万はくだらないのでは?
そんな貴重盤を細部にわたってマニアックに復刻してくれる、澤野さんに素直に感謝!
ライナーノートにも書かれているが、おそらくオリジナルのプレス枚数は多くても数百枚であろう。今回の復刻の方が、相当多くプレスされたと思うけれども、既に在庫完売であるらしい。
仙台のDISKNOTE、大阪のミムラ、福岡のキャットフィッシュにはまだあるかもしれません。
入手したい方は、一刻も早く問い合わせされた方がよいですよ。
持っているだけで、幸せになれるレコードだと思います。

今日は早朝からマラソン大会にはじめて出場して、(といっても5KMですが・・・)
その後、N山さんと研究会。たかが5KMと半分ばかにしていたのが、レースが始まってみれば日頃のペースがすっかり乱れてしまい、最後の1KMはアップアップで何とかゴールした次第。油断大敵とはこういうことをいうのですね。
ALTEとFRODEのNYMO兄弟はノルウェーの主流派サックス奏者で、弟のALTEがテナー、兄のFRODEがアルト奏者として住み分けされているようだ。
兄が1975年生まれ、弟が1977年生まれの二人とも新進気鋭のサックス奏者と言えよう。二人ともはトロンハイムの音楽学校出身で、デイブ・リーブマンが師匠にあたる。
その二人がピアノの重鎮ROGER KELLAWAYを向かえて行ったライブ録音が本作となった。
似たような音楽環境を経験した二人なので、楽器の違いはあれどスタイルの相似性は否めない。弟のALTEがテナーなので、よりリーブマンの影響を感じさせるが、リーブマンほどファナティックな語り口ではなく、クールな内に秘めた情熱を感じさせるプレイ、兄のFRODEは、もちろんアルトサックスの特性もあるのだが、スピード感溢れたフレーズでジム・シナイデロやケニー・ギャレットの影響も感じさせるテクニックに裏づけされた流麗なソロワークを披露する。
彼らのソロに間にはさまれるROGER KELLAWAYのソロはさすが年季のはいったいぶし銀プレイでこのアルバムの価値を高めている。
3曲目の「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ」はケラウェイのピアノトリオで演奏され、このアルバムのいいアクセントになっていると思う。
ALTEとFRODEに関しては1曲目ハル・ギャルパーの「TRIPLE PLAY」と4曲目ブランフォード・マルサリスの「ケインとアベル」でのプレイが一番いいように思う。
ライブ録音ということもあってやや冗長なところ無きにしもあらずだが、このノルウェーの若手サックス奏者の成長を見守っていきたいと思う。
メンバーはALTE NYMO(TS)FRODE NYMO(AS)ROGER KELLAWAY(P)OLE MORTEN VAGAN(B) HAKON MJASET JOHANSEN(DS)
録音は2002年8月6日 OSLO

カナダの中堅サックス奏者の1990年代初頭のカルテット作品で、岡山のLPコーナーで買ったもの。ピアノにはジョン・バランタインが参加している。
デイブ・リーブマンが指導したことがあるらしく、このデビューアルバムにもちょこっと賛辞を寄せている。
この当時師匠のリーブマンはテナー休業中だったが、JOHN NUGENTはテナーサックス一本で、結構硬質なトーンでゴリゴリ吹いている。JOHN BALLANTYNEもマッコイばりの迫力ある疾走するようなモーダルソロを弾いており、演奏自体ギミックなしのリアルファイトを展開しているような趣き。
ベースとドラムもベテラン、NEIL SWAISON,JERRY FULLERが担当していて切れ味鋭いサポートをおこなっていてカルテットのバランスがとても良い。
リーダー自身にデビューアルバムということもあって、余裕とか遊び心などは全くなく、レコーディングに集中している様が感じられるのだけど、ピアノトリオの方がジャージーな雰囲気をかもし出していて上手く緩急をつけてアルバムをメリハリあるものにしていると言えよう。
NUGENTはこの当時まだまだ表現の引き出しの多いプレイヤーとは言えず、語り口はどちらかと言うと狭い無骨な印象を受けるのだが、それが決してマイナス要因になっていない。
テナー一本に賭ける男の心意気みたいなものが、そのプレイににじみ出ていることを評価したい。
磨けば、光る原石の輝きをこの頃の演奏から感じるのだ。
ベストテイクは5曲目「STABLEMATES」。
あれから15年経過したけど、今どうしているのだろう?
メンバーはJOHN NUGENT(TS)JON BALLANTYNE(PNEIL SWAINSON(B)JERRY FULLER(DS)
録音は1990年3月24,25日 CANADA

WIDE SOUNDからちょっと前にリリースされたイタリアの新進ピアニストのリーダーアルバム。フロントにFRANCESCO BEARZATTIとMARCO TAMBURINIのクレジットを発見して1曲目に「FOOTPRINTS」を演っているので買うことにした。
BEAZARZATTIが、テクニカルで柔らかなトーンでテーマからアドリブになだれ込みむ。自身のアルバムでは前にも書いたが、フューチャージャズっぽいことを演っているけど、こういう主流派的なプレイでもっとも実力が発揮されているように思う。KEKKO FORNARELLIも気合の入ったソロを展開している。
2曲目でのMARCO TAMBURINIのミュートプレイはマイルスというよりも大先輩パオロ・フレスを彷彿させる。
このバラードでは、美しい響きの流麗なソロをFORNARELLIはとっていて、そういうところはこれまたイタリアの生んだ今や世界的ピアニストENRICO PIERANUNZIから受け継いだものなのだろうか?
「FOR HEAVEN'S SAKE」ではBEARZATTIのまろやかで、歌心あるテナーがフューチャーされる。続く「BLUESETTE」はピアノトリオでプレイ。
オリジナル作品ではFORNARELLIやBEARZATTIもより大胆で自由な解釈のアドリブをしていて決して無調になるわけではないが、自由度高めのソロを展開してる。
現代イタリアジャズ界若手によるスマートなイタリアンバップ作品だと思う。
メンバーはKEKKO FORNARELLI8P)FRANCESCO BEARZATTI(TS)MARCO TAMBURINI(TP)MAURUZIO QUINTAVALLE(B)MIMMO CAMPANALE(DS)
録音は2004年12月、2005年1月 BARI,ITALY

FSNTの近作、ニューヨークのサックス奏者JOHN O'GALLAGHERのリーダーアルバムでN山さんからお借りしたもの。
AXIOMというグループ名で活躍している2作目らしいけど、前作は未聴で本作がO'GALLAGHERの作品を聴くのは初めて。
マリア・シュナイダー・オーケストラのメンバーやニューヨーク・サキソフォン・サミットというグループでも活躍しているらしい。
メンバーの中ではやはりTONY MALABYの参加が目を引く。
O'GALLAGHERがアルト、MALABYがテナーを担当していて二人とも持ち替えでソプラノを吹いている。
二つの解き放たれた糸が中を舞い、絡み合い一本の糸になっていくような浮遊感覚に溢れたたゆとうイメージのする曲が多く、人によっては強烈な眠気を喚起するかもしれない。
彼らが目指している音楽が、元来ポピュラーなものを指向しているものではないし、従来のジャズのイディオムで語られるスタイルもなくオリジナルな音楽を創造することを目標としているので、オープンマインドで接しないと中々耳に入ってこないかもしれない。
どこからどこまでが作曲で、どこからが即興というのが明確に聴いていて分かりにくい最近のブルックリン派の連中にしばしば見受けられる演り方と言ったらよいだろうか?
まだまだ消化不良な部分も多くてだれてしまうところも無くはないのだが、カルテットのメンバーが有機的に絡み合い、唸らせられる部分もあって今後の彼らの音楽的発展、成熟に期待したい。
メンバーはJOHN O'GALLAGHER(AS,SS)TONY MALABY8TS,SS)JOHN HERBERT(B)
JEFF WILLIAMS(DS)
録音は2004年1月30日 N.J.

あれは、もう20年前のことになるのだ。
外は雨が降りしきるジャズ喫茶のカウンターにいつもの如く座ってマスターとポツリポツリ会話をしていた。
新譜で買ったばかりの与世山澄子の新作「WITH MAL」をかけてもらった時、マスターが急に黙り込んでしまった。
B面最後の曲「THE NEARNESS OF YOU」が終わってからも数回以上針音をたてながらレコードがプレイヤーの上を回り続けていた。
ようやくピックアップを上げてマスターが言った。
「日本人のボーカルでこんなに深い表現できる人がいるとはなぁ・・・」
あまり褒めることのない辛口のマスターの言葉少なめだが、賞賛していることは充分理解できた。
私はと言うと、その頃はボーカル門外漢で、あまり良さが分からず、そんなもんかなぁという反応だったと思う。
時は流れて、20年ぶりの与世山澄子の新作は自身の店「インタリュード」で録音された。バックのミュージシャンはぐっと若返り、ピアノはマルや山本剛から南博に、ベースは稲葉国光や岡田勉から安ヶ川大樹に、サックスは峰厚介から菊地成孔に変わっている。
与世山澄子だけがずっとそこに存在し続けていたかのように変わっていない。
いや、年齢は20年分もちろん年をとっているし、声も聞き比べれば、太くなっていて若い頃の瑞々しい保湿成分のような部分は失われているのかも知れない。
そんなことなど、取るに足らないどうでもいいことのように思わせる「大きさ」が唄の中に確固として存在していて、圧倒される。
与世山澄子という生き方が唄の中に満ち溢れているのである。
「MISTY」「LOVER MAN」「NIGHT AND DAY」「POOR BUTTERFLY」「WHAT A WONDERFUL WORLD」「SO IN LOVE」、おそらく今までに何千回と歌ったであろうスタンダードを、こちらが初めて聴くように響いてくるのはそういうバックボーン、生き様が唄の中に込められているからであろう。
共演した東京の今を生きる3人の若手ミュージシャンも、「ジャズの随」を肌身で体感するいい勉強になったのではないだろうか?
与世山にとっても息子ほど年の離れたミュージシャンとのレコーディングは楽しく刺激的なものだったに違いない。
これを機会にライブツアーを行って欲しいいような、欲しくないような微妙なファン心理に心揺れるのであった。
メンバーは与世山澄子(VO)南博(P)安ヶ川大樹(B)菊地成孔(TS)
2005年作品

フランスの女流ピアニストCLAUDINE FRANCOIS率いるカルテットによるライブ作品。スティーブ・レイシーとの交流、作品が多かったSTEVE POTTSがフロントを全面的に任されていてこれが大いに購買意欲を湧かせた。
去年の春先発売されたエスカイア誌「JAZZ IN PARIS」の表紙とカラー写真が、仁王立ちしてサックスを咆哮しているポッツの姿をローアングルから捕らえたものでナイスショットだった。
リーダーのCLAUDINE FRANCOISは大向うを張らせるタイプのミュージシャンではなくテクニックに頼るというより、自身の感覚を大事にしている演奏家だと思う。 全体のサウンドとインタープレイ重視して、スポンティ二アスに反応し場を切り開いていくタイプのミュージシャンと言ったら良いだろうか。
もちろん懐には刀を持っていていざという時には鋭い切り込み、アクション技を繰り出すことも可能なのだけど、滅多にそれを出すことはなく、叙情的表現においても非凡なところをみせる。
STEVE POTTSのサックスがこれほど全面的に収録された作品は初めて耳にした。 それもオーネット・コールマン、モンク、マル・ウォルドロンなどのオリジナルを大々的に演奏しているのだ。
JEAN-JACQUES AVENELとJOHN BETSHの素晴らしいリズムの中をその二人のソロが自由に泳ぎまわり、時には有機的に絡み合う。
ライブと言う事もあって一曲、一曲が結構長尺なのだが、ソロが充実しているので全く長さを感じない。
メンバーはCLAUDINE FRANCOIS(P)STEVE POTTS(AS,SS)JEAN-JACQUES AVENEL(B)
JOHN BETSCH(DS)
録音は2003年6月18,19日

イタリアテナー界のホープ、DANIELE SCANNAPIECOの新作で、前作とはリズムセクションが変わり、DADO MORONI、IRA COLEMAN,GREG HUTCHINSONと豪華メンバーになっている。トランペットに2曲のみだがFABRIZIO BOSSOも参加。
こう聴くと、誰が買わずにおられようか、DUに注文しいまいましたぁ!
オープニングからしなやかで勢いのある快適なサウンドが飛び出してくる。相変わらずBOSSOのトランペットはソリッドなアクション技を織り込みつつ湧き出でる泉の如くフレーズの連続でいつまでも聴いていたいと思わせるほど素晴らしい。
DAMIELE SCANNAPIECOも成長著しく、表現の幅が拡がりテナーサックスの音そのものに以前にまして様々なニュアンスが込めれるようになり、説得力が増したと思う。この事は9曲目「AUTUMN IN NEW YORK」を聴けばよく分かるだろう。
この手垢にまみれた演奏してみると意外にオリジナル性を出すのが難しい曲をうまくまとめ上げている。
このアルバムは先に述べたようにBOSSOが2曲参加していてアルバムに変化をもたせており、またオリジナル曲もバラエティーに富んだ曲調を用意して、曲によってはストリングスがからむなどアレンジにも力が入った作りとなっている。
仮にそうしたものが全く無くて、アルバム一枚まるまる生身のSCANNAPIECOのワンホーンのアルバムだとしたら、どうか?
正直いって、ジョシア・レッドマン、クリス・ポッター、マーク・ターナー、エリック・アレキサンダーなどと同列で語れるかと問われるとまだまだ努力の余地が残されていると言わざる得ない。
SCANNAPIECOには、彼らのライバルになる実力を充分持ち合わせている才能の持ち主だと思うので今後も期待していきたい。
メンバーはDANIELE SCANNAPIECO(TS)FABRIZIO BOSSO(TP)DADO MORONI(P)IRA COLEMAN(B)GREG HUTCHINSON(DS)
2004年4月20,21,22日

今年の初めにレビューしたキューバ出身の新人ピアニストのリーダーアルバム。
FSNTからのリリースで前作と同様、今回もシーマス・ブレイクが参加している。
SEAMUS BLAKEの参加は2曲のみだが、いつにまして豪放なブローで、起伏に富んだスリリングなソロを展開していて聴き応えがある。
ANTONIO SANCHEZのドラムが素晴らしく歯切れの良い的確なビートを叩き込んでいて、MANUEL VALERAの楽曲と相性が抜群。
前作では色々な楽想の曲を一枚のアルバムに盛り込みすぎてやや統一感に欠ける仕上がりだったが、今作は、ピアノトリオ=ラテンテイスト、カルテット=ネオバップという明確な図式の元にプロデュースされているので統一性、ストーリー性があってその分分かりやすく聴きやすい。
あまりべたつかない哀愁のメロディーがさりげなく盛り込まれている3曲目「ADIOS A CUBA」。中々の名曲だと思う。
チャーリー・ヘイデンが好みそうな楽曲と言ったら分かってもらえると思う。
シーマスは1曲目、6曲目に参加しているのであるがこれがアルバムのいいメリハリとなっていて、アルバムを通してだれることの無いつくりとなっている。
ミッシェル・カミロやゴンザロ・ルボルカバ、ラテン系の有能なピアニストは多いけどこのMANUEL VALERAも近い将来その仲間に充分入ることが可能なポテンシャルの持ち主だと思う。
柔らかく粒立ちの良いタッチを武器に正確なリズムで鍵盤上を縦横無尽に駆け巡るスタイルはラテン系ピアニストに良く見られるスタイルだけど、VALERAの場合それだけにとどまらず思索的で繊細な表現にも非凡なところを発揮する。
今後も注目していきたいピアニストの一人である。
メンバーはMANUEL VALERA(P)BEN STREET(B)ANTONIO SANCHEZ(DS)SEAMUS BLAKE(TS)
録音は2004年9月2日 NYC

15年位前、JR三ノ宮駅前にあったジャズレコード専門店「JR」で買ったもの。
ジャケットを見て「?,?,?」と思われる方も多いかもしれない。
そう、デザインがボブ・ディランの有名盤のパロディーだからである。
リリースしたのはイギリスのオリジナル・レコードで、録音もロンドンで行われている。
クリス・ハンターは80年代後半、ギル・エヴァンス・オーケストラへの参加やパドルホイールへのリーダーアルバムの吹き込みから我が国のジャズシーンで次第に認知されていったが、このレコーディングが行われた1980年頃はほとんど知られていなかった。
この頃のプレイから現在のプレイに通ずるスタイルをほとんど確立していて、2曲目、STEVIE WONDER「TOO HIGH」ではエフェクターをうまく使ってロックテイストに溢れたファンキーサックスを聴かせている。
アルバムのサウンドは、どことなくスティーブ・グロスマンの「PERSPECTIVE」に似ている。グロスマンのアルバムが確か1978年だったから、参孝にしたのかもしれない。
3曲目MIKE WESTBROOKの「JULY79」では女性コーラスも導入して中々プログレッシブロックぽい音づくり。もっともアドリブはサンボーンのスタイルをずっとジャズぽくしたプレイでバックとのサウンドとのミスマッチさ加減がB級アルバムらしいところか?
何故かエリントンの「PRELUDE TO A KISS」がB面半ばで、ピアノとのデュオで演奏される。クリスの好きな曲なんだろうか?
ラストは最もフュージョンライクな聴きやすいメロディーをもった曲で題名通り「HAPPY ENDING」で終わる。
個人的には今の中途半端なクリスよりこの頃の演奏をかっている。
メンバーはCHRIS HUNTER(AS,TS,SS)BRIAN GODDING(ELG)PHIL CRANHAM(ELB)ROBIN SMITH(P,KEY,SYNTH)DAVE EARLY(DS,PER)JACKI BENAR(VO)
1980年作品

フランス系カナダ人のテナー奏者JEAN-CHRISTOPHE BENEYの新作。
横顔がボブ・ロックウェルに似ているなぁ。そのロックウェルはチャック・ウィルソンに似ているだけれど。裏ジャケの正面からとった顔写真はそれほど厳ついと言うか精悍な顔ではなくてもう少し優しい顔つき。
顔の事は差し置いて新作の話。
カルテット主体の編成にパーカッション、ギター、ボーカルが曲によって絡むという作品だが、あくまでもサウンドの核となっているのはBENEYのテナーサックス。
その音色は、マーク・ターナーやクリス・ポッター、クリス・チークに似通ったバランスのとれた深みのある音。高音部ではハーモニクスを使って演奏にメリハリをつけたりもするテクニシャンでもある。
でも基本的に指向している音楽はあまり、難しいものではなくて結構ほんわかしていて和み系サウンドに聴こえないこともない。
曲調やリズムは変化に富んでいて決してキャッチーな売れ線のメロディーが展開されることはないのだけど、全体的にそういう印象を受けるのだ。
フェンダーローズの涼しげな音が効果的に使われているのも理由に挙げられるかも知れない。
とにかく音楽がせかせかしておらず、ゆったりとプレイされていて、それが緊張感をスポイルすることなしにアルバムを通して展開していることを評価したい。
けっして斬新な音楽ではないが、時々取り出して聴きたくなるワンホーンアルバムという感じだ。
メンバーはJEAN-CHRISTOPHE BENEY(TS)PIERRE DE BETHMANN(P,ELP)VINCENT ARTAUD(B)KARL JANNUSKA(DS)他
録音は2004年4月5,6日 FRANCE

ノルウェーの注目すべきレーベルJAZZAWAYからの新譜で、これまた注目すべきテナー奏者トニー・マラビーがらみのトリオ演奏ということで、春先に情報をしってからリリースを心待ちにしていた一枚。
ベースはFSNTから「OVERSEAS」「OVERSEAS2」を今までリリースしているノルウェーのベーシストEIVIND DPSVIKが担当。
2004年の夏、ストックホルムのライブハウス「THE GLENN MILLER CAFE」で実況
録音されたもの。
トニー・マラビーには注目していて2年前の個人的なジャズマン・オブ・ジ・イヤーに選出したほど要チェックしているミュージシャン。
このトリオでのトニー・マラビーのプレイは今まで聴いてきた中で最もフリー度が高い内容のもので、曲によってはほとんどフレーズを吹かずに、サウンドの断片を変形、加工し音のニュアンス、パワーだけで勝負している曲すらある。
音に込められたイメージの断片、カラーがカレイドスコープを覗き込んでいるように、収縮、拡散し、新たな場に展開していく。
トニー・マラビーの奏者としての個性はそういうプレイスタイルからも薄められることなしに、逆に裸の姿が捕らえられているといえるかも知れない。
意識的にピッチのトーンコントロールをしたり、ハーモニクス処理などサウンド面においてアイラーの影響を感じさせるところもあるが、それは技術面の一部での話であって、彼らの演奏に60年代のフリージャズの精神性を感じ取るところはない。
純粋にプレイ、サウンドを追及しているだけであって、当時のフリージャズが持っていた時代の空気感のようなものはない。
普通のテナートリオだと思って聴くととんだ反発を食らうかもしれないがこれは、
テナー奏者としてのトニー・マラビーの純粋な姿が浮き彫りにされたエポックメイキングな一作かも知れない。
そしてそのサウンドの断片を心をからっぽにして耳を澄ましてみるとメロディアスに聴こえてくる瞬間すらあるのだ。
これこそサックス奏者としての力量を表すバロメーターかもしれない。
他のメンバーのことに全く触れなかったけれども、トリオとしてのサウンドが確立されているのは彼らがあってのことは言うまでもない。
メンバーはTONY MALABY(TS)EIVIND OPSVIK(B) JEFF DAVIS(DS)
録音は2004年8月 STOCKHOLM

2年位前、広島のディスクマーケットで発見した一枚。
全く知らないミュージシャン、レーベルだったが、RICK MARGITZAが参加しているのと、「INVITATION」を演奏していることに大いに購買意欲をそそられて即買いしてしまった。
RICK MARGITZAは、安定したテクニックでどんなタイプのミュージシャン、音楽にも自分の個性を薄めることなしに器用に立ち回ることの出来るクレバーなミュージシャンだと思う。
あまりにもフレキシブルに様々な状況に上手く対応できるので、それが逆にRICKのミュージシャンとしての焦点をぼかしてしまっていると言えるのかも知れない。
実際、MARGITZAのプレイに関しては、どんな難曲でも、危なげなく涼しげに楽々クリアしているようなイメージが残っているのだ。
お目当ての「INVITATION」でも、文句のつけようの無い素晴らしいテナーソロを展開している。曲調のせいもあると思うけど、いつもより親しみやすいフレーズが聴き取れないこともない。
それでも、RICKのプレイにはどこか優等生の模範的解答のような印象がついて止まない。少しはハメもはずして不良性の匂いを感じさせるプレイを聴いてみたいと思うのは私だけだろうか?
意外とRICKが今以上にブレイクするポイントはこういうところなんじゃないかと主伝居る。
リーダーのPASCAL SALMONは、良くも悪くも典型的なヨーロピアンピアニストの趣きで、トリオとリック・マーギッツァーとの相性はとても良い。
ベースのGILDAS BOCLEは、アルバート・スティソンやアーデルハルト・ロイディンガー、アラダー・ペゲ級のピッチカートのよる速弾きソロが素晴らしい。
トリオによる演奏は数曲だけども優雅な響きも感じられこれはこれでとても良い。
セッションだからある程度仕方ないのかも知れないが個人的にはもう少しRICK MARGITZAとPASCAL SALMONトリオとの緊密な応酬を聴きたかった。
メンバーはPASCAL SALMON(P)GILDAS BOCLE(B)MARCELLO PELLITTERI(DS)
RICK MARGITZA(TS,SS)
録音は1994年3月 NY

日本でも結構人気が出てきているDAN CRAYの最新ピアノトリオ作品。
オープナーのラテン調の曲に耳を奪われた。
知ってる曲なんだけど、誰の曲か思い浮かばない。
「いい曲だなぁ」とクレジットを見て納得。
スティービー・ワンダーの「DON'T BE WORRY 'BOUT A THING」だった。
DAN CRAYの料理の仕方があまりにも見事なものだったのでポップチューンと結びつかなかったのだ。
この曲がもつ躍動感、陽気で明るい雰囲気、ラテン的な歌謡性などの魅力を見事にピアノトリオジャズにトランスレートしていて、この1曲でこの作品の素晴らしさを予感した。
続いての3曲は有名曲を演奏するが普通には演らずに何か工夫が仕掛けてある。
「JUST ONE OF THOSE THINGS」など全く違う曲かと思うほどかけ離れたメロディーから始まり、途中バロック風のピアノソロを挟んで次第に種明かしがなされる仕組みになっていてスリルがある。
ピアノのうまさも特筆できる。速弾きしても一音一音、音が粒だっていてよく聴き取れるのだ。
ウェイン・ショーターの「NIGHT DREAMER」を超スローテンポで演奏する他に
ジャズマンオリジナルはダメロン、コリア、シルバー等をプレイ。
次第に盛り上げていったり、そこはかとない叙情性をさりげなく織り込む技は熟練の技。
「SUMMER IN CENTRAL PARK」ホレス・シルバーにこんな旋律の曲があったとは今まで知らなかった。
グルービーなノリで「WITHOUT A SONG」をディグした後は
ラストは自作の「GOOD MORNING」「GOOD BYE」でしっとりと締めくくられる。
ダン・クレイのやる気が漲ったピアノトリオ極上エンターテイメントリラクゼーション盤として推薦いたします。
メンバーはDANCRAY(P)CLARK SOMMERS(B)GREG WYSER-PRATTE(DS)
録音は2005年5月2-4日 CHICAGO

今から5年ほど前、ネットサーフィンしていて偶然ANNE PHILLIPSのホームページにたどり着きそこで、新作がリリースされたことを知った。
アン・フィリップスが現役で歌手を続けていること自体が驚きであったし、ましてやこうして新作をリリースしていることにとても驚いたのを覚えている。
今と違って電話回線の途中でぶち切れるサウンドサンプルを何度も聴いて何とかしてその頃から手に入れたいと思っていたのだ。
数ヶ月くらいして「レコードコレクターズ」にレビューが載ったはずだけど、販売しているショップは残念なことに見つからなかった。
この作品が今回CD BABYから直接買ってみた理由の一つなのは間違いない。
今からかれこれ16,7年前になるだろか、フレッシュサウンドからアン・フィリップスのルーレット盤「BORN TO BE BLUE」が復刻された。
ビル群を背景にした港に佇むコートを着た物憂げな表情のアン・フィリップスの姿を捕らえたショットは思わずジャケット買いしたくなる一作。
岡山の「LPコーナー」に入荷していて即買いを決め込んだ。他のブツを物色している間になんて言う事か他の人にさらわれてしまったのだ。
店長のH井さんに聞くと、最後の一枚だったと入荷告げられる。
その後訪れた倉敷の「GREEN HOUSE」で無事再会できて事なきをえたのであるが・・・
そのアン・フィリップスのアルバムはジャケットと同じくその歌も選曲もそこはかとない寂寥感に包まれた都会的センス溢れるとても好ましいものだった。
聞けば、唯一の作品と言うではないか。
そう聞くと余計に愛着がまして、大事に大事に聴いてきた。
アン・フィリップスという存在自体がそんなわけで自分の中で伝説化、幻の存在となっていたので冒頭で書いたように、アンが歌手活動を継続していておまけに新作をリリースしていることに狐にでも騙されたように驚いたのであった。
ようやく聴く事が出来た。
全15曲、40年以上前の前作では全て渋めのスタンダードでかためられていたのに対し、本作は全てアンの作詞作曲によるもの。
そのことからもずっと音楽活動を現役でおこなってきたことが窺がえる。
若い頃の消え入りそうな清涼感のある声ではなく、人生経験を積んだ憂いのある声。そこには力強さもある。唄の表現幅も拡がって1曲ごとの感情表現がバラエティーに富んでいて飽きさせない。
それでいて一本筋が通っていてどのようなタイプの楽曲にもアン・フィリップスの存在がしっかりとしめされているのだ。
個人的には1,6,7曲目が気に入っている。
夜、一人でじっくり聴きこみたいアルバム。
バックも間違いないメンバーだけに最高の伴奏を聴かせている。
メンバーはANNE PHILLIPS(VO)BOB KINDRED(TS,CL)ADAM ASARNOW(P)JAY LEONHART(B)GRADY TATE(DS)SCOTT HARDY(G)
2000年作品

SKJ RECORDS,すなわちSCOTT KYLE RECORDS自費出版レコードだ。
メンバーのクレジットを見て急に興味が湧いてきた。
90年代初頭ジャズメディアで注目されてその後とんと音沙汰を聞かなかったCHRISTOPHER HOLLYDAYの名前をみつけたからだ。
ホリデイ・ブラザーズとしてメディアに紹介されて以来人気が急上昇して大手レーベルNOVUSと契約、マクリーン系のフレージングを巧みにあやつり3枚のアルバムをリリース。その後とんと情報が立ち消えになってしまっていた。
当時の演奏、決して悪くはないのだが、ジャズを一生懸命勉強してうまく演奏できましたっていうような、優等生的なイメージがつきまとってホリデイ自身の生身の心からのプレイの感じがしなかったのも事実。
説得力、必然性が感じられない音に対してジャズファンは敏感に反応する。
やがてレーベル契約解除、音信が途絶えてしまったのだ。
このアルバムのインナースリーブの裏は録音風景が写っているのだけれどこれが、どうやらアルバムのリーダー、SCOTT KYLEの家の様なのである。
裏ジャケに「IN MY LIVING ROOM STUDIO」ってクレジットされていた。
自費録音ゆえの経費節減もあるのだろうが、これがこのレコーディングを家庭的で暖かなハードバップセッションに導いていると思う。
実にリラックスした雰囲気で各人が伸び伸びとセッションを楽しんでいる状況が伝わってくるので、聴いているこちらにもその雰囲気が伝わってくる。
奇を衒ったプレイは一切無い。
「1001」をひろげながら「次何やろうかっ?」っていう感じで選曲も実にスタンダードなものがピックアップされている。
ホリデイもスポットの当たったジャズ界のセンターコートからこういうローカルなジャズシーンで楽しげに等身大の演奏をしている。
十数年を経てバップフレーズにも説得力が増してこのセッションではやはり頭ひとつ抜きん出た存在。
リーダーのトロンボーンも時々音が擦れたり、ミストーンがあるが悪くはない。
ホリデイ久々の近況報告とハードバップ名曲選、ほのぼのしたセッションの雰囲気を味わう作品だと思う。
メンバーはSCOTT KYLE(TB)CHRISTOPHER HOLLYDAY(AS)ROBERT LAWSON(G)JUSTIN GRINNELL(B)DAVE PSCHAIDA(DS)
録音は2005年2月5,13日 SAN DIEGO

ワシントン.D.C.近辺を主なエリアとして活動しているERIC BYRDトリオの2001年作品。
ERIC BYRDトリオは15年以上プロ活動をしていて、ブルースアレイなど地元のジャズクラブに出演したり、モントルージャズフェスティヴァや南米のジャズフェスにも出場。2001年秋にはアメリカの音楽使節大使として6週間南米に滞在して演奏活動やクリニックをおこなった。
今までに、ウィントン・マルサリス、マイク・スターン、ゲイリー・トーマス、チャーリー・バード、エセル・エニス、バック・ヒル、キーター・ベッツなどと共演したことがある。
そんな経歴の持ち主であるエリック・バードの2001年に録音された第2作目にあたる作品。
エリックのプレイの特徴はゴスペル音楽やブルースに影響を受けたブルージーで歌心あるフレーズにあって、伝統的な黒人ピアニスト(有名どころではウィントン・ケリーやレッド・ガーランド、渋めではエバンス・ブラッドショウ、ジョン・ライトやディック・モーガンなど)をよく研究した後うかがえる。
すこしレイドバックしたダウン・トゥ・アースな雰囲気など現代の若手ピアニストには出しにくいところを、エリックはごく自然に表現しきってみせる。
サイラス・チェスナットやエリック・リードにひけをとらない実力の持ち主だと言うのは私の買いかぶりだろうか?
作曲もうまくて本作に収録されているオリジナルは佳曲揃いで飽きることがない。
ALPHONSO YOUNG,JR.の切れ味鋭いシンバルレガートやBHAGWAN KHALSAの地を這うランニングベースとのコンビネーションも抜群でトリオとしての一体感がある。
アメリカのローカルジャズシーンにはこうした隠れた実力者がまだまだいると思われさすがにジャズのメジャーリーグの奥行きの深さを実感する。
こういうマイナーな作品を見つけ出して聴くのもジャズファンとしての醍醐味だと思う。
メンバーは、ERIC BYRD(P)BHAGWAN KHALSA(B)ALPHONSO YOUNG,JR.(DS)
2001年作品
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【北川莉央・生田衣梨奈・石田亜佑美…
- (2024-11-23 07:10:07)
-
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- ブラックペアン シーズン2 Blu-ray B…
- (2024-11-12 17:59:58)
-
-
-

- 吹奏楽
- 「ドラゴンクエスト」ウインドオーケ…
- (2024-11-23 06:22:12)
-
© Rakuten Group, Inc.