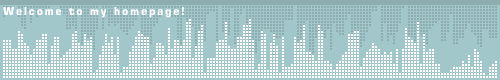音円盤アーカイブス(2006年6月7月)

大阪で30年以上前から、この人の名前を知らないジャズファンは、もぐりというくらい、日本屈指のピアニスト、田中武久がひさしぶりにリリースした2002年ピアノトリオ作品。
今から四半世紀ほど前、初めて聴いた時の印象のことは、ここに記しています。
http://plaza.rakuten.co.jp/ventoazul/4010
田中武久は、自分の店「セント・ジェームス」を1977年に開店以来、来る日も来る日も、夜毎ピアノの前に座り、集うファンに上質のジャズを送り続けている。
この間、いや開店前にも内外の驚くようなミュージシャンに何度となくバンド加入を誘われた。
これらを、全て断ってきて、大阪に居座り続けた頑固者。
金銭面や知名度を考えれば、上京しない手は無いのに、田中は大阪にこだわり続けた。
そんな大阪を愛する田中の自作の曲名(邦題)は、ウィットがきいていて洒落ている。
人生哲学が表れているような曲名といってもよいのかも知れない。
「苦しくも、また楽し」「金は天下の周りもの」「残月」「桜吹雪の調べ」
おそらく、このアルバムでも、日頃のライブ演奏となんら変わったことはしていないのではないかと思われる。
否、ドラムスが愛弟子、東原力哉だから気分が高揚しているか?
歌心、スイング、ジャズスピリッツ、どれをとってもピカイチのピアノだと思う。
飾り立てることのない、ナチュラルなフレーズからは、ペーソスさえも聴こえてくる。
田中のピアノを聴ける大阪のジャズファンは幸せだと思う。
メンバーは田中武久(P)神田芳郎(B)東原力哉(DS)
1.BITTER SWEET
2.A CHILD IS BORN
3.MONEY WILL COME AND GO
4.A MORNING MOON
5.IT'S ONLY A PAPER MOON
6.A FANTSY OF CHERRY BLOSSOMS
7.ZINGARO
8.I'VE GROWN ACCUSTOMED TO HER FACE
2002年作品

6月14日のあかぎ小次郎さんの「JAZZの細道」PCM日記を読んで頷きましたね、私も。
ちょっと長いけど、引用させてもらいます。
音楽の聴ける自営業者にとって、「仕事はかどる盤」という非常に大切なアイテムが。
超名盤、初聴き、耳障り・・・こういうものは、それぞれ別の意味で気をとられるために失格。
毎度お馴染みのミュージシャンが、オーソドックスに、軽快にやってくれるジャズ、これがイイ。このゾーンに入るお気に入り盤、世間の評価は大抵3つ星以下だったりするが、生活密着的5つ星、そんな必需品があるんだよね。( あかぎ小次郎さん記)
私も、そうなってから星は別にしてそういうの、認識しましたね。
私の場合、作業の種類によっても、微妙に捗るカテゴリーが違うようです。
梱包作業時、メール連絡時→手の動きが速くなり、キーボード打つのが速くなる、ファブリッジオ・ボッソなどのイタリアン・ハード・バップ
新着商品のHPアップ時→商品紹介の文章が浮かびそうな、軽快でありながら、邪魔にならないピアノトリオ
営業戦略考案時(そんなたいしたもんか?)→何故かボサノバが多いですね。
週末JAZZのブログ記事(このブログ)→アップしている作品(当たり前か?)
商品仕入れ選定時→仕入れようとしている作品(これも当たり前ですね(笑))
売り上げ集計時→少ない売り上げに涙する身をひたすら慰めてくれる白人ボーカル盤(これを聴いている時間がながいのだなあ。)
というわけで、本日は英国のボーカリスト、DAISY CHUTEちゃんに、膝枕してもらって慰めてもらってます。
ジャケ通りの、可憐でキュート、ストレートな歌唱が実にイイです。
と、今日はあまりとやかく言わずに、デイジーちゃんのボーカル聴いてるVENTO AZULであった。
メンバーはDAISY CHUTE(VO)DAVID PATRICK(P)ADAM SORENSON(DS)ANDY SHARKEY(B)
1. I Just Found Out About Love
2. Lazy Afternoon
3. Dindi
4. You Go To My Head
5. Girl Talk
6. Blackberry Winter
7. Too Young To Go Steady
8. If I Were A Bell
9. Little Girl Blue
10. Waltz For Debby
11. Detour Ahead
12. Bill
13. I Like It Here
2005年作品

コネティカット出身のピアニスト、CHRISTIAN SANDSの2002年デビュー作品。
今風の黒人とういか、彼のHPのトップページの姿は、ジャズミュージシャンというより、ヒップホップやクラブ系音楽のミュージシャンという感じです。
それもそのはず、彼はとても若いピアニストなのです。
2006年のグラミー賞の授賞式でピアノを弾いたという記事を読んだのだけど、今年16歳ということだから、このデビュー作録音時は、なんと、12歳ということになる。
天才や神童という称号を、今までに何人もの若きピアニストが与えられてきたけど、(セルジオ・サルバト-レとか最近ではエルダー・ジャンギロフ、オースチン・ペラルタとか)10年後はただのピアニストという例が、ままにある。
そういう称号を与えられるピアニストに比べれば、クリスチャンのピアノは微笑ましいものがあるといえよう。
彼らほどの超絶技巧のテクニックや、早弾きは、クリスチャンのピアノにはない。
ただ、このピアニスト、メロディーのうたわせどころ、聴かせる壺を見事に知っているのだ。
「4月の思い出」や「チュニジアの夜」をこんなに魅力的に弾ける若手ピアニストを私は他に知らない。
この作品の後に、2004年に「HARMONIA」というセカンド作もリリースしているのだけど、確実に進歩したプレイをしていて。デビューした時が一番ピークで、あとが先細りしていくよりも、クリスチァンのように、1作ごとに、成長していく姿がレコーディングに刻まれていくほうがずっとファン冥利に尽きると思うのだ。
最初から老成したというか、完成しすぎた姿を見せられるよりそのほうが追いかけていて楽しいと思うのだけどどうだろうか?
メンバーはCHRISTIAN SANDS(P)JEFF FULLER(B,ELB)JESSE HAMEEN(DS)
2002年作品

この作品、注文してから、入荷するまで約5ヶ月もかかった。
メンバーがDREW GRESSとJEFF BALLARDなので、これは売れそうだと、一度に大量に注文したのがいけなかったみたいなのだ。
在庫が揃うまで発送されなかったものだから、こんなに時間がかかったのです。
ようやく、今日届きました。
STEVE SCHMIDT(スティーブ・シュミット)はシンシナティのピアニストで、地元のクラブやビッグバンドのピアニストとしても活躍しているようです。
シンシナティというと、「シンシナティ・キッド」という賭博場が舞台の映画があったけれども、
この映画の主演男優も同じスティーブだった。
ラストシーンで、マックイーンと少年とのダイムの裏表を賭ける落ちが、いまだに印象的な映画です。
シンシナティというと、そんなイメージしか漠然思い浮かばないのですが、この作品はシンシナティから大都会ニューヨークへ繰り出して、一流のリズムセクションとともに録音した作品でシュミット本人も相当、力を入れて望んだことが推し量れる。
ただ、そこはベテラン、自身の音楽性を見失わず、日頃の自分をありのまま自然に表現しているtころが、若手の初リーダーアルバムなんかと違うところ。
モンク調のリズムフィギュアー、エバンスの叙情性、フレッド・ハーシュの繊細さ、メルドーの先鋭性、ケリー風のグルービーなファンキー節まで繰り出す、引き出しの多い切り口は、わざとらしさやあざとさがなく、ナチュラルである。
DREW GRESS とJEFF BALLARDの二人もさすがに一流、自分の持ち味をだしつつ、素晴らしい協調性をみせ、即席のセッショントリオとは、とても思えないほど。
やはり、一流と呼ばれるようなミュージシャンやシュミットのようにこの道何十年もピアノ一本で食っているような連中は、懐の奥が深いなぁと思うのである。
ライナーは、30年来の親友、フレッド・ハーシュが書いている。
メンバーはSTEVE SCHMIDT(P)DREW GRESS(B)JEFF BALLARD(DS)
1. Monkyside
2. Bon Air
3. For The Music
4. Red And Orange
5. Forgiveness
6. West Coast Blues
7. Anthem
8. I Wish I Knew
9. Lullaby Of The Leaves
10. When I Grow Too Old To Dream
録音は2004年8月2日 NYC

そう言えばこの作品も、未だ紹介していなかったなと思い、本日急に思い立って紹介。
バンド名通り、ジェリー・マリガンのチェット・ベイカーやボブ・ブルックマイヤー時代のサウンドを再現することを目的とした作品です。
こういう作品を取り上げると、そんなんだったらオリジナルのパシフィックのマリガン聴けばいいではないかと思う方がおられよう。
それは、ある意味確かに正解かもしれない。
ただ、逆にそういう方は本当にジャズが好きなのかなとも思ってしまうのだ。
音楽の楽しみ方を知らないのではないかとも言っても過言でないかもしれない。
楽しもうという心、余裕といったものに欠けて、歴史至上主義、俯瞰主義、えてしてこういう方は間違いなく一流志向で、B級作品など実際は目にもかけていないような気がする。
ましてや、C級、D級になると言わずもがな・・・
あのね、その辺の重箱の隅をつつくようなところまで聴いてみて、はじめて名盤の素晴らしさ、そしてある意味人をはねつけるような冷たさというのが分かると思うのですね。
名盤や本に掲載されている作品だけを一生懸命コレクションされている方がいるかもしれないけど、これもそういう方は本当にジャズを好きで聴いているのかなと思ってしまうのだ。
そういう方はきっと真面目な方で勉強している感覚でジャズを聴いているのではないかと思う。
確かに、ある時期集中してジャズのお勉強も、大事といえば大事で、これをせずに自分の気の向くまま好きなものだけを聴いていると、間違いなく偏った音楽嗜好の、ボタンを最初の段階で掛け間違ったジャズファンが形成されるのも紛れもない事実なのですが、いつまでもそういうのじゃこれまた発展性がないのであります。
ちょっと言葉が過ぎたかもしれない。
基本的に各人の趣味の世界なので、何をどういう風に聴こうが全く問題はなくて、好きなように聴けば良いのですよ。
ただ、ジャズの本当の奥深いところ、美味しい部分を骨の髄までしゃぶろうとしたらそれくらいの覚悟で取り掛からないと到達できないという話なのです。
田崎真也が、世界ソムリエコンクールで優勝するまでに、家3軒分のワインを飲んだという逸話がありますが、もし世界ジャズファンコンクールというものがあるとすれば、それに優勝するのにかかるお金は一体どのくらいかかるのだろう?
どちらにしても、莫大な時間と財を費やして真の意味で、道楽を極めることが出来ると思うのです。
最後に作品のメンバーと曲紹介を・・・
Dave Karr: baritone sax
Dave Graf: trombone
Gordy Johnnson: bass
Tanner Taylor: piano
Phil Hey: drums
1. Intro
2. Bweebida Bobbida
3. Intro
4. Line For Lyons
5. Intro
6. Bernie's Tune
7. Intro
8. Walking Shoes
9. Intro
10. Jeru
11. Intro
12. You Took Advantage Of Me
13. Intro
14. I Know, Don't Know How
15. Thank You
16. Wrap Up
17. Django's Castle
2004年作品

現代で活躍している若手ピアニストに欠けるもの、それは親しみやすさだろう。
向こうのほうからこちらに近づいてきてくれ、肩を叩きあい、ハグ、ハグの世界。
カルフォルニア州、ベイエリアで活躍しているピアニスト、デビット・ウドルフはそんなインティメイトな雰囲気を持つピアノ弾き。
渋めの選曲といい、リリカルで繊細なタッチは、誰もがトミー・フラナガンを連想するのではないだろうか?
4曲目はレターメンの歌唱が有名な「涙のくちづけ」、あまりジャズバージョンを聴かない曲だけど、これは良い。
たぶん、誰もが口ずさめるメロディーだろう。
渋いスタンダードナンバーの中に超有名曲を持ってくる匙加減もセンスが良い。
歌手のシェリー・ロバーツと活動を共にすることが多いようだけど、唄伴の上手いところもフラナガンに似ています。
メンバーはDAVID UDOLF(P)CHRIS AMBERGER(B)BOB BRAYE(DS),JAIMEO BROWN(DS)
1. Love You Madly
2. Isn't It a Pity
3. Here's to My Lady
4. Sealed With a Kiss
5. Love Walked In
6. Why Did I Choose You
7. Suddenly It's Spring
8. Change Partners
9. Spring Will Be a Little Late This Year
録音は1999年6月8月 SANTA ROSA,CA

この作品も、昨年の秋頃、入荷していたものだったのですが、未紹介だったようです。
PATRIZIA SCASCITELLIは、イタリア時代にSPLASC(H)やTBCから既にリーダーアルバムをリリースしていますが、NYに移り住んで最初のアルバムが、当作品「CLOSE UP」となります。
リー・コニッツやフランコ・アンブロゼッティらとのアルバムもあってイタリア時代に既に実績を残しているピアニストなのが分かります。
同郷のADA ROVATTIや黒人アルトのマーク・グロスを参加させた三管編成となっています。
いつかミリアム・アルターというベルギーの女流ピアニストの紹介のところでも書いたけど、PATRIZIAもどちらかというと、作曲に特に非凡な才能を発揮するミュージシャンだと思います。
1曲、1曲がカラフルで個性的、このレコーディングセッションに集まったミュージシャンはきっとレコーディングが楽しかったに違いない。
各々の曲解説はしませんが、アーティスティックで創造性豊かな部分とキャッチーでポップテイストを含んだ親しみやすさがバランスよく配合された彼女の楽曲は魅力的です。
8曲目「UPTOWN BOSSA」を耳にしてもらえば、その辺のことは一番手っ取り早く理解していただけるのではないかと思う。
メンバーはPATRIZIA SCASCITELLI(P)JIM SEELEY(FLH,TP)MARK GROSS(AS,SS,CL)ADA ROVATTI(TS)
BOBO BOWEN(B)CARLOS CERVANTES(DS)
録音は2003年6月17,18日 SYSTEM TWO STUDIO, BROOKLYN,NY

トロントの若手ピアニスト、Greg de Denusの2003年デビュー作品。
うららかな午後の柔らかい日差しの中を吹き抜ける風のようなピアノです。
曲調も演奏もパステルタッチの落ち着いた印象の作品なので、一聴した限りでは強いインパクトは残さないかもしれない。
思索的な曲調やそこはかとない叙情性は、研究したジョン・テイラーやフレッド・ハーシュからの影響かもしれない。エンリコっぽいところも少し見受けられる。
グレッグのピアノは、表現の深みやスタイルの確立といった点で、まだまだ先人達に、一歩譲るのかもしれない。
それは認めよう。
しかし、ステップの軽やかな何処にでも行けそうな風通しのよい、グレッグのピアノを聴いていると、エトランゼ気分を味わえるのだ。
この感じ、悪くない。
メンバーはGreg de Denus(p)Brandi Disterheft(b)Sly Juhas(ds)
1. The Searcher
2. Peace at Last
3. Desert Traveller
4. Alter Ego
5. Fog
6. Wise Ones
7. Everything I Love
2003年作品

入荷案内がきて2週間くらいの早さで入荷しました。
この作品のメンバーを見れば、誰でも聴いてみたくなるんじゃないだろうか?
COWBELL MUSICの番人として、今のりにのっているBENJAMIN KOPPELと老いてますます元気なPHIL WOODSのツーアルトに「WHAT HAPPEND!」が超ロングベストセラーなALEX REAL TRIOが合体したクインテット作品となっています。
1曲目の先発ソロはコッペル。
バップをベースとしながら、そこは現代のアルト奏者というか、この人日本の菊地成孔なみに幅広い音楽性の持ち主で、ときおり鋭角的なラインを差し込んで非凡なところを見せつける。
続くウッズは、円熟の極み、貫禄で対応。
但し、二人にバトルモードはなく、リスペクトムードが溢れた「楽しく音楽やろうぜぃ!」モードが満ち溢れているのである。
それししても、ウッズの音の素晴らしさはどうだろう。
特徴のあるフレージング、高音域に駆け上がるときの爽快感、音色のダークネス、ブライトネスの使い分け、音の表情、深さはまさに、それだけで芸術品といえるのではないか?
この年になっても、衰えをみせないクォリティーを維持できるのは、練習もあるのだろうけど、健康面での節制もあるのではないかと思う。
パーカーのように短く刹那的に生きるのも人生だし、ウッズのように、一生かかってビバップを全うするのも素晴らしいジャズマン人生だと思う。
「WAHT HAPPENED!」アレックス・リールのトリオの好サポートによって、この作品がより素晴らしいものになったのは間違いない。
最近では屈指のアルトバトルだと思う。
メンバーは、BENJAMIN KOPPEL(AS)PHIL WOODS(AS)HEINE HANSEN(P)MADS VINDING(B)ALEX RIEL(DS)
2005年6月録音

そういえば、当店で昨年からコンスタントに売れているこの作品を未紹介だったなと思い、本日はこれを取り上げます。
LENNY ROBINSONは1956年ボルチモアで生まれ、現在メリーランドを拠点に活躍している中堅ドラマー。
この作品は、FSNTにリーダー作や、ドナルド・ハリソンとも録音歴がある、ANDREW ADAIRを迎えた
ピアノトリオ作品で、2005年自主制作でリリースされました。
アンドリュー・アデアーがこんなに素晴らしいピアニストだとは、思わなかった。
ヴォーカルもするので、弾き語り系のピアニストなのだろうと思っていたのですが、どうして、どして、ケリー~クラークを基点にモダンジャズピアノを一回りは俯瞰し消化しているとは思うのだけど、この人のピアノの良いところはそれをあからさまにひけらかさないところ。
語り口が平易で、誰もが分かりやすいピアノを弾いてくれている。
ノリの良さと歌心が満載で、グルービーでコクがある。
モダンジャズピアノを聴いたなぁという満足感を間違いなく与えてくれるでしょう。
リーダーの軽いクッションを伴う、50年代風のザックリ感のあるドラミングは、まさにアデアーのピアノとの相性バッチリで、ジャズ喫茶でかかったとすれば、皆がジャケットを見に来るだろう事が想像に難くない。
メンバーはANDREW ADAIR(P)GAVIN FALLOW(B)LENNY ROBINSON(DS,MARIMBA)BOBO BUTTA(P)1曲のみ
1. Close Your Eyes
2. I Didn't Know What Time It Was
3. From This Moment On
4. Easy To Remember
5. Little B's Poem
6. Goodbye Porkpie Hat
7. The Turnaround
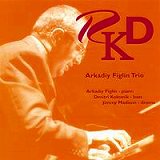
「このCDのスタンダードの解釈にとても感銘を受けた。もっと聴かれるべきピアニストだ。」とホレス・シルバーに言わしめたARKADY FIGLINはロシア生まれ、現在NYで活躍するピアニストです。
クラッシックで培われたテクニックを武器に鍵盤上を縦横無尽に駆け巡る様は、あたかも全盛期のピーターソンのよう。
「枯葉」のイントロにさりげなくバッハを引用したり、ラフマニノフの曲を演奏したりしても、さりげなく演奏されるので、違和感もなく、嫌味がない。
テクニックの為のテクニックという使われ方ではなく、まっすぐストレートにスイングする事を心掛けておりとても好感がもてる。
メンバーはARKADIY FIGLIN(P)DMITRI KOLESNIK(B)JIMMY MADISON(DS)
2001年5月16,17日録音 NYC
1. Somebody loves me
2. I hear a Rhapsody
3. Autumn leaves
4. You stepped out of a dream
5. Clair de Lune(Moonlight) in Vermont
6. Who knows
7. No mercy
8. Lilacs
9. RKD

DUCKSTEP TRIOが、今朝入荷したので、こちらのブログ(訪問者が「店長日記」は少ないもので)でも重複しますが、紹介。
Luca Marianini(tp) Giovanni Belli(g)Graziano Brufani(b)の3人からなるイタリアの変わった編成のトリオなのだけど、この楽器の編成というと最近ではSWEET JAZZ TRIOが有名だけど、このトリオは、チェット・ベイカー・トリビュートとでもいうCRISSCROSSに録音のあるCatherine/Harrell/Van De GeynやVERVEのハービー・ハンコック集McBride/Payton/Whitfield にインスパイアされて結成されたトリオらしい。
1. Driftin
2. Duckstep
3. I Remember you
4. Love For Sale
5. Melody For Cristina
6. Une Belle Histoire
7. Jo For Wes
8. Funk In Deep Breeze
9. Kika
6曲目を聴いた時、どこかで聴いたような旋律だなぁと思い、メロディーを頭の中で反芻していると、思いだした。
ミスターサマータイム ♪♪♪・・・・
サーカスの大ヒット曲をそれこそ、ニースか、リビエラか、夏の打ち寄せる波の海岸べりの向こう側の地平線上に夕陽が沈んでいくのが見えるような・・・そんな情景が思わずとも浮かんでくるような、実に壺にはまった演奏を繰り広げているのです。
この1曲で仕入れ決定でしたね。
他の曲も結構いい感じで、ちょっとこれはお薦めですよ!
SWEET JAZZ TRIOをお気に入りのかたには、120%お薦め致します。
メンバーはLuca Marianini(tp) Giovanni Belli(g)Graziano Brufani(b)
2006年作品

こうやってCD屋やっていると、売れる作品と売れない作品の落差の激しいことに、改めて実感いたします。(なんの業種でも一緒だろうけど)
注文が集中するものと目にもかけられないものとの差は本当に激しい。
今日取り上げる、カルビン・ヒル盤は後者の良い例で、なんと開店の時に仕入れたものが未だに1枚も売れていないのです。
試聴してみて良かったのでオーダーしたのだけど、見事に当てが外れた実例。
よくよく考えれば、売れない原因が分かる。
ジャケットが貧弱で、目を惹かないし、ジャズで最も大切なメンバーもクレジットされていないのである。
これでは、誰も買わないだろう。
アメリカのディーラーのキャプションにもメンバーの表記がなかった。
カルビン・ヒルが、地味なベーシストなのだけど、この作品実は共演ミュージシャンが粒よりのメンバーなのです。
MICHAEL COCHRANE(P),YURON ISRAEL(DS).JOE LOCKE(VIB)
マイケル・コクレーン、昔から個人的に愛聴しているピアニストで、うまいプレーヤーではないのだけれど、フレーズのひとつひとつが本当に唄っている、分かりやすい口ずさめるようなフレーズを弾くアジのあるピアニストだと思います。
MJQが、NYのカーライルホテル(実際に出演していた)のラウンジのように、落ち着きのある洗練されたイメージに対し、このカルテットのサウンドはもっと親しみのある気軽に立ち入ることの出来るダウンタウンのレストランバーのような感じですね。
スタイリッシュに飛ばすジョー・ロックのビブラフォンとコクレーンの旨口仕立てのコクのあるピアノが好対照をなしていて悪くないです。
MJQのような個性を確立しているかというと正直なところ首を振らざるをえないのだけど。あくまでもレコーディングのために集ったメンバーなので、バンドとて、ユニットとしての個性を求めるのは酷というべきか。
とにかく、素通りするには惜しい、好内容のセッションが記録されています。
1. I Fall In Love Too Easily
2. Falling in Love with Love
3. I've Never Been in LOve Before
4. All the Things You Are
5. Beautiful Love
6. Hymn A L'Amour
7. What is This Thing Called Love
8. I Can't Give You Anything But Love
9. When I Fall in Love
2005年作品

昨年のちょうど梅雨が明けたころだったと思う。
久しぶりに行きつけのライブハウスに足を運んだ時に、偶然、当アルバムのシーナきのはらのヴァイオリンを聴いたのです。
その日はあいにく、清水さんがお休みで、若い女性のピアノトリオの演奏だった。
今から思うにプロモーションかなにかで、来広していたのだと思うのだけど、飛び入りで数曲演奏を聴くことができたのだ。
このアルバムに収録されている「ダークアイズ」と「リベルタンゴ」を確か演奏したと思う。
3曲目は、何かリクエストをということで、一番前に座っていた私はすかさず「夜は千の眼をもつ」をリクエスト。
ゲストでの飛び入りだったので約20分くらいの短い演奏だったけれども、充実した演奏で、素晴らしいジャズバイオリニストを発見したとその時胸の中で思った。
その時に、この作品を自主制作したことも知ったのですが、あいにく持ち合わせがなく、その時入手できず、後ろ髪ひかれる思いだったのです。
今回、思い立って本人に連絡。
快く卸売りを承諾くださり、ここに販売できるようになりました。
シーナきのはらのバイオリンは、まるでボーカリストが唄うように、本人の肉声が聴こえてくる。曲テーマのメロディーはもちろん、アドリブで速いフレーズになっても、決してフレーズが走らずに、一音一音が唄っているように聴き取れるのだ。
このアルバム、メンバーが実は凄いのだ。
田中武久(P)安ヵ川大樹(B)大坂昌彦(DS)
彼女のジャズ演奏において田中は、師匠的存在であり、このアルバムでも、まばゆいばかりのピアノを聴かせてくれている。
全曲聞き物だけれども、個人的には「ZINGARO」「DETOUR AHEAD」「LIBERTANGO」が気に入っている。
日本人のジャズバイオリンの演奏って、一般的には寺井尚子しか思い浮かばないと思うのだけど、どうしてどうして、それに勝るとも劣らない素晴らしいジャズバイオリストだと思う。
メンバーはシーナきのはら(VLN)田中武久(P)安ヵ川大樹(B)大坂昌彦(DS)
2005年5月12,13日

このアルバム、入荷案内は3月にあって、当初は4月末くらいに入荷の予定だったのだけど、諸事情により遅れに遅れ、初回分が6月末にようやく入荷。
初回の数を誤り、少量すぎて(実はもう入荷しないのかとなかば諦めていた?途中追加もせず。)
予約分だけで完売状態。
入荷と同時に確かめると、ひと月後に入荷予定ありとのこと。
すぐに、追加オーダーを致しました。
「出た時から名盤の仲間入り」とは、ヘルゲ・リエン新作発売時のディスクユニオンの山本さんの言葉だけど、それは、この作品にもあてはまる。
すでに、吉祥寺方面では大絶賛の渦に店内が満ち溢れたというではないか!
まだ、手にいれていない方は見つけたら、躊躇なく手にとってレジに足を運ぶことをお薦めする。
フランスのピアニスト、SERGIO GRUZがアルゼンチンのレーベルMDRからリリースした作品。
まさに、「南米のパリ」的作品だ思う。
こちらまでの距離感が絶妙というか、ハッとするほど美しくスウィートなフレーズを奏でたかと思うと、次の瞬間、手元からするっと抜け落ちて、予想しない展開へ移行する。
離れていったと思えば、再び戻ってきてこの上ない優しいフレーズを発する。
その繰り返し、繰り返し。
まさに、絶妙な匙加減というべき、語り口。
愛のフランス的デカダンスと南米のラテン的情熱が、巧みに交錯した独創的な作品です。
まだ、鑑賞してから日が浅いのだけど、日が経つにつれこの作品にはまっていく自分がいる。
たぶん、今日より、明日、明日よりあさってのほうがより深く愛聴しているだろう。
気のせいだろうか?
作品からはブエノスアイレスの街の乾いた空気感まで漂ってくるような気がする。
メンバーはSERGIO GRUZ(P)JUAN SEBASTIAN JIMENEZ(B)ANTOINE BANVILLE(DS)
2004年作品

ポール・モチアンのECMにつぐ、今年2作目のリリースとなる作品。
オン・ブロードウェイ・シリーズの4作目。
TRIO2000(モチアン、C・ポッター、L・グラナディアー)+ONEのもので、今回ONEに当たる存在は、菊池雅章とレベッカ・マーティンにあたる。
モチアンのこのプロジェクトは、文字通り、グレート・アメリカン・ソング(ブロードウェイ・ソングス)に光を当て、現代の時代にもう一度彼らなりの解釈で再提示することが趣旨だと思われるのだが、あまり難しく考える必要は無いのではないかと思う。
要は、歌にスポットを当て、メロディーにフォーカスを絞り込んでいると考えればよいのだと思う。
だから、ここでは皆が歌うことに最も重きを置いている。
クリス・ポッターのこんなに、オーソドックスで落ち着いたプレイも他のアルバムではそう聴けるものではないのではないかな。
高音部では、マーク・ターナー経由のウォーン・マーシュの間接的影響も見受けられ、クールな演奏をみせてくれています。
そう、ここでは皆クール。
モチアンもプーさんも(唸り声は聞かれますが・・・)・・・。
レベッカ・マーティンのひんやり冷気を含んだ清涼系ボイスにポッターがオブリガードつける場面など、思わず聞き惚れてしまいます。
もちろん、50年代のアルバムとは、匂いと質感が全く異なる。
何故なのかその違いについて考えているのだけど、直ぐに上手い答えがでてこない。
立っているプラットホームが違うというか、モチアン達が50年代までの歌の時代に対し、止揚された世界を構築しようとしているように思えてならないのだけど、上手く言葉が出てこない。
こんな、考え事しなくとも、ひたすら聴くだけで充分魅力的なアルバムでもあります。
メンバーはPAUL MOTIAN(DS)CHRIS POTTER(TS)LARRT GRENADIER(B)REBECCA MARTIN(VO)MASABUMI KIKUCHI(P)
録音は2005年11月21-23日 AVATAR STUDIO , NYC

NYで活躍しているギタリストJAY AZZOLINAの2002年作品。
GARY VERSACEのB-3オルガンが参加したオルガントリオです。
ジェイ・アゾリーナは、スパイロジャイラやハービー・シュワルツのバンドのメンバーでもあっただけに、オーソドックスなジャズからフュージョンを経たとてもヴァーサイタルなスタイルの持ち主のようです。
今までにレコーディング、共演したミュージシャンの名前を列記してもそのことが分かります。
Dave Samuels, Kenny Werner, Fred Hersch, Jeff Beal, David Mann, Ron McClure, Herbie Mann, Chuck Mangione, Jerry Bergonzi, Marc Copeland Michael Franks, Donna Summer, The Manhattan Transfer, Carly Simon and Rickie Lee Jonesなどなど。
1曲目など、一頃のジョンスコを曲調、演奏とも連想させるところがあって、クールで決まっている演奏です。
オルガンのゲイリー・ヴェルサーチ、アダム・ナスバウムとのトリオの一体感も出ていて、ジミー・スミスやラリー・ヤングのオルガントリオとは、全然違うサウンドが鳴っている。
ジョンスコとラリー・ゴールディングスが一緒に演ったアルバムに一番似ているしれない。
とにかく、テクニックとか新しさより、バンドとしての風通しのよい表現は、オーソドックスな4ビートジャズからモードジャズ、ロック、ブルース、C&W,ファンクを包括したその自然で、どれが突出するでないオールラウンドな音楽性はやはり70年以降のフュージョンをリアル体験したギタリストならではのものと思われる。
ライブ作品なのだけど、実際こんな演奏目の当たりにしたらゴキゲンで、さぞビールの消費量が上がるだろうなぁ。
メンバーはJAY AZZOLINA(G)GARY VERSACE(ORG)ADAM NUSSBAUM(DS)
2001年12月21日 ONE STATION PLAZA, NY

プエルトリコの若手ベーシスト、RAMON VAZQUEZ(レイモン・ヴァスケス)の2004年デビュー作品。
一曲目がなんせ、トリスターノの「エイプリル」ときたもんだ。
モンクにエリントン、エグベルト・ギスモンティとくれば、アンテナがひくひくとなり、早速取り寄せてみた。
スピード感があって、カラフルなラテンテイストのジャズが演じられているのであるが、この風通しのよさは何なのだろう?
フットワークが軽いというか、軽薄な意味でのライト感覚ではなくて、ジャズの通史、伝統を重んじた上でのそういったわだかまり、こだわりといったものを一旦横に置いて、自分の内側から滲み出る音楽感性を、ナチュラルに表現していると思うのだ。
力みがないので、サウンドに勢いがあるし、どこにでもいけそうな身の軽さが心地よい。
スポーツに興じた後のシャワーのような爽快感があるジャズ。
メンバーは、1曲だけ参加のアレックス・アカーニャを除けば、皆、無名で強烈な個性の持ち主はいないけれど、このサウンド、面白い。
ヴァスケスは、アコースティック、エレキの両方のベースを弾いているが、どちらに比重がかかっているという感じがなくて、同等の位置付けになっているように感じる。
最近ではそういうベーシストが増えているのかもしれないが、ヴァスケスは楽器においても音楽観と同じくイーブンな立場をもっているベーシストのような気がする。
メンバーはRAMMON VAZQUEZ(B,ELB)ALEJANDRO AVILES(AS)JOSE ENCARNACION(SAX)HENRY COLE(DS)HECTOR MATOS(DS)ALEX ACUNA(DS)YAN CAROS ARTIME(P)AMUNI NACER(KEY)PAOLI MEJIAS(CONGA)EDDIE WAKES(VO)PAOLA VAZQUES(VLN)CANDIDO REYES,RAYMON RIOS8G)JOCHY RODRIGUEZ(TP)曲によって異なる。
2004年作品

AMANDA BEISINGERはCA,サンタクルーズ生まれ、現在NYで活躍しているボーカリスト。
ジャズをベースにしたフォーキーで涼しげな歌声は聴いているとこちらの気分も本当に和んできます。
ジョニ・ミッチェル系というかノラ・ジョーンズ系というか正統派のジャズボーカルでは全くないのだけど、この声と歌は私好み。(いつも言っていますが、ボーカルに関しては客観的視点全くなしの100%個人的好みで書いているし、聴いています。)
私事なのだけど、この一月何かと気ぜわしい日々が続き、目は充血、慢性的寝不足の日々が続き、ストレスを背中にしっかりと溜めこんでいる今日この頃なのでございますが、彼女のような天然癒し系、清涼ウィスパーボイスを聴くと、ほっとします。
6曲入りのミニアルバムで、20数分という時間も、丁度良いです。
この2,3日、休憩中にずっと流している。
ア-ロン・パークスがピアノを弾いている事も特筆できよう。
彼のトリオとアコースティックギターから生み出されるサウンドもアマンダの唄にとてもマッチしています。
1. These Days
2. By Your Side
3. Far Away
4. Welcome Sunrise
5. Up On The Roof
6. Every Time We Say Goodbye
全部良いのだけど、個人的には3と4と6が最も気に入っている。
夜の帳が降りてきた頃、戸外で気持ちの良い風に吹かれているような気分。
メンバーはAMANDA BAISINGER(VO)AARON PARKS(P)LIETH GANZ(G)PETER SLAVOV(B)KENDRICK SCOTT(DS)
2005年作品

チュニジア出身のピアニスト、WAJDI CHERIFの2003年作品で、パーカッションが参加したほぼピアノトリオの作品といってもよいと思う。
私自身、彼の名前を聞くのもはじめてであったし、チュニジアというと、文字通り「チュニジアの夜」に馴染みがあるくらいで、今までのジャズ人生でまったくといってよいくらい接点がなかった国であります。
日本では全く無名だけれども海外では、結構名が知られているらしく、2005年には最新作「JASMINE」の1曲目が国際作曲コンペ(82ヶ国から15000曲がエントリー)で賞を受賞したらしい。ソニー・ロリンズやジョン・スコフィールド、トム・ウェイツらが審査員を努めた。
パリのジャズクラブ「SUNSIDE」にも定期出演しているようです。
1曲目の出だしの旋律こそ、アフリカというよりもむしろ、中近東あたりのオリエンタルな雰囲気を感じるメロディーなのですが、アドリブ自体はグイグイと引っ張っていく、力強い推進力を感じるもので、楽曲の独創性と並んで、プレイ自体もテクニシャンではないけれども、響きを大切にするユニークなピアニストだと思う。
ダラー・ブランドを初めて聴いた時のように、既存のピアニストのスタイルに当てはめることが困難な今まで聴いたことのないタイプで、そのあたりがとても新鮮であり、オリジナルなものを感じます。
抒情的なイントロから快適な4ビートでスイングする4曲目「WATING FOR PARIS」は、このアルバム、一押しの演奏です。
正統派のピアノトリオからも、絶賛されるのではないかと思います。
独創性の強いエスニック風味の効いたワールドジャズと正統派ピアノトリオ演奏を上手くバランスをとっていけば、より認知度が高まり、注目されるのではないかと思う。
一度、耳にしてみて欲しいチュニジアのピアニストです。
メンバーはWAJDI CHERIF(P)HABIB SAMADI(PER)JEFF BOUDREAU(B)DIEGO IMBERT(B)
2002年10月22日録音

ENRICO PIERANUNZUIの新作が出るとの報を、聞いてそのタイトルが「BALLADS」というタイトルだと知って、過去のアルバムのコンピレーションではないかと思い、直ぐに問い合わせしたのですが、中々内容の中身が分からずに入荷までやきもきしていた一枚。
幸い、心配は危惧に終わってなにより。
全編、新録の作品です。
エンリコには、よく言われることだけど、三つの側目がある。
1.抒情の人、この世のものとは思えないほど美しく耽美性を感じるほどのメロディーの洪水、ロマン派の側面、
2.ジャズメンとして卓越した技量によるインプロバイザーとしてのスペシャリストである面、
3.メロディストとしての反動の部分か、フリーインプロヴィゼーションを探求する側面。
この3つの特性それぞれがエンリコの音楽として消化されており、そのどれもが魅力的であり、表裏一体となっている。
アルバムによって、その匙加減が微妙に異なっており、違いを楽しむのがエンリコの正しい鑑賞法かもしれません。
このアルバムは、タイトル通りバラード演奏ばかりを集めた作品なので、最初に挙げたエンリコの特質が色濃くでたものなのは、間違いないです。
さすがは、エンリコ、バラードばかり演奏しても深いです。
個人的ベストは8曲目「NIGHT AFTER NIGHT」。
極上のシャンパンを開けた時のような気分を味わえる一品だと思う。
メンバーはENRICO PIERANUNZI(P)MARC JOHNSON(B)JOEY BARON(DS)
録音は2004年6月17,18日 ROME
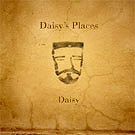
しばらく前にMOSEROBIEから、リリースされたDAISYというサックストリオの2005年作品。
MOSEROBIEやJAZZAWAY,TUM REORDSといったあたりの新興レーベルは北欧の新しいジャズシーンをリアルに映し出してくれていて、興味がつきない。
同じ北欧のJAZZAWAYからリリースされている、TRINITYやSHAGMA MUSICなどのサックストリオに比べれば、轟音度は低いので、一聴おとなしい印象を受けるかもしれないが、聴き進めるにしたがって、メラメラと青白い炎が燃え上がってくるかのように、演奏は次第に熱気を帯びたものになっていきます。
もちろん、60年代の黒人フリー系の激情サウンドではないし、先にも述べたように轟音、爆音系サックストリオではなく、どちらかというとリズムセクション含めて(実際のライブではまた違うのかもしれないが)スタイリッシュな表現をめざしている印象を受ける。
一曲目など、牧歌的なおおらかなイメージを感じさせ、直情的なサウンドを志向しているグループではどうやらなさそうなので、そういう彼らの音楽性をどう感じるかのよって評価が分かれるかもしれない。
曲によっては、オーネットやコルトレーンの曲っぽいものがあって、それを直情的に表現するのではなく、ある種の軽やかさでもって演奏しているように聴こえる。
重くはないのであります。
このあたり、意外と現代北欧系ジャズの特徴のひとつに、挙げられるかもしれない。
メンバーはJOAKIM ROLANDSON(SAX)THOMMY LARSSON (DS)PETER JANSON(B)
2005年9月17,18日録音

フランスからまた、新人ピアニストのピアノトリオ作品がリリースされた。
ドラムがダニエル・ユメールだし、卸元のキャプションでもとても高く評価されていたので、実際の音を聴くのが楽しみだった一枚です。
過去にフランスの若手中堅ピアニストというと、マニュエル・ロシュマンやフランク・アヴィタビレ、バプティステ・トラティニオンら優秀でテクニシャンという印象が強いのだけど、このGABRIEL ZUFFEREY(ガブリエル・ザフェリー)もその系譜を継承しているピアニストの感が高い。
このピアニスト、ただ闇雲に鍵盤高速弾きのテクニックひけらかしタイプのピアニストではない。
精巧なガラス工芸品が繊細で、様々な輝きを放つのに似て、この新人ピアニストの指からも色々な光が解き放たれる。
幅広い音楽性も持ち合わせているようで、間口の広い奏法とともに、今後一番掘り下げていくところ、つまりこれぞ、GABRIEL ZUFFEREYという個性を体得すれば、先の先輩を追い抜いて、ぺトルチアーニ級の存在になる可能性を秘めた人材とみた。
それにしても、ユメール翁のドラムといったら・・・
オールラウンドでありながら、自身の作品ではハイブロウな作品をリリースする老いてますます多岐にわたる幅広い音楽活動は、もっと注目されても良いと思います。
誰か、ユメールのグループの作品を録音してくれないだろうか?
今、この人と平井庸一のレコーディングを最も切望します。
あっー、ボッサではソニア・ローザね!
脱線、脱線!
今作品は3年前のものなので、現在はもっと成長した凄いピアノが聴けるのではないかと思う。
ZUFFEREYの新録も早くすべしなのは云うまでもない。
メンバーはGABRIELK ZUFFEREY(P)SEBASTIEN BOISSEAU(B)DANIEL HUMAIR(DS)
2003年9月録音

フランスのテナー奏者STEPHANE SPIRAのデビュー作ワンホーンアルバム。
ピアノはOLIVER HUTMAN,ベースはGILLES NATUREL,ゲストにSTEPAHNE BELMONNDOが参加して3曲はクインテット編成で演奏されています。
リーダーのSTEPHANE SPIRAは、決して派手なプレイヤーではなくて、テクニカルなフレーズもあまり用いず、サウンド重視型のサックスプレイヤーと言えるかもしれない。
OLIVER HUTMANの抒情感溢れるピアノとの相性も抜群で、ヨーロッパ古城のほとり的なロマンを形成しているといえます。
EGEAレーベルの最もジャズ寄りの作品を聴いている感じをイメージしてもらえば、一番わかり易いだろうか?
一聴、派手さのない演奏なので、良さが分かりにくいかもしれないですが、二度、三度聴き返すうちにすっかり、はまっている自分がいるのに気付くといった仕掛け。
魅力的なオリジナルにはさまれるジミー・ロウルズ「ピーコックス」アントニオ・カルロス・ジョビン「LUIZA」も渋いです。
大人の国、フランスだからこそ、生まれるストレートアヘッドな渋いジャズだと思う。
メンバーはSTEPHANE SPIRA(TS,SS)OLIVIER HUTMAN(P)PHILIPPE SOIRAT(DS)GILLES NATUREL(B)STEPHANE BELMONDO(FLH)
2004年12月録音

オランダの中堅ピアニスト、COR BAKKERの2005年トリオ作品。
2曲目のショパンのプレリュード(アスペクト・イン・ジャズのテーマで知られる有名なアレです。)など、聴いていると高級ホテルの貴賓室かどこかで、午後のひと時紅茶なんぞを頂きながら一人過ごしているような、普段の自分の生活とはおよそ場違いな場面を想像してしまいがちですが、この雰囲気決して悪くないぞ。
ジャズにスリルや昂揚を求める方には間違ってもお薦めしないけど、たまにはこういうジャズにも耳をかたむけて欲しいと思います。
難しいのばかり聴いているといつか、煮詰まってしまうから・・・
実際、イージーリスニングジャズの要素が、強いことは否めない。
アドリブらしいアドリブはほとんどとらずに、テーマを凌駕するようなフェイクっぽいフレーズどまりの演奏が多いのですが、音楽として素晴らしいのでそんなことは、取るに足らない事だと思います。
だからどうしたと、開き直りたいですね。
こんなに、美しくピアノを奏でるピアニストもそうざらにはいないと思うのです。
このアルバムは、メロディーの宝石箱として、コレクションに加える価値が充分あると思います。
リラックスしたい時、心の平静を保ちたい時、今で言うチルアウトしたい時などには、最高の一枚になるのではないかと思います。
Cor Bakker - Piano
Edwin Corzilius - Bass
Frits Landesbergen - Drums
Jeroen de Rijk - Percussion
01 Angel Smile (3:56)
02 Prelude Opus 28 no 4 (5:03)
03 Adios Nonino (4:58)
04 Adagio (4:15)
05 Velas (4:06)
06 The Final Question (2:18)
07 Message In A Bottle (5:13)
09 Hard To Say Goodbey (6:10)
10 Prelude Opus 28 no 20 (3:40)
11 Giga (3:45)
12 Esther (5:09)
13 Contemplation (4:32)
2005年 AMSTERDAM 録音
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪12/23『日経エンタテイン…
- (2024-11-26 13:07:15)
-
-
-

- オーディオ機器について
- SAEC SLA-500 LANケーブル
- (2024-11-25 00:00:16)
-
-
-
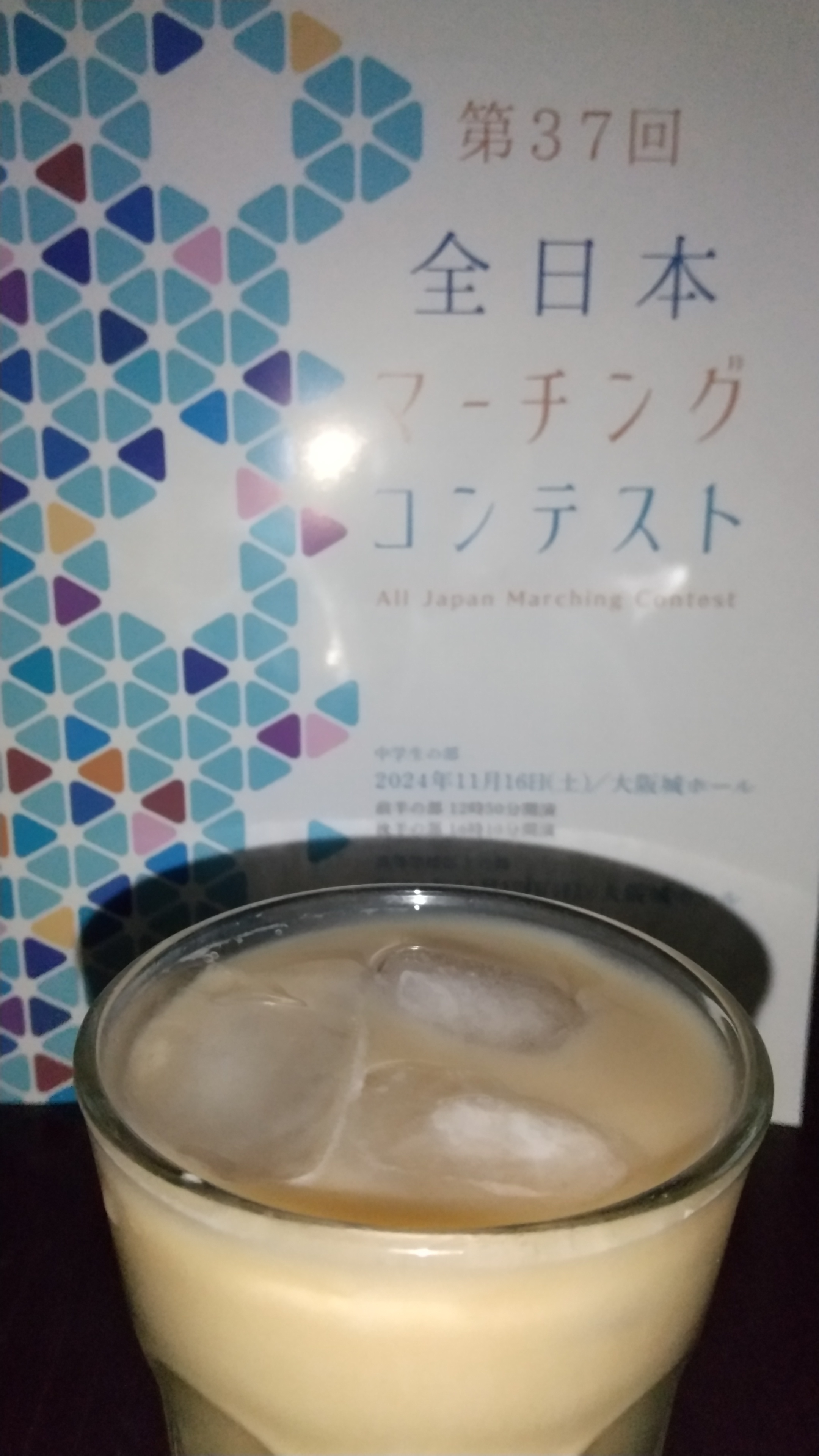
- 吹奏楽
- マーチング全国大会 金賞
- (2024-11-25 06:27:11)
-
© Rakuten Group, Inc.