2025年06月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

ザ・ウィンザーホテル洞爺(北海道)
2008年に洞爺湖サミットの会場になったザ・ウィンザーホテル洞爺。当時の首相は福田康夫さん。先進諸国にロシアとEUを加え、サルコジ大統領(仏)、ブッシュ大統領(米)、ブラウン首相(英)、メルケル首相(独)、ベルルスコーニ首相(伊)、ハーパー首相(加)、メドベージェフ大統領(露)、バローゾ委員長(EU)がこの地を訪れた。その時の報道を見て以来、一度は行きたいと思っていた場所に今回ようやく行くことができた。本当は、行きたい、よりも、泊まりたい、と思っていたこのホテル。今回は日程の都合上(本当に…)ランチに立ち寄っただけだったけど、とりあえずの念願は叶った。ホテル地下の駐車場に車を停め、ロビーに上がると大きな窓ガラスを通して洞爺湖が一望にできた。ホテルの高級感は期待通り。ウェブサイトの写真と違ってちょっと…なんてことはまったく感じなかった。写真は載せていないが、今回のランチはホテル内のレストラン「ギリガンズアイランド」にて。洞爺湖の絶景を見下ろしながら贅沢な時間を過ごした。
June 30, 2025
コメント(0)
-

仙台の旧町名「南染師町」(今も南染師町。一部は若林区文化町)
広瀬川から水をひく七郷堀に沿って東西に延びる染物職人の町「南染師町」(みなみそめしまち)。歩いてみると、当時から伝わる染物屋さんを堀沿いに2軒見つけた。(越後屋染物店)※この建物は2025年1月頃解体。解体直前までこの建物はきれいに維持されていた。(永勘染工場)※この日は日曜日。シャッターはおりていたが看板に歴史を感じた。藩政時代からの町名「南染師町(みなみそめしまち)」は、その一部が昭和42年の住居表示で文化町に変わっているが、東西に長い町の多くの部分は、今も仙台市若林区南染師町を住所としている。(七郷堀。フェンスがあって今は人が立ち入れない。この堀の両側が南染師町になっていて、突き当りに見えるのは東北新幹線とJR東北線の線路。南染師町は堀沿いに線路の向こう側まで続いている)辻標57番「南石切町/南染師町」には、次の記載がある。【南染師町】・伊達氏に従って仙台に移り越路に住んでいた染師職人が、寛永13年(1636)の政宗公墓所造営にあたりここへ移された。・城下町方二十四町のひとつで、伊達御供を誇る六軒を中心として七郷堀を利用しながら需要の多い木綿染を独占的に扱って栄えた。・京都から分霊された愛染明王は染師たちから厚く信仰されてきた。仙台市HP「町名に見る城下町」は、南染師町を次のように説明している。・南材木町の東に位置する、七郷堀沿いの町。文字どおり、染師たちの住んだ町である。若林染師町ともいわれた。・米沢から岩出山を経て仙台につき従ってきた伊達家お抱えの染師たちは越路(いまの霊屋下)に住んでいたが、寛永13年(1636)の政宗の死去にともなう瑞鳳殿造営のため、この地に移された。・藩政時代には職人の屋敷の間口は6間と定められていたが、染師町では干し場が必要なため半間広い6間半だった。七郷堀の水を使った染め物は質が高かったという。・藩政時代、仙台の染師町は2カ所あり、もうひとつは北目町と田町の間にあって上(北)染師町と呼ばれた。対照的な歴史を持ち、上染師町が主に上級武士を相手に絹物を扱い藩の御用を勤めたのに対し、南染師町は木綿が主で足軽の脚絆の需要に応え、大町の商人の染物も独占して扱った。・上染師町が明治以後は藩の保護を失い衰退したのにくらべ、南染師町でははいまも染物屋が仕事を続けている。また、染師たちの信仰を集めた愛染明王がいまも祀られている。(愛染明王堂)
June 25, 2025
コメント(0)
-

映画「国宝」【感想】
おそらく素でも顔立ちの美しい2人の俳優、吉沢亮と横浜流星が歌舞伎の女形を競演していた。映画「国宝」3時間を超える大作を週末の午前、映画館の大スクリーンで堪能した。劇場、舞台、観客席、そして所作。美しい映像の連続で、これぞ映画館で観るべき映画だと思った。『任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる、主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。』(公式ウェブサイトより)世襲こそが伝統を受け継ぐ本道とされ、血筋が重んじられる歌舞伎の世界に、暴力団の組長を父に持つ少年、喜久雄(黒川想矢→吉沢亮)が身を置くことになる。厳しい修行により喜久雄の才能は見事に開花していった一方で、歌舞伎界では邪道とされる出自であることにも苦しめられ続ける。それでも喜久雄はひたすら女形を演じ続けた。場所も厭わず。そしてそれ以外のあらゆるものを犠牲にして。映像は常に美しく、ストーリーは常に重い、そんな映画だった。けれど、重いながらもテンポ良くストーリーは展開し、観ている自分の重苦しい気持ちは、場面転換に度々救われた。渡辺謙と田中泯はもちろん、豪華な俳優陣が主役2人の演技を引き立たせていた。繰り返しになるが、映像の美しさは圧倒的だった。監督は李相日さん。以前「フラガール」を観たことを覚えているが、李相日監督の印象は「国宝」を観て新たになった。本当に美しい映画だった。李さんの作品をまた観てみたいと思った。
June 20, 2025
コメント(0)
-
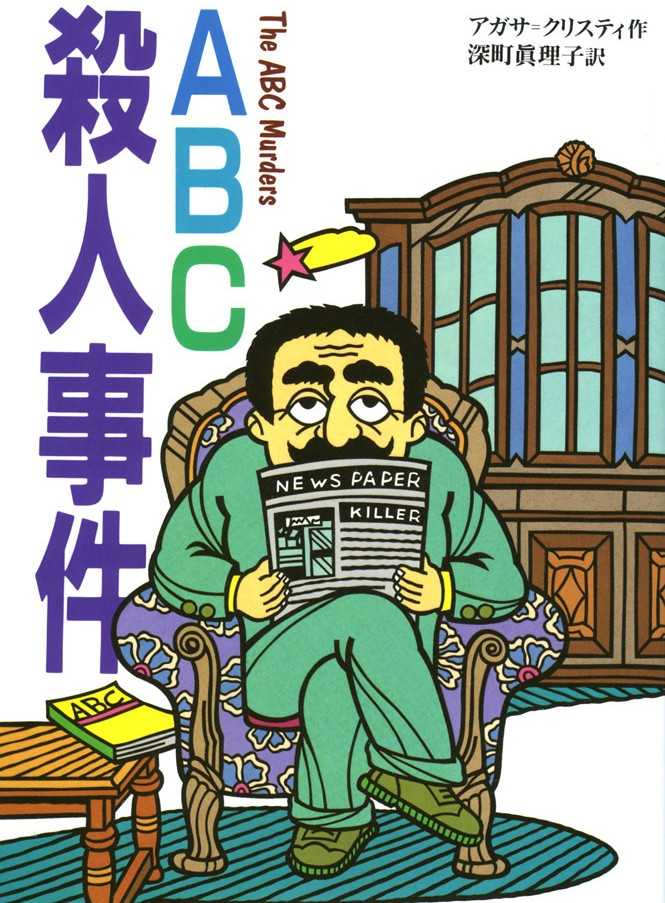
「ABC殺人事件」アガサ・クリスティ作 深町眞理子訳(偕成社文庫)
年度の変り目は、なぜか毎日落ち着かなくて、なんか嫌だ。急に忙しくなったと言うほど慌ただしくはないし、逆にやることがなくなって慌てているわけでもない。なのになぜ…。理由はおそらく…素の自分ではない自分でいる時間、作った自分で他人と接している時間が長いからではないか…。自分の中に自分がいないまま生きている時間が長いからではなかろうか…。そんな自己診断をしてみた。年度替わりはどうしても初めて行く場所や初めて会う人、初めてする仕事が多いから、必要以上に周囲を気遣うことは仕方がないとも思うし、この程度の経験はこれまで何度もしてきた気もする(忘れたけど…)でも、なんか嫌だ。そこで、少しムリしても自分だけの時間をつくってやろうと思った。だけど自分だけの時間とはなんだ…?よくわからないけど、とりあえず誰にも邪魔されない静かな空間に身を置いて、しばし本を読んでみることにした。本は難しいものではなくて、上質なエンターテイメントが良いと思った。家の中を探して見つけたのがアガサ・クリスティの「ABC殺人事件」。子供部屋で見つけた古い本なので、子供向けの本なのだけど、きっと内容は大人向けと変わらないのではないか、と思いながら読んだ。振り仮名が振ってあるくらいの違いかな…と。読み始めてすぐに、ポアロをはじめ登場人物たちの気の利いた言い回しに魅了された。アガサ・クリスティの作品を読むのは今回が初めてだと思う。今さらながら、もっと読みたいと思った。面白かった。
June 16, 2025
コメント(0)
-

昭和新山(北海道有珠郡壮瞥町)
僕にとっての昭和の大横綱は、北の湖関。同時代の横綱、輪島の人気が高かったことと、北の湖が憎らしいほど強かったこともあって、「北の湖が好き」と言うと「へぇ~…」と意外そうに返されることが多かった。たけど強い北の湖はカッコよかった。その北の湖関の生まれ故郷、壮瞥町(そうべつちょう)にある昭和新山にほぼ20年ぶりに行った。山のふもとにある駐車場の料金は普通車が1日500円。近くにはクマ牧場や有珠山ロープウェイがあった。20年前と比べると、お土産屋さんが立ち並ぶ場所が、昭和新山のふもとから、ロープウェイ・クマ牧場の近くに移動していたように思えたけど、相変わらず賑やかな観光地だった。そして今回は外国人観光客の姿がとても多かった。20年前も今回も、家族と一緒に行ったので、昔の写真を見ながら同じ場所を探して、同じポーズで写真を撮ってみたりした。写真を見比べると、昭和新山の看板は新しくなっていて、僕たち家族は20年分成長していて、まぁ…これはしょうがない…と思った。自分の《成長》はさておき、子どもの成長は心底ありがたいし、成長した子どもと一緒にまた昭和新山に来られたことにはとても感謝している。
June 11, 2025
コメント(0)
-
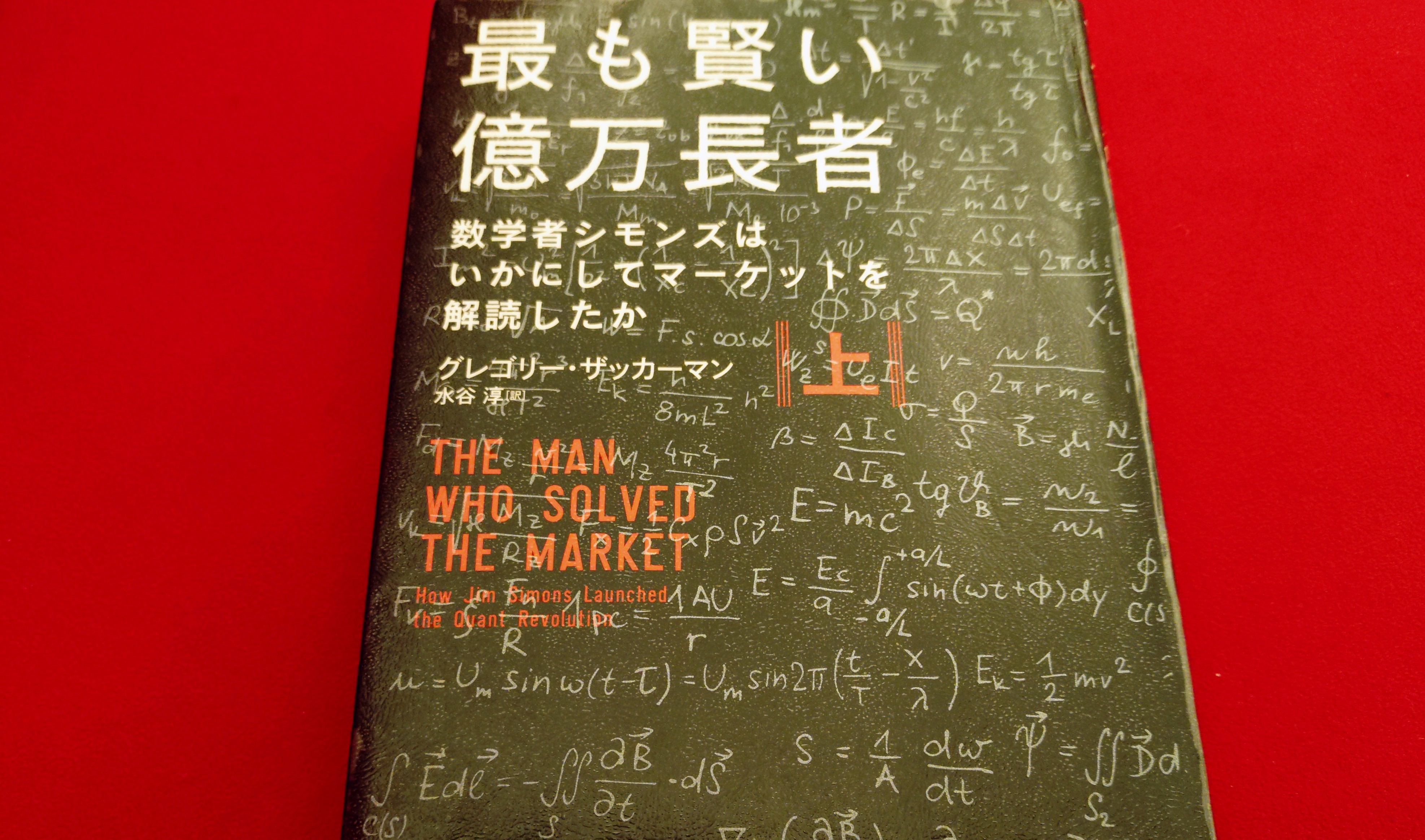
「最も賢い億万長者-数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したか-(上)」グレゴリー・ザッカーマン著(ダイヤモンド社)
原題は「The man who solved the market - How Jim Simons launched the Quant Revolution-」。2019年に出版され、日本語版は水谷淳氏の訳により2020年に発行されている。Quantには「定量的データを利用する金融アナリスト」という意味があるらしい。【感想】僕も今、NISAの流行りに乗っかって、お小遣いの余りで投資信託を買っている。(残念ながら今のところプラスとマイナスを行ったり来たり…!ガマンガマン…)小銭でも投資家気分が味わえて楽しいし、もちろん「増えて欲しい」が一番の願いだけど、その一方で、株を買う時のように投資する会社とのつながりを感じないところが寂しい、とも感じている。ジム・シモンズ氏を始め、この本に出てくる人たちは、金融市場でのお金の奪い合いのために高度な数学の知識と天才と称される頭脳、加えて膨大なエネルギーを日々費やしていた。彼らからは投資先を応援する気持ちなどは微塵も感じなかったし、投資先を詳しく知ろうともしていないように思えた。投資スタイルとして余り共感できなかった。だけど、理解できない世界の話だからこそ、この際読んでみたいとも思った。上巻を読み終えて、彼らの考え方が少し理解できたような気がするし、ふんだんに盛り込まれた個人的なエピソードを通じて、登場人物に対する親しみも湧いてきた。それでも、この手の投資術はやっぱり邪道ではないか、との思いは拭えない。ちなみに本書の83-84頁で、著者は投資家を次のようにタイプ分けしている。①「一部の投資家や学者は、市場のジグザグな動きはランダムであって、入手可能な情報はすでに価格の中に織り込まれており、価格を上下させるのは予測不可能なニュースだけであると考えていた。」本書の前に読んだ本の主人公はこの立場を取っていたと思う。市場の予測は不可能だから常に暴落に備えるべきと考え、いわゆる暴落保険のような投資をポートフォリオの一部に組み込み、その結果、膨大な利益を生み出していた。②「その一方で、価格の変動に反映されるのは、経済や企業に関するニュースを予測してそれに反応するという投資家の取り組みなのであって、その取り組みがときに実を結ぶのだと考える者もいた。」一般的なプロの投資家の考え方はこれだと思う。専門的な知見と経験によって市場の変動はある程度予想できるとし、市場平均を上回る利益を唱い投資を募っている。③「シモンズは独特の見方を取った。大量のデータを入念に調べ、ほかの人にはランダムに見えるところに秩序を見いだすことに慣れていた。」これが本書の主人公、ジム・シモンズの立場。天才的な数学者が、高度な数式を駆使することで不規則にしか見えない売買価格の動きに一定の規則性を見出し、人間の感情を極力排除した売買を繰り返す。その手法で圧倒的な成果を挙げていった。だけどシモンズ氏らがこのビジネスモデルを立ち上げた1970-80年代に、シモンズの頭脳に付いていけるようなコンピューターはあったのだろうか。僕自身の記憶では、かわいらしい形をしたマッキントッシュコンピューターがアメリカの家庭に爆発的に普及したのが1980年代の半ばくらいから。性能的にはワープロに毛が生えたくらいのものだったように思う。シモンズたちはいったいどんなツールで複雑な数式を操り、投資にも応用できるシステムを組み立てて行ったのだろうか…などと、少し本質からはずれたことを読みながら考えてもいた。少々お腹いっぱい…すぐに下巻を読み始めるか、インターバルをおくか、少し考えようと思う。
June 6, 2025
コメント(0)
-

春の風景(札幌・白石こころーど)
その昔、国鉄の千歳線が走っていた「白石こころーど」(札幌市白石区)。今は人と自転車だけがゆるゆると行き交うこの小道を横切るのも、今年で3年目になる。毎回それぞれ、いろんな用事で、いろんなことを考えながらこの場所を通るけど、いつも立ち止まって写真を撮りたくなる。そして春夏秋冬、いつ通っても心が落ち着く。今回は春。走っている人、自転車の人、歩いている人。時として横切るのが大変なくらいたくさんの人たちがこの道を楽しんでいた。
June 1, 2025
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1









